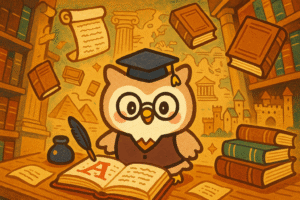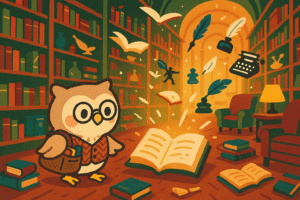あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】レフ・トルストイのおすすめ小説ランキングTOP13

レフ・トルストイとは?19世紀ロシア文学を代表する文豪の生涯と思想
レフ・ニコラエヴィチ・トルストイ(1828-1910)は、帝政ロシアの小説家、思想家です。フョードル・ドストエフスキー、イワン・ツルゲーネフと並び、19世紀ロシア文学を代表する文豪として知られています。代表作には『戦争と平和』『アンナ・カレーニナ』『復活』などがあり、その作品は文学だけでなく、政治や社会にも大きな影響を与えました。
トルストイは、ロシアのヤースナヤ・ポリャーナで伯爵家の四男として生まれました。裕福な家庭でしたが、幼い頃に両親を亡くすという経験をしました。大学を中退後、軍隊に入隊し、クリミア戦争などに従軍。この時の体験は、『セヴァストーポリ物語』などの作品に結実し、後の非暴力主義思想の素地になったとされています。
作家として名声を得た後も、トルストイは常に「いかに生きるべきか」と自問し続けました。晩年にはキリスト教的人道主義の立場から非暴力主義を唱え、その思想はマハトマ・ガンディーにも影響を与えたことで知られています。贅沢な生活を恥じ、夫人との不和に悩んだすえ、82歳で家出を決行し、その旅の途中で肺炎のため駅長官舎でその生涯を閉じました。
トルストイ小説の魅力とは?壮大な物語と深遠な人間探求
トルストイの小説が今なお世界中の人々を惹きつけてやまない魅力は、その壮大なスケールと、人間の内面を深く掘り下げる鋭い洞察力にあると言えるでしょう。彼の作品は、単なる物語の枠を超え、人生そのものを問い直す力を持っています。
代表作『戦争と平和』では、ナポレオン戦争という歴史的な大事件を背景に、500人以上もの登場人物が織りなす人間模様が写実主義の手法で鮮やかに描かれています。トルストイは、歴史の大きなうねりに翻弄されながらも必死に生きる人々の喜びや悲しみ、愛や苦悩を克明に描写することで、読者を物語の世界へと引き込むのです。
また、『アンナ・カレーニナ』では、社会の慣習に逆らい、自らの愛に生きようとする女性の悲劇を通して、人間の心の複雑さや矛盾を見事に描き切っています。トルストイの作品に共通するのは、「いかに生きるべきか」という根源的な問いです。彼は、愛、死、信仰、社会といった普遍的なテーマを通して、人間のあり方を深く探求し続けました。その深遠な人間探求こそが、時代を超えて私たちの心を揺さぶり続けるトルストイ文学の核心なのです。
レフ・トルストイのおすすめ小説ランキングTOP13
19世紀ロシア文学の巨匠、レフ・トルストイ。その作品は、壮大な歴史絵巻から個人の内面に深く迫る物語まで、多岐にわたります。「名前は知っているけれど、どの作品から読めばいいかわからない」という方も多いでしょう。
この記事では、トルストイの数ある名作の中から、特におすすめの13作品をランキング形式でご紹介します。不朽の名作から、思想が色濃く反映された作品、初心者でも読みやすい民話まで、幅広く選びました。このランキングを参考に、トルストイ文学の深遠な世界の扉を開いてみてください。
1位『戦争と平和』
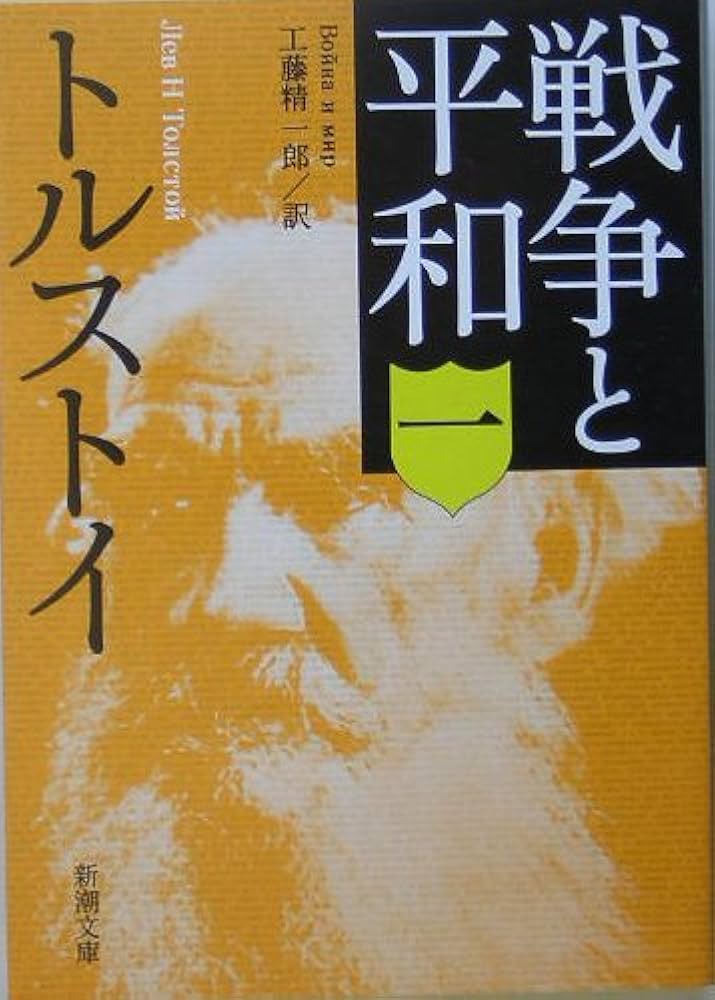
『戦争と平和』は、ナポレオンのロシア遠征を背景に、19世紀初頭のロシア社会を壮大なスケールで描いた歴史小説です。500人を超える登場人物が織りなす人間模様を通じて、戦争の悲惨さと平和の尊さ、そして人生の意味を問いかける作品です。
物語は、ピエール、アンドレイ、ナターシャという3人の貴族の若者を中心に展開します。彼らが戦争という過酷な現実の中で、愛や憎しみ、喜びや苦悩を経験しながら成長していく姿が、写実主義の手法で鮮やかに描き出されています。トルストイ自身の思索も反映されており、歴史とは何か、人間はいかに生きるべきかという哲学的な問いが散りばめられています。
その圧倒的なボリュームから敬遠されがちですが、一度読み始めれば、登場人物たちの生き様に引き込まれ、まるで自分がその時代に生きているかのような没入感を味わえます。ロシア文学、ひいては世界文学の最高峰と称される不朽の名作です。
 ふくちい
ふくちい壮大な物語に圧倒されるけど、登場人物たちの人生が濃密で読み終えた後の感動は格別だよ!
2位『アンナ・カレーニナ』
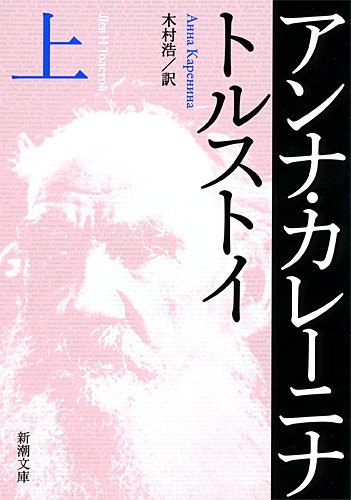
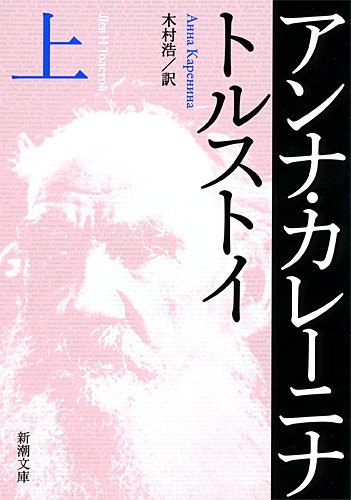
『アンナ・カレーニナ』は、『戦争と平和』と並ぶトルストイの代表作で、19世紀ロシアの貴族社会を舞台にした長編小説です。物語は、政府高官の美しい妻アンナ・カレーニナが、青年将校ヴロンスキーと恋に落ち、家庭を捨てて愛に生きようとする姿を中心に描かれています。
一方で、誠実な地主リョーヴィンの結婚生活と精神的な探求が並行して語られ、アンナの破滅的な情熱と対比されます。このリョーヴィンの姿には、トルストイ自身の体験や思想が色濃く反映されているとされています。
本作は、単なる不倫小説ではなく、当時の社会の偽善や道徳観、女性の生き方、そして「真の幸福とは何か」という普遍的なテーマを鋭く問いかけます。その緊密な構成と心理描写の巧みさから、現代の作家たちによる投票で世界文学史上ベストテンの第1位に選ばれたこともある、まさに傑作中の傑作です。



アンナの選択が切なくて…。愛と社会の狭間で揺れる姿に、胸が締め付けられるんだ。
3位『復活』
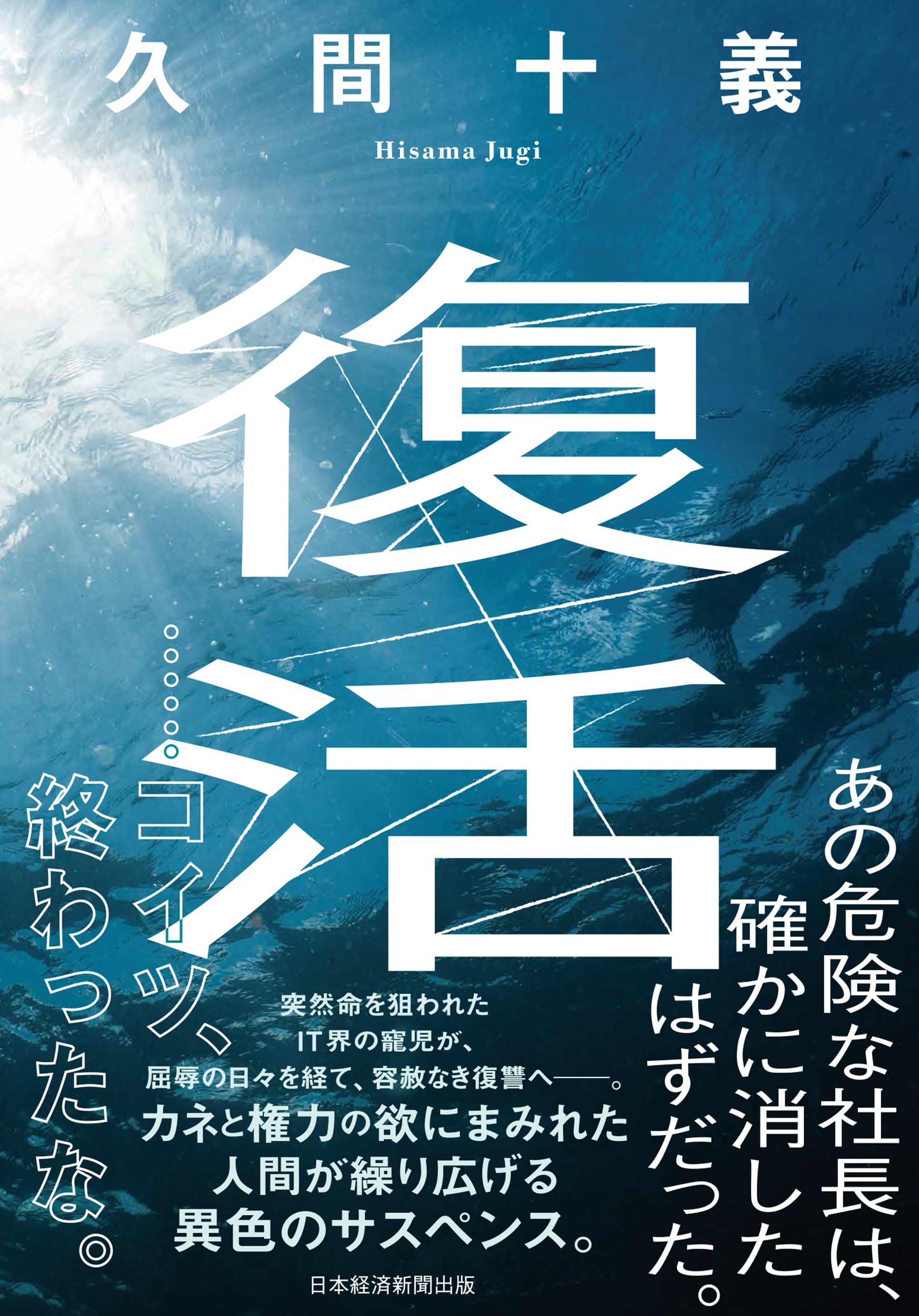
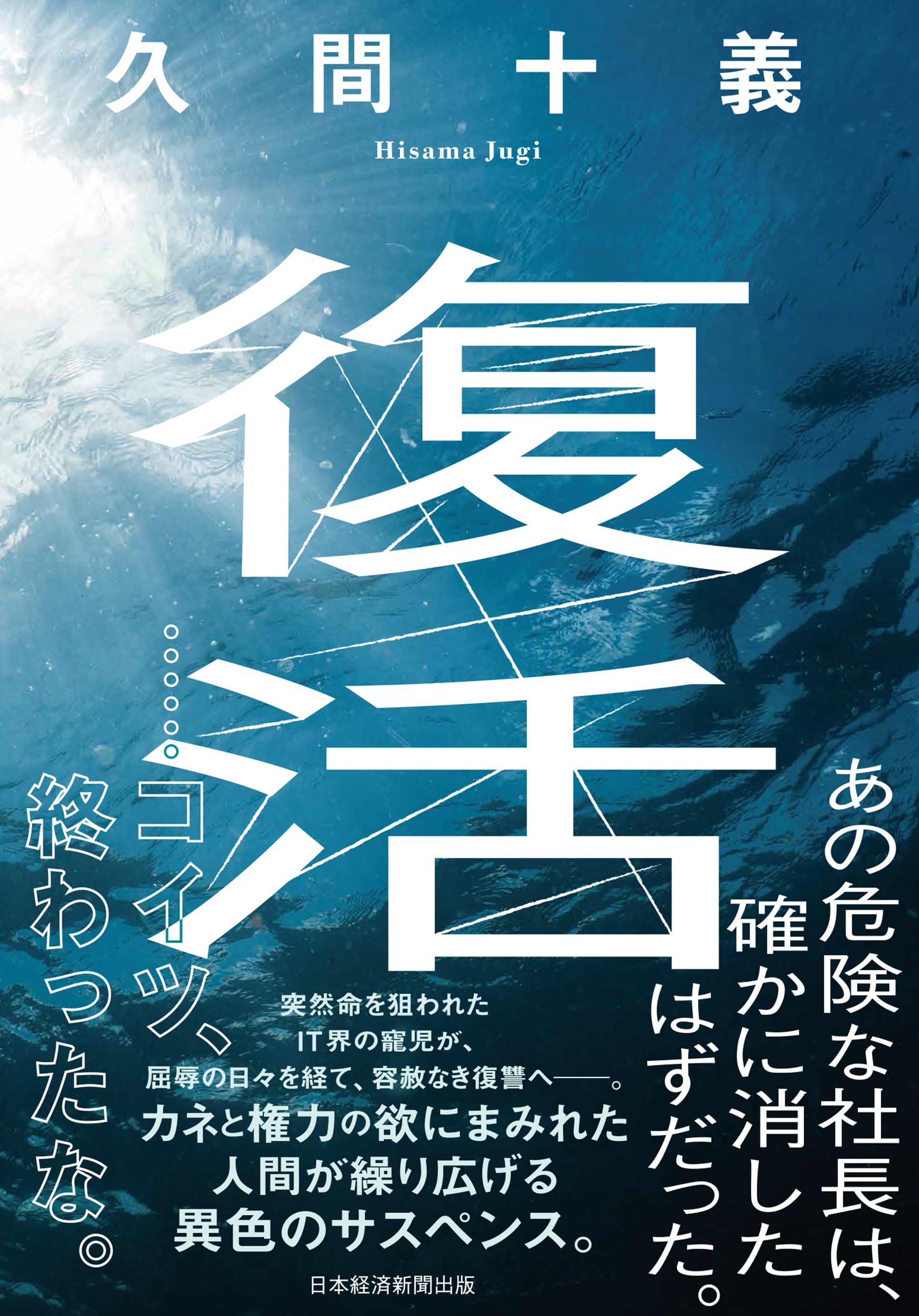
『復活』は、『戦争と平和』『アンナ・カレーニナ』と並ぶトルストイの三大長編の一つで、彼の後期の思想が最も色濃く反映された作品です。物語は、貴族の青年ネフリュードフが、かつて自分が誘惑し捨てた女性カチューシャと、裁判の陪審員として再会するところから始まります。
彼女が殺人の罪でシベリア流刑を宣告されたことを知ったネフリュードフは、自らの罪を悔い、彼女の「復活」のために奔走することを決意します。この過程で、彼は裁判所や監獄、政府機関の不正や非人道性を目の当たりにし、社会そのものの矛盾に気づいていくのです。
本作は、一人の男の贖罪の物語であると同時に、当時のロシア社会の腐敗を鋭く批判した社会小説としての側面も持っています。トルストイがロシア正教会から破門されるきっかけとなった作品としても知られ、彼の思想の集大成とも言える重厚な一作です。



人の罪と許しについて、深く考えさせられる作品だよ。ネフリュードフの決意がすごいんだ。
4位『イワン・イリイチの死』
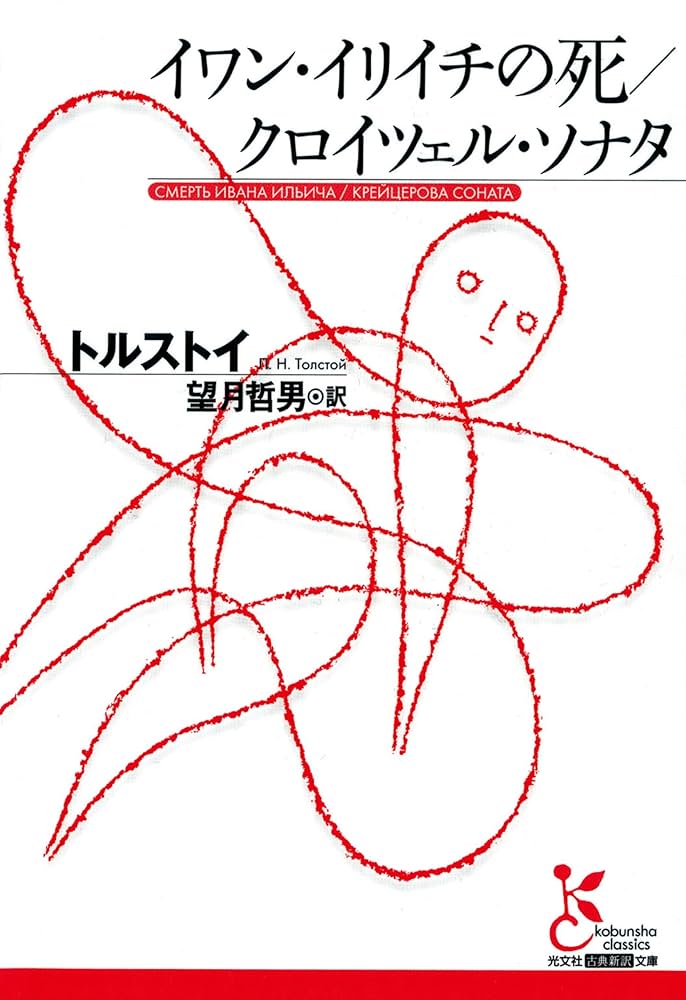
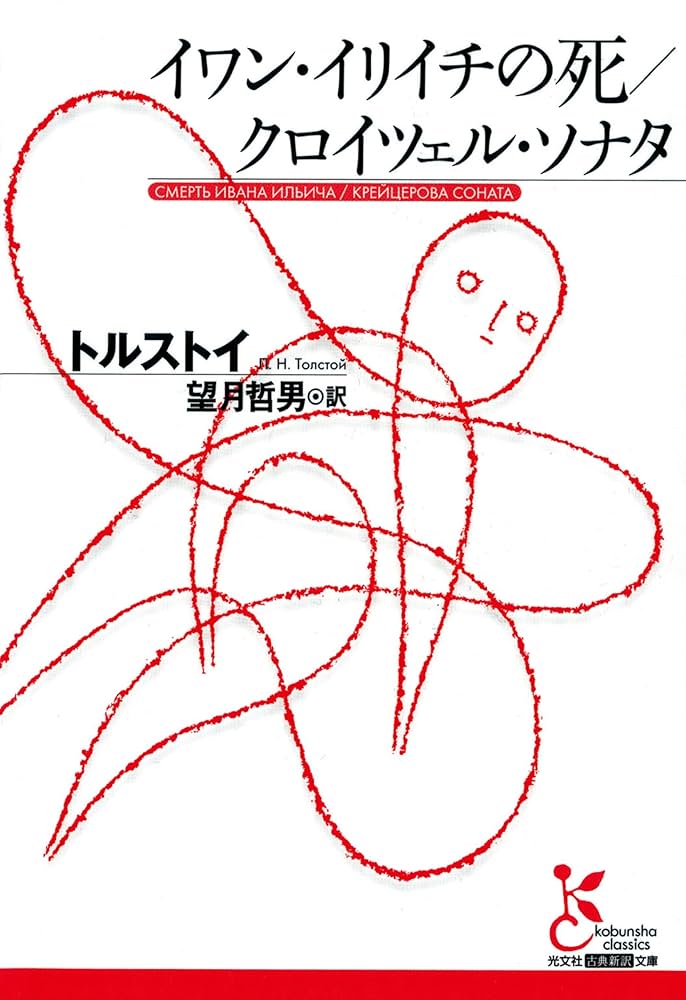
『イワン・イリイチの死』は、トルストイの中期を代表する傑作中編です。順風満帆な人生を送ってきた高等法院判事イワン・イリイチが、ある日突然、不治の病に冒され、死に至るまでの過程を克明に描いた作品です。
病の進行とともに、彼はこれまで自分が築き上げてきた社会的成功や家庭が、いかに偽りに満ちたものであったかに気づかされるのです。家族や同僚の無関心と欺瞞の中で、彼は激しい肉体的苦痛と精神的孤独に苛まれます。
この作品は、死を目前にした人間の内面を徹底的に見つめ、「人生の意味とは何か」「真の幸福とは何か」を読者に鋭く問いかけます。比較的短い作品ながら、その衝撃と感動は長編にも劣りません。トルストイの思想の核心に触れることができる、必読の一冊です。



本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。
5位『トルストイ民話集』(『人はなんで生きるか』『イワンの馬鹿』など)
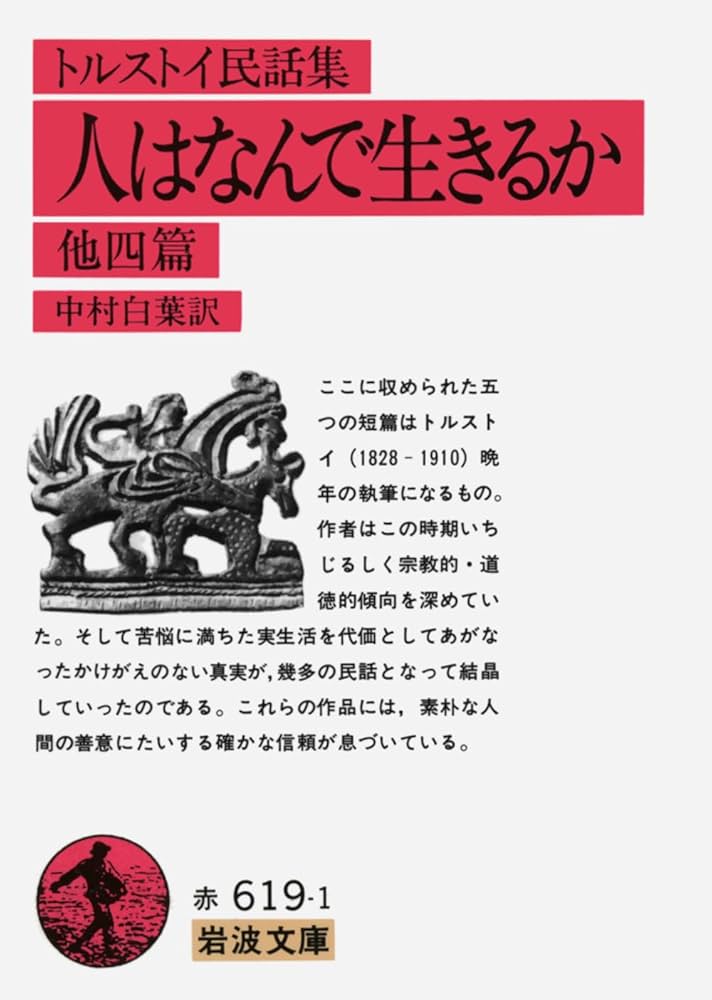
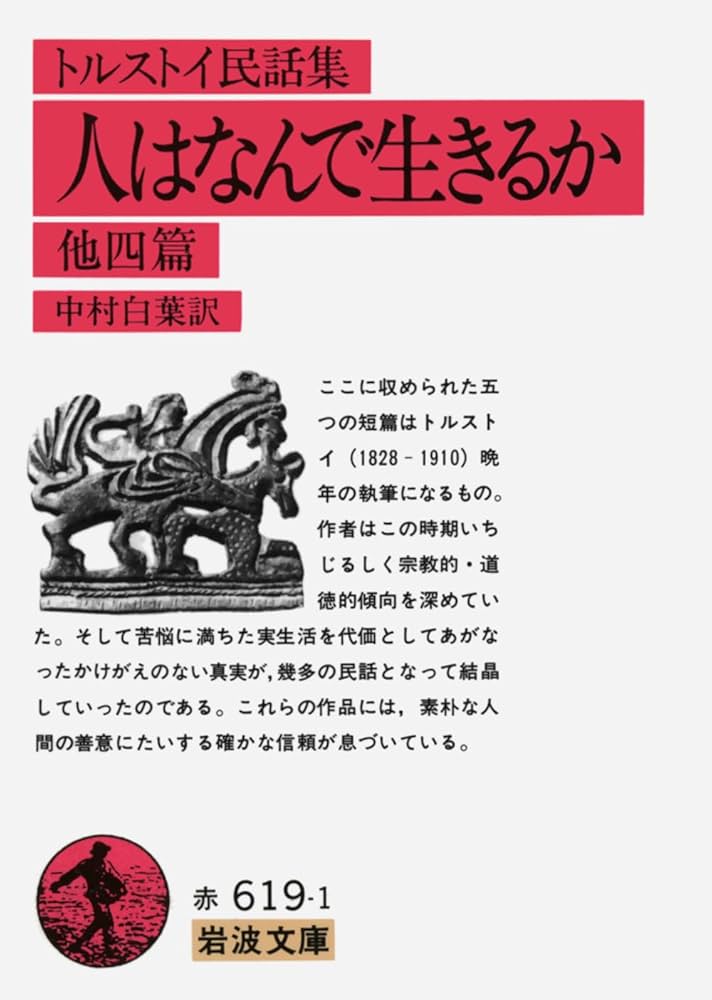
トルストイは、農民の子どもたちのために、ロシアの民話を基にした多くの物語を執筆しました。それらは『人はなんで生きるか』や『イワンの馬鹿』といった作品集にまとめられています。
これらの民話は、平易な言葉で書かれていながら、キリスト教的な愛や労働の尊さ、非暴力といったトルストイの思想の核心が込められています。「人はなんで生きるか」では愛の重要性を、「イワンの馬鹿」では素朴で正直な生き方の価値を説いています。
物語としての面白さはもちろん、人生の教訓に満ちたこれらの作品は、大人から子どもまで楽しむことができます。トルストイの長編小説は難しそうだと感じる初心者の方にとって、彼の思想や文学に触れるための絶好の入り口となるでしょう。



シンプルだけど、すごく心に響く話ばかりなんだ。『人はなんで生きるか』は、読むたびに新しい発見があるよ。
6位『幼年時代』
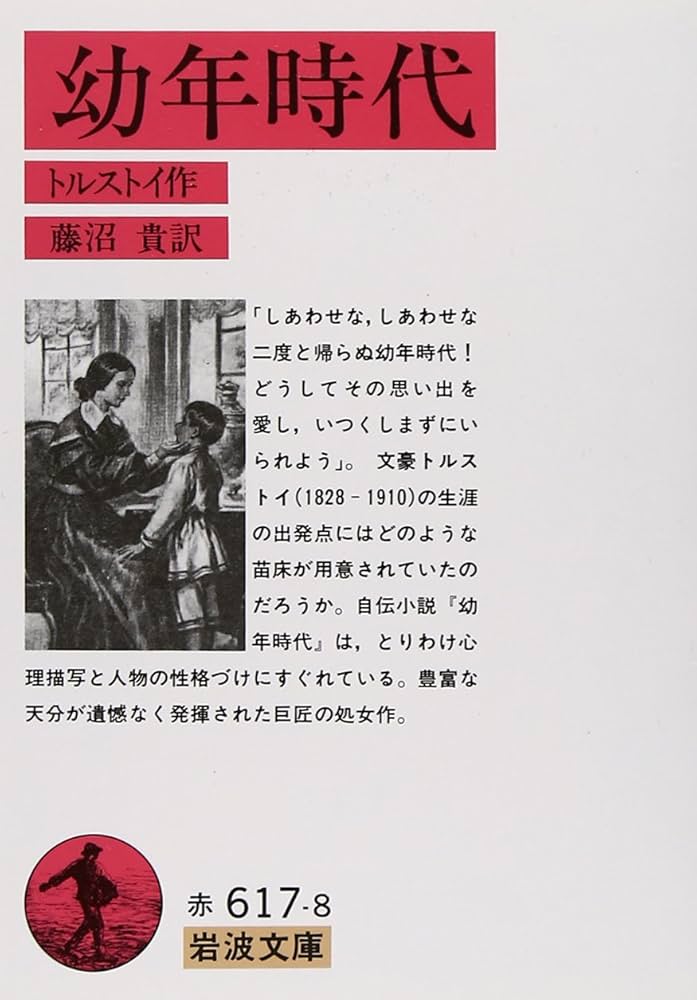
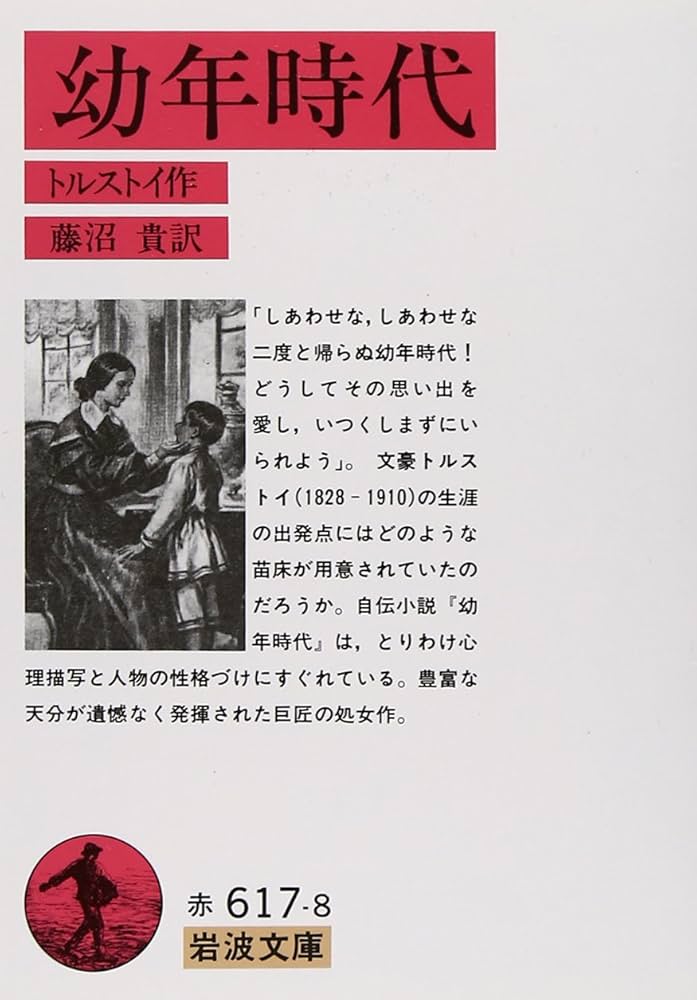
『幼年時代』は、1852年に発表されたトルストイのデビュー作であり、自伝的要素の強い三部作(『幼年時代』『少年時代』『青年時代』)の第一部です。この作品でトルストイは、新進作家として大きな注目を集めました。
物語は、主人公である10歳の少年ニコライの視点から、家族との愛情あふれる日々や、初めての恋、母親の死といった出来事が瑞々しい感性で描かれています。子供の世界をこれほど繊細かつ正確な心理描写で描き出した作品は、当時としては画期的なものでした。
大人の視点から過去を美化するのではなく、子供が感じたままの世界をありのままに再現しようとする試みは、後のトルストイ文学の写実主義的なスタイルの原点とも言えます。誰しもが経験したであろう子供時代の懐かしい感情を呼び覚ましてくれる、感動的な作品です。



自分の子供の頃を思い出しちゃったな。甘酸っぱくて、ちょっと切ない気持ちになるんだ。
7位『コサック』
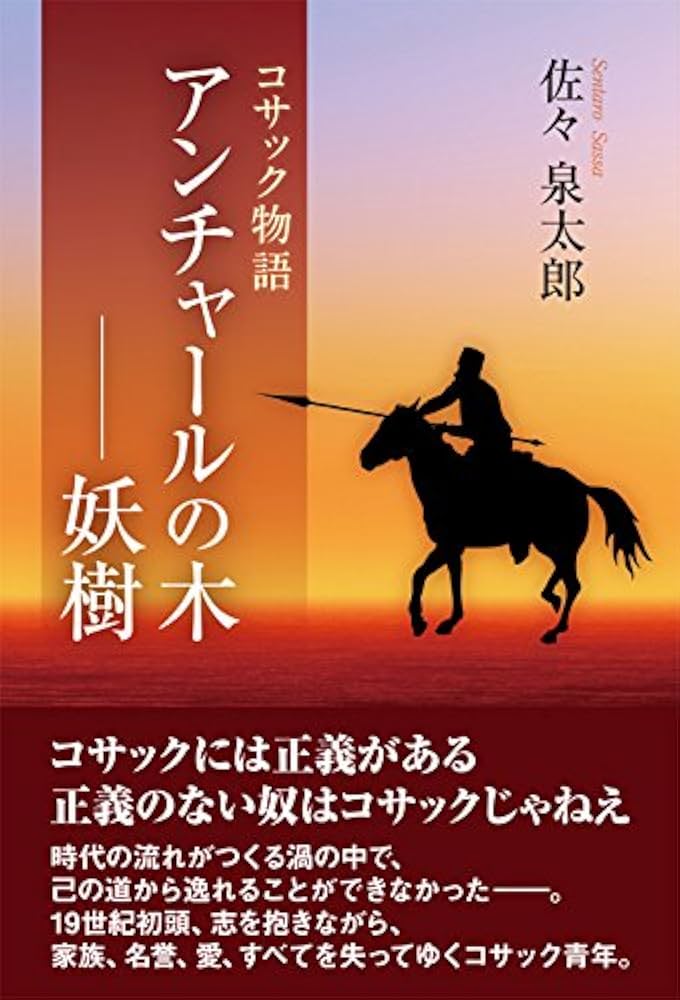
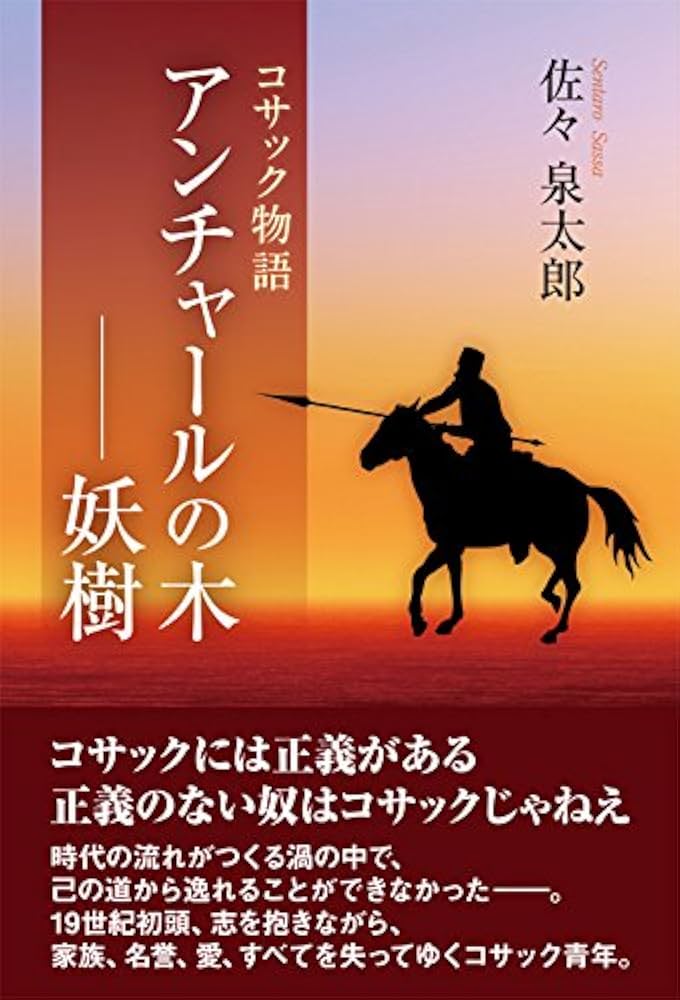
『コサック』は、トルストイがカフカース(コーカサス)での従軍体験を基に執筆した中編小説です。都会の虚飾に満ちた生活に嫌気がさした貴族の青年オレーニンが、カフカースのコサックの村に赴き、そこで雄大な自然と素朴な人々と出会う物語です。
オレーニンは、自然と一体化して生きるコサックの力強い生命力に魅了され、現地の娘マリヤーナに恋をします。彼は文明社会と未開の自然との間で葛藤し、自らの生き方を見つめ直していきます。
この作品では、若き日のトルストイ自身が抱いていたであろう、人生への模索や自然への憧憬が鮮やかに描かれています。後の大作とは異なる、青春小説のような瑞々しさと情熱が感じられる一作です。



大自然の中で自分を見つめ直すって、なんだかロマンがあるよね!オレーニンの気持ち、わかるなあ。
8位『クロイツェル・ソナタ』
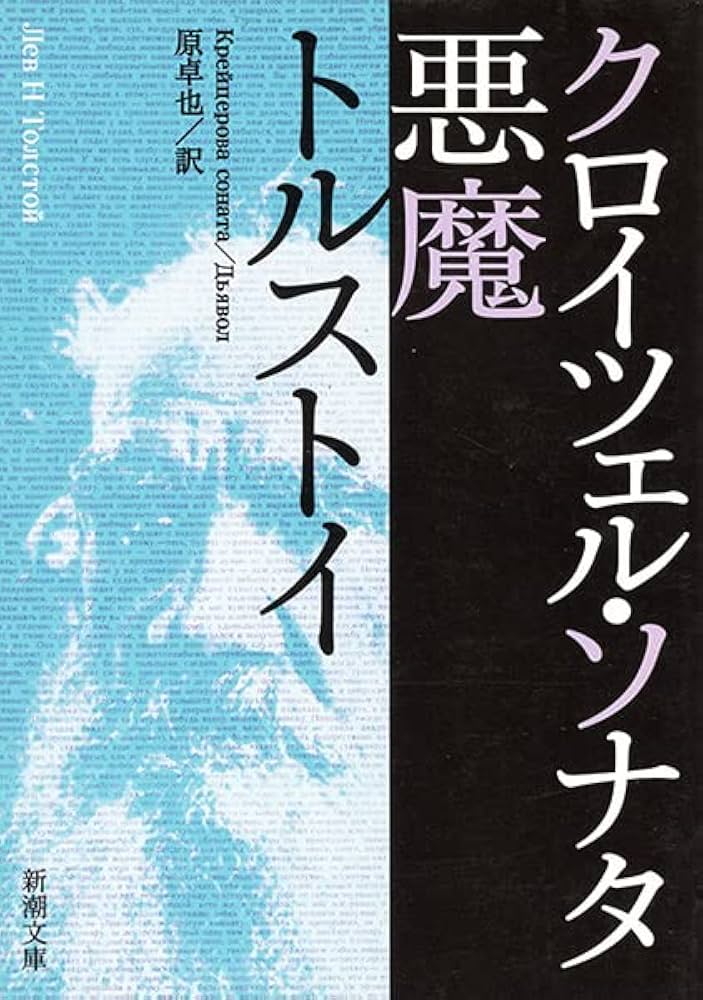
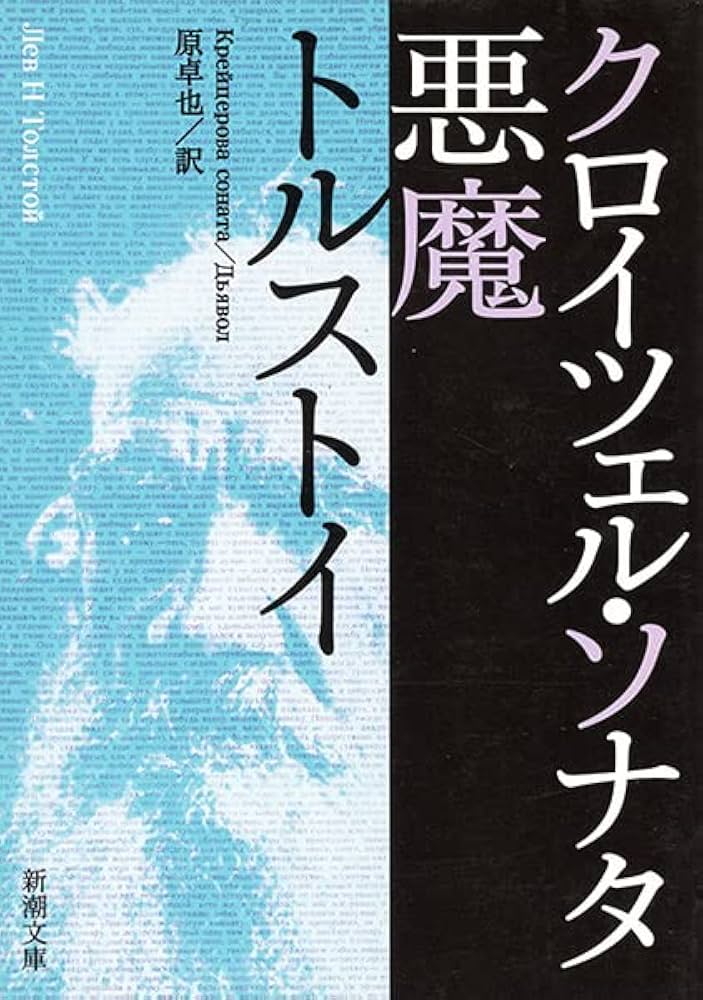
『クロイツェル・ソナタ』は、結婚、性、嫉妬といったテーマを大胆に扱い、発表当時に大きな物議を醸した問題作です。物語は、列車に乗り合わせた主人公ポズドヌイシェフが、かつて妻を殺害した過去を乗客に告白するという形式で進みます。
彼は、妻が音楽家とベートーヴェンの『クロイツェル・ソナタ』を演奏するのを聞き、激しい嫉妬に駆られて妻を殺害するに至った経緯を語ります。その告白を通して、トルストイは当時の結婚制度や男女関係に潜む偽善を鋭く批判し、禁欲的な思想を展開しました。
人間の愛憎が渦巻く心理を深くえぐり出したこの作品は、その過激な内容から検閲によって発禁処分を受けました。トルストイの後期の思想を知る上で欠かせない、強烈なインパクトを持つ一作です。



音楽が引き金で悲劇が起きるなんて…。人間の嫉妬心の恐ろしさを描いていて、ゾクッとしちゃうね。
9位『悪魔』


『悪魔』は、人間の内に潜む抗いがたい情欲の恐ろしさを描いた中編小説です。トルストイの死後、遺稿の中から発見された作品として知られています。
物語の主人公は、若き地主エフゲーニイ。彼は結婚前に農家の美しい人妻ステパニーダと関係を持ちますが、結婚を機に彼女との関係を断ち切ります。しかし、幸福な結婚生活を送る中でステパニーダと再会したことで、彼の心に抑えきれない欲望の炎が再び燃え上がります。
理性と道徳、そして妻への愛と、肉体的な情欲との間で激しく葛藤する主人公の姿を、トルストイは容赦ない筆致で描きます。人間の意志の弱さと、一度火が付いた情念の恐ろしさを描き切った、戦慄を覚えるほどの作品です。



タイトルがもう怖いんだけど…。人間の心の中には、本当に「悪魔」が住んでいるのかもしれないね。
10位『主人と下男』
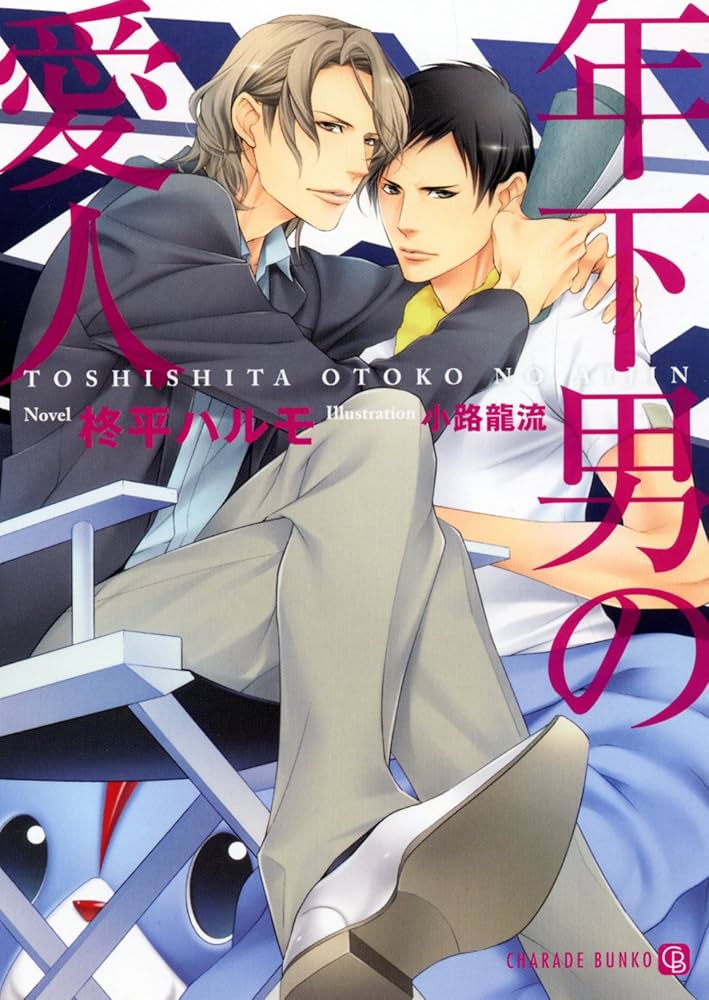
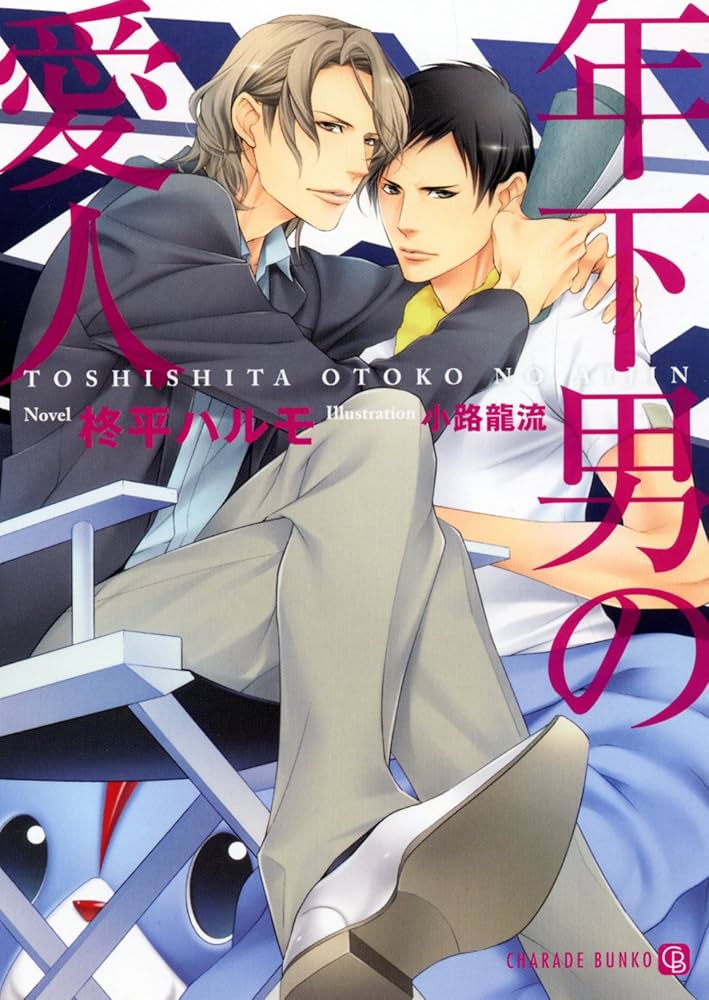
『主人と下男』は、トルストイ晩年の傑作とされる短編小説です。強欲な地主ワシーリイと、その下男ニキータが、吹雪の中で道に迷い、死の危機に瀕する物語です。
金儲けのことしか頭になかったワシーリイは、極限状態の中で初めて死を意識し、自らの人生の空しさに気づきます。そして彼は、凍え死にそうになっているニキータを救うため、自らの体を投げ出して彼を温めるという自己犠牲的な行動に出ます。
この作品は、死を前にした人間の内面の変化を通して、真の愛とは何か、利己主義を超えた献身の尊さを描いています。簡潔な文章の中に、トルストイの宗教的・道徳的な思想が凝縮された、深く心に響く物語です。



最後の主人の行動に涙が出ちゃう…。本当の豊かさって何だろうって、考えさせられるよ。
11位『セヴァストーポリ物語』
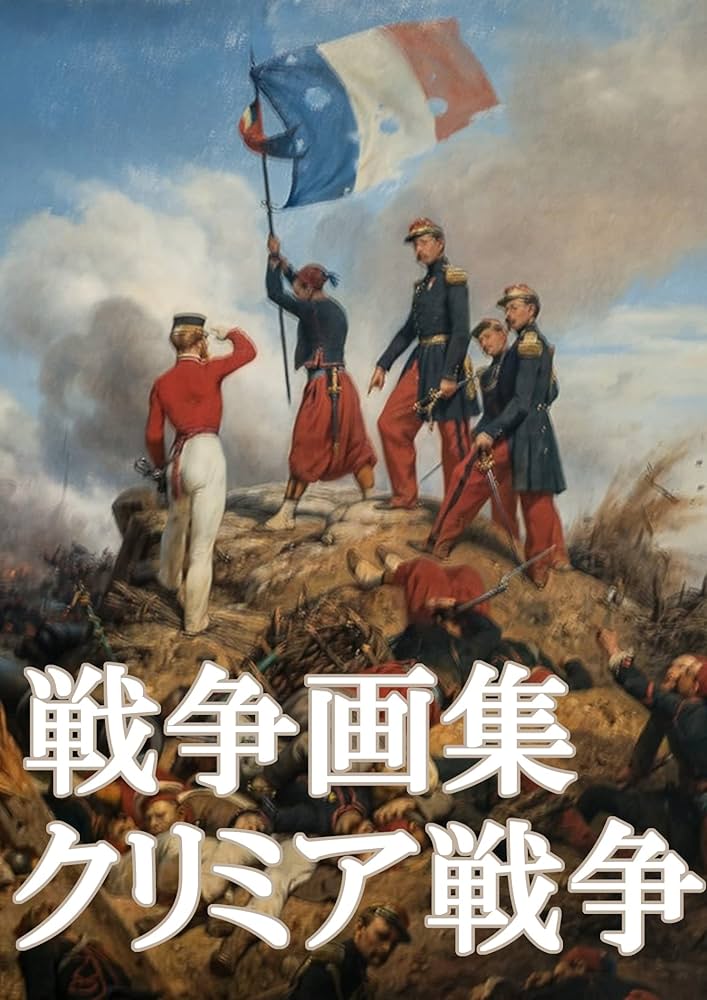
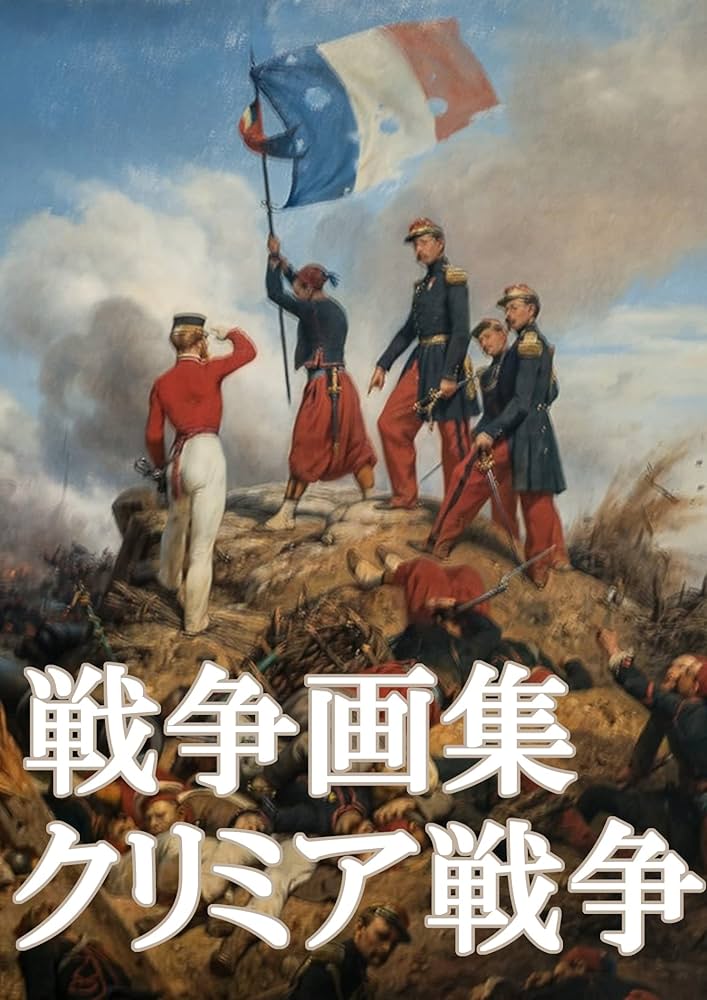
『セヴァストーポリ物語』は、トルストイが将校として従軍したクリミア戦争の激戦地、セヴァストーポリ要塞での体験を基に描かれた3つの作品からなる戦記文学です。この作品によって、トルストイは作家としての地位を確立しました。
英雄的な戦争物語ではなく、兵士たちの日常や、負傷兵が苦しむ野戦病院の様子、そして死の恐怖といった戦争の現実をありのままに描いています。華やかな戦闘シーンの裏にある、戦争の無意味さと非人間性をリアルな筆致で告発しています。
特に、物語の真の主人公は「真実」であると宣言する一節は有名です。後の『戦争と平和』にも通じる、トルストイのリアリズムと反戦思想の原点がここにはっきりと見て取れます。戦争文学の古典として、今なお重要な意味を持つ作品です。



戦争のリアルな描写が生々しくて、衝撃的だった。英雄なんていない、ただ「真実」があるだけっていう言葉が重いね。
12位『ハジ・ムラート』


『ハジ・ムラート』は、トルストイが晩年に執筆し、死後に出版された中編小説です。カフカース戦争でロシアに抵抗した実在の英雄、ハジ・ムラートを主人公に、彼の誇り高くも悲劇的な生涯を描いた作品です。
家族を救うために一度はロシアに投降したハジ・ムラートでしたが、ロシア側の欺瞞と、敵であるシャミールからの脅威との間で板挟みになります。彼は自らの尊厳と家族への愛のために、絶望的な戦いに身を投じていきます。
この作品では、ロシア帝国主義への批判的な視点とともに、権力に屈しない不屈の精神と人間の生命力が見事に描かれています。晩年のトルストイが到達した、無駄のない簡潔な文体と円熟した芸術性が光る、最後の傑作です。



ハジ・ムラートの生き様が本当にかっこいいんだ!最後まで誇りを失わない姿にシビれるよ。
13位『光あるうち光の中を歩め』
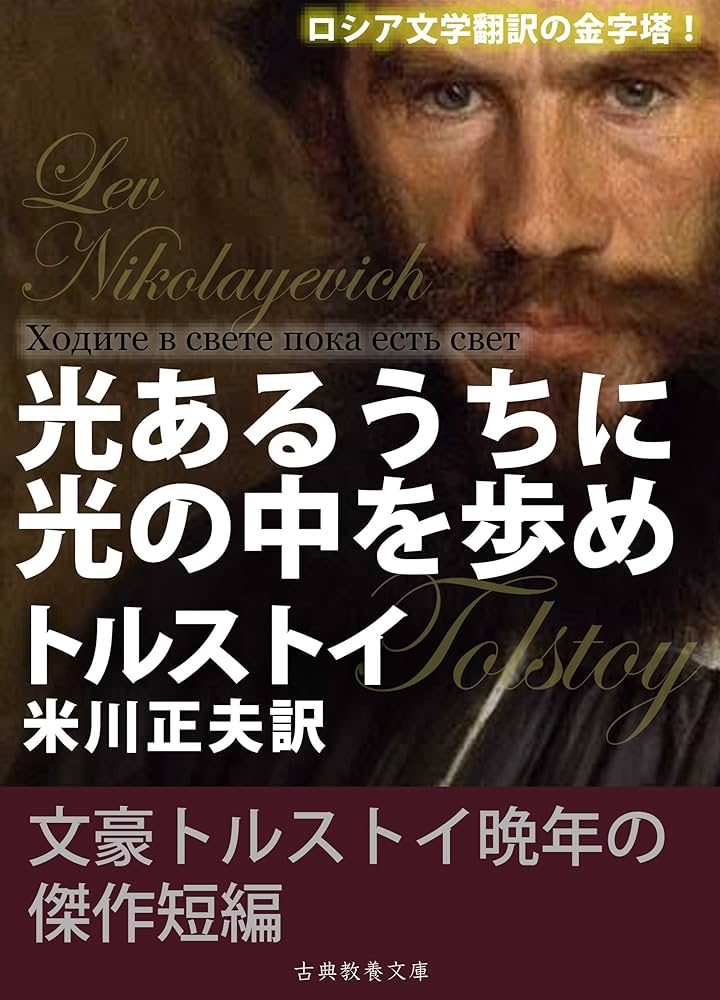
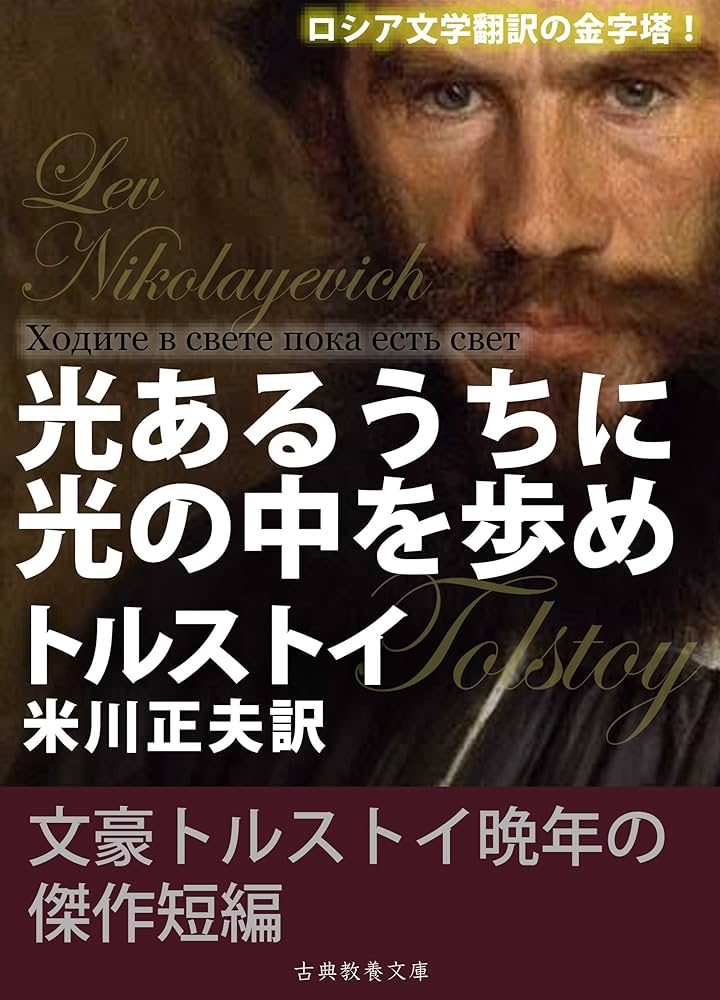
『光あるうち光の中を歩め』は、トルストイの後期のキリスト教思想が色濃く反映された物語です。古代ローマ時代を舞台に、裕福な商人の息子ユリウスと、キリスト教徒のパンフィリウスという二人の青年の対照的な人生を描いています。
快楽と富を追求するユリウスの人生と、愛と奉仕に生きるキリスト教徒たちの質素な生活を対比させることで、トルストイは真の幸福とは何かを問いかけています。物語を通して、彼の非暴力や財産の否定といった思想が分かりやすく説かれています。
小説としての面白さというよりは、トルストイの思想を理解するための寓話的な作品と言えるかもしれません。彼の宗教観や道徳観に関心がある読者にとっては、非常に興味深い一冊となるでしょう。



どっちの生き方が幸せなんだろうって考えちゃうね。物質的な豊かさだけが全てじゃないってことかな。
何から読む?トルストイ初心者におすすめの作品と読む順番
トルストイの作品は長編で難解なイメージがあるかもしれませんが、初心者でも楽しめる作品はたくさんあります。何から読めばいいか迷っている方のために、おすすめの読む順番をご紹介しましょう。
まずは、短編や民話集から始めるのがおすすめです。『トルストイ民話集』に含まれる「人はなんで生きるか」や「イワンの馬鹿」は、平易な言葉で書かれていながら、トルストイの思想の核心に触れることができます。また、死と生の意味を鋭く問う中編『イワン・イリイチの死』も、比較的短く読みやすいながら強烈な読書体験ができる一冊です。
次に、トルストイの自伝的小説『幼年時代』や、若き日の体験が基になった『コサック』といった中編に挑戦してみるのも良いでしょう。これらの作品でトルストイの文体や世界観に慣れたら、いよいよ『アンナ・カレーニナ』や『戦争と平和』といった三大長編に挑んでみるのが王道と言えるでしょう。焦らず、自分のペースで巨匠の世界を旅してみてください。
まとめ:文豪トルストイが作品を通して問いかけるもの
レフ・トルストイは、その生涯を通じて作品の中で一貫して「人間はいかに生きるべきか」という根源的な問いを投げかけ続けた作家です。彼の作品は、壮大な歴史物語から個人の内面の葛藤まで、様々な形でこのテーマを探求しています。
『戦争と平和』では歴史のうねりの中での個人の生き方を、『アンナ・カレーニナ』では社会の因習と愛との間で揺れる魂を、そして『復活』では罪と贖罪を通じた精神的な再生を描いています。これらの物語を通して、トルストイは愛、死、信仰、正義といった普遍的な問題と真摯に向き合いました。
彼の作品を読むことは、単に物語を楽しむだけでなく、自分自身の人生や生き方について深く考えるきっかけを与えてくれるでしょう。時代や国境を越えて、トルストイの問いかけが今なお多くの人々の心を打ち続けるのは、そこに誰もが向き合わなければならない人生の真実が描かれているからなのです。