あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】ジャン=ポール・サルトルの小説おすすめランキングTOP5

ジャン=ポール・サルトルのおすすめ小説を読む前に知りたい実存主義
サルトルの小説世界に飛び込む前に、彼の思想の根幹である「実存主義」について少しだけ触れておきましょう。これを知っていると、物語の深みがぐっと増すはずです。
サルトルの実存主義を象徴する最も有名な言葉が「実存は本質に先立つ」です。 ちょっと難しい言葉に聞こえるかもしれませんが、考え方はシンプルです。
例えば、ハサミやペンのような「モノ」は、「何かを切るため」「文字を書くため」といった目的(本質)が先にあり、その目的のために作られ、存在(実存)します。 しかしサルトルは、人間はそうではないと考えました。人間には、生まれ持った目的や運命(本質)は存在しないというのです。
私たちはまず、理由もなくこの世界に「存在」し、その後の人生で何をするか、どんな人間になるかを自らの意志で選び取っていきます。 つまり、自分の行動や選択によって、自分自身の「本質」を後から作っていく存在なのです。この絶対的な自由と、その選択に対する責任こそが、サルトルが小説を通して描き続けたテーマでした。
ジャン=ポール・サルトルの小説おすすめランキングTOP5
実存主義という少し硬い話のあとは、いよいよサルトルの小説の世界へご案内します。彼の作品は、哲学的なテーマを扱いながらも、私たち自身の人生と地続きの悩みや葛藤を描いた、魅力的な物語ばかりです。
サルトルは哲学者であると同時に、優れた小説家・劇作家でもありました。 彼は自身の難解とも言われる哲学思想を、より多くの人に届けるために小説という形式を選んだのです。 物語の登場人物たちが直面する不条理な現実や、そこでの選択を通して、「自由であること」の重みや不安、そして希望を鮮やかに描き出しました。
今回は、そんなサルトル文学の神髄に触れられる代表的な小説を、ランキング形式で5作品ご紹介します。どの作品も、読後にきっとあなたの世界の見え方を少しだけ変えてくれるはずです。
1位『嘔吐』
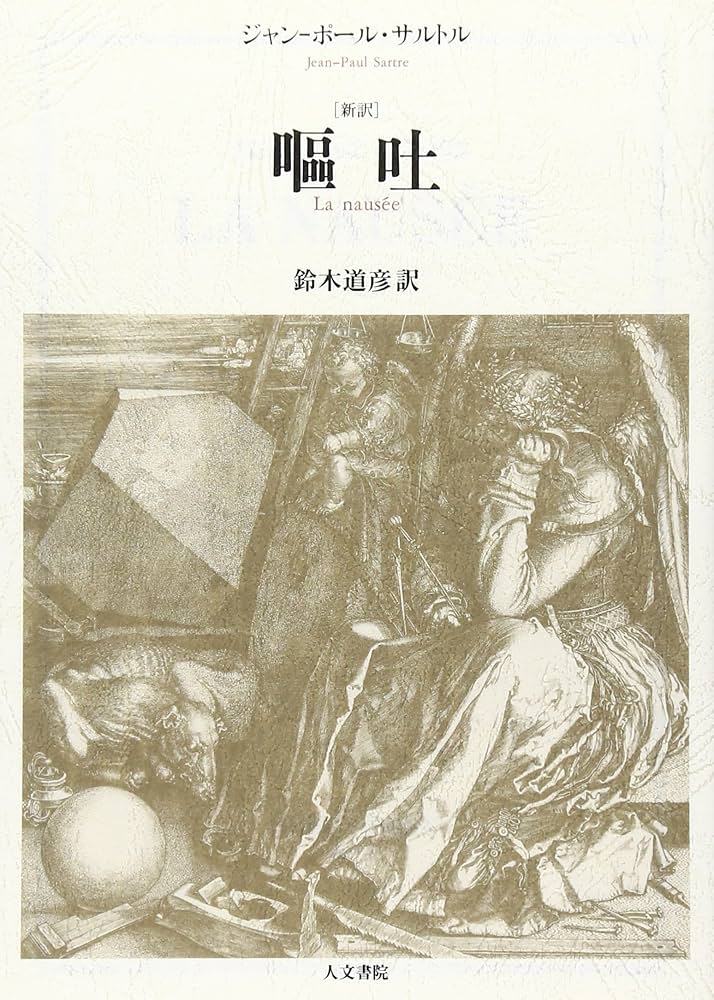
堂々のランキング1位は、サルトルの名を世に知らしめた処女長編小説『嘔吐』です。 この作品は「実存主義の聖典」とまで呼ばれ、サルトル文学、ひいては20世紀文学を語る上で欠かせない金字塔と言えるでしょう。
物語は、歴史研究者である主人公アントワーヌ・ロカンタンの日記形式で綴られます。 港町で単調な研究生活を送っていた彼は、ある日、道端の小石を拾おうとした瞬間に得体の知れない「吐き気」に襲われます。 その日を境に、彼は身の回りのあらゆるモノが持つ「ただ、そこにある」という存在の不気味さに気づき、強烈な嫌悪感を覚えていくのです。
この「吐き気」の正体こそ、人間には生きる目的や意味が予め与えられていないという「実存」の不安そのものです。 ロカンタンが体験する奇妙な感覚を通して、読者はサルトルの哲学の核心を肌で感じることができます。少し難解に感じるかもしれませんが、人間の存在の根源に触れるような、唯一無二の読書体験があなたを待っています。
 ふくちい
ふくちいわたし、このロカンタンが感じる「吐き気」ってすごく分かるんだ。世界のすべてが気持ち悪く見えちゃう瞬間って、あるよね…。
2位『壁』
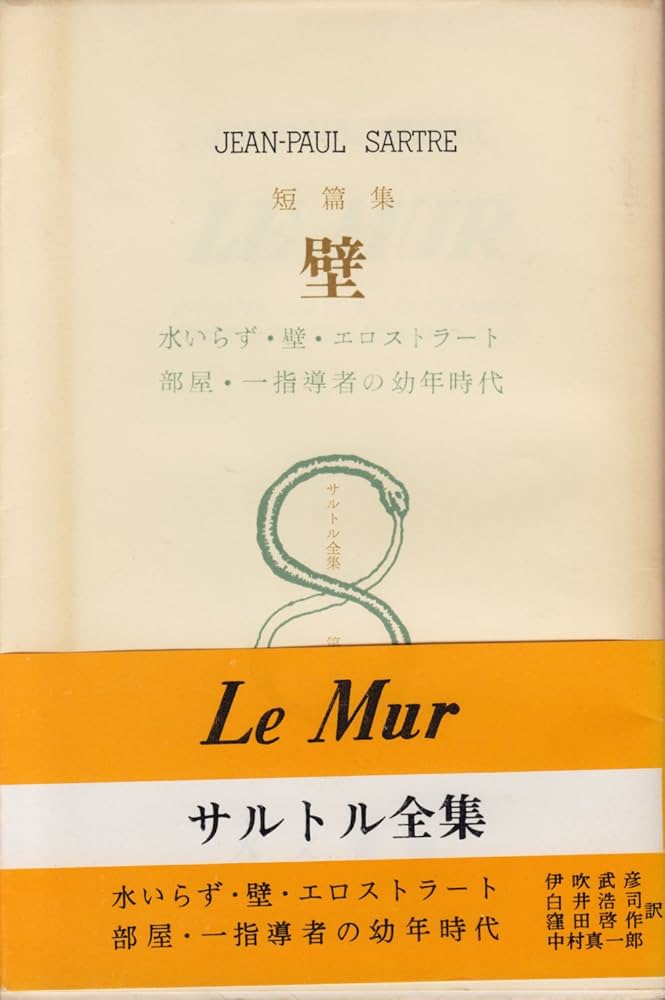
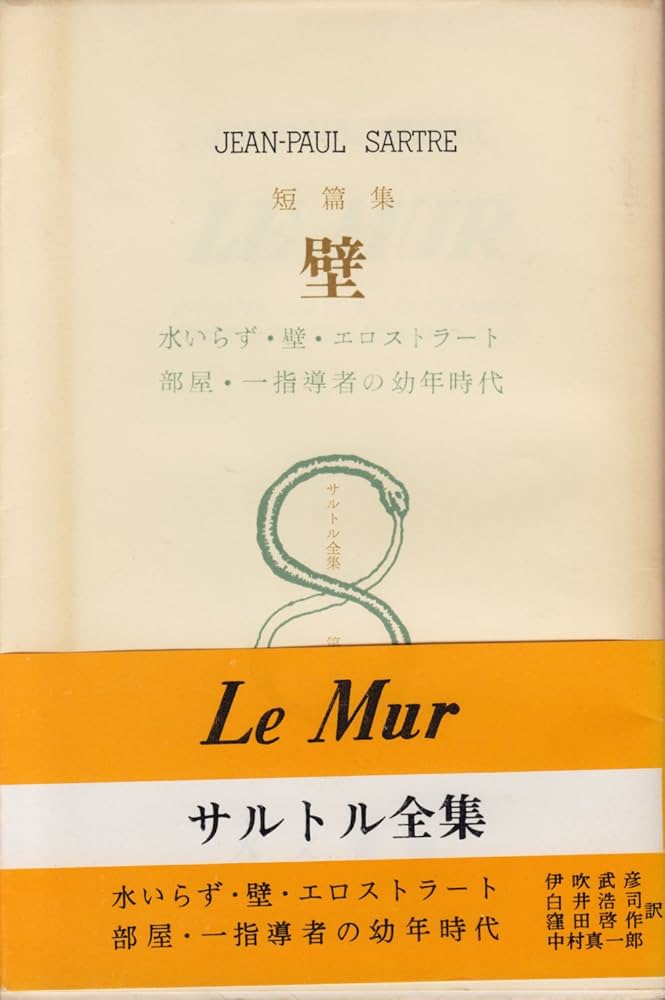
第2位は、サルトル初期の傑作短編集の表題作である『壁』です。 『嘔吐』が日常に潜む実存の不安を描いた作品だとすれば、こちらは死を目前にした極限状況における人間の姿を鋭く描き出しています。
舞台はスペイン内戦のさなか。 反ファシスト運動に加わっていた主人公パブロは、仲間と共に捕虜となり、翌朝の銃殺刑を宣告されます。 鉄格子の中で死の恐怖と向き合うパブロに、将校は取引を持ちかけます。仲間のリーダーの居場所を白状すれば、お前の命だけは助けてやろう、と。
仲間を裏切る気などないパブロは、死を覚悟し、将校をからかうつもりで全くのでたらめの隠れ場所を告げます。 しかし、その偶然の嘘が、誰も予期しなかった皮肉で不条理な結末を引き起こすことになるのです。 人間の意志や選択が、いかに「偶然」に左右されてしまうのか。サルトルが突きつける冷徹な現実に、読者は震撼させられるでしょう。



本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。
3位『自由への道 第1部 分別ざかり』
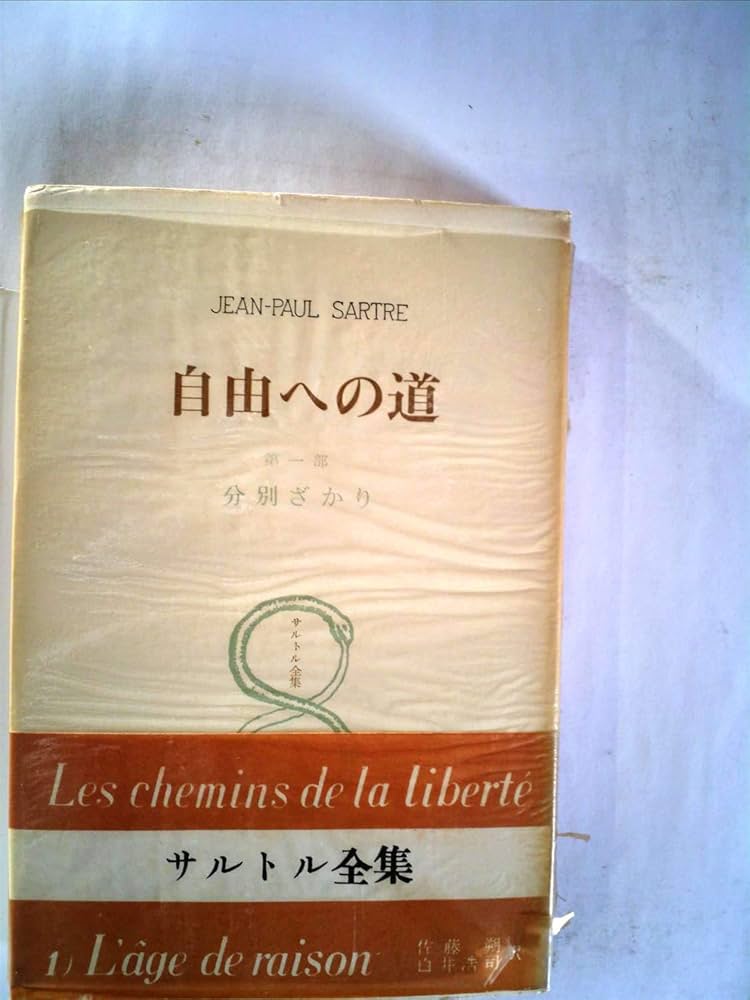
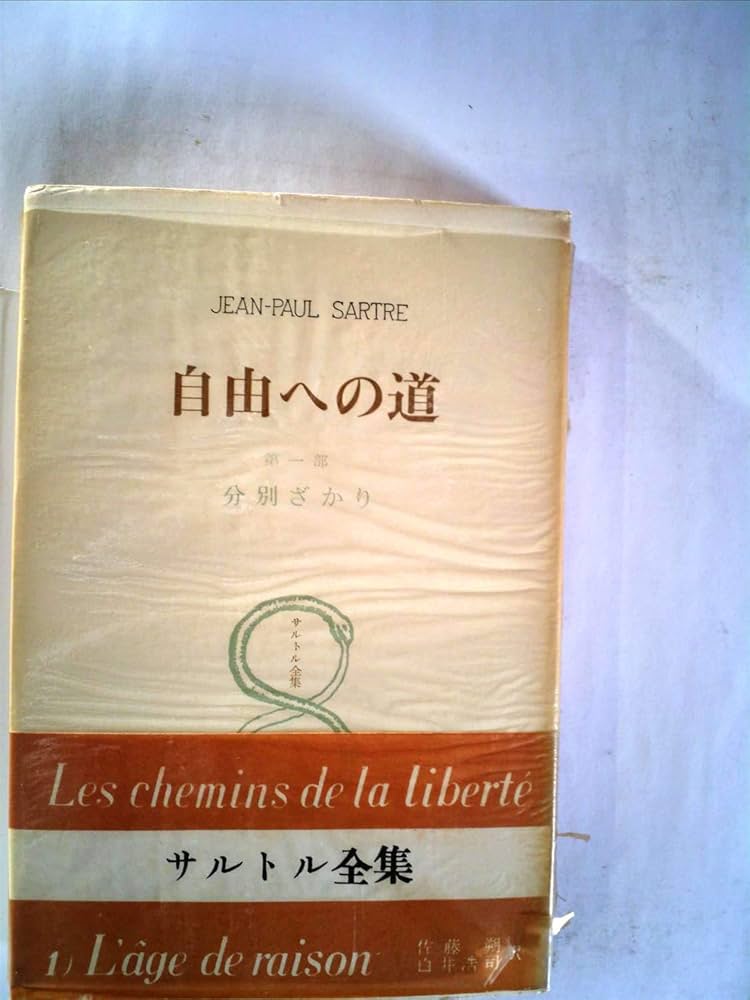
第3位には、サルトルの未完の大河小説『自由への道』の第1部『分別ざかり』がランクインしました。この作品は、これまでの2作とは異なり、より具体的な社会状況の中で「自由」の意味を問う、壮大な物語の幕明けです。
舞台は第二次世界大戦前夜のパリ。主人公は、「自由」を信条とする34歳の哲学教師マチウです。彼は何にも縛られず、自らの意志ですべてを選択する生き方を理想としていました。しかし、長年の恋人マルセルの妊娠をきっかけに、その理想は大きく揺らぎ始めます。
結婚という「束縛」を避けたいマチウは、堕胎のための金策に走り回りますが、その過程で友人や家族との関係がこじれ、自らの選択が他者を巻き込んでいく現実に直面します。観念的な「自由」が、現実の責任を前にしていかに脆いものであるかを突きつけられるマチウの姿は、私たち自身の生き方をも問い直させてくれるでしょう。



自由でいたいって気持ちは分かるけど、マチウの行動はちょっと無責任すぎるかな。でも、そこが人間らしいのかもしれないね。
4位『自由への道 第2部 猶予』
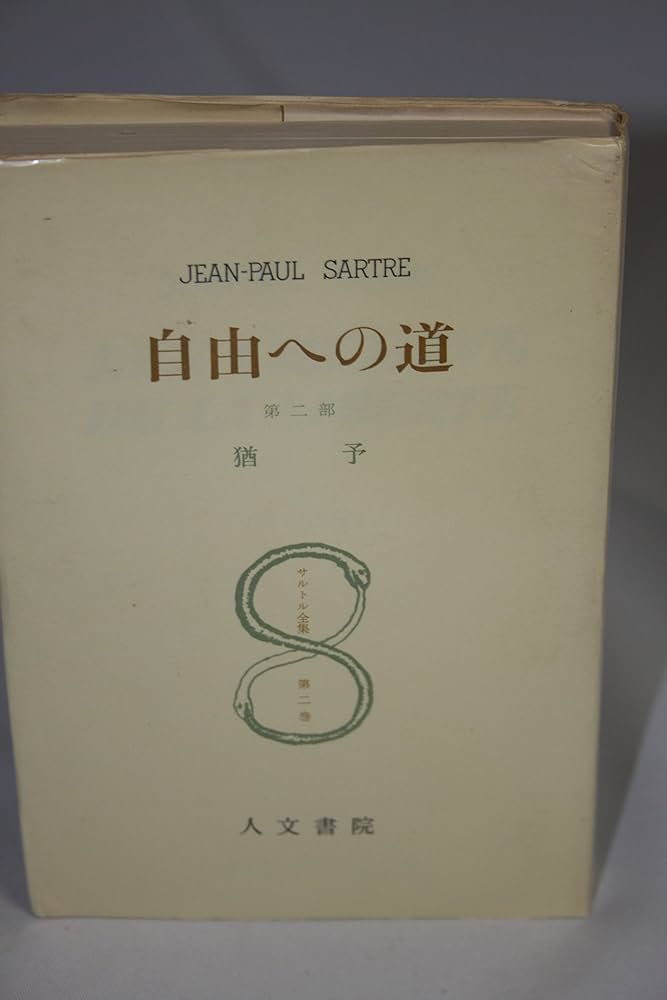
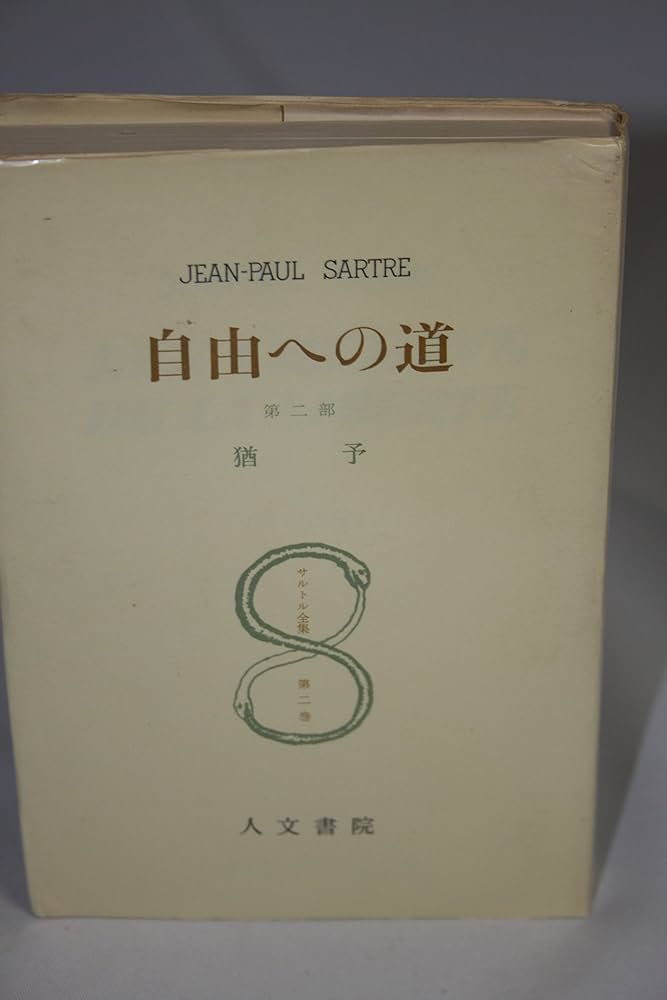
続いて第4位は、『自由への道』の第2部『猶予』です。前作『分別ざかり』が個人の内面的な葛藤に焦点を当てていたのに対し、本作では物語のスケールが一気に拡大し、歴史の大きなうねりが描かれます。
物語の背景となるのは、1938年9月、第二次世界大戦勃発の引き金ともなった「ミュンヘン会談」です。ナチス・ドイツによるチェコスロバキア領土要求をめぐり、ヨーロッパ全土に戦争の危機が迫っていました。サルトルは、この歴史的事件の当事者である政治家たちの動きと、それに翻弄されるマチウをはじめとしたパリの一般市民の姿を、映画のように交互に映し出す手法で描いています。
召集令状を受け取ったマチウは、個人の「自由」がいかに歴史的な状況に左右されるかを痛感します。戦争という巨大な現実を前に、人々はどのような選択を迫られるのか。個人の物語と歴史の物語が交錯する、重厚な一冊です。



個人の悩みと世界の動きが同時に描かれるなんて、すごい構成だよね。自分だったらどうするかなって考えちゃうな。
5位『自由への道 第3部 魂の中の死』


ランキングの最後を飾るのは、『自由への道』三部作の第3部『魂の中の死』です。物語は1940年6月、ナチス・ドイツの侵攻によってフランスが敗北するという絶望的な状況下で展開します。
前作のラストで召集された主人公マチウの部隊は、ろくに戦うこともなく敗走を重ね、ついには上官にも見捨てられてしまいます。降伏を待つだけの無力な状況の中で、これまで観念的な自由にこだわり、主体的な選択から逃げてきたマチウは、ついに一つの決断を下します。
彼は、圧倒的に不利な状況と知りながら、仲間と共にドイツ軍に最後の抵抗を試みるのです。教会の鐘楼に立てこもり、銃弾を一発撃つごとに過去の自分と決別し、生まれて初めて真の「自由」を実感するマチウの姿は、この長大な物語の一つのクライマックスと言えるでしょう。極限状態において、人間はいかにして自らの尊厳をかけて自由を行使するのか。その問いが胸に迫る一作です。



絶望的な状況で、初めて本当の自由を見つけるなんて…。マチウの最後の選択には、なんだか泣けてきちゃうな。
サルトルのおすすめ小説ランキングを参考に、人間の「自由」と向き合う読書体験を
今回は、ジャン=ポール・サルトルのおすすめ小説をランキング形式でご紹介しました。『嘔吐』の哲学的な思索から、『自由への道』の歴史的な群像劇まで、その作風は多岐にわたりますが、一貫して流れているのは「人間はいかにして自由であるか」という根源的な問いです。
サルトルは「人間は自由であり、つねに自分自身の選択によって行動すべきものである」という言葉を残しています。 彼の小説の登場人物たちは、不条理な現実や極限状況に置かれながらも、悩み、苦しみ、そして自らの意志で未来を選択しようとします。その姿は、情報が溢れ、何が正解か分からなくなりがちな現代を生きる私たちに、多くの示唆を与えてくれるはずです。
サルトルの小説は、決して簡単な読書体験ではないかもしれません。しかし、ページをめくるごとに、あなた自身の「自由」や「人生の選択」について深く考えるきっかけとなるでしょう。このランキングを参考に、ぜひサルトルが投げかける問いと向き合う、濃密な読書の時間をお過ごしください。



