あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチのおすすめ作品ランキングTOP5

スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチとは?―ノーベル文学賞作家の素顔と「声の文学」
スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチは、2015年にノーベル文学賞を受賞したベラルーシの作家・ジャーナリストです。彼女の作品は、「我々の時代における苦難と勇気の記念碑と言える多声的な叙述」と評され、世界中で高く評価されています。
1948年にウクライナで生まれ、ベラルーシ人の父とウクライナ人の母を持つアレクシエーヴィチは、大学でジャーナリズムを学んだ後、その道を歩み始めました。彼女の作品の最大の特徴は、歴史の渦に巻き込まれた名もなき人々の「声」に耳を傾ける、徹底したインタビューに基づいている点です。第二次世界大戦に従軍した女性たち、チェルノブイリ原発事故の被災者、ソ連崩壊を経験した人々など、これまで光が当てられてこなかった人々の生々しい証言を集め、文学作品として昇華させています。
この独自の手法は「声の文学」とも呼ばれ、一人ひとりの感情や記憶を丹念に紡ぎ合わせることで、公式の歴史記録からはこぼれ落ちてしまう真実を浮かび上がらせます。国家が語る大きな物語ではなく、個人の小さな物語の集合体から歴史を描き出すその姿勢は、時に政府と対立することもありました。それでもなお、彼女は人々の声に寄り添い、その記憶を後世に伝えるための執筆活動を続けています。
スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチのおすすめ作品ランキングTOP5
ここからは、スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチの数ある傑作の中から、小説ヨミタイ編集部が厳選したおすすめ作品をランキング形式でご紹介します。どの作品も、私たちが知らなかった歴史の側面を、人々の生の声を通して教えてくれるものばかりです。
彼女の作品を読むことは、時に辛い現実に直面することでもあります。しかし、それ以上に、困難な時代を生き抜いた人々の魂の叫びに触れ、深く心を揺さぶられる体験となるでしょう。アレクシエーヴィチ文学の入り口として、ぜひ参考にしてみてください。
1位『戦争は女の顔をしていない』
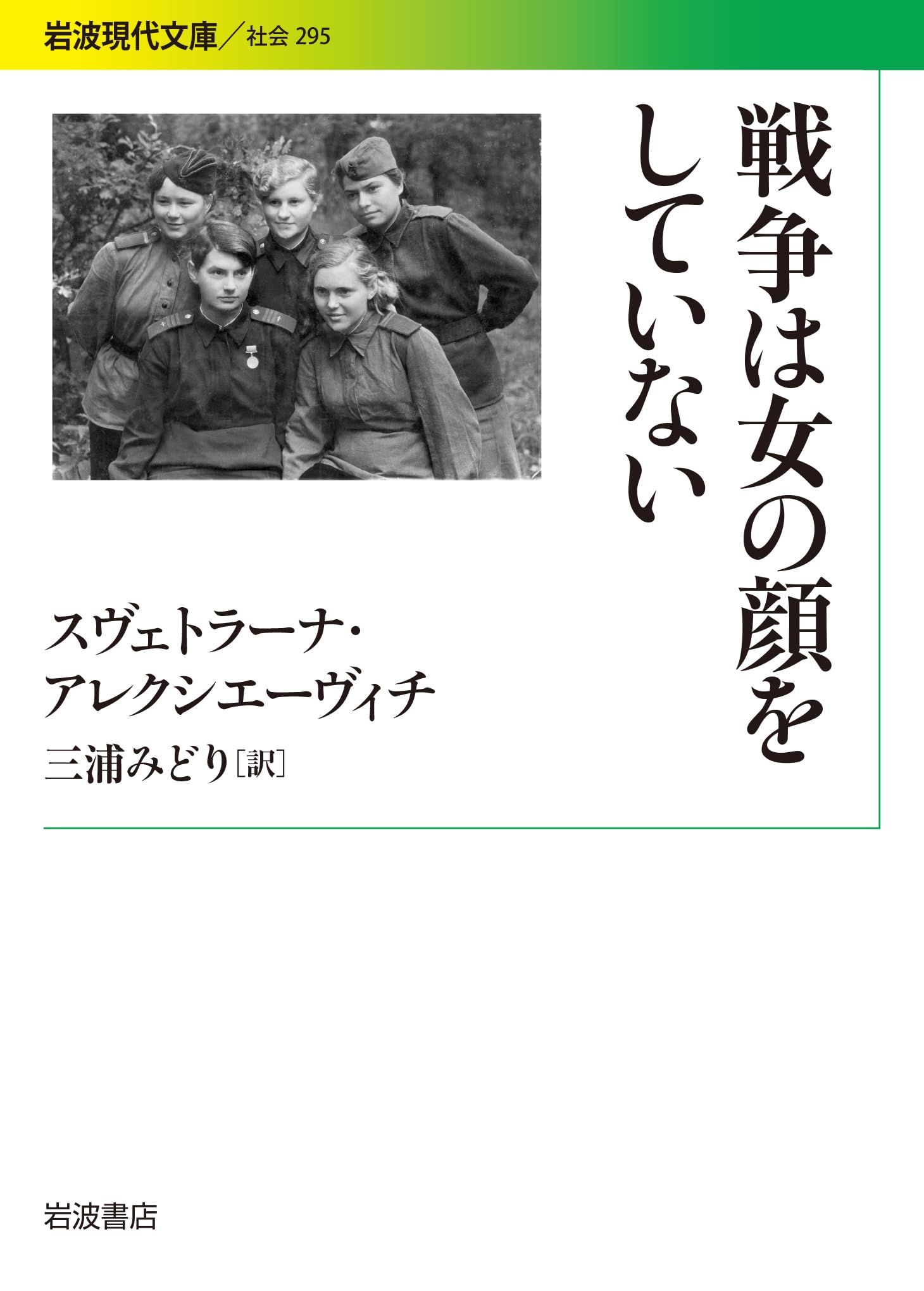
堂々の1位は、アレクシエーヴィチのデビュー作にして主著である『戦争は女の顔をしていない』です。この作品は、第二次世界大戦の独ソ戦において、兵士として武器を手にした100万人以上のソ連の従軍女性たちに光を当てています。著者は500人を超える女性たちに丹念に取材を行い、これまで語られることのなかった「女性の視点から見た戦争」を克明に描き出しました。
狙撃兵、洗濯係、軍医――。様々な立場で戦争に関わった彼女たちの口から語られるのは、英雄譚とはほど遠い、あまりにも生々しい日常の記憶です。戦場で初めて生理を迎えた少女の話や、敵兵を殺した後の罪悪感、そして戦場での恋。そこには、これまで男性の言葉だけで語られてきた戦争の歴史からは見えてこなかった、衝撃的な真実が詰まっています。
さらにこの本が胸に迫るのは、彼女たちが戦後も苦しみ続けたという事実です。英雄として迎えられるどころか、世間から白い目で見られ、自らの過去をひた隠しにして生きなければなりませんでした。歴史から消された声を拾い集めたこの一冊は、私たちに戦争のもう一つの顔を突きつけます。
 ふくちい
ふくちいわたしも読んだけど、これは本当に衝撃的だった…。戦争の悲惨さだけじゃなくて、女性が経験した二重の苦しみが描かれていて、言葉を失ったよ。
2位『チェルノブイリの祈り 未来の物語』


1986年に起きたチェルノブイリ原子力発電所事故。この未曾有の悲劇に巻き込まれた人々の声を丹念に拾い集めたのが、第2位の『チェルノブイリの祈り』です。アレクシエーヴィチは被災地に赴き、事故処理にあたった消防士、故郷を追われた住民、そして放射線の影響で生まれた子どもたちなど、数多くの当事者にインタビューを行いました。
この作品が衝撃的なのは、事故の技術的な解説ではなく、そこに生きた一人ひとりの「個人的な体験」に徹底して焦点を当てている点です。愛する夫が放射性物質そのものになっていく姿を看取った妻の独白。汚染された土地で動物を処分し続けた兵士の苦悩。目に見えない死の恐怖の中で、人々が何を思い、どう生きたのか。その声の集積は、読む者の胸を強く打ちます。
国家による情報の隠蔽や、被災者が受けた差別など、社会的な問題にも鋭く切り込んでいます。福島第一原発事故を経験した私たち日本人にとっても、決して他人事ではない、未来への警鐘と祈りが込められた一冊です。



冒頭の消防士の奥さんの話は、本当に読むのが辛かった…。愛と絶望が入り混じっていて、人間の感情の極限を見た気がするよ。
3位『セカンドハンドの時代――「赤い国」を生きた人びと』
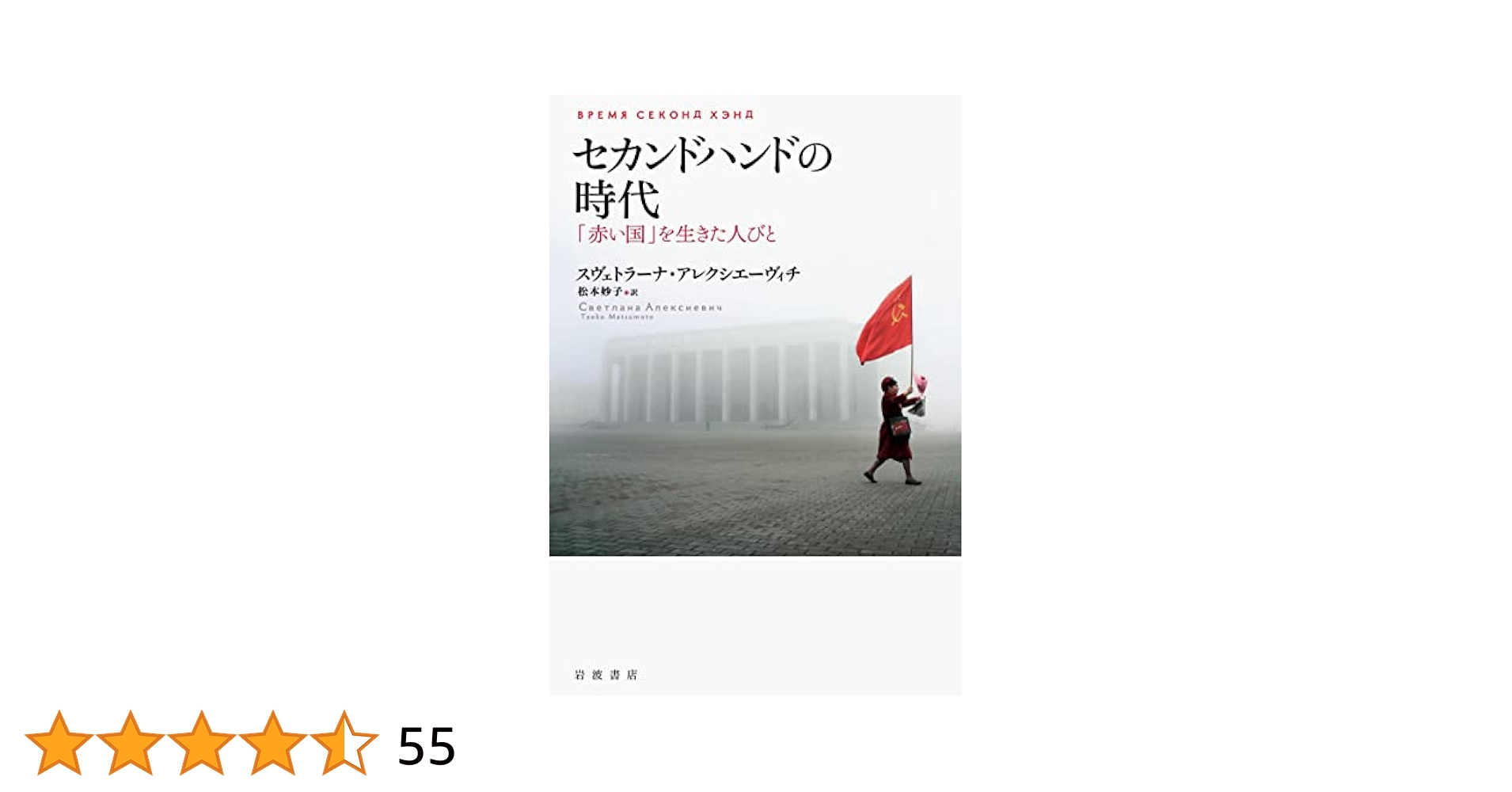
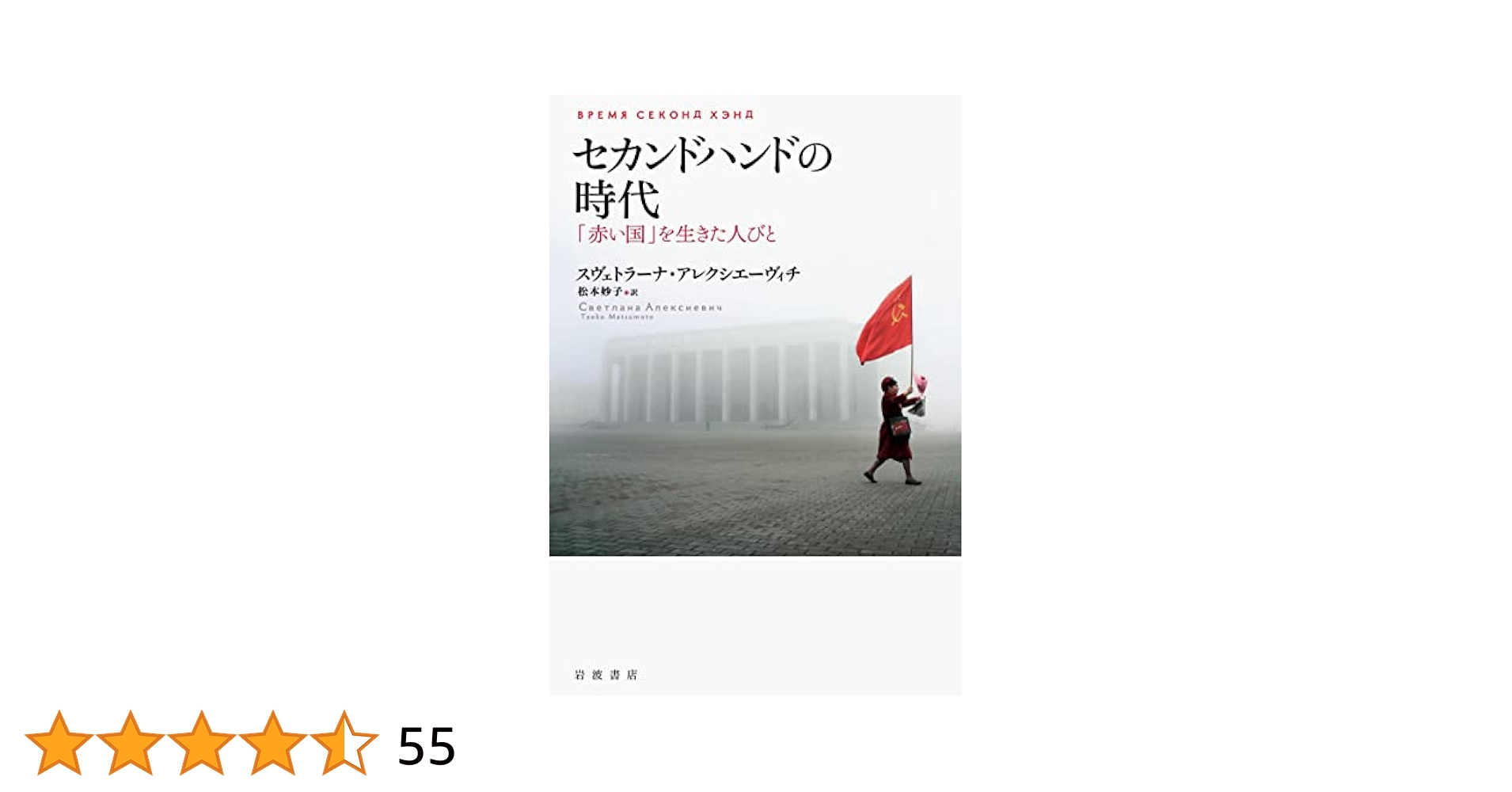
第3位は、1991年のソ連崩壊という歴史的な大転換期を生きた人々の声を集めた『セカンドハンドの時代』です。70年続いた社会主義国家が消滅し、資本主義社会へと移行する中で、人々は何を失い、何を見出したのか。アレクシエーヴィチは、この壮大な記録文学を完成させました。
本書に登場するのは、強制収容所の経験者から、民族紛争を逃れた難民、そしてごく普通の市民まで、実に多様な人々です。ソ連時代を「偉大な時代だった」と懐かしむ声、自由化を歓迎したものの急激な変化に戸惑う声、貧困や格差に苦しむ声。そこには、「赤い国」の記憶と、新しい時代への希望と絶望が複雑に絡み合った、人々の魂の軌跡が刻まれています。
「セカンドハンド」というタイトルは、ソ連という大きな物語を失い、借り物の価値観で生きるしかない人々の空虚感を象徴しています。一つの国家の終わりが、一人ひとりの人生に何をもたらしたのかを問いかける、重厚な一冊です。



ソ連っていう国がなくなった後の人々の話、すごく考えさせられたな。当たり前だったものが全部変わっちゃうって、想像もつかないよ。
4位『亜鉛の少年たち――アフガン帰還兵の証言』
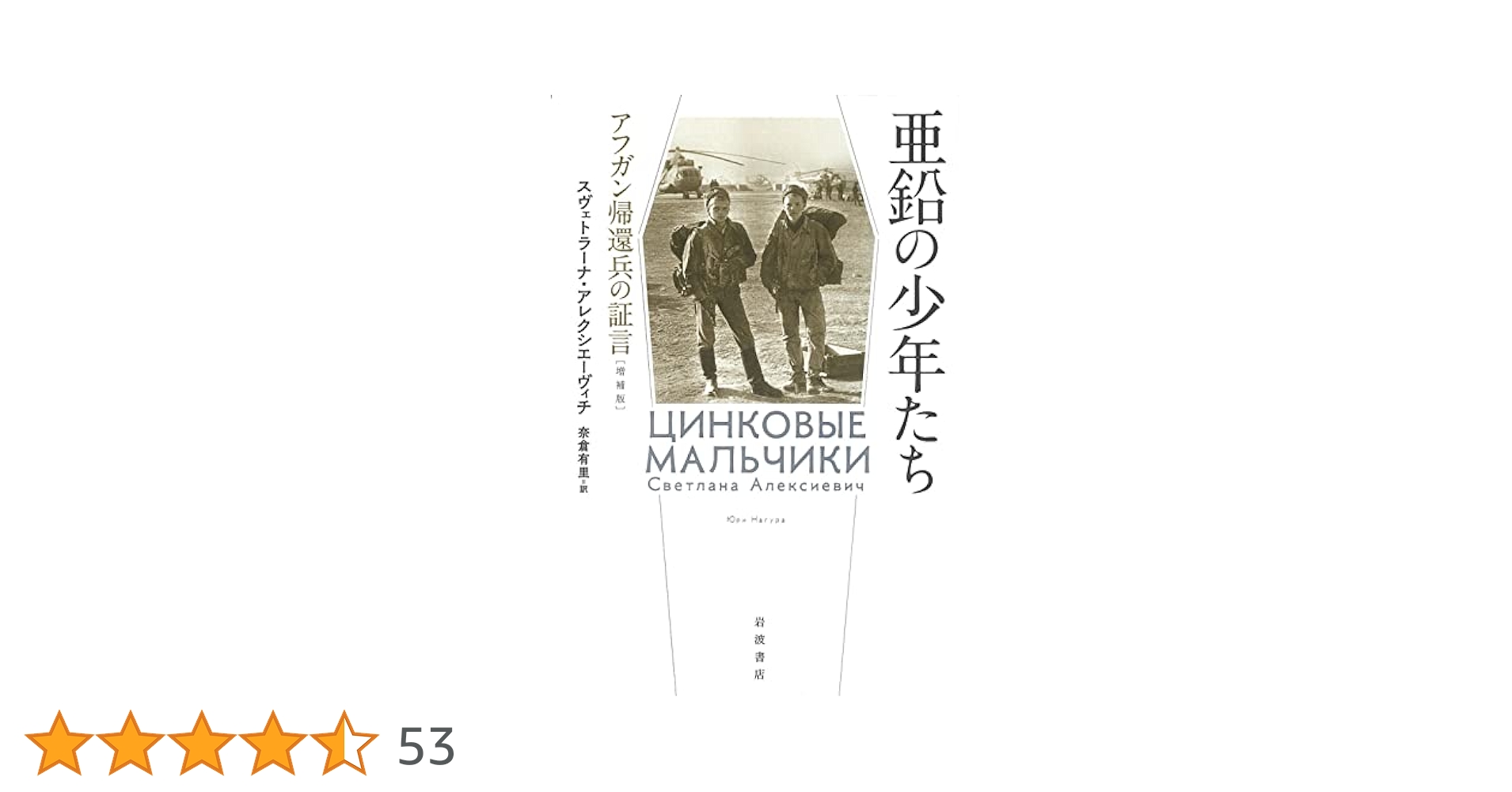
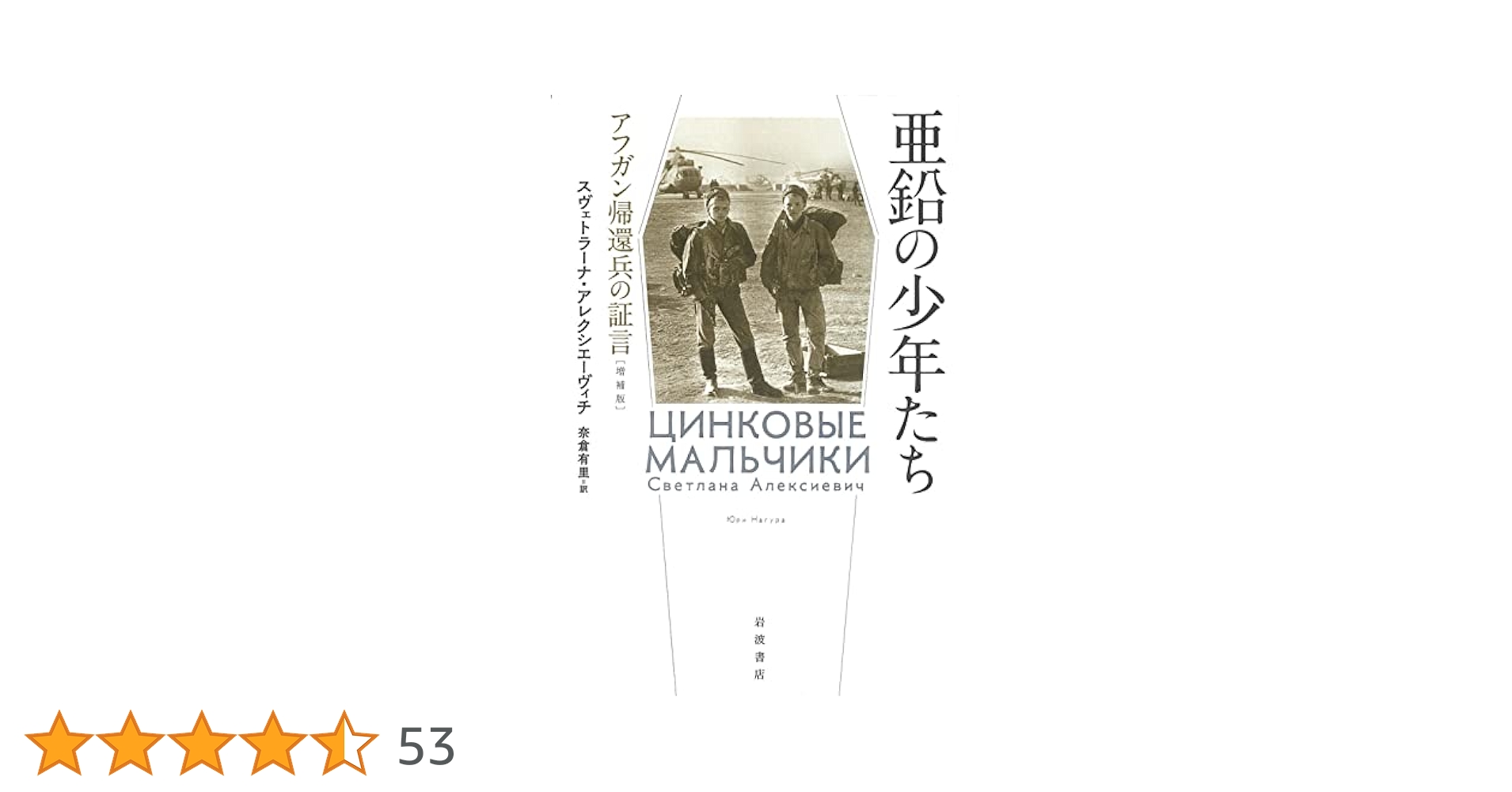
第4位は、1979年から10年間に及んだソ連のアフガニスタン侵攻の真実を、兵士たちの声から明らかにした衝撃作『亜鉛の少年たち』です。当時、ソ連政府はこの戦争を「国際友好の義務を果たす」崇高な任務だと宣伝していました。しかし、戦地から帰還したのは英雄ではなく、心と体に深い傷を負った若者たちでした。
タイトルにある「亜鉛の少年たち」とは、戦死し、亜鉛製の棺に密封されて故郷に戻ってきた若い兵士たちのことを指します。遺族でさえ、その顔を見ることは許されませんでした。アレクシエーヴィチは、生きて戻った帰還兵や、息子を奪われた母親たちに取材を敢行。彼らの口から語られるのは、公式発表とはかけ離れた、殺戮と狂気に満ちた戦場の実態でした。
この本は、国家が隠蔽した戦争の不都合な真実を暴いたことで、発表後に著者自身が裁判に訴えられるという事態にまで発展しました。大義名分のもとで若者の命がどのように使い捨てられていくのかを、痛烈に告発する一冊です。



本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。
5位『ボタン穴から見た戦争――白ロシアの子供たちの証言』
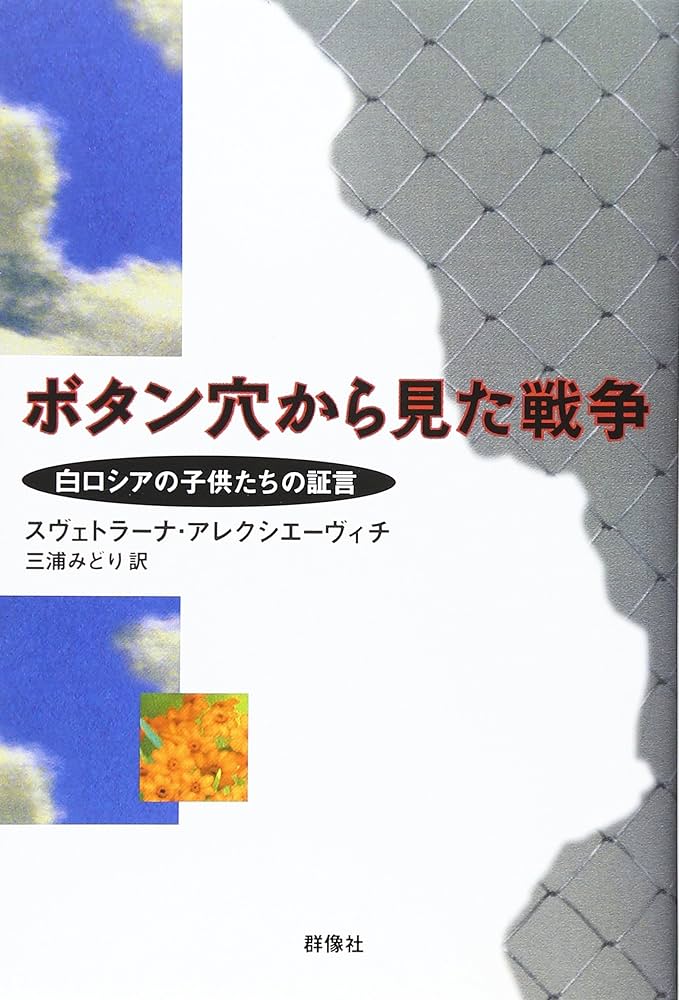
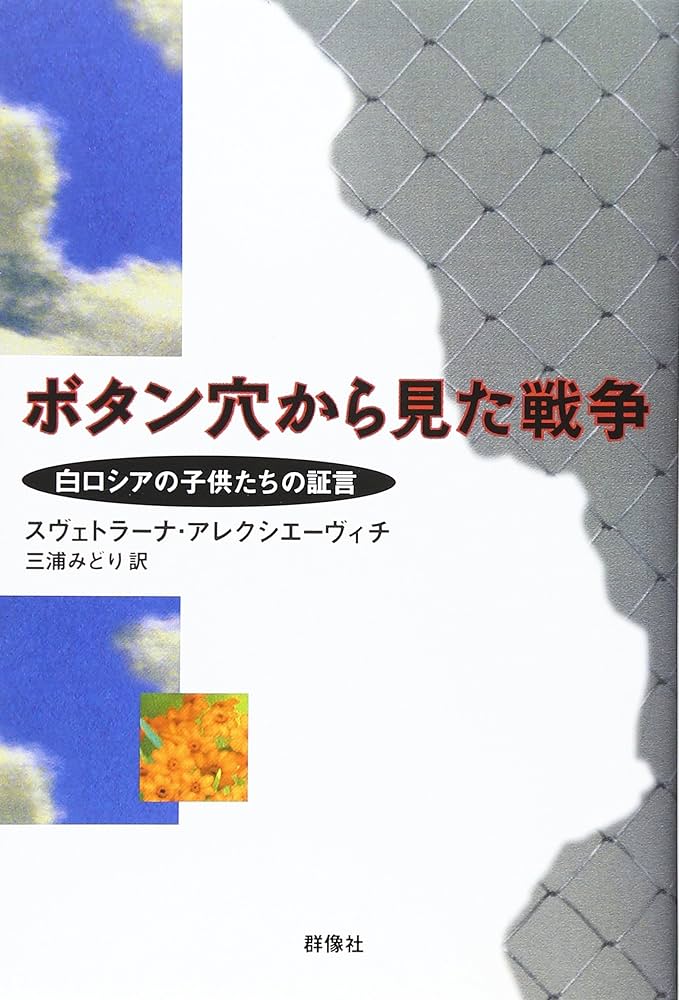
ランキングの最後を飾るのは、『戦争は女の顔をしていない』に続いて発表された『ボタン穴から見た戦争』です。この作品が光を当てるのは、第二次世界大戦中にナチス・ドイツの侵攻を受けたベラルーシで、最も無垢で無力な存在であった子供たちです。
アレクシエーヴィチは、戦争当時に15歳以下だった101人にインタビューを行いました。目の前で母親が撃たれるのを見た記憶、村人が納屋ごと焼き殺される光景、孤児としてさまよった日々――。大人のように状況を整理したり、イデオロギーで解釈したりすることなく、ただ「見たまま」を語る子供たちの言葉は、戦争の残酷さを最も直接的に私たちの胸に突き刺します。
「爆弾が落ちてくるところを、怖くてオーバーを被りながらボタンの穴から見ていた」という一人の少女の証言は、そのまま本書の邦題にもなっています。子供たちの純粋な視点を通して語られるからこそ、戦争の非人間性がより一層際立つ、忘れがたい一冊です。



子供の視点だからこそ、戦争の異常さが際立つんだよね…。無垢な言葉が一番心に刺さるよ。




