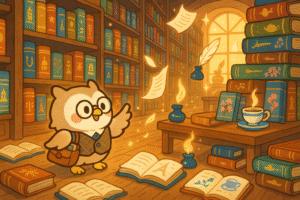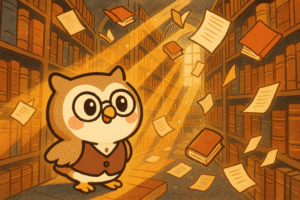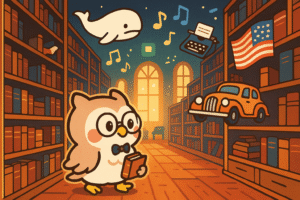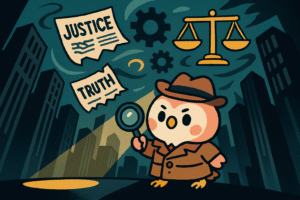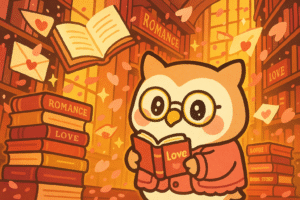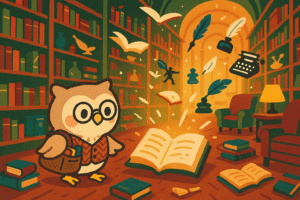あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】ノーベル文学賞のおすすめランキングTOP20

ノーベル文学賞とは?文学界最高峰の栄誉
ノーベル文学賞は、ダイナマイトの発明者として知られるスウェーデンのアルフレッド・ノーベルの遺言に基づいて創設されたノーベル賞の一部門です。物理学、化学、生理学・医学、平和、そして経済学と並ぶ賞の一つで、1901年から授与が始まりました。
ノーベルの遺言には、「文学の分野で理想主義的傾向の最も優れた作品を創作した人物に」賞を贈るよう記されています。この賞は特定の一作品に与えられるのではなく、作家の生涯にわたる文学活動全体が評価の対象となります。ただし、選考の上で特に重要とされた作品名が挙げられることもあります。選考はスウェーデン・アカデミーが担当し、その過程は50年間秘密にされるなど、その権威と注目度は文学賞の中でも最高峰と言えます。
【2025年最新】ノーベル文学賞のおすすめ作品ランキングTOP20
ノーベル文学賞と聞くと、少し難しそうなイメージがあるかもしれません。しかし、受賞作家たちの作品は、時代や国境を越えて人々の心を揺さぶる普遍的なテーマを描いたものが数多くあります。
ここでは、そんなノーベル文学賞受賞作家の作品の中から、特に読みやすく、文学の面白さを存分に味わえるおすすめの20作品をランキング形式でご紹介します。歴史に名を刻んだ巨匠たちの世界に、ぜひ触れてみましょう。
1位『百年の孤独』 ガブリエル・ガルシア=マルケス
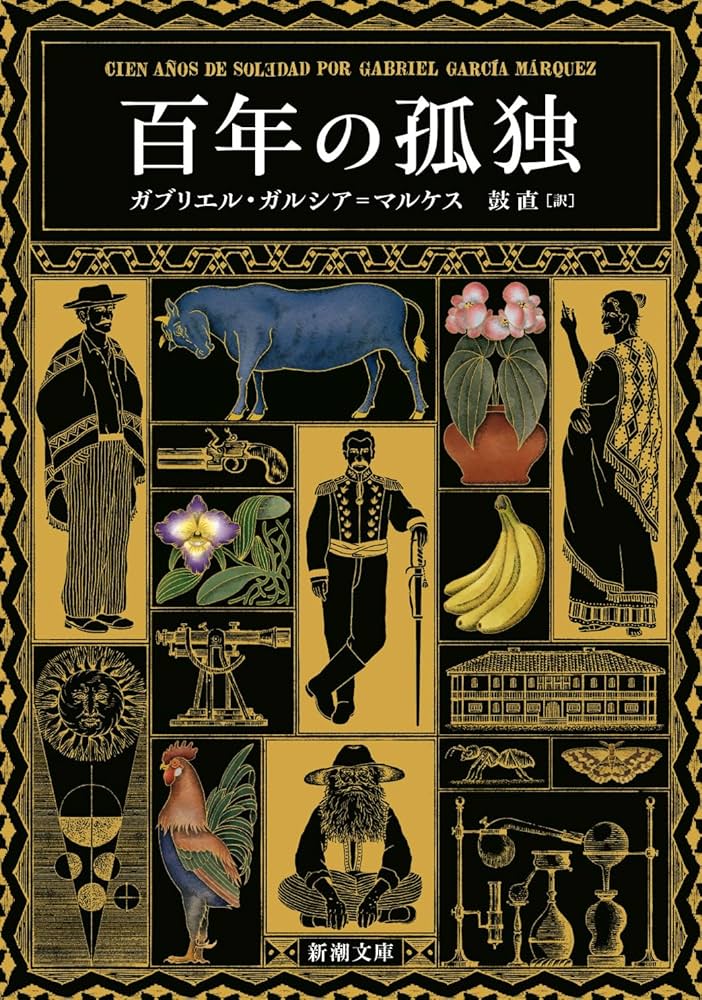
1982年にノーベル文学賞を受賞したガブリエル・ガルシア=マルケスの代表作、『百年の孤独』。南米コロンビアの架空の村マコンドを舞台に、創設者一族であるブエンディア家の百年にわたる栄枯盛衰を描いた物語です。
この作品の最大の特徴は、現実と幻想が入り混じる「マジックリアリズム」という独特な手法です。幽霊が当たり前のように現れたり、空から黄色い花が降り続いたりと、不思議な出来事が日常として描かれます。壮大な一族の歴史を通して、人間の愛や孤独、運命といった普遍的なテーマが浮かび上がる、まさに文学の金字塔です。
 ふくちい
ふくちい一族の歴史が壮大すぎて、家系図をメモしながら読んだよ。不思議な世界観にどっぷり浸れるのが最高なんだ!
2位『老人と海』 アーネスト・ヘミングウェイ
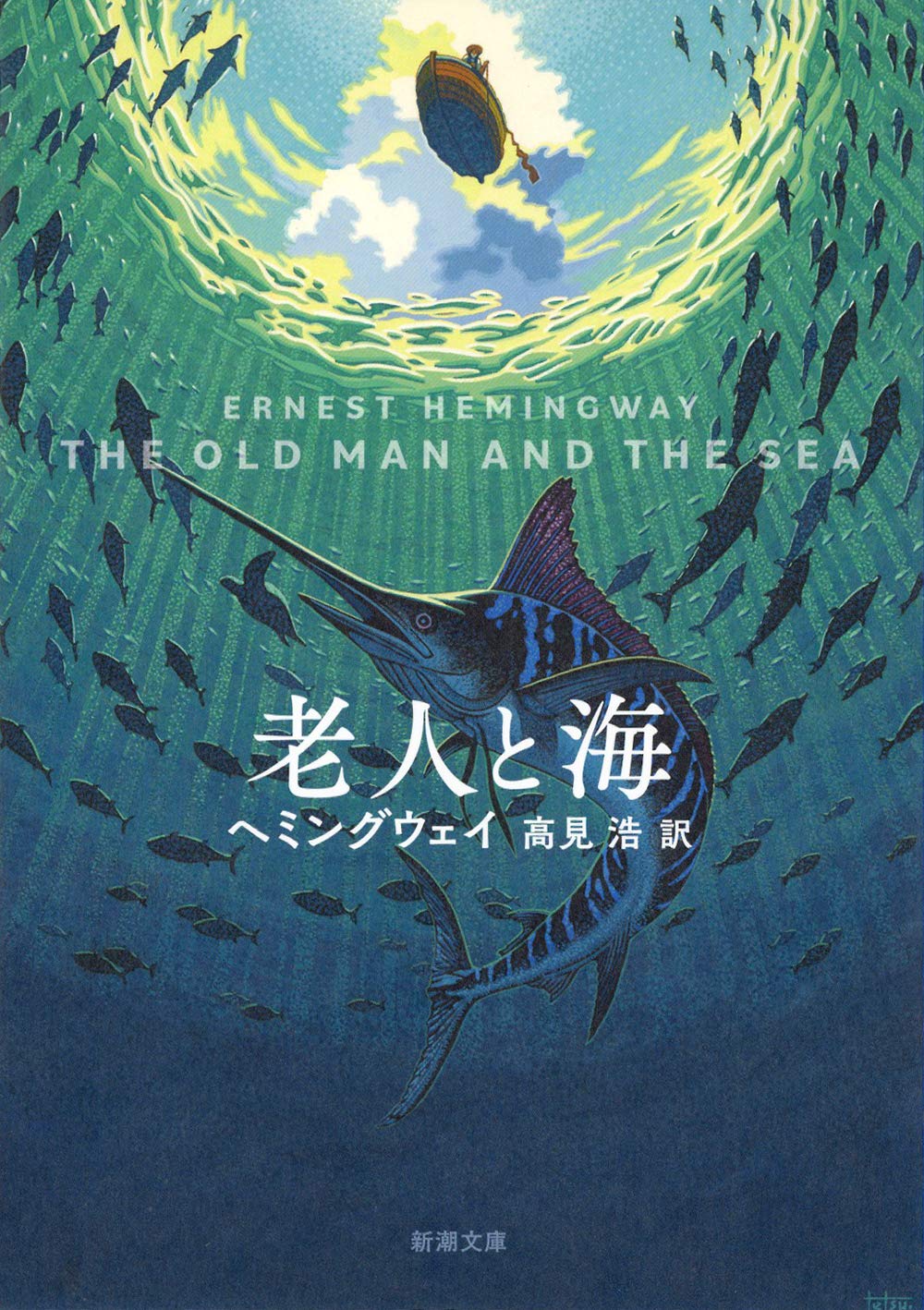
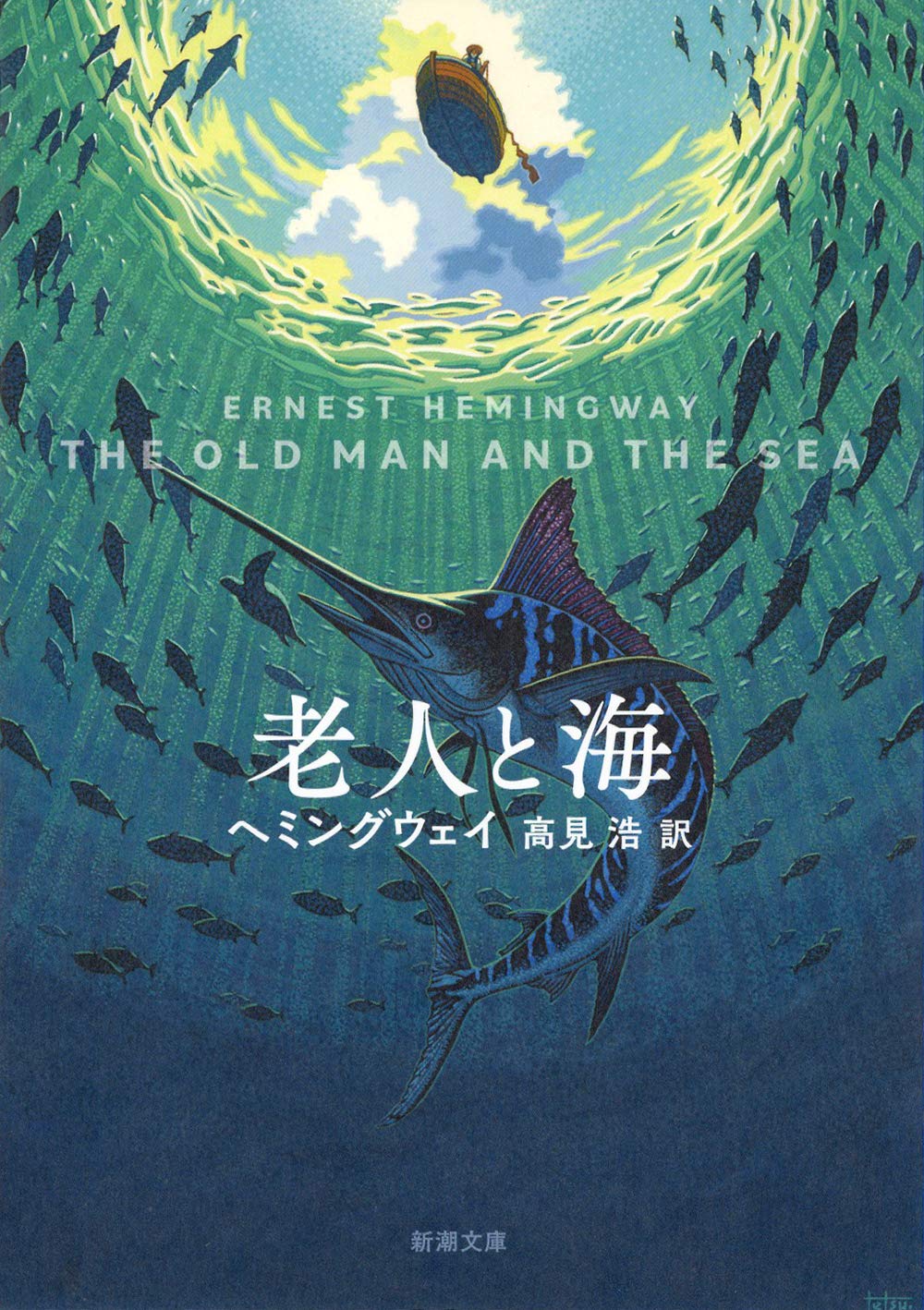
1954年にノーベル文学賞を受賞したアメリカの文豪、アーネスト・ヘミングウェイ。彼の受賞理由として高く評価されたのが、この『老人と海』です。キューバの老漁師サンチャゴが、巨大なカジキを相手に繰り広げる孤独な死闘を描いています。
84日間も不漁が続く中、ついに大物を釣り上げた老人の不屈の精神。その姿を通して、「人間は負けるようには作られていない」という有名な一節に象徴される、人間の尊厳や誇りが力強く描かれています。ヘミングウェイ特有の簡潔で力強い文体も魅力で、ページ数は少ないながらも、読後に深い余韻を残す傑作です。



短いお話なのに、読み終わった後の満足感がすごいんだ。サンチャゴの諦めない心に、勇気をもらえるよ。
3位『異邦人』 アルベール・カミュ
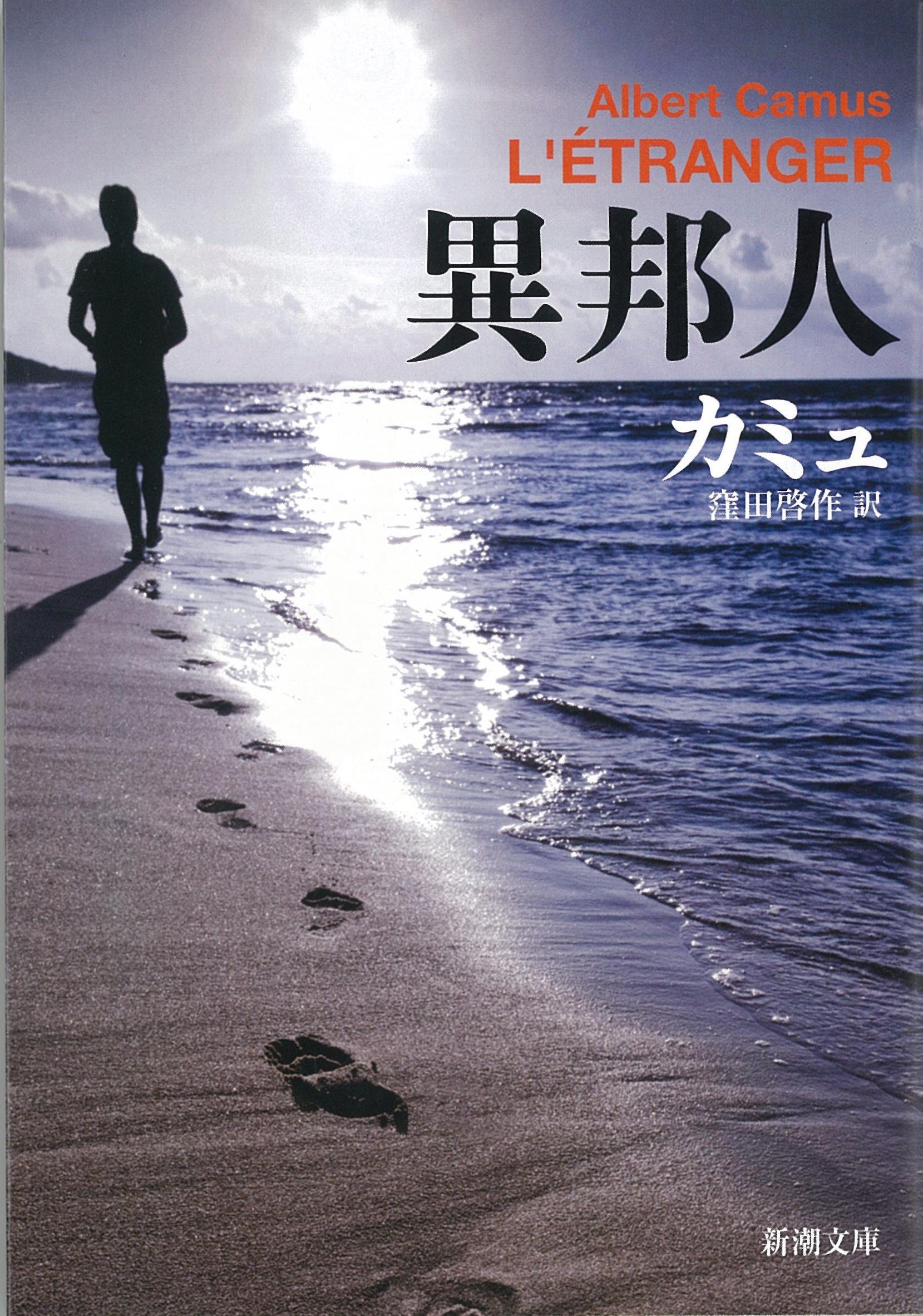
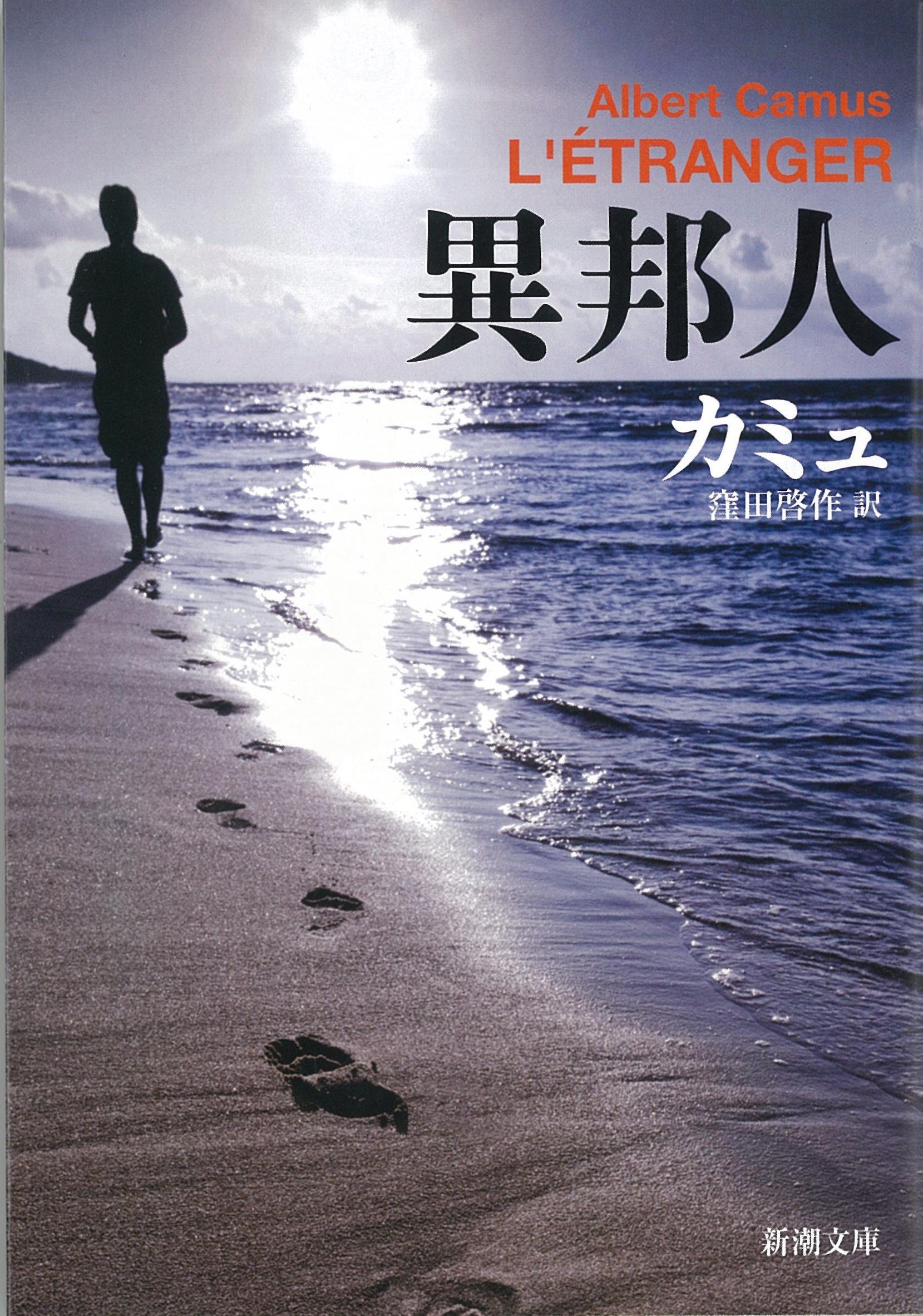
1957年にノーベル文学賞を受賞したフランスの作家、アルベール・カミュ。彼の名を世界に知らしめたのが、この『異邦人』です。物語は、主人公のムルソーが母親の死の翌日に海水浴に行くという、衝撃的な場面から始まります。
感情や社会の常識に無関心なムルソーが、太陽の眩しさを理由に殺人を犯し、裁判にかけられていく姿を通して、人生の「不条理」というテーマが突きつけられます。なぜ彼は罪を犯したのか、そして社会と相容れない彼の存在は何を意味するのか。読者に鋭い問いを投げかける、20世紀文学を代表する一冊です。



主人公のムルソーの気持ちが全然わからなくて、ちょっと戸惑ったかな。でも、だからこそ色々考えさせられる作品なんだよね。
4位『雪国』 川端康成
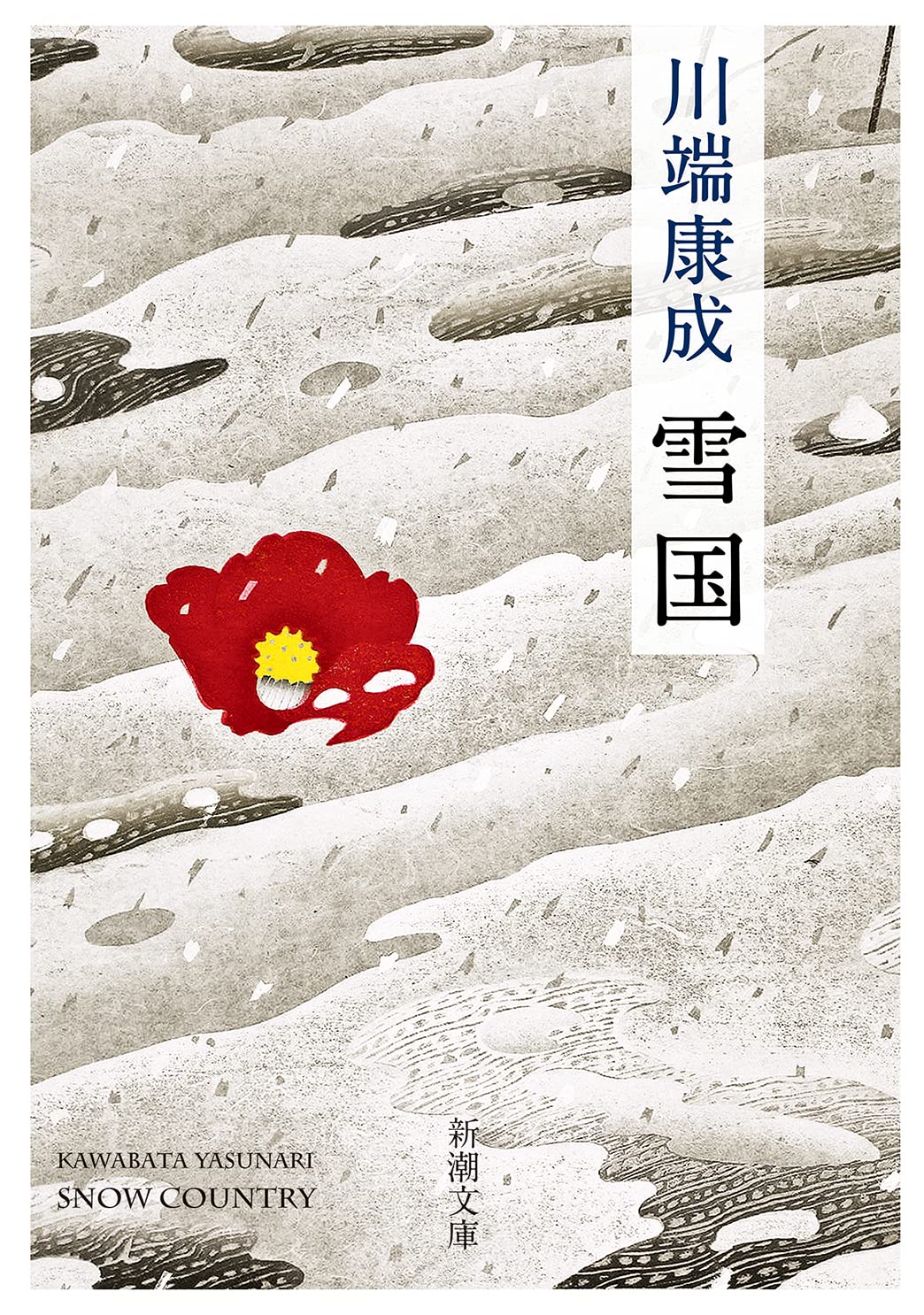
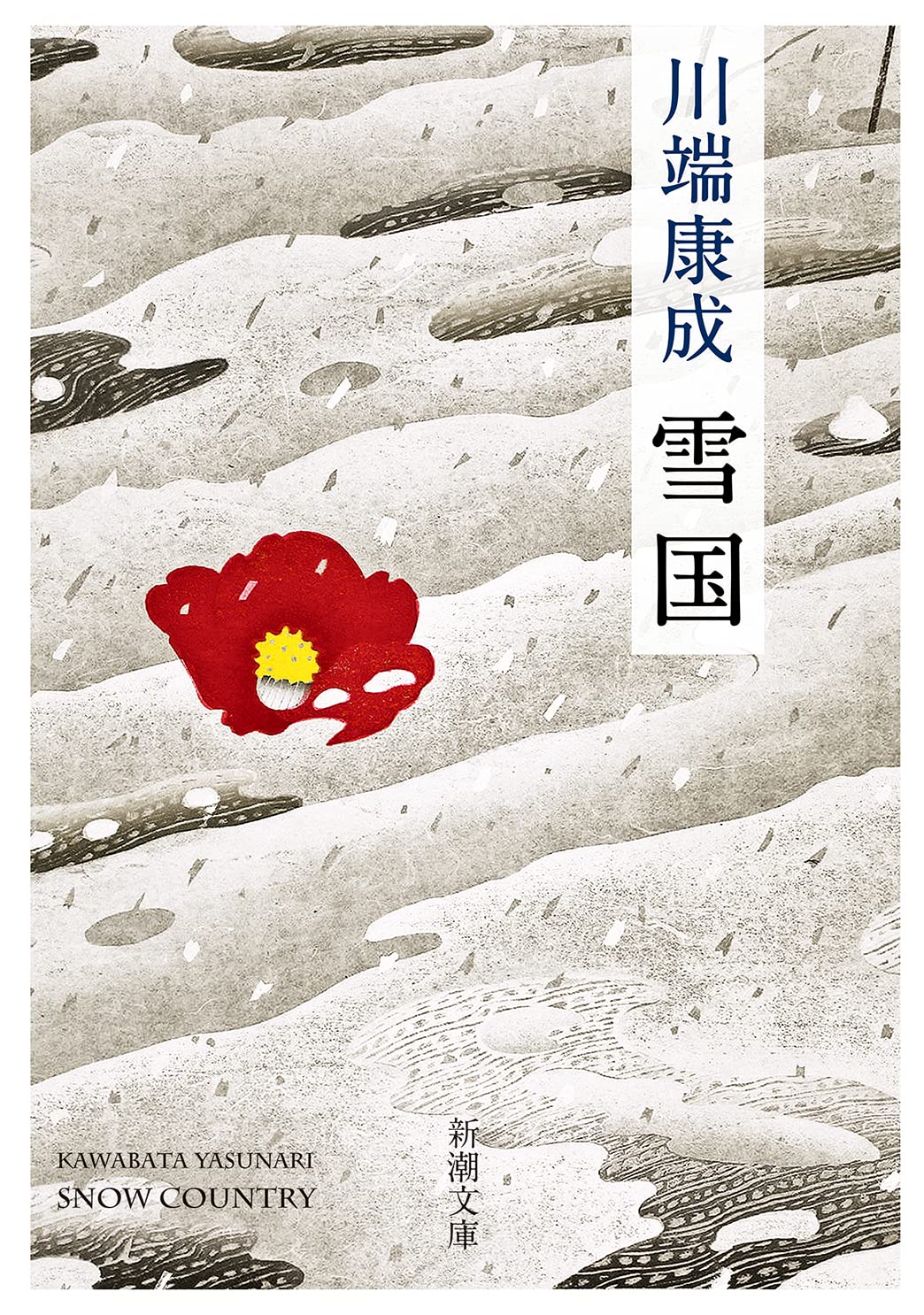
1968年、日本人として初めてノーベル文学賞を受賞した川端康成。受賞理由として「日本人の心の精髄を、すぐれた感受性をもって表現する芸術的手腕」が高く評価されました。その代表作が、この『雪国』です。
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」という、あまりにも有名な一文で始まるこの物語。雪深い温泉町を舞台に、妻子ある男・島村と、芸者・駒子の儚くも美しい恋愛模様が描かれます。日本の伝統的な美意識や、登場人物たちの繊細な心の機微が、研ぎ澄まされた文章で表現されており、読む者の心を静かに揺さぶります。



文章が本当に綺麗で、まるで美しい絵画を見ているみたいだったよ。日本の美しさを再発見できる作品だね。
5位『わたしを離さないで』 カズオ・イシグロ
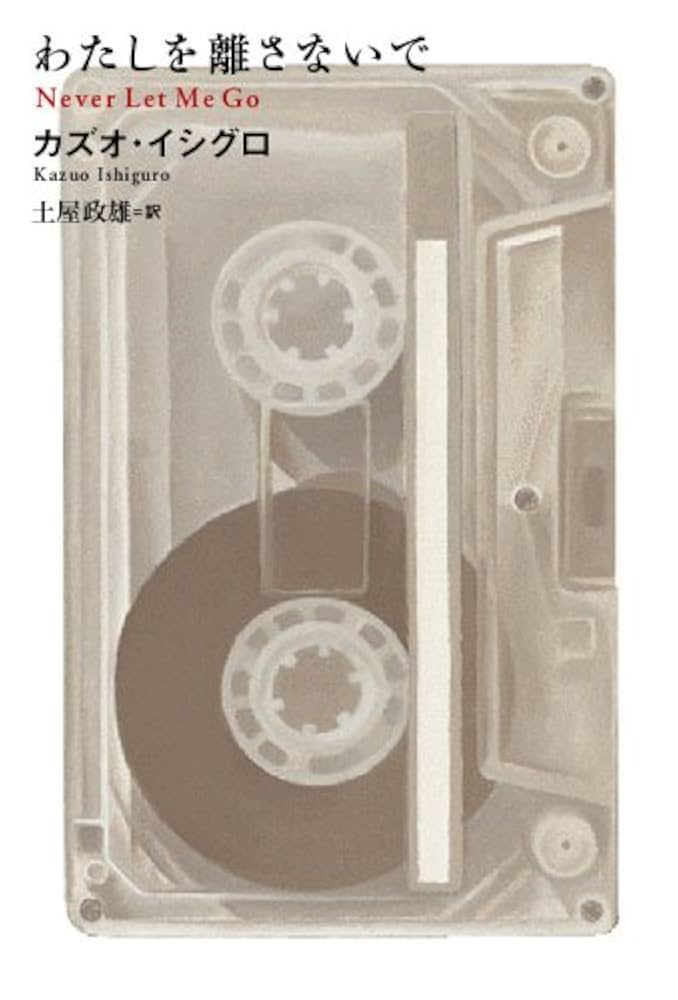
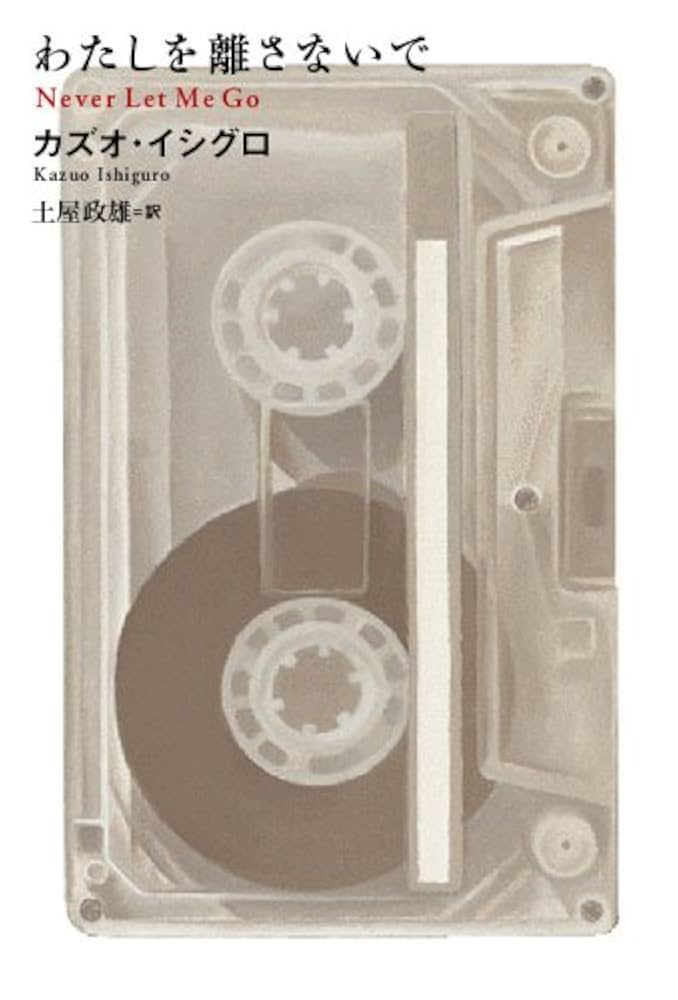
2017年にノーベル文学賞を受賞した日系イギリス人作家、カズオ・イシグロ。彼の作品の中でも特に人気が高いのが、この『わたしを離さないで』です。外界から隔絶された施設で育ったキャシー、ルース、トミーの3人の友情と恋愛、そして彼らに課せられた過酷な運命を描いています。
物語は穏やかに進みますが、徐々に明かされていく衝撃の事実に、読者は心を強く揺さぶられます。生命倫理や人間の尊厳といった重いテーマを扱いながらも、登場人物たちの切ない感情が胸に迫る、感動的な一作です。SF的な設定でありながら、普遍的な愛の物語として多くの人の心を掴んでいます。



読み終わった後、しばらく動けなくなっちゃった…。切ないけど、すごく大切なことを教えてくれる物語だよ。
6位『怒りの葡萄』 ジョン・スタインベック
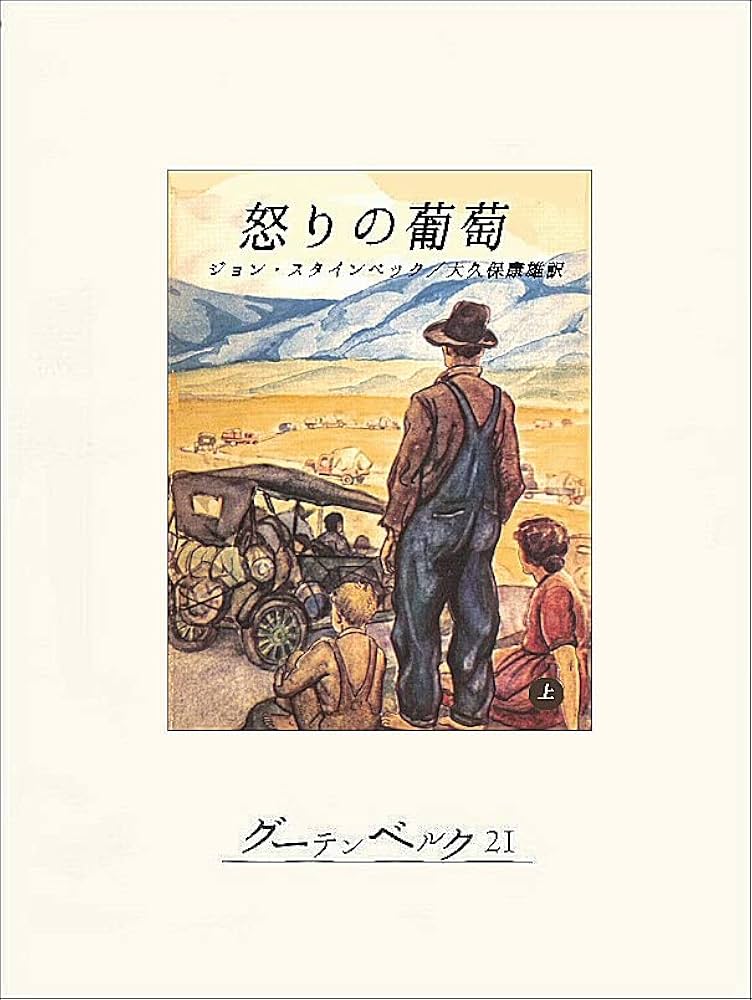
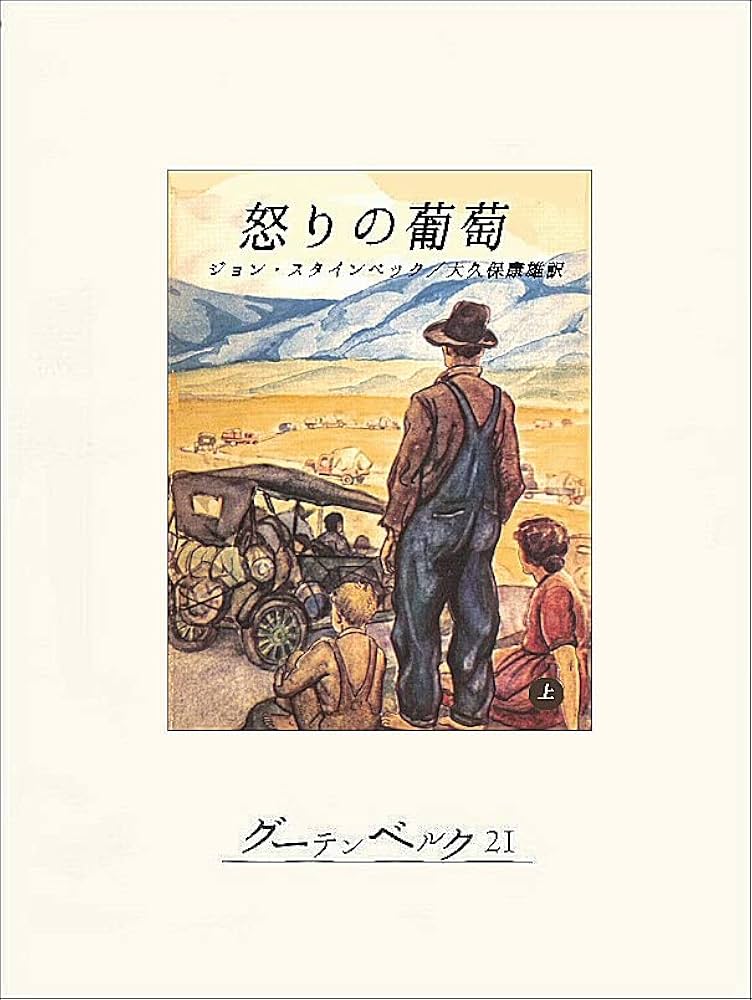
1962年にノーベル文学賞を受賞したアメリカの作家、ジョン・スタインベック。彼の代表作である『怒りの葡萄』は、1930年代の世界恐慌時代のアメリカを舞台にした社会派小説です。
不況と自然災害で土地を追われた小作農一家・ジョード家が、希望を求めて故郷オクラホマからカリフォルニアへと旅をする過酷な道のりを描いています。貧困や搾取といった社会の矛盾に直面しながらも、力強く生き抜こうとする人々の姿は、時代を超えて読む者の胸を打ちます。アメリカ文学の古典として、今なお多くの人々に読み継がれている不朽の名作です。



家族の絆の強さに感動したよ。どんなに辛い状況でも、希望を捨てちゃいけないって思わせてくれるんだ。
7位『万延元年のフットボール』 大江健三郎
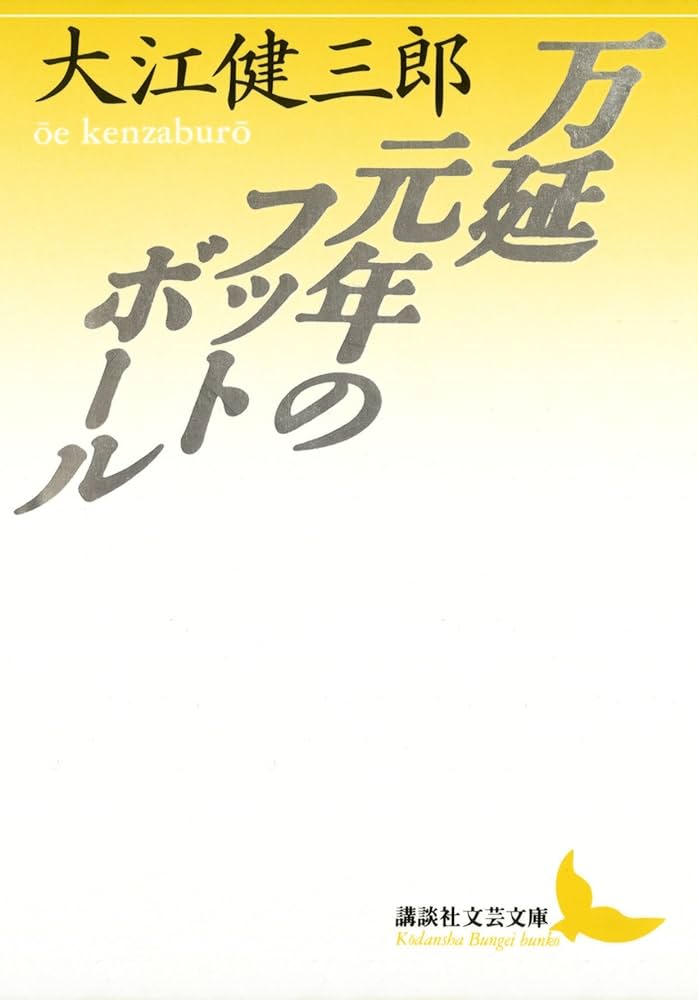
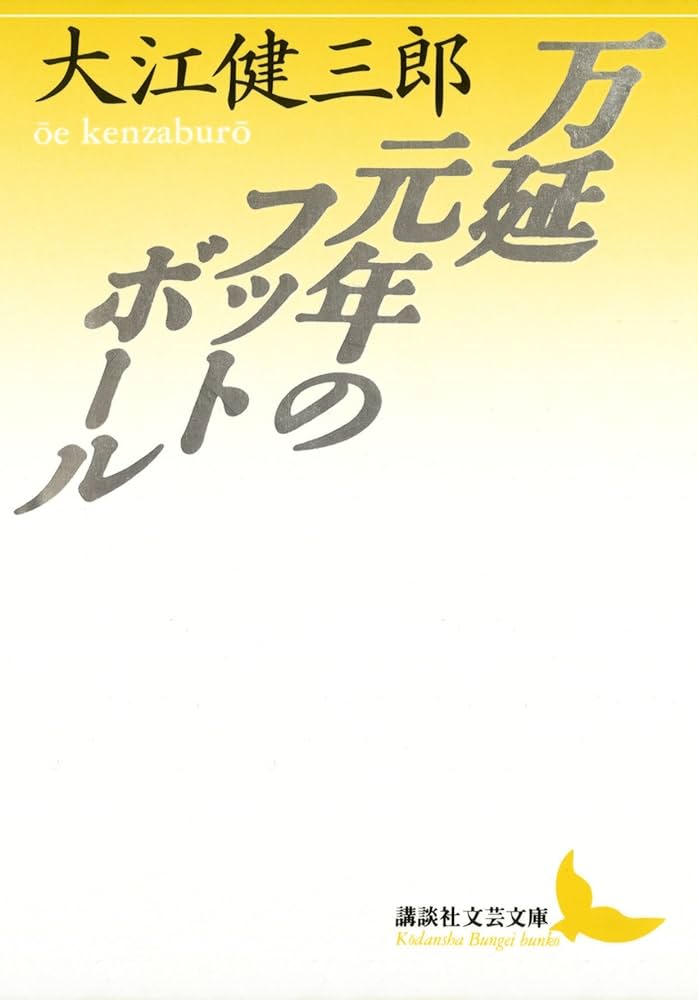
1994年に川端康成に次いで日本人で2人目のノーベル文学賞を受賞した大江健三郎。彼の初期の代表作が、この『万延元年のフットボール』です。都会での生活に敗れた主人公・蜜三郎が、障害を持つ弟・鷹四と共に、四国の谷間の村に帰郷するところから物語は始まります。
村の歴史と神話、そして兄弟の過去が複雑に絡み合いながら、物語は展開していきます。戦後日本の社会や、人間の魂の救済といった重厚なテーマを、独特の文体で描いた作品です。少し難解な部分もありますが、その力強い物語は読む者に強烈な印象を残します。



ちょっと難しいけど、物語のパワーがすごくて引き込まれちゃった。歴史と現代が繋がる感覚が面白いんだよね。
8位『戦争は女の顔をしていない』 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
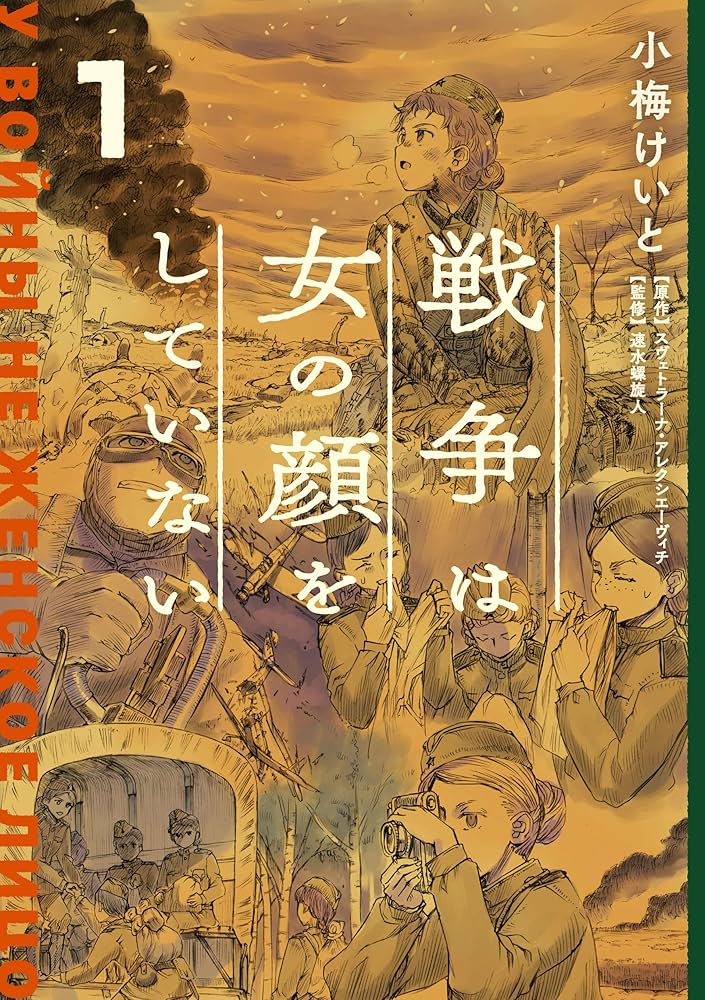
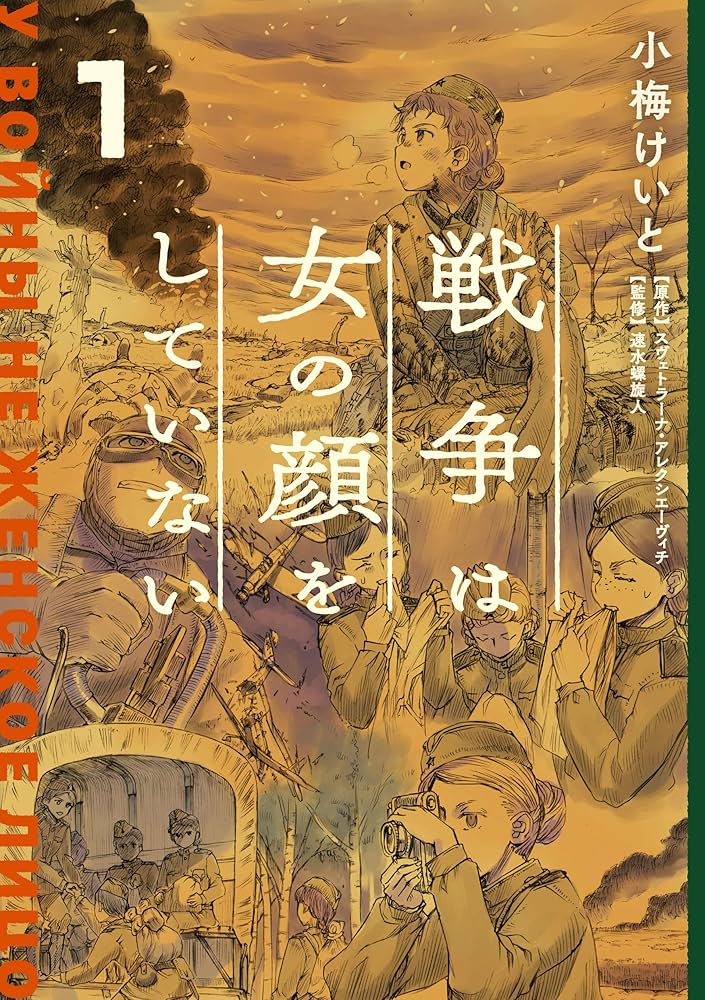
2015年にノーベル文学賞を受賞したベラルーシの作家、スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ。彼女は、多くの人々の声を集めて歴史を描く「声の小説」という独自の手法で知られています。本作は、第二次世界大戦に従軍した500人以上の女性たちの証言をまとめたノンフィクション作品です。
これまで語られることの少なかった、女性から見た戦争の真実がここにあります。兵士として、看護師として、あるいはパルチザンとして戦争を生き抜いた女性たちの生々しい声は、戦争の悲惨さと非人間性を克明に伝えます。歴史の裏側に埋もれていた声に耳を傾ける、貴重な一冊です。



本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。
9位『魔の山』 トーマス・マン
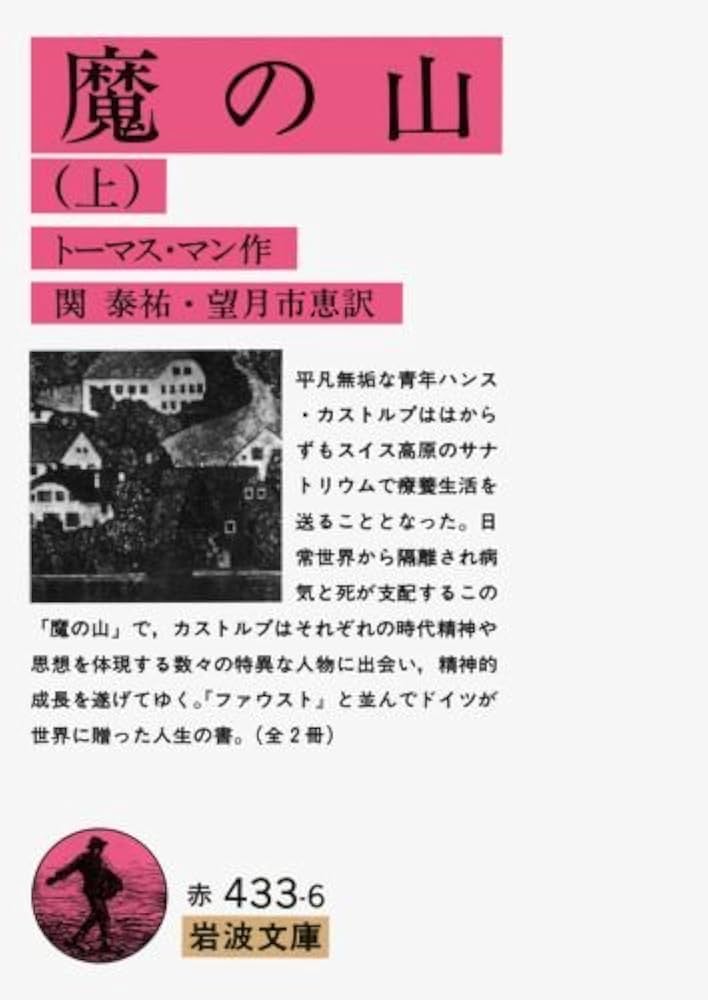
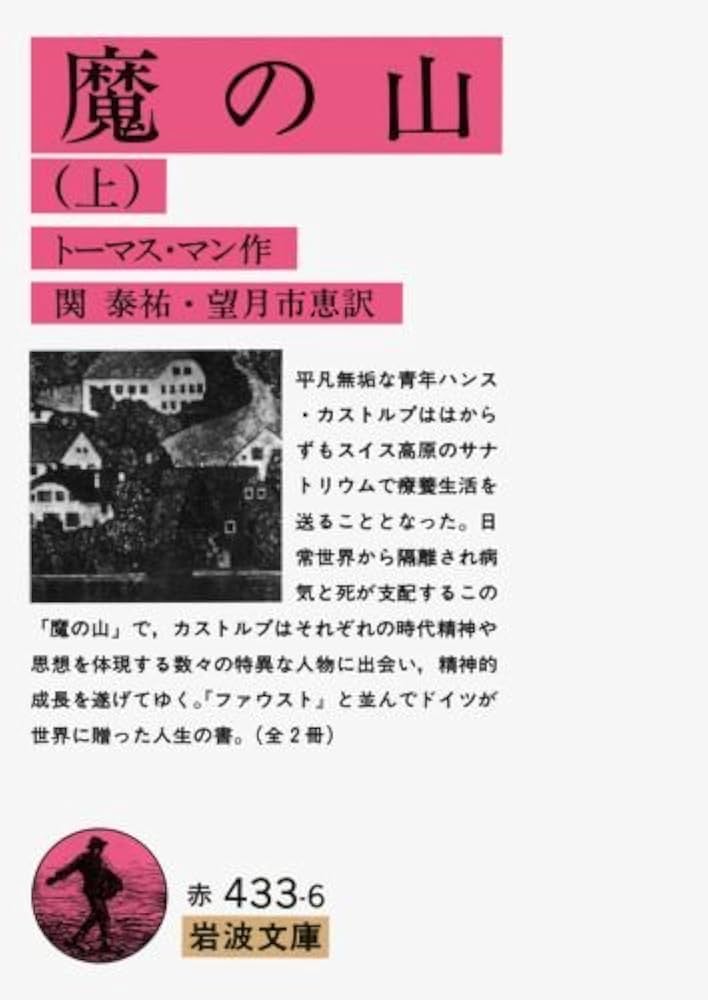
1929年にノーベル文学賞を受賞したドイツの文豪、トーマス・マン。彼の代表作の一つである『魔の山』は、第一次世界大戦前のヨーロッパを舞台にした長編教養小説です。
主人公の青年ハンス・カストルプが、いとこを見舞うために訪れたスイスのサナトリウム(療養所)で、7年間を過ごす物語です。閉ざされた療養所での様々な人々との交流を通して、時間、生と死、病、愛といった哲学的なテーマが深く掘り下げられていきます。ヨーロッパの知性が凝縮されたような、重厚で読み応えのある作品です。



すごく長いお話だけど、登場人物たちの会話が哲学的で面白いんだ。じっくり時間をかけて読むのがおすすめだよ。
10位『ブリキの太鼓』 ギュンター・グラス
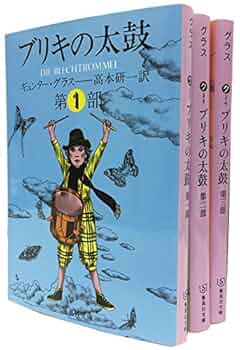
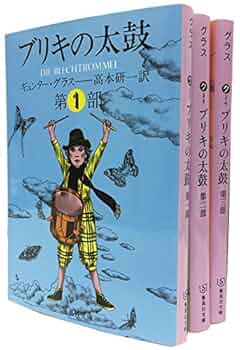
1999年にノーベル文学賞を受賞したドイツの作家、ギュンター・グラス。戦後ドイツ文学の最も重要な作品の一つと称されるのが、この『ブリキの太鼓』です。物語は、3歳の誕生日に自らの意思で成長を止めた少年オスカルの視点から語られます。
オスカルは、奇声でガラスを割り、ブリキの太鼓を叩き続けることで、大人たちの醜い世界に抵抗します。彼の目を通して、ナチスが台頭し、戦争へと突き進んでいく時代の狂気が、グロテスクかつユーモラスに描かれます。パワフルで独創的な世界観が魅力の、一度読んだら忘れられない強烈な作品です。



主人公のオスカルがとっても個性的!彼の視点から見る世界は、ちょっと怖いけどすごく引き込まれるんだ。
11位『蠅の王』 ウィリアム・ゴールディング
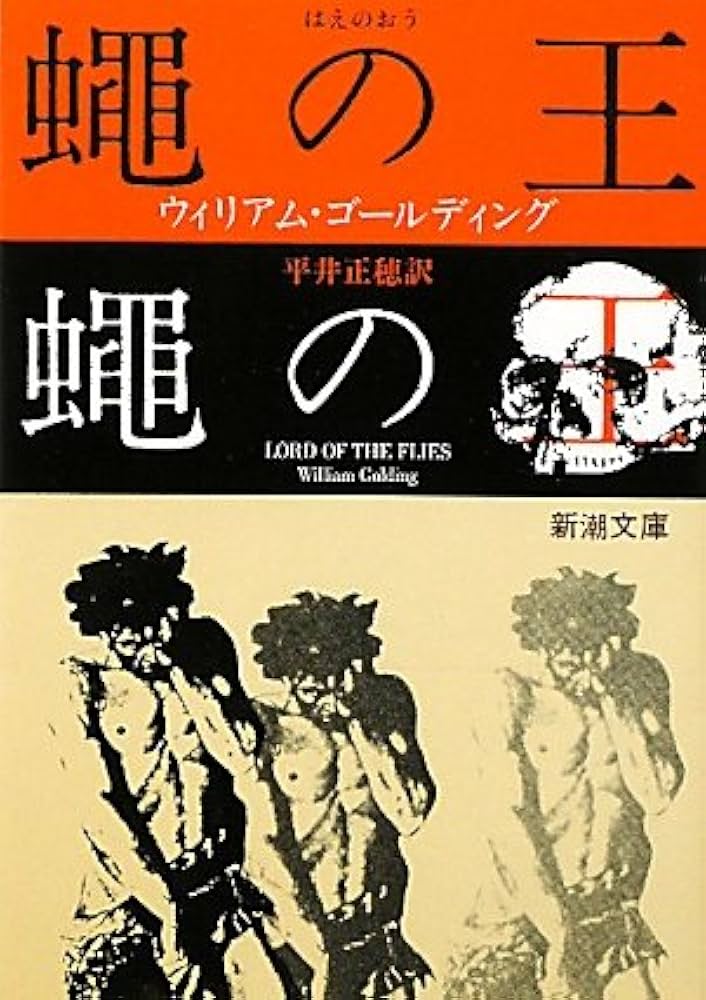
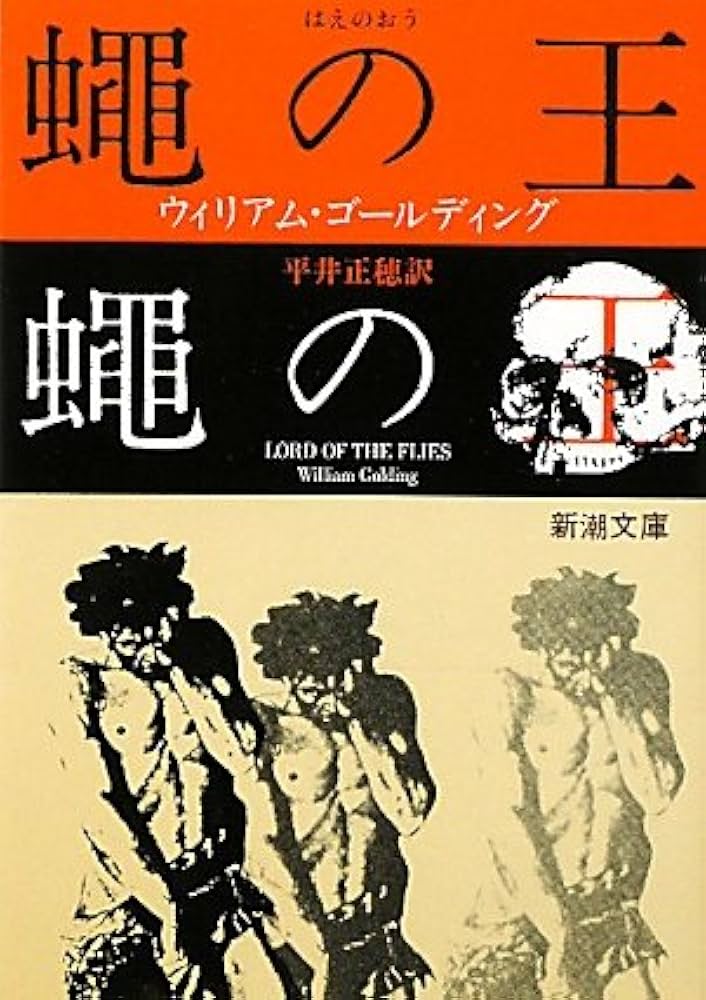
1983年にノーベル文学賞を受賞したイギリスの作家、ウィリアム・ゴールディングの代表作です。飛行機事故で無人島に取り残された少年たちが、生き残るためにサバイバル生活を送る中で、次第に人間性を失い、対立していく様子を描いた物語です。
最初は協力し合っていた少年たちが、恐怖や猜疑心から、やがて野蛮な集団へと変貌していく過程は、読む者に衝撃を与えます。人間の心に潜む闇や、文明社会のもろさを鋭く描き出した作品として、世界中で読み継がれています。



本作における人間の本性が剥き出しになる様は、社会というものが如何に脆い基盤の上に成り立っているかを痛感させる。
12位『日の名残り』 カズオ・イシグロ
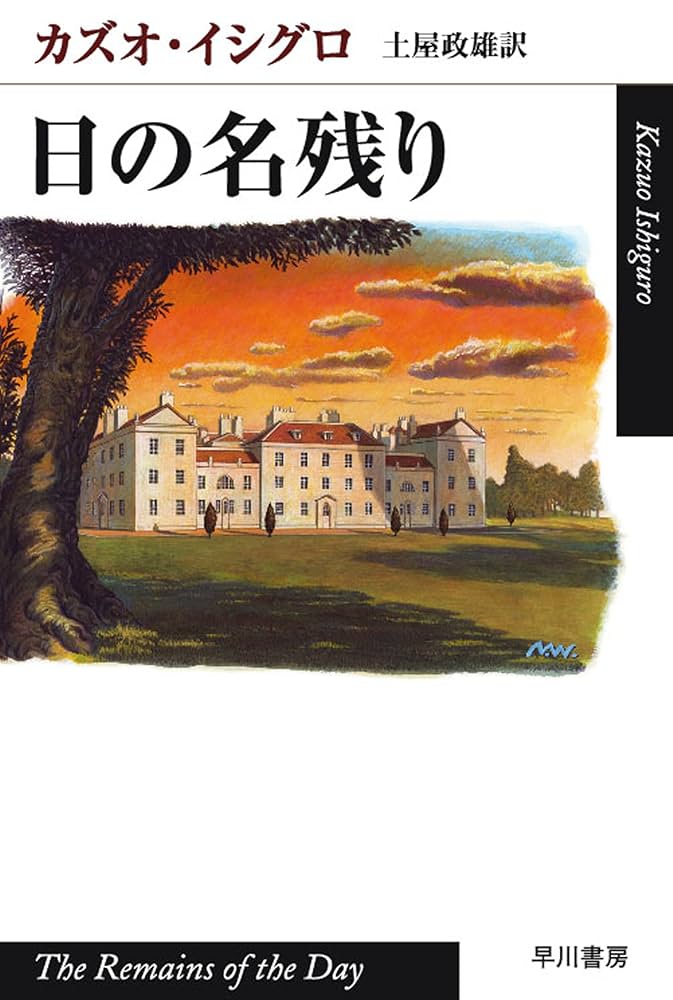
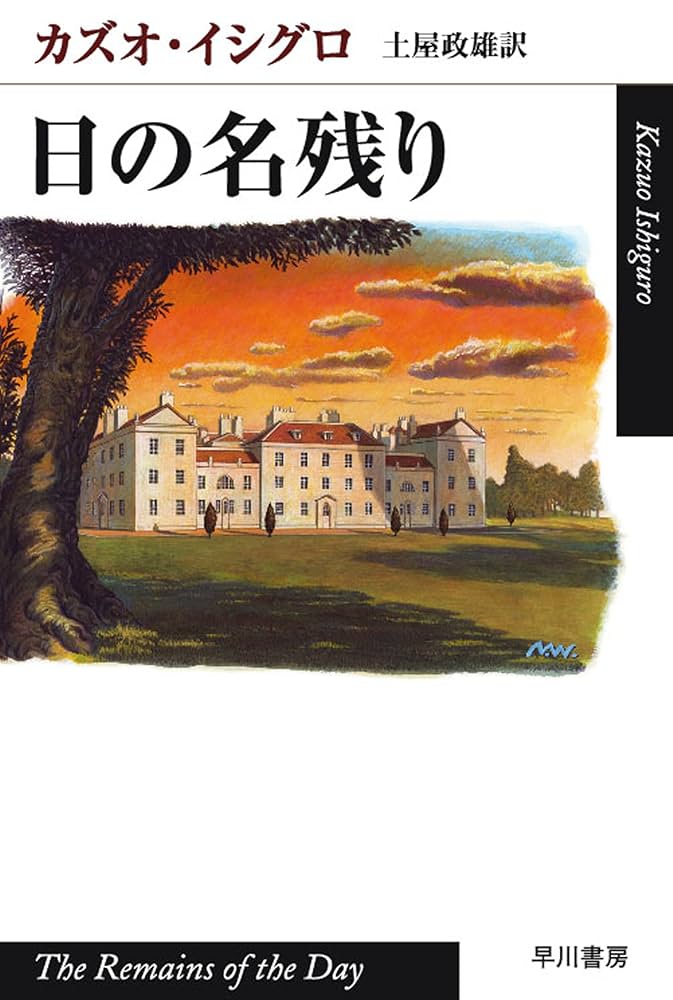
カズオ・イシグロの作品の中でも、イギリス最高の文学賞であるブッカー賞を受賞し、彼の名を世界的に高めた傑作です。物語は、長年イギリス貴族に仕えてきた老執事スティーブンスが、昔を回想しながら旅をする形で進みます。
彼は完璧な執事としての誇りを胸に生きてきましたが、その裏で犠牲にしてきたものがあったのではないかと自問自答します。失われた時間や人生の選択について、静かな語り口で深く問いかける物語です。主人公が自身の過去を語る「信頼できない語り手」という手法も巧みで、読者は行間に隠された真実を探りながら読み進めることになります。



主人公の気持ちを考えると、胸が締め付けられるようだった…。自分の人生を振り返りたくなる、静かで深い物語だよ。
13位『収容所群島』 アレクサンドル・ソルジェニーツィン
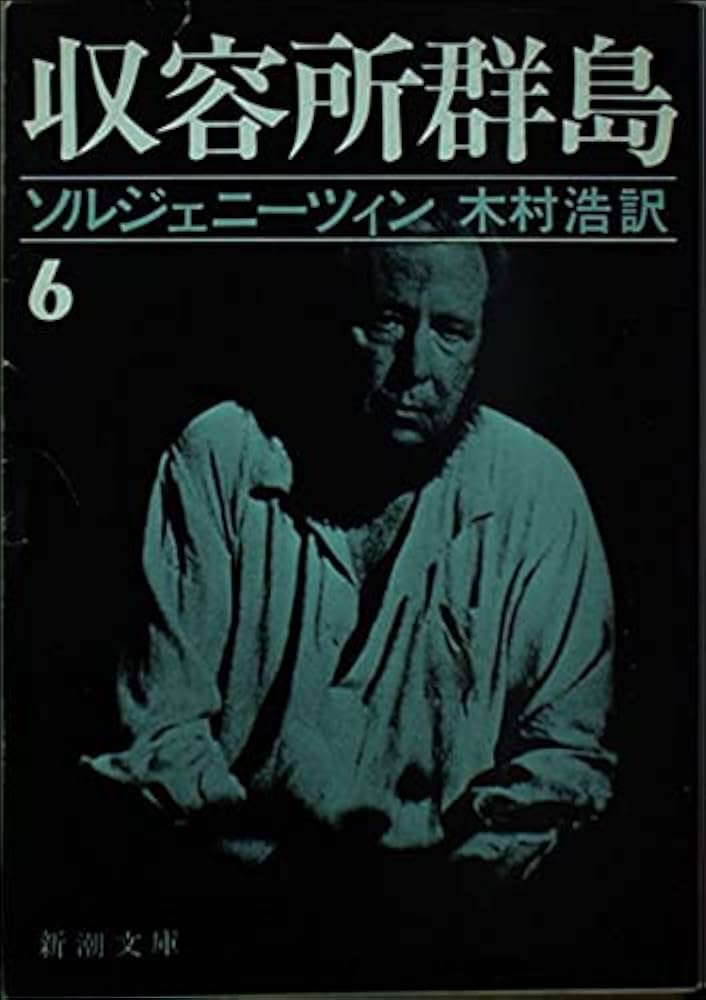
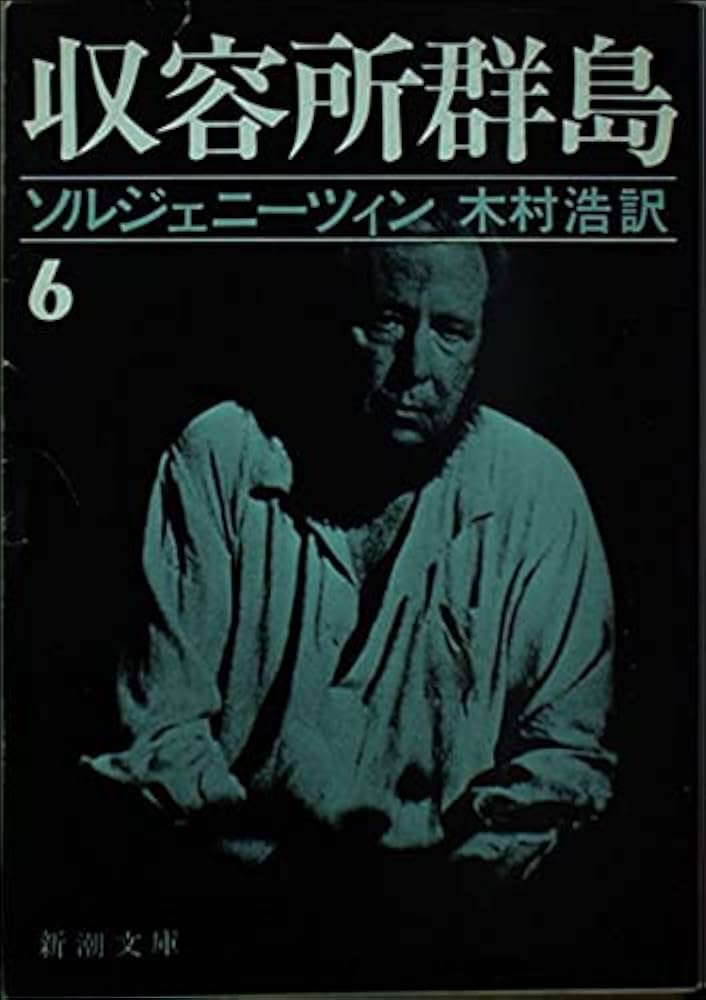
1970年にノーベル文学賞を受賞した旧ソ連の作家、アレクサンドル・ソルジェニーツィン。彼自身も収容所での生活を経験しており、その体験と多くの人々の証言を基に、ソ連の強制収容所の実態を告発したのがこの作品です。
文学の形式を取りながらも、その内容はスターリン体制下で行われた弾圧の恐るべき真実を暴く、歴史的なノンフィクションです。この作品が西側で出版されると世界中に衝撃を与え、ソ連の暗部を白日の下に晒しました。人間の尊厳が極限まで踏みにじられる状況を描いた、人類の負の遺産ともいえる一冊です。



本書に記録された事実は、人間が人間に対して如何に残酷になれるかという問いを突きつけてくる。直視すべき歴史の証言だ。
14位『恥辱』 J・M・クッツェー
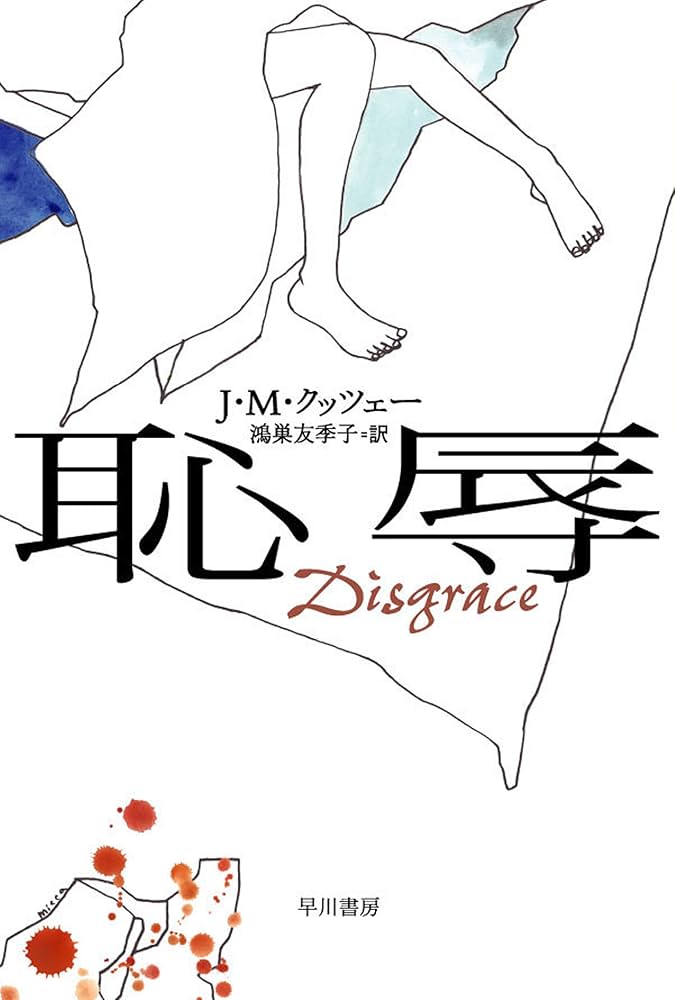
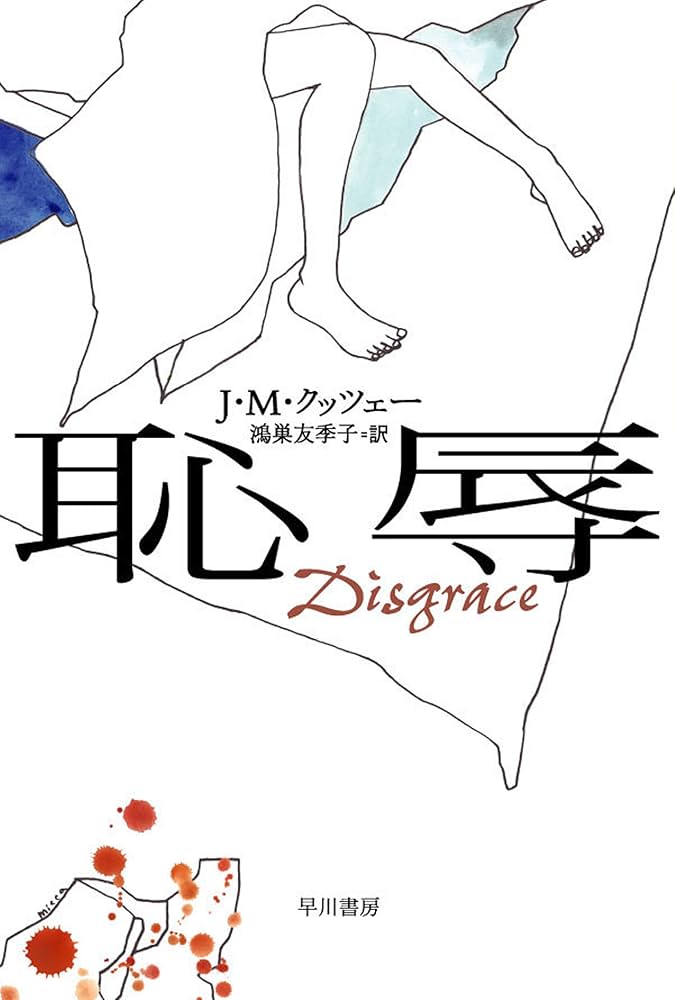
2003年にノーベル文学賞を受賞した南アフリカ出身の作家、J・M・クッツェー。ブッカー賞を2度受賞した唯一の作家でもあり、そのうちの1作がこの『恥辱』です。
物語の舞台は、アパルトヘイト(人種隔離政策)が撤廃された後の南アフリカ。大学教授のデイヴィッドが、教え子との関係が問題となり職を失い、娘のもとで暮らす中で、ある暴力的な事件に巻き込まれていきます。人種間の対立や暴力、そして個人の尊厳といったテーマが、容赦のない筆致で描かれます。読後に重い問いを投げかけられる、衝撃的な作品です。



読んでいてすごく苦しくなったけど、目をそらしちゃいけない問題だと思ったよ。人間の複雑さを考えさせられるんだ。
15位『ビラヴド』 トニ・モリスン
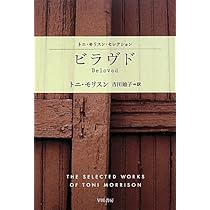
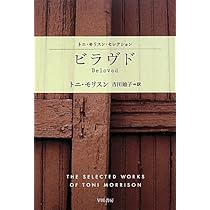
1993年にアフリカ系アメリカ人女性として初めてノーベル文学賞を受賞したトニ・モリスン。彼女の代表作であり、ピューリッツァー賞も受賞したのが『ビラヴド』です。
物語は、奴隷制から逃亡した過去を持つ女性セテのもとに、ある日「ビラヴド」と名乗る不思議な娘が現れるところから始まります。この出会いをきっかけに、セテが心の奥底に封じ込めていた奴隷時代の忌まわしい記憶が蘇ってきます。アメリカの歴史の暗部である奴隷制というテーマを、幻想的な手法で描き出した力強い作品です。



過去の記憶って、こんなにも人を縛り付けるんだって思った…。悲しいけど、すごく愛に満ちた物語でもあるんだ。
16位『わたしの名は紅』 オルハン・パムク
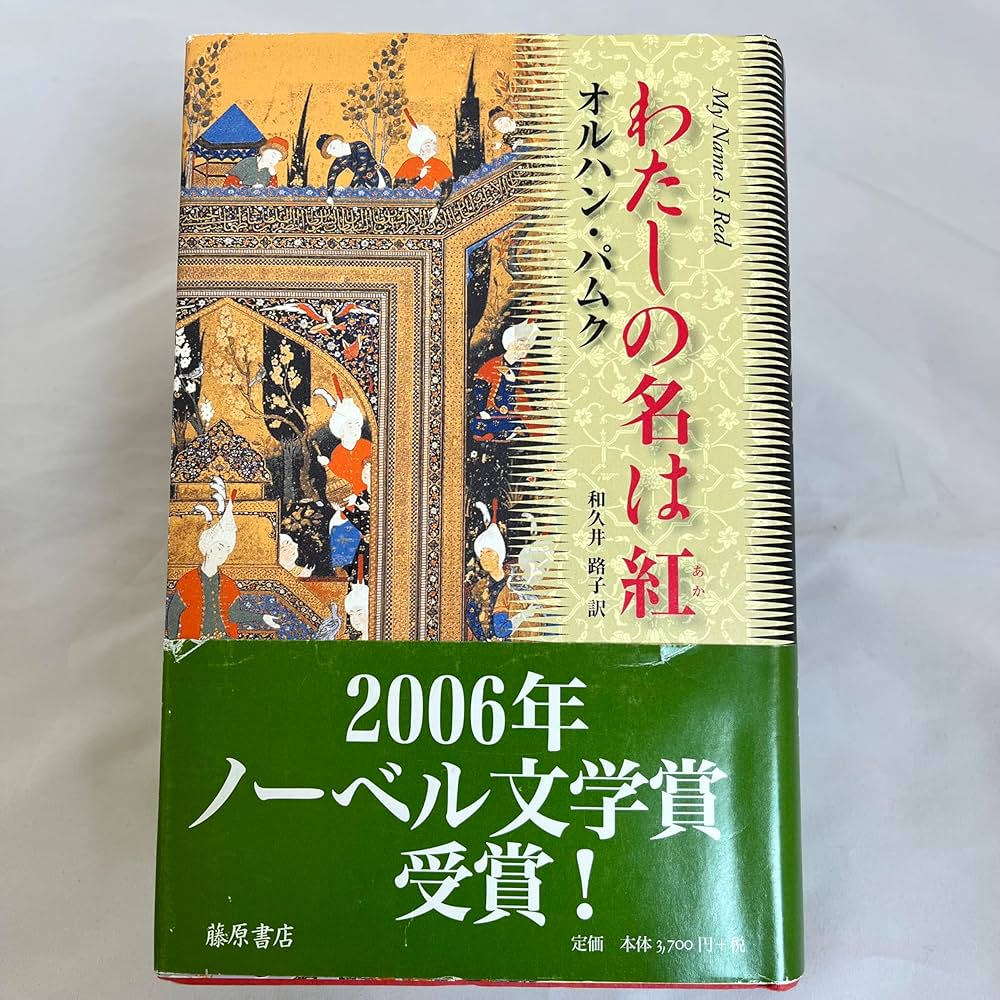
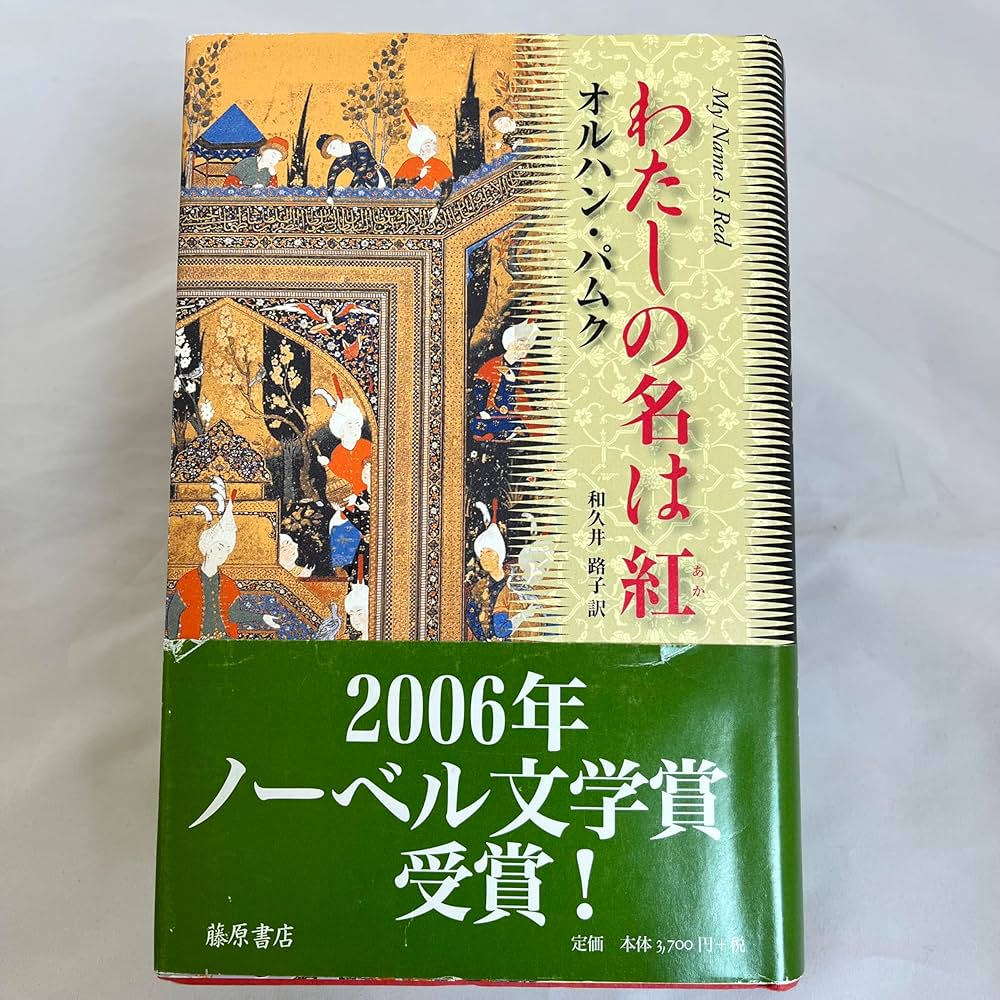
2006年にトルコ人として初めてノーベル文学賞を受賞したオルハン・パムク。彼の代表作である『わたしの名は紅』は、16世紀末のオスマン帝国を舞台にした、芸術と愛、そして殺人を巡るミステリー小説です。
細密画師(ミニアチュール画家)たちが、スルタン(皇帝)の命で秘密の写本を制作する中、一人の画師が殺害されます。犯人は一体誰なのか。物語は、人間だけでなく、死体や犬、金貨、そして「紅」という色までもが語り手となる、非常にユニークな形式で進みます。東西の文化が交差するイスタンブールの街を背景に、芸術論も交えながら展開する、知的好奇心を刺激される一冊です。



いろんなものが喋り出すのがすごく面白かった!ミステリーとしても楽しめるし、昔のトルコの芸術の世界も知れてお得な気分だよ。
17位『シンプルな情熱』 アニー・エルノー
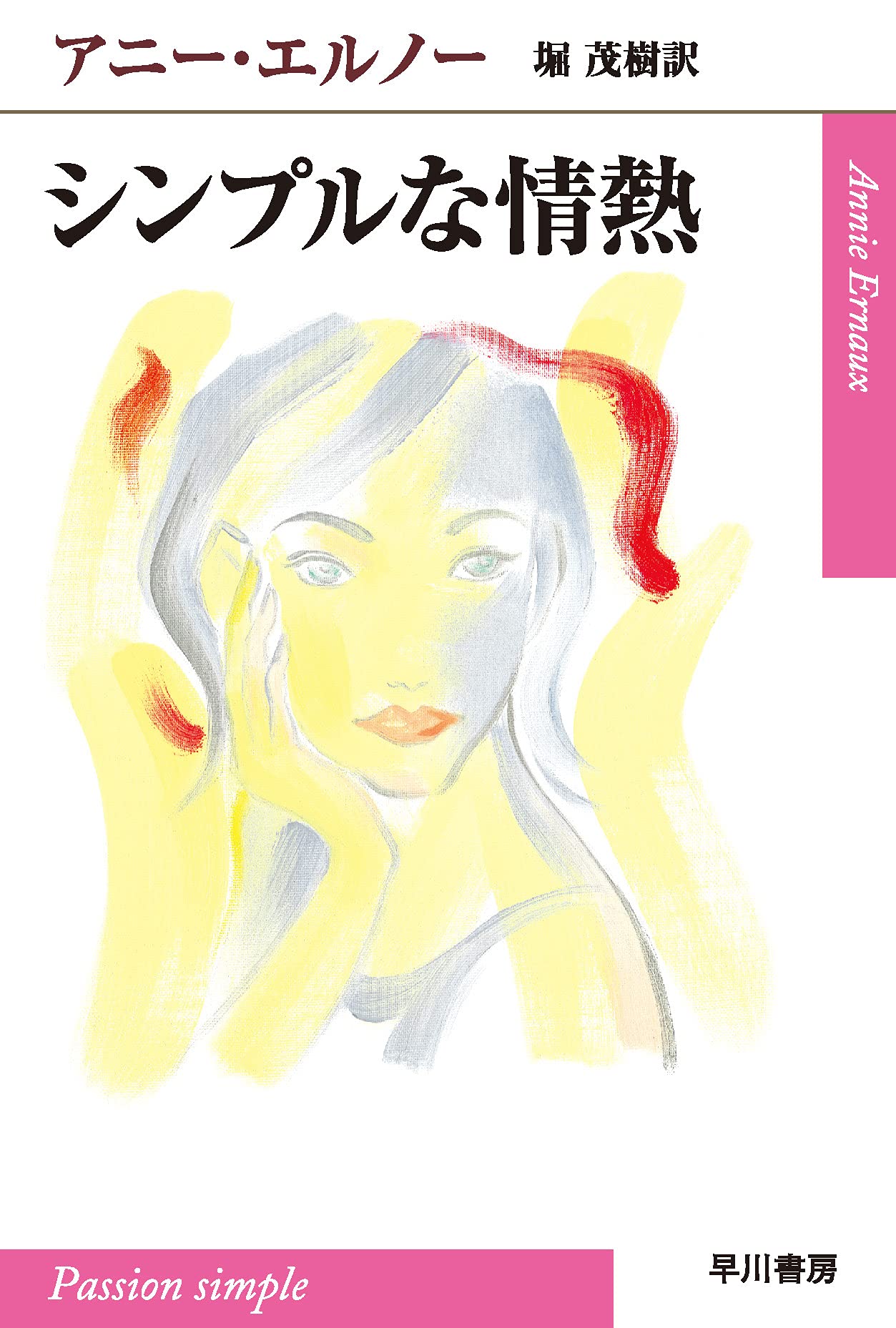
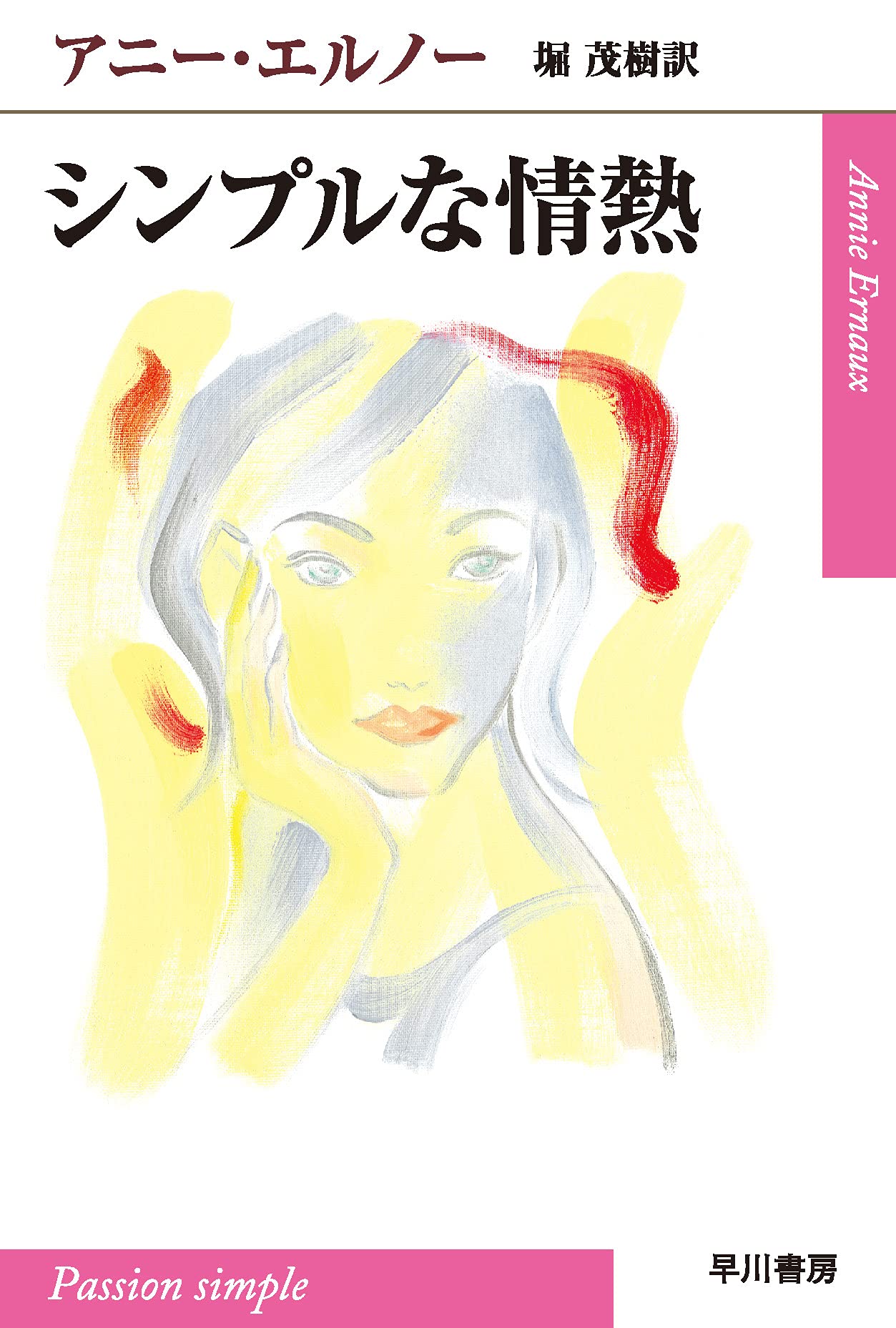
2022年にノーベル文学賞を受賞したフランスの作家、アニー・エルノー。彼女は自身の体験を赤裸々に綴る作風で知られています。この『シンプルな情熱』は、外国人の既婚男性との恋愛にのめり込んでいく自身の姿を、冷静な筆致で描いた私小説です。
恋愛の喜びや幸福感だけでなく、待ち続ける時間の苦しさや、相手に完全に依存してしまう自分自身を、客観的な視点から徹底的に見つめています。短い作品ながら、恋愛という感情の本質を鋭く切り取っており、多くの読者の共感を呼んでいます。



すごく正直な文章で、読んでいてドキドキしちゃった。恋愛の持つパワーってすごいなって改めて思うかな。
18位『赤い高粱』 莫言
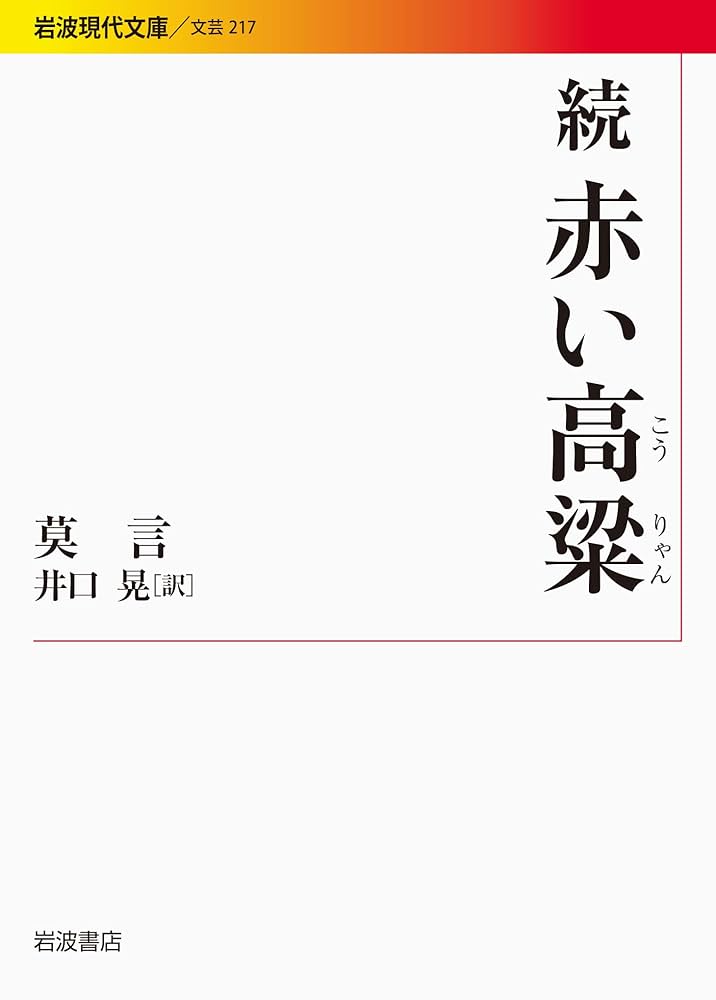
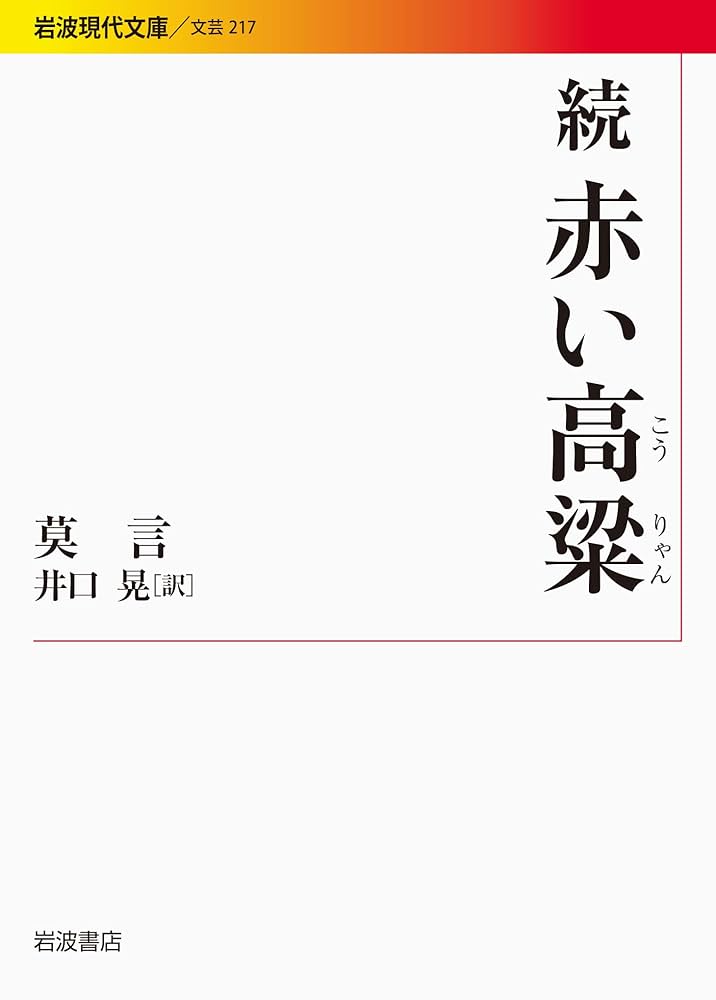
2012年に中国国籍の作家として初めてノーベル文学賞を受賞した莫言(モー・イエン)。彼の代表作が、この『赤い高粱』です。20世紀の中国を舞台に、ある一族の三代にわたる激動の歴史を、壮大なスケールで描いています。
物語の中心となるのは、一面に広がる赤い高粱(コーリャン)畑。そこは愛憎や生死が渦巻く、生命力にあふれた場所として描かれます。日中戦争などの過酷な歴史を背景にしながらも、土着的でエネルギッシュな人々の姿が、マジックリアリズムを思わせる幻想的な筆致で語られます。映画化もされ、世界的に高い評価を受けました。



生命力が爆発してるって感じの物語だった!赤い高粱畑のイメージが、ずっと頭から離れないんだよね。
19位『暗いブティック通り』 パトリック・モディアノ
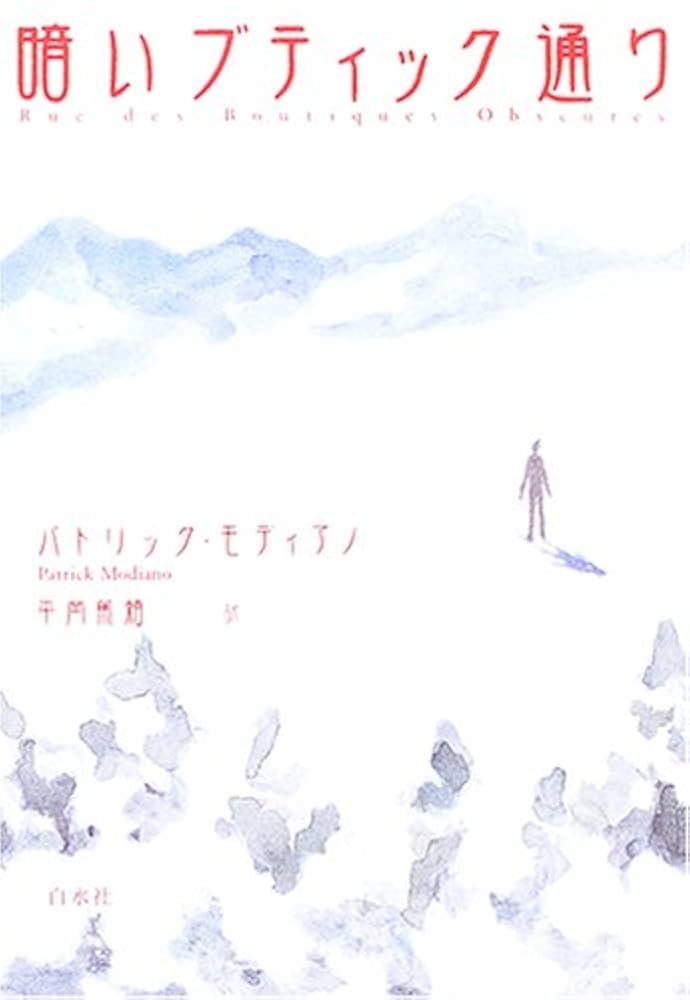
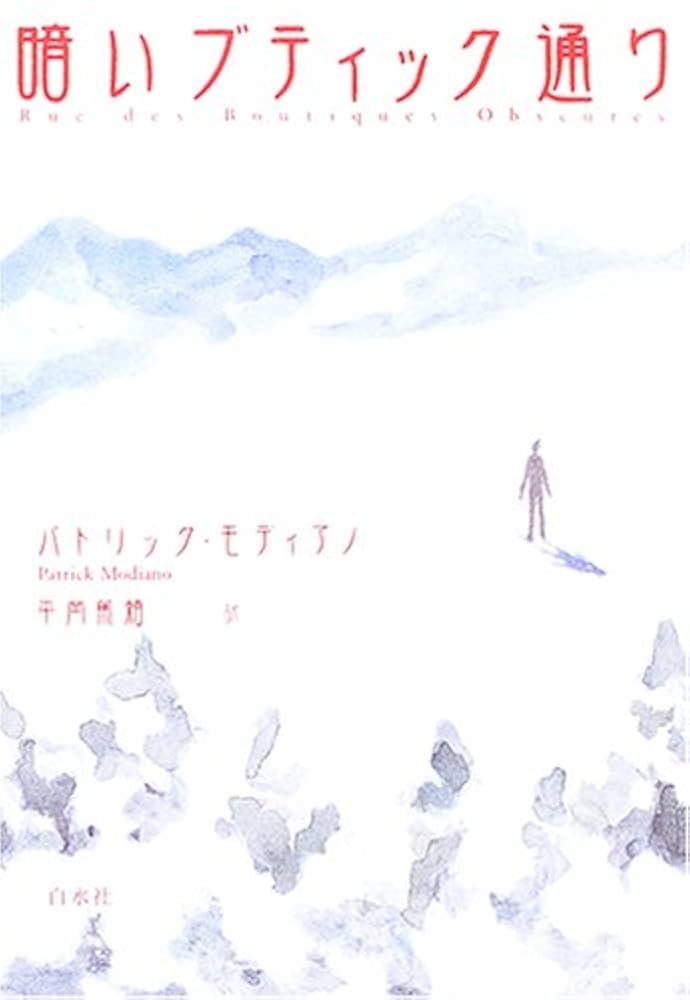
2014年にノーベル文学賞を受賞したフランスの作家、パトリック・モディアノ。彼の作品は、「記憶」をテーマにしたものが多いことで知られています。この『暗いブティック通り』は、記憶喪失の探偵が、自分自身の過去を探し求める物語です。
主人公は、わずかな手がかりを頼りに、かつての自分を知る人々を訪ね歩きます。その過程で、ナチス・ドイツ占領下のパリの暗い時代が浮かび上がってきます。失われた過去を追い求める主人公の姿は、どこか切なく、ミステリアスな雰囲気に満ちています。読者もまた、主人公と共に記憶の迷宮を彷徨うような感覚を味わうことになるでしょう。



自分が誰なのかを探す旅って、なんだか不思議な気持ちになるね。昔のパリの街を歩いているみたいな気分になれたよ。
20位『ペスト』 アルベール・カミュ
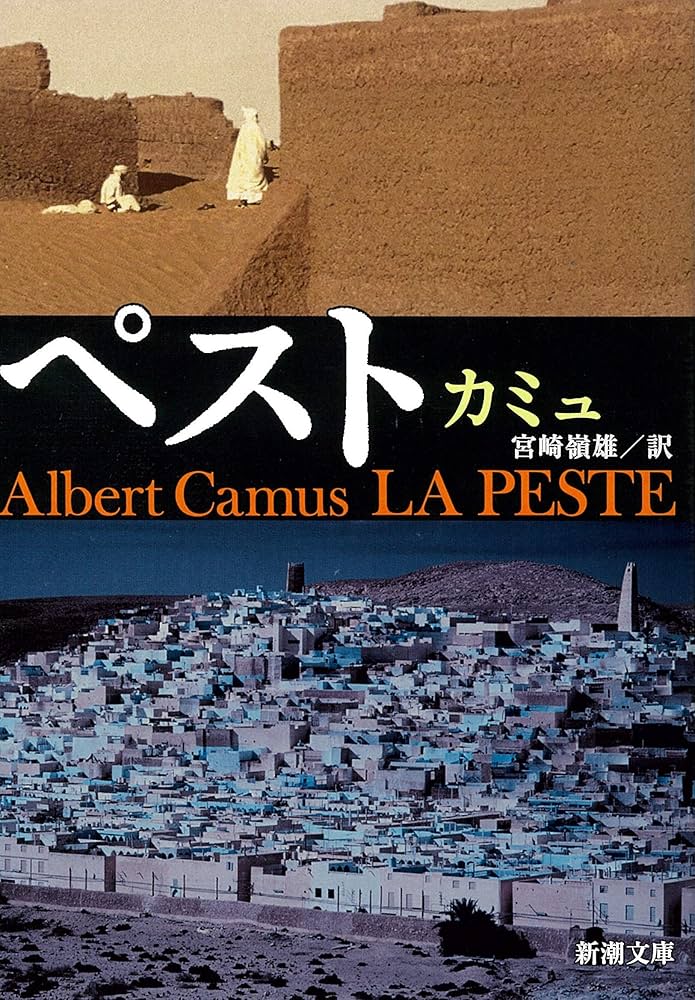
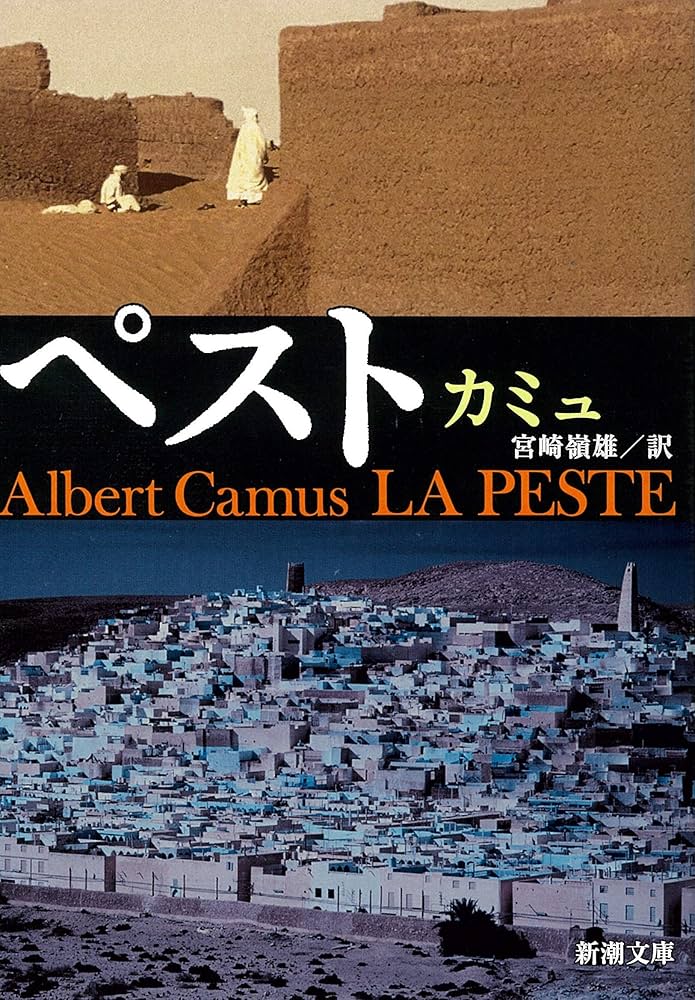
『異邦人』と並ぶカミュの代表作で、ノーベル文学賞受賞の大きな要因となった作品です。アルジェリアの港町オランが、高い致死率を持つ伝染病・ペストによって封鎖されるところから物語は始まります。
極限状態に置かれた人々が、絶望や恐怖とどのように向き合い、行動するのか。医師リウーをはじめとする登場人物たちの姿を通して、不条理な状況に対する人間の抵抗や連帯が描かれます。単なるパニック小説ではなく、人間の尊厳とは何かを問いかける、普遍的なテーマを持った物語です。



大変な状況の中でも、自分のやるべきことを淡々とこなす人たちの姿に感動したよ。連帯することの大切さを教えてくれるんだ。
ノーベル文学賞作品を読んで、文学の奥深い世界に触れよう
ノーベル文学賞を受賞した作品は、それぞれがユニークな世界観を持ち、私たちに新しい視点や深い感動を与えてくれます。時代や国、文化は違えど、そこに描かれているのは人間の喜びや悲しみ、愛や孤独といった、誰もが共感できる普遍的なテーマです。
今回ご紹介した20作品は、その中でも特に、これからノーベル文学賞作品を読んでみようという方にぴったりの名作ばかりです。気になる一冊を手に取って、ぜひ文学の奥深い世界の扉を開いてみましょう。きっと、あなたの人生を豊かにする一冊に出会えるはずです。