あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】古井由吉のおすすめ小説ランキングTOP19

はじめに:古井由吉文学の深淵へようこそ
『小説ヨミタイ』編集長のふくちいです。今回は、日本文学の中でも独特の光を放つ作家、古井由吉の作品世界にご案内します。古井由吉(1937-2020)は、ドイツ文学の研究者・翻訳家としてキャリアをスタートさせ、その後、小説家として数々の名作を生み出しました。
彼の作品は、しばしば「内向の世代」という言葉で語られます。これは、社会的な出来事よりも個人の内面や日常の微細な変化に目を向けた作家たちを指す言葉です。古井文学の魅力は、日常に潜む非日常や、人間の内面の奥深くにある混沌とした感覚を、濃密で美しい文章で描き出す点にあります。その文体は時に難解とも言われますが、一度その世界に足を踏み入れれば、他に類を見ない深い読書体験が待っています。
この記事では、古井由吉の数ある名作の中から、特におすすめの19作品をランキング形式でご紹介します。初めて古井作品に触れる方から、さらに深く読み進めたい方まで、きっとお気に入りの一冊が見つかるはずです。
古井由吉のおすすめ小説ランキングTOP19
ここからは、いよいよ古井由吉のおすすめ小説ランキングを発表します。彼の代表作から、知る人ぞ知る名作まで幅広く選びました。
それぞれの作品が持つ独特の雰囲気やテーマを、あらすじやポイントと共にご紹介していきます。古井由吉の文学の森へ、一緒に分け入っていきましょう。
1位『杳子・妻隠』

堂々の1位は、古井由吉の芥川賞受賞作『杳子』と、同時期に書かれた『妻隠』を収録した一冊です。古井文学の出発点ともいえる作品で、その魅力と特徴が凝縮されています。
『杳子』は、登山中に「彼」が出会った精神を病む女子大生・杳子との、孤独で斬新な愛の世界を描いた物語です。日常と狂気の境界線が曖昧になっていくような、濃密で混沌とした筆致は、読む者を陶然とさせます。一方、『妻隠』は、都会で暮らす若い夫婦の日常に潜む深淵を描き出しています。どちらの作品も、ストーリーを追うというよりは、その独特の文体と感覚に身を委ねるように読むのがおすすめです。
 ふくちい
ふくちい『杳子』の、現実と幻想の境目が溶けていくような感覚がすごい…。わたし、ちょっと混乱してきたかも。
2位『槿』
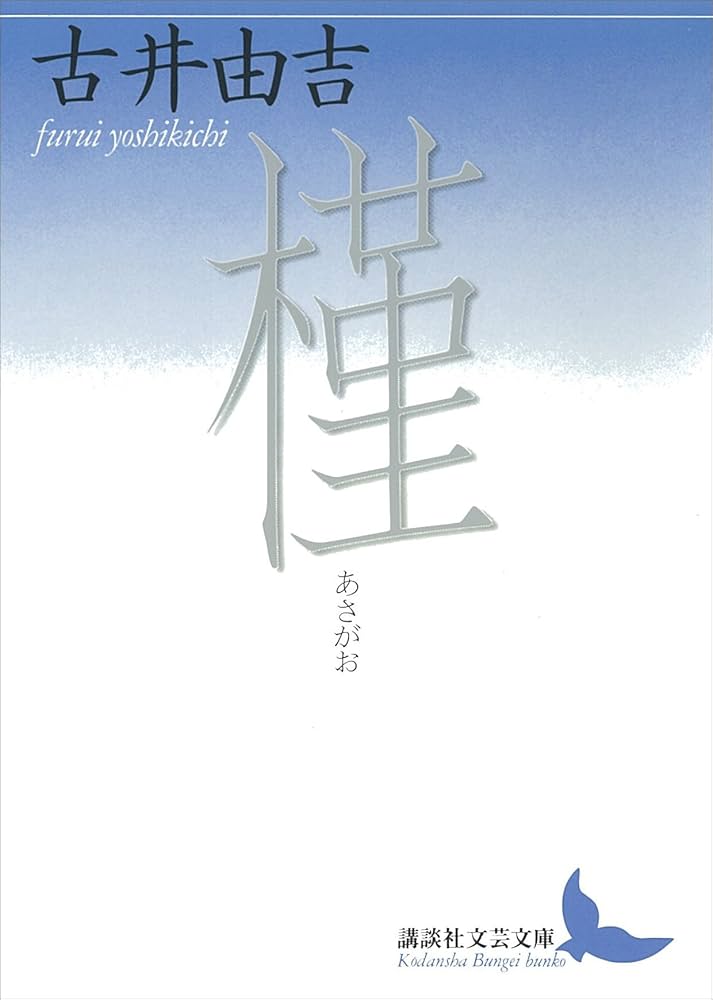
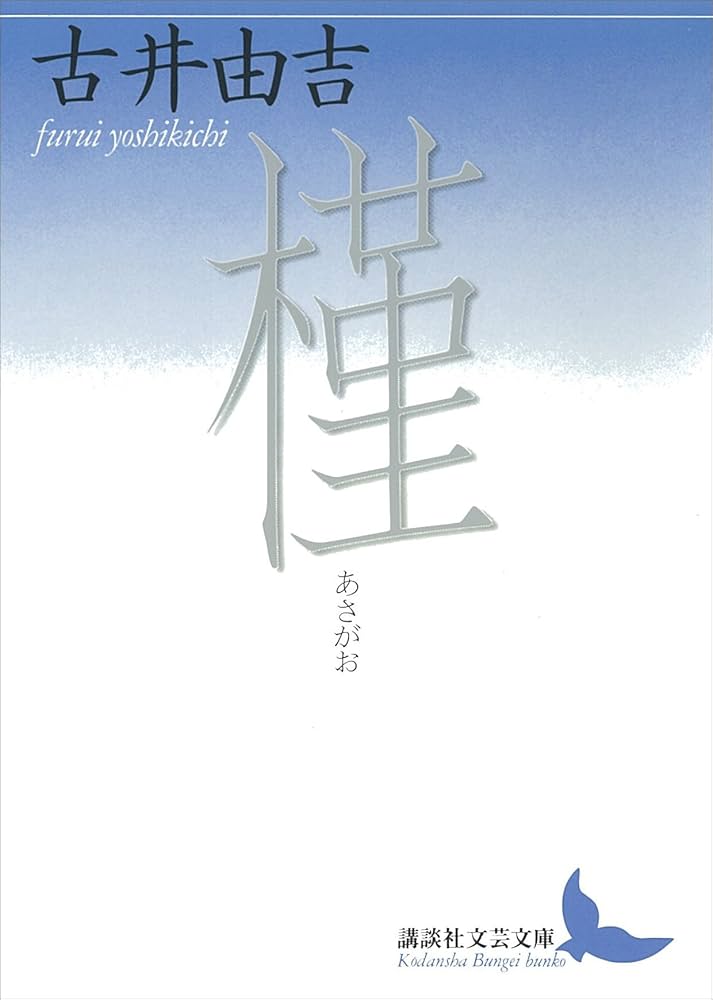
2位にランクインしたのは、谷崎潤一郎賞を受賞した『槿』です。この作品は、中年男と若い女の奇妙な同棲生活を通して、日常に潜むエロスや狂気を描き出しています。
古井由吉の作品の中でも、特に生と性が濃密に描かれているのが特徴です。登場人物たちの行動は時に不可解に思えますが、その内面でうごめく感情や欲望が、独特の文体で生々しく伝わってきます。古井文学の真骨頂である、人間の内奥に深く分け入っていくような読書体験ができる一冊です。



人間の奥底にあるものをじっと見つめているような作品だね。読み応えがあって、わたしは好きだよ。
3位『辻』
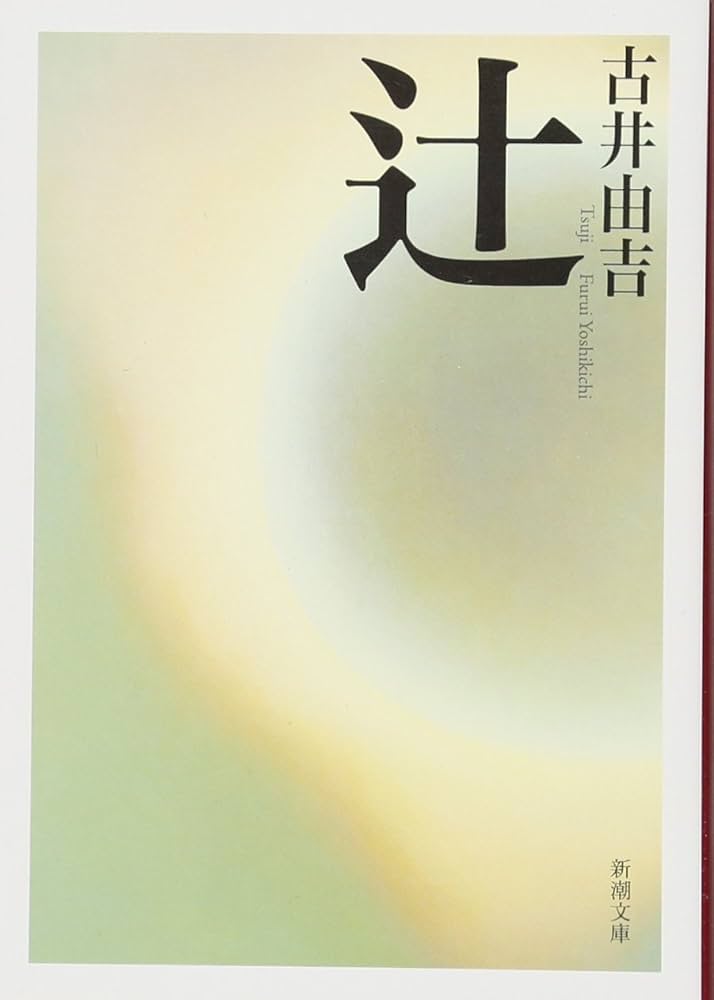
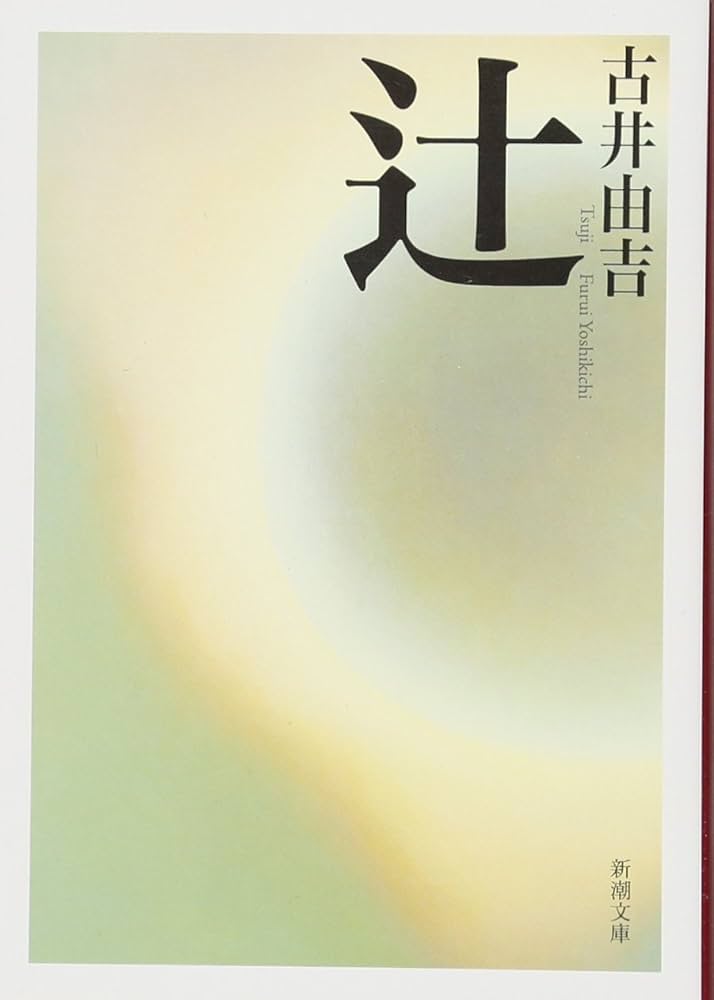
3位は、12の連作短編からなる『辻』です。父と子、男と女といった人間関係の中で、人々がふと差し掛かる人生の「辻」を描いています。
それぞれの短編は独立していますが、全体を通して読むことで、生と死、日常と狂気、現実と神話といったテーマが響き合います。古井由吉の練り上げられた濃密な文体は、読む者に深い思索を促し、まるで文学の森を彷徨うような感覚を与えてくれます。



一篇一篇が宝石みたいに美しい短編集だね。言葉の選び方が本当に見事で、うっとりしちゃうな。
4位『仮往生伝試文』
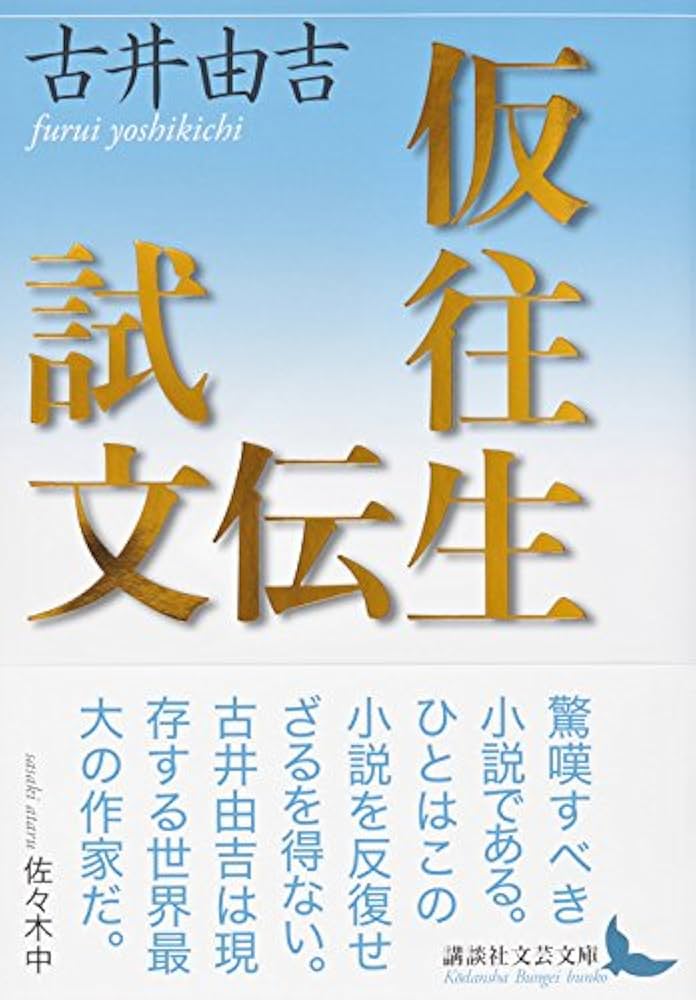
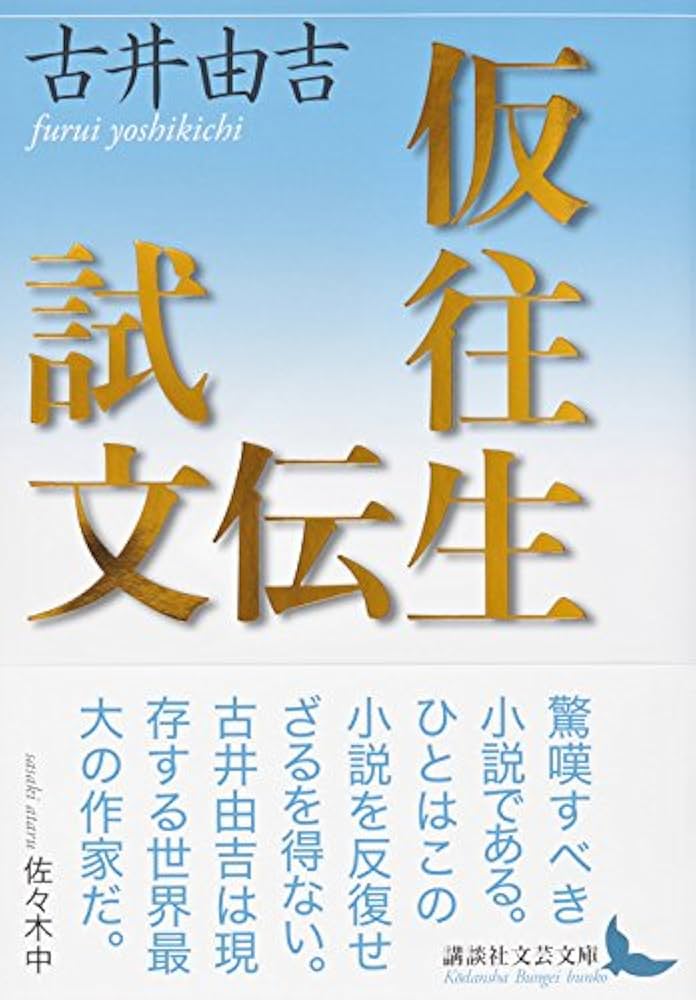
4位は、読売文学賞を受賞した『仮往生伝試文』です。この作品は、『今昔物語』など日本の古典説話に登場する、世を捨てた僧侶たちの逸話を下敷きにしています。
古井由吉は、古典の世界と現代的な感性を見事に融合させ、生とは何か、死とは何かという根源的な問いを投げかけます。その文章は時に難解でありながらも、日本語の可能性を極限まで追求したような凄みを感じさせます。日本語で書かれた小説の金字塔の一つとも評される、重厚な一冊です。



古典の世界にダイブするような感覚が面白いね。昔の人も今の人も、生と死について考えることは同じなんだなあって思ったよ。
5位『山躁賦』
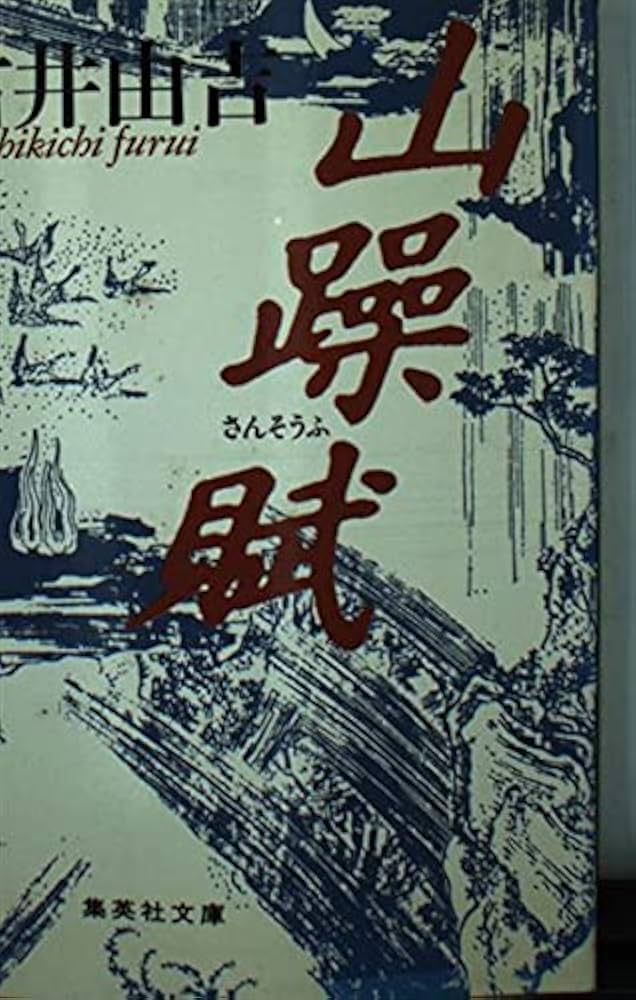
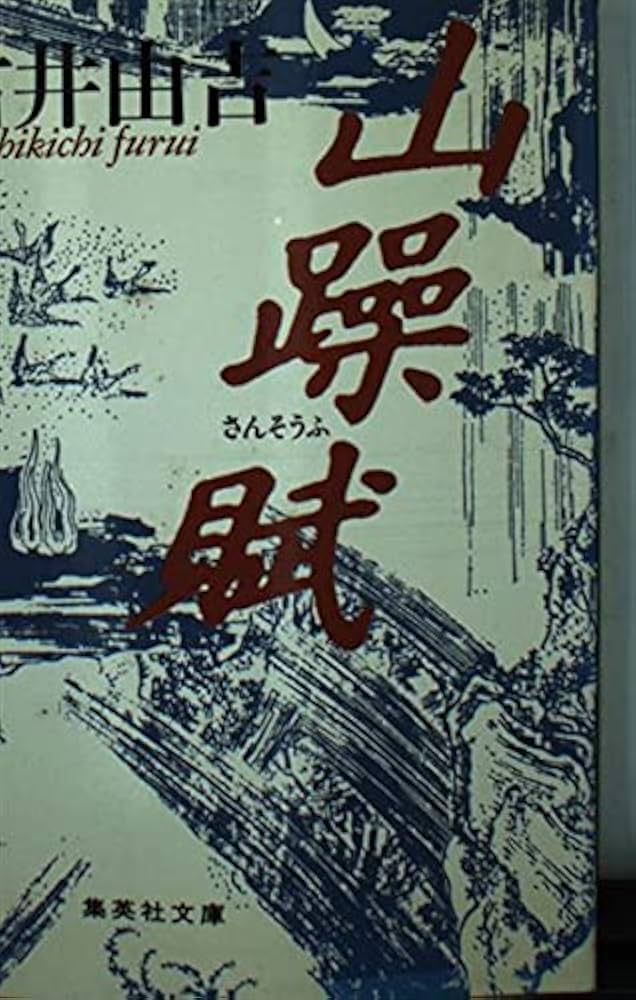
5位には、古井文学の転換点ともいわれる連作短編集『山躁賦』がランクイン。病み上がりの「私」が、比叡や高野といった山々を巡る旅を描いています。
この作品では、現実と幻想、現在と過去、生と死の境界が溶け合っていくような、不思議な感覚を味わうことができます。山に棲むモノたちの気配や、自然の中に溶け込んでいくような主人公の意識が、研ぎ澄まされた文章で描写されています。物語や自我から解き放たれ、古典的な世界へと傾斜していく古井文学の新たな境地が示された一冊です。



山の空気に包まれるような、不思議な読後感だったな。自然と一体になるって、こういう感じなのかな。
6位『白髪の唄』
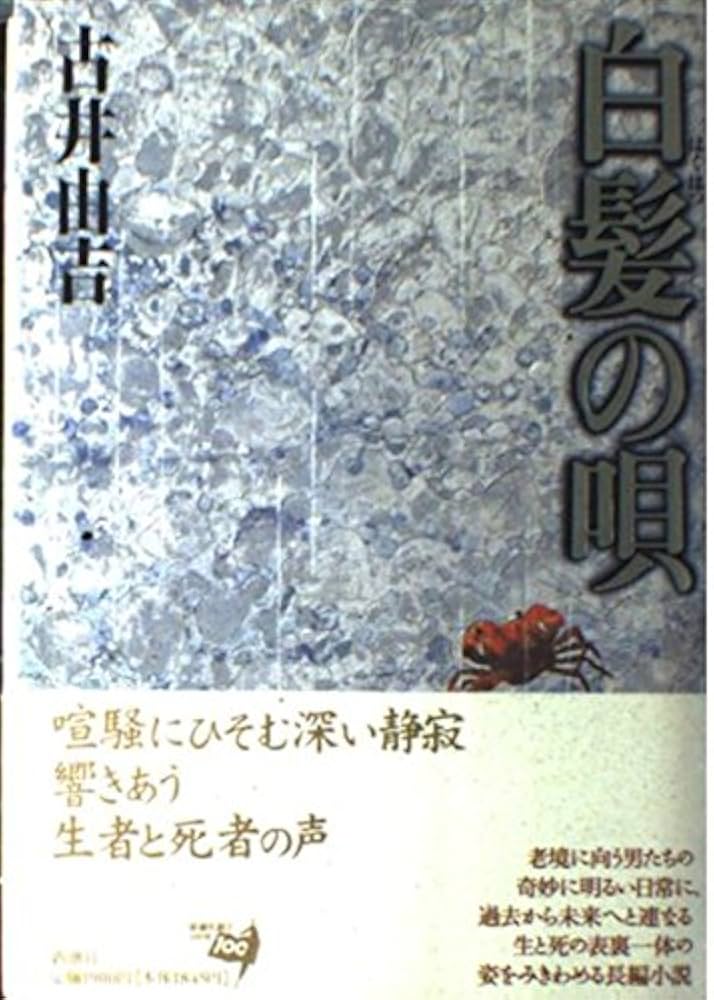
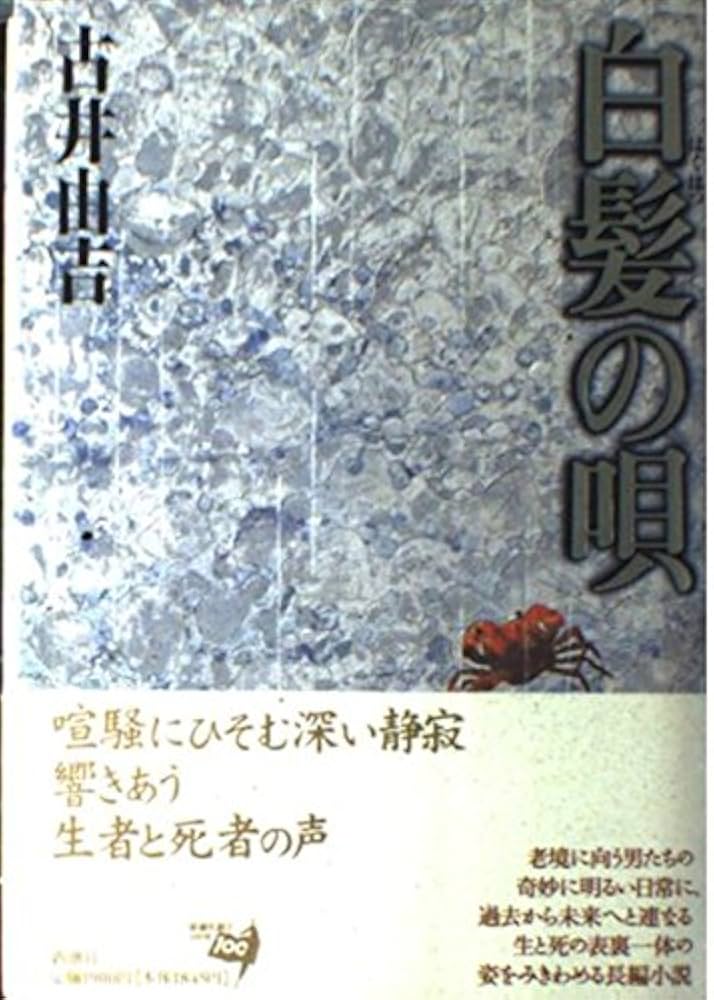
6位は、毎日芸術賞を受賞した『白髪の唄』です。この作品は、老いをテーマに、人間の生と死を深く見つめた一冊です。
古井由吉の円熟した筆致で、老いゆくことの哀しみや滑稽さ、そしてその中にある尊厳が静かに描き出されています。登場人物たちの何気ない日常の描写の中に、人生の深淵が垣間見えるような、味わい深い作品です。古井文学の中でも、特に落ち着いたトーンで、じっくりと読み進めたい一冊と言えるでしょう。



老いるってどういうことなんだろうって、深く考えさせられたよ。静かだけど、心にずしんと響く作品だね。
7位『ゆらぐ玉の緒』
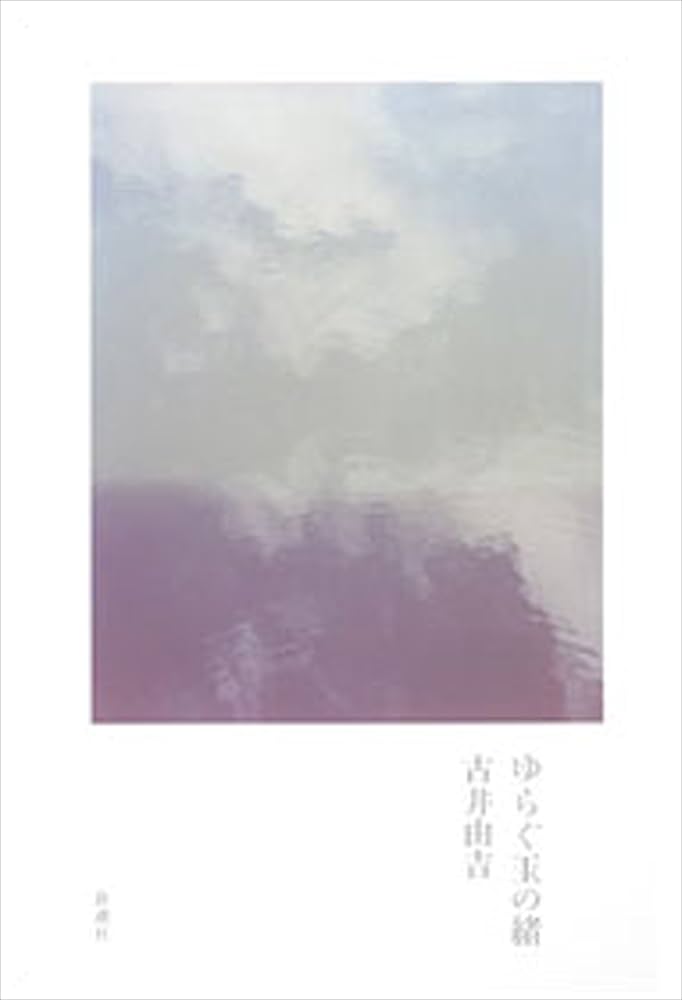
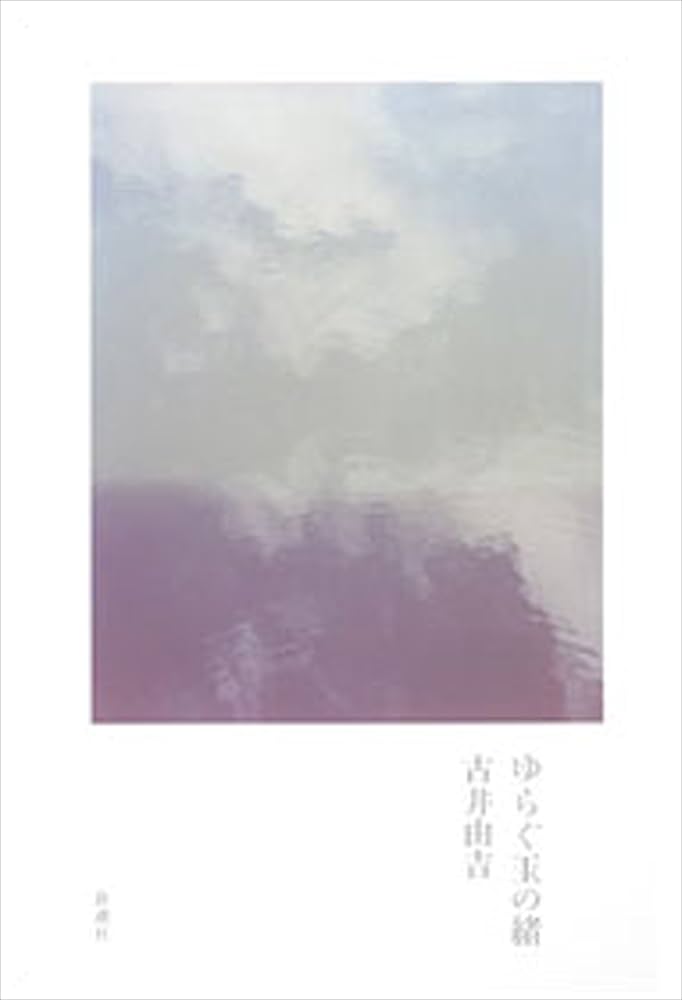
7位にランクインしたのは『ゆらぐ玉の緒』です。この作品は、古井由吉の文学的特徴である、日常と非日常の境界線が揺らぐ様を巧みに描いています。
物語は、主人公の周りで起こる些細な出来事や、ふとした記憶の断片を丁寧に拾い上げながら進んでいきます。その中で、現実の足元が静かに崩れていくような、独特の不安感と浮遊感が読者を包み込みます。「玉の緒」とは命綱や魂を意味する言葉であり、その名の通り、生きることの儚さや危うさを感じさせる一冊です。



なんだか足元がふわふわするような不思議な感覚…。物語の世界に迷い込んじゃったみたいだよ。
8位『木犀の日 古井由吉自選短篇集』
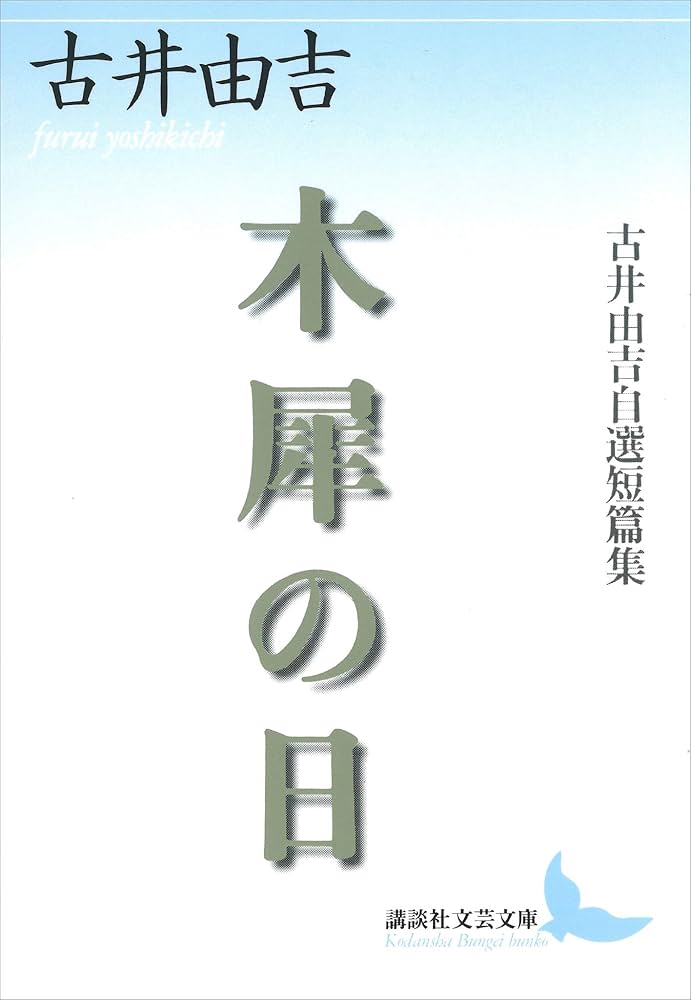
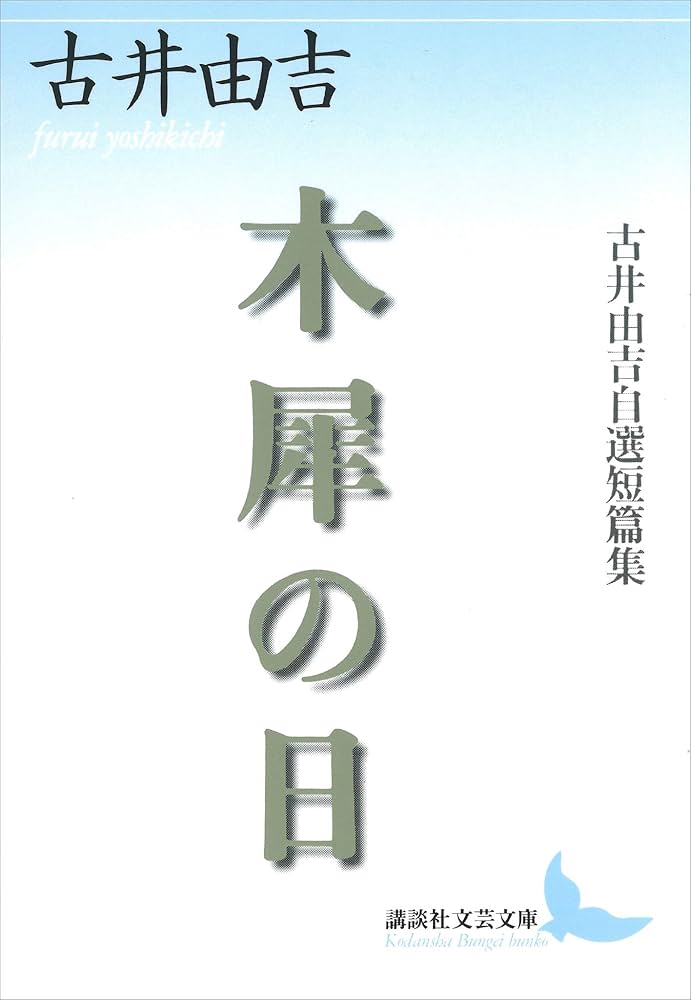
8位は、古井由吉自身が選んだ短編を集めた『木犀の日』です。古井文学のエッセンスが詰まったこの一冊は、初めて彼の作品に触れる方にもおすすめです。
収録された作品は多岐にわたりますが、いずれも日常の風景の中に潜む人間の心の機微や、ふとした瞬間に訪れる生の不思議さを捉えています。研ぎ澄まされた文体で描かれる世界は、一篇一篇が独立した完成度を誇りながら、通して読むことで古井由吉という作家の全体像を浮かび上がらせます。短編の名手としての一面も知ることができる、貴重な一冊です。



いろんなお話が詰まってて、宝箱みたいだね!どの短編も味わい深くて、一気に読んじゃったよ。
9位『水』
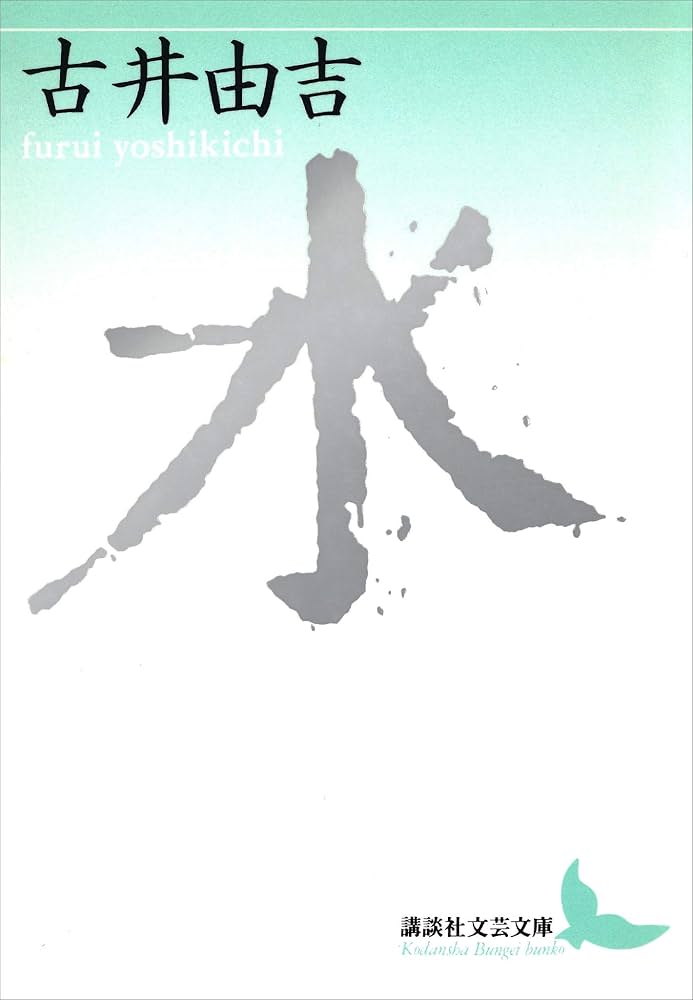
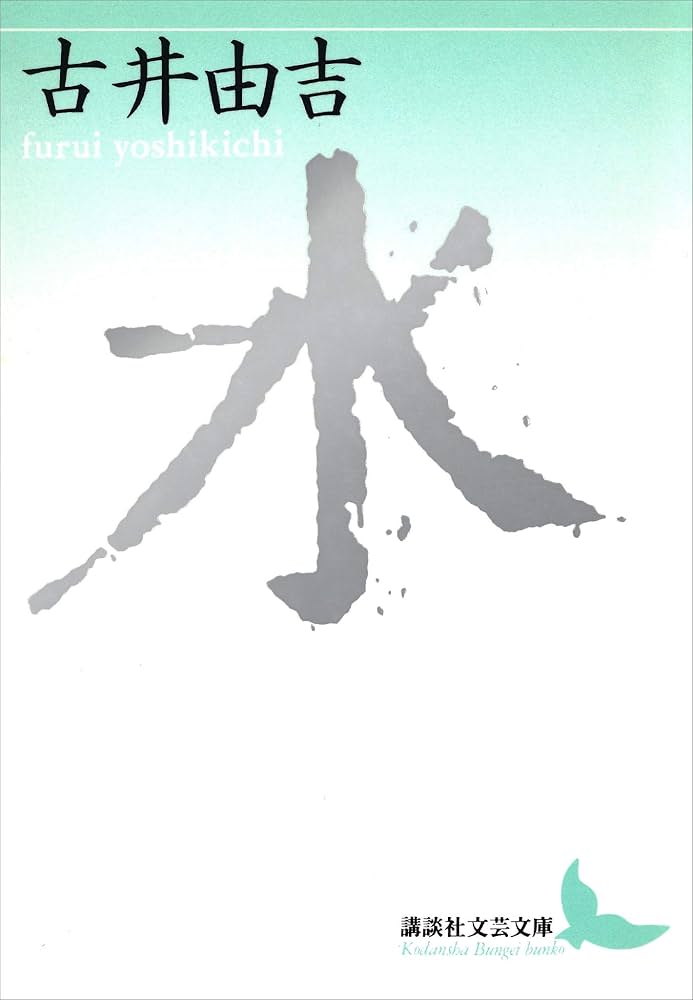
9位は、その象徴的なタイトルが印象的な『水』です。この作品では、「水」というモチーフが様々な形で登場し、物語全体を覆っています。
雨、川、湿気、体液といった「水」のイメージを通して、生と死、記憶、そして意識の深層が描かれていきます。物語は明確な筋を持つというよりは、水の流れのように変容し、読者の感覚に直接働きかけてくるようです。古井由吉の、言葉によって世界の捉え方そのものを変容させてしまうような、魔術的な筆致を堪能できる作品です。



「水」のイメージがずっと頭の中に残ってるな。なんだか心が洗われるような、不思議な読書体験だったよ。
10位『やすらい花』
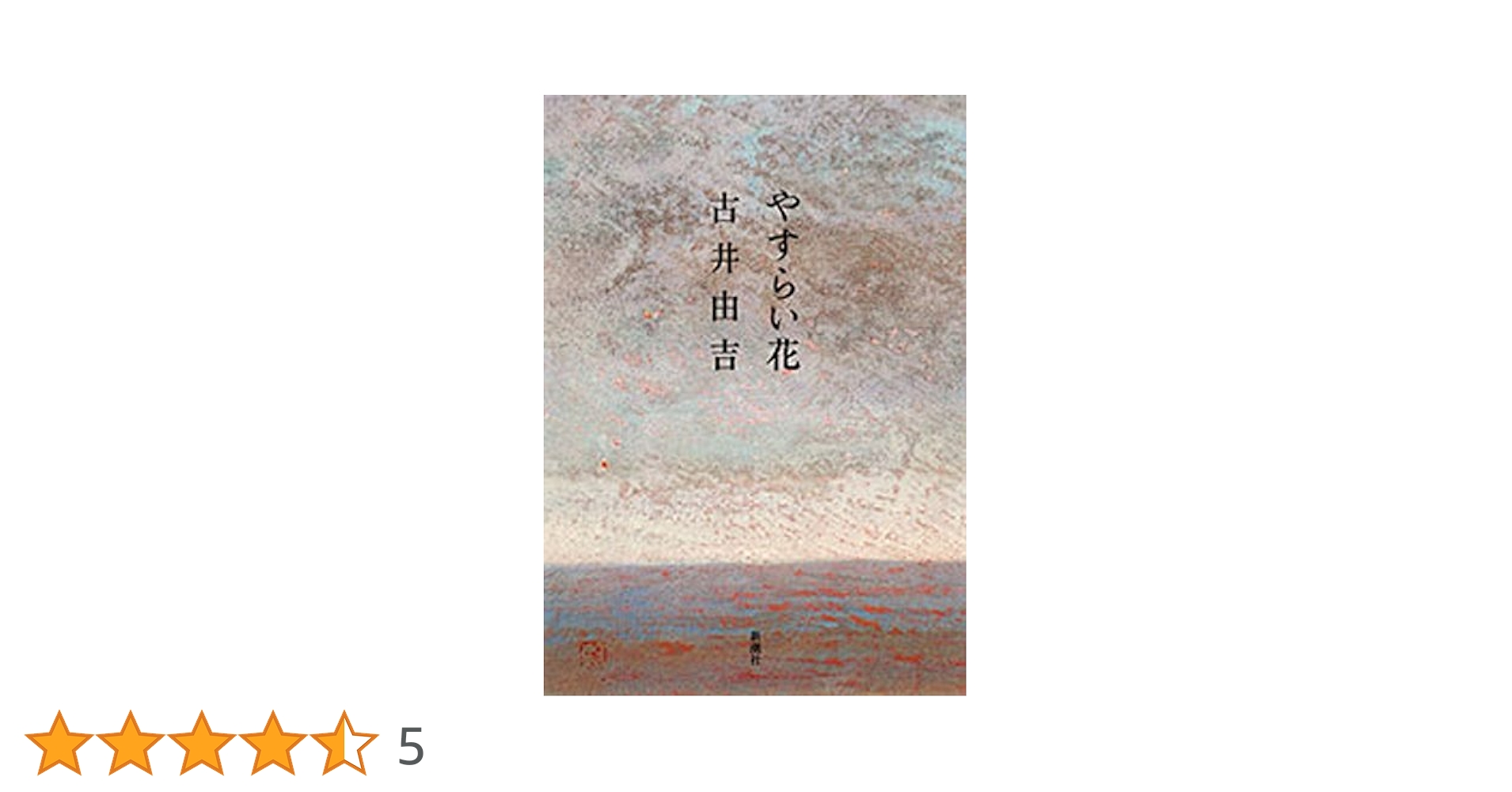
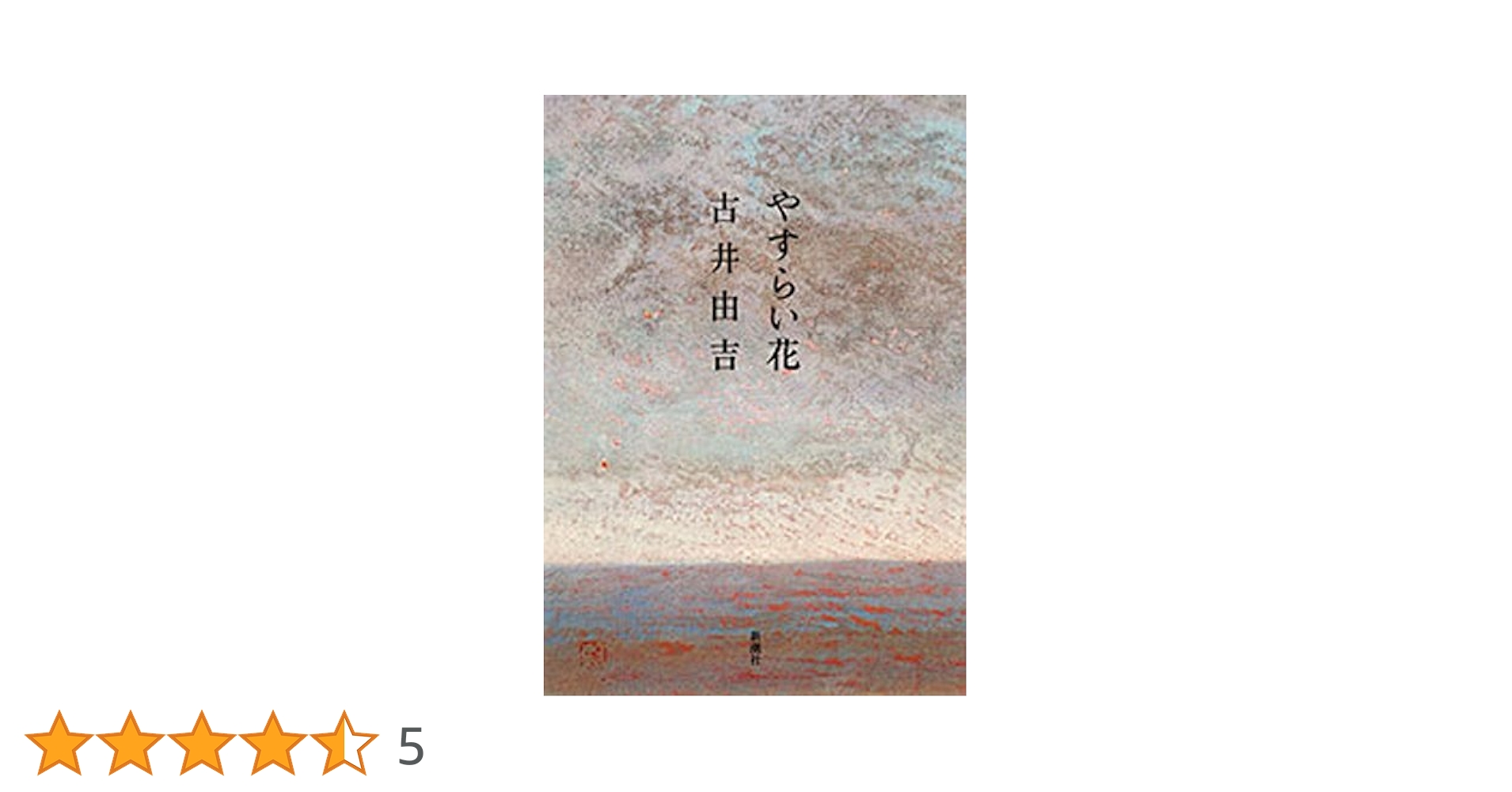
10位には、『やすらい花』がランクインしました。この作品は、古井文学の中でも特に文章の密度と美しさが際立つ一冊です。
物語は、ある夫婦の日常を中心に展開しますが、その背後には歴史や神話の世界が広がっています。現実と幻想が交錯する中で、人間の営みの儚さと、それでも続いていく生の力強さが描かれます。古井由吉の円熟期を代表する傑作であり、その豊潤な言葉の世界にじっくりと浸りたい読者におすすめです。



言葉の一つ一つが本当に美しい…。まるで詩を読んでいるような気持ちになったよ。
11位『雪の下の蟹・男たちの円居』
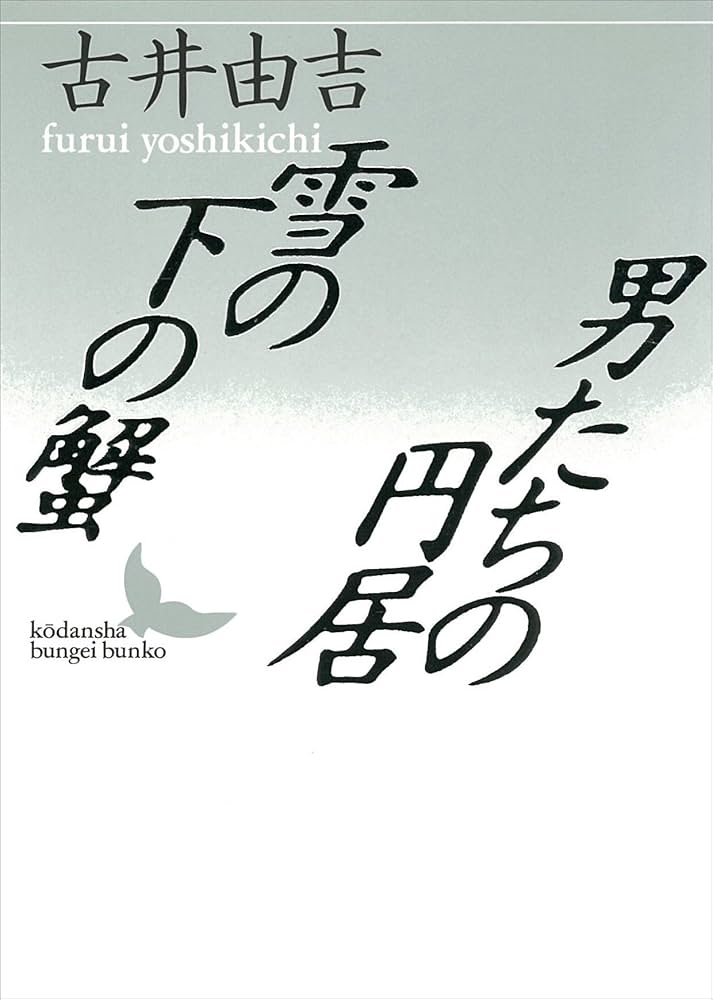
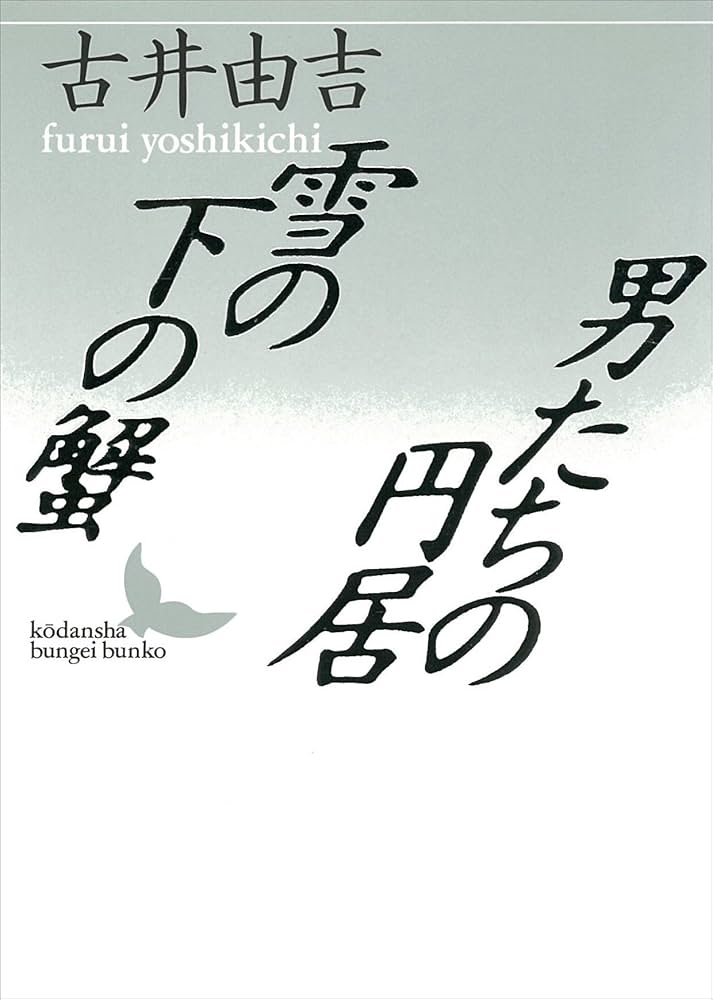
11位は、初期の短編「雪の下の蟹」と、芥川賞候補作にもなった中編「男たちの円居」を収録した一冊です。
「男たちの円居」は、友人たちが集まって酒を酌み交わすというシンプルな設定の中に、それぞれの男たちが抱える孤独や過去を浮かび上がらせます。一方、「雪の下の蟹」では、日常の風景がふとしたきっかけで異様な貌をのぞかせる瞬間が描かれます。どちらの作品も、後の古井文学へと繋がるテーマや文体の萌芽が見られ、ファンにとっては興味深い一冊と言えるでしょう。



男の人たちの会話って、なんだか独特の空気感があるよね。静かなんだけど、その奥に色々なものが隠れてる感じがしたよ。
12位『野川』
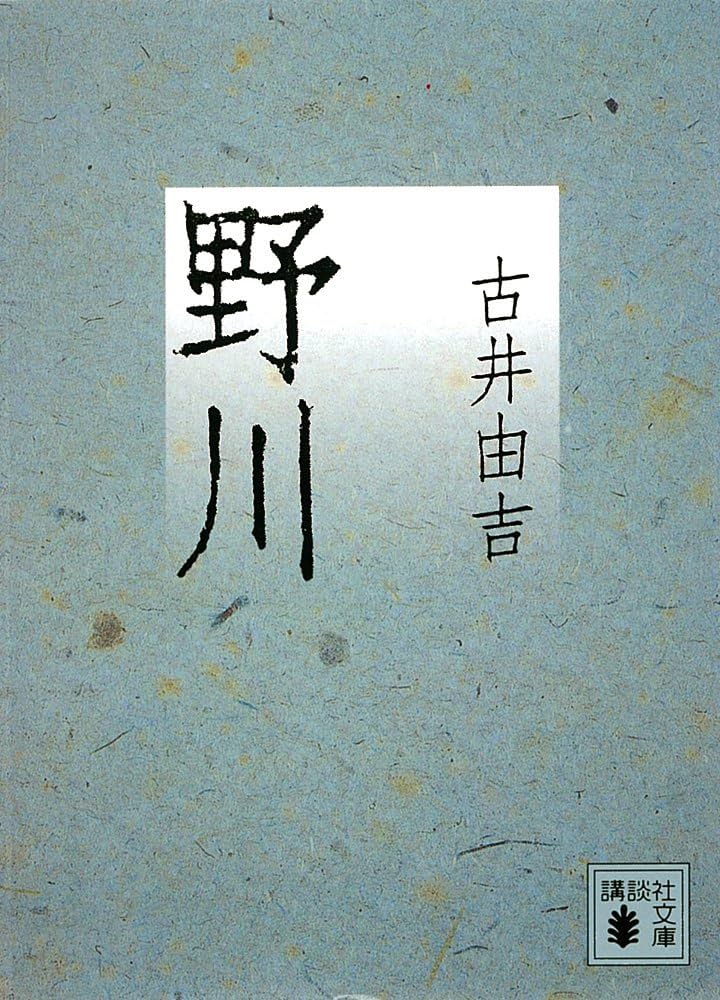
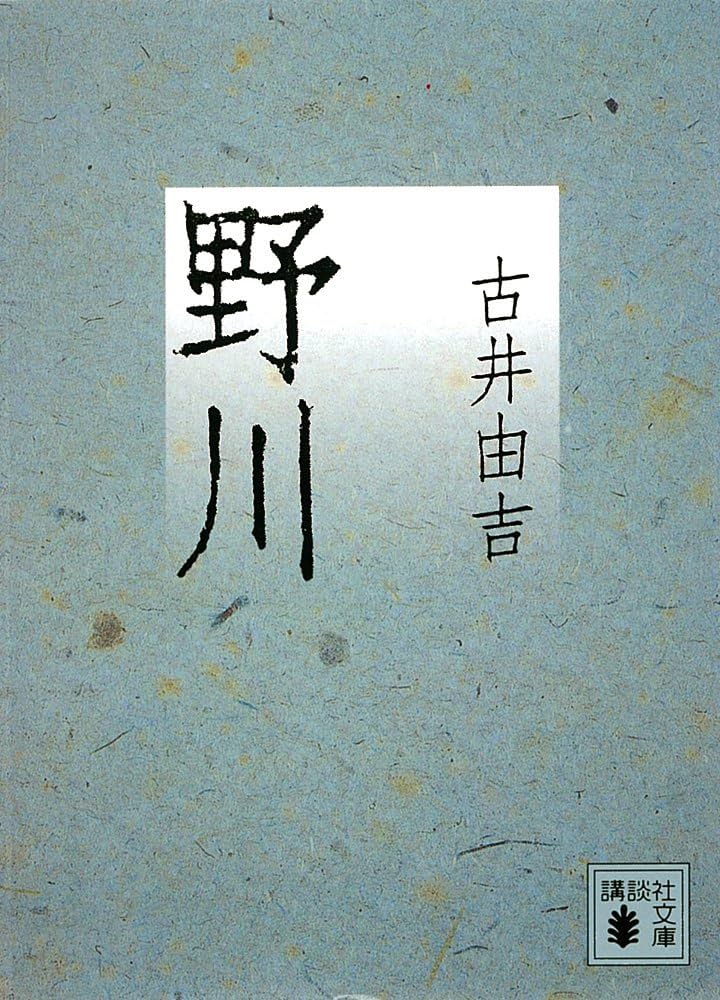
12位にランクインしたのは、武蔵野の風景を背景にした『野川』です。この作品では、身近な自然の描写を通して、人間の記憶や時間の流れが描かれています。
主人公が野川のほとりを散策する中で、過去の記憶や土地にまつわる物語が蘇ってきます。穏やかな筆致の中に、失われたものへの郷愁や、変わりゆく時代への眼差しが感じられます。古井由吉の作品の中では比較的読みやすい部類に入り、その詩的な世界観に触れる入り口としても適した一冊です。



川沿いを散歩しているような、のんびりした気持ちで読めたな。昔の風景が目に浮かぶようだったよ。
13位『栖』
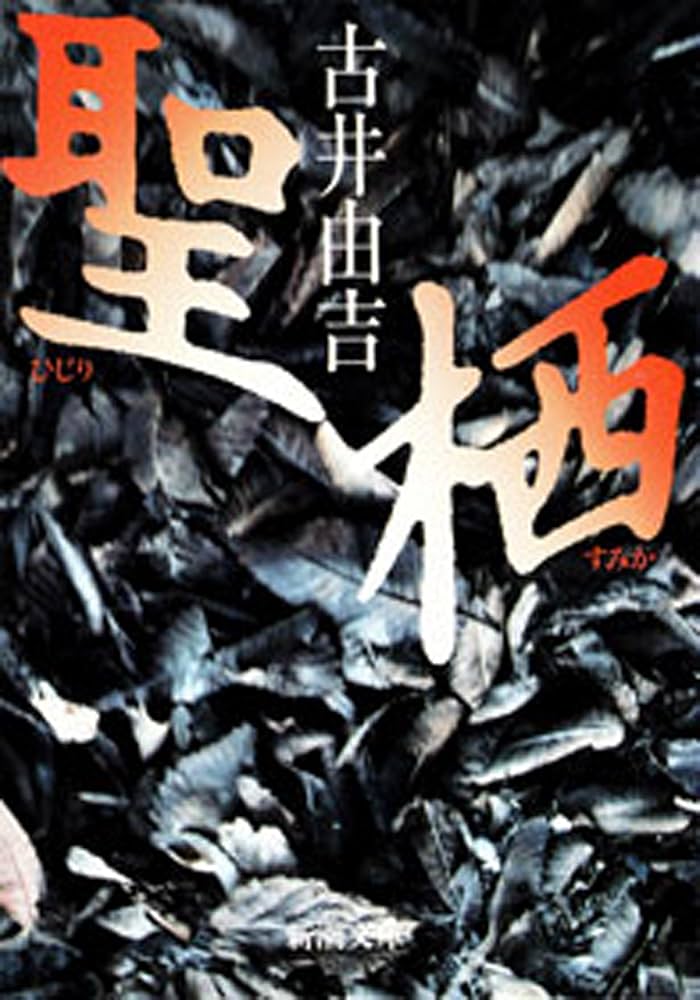
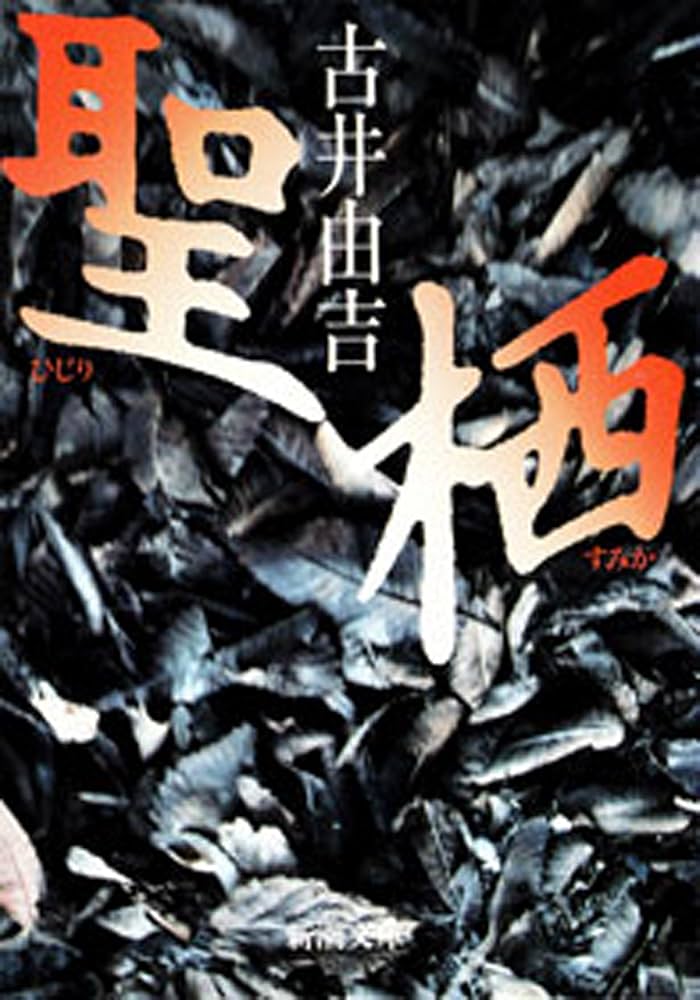
13位は、日本文学大賞を受賞した『栖』です。「栖(すみか)」というタイトルが示すように、この作品は人が住まう場所や、心の拠り所をテーマにしています。
物語は、ある家族の日常を淡々と描きながら、その生活の根底にある不安や揺らぎを巧みに捉えています。当たり前のように思える「家」や「家族」という存在が、決して盤石なものではないことを、古井由吉は静かな筆致で示唆します。人間の存在の根源を問うような、哲学的な深みを持った作品です。



自分の「すみか」ってどこなんだろうって考えちゃった。家族とか、安心できる場所の大切さを改めて感じたよ。
14位『鐘の渡り』
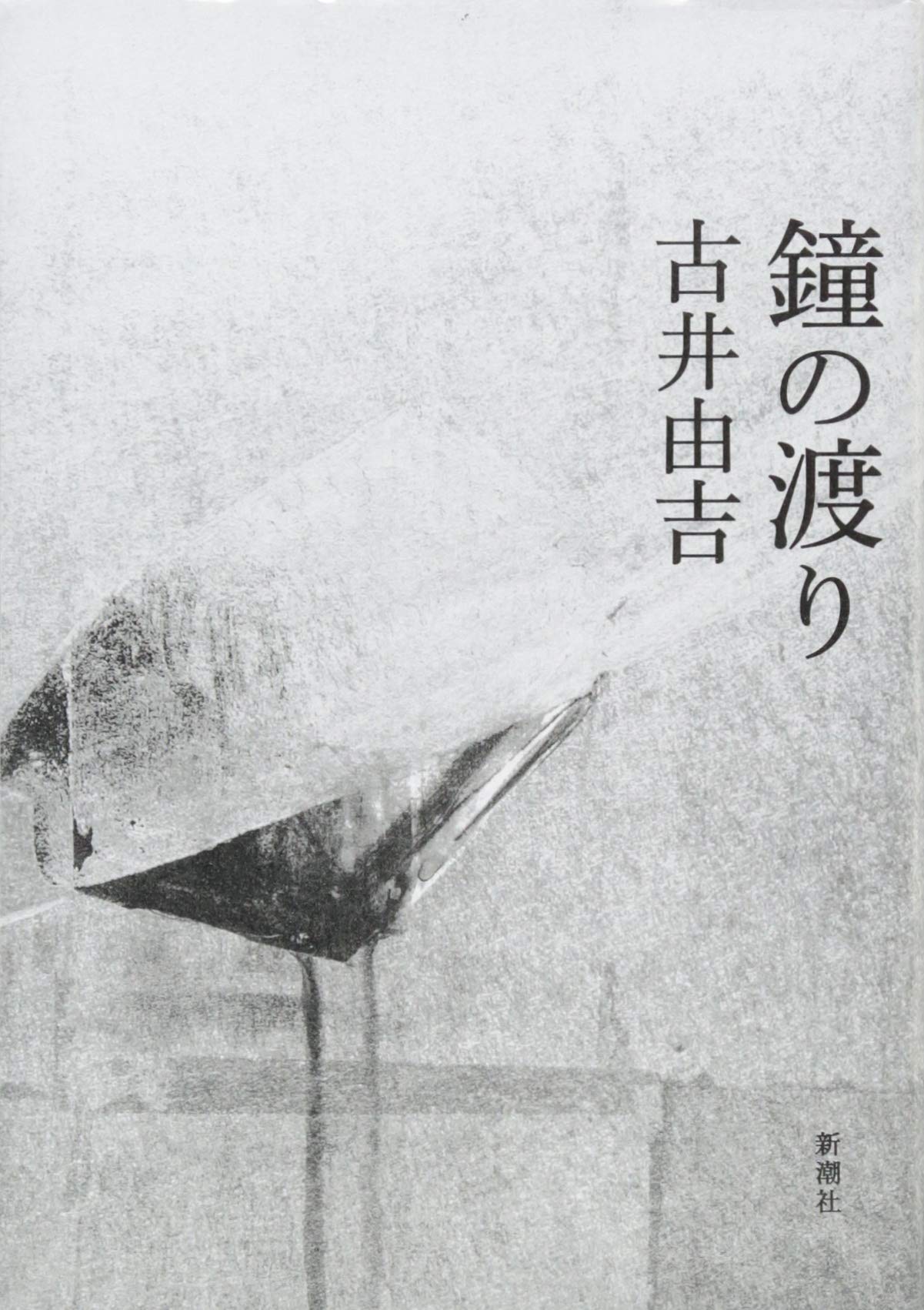
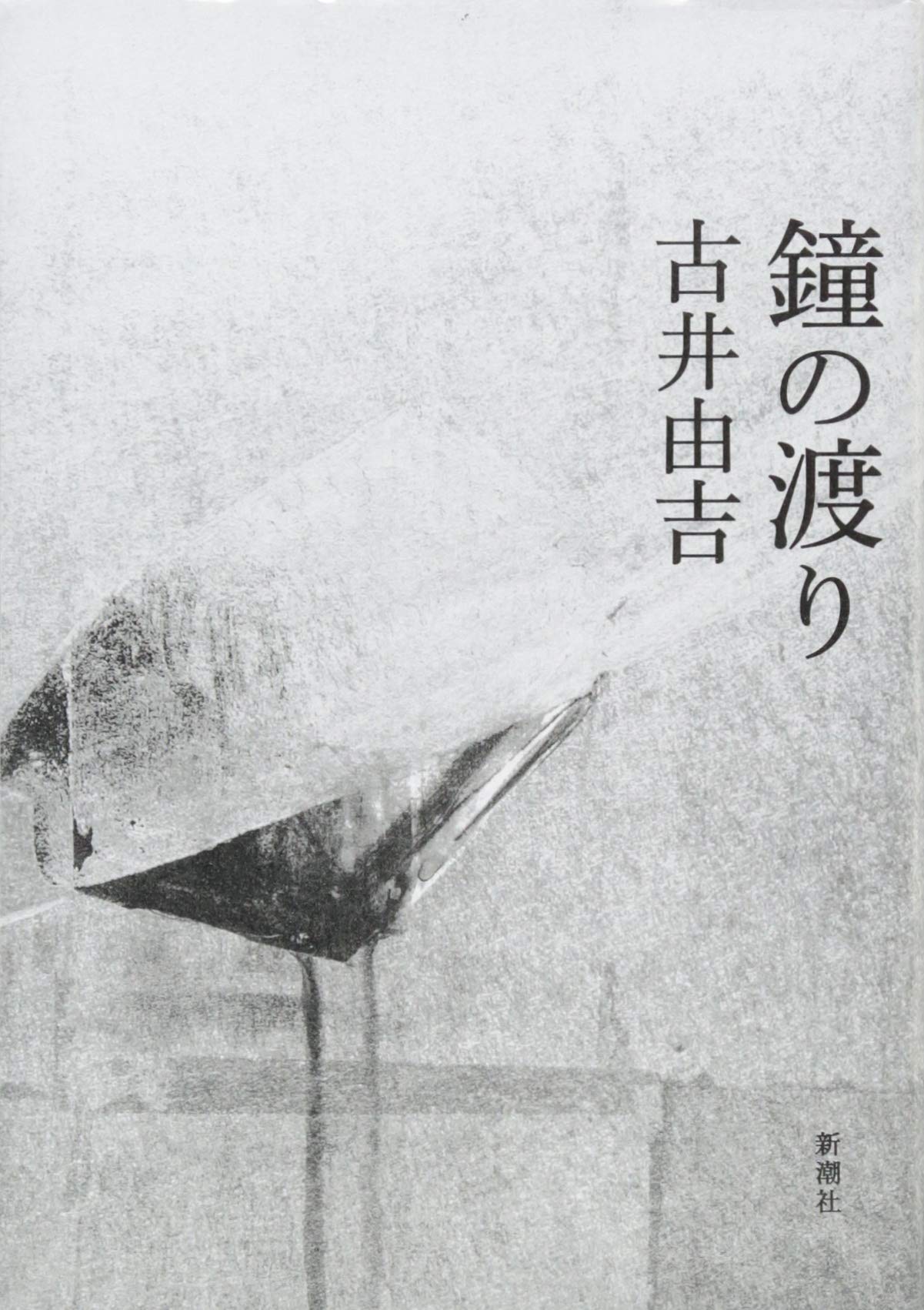
14位は、8つの短編からなる連作集『鐘の渡り』です。表題作では、妻を亡くした友人と旅に出た男の、妖しい山路が描かれます。
この作品集では、生と死、此岸と彼岸の境界が極めて曖昧に描かれているのが特徴です。紅葉が燃える山、女人の匂いが立ちのぼる森、そして夜の峠に響く鐘の音。五感を刺激するような描写が、読者を現実から少しだけ離れた場所へと誘います。古井由吉の言語表現の最先端とも評される、美しくもどこか不穏な一冊です。



なんだか不思議な山に迷い込んだみたい…。鐘の音がずっと耳に残っていて、ちょっと怖いけど惹きつけられるよ。
15位『聖』
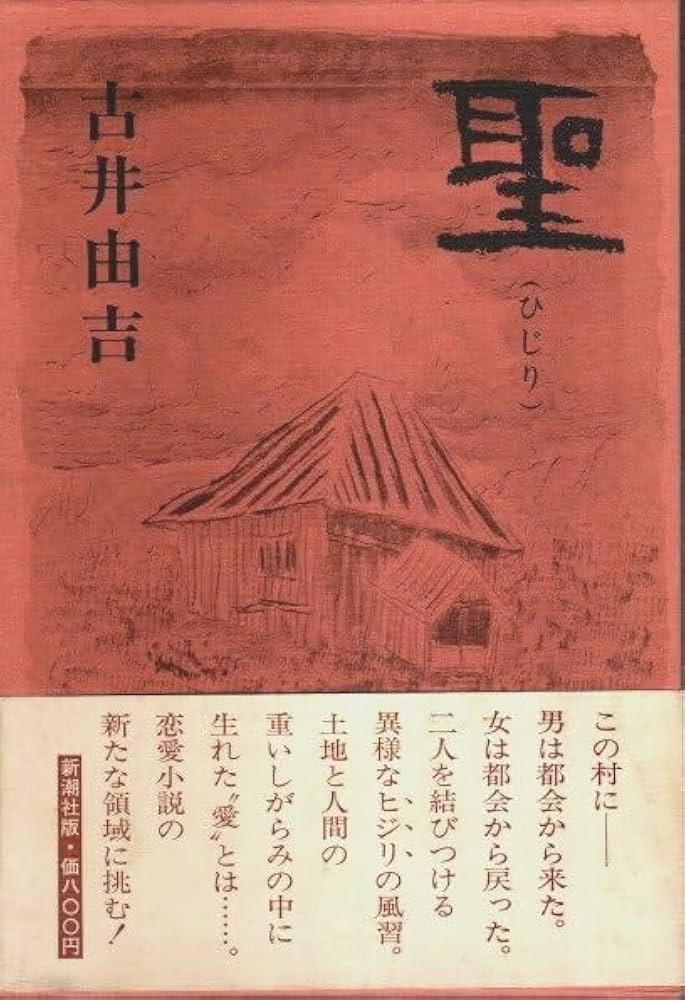
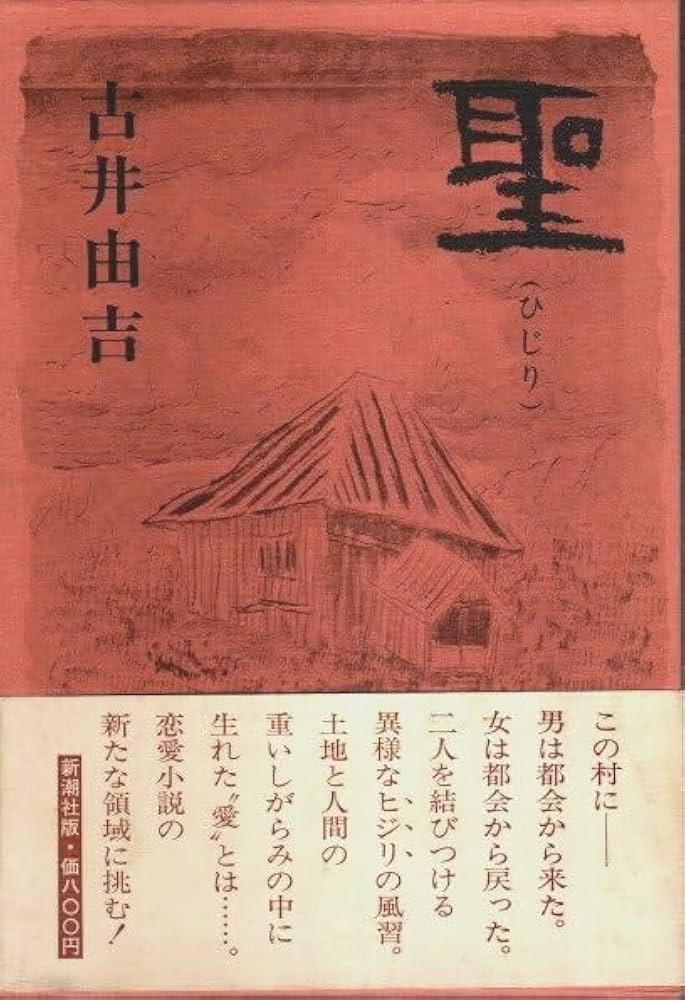
15位には、『聖』がランクインしました。この作品は、聖(ひじり)と呼ばれる、世俗を捨てて山野を巡る人々の姿を描いています。
古井由吉は、民俗的なモチーフに関心を寄せ、土俗的な世界を作品に取り入れています。『聖』では、常識的な世界の外側で生きる人々の、常人には理解しがたい精神性や生き様が、畏敬の念を込めて描かれています。近代的な自我とは異なる価値観に触れることで、読者自身の生き方をも問い直させるような、力強い作品です。



俗世間から離れて生きるって、どんな感じなんだろう。わたしには真似できないけど、少し憧れるかもしれないな。
16位『この道』
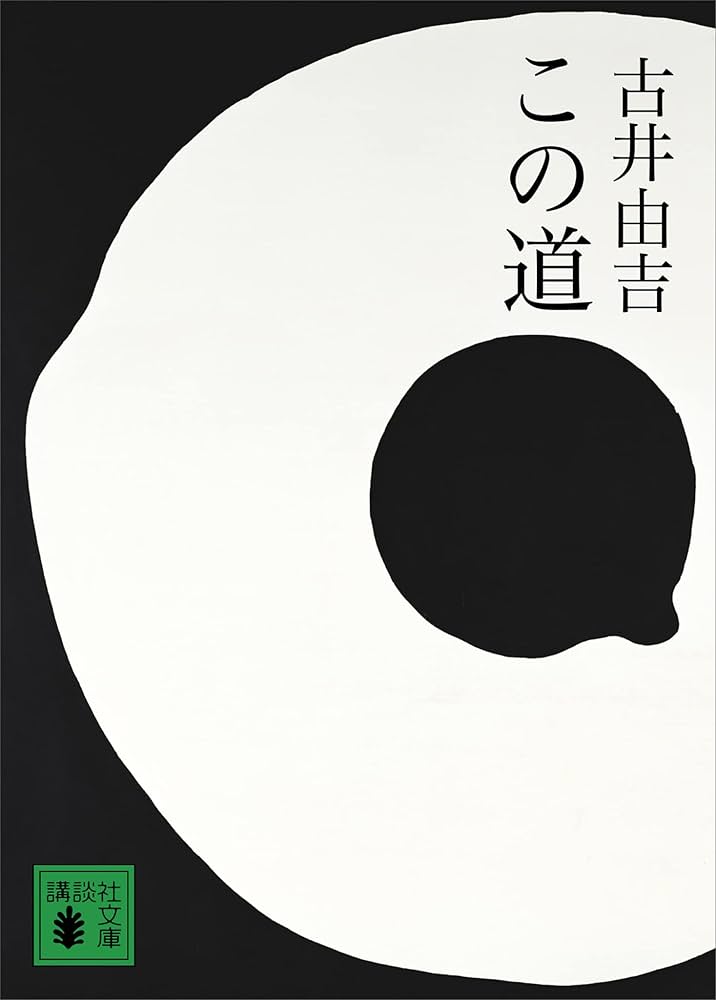
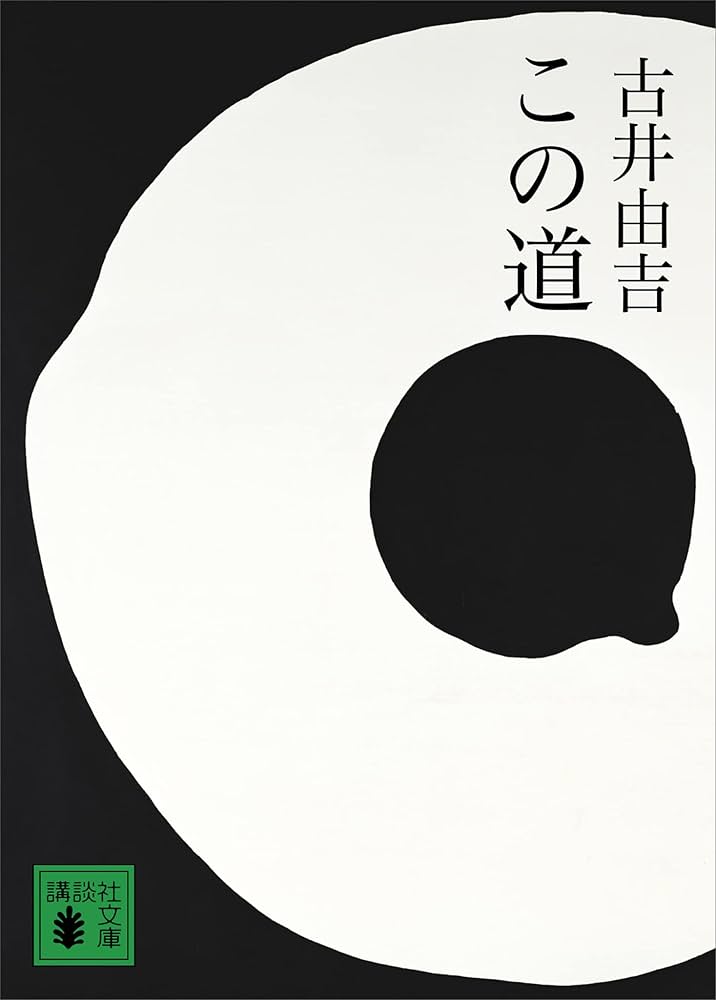
16位は、ある男が歩んできた人生の道のりを静かに振り返る『この道』です。古井由吉の晩年の作品であり、その円熟した境地が感じられます。
派手な出来事が起こるわけではありませんが、主人公の記憶の断片をたどる中で、人生の様々な局面が浮かび上がってきます。過ぎ去った時間への愛おしみや、避けられぬ老いと死への諦観が、抑制の効いた美しい文章で綴られています。人生の黄昏時に差し掛かった人間の内面を深く描いた、味わい深い一冊です。



自分の人生を振り返るって、こういう感じなのかな。静かで、少しだけ切ない気持ちになったよ。
17位『親』
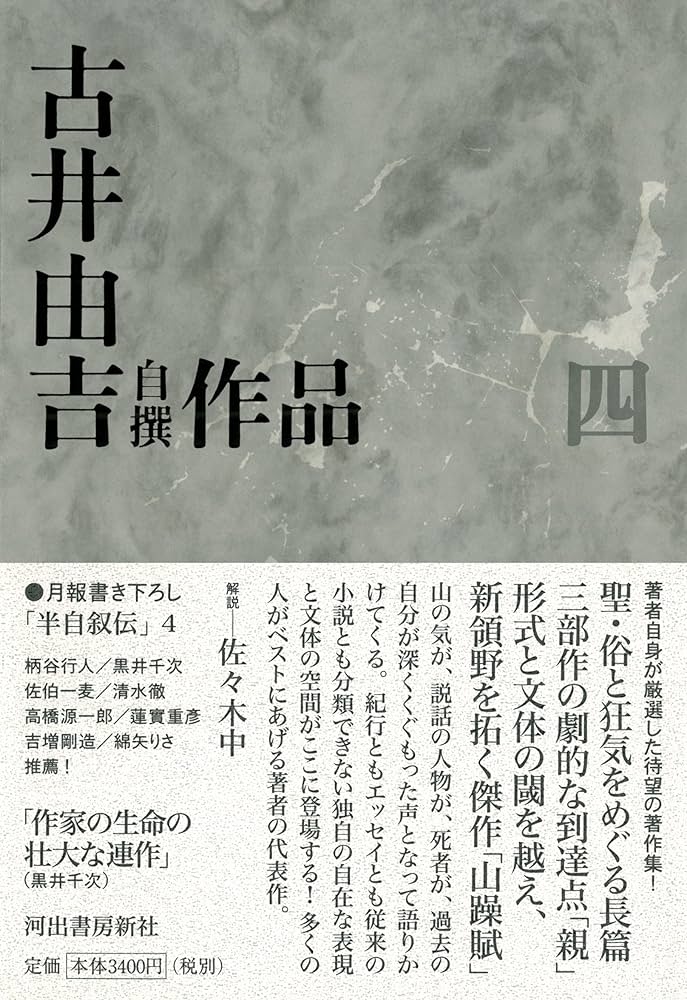
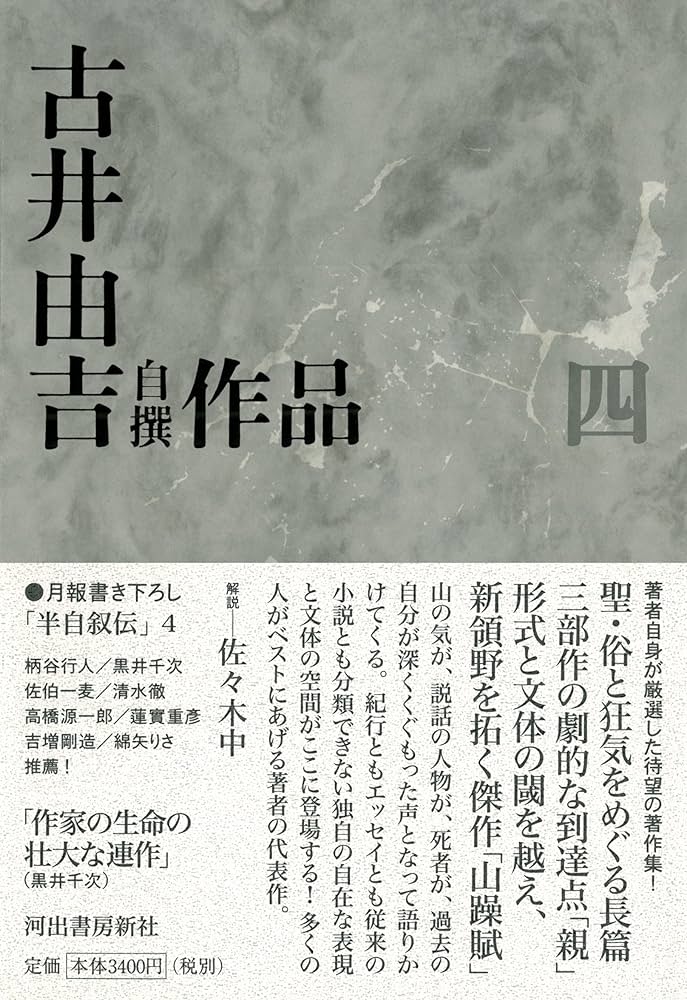
17位にランクインしたのは、そのものずばりのタイトルが印象的な『親』です。この作品は、親と子の複雑で断ち切りがたい関係性をテーマにしています。
誰もが経験するであろう、親との関係。その中で生じる愛情、憎しみ、憐れみ、そして理解といった、一言では言い表せない複雑な感情の機微を、古井由吉は丹念に描き出します。自身の親との関係や、自分が親であることの意味を考えさせられる、普遍的なテーマを扱った作品です。



親子の関係って、本当に色々あるよね…。読んでいて、自分の親のことを思い出して、ちょっと泣いちゃった。
18位『眉雨』
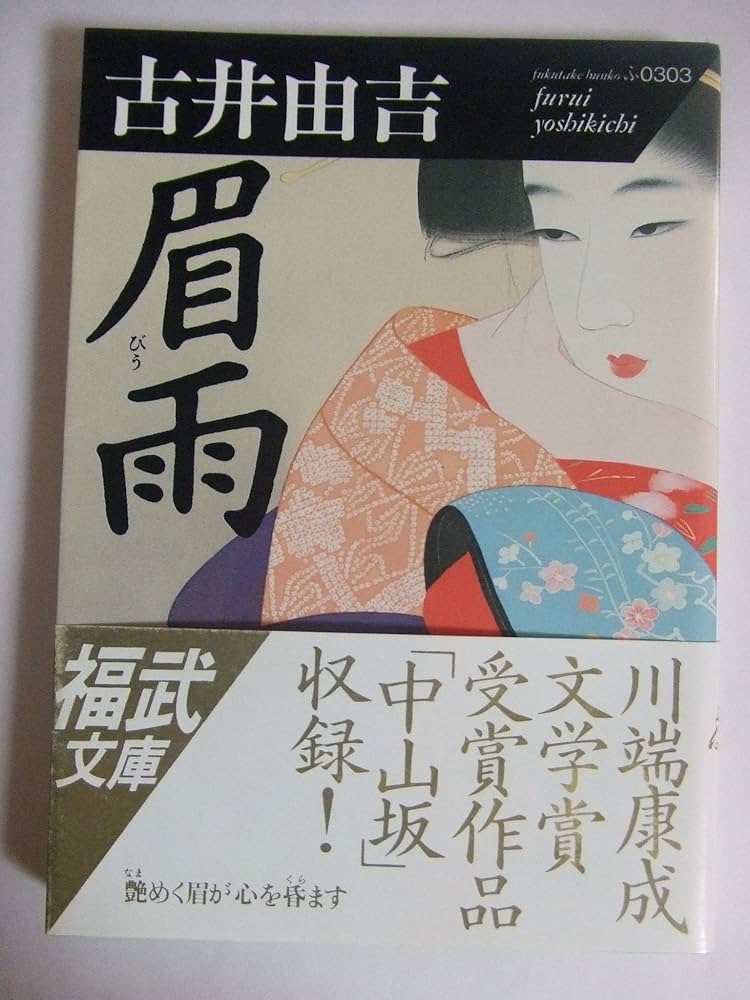
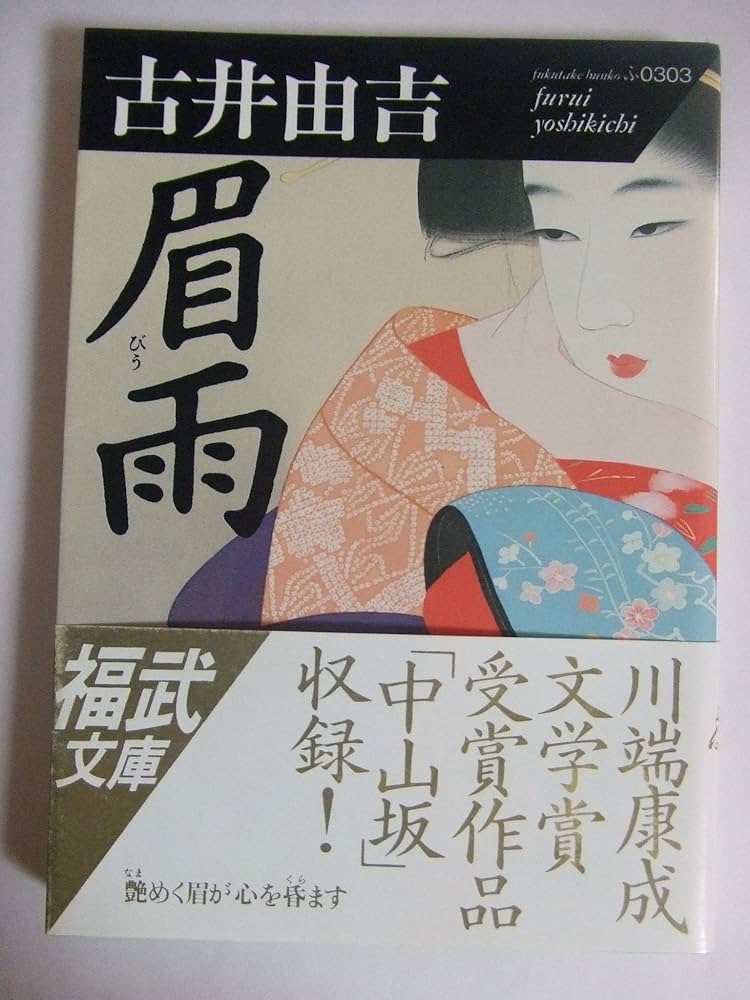
18位は、繊細な感覚が光る『眉雨』です。この作品は、日常の中にふと現れる、言葉にしがたい感覚や気配を捉えようと試みています。
例えば、雨の日の気配や、人の表情の微細な変化といった、普段は見過ごしてしまいがちな事柄に、古井由吉は鋭い観察眼を向けます。



普段は気にしないような小さなことに、こんなに豊かな世界が広がってるなんて驚きだよ。世界が違って見えてくる感じがするね。
19位『楽天記』
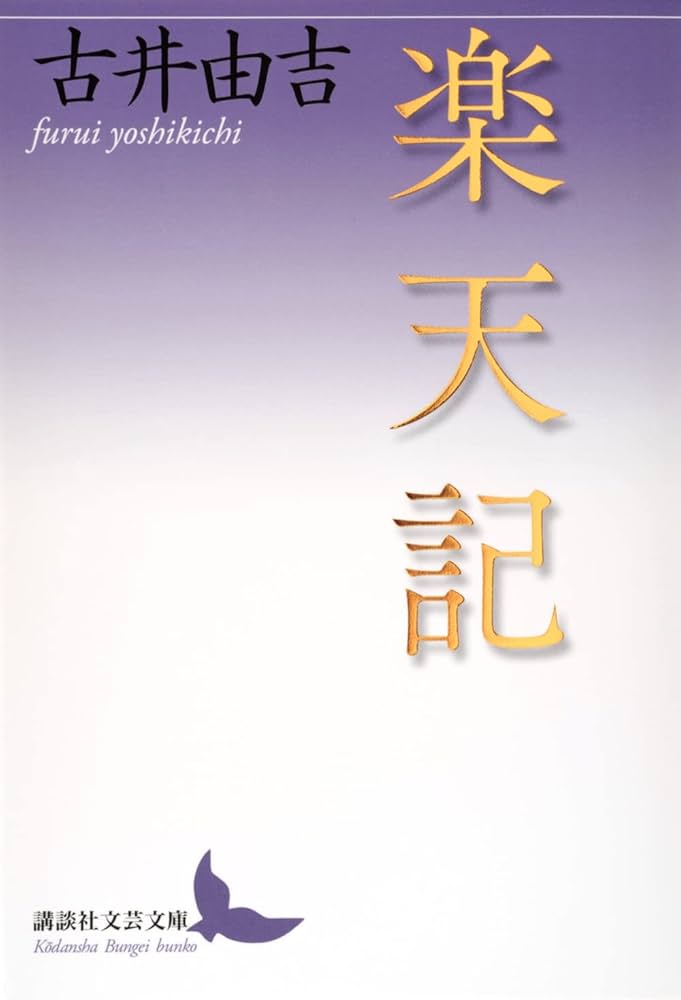
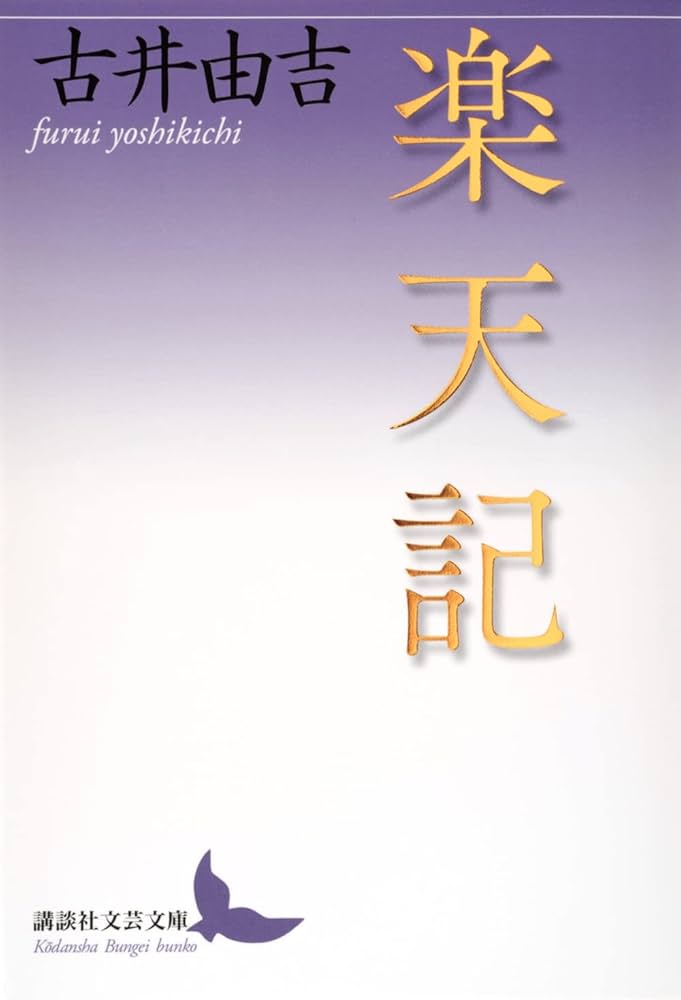
ランキングの最後を飾るのは、長編小説『楽天記』です。作家である主人公・柿原の日常を通して、老いや死への思いが描かれます。
夢の中の息子との対話、旧約聖書の言葉、亡き友人の仕草など、うつろいゆく日々の中で、生と死の諸相が密やかに重なり合います。私小説的な手法を用いながら、人間の精神の深奥へと分け入っていく自在な筆致は、まさに古井文学の真骨頂です。生涯を「よろぼい」ながら生きる人々の心にある「楽天」とは何かを問いかけます。



老いることや死ぬことを考えながらも、どこか軽やかに生きる。そんな「楽天」的な生き方に、わたしはすごく惹かれるな。
まとめ:古井由吉の小説を読み解くために
ここまで、古井由吉のおすすめ小説をランキング形式でご紹介してきました。彼の作品は、明確なストーリーを追うよりも、その濃密な文体と、言葉が喚起する感覚に身を委ねることで、より深く味わうことができます。
もし、どの作品から読めばいいか迷ったら、まずは芥川賞受賞作である『杳子・妻隠』や、自選短編集である『木犀の日』から手に取ってみるのがおすすめです。そこから、古典的な世界に触れたいなら『仮往生伝試文』、生と性の深淵を覗きたいなら『槿』へと読み進めていくのも良いでしょう。
古井由吉の文学は、私たちに日常の奥深さや、人間の存在そのものの不思議さを教えてくれます。ぜひこの記事を参考に、あなたにとっての特別な一冊を見つけてみてください。





