あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】野坂昭如の小説おすすめランキングTOP12

野坂昭如とは?- 戦争体験と「焼跡闇市派」の視点で人間の性を描いた作家
野坂昭如(のさか あきゆき)は、小説家、作詞家、歌手、政治家など、多彩な顔を持つ作家です。自身のことを「焼跡闇市派」と称し、その作品の多くには、自身の過酷な戦争体験が色濃く反映されています。
1945年の神戸大空襲で養父を亡くし、疎開先で1歳半の義妹を栄養失調で亡くすという壮絶な体験は、『火垂るの墓』などの作品の原点となりました。野坂昭如は、戦争の悲惨さや人間の業、性を、時にユーモラスに、時に辛辣な視点で描き出し、戦後日本文学に大きな影響を与えました。
【2025年最新】野坂昭如のおすすめ小説ランキングTOP12
ここからは、数ある野坂昭如の作品の中から、今こそ読んでほしいおすすめの小説をランキング形式でご紹介します。戦争文学の金字塔から、人間の欲望を赤裸々に描いた問題作まで、野坂作品の多岐にわたる魅力に触れられるラインナップです。
それぞれの作品が持つ独特の世界観や、心に深く突き刺さるメッセージを感じてみてください。あなたの心に残る一冊が、きっと見つかるはずです。
1位『アメリカひじき・火垂るの墓』
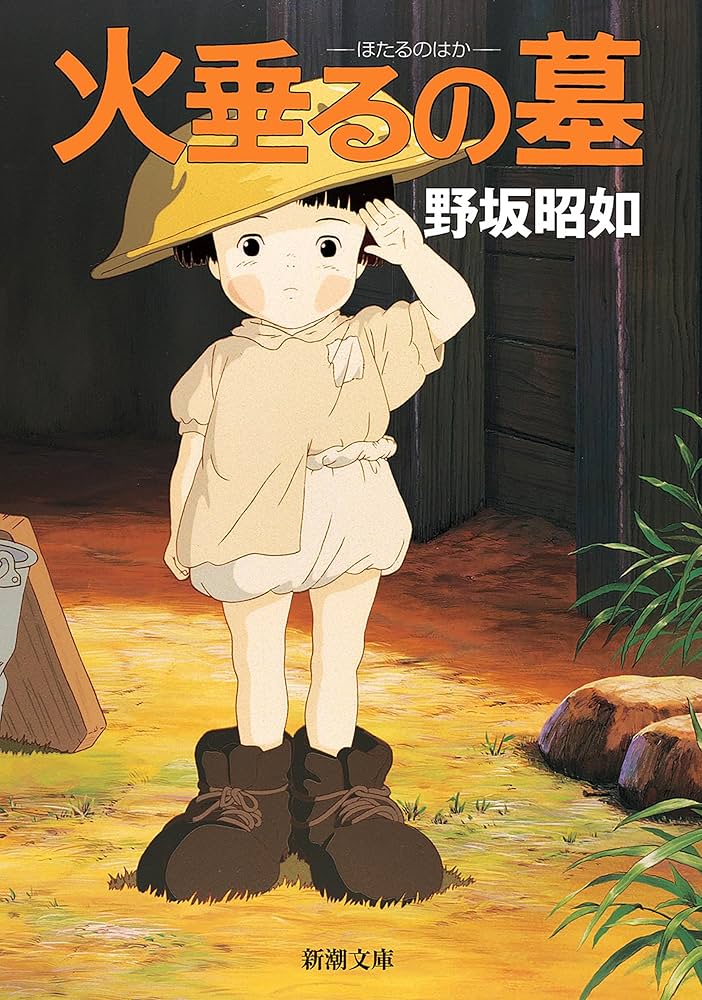
野坂昭如の代表作であり、1968年に第58回直木賞(1967年度下半期)を受賞した作品です。表題作の『アメリカひじき』は、戦後の日本人が抱えるアメリカへのコンプレックスを、『火垂るの墓』は神戸大空襲下での幼い兄妹の悲劇を描いています。
特に『火垂るの墓』は、作者自身の戦争体験が基になっており、妹を失ったことへの贖罪の念が込められた半自伝的な小説です。戦争の残酷さと、その中で失われていく命の儚さを描き、読む者の胸を強く打ちます。野坂文学の原点ともいえる、必読の一冊です。
 ふくちい
ふくちいわたし、この物語は涙なしには読めないよ…。清太の気持ちを考えると、胸が張り裂けそうになるんだ。
2位『エロ事師たち』
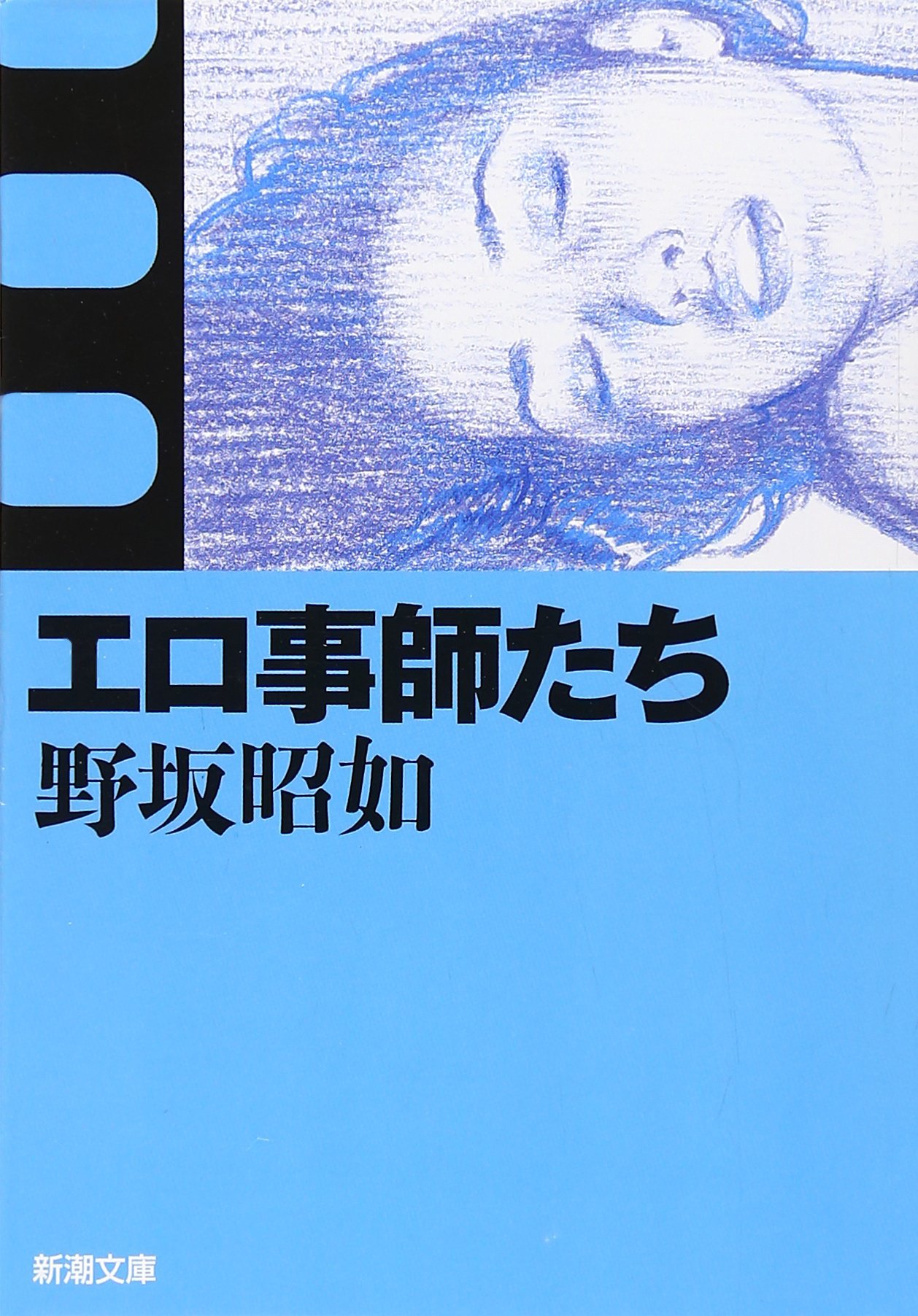
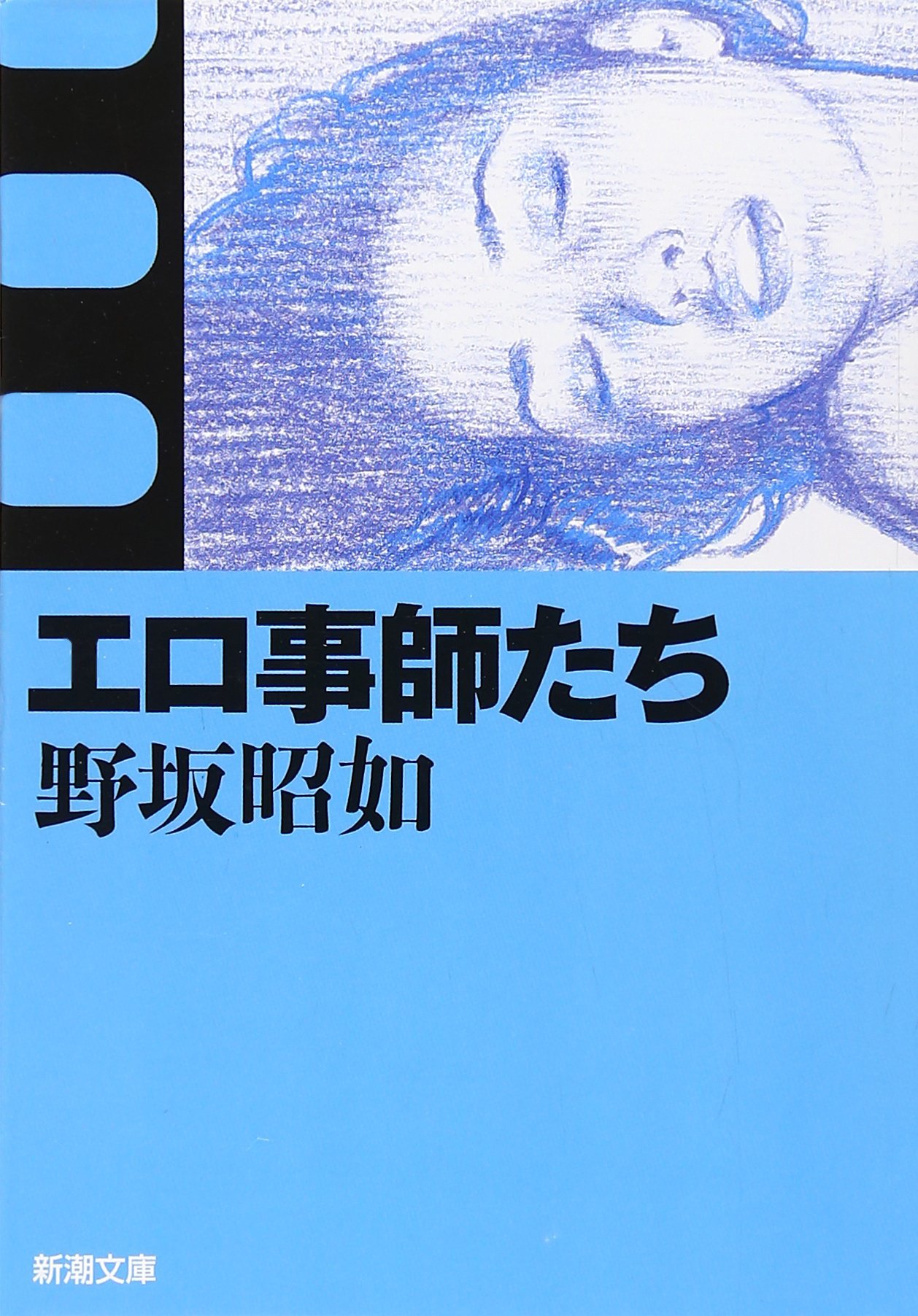
1963年に発表された野坂昭如の小説家としてのデビュー作です。ポルノ映画の撮影や販売などで生計を立てる主人公「スブやん」を通して、人間の飽くなき性への欲望を赤裸々かつユーモラスに描いています。
戦後の混乱期をたくましく生きる人々のエネルギーと、人間の根源的な性をテーマにした本作は、大きな注目を集めました。野坂昭如のもう一つの側面である、猥雑でパワフルな世界観を存分に味わえる作品です。



人間の欲望をここまで書けるなんて衝撃的だよ。でも、登場人物たちがどこか憎めなくて魅力的なんだよね。
3位『戦争童話集』
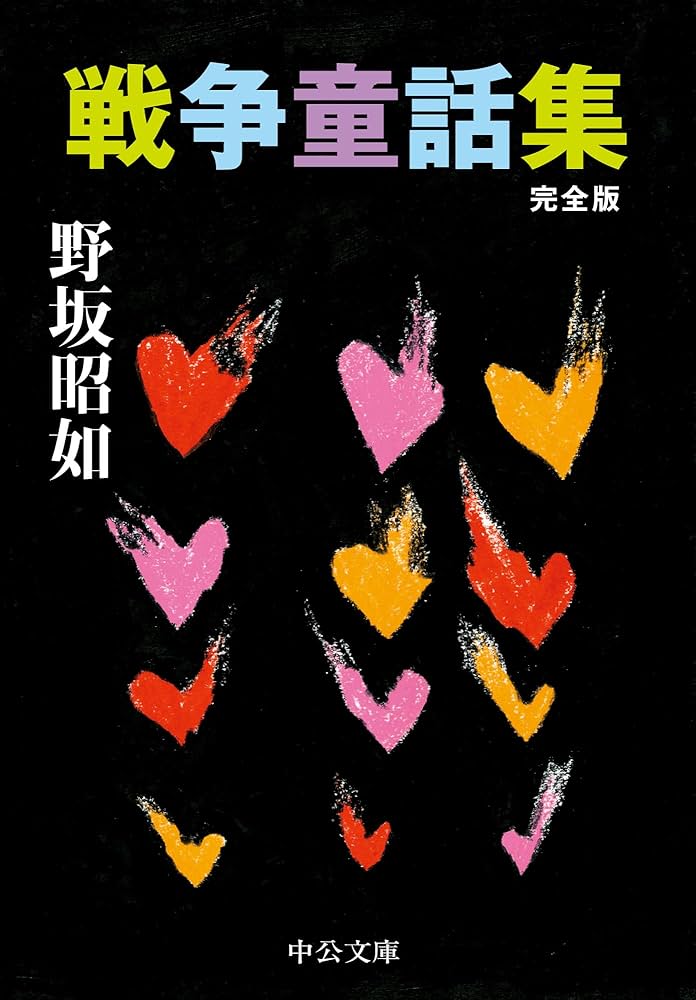
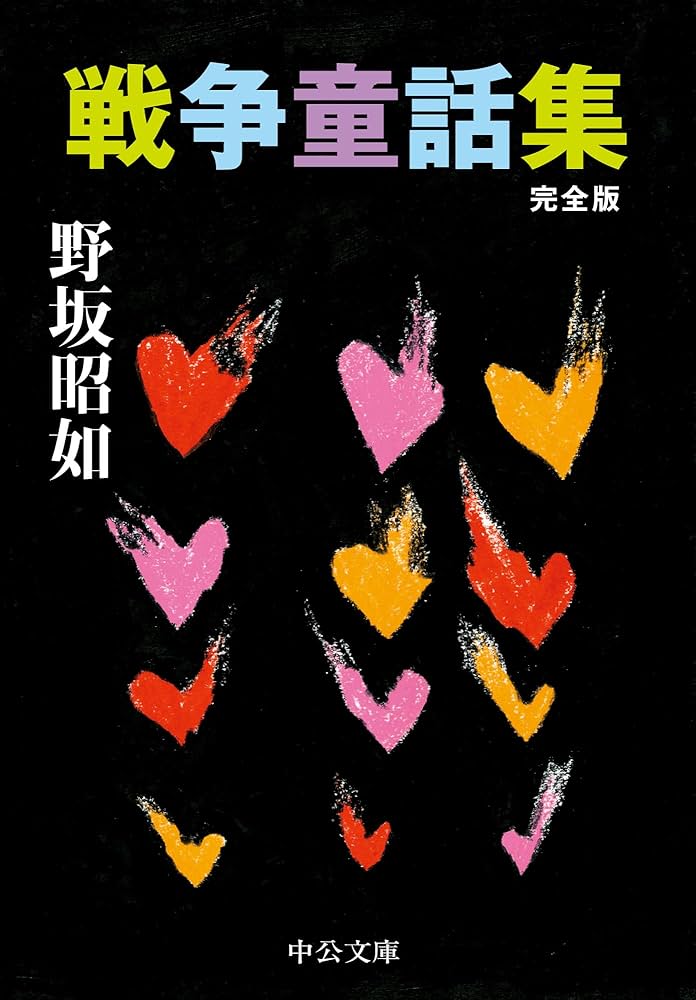
『凧になったお母さん』や『焼跡の、お菓子の木』など、戦争を題材にした12の短編が収められた作品集です。一見すると子供向けの「童話」という形式を取りながらも、その内容は戦争の理不尽さや悲劇を容赦なく描いています。
動物やモノの視点から語られる物語は、人間の愚かさや戦争の無意味さを一層際立たせます。子供だけでなく、大人にこそ読んでほしい、平和の尊さを問い直すきっかけとなる一冊です。



本作における戦争の描写は、感傷を排した冷徹な視点で貫かれている。これは作者が体験した現実の過酷さを、何らオブラートに包むことなく提示しようとする意志の表れだろう。
4位『とむらい師たち』
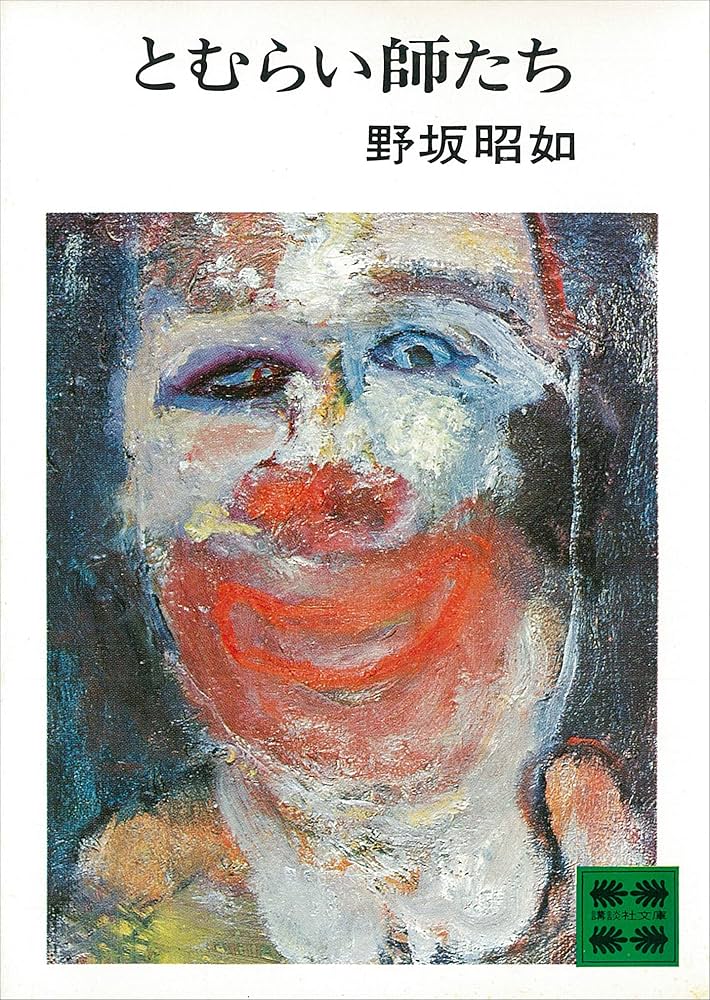
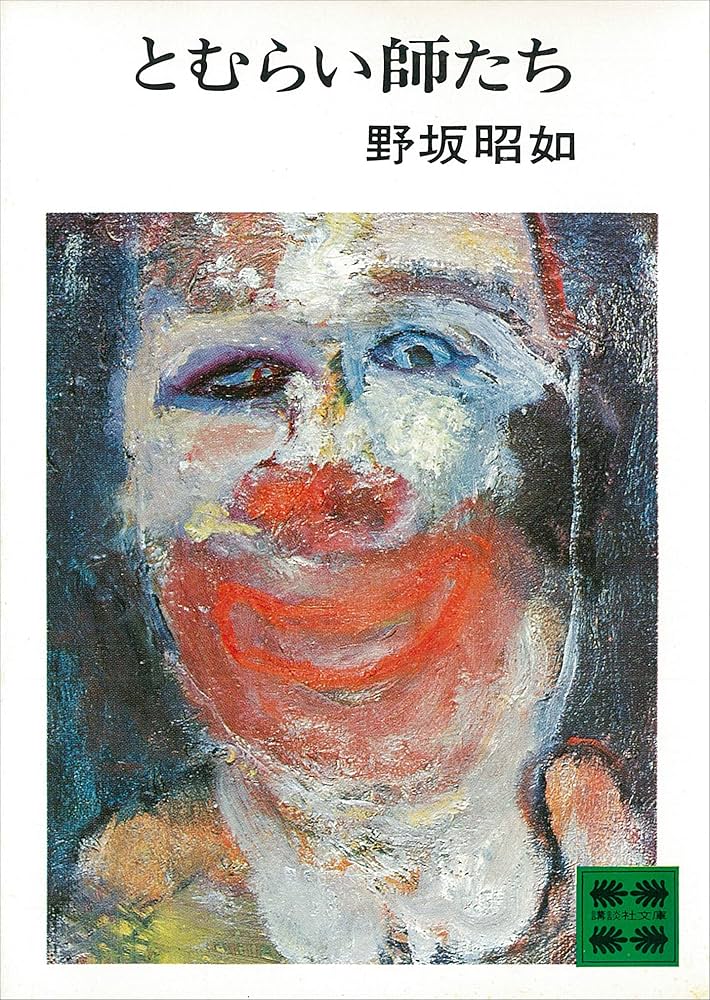
「葬式」をテーマに、様々な死の形とそれを取り巻く人間模様を、ブラックユーモアを交えて描いた連作短編集です。主人公は、あらゆる葬儀を仕切るプロフェッショナル「とむらい師」。
彼の目を通して語られるのは、滑稽でありながらもどこか物悲しい、人間の生と死のドラマです。野坂昭如ならではの独特の死生観と、皮肉の効いた視点が光る作品。しんみりとするだけでなく、思わず笑ってしまうようなエピソードも多く、そのバランス感覚が絶妙です。



お葬式がテーマなのに笑えるなんて不思議だよ。でも、だからこそ「死」について深く考えさせられるのかもね。
5位『文壇』
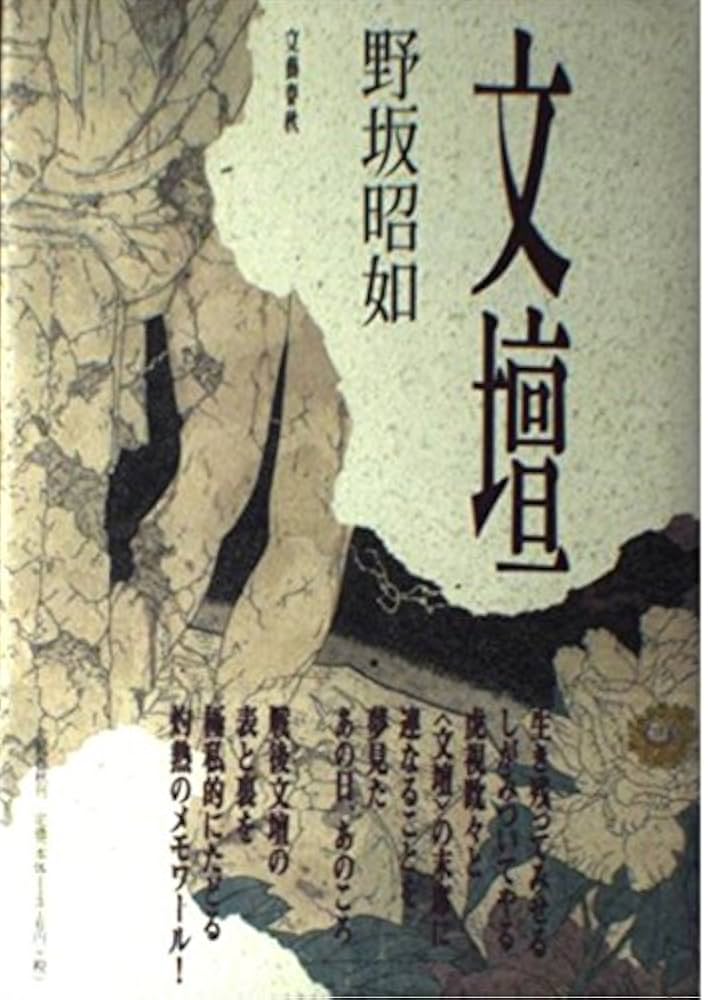
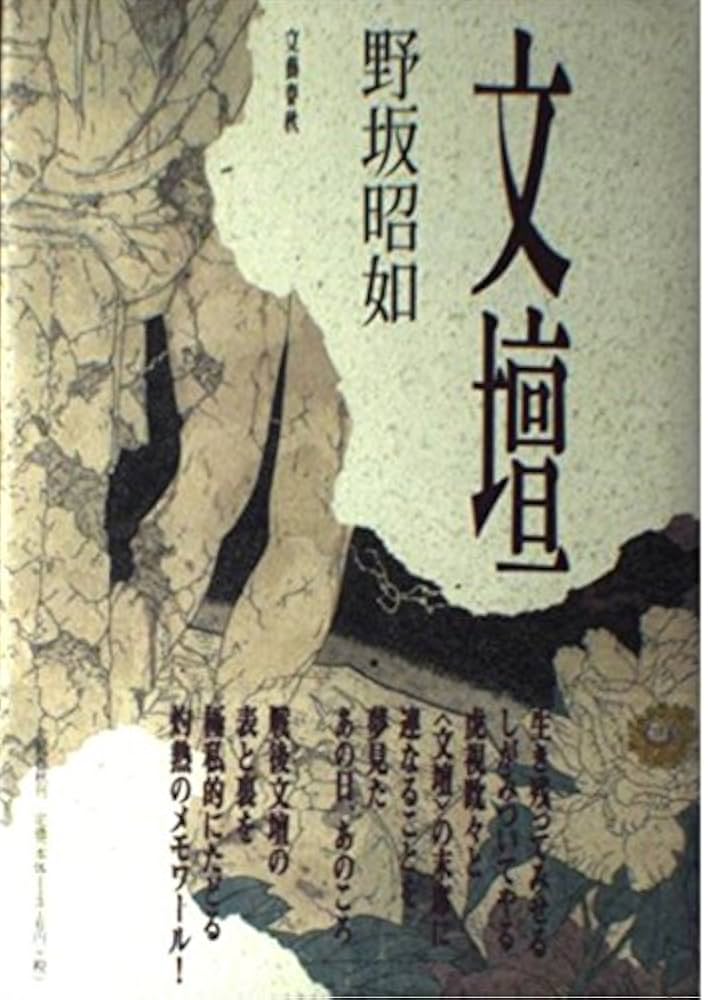
2002年に泉鏡花文学賞を受賞した、野坂昭如の私小説的な作品です。作家「野坂昭如」を思わせる主人公が、文壇で出会った実在の作家たちとの交流や、自身の創作活動について赤裸々に綴っています。
三島由紀夫や開高健といった文豪たちが実名で登場し、彼らとのエピソードが生き生きと描かれています。作家の苦悩や葛藤、そして文学への情熱が伝わってくる、文学ファン必読の一冊です。



昭和の文豪たちの素顔が垣間見えて、すごく面白いよ。作家って、やっぱり人間味あふれる人たちなんだね。
6位『骨餓身峠死人葛』
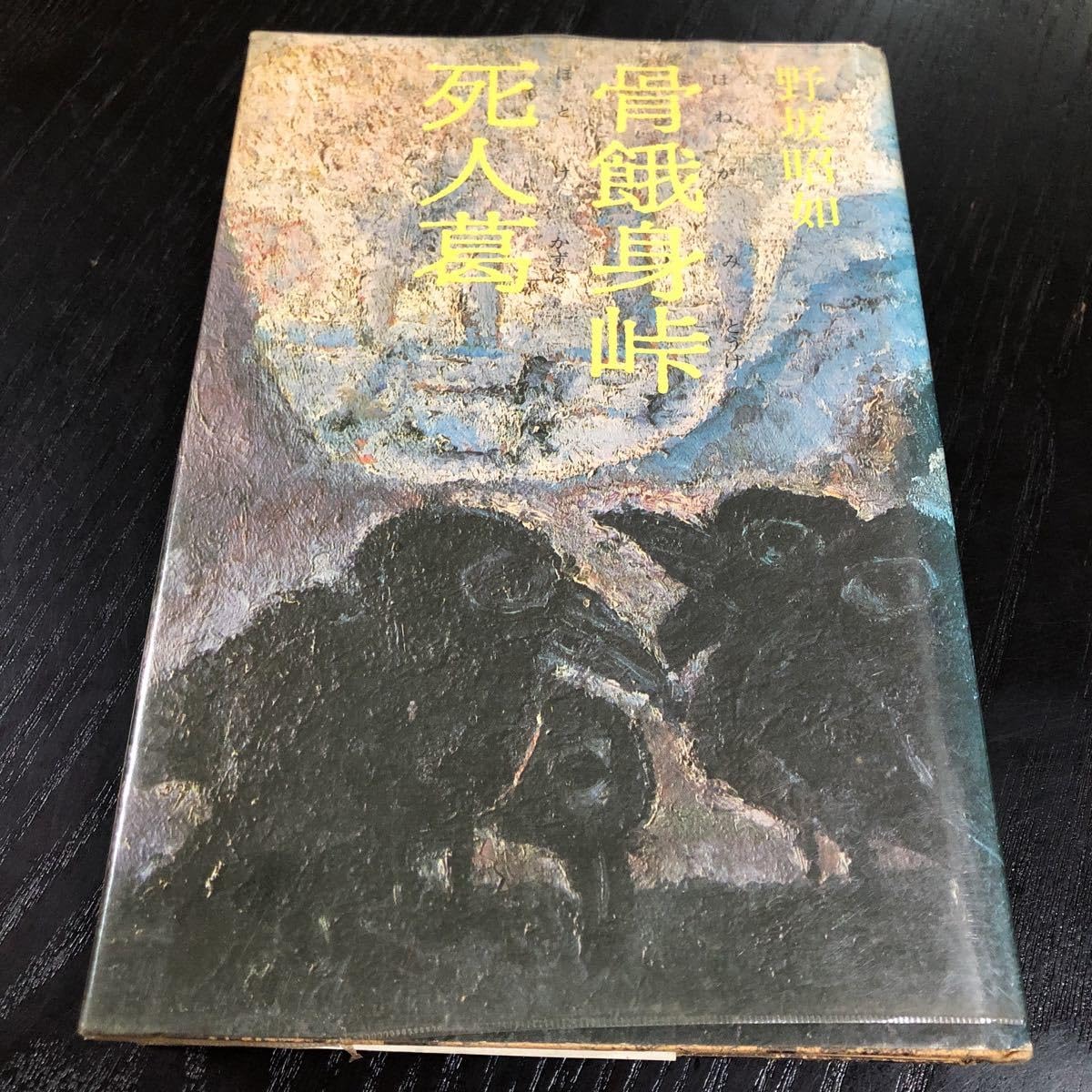
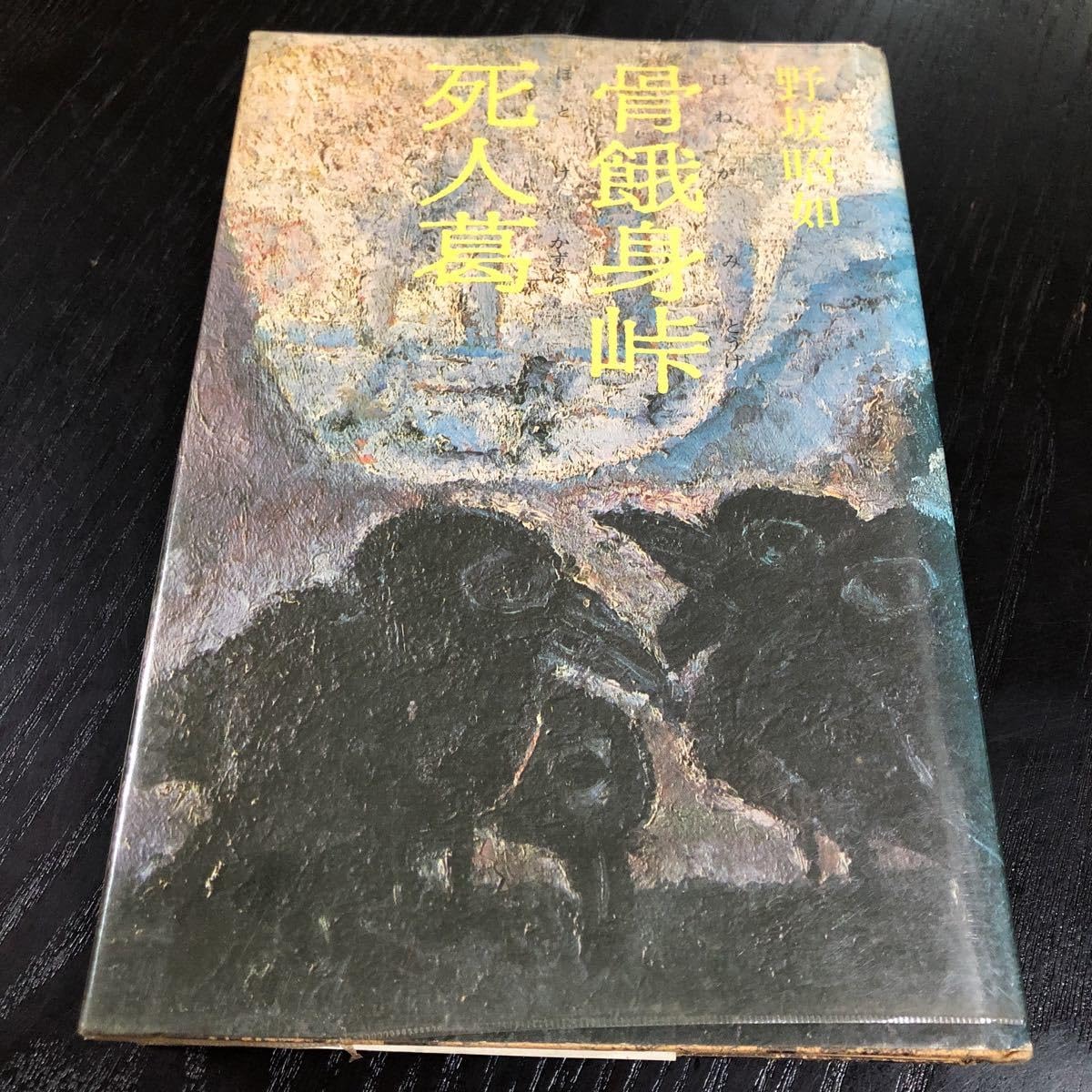
飢餓や人肉食といった極限状況における人間の本性を、グロテスクかつ幻想的に描いた問題作です。物語の舞台は、飢えに苦しむ人々がさまよう「骨餓身峠」。
そこで繰り広げられる壮絶な生存競争と、狂気の世界が圧倒的な筆致で描かれています。人間の倫理観が崩壊した世界で、人はどこまで人でいられるのかを問いかける、強烈な読書体験をもたらす一冊です。



極限状態における人間の変容を描く筆致は、読者の安寧を徹底的に破壊する。本作が内包する暴力性は、表層的な恐怖を凌駕する根源的な問いを我々に突きつける。
7位『マリリン・モンロー・ノー・リターン』
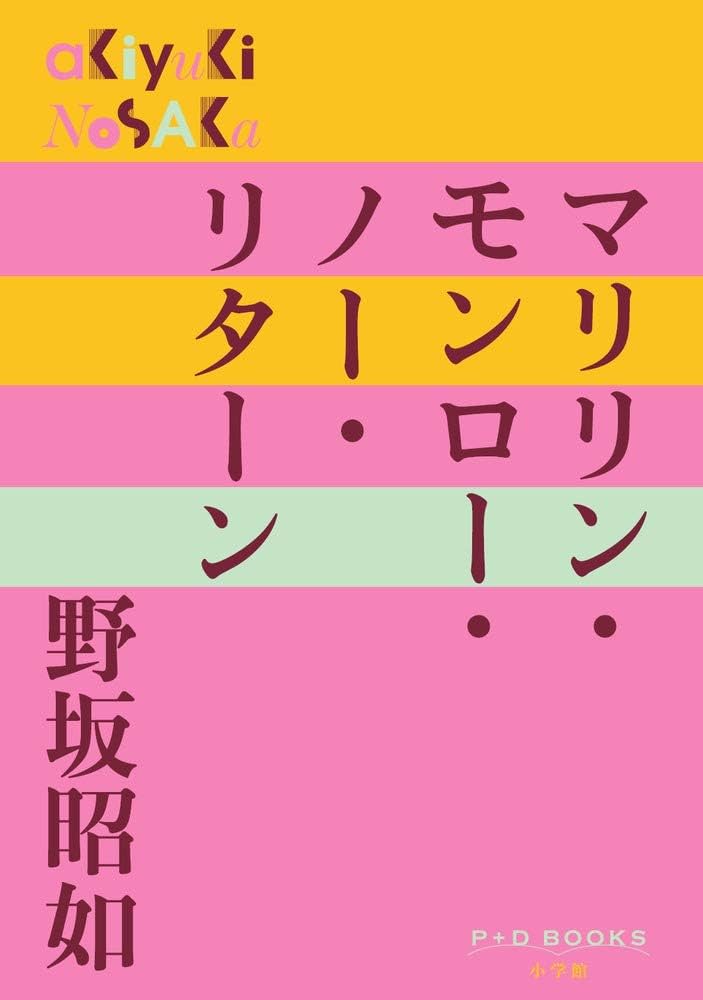
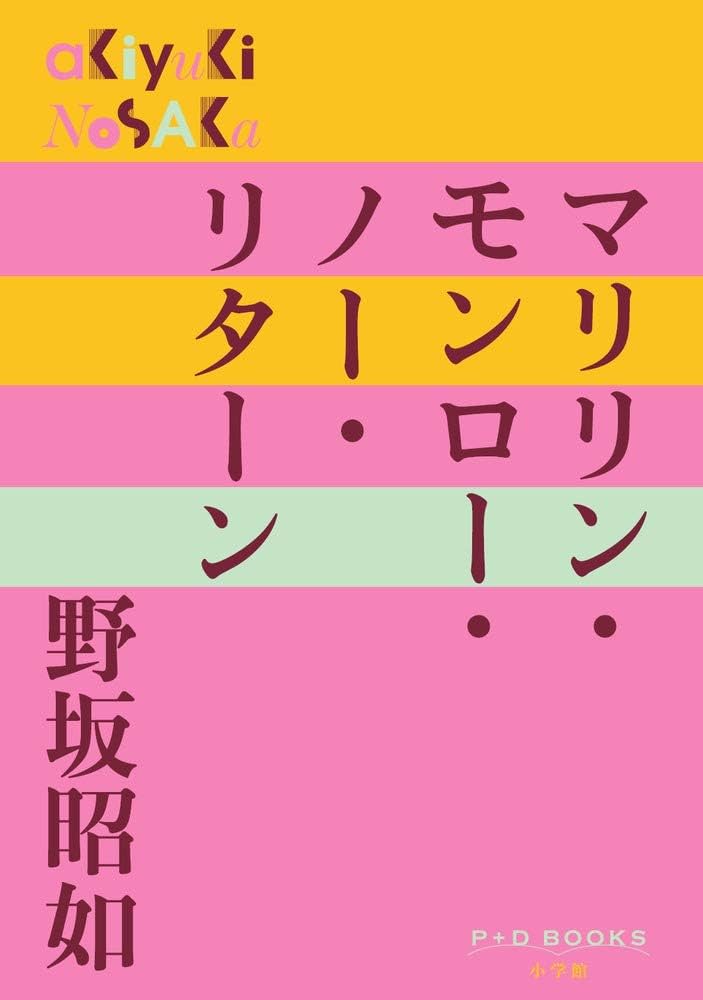
表題作を含む、洒脱で軽妙なタッチが魅力の短編集です。野坂昭如自身が歌う同名のシャンソンの歌詞も有名で、彼の多才ぶりがうかがえます。
物語は、華やかさとその裏にある哀愁を描き出しており、都会的なセンスと独特のユーモアが光ります。戦争文学や人間の業を描いた重厚な作品とは一味違った、野坂昭如のスタイリッシュな一面に触れることができる作品です。



このタイトル、すごくおしゃれだよね!ちょっと切ないけど、軽やかなリズムで読めるのがいい感じ。
8位『好色の魂』
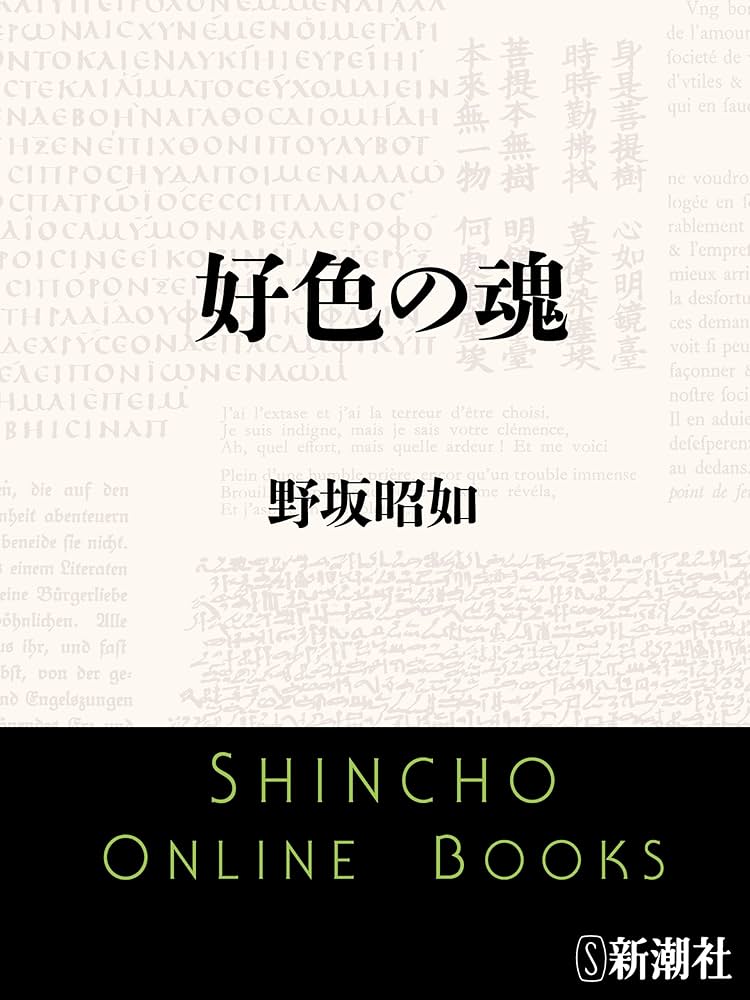
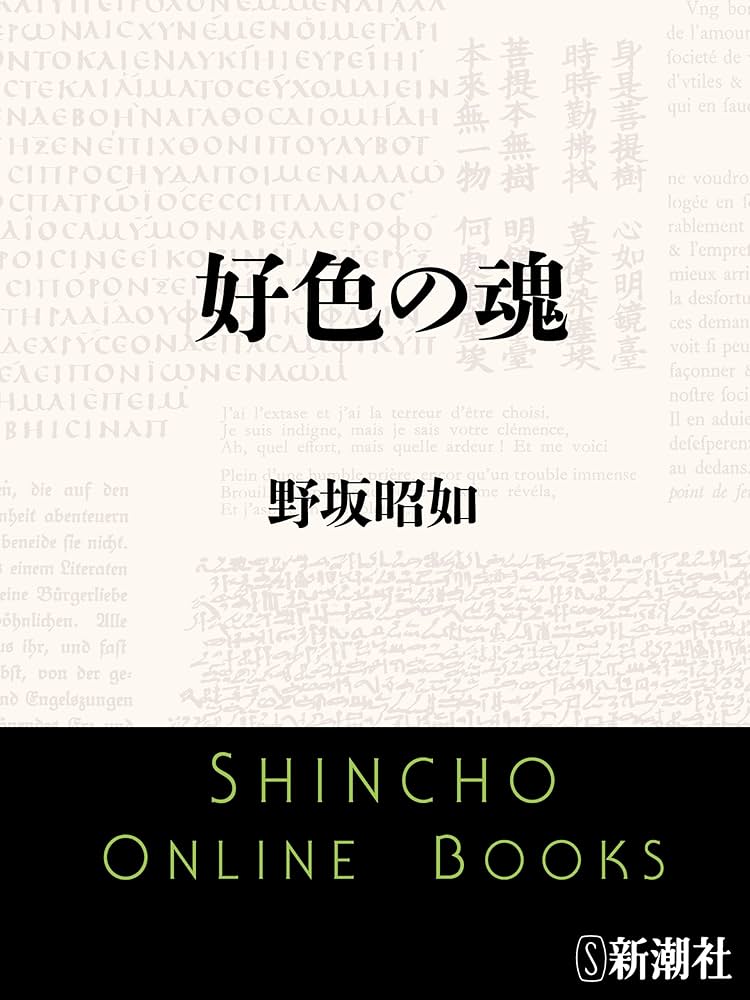
『エロ事師たち』と並び、人間の「性」をテーマにした野坂昭如の代表作の一つです。本作では、より深く、そして哲学的に人間の性欲や愛の形が探求されています。
様々な登場人物たちの性を通して、人間の業の深さや、生きることへの執着を描き出しています。猥雑でありながらも、どこか純粋さを感じさせる独特の世界観は、一度読むと忘れられない強烈なインパクトを残します。



うーん、人間の欲望って本当に底が知れないね…。ちょっとドキドキしたけど、目が離せなかったよ。
9位『一九四五・夏・神戸』
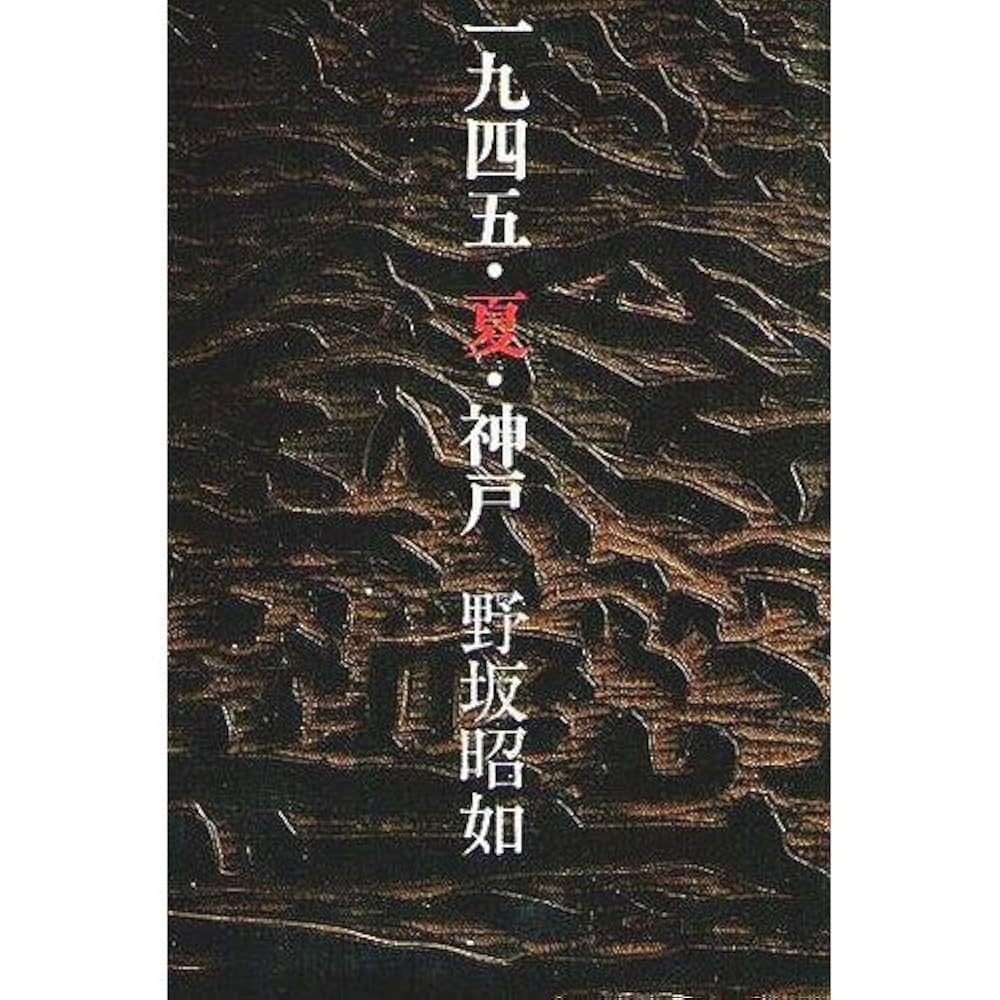
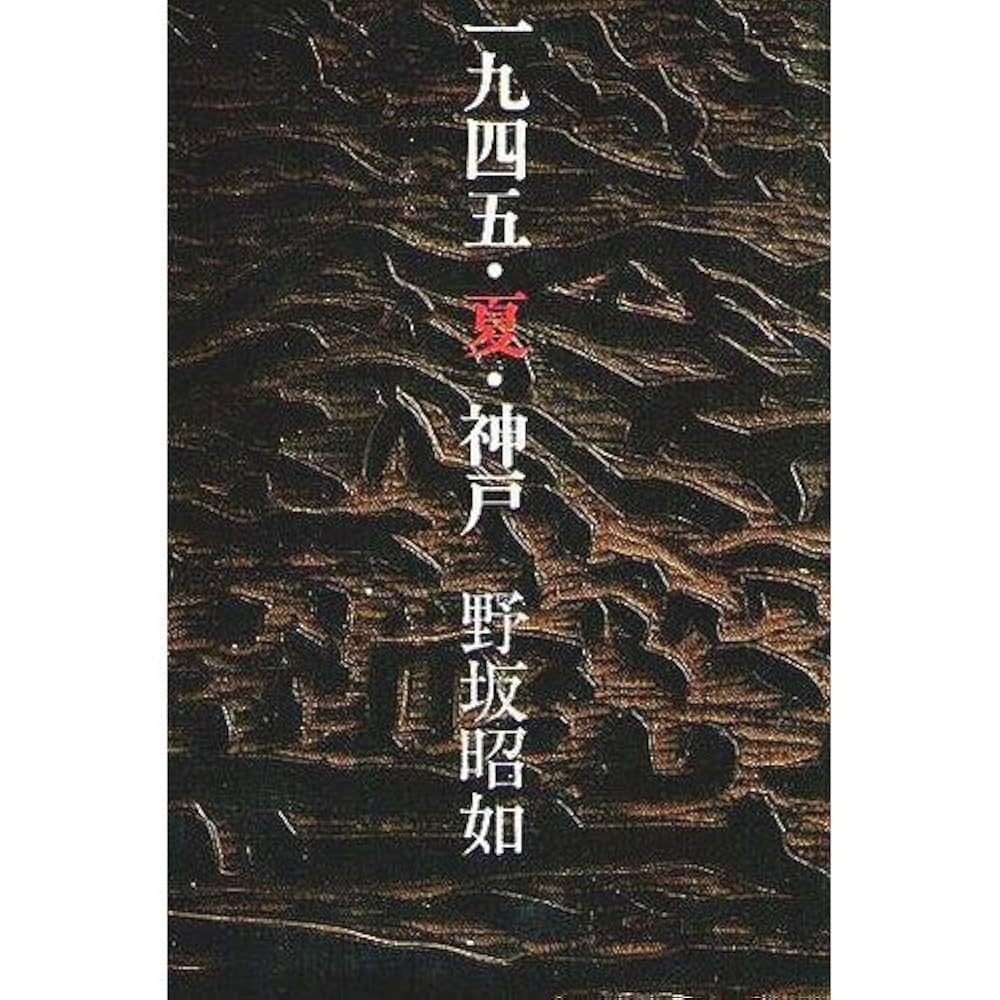
『火垂るの墓』と同様に、神戸大空襲を題材にした長編小説です。自身の体験をより克明に、そして多角的な視点から描いており、戦争がもたらす悲劇の全体像を浮き彫りにしています。
空襲によって日常が破壊されていく様子や、極限状況に置かれた人々の姿がリアルに描かれています。戦争の記憶を風化させないという、野坂昭如の強い意志が感じられる作品です。



『火垂るの墓』とは違う視点で戦争が描かれていて、すごく考えさせられたよ。戦争は二度と起こしちゃいけないって、改めて思うね。
10位『受胎旅行』
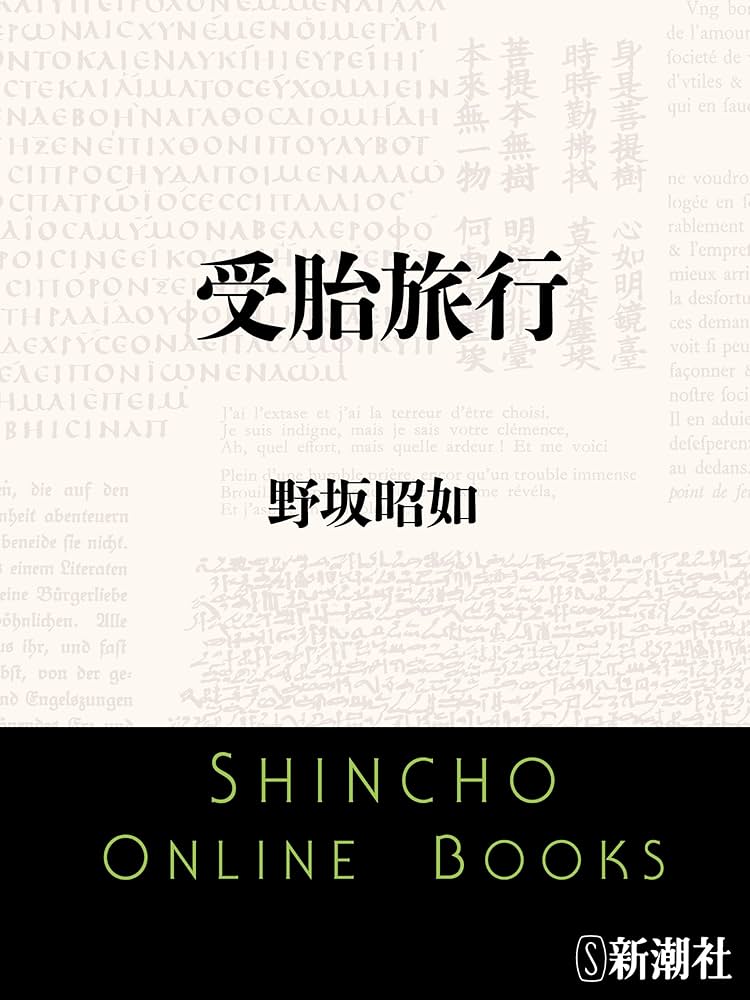
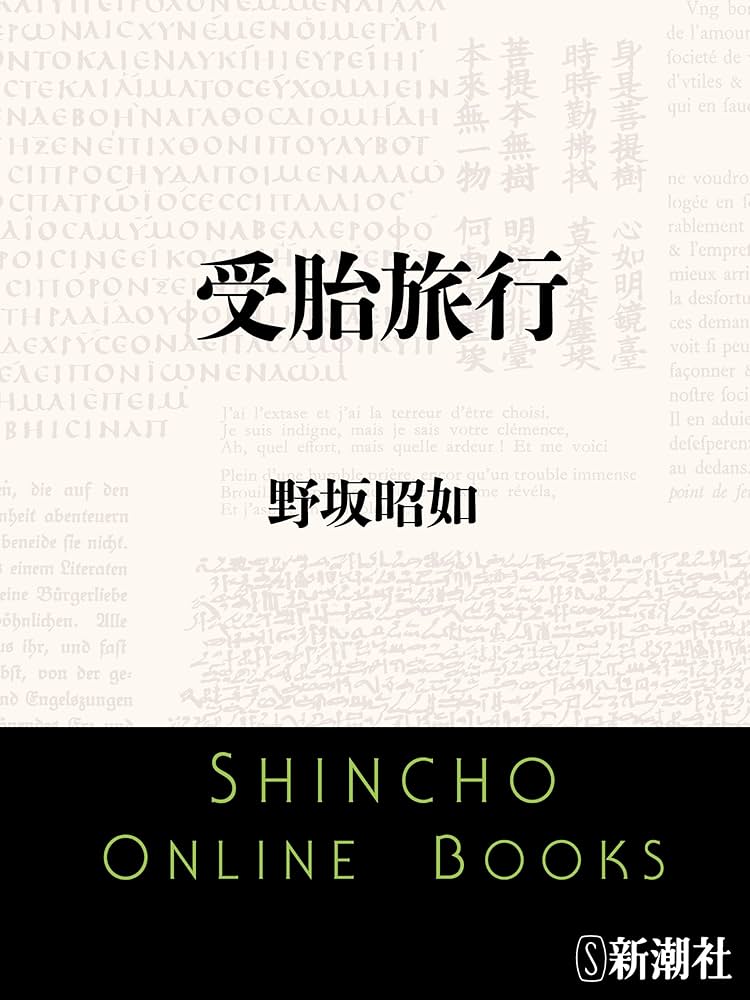
子供を授かるために、夫婦が温泉地を旅する様子をコミカルに描いた作品です。深刻になりがちなテーマを、野坂昭如ならではのユーモアと軽妙な筆致で明るく描き出しています。
夫婦の珍道中を通して、生命の神秘や家族の絆といったテーマが温かく語られます。重厚な作品の多い野坂文学の中では異色ともいえる、心温まる読後感が魅力の一冊です。



この夫婦、なんだか可愛くて応援したくなっちゃうな。クスッと笑えるのに、最後はジーンとくる素敵な物語だよ。
11位『東京小説』
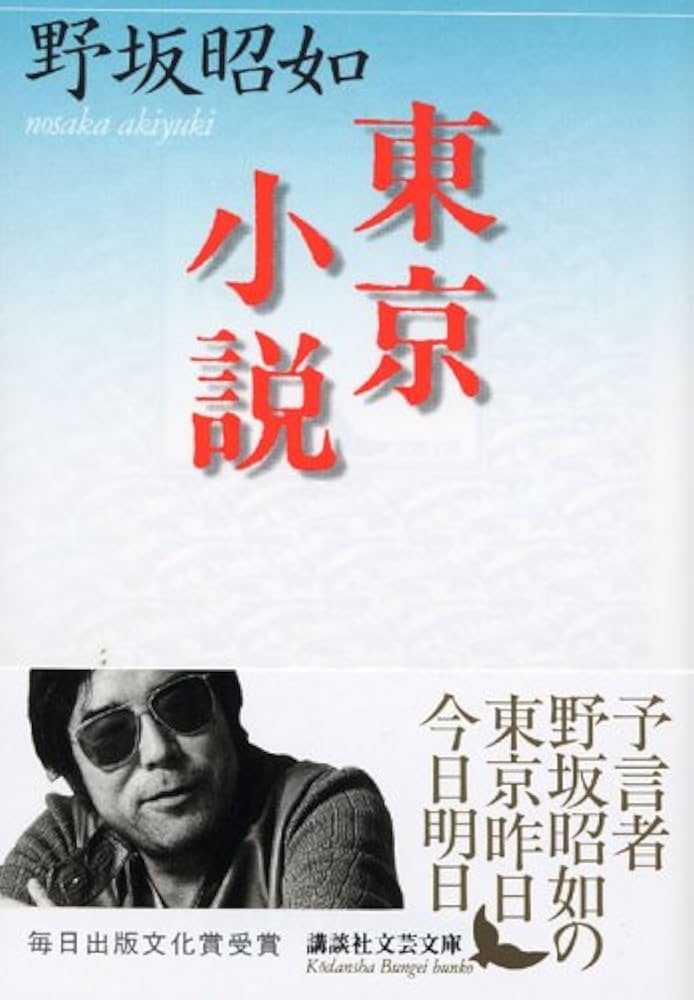
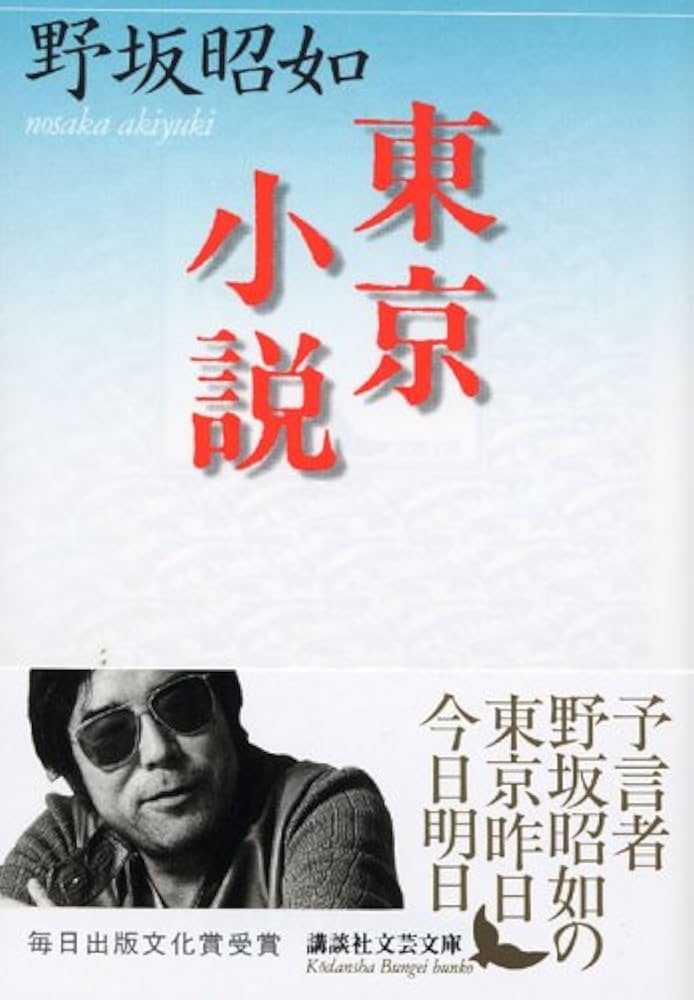
東京の様々な街を舞台に、そこに生きる人々の人間模様を鮮やかに切り取った連作短編集です。高度経済成長期の東京の風景や、時代の空気感が巧みに描かれています。
都会の片隅で生きる人々の喜びや悲しみ、孤独が、野坂昭如の鋭い観察眼を通して描き出されています。それぞれの短編が独立しながらも、全体として「東京」という都市の多面的な顔を映し出している作品です。



わたし、東京のいろんな街を散歩している気分になったよ。昔の東京ってこんな感じだったのかなって想像が膨らむね。
12位『赫奕たる逆光』
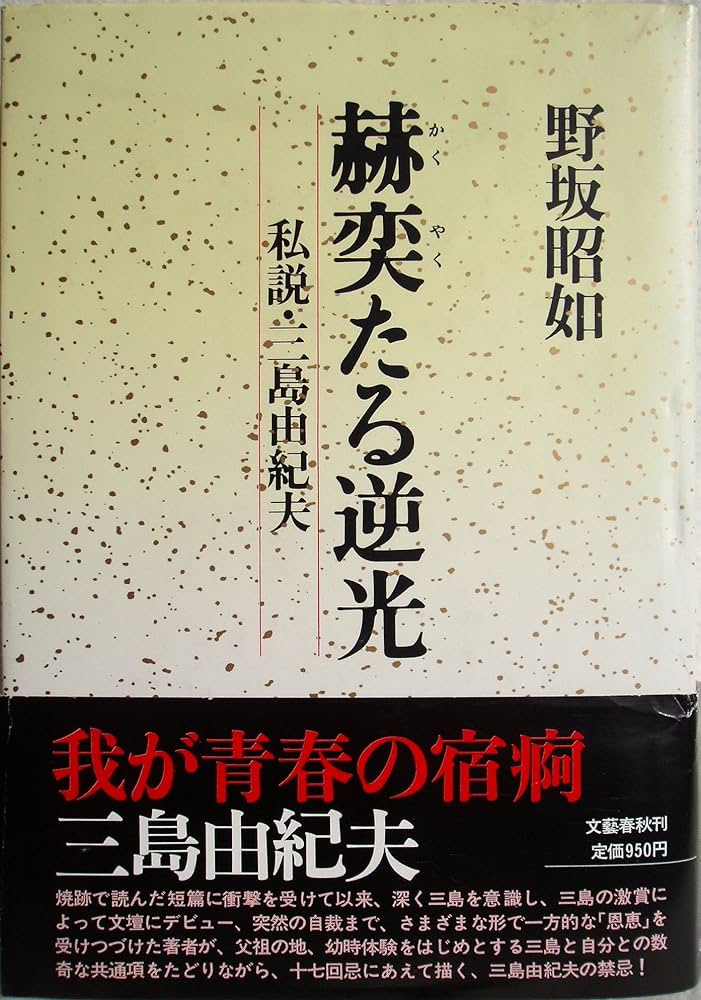
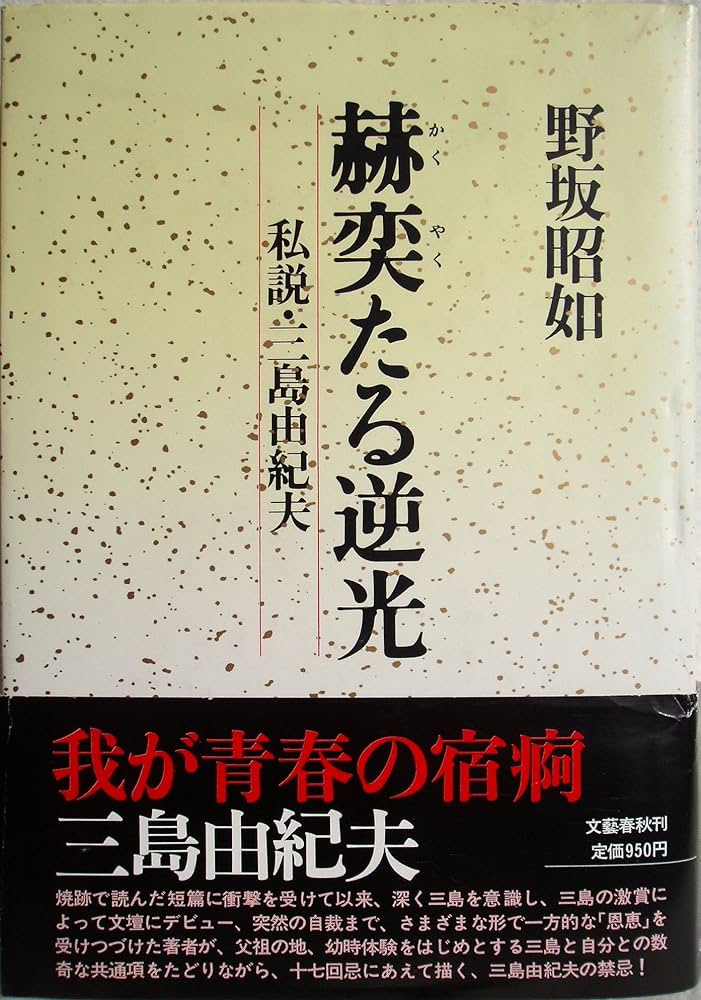
老いや死といった重いテーマを扱いながらも、それを湿っぽくならずに、むしろ力強く描き出した長編小説です。主人公の老作家が、自らの死と向き合いながら、過去を回想し、生の意味を見つめ直します。
衰えゆく肉体とは裏腹に、精神はますます赫奕(かくやく)と輝きを増していく様が描かれています。人生の終盤をどう生きるかという普遍的な問いを、野坂昭如ならではの視点で問いかける、深みのある作品です。



老いることは、ただ悲しいだけじゃないんだね。最後まで自分らしく生きるって、すごくカッコいいことなんだって思ったよ。
まとめ:今こそ読みたい野坂昭如の小説
野坂昭如の小説は、戦争の記憶、人間の性や業といった、私たちが普段目を背けがちなテーマに鋭く切り込んでいます。しかし、その根底には常に人間への深い洞察と、生きることへの強い肯定があります。
彼の作品に触れることは、戦後という時代を知り、そして現代を生きる私たち自身の姿を映し出す鏡を覗き込むような体験となるでしょう。今回ご紹介した作品をきっかけに、ぜひ野坂昭如の奥深い文学の世界に足を踏み入れてみてください。


