あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】安藤鶴夫のおすすめ作品ランキングTOP10

安藤鶴夫とは?寄席と東京を愛した随筆の名手
安藤鶴夫(あんどう つるお)は、小説家であり、落語や文楽、歌舞伎といった演芸の評論家としても活躍しました。1908年に東京浅草で、義太夫の8代目竹本都太夫の長男として誕生。そのため、幼い頃から芸事に親しんで育ちました。
法政大学を卒業後、都新聞(現在の東京新聞)に入社し、文楽や落語の批評を担当。江戸っ子らしい歯切れの良い文章で注目を集め、「アンツル」の愛称で多くの人々に親しまれました。1963年には、老講談師を描いた『巷談 本牧亭』で第50回直木賞を受賞し、小説家としての地位も確立します。彼の作品は、失われゆく東京の風景や寄席の活気、芸人たちの息づかいを鮮やかに描き出し、今なお多くの読者を魅了しています。
【2025年最新】安藤鶴夫のおすすめ作品ランキングTOP10
ここからは、数ある安藤鶴夫の作品の中から、特におすすめしたい名作をランキング形式でご紹介します!「アンツル」の愛称で親しまれた彼の作品は、落語や文楽といった伝統芸能の奥深さや、古き良き東京の情緒を生き生きと伝えてくれます。
今回のランキングでは、直木賞を受賞した代表作から、寄席の魅力が詰まった随筆、名人たちの芸を切り取った評論まで、幅広く選びました。どの作品も、安藤鶴夫ならではの粋で愛情あふれる視点が光る逸品ばかりです。ぜひ、このランキングを参考にして、あなたのお気に入りの一冊を見つけてみてください。
1位『巷談 本牧亭』
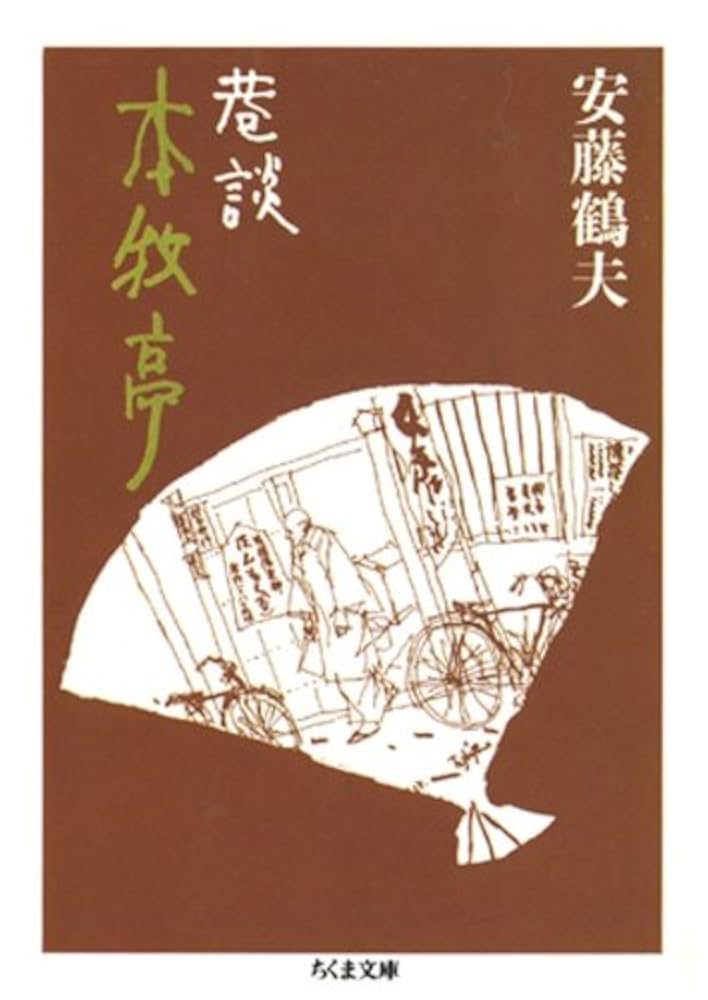
安藤鶴夫の代表作であり、1963年に第50回直木賞を受賞した不朽の名作です。この作品は、芸に生きる老講談師・桃川燕雄の姿を鮮やかに描き出しています。
物語の舞台は、かつて上野にあった講釈場「本牧亭」。時代の変化とともに失われゆく講談の世界で、芸一筋に生きる主人公の誇りと哀愁が、安藤鶴夫の巧みな筆致で綴られます。寄席の熱気や芸人の息づかいまでが伝わってくるような臨場感あふれる描写は、圧巻です。芸能の世界に詳しくない人でも、一つの道を究めようとする人間の生き様に深く引き込まれるでしょう。
 ふくちい
ふくちい芸に生きた男の生き様がかっこよすぎるよ。時代の流れが少し切ないけど、そこがいいんだ。
2位『わたしの寄席』
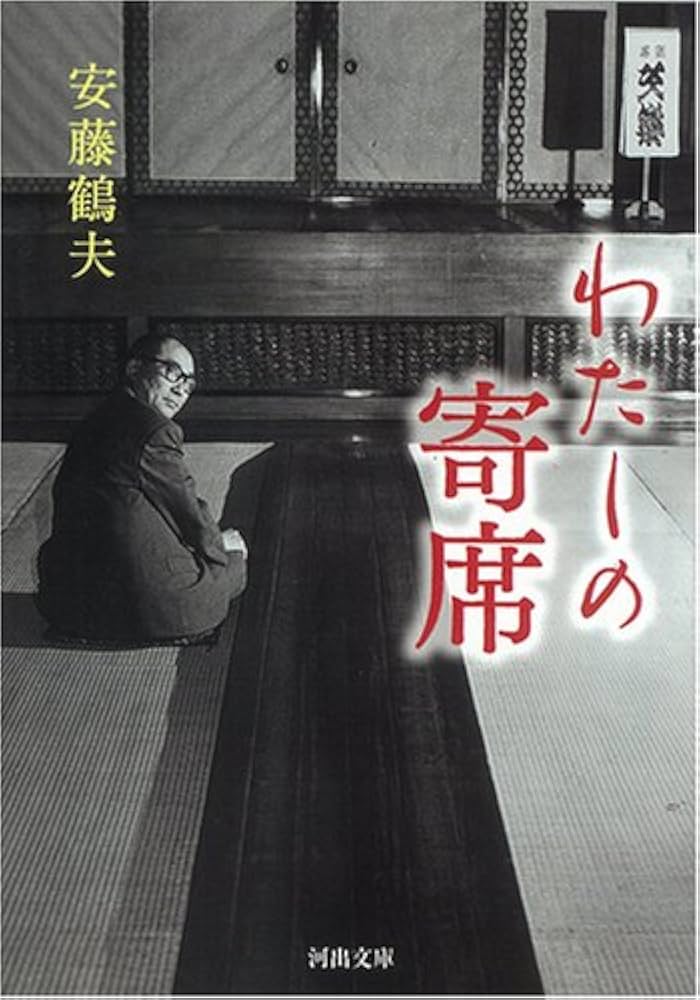
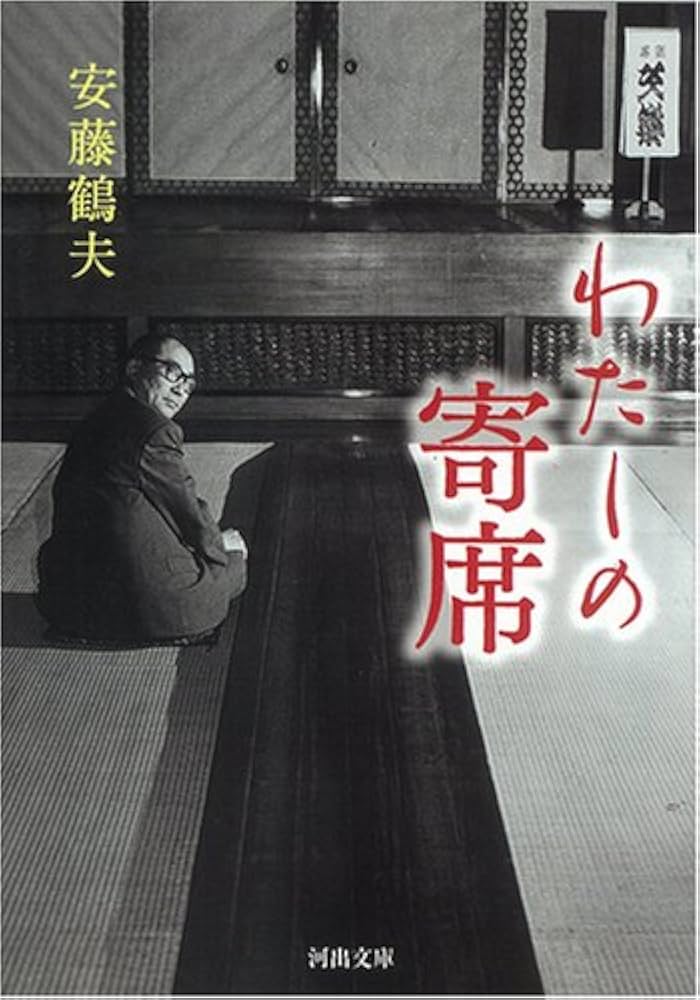
『わたしの寄席』は、安藤鶴夫の寄席への深い愛情が凝縮された随筆集です。落語、漫才、奇術、曲芸など、寄席で繰り広げられる様々な演芸と、そこに集う人々を温かい眼差しで描いています。
本書を読めば、まるで昭和の寄席にタイムスリップしたかのような気分を味わえます。名人たちの伝説的な高座の様子から、客席の雰囲気、楽屋裏の逸話まで、寄席の魅力が余すところなく語られています。安藤鶴夫の軽妙洒脱な文章に導かれ、寄席という空間が持つ独特の熱気と笑い、そして哀愁に触れることができる一冊です。



これを読むと、今すぐ寄席に行きたくなっちゃうな。昔の東京の空気感が伝わってきて、なんだか落ち着くんだ。
3位『わが落語鑑賞』
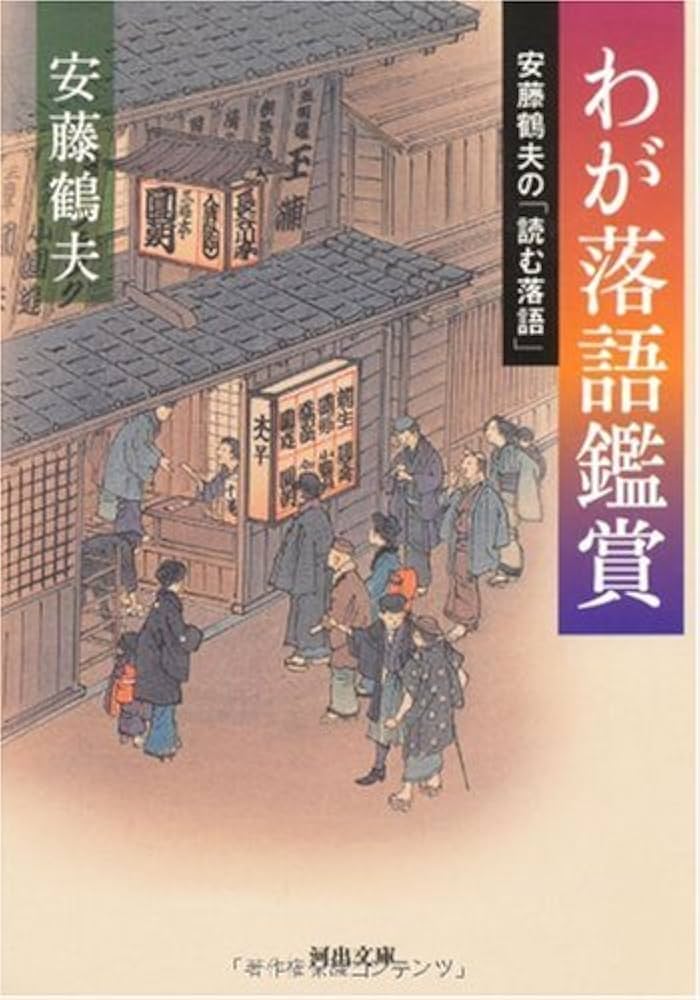
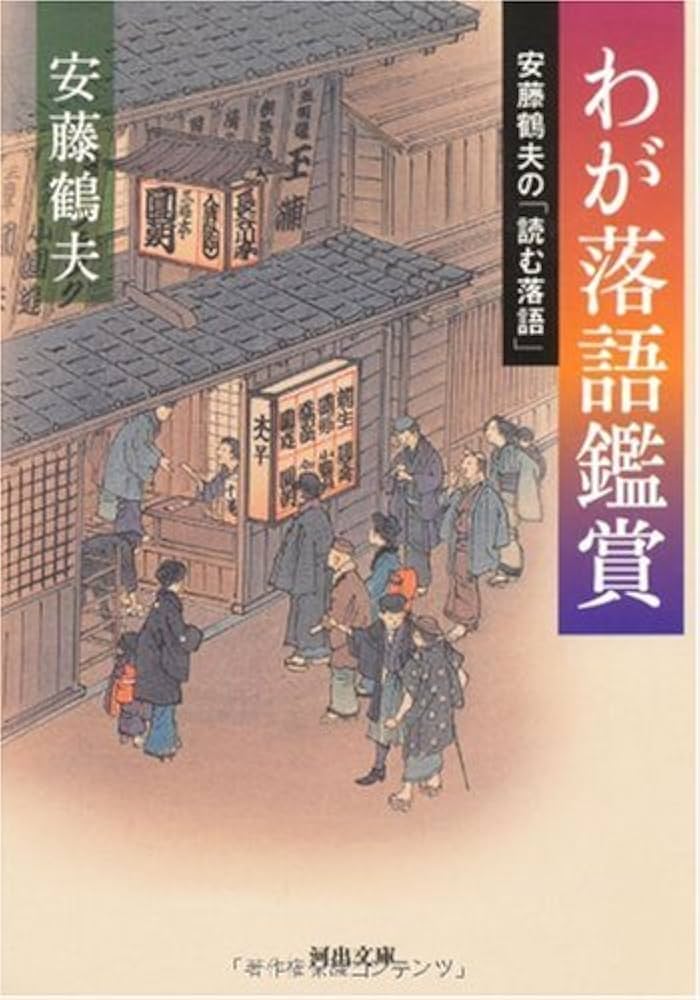
安藤鶴夫が演芸評論家としての評価を確立するきっかけとなった一冊です。特に、名人・八代目桂文楽の芸談を聞き書きした章は圧巻で、落語の芸を活字で見事に再現したと高く評価されました。
この本では、昭和を代表する名人たちの芸の本質が、安藤鶴夫ならではの鋭い視点で解き明かされています。単なる落語の解説書ではなく、芸人の生き様や哲学にまで踏み込んだ内容は、落語ファンでなくても引き込まれること間違いなしです。名人たちがどのような思いで高座に上がっていたのか、その息づかいまで感じられるような名著といえるでしょう。



名人たちの芸談が本当に面白いんだよね。落語の奥深さを知ることができる、すごく知的な一冊だよ。
4位『寄席はるあき』
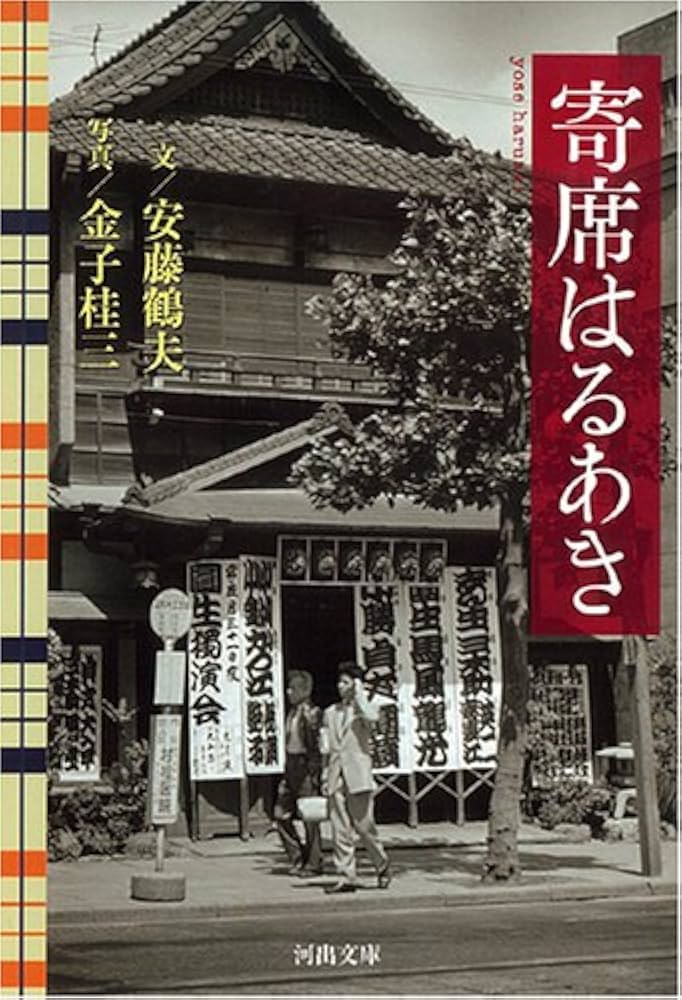
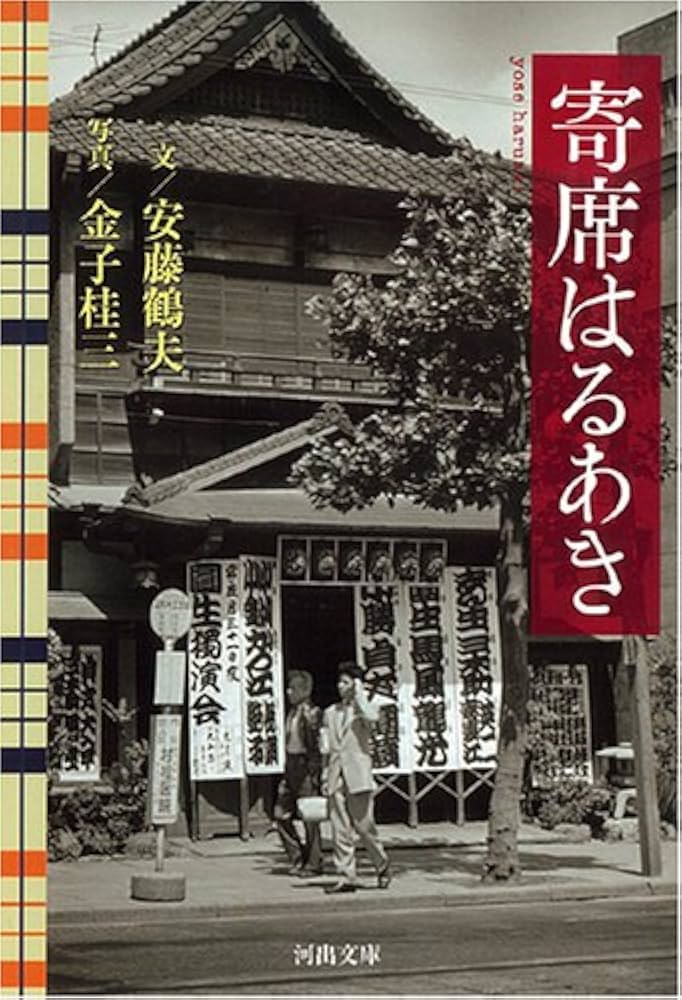
『寄席はるあき』は、春夏秋冬、季節の移ろいとともに寄席の風景を描き出した随筆集です。安藤鶴夫の繊細な観察眼と描写力が光る作品で、寄席の空気感をより深く味わいたい人におすすめです。
春の華やかな雰囲気から、夏の夕涼み、秋の物悲しさ、冬の暖かさまで、四季折々の寄席の情景が目に浮かぶように描かれています。登場する芸人たちの人間味あふれるエピソードも満載で、彼らの日常や素顔に触れることができます。ページをめくるたびに、古き良き日本の季節感と寄席の温かい雰囲気に包まれるような一冊です。



四季を通して寄席を描くなんて、すごく粋だよね。ページをめくるたびに心がほっこりするんだ。
5位『歳月』
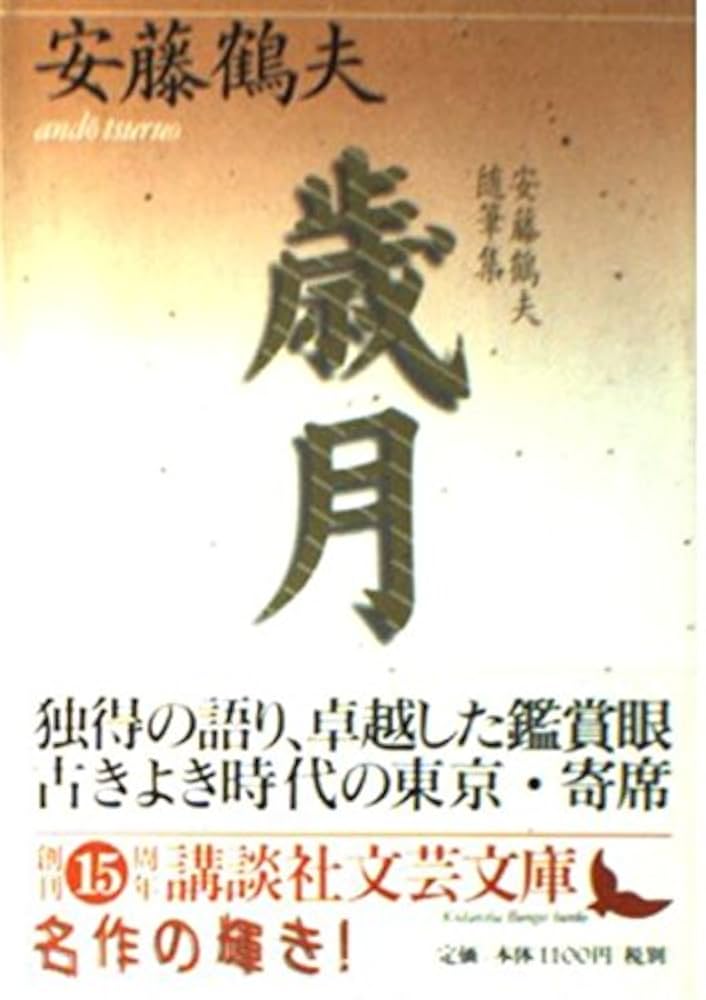
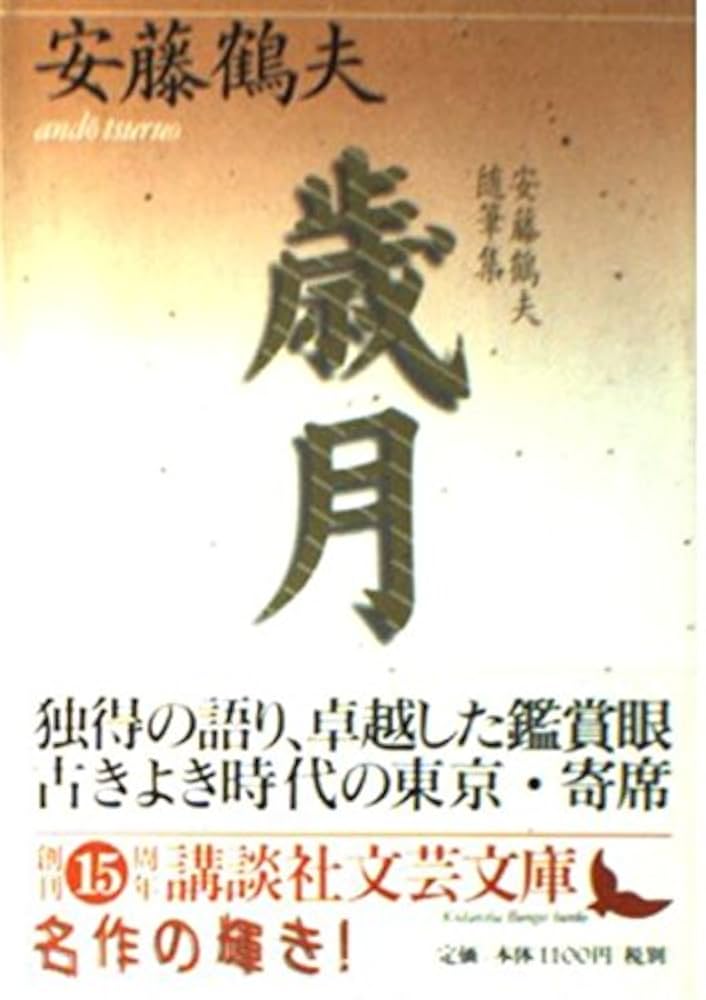
『歳月』は、安藤鶴夫自身の半生を振り返った自伝的な随筆集です。幼少期の思い出から、新聞記者時代のエピソード、そして多くの芸人たちとの交流が、飾らない言葉で率直に綴られています。
この作品を読むと、安藤鶴夫という人物の魅力や、彼がどのようにして芸事への深い見識を培ってきたのかがよく分かります。特に、彼が愛した東京の街や人々への温かい眼差しが印象的です。彼の人生を通して、昭和という時代の空気を感じることができる、味わい深い一冊です。



作者の人柄が伝わってくる作品だね。彼の人生を通して、昭和の空気を一緒に旅している気分になるよ。
6位『東京の面影』
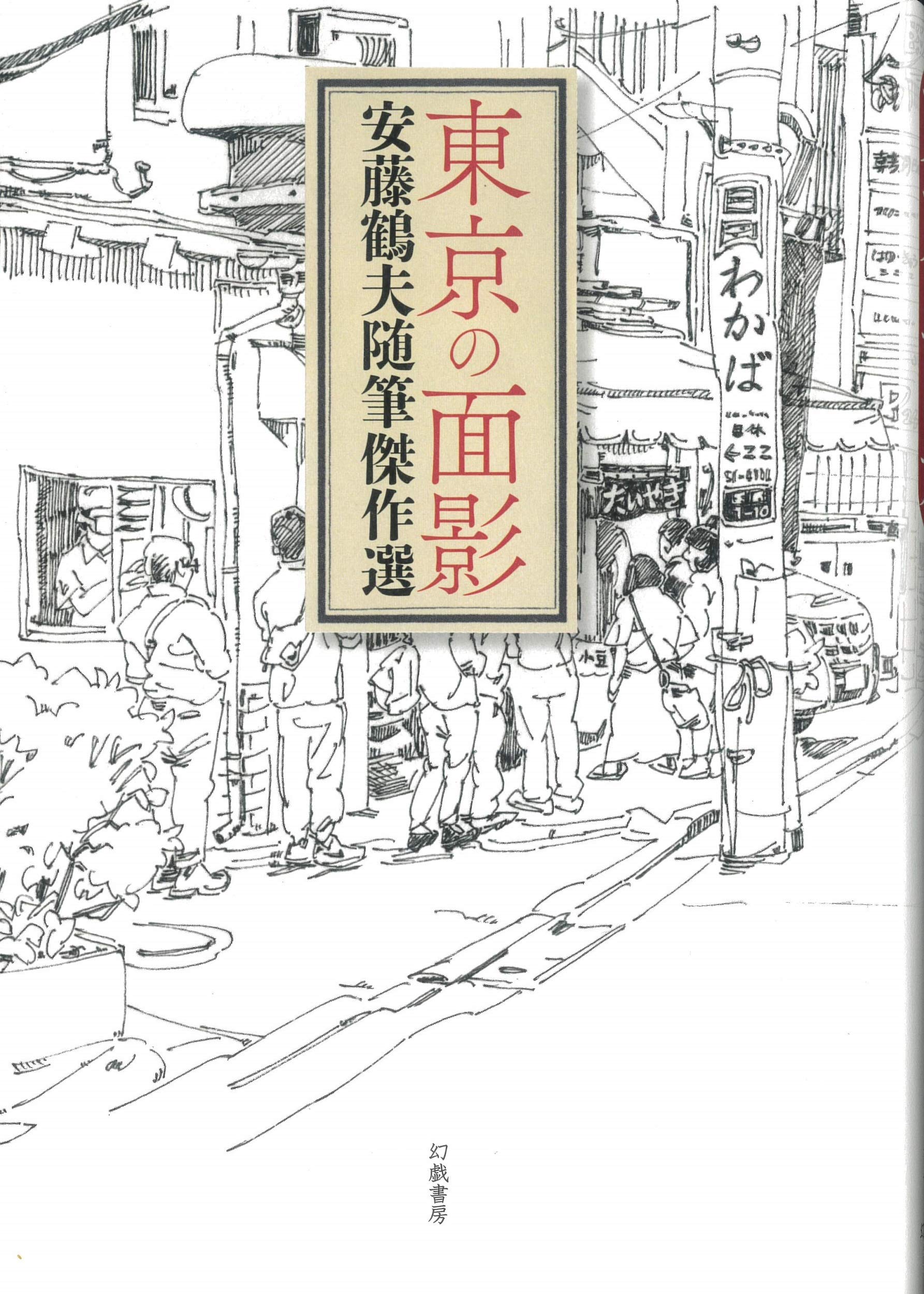
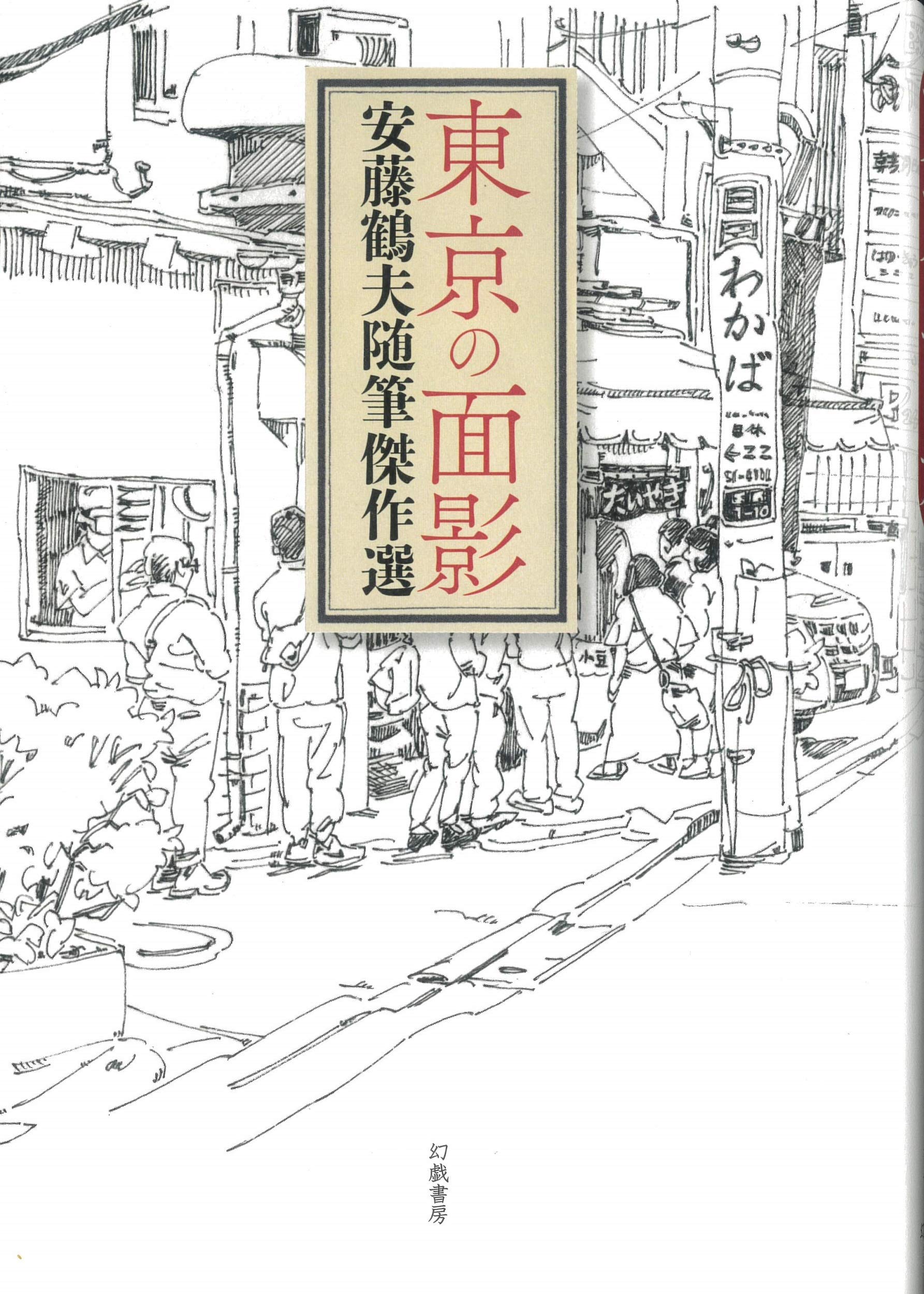
安藤鶴夫がこよなく愛した「東京」の、失われゆく風景や風俗を描き出した随筆集です。彼の生まれ故郷である浅草をはじめ、下町の情緒あふれる街並みが、懐かしくも美しい文章で綴られています。
この本を読んでいると、まるで昔の東京を散歩しているかのような気分になります。都電が走り、人々が活気に満ちていた時代の空気感が、鮮やかに蘇ってくるようです。近代化によって姿を変えてしまった東京の、かつての美しい面影に触れることができる貴重な一冊。東京が好き、あるいは昔の日本の風景に興味があるという方に、ぜひ読んでいただきたい作品です。



もう見られない東京の風景が描かれていて、なんだか切ないな。でも、その美しさに涙が出そうだよ。
7位『三木助歳時記』
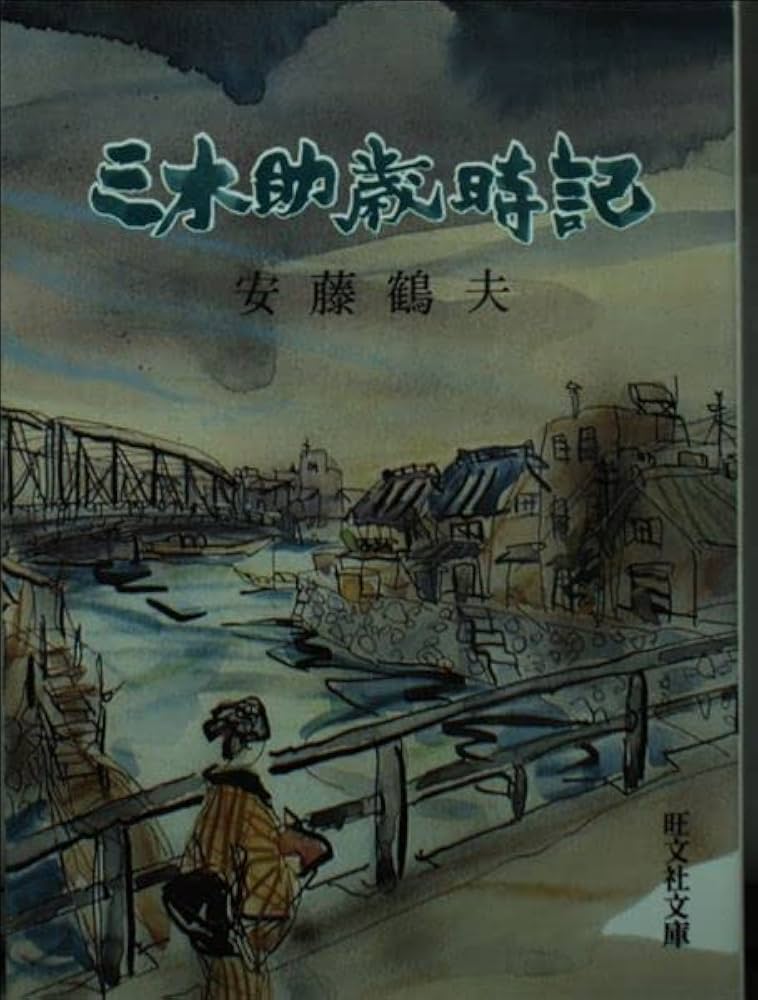
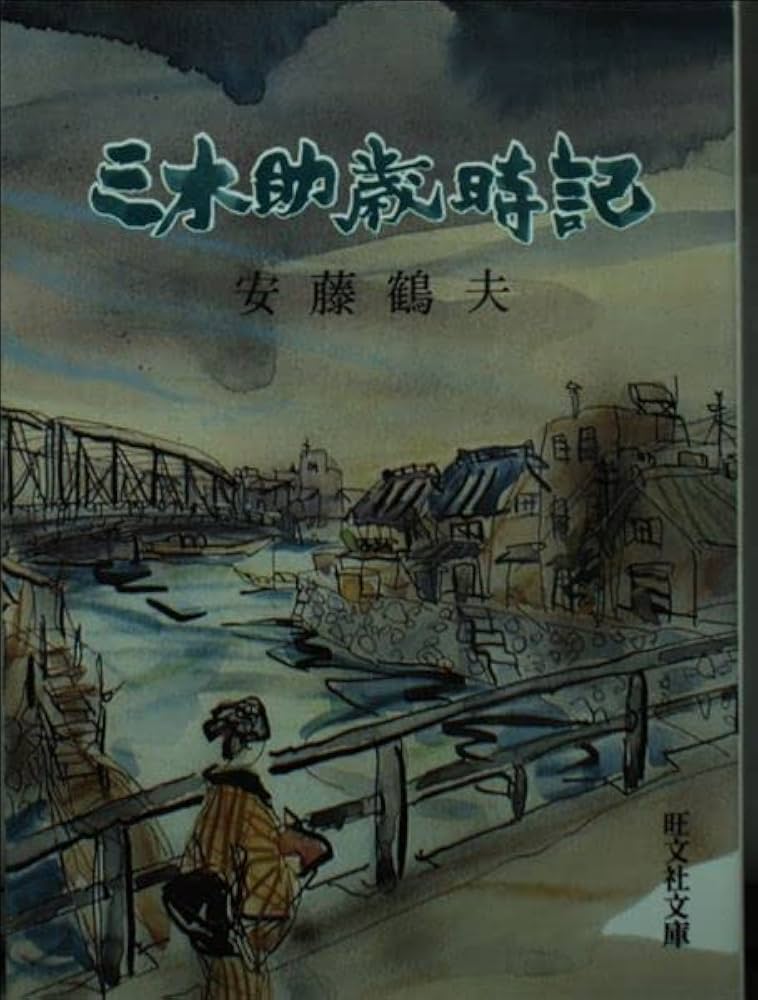
江戸っ子の粋な芸風で一世を風靡した落語家、三代目桂三木助の生涯を描いた作品です。安藤鶴夫は三木助の芸に惚れ込んでおり、その深い敬愛の念が文章の端々から伝わってきます。
名人として知られる三木助の芸の素晴らしさはもちろん、その裏にあった苦悩や人間的な魅力にも光を当てています。一人の芸人の生き様を通して、落語という芸の奥深さや厳しさを描き出した傑作です。残念ながら、この作品は新聞連載中に安藤鶴夫が亡くなったため未完に終わっていますが、それでも読む者の心を強く揺さぶるでしょう。



作者の熱量がすごくて圧倒されちゃうよ。未完なのが本当に惜しまれる作品なんだ…。
8位『文楽 芸と人』
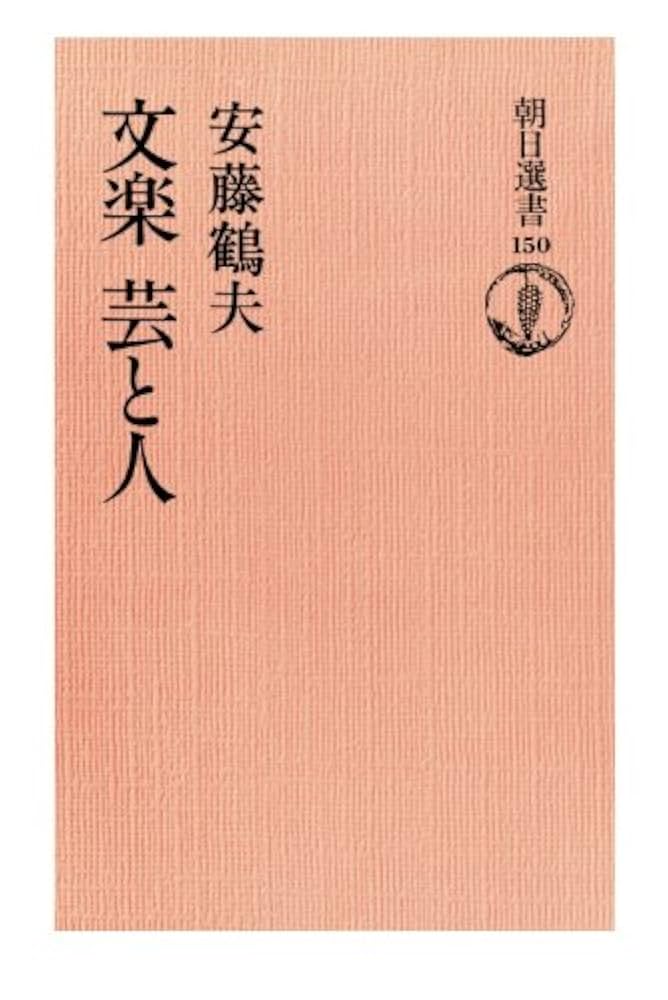
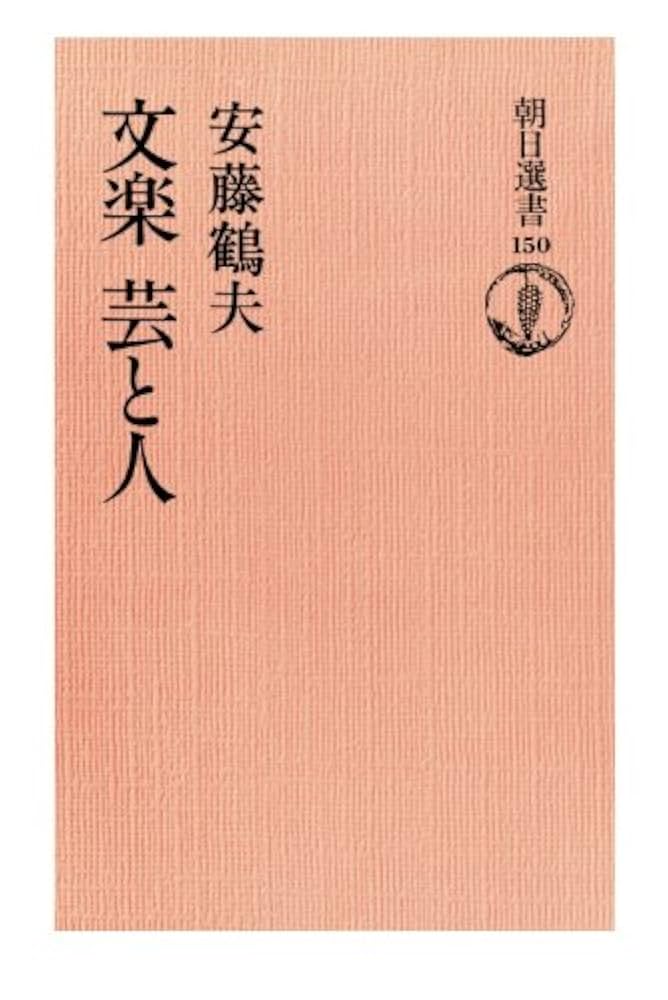
安藤鶴夫のもう一つの専門分野である「文楽」の魅力を深く掘り下げた評論・随筆集です。彼は新聞記者時代から文楽の批評を担当しており、その見識の深さは広く知られていました。
この本では、文楽の歴史や仕組みといった基本的な知識から、名人と呼ばれる人形遣いや太夫たちの芸談まで、文楽の世界が多角的に解説されています。専門的な内容でありながら、安藤鶴夫の分かりやすく情熱的な文章によって、初心者でもその奥深い魅力に触れることができます。文楽鑑賞のお供にも最適です。



文楽って少し難しそうだけど、これを読むと興味が湧いてくるんだ。芸人さんたちのプロ意識がすごいよ!
9位『落語国・紳士録』
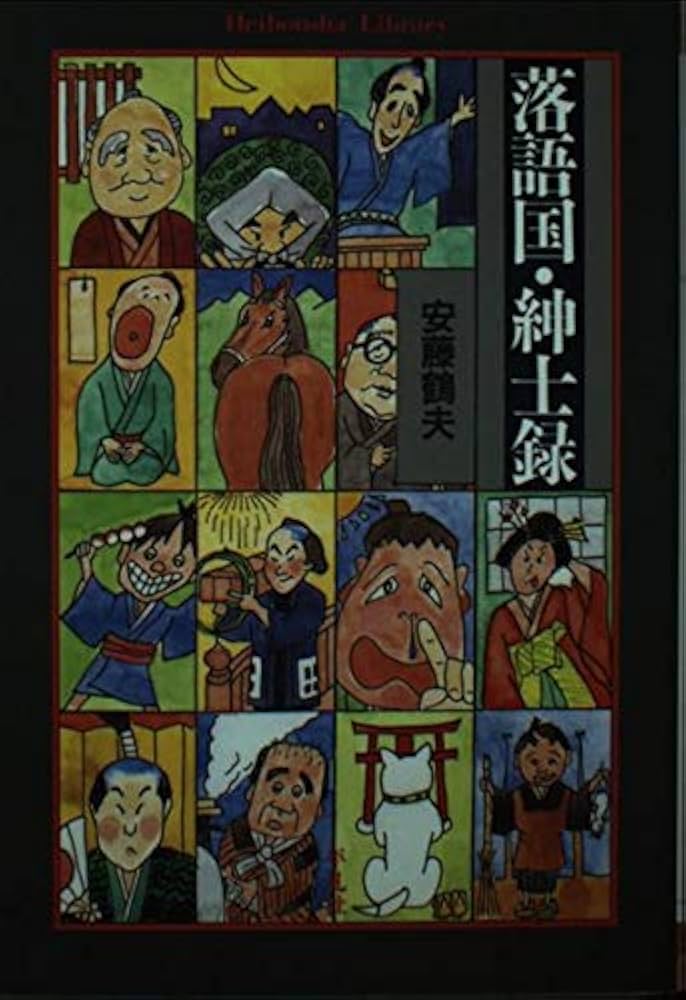
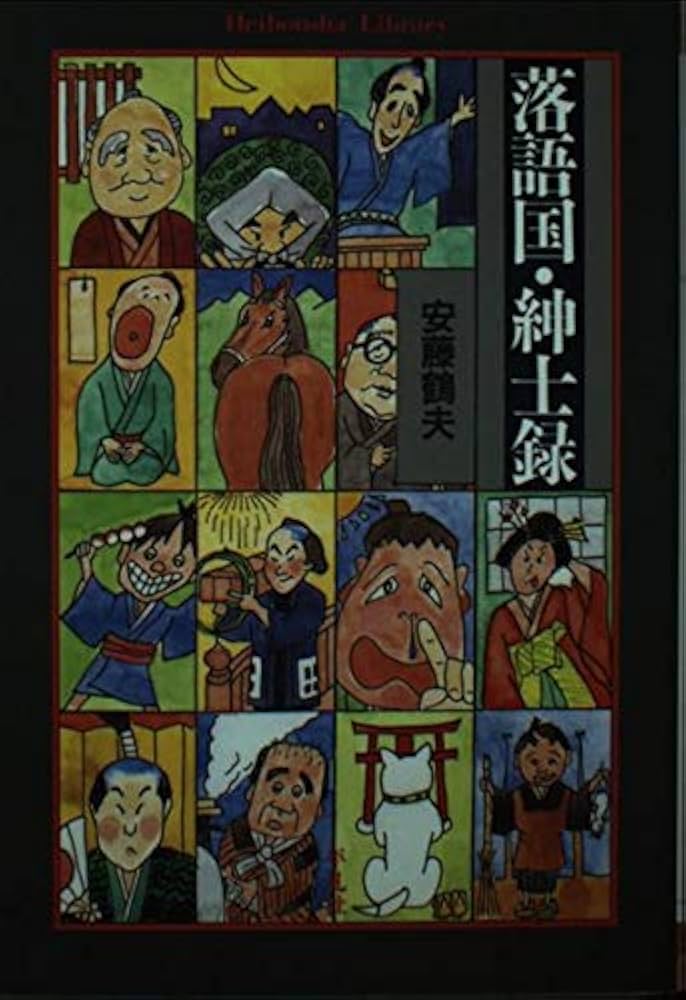
『落語国・紳士録』は、落語界を彩った様々な人物にスポットを当てたユニークな一冊です。名人上手だけでなく、少し変わった師匠や前座、さらには寄席に集う客まで、多種多様な「紳士」たちの姿を愛情たっぷりに描いています。
それぞれの短いエピソードから、落語界という特殊な世界の人間模様が垣間見え、非常に興味深く読めるでしょう。安藤鶴夫の人間観察の鋭さと、登場人物への温かい眼差しが感じられる作品です。落語の世界をより深く、人間味あふれる角度から楽しみたい方におすすめします。



いろんな師匠たちのエピソードが面白い!落語界って本当に個性的な人が多くて、人間観察が好きな人にはたまらないかも。
10位『寄席紳士録』
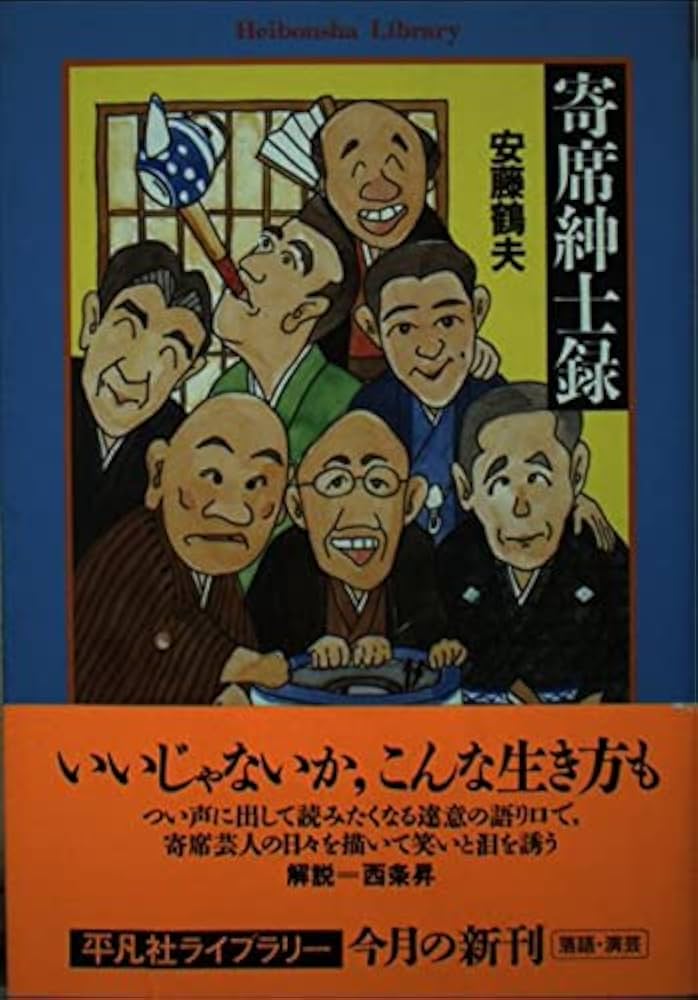
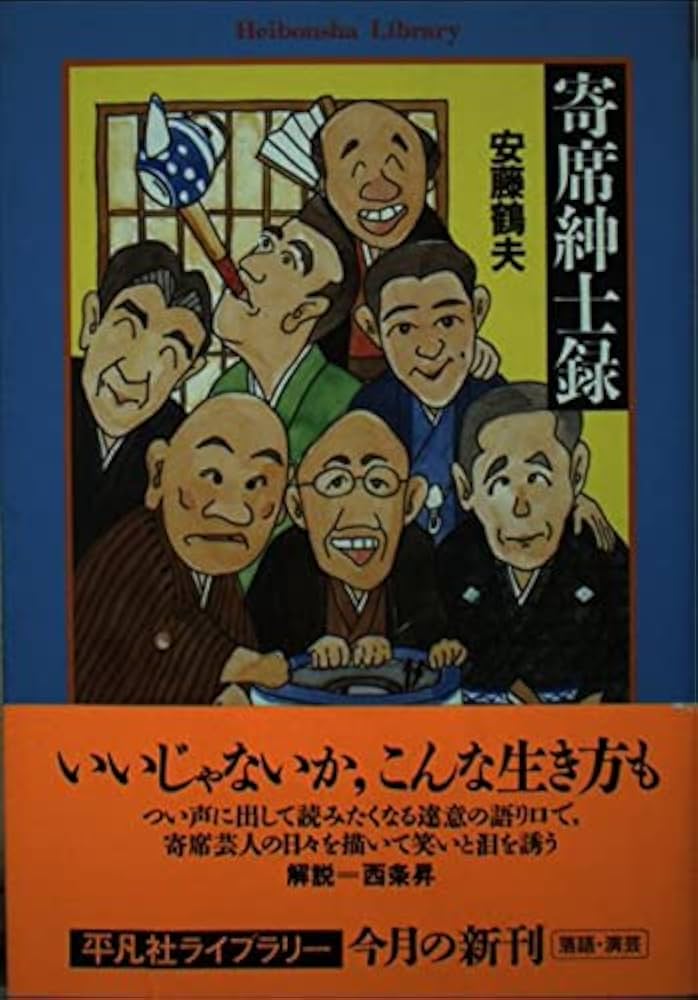
ランキング9位の『落語国・紳士録』と似たテーマを扱っていますが、こちらはより寄席という空間に集う人々に焦点を当てた作品です。芸人だけでなく、席亭や下足番、そして個性的な常連客など、寄席を支える様々な人々の生態をユーモラスに描いています。
安藤鶴夫の軽妙な筆致で語られるエピソードの数々は、どれもくすりと笑えるものばかり。この本を読めば、寄席が単に芸を見る場所ではなく、様々な人間が集うコミュニティであったことがよく分かります。寄席の持つアットホームで温かい雰囲気が伝わってくる名随筆といえるでしょう。



寄席にいるお客さんの話も面白いんだよね。みんな寄席が大好きなのが伝わってきて、温かい気持ちになるよ。
安藤鶴夫作品の選び方|初心者におすすめの一冊は?
安藤鶴夫の作品は、落語、講談、文楽、あるいは古き良き東京の街並みなど、様々なテーマを扱っています。そのため、まずはあなたが興味のある分野から手にとってみるのがおすすめです。
もし、どの作品から読めばいいか迷ってしまう初心者の方には、やはり直木賞を受賞した代表作『巷談 本牧亭』がおすすめです。芸に生きる男の物語として、落語や講談に詳しくなくても十分に楽しむことができます。また、寄席の雰囲気を気軽に味わってみたいという方には、随筆集の『わたしの寄席』も読みやすく、入門編として最適です。
まとめ:安藤鶴夫の作品で古き良き日本の芸能と情緒に触れよう
安藤鶴夫の作品は、落語や文楽といった日本の伝統芸能の魅力を、生き生きとした文章で現代に伝えてくれます。彼の文章を通して、私たちは名人たちの息づかいや寄席の熱気、そして失われた東京の美しい風景に触れることができます。
その世界は、どこか懐かしく、そして温かい人間味に満ちています。今回ご紹介したランキングを参考に、ぜひ安藤鶴夫の世界に足を踏み入れてみてください。きっと、あなたの心に深く残る一冊と出会えるはずです。

