あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】井上ひさしのおすすめ小説・人気ランキングTOP12
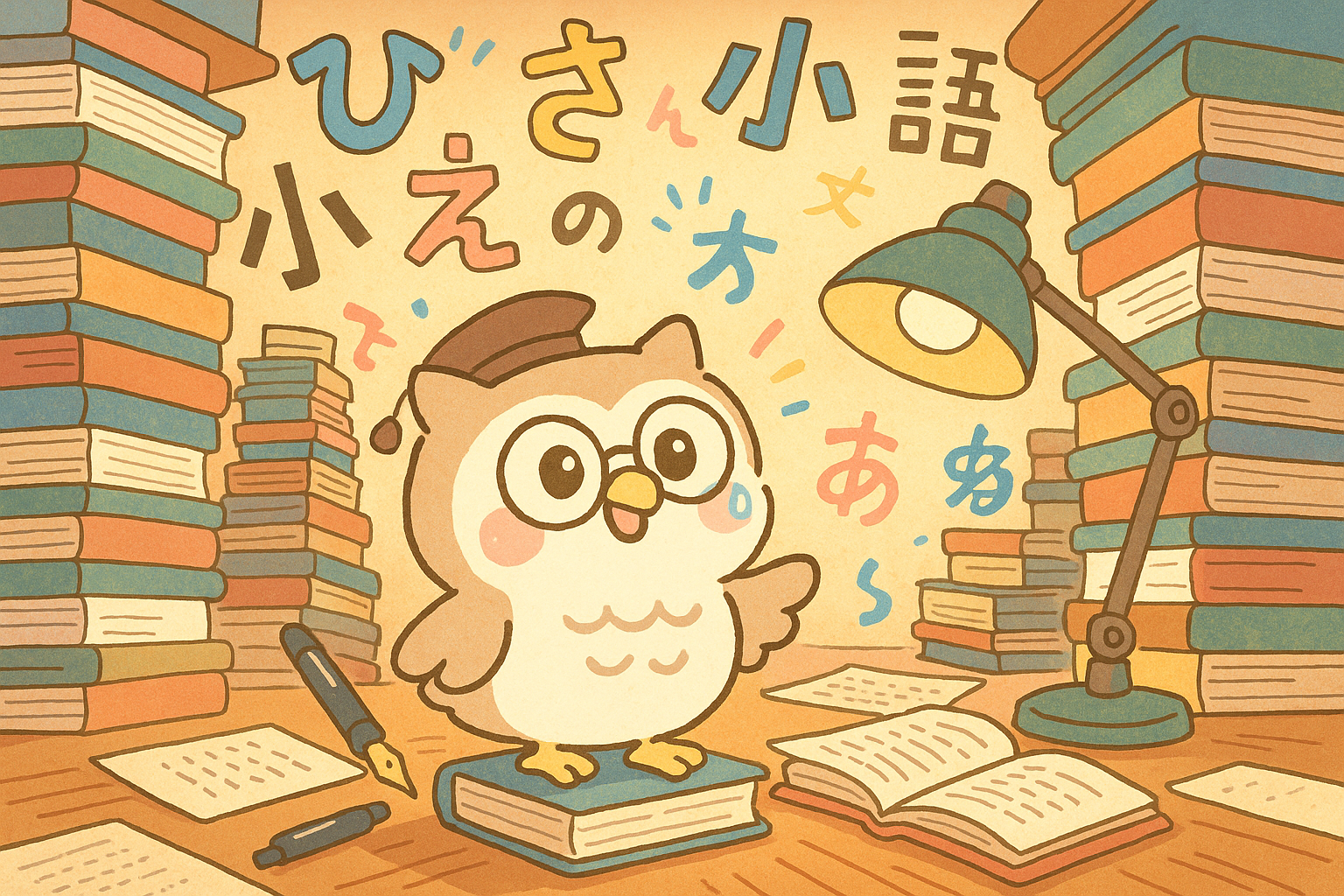
井上ひさしとは?今なお愛される国民作家の魅力に迫る
井上ひさし(本名:井上 廈)は、1934年山形県生まれの小説家、劇作家、放送作家です。 上智大学在学中から台本を書き始め、卒業後は放送作家としてNHKの人形劇『ひょっこりひょうたん島』の脚本を手がけ、一躍人気作家となりました。 その後、小説や戯曲の分野でも才能を発揮し、数多くの傑作を世に送り出しています。
井上ひさしの作品の最大の魅力は、巧みな言葉遊びやユーモア、そして社会への鋭い風刺が織り交ぜられている点です。 彼は自らの創作姿勢を「難しいことを易しく、易しいことを深く、深いことを愉快に、愉快なことを真面目に書くこと」と語っており、その言葉通り、エンターテインメント性の高い作品の中に、日本語の奥深さや社会の本質を突くテーマが込められています。 その功績から直木賞、谷崎潤一郎賞、菊池寛賞など数々の文学賞を受賞し、2004年には文化功労者にも選ばれています。 2010年に亡くなった後も、その作品は多くの読者に愛され、舞台で上演され続けている国民的作家です。
井上ひさしのおすすめ小説・人気ランキングTOP12
「言葉の魔術師」とも称される井上ひさしは、その生涯で非常に多岐にわたるジャンルの小説を書き上げました。壮大な歴史小説から奇想天外なSF、心温まる青春物語、そして言葉のトリックを駆使したミステリーまで、その作風は一言では語り尽くせません。
これからご紹介するランキングは、そんな井上ひさしの多彩な作品群の中から、特に人気が高く、初めて読む方にもおすすめの12作品を厳選したものです。どの作品にも、彼ならではのユーモアと、日本語の豊かさを再発見させてくれる魅力が詰まっています。ぜひ、このランキングを参考にして、あなたのお気に入りの一冊を見つけてみてください。
1位『吉里吉里人』
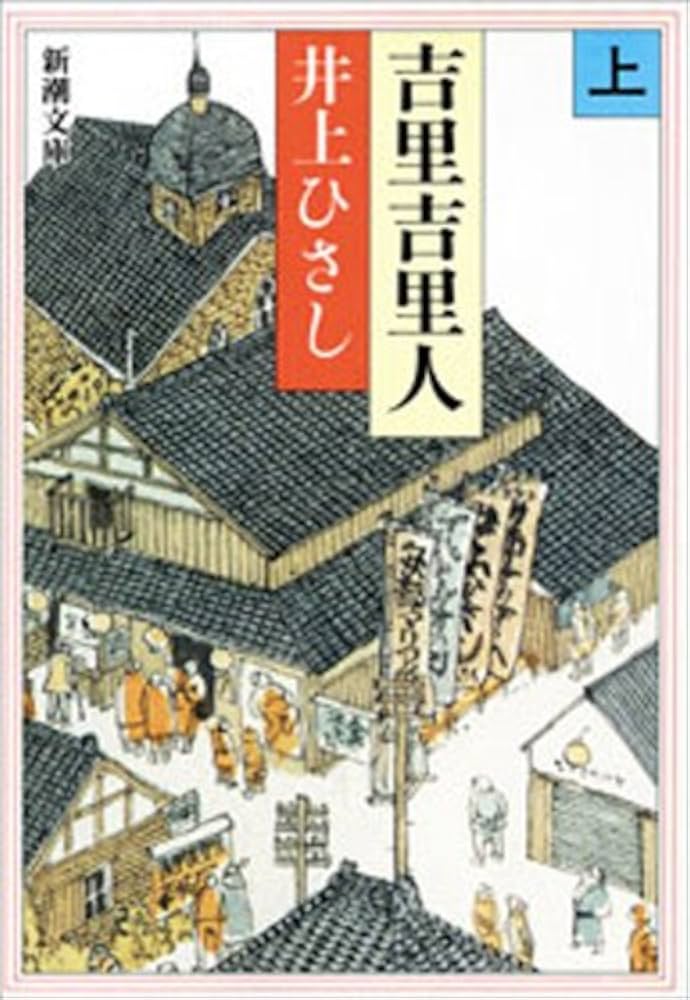
『吉里吉里人』は、1981年に刊行された井上ひさしの代表作の一つです。 物語は、東北地方の小さな村「吉里吉里国」が、ある日突然日本からの独立を宣言するという、奇想天外な設定から始まります。独自の言語や通貨まで持つ吉里吉里国と、日本政府との間で繰り広げられる攻防が、壮大なスケールとユーモアたっぷりに描かれています。
この作品は、単なるエンターテインメント小説にとどまりません。国家とは何か、言語とは何か、そして地方の自立とはどうあるべきかといった、普遍的で深いテーマを読者に問いかけます。その文学的価値は高く評価され、日本SF大賞や読売文学賞を受賞しました。 井上ひさしの魅力である言葉遊びと社会風刺が存分に味わえる、まさに最高傑作と呼ぶにふさわしい一作です。
 ふくちい
ふくちい言葉の洪水に圧倒されちゃうよ。国家とは何かを考えさせられる、唯一無二の作品だね。
2位『十二人の手紙』
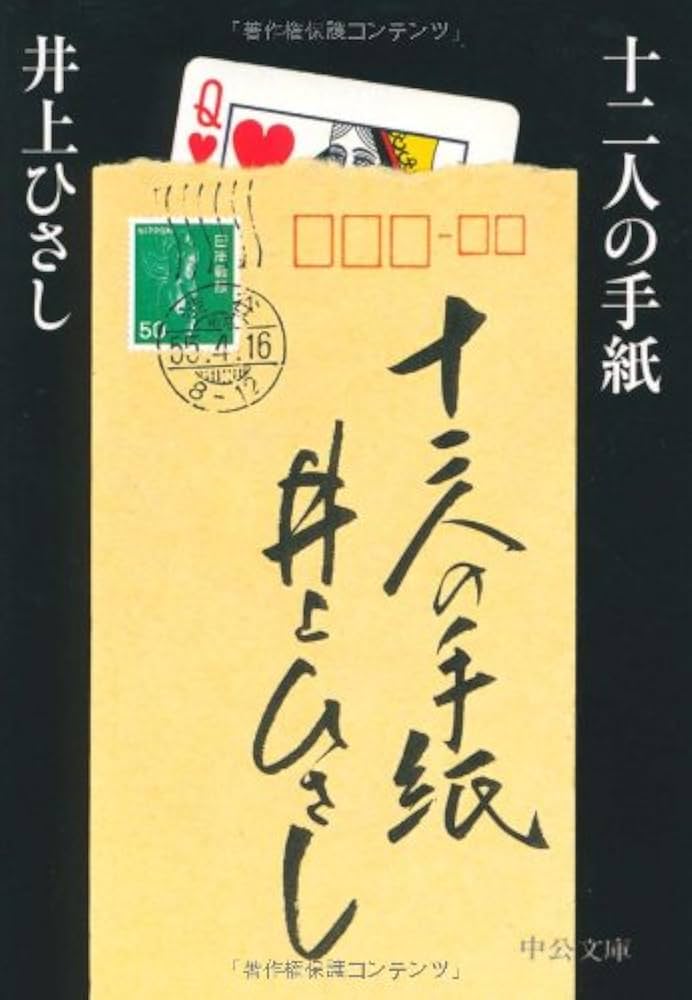
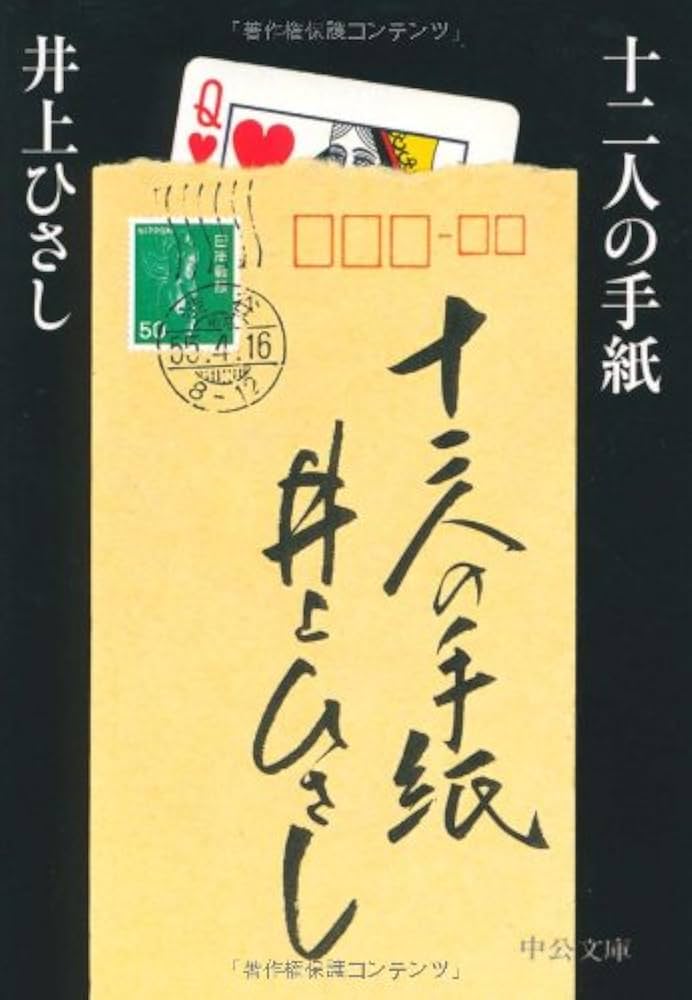
1978年に刊行された『十二人の手紙』は、12通の手紙だけで物語が構成されるという、非常にユニークな形式の書簡体小説です。 それぞれの手紙は異なる差出人と宛先を持ち、一見すると独立した短編のように読めますが、読み進めるうちに、それらの背後に隠された一つの事件や複雑な人間関係が徐々に浮かび上がってきます。
この作品の凄さは、登場人物の性格や感情、そして物語の謎が、手紙の文面という限られた情報から見事に描き出されている点にあります。読者は断片的な情報を頼りに全体像を推理していく、まるで探偵のような楽しみを味わうことができます。この巧みな構成と文学性が高く評価された傑作です。



手紙だけで物語が進むなんて驚きだよ。登場人物の息づかいが聞こえてくるみたいで、一気に読んじゃった!
3位『ブンとフン』


『ブンとフン』は、井上ひさしが小説家として初期に発表した、抱腹絶倒のファンタジーコメディです。 物語は、売れない小説家「フン」が書いた物語の主人公である大泥棒「ブン」が、ある日突然、現実世界に飛び出してくるところから始まります。 理屈っぽいフンと、豪快で行動的なブン。正反対の二人が繰り広げる奇妙な共同生活と大冒険が、テンポの良い会話と奇想天外な展開で描かれます。
井上ひさし特有の言葉遊びやナンセンスなギャグが全編にわたって散りばめられており、子どもから大人まで純粋に「笑い」を楽しめるエンターテインメント作品です。 しかし、その笑いの裏には、権威や常識に対する鋭い風刺も込められています。何度も舞台化されていることからも、その人気の高さがうかがえる一冊です。



とにかく笑いたいならこれだね!ブンとフンのやり取りが最高で、ページをめくる手が止まらないよ。
4位『東慶寺花だより』
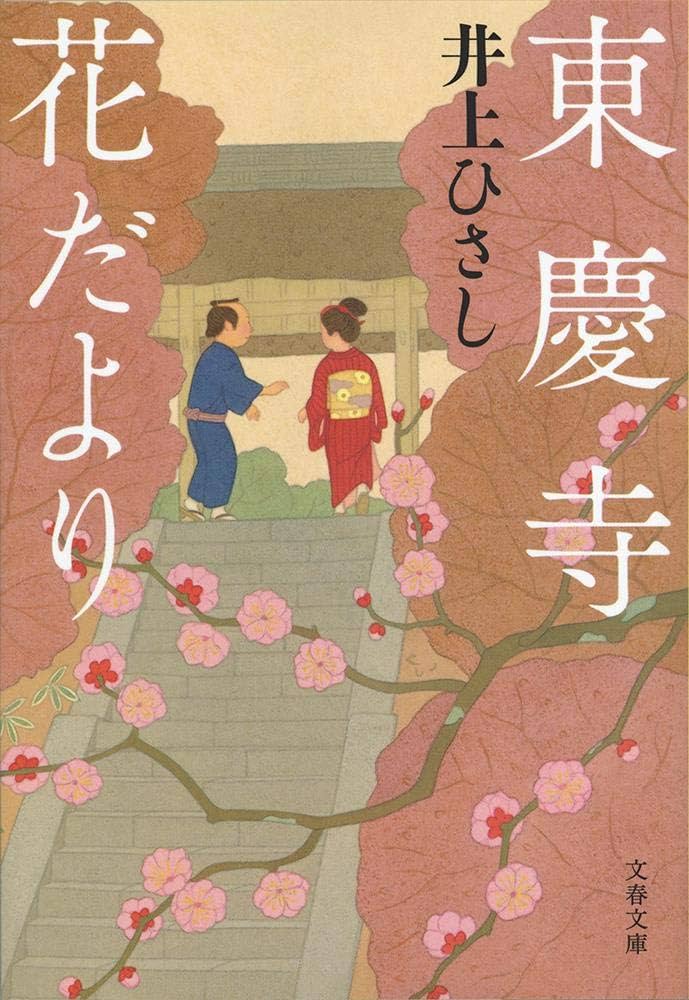
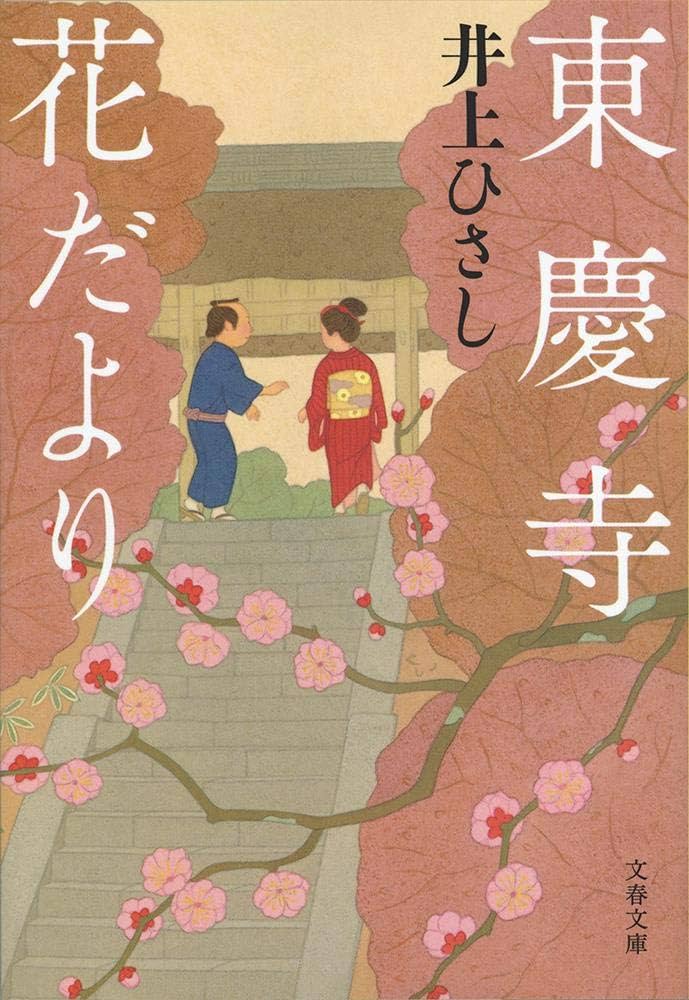
江戸時代の鎌倉に実在した「縁切寺」である東慶寺を舞台にした、連作短編集です。 当時、夫との離縁を望む女性たちが最後の駆け込み場所としたこの寺で、様々な事情を抱えた女性たちの人生模様が、ユーモアと温かい眼差しで描かれています。
物語の聞き手となるのは、戯作者を目指す医者の卵・信次郎。彼の目を通して語られる女性たちの物語は、どれも一筋縄ではいかないものばかり。封建的な社会の中で、したたかに、そして力強く生き抜こうとする女性たちの姿は、現代の私たちにも多くの共感と感動を与えてくれます。



江戸時代の女性たちのたくましさに感動するよ。切ないけど温かい物語が心に残るんだ。
5位『ナイン』
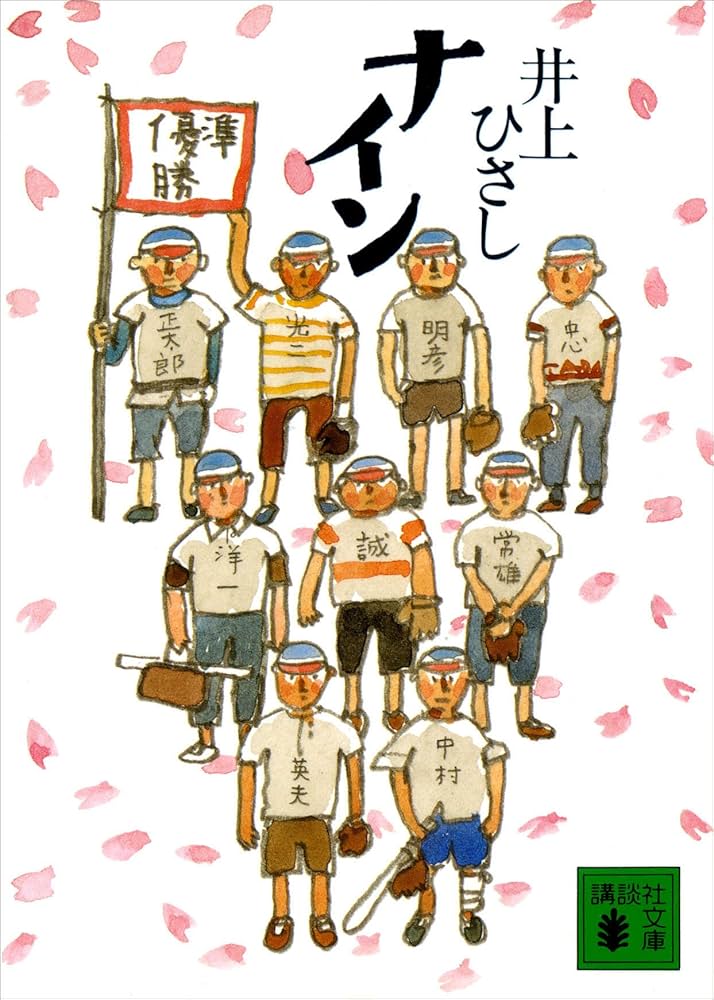
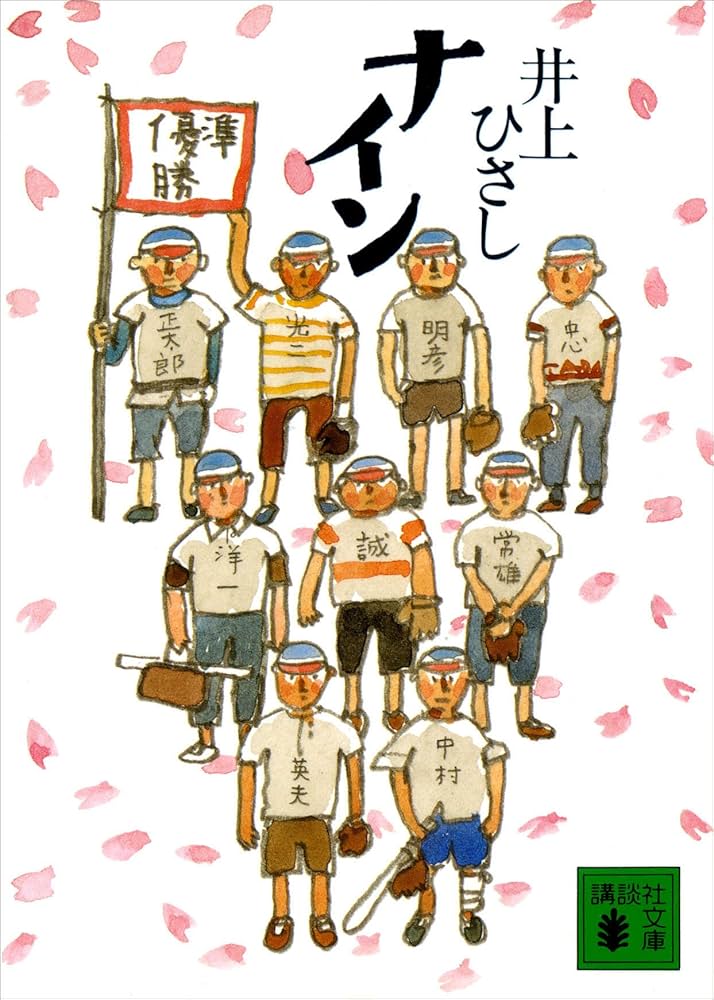
『ナイン』は、井上ひさしがこよなく愛した野球をテーマにした青春小説です。東北の弱小高校野球部が甲子園を目指すという王道のストーリーですが、その語り口がユニーク。9人の登場人物、それぞれの視点から物語が語られる連作短編形式で構成されています。
エースピッチャーの葛藤、補欠部員の想い、監督の苦悩、そして彼らを見守る人々。それぞれの立場からの物語がパズルのように組み合わさることで、一つのチームの姿が立体的に浮かび上がってきます。単なるスポーツの勝敗だけでなく、野球を通して描かれる少年たちの友情や成長、そしてほろ苦い青春のドラマが、読者の胸を熱くさせます。野球好きはもちろん、青春小説が好きなすべての人におすすめしたい爽やかな一冊です。



野球好きにはたまらない一冊だよ。青春の甘酸っぱさが詰まってて、自分の高校時代を思い出しちゃうな。
6位『東京セブンローズ』
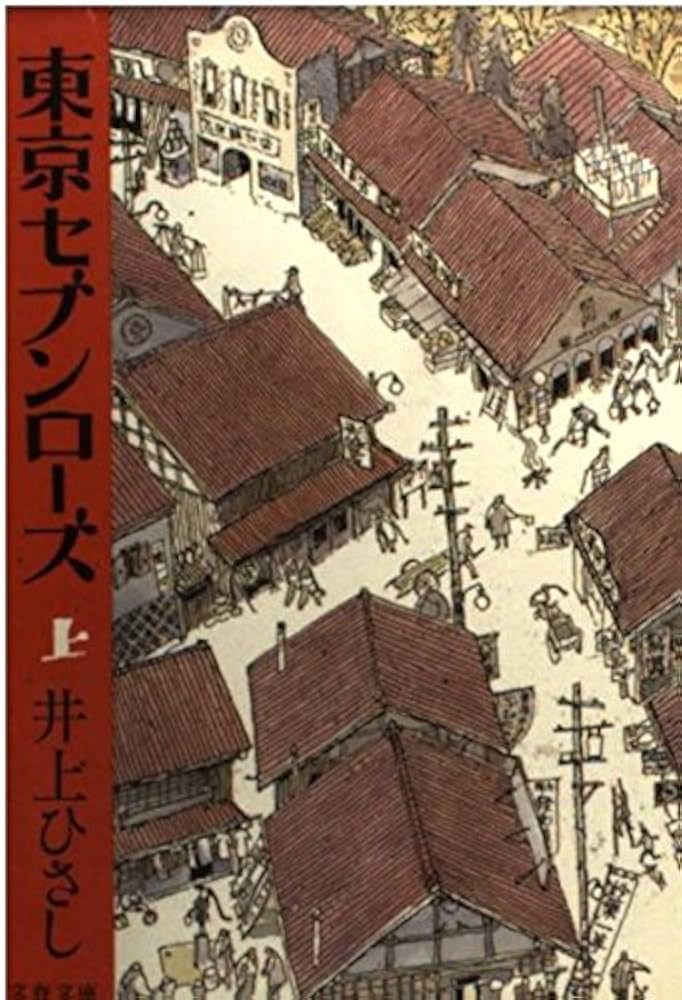
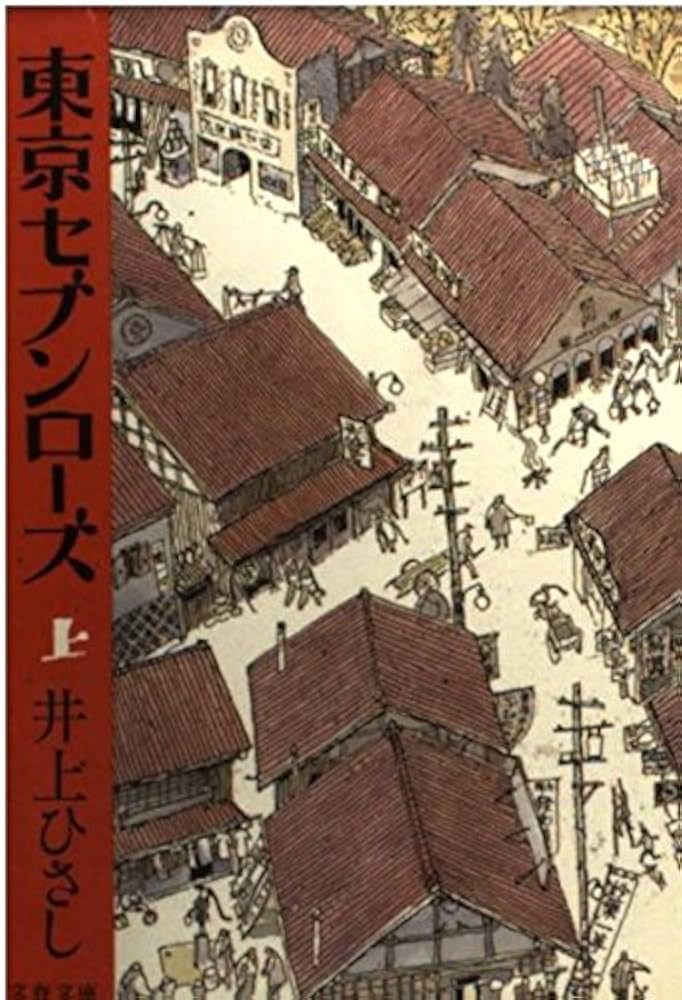
終戦直後の混乱期、GHQによる日本語ローマ字化計画という陰謀に立ち向かった7人の女性たちの活躍を描いた大作です。 物語は、東京の下町に住む団扇屋の主人が綴る日記形式で進み、当時の庶民の生活が生き生きと描写されています。
物資も食料も乏しい時代でありながら、人々は笑いを忘れず、たくましく生きていました。 そんな中、日本の文化の根幹である「日本語」を守るために立ち上がったのが、それぞれに戦争の傷跡を背負った7人の女性「セブンローズ」でした。 彼女たちが知恵と魅力を武器に、占領軍の有力者たちと渡り合う様は痛快そのもの。重いテーマを扱いながらも、井上ひさしならではのユーモアと軽快な筆致で、読者をぐいぐいと物語に引き込みます。第47回菊池寛賞を受賞した、井上文学の傑作の一つです。



大変な時代でも笑いと知恵で立ち向かう姿に勇気をもらえるよ。日本語の美しさを再発見できるんだ。
7位『不忠臣蔵』
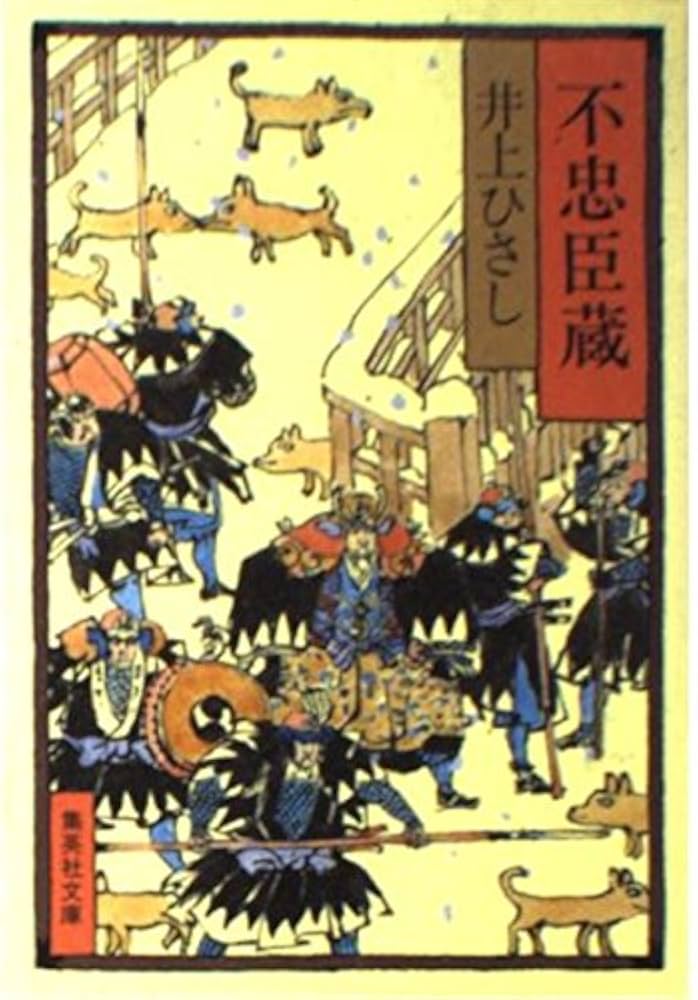
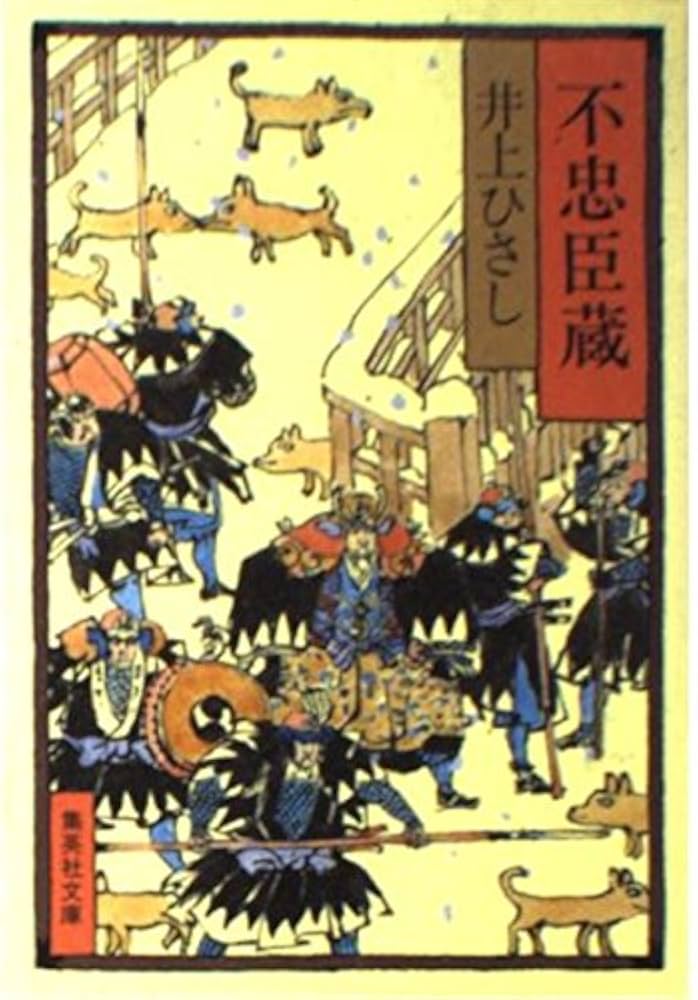
誰もが知る「忠臣蔵」の物語を、全く新しい視点から描いたユニークな歴史小説です。 井上ひさしが光を当てたのは、赤穂浪士四十七士として討ち入りに参加した英雄たちではなく、討ち入りに参加しなかった浪士たちでした。
なぜ彼らは討ち入りに参加しなかったのか?そこには「忠義」という一つの価値観だけでは測れない、人間味あふれる様々な理由がありました。病気の親の介護、貧困、あるいは単純に討ち入りを馬鹿馬鹿しいと思っていた者まで。本作では、そんな「不忠」のレッテルを貼られた人々の言い分が、ユーモラスかつ説得力をもって語られます。歴史の「if」を楽しみながら、物事を多角的に見ることの面白さを教えてくれる作品であり、第20回吉川英治文学賞を受賞しています。



忠臣蔵の裏側を想像するとワクワクするね。歴史の見方が変わる面白い一冊だよ。
8位『モッキンポット師の後始末』
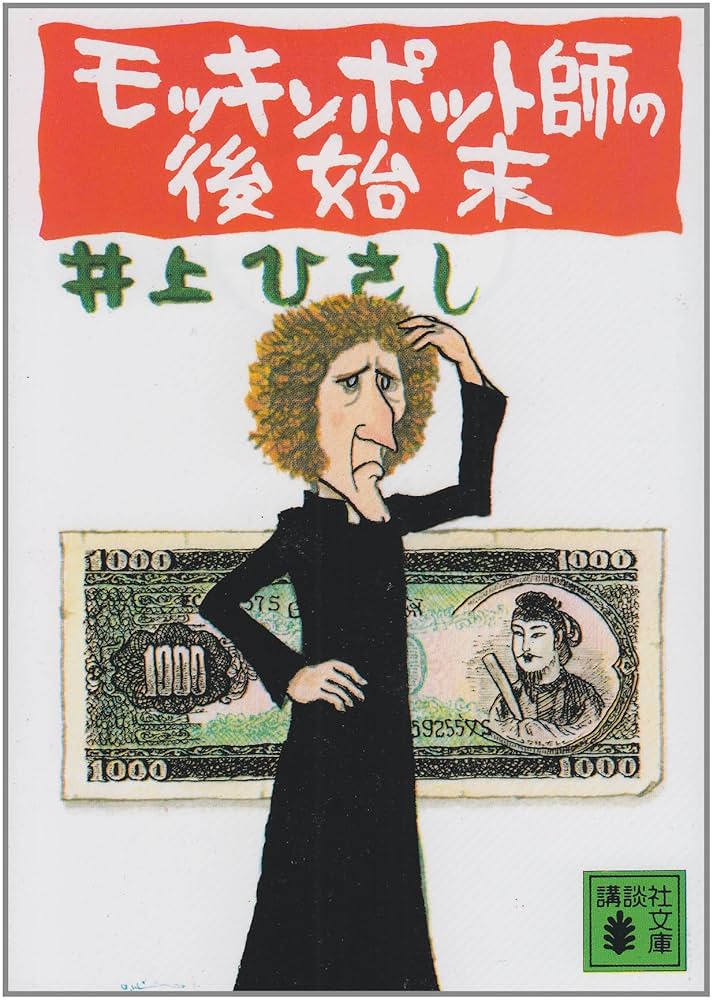
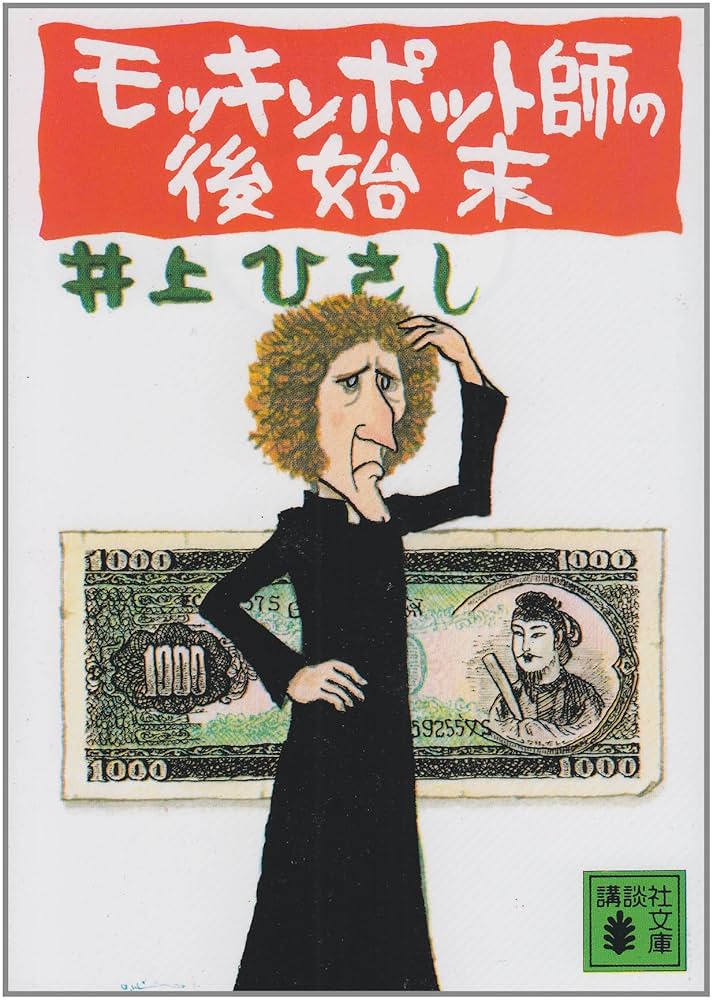
井上ひさしの自伝的要素も含まれる、ユーモアあふれる連作短編集です。 物語の舞台は、昭和30年代のカトリック学生寮。 主人公の小松をはじめとする貧乏学生3人組が、食費や金のために奇想天外な騒動を次々と巻き起こします。
鶏を盗んで丸焼きにしたり、ニセの野球チームを作ってアルバイトをしたりと、その行動は破天荒そのもの。 そして、彼らが起こす騒動の後始末にいつも奔走させられるのが、お人好しで関西弁を話すフランス人神父のモッキンポット師です。 学生たちの悪知恵と、それに振り回される神父の姿が軽快な筆致で描かれ、読者は何度も笑わされることでしょう。ドタバタコメディの中に、どこか懐かしく温かい空気が流れる作品です。



学生たちのむちゃくちゃな行動に大笑いしちゃった!神父様は気の毒だけど、愛にあふれててほっこりするよ。
9位『四千万歩の男』
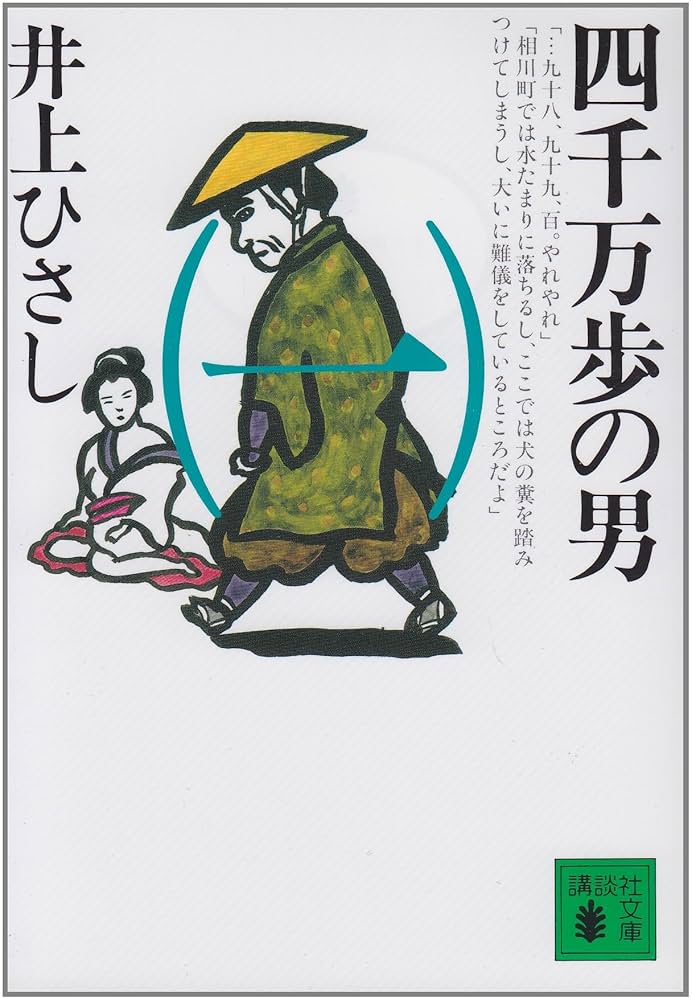
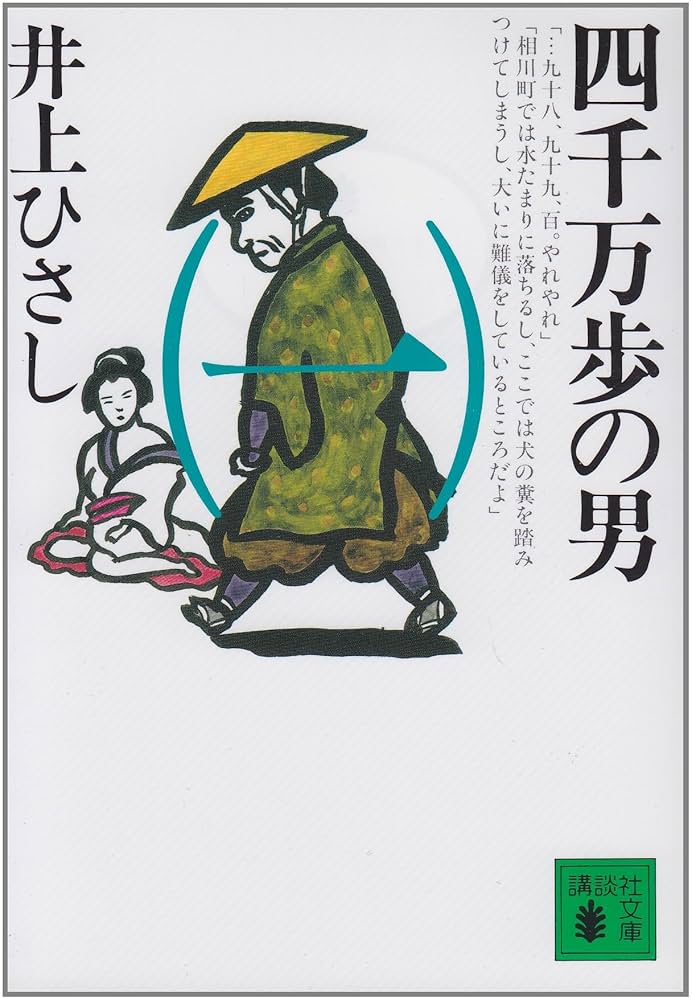
日本で初めて実測による全国地図を作製した江戸時代の測量家・伊能忠敬の壮大な生涯を描いた歴史大作です。 井上ひさしは膨大な資料を徹底的に調査し、忠敬が50歳を過ぎてから天文学を学び始め、70歳を過ぎてもなお日本全国を自らの足で歩き続けた、驚くべき情熱と探究心に満ちた人生を鮮やかに描き出しました。
全5巻にも及ぶ長編ですが、精密な測量の旅の様子だけでなく、道中で出会う人々との交流や江戸時代の文化・風俗も詳細に描かれており、読者を飽きさせません。何かを始めるのに遅すぎることはない、という強いメッセージと、一つのことを成し遂げる人間の偉大さに、深い感動を覚えることでしょう。



伊能忠敬の情熱がすごすぎるよ!夢を追いかけることの素晴らしさを教えてくれる、感動的な作品なんだ。
10位『青葉繁れる』
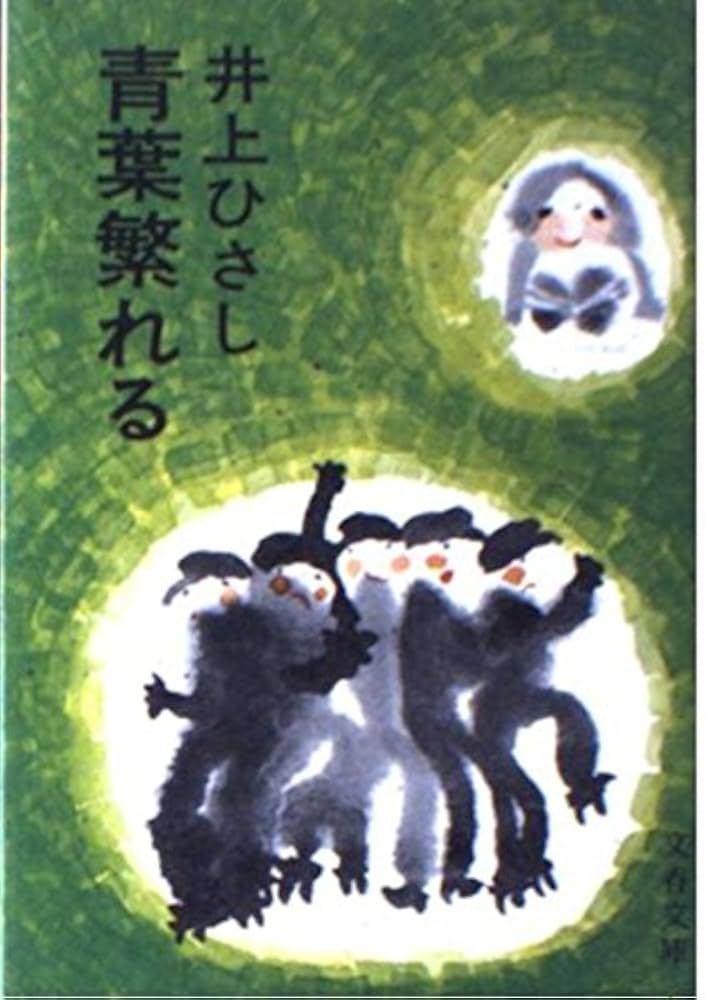
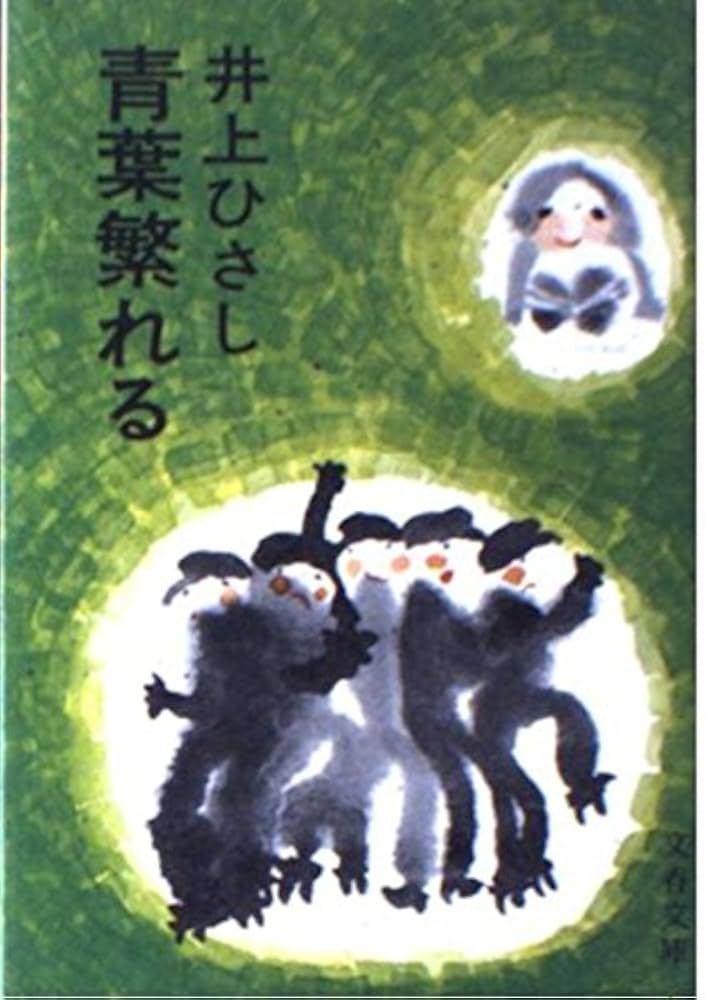
井上ひさし自身の高校時代の実体験が色濃く反映された、自伝的な青春小説です。 舞台は戦後の仙台。旧制高校の個性豊かな学生たちが繰り広げる、友情や恋愛、そして将来への希望と不安に満ちた日々が、ユーモアを交えて瑞々しく描かれています。
主人公の稔は、成績は劣等生ながらも感受性豊かな少年。 東京から来た秀才の転校生との出会いをきっかけに、彼の日常は少しずつ変化していきます。 仲間たちとの悪ふざけや、憧れの女性への淡い恋心など、誰もが経験するであろう青春のきらめきとほろ苦さが詰まっています。どこかノスタルジックで、温かい読後感に包まれる作品です。映画化やドラマ化もされた、井上ひさしの青春文学の代表作です。



作者の青春が詰まった作品だね。昔の学生生活って、今と違う面白さがあって新鮮だよ。
11位『四捨五入殺人事件』
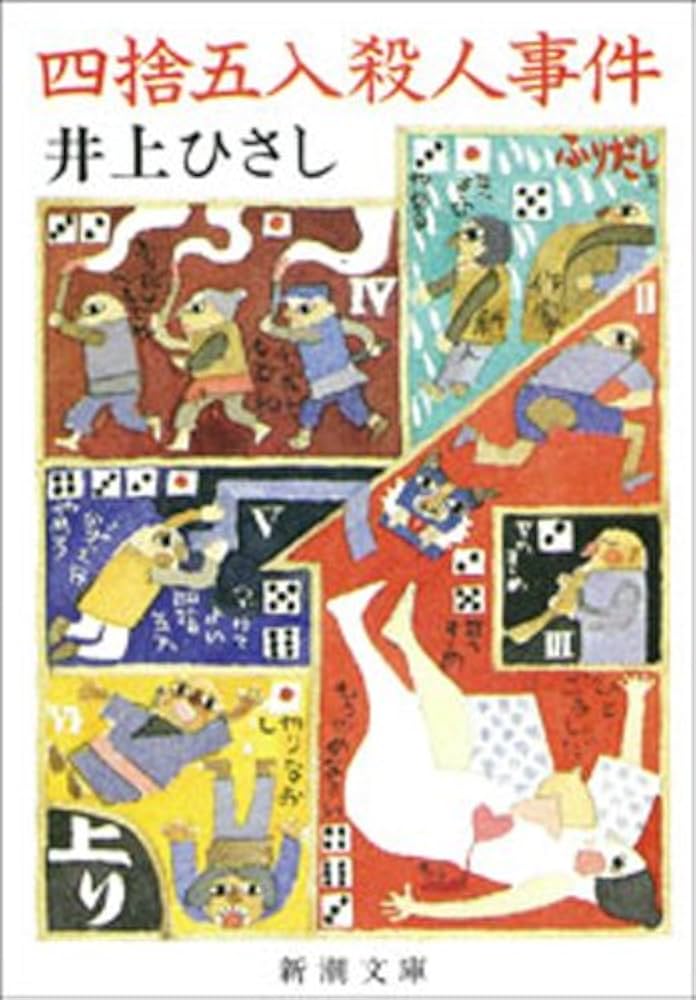
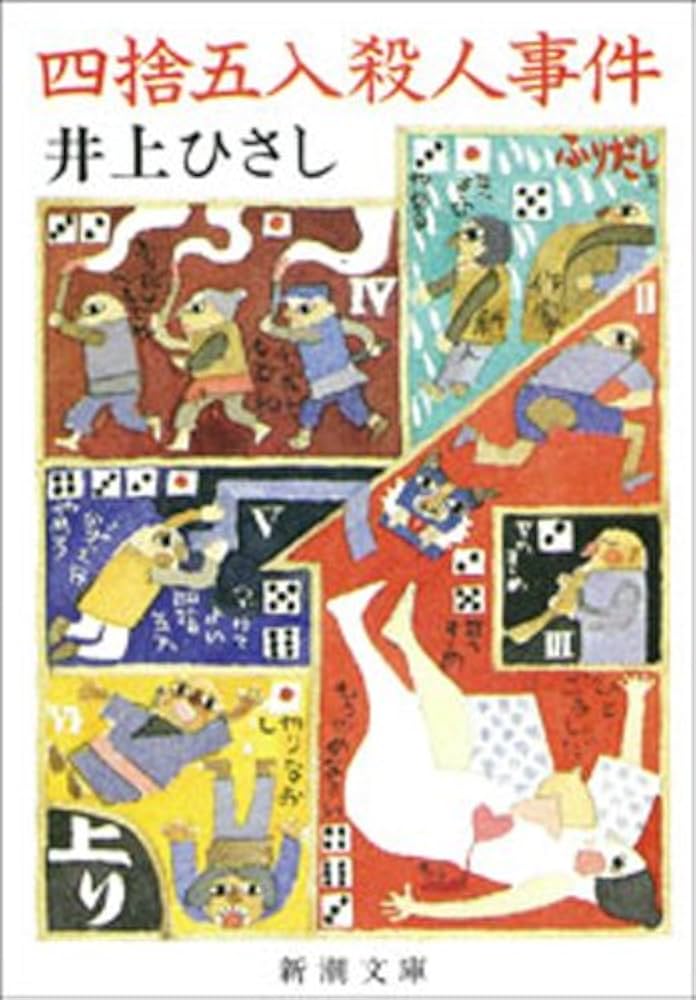
『四捨五入殺人事件』は、井上ひさし流の言葉遊びがふんだんに盛り込まれた、異色のパロディ・ミステリーです。 物語の舞台は、大雨で陸の孤島と化した山奥の温泉旅館。 講演会のために宿泊していた二人の作家が、そこで起こる連続殺人事件に巻き込まれていきます。
この作品の面白さは、本格ミステリーの体裁を取りながらも、事件の謎解きに言葉のトリックやダジャレが巧みに使われている点です。探偵役を務めるのは、あの有名な金田一耕助…ではなく、そのパロディキャラクターである国語学者の金田一京助。彼が言語学的な視点から事件の真相に迫っていく展開は、まさに「言葉の魔術師」井上ひさしの真骨頂と言えるでしょう。ミステリーファンはもちろん、言葉遊びが好きな方なら誰もが楽しめる快作です。



言葉のトリックで事件を解決するなんて、さすがだね!ミステリーなのに笑っちゃうところが最高なんだ。
12位『新釈 遠野物語』
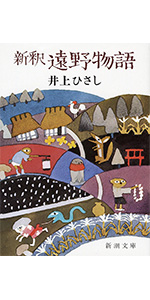
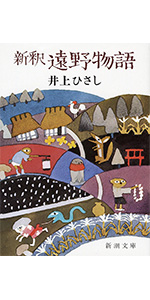
日本の民俗学の金字塔である、柳田国男の『遠野物語』。そこに記された岩手県遠野地方に伝わる不思議な伝承の数々を、井上ひさしが独自の解釈で小説として再構築したのが本作です。
座敷童子、河童、神隠しといった、原作の持つ幻想的で少し怖い世界観はそのままに、井上ひさしはそこに登場する人々の人間ドラマに焦点を当て、物語に新たな命を吹き込みました。なぜ人々はそのような不思議な話を語り継いできたのか。その背景にある人々の喜びや悲しみ、そして素朴な信仰心が、温かい筆致で描かれています。日本の原風景や、昔の人々の暮らしに思いを馳せることができる、味わい深い一冊です。



日本の昔話や不思議な話が好きなら絶対におすすめだよ。少し怖いけど、どこか懐かしい気持ちになるんだ。
まとめ:井上ひさし作品を読んで言葉の面白さに触れよう
ここまで、井上ひさしのおすすめ小説をランキング形式でご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。壮大な歴史小説から奇想天外なコメディ、そして心温まる青春物語まで、そのジャンルの幅広さに改めて驚かされます。
しかし、どの作品にも共通しているのは、その根底に流れる日本語への深い愛情と、言葉の持つ面白さを伝えたいという強い想いです。 井上ひさしの作品を読むことは、単に物語を楽しむだけでなく、私たちが普段何気なく使っている日本語の豊かさや奥深さを再発見する旅でもあります。今回のランキングを参考に、ぜひ気になる一冊を手に取って、言葉の魔術師が紡ぎ出す唯一無二の世界に触れてみてください。

