あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】宇能鴻一郎のおすすめ小説ランキングTOP20

はじめに:宇能鴻一郎とは?芥川賞作家にして官能小説の巨匠の魅力
宇能鴻一郎(うの こういちろう)は、純文学と官能小説という二つの領域で大きな足跡を残した作家です。 1934年に北海道札幌市で生まれ、東京大学大学院在学中の1962年に『鯨神』で第46回芥川賞を受賞しました。 この作品は、巨大なクジラと漁師の死闘を描いた重厚な物語で、映画化もされています。
芥川賞作家として純文学の世界でキャリアをスタートさせた後、1970年代からは官能小説の分野に活動の軸足を移します。 特に「あたし、〇〇なんです」といった女性の独白形式を用いた独特の文体は一世を風靡し、多くの読者を獲得しました。 純文学の確かな筆力と、人間の性と死に迫るテーマ性、そしてエンターテイメント性を融合させた作風が、宇能鴻一郎の大きな魅力と言えるでしょう。 また、嵯峨島昭(さがしま あきら)名義でミステリー小説を手がけるなど、その活動は多岐にわたります。
宇能鴻一郎のおすすめ小説ランキングTOP20
ここからは、宇能鴻一郎のおすすめ小説をランキング形式でご紹介します。純文学の傑作から、官能小説の代表作、さらにはグルメエッセイまで、多彩なラインナップを揃えました。ぜひ、あなたの好みに合う一冊を見つけてみてください。
1位『姫君を喰う話 宇能鴻一郎傑作短編集』
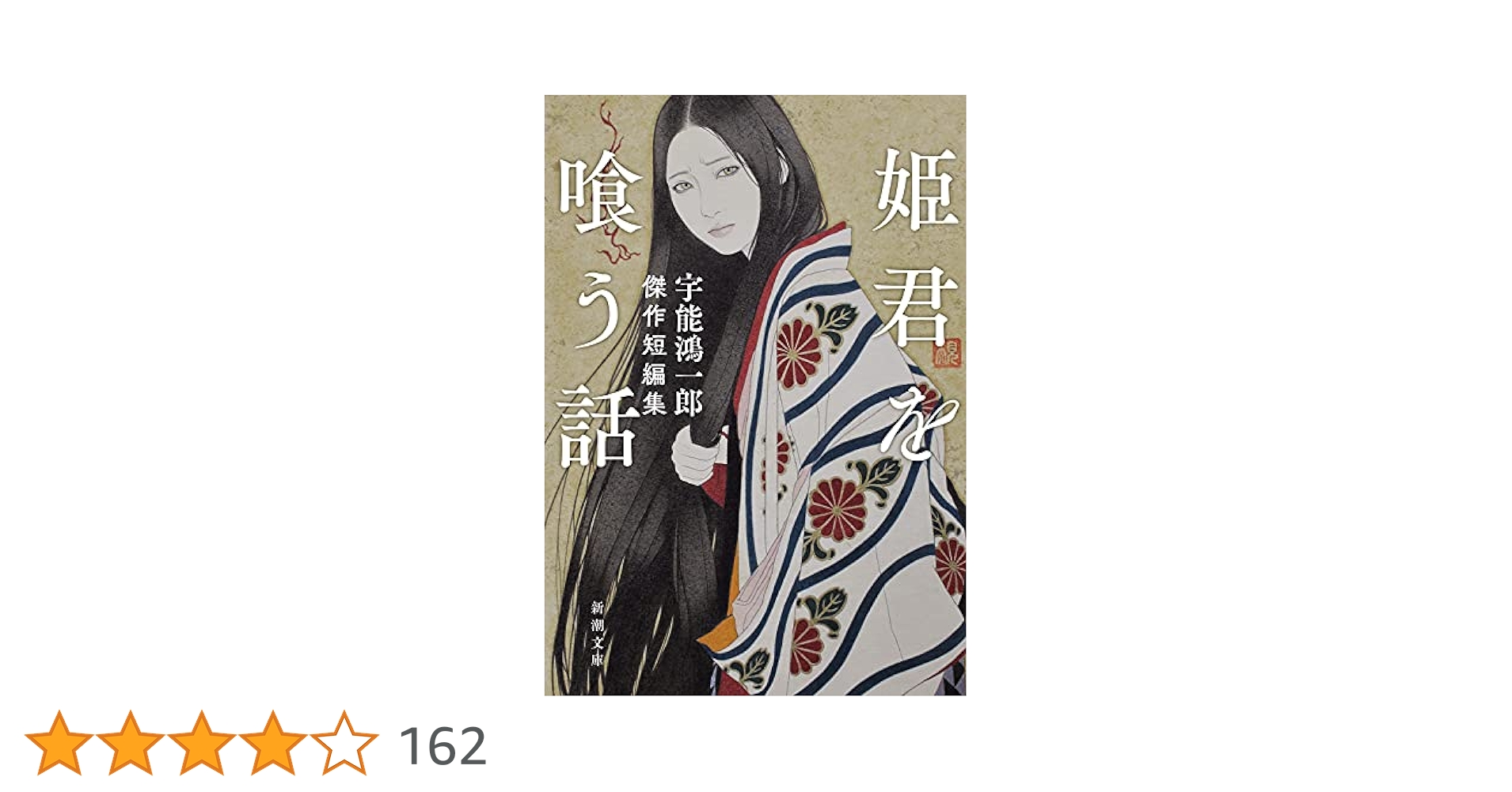
宇能鴻一郎の神髄に触れるなら、まずはこの傑作短編集がおすすめです。2021年に新潮文庫から発売され、発売後すぐに重版がかかるなど異例の売れ行きを見せました。 本書には、表題作「姫君を喰う話」や芥川賞受賞作「鯨神」をはじめとする、選りすぐりの6編が収録されています。
純文学作家としての圧倒的な筆力と、官能と狂気が渦巻く濃厚な世界観を一度に味わえるのが最大の魅力です。宇能文学の入門書として、またその奥深さを再確認するための一冊として、多くの読者に支持されています。中学三年生で宇能作品に出会ったという作家の篠田節子さんが解説を寄せており、作品をより深く理解する手助けとなるでしょう。
 ふくちい
ふくちい純文学と官能が一度に味わえるなんてお得だね。宇能先生の才能の幅広さにびっくりしちゃうよ。
2位『鯨神』
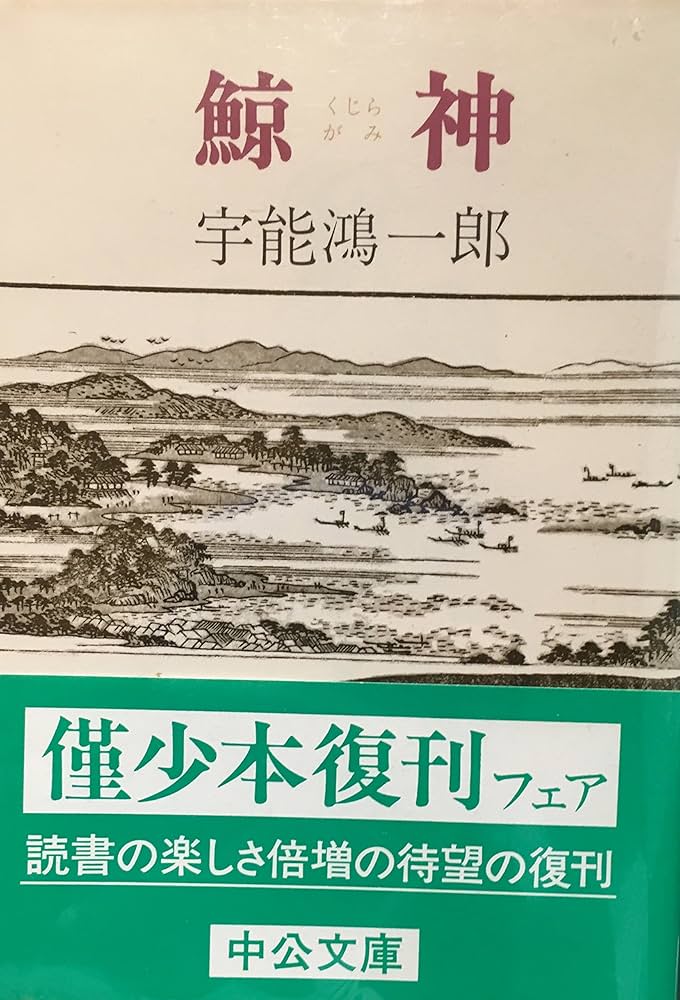
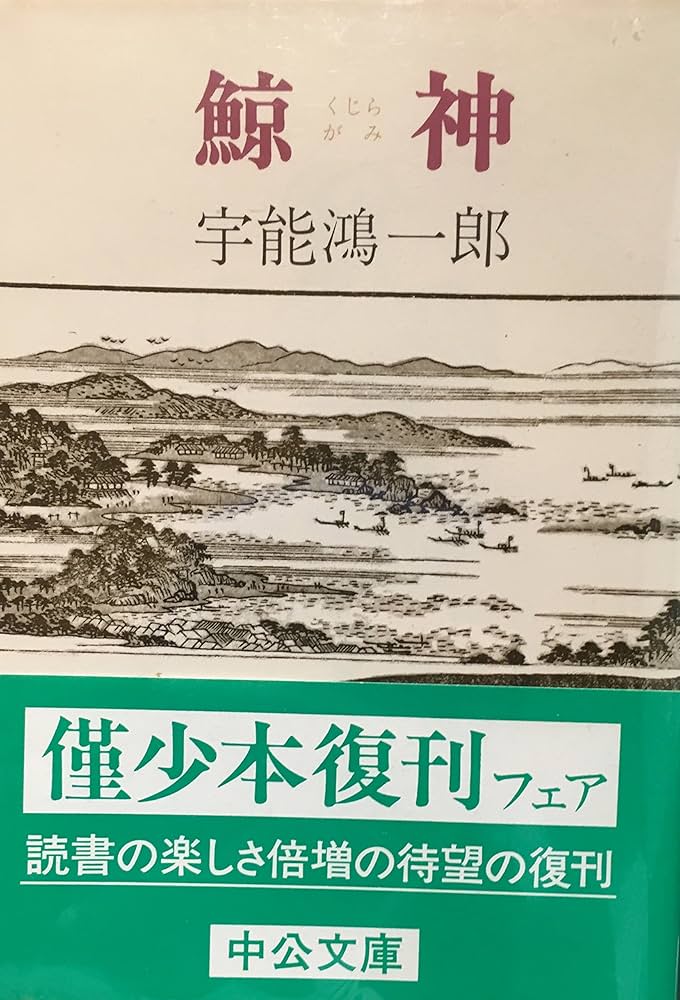
『鯨神』は、1962年に第46回芥川賞を受賞した宇能鴻一郎の代表作です。 物語の舞台は明治初年の長崎県平戸島。 祖父、父、兄を巨大な鯨に殺された若い漁師が、復讐を誓って死闘を繰り広げるという壮大な物語です。
この作品の魅力は、なんといってもその圧倒的な熱量と迫力ある描写にあります。 鯨と人間の闘いを描いた奔放な筆致は高く評価され、芥川賞の選評でも「若く健康な空想力と、たくましい描写力に感心した」と称賛されました。 純文学作家・宇能鴻一郎の力量を存分に感じられる、文学史に残る傑作です。



復讐のために巨大なクジラと戦うなんて、すごく燃える展開だね!想像するだけでドキドキしちゃうよ。
3位『アルマジロの手 宇能鴻一郎傑作短編集』
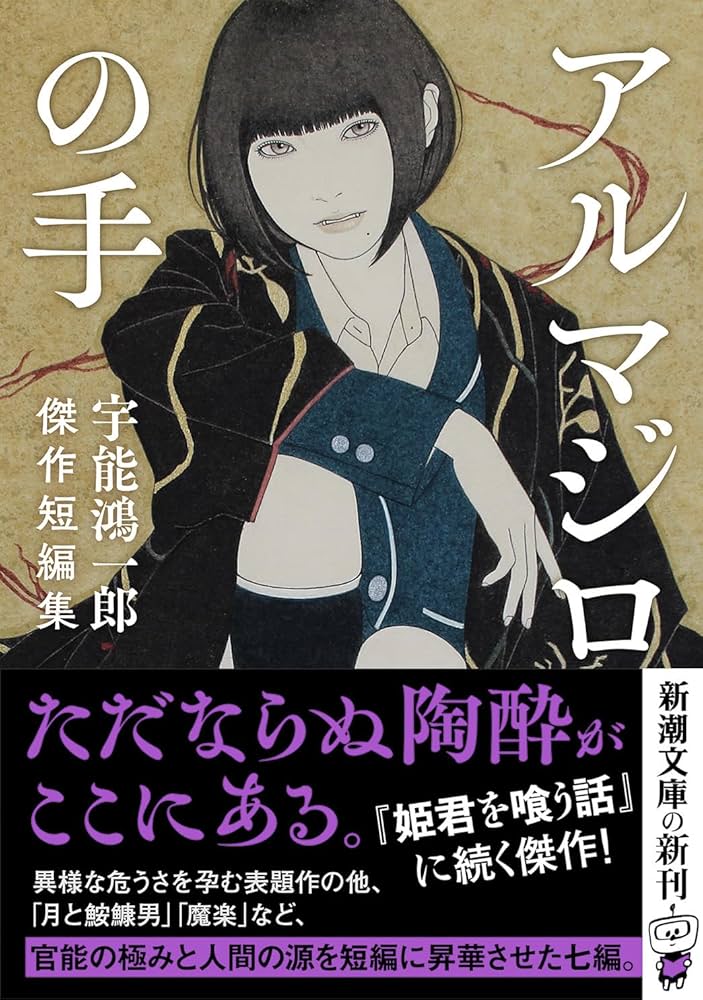
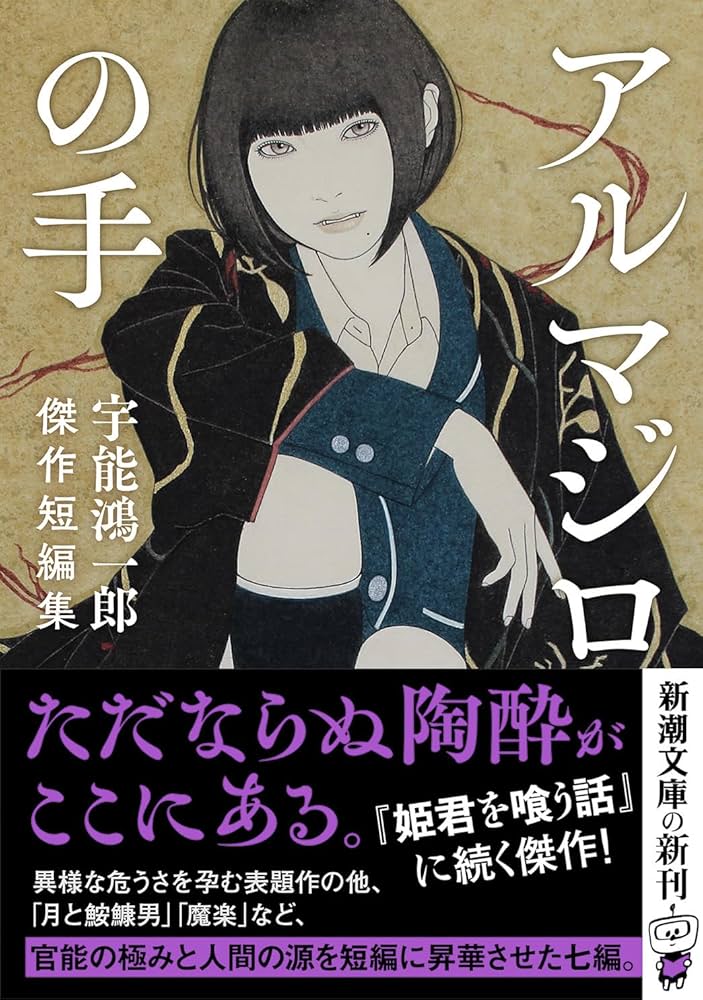
『アルマジロの手』は、宇能鴻一郎の多彩な才能が光る傑作短編集です。表題作をはじめ、初期の純文学作品から官能的な要素を含む作品まで、幅広い作風の短編が収録されています。
一筋縄ではいかない奇妙で幻想的な物語が多く、読者の想像力をかき立てます。純文学の枠にとらわれない自由な発想と、それを支える確かな文章力が見事に融合しており、宇能鴻一郎という作家の引き出しの多さを感じさせてくれる一冊です。ミステリアスな物語が好きな方や、少し変わった読書体験をしたい方におすすめです。



『アルマジロの手』ってタイトルからして不思議な感じがするね。どんな物語が詰まっているのか、すごく気になるよ。
4位『味な旅 舌の旅』
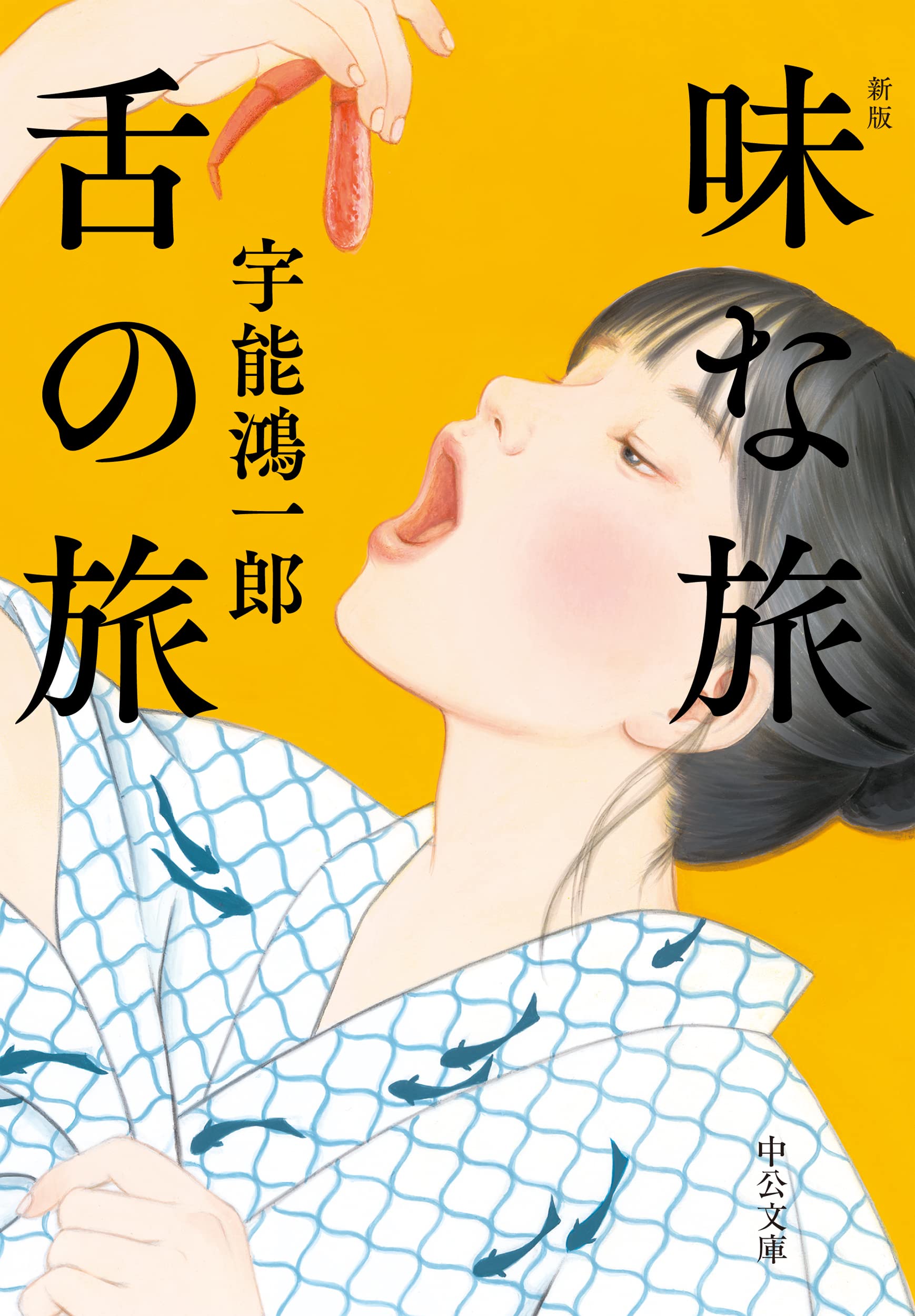
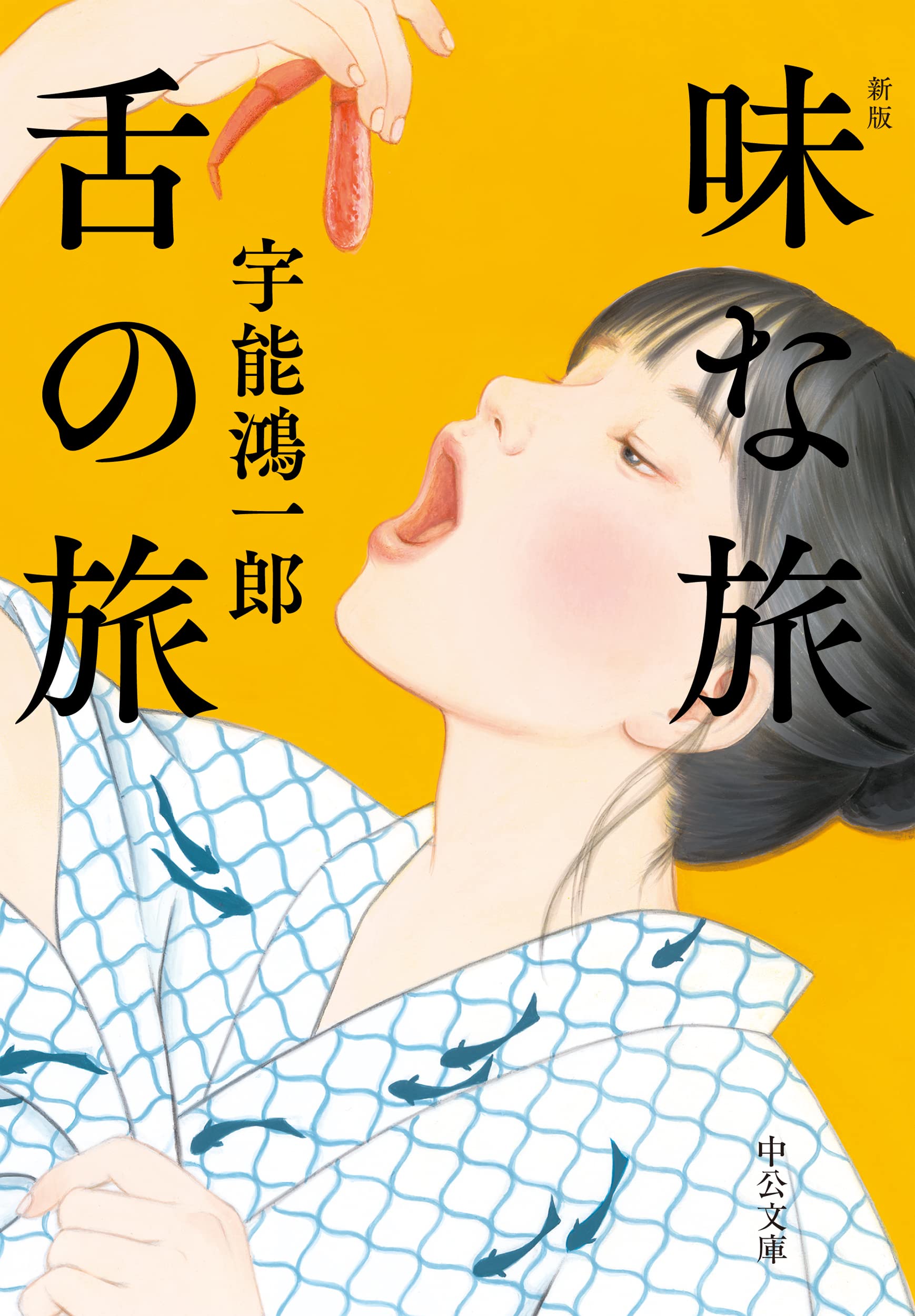
『味な旅 舌の旅』は、小説家としてだけでなく、美食家としても知られた宇能鴻一郎による名エッセイです。 本書では、日本各地を旅して出会った美味しいものや、食にまつわる思い出、独自の食哲学が軽妙な筆致で綴られています。
単なるグルメガイドではなく、食を通して人生の豊かさや楽しみ方を教えてくれるのが本書の魅力です。読んでいるだけでお腹が空いてくるような巧みな描写は、さすが小説家ならでは。旅や食べることが好きな方はもちろん、日常にちょっとした彩りを加えたい方にもおすすめの一冊です。



美味しいものを食べてる時って本当に幸せだよね。宇能先生がどんなものを食べていたのか、こっそり覗いてみたいな。
5位『むちむちぷりん』
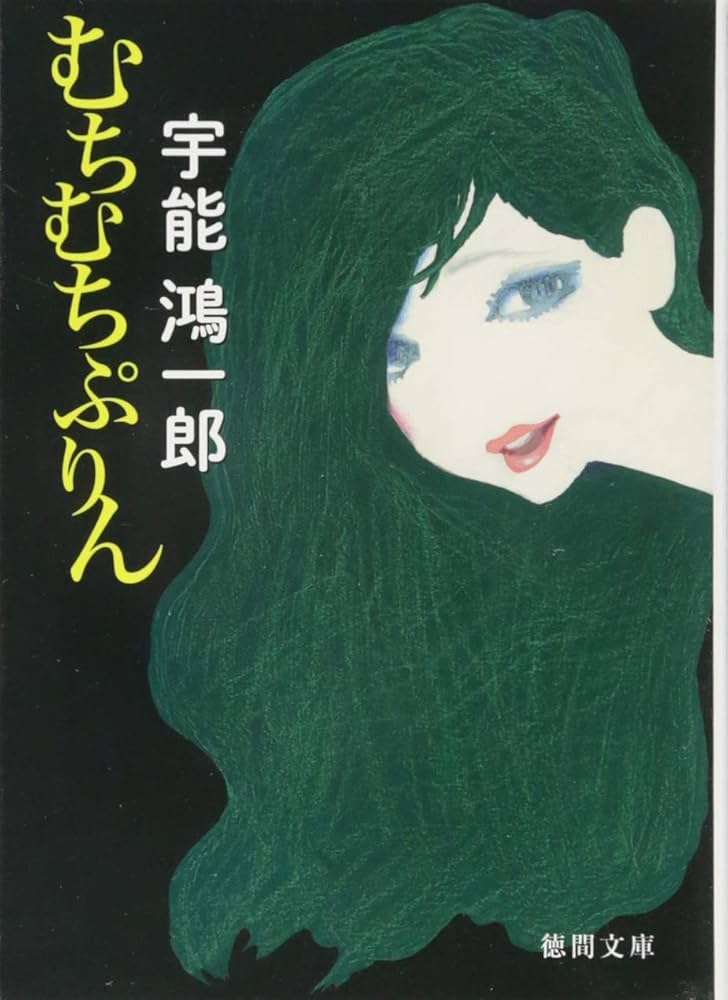
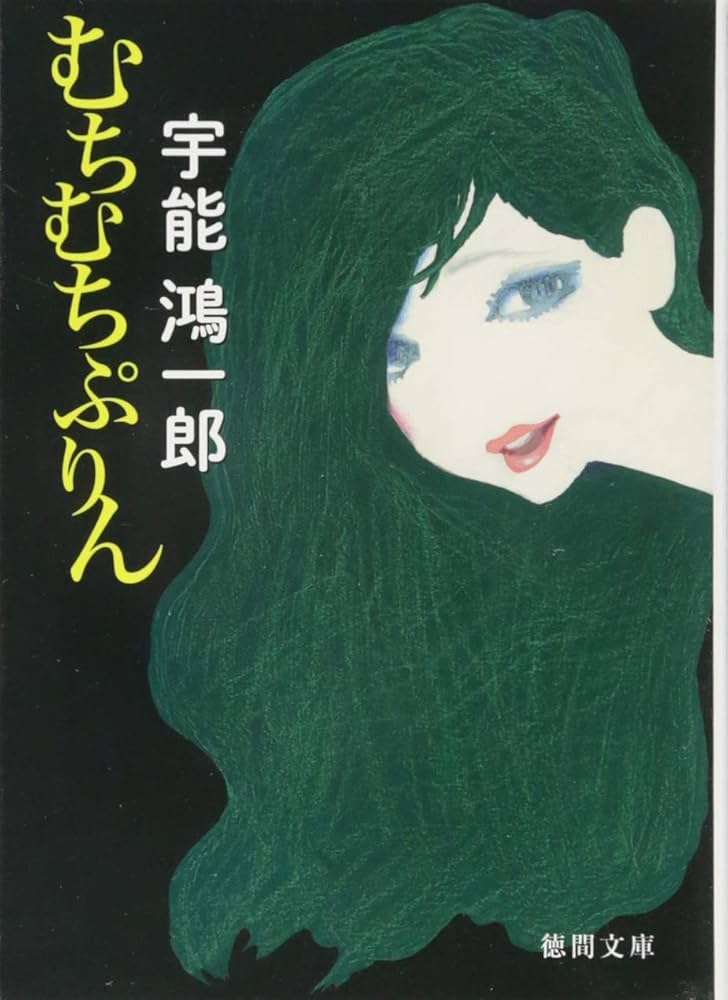
『むちむちぷりん』は、官能小説家としての宇能鴻一郎の名を世に知らしめた代表作の一つです。 「あたし、〇〇なんです」という女性の独白体で物語が展開するスタイルは、宇能鴻一郎が確立した画期的な手法でした。
直接的な表現を多用するのではなく、女性の語り口や心理描写によって読者の想像力を掻き立てるのが特徴です。 あっけらかんと性を楽しむ女性たちの姿を軽妙なタッチで描き、官能小説の世界に新たな風を吹き込みました。 タイトルのインパクトもさることながら、文学的な技巧に裏打ちされた新しい官能小説の形を示した作品として、今なお多くのファンに愛されています。



『むちむちぷりん』ってすごいタイトルだね!一度聞いたら忘れられないインパクトだよ。
6位『べろべろの、母ちゃんは…』
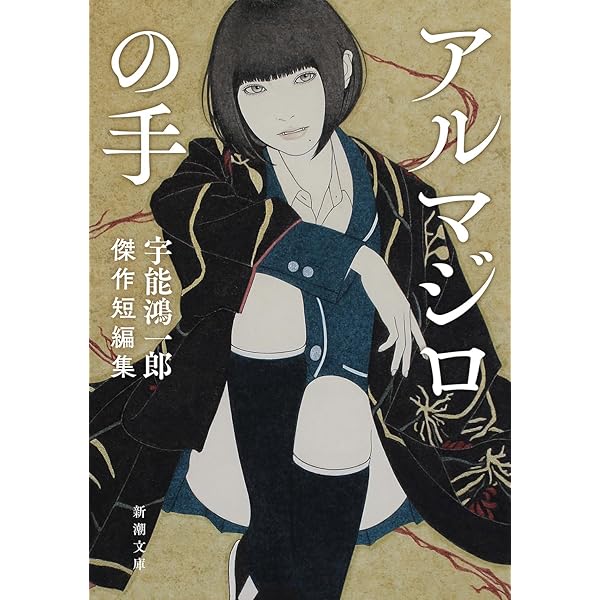
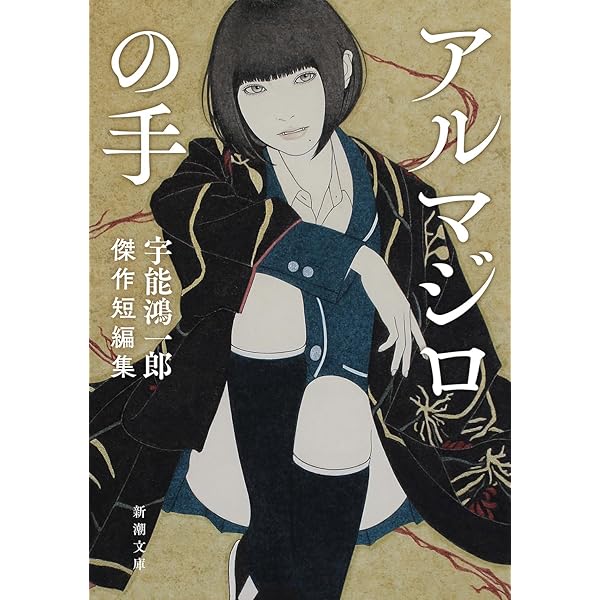
『べろべろの、母ちゃんは…』は、宇能鴻一郎の官能小説の中でも特に人気の高い作品です。タイトルからして強烈なインパクトを放っていますが、その内容は人間の業や性を深くえぐる、文学性の高いものとなっています。
宇能作品の特徴である女性の独白体を用いながら、母と子の複雑な関係性や、人間の内に秘められた欲望を描き出しています。ただ刺激的なだけでなく、物語の奥にはどこか物悲しさや切なさが漂っており、読後に深い余韻を残します。官能小説の枠を超えた人間ドラマとして、多くの読者を惹きつけてやまない一冊です。



なんだか切ないお話なのかな…。タイトルからは想像できない、深い物語が隠れていそうだね。
7位『甘美な牢獄』
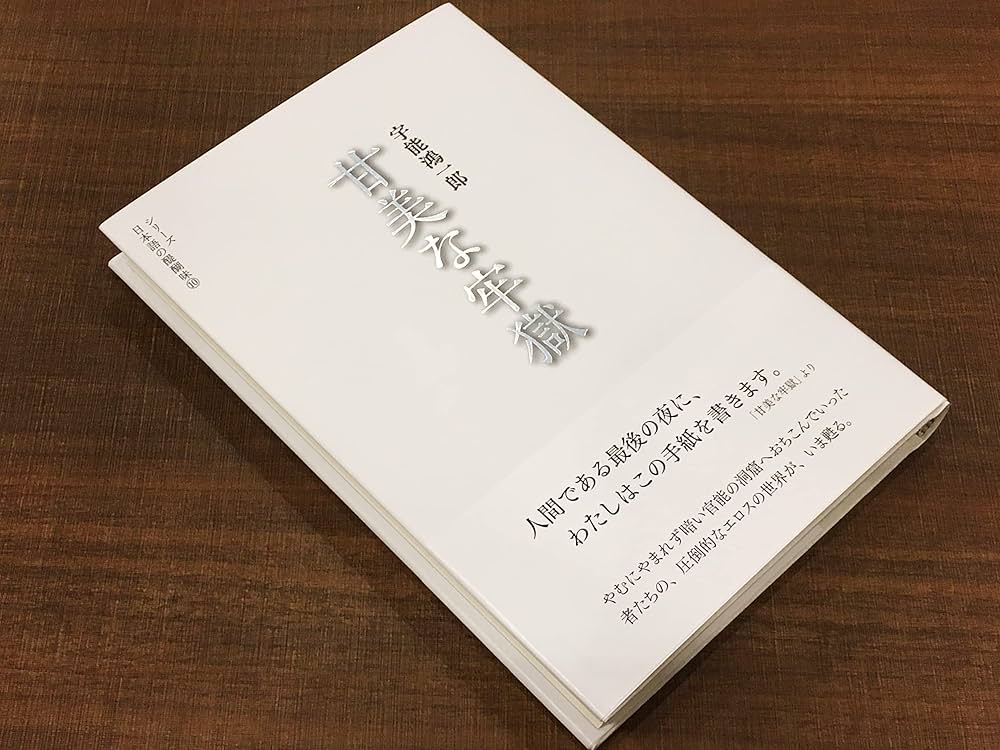
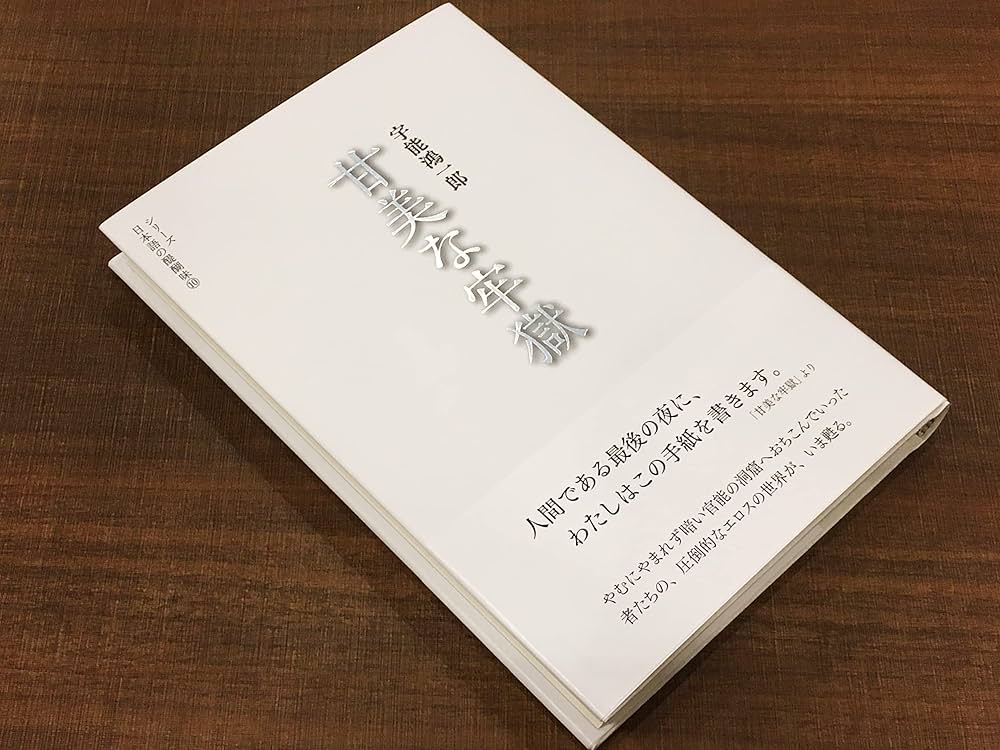
『甘美な牢獄』は、宇能鴻一郎の官能と幻想が入り混じった独特の世界観が存分に味わえる作品です。閉鎖的な状況に置かれた登場人物たちの、異常な心理や倒錯した関係性を描いています。
この作品の魅力は、美しくもどこか退廃的な雰囲気と、読者の倫理観を揺さぶるような背徳的な物語にあります。人間の心の奥底に潜む欲望や狂気を、巧みな筆致で描き出す手腕はまさに圧巻。日常から離れた刺激的な読書体験を求める方に、ぜひ手に取ってほしい一冊です。



甘美な牢獄…なんて魅惑的な響きなんだろう。ちょっと怖いけど、その世界を覗いてみたくなっちゃうね。
8位『秘本西遊記』
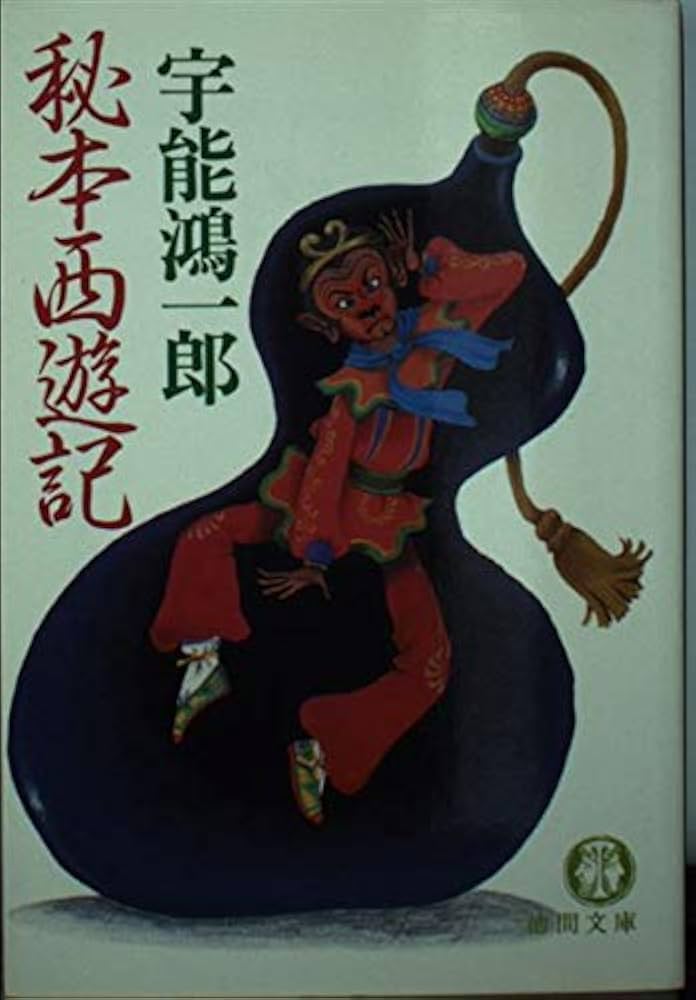
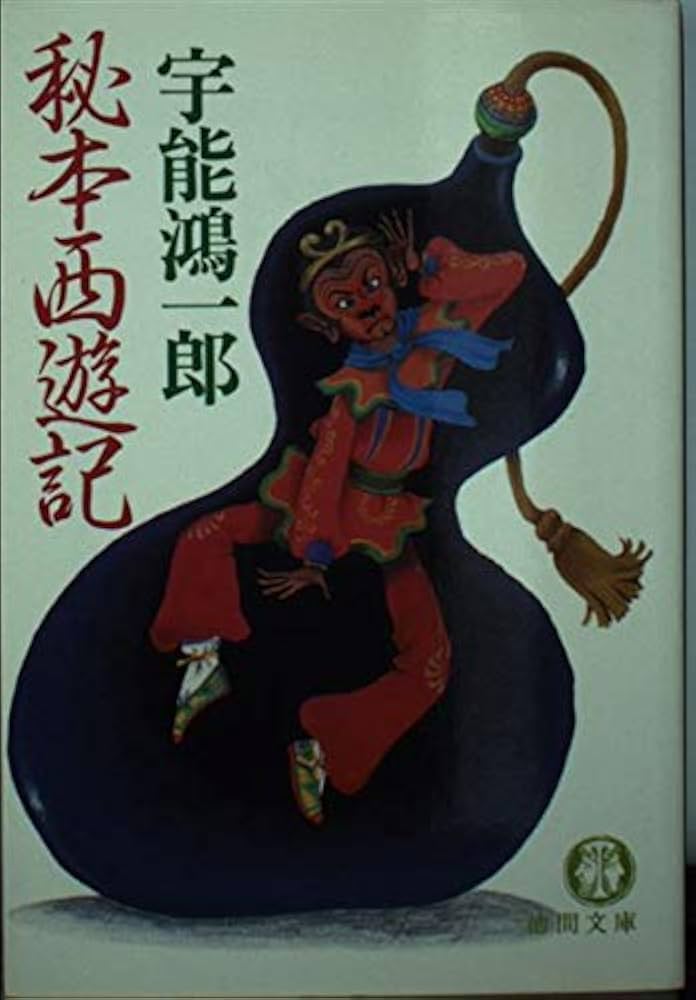
『秘本西遊記』は、中国の古典『西遊記』を宇能鴻一郎流に大胆にアレンジしたパロディ小説です。誰もが知る三蔵法師一行の旅を、官能とユーモアを交えて全く新しい物語に生まれ変わらせています。
原作のキャラクター設定を巧みに利用しながら、奇想天外なエロティック・アドベンチャーを繰り広げます。宇能鴻一郎の持つユーモアのセンスと、奔放な想像力がいかんなく発揮された快作です。古典文学の新たな楽しみ方を提示してくれると同時に、エンターテイメント小説としての完成度も非常に高い作品と言えるでしょう。



あの西遊記がエロティック・アドベンチャーになるなんて!悟空たちがどんな活躍をするのか、すごく気になるよ。
9位『夢十夜 双面神ヤヌスの谷崎・三島変化』
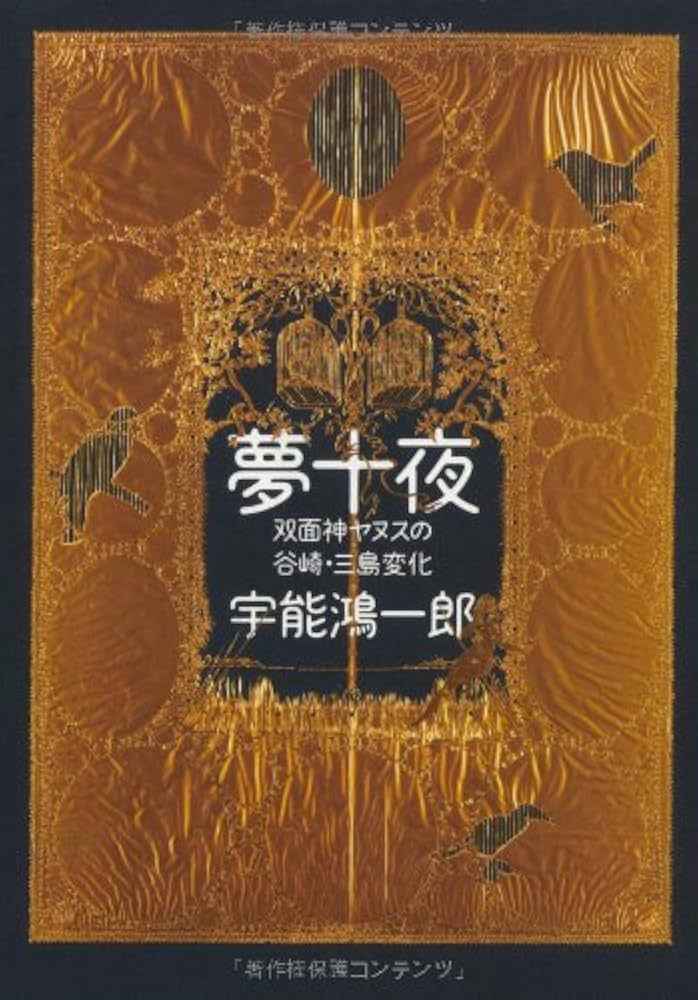
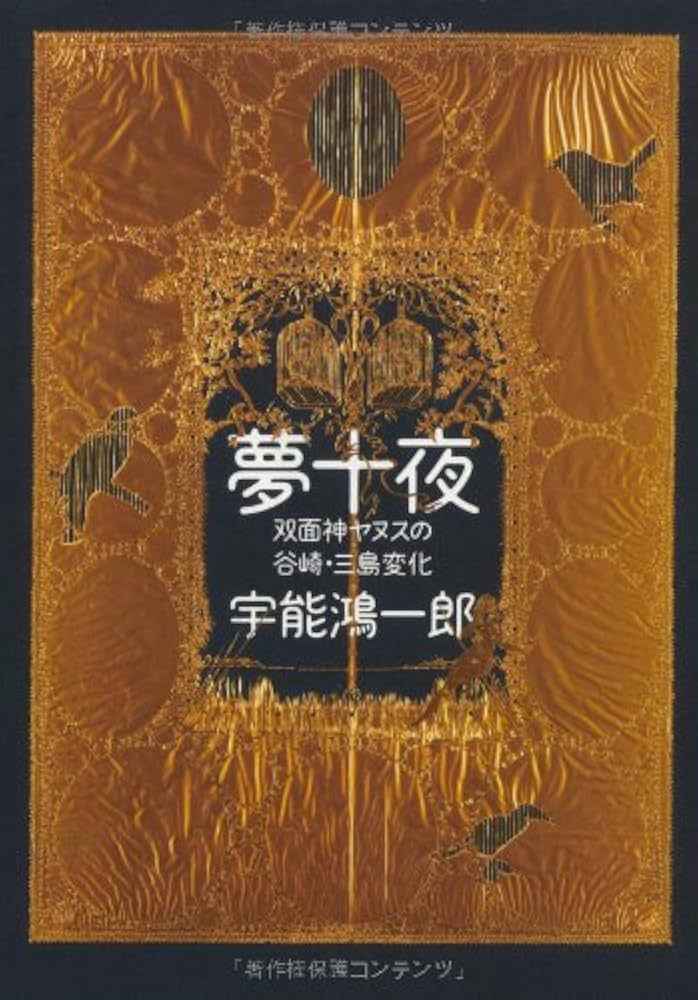
長年、官能小説という大衆文学の第一線を走り続けてきた作家が、自身の文学的ルーツや思索を深く掘り下げた、批評性の高い作品です。 純文学作家としての宇能鴻一郎の知性と教養が凝縮されており、読み応えは抜群。日本近代文学に詳しい方であれば、より一層楽しめること間違いなしの一冊です。



漱石、谷崎、三島をミックスするなんて、まるで文学の実験室みたいだね。わたしの知的好奇心がくすぐられちゃうよ。
10位『濡れて飛ぶ』
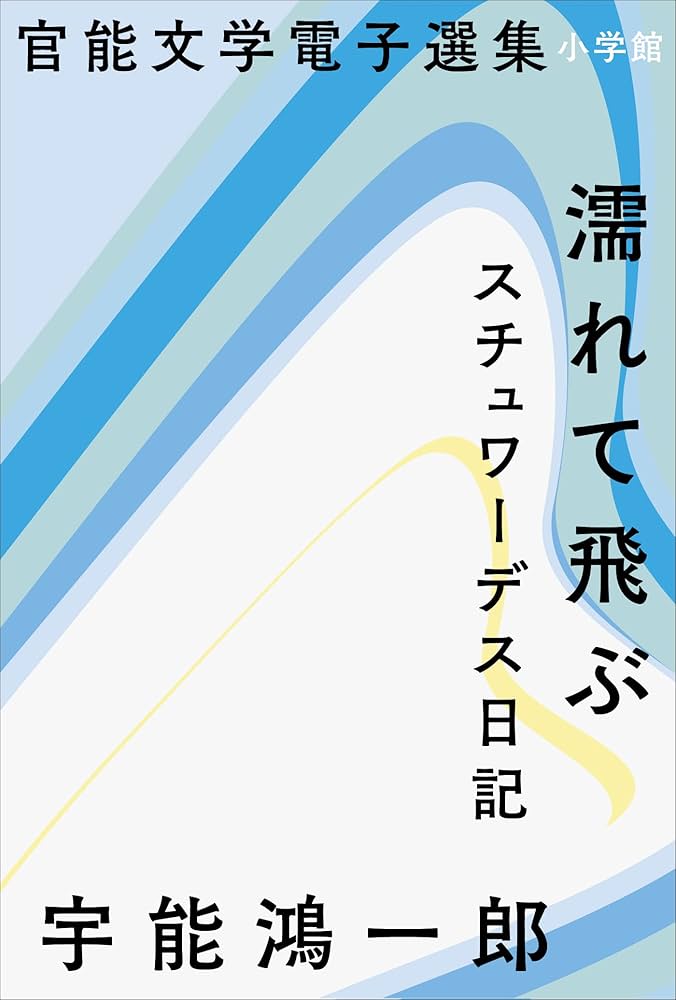
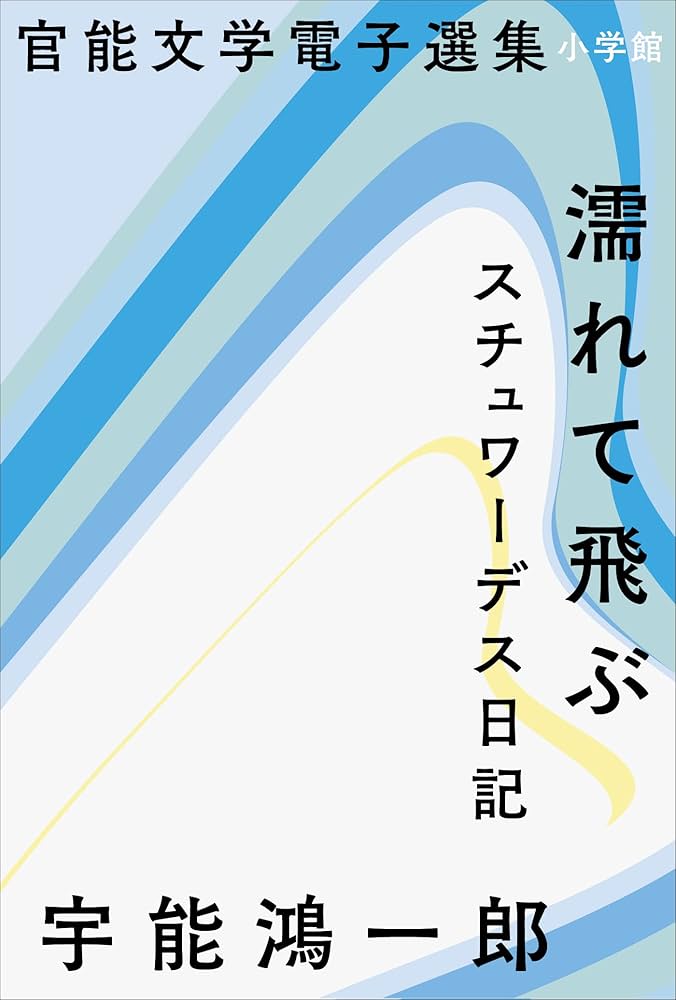
『濡れて飛ぶ』は、宇能鴻一郎の官能小説の中でも、特にストーリー性が高く評価されている作品の一つです。女性の視点から描かれる恋愛模様や性の葛藤が、読者の共感を呼びます。
宇能作品ならではの軽妙な文体は健在ですが、登場人物たちの心情がより丁寧に、そして切なく描かれているのが特徴です。単なる官能的な描写に留まらず、恋愛小説としても楽しめる深みを持っています。官能小説は初めてという方でも、比較的読みやすい作品かもしれません。



恋愛小説としても楽しめるんだね。官能小説の入り口として読むのに、ちょうどいいかもしれないな。
11位『肉の壁』
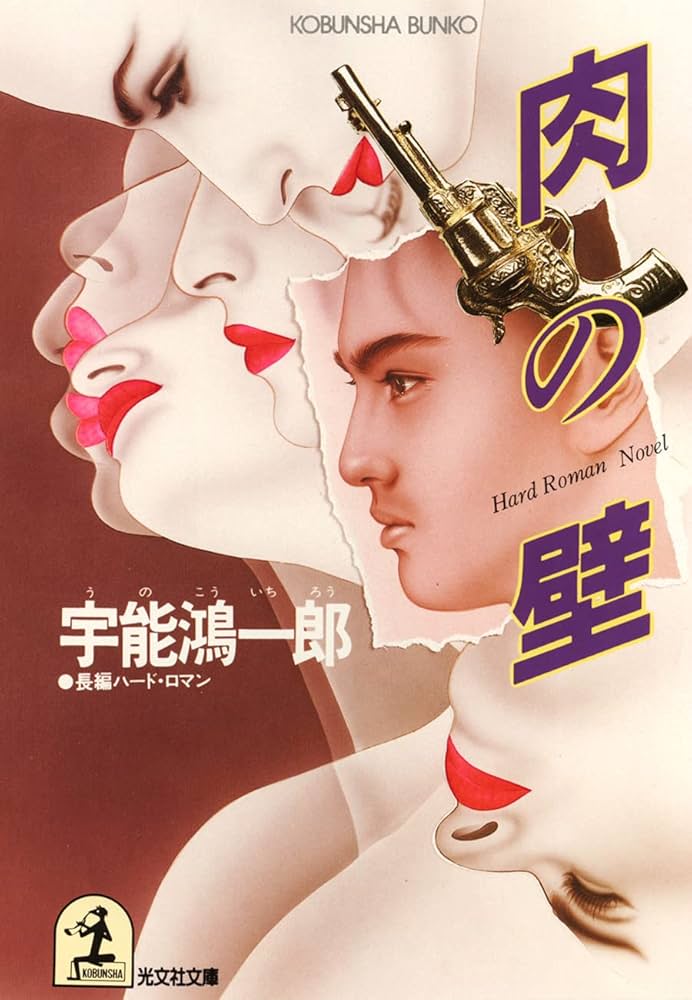
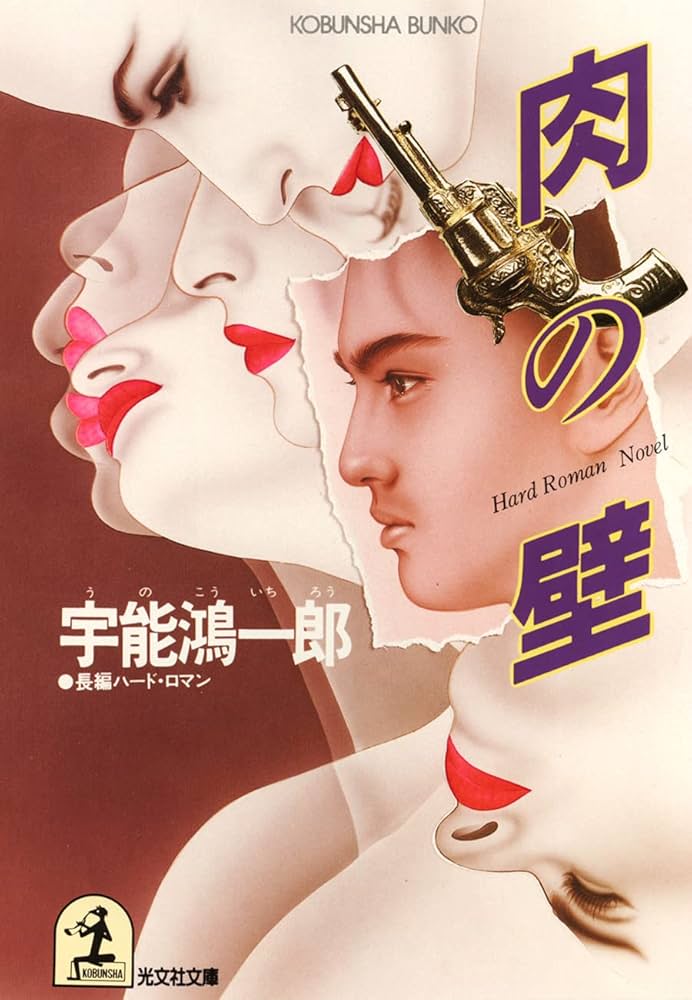
『肉の壁』は、宇能鴻一郎の初期の作品で、純文学とエンターテイメント性が融合したスリリングな物語です。ある種の極限状況に置かれた人間たちの、剥き出しの欲望や生存本能を描いています。
後の官能小説につながる「性と死」というテーマを扱いながらも、物語の展開は息もつかせぬサスペンスフルなものとなっています。人間の本質に迫る重厚なテーマと、読者を飽きさせない巧みなストーリーテリングが見事に両立した一冊。宇能鴻一郎の作家としての懐の深さを感じさせます。



サスペンスフルな展開はドキドキしちゃうね!人間の本能が描かれる物語って、ちょっと怖いけど惹かれちゃうな。
12位『耽溺』
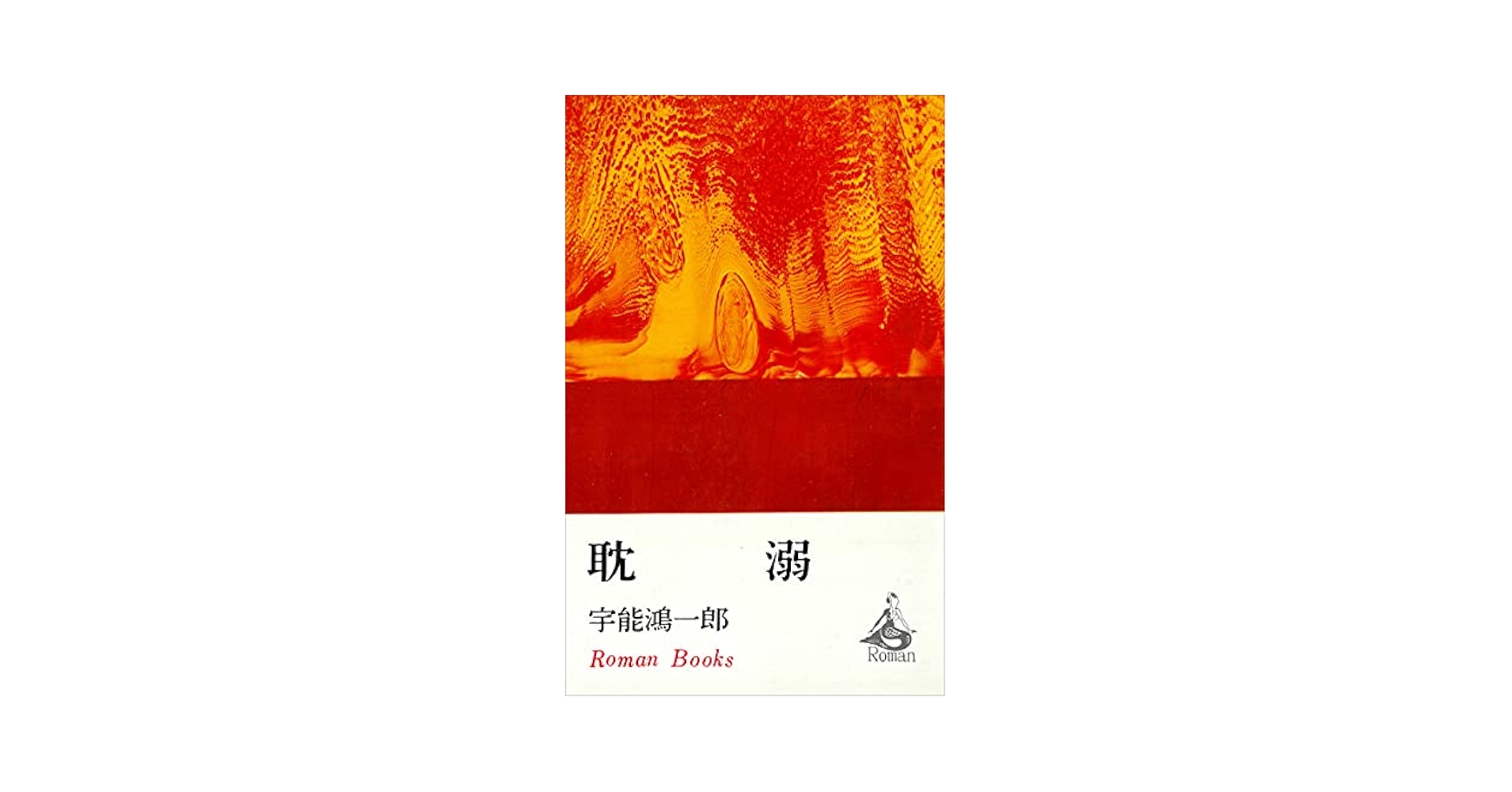
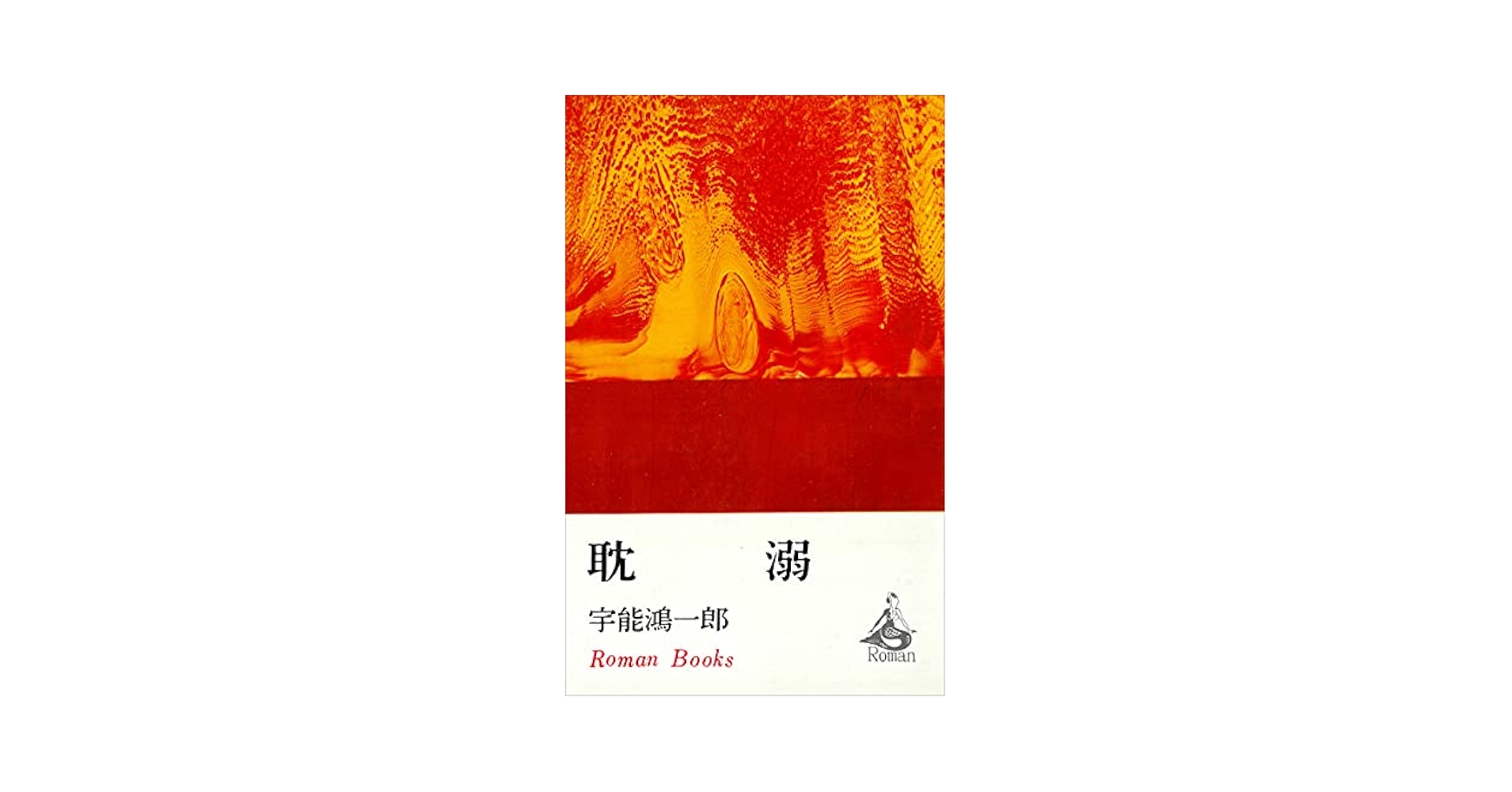
『耽溺』は、そのタイトルの通り、ある一つのことに深く溺れていく人間の姿を描いた官能小説です。宇能鴻一郎の真骨頂ともいえる、人間の執着心やフェティシズムを深く掘り下げた作品となっています。
読んでいるうちに、登場人物たちの倒錯した世界に引きずり込まれるような、独特の読書体験ができます。人間の理性が欲望によっていかに脆く崩れ去るかを、官能的かつ文学的に描き出した問題作。刺激の強い作品を求める読者におすすめです。



本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは、作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。
13位『好色源氏物語』
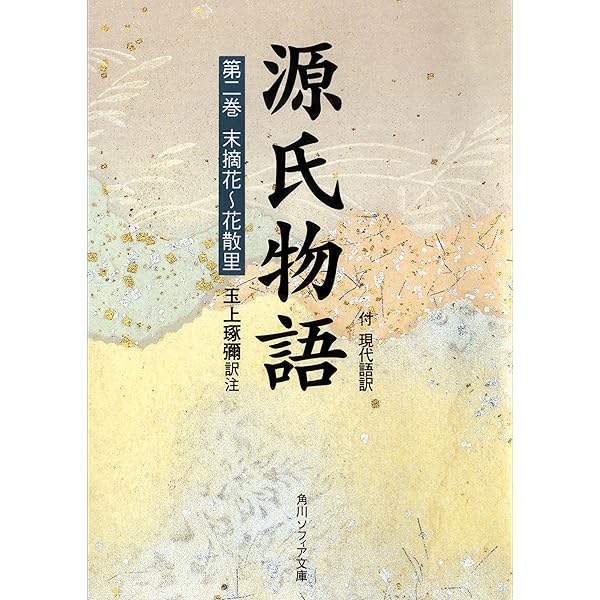
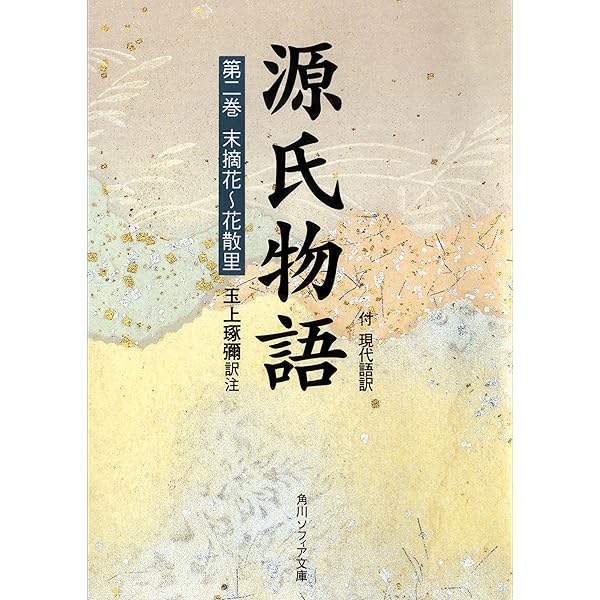
『好色源氏物語』は、『秘本西遊記』と同様に、古典文学を題材にした宇能鴻一郎流のパロディ作品です。言わずと知れた日本の古典『源氏物語』の世界を、大胆不敵な解釈で「好色」な物語として再構築しています。
光源氏をはじめとする登場人物たちが、より人間臭く、欲望に忠実なキャラクターとして生き生きと描かれているのが魅力です。宇能鴻一郎の古典に対する深い知識と、それを遊び心たっぷりに解体してみせるユーモアのセンスが光ります。原作を知っている人はもちろん、知らない人でも楽しめるエンターテイメント作品です。



あの雅な源氏物語がどうなっちゃうんだろう?光源氏の新しい一面が見られそうで、わくわくするね!
14位『花魁』
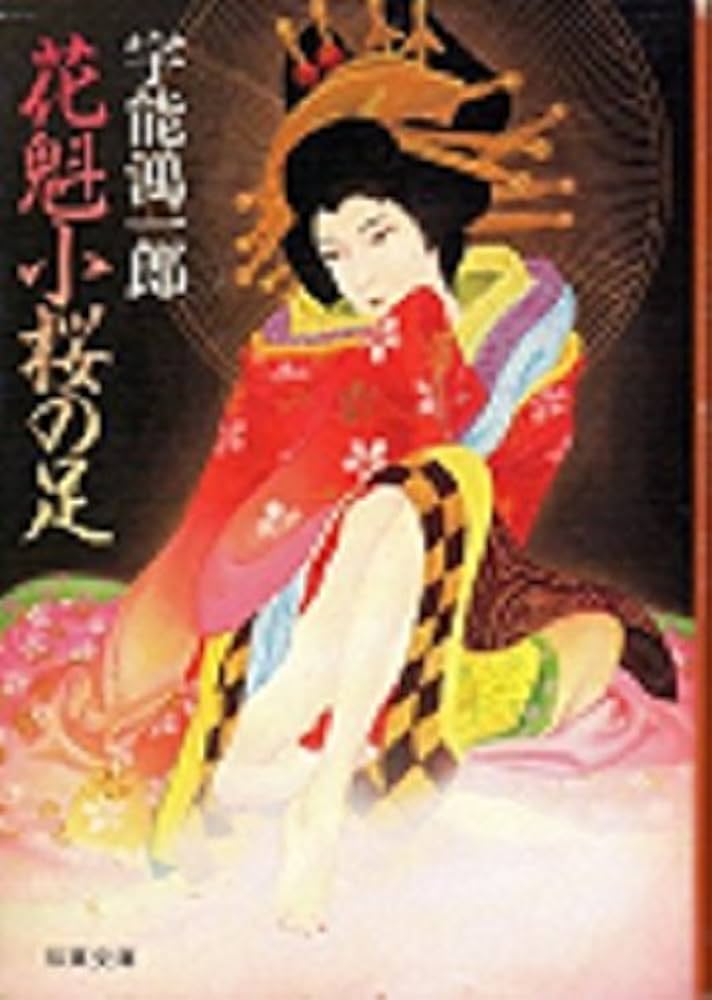
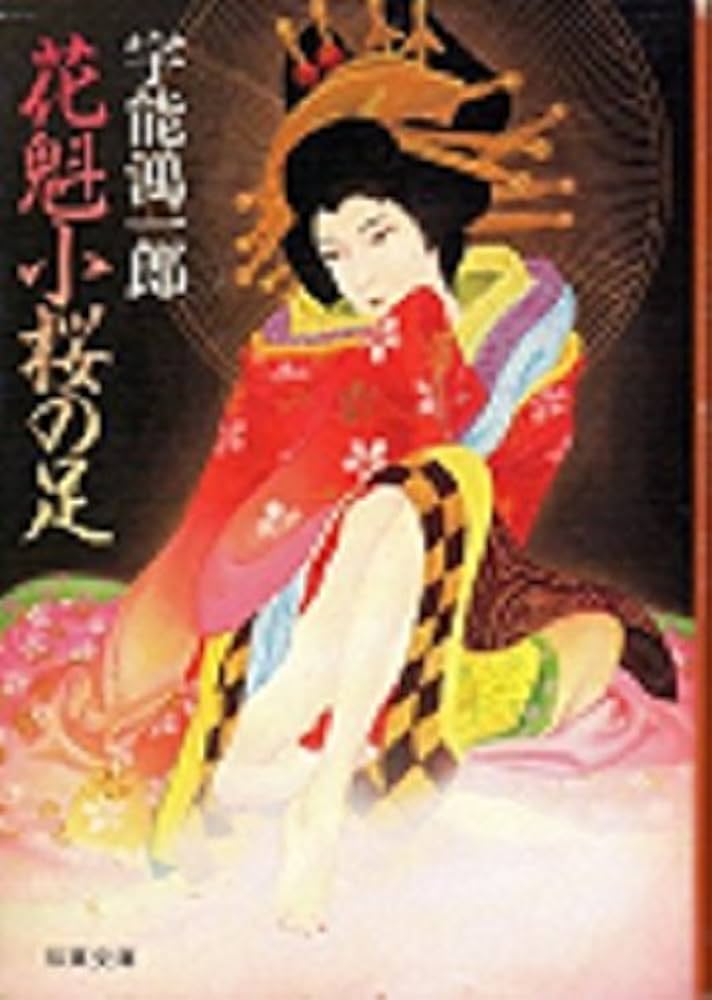
『花魁』は、江戸時代の遊郭を舞台に、花魁たちの生き様を鮮やかに描いた時代官能小説です。華やかな世界の裏側にある、女性たちの哀しみや強さ、そして情念が丁寧に描き出されています。
歴史的な考証に基づきながらも、宇能鴻一郎ならではの官能的な筆致で、遊郭の世界をリアルに再現しています。登場人物たちの息遣いまで聞こえてくるような臨場感あふれる描写は圧巻。歴史小説が好きな方や、女性たちのドラマティックな物語に惹かれる方におすすめの一冊です。



華やかな世界の裏側には、きっと色々なドラマがあるんだろうな。花魁たちの生き様に胸が熱くなりそうだよ。
15位『人妻』
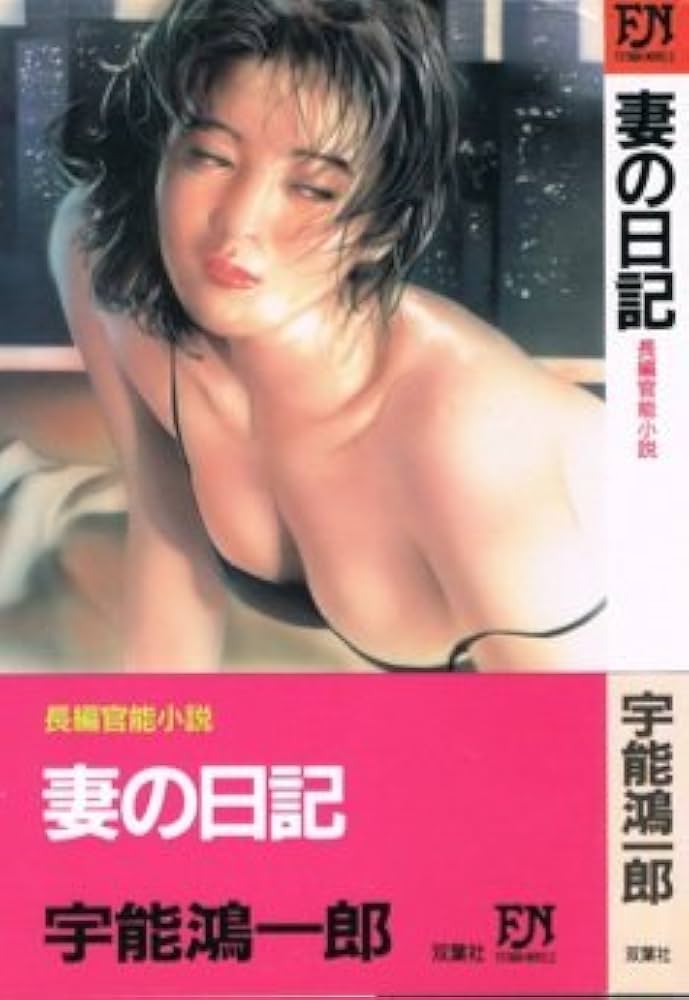
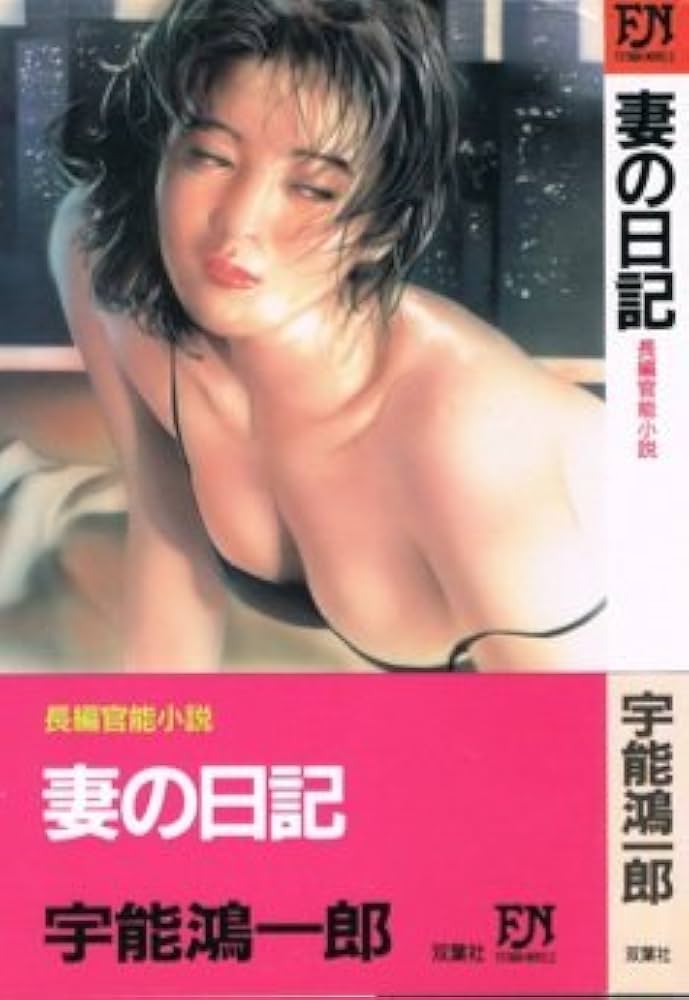
『人妻』は、宇能鴻一郎が数多く手がけたテーマの一つである「人妻」の官能を描いた作品群の代表格です。平凡な日常を送る主婦が、ふとしたきっかけで性の悦びに目覚めていく様を、得意の独白体で綴っていきます。
この作品の魅力は、背徳感と解放感が入り混じった、女性の複雑な心理描写にあります。読者は主人公の秘密を共有しているような、スリリングな感覚を味わうことができるでしょう。宇能鴻一郎の人間観察の鋭さが光る、官能小説の王道ともいえる一冊です。



日常の中の非日常って、なんだかドキドキするテーマだね。主人公の気持ちに寄り添って読んじゃいそうだよ。
16位『刺青綺譚』
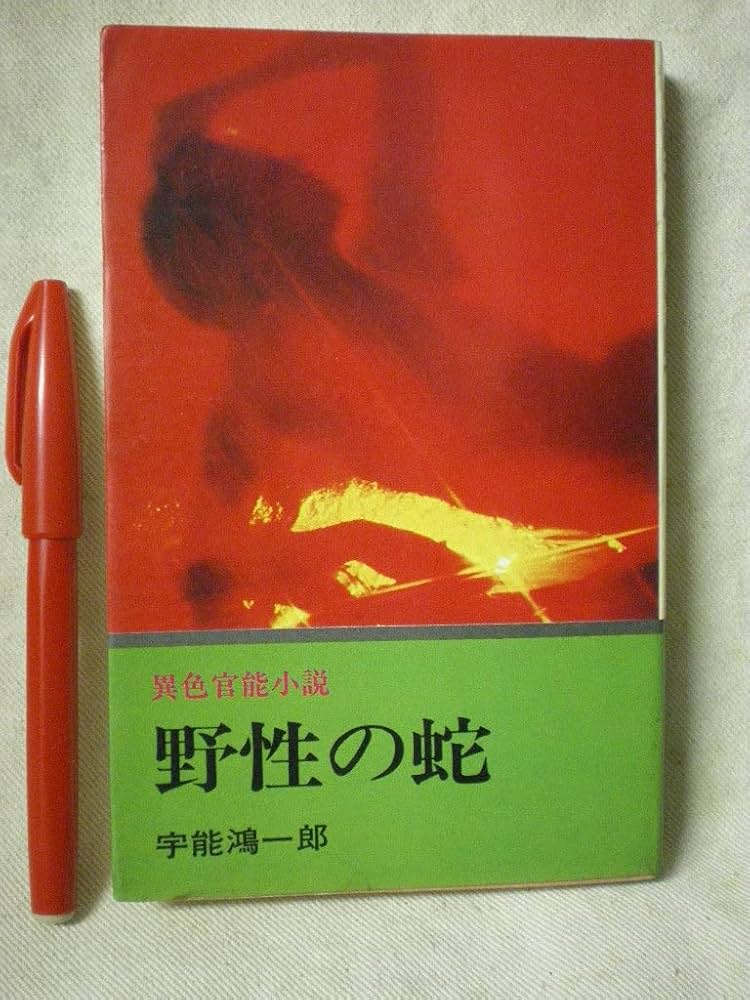
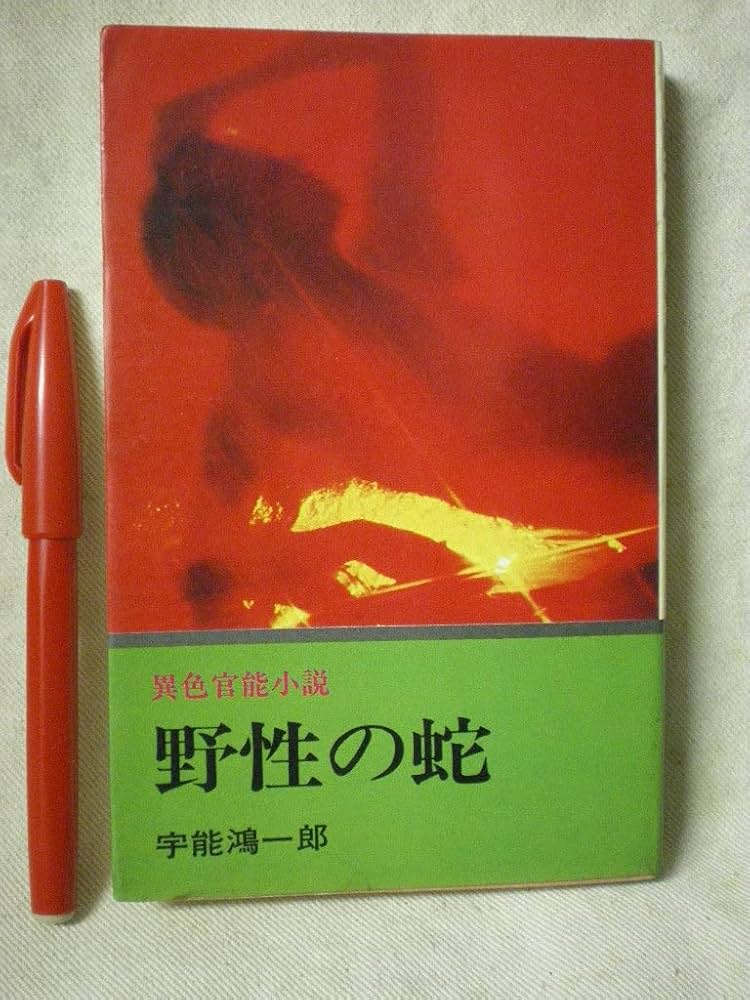
『刺青綺譚』は、谷崎潤一郎の『刺青』にオマージュを捧げつつ、宇能鴻一郎独自の世界観で描かれた作品です。刺青というモチーフを通して、人間の美意識や痛み、そして快楽が倒錯的に絡み合う様を描いています。
耽美的で妖しい雰囲気が全体を支配しており、読者を官能と幻想の迷宮へと誘います。宇能鴻一郎が持つ文学的な素養と、人間の深層心理を探求する姿勢が色濃く反映された一作。芸術性の高い、一味違った官能小説を読んでみたい方におすすめです。



刺青って、なんだか妖艶でミステリアスなイメージだよね。美しさと痛みが混じり合う世界、ちょっと怖いけど惹かれちゃうな。
17位『西洋淫具事典』
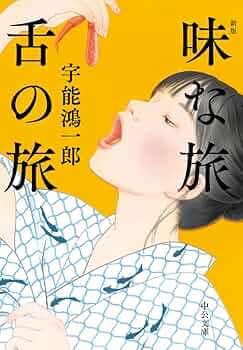
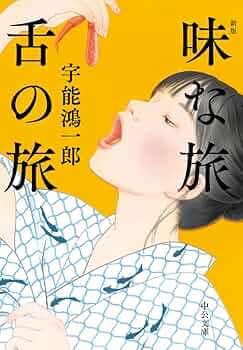
『西洋淫具事典』は、小説ではなく、古今東西の様々な「淫具」について解説したユニークな事典形式の読み物です。宇能鴻一郎の飽くなき探究心と、博覧強記ぶりがうかがえる一冊となっています。
単にモノを紹介するだけでなく、それらが人間の歴史や文化の中でどのような役割を果たしてきたのかを、独自の視点で考察しています。知的好奇心を刺激される、大人のための教養書とも言えるでしょう。宇能鴻一郎の引き出しの多さに、改めて驚かされること間違いなしです。



事典まで作っちゃうなんて、宇能先生の探究心はすごいね!ちょっとマニアックだけど、読んでみたくなっちゃうよ。
18位『踊り子殺人事件』
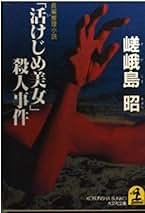
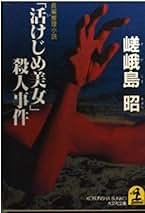
『踊り子殺人事件』は、宇能鴻一郎が「嵯峨島昭(さがしま あきら)」というペンネームで発表したミステリー小説です。 官能小説家として知られる宇能の、もう一つの顔である推理作家としての一面が楽しめる作品です。
ダンディな酒島警視と人妻探偵の鮎子さんが活躍する、グルメ要素も盛り込まれたライトな作風が特徴です。 軽妙なキャラクターの掛け合いと、テンポの良いストーリー展開で、ミステリー初心者でも気軽に楽しめます。官能小説とは一味違った、エンターテイメント作家としての宇能鴻一郎の才能を発見できる一冊です。



ミステリーも書いていたなんて知らなかったよ!人妻探偵が活躍するグルメミステリー、面白くないわけがないよね。
19位『血の聖壇』
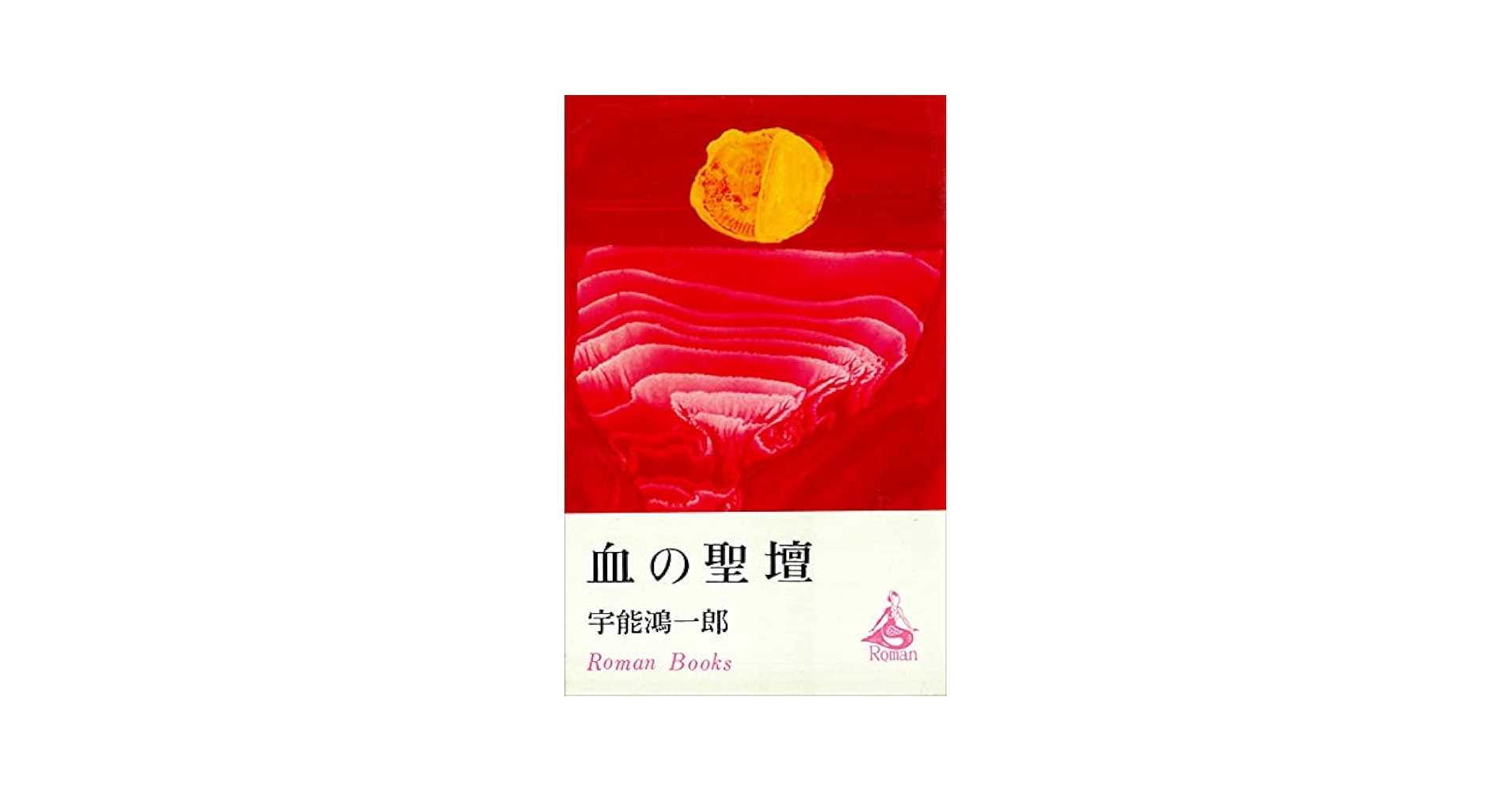
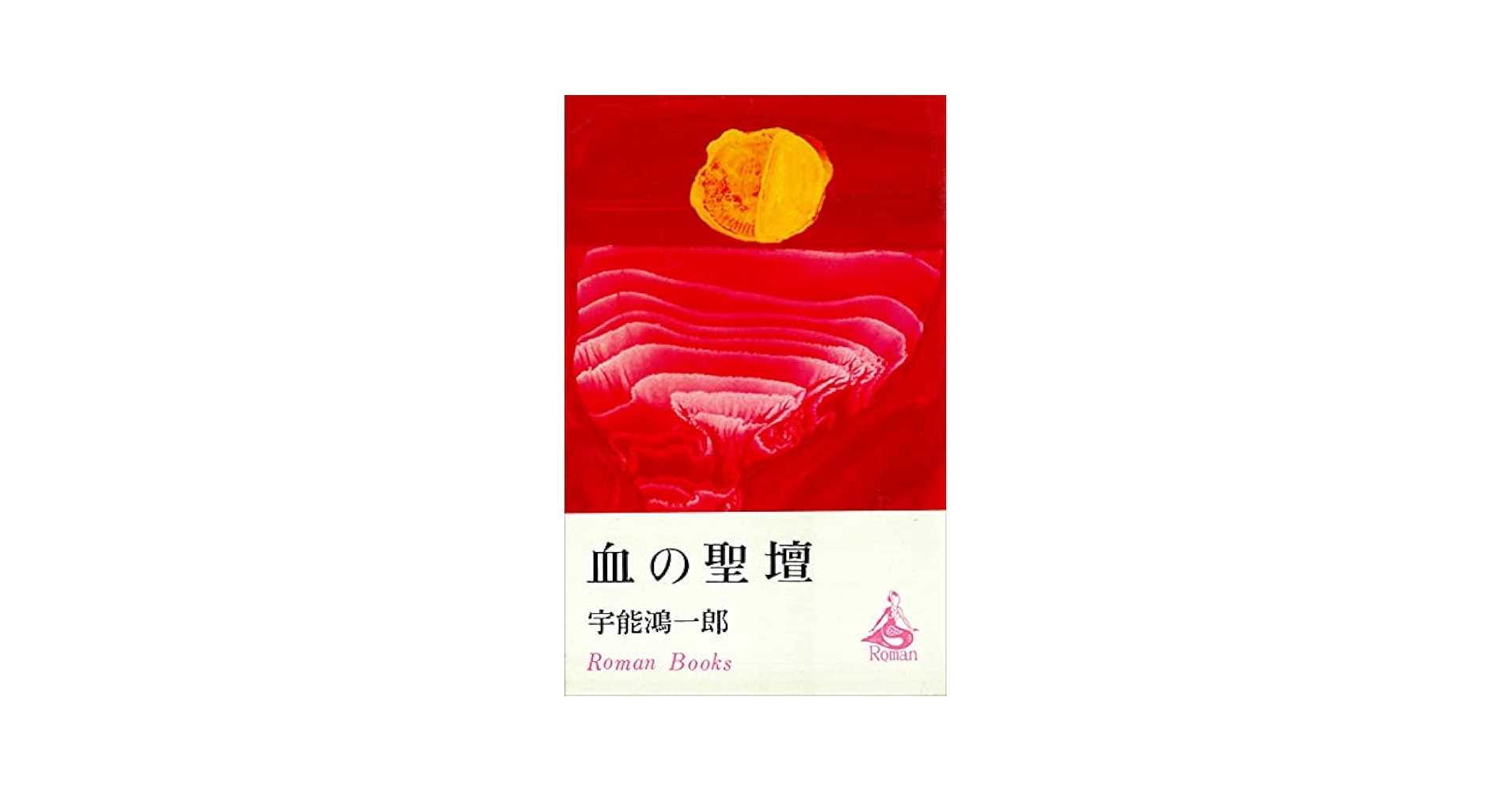
『血の聖壇』は、宇能鴻一郎作品の中でも特にハードで過激な描写が多いことで知られる一作です。人間の狂気や残虐性を、一切の妥協なく描き切っています。
この作品は、読者の倫理観や常識を根底から揺さぶるほどの強烈なインパクトを持っています。美しい文体で綴られる地獄絵図は、恐怖と同時にある種の魅力を放っており、一度読んだら忘れられない体験となるでしょう。刺激に耐性のある、コアな宇能ファン向けの作品と言えます。



本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。人間の狂気を描くという点において、この作品の右に出るものはないだろう。
20位『光りの飢え』
『光りの飢え』は、宇能鴻一郎が東京大学大学院在学中に発表し、芥川賞候補となった記念碑的な短編です。
若き日の宇能が持つ、有り余るほどのエネルギーと、社会の底辺で生きる人々への鋭い眼差しが詰まっています。選評では「エネルギーの過剰からの失敗」も指摘されましたが、それこそが新人作家の魅力であるとも言えるでしょう。 官能小説家になる前の、純文学作家としての宇能鴻一郎の原点に触れられる貴重な一作です。



デビュー前の作品って、作家さんの原石みたいでワクワクするよね。ここからあの『鯨神』が生まれたんだなあ。
まとめ:宇能鴻一郎の多岐にわたる作品世界を堪能しよう
ここまで、宇能鴻一郎のおすすめ小説をランキング形式でご紹介してきました。芥川賞を受賞した純文学の傑作『鯨神』から、一世を風靡した官能小説『むちむちぷりん』、さらにはグルメエッセイやミステリーまで、そのジャンルは驚くほど多岐にわたります。
どの作品にも共通しているのは、人間の本質に迫ろうとする鋭い視点と、それを支える卓越した文章力です。純文学作家としての素養があったからこそ、彼の官能小説は単なる刺激的な読み物にとどまらない、文学的な深みを持つことができました。ぜひ今回のランキングを参考に、あなたが最も惹かれる一冊から、宇能鴻一郎の奥深い作品世界に足を踏み入れてみてください。


