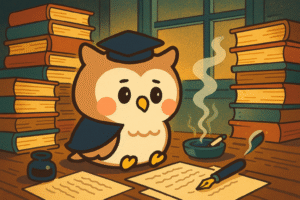あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】長部日出雄のおすすめ小説ランキングTOP15

はじめに:多彩な作品世界が魅力の作家・長部日出雄とは?
長部日出雄(おさべ ひでお)は、1934年に青森県弘前市で生まれた小説家・評論家です。 早稲田大学を中退後、新聞記者や映画評論家として活動し、その後小説家に転身しました。 2018年に84歳で亡くなるまで、数多くの作品を世に送り出しています。
長部日出雄の作品世界は、故郷・津軽を舞台にした物語が大きな柱となっています。 また、太宰治や棟方志功といった同郷の偉人たちの評伝も手掛けており、その探究心は歴史、宗教、芸術、映画と幅広いジャンルに及びました。 1973年には『津軽世去れ節』などで直木賞を受賞したほか、芸術選奨や大佛次郎賞など数々の文学賞に輝いています。
長部日出雄のおすすめ作品ランキングTOP15
ここからは、長部日出雄の数ある名作の中から、特におすすめしたい作品をランキング形式で15作ご紹介します。
直木賞受賞作をはじめ、歴史上の人物を描いた評伝小説、深い思索に満ちた評論まで、彼の多彩な才能が光る作品が揃いました。この記事を読めば、きっとあなたの知的好奇心を刺激する一冊が見つかるはずです。
1位『津軽世去れ節』
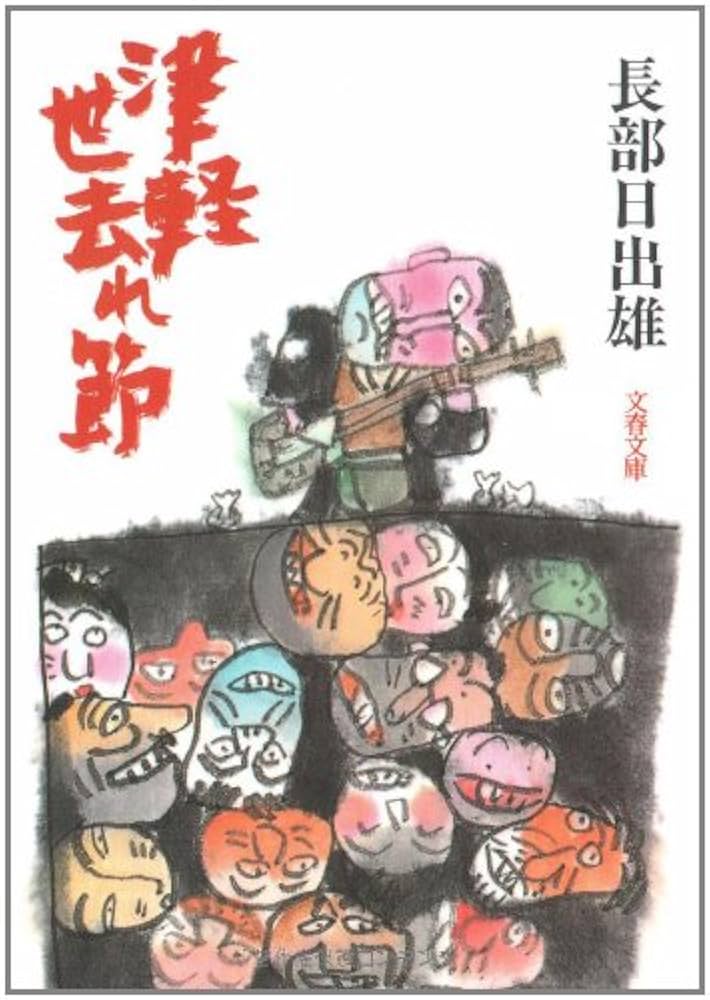
長部日出雄の代表作であり、1973年に第69回直木賞を受賞した作品です。 本作は津軽を舞台にした6つの短編からなる作品集で、長部日出雄の原点ともいえる一冊です。
表題作の『津軽世去れ節』では、津軽三味線の大成者である実在の人物、黒川桃太郎の破天荒な生涯が描かれています。 明治から昭和にかけて、酒と賭博に溺れながらも、その三味線の音で津軽の民衆を熱狂させた天才の生き様が、津軽の厳しい風土とともに鮮烈に描き出されています。
 ふくちい
ふくちい津軽三味線の世界って、こんなに激しくてロックだったんだ! わたし、歴史に埋もれた天才たちの物語に弱いんだよね。
2位『桜桃とキリスト もう一つの太宰治伝』
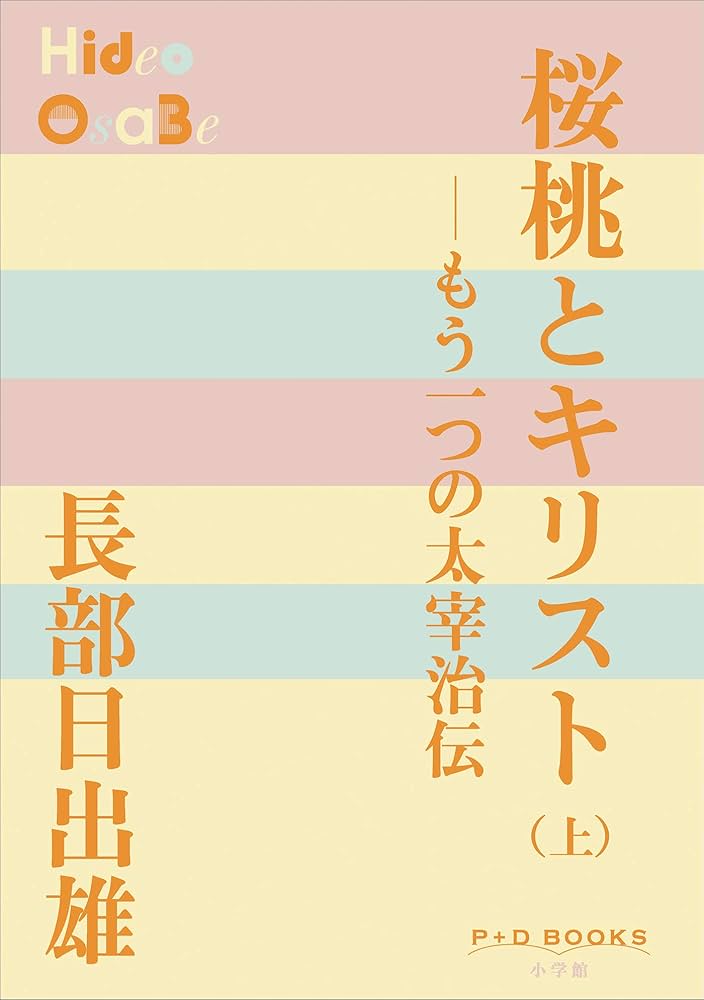
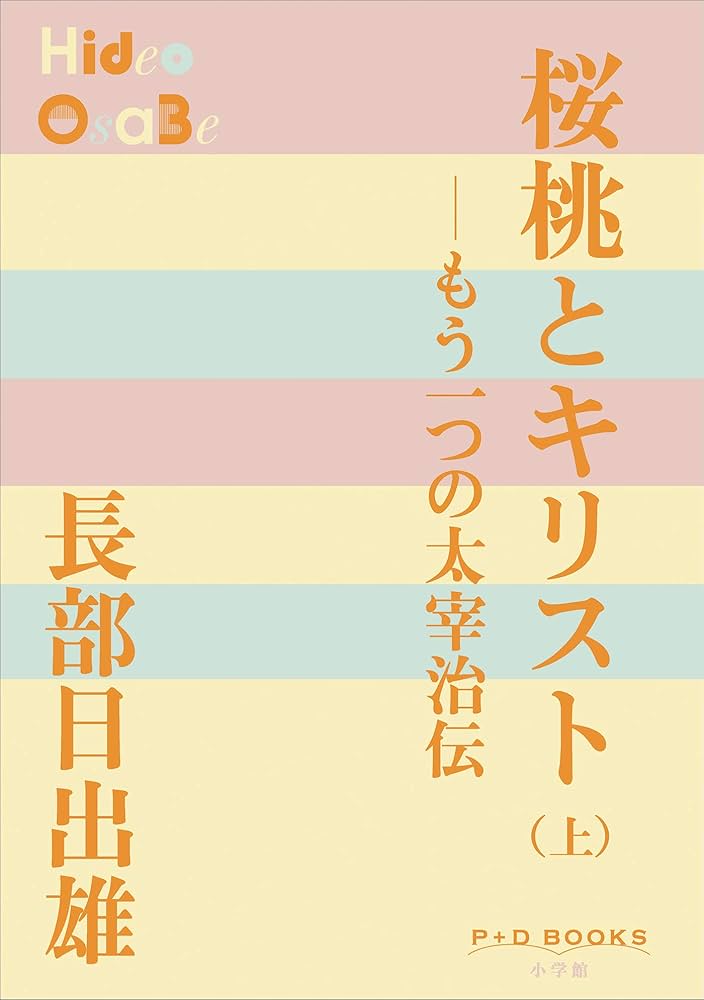
同郷の偉人・太宰治の後半生を描いた、長部日出雄渾身の長編評伝です。本作は第29回大佛次郎賞と第15回和辻哲郎文化賞をダブル受賞し、高く評価されました。
妻・美知子との結婚から玉川上水での衝撃的な最期まで、太宰治の作家としての絶頂期とその苦悩を克明に描いています。 これまでの太宰治像を覆すような、妻が創作に与えた影響やキリスト教との関わりなど、著者ならではの新しい視点が盛り込まれているのが特徴です。



太宰治のイメージがガラッと変わるかもしれない一冊だよ。同じ故郷の作家だからこそ描ける、愛情と深みがすごいんだ。
3位『鬼が来た 棟方志功伝』
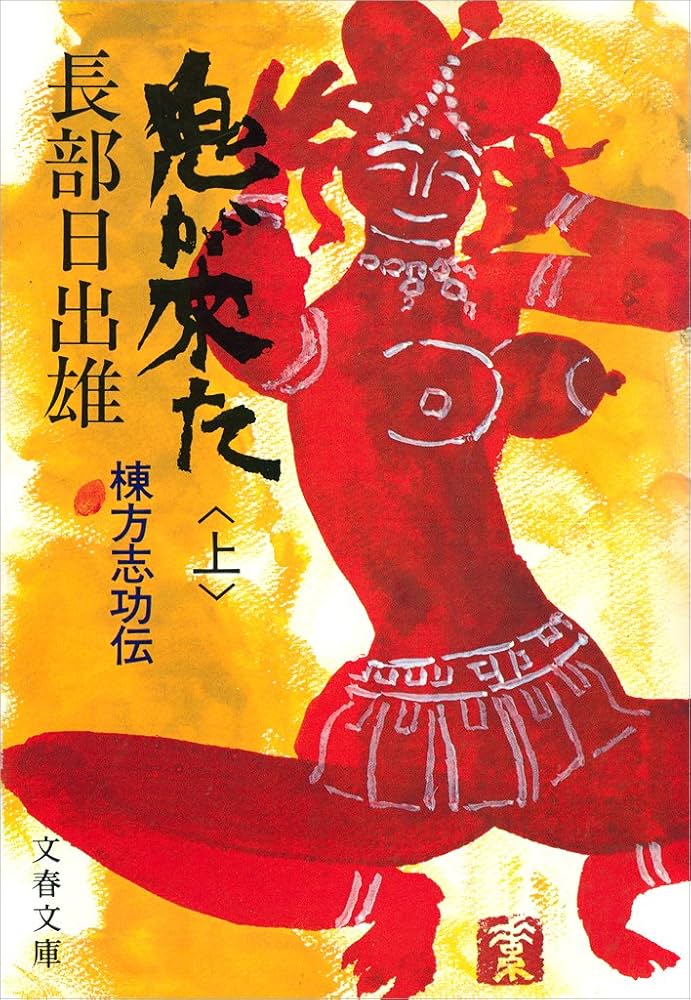
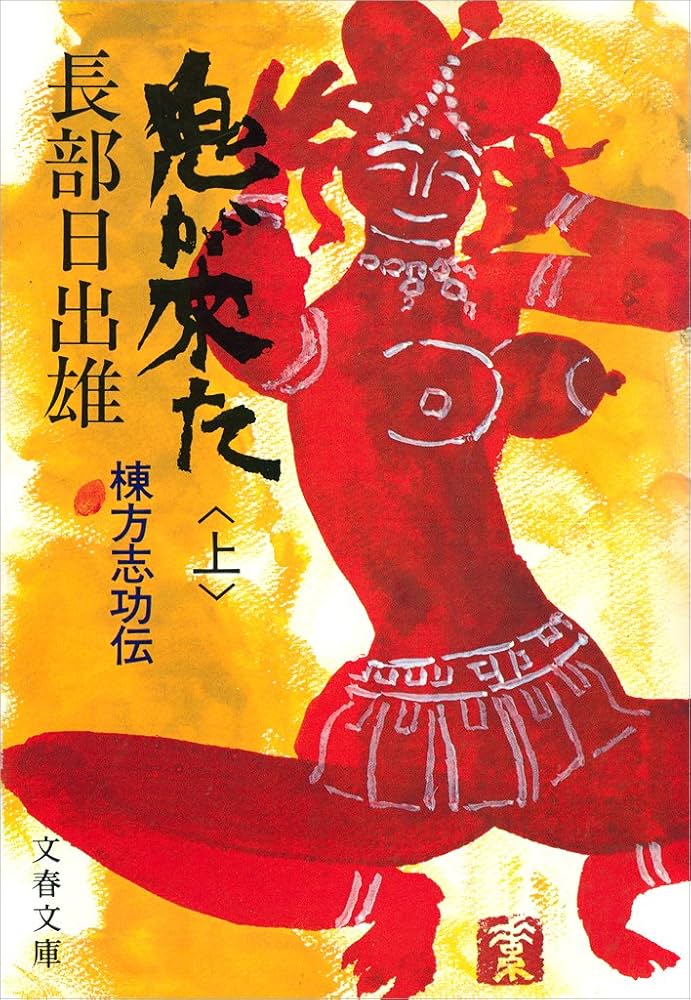
「わだばゴッホになる!」と叫んだ世界的板画家・棟方志功の強烈な生涯を、同じ青森県出身の長部日出雄が描いた傑作評伝です。 本作は1980年に芸術選奨文部大臣賞を受賞しました。
青森の貧しい鍛冶屋の家に生まれ、極度の近視を抱えながらも、いかにして世界的なアーティストへと駆け上がっていったのか。 その創造の源泉にある津軽の風土、そして柳宗悦や太宰治といった人々との交流と葛藤を、膨大な取材をもとに生き生きと描き出しています。



棟方志功のエネルギーが爆発してる! 同じ青森出身の太宰治とのエピソードも面白くて、一気に読んじゃったよ。
4位『見知らぬ戦場』
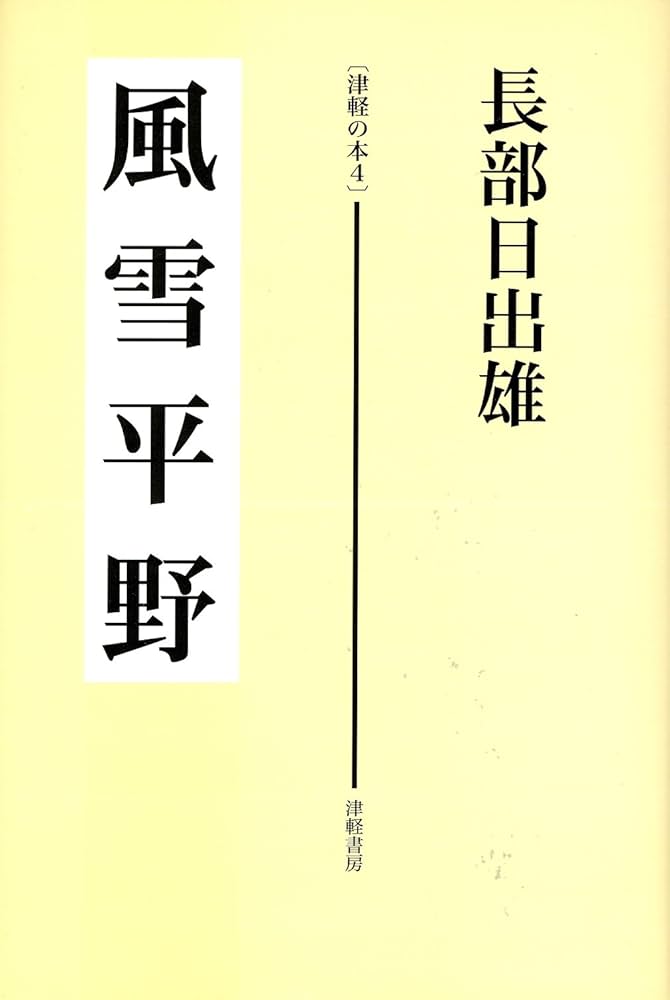
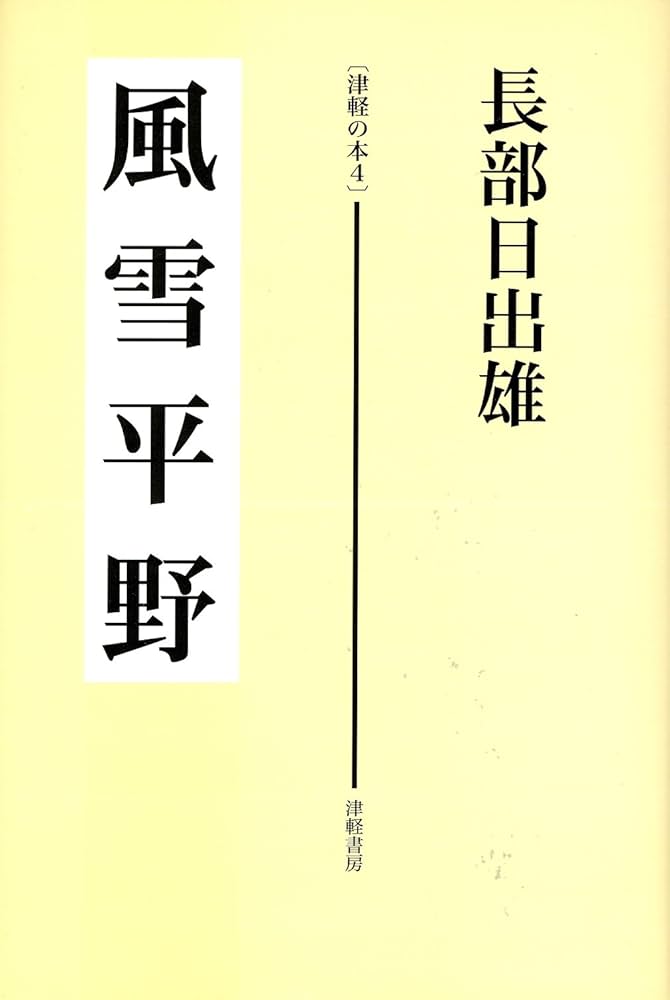
1987年に第6回新田次郎文学賞を受賞した、戦争文学の傑作です。 太平洋戦争末期のフィリピン・ルソン島を舞台に、日本兵と現地ゲリラの壮絶な戦いを描いています。
この作品の大きな特徴は、敵である日本兵と、故郷を守るために戦う山岳民族ゲリラ、その両者の視点から戦争の悲惨さを描き出している点です。 実は作者自身も兄をこの北ルソンの戦いで亡くしており、その個人的な体験と綿密な取材が、物語に圧倒的なリアリティと深みを与えています。



戦争を敵と味方の両側から描くなんて…。兄を亡くした作者の想いが詰まっていて、胸が苦しくなるよ。
5位『「古事記」の真実』
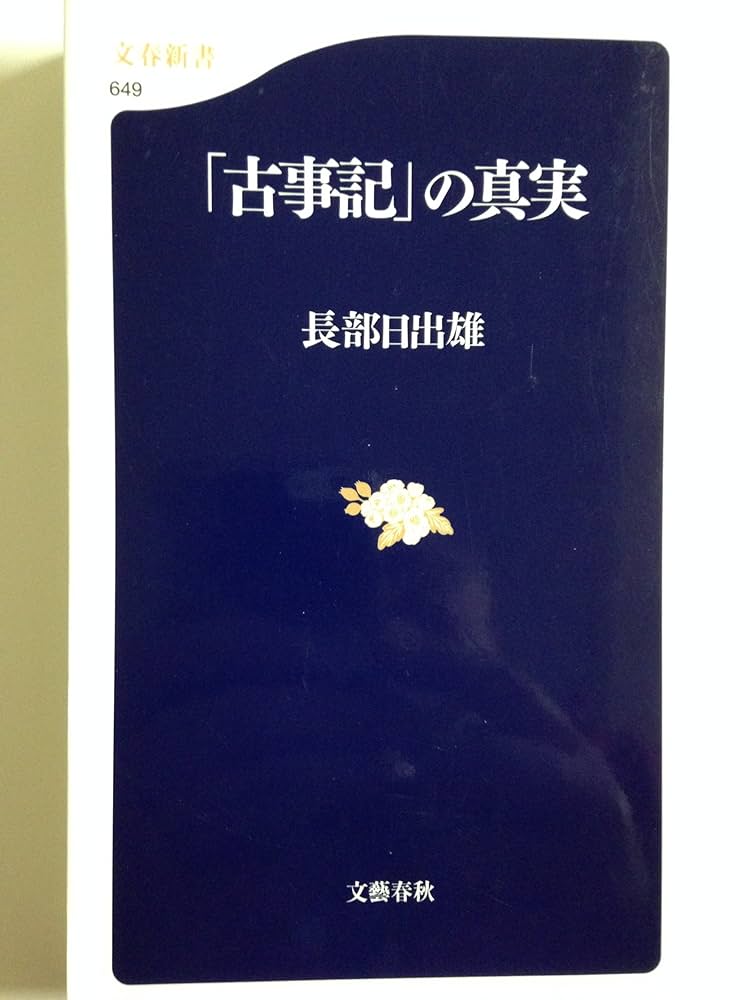
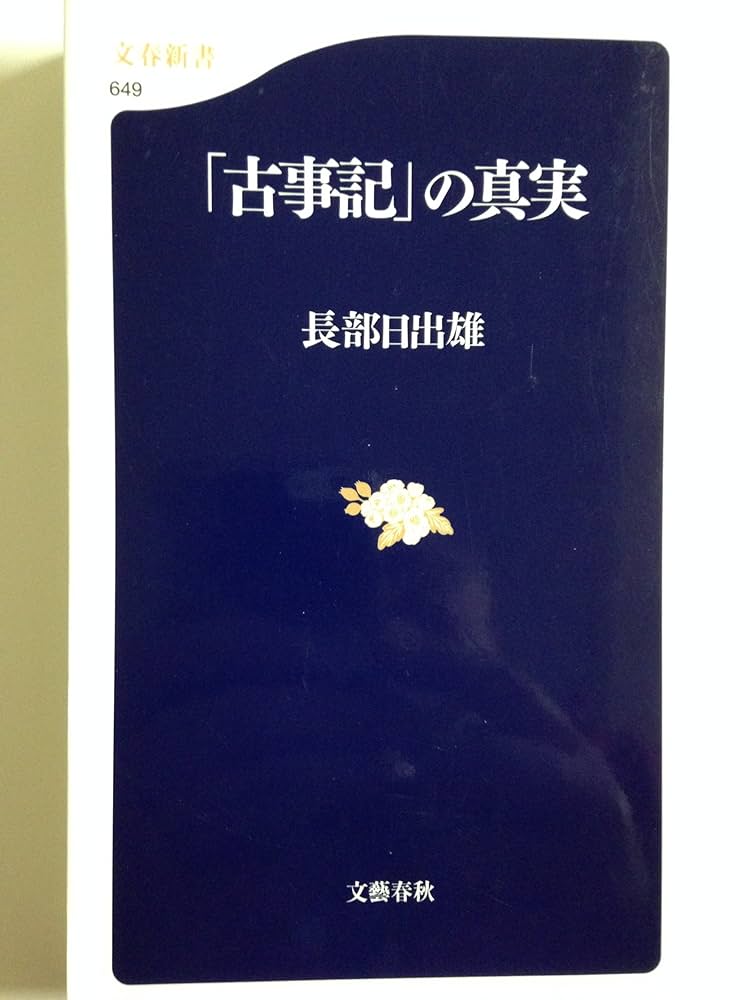
日本最古の歴史書『古事記』に秘められた謎を、作家・長部日出雄が独自の視点でスリリングに解き明かす一冊です。 難解なイメージのある『古事記』ですが、本書を読めば、そこに描かれた神々の人間くさい物語に引き込まれるはずです。
本書では、「『古事記』を口述した稗田阿礼は女性だった」「『古事記』はもともと演劇の台本だった」など、常識を覆すような大胆な仮説が次々と提示されます。 著者が自身の足で神話の舞台を訪ね歩き、作家ならではの想像力で古代日本の実像に迫っていく様は、まるで歴史ミステリーを読んでいるかのような興奮を覚えます。



古事記ってこんなに面白かったんだ! 稗田阿礼が女性だったかも、なんて考えるとワクワクするよね。
6位『辻音楽師の唄 もう一つの太宰治伝』
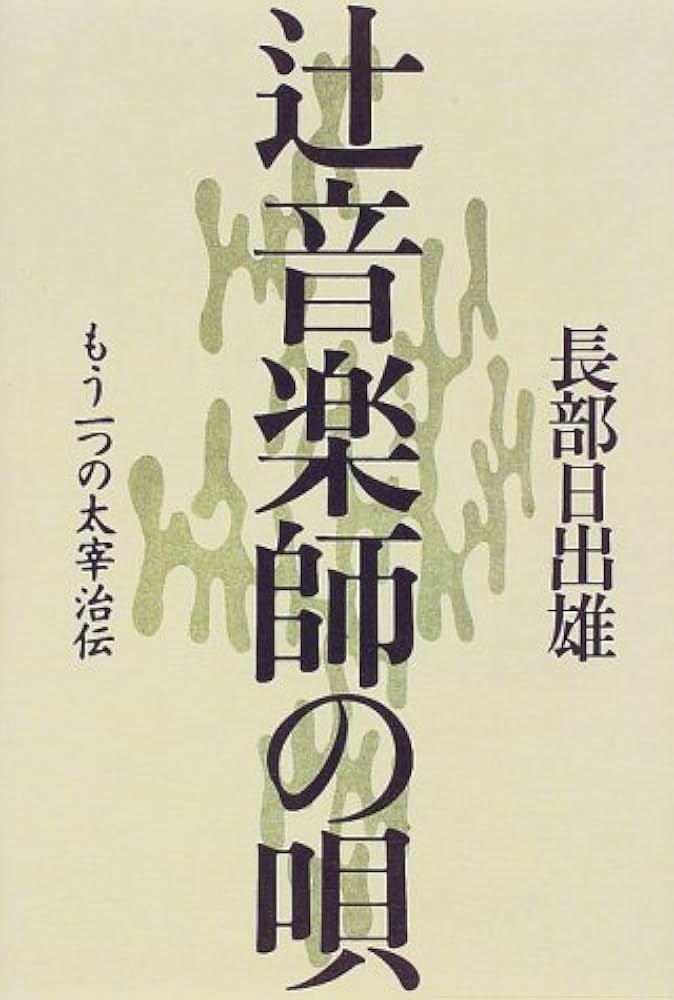
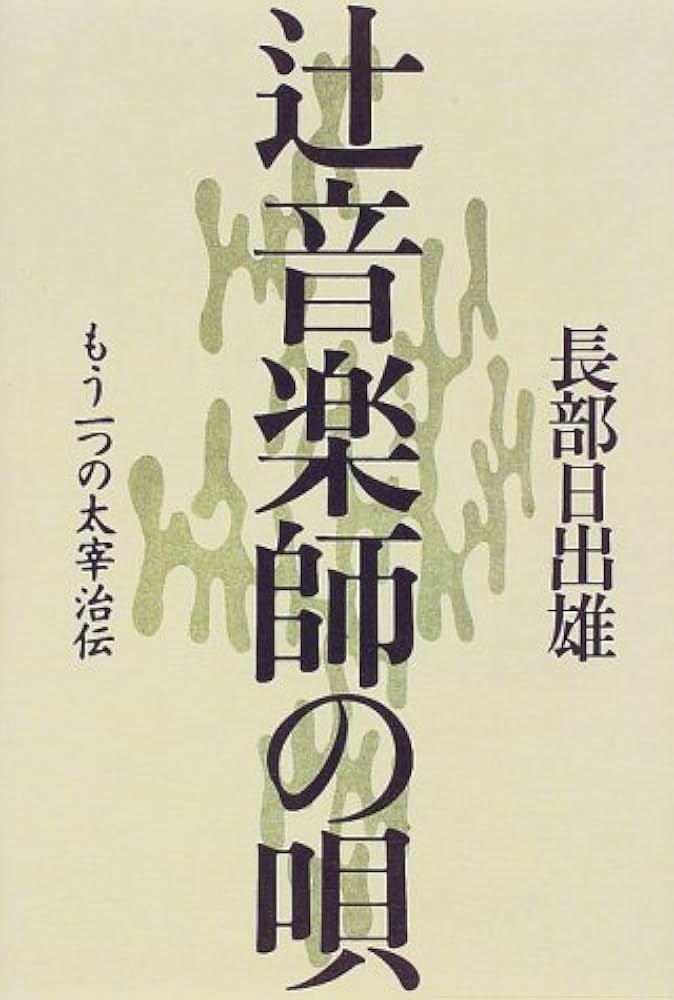
『桜桃とキリスト』と対をなす、もう一つの太宰治伝です。こちらは太宰の幼年期から精神病院に入るまでの前半生に焦点を当てています。
裕福な家に生まれながらも感じていた強烈な孤独感や、実家への憎しみ、そして彼を心中未遂事件へと駆り立てたものは何だったのか。 同じ津軽出身の著者だからこそ描き得た、人間・津島修治(太宰の本名)の繊細な心のひだを、深い愛情と理解をもって解き明かしていきます。



太宰治の前半生を知るならこの一冊だね。どうして彼があんな作品を書くようになったのか、そのルーツがわかる気がするよ。
7位『二十世紀を見抜いた男 マックス・ヴェーバー物語』
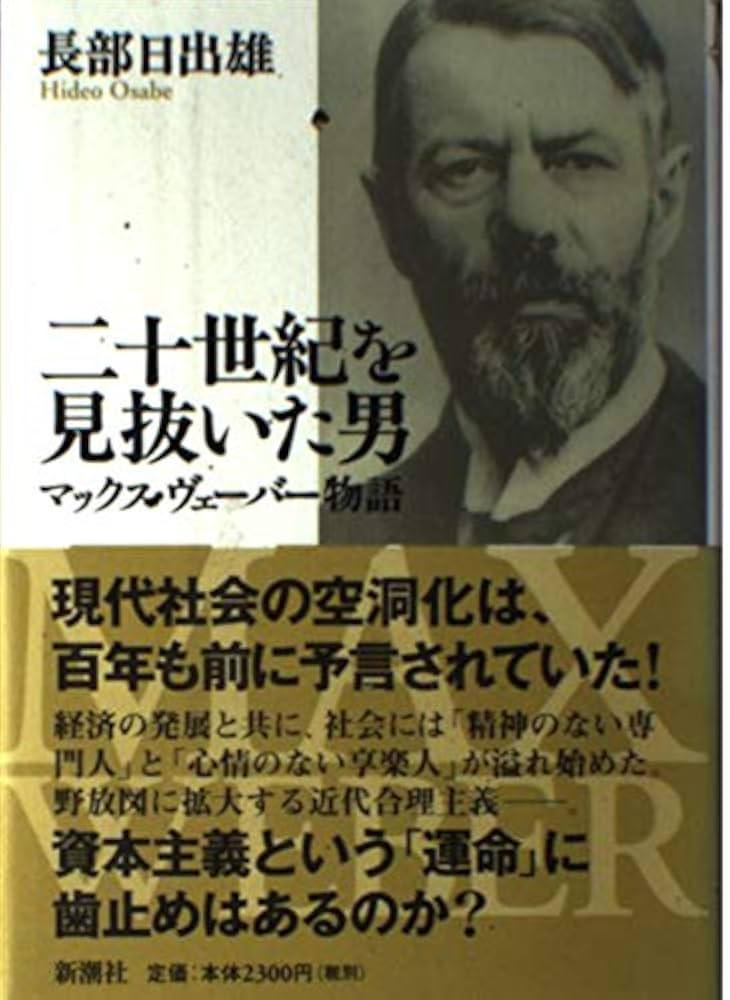
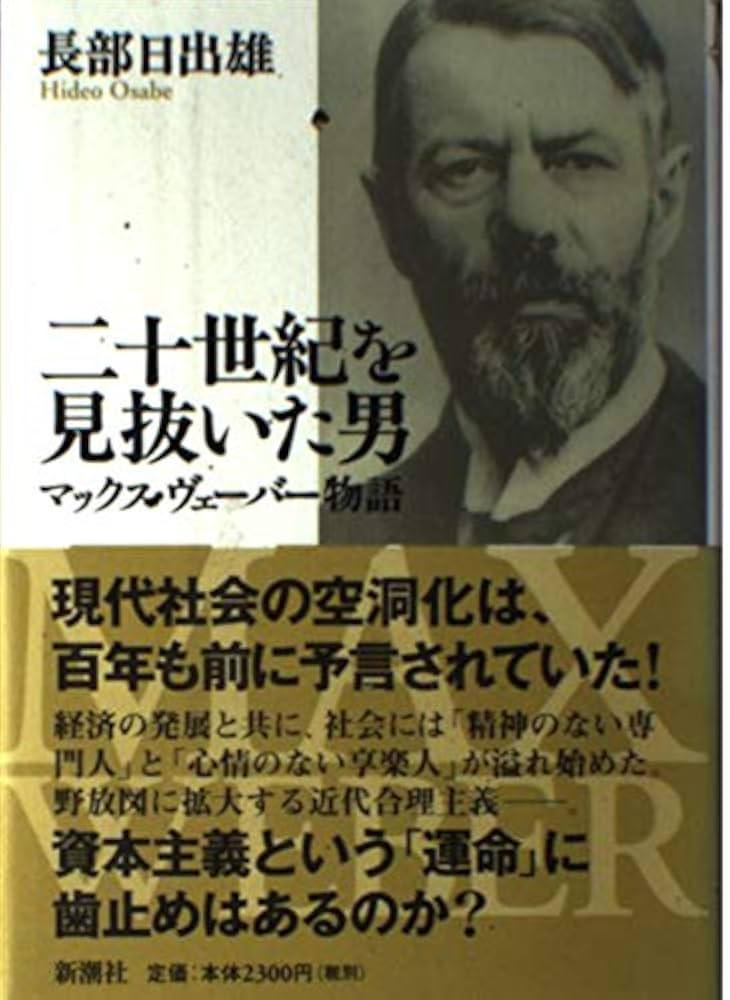
『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』で知られるドイツの社会学者、マックス・ヴェーバー。 彼の生涯と思想に、作家である長部日出雄が迫った一冊です。
本書は、ヴェーバーが100年以上も前に、現代社会の姿をいかにして見抜いていたかを解き明かします。 経済が発展した果てに「精神のない専門人、心情のない享楽人」がはびこる――。 ヴェーバーの鋭い指摘は、まさに現代を生きる私たちへの警告のようです。 専門書とは一味違う、物語として読めるヴェーバー入門としてもおすすめです。



100年以上も前に現代を見抜いていたなんて、ヴェーバーってすごい人だね! ちょっと難しいテーマだけど、物語だから読みやすいよ。
8位『まだ見ぬ故郷 高山右近の生涯』
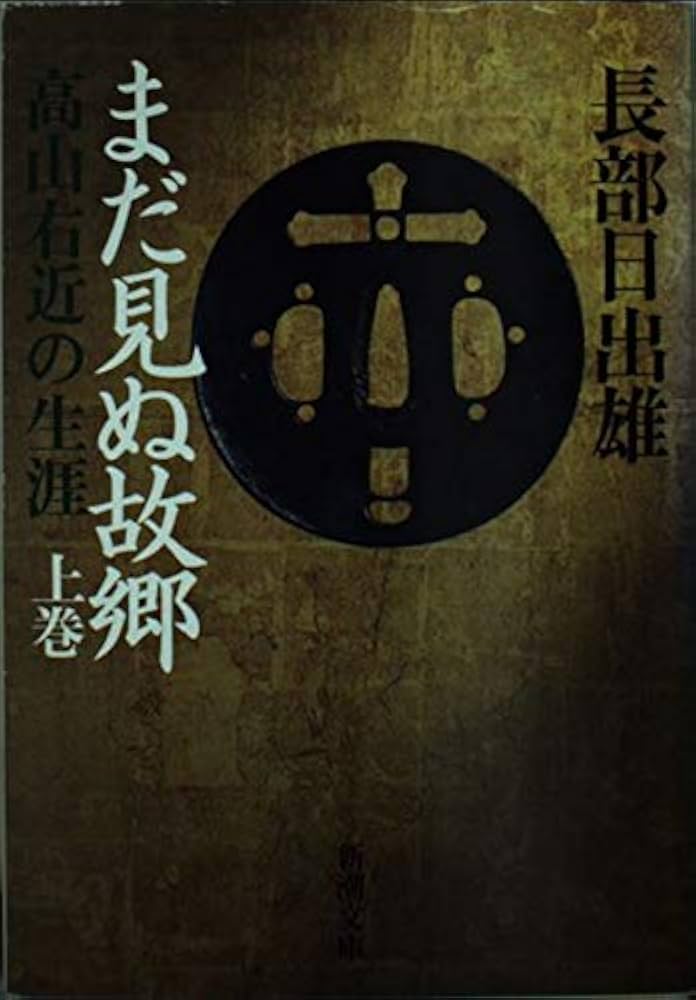
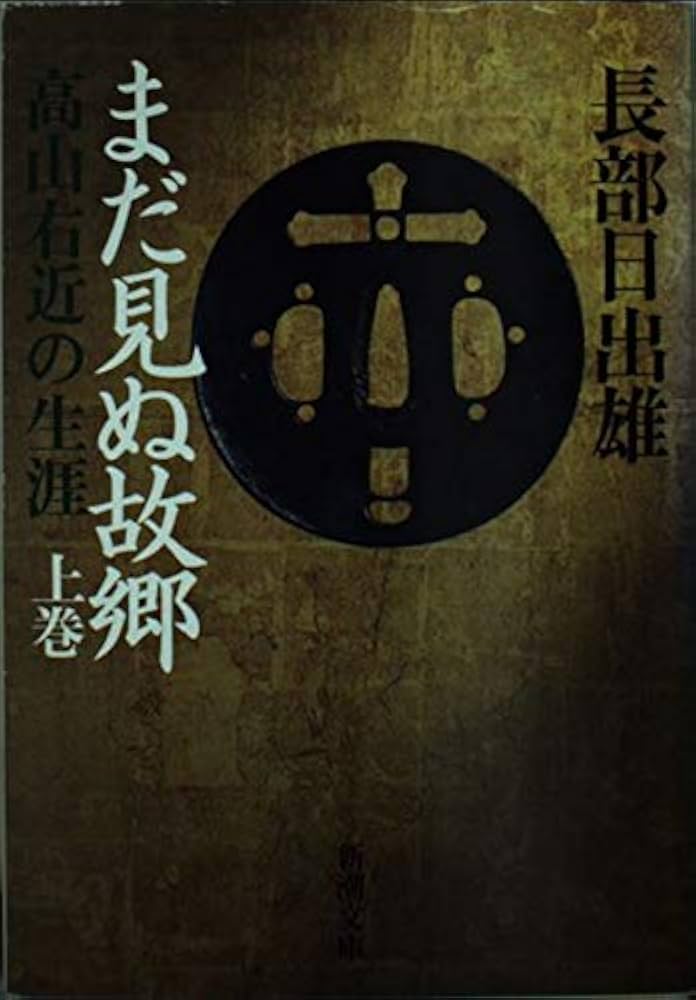
戦国時代に生きたキリシタン大名・高山右近の波乱に満ちた生涯を描く歴史大作です。織田信長や豊臣秀吉といった天下人たちに仕えながらも、自らの信仰を最後まで貫き通した右近の生き様が描かれます。
武将としての才覚と、厚い信仰心との間で葛藤し、ついには全てを捨てて国外追放の道を選ぶ高山右近。彼の清廉な人柄とゆるぎない信念は、終焉の地マニラでも多くの人々の心を打ちました。 権力や富よりも大切なものとは何かを、静かに、しかし力強く問いかけてくる作品です。



自分の信じるもののために全てを捨てるなんて…。高山右近の生き様、かっこよすぎるよ。涙なしには読めないかも。
9位『密使 支倉常長』
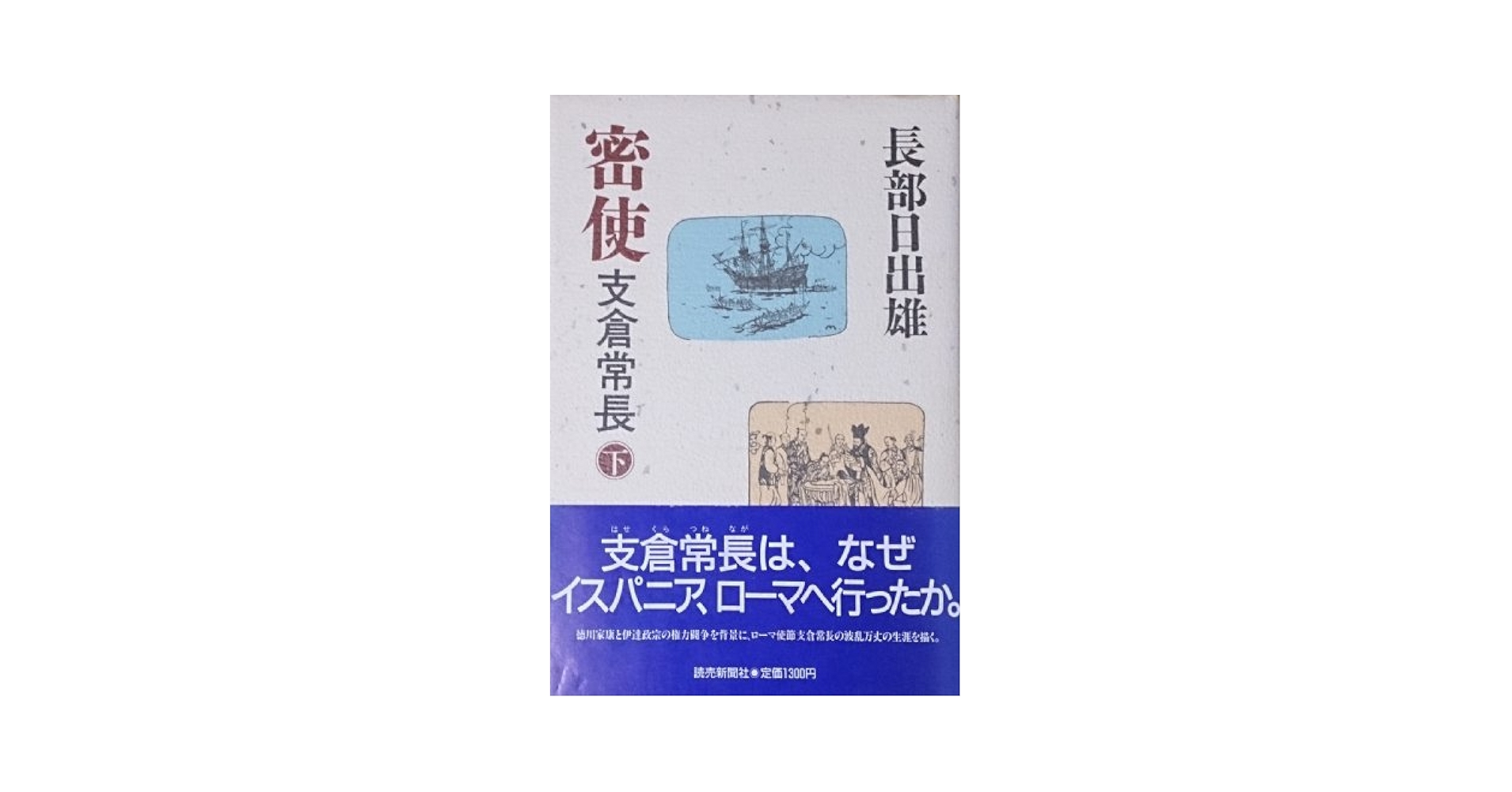
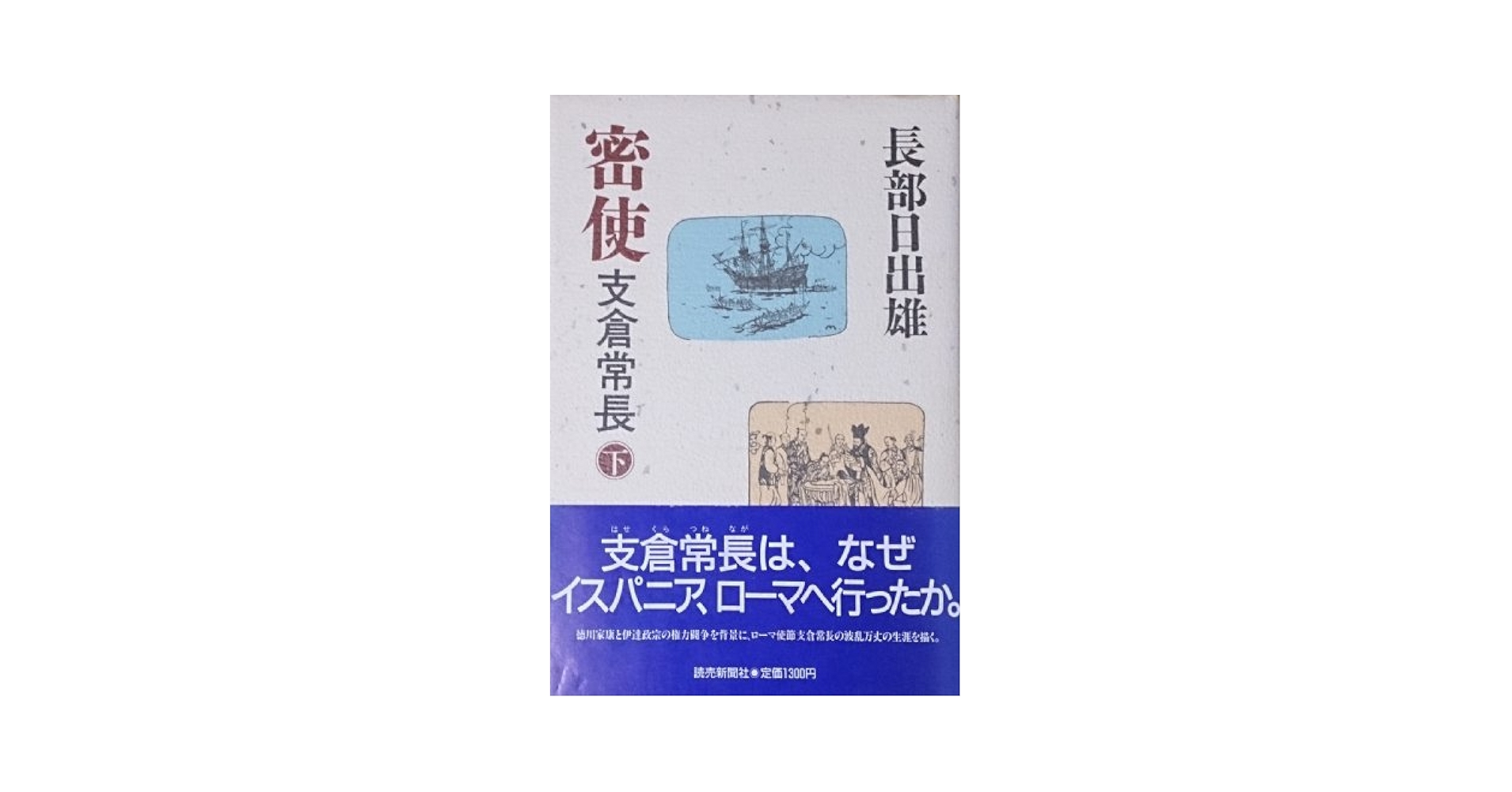
慶長遣欧使節団を率いてヨーロッパに渡ったことで知られる武将・支倉常長。 彼が主君・伊達政宗から託された真の使命とは何だったのか。著者独自の大胆な解釈で描く、壮大な歴史ロマンです。
豊臣家が滅び、徳川の世が始まろうとする中、幕府から危険視される伊達政宗。 彼は家を取り潰されぬための起死回生の一手として、支倉常長を密使としてヨーロッパへ派遣します。 表向きは通商交渉、しかしその裏には驚くべき密命が隠されていました。歴史の裏側に隠された壮大なドラマに、知的好奇心が刺激されること間違いなしです。



ただの貿易交渉じゃなかったんだ! 政宗の密命を帯びて世界を旅するなんて、スケールが大きくてワクワクするね!
10位『津軽風雲録』
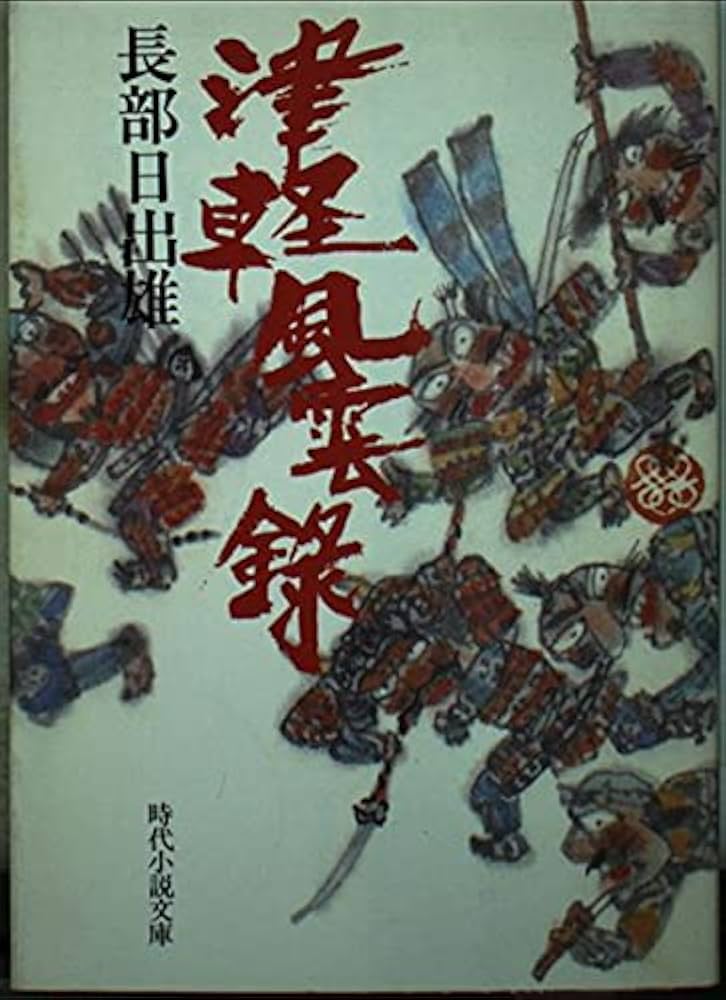
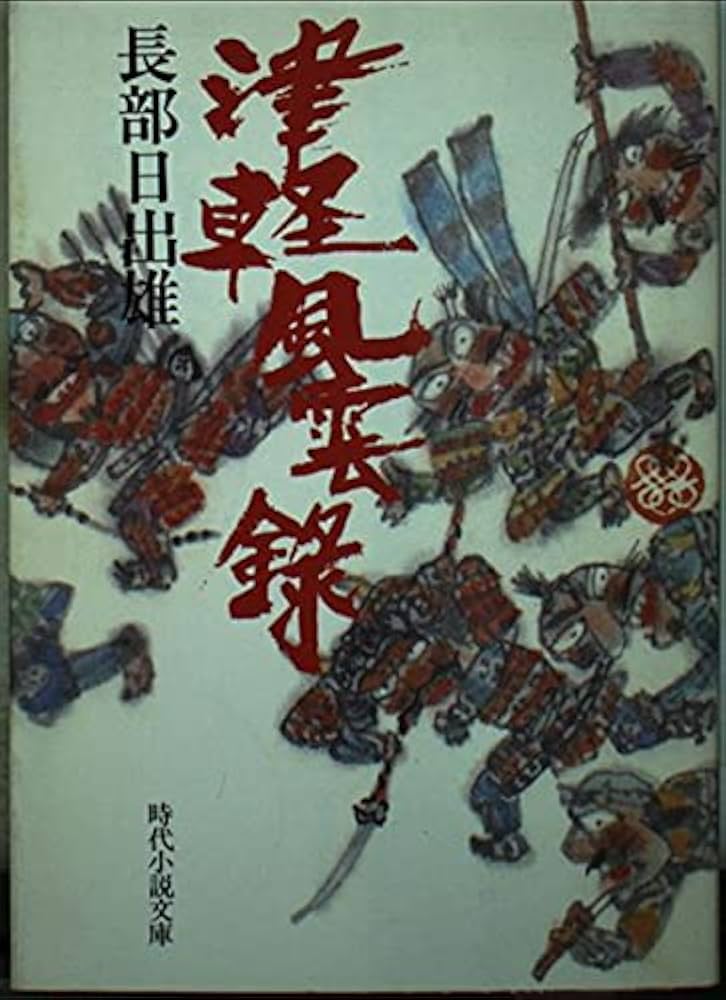
戦国時代、下剋上によって津軽を統一した武将・津軽為信の活躍を描いた痛快歴史物語です。 著者の故郷である津軽を舞台に、野望に燃える男たちのドラマが繰り広げられます。
物語の主人公は、一代で津軽の領主となった津軽為信。 彼は百姓や野盗といったアウトローたちを巧みに手なずけ、奇想天外な謀略と奇襲を駆使して敵対勢力を打ち破っていきます。 登場人物たちが交わす活気ある津軽弁も本作の魅力の一つで、物語に独特の躍動感を与えています。



津軽弁で繰り広げられる戦国絵巻、すごく面白そう! ならず者たちを率いて天下を狙うなんて、まさにヒーローだね。
11位『「阿修羅像」の真実』
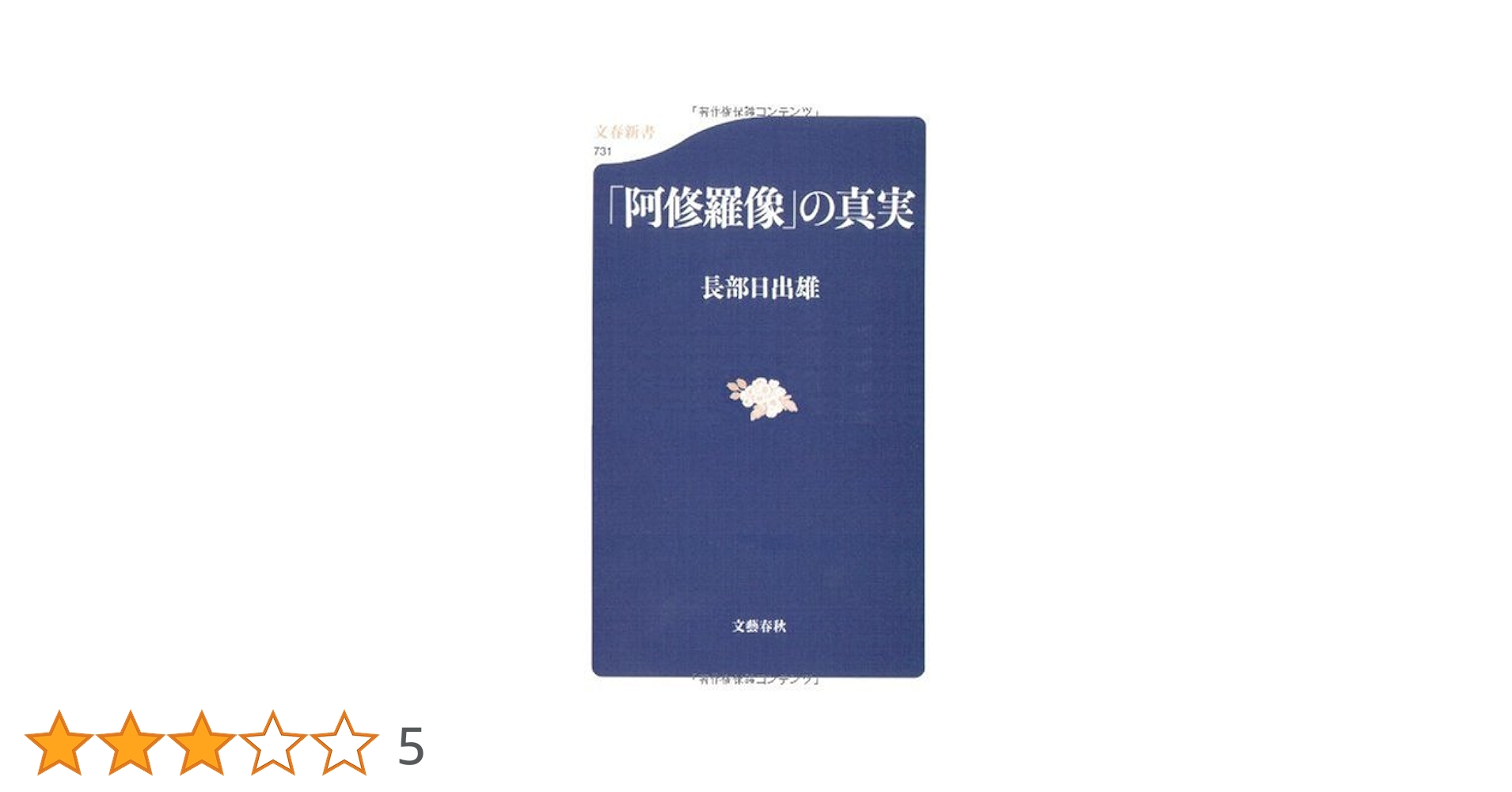
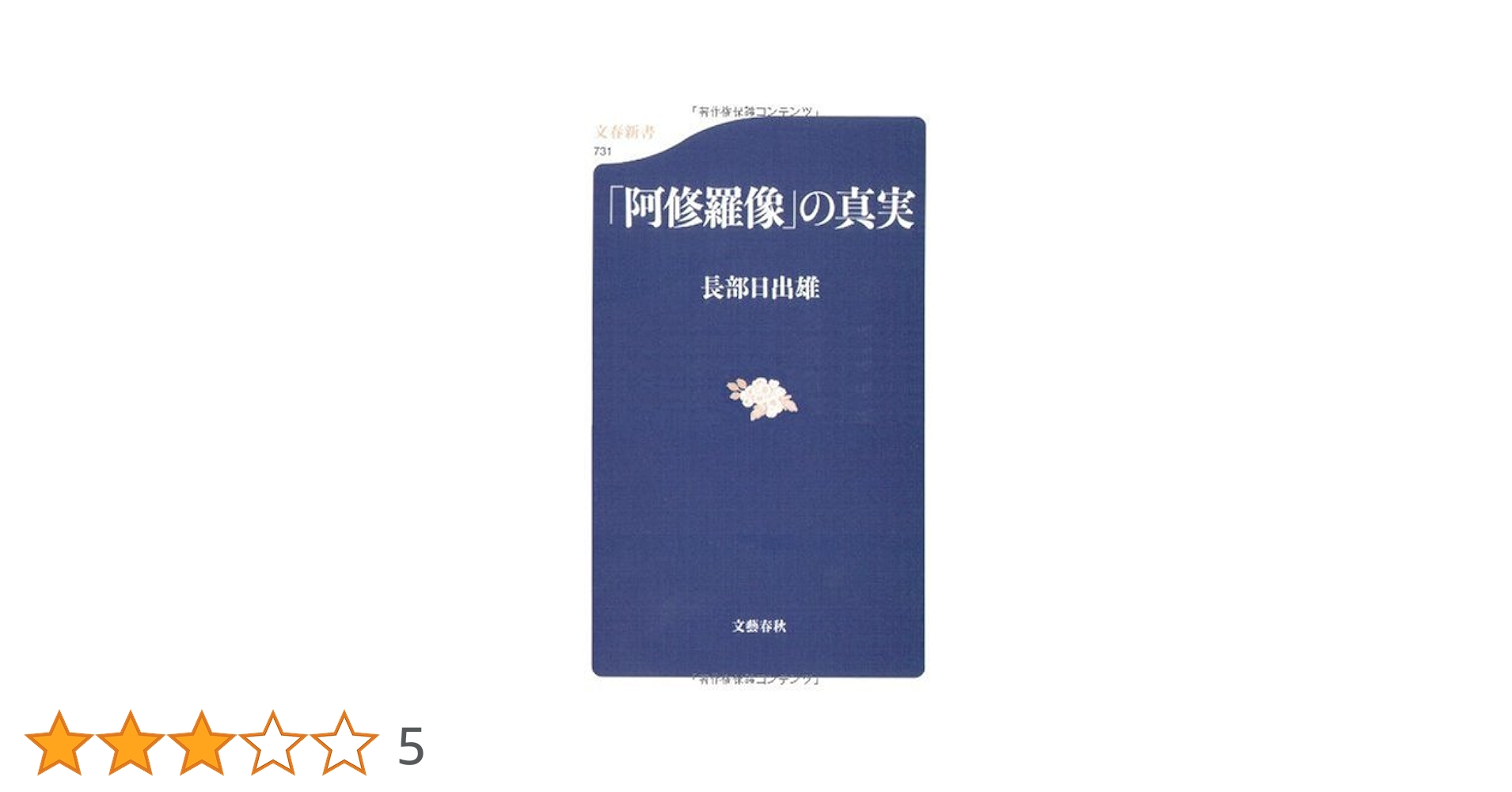
多くの人々を魅了してやまない奈良・興福寺の国宝、阿修羅像。その謎めいた表情に隠された真実とは何か。長部日出雄が、天平時代を生きた光明皇后の生涯を通して、その秘密に迫ります。
本来は戦いの神である阿修羅が、なぜあのような憂いを帯びた表情をしているのか。 著者はそのモデルを聖武天皇の后・光明皇后であると大胆に推察。 中国の兵馬俑に見られるような写実彫刻の系譜をたどりながら、仏像に込められた光明皇后の「懺悔」の思いを解き明かしていきます。



阿修羅像のモデルが光明皇后だったかもしれないなんて、ロマンがある話だね。歴史の裏側をのぞいているみたいでドキドキするよ。
12位『仏教と資本主義』
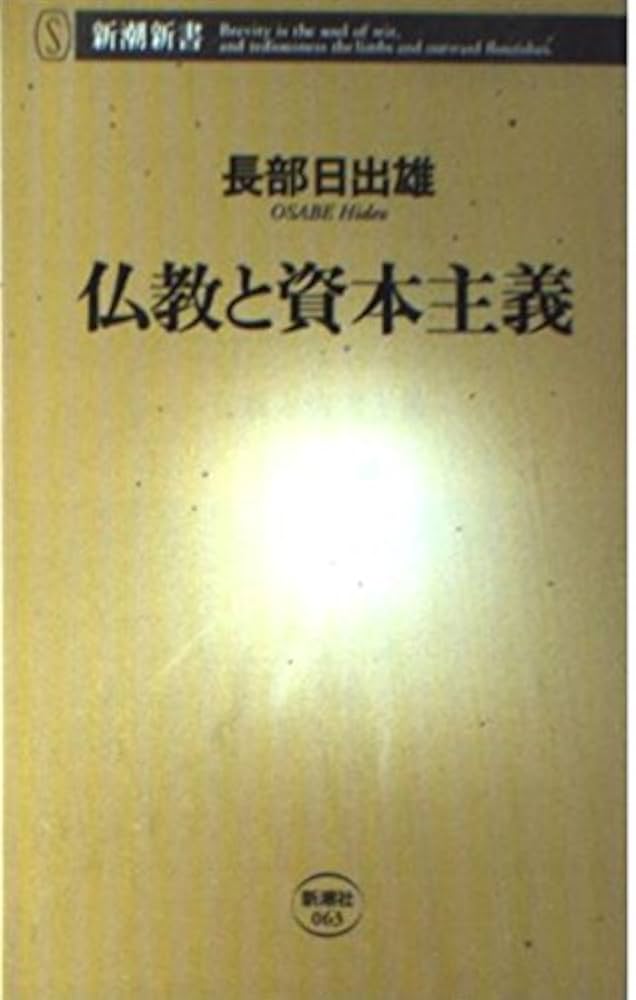
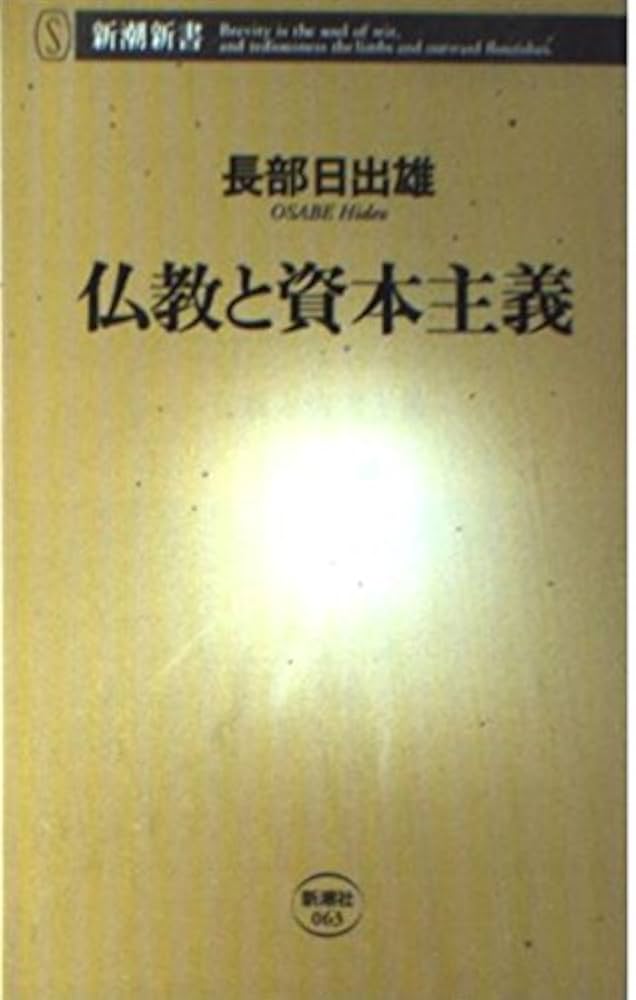
マックス・ヴェーバーは、西欧の資本主義の精神をプロテスタンティズムの倫理に見出しました。 しかし長部日出雄は、日本にはそれより遥か昔、8世紀の天平時代にすでにその萌芽があったと大胆な説を提唱します。
その中心人物が、東大寺の大仏建立に尽力した僧侶・行基です。 彼が広めた仏教の教えの中に、近代的な労働倫理や職業観につながる精神があったと著者は指摘します。 日本独自の資本主義のルーツを仏教に求めるという、ユニークな視点が知的好奇心をくすぐる一冊です。



日本の資本主義のルーツが奈良時代にあるなんて、考えたこともなかったよ! 歴史の新しい見方ができて面白いね。
13位『邦画の昭和史 スターで選ぶDVD100本』
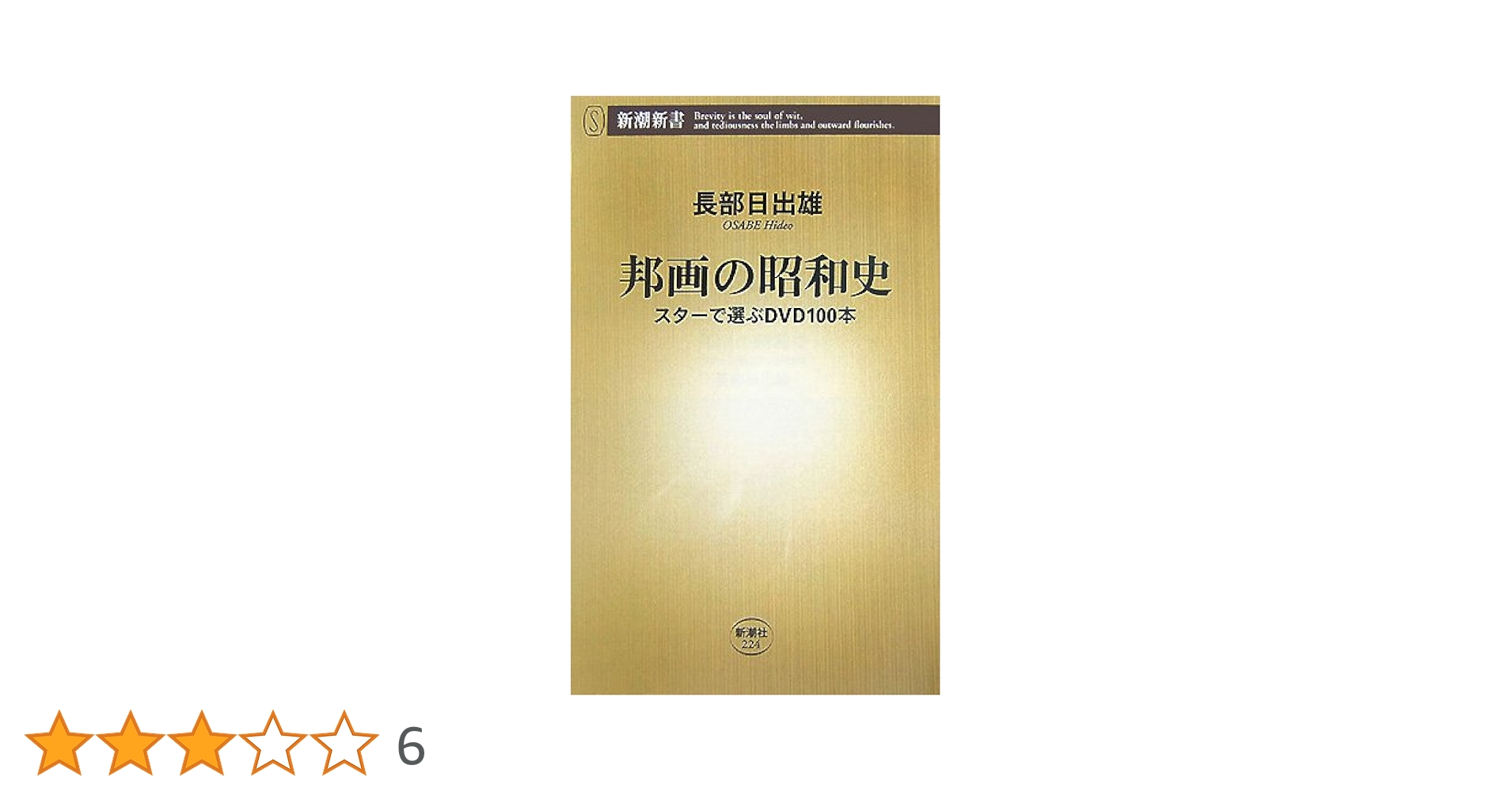
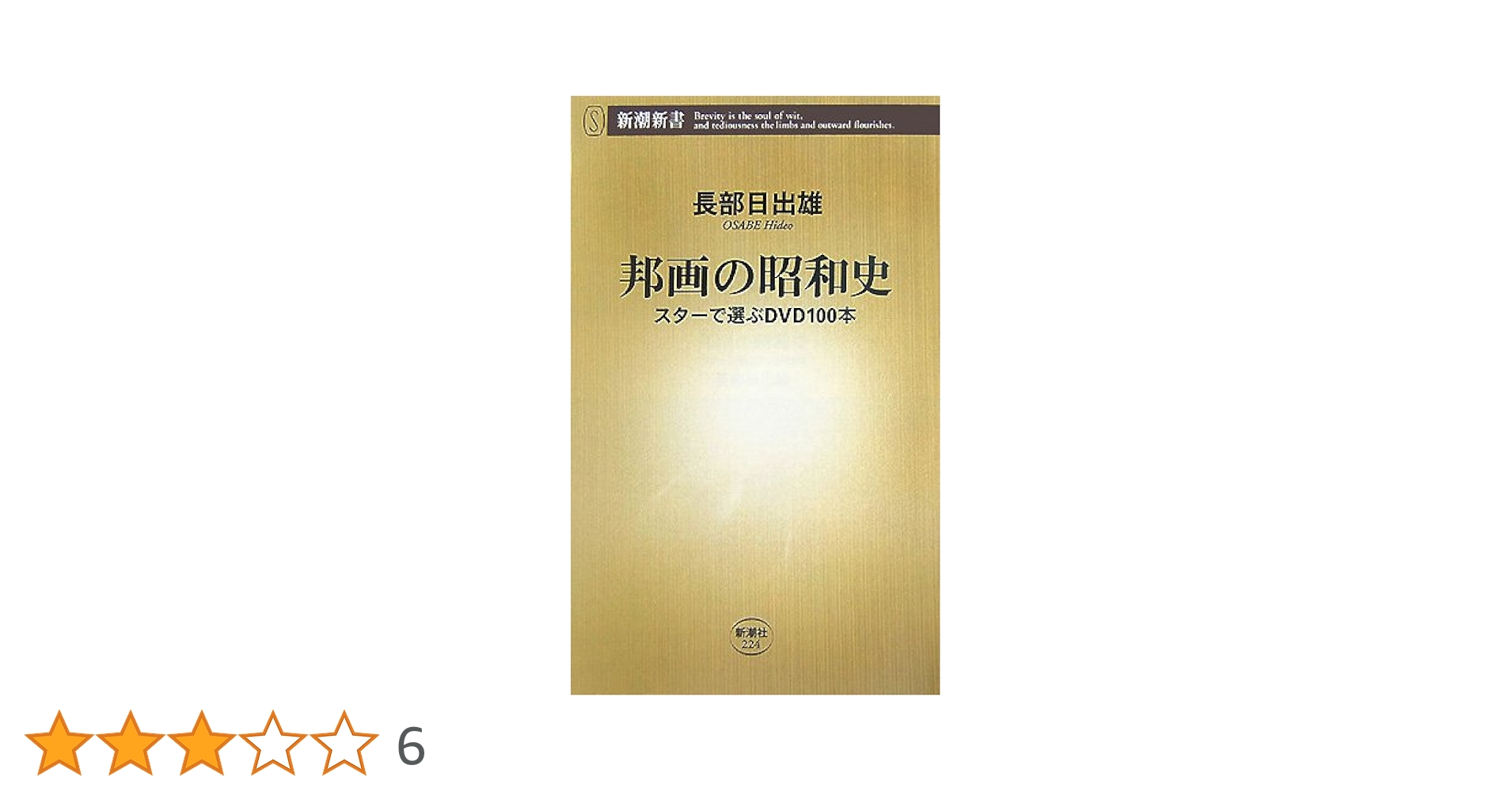
映画評論家としての一面も持つ長部日出雄が、独自の視点で昭和の日本映画を語り尽くす一冊です。 本書では、三船敏郎、石原裕次郎、原節子といった昭和を代表する映画スターたちを軸に、著者が厳選した100本の傑作DVDが紹介されます。
テレビがまだ普及していなかった時代、映画は庶民にとって最高の娯楽でした。 人々は銀幕のスターに何を求め、熱狂したのか。 本書を読めば、昭和という時代の空気感とともに、日本映画の黄金期の熱気が生き生きと蘇ってきます。映画ファンならずとも楽しめる、画期的な日本映画史入門です。



昭和の映画スターって、本当に華やかでかっこいいよね! この本をガイドに、週末は昭和映画三昧なんてのもいいかも。
14位『戦場で死んだ兄をたずねて』
『見知らぬ戦場』の原点ともいえる、著者自身の体験を綴ったノンフィクションです。 太平洋戦争末期のフィリピン・ルソン島で戦死した兄。その最期の地を訪ねる旅が、本書の主題となっています。
兄の死の真相を求める旅は、やがて日本がフィリピンの人々に対して何を行ったのかを知る旅へと変わっていきます。日本軍によって平和な村を戦場とされ、多くのものを奪われた現地の人々の痛み。 加害者と被害者、両方の視点から戦争の真実を見つめ直す、重く、しかし大切な問いを投げかける一冊です。



お兄さんを亡くした場所を訪ねるなんて、すごく勇気がいることだよね…。戦争について、深く考えさせられる本だよ。
15位『反時代的教養主義のすすめ』
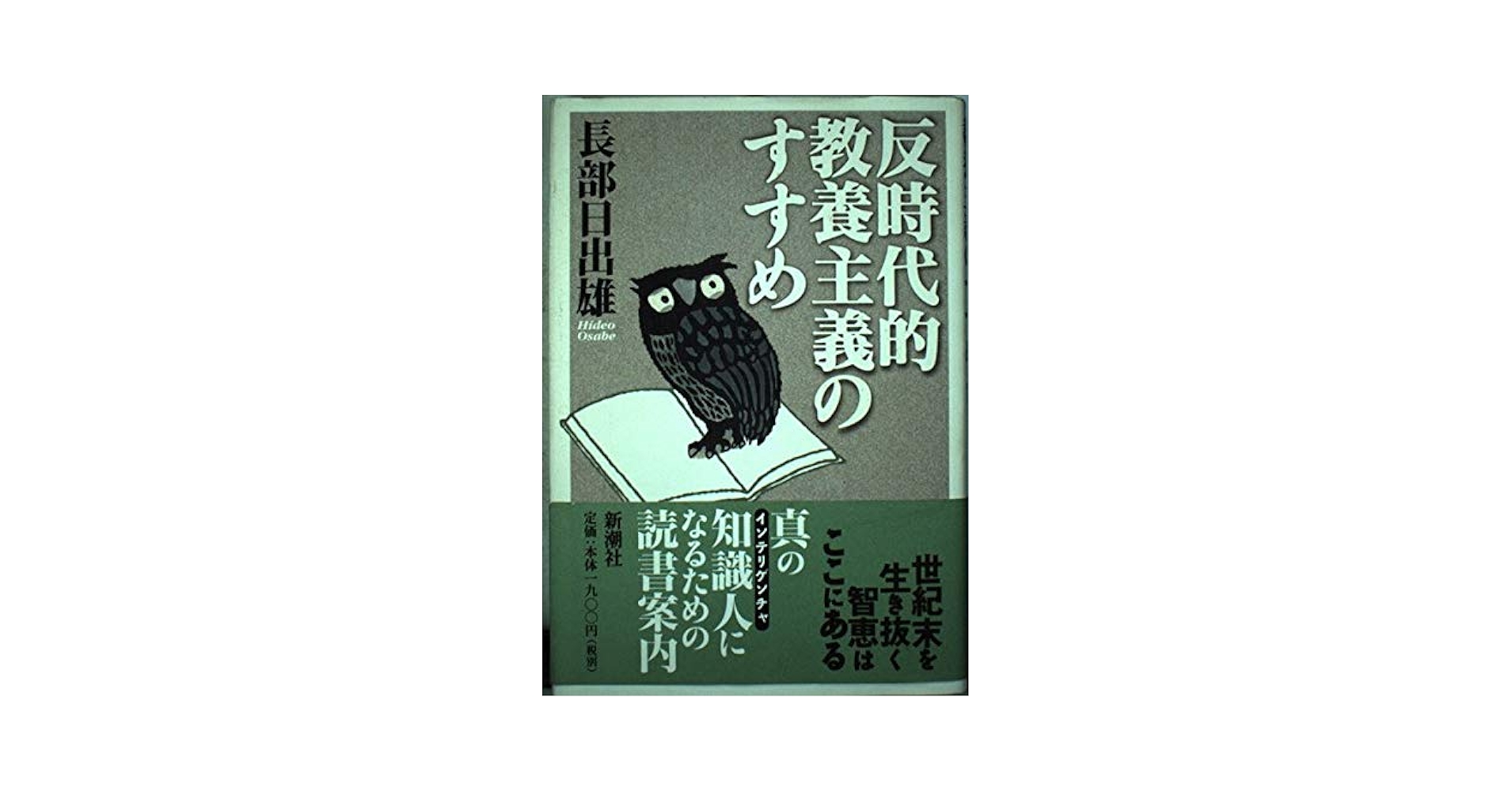
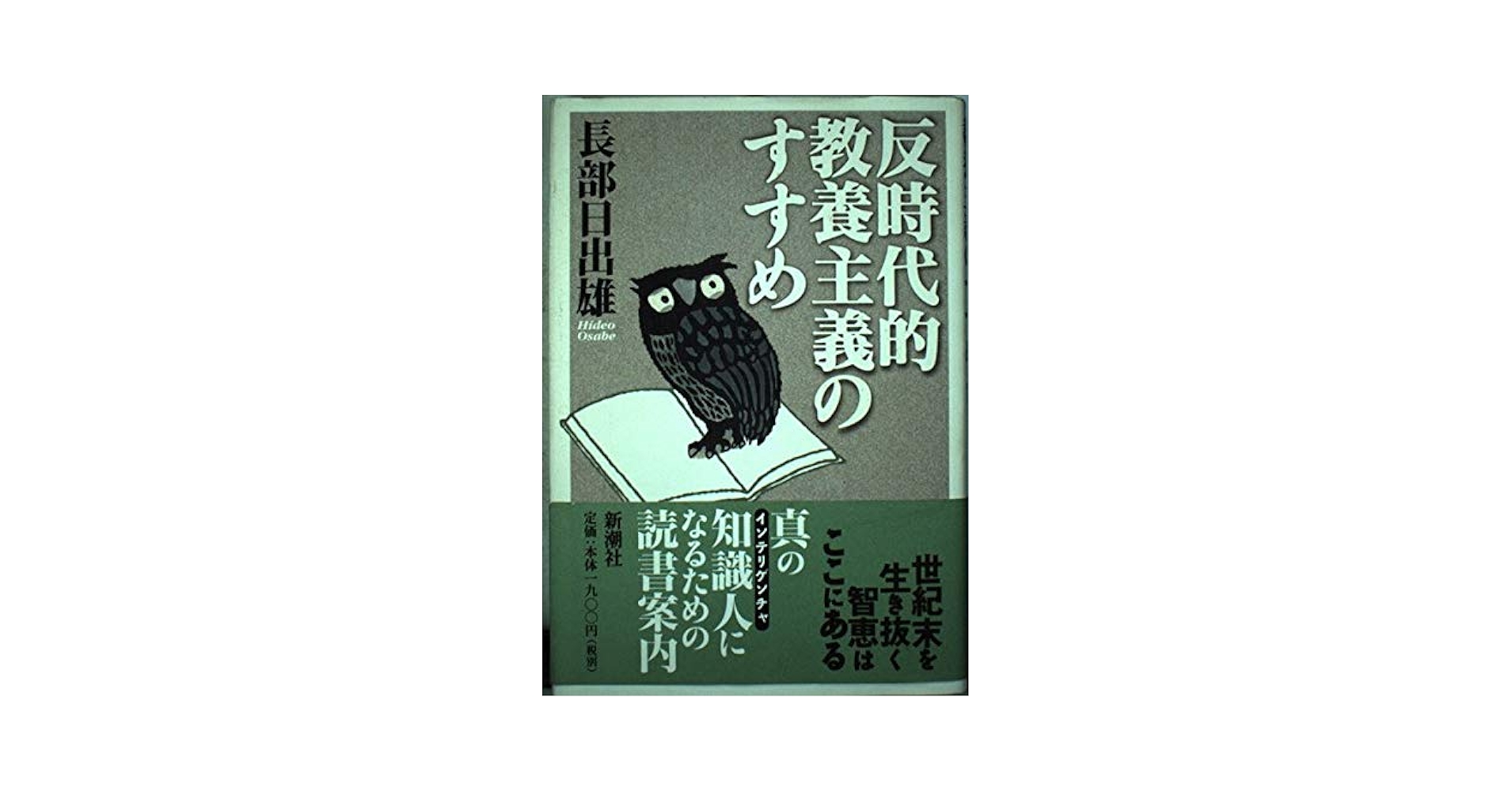
効率や実用性ばかりが求められる現代に、あえて「教養」の重要性を説く一冊です。 すぐに役立つ知識やスキルではなく、人生を豊かにするための「知の体力」をどう身につけるか、そのヒントが詰まっています。
本書では、ドストエフスキーやカントといった西洋哲学から仏教思想まで、古今東西の知の遺産が紹介されます。 一見すると難解な思想家たちの言葉を、著者が現代的な視点から分かりやすく解説してくれるので、知的好奇心が刺激されることでしょう。 巻末には、著者自身の闘病体験から得られた死生観も綴られており、深く考えさせられます。



すぐに役立つことだけが勉強じゃないんだよね。人生を深く味わうための教養、わたしも身につけたいな。
おわりに:長部日出雄の作品で知的好奇心を満たす読書体験を
長部日出雄のおすすめ小説ランキング、いかがでしたでしょうか。
故郷・津軽を舞台にした情熱的な物語から、歴史上の人物の知られざる生涯、そして現代社会を鋭く見つめる評論まで、その作品世界は驚くほど多彩です。どの作品にも共通しているのは、徹底した取材に裏打ちされたリアリティと、物事の本質に迫ろうとする真摯な眼差しです。
長部日出雄の作品は、私たちに新しい知識や視点を与え、知的好奇心を大いに満たしてくれます。ぜひこの機会に一冊手に取って、奥深い読書の世界に浸ってみてください。