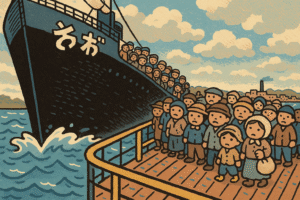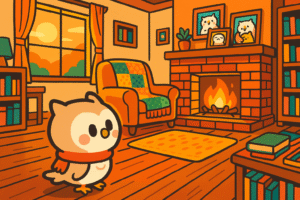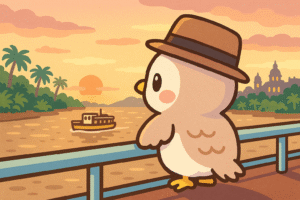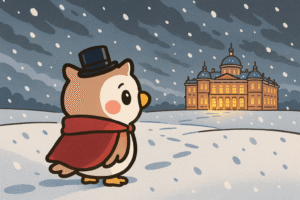あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】小島信夫の小説おすすめランキングTOP13

はじめに:戦後文学の鬼才・小島信夫の魅力とは
小島信夫(1915〜2006年)は、日本の戦後文学を語る上で欠かせない小説家の一人です。遠藤周作や安岡章太郎らとともに「第三の新人」と称され、戦後の新しい文学の担い手として文壇に登場しました。その作品は、ユーモアと風刺に富んだ独特の文体で知られ、人間の心理や社会の矛盾を鋭く描き出しています。
小島信夫の魅力は、私小説的な要素を取り入れながらも、虚実が入り混じる実験的な手法を駆使し、常に「小説」という形式の可能性を追求し続けた点にあります。戦争体験や「家族」という普遍的なテーマを扱いながらも、そのアプローチは一筋縄ではいきません。本記事では、そんな鬼才・小島信夫の奥深い文学世界に触れるため、代表作から隠れた名作まで、おすすめの小説をランキング形式でご紹介します。
小島信夫の小説おすすめランキングTOP13
ここからは、いよいよ小島信夫のおすすめ小説ランキングTOP13をご紹介します。芥川賞を受賞したあまりにも有名な初期の代表作から、円熟期の実験的な長編小説、そして晩年の作品まで、幅広くランクインしました。
どの作品も、日常に潜む非日常や人間の滑稽さ、そして生の本質を巧みに描き出しています。このランキングを参考に、ぜひ小島信夫の唯一無二の文学世界への扉を開いてみてください。
1位『アメリカン・スクール』
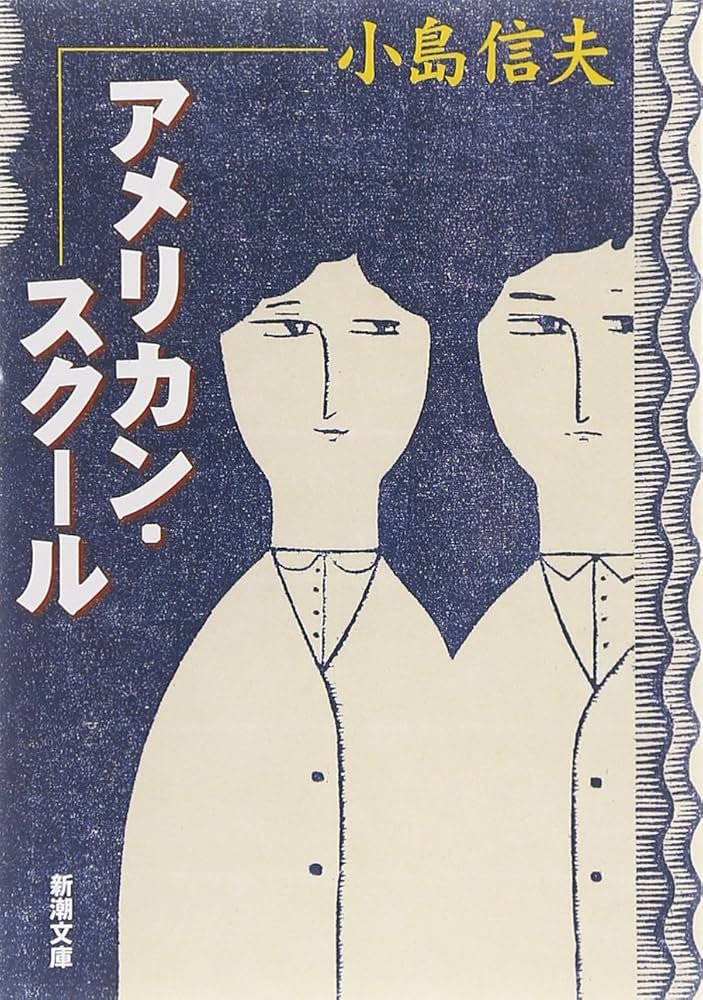
小島信夫の名を一躍有名にした、第32回芥川賞受賞作です。敗戦直後の日本を舞台に、アメリカの占領軍が運営する学校(アメリカン・スクール)を見学することになった日本人英語教師たちの姿を、ユーモラスかつ痛烈に描いています。
主人公の伊佐は、英語力に自信がなく、戦勝国アメリカに対して卑屈な感情を抱いています。一方、同僚の山田は自信過剰に英語をひけらかそうとします。この対照的な登場人物たちを通して、当時の日本人が抱えていた劣等感や虚栄心、そして日米間の複雑な関係性が巧みに風刺されています。小島信夫文学の入門書として、まず最初に読んでおきたい一冊です。
| 発表年 | 1954年 |
|---|---|
| 受賞歴 | 第32回 芥川龍之介賞 |
| ジャンル | 短編小説、風刺小説 |
 ふくちい
ふくちい戦勝国と敗戦国、その間で揺れる人々の心がリアルだよ。コミカルだけど、すごく切実な物語なんだ。
2位『抱擁家族』
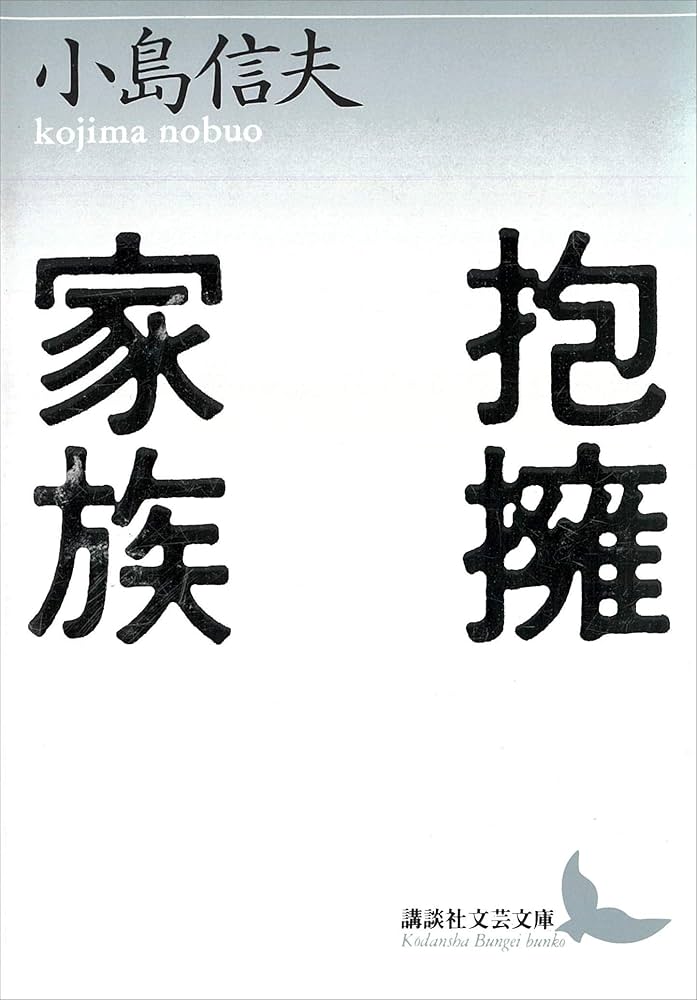
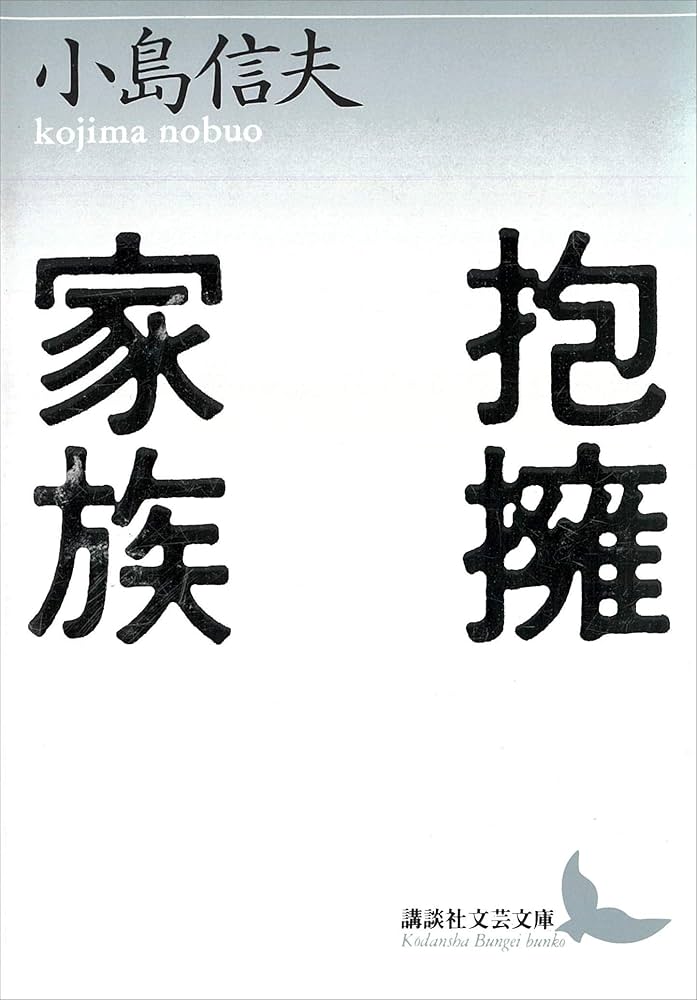
戦後文学の金字塔とも評される、小島信夫の代表的な長編小説です。この作品で、小島は第1回谷崎潤一郎賞を受賞しました。物語は、大学教師である主人公・三輪俊介の妻、時子のアメリカ兵との不貞が発覚するところから始まります。
妻の裏切りをきっかけに、俊介は家族の絆を取り戻そうと郊外に新しい家を建てますが、その試みもむなしく、妻は病で亡くなり、息子は家を出て行ってしまいます。一見するとシリアスな家庭崩壊の物語ですが、そこには小島信夫特有のどこか滑稽で歪んだ人間模様が描かれており、「家族」とは何か、「家庭」とは何かを読者に鋭く問いかけます。作者自身の妻との死別体験も色濃く反映されていると言われています。
| 発表年 | 1965年 |
|---|---|
| 受賞歴 | 第1回 谷崎潤一郎賞 |
| ジャンル | 長編小説、家族小説 |



家族ってなんだろうって、深く考えさせられちゃうな…。幸せの形って、一つじゃないのかも。
3位『うるわしき日々』
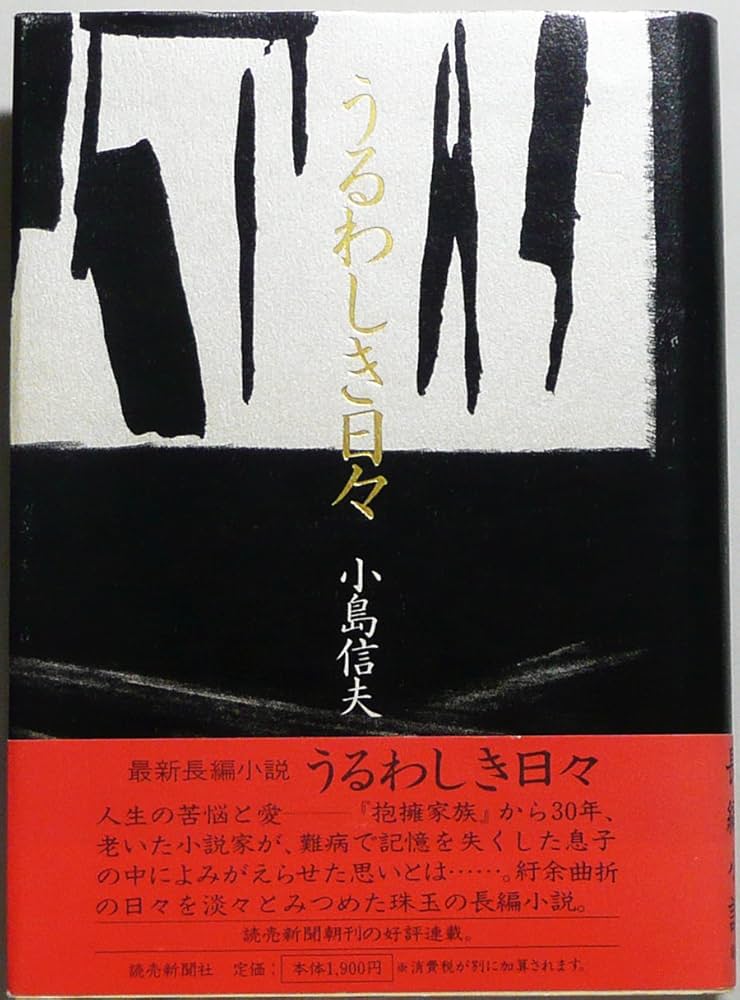
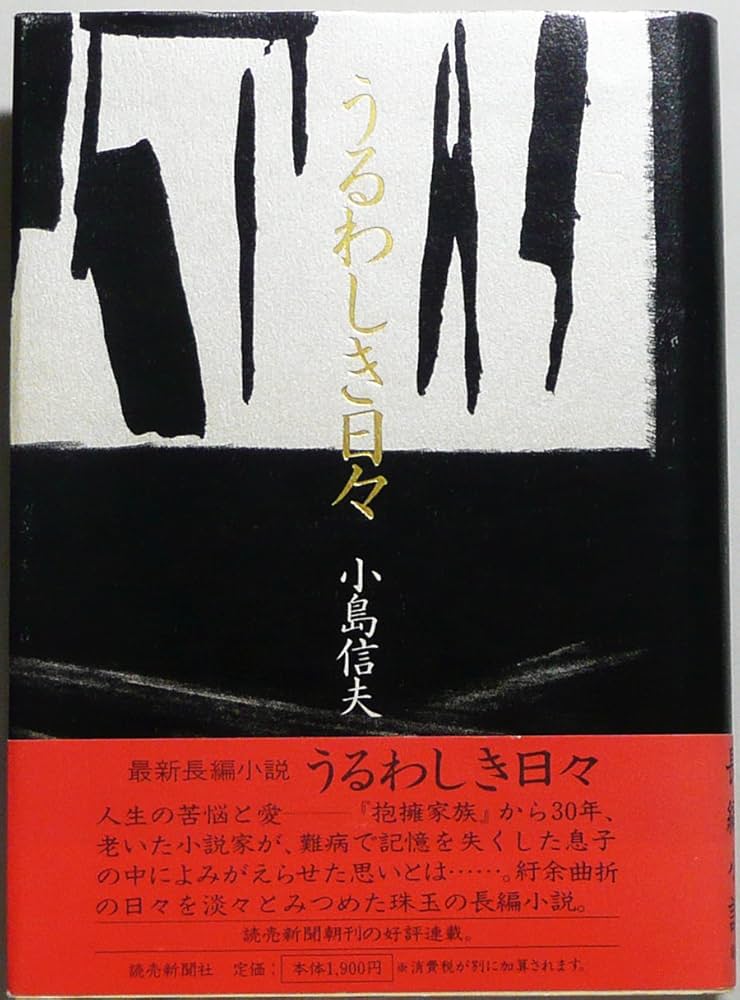
1997年に読売文学賞を受賞した、小島信夫の晩年の傑作です。この作品では、老境に達した作家である主人公が、自身の過去の記憶や日々の出来事を、夢とも現実ともつかない筆致で綴っていきます。
物語には明確な筋書きがあるわけではなく、主人公の意識の流れを追うように、断片的なエピソードが連なります。しかし、その一つひとつが鮮烈なイメージを喚起し、老いと死、記憶、そして文学そのものについての深い思索が込められています。小島文学の集大成ともいえる、静謐ながらも力強い一冊です。
| 発表年 | 1997年 |
|---|---|
| 受賞歴 | 第49回 読売文学賞 |
| ジャンル | 長編小説 |



なんだか不思議な小説だったな。老作家の夢の中を散歩している気分になったよ。
4位『残光』
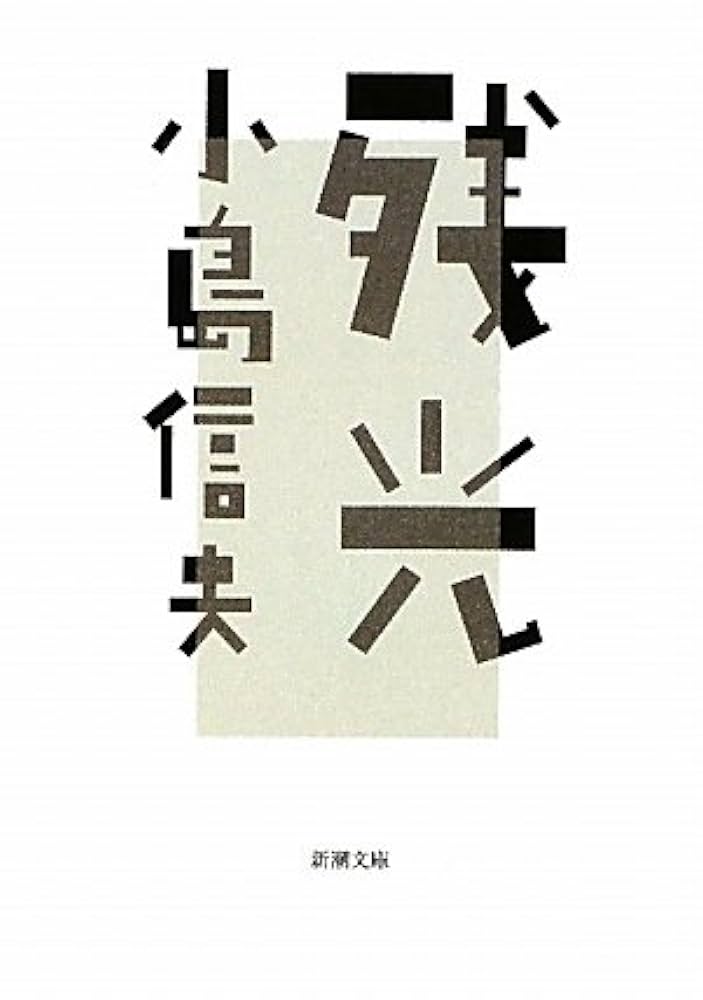
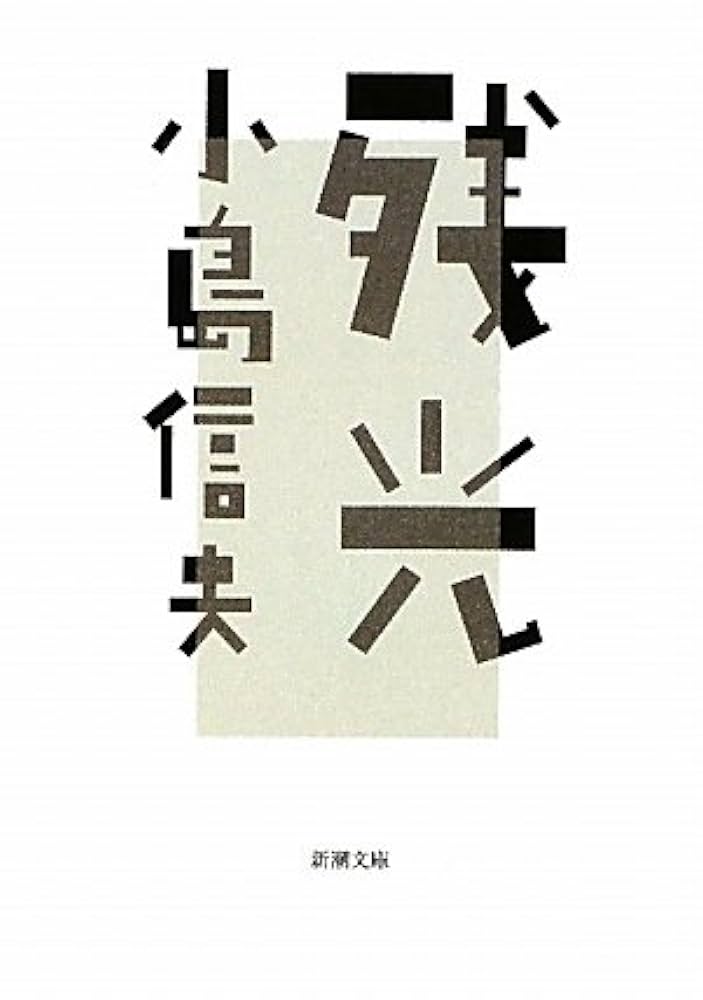
2006年に発表された、小島信夫の遺作となった長編小説です。主人公は、やはり老作家。彼は亡き妻を想い、過去の出来事を回想しながら、死の影が色濃く漂う現在を生きています。
この作品は、前作『うるわしき日々』から続くテーマである「老い」と「死」をさらに深く掘り下げています。衰えゆく身体、薄れゆく意識の中で、それでもなお「書くこと」への執念を燃やし続ける作家の姿は、鬼気迫るものがあります。小島信夫が最期にたどり着いた文学の境地を、ぜひ見届けてください。
| 発表年 | 2006年 |
|---|---|
| 受賞歴 | – |
| ジャンル | 長編小説 |



これが最後の作品だと思うと、胸が詰まるよ…。作家の魂そのものを感じたんだ。
5位『別れる理由』
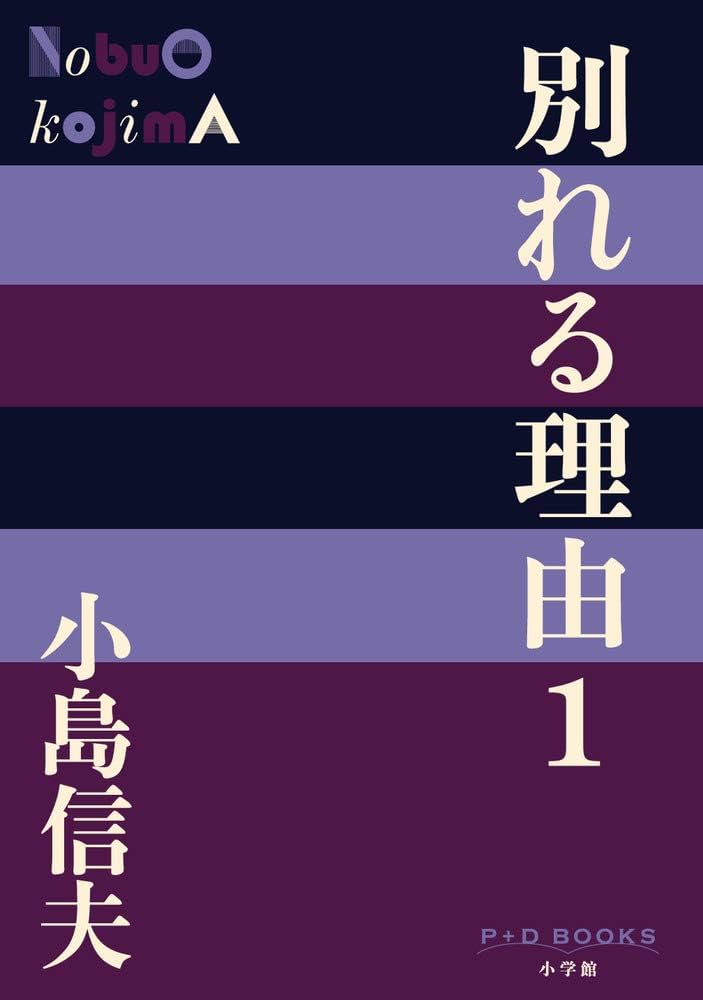
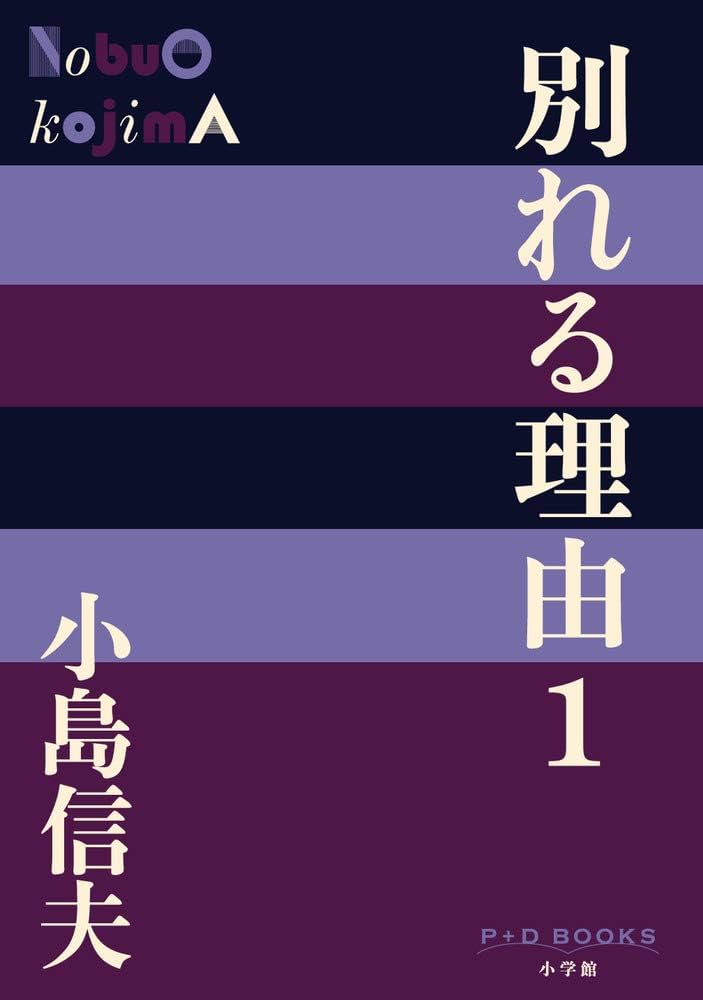
雑誌『群像』に14年間、全150回にわたって連載された、小島信夫のライフワークともいえる超大作です。この作品で野間文芸賞を受賞しました。主人公である小説家「おれ」の日常や思索が、現実と虚構の境界を自在に往来しながら、際限なく綴られていきます。
実在の人物が実名で登場したり、作者自身と思われる人物が物語に介入したりと、その実験的な手法は、従来の小説の概念を大きく揺さぶりました。長大な作品ですが、その奔放でユーモラスな語りに引き込まれ、唯一無二の読書体験ができます。「小説とは何か」という問いそのものを体現したような、記念碑的作品です。
| 発表年 | 1982年(単行本) |
|---|---|
| 受賞歴 | 第35回 野間文芸賞 |
| ジャンル | 長編小説 |



14年の連載ってすごい!小説家の頭の中って、こんなに自由なんだってワクワクしちゃうよ。
6位『美濃』
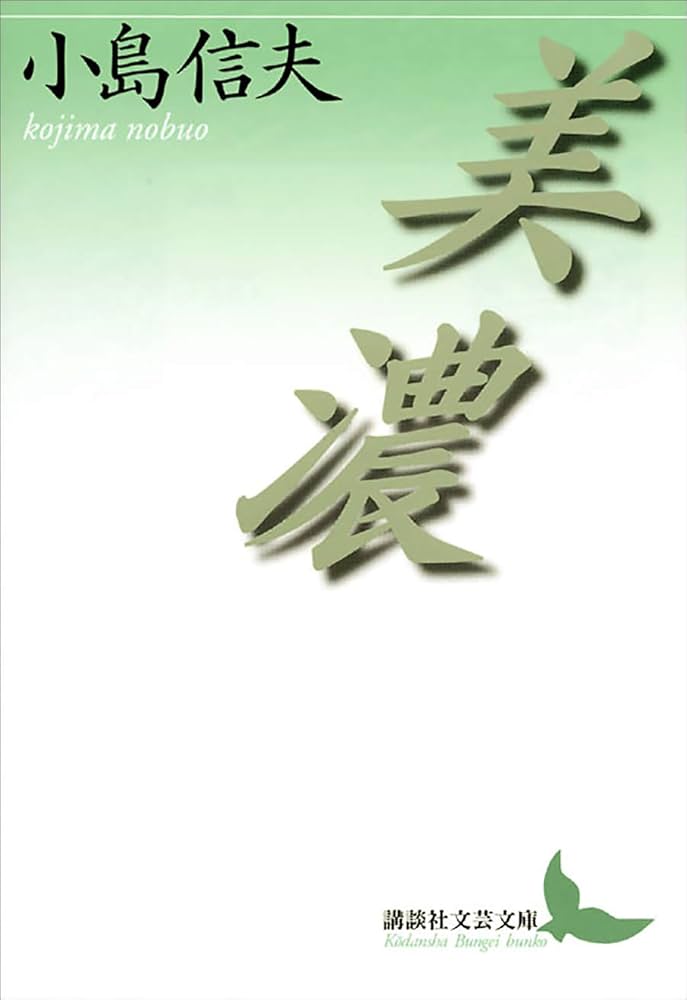
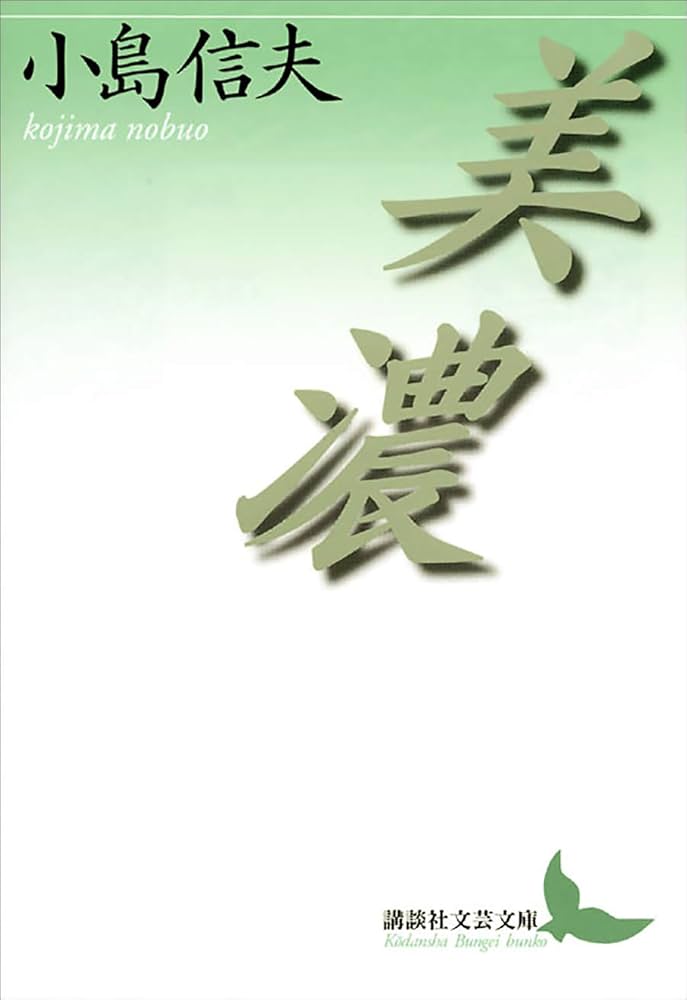
小島信夫の故郷である岐阜(美濃)を舞台にした長編小説です。この作品では、故郷の風土や人々を、愛情と批評の入り混じった視点で描いています。主人公が旧友たちと再会し、過去と現在が交錯する中で、地方都市の現実や人間関係の機微が浮かび上がります。
『別れる理由』と同様に、実在の友人らがモデルとして登場し、虚実が入り乱れる手法が取られています。ローカルな世界を扱いながらも、そこには日本という国や社会全体に通じる普遍的なテーマが横たわっています。自身の故郷に思いを馳せながら読んでみるのも面白いかもしれません。
| 発表年 | 1981年 |
|---|---|
| 受賞歴 | – |
| ジャンル | 長編小説 |



自分の故郷が小説になったらどうかなって想像しちゃった。ちょっと照れくさいけど、嬉しいかもね。
7位『殉教・微笑』
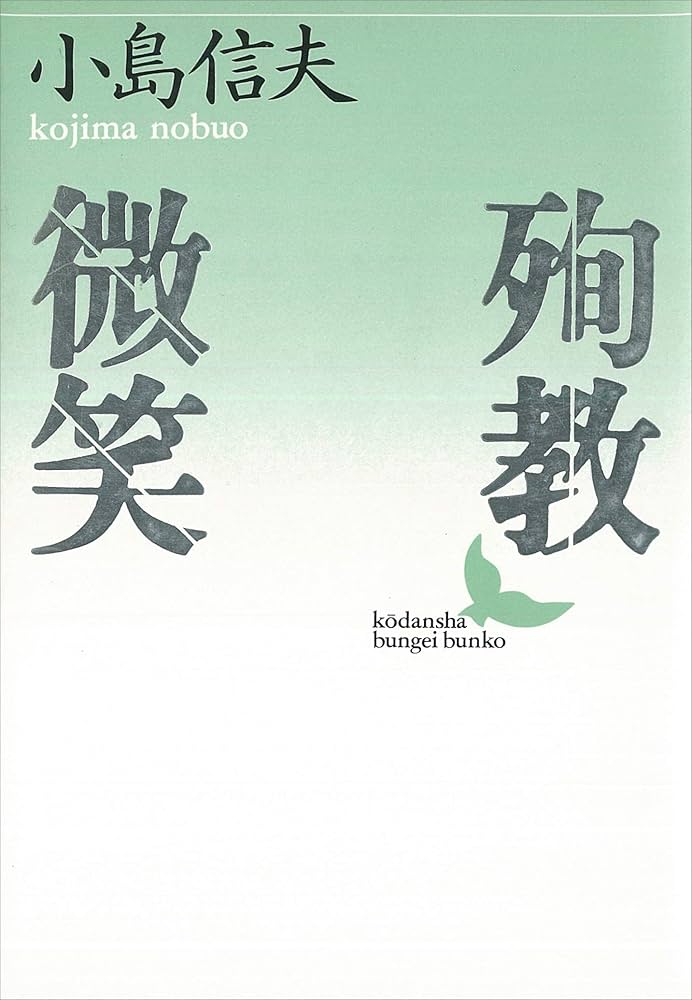
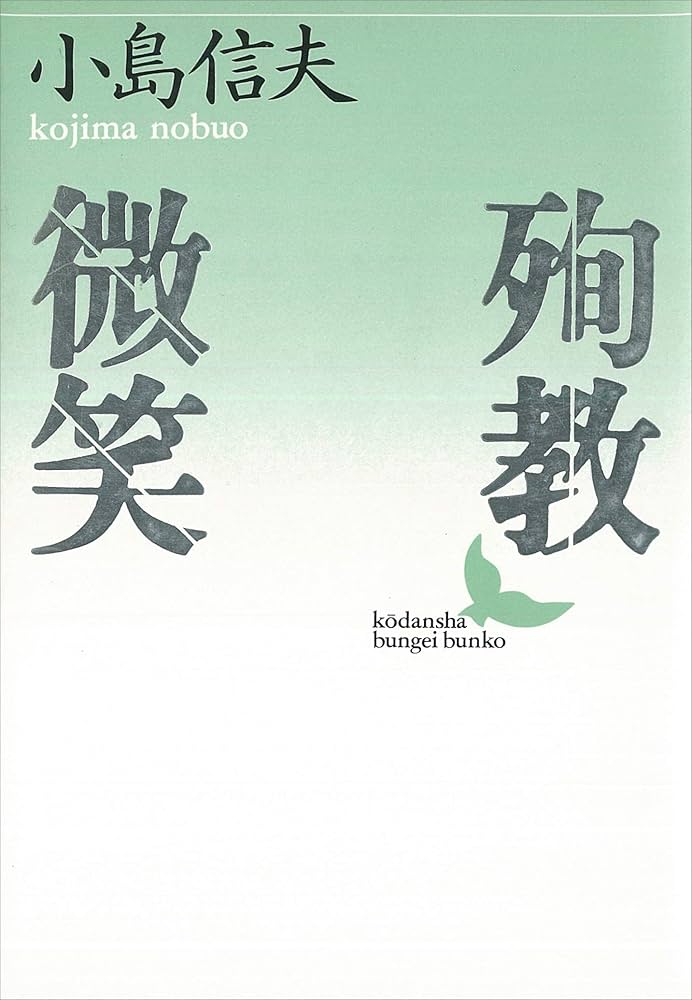
初期の短編「殉教」と「微笑」を収めた作品集です。表題作の「殉教」は、信仰と人間の弱さという重いテーマを扱いながらも、小島信夫らしいブラックユーモアを交えて描かれています。
一方の「微笑」は、戦時中のエピソードを基にした作品です。これらの初期作品には、後の長編小説で展開されるテーマの萌芽や、独特の文体の原型を見ることができます。小島信夫の文学の原点に触れたい方におすすめの一冊です。
| 発表年 | 1954年(殉教) |
|---|---|
| 受賞歴 | – |
| ジャンル | 短編集 |



信仰と人間の弱さってテーマ、重いけど考えさせられるな。ブラックユーモアの切れ味がすごいよ。
8位『小銃』
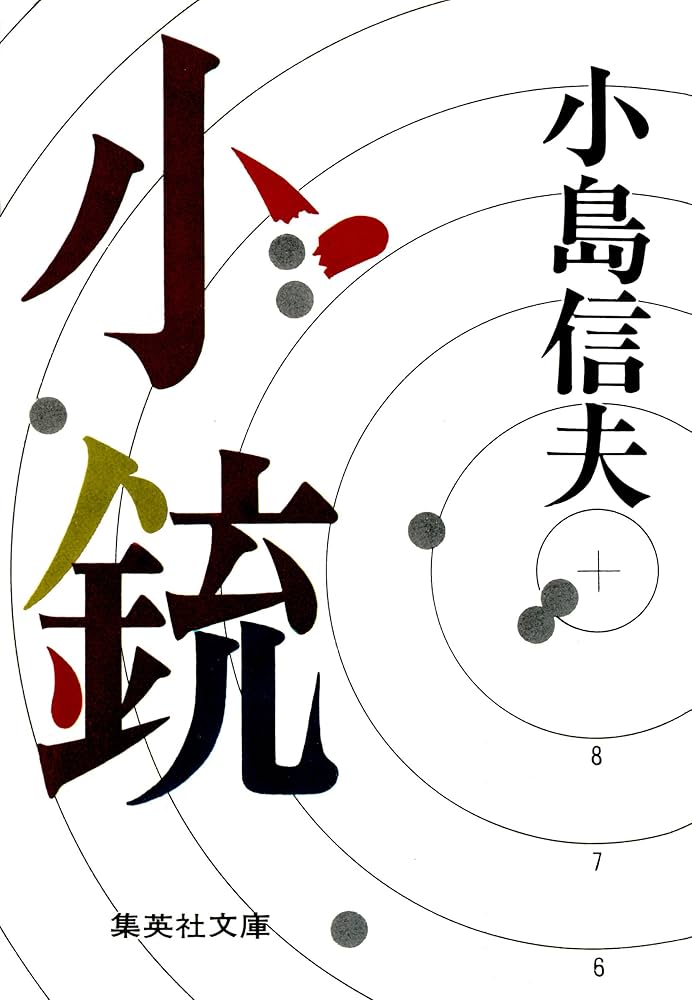
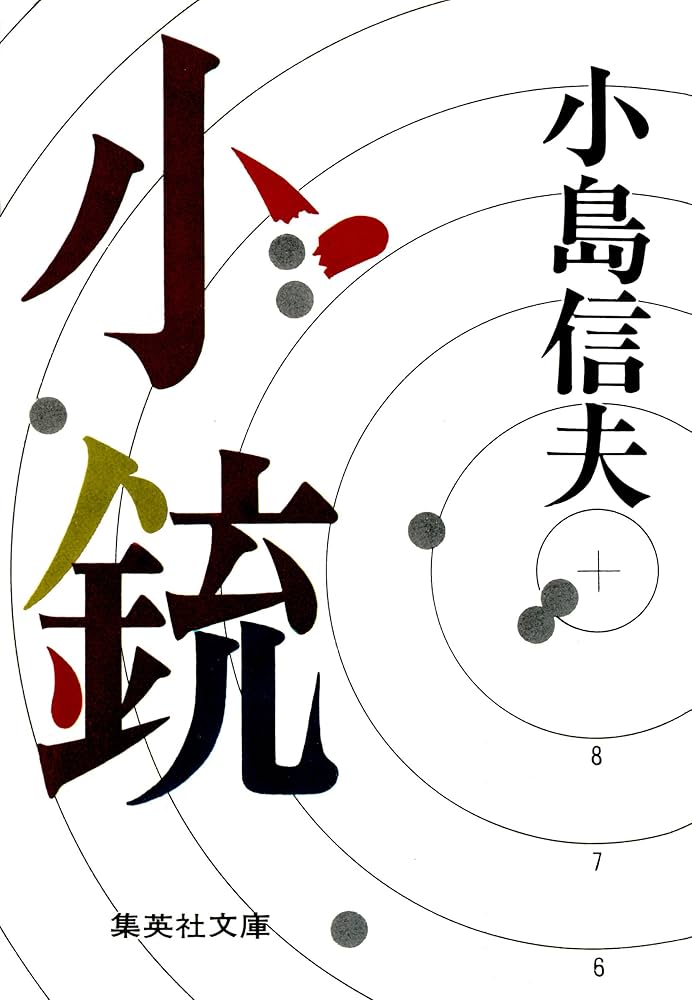
小島信夫の文壇デビュー作であり、戦争文学の傑作としても名高い短編です。この作品は、作者自身の中国での従軍体験が基になっています。物語は、兵士である主人公が、ある出来事をきっかけに「小銃」という一個の物体に異常なまでに執着し、翻弄されていく様を描きます。
戦争という極限状況における人間の心理が、乾いた筆致で克明に描き出されています。英雄的な物語でも、悲惨さを声高に叫ぶ物語でもない、戦争の不条理と、その中で歪んでいく日常を淡々と描くスタイルは、かえって読者に強烈な印象を残します。
| 発表年 | 1952年 |
|---|---|
| 受賞歴 | – |
| ジャンル | 短編小説、戦争小説 |



本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。戦争が人間から何を奪うのか、その本質を突いている。
9位『月光・暮坂 小島信夫後期作品集』
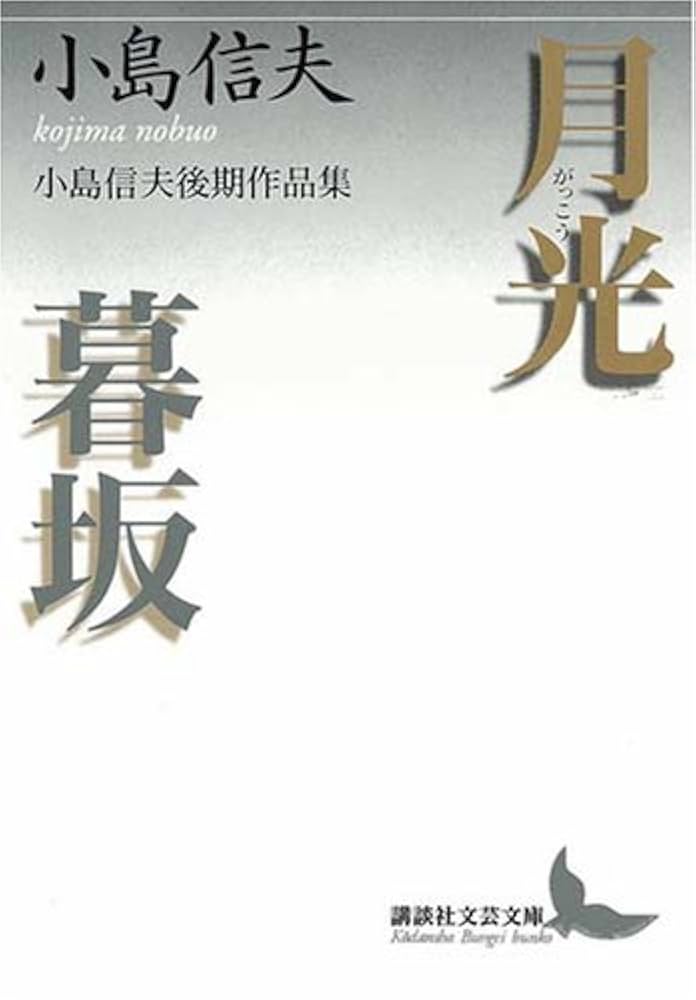
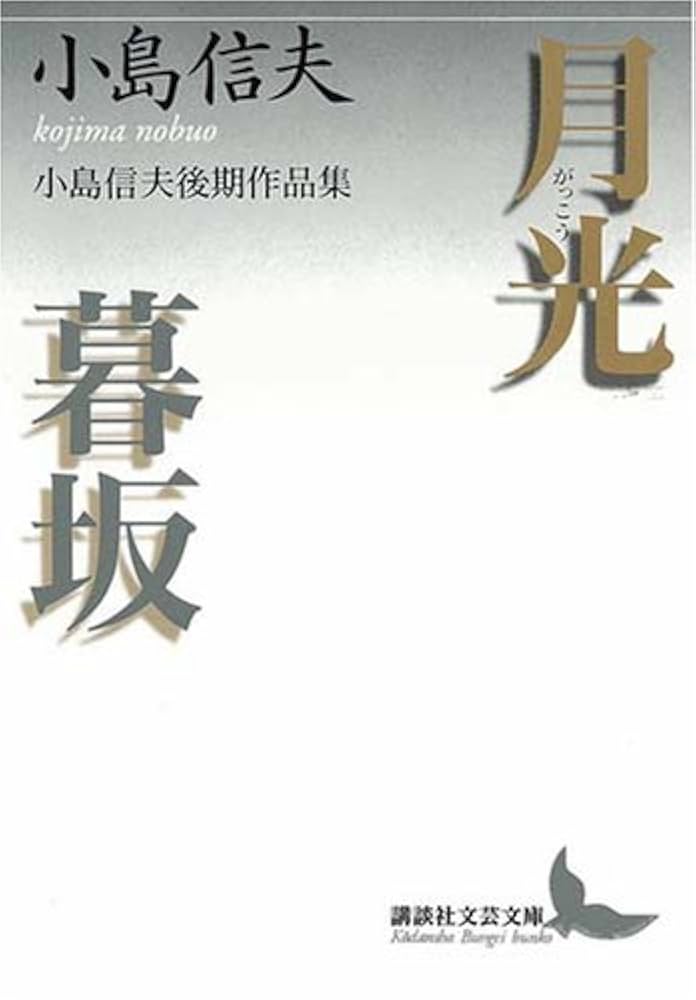
『月光』や『暮坂』など、小島信夫の後期から晩年にかけての円熟した作品群を収めた一冊です。これらの作品では、老いを迎え、死を意識した主人公の日常が、静かな筆致で描かれています。
若い頃の作品に見られたような激しい風刺や実験精神は影を潜め、より内省的で、人生の機微や哀歓を深く見つめるような作風が特徴です。しかし、その根底には、人間という存在への尽きない興味と、ユーモラスな視点が常に流れています。小島文学の新たな一面を発見できる作品集です。
| 発表年 | – |
|---|---|
| 受賞歴 | – |
| ジャンル | 作品集 |



年を重ねてからの作品って、深みが増すよね。若い頃とは違う、穏やかな視線を感じるな。
10位『各務原・名古屋・国立』
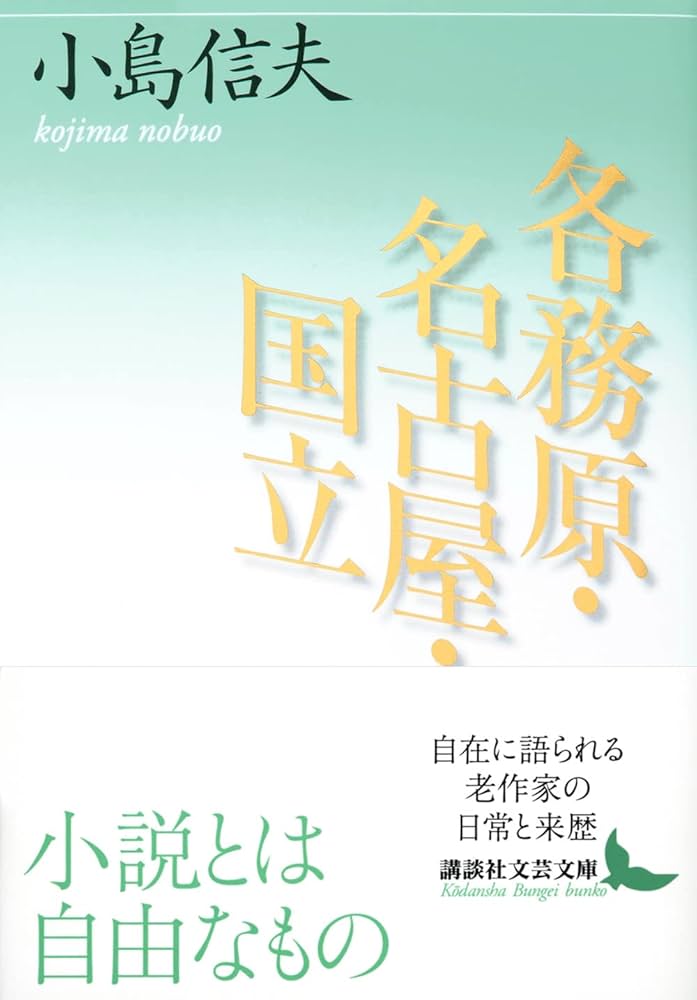
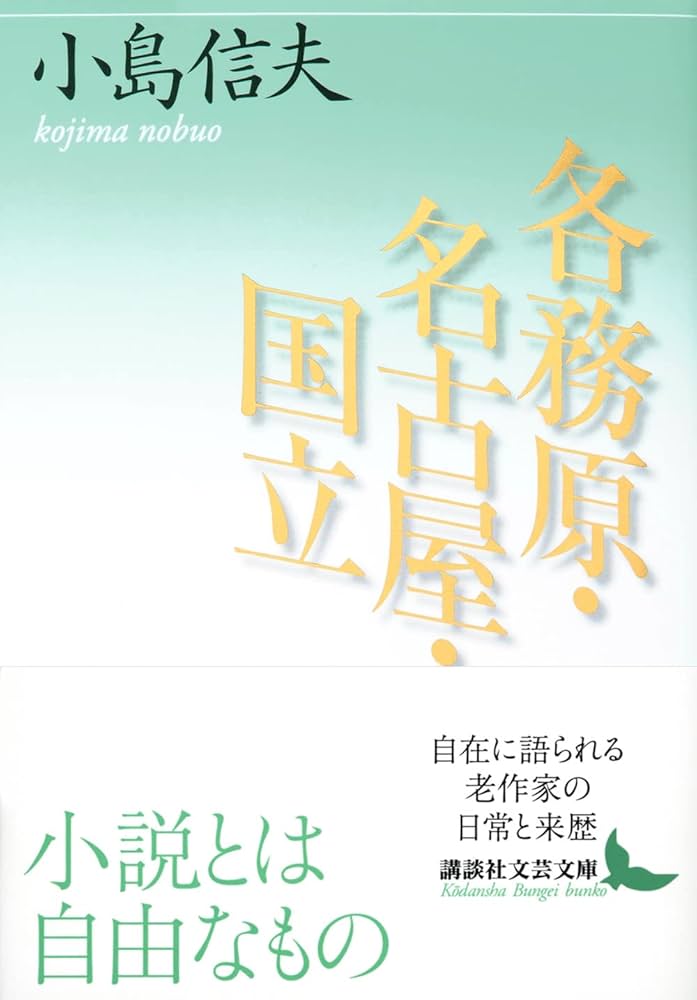
故郷の地名(各務原)や、かつて住んだ街(名古屋、国立)をタイトルに冠した、自伝的色彩の濃い連作短編集です。それぞれの土地での思い出や出来事が、過去と現在、記憶と創作の間を自由に行き来しながら語られます。
私小説的な要素が強い作品ですが、単なる思い出話に終わらないのが小島信夫の真骨頂。記憶は変容し、事実は小説的に再構築されていきます。読者は、作家の記憶を巡る旅に同行するような、不思議な読書体験を味わうことができるでしょう。
| 発表年 | 2002年 |
|---|---|
| 受賞歴 | – |
| ジャンル | 連作短編集 |



地名がタイトルって面白いね。その場所を旅してみたくなるよ、物語の聖地巡礼みたいに。
11位『ハッピネス』
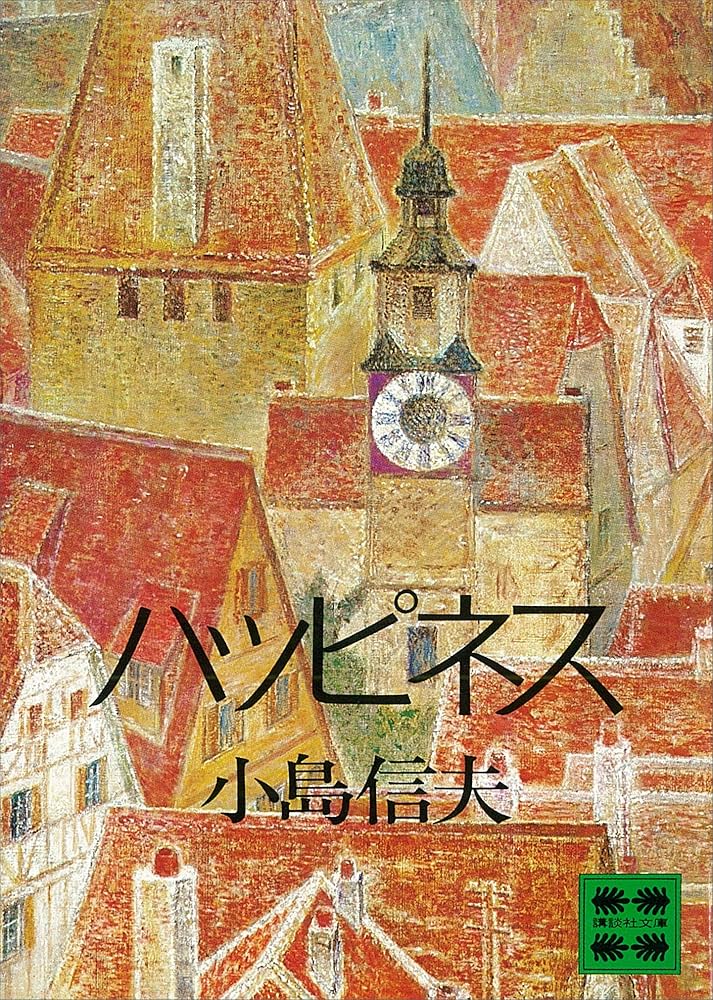
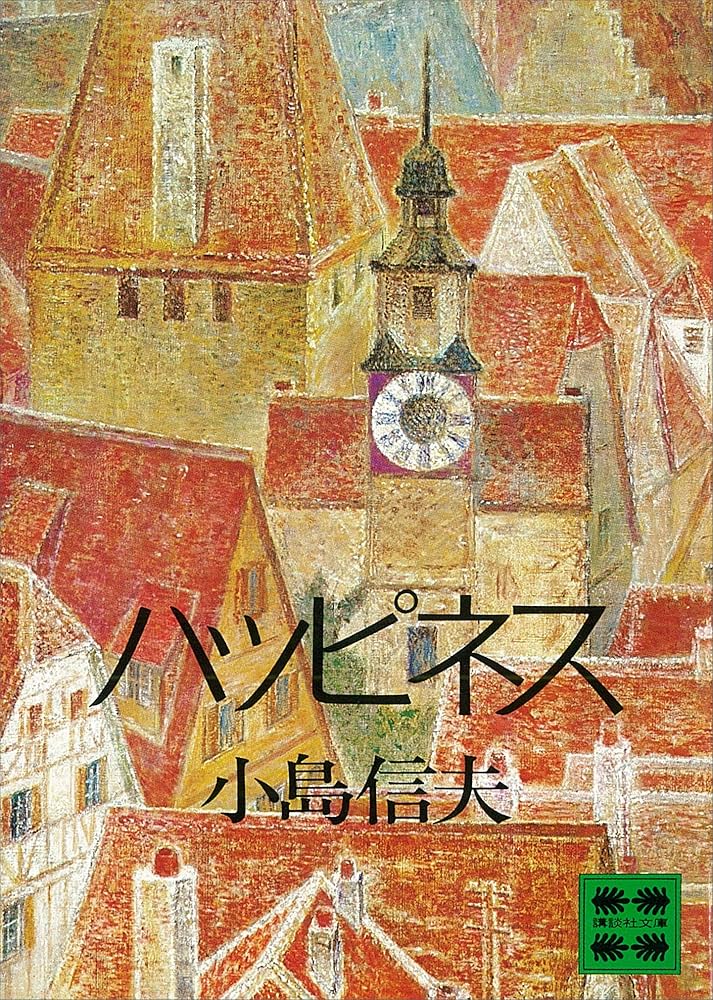
老夫婦の日常を淡々と、しかしどこかコミカルに描いた長編小説です。主人公の老作家は、妻との何気ない会話や、日々のささやかな出来事の中に、幸福(ハッピネス)の形を見出そうとします。
大きな事件が起こるわけではありませんが、老夫婦のやり取りの中に、長年連れ添ったからこその愛情や、人生のペーソスが滲み出ています。小島信夫の温かい眼差しが感じられる作品であり、読後には穏やかな気持ちになれる一冊です。
| 発表年 | 1974年 |
|---|---|
| 受賞歴 | – |
| ジャンル | 長編小説 |



『ハッピネス』ってタイトルがいいな。特別なことじゃなく、日常の中にこそ幸せはあるんだって思わせてくれるよ。
12位『墓碑銘』
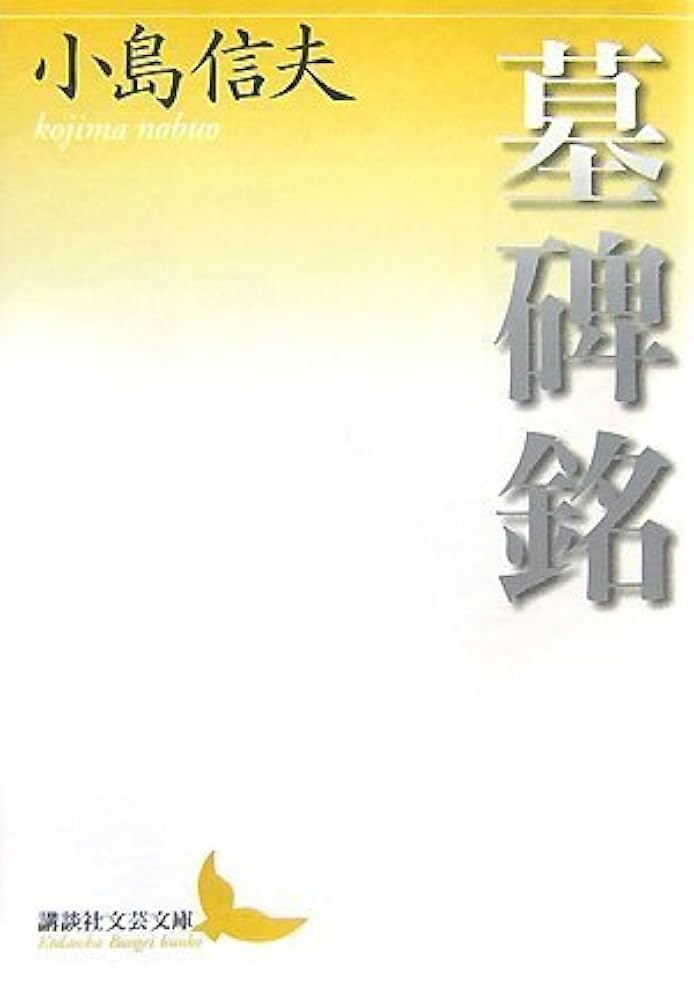
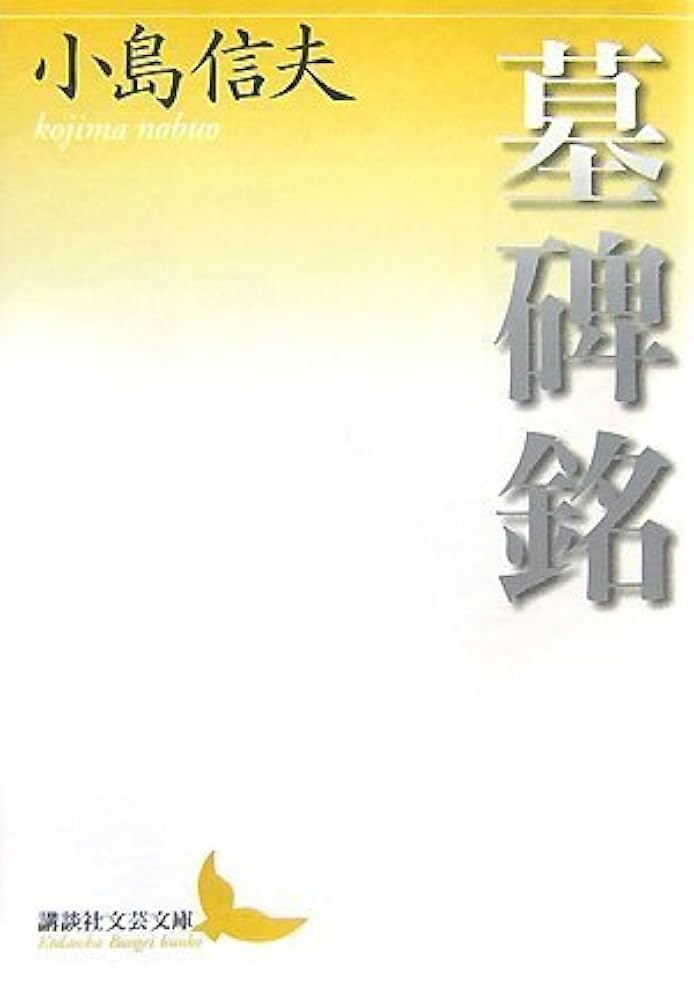
こちらも小島信夫の初期の短編作品です。この作品では、ある男の死をめぐる人々の反応や思惑が、シニカルな視点で描かれています。
死という厳粛なテーマを扱いながらも、登場人物たちの行動はどこか滑稽で、人間のエゴや偽善が暴かれていきます。初期の小島信夫が得意とした、ブラックユーモアの効いた作風が存分に発揮された一編です。『アメリカン・スクール』や『小銃』と合わせて読むことで、作家の初期の世界観をより深く理解できます。
| 発表年 | 1953年 |
|---|---|
| 受賞歴 | – |
| ジャンル | 短編小説 |



死という事象を前にして露呈する人間のエゴイズムと偽善。その滑稽さを冷徹な視点で切り取っている点が興味深い。
13位『城壁・星 戦争小説集』
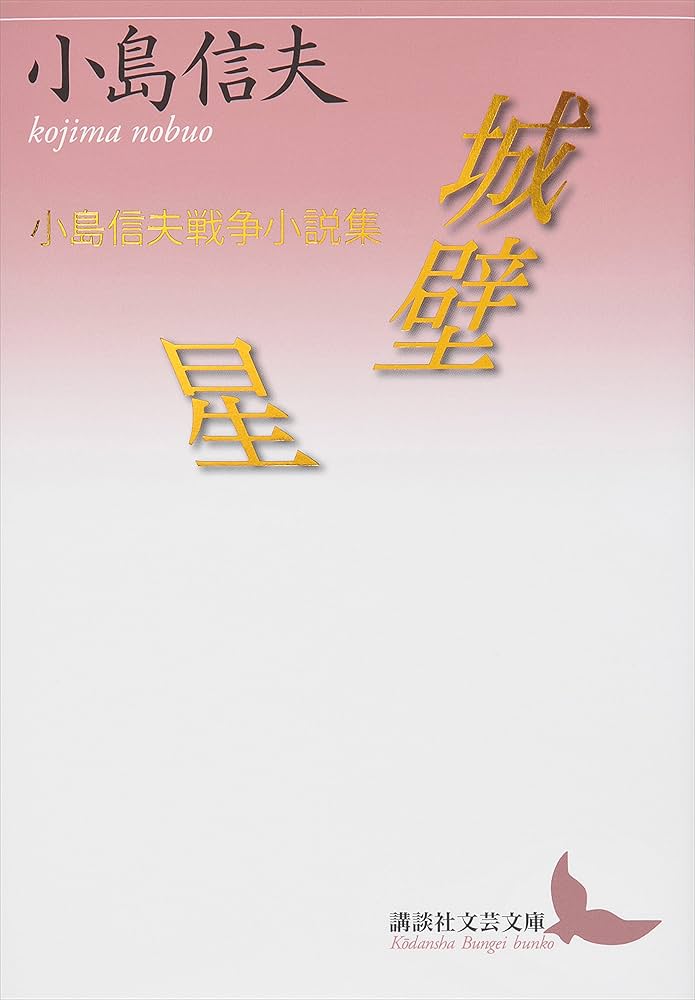
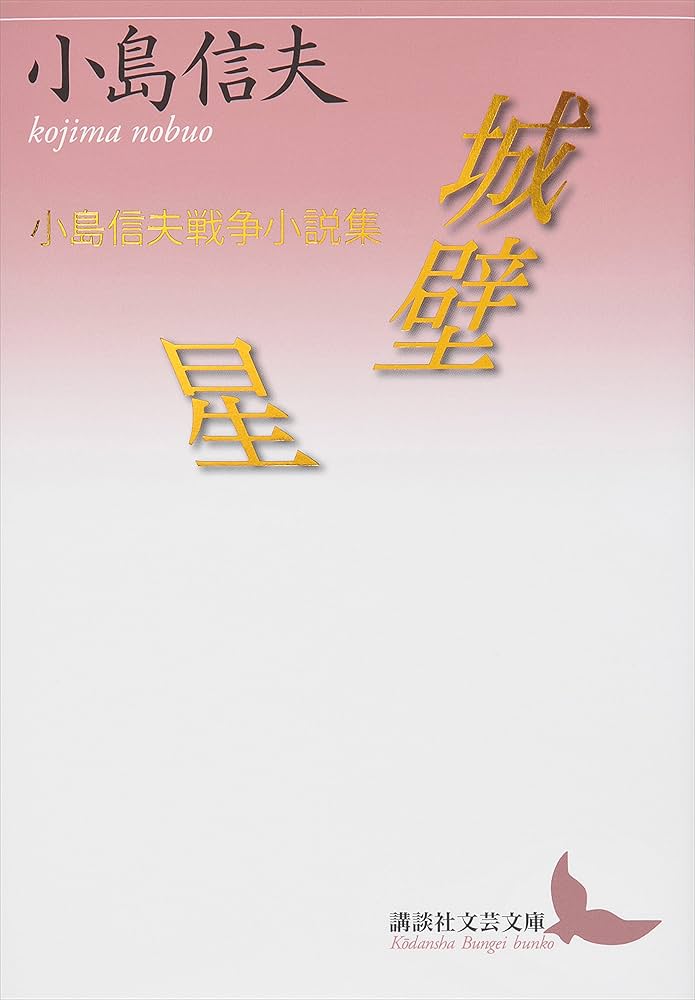
デビュー作「小銃」をはじめ、「城壁」「星」など、小島信夫が手掛けた戦争をテーマにした小説を集めた作品集です。これらの作品は、作者自身の従軍体験に基づいており、戦場のリアルな描写と、極限状態に置かれた兵士たちの心理が描かれています。
しかし、単なる戦争の悲惨さを告発するのではなく、戦争という異常な状況がもたらす人間の行動や心理の歪みを、冷徹なまでに客観的な視点で見つめているのが特徴です。戦争文学というジャンルに新たな視点をもたらした、重要な作品群と言えるでしょう。
| 発表年 | – |
|---|---|
| 受賞歴 | – |
| ジャンル | 作品集、戦争小説 |



ここでもまた、戦争という主題に対する作者の冷静な観察眼が光る。英雄も悪人も存在しない、ただ人間がいるだけ、という事実を突きつけられる。
まとめ:どの作品から読む?小島信夫のおすすめ小説で文学の深淵に触れる
ここまで、戦後文学の鬼才・小島信夫のおすすめ小説をランキング形式でご紹介してきました。ユーモアと風刺、シリアスなテーマ、そして前衛的な実験精神まで、その作風は非常に多彩です。
もし、どの作品から読めばいいか迷ったら、以下を参考にしてみてください。
- 小島信夫入門なら:まずは芥川賞受賞作『アメリカン・スクール』から。戦後の空気感と、小島文学の原点であるユーモアと風刺の切れ味を堪能できます。
- 戦後文学の金字塔に触れたいなら:谷崎潤一郎賞を受賞した『抱擁家族』は外せません。戦後日本の「家族」の変容を鋭く描いた傑作です。
- 小説の実験性を味わいたいなら:14年にわたる連載の末に完成した『別れる理由』がおすすめです。虚実入り乱れる奔放な物語は、唯一無二の読書体験をもたらしてくれるでしょう。
このランキングをきっかけに、一人でも多くの方が小島信夫の奥深い文学の世界に触れてくだされば幸いです。