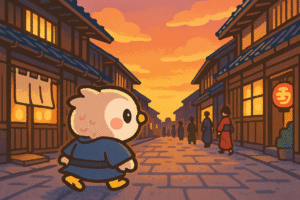あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】立野信之のおすすめ小説人気ランキングTOP9

はじめに:歴史の激動を描いた直木賞作家・立野信之の魅力
日本の近代史、特にその激動の時代を鋭く描き出した作家、立野信之(たてののぶゆき)をご存知でしょうか。自身の軍隊体験や社会運動への関わりを基に、プロレタリア文学の旗手としてキャリアをスタートさせました。
その後、時代の大きなうねりの中で思想的な転向を経験し、戦後は日本の現代史をテーマにした数々の重厚な作品を発表しました。中でも、二・二六事件の真相に迫った『叛乱』で第28回直木賞を受賞し、その名を不動のものとします。
立野信之の魅力は、歴史上の出来事や人物を、まるでドキュメンタリーのようにリアルに、そして人間味豊かに描き出す点にあります。彼の作品を通じて、教科書だけでは知ることのできない、歴史の裏側や人々の息遣いを感じてみませんか。
立野信之のおすすめ小説人気ランキングTOP9
ここからは、歴史の深淵を覗き見るような立野信之の作品の中から、特におすすめの小説をランキング形式でご紹介します。
直木賞受賞作をはじめ、日本の近代史を動かした重要な出来事や人物に焦点を当てた名作が揃っています。どの作品から読もうか迷っている方は、ぜひこのランキングを参考に、気になる一冊を見つけてみてください。
1位『叛乱』
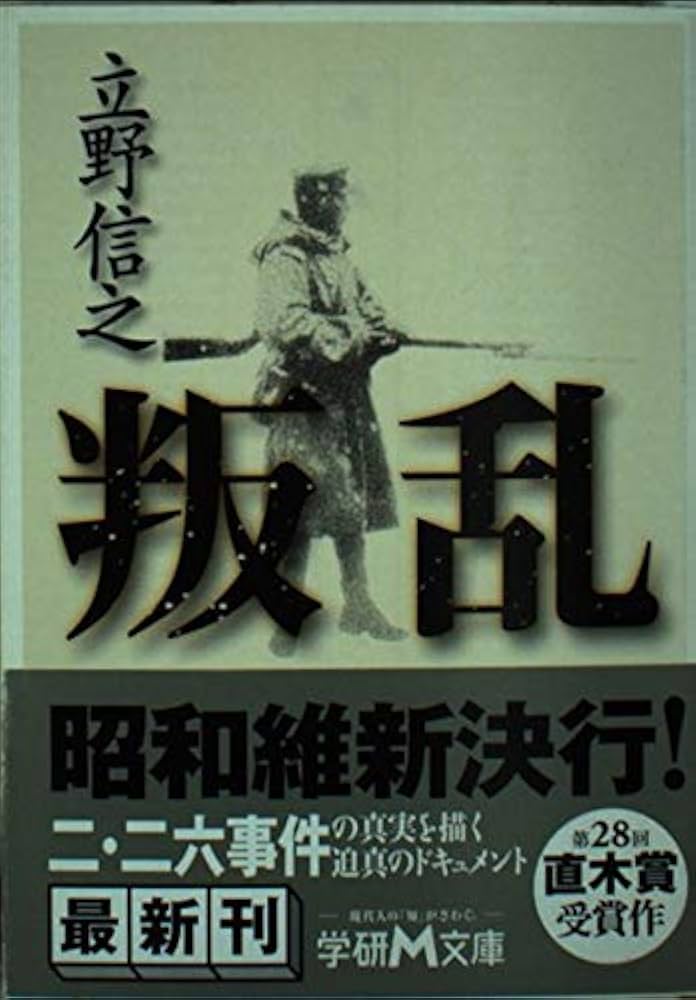
堂々の1位は、立野信之の名を世に知らしめた第28回直木賞受賞作『叛乱』です。この作品は、昭和史を揺るがした大事件「二・二六事件」を題材にした歴史小説で、立野文学の最高峰とも言える一作です。
物語は、陸軍内部の派閥対立が激化し、青年将校たちが「昭和維新」を掲げて決起するまでの緊迫した道のりを克明に追っていきます。丹念な資料調査に基づいて描かれる本作は、ドキュメンタリーのような迫力があり、なぜ若者たちがクーデターへと突き進んでしまったのか、その情熱や苦悩、そして誤算を生々しく描き出しています。
歴史の教科書だけでは分からない、事件の裏側にいた人間たちのドラマに引き込まれること間違いなし。日本の近代史に興味があるなら、まず読んでおきたい傑作です。
 ふくちい
ふくちい歴史の大きなうねりに翻弄される人々の姿が、本当にリアルだよ。わたしも思わず引き込まれちゃった。
2位『太陽はまた昇る―公爵近衛文麿』
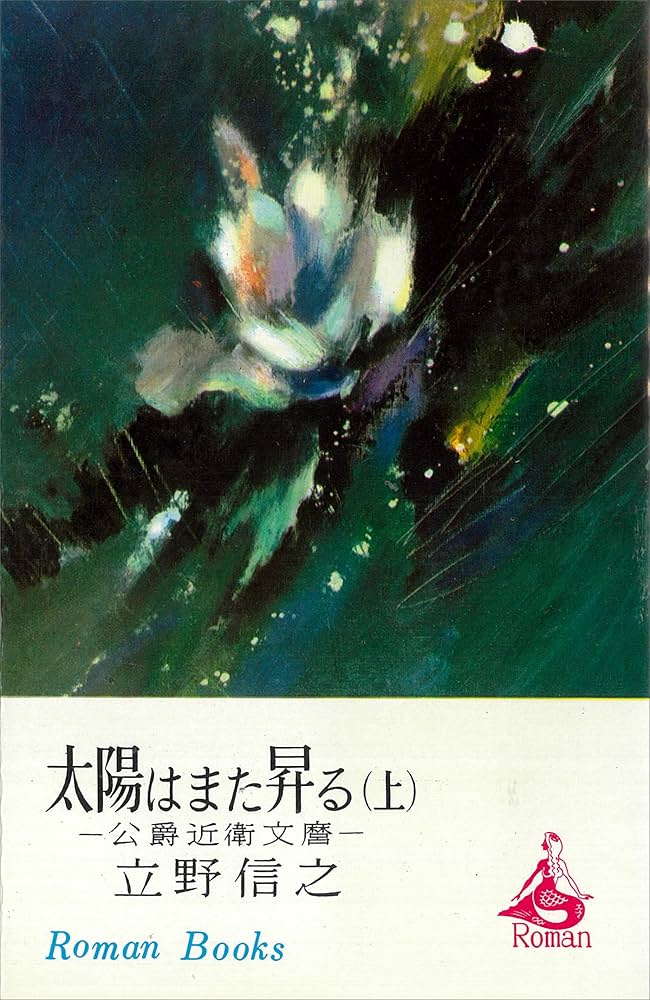
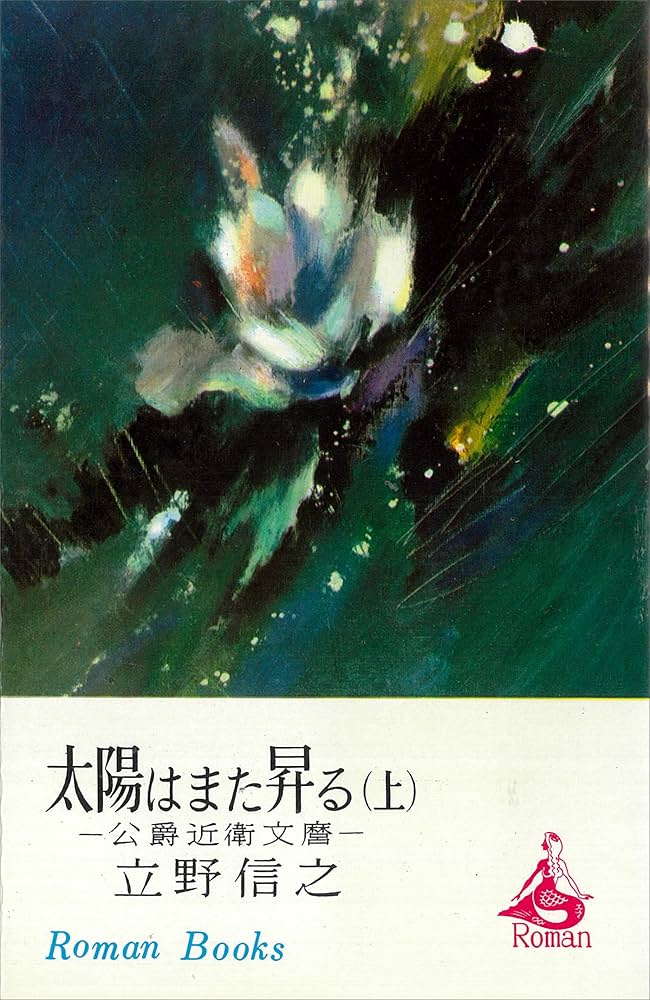
ランキング2位は、三度にわたって総理大臣を務めた昭和史の重要人物、近衛文麿の生涯を描いた『太陽はまた昇る―公爵近衛文麿』です。この作品は、戦争へと突き進む激動の時代に、国の舵取りを任された一人の公爵の苦悩と葛藤に迫ります。
物語は、第二次近衛内閣の発足から始まり、日独伊三国同盟の締結、難航する日米交渉、そして太平洋戦争開戦へと至る歴史の大きな流れを、主人公・近衛文麿の視点から描いていきます。軍部の台頭という抗いがたい力の中で、平和への道を模索し続ける近衛の姿は、読む者の胸に深く迫ります。
歴史の「もしも」を考えさせられるだけでなく、リーダーとしての孤独や重圧といった普遍的なテーマも内包した一作。歴史小説ファンならずとも、多くの示唆を得られるでしょう。



国のトップに立つ人の苦悩って、想像を絶するものがあるんだろうな。平和を願う気持ちが切ないよ。
3位『黒い花』
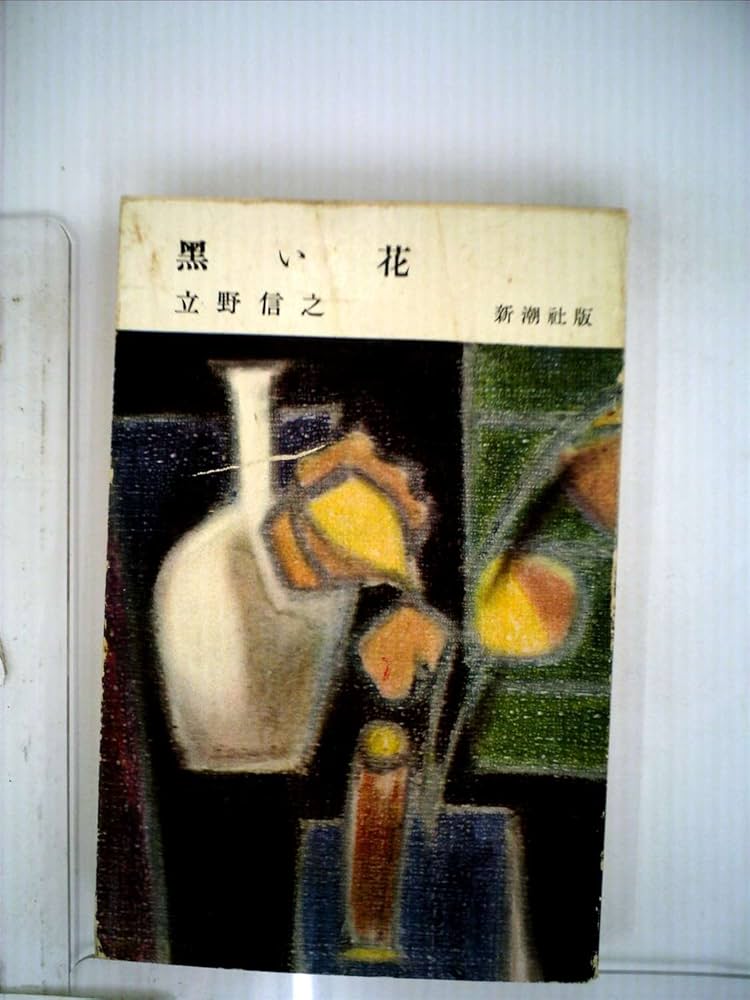
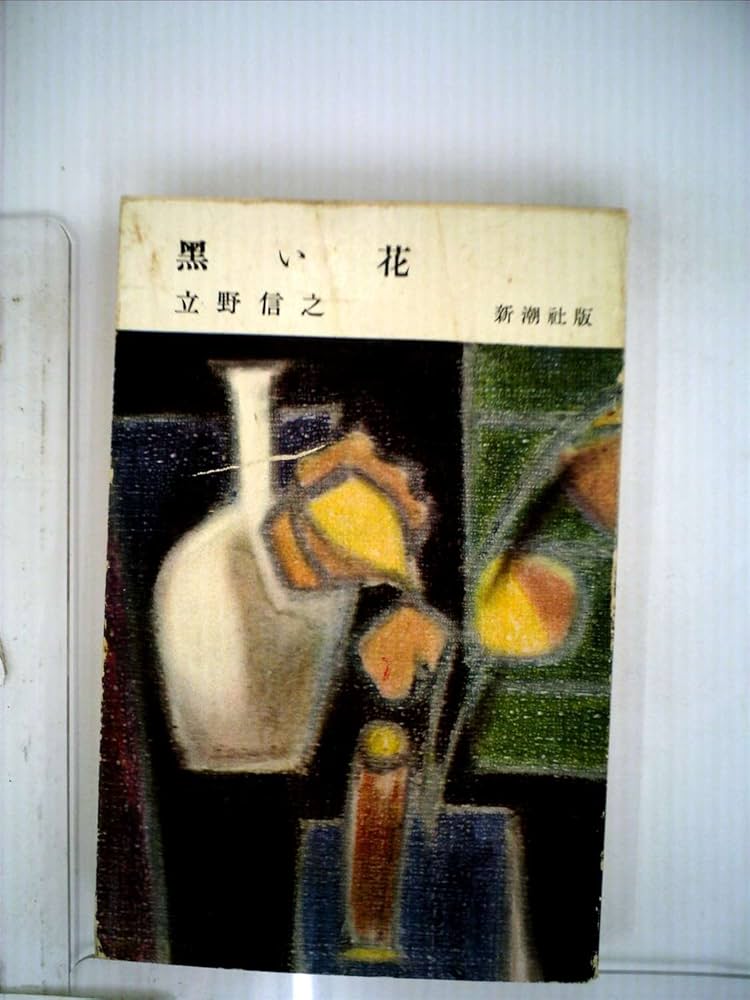
3位には、タイトルからしてミステリアスな雰囲気が漂う『黒い花』がランクインしました。立野信之の作品群の中でも、特に社会の深層に切り込んだ一作として知られています。
この作品では、戦後の日本におけるアナーキズム(無政府主義)運動に生きた人々の思想と葛藤が描かれています。立野信之の鋭い観察眼によって、理想と現実の間で揺れ動く人間の姿が浮き彫りにされており、読者は物語の世界に深く引き込まれるでしょう。
社会の矛盾や人間の複雑な心理に興味がある方に、ぜひ手に取っていただきたい作品です。



『黒い花』ってタイトル、なんだか意味深だよね…。どんな物語が隠されているのか、すごく気になるよ。
4位『明治大帝』
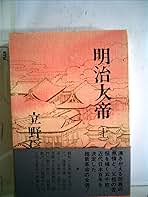
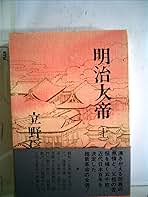
4位は、日本の近代化を象徴する偉大な君主、明治天皇の生涯を壮大なスケールで描いた歴史大作『明治大帝』です。この作品は、立野信之が長年にわたる調査と取材を重ねて完成させた、まさに畢生の大著と言えるでしょう。
幕末の動乱期に生まれ、西洋列強の脅威にさらされる中で、いかにして日本を近代国家へと導いたのか。その苦悩と決断、そして人間としての明治天皇の姿を、生き生きと描き出しています。1962年には舞台化もされるなど、多方面で高い評価を受けました。
日本の近代がどのように形作られていったのかを、その中心にいた人物の視点から深く理解できる一作。歴史好きにはたまらない読み応えです。



一人の人間が国を大きく変えていくって、すごいことだよね!わたし、こういう壮大な物語が大好きなんだ。
5位『昭和軍閥』
5位にランクインしたのは、日本の運命を大きく狂わせた「軍閥」の実態に迫る『昭和軍閥』です。なぜ軍部は暴走し、日本は破滅的な戦争へと突き進んでしまったのか。その根源を、陸軍内部の権力闘争や思想対立から解き明かしていきます。
『叛乱』でも描かれた統制派と皇道派の対立をはじめ、満州事変から太平洋戦争終結に至るまで、軍閥が形成され、そして崩壊していく過程を克明に描いています。歴史の記録者としての立野信之の真骨頂が発揮された、重厚なノンフィクション・ノベルです。
「昭和史」という時代の空気を肌で感じたい方、そして歴史の教訓を学びたいと考えるすべての方におすすめします。



軍閥って聞くと、なんだか怖いイメージがあるな…。でも、どうしてそうなったのか知るのは大事なことだよね。
6位『茫々の記―宮崎滔天と孫文』
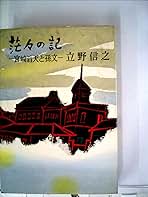
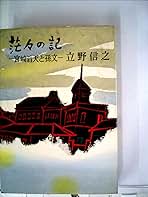
6位は、国境を越えた友情と革命への情熱を描いた『茫々の記―宮崎滔天と孫文』です。この作品は、中国革命の父・孫文を支え続けた日本人、宮崎滔天の波乱に満ちた生涯を追った物語です。
思想家であり革命家でもあった宮崎滔天が、いかにして孫文と出会い、その革命事業に身を投じていったのか。アジアの未来を憂い、理想に燃えた男たちの熱いドラマが繰り広げられます。
二人の間にある深い信頼と友情は、現代の私たちにも多くのことを教えてくれます。歴史の教科書には載らない、知られざる偉人たちの物語に触れてみませんか。



国が違っても、同じ夢に向かって頑張るって素敵だね!こういう熱い友情、わたしも憧れちゃうな。
7位『日本占領』
ランキング7位は、終戦直後の日本を描いた衝撃作『日本占領』です。敗戦によって未曽有の混乱に陥った日本を舞台に、GHQによる占領政策の下で人々がどのように生きたのかをリアルに描き出しています。
これまでの価値観が根底から覆され、新たな秩序が生まれていく中で、人々は何を考え、どのように未来を模索したのか。現代日本の原点ともいえる時代を、立野信之は鋭い筆致で描き切りました。
私たちが今生きるこの社会が、どのようにして形作られたのか。そのルーツを知る上で欠かせない一冊と言えるでしょう。



戦争が終わった後の日本って、どんな感じだったんだろう?今の平和な毎日が、当たり前じゃないって感じるね。
8位『軍隊病』
8位は、立野信之の原点ともいえる初期の代表作『軍隊病』です。自身の軍隊経験を基に書かれたこの短編集は、プロレタリア作家としての彼の地位を確立した作品として知られています。
軍隊という閉鎖的な組織の中で、人間性がどのように抑圧され、歪められていくのか。その不条理と非人間性を、兵士たちの視点から生々しく告発しています。表題作「軍隊病」をはじめ、「標的になつた彼奴」など、強烈な印象を残す作品が収められています。
立野文学の出発点を知る上で非常に重要な作品であり、その後の歴史小説とはまた違った、剥き出しのリアリズムが胸に迫ります。



本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。
9位『赤と黒』
ランキングの最後を飾るのは、明治時代に起きた大逆事件をテーマにした『赤と黒』です。この事件は、社会主義者や無政府主義者が明治天皇の暗殺を計画したとして、多数が検挙、処刑されたものです。
立野信之は、この歴史的事件の真相に迫り、国家権力によって思想が弾圧されていく恐怖と、それに抗おうとした人々の姿を描き出しました。『黒い花』と並び、社会の暗部に光を当てた重要な作品と位置づけられています。
「正義とは何か」「国家とは何か」といった重いテーマを読者に問いかける、骨太な社会派小説。歴史の闇に葬られがちな事件に、改めて目を向けるきっかけを与えてくれるでしょう。



なんだか難しそうだけど、すごく大切なことが書かれていそうだね。わたしも読んでみようかな…。
まとめ:立野信之の小説で日本の近代史を深く知る
ここまで立野信之のおすすめ小説をランキング形式でご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
直木賞受賞作の『叛乱』をはじめ、彼の作品は日本の近代史における重要な局面を切り取ったものばかりです。プロレタリア作家としての出発、思想的な転向、そして戦後の歴史小説家としての活動と、彼自身の人生もまた、日本の激動の歴史と深く結びついていました。
立野信之の小説を読むことは、単に歴史上の出来事を知るだけでなく、その時代を生きた人々の息遣いや葛藤を感じることでもあります。彼の作品を通じて、日本の近代史をより深く、そして人間味あふれる物語として体験してみてください。きっと、新たな発見があるはずです。