あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】星川清司のおすすめ小説ランキングTOP10
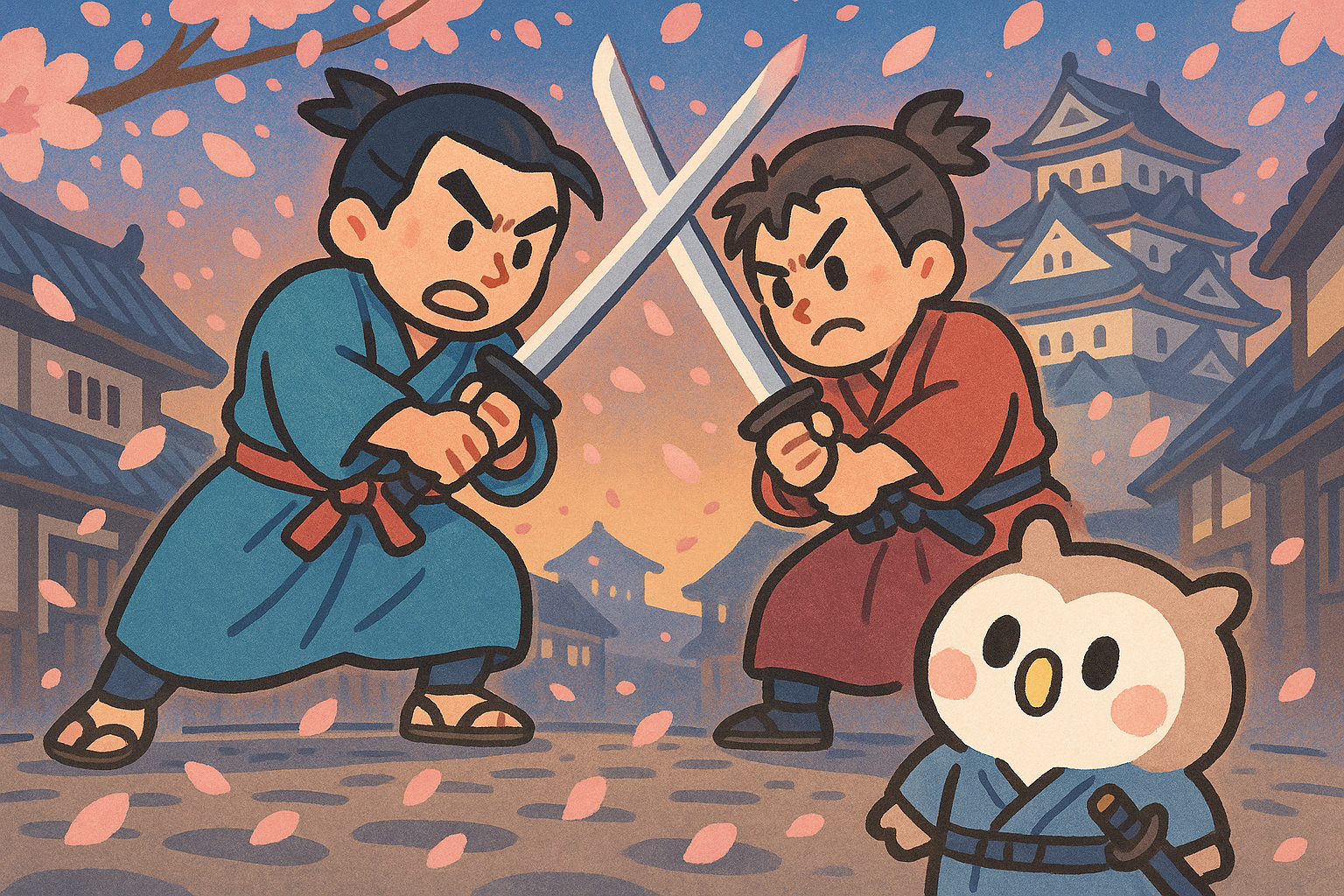
はじめに:脚本家から小説家へ、星川清司の文学世界とその魅力
星川清司(ほしかわ せいじ)は、映画やテレビドラマの脚本家として輝かしい経歴を持ちながら、味わい深い歴史小説を数多く残しました。1921年に東京で生まれた彼は、幼い頃から映画に親しみ、30歳を過ぎて脚本家の道を志します。大映京都撮影所と契約してからは、『眠狂四郎シリーズ』の初期作品など、数々のヒット作の脚本を手がけました。
脚本家として確固たる地位を築いた後、小説の執筆を始めます。1989年には、処女作である『小伝抄』で第102回直木賞を受賞。68歳2ヶ月での受賞は、当時の直木賞最年長記録として大きな話題になりました。その後も、江戸の市井に生きる人々の人情や、芸の道に生きる人間の業を巧みに描き出し、多くの読者を魅了し続けています。
星川清司の小説の選び方3つのポイント
脚本家出身という異色の経歴を持つ星川清司。その作品世界は広く、どれから読めばいいか迷ってしまうかもしれません。そこで、ここではあなたにぴったりの一冊を見つけるための3つのポイントをご紹介します。
まずは、描かれる「実在の人物」に注目するのがおすすめです。『利休』や『小村雪岱』のように、歴史上の有名な芸術家や文化人を題材にした作品が多く、彼らの知られざる生涯や苦悩に触れることができます。あなたが興味のある人物から選んでみるのも良いでしょう。
次に、江戸の「粋」な世界観に浸るという選び方もあります。『今戸橋晩景』や『江戸よいとこ』など、江戸の町を舞台に、そこに生きる人々の人情や暮らしを鮮やかに描いた作品は星川作品の真骨頂です。江戸時代の雰囲気が好きな方には特におすすめです。
そして、受賞歴を参考にするのも一つの方法です。デビュー作にして直木賞を受賞した『小伝抄』は、初めて星川作品に触れる方にぴったりです。また、泉鏡花文学賞の候補にもなった『入相の鐘』など、文学的な評価の高い作品から読んでみるのも、その魅力に深く触れるきっかけになるでしょう。
【2025年最新】星川清司のおすすめ小説人気ランキングTOP10
それでは、星川清司のおすすめ小説をランキング形式でご紹介します。脚本家として培われた巧みな構成力と、人間味あふれる登場人物が織りなす物語は、どれもあなたを江戸の奥深い世界へと誘ってくれるでしょう。数々の名作の中から、特に人気の高い10作品を厳選しました。気になる作品を見つけて、ぜひ手に取ってみてください。
1位『小伝抄』
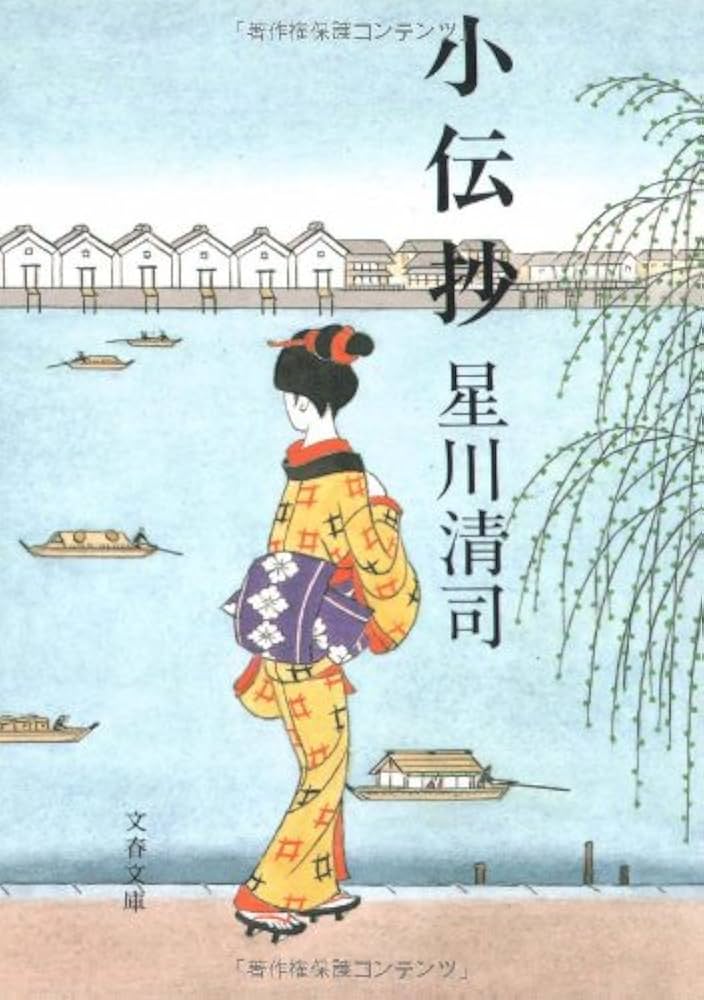
星川清司の小説家としてのデビュー作であり、第102回直木賞を受賞した記念碑的な作品です。68歳という当時としては最高齢での受賞は、大きな話題を呼びました。物語は、江戸時代の女絵師・小伝の生涯を、彼女に絵を教えた狩野派の絵師の視点から描いています。
色香あふれる小伝の奔放な生き様と、彼女を取り巻く男たちの姿が、熟練の筆致で鮮やかに描き出されます。脚本家として長年培ってきた構成力がいかんなく発揮されており、読者を一気に物語の世界へ引き込みます。星川文学の出発点として、まず最初に読んでおきたい一冊です。
 ふくちい
ふくちいデビュー作で直木賞ってすごいよね。68歳で新しい挑戦をする姿に勇気をもらえるな。
2位『小村雪岱』


大正から昭和初期にかけて活躍した装幀家・小村雪岱(こむら せったい)の生涯を描いた伝記的小説です。泉鏡花の著作をはじめ、数多くの本の装幀を手がけたことで知られる雪岱。その洗練された美意識と、芸術に捧げた情熱的な人生が描かれています。
華やかな大正ロマンの世界を背景に、雪岱の芸術家としての葛藤や、彼を取り巻く人々との交流が丁寧に綴られています。美しい日本語で紡がれる物語は、まるで一冊の美しい装幀本を眺めているかのような豊かな気持ちにさせてくれます。芸術やデザインに興味がある方には特におすすめの作品です。



装幀家が主人公って珍しいよね。本が好きな人なら絶対楽しめると思うな。
3位『櫓の正夢―鶴屋南北闇狂言』
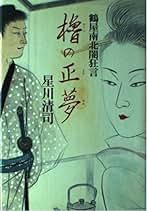
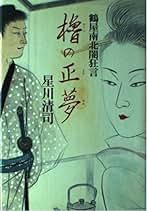
『東海道四谷怪談』などで知られる江戸時代の狂言作者、四代目鶴屋南北(つるや なんぼく)を主人公にした作品です。人間の欲望や愛憎を赤裸々に描き出し、当代きっての人気作者となった南北。その創作の裏にあったであろう、彼の壮絶な人生と執念に迫ります。
歌舞伎や江戸の演劇の世界を背景に、南北の狂気と才能が鮮烈に描かれています。人間の心の闇を覗き込むような、スリリングな物語展開は圧巻の一言。星川清司の新たな一面を発見できる、読み応えのある一冊です。



鶴屋南北の闇が深くてゾクゾクするよ。人間の業を描かせたら、やっぱりすごい作家さんだね。
4位『今戸橋晩景』
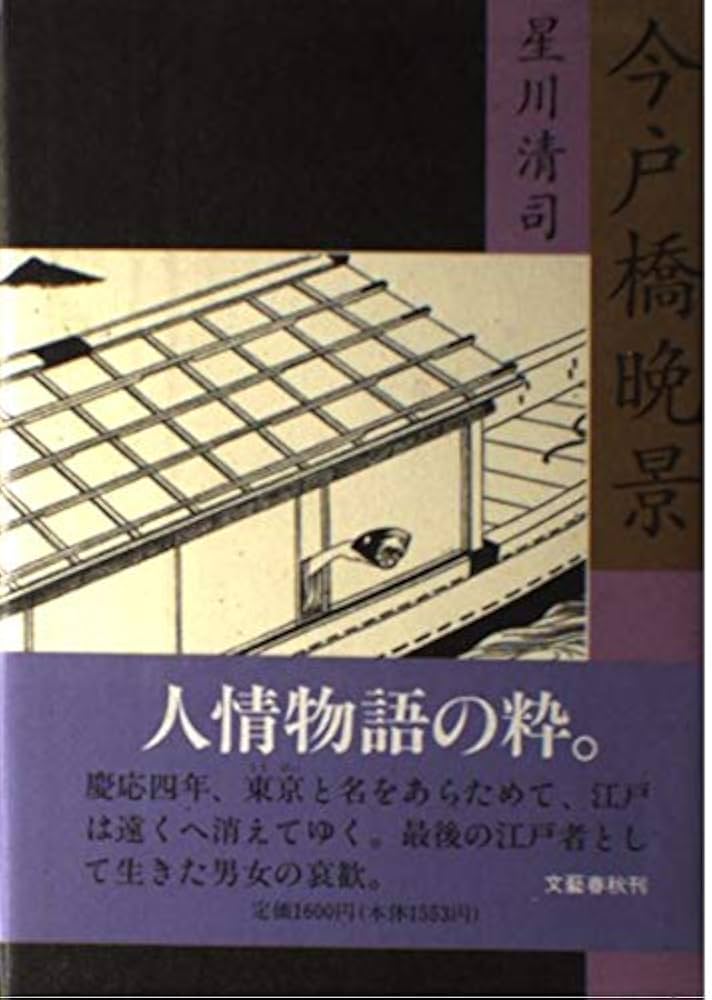
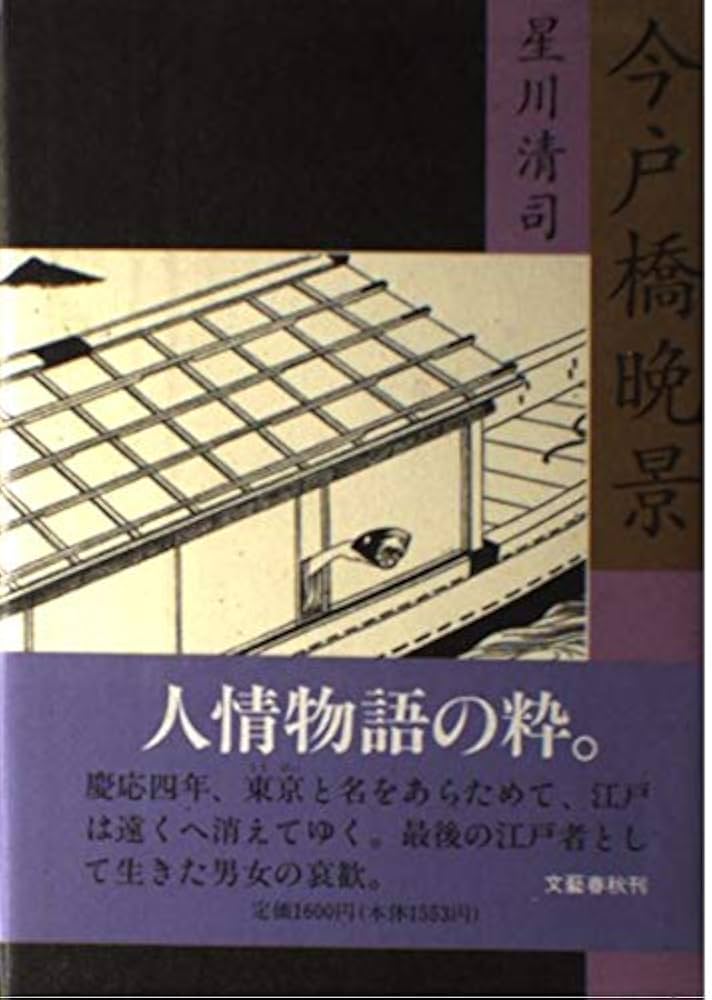
江戸の今戸橋を舞台に、そこで暮らす人々のささやかな日常と哀歓を描いた作品です。主人公は、かつては腕利きの職人だった老人。時代の移ろいとともに変わりゆく江戸の町で、彼は何を想い、どのように生きていくのか。その姿がしみじみとした筆致で描かれます。
派手な事件が起こるわけではありませんが、登場人物一人ひとりの息づかいが聞こえてくるような、丁寧な人物描写が魅力です。読後は、まるで江戸の町を散歩したかのような、温かくも切ない余韻に包まれるでしょう。江戸の情緒にどっぷりと浸りたい夜におすすめの一冊です。



江戸の日常って感じがして、すごく落ち着くんだ。こういうしっとりした話もいいよね。
5位『夢小袖』
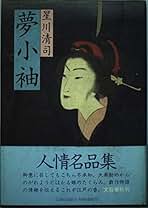
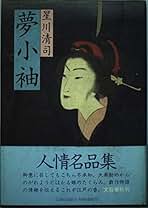
江戸の町を舞台に、美しい小袖を巡って繰り広げられる人間模様を描いた作品です。一枚の着物が、人々の運命をどのように変えていくのか。愛憎、嫉妬、そして希望が、鮮やかな小袖の柄のように織りなされていきます。
星川清司の真骨頂ともいえる、江戸の職人世界の描写が光る一作です。着物に込められた人々の想いや、それを生み出す職人たちの技と心意気が丁寧に描かれており、日本の伝統文化の奥深さに改めて気づかされます。物語の結末には、切なくも美しい感動が待っています。



着物をめぐる話ってだけでワクワクする!職人さんのこだわりとか、読んでてすごく楽しいんだ。
6位『入相の鐘』
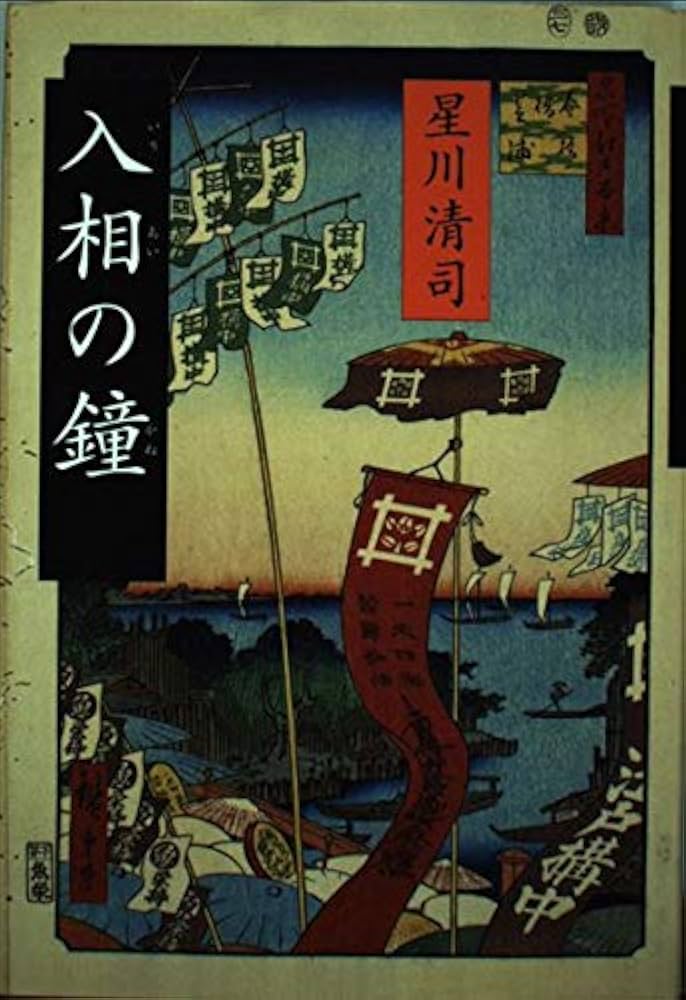
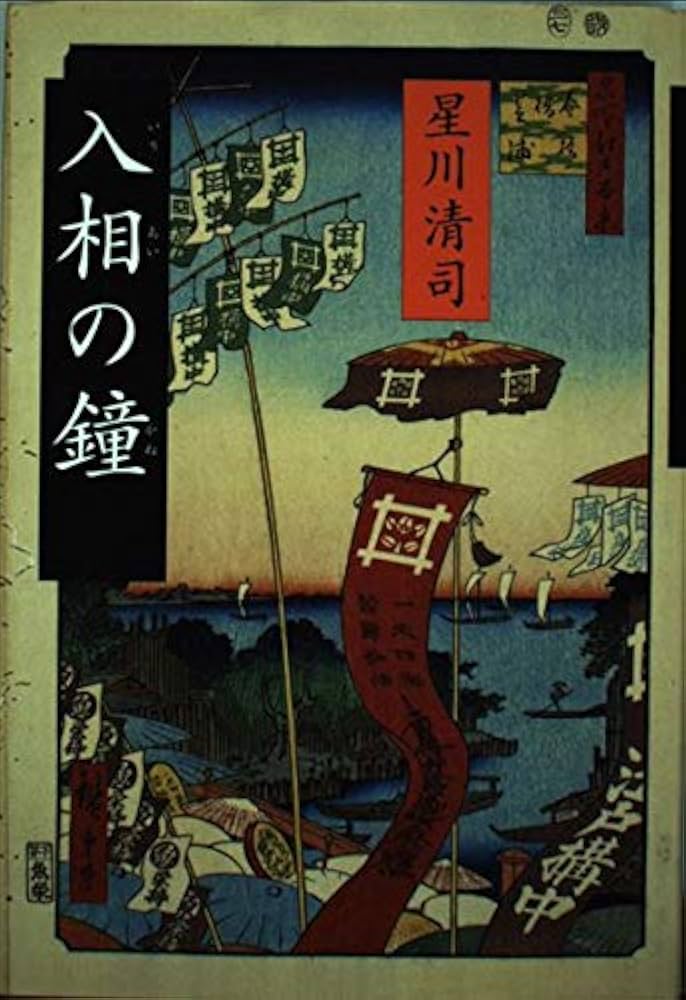
第26回泉鏡花文学賞の候補作にもなった、文学的評価の高い一冊です。物語は、ある寺の鐘を巡る人々の因縁と、そこに秘められた悲しい過去を解き明かしていく構成になっています。静かな筆致の中に、人間のどうしようもない業や情念が描かれており、読者の心を深く揺さぶります。
ミステリーのような趣もあり、ページをめくる手が止まらなくなるでしょう。星川清司の巧みなストーリーテリングと、人間の内面に深く迫る洞察力が融合した傑作です。じっくりと物語の世界に浸りたい方におすすめします。



鐘にそんな過去があったなんて…。人間の業って深くて、ちょっと怖くなっちゃうな。
7位『おかめひょっとこ』


江戸の庶民の暮らしを、ユーモアとペーソスを交えて描いた作品集です。表題作の「おかめひょっとこ」をはじめ、市井に生きる人々の何気ない日常の中に潜む、おかしみや哀しみを鮮やかに切り取っています。
登場するのは、決して特別ではない、どこにでもいるような人々。しかし、彼らの生き様には、たくましさや優しさがあふれています。読めば心がほっこりと温かくなるような、人情味あふれる物語ばかりです。少し疲れた時に手に取れば、明日への活力がもらえるかもしれません。



江戸の人たちの話、面白くて好きだな。みんな一生懸命生きてて、応援したくなっちゃうよ。
8位『カツドウヤ繁昌記』
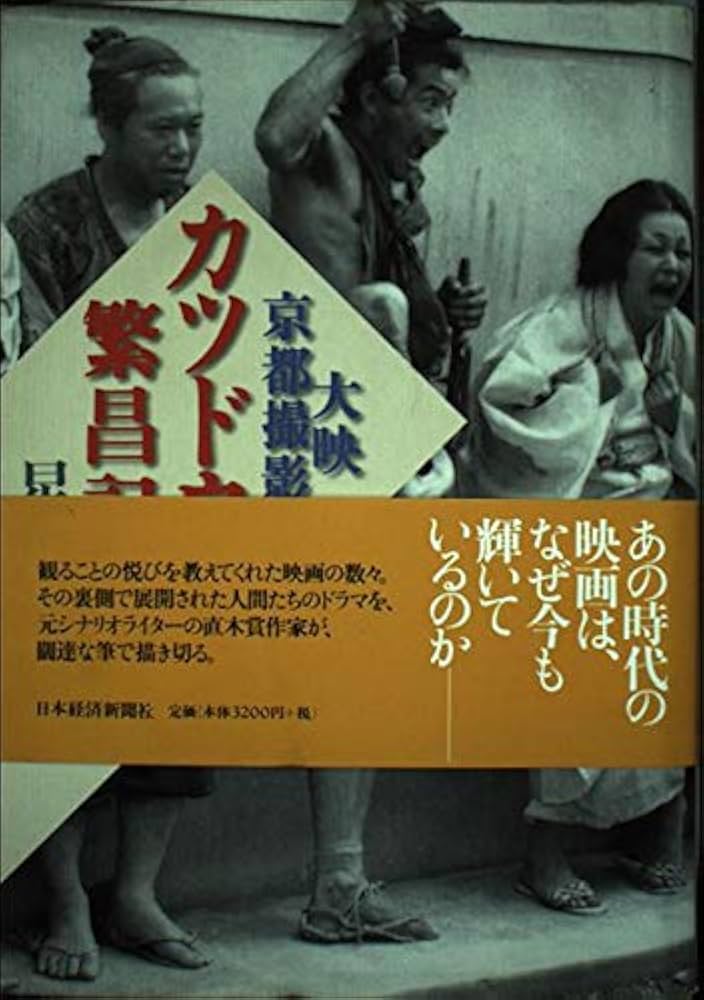
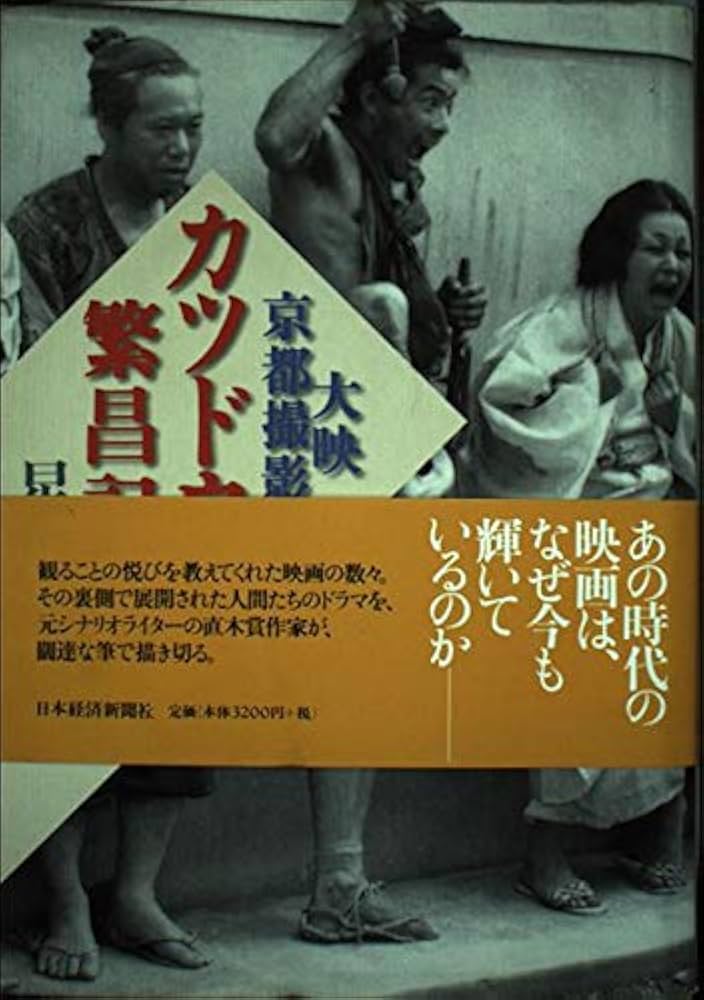
星川清司自身の経験が色濃く反映された、自伝的色彩の濃い一作です。戦後の日本映画界を舞台に、「カツドウヤ」と呼ばれた映画人たちの情熱や葛藤、そして映画作りの現場の熱気を生き生きと描いています。
脚本家として市川雷蔵ら多くの名優、名監督と仕事をしてきた著者だからこそ描ける、リアルな撮影所の日常が魅力です。映画が娯楽の王様だった時代の活気と、そこに生きた人々の人間臭さが伝わってきます。映画ファンはもちろん、一つの仕事に情熱を注ぐ人々の物語が好きな方にもおすすめです。



昔の映画作りの現場って、こんなに熱かったんだね。わたしもこの時代に生まれてみたかったな。
9位『江戸よいとこ』


江戸の四季の移ろいとともに、そこに生きる人々の日常を切り取った珠玉の短編集です。花見や祭り、雪景色といった江戸ならではの風物詩を背景に、様々な人間ドラマが繰り広げられます。
一篇一篇は短いながらも、読後には深い余韻が残ります。星川清司の洗練された文章が、江戸の町の空気感を見事に再現しており、まるでタイムスリップしたかのような感覚を味わえるでしょう。江戸の粋や風情に触れたい方にぴったりの一冊です。



これを読むと、江戸の町を散歩してる気分になるんだ。四季折々の風景が目に浮かぶようだよ。
10位『利休』
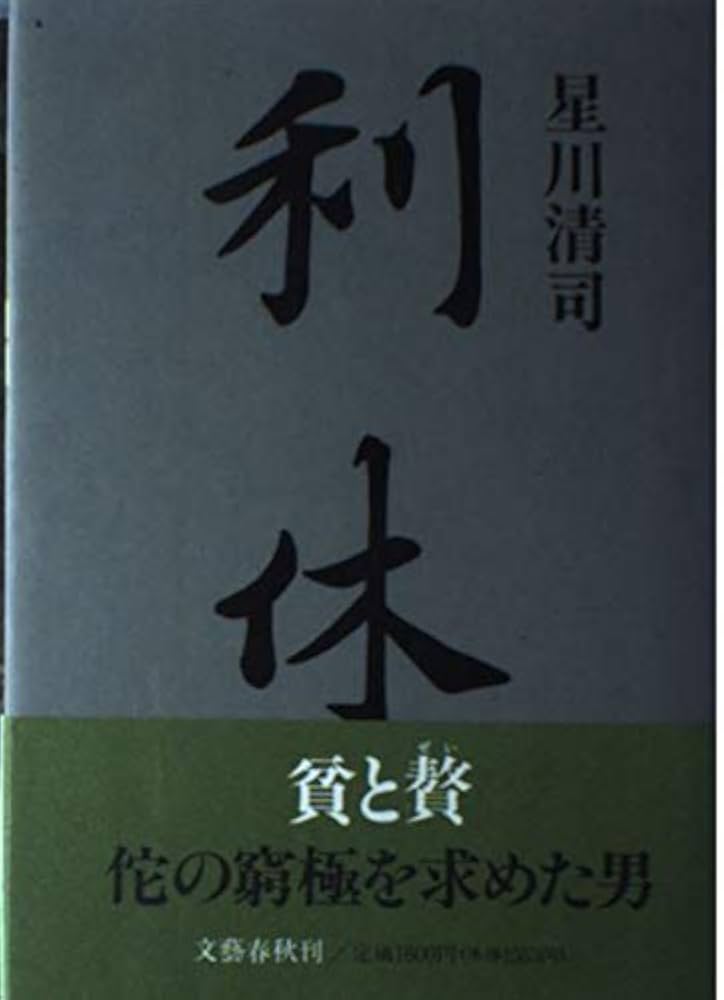
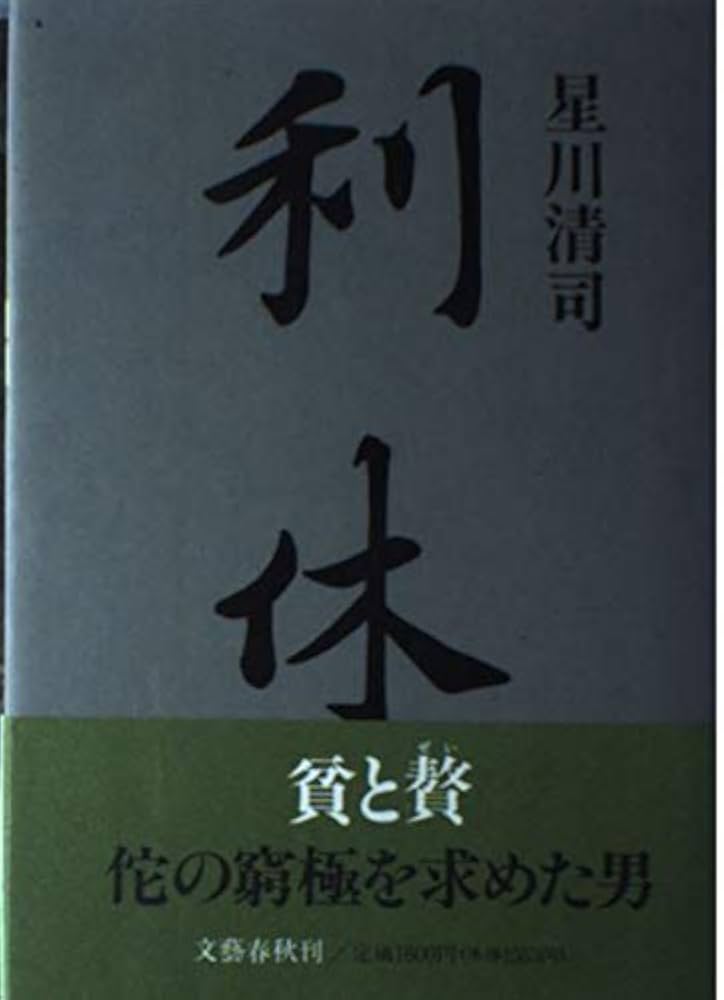
安土桃山時代の茶人・千利休の生涯を、独自の視点で描いた歴史小説です。勅使河原宏監督による同名の映画も有名ですが、そちらは野上彌生子の小説『秀吉と利休』を原作としています。天下人・豊臣秀吉との緊張感あふれる関係を軸に、美を追求し続けた利休の孤高の精神に迫ります。
なぜ利休は、権力に屈することなく自らの美学を貫き、死を選ばなければならなかったのか。その謎に満ちた最期まで、息をのむような展開で描かれます。茶道の世界の奥深さとともに、時代に翻弄されながらも信念を貫いた一人の人間の生き様が胸を打つ作品です。



利休の美学、かっこいいね。自分の信じるもののために命をかけるって、すごい覚悟だよ。
星川清司の全小説作品一覧
星川清司が遺した小説作品は、脚本家としての仕事と並行して執筆された、まさに珠玉の作品群です。ここでは、彼の発表した主な小説を一覧でご紹介します。ランキングで気になった作品以外にも、あなたの心に響く一冊が隠れているかもしれません。
| 発表年 | 作品名 |
|---|---|
| 1990年 | 小伝抄 |
| 1990年 | おかめひよっとこ |
| 1991年 | 夢小袖 |
| 1993年 | 櫓の正夢―鶴屋南北闇狂言 |
| 1994年 | 利休 |
| 1995年 | 今戸橋晩景 |
| 1996年 | 小村雪岱 |
| 1997年 | 江戸よいとこ |
| 1997年 | 大映京都撮影所カツドウヤ繁昌記 |
| 1998年 | 入相の鐘 |
まとめ:星川清司の小説を読んで江戸の粋に触れよう
脚本家として映像の世界で腕を磨き、小説家として円熟の境地を切り拓いた星川清司。その作品は、巧みな物語の運びと、江戸の市井に生きる人々への温かい眼差しに満ちています。歴史上の人物の知られざる一面や、職人たちの心意気、そして庶民のささやかな日常の輝きを、見事な筆致で描き出しました。
今回ご紹介したランキングを参考に、ぜひ気になる一冊を手に取ってみてください。ページをめくれば、そこには活気と人情にあふれた江戸の世界が広がっているはずです。星川清司の小説を通して、忘れかけていた日本の「粋」な心に触れる、豊かな読書体験をしてみてはいかがでしょうか。




