あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】森敦の小説おすすめ人気ランキングTOP5

はじめに:61歳で芥川賞を受賞した孤高の作家・森敦とは
森敦(もり あつし)は、1912年に長崎市で生まれた小説家です。旧制第一高等学校を中退後、横光利一に師事し、1934年に22歳で新聞に小説『酩酊船』を連載して文壇デビューを果たしました。同年には太宰治や檀一雄らと共に同人誌『青い花』を創刊するなど、若くしてその才能を嘱望されます。
しかし、その後長い間文壇から姿を消し、日本各地を放浪する生活を送りました。印刷会社などで働きながら執筆を続け、デビューから約40年の時を経た1973年に発表した『月山』で、翌1974年に第70回芥川賞を受賞し、大きな話題を呼びました。受賞時の年齢は62歳で、当時としては史上最高齢の記録でした。その後も『われ逝くもののごとく』で野間文芸賞を受賞するなど、独自の文学世界を築き上げ、1989年に77歳でその生涯を閉じました。
森敦の小説おすすめ人気ランキングTOP5
ここからは、森敦のおすすめ小説をランキング形式でご紹介します。彼の作品は、自身の長い放浪生活や人生経験が色濃く反映されているのが特徴です。
生と死、現世と幽界のあわい、そして日本の土着的な風土など、深遠なテーマを扱いながらも、その文章は読む者の魂を揺さぶる力強さに満ちています。今回は、芥川賞受賞作『月山』をはじめ、森敦文学の神髄に触れられる5作品を厳選しました。ぜひ、気になる一冊を見つけてみてください。
1位『月山』
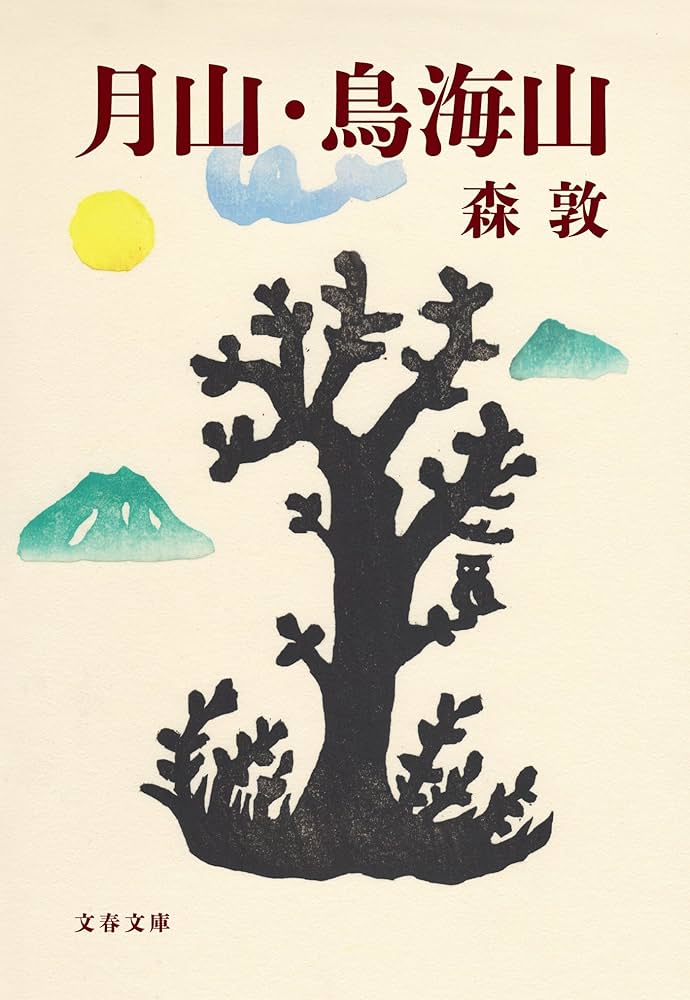
森敦の名を世に知らしめた、第70回芥川賞受賞作です。主人公の「わたし」が、あてもなく辿り着いた山形県の霊山・月山の麓にあるお寺で一冬を過ごす物語。雪に閉ざされた村は、まるで現世から隔離されたような静謐な空気に包まれています。
村人たちとの交流の中で垣間見える、死生観や土着の文化。厳しい自然と共に生きる人々の姿を通して、この世とあの世の境界が溶け合っていくような、幻想的な世界が描かれます。物語に大きな事件は起こりませんが、独特の「ですます」調の文体と、じんわりと心に染み渡るような情景描写が、読者を幽玄の世界へと誘います。1979年には映画化もされた、森敦文学の最高峰と名高い一作です。
 ふくちい
ふくちいわたしもこの世ならぬところに迷い込んでしまったみたい…。静かな世界にどっぷり浸れるのがたまらないんだよね。
2位『われ逝くもののごとく』


森敦が晩年に心血を注いで書き上げた、畢生(ひっせい)の長編大河小説。1987年に第40回野間文芸賞を受賞した作品です。物語の舞台は、著者自身も青春時代を過ごした山形県の庄内平野です。
「死」の世界を描いた『月山』と対をなす「生」の物語とも言われ、庶民の生と死が混然一体となった「生死一如」の世界観が色濃く反映されています。現実なのか幻なのか、その境界が曖昧になるような不思議な読書体験は、まさに森敦文学の真骨頂。700ページ近い大作ですが、ページをめくる手が止まらなくなるでしょう。



壮大な物語に圧倒されちゃった!サキさん一家の生き様が、力強く心に響くんだよ。
3位『鳥海山』
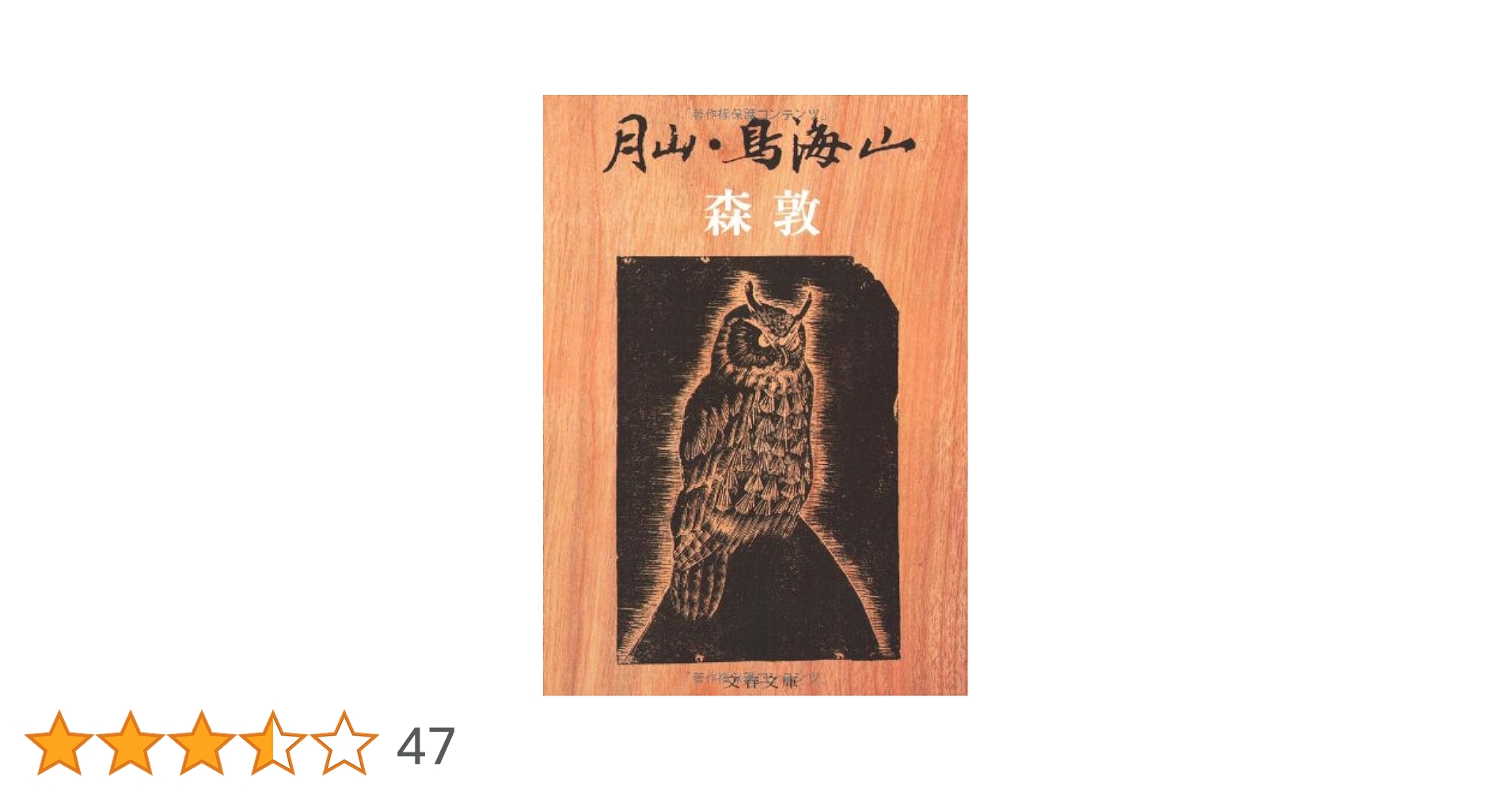
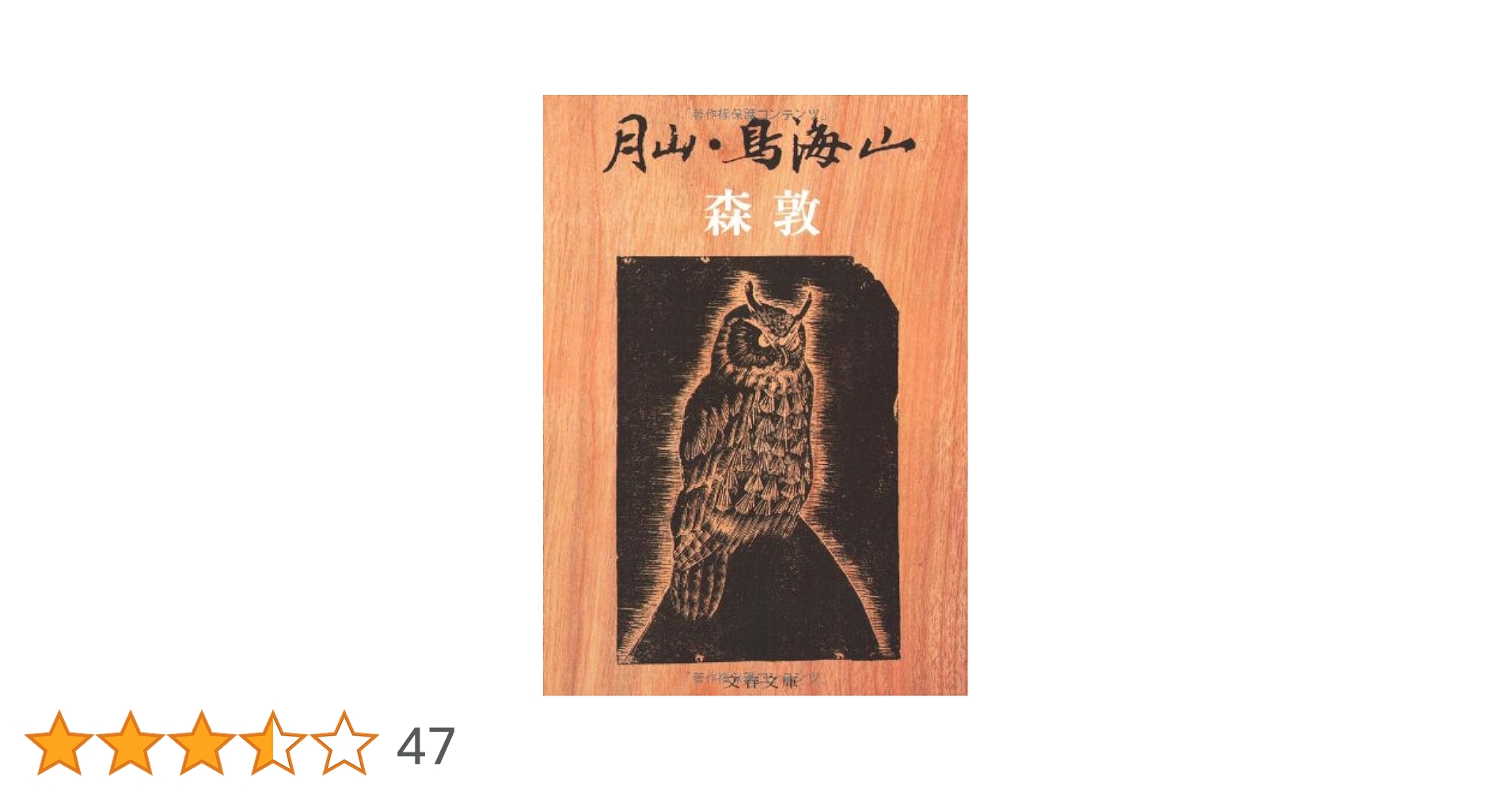
芥川賞受賞作『月山』の姉妹編とも評される短編集です。文庫版では『月山』と一緒に収録されていることが多く、ぜひあわせて読んでほしい一冊。物語のモチーフとなるのは、庄内平野を挟んで月山と対峙するようにそびえる鳥海山です。
「死の山」としての月山に対し、鳥海山は「生の山」として対照的に描かれています。『月山』で雪深い世界にいた「わたし」が、光り輝く鳥海山を望む峠へと向かう姿は、まさに再生の物語。閉ざされた世界から開かれた世界へと向かう、どこか明るい光を感じさせる作品群が、読者の心に新たな希望を灯してくれるでしょう。



『月山』を読んだあとに読むと、光が差してくる感じがしていいんだ。セットで読むのが絶対おすすめだよ!
4位『浄土』
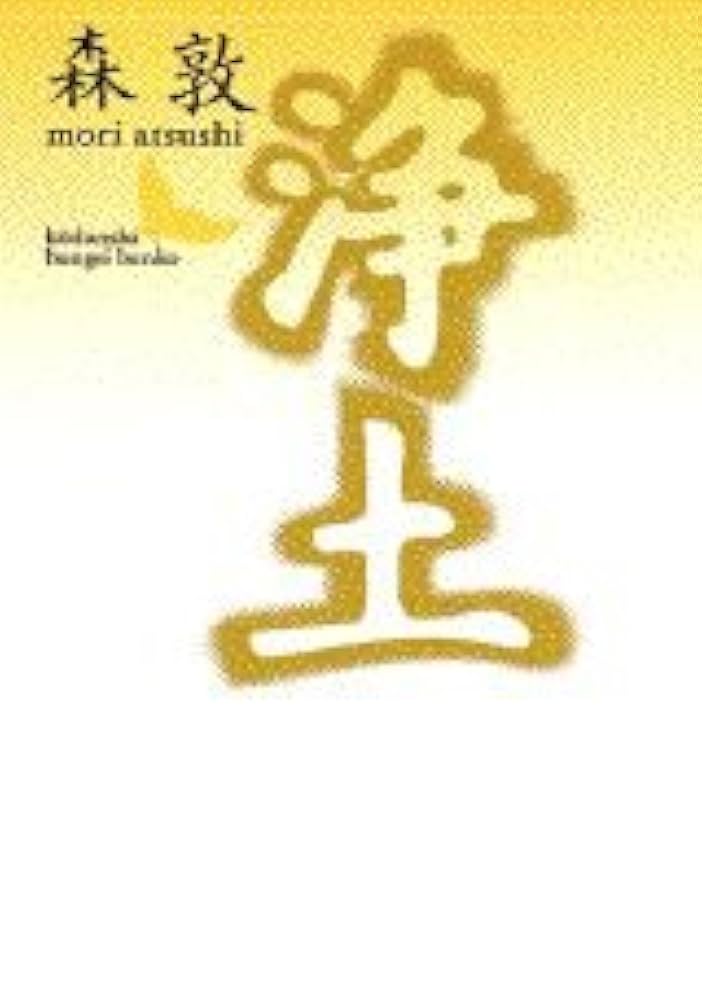
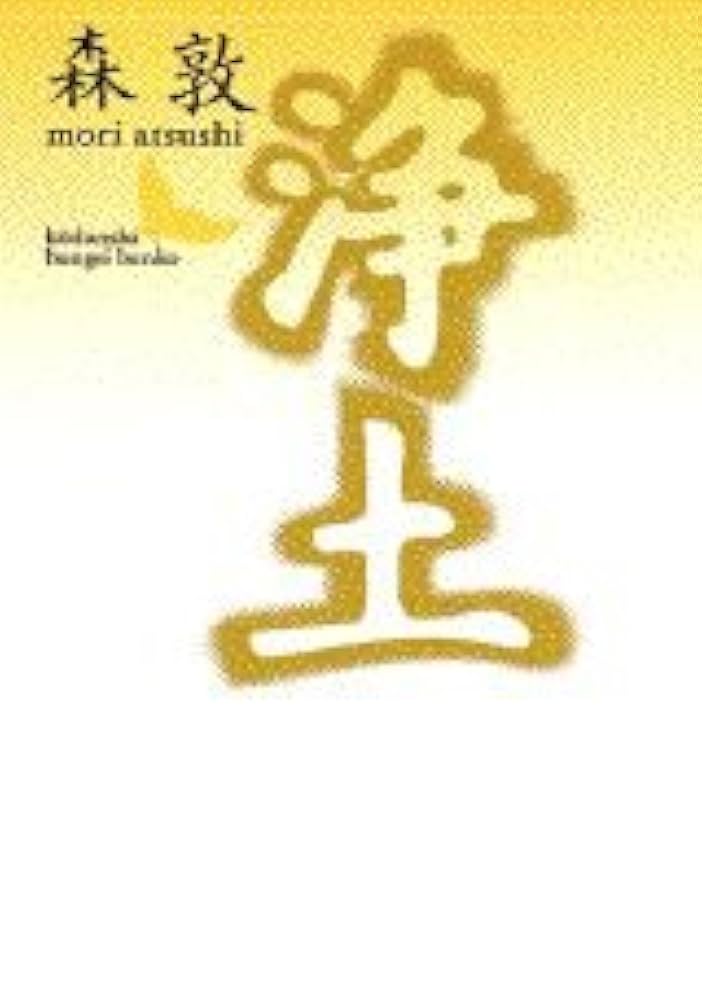
表題作「浄土」は、著者自身の幼少期の体験が色濃く反映された私小説的な作品。物語は、かつて暮らした京城(現在のソウル)での、一人の少女との淡い思い出から始まります。
幼い日の記憶と、老いた現在の視点が交錯しながら、人生の至福や仏教的な死生観が静かに描かれていきます。著者が生涯をかけて探求した、静謐で美しい精神世界に触れることができる一冊です。



なんだか懐かしくて、胸がキュッとなるんだよね。美しい文章にうっとりしちゃうな。
5位『わが青春 わが放浪』
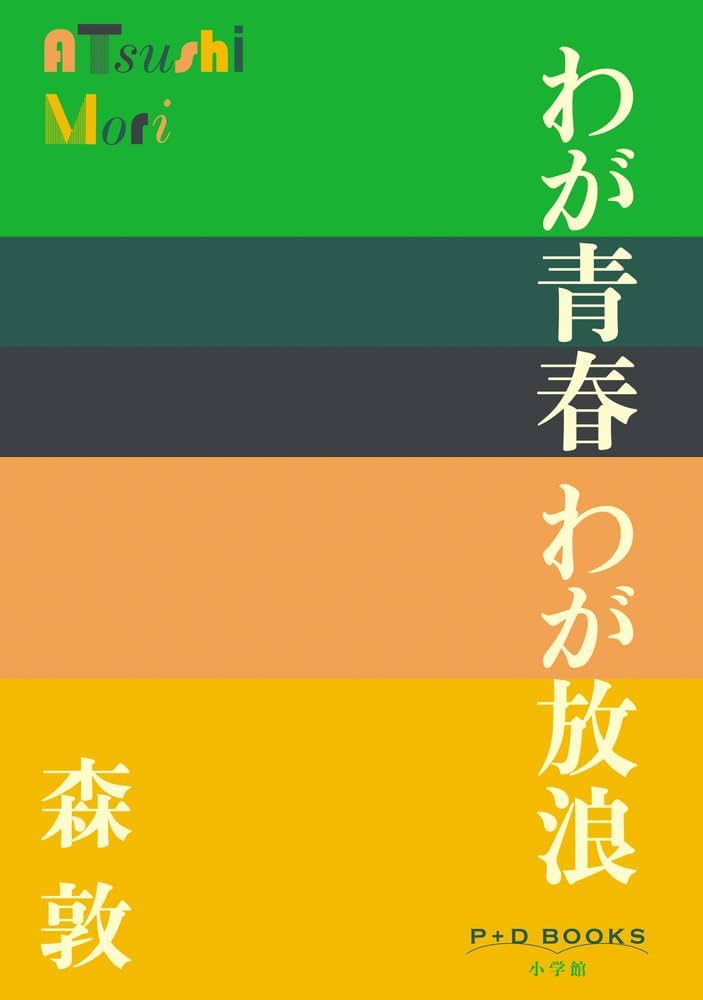
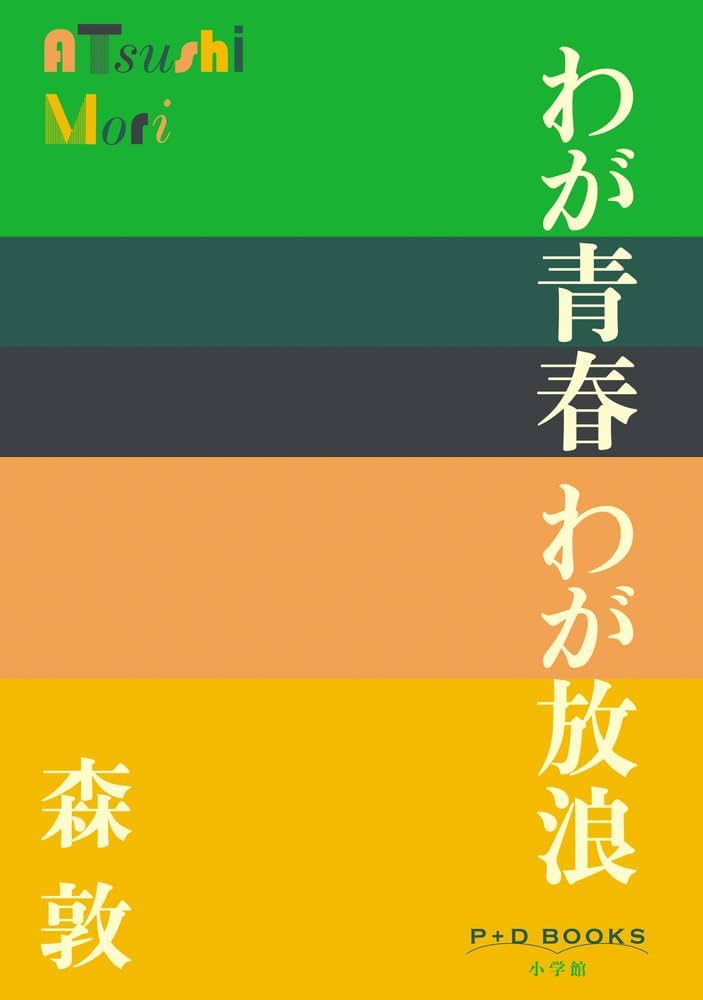
森敦の自伝的な随想集で、彼の人生と文学の背景を知る上で欠かせない一冊です。22歳で華々しくデビューしながらも、なぜ約40年もの間、文壇から離れ放浪生活を送ったのか。本書では、これまであまり語られてこなかった空白の期間が、彼自身の言葉で生き生きと綴られています。
師と仰いだ横光利一への思慕、そして太宰治や檀一雄といった同時代の文豪たちとの赤裸々な交友録は、さながら小説のような面白さです。芥川賞受賞に至るまでの道のりを知ることで、彼の作品をより深く味わうことができるでしょう。森敦という作家の人間的な魅力に迫る、入門書としてもおすすめです。



太宰治たちとのエピソードが面白い!作家の裏側をのぞいているみたいで、わくわくするよ。
おわりに:森敦文学の深遠な世界を旅しよう
森敦の文学は、彼自身の長い放浪生活と実体験に深く根ざしています。その作品世界は、生と死、現実と幻想が溶け合う「幽明界」を思わせる独特の雰囲気に満ちています。静かな抒情性の中に、数学的な思考に裏打ちされた強固な論理が潜んでいるのも大きな特徴です。
一見、難解に感じられるかもしれませんが、その文章の奥には、土地の風土に根ざした人々の営みや、普遍的な魂の救済といったテーマが横たわっています。今回ご紹介した5作品は、いずれも森敦文学の深遠な世界への入り口となるものばかりです。ぜひ一冊手に取り、その唯一無二の魅力に触れてみてください。きっと、あなたの心に残る一節が見つかるはずです。


