あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】佐木隆三のおすすめ小説ランキングTOP15

佐木隆三の小説世界へようこそ!おすすめ人気作品をランキングで徹底解説
実際に起きた事件をベースに、人間の心の奥深くを描き出すノンフィクションノベル。そのジャンルで独自の地位を築いた作家、それが佐木隆三です。彼の作品は、ただ事件の概要をなぞるだけではありません。
徹底的な取材を通して、犯罪者の生い立ちや社会の底辺で生きる人々の現実に迫ります。この記事では、そんな佐木隆三の魅力あふれる小説の中から、特におすすめの作品をランキング形式でご紹介します。人間の複雑さや社会の矛盾を鋭くえぐる、彼の唯一無二の世界に触れてみましょう。
まずは知っておきたい!ノンフィクションノベルの巨匠・佐木隆三とは
佐木隆三は、1937年生まれの小説家です。製鉄所に勤務しながら執筆活動を始め、1963年に「ジャンケンポン協定」で新日本文学賞を受賞し、作家デビューを果たしました。彼の名を一躍有名にしたのが、実際の事件を徹底的な取材に基づいて小説として再構築する「ノンフィクション・ノベル」という独自の手法でした。
1976年には、連続殺人犯をモデルにした『復讐するは我にあり』で直木賞を受賞。その後も裁判傍聴をライフワークとし、数々の犯罪事件や社会の底辺で生きる人々に光を当てた作品を発表し続けました。2015年に亡くなるまで、人間の内面に潜む闇と光を描き続けた、まさに「ノンフィクションノベルの巨匠」と呼ぶにふさわしい作家です。
佐木隆三のおすすめ小説人気ランキングTOP15
ここからは、いよいよ佐木隆三のおすすめ小説をランキング形式でご紹介します。直木賞受賞作から、映画化された話題作、そして社会に大きな衝撃を与えた事件の深層に迫る作品まで、彼の多岐にわたる執筆活動の軌跡をたどります。
どの作品も、人間の複雑な心理や社会の矛盾を鋭く描き出しており、一度読んだら忘れられない強烈な印象を残すものばかりです。あなたにとって特別な一冊が、このランキングの中からきっと見つかるはずです。
1位『身分帳』
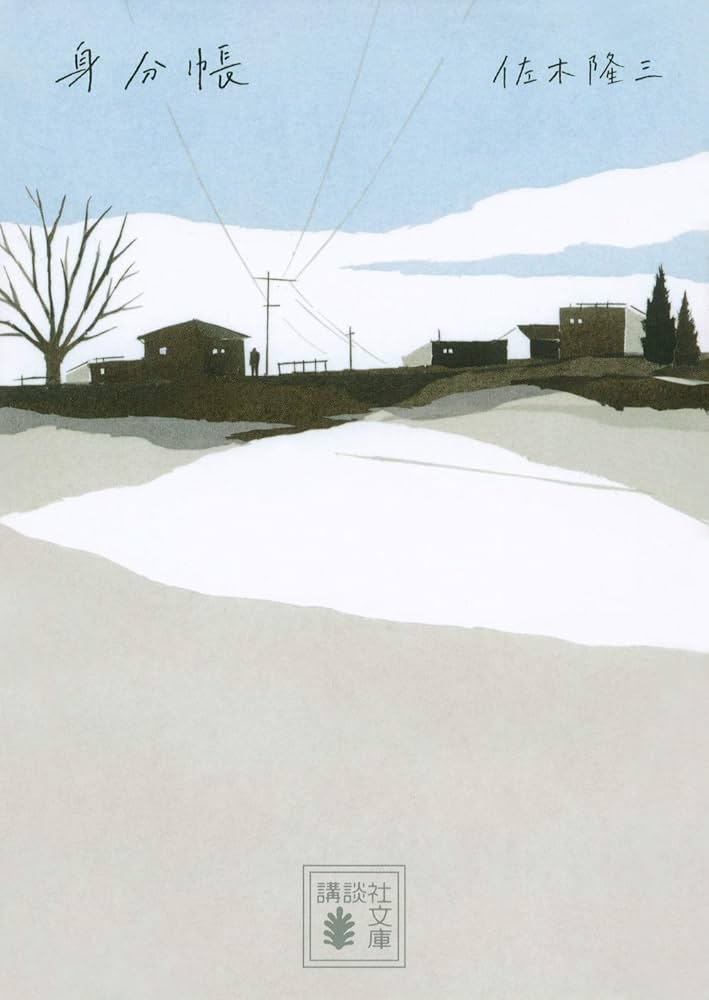
堂々の1位は、佐木隆三の優しさが滲み出る傑作『身分帳』です。人生の大半を刑務所で過ごした元ヤクザの男が、社会の冷たい風に吹かれながらも、必死に更生しようともがく日々を描いています。
この作品は、実際に佐木が取材した人物をモデルにしており、そのリアリティは圧巻です。人間の再生の困難さと、それでも失われない希望を丁寧に描き出し、1991年には伊藤整文学賞を受賞しました。近年、役所広司さん主演で『すばらしき世界』として映画化されたことでも大きな話題を呼びました。
 ふくちい
ふくちい主人公の不器用だけど懸命な生き様に涙が止まらなかったよ。社会の厳しさと、それでも残る人の温かさが胸に刺さるんだ。
2位『復讐するは我にあり』
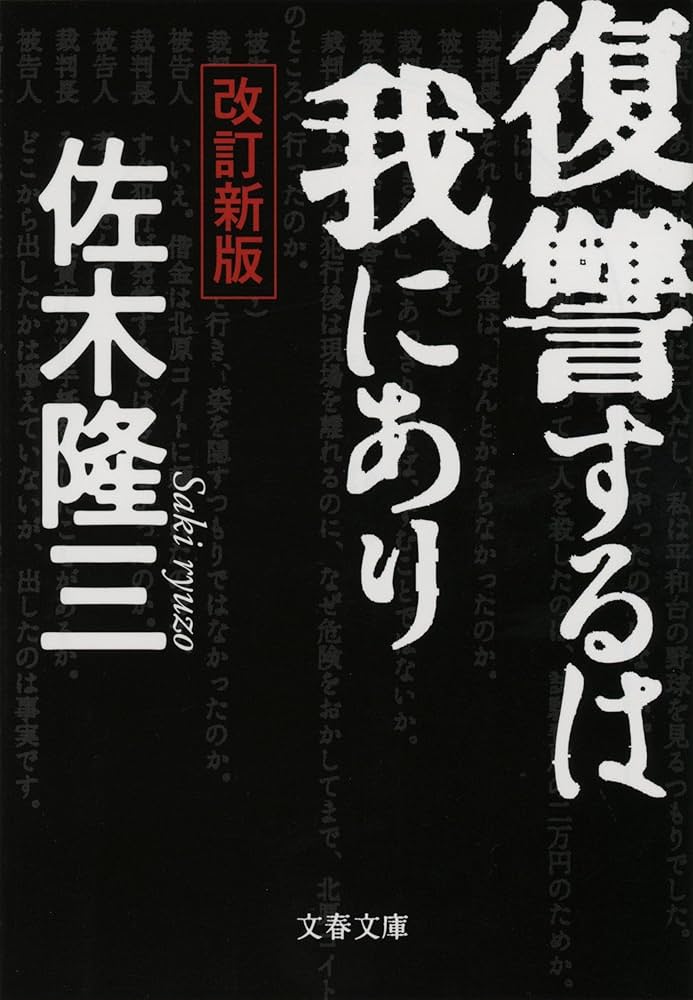
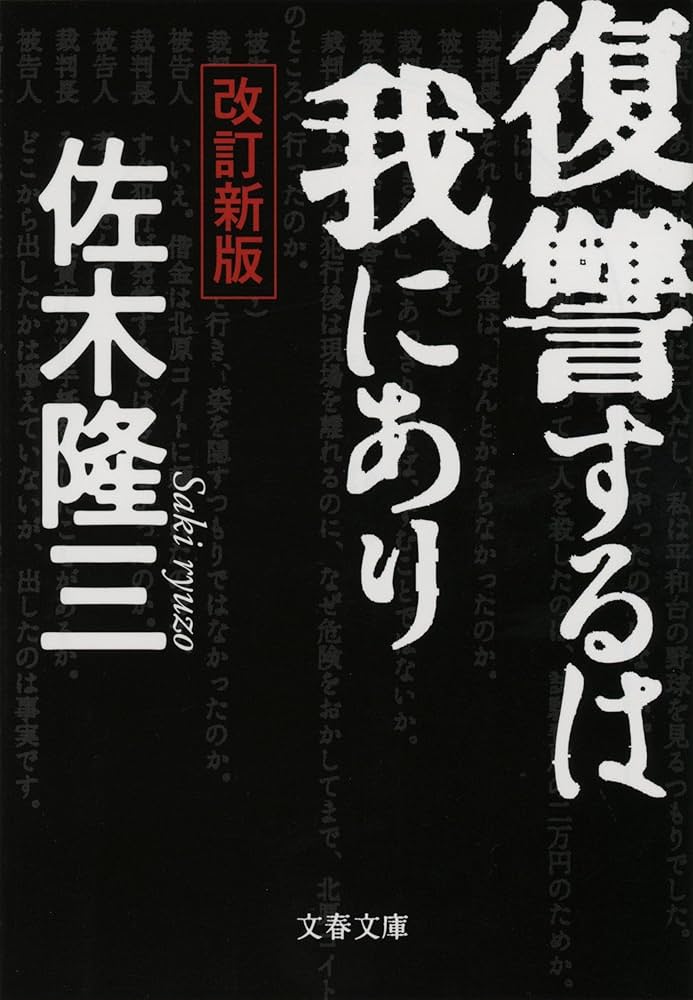
佐木隆三の名を世に知らしめた不朽の名作が、第74回直木賞受賞作『復讐するは我にあり』です。実際に起きた連続殺人事件「西口彰事件」をモデルに、凶悪な殺人犯・榎津巌の78日間にわたる逃亡劇を克明に描いています。
なぜ彼は、ためらいなく人を殺し、逃げ続けることができたのか。佐木隆三の筆は、警察やマスコミの視点だけでなく、犯人自身の内面や、彼を取り巻く人々の姿も描き出します。人間の心の奥底に潜む闇をえぐり出した本作は、今村昌平監督によって映画化もされ、日本映画史に残る傑作として知られています。



徹底して突き放した客観的描写が、かえって事件の本質を炙り出す。犯罪ノンフィクションの金字塔と呼ぶにふさわしい傑作だ。
3位『わたしが出会った殺人者たち』
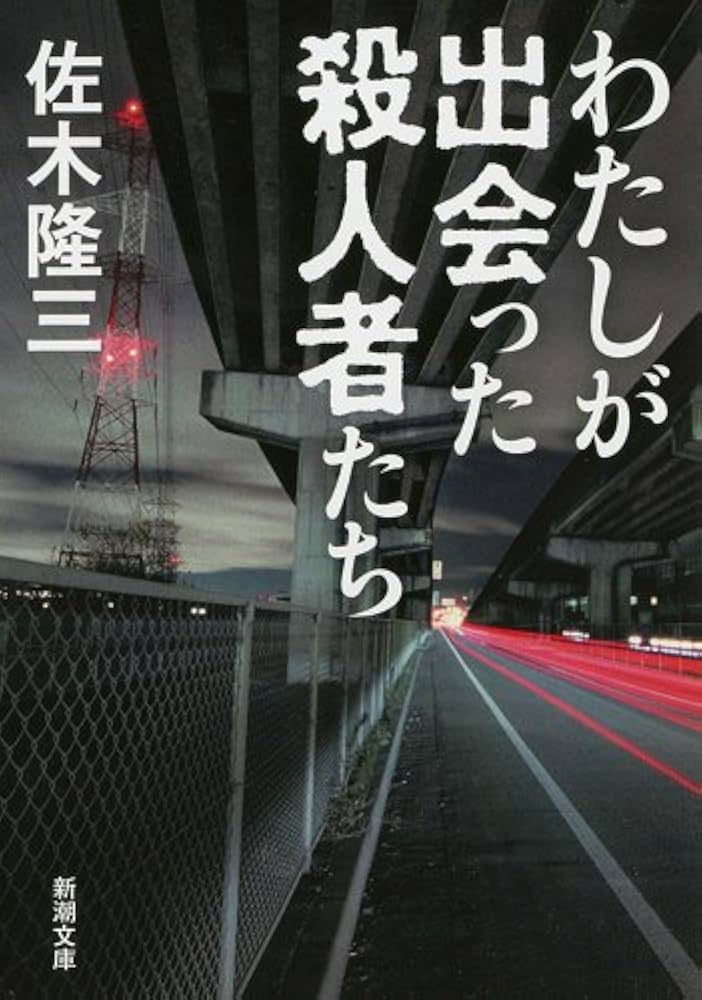
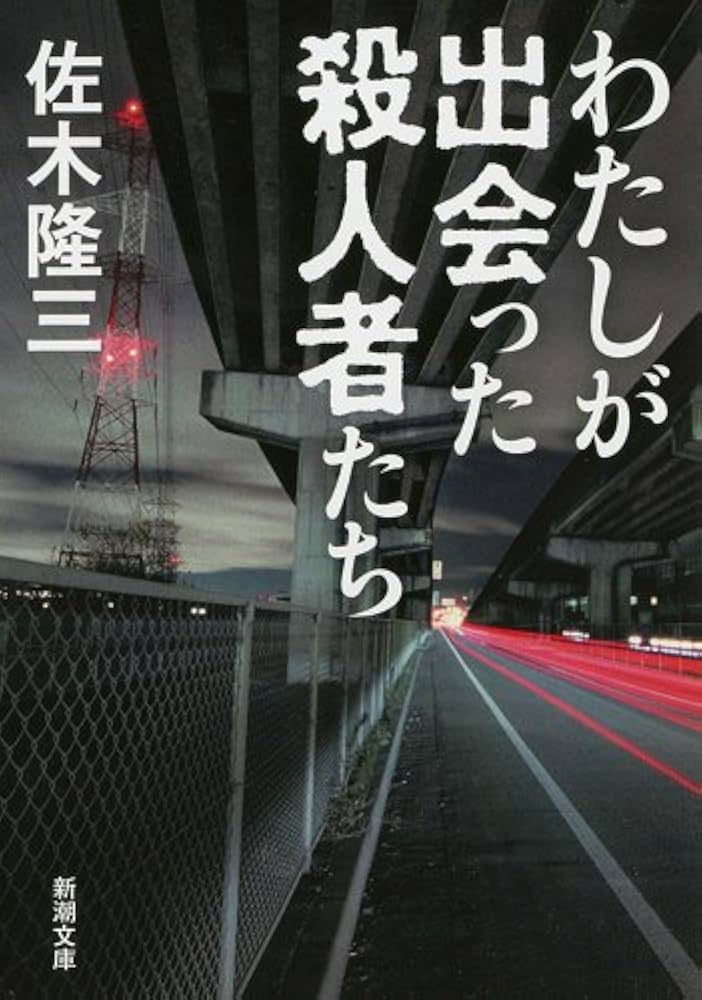
犯罪ノンフィクションの巨匠である佐木隆三が、自らの取材人生を振り返る一冊が『わたしが出会った殺人者たち』です。本作には、『復讐するは我にあり』のモデルとなった西口彰や、連続射殺事件の永山則夫など、彼が実際に関わった殺人者たちが登場します。
佐木は、彼らと交わした書簡や面会でのやり取りを通して、その人物像に肉薄していきます。単なる事件記録ではなく、殺人者というレッテルを貼られた人間たちの生身の姿を浮き彫りにした貴重なドキュメントです。作家・佐木隆三の覚悟と眼差しを感じられる作品と言えるでしょう。



殺人者と直接向き合った作家の記録は重みが違うね…。人間の複雑さを突きつけられて、ちょっと動揺しちゃうよ。
4位『慟哭 小説・林郁夫裁判』
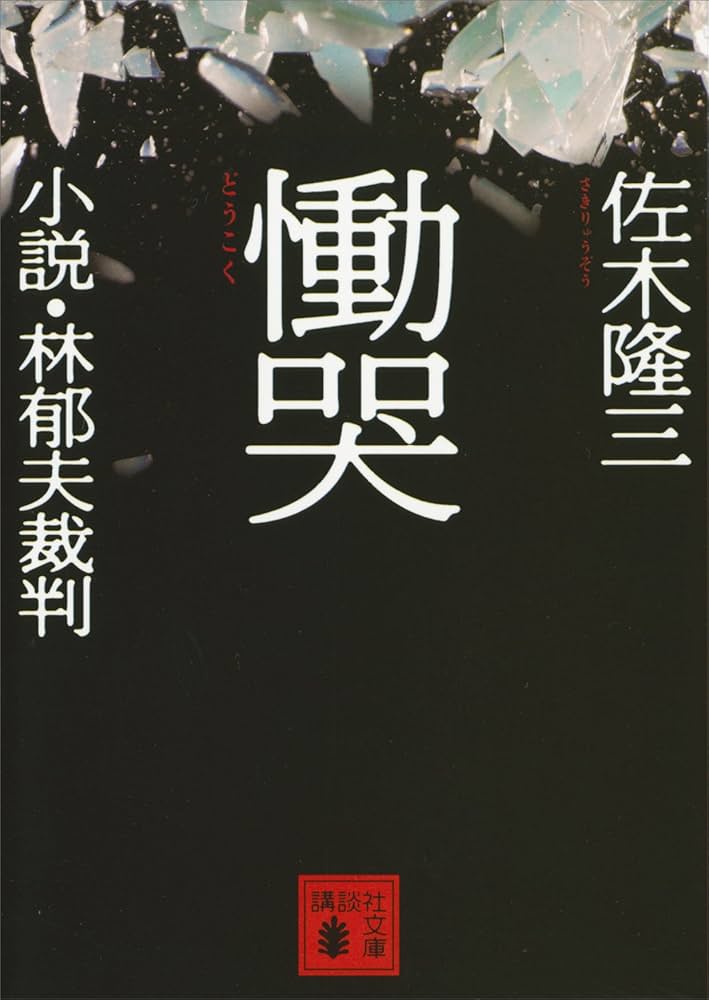
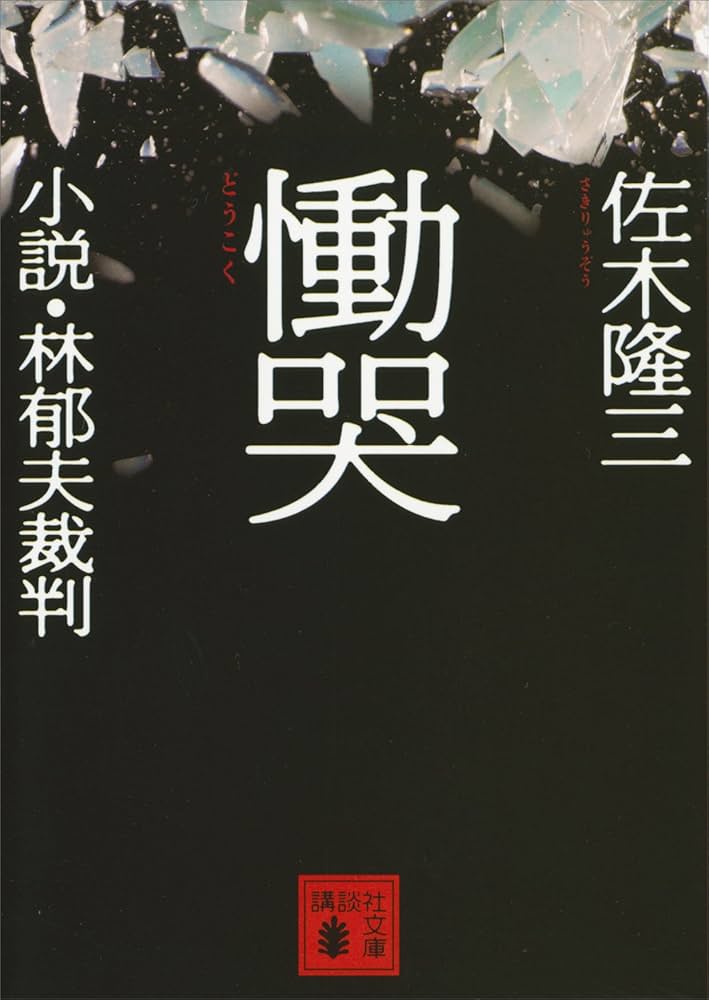
日本中を震撼させたオウム真理教による地下鉄サリン事件。本作は、実行犯の一人でありながら、法廷で事件の全貌を告白した元幹部・林郁夫の裁判を追ったノンフィクション・ノベルです。
「私がサリンをまきました」という衝撃的な告白から始まる法廷。佐木隆三は、林郁夫の証言を通して、なぜエリート医師がカルト教団にのめり込み、無差別殺人に至ったのか、その心の軌跡を丹念に描き出します。事件の真相と人間の心の脆さに迫る、重厚な一冊です。



克明な法廷描写が、事件の異常性を際立たせている。エリート医師が堕ちていく過程の分析は、冷徹そのものだ。
5位『死刑囚 永山則夫』
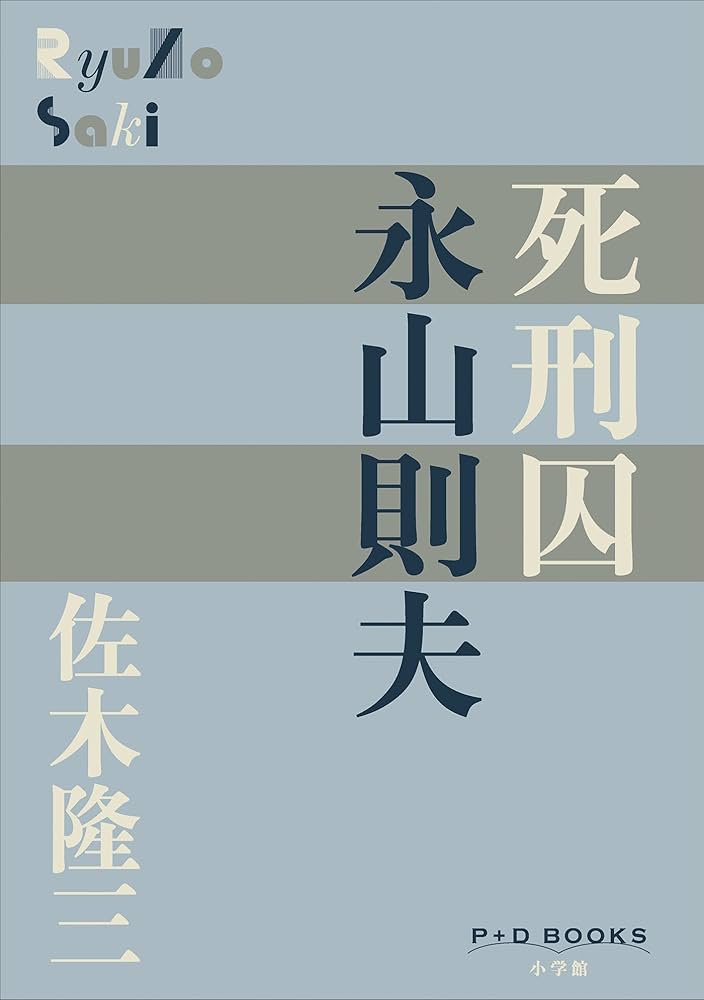
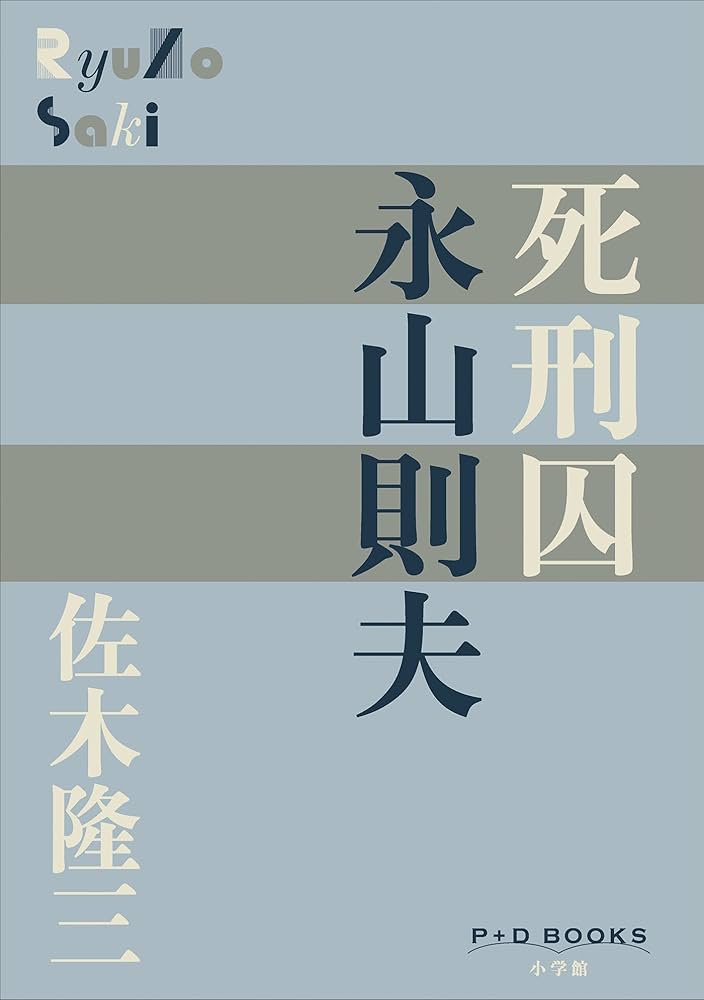
1968年に日本各地で4人を射殺し、「連続射殺魔」として世間を恐怖に陥れた永山則夫。本作は、彼の生い立ちから犯行、そして逮捕後の獄中での変化までを描いたノンフィクション・ノベルです。
貧困と虐待という過酷な環境で育った少年が、なぜ凶悪な犯罪者へと変貌してしまったのか。佐木隆三は、膨大な資料と取材に基づき、永山則夫という人間の内面に深く迫ります。犯罪を生み出す社会の構造についても考えさせられる、衝撃的な作品です。



永山則夫という個人を通して、犯罪を生み出す社会構造を問うている。これは極めて重要な記録文学と言えるだろう。
6位『なぜ家族は殺し合ったのか 北九州一家監禁殺人事件』
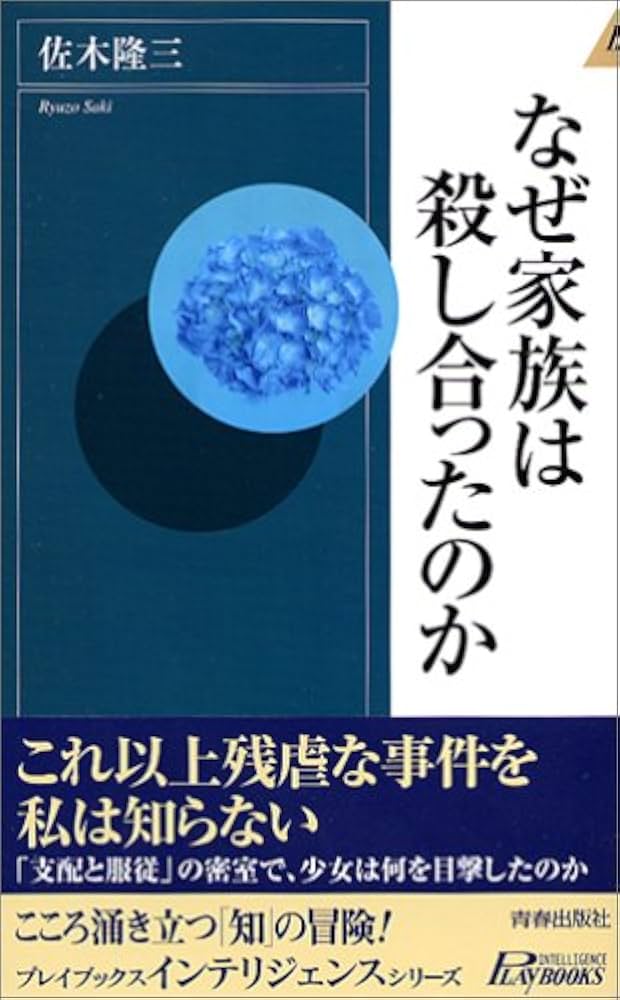
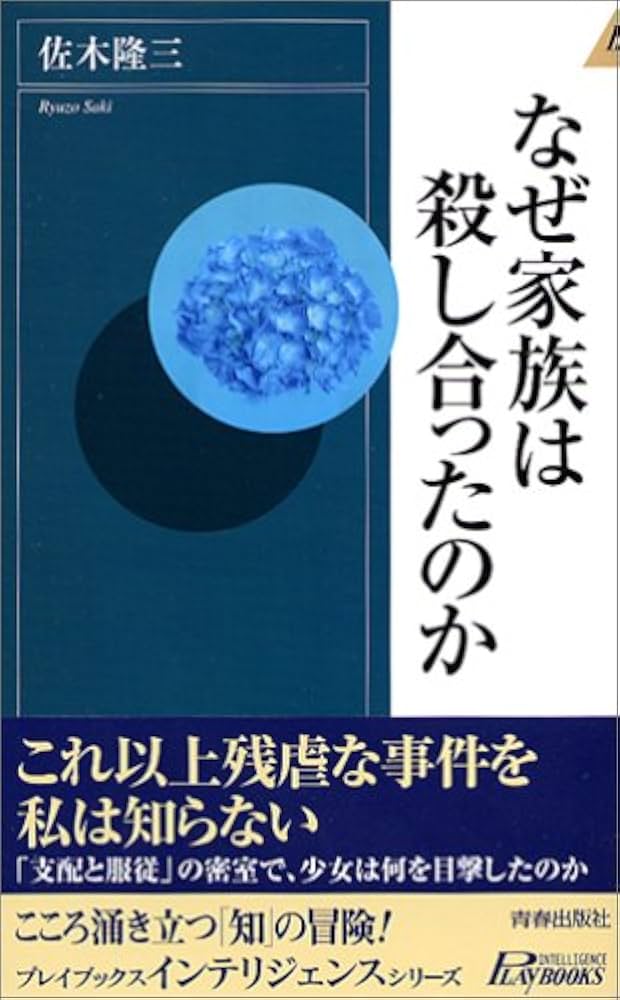
犯罪史上類を見ない、おぞましい事件として知られる「北九州一家監禁殺人事件」。本作は、主犯の男女によって一家が支配され、互いを殺し合わせるに至った事件の真相に迫るノンフィクションです。
人間の良心や倫理観が、いかに脆く崩れ去っていくのか。佐木隆三は、生存者の証言や裁判記録を基に、この地獄のような状況を克明に描き出します。人間の心の闇の深淵を覗き込むような、戦慄の一冊です。



本書が描き出すのは、心理的支配の極致とその恐怖だ。淡々とした筆致だからこそ、事件の異常さが際立つ。
7位『深川通り魔殺人事件』
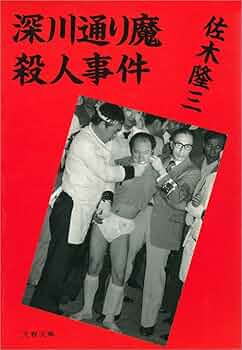
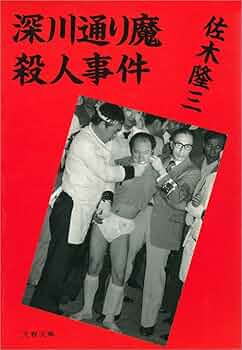
1981年、東京・深川の商店街で白昼に起きた無差別殺傷事件。本作は、4人が死亡、2人が重傷を負ったこの惨劇の犯人、川俣軍司の犯行に至るまでの軌跡と裁判の全記録を描いた作品です。
覚醒剤の後遺症による幻覚に悩まされ、犯行に及んだとされる男。しかし、その精神状態は本当に「心神喪失」だったのか。裁判では、犯人の責任能力の有無が大きな争点となりました。「キレる」現代人の犯罪の根源を探る上で、今なお重要な問いを投げかける一冊です。



動機が理解不能な犯罪を、司法がいかに裁くのか。その限界を浮き彫りにした作品であり、現代にも通じる問いを投げかける。
8位『小説 大逆事件』
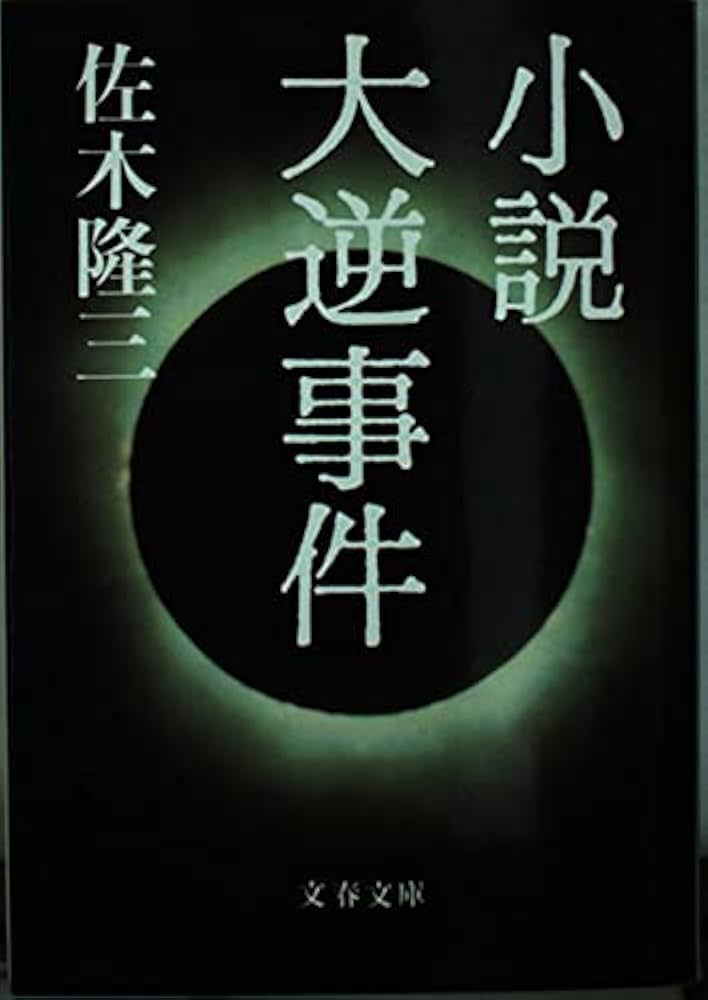
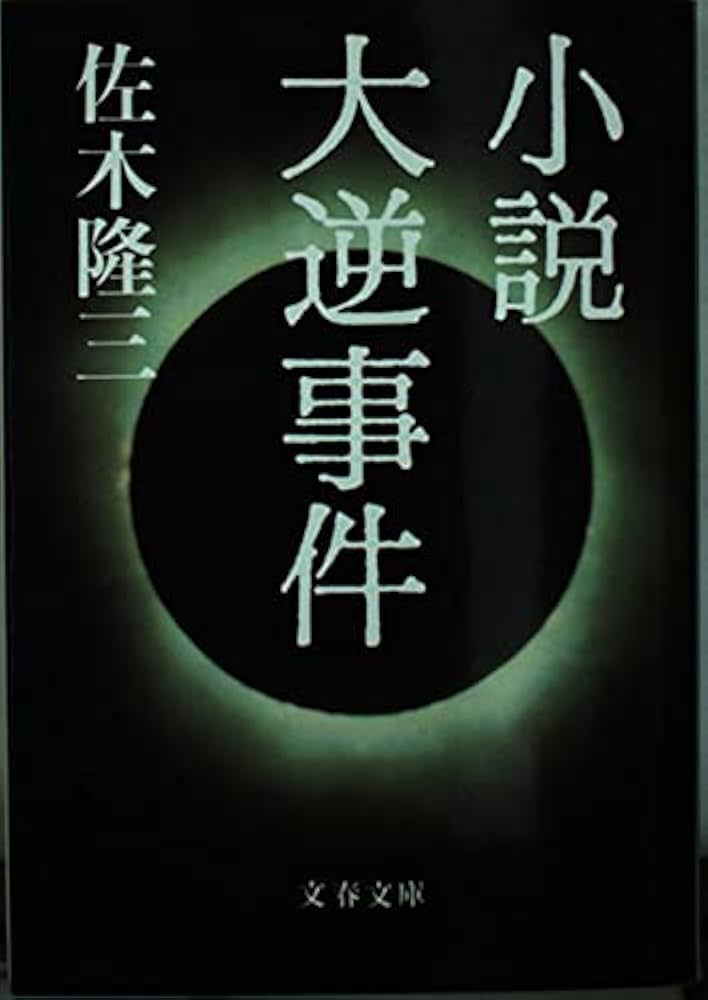
明治時代末期に起きた、社会主義者や無政府主義者が明治天皇の暗殺を計画したとして検挙された「大逆事件」。本作は、この歴史的事件の真相に、小説という形で迫った意欲作です。
国家による陰謀であったという説も根強いこの事件。佐木隆三は、膨大な史料を読み解き、事件関係者たちの人間模様や思想的背景を鮮やかに描き出します。日本の近代史の闇に光を当てた、重厚な歴史ノンフィクション・ノベルです。



教科書じゃわからない、事件の裏にある人間ドラマがすごいんだ。歴史の闇に迫る、一級品の歴史小説だよ。
9位『音羽幼女殺害事件 山田みつ子の「心の闇」』
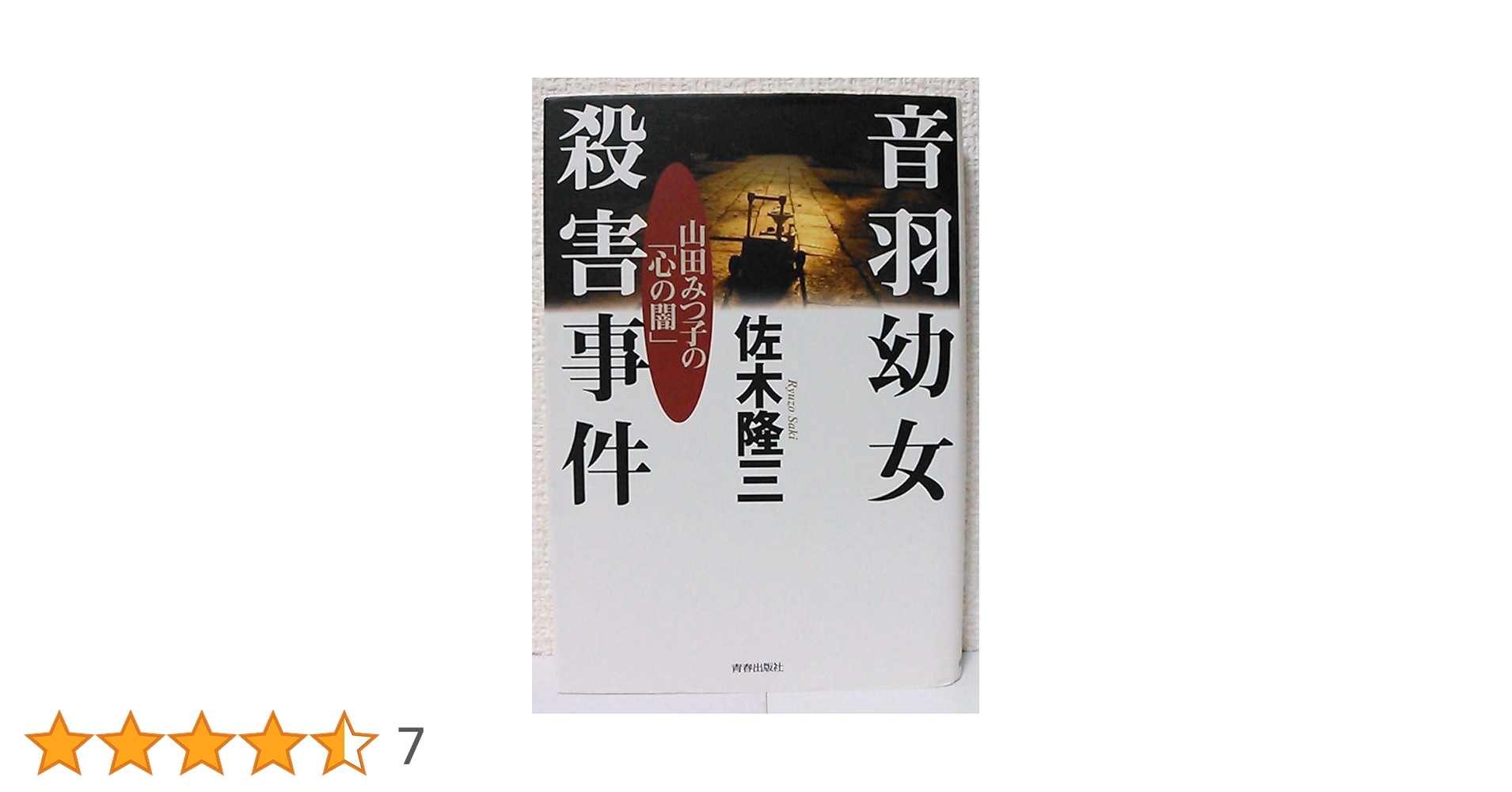
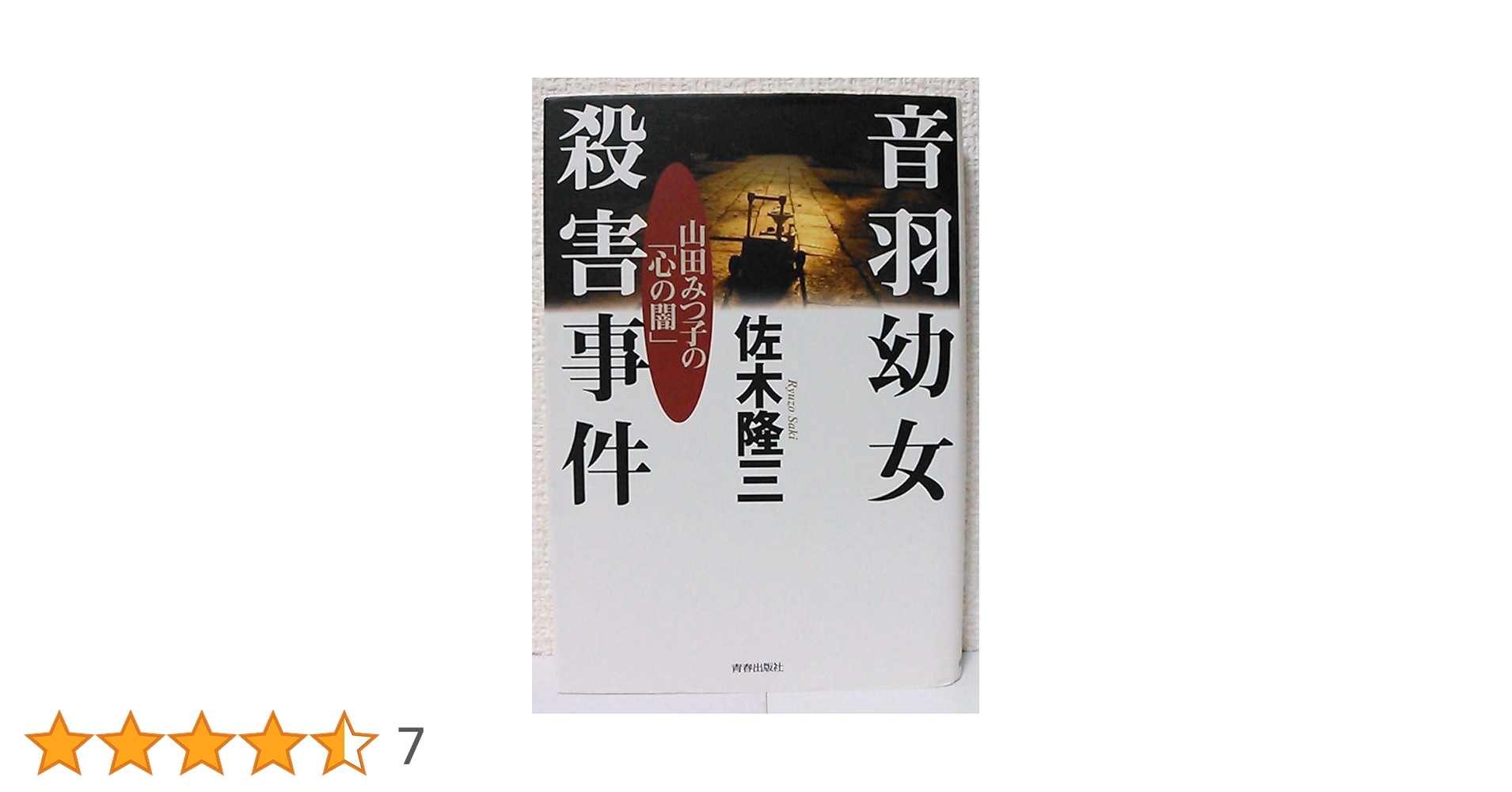
1999年、同じ幼稚園に子供を通わせる母親が、いわゆる「ママ友」の娘を殺害するという衝撃的な事件が起きました。本作は、この「お受験殺人」とも呼ばれた事件の公判を傍聴し、加害者である山田みつ子の心の闇に迫ったルポルタージュです。
ごく普通の主婦が、なぜ幼い子供の命を奪うという凶行に及んだのか。母親同士の嫉妬や見栄、受験戦争のプレッシャーなど、現代社会が抱える病理を浮き彫りにします。子育て中の読者にとっては、特に身につまされる部分が多いかもしれません。



ごく普通の日常が、こんな悲劇に繋がるなんて…。人間の心の闇は、本当にすぐ隣にあるのかもしれないね。
10位『沖縄と私と娼婦』
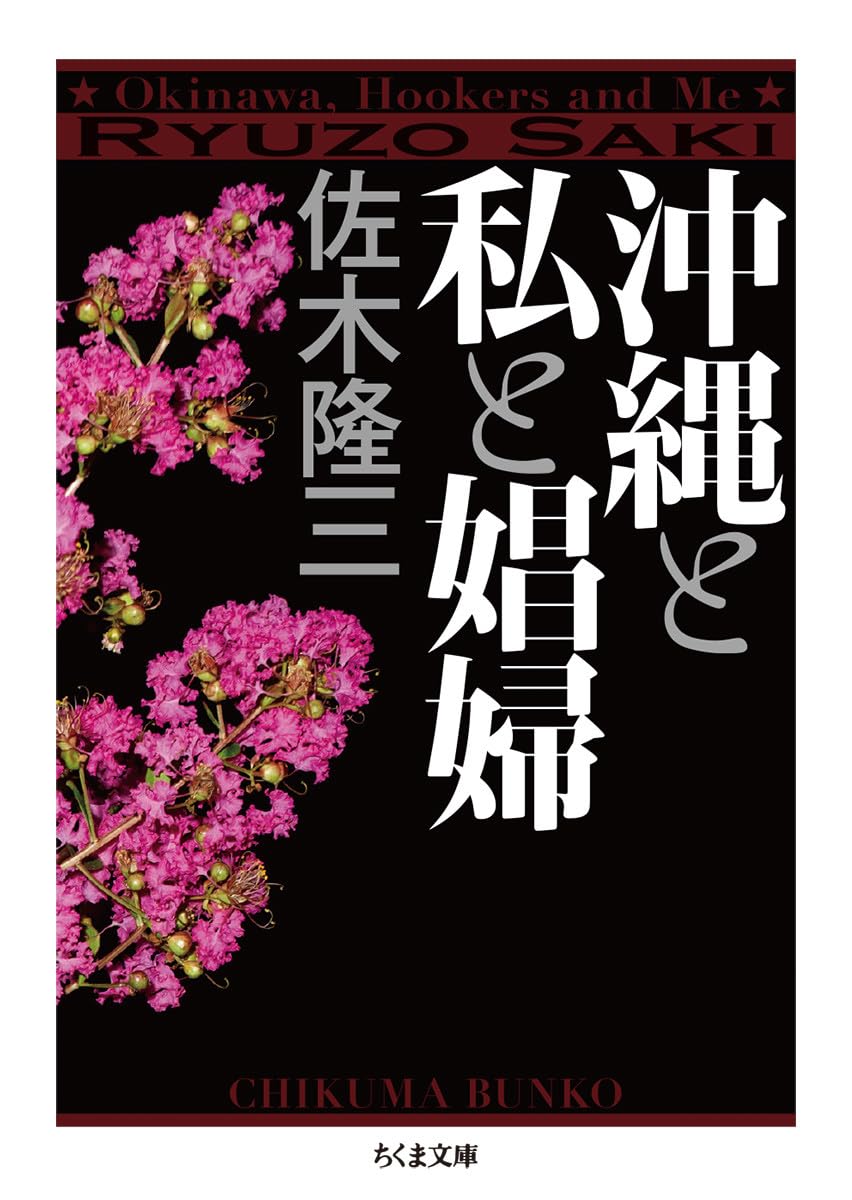
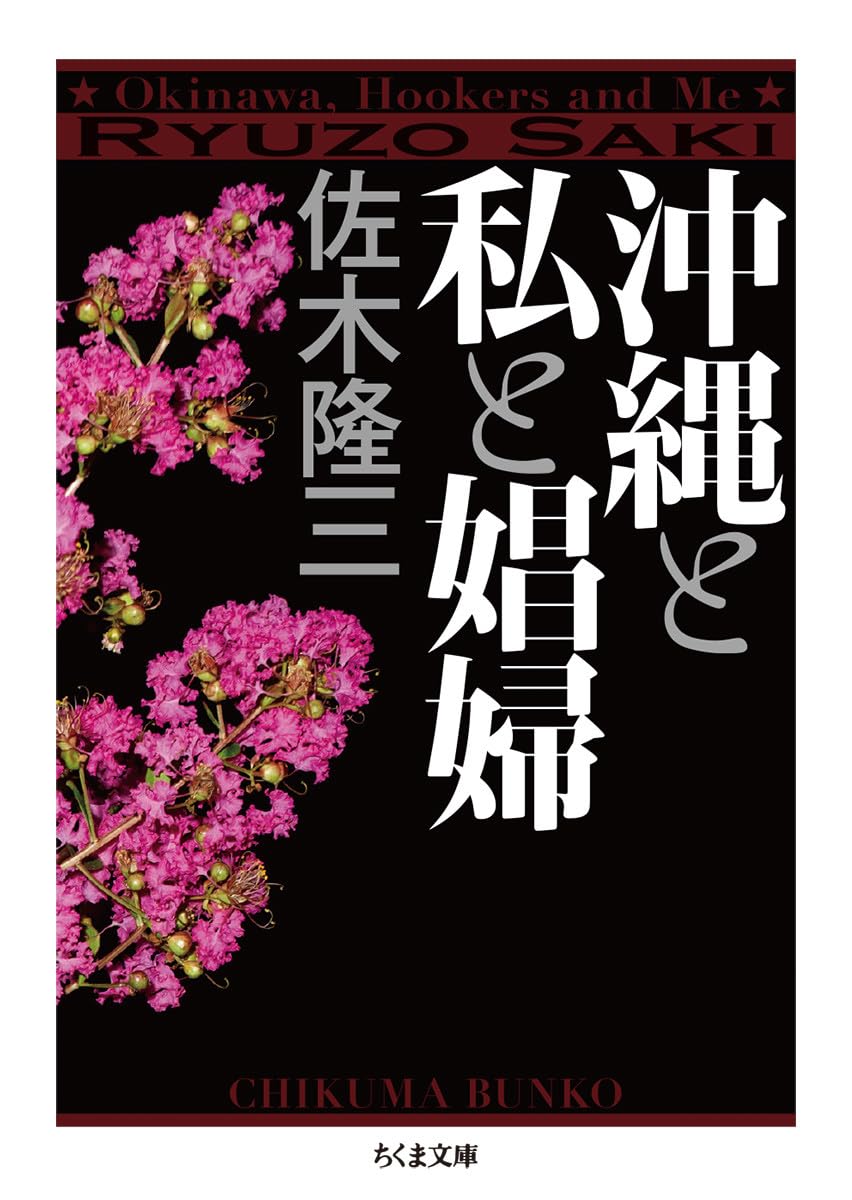
佐木隆三の初期の作品で、沖縄を舞台にした私小説的な一冊です。作家自身を投影したと思われる主人公が、沖縄の女性たち、特に米軍基地の周辺で生きる娼婦たちと交流する中で、沖縄の現実と自らの内面を見つめていきます。
本土から来た作家の視点を通して、戦後の沖縄が抱える痛みや矛盾、そしてそこに生きる人々のたくましさが描かれます。犯罪ノンフィクションとは異なる、佐木隆三の文学的な側面が色濃く出た作品です。



沖縄の光と影がリアルに伝わってくるね。犯罪ノンフィクションとは違う、作家の私的な眼差しが心地いいんだ。
11位『法廷のなかの人生』
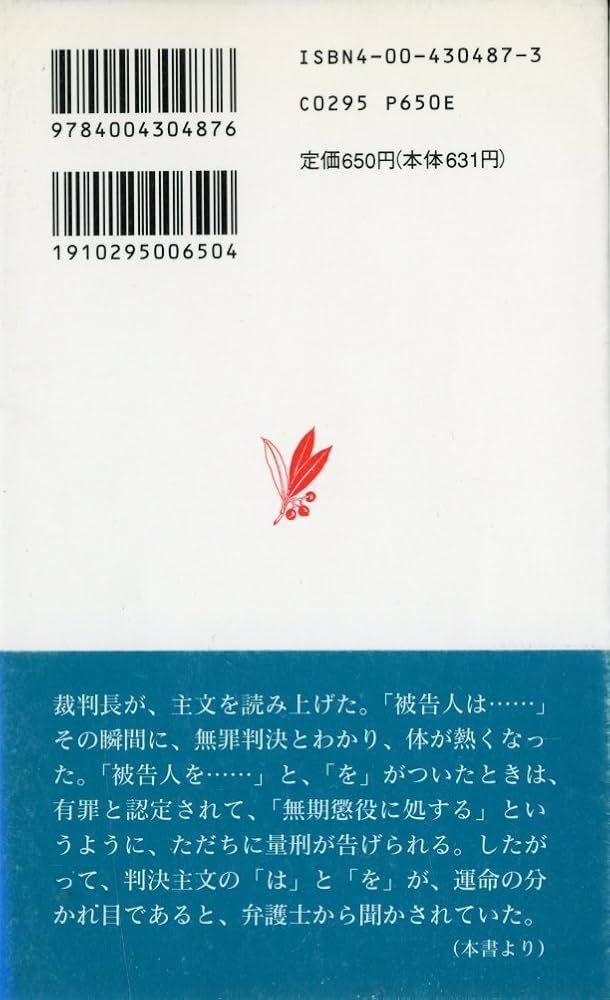
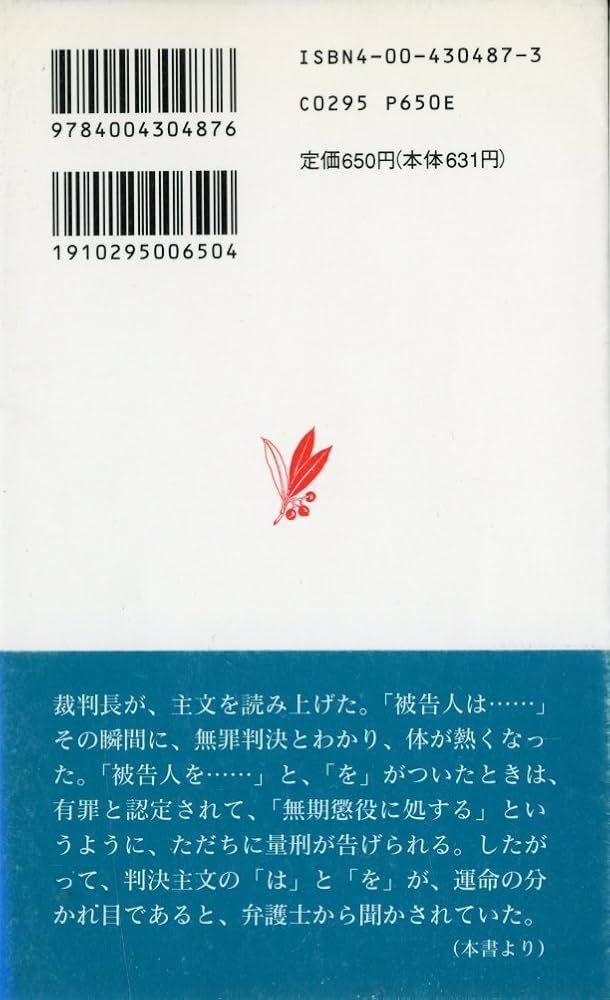
ライフワークとして裁判傍聴を続けた佐木隆三。本作は、彼が長年にわたって見つめてきた法廷での人間模様を綴ったエッセイ集です。
殺人事件のような重大犯罪から、窃盗や詐欺といった身近な犯罪まで、様々な裁判が取り上げられます。被告人、検察官、弁護人、そして裁判官。それぞれの立場の人々が織りなすドラマを通して、人生の縮図が浮かび上がります。法律や裁判に詳しくない人でも、引き込まれるように読んでしまう一冊です。



法廷って特別な場所だと思ってたけど、こんなに人間臭いドラマがあるんだね。いろんな人生が詰まってて、一気に読んじゃったよ。
12位『海燕ジョーの軌跡』
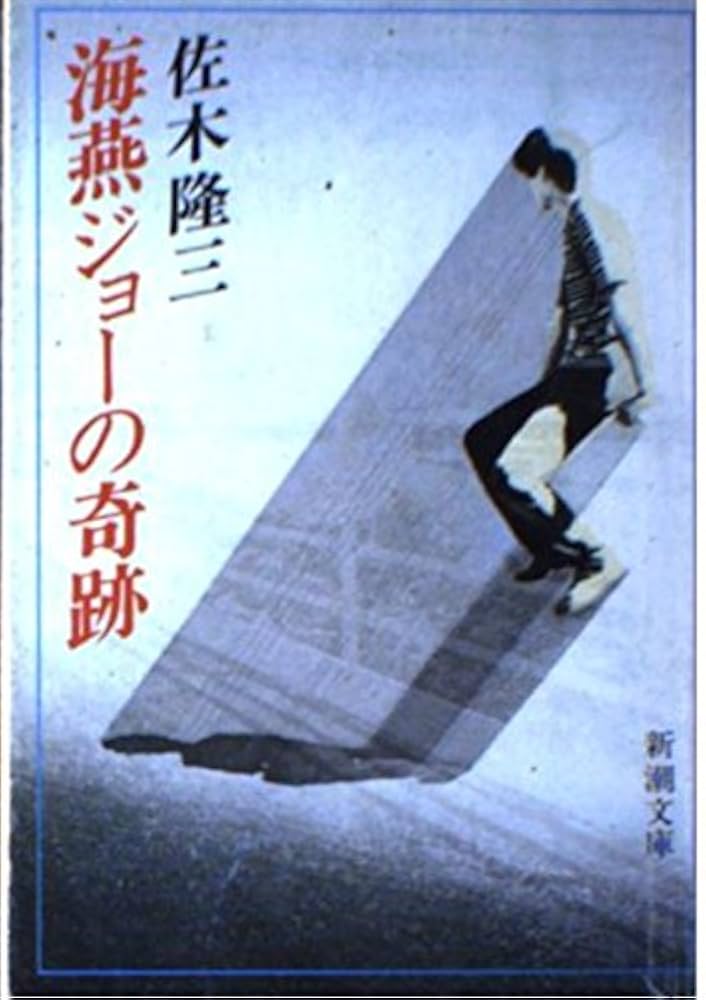
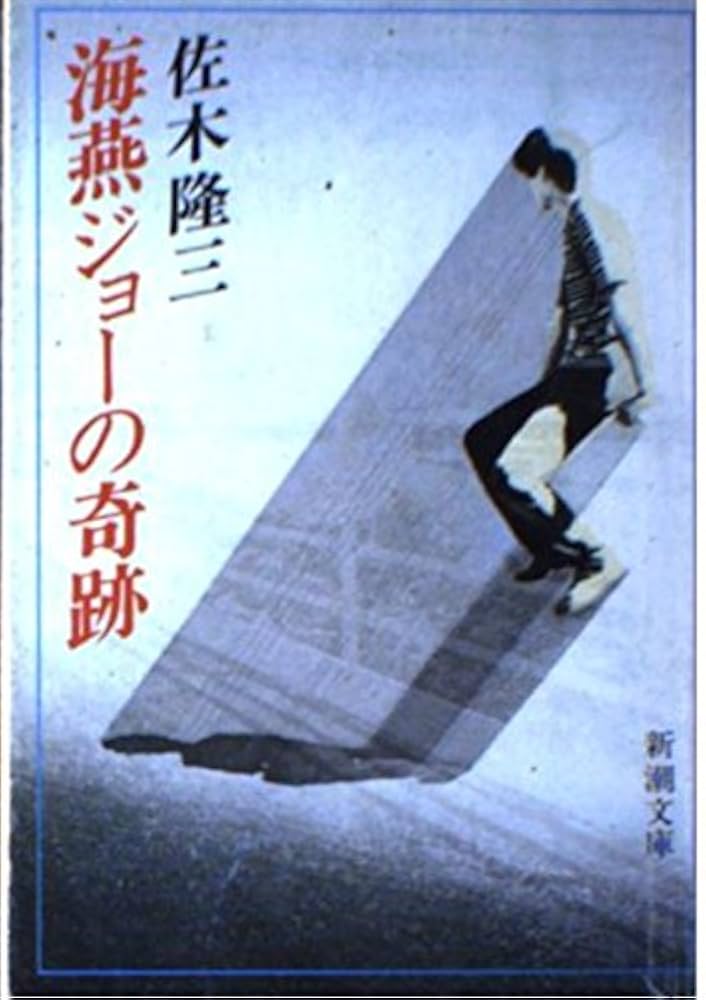
沖縄出身で「海燕ジョー」のリングネームで活躍した、実在のプロボクサー・故眞榮城朝盛の生涯を描いたノンフィクションです。彼は将来を嘱望されながらも、傷害事件を起こしてリングを去り、若くして亡くなりました。
沖縄から本土へ渡り、栄光と挫折を味わった一人のボクサーの人生を通して、沖縄が置かれた複雑な状況や、夢を追う若者の純粋さと危うさを描き出します。ボクシングファンはもちろん、多くの人の胸を打つ青春物語です。



夢に向かって一直線に駆け抜ける姿が眩しい!切ない結末だけど、読んだ後に胸が熱くなる最高の青春小説だよ。
13位『ジャンケンポン協定』
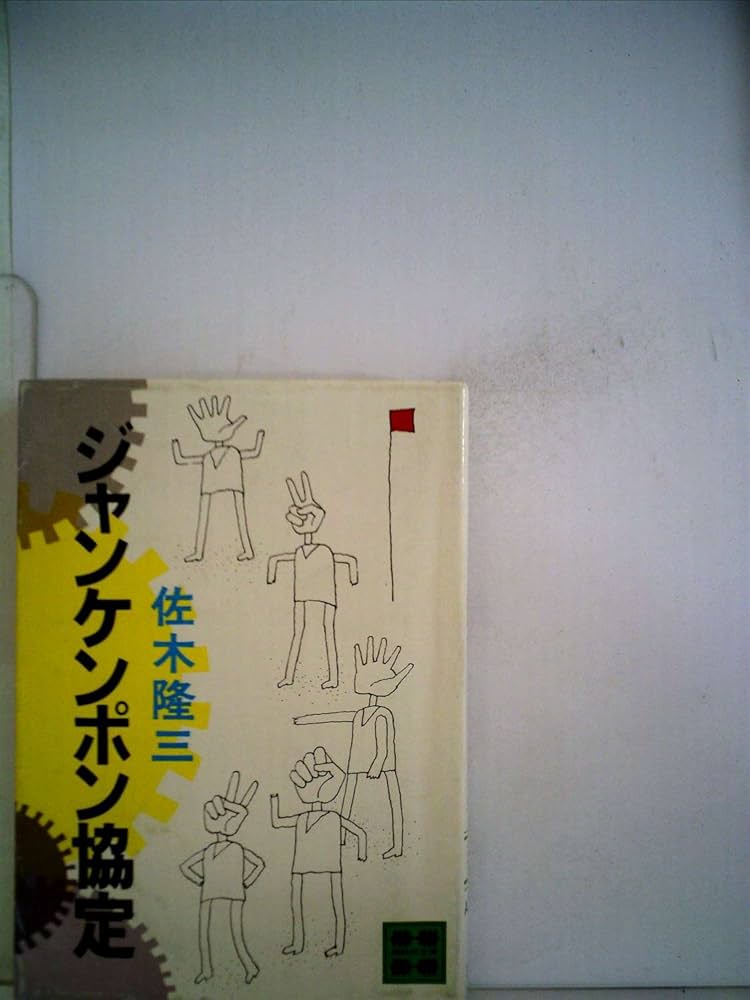
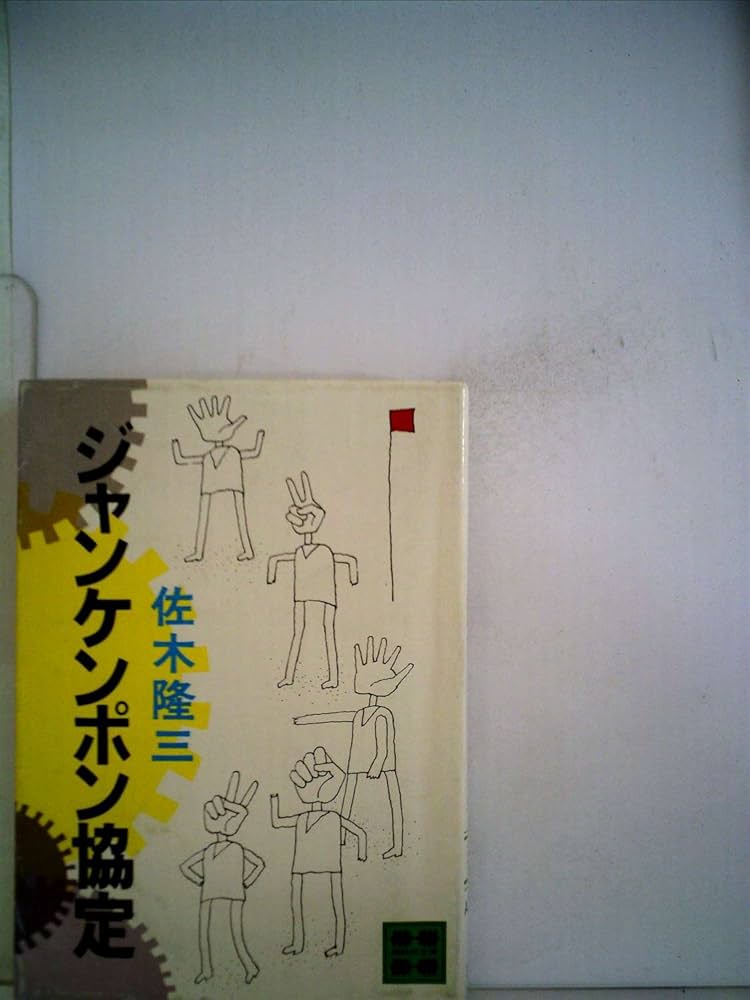
1963年に新日本文学賞を受賞した、佐木隆三の作家デビュー作です。八幡製鉄所(現・日本製鉄)に勤務していた自身の経験を基に、労働組合の内部を描いた作品として知られています。
会社と組合幹部が、労働者をジャンケンで負けた方から解雇するという理不尽な協定を結ぶという、風刺の効いた物語です。労働者たちがユーモアと団結でこの協定を骨抜きにしていく様子が描かれており、後の犯罪ノンフィクションとは一味違った、社会派作家としての原点を感じさせます。



ジャンケンでクビが決まるなんてひどい話だよね。でも、それにユーモアで対抗する労働者たちが最高なんだ!
14位『大罷業』
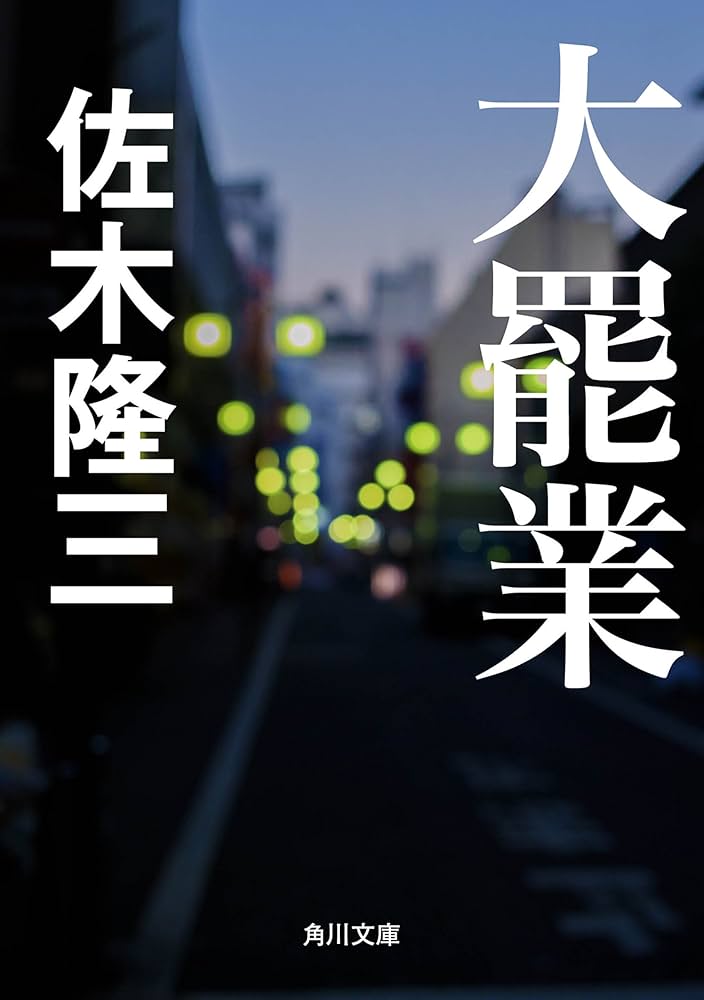
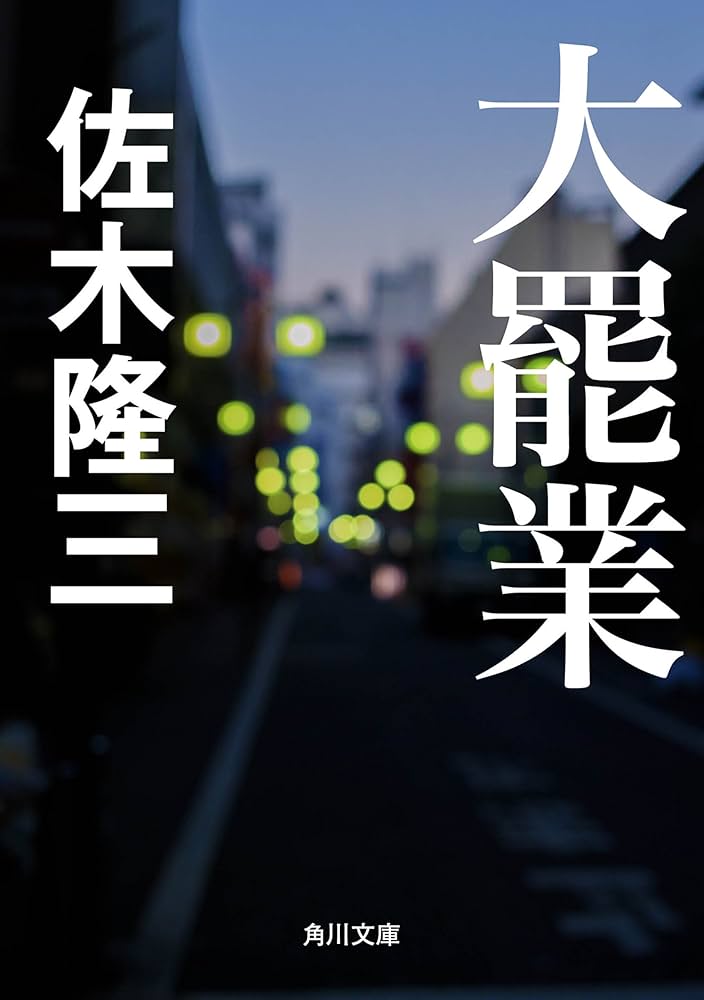
佐木隆三が八幡製鉄所に勤務していた1961年に発表した、初期の重要作です。戦後の労働運動史に残る三井三池争議をモデルに、大規模なストライキ(罷業)に揺れる炭鉱の町を描いています。
労働者たちの団結と対立、会社との激しい攻防、そして運動に翻弄される家族の姿。自身の労働組合での活動経験を持つ佐木だからこそ描ける、リアリティあふれる描写が特徴です。日本の高度経済成長を支えた、炭鉱労働者たちの力強い生き様が伝わってきます。



昔の労働運動って、こんなに激しかったんだね。社会を動かそうとする人々の熱気が伝わってくるよ。
15位『恋文三十年 沖縄・仲間翻訳事務所の歳月』
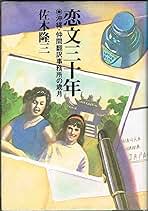
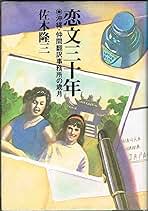
佐木隆三の作品は犯罪小説だけではありません。『恋文三十年 沖縄・仲間翻訳事務所の歳月』は、戦後の沖縄を舞台にした感動的なノンフィクションです。米兵と沖縄の女性たちの間で交わされる「恋文」の代筆を30年以上続けた女性、仲間幸子さんの人生を追っています。
一通一通の手紙から見えてくるのは、沖縄が経験してきた苦難の歴史と、翻弄されながらもたくましく生きた人々の姿です。国際結婚や国籍問題といった社会的なテーマを扱いながらも、個人の愛や希望を丹念に描き出した、心温まる一冊となっています。



手紙を通して沖縄の戦後史を描くなんて、すごい視点だよね。犯罪小説とは違う、佐木さんの優しい眼差しに癒されるんだ。
佐木隆三の人気小説を読んで、人間の深淵に触れてみませんか
ここまで、佐木隆三のおすすめ小説をランキング形式でご紹介してきました。彼の作品は、実際に起きた事件や実在の人物をモデルにしているからこそ、読む者の心に強く迫ってきます。
なぜ人は罪を犯すのか。社会の正義とは何か。そして、人間の尊厳とはどこにあるのか。佐木隆三の小説は、私たちにそうした根源的な問いを投げかけます。彼の作品を読むことは、安全な場所から人間の心の深淵を覗き込むような、スリリングで示唆に富んだ体験となるでしょう。この機会にぜひ、佐木隆三の世界に足を踏み入れてみませんか。


