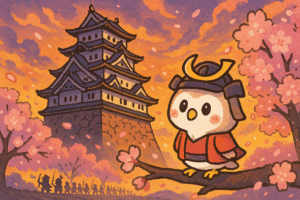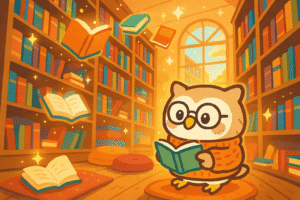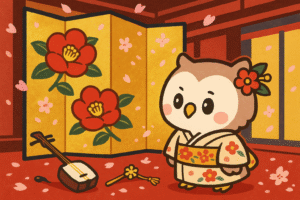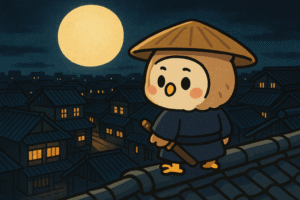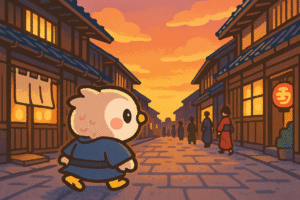あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】幕末小説のおすすめランキングTOP30

幕末小説の魅力とは?初心者にもわかる選び方のポイント
幕末と聞くと「なんだか難しそう…」と感じる人もいるかもしれません。でも実は、幕末は日本の歴史のなかでも特にドラマチックで、魅力的な人物がたくさん登場する時代なのです。約260年続いた江戸幕府の終わりと、新しい時代「明治」の始まりが交差する激動の時代、それが幕末です。
この時代の魅力は、なんといっても個性豊かな人物たちの生き様。坂本龍馬や新選組の土方歳三といった有名な志士たちだけでなく、これまであまり知られていなかった人物にも、それぞれの正義や信念があったことが小説を通して伝わってきます。外国からの圧力(黒船来航)という大きな変化のなかで、国を想い、未来を憂い、必死に生きた人々の姿には、現代の私たちも心を揺さぶられます。
「どの小説から読めばいいかわからない」という初心者の方は、まず好きな歴史上の人物や、興味のあるテーマで選ぶのがおすすめです。例えば、新選組が好きなら土方歳三が主人公の『燃えよ剣』、坂本龍馬に興味があるなら『竜馬がゆく』といった選び方です。また、1話完結の短編集から読み始めて、時代の雰囲気に慣れていくのも良い方法ですよ。
【決定版】幕末小説おすすめ人気ランキングTOP30
ここからは、いよいよ幕末を舞台にした小説のおすすめランキングを発表します!歴史小説の大家である司馬遼太郎作品はもちろん、浅田次郎や池波正太郎といった人気作家の作品、そして女性作家が描く新しい視点の物語まで、幅広くランクインしました。あなたのお気に入りの一冊がきっと見つかるはずです。激動の時代を生きた人々の熱いドラマを、ぜひ小説を通して体感してみてください。
1位『竜馬がゆく』司馬遼太郎
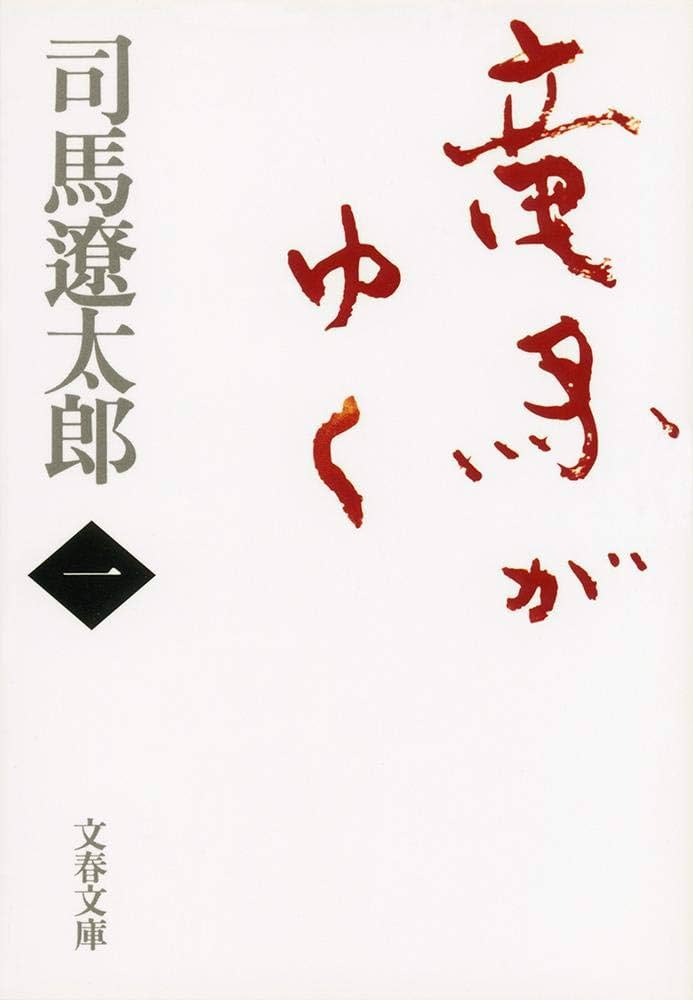
幕末小説のランキングで堂々の1位に輝いたのは、もはや説明不要といえる国民的歴史小説、司馬遼太郎の『竜馬がゆく』です。総発行部数は2,500万部を超え、日本文学の金字塔ともいえる不朽の名作として知られています。この作品をきっかけに、坂本龍馬ファンになったという人も少なくありません。
物語は、土佐の郷士の家に生まれた弱虫な末っ子だった竜馬が、江戸での剣術修行や様々な人々との出会いを経て、幕末の風雲児へと成長していく姿を描いています。藩という小さな枠組みにとらわれず、自由な発想で日本の未来を切り開こうとする竜馬の生き様は、読む人に勇気と感動を与えてくれます。私たちが抱く坂本龍馬のイメージは、この作品によって形作られたといっても過言ではないでしょう。
 ふくちい
ふくちい竜馬の型破りな生き様は、ページをめくる手が止まらないよ。閉塞感を吹き飛ばすような爽快感が最高なんだ!
2位『燃えよ剣』司馬遼太郎
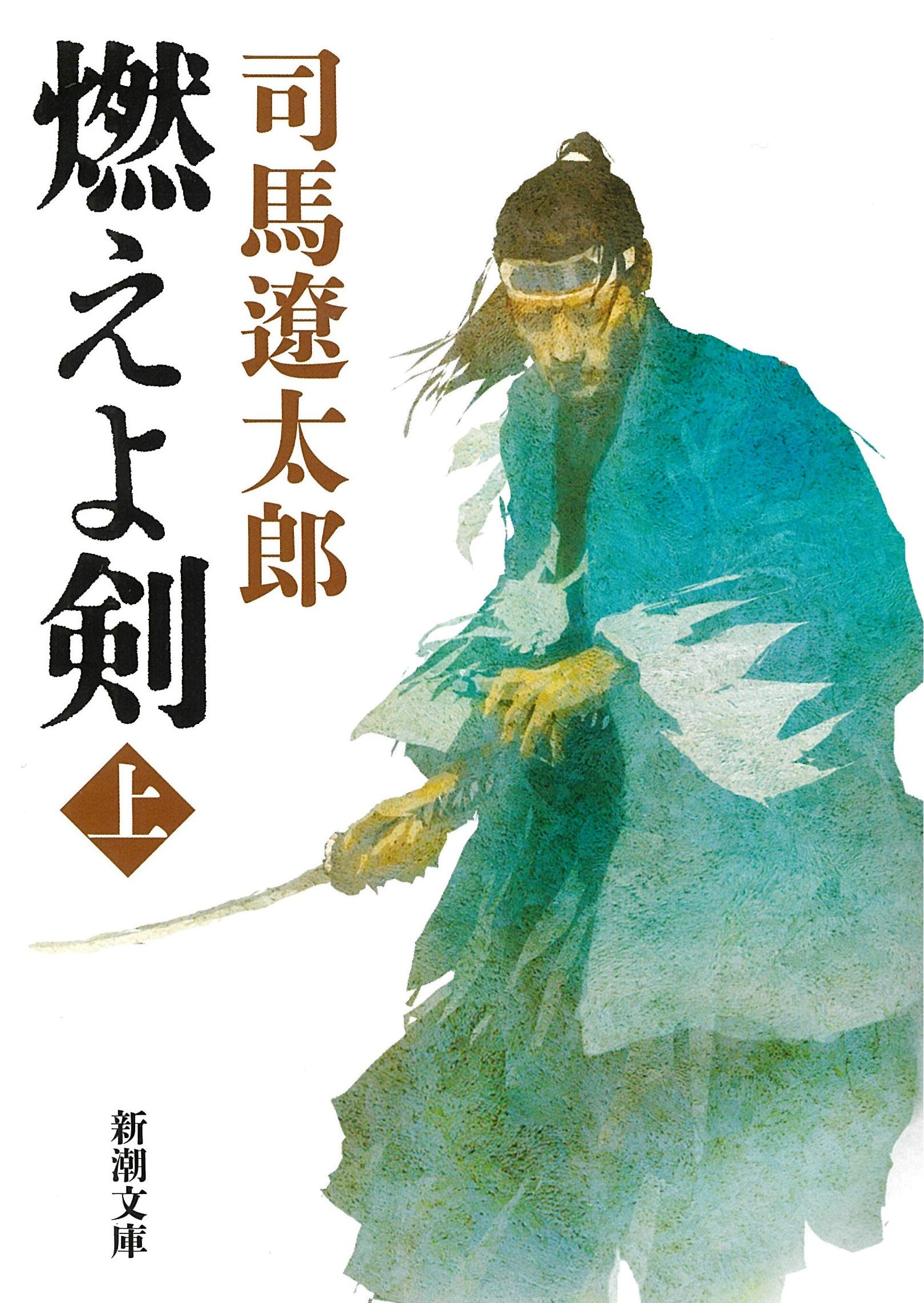
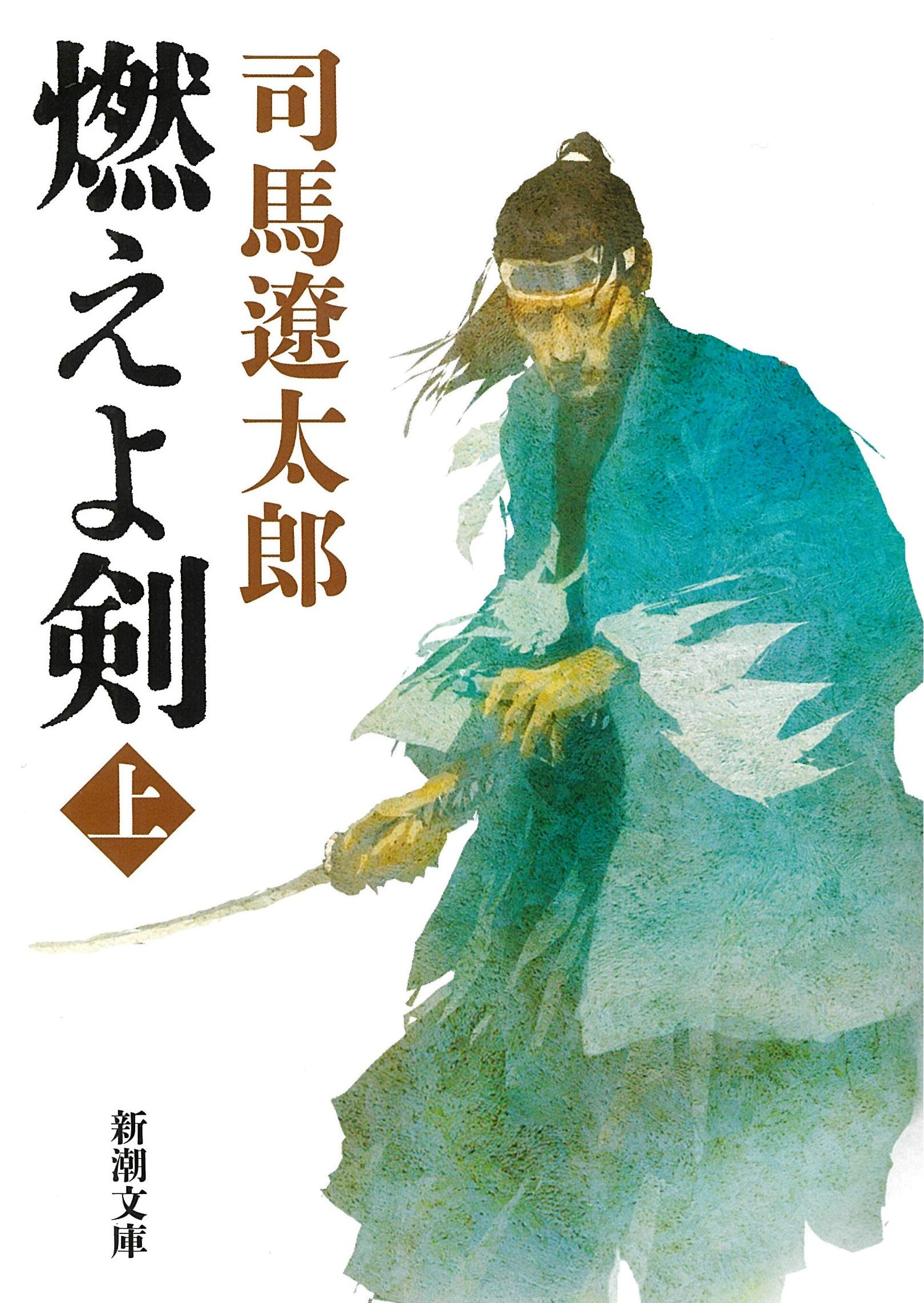
坂本龍馬と並び、幕末のスターとして絶大な人気を誇る新選組。その副長・土方歳三の生涯を描いた司馬遼太郎の『燃えよ剣』が2位にランクインしました。累計発行部数500万部を突破した、こちらも司馬文学の代表作の一つです。
武州石田村の百姓の子、「バラガキのトシ」と呼ばれた歳三が、いかにして「鬼の副長」と恐れられる存在になったのか。彼の胸には、ただひたすらに剣に生き、剣に死ぬという美学がありました。組織のために非情に徹する一方で、仲間や恋人に見せる人間的な魅力も描かれており、そのギャップに多くの読者が惹きつけられます。新選組の成り立ちから、京都での壮絶な戦い、そして箱館での最期まで、土方歳三という一人の男の人生が鮮やかに描き出されています。



わたし、土方歳三のストイックな生き様が好きなんだ。自分の信念を貫き通す姿は、まさに武士って感じがしてかっこいいよね。
3位『壬生義士伝』浅田次郎
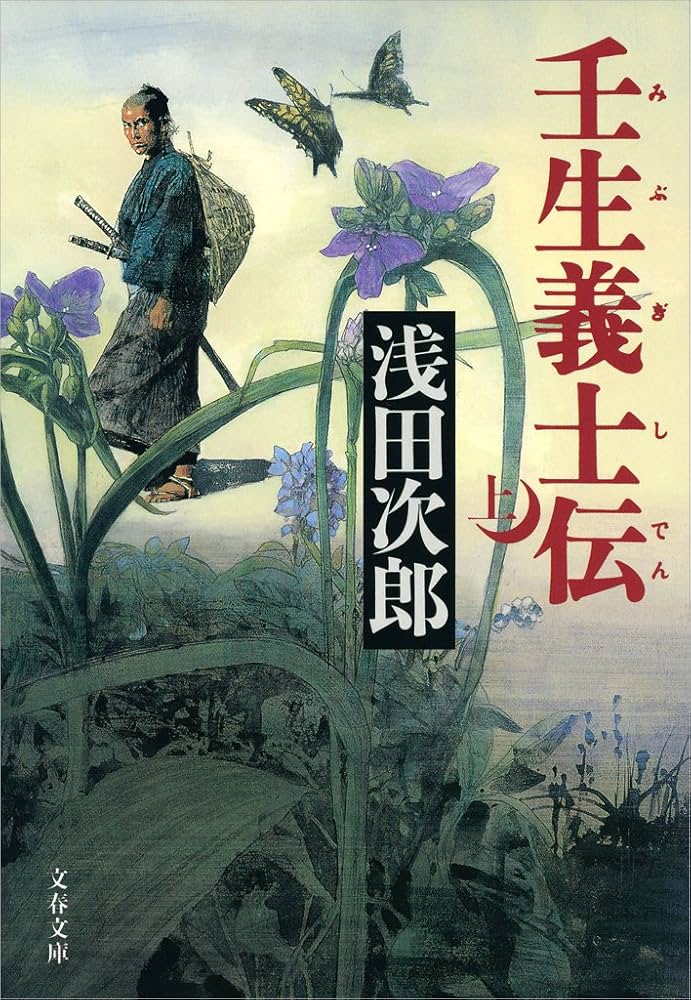
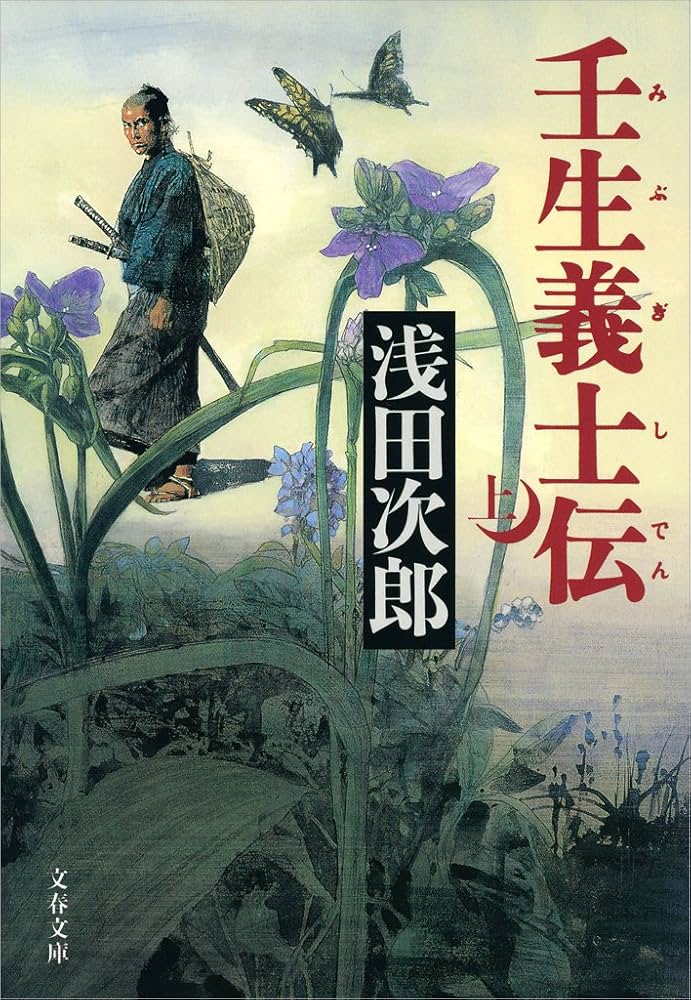
司馬遼太郎作品が上位を占めるなか、浅田次郎の傑作『壬生義士伝』が3位に食い込みました。新選組を題材にした小説は数多くありますが、本作は「泣ける新選組小説」として多くの読者の心を掴んでいます。柴田錬三郎賞を受賞した、浅田文学の金字塔ともいえる作品です。
主人公は、盛岡藩出身で新選組に入隊した吉村貫一郎。彼は、家族を養う金のために脱藩し、守銭奴と蔑まれながらも剣を振るい続けます。しかし、その行動の根底にあったのは、故郷に残した妻と子への深い愛でした。新選組で唯一、庶民の心を失わなかった男の、あまりにも切なく、そして気高い生涯が描かれています。様々な人物の視点から貫一郎の人物像が語られていく構成も見事です。



もう涙なしでは読めないよ…。家族を想う貫一郎の気持ちを考えると、胸が締めつけられるんだ。
4位『新選組血風録』司馬遼太郎
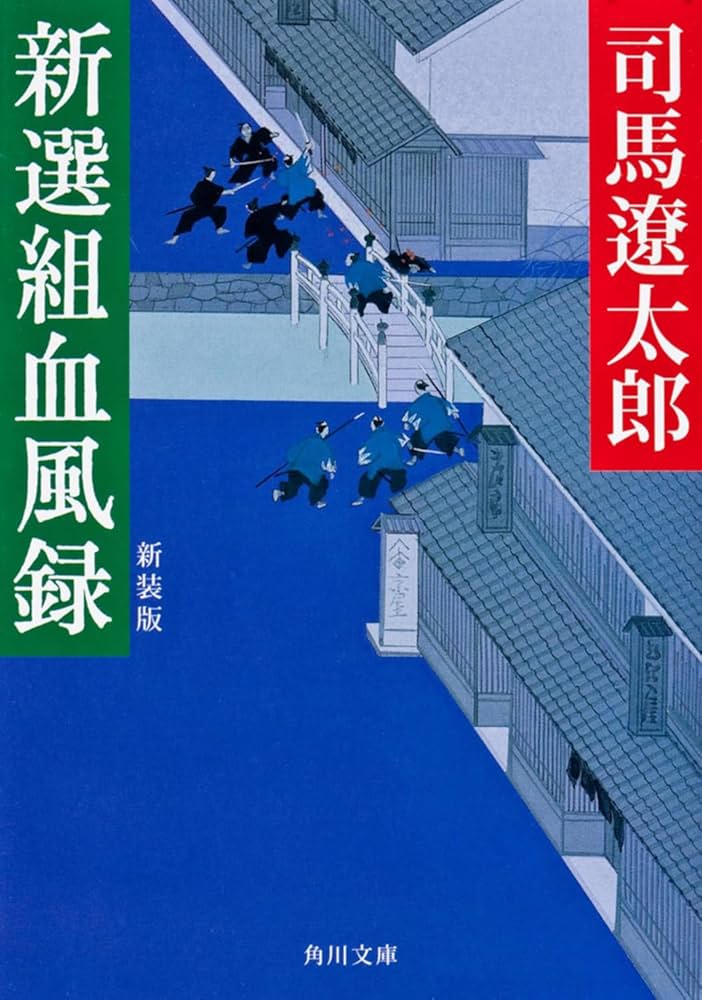
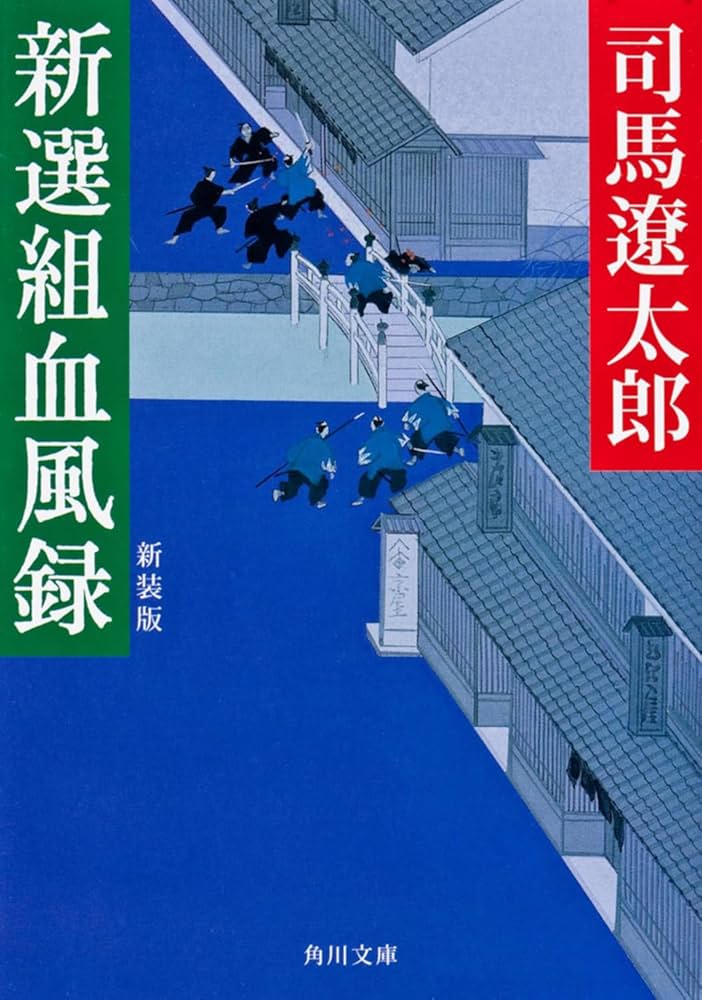
再び司馬遼太郎作品、『新選組血風録』がランクイン。こちらは『燃えよ剣』のように一人の人物を追う長編とは異なり、新選組に所属した様々な隊士たちを主人公にした全15編の短編集です。一話完結なので、歴史小説初心者でも非常に読みやすいのが特徴です。
沖田総司や斎藤一といった有名な剣客から、あまり知られていない隊士まで、個性豊かな人物たちが次々と登場します。それぞれの物語を通して、新選組という組織の光と影、隊士たちの生き様や掟の厳しさ、そして彼らが抱えた夢や苦悩が浮き彫りになります。剣に生き、剣に散った男たちの鮮烈なドラマが、簡潔ながらも味わい深い筆致で描かれています。



短編集だから、ちょっとした時間にサクッと読めるのがいいよね。いろんな隊士のエピソードを知ると、もっと新選組が好きになること間違いなしだよ!
5位『世に棲む日日』司馬遼太郎
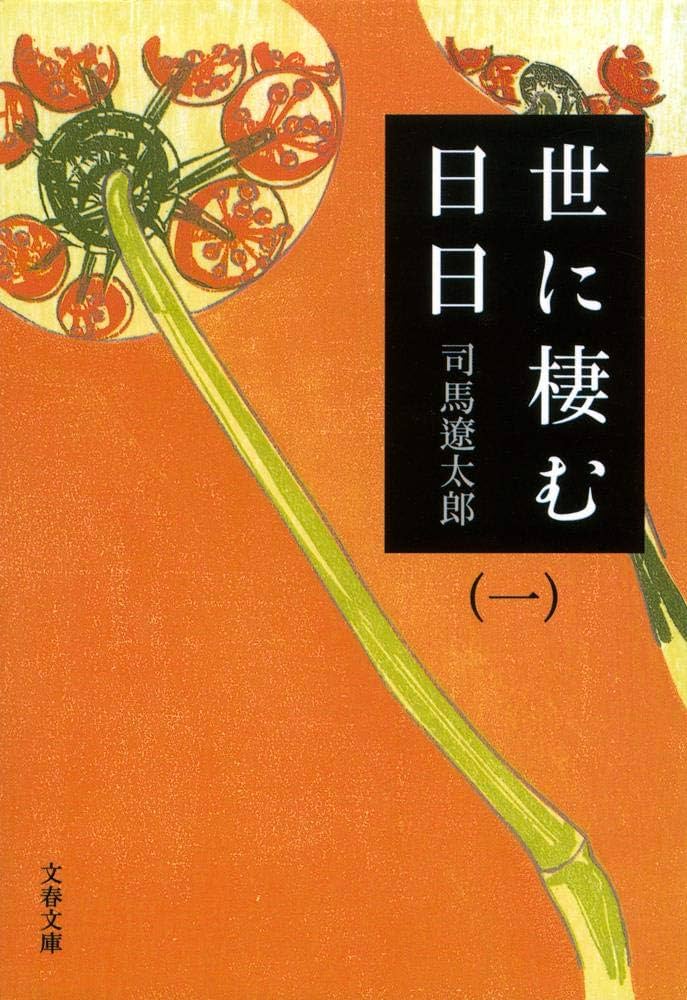
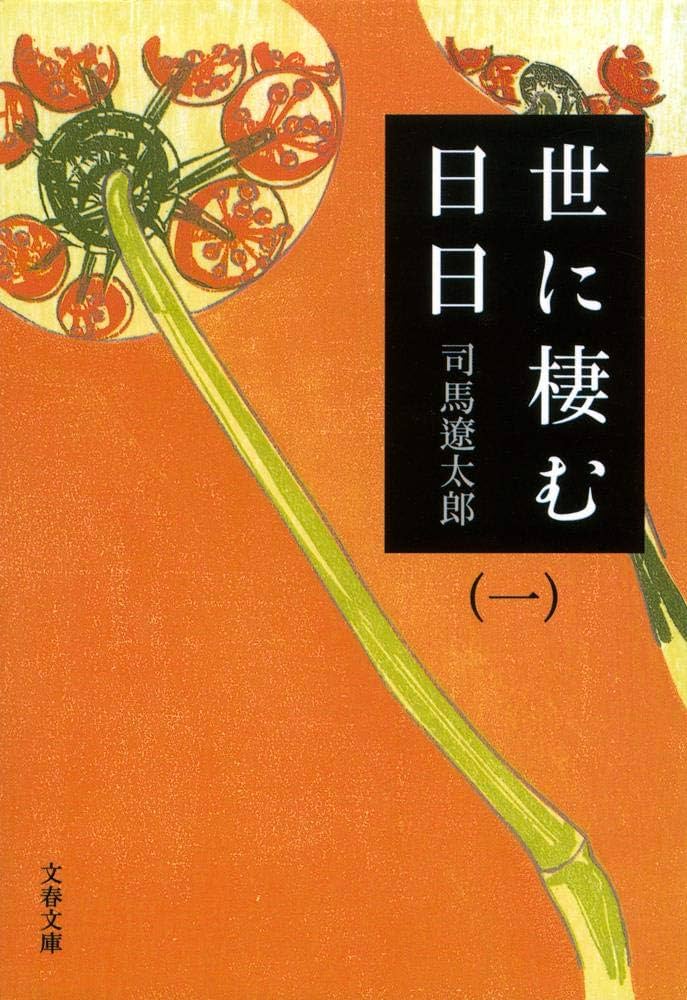
5位は、幕末の思想と行動の源流を描いた司馬遼太郎の『世に棲む日日』です。この物語は二部構成になっており、前半では長州藩の思想家・吉田松陰、後半ではその弟子であり、奇兵隊を創設した革命家・高杉晋作の生涯が描かれています。
松陰が松下村塾で未来を担う若者たちに何を教え、その情熱が弟子たちにどう受け継がれていったのか。そして、師の想いを継いだ晋作が、いかにして常識外れの発想と行動力で時代を動かしていったのか。師弟の絆と、思想が行動へと昇華されていく過程がダイナミックに描かれています。幕末の長州藩、そして維新の原動力を知る上で欠かせない一冊です。



吉田松陰の情熱と、それに応えようとする高杉晋作の姿がすごく熱いんだ。まさに「時代が動く瞬間」を感じられる小説だよ。
6位『峠』司馬遼太郎
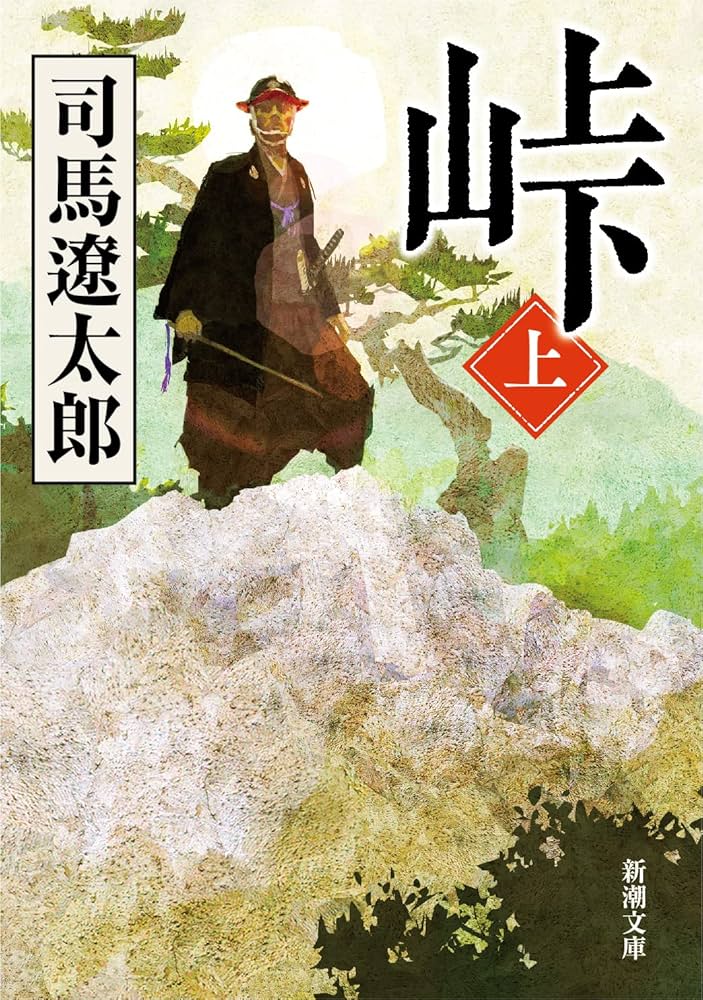
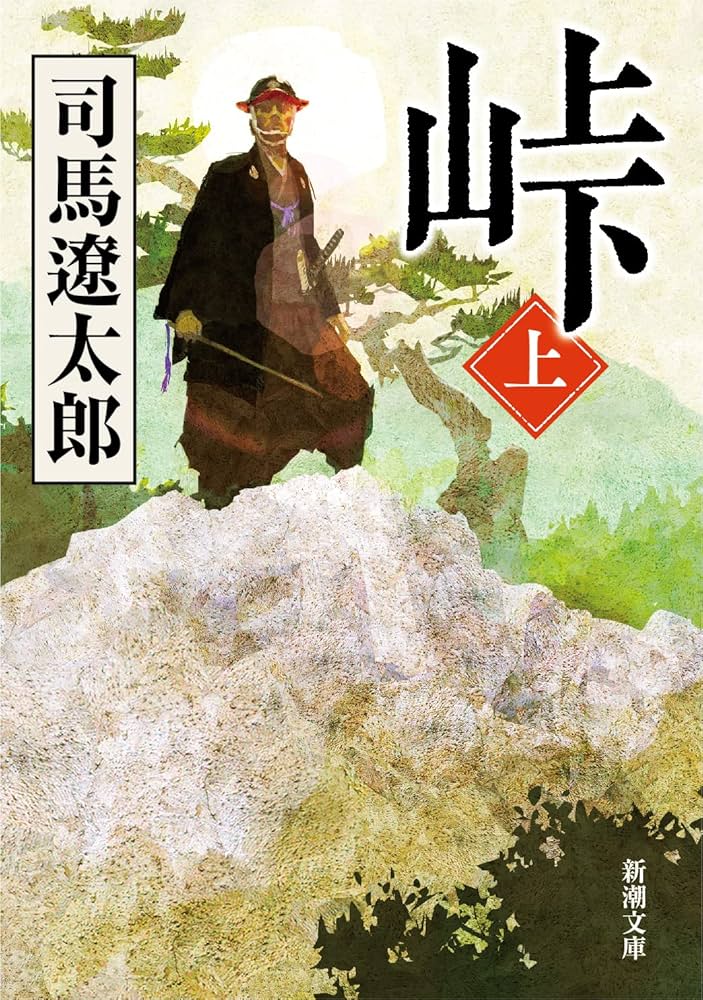
6位にランクインしたのは、幕末の小藩、越後長岡藩の家老・河井継之助の生涯を描いた司馬遼太郎の『峠』です。彼は、徳川にも官軍にも属さない「武装中立」という理想を掲げ、故郷を戦火から守るために奔走しました。
最新のガトリング砲を購入し、藩の軍備を近代化するなど、先見の明を持っていた継之助。しかし、時代の大きな流れは彼の理想を飲み込み、長岡藩は戊辰戦争の中でも特に熾烈な北越戦争へと突入していきます。自らの信念を貫き、最後まで故郷のために戦い抜いた男の、壮絶で孤高な生き様が描かれた傑作です。



大きな力に屈せず、自分の信じる道を突き進む継之助の姿は、なんだか応援したくなっちゃうんだよね。彼の生き様は、現代の私たちにも響くものがあると思うな。
7位『花神』司馬遼太郎
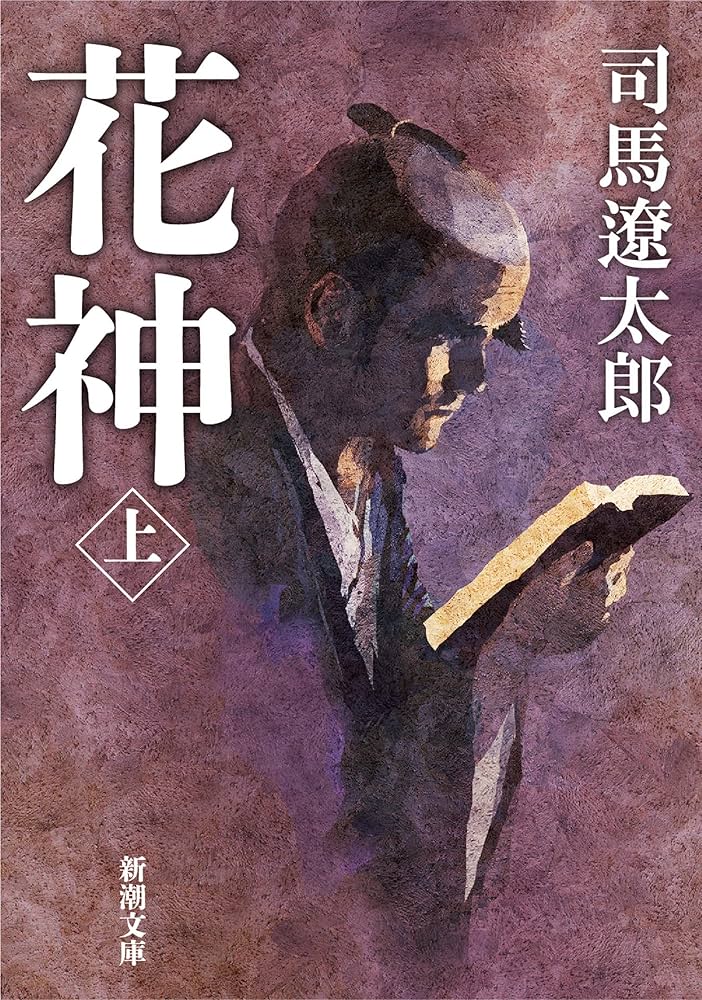
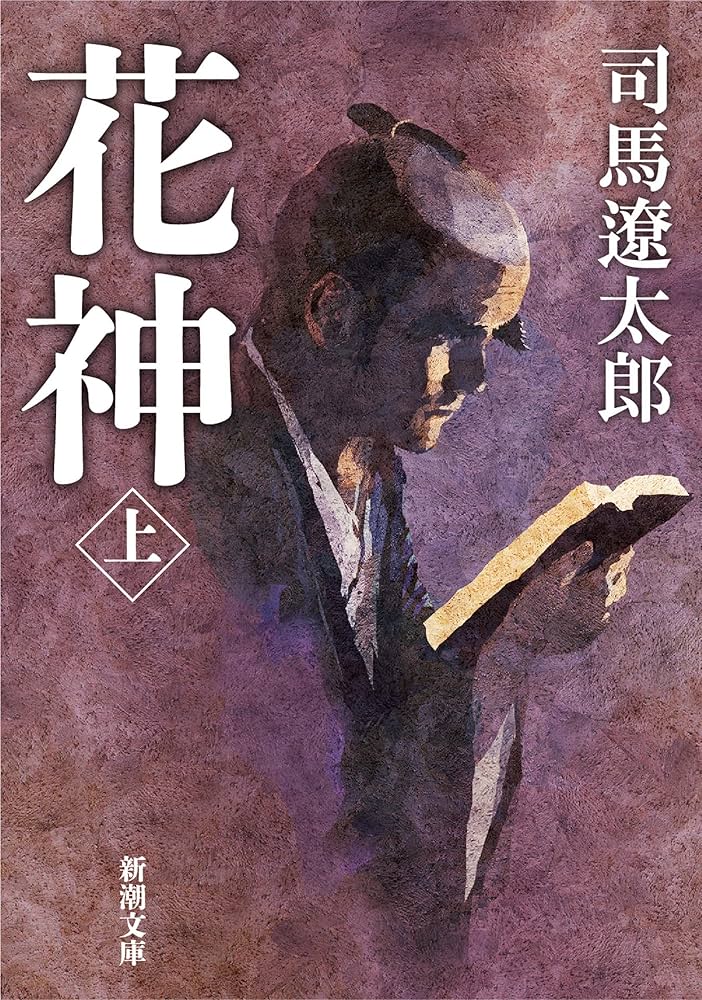
7位は、日本の近代陸軍の創設者である大村益次郎(村田蔵六)を主人公にした、司馬遼太郎の『花神』です。緒方洪庵の適塾で蘭学を学んだ一介の村医者が、その類まれな才能を見出され、やがて討幕軍の司令官として時代を動かしていく様を描いています。
感情を排し、常に合理的な思考で物事を判断する益次郎の姿は、まさに「時代の化身」のよう。古い価値観が支配する幕末において、彼の近代的な軍事思想や戦術はなかなか理解されません。しかし、彼は一切の妥協をせず、自らの信じる道を進み続けます。維新の「裏方」ともいえる天才の、ユニークな生涯と思考に触れられる一冊です。



大村益次郎って、他の幕末の志士たちとはちょっと違ったタイプの天才なんだよね。彼の合理的な考え方は、読んでいてすごく新鮮で面白いよ!
8位『最後の将軍 徳川慶喜』司馬遼太郎
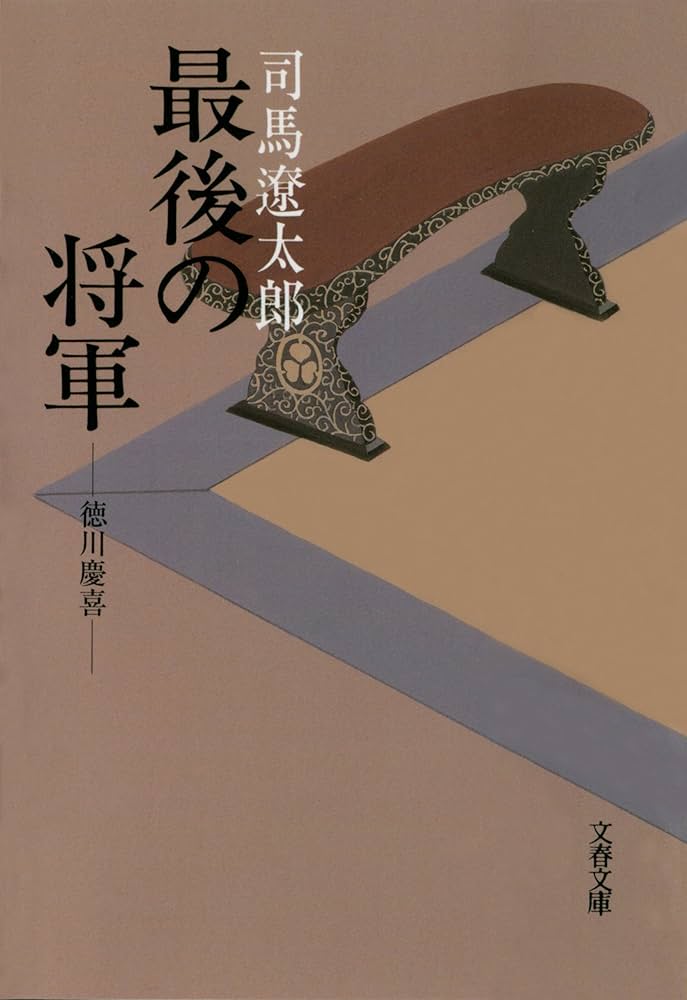
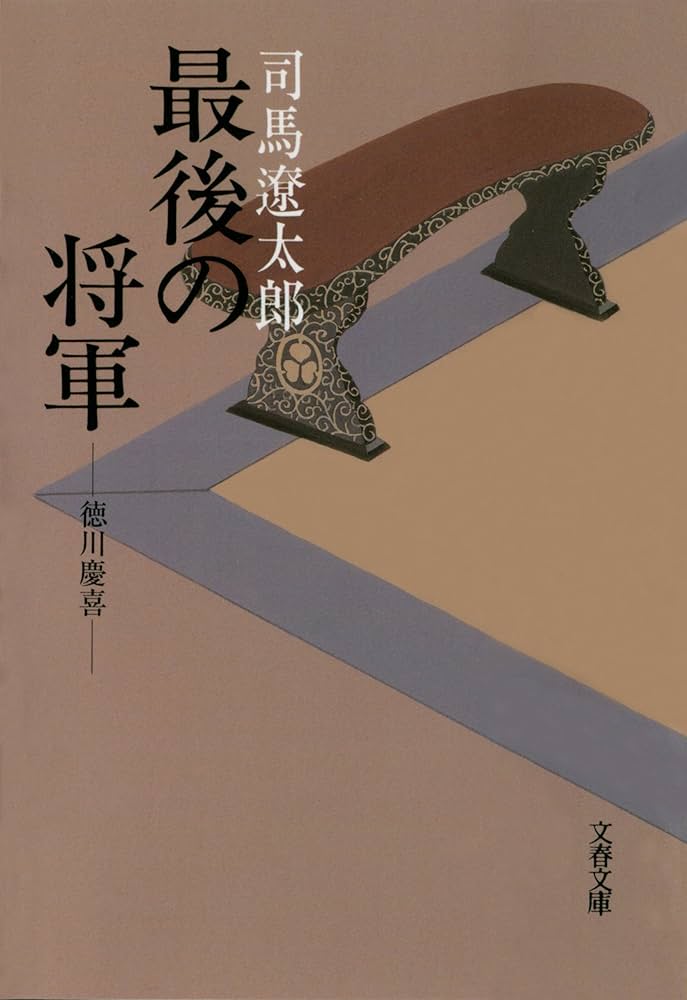
8位には、江戸幕府15代将軍、そして最後の将軍となった徳川慶喜の生涯を描いた司馬遼太郎の『最後の将軍 徳川慶喜』がランクインしました。徳川幕府という巨大な組織の終焉を、そのトップの座にあった人物の視点から描いた作品です。
「家康の再来」とまで言われたほどの英明さを持ちながらも、複雑な政治状況の中で常に難しい決断を迫られた慶喜。彼の胸の内には、どのような葛藤や孤独があったのでしょうか。大政奉還という歴史的な決断に至るまでの彼の苦悩や、鳥羽・伏見の戦いでの不可解な行動の真意など、歴史の謎に迫ります。徳川慶喜という人物の多面的で複雑な内面を、見事に描き出した名作です。



慶喜の立場って、本当に苦しかっただろうなって思うんだ。巨大な組織のトップに立つことの孤独と重圧がひしひしと伝わってくるよ…。
9位『翔ぶが如く』司馬遼太郎
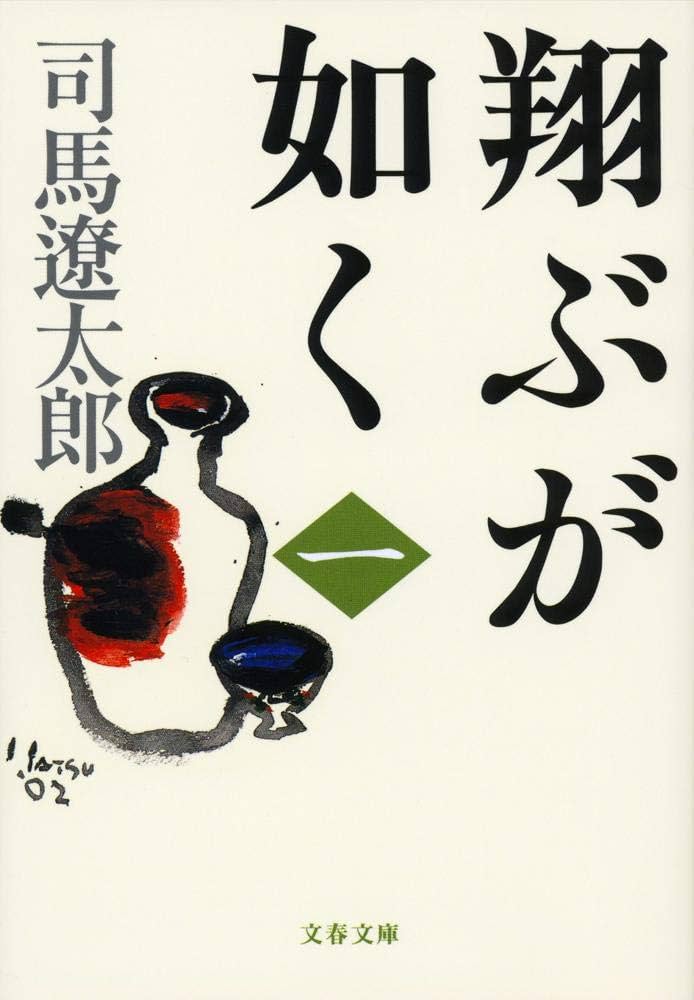
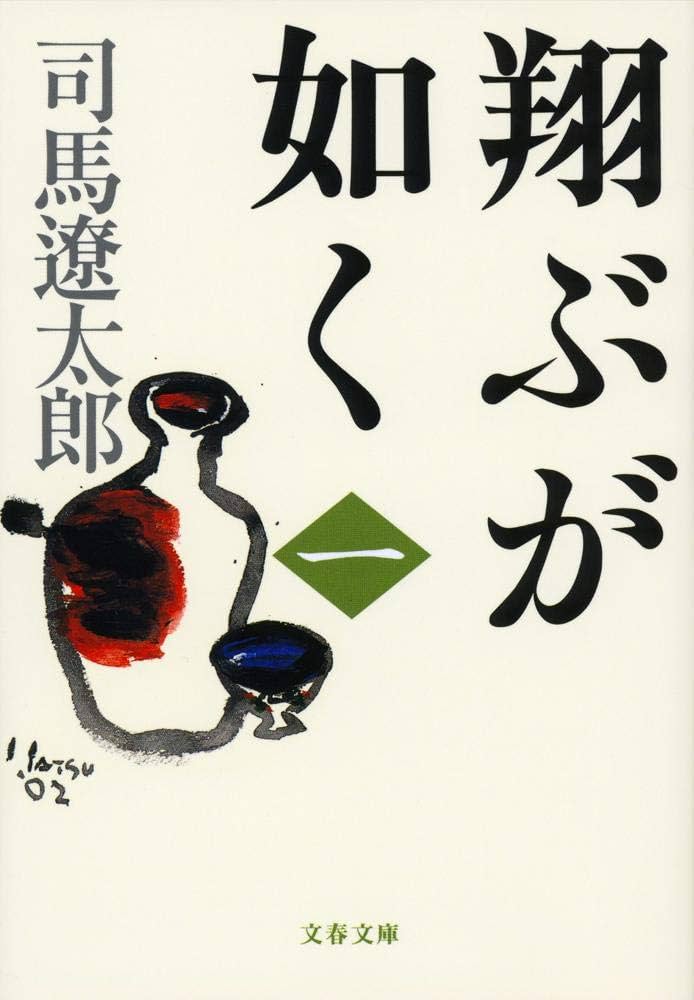
9位は、明治維新後の日本を描いた司馬遼太郎の長編大作『翔ぶが如く』です。この物語の主人公は、維新の三傑と称される西郷隆盛と大久保利通。かつては薩摩藩で共に維新を成し遂げた盟友であった二人が、なぜ西南戦争で敵味方に分かれて戦わなければならなかったのか、その謎に迫ります。
新しい国づくりへの考え方の違いから、次第にすれ違っていく二人の関係が丹念に描かれています。幕末の動乱を生き抜き、新しい時代を築いた英雄たちの、その後の栄光と悲劇を知ることができる作品です。全10巻という長編ですが、明治という新しい時代の光と影を深く理解するために、ぜひ挑戦してほしい一冊です。



あんなに仲が良かった二人が、どうして…って思うと、すごく切ない気持ちになるんだ。歴史の大きな流れの中では、個人の力ではどうにもならないことがあるんだね。
10位『酔って候』司馬遼太郎
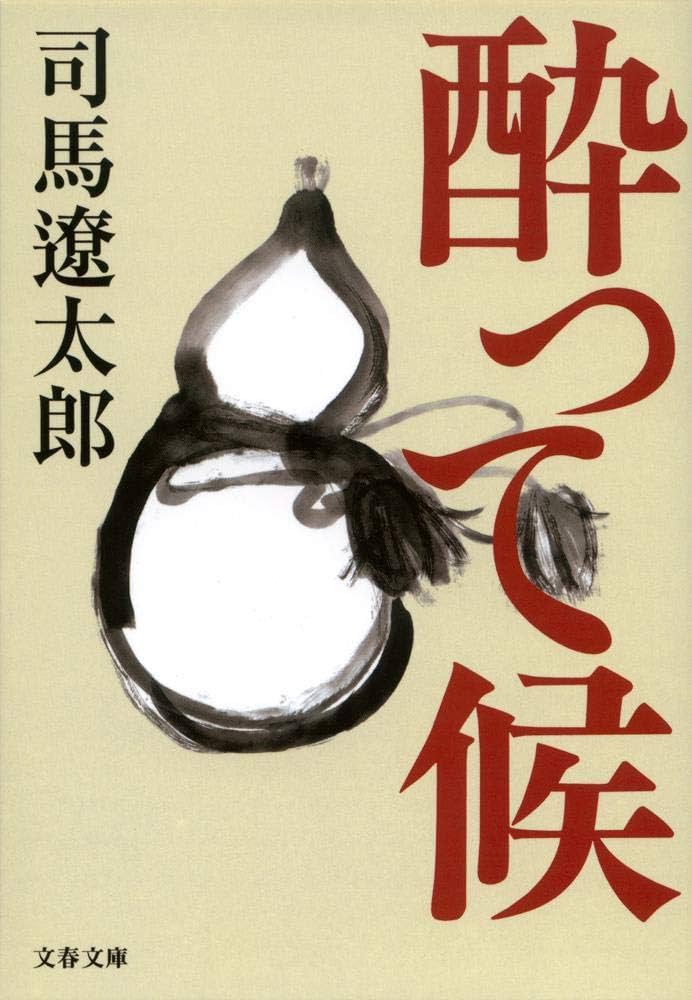
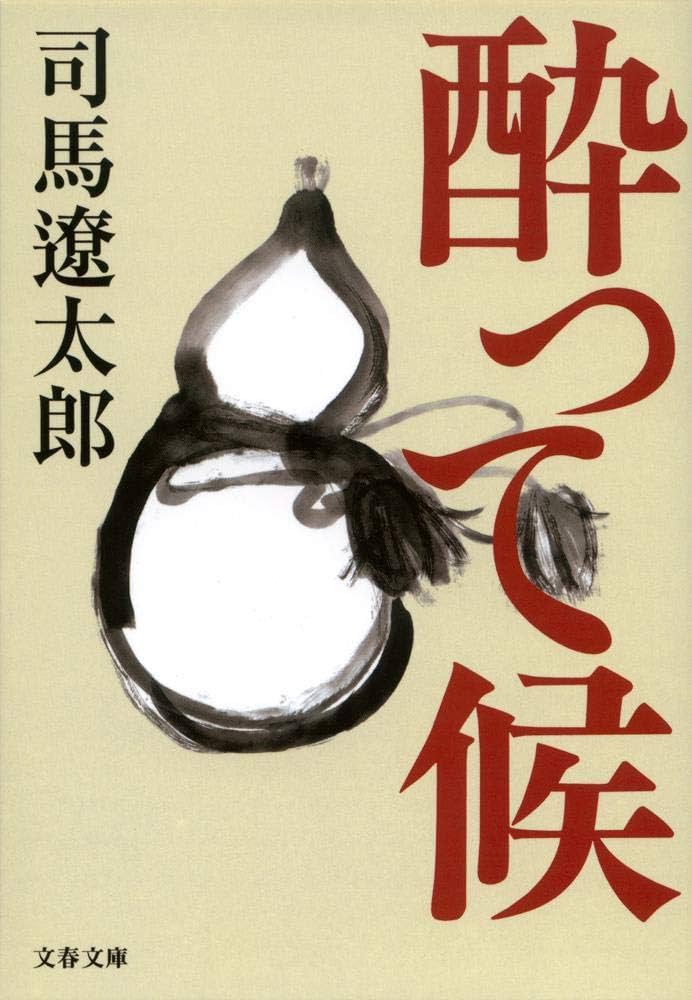
司馬遼太郎の短編集『酔って候』が10位にランクイン。この作品は、幕末期に活躍した4人の個性的な大名たちに焦点を当てています。登場するのは、土佐藩の山内容堂、薩摩藩の島津久光、宇和島藩の伊達宗城、そしてジョン万次郎を育てた漁師の中浜主人の4人です。
彼らは歴史の教科書では脇役として扱われがちですが、それぞれが非常に人間味あふれる魅力的な人物として描かれています。特に、酒をこよなく愛し、時に奇行に走りながらも鋭い政治感覚を持っていた山内容堂のエピソードは強烈な印象を残します。歴史小説初心者でも楽しみやすく、幕末という時代の多様な側面を知ることができる一冊です。



教科書ではわからない、殿様たちの意外な一面が知れてすごく面白いよ!みんな個性的で、人間臭くて、なんだか親しみが湧いちゃうんだよね。
11位『幕末』司馬遼太郎
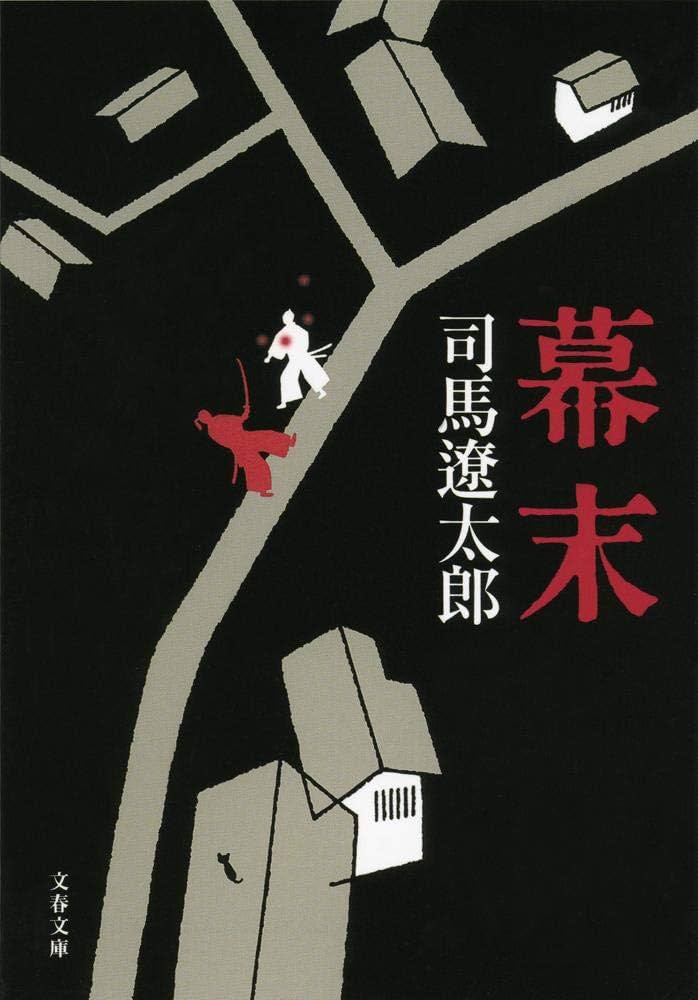
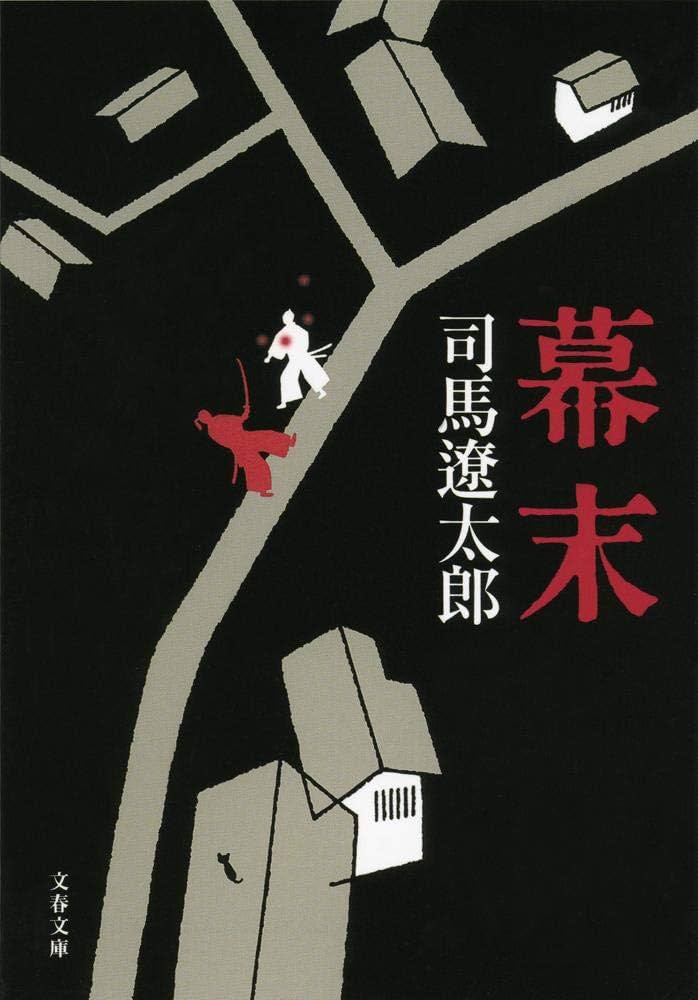
11位は、その名もずばり『幕末』。司馬遼太郎による、幕末に生きた様々な人物たちを描いた短編集です。坂本龍馬や高杉晋作といった有名人だけでなく、これまであまり光が当てられてこなかったような人物にも焦点を当て、彼らの知られざるエピソードを鮮やかに描き出しています。
例えば、新選組に粛清された芹沢鴨の豪快な生き様や、勝海舟を斬ろうとして逆に諭された男の話など、興味深い物語が満載です。一つ一つの物語は短くとも、そこには時代の空気や人間の業が凝縮されています。この短編集を読むことで、幕末という時代がいかに多くの個性的な人々によって動かされていたかがよく分かります。



いろんな人物の視点から幕末を見られるのが楽しいんだ。この本を読むと、歴史は一人の英雄だけじゃなく、たくさんの人々の生き様でできているんだなって実感するよ。
12位『胡蝶の夢』司馬遼太郎
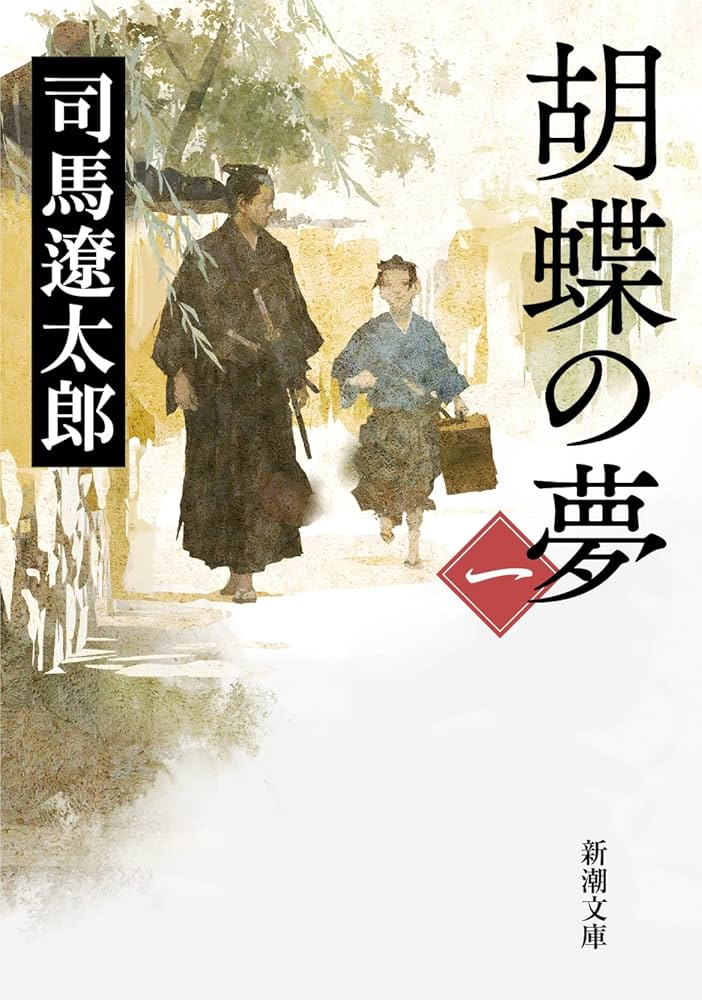
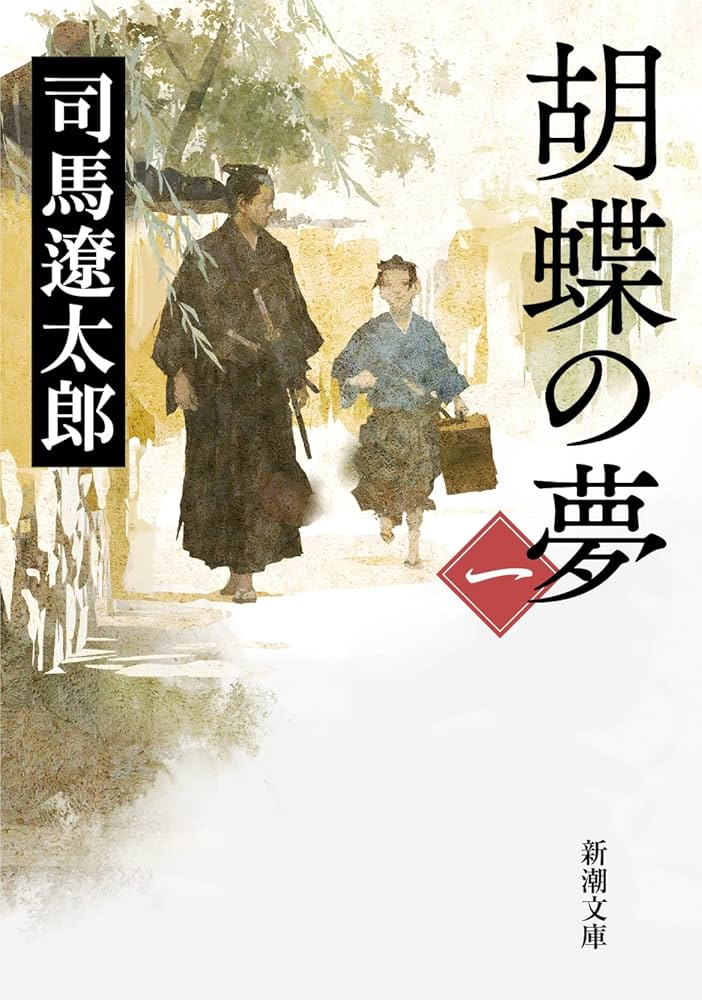
12位には、これまでの幕末小説とは一味違った視点から描かれた、司馬遼太郎の『胡蝶の夢』がランクインしました。この作品のテーマは「医学」。幕末から明治にかけて、日本の近代医学の礎を築いた二人の医師、司馬凌海と松本良順を主人公に据えています。
動乱の時代にあって、彼らは刀ではなくメスを手に、多くの人々の命を救おうと奮闘します。西洋医学の導入を巡る葛藤や、古い慣習との戦いなど、医療という視点から見る幕末は非常に新鮮です。志士たちの戦いの裏側で、このような知られざる戦いがあったことに驚かされるでしょう。医学史に興味がある方はもちろん、新しい切り口の幕末小説を読みたい方におすすめです。



剣や鉄砲だけが幕末の戦いじゃなかったんだね。人の命を救うために戦ったお医者さんたちがいたなんて、なんだか感動しちゃうな。
13位『天璋院篤姫』宮尾登美子
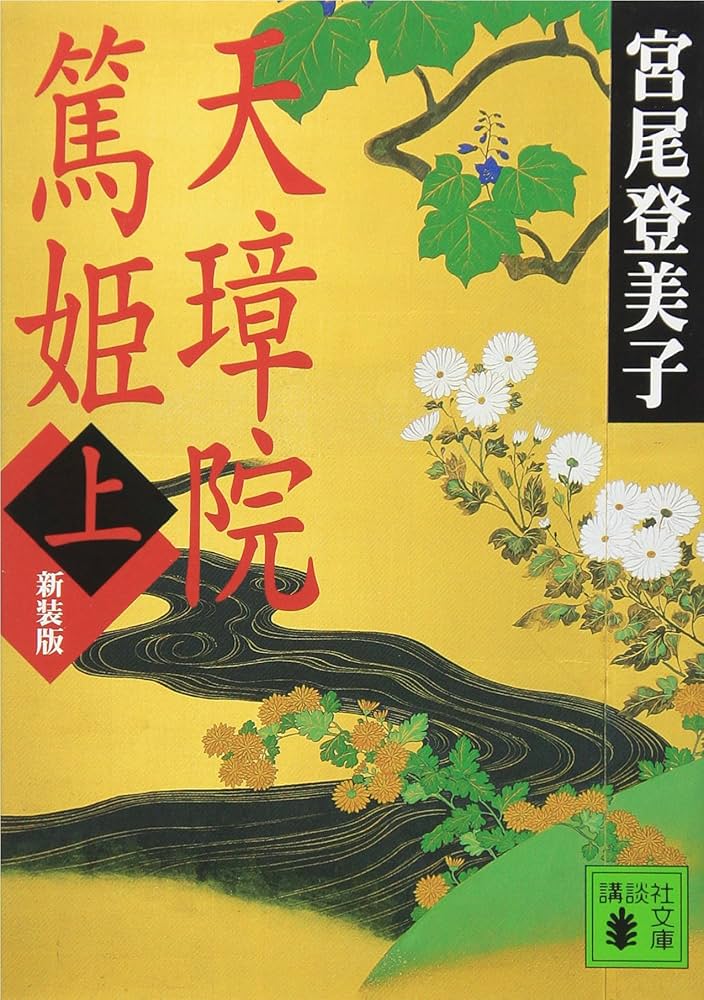
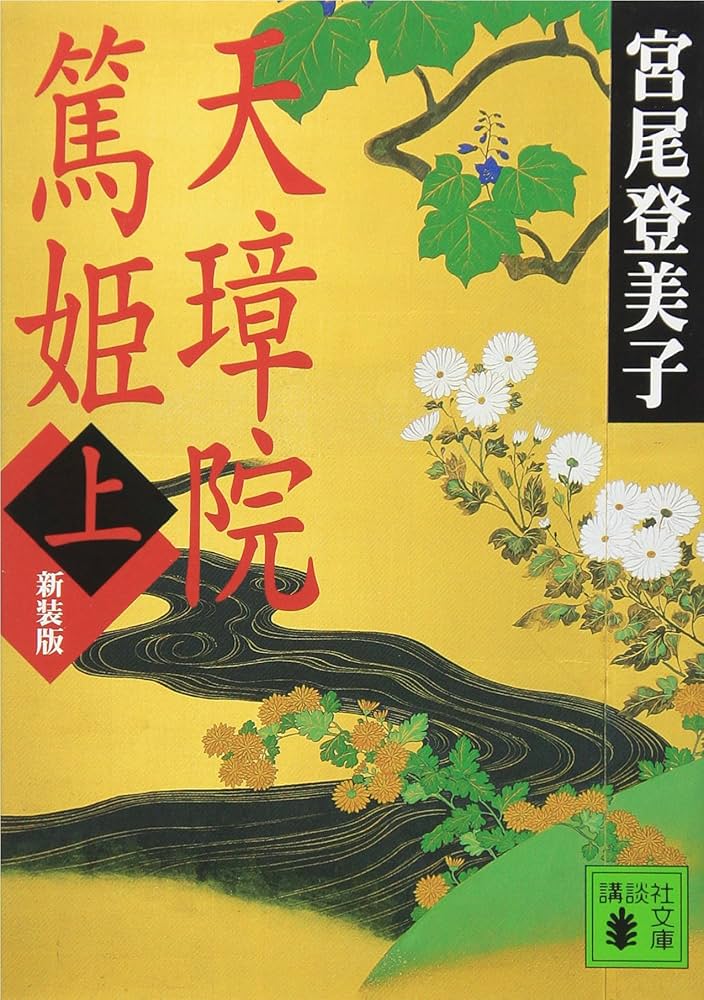
13位は、宮尾登美子が描く『天璋院篤姫』です。NHK大河ドラマの原作としても知られ、多くの人々に愛された作品です。薩摩藩島津家の分家に生まれた篤姫が、13代将軍・徳川家定の正室として大奥に入り、やがて徳川宗家を背負って激動の時代を生きていく姿を描いています。
男たちの政治の世界の裏側で、大奥という女性たちの世界では何が起こっていたのか。聡明で芯の強い篤姫が、徳川家を守るためにいかに戦ったのかが、緻密な筆致で描かれています。彼女の波乱万丈の人生を通して、女性の視点から幕末という時代を捉え直すことができる、重厚な歴史大作です。



篤姫の、自分の運命を受け入れて強く生きていく姿にすごく勇気をもらえるんだ。女性の視点から描かれる幕末も、また違った面白さがあるよね。
14位『麒麟児』葉室麟
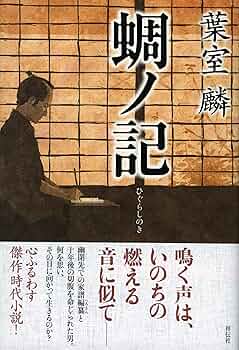
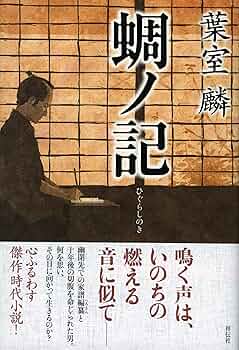
14位には、葉室麟の『麒麟児』がランクイン。この作品は、6位の『峠』と同じく、越後長岡藩の家老・河井継之助を主人公としています。同じ人物を描きながらも、作家によってその解釈や描き方が異なるのが歴史小説の面白いところです。
葉室麟は、継之助の持つ「武士としての義」や「人間としての情」に深く迫ります。藩の運命を背負い、苦渋の決断を重ねていく継之助の姿は、読む者の胸を打ちます。司馬遼太郎の『峠』を読んだことがある人も、また新たな河井継之助像に出会えるはずです。武士の生き様や矜持を描かせたら右に出る者はいない、葉室麟の真骨頂ともいえる一冊です。



同じ人物を違う作家さんが描くと、こんなにも印象が変わるんだね!読み比べてみると、歴史の面白さがもっと深まる気がするな。
15位『一刀斎夢録』浅田次郎
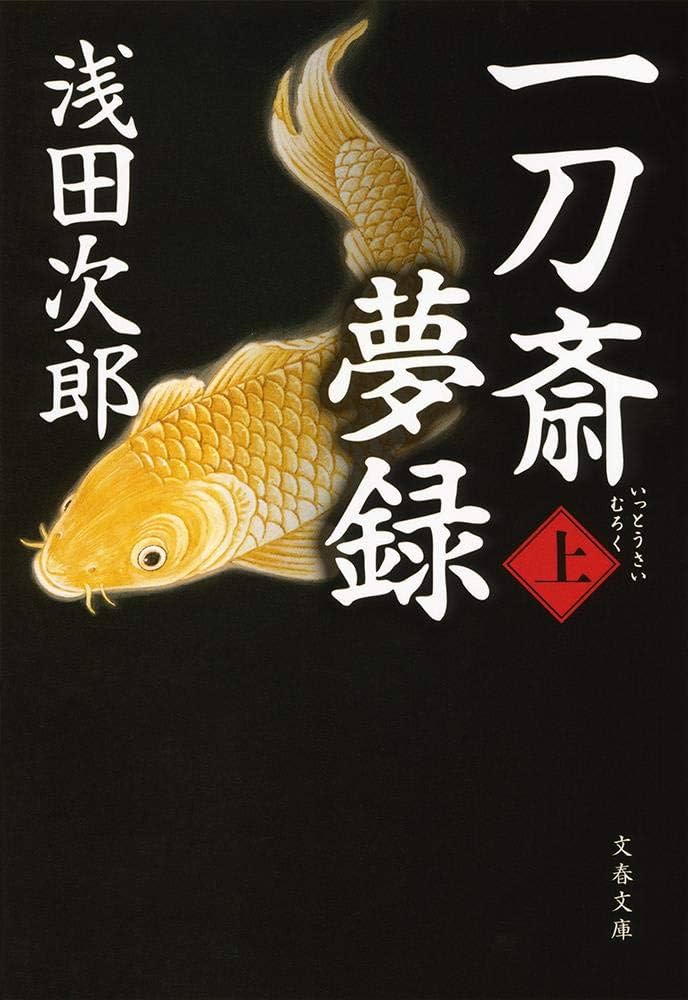
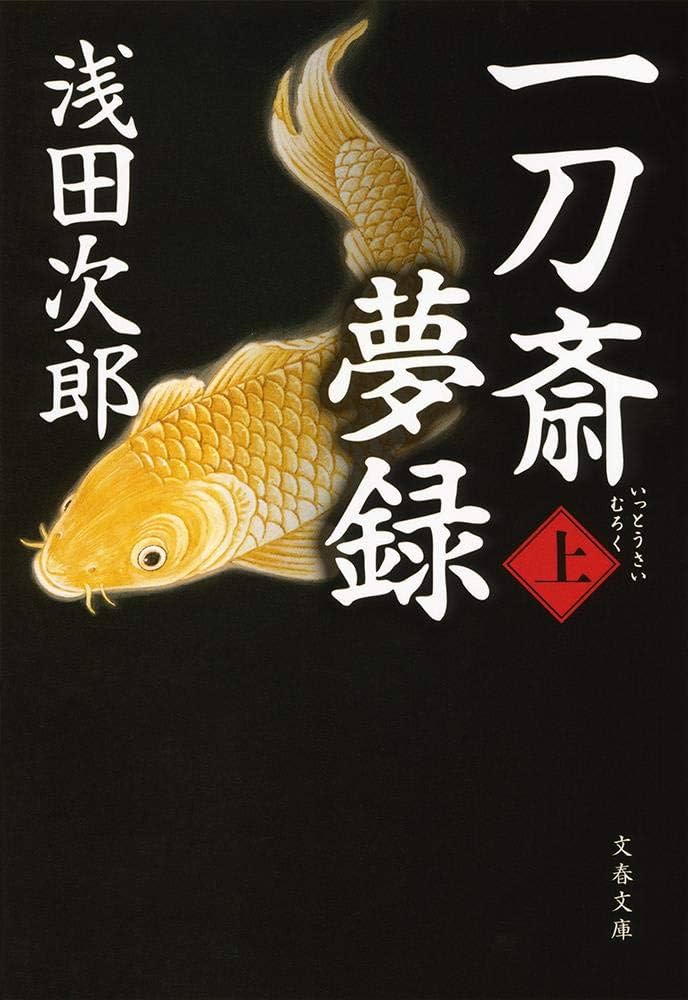
15位は、浅田次郎が描くもう一つの新選組物語『一刀斎夢録』です。主人公は、新選組の中でも最強の剣客と謳われ、謎の多い人物として知られる三番隊組長・斎藤一。明治の世を生き延びた彼が、自らの壮絶な半生を振り返るという形で物語は進みます。
新選組の誕生から、池田屋事件、鳥羽・伏見の戦い、そして会津戦争まで、斎藤一は常に最前線で戦い続けました。彼は何を想い、何のために剣を振るったのか。最後まで武士としての義を貫き通した男の、寡黙な背中が目に浮かぶようです。浅田次郎ならではの、哀愁と温かみに満ちた筆致で描かれる、もう一人の「義士」の物語です。



斎藤一って、ミステリアスでかっこいいよね。彼が最後まで見届けた新選組の真実って何だったんだろうって、すごく引き込まれちゃうんだ。
16位『幕末遊撃隊』池波正太郎
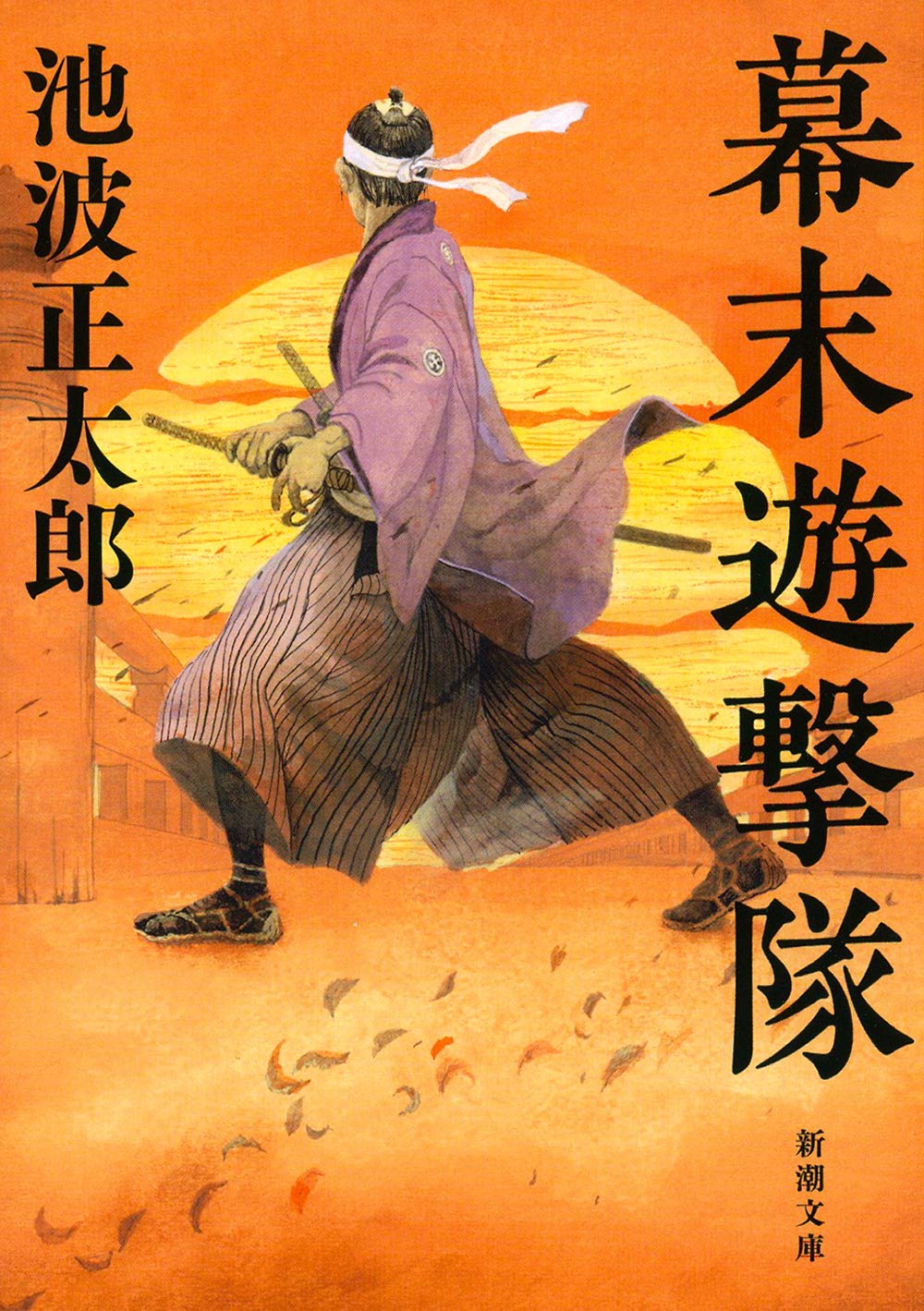
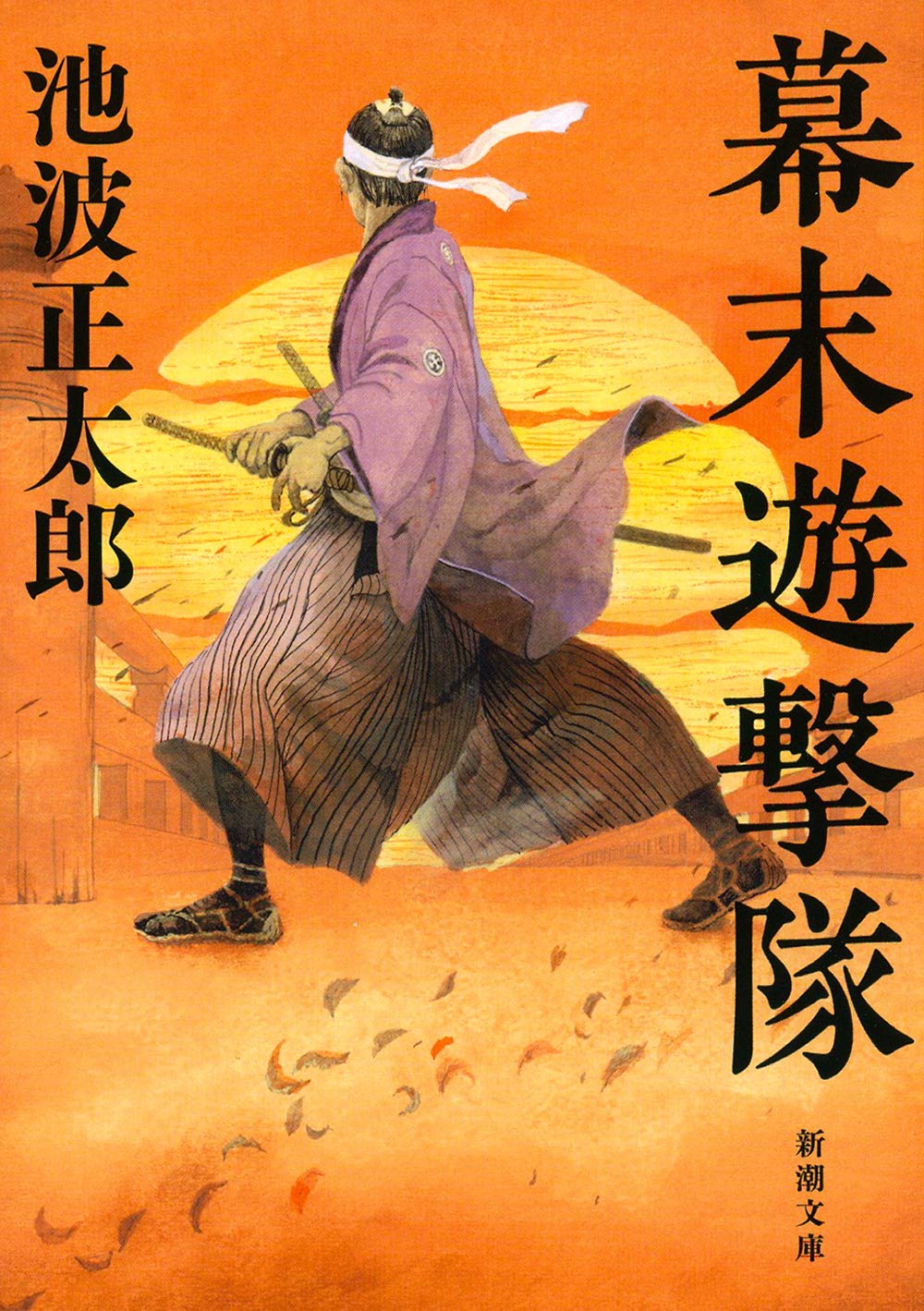
16位には、時代小説の名手・池波正太郎の『幕末遊撃隊』がランクインしました。主人公は、幕臣でありながら剣客として名を馳せた伊庭八郎。心形刀流の名門道場の跡継ぎとして生まれ、若くして「江戸一番の美男子」と謳われた彼の、短くも鮮烈な生涯を描いています。
将軍警護のために京へ上った八郎は、仲間たちと遊撃隊を組織し、新政府軍と激しい戦いを繰り広げます。結核を患いながらも、最後まで幕府への忠義を尽くそうとする彼の姿は、潔く、そして美しい。池波正太郎らしい軽快な筆致と、江戸っ子らしい伊庭八郎の小気味よいキャラクターが魅力の、エンターテイメント性あふれる傑作です。



伊庭八郎の生き様が、とにかくかっこいいんだ!池波先生の描く剣客小説は、読んでいてスカッとするよね。
17位『人斬り半次郎』池波正太郎
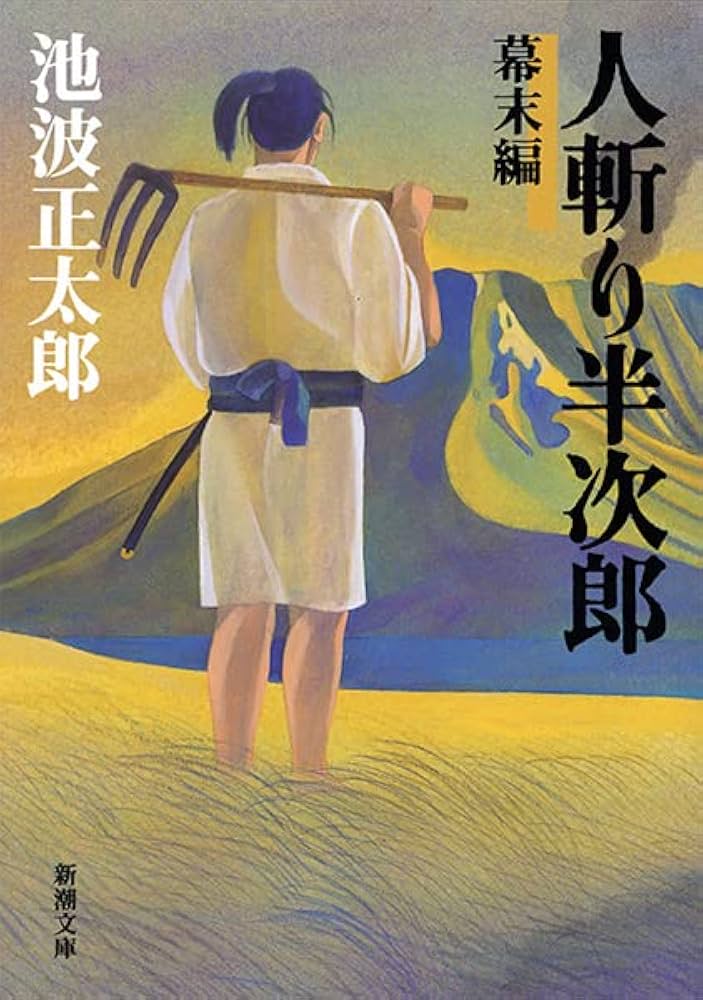
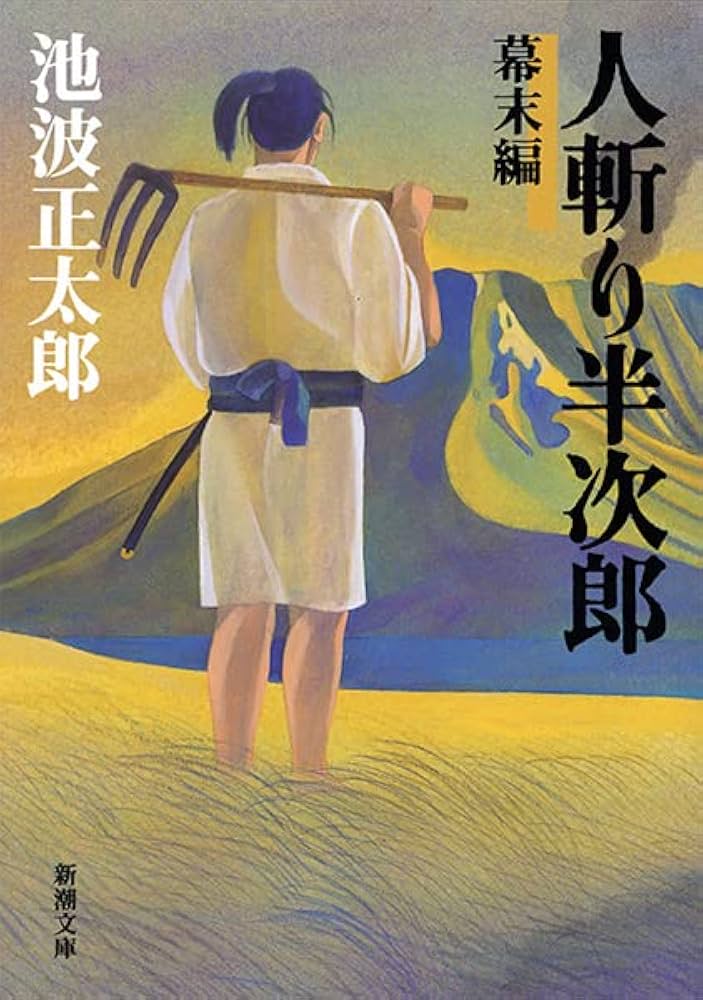
池波正太郎作品が続きます。17位は、幕末四大人斬りの一人と恐れられた薩摩藩士・中村半次郎(後の桐野利秋)を主人公にした『人斬り半次郎』です。人並み外れた剣の腕を持ちながらも、どこか人懐っこく憎めない半次郎のキャラクターが魅力的に描かれています。
貧しい下級武士の家に生まれた半次郎が、西郷隆盛という偉大なリーダーに出会い、いかにして時代を動かす存在になっていったのか。彼の目線を通して見ることで、英雄・西郷隆盛の偉大さや、激動の時代を生きた普通の人々の生活を肌で感じることができます。人を斬るという宿命を背負った男の、孤独と栄光の物語です。



「人斬り」って聞くと怖いイメージだけど、半次郎の人間的な魅力にどんどん惹きつけられちゃうんだ。彼の純粋さが、なんだか切ないよね。
18位『黒龍の柩』北方謙三
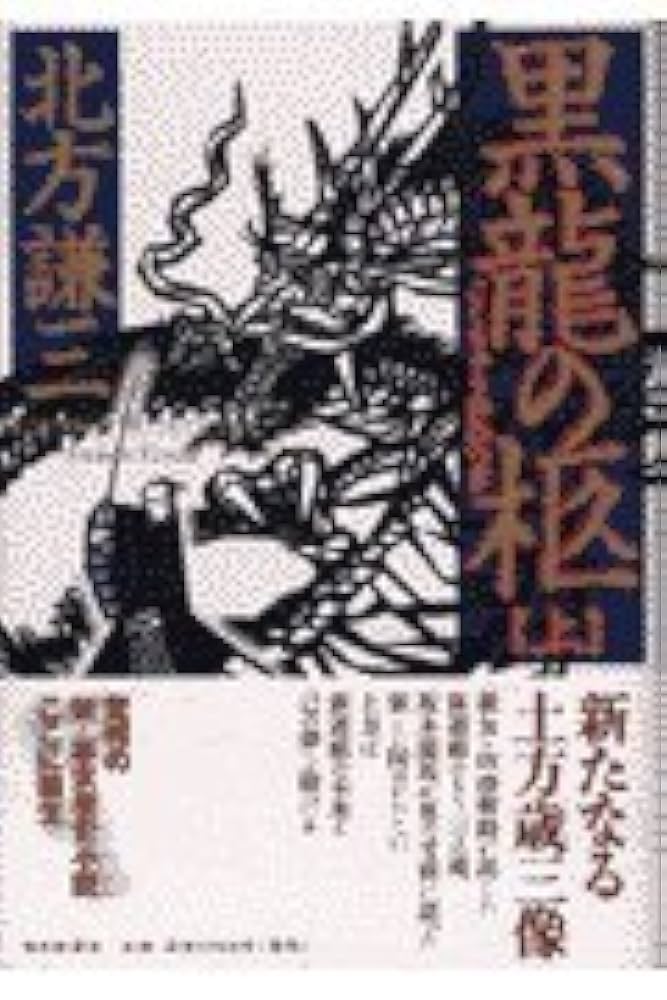
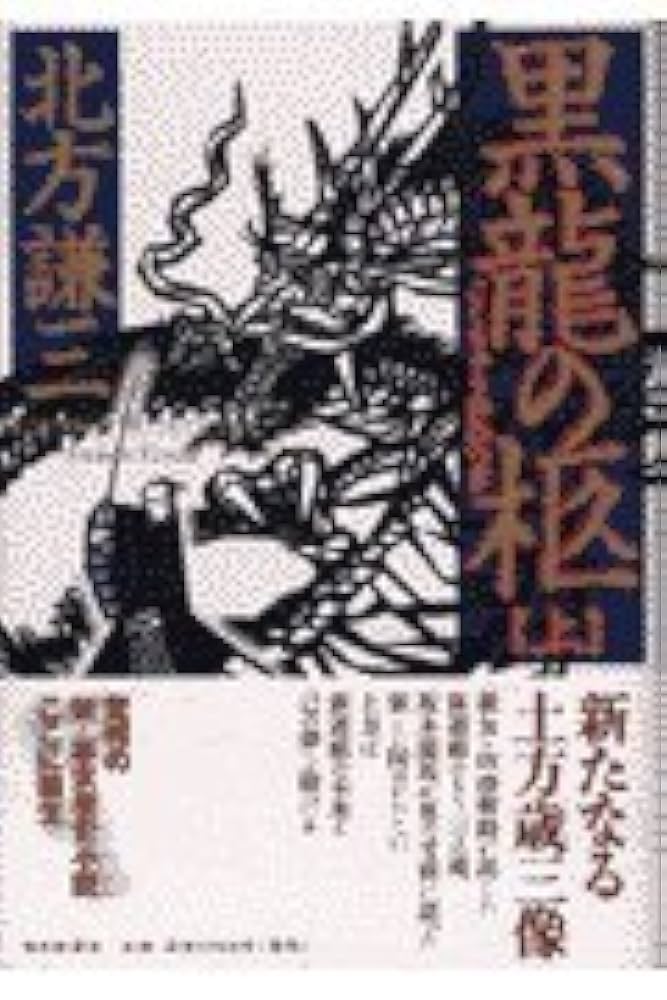
18位は、ハードボイルド小説の巨匠・北方謙三が幕末を描いた『黒龍の柩』です。物語の舞台は、戊辰戦争の最後の戦いの地となった蝦夷(えぞ)、現在の北海道。土方歳三や榎本武揚といった旧幕府軍の残党たちが、新政府軍を相手に最後の戦いを挑む姿を、北方謙三ならではの熱い筆致で描いています。
敗北を悟りながらも、己の信念のために戦い続ける男たちの姿は、まさに圧巻の一言。極寒の大地で繰り広げられる、魂と魂がぶつかり合うような激しいドラマに、胸が熱くなること間違いなしです。北方謙三ファンはもちろん、熱い男たちの物語が好きな人にはたまらない一冊でしょう。



北方先生が描く男たちの生き様は、いつ読んでも痺れるね。極限状況でこそ、人間の真価が問われるんだ。
19位『西郷どん!』林真理子
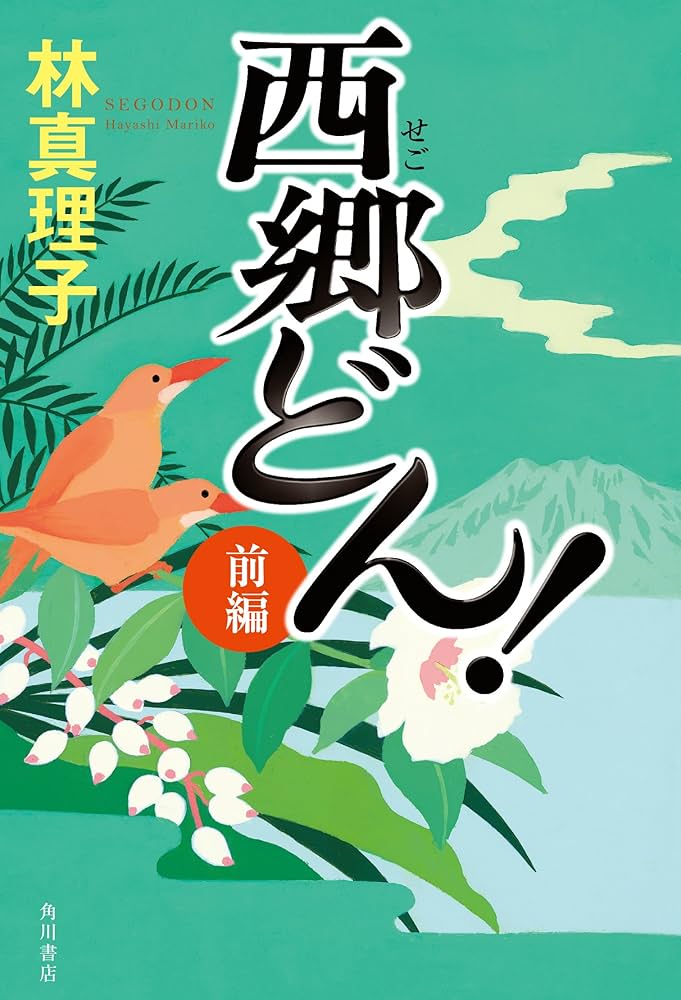
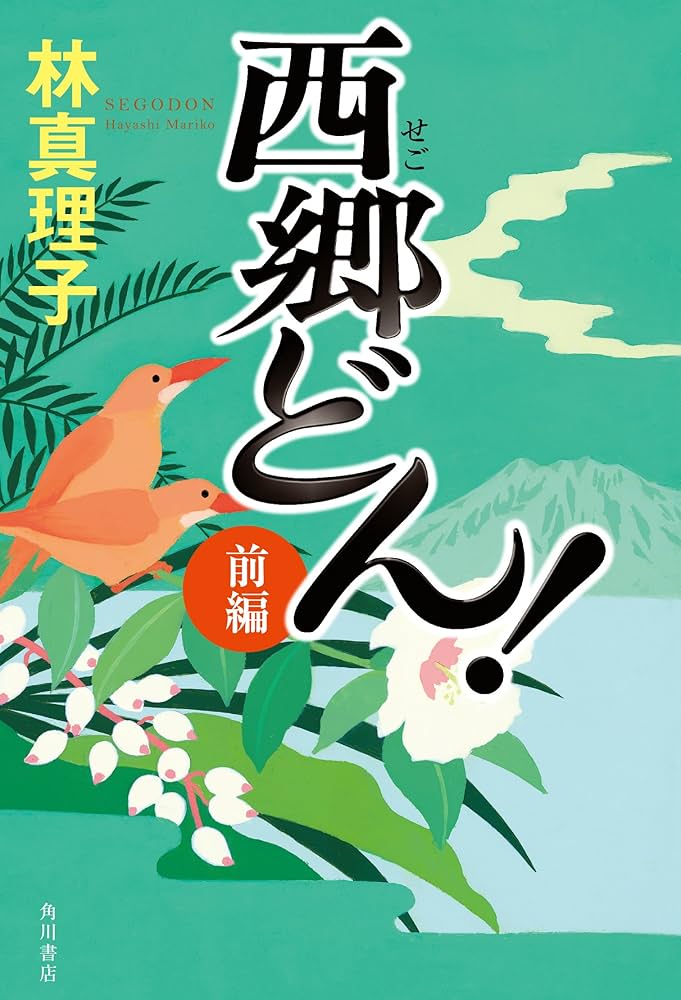
19位には、2018年のNHK大河ドラマの原作ともなった林真理子の『西郷どん!』がランクイン。維新の英雄・西郷隆盛の生涯を、家族や師弟、友人、そして愛した女性たちとの深く温かい人間関係を通して描いた作品です。
これまで英雄として語られることの多かった西郷隆盛ですが、この小説では、悩み、笑い、涙する、人間味あふれる「西郷さん」として生き生きと描かれています。特に、二度の島流しや、身分違いの恋など、彼の人生の知られざる側面に光を当てているのが特徴です。林真理子ならではの視点で描かれる、新しい西郷隆盛像にきっと魅了されるはずです。



英雄っていうイメージが強かったけど、この本を読むと西郷さんがすごく身近な存在に感じられるんだ。彼の優しさと大きさに、なんだかホッとしちゃうな。
20位『和宮様御留』有吉佐和子
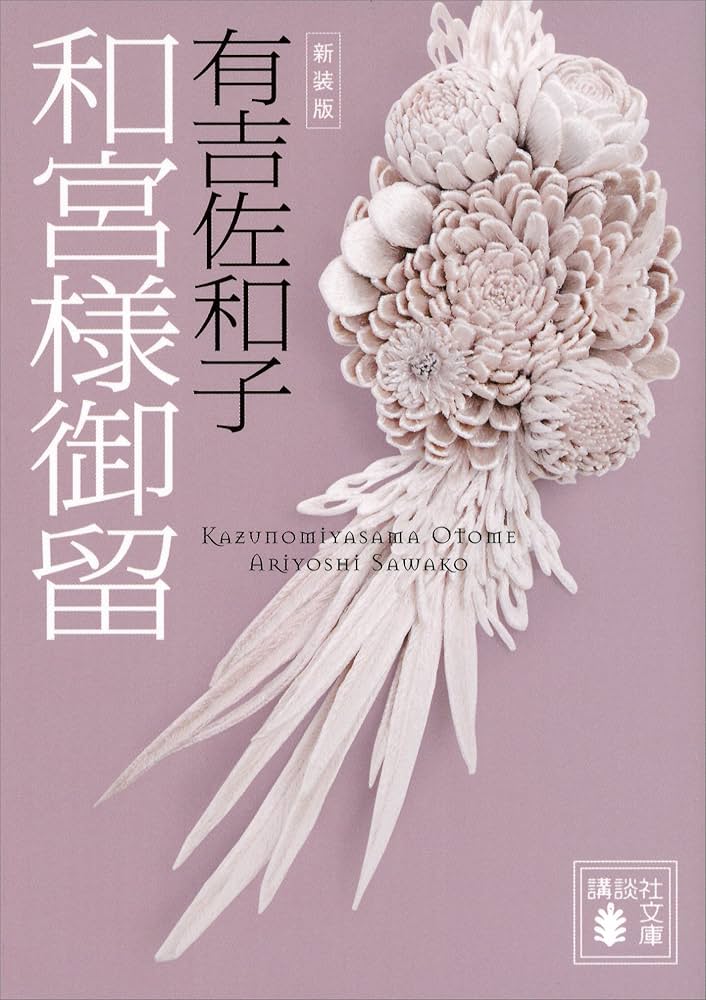
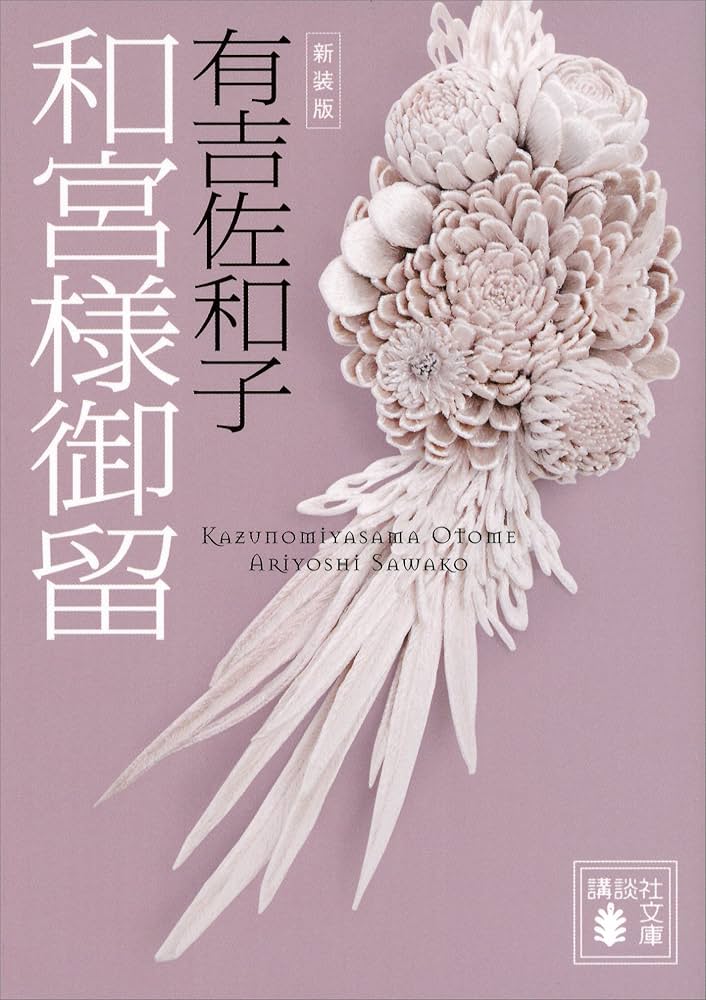
20位は、有吉佐和子の歴史ミステリー『和宮様御留』です。公武合体政策のため、仁孝天皇の皇女・和宮が14代将軍・徳川家茂に嫁いだという史実。しかし、もし江戸へ下ったのが偽物の和宮だったら…?という大胆な設定で物語が展開します。
大奥を舞台に、様々な人々の思惑が渦巻く中で、替え玉として生きることを強いられた少女の運命を描いています。歴史の「もしも」に迫るミステリー要素と、時代の波に翻弄される女性の悲劇が巧みに織り交ぜられており、読者は最後までページをめくる手が止まらなくなるでしょう。歴史の裏側に隠されたかもしれない、もう一つの物語に想いを馳せてみてください。



え、もし和宮様が偽物だったら…!?って、考えただけでドキドキしちゃうよね。歴史のミステリーって、想像力が掻き立てられてすごく面白いんだ!
21位『我は景祐 幕末仙台流星伝』熊谷達也
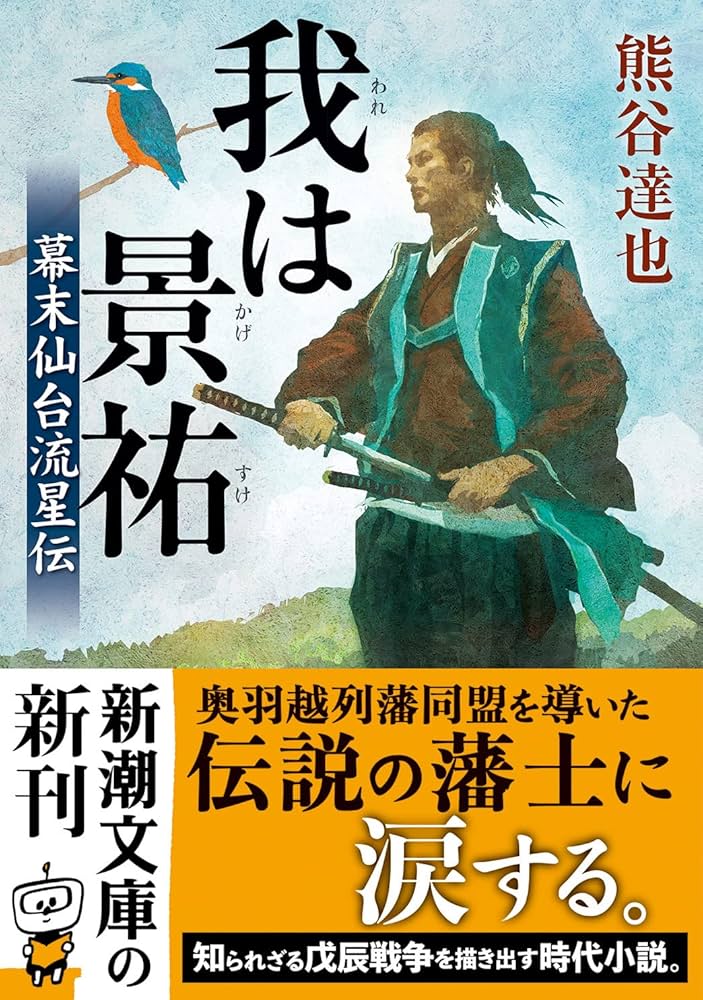
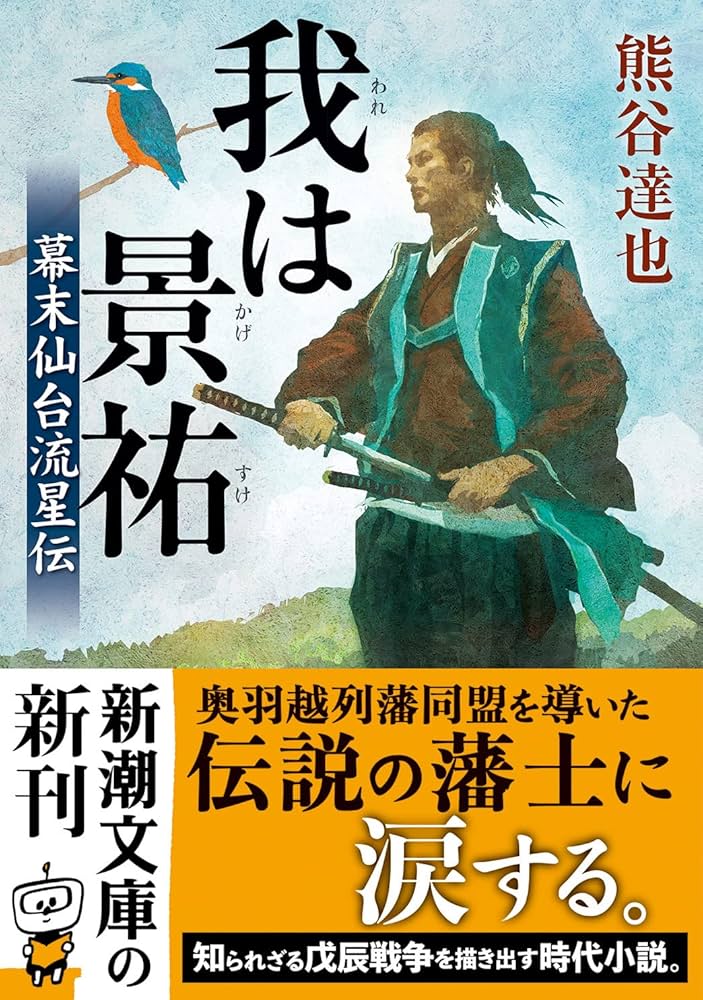
21位にランクインしたのは、熊谷達也の『我は景祐 幕末仙台流星伝』。幕末の歴史は薩長土肥を中心に語られがちですが、この作品は東北・仙台藩の視点から戊辰戦争を描いています。
主人公は、仙台藩の藩士であり、日本で初めてフランス式の軍楽隊を組織した星恂太郎。彼は、藩が降伏した後も戦うことをやめず、榎本武揚率いる旧幕府軍に合流して箱館まで転戦します。勝者の歴史の影に隠された、敗者の側の正義と誇りとは何だったのか。東北の雄藩としての意地を胸に、最後まで戦い抜いた男たちの熱いドラマが胸を打ちます。



薩長だけが幕末の主役じゃないんだよね。東北からの視点で描かれる物語は、歴史の多面性を教えてくれるからすごく興味深いな。
22位『新選組 幕末の青嵐』木内昇
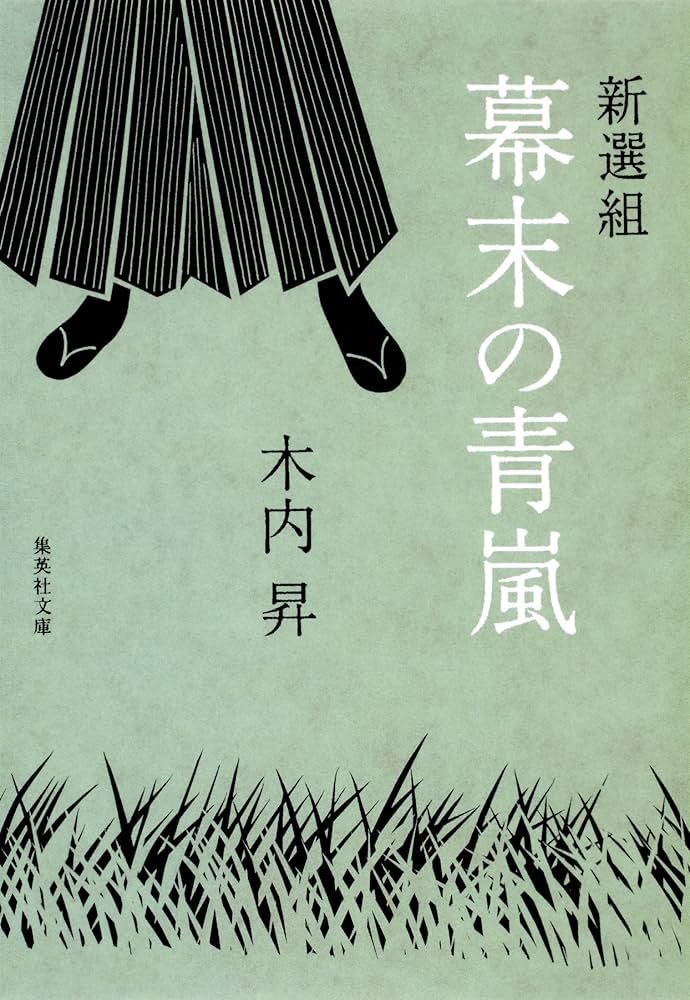
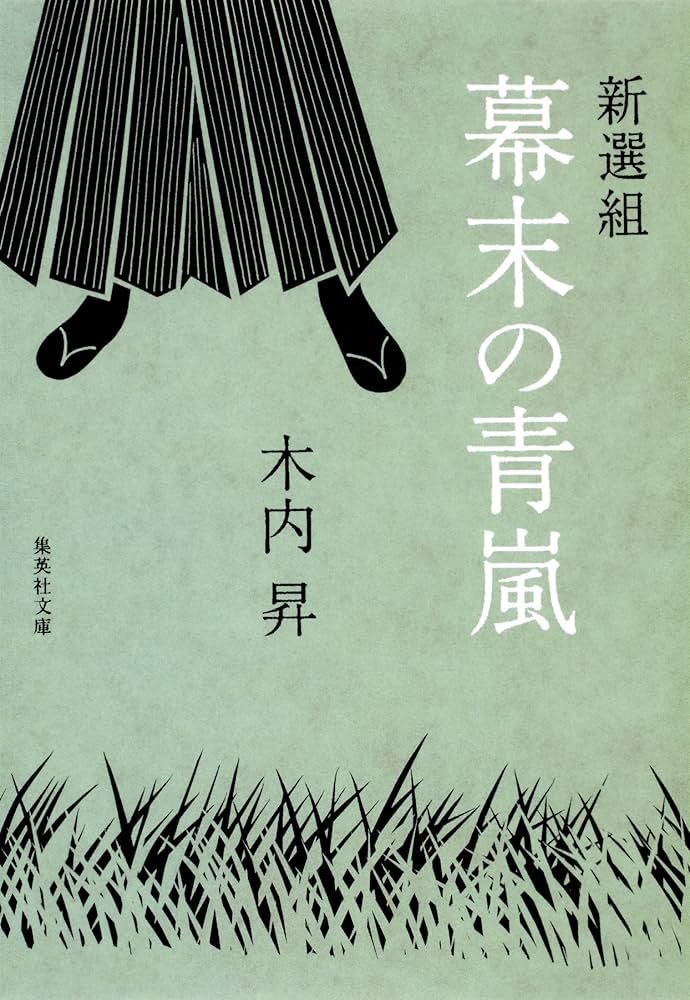
22位は、新しい視点から新選組を描いた木内昇の『新選組 幕末の青嵐』です。多くの新選組小説が近藤勇や土方歳三といったスター隊士を主人公にするのに対し、この作品では会計方という裏方の役職に就いていた河合耆三郎という人物に焦点を当てています。
剣の腕ではなく、そろばんの腕で隊に貢献しようとする耆三郎。しかし、武士としての価値観が支配する組織の中で、彼の立場は次第に危うくなっていきます。華々しい活躍の裏側にある、組織の理不尽さや人間の弱さ、そして名もなき隊士たちの苦悩がリアルに描かれており、これまでの新選組のイメージを覆されるかもしれません。



キラキラした新選組だけじゃないんだ…。弱い立場から見た組織のリアルさが、すごく心に刺さる物語だよ。
23位『歳三之夢』北方謙三
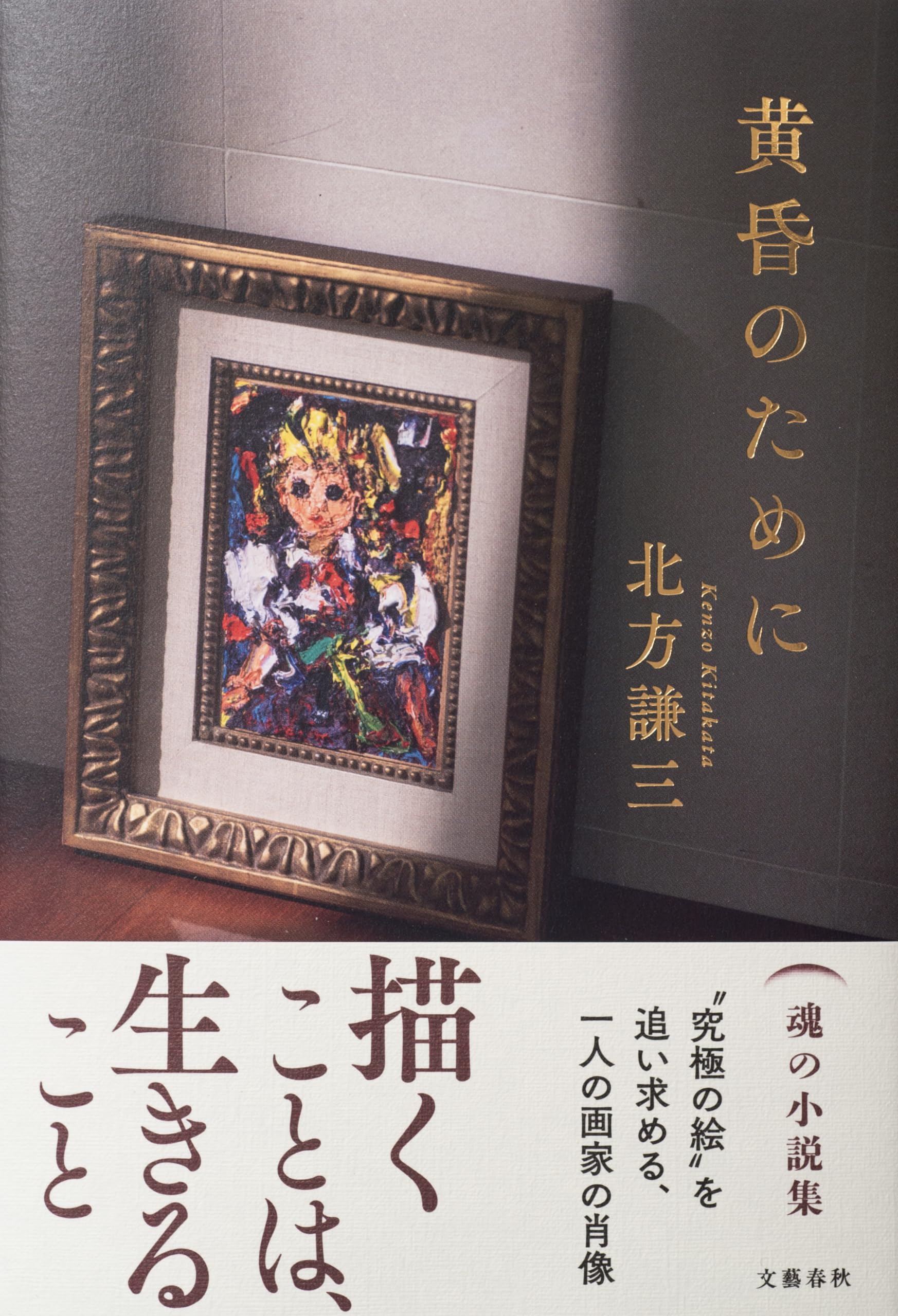
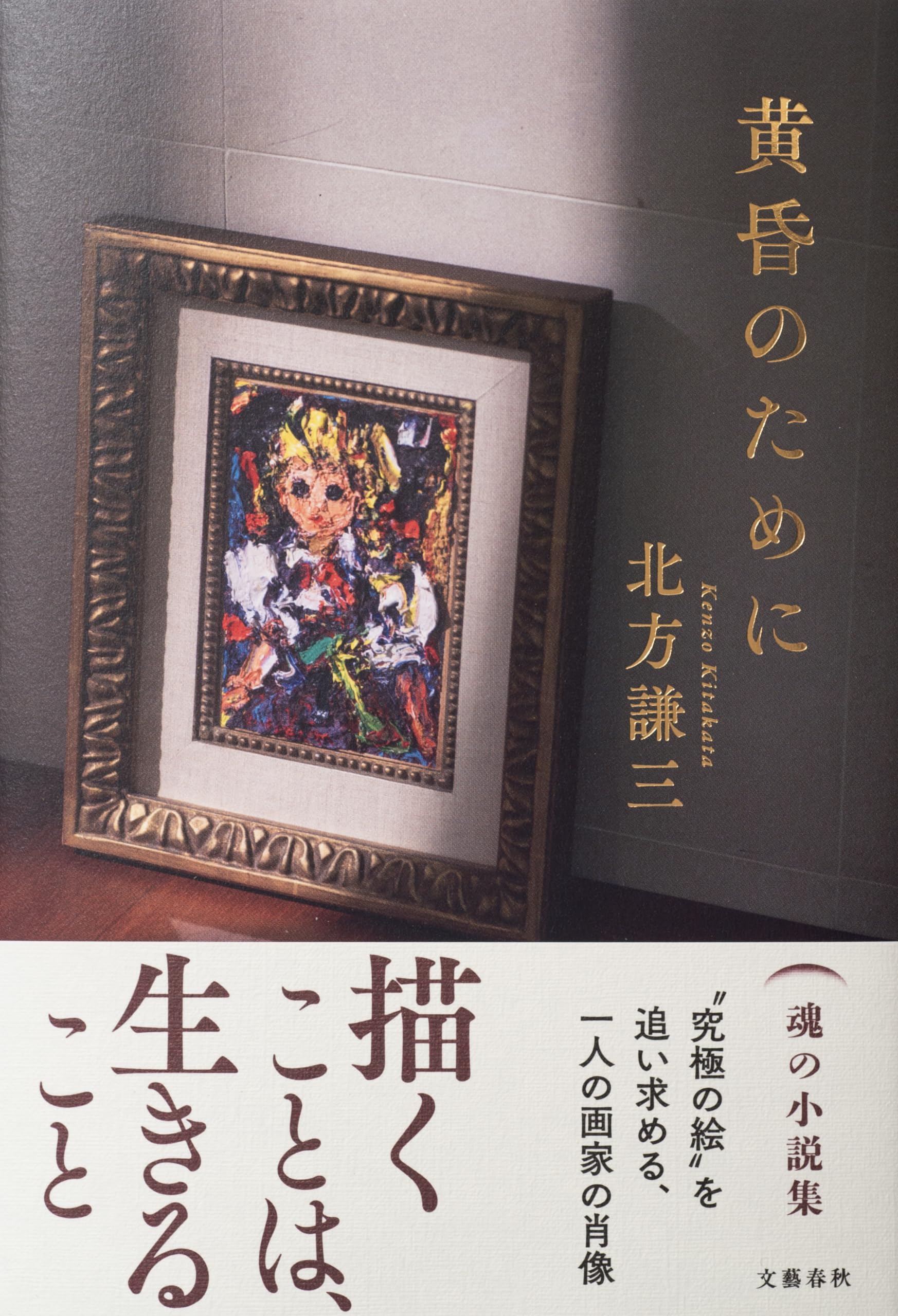
23位には、再び北方謙三作品が登場。『黒龍の柩』と同じく箱館戦争を舞台にしていますが、こちらは土方歳三その人に焦点を当てた物語です。北方ハードボイルドの世界観で描かれる土方歳三は、まさに孤高の戦士そのものです。
敗色が濃厚になる中で、土方は何を夢見て戦い続けたのか。彼の内面に深く迫り、その生き様を熱く、そして切なく描き出します。史実に基づきながらも、北方謙三ならではの解釈が加わった土方歳三像は、ファンならずとも必見です。男の美学が凝縮された一冊と言えるでしょう。



北方先生の手にかかると、土方歳三の格好良さがさらに際立つね!彼が最後まで見続けた夢を思うと、胸が熱くなるよ。
24位『会津の義 幕末の藩主松平容保』中村彰彦
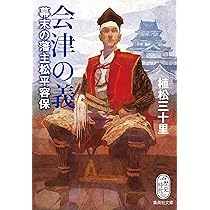
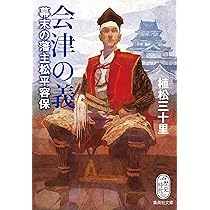
24位は、幕末の悲劇の藩として知られる会津藩の藩主・松平容保の生涯を描いた、中村彰彦の『会津の義 幕末の藩主松平容保』です。京都守護職という貧乏くじを引かされ、最後まで幕府への忠義を尽くした結果、朝敵の汚名を着せられてしまった会津藩。
そのトップであった松平容保は、どのような思いで藩を率いていたのでしょうか。彼の誠実で義理堅い人柄と、藩主としての苦悩が丁寧に描かれています。会津戦争の悲劇だけでなく、なぜ会津がそこまでして「義」を貫こうとしたのか、その精神的支柱を知ることができる作品です。



会津藩の物語は、本当に切ない…。でも、彼らが守ろうとした「義」の精神は、時代を超えて人の心を打つんだね。
25位『青山に在り』山本一力
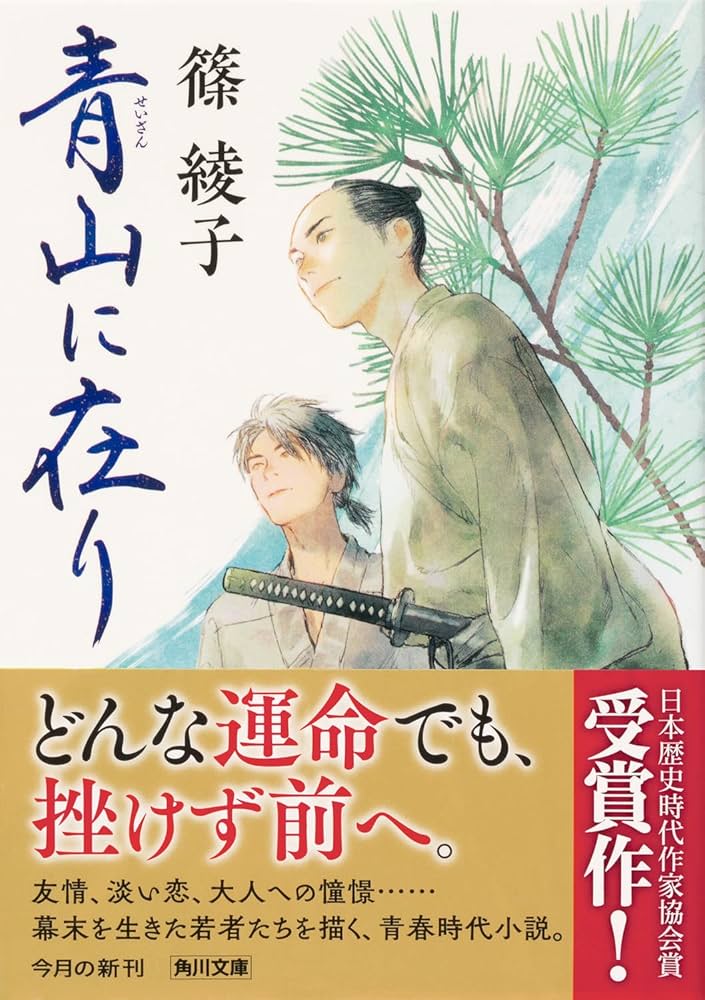
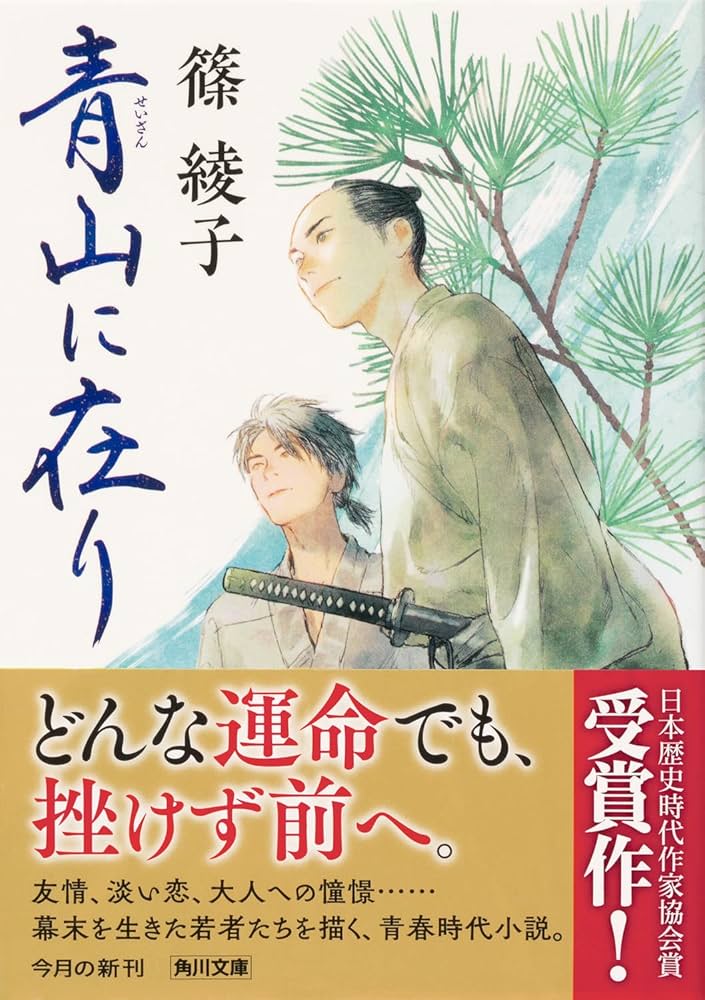
25位は、山本一力の『青山に在り』。これまでの作品とは異なり、武士ではなく、幕末から明治という激動の時代を生きた商家の家族を主人公にした物語です。
時代の大きな変化は、志士たちだけでなく、市井に生きる普通の人々の生活にも大きな影響を与えました。価値観が根底から覆される中で、彼らはいかにして商いを続け、家族を守り、たくましく生きていったのか。庶民の視点から時代の移り変わりを描くことで、歴史をより立体的に感じることができます。人情味あふれる登場人物たちに、きっと元気をもらえるはずです。



武士だけじゃなく、商人たちの視点から見る幕末もすごく面白いんだ。時代の変化に負けずに頑張る姿に、勇気をもらえるよ!
26位『流転の中将』江宮隆之
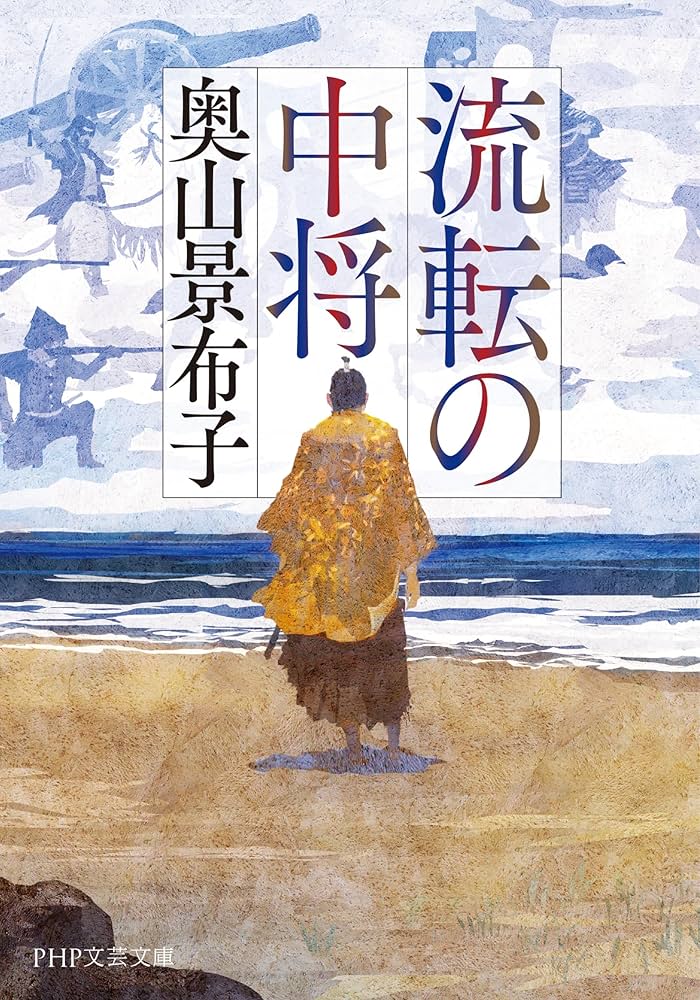
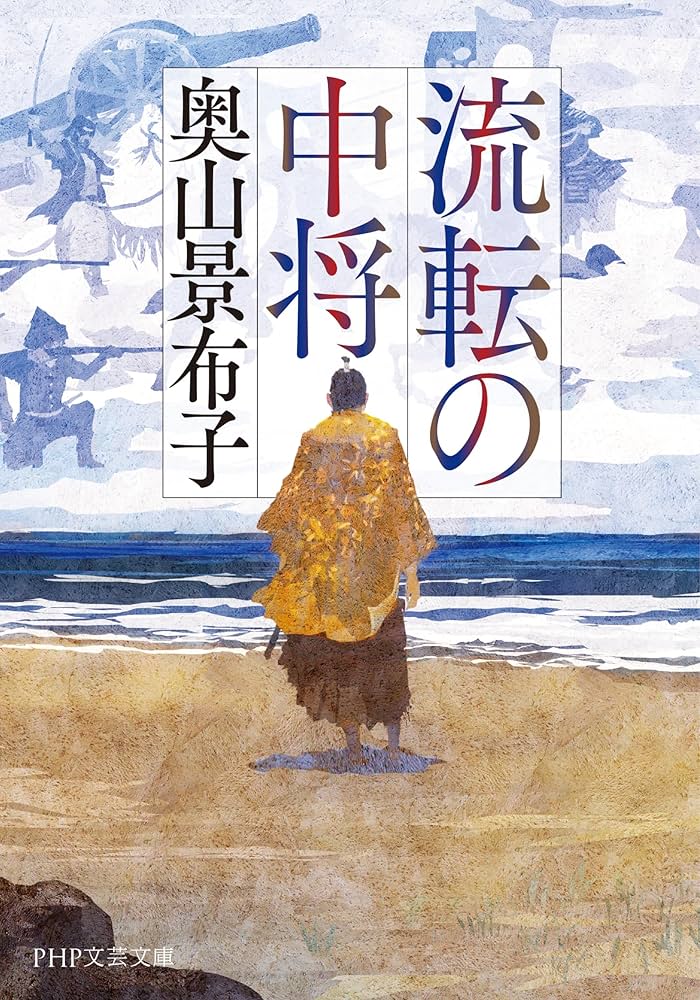
26位には、会津藩士・秋月登之助の数奇な運命を描いた江宮隆之の『流転の中将』がランクイン。秋月登之助は、戊辰戦争で活躍したものの、戦後は生き延び、明治の世で全く別の人生を歩んだ人物です。
敗者として、彼は何を思い、どのように新しい時代と向き合ったのでしょうか。幕末の終わりは、多くの人々にとって新しい人生の始まりでもありました。戦争が終わった後の「その後」の人生に焦点を当てることで、時代の変化の重みと、人間の持つ生命力の強さを感じさせてくれる一冊です。



戦いが終わっても、人生は続くんだよね。敗者となった人たちが、その後どう生きたのかを知るのも、歴史の面白いところだと思うな。
27位『イクサガミ』今村翔吾
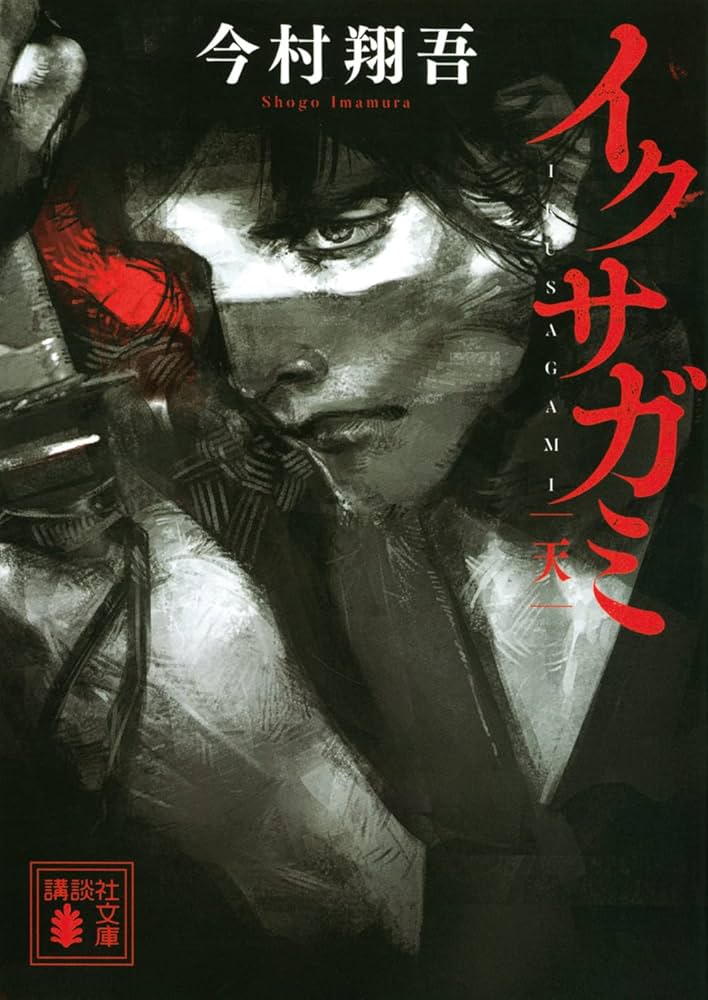
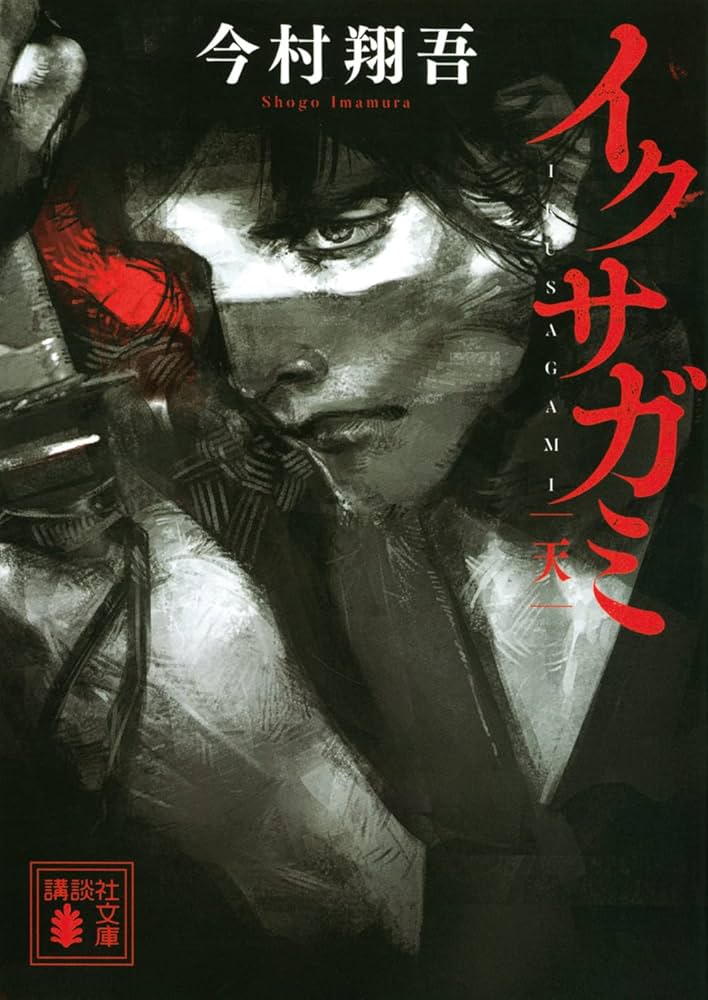
27位は、今最も勢いのある歴史・時代小説家の一人、今村翔吾のエンターテイメント大作『イクサガミ』です。時は幕末、明治政府によって仕組まれた理不尽な殺人ゲーム「汰刃(たば)の沙汰」に参加させられた人々の、壮絶なサバイバルが描かれます。
歴史的事実をベースにしながらも、奇想天外な設定とスリリングな展開で、読者を一気に物語の世界へ引き込みます。なぜこのゲームは始まったのか? そして、生き残るのは誰なのか? 息もつかせぬ展開に、ページをめくる手が止まらなくなること間違いなし。新しいタイプの幕末小説を読みたい方におすすめです。



幕末が舞台のデスゲームなんて、設定が斬新すぎるよ!ハラハラドキドキの展開に、一気読みしちゃった。
28位『威風堂々』伊東潤
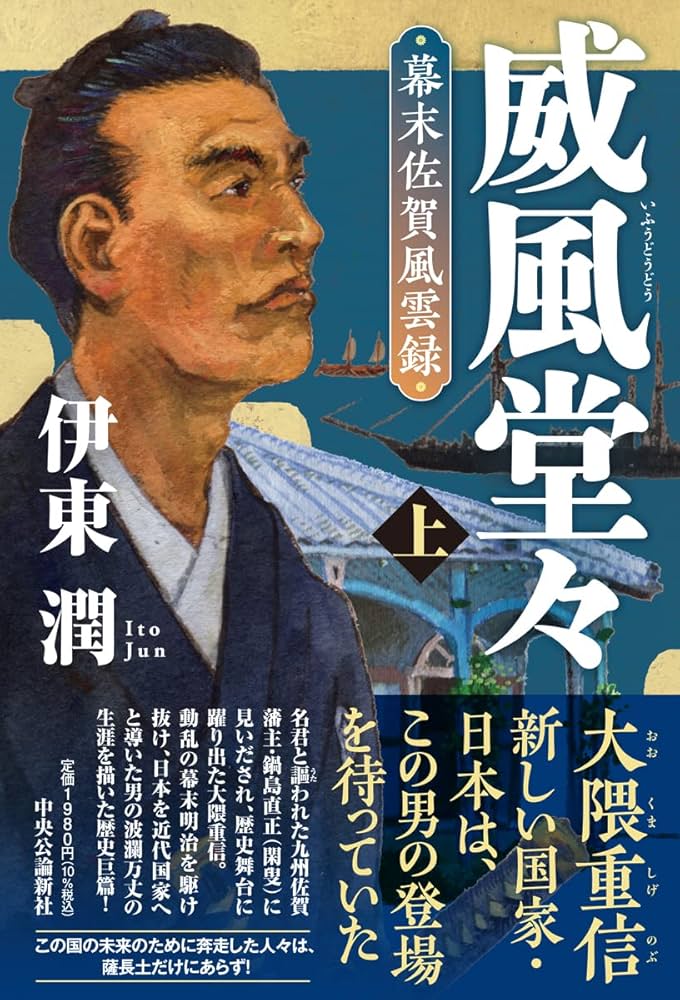
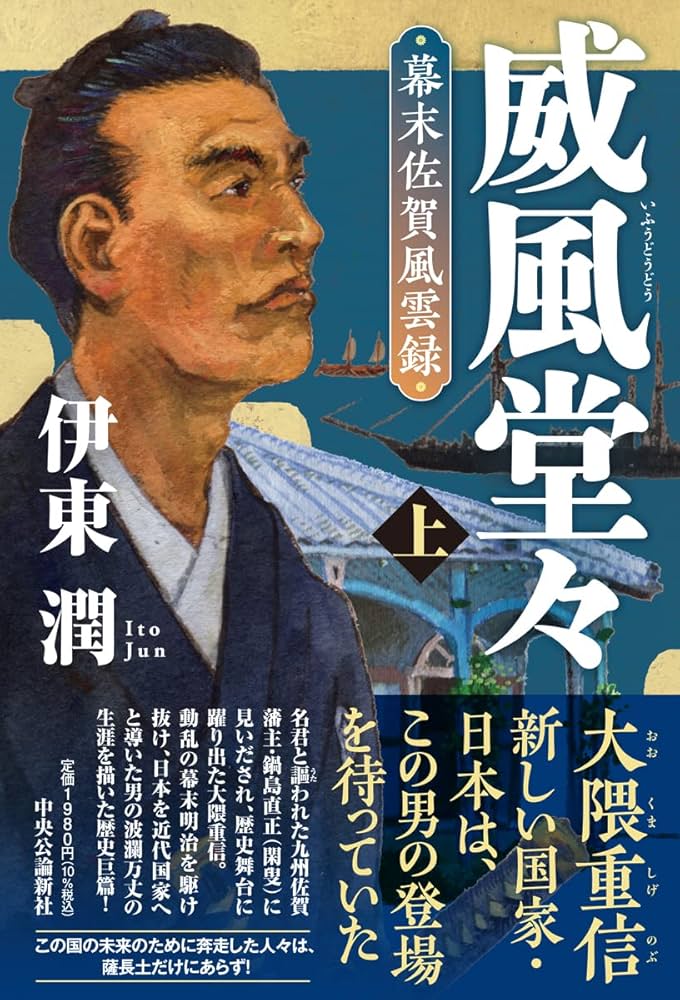
28位は、伊東潤の『威風堂々』。この作品は、武蔵国岡部藩という、わずか二万石の小さな藩を舞台にしています。大きな藩の思惑に翻弄されながらも、藩の存続と領民の生活を守るために奔走する人々の姿を描いた物語です。
歴史の主役にはなれない、弱者の視点から見る幕末は、また違ったリアルさがあります。彼らは、限られた情報と戦力の中で、いかにして生き残りの道を探ったのか。知恵と勇気で難局に立ち向かう人々の姿に、胸が熱くなります。歴史のダイナミズムの裏側にある、名もなき人々の奮闘を描いた傑作です。



小さな藩にも、守るべきものと誇りがあったんだね。大きな歴史の流れの中で、必死に生きる人々の姿に感動しちゃうな。
29位『螢の剣』葉室麟
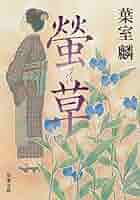
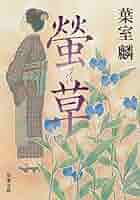
29位には、葉室麟の『螢の剣』がランクイン。葉室作品らしい、武士の矜持と切ない人間ドラマが光る一冊です。主人公は、藩の不正を暴くために、あえて「鳥刺し」という不遇の身分に甘んじている武士・瓜生新兵衛。
彼は、亡き親友の妹を守りながら、不正の証拠を掴む機会をじっと待っています。その胸に秘めた固い決意と、内に秘めた優しさが、読む者の心を打ちます。派手な活躍はありませんが、武士として、一人の人間として、誠実に生きようとする主人公の姿が深く印象に残る作品です。静かな感動を味わいたい方におすすめします。



信念のために、じっと耐える主人公の姿がすごく切ないんだ…。派手じゃないけど、心にじんわりと染みる物語だよ。
30位『夜明け前』島崎藤村
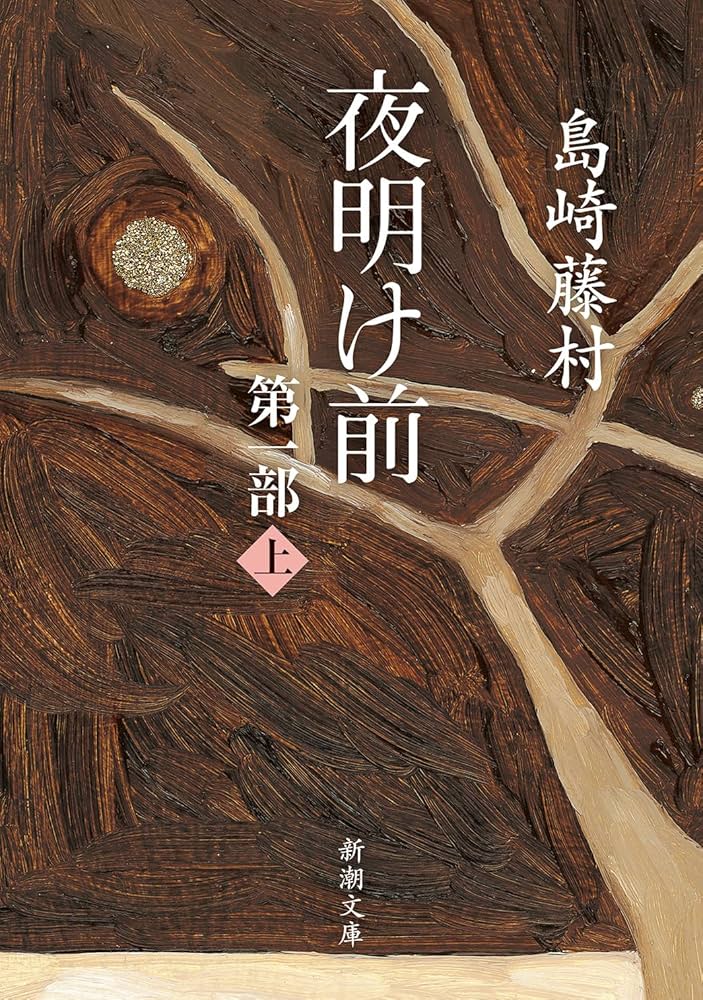
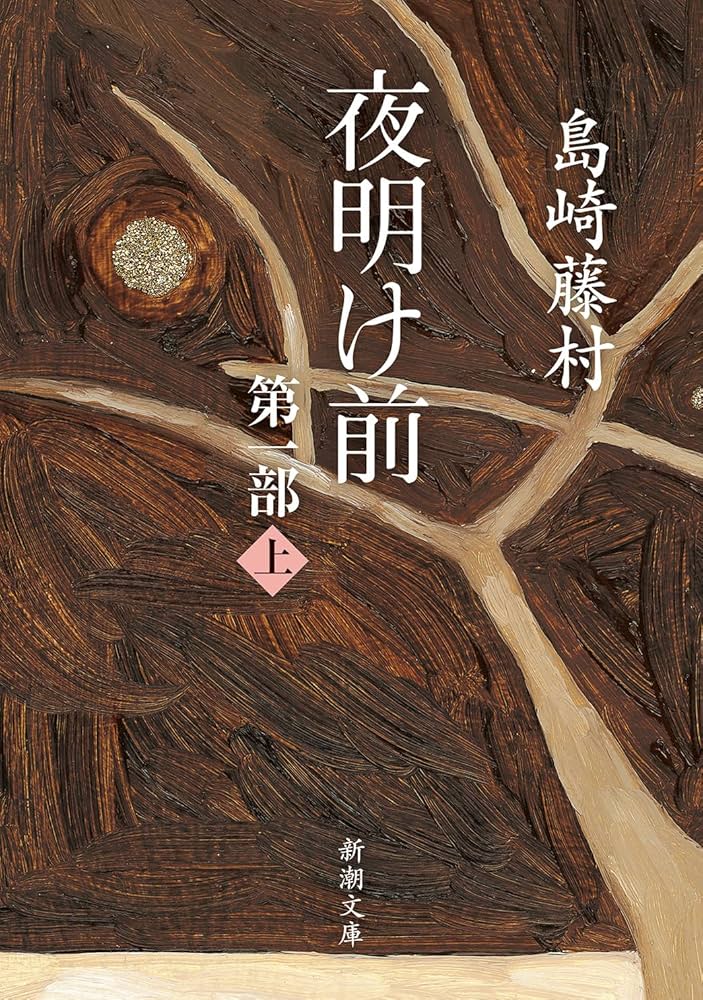
ランキングの最後を飾るのは、日本近代文学の最高峰の一つ、島崎藤村の『夜明け前』です。幕末から明治へと移り変わる時代を背景に、木曽・馬籠宿の庄屋である青山半蔵の苦悩に満ちた生涯を描いています。
平田篤胤の国学に傾倒し、王政復古による新しい世の中を夢見ていた半蔵。しかし、彼が待ち望んだ「夜明け」である明治維新は、理想とはかけ離れたものでした。時代の大きな変化に翻弄され、理想と現実の狭間で精神的に追い詰められていく主人公の姿は、読む者に強烈な問いを投げかけます。歴史小説という枠を超えた、普遍的な人間の苦悩を描いた不朽の名作です。



時代の大きな変化って、希望だけじゃなくて、たくさんの苦しみも生むんだね…。半蔵の苦悩を思うと、すごく考えさせられる物語だよ。
あなたにぴったりの幕末小説を見つけて、激動の時代に想いを馳せよう
幕末小説おすすめランキングTOP30、いかがでしたでしょうか?坂本龍馬や新選組といった王道の物語から、女性や商人、敗者の視点で描かれたもの、さらにはエンターテイメント性の高いものまで、本当に様々な作品がありましたね。気になる一冊は見つかりましたか?
どの小説も、激動の時代を必死に生きた人々の息吹を感じさせてくれるはずです。ぜひ、あなたにぴったりの一冊を手に取って、幕末という時代の熱気とドラマに浸ってみてください。きっと、歴史の面白さに夢中になること間違いなしですよ。