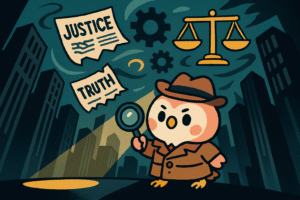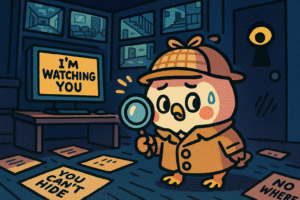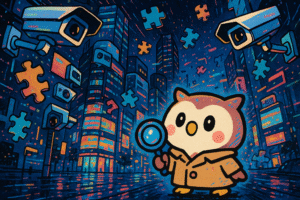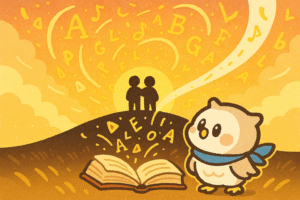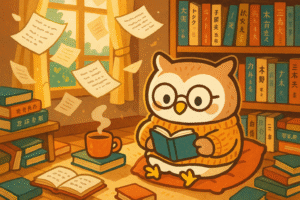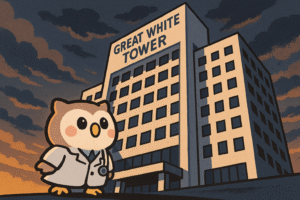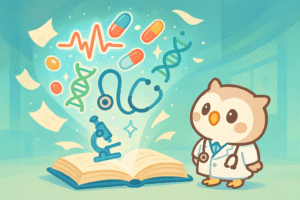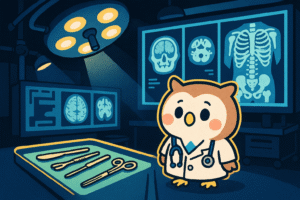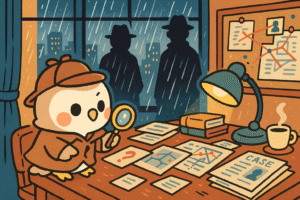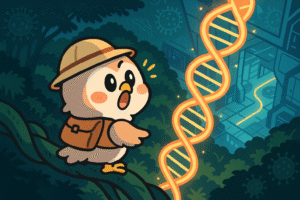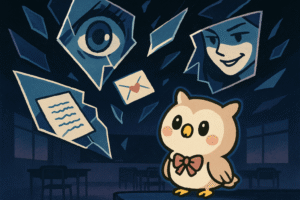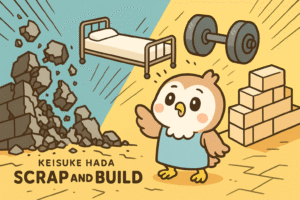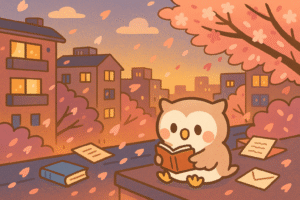あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】社会問題がテーマのおすすめ小説ランキングTOP30

小説で現代社会を読み解く:社会問題がテーマの作品が持つ魅力
私たちの生きる現代社会は、貧困や格差、少年犯罪、医療問題など、さまざまな課題を抱えています。ニュースや新聞で情報を得ることはできても、どこか遠い世界の話のように感じてしまうことはありませんか?
社会問題がテーマの小説は、そうした課題を物語という形で、より身近に、そして深く理解するきっかけを与えてくれます。登場人物たちの葛藤や喜び、悲しみを通して、問題の本質に触れることができるのが大きな魅力です。エンターテイメントとして楽しみながら、私たちの社会について考える。そんな知的な時間を過ごしてみませんか?
【2025年最新】社会問題がテーマのおすすめ小説ランキングTOP30
ここからは、編集部が厳選した「社会問題がテーマのおすすめ小説」をランキング形式でご紹介します。
現代社会のリアルな闇や問題に鋭く切り込んだ作品から、家族のあり方や人間の尊厳を問う感動的な物語まで、あなたの心を揺さぶる一冊がきっと見つかるはずです。
1位『護られなかった者たちへ』中山七里
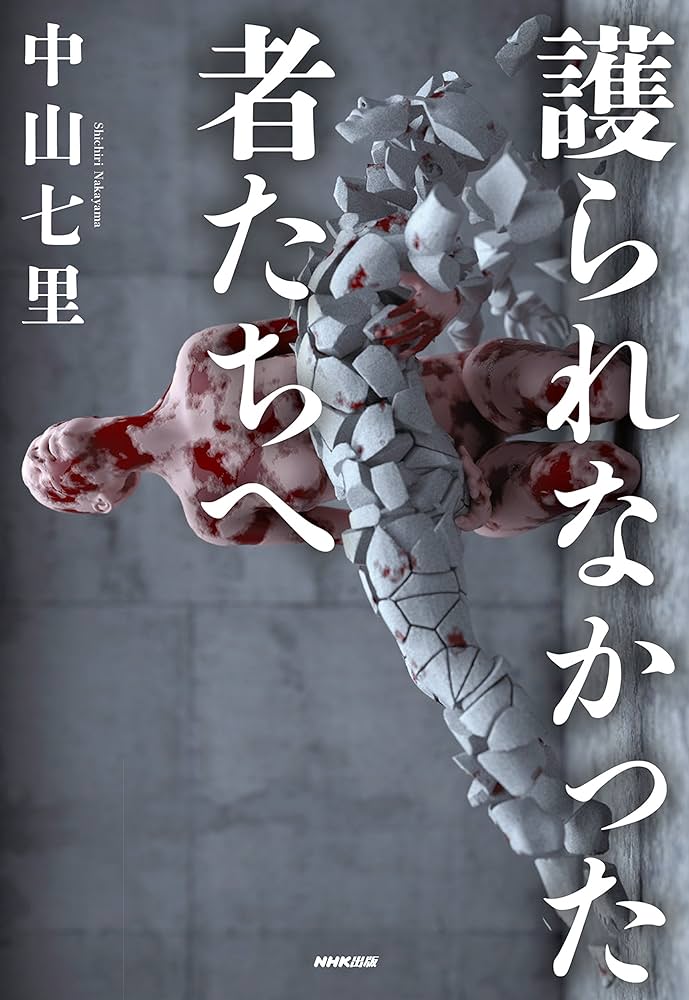
東日本大震災と生活保護制度の闇をテーマにした、社会派ミステリーの傑作です。 連続殺人事件の裏に隠された、あまりにも切ない真実。制度の狭間でこぼれ落ちていく命を前に、私たちは何を思うのでしょうか。
ミステリーとしての完成度の高さはもちろん、本当に護られるべきは誰なのかという重い問いを読者に突きつけます。福祉事務所で働く人々の苦悩も描かれており、多角的な視点から問題を捉えることができます。
 ふくちい
ふくちい制度の矛盾がもどかしい…。本当に助けが必要な人に届かないのがつらいね。
2位『希望が死んだ夜に』天祢涼
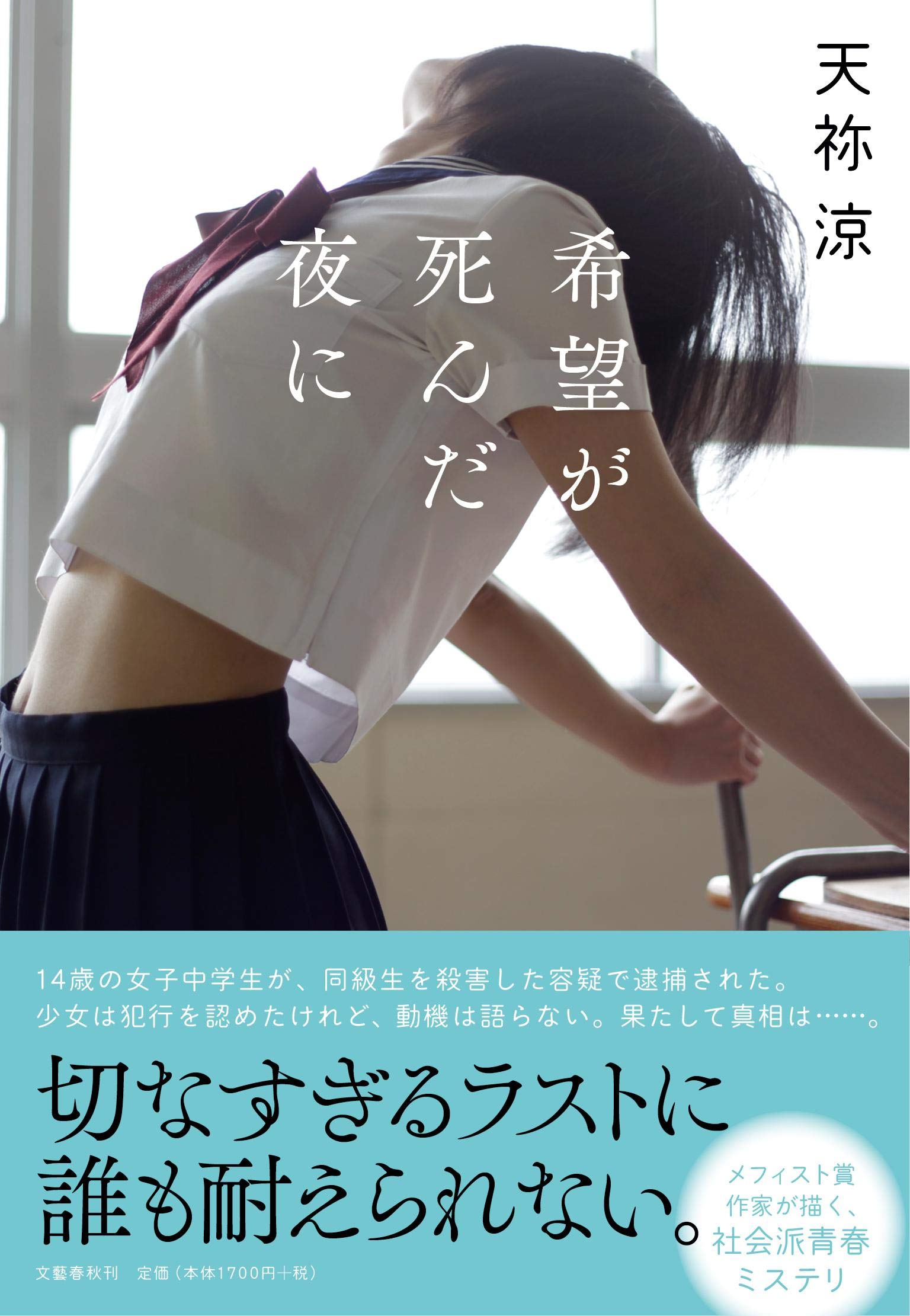
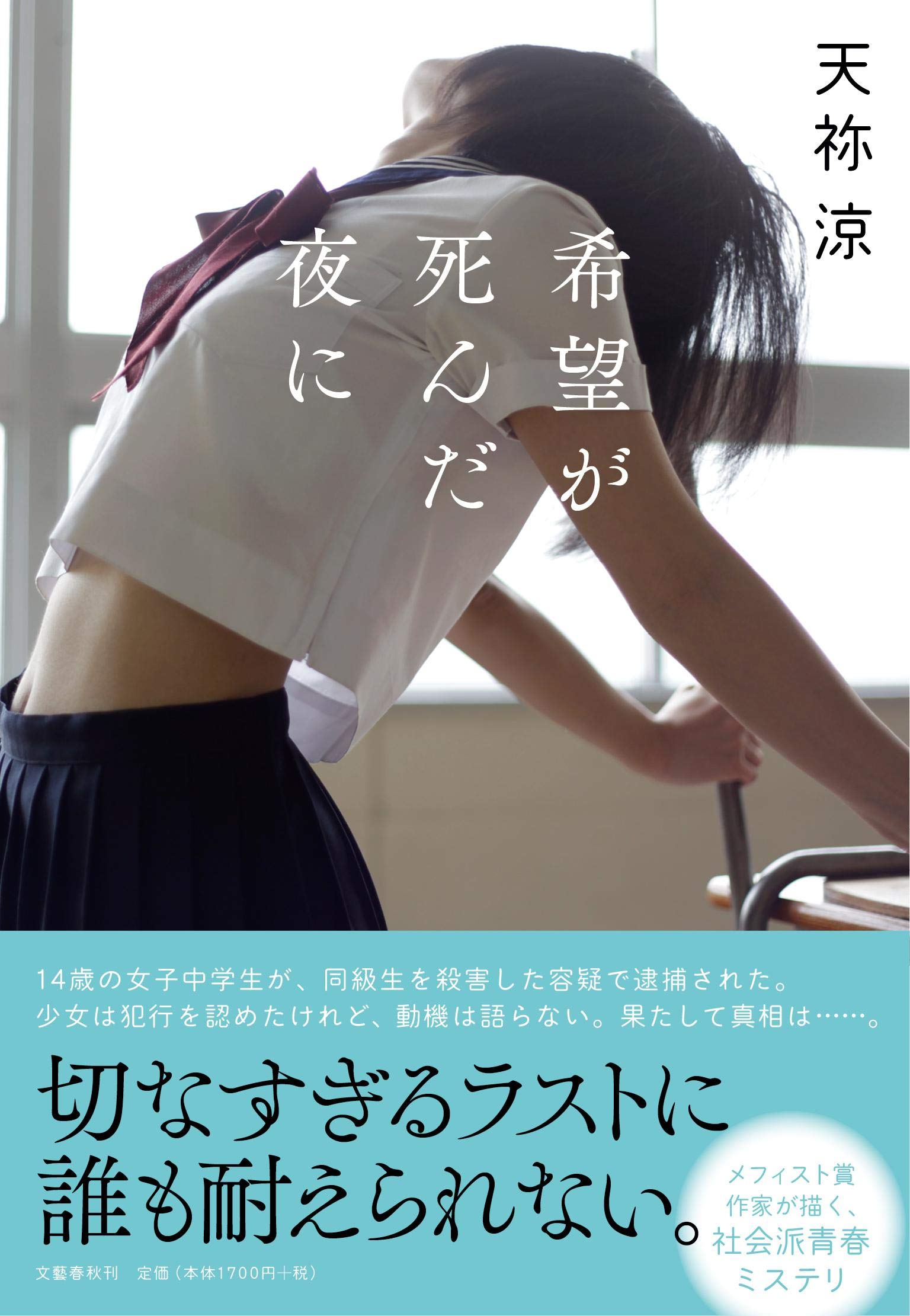
子どもの貧困という、現代社会が抱える深刻な問題に光を当てた社会派ミステリー。 14歳の少女が同級生を殺害した容疑で逮捕されますが、動機については固く口を閉ざします。
捜査を進める刑事たちが目の当たりにするのは、貧困に苦しむ子どもたちの壮絶な現実でした。なぜ少女は希望を失ってしまったのか。その背景にある社会の歪みに、胸が締め付けられる作品です。



子どもたちの希望が奪われるなんてつらすぎるよ…。社会全体で考えなきゃいけない問題だね。
3位『ロスト・ケア』葉真中顕
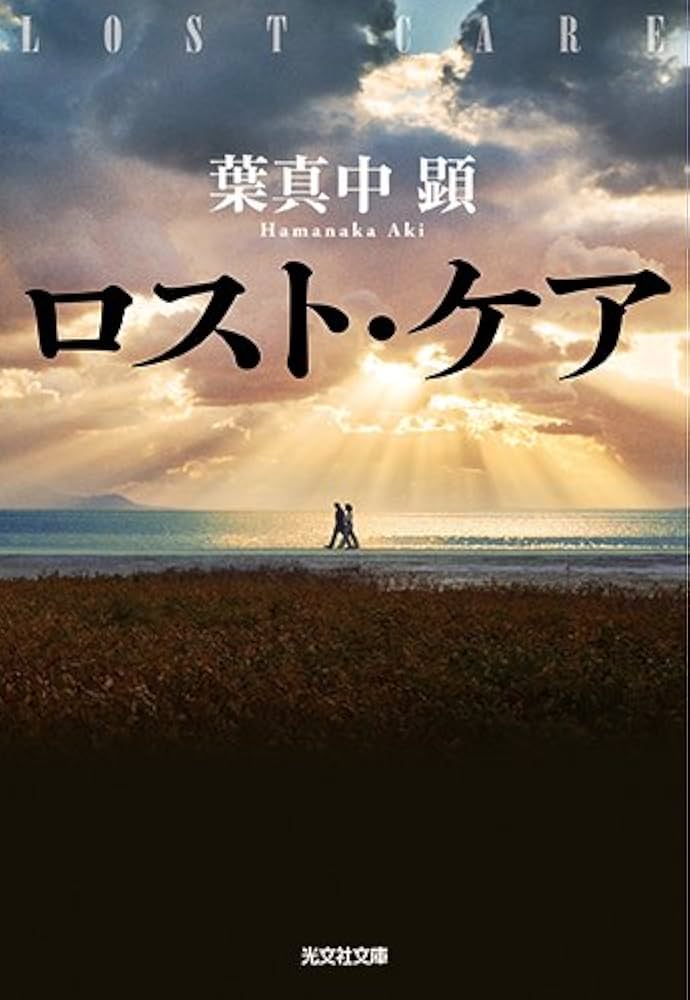
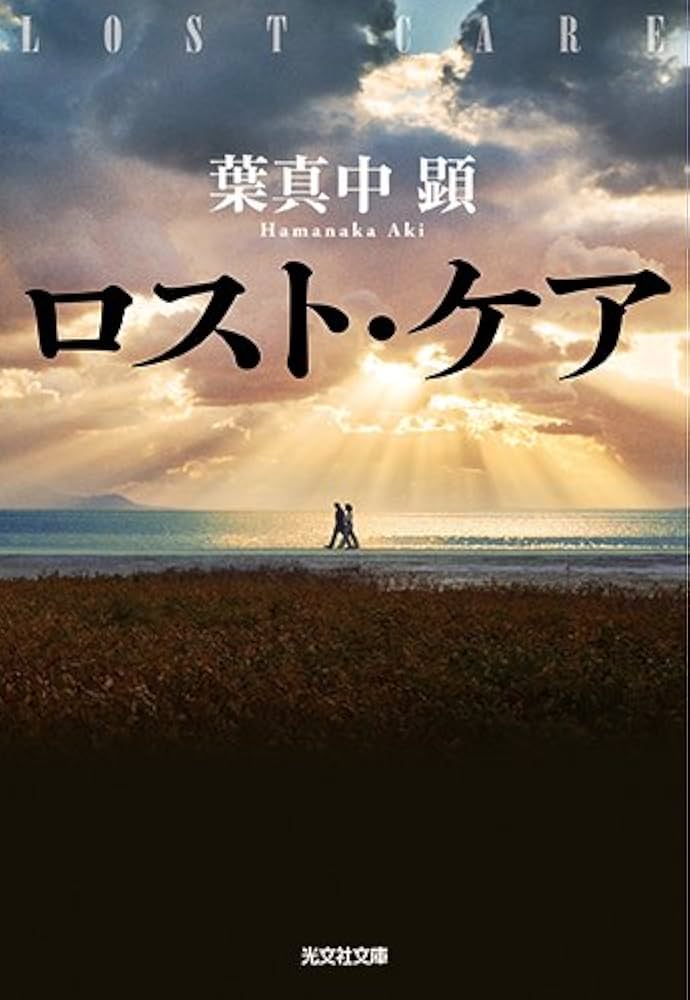
介護をテーマに、現代社会が抱える問題を浮き彫りにした衝撃作です。介護士による連続殺人事件が発生。犯人は「これは殺人ではなく“救い”だ」と主張します。
彼の言う“救い”とは一体何なのか。高齢化社会が急速に進む中で、介護の現場が直面する過酷な現実と、そこから生まれる絶望がリアルに描かれています。正義とは何か、命の尊厳とは何かを深く考えさせられるでしょう。



介護の現実が重すぎて、胸が苦しくなるよ。これはわたしたちの未来の話かもしれないね。
4位『火車』宮部みゆき
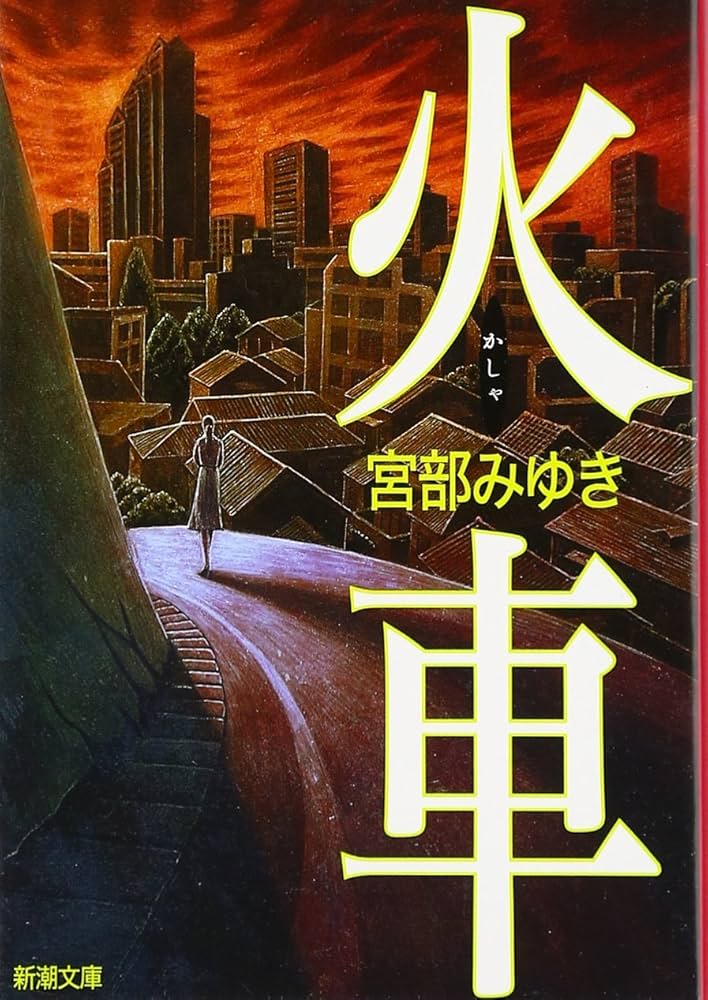
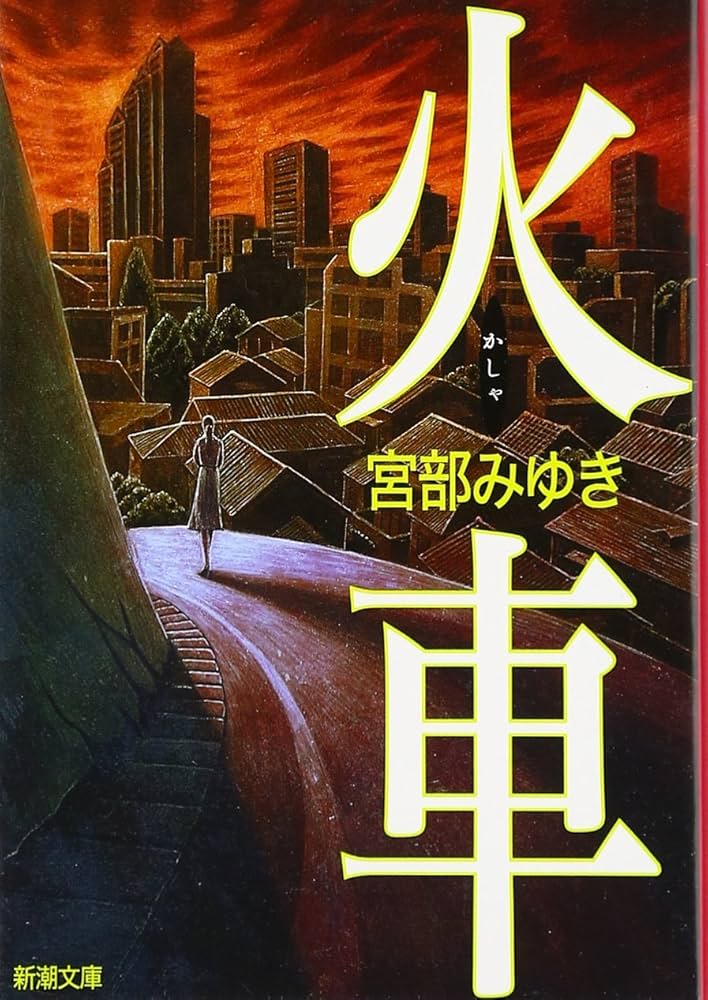
カード破産や多重債務といった、消費者金融にまつわる社会問題をテーマにしたミステリー小説の金字塔です。 休職中の刑事が、失踪した婚約者の行方を追ううちに、カード社会の恐ろしい闇に引きずり込まれていきます。
なぜ彼女は自分の存在を消さなければならなかったのか。その謎を追う過程で、借金地獄の凄惨な実態が明らかになります。 1992年に発表された作品ですが、そのテーマは現代にも通じる普遍的な恐ろしさを持っています。



お金の怖さを思い知らされる一冊だよ。ミステリーとしても一級品だから、ぜひ読んでみてほしいな。
5位『Aではない君と』薬丸岳
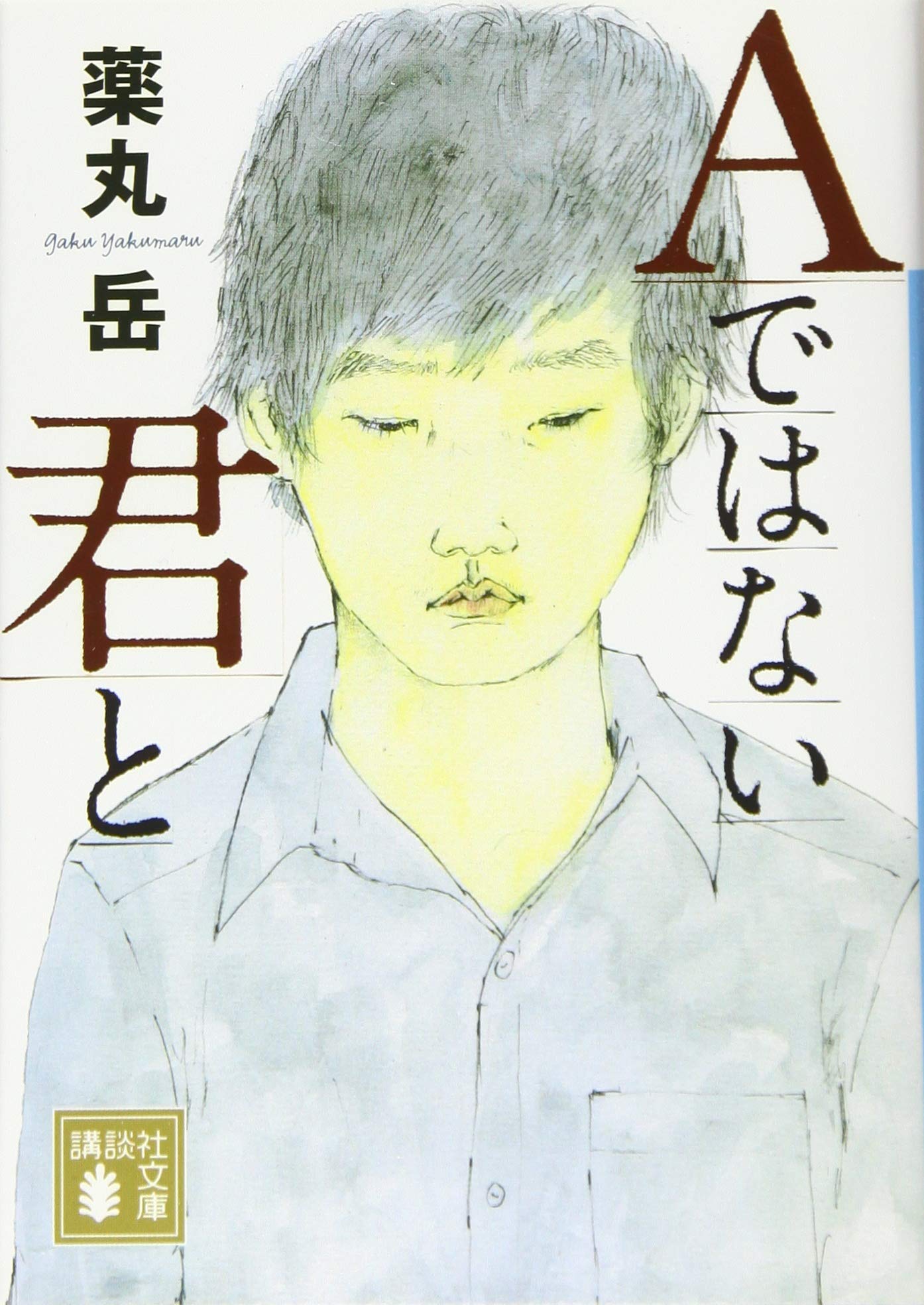
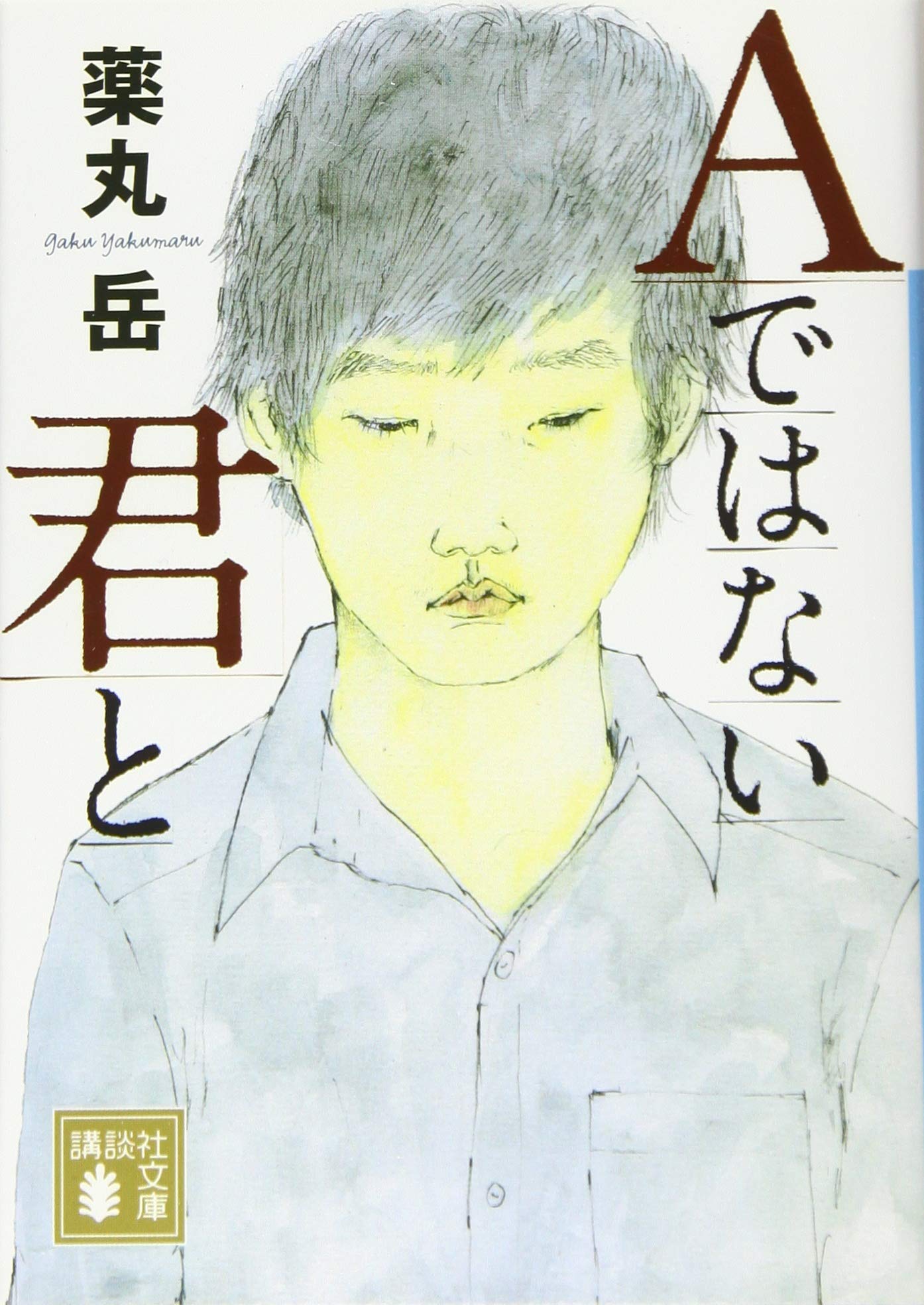
少年犯罪をテーマに、「加害者家族」が直面する過酷な現実を描いた作品です。 もしも自分の息子が、同級生を殺害してしまったら。父親は絶望の淵で、息子を信じ、向き合うことができるのでしょうか。
被害者遺族の悲しみはもちろん、加害者家族が社会から向けられる厳しい目や、終わりのない苦悩が丁寧に描かれています。愛情とは何か、家族とは何か、そして赦しとは何か。答えの出ない問いに、心を揺さぶられる物語です。



加害者家族の視点がすごくつらかった…。どっちの立場も苦しくて、涙なしには読めないよ。
6位『さまよう刃』東野圭吾
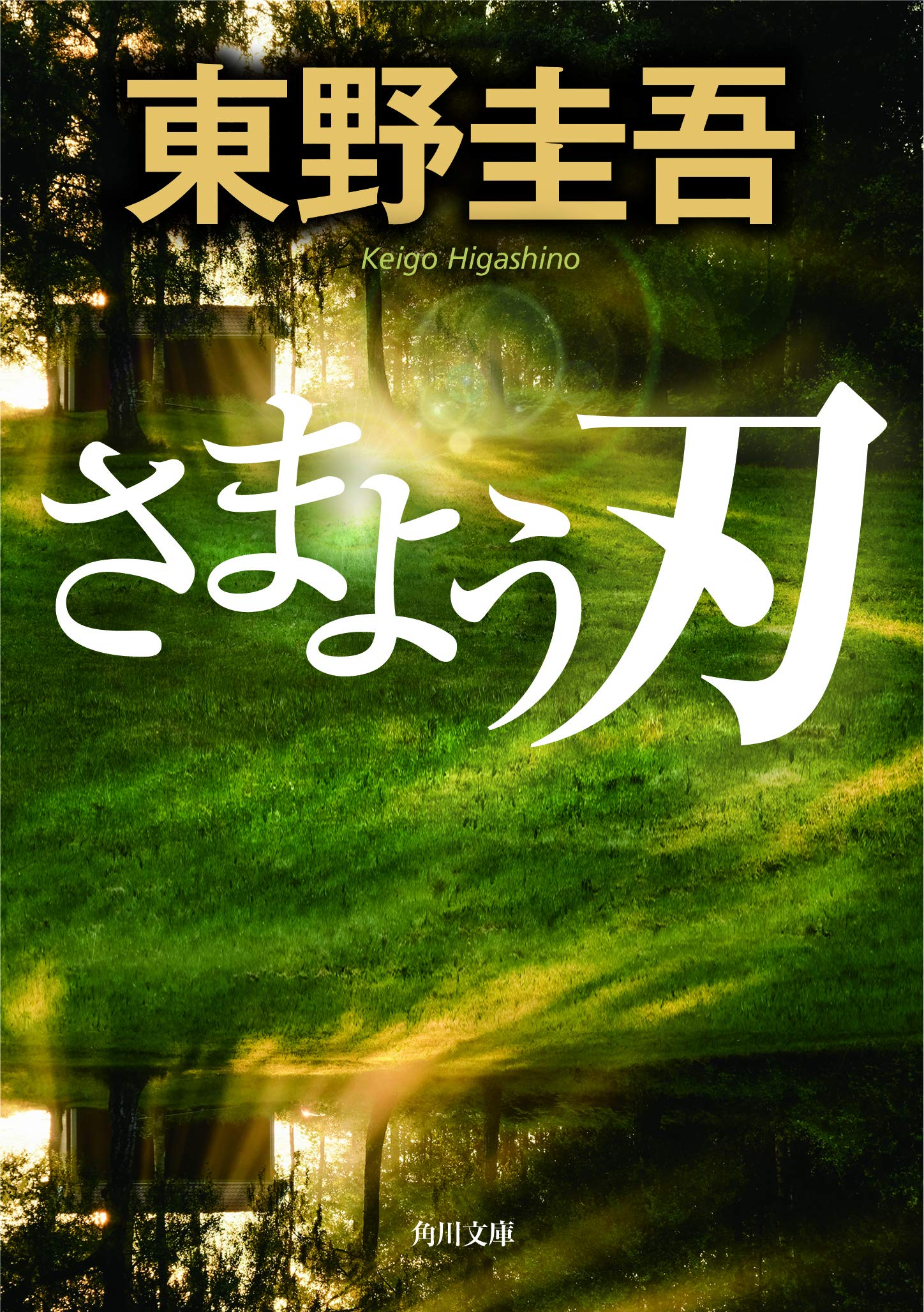
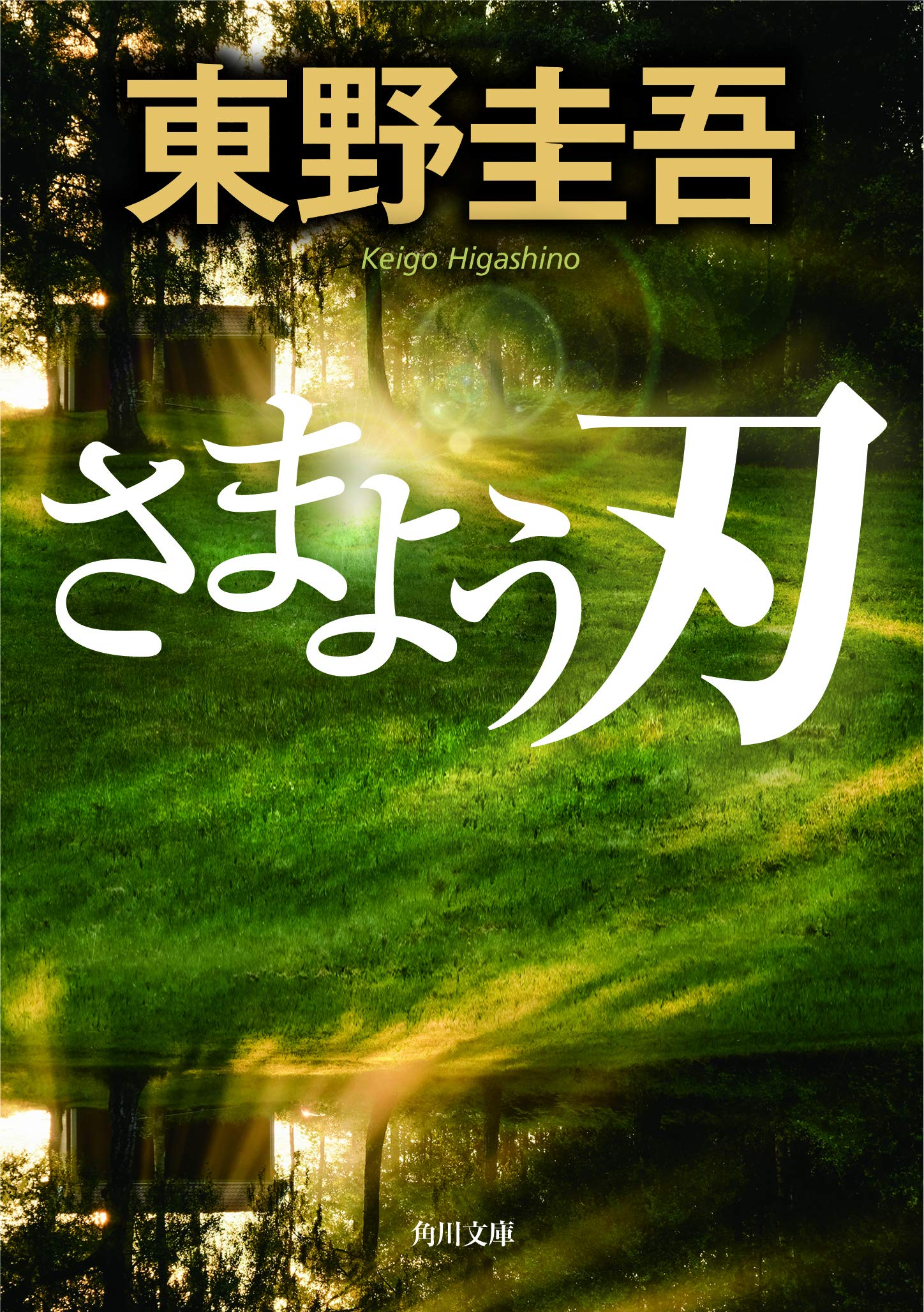
少年犯罪と、被害者遺族による復讐という重いテーマに挑んだ問題作です。 未成年の少年グループによって娘を無残に殺された父親が、法律で裁かれない犯人たちに自らの手で制裁を下すため、復讐の旅に出ます。
もし自分の子どもが同じ目に遭ったら、あなたはどうしますか? 正義とは何か、法は本当に被害者を守っているのか、という根源的な問いを突きつけられます。 父親の悲痛な叫びと、やるせない怒りに、ページをめくる手が止まらなくなるでしょう。



本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。
7位『絶叫』葉真中顕
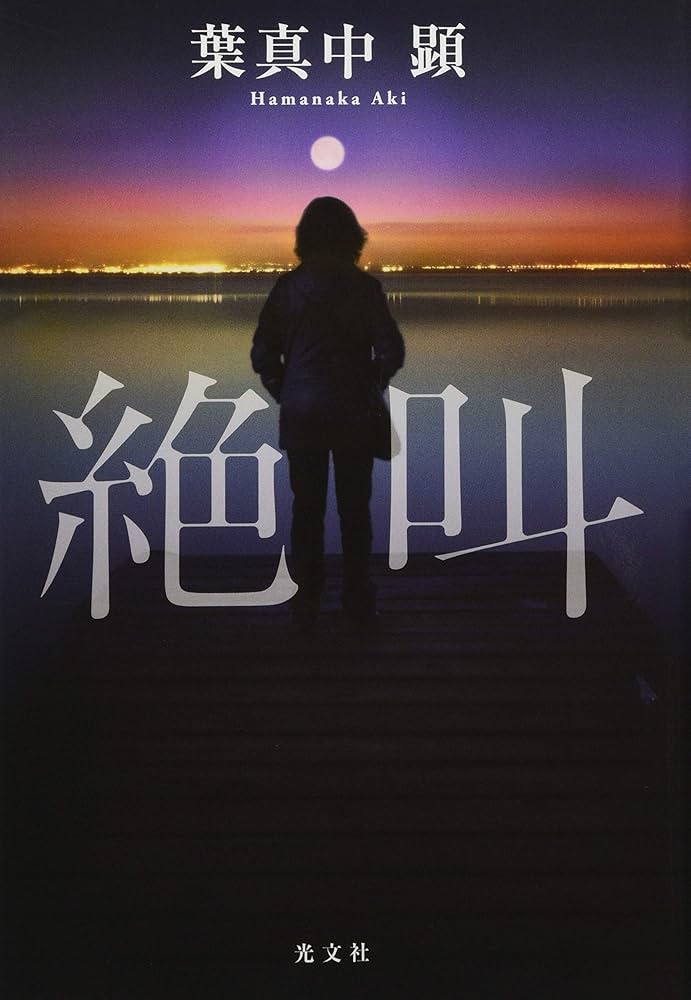
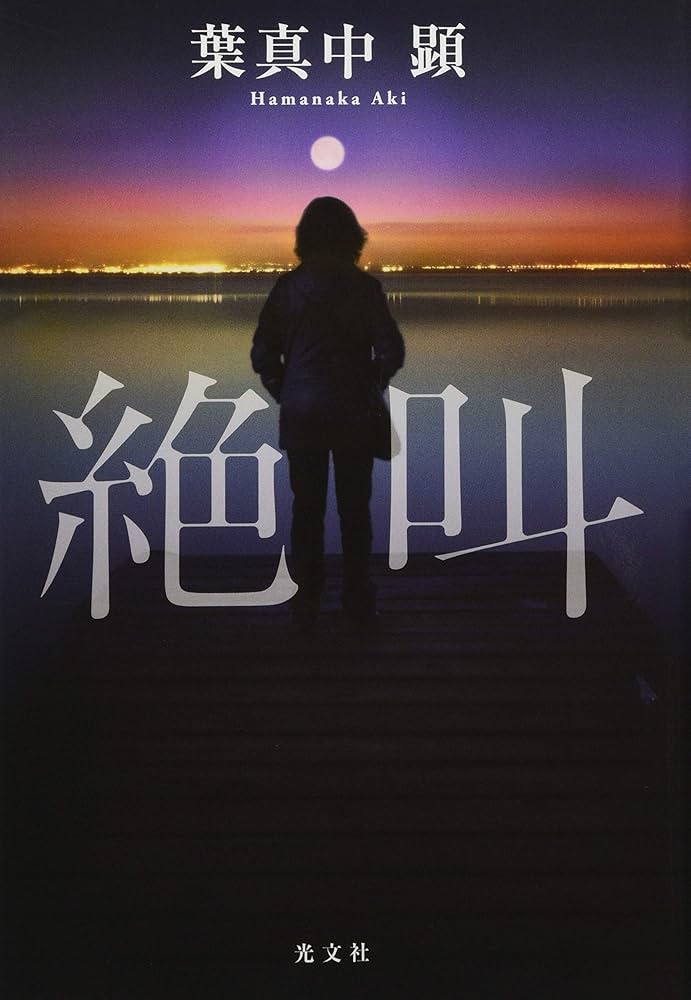
現代社会に潜む「無縁社会」や「貧困」といったテーマを背景に、ひとりの女性が転落していく様を描いた社会派ミステリーです。 平凡だったはずの女性は、なぜ社会の片隅で誰にも知られず、孤独な死を迎えることになったのか。
彼女の人生をたどることで、現代社会の冷たさや、人が容易に孤立してしまう恐ろしさが浮き彫りになります。他人事とは思えないリアルな描写に、思わず背筋が凍るかもしれません。社会とのつながりの大切さを改めて考えさせられる作品です。



主人公が追い詰められていくのがリアルで怖かった…。誰にでも起こりうる話だと思うとぞっとするよ。
8位『64(ロクヨン)』横山秀夫
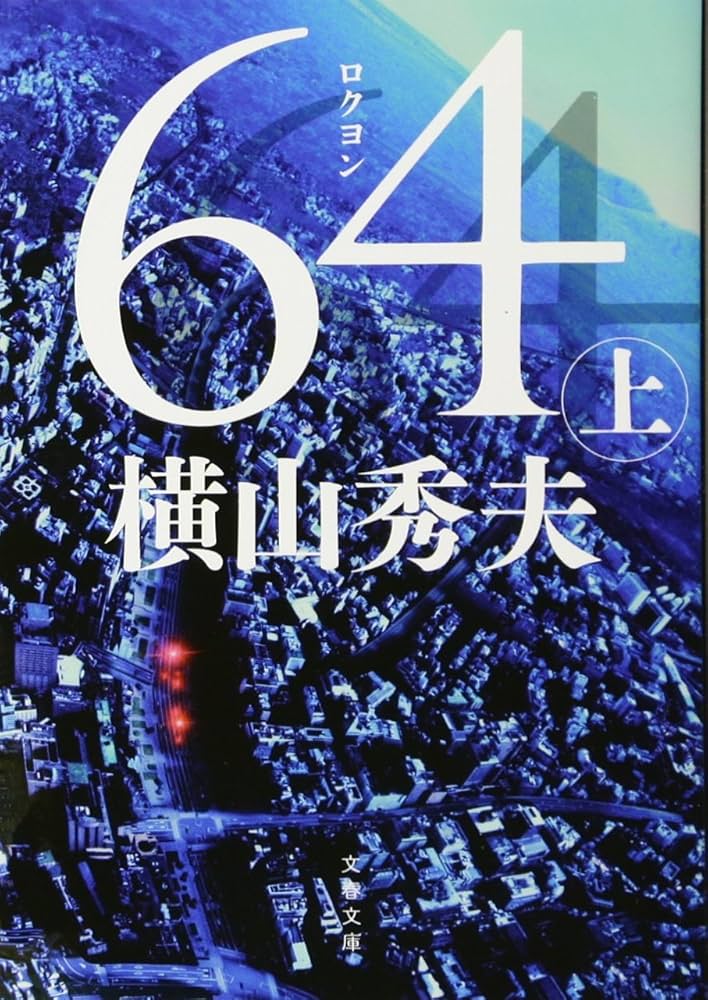
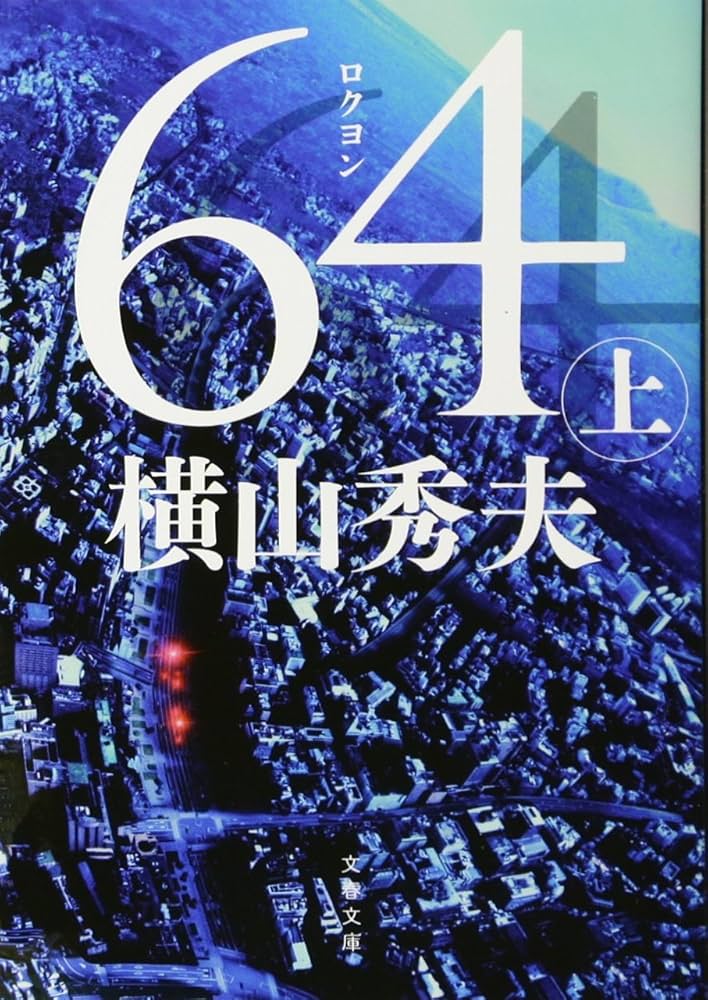
昭和64年に起きた未解決の少女誘拐殺人事件、通称「ロクヨン」を軸に、警察組織の内部対立や隠蔽体質、そして報道のあり方を鋭く描いた傑作です。
主人公は、事件を追う刑事ではなく、警察の広報官。記者クラブとの対立や、組織内部のしがらみに苦悩しながらも、時効が迫る「ロクヨン」の真相に迫ろうとします。巨大な組織の中で翻弄される個人の葛藤が、息もつかせぬ展開で描かれます。重厚な人間ドラマと、圧巻のストーリーテリングに引き込まれること間違いなしです。



警察組織のリアルな描写がすごい!広報官の視点っていうのが新鮮で、一気に読んじゃったよ。
9位『空飛ぶタイヤ』池井戸潤
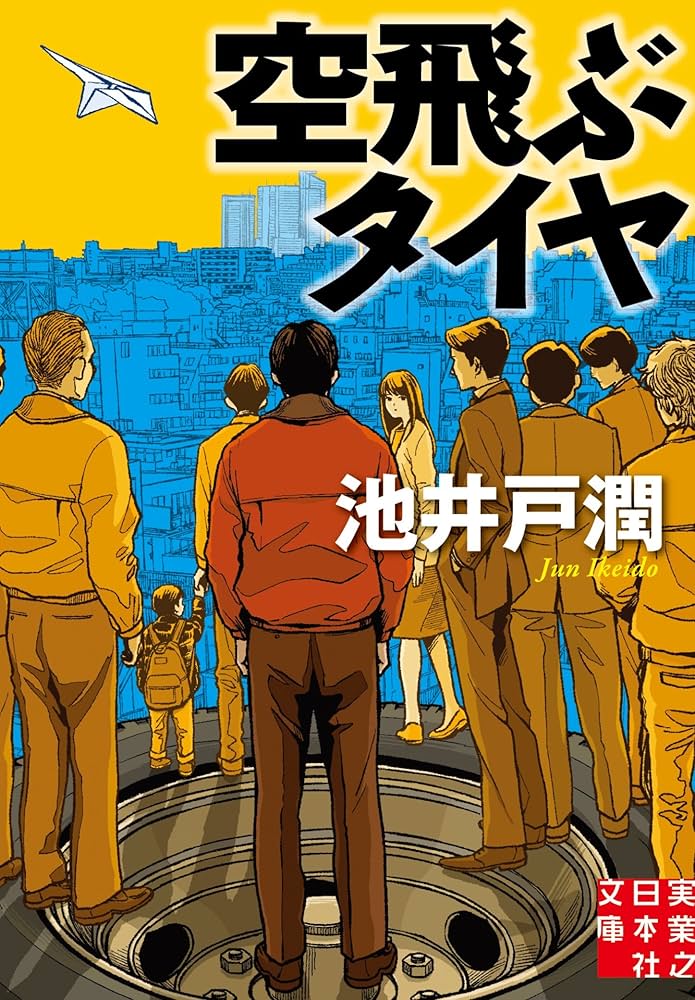
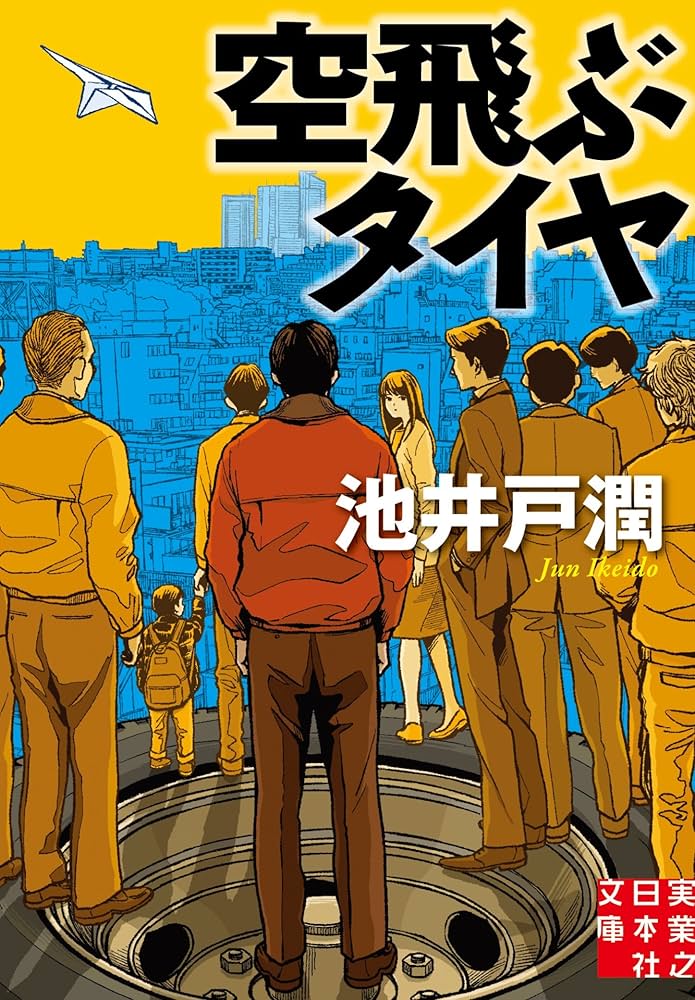
ある日突然起きたトレーラーの脱輪事故。整備不良を疑われた運送会社の社長が、自社の無実を証明するため、製造元である巨大自動車メーカーの闇に立ち向かう物語です。
テーマは、大企業によるリコール隠しという不正。 中小企業の社長が、圧倒的な力を持つ大企業を相手に、社員や家族、そして自社の誇りを守るために戦う姿に胸が熱くなります。働くとは何か、正義とは何かを問いかける、池井戸潤の真骨頂ともいえる作品です。



巨大な権力に立ち向かう姿がかっこよすぎる!明日から頑張ろうって勇気をもらえる小説だよ。
10位『罪の声』塩田武士
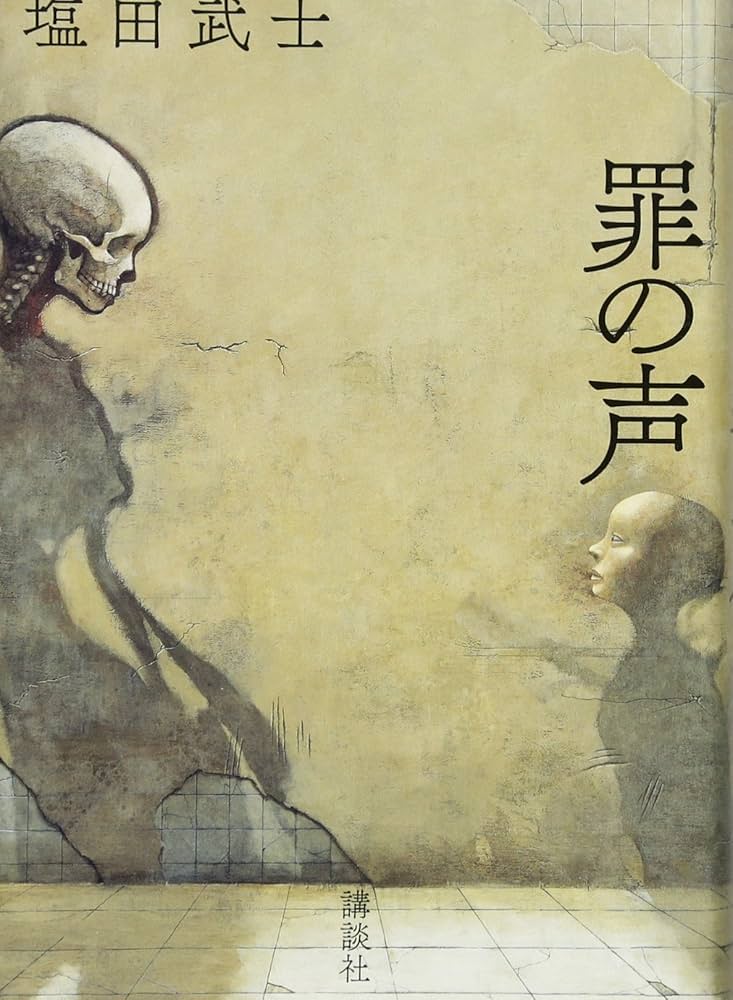
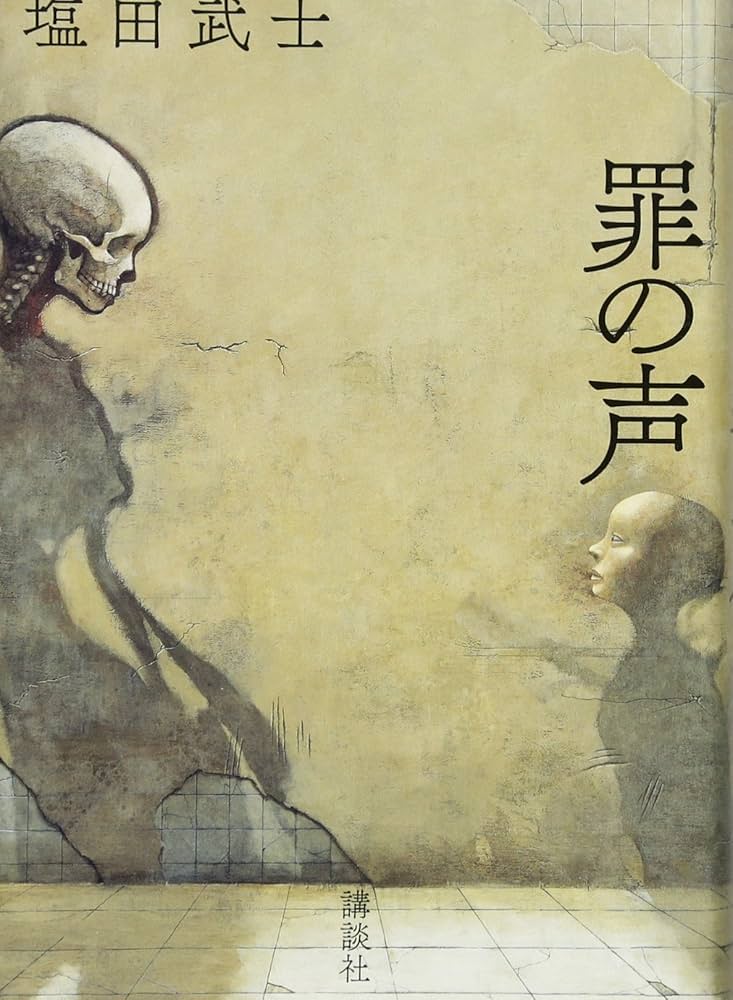
昭和最大の未解決事件「グリコ・森永事件」をモチーフに、事件に翻弄された人々の人生を描いた社会派ミステリーです。 新聞記者の阿久津と、偶然にも事件で使われた脅迫テープに自分の幼い頃の声が使われていたことを知る曽根。 二人の視点から、30年以上の時を経て事件の真相に迫っていきます。
この物語の核心は、犯人探しだけでなく、知らぬ間に犯罪に加担させられた子どもたちの、その後の人生にも光を当てている点です。 事実を元にしたフィクションならではのリアリティと、深い人間ドラマが胸を打つ、読み応えのある一冊です。



未解決事件の裏にこんなドラマがあったなんて…。事実とフィクションの絡み合いが絶妙で、すごく引き込まれたよ。
11位『理由』宮部みゆき
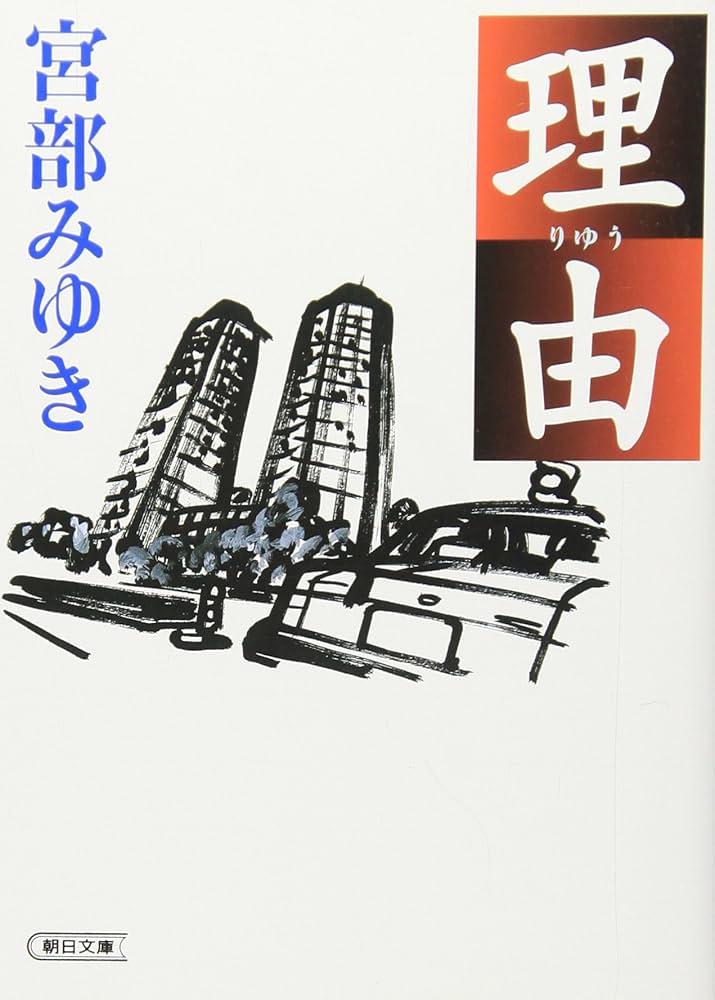
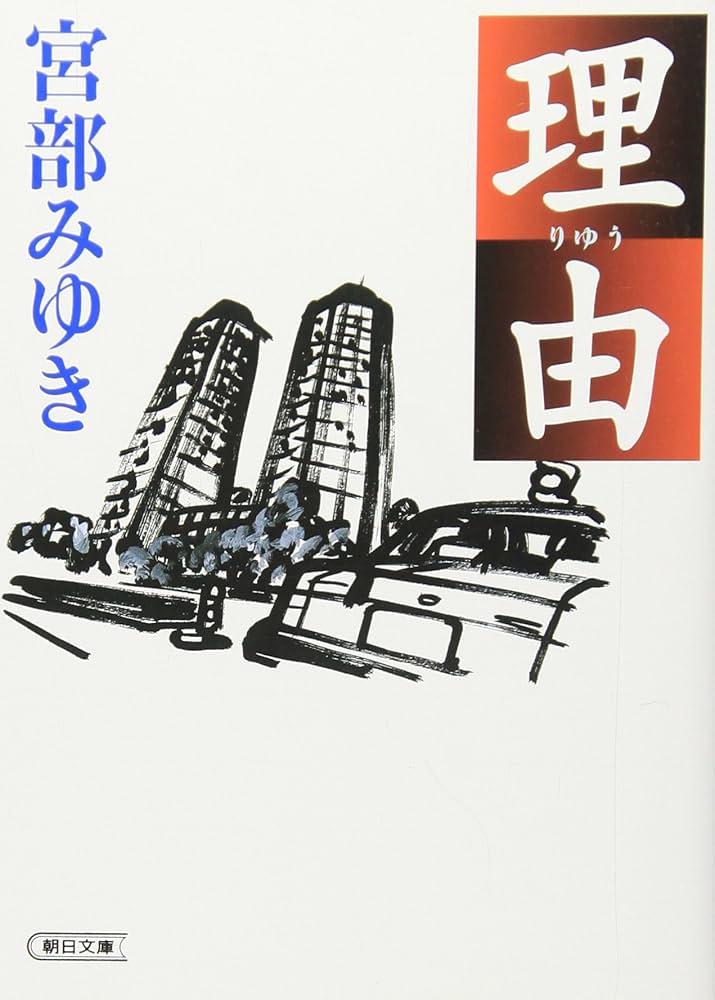
超高層マンションで起きた一家4人の殺人事件。しかし、捜査が進むにつれて、彼らが本当の家族ではなかったことが判明します。 この作品は、事件の関係者たちへのインタビューを重ねていくドキュメンタリー形式で、事件の真相を解き明かしていくユニークな構成が特徴です。
なぜ彼らは家族のふりをしていたのか、そしてなぜ殺されなければならなかったのか。 多くの人々の証言から、現代社会における家族のあり方や、都市の孤独といったテーマが浮かび上がってきます。 第120回直木賞を受賞した、宮部みゆきの代表作の一つです。



色々な人の視点から語られるのが面白いね。パズルのピースがはまっていくみたいで、夢中で読んじゃったよ。
12位『パレートの誤算』柚月裕子
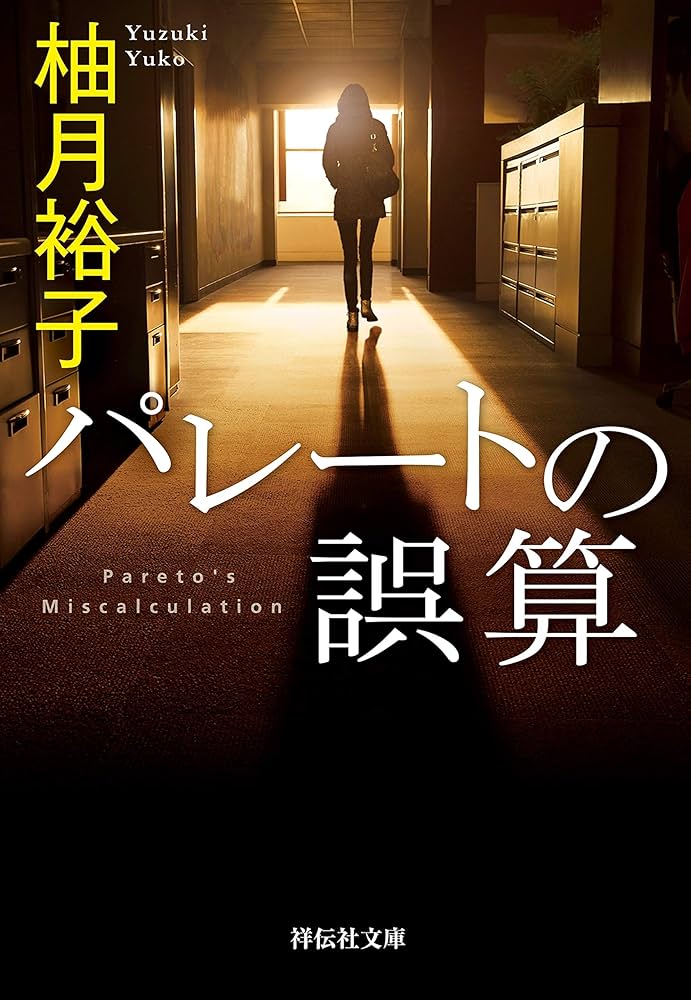
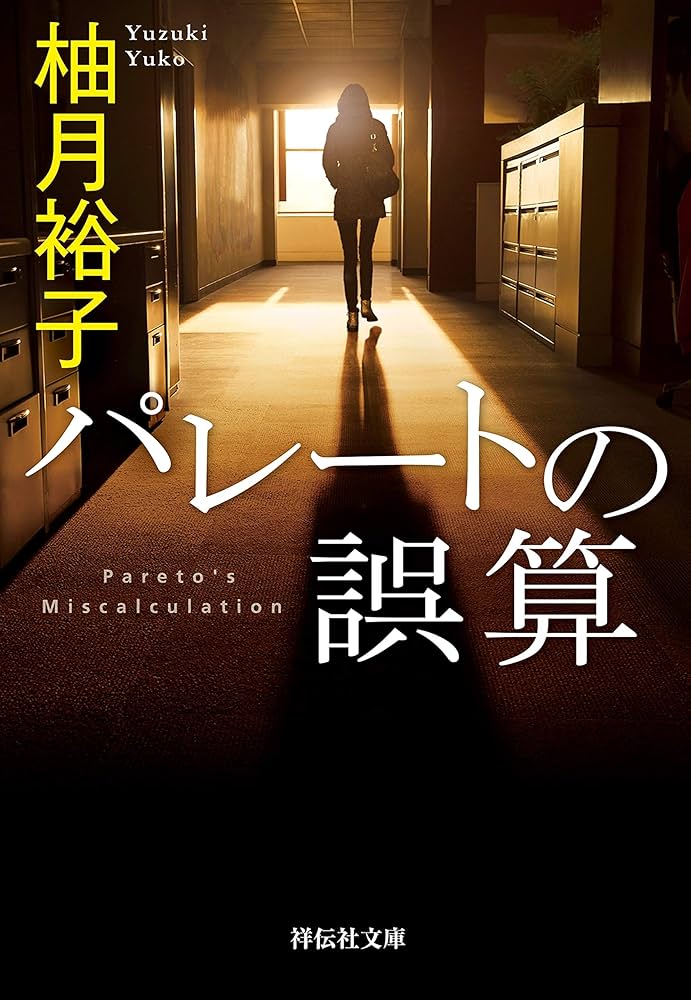
生活保護をテーマに、ケースワーカーの主人公が制度の闇と不正に迫る社会派ミステリーです。 市役所の新人職員である主人公は、ある受給者の死をきっかけに、生活保護を食い物にする「貧困ビジネス」の存在に気づきます。
本当に支援を必要としている人々を追い詰める、制度の矛盾と非情な現実がリアルに描かれています。 私たちの税金がどのように使われているのか、そして社会のセーフティネットはどうあるべきか。社会保障のあり方を深く考えさせられる作品です。



生活保護の現場ってこんなに大変なんだね…。知らない世界だったけど、すごく勉強になったよ。
13位『震える牛』相場英雄
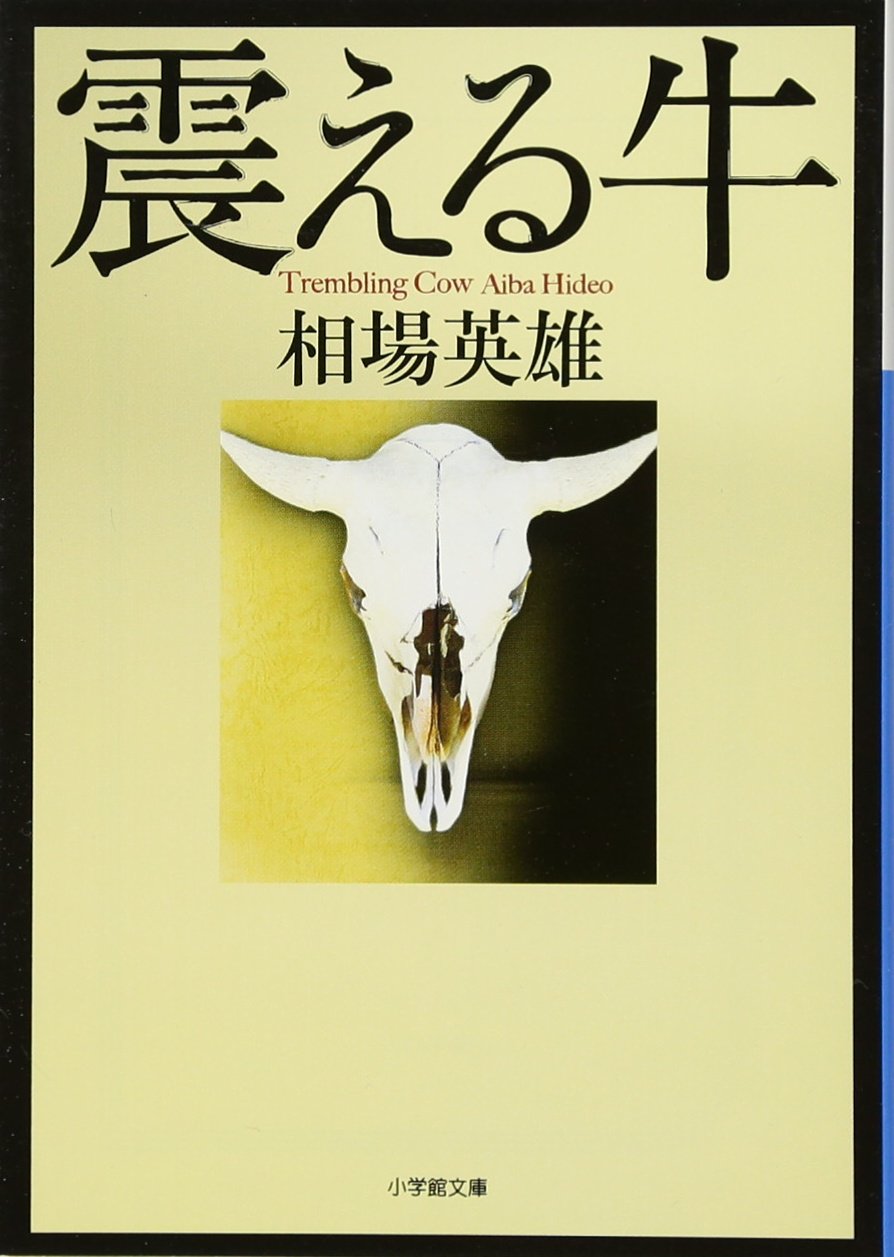
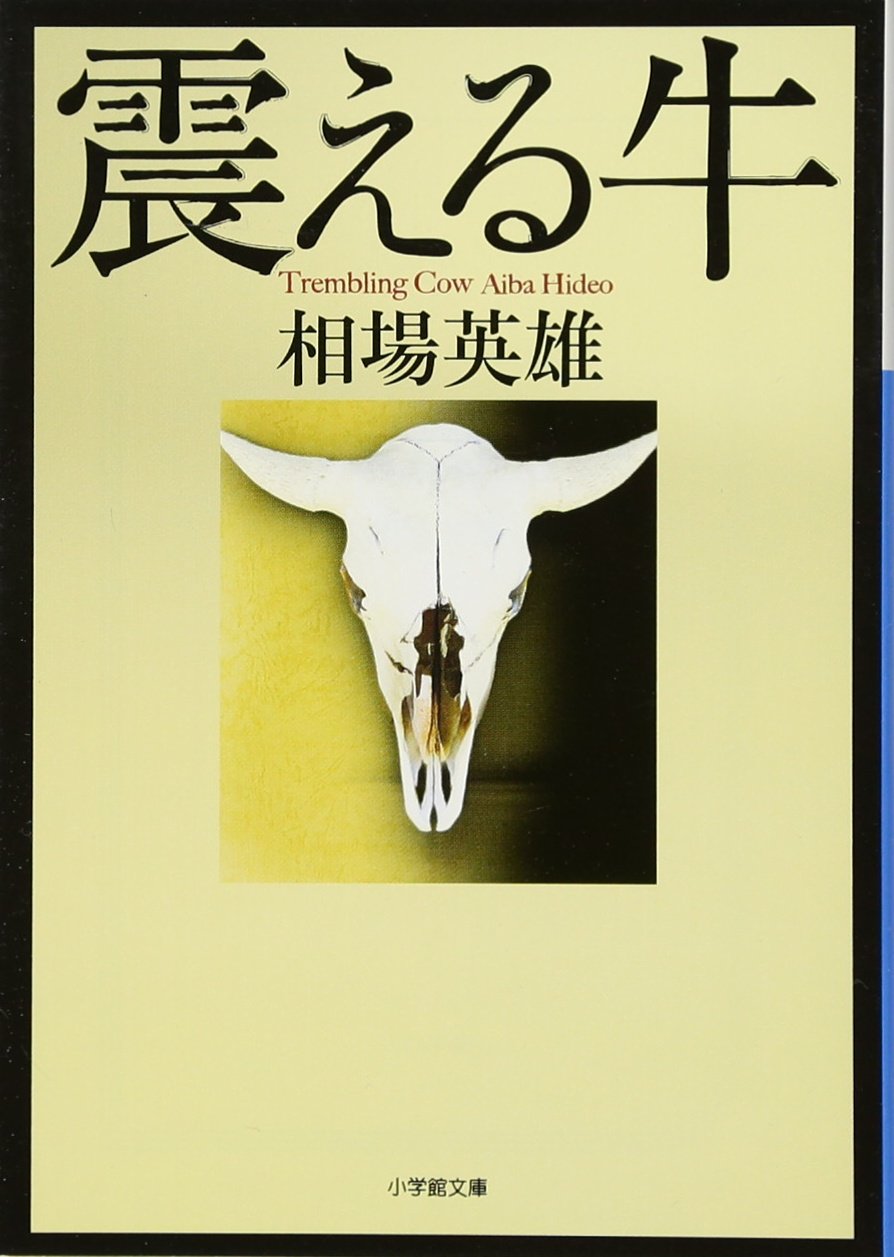
BSE(牛海綿状脳症)問題や食品偽装、大企業の隠蔽体質といったテーマに切り込んだ社会派サスペンスです。 未解決の殺人事件を追う刑事と、食品偽装疑惑を追う記者の二つの視点から、食の安全を脅かす巨大な闇に迫ります。
私たちが毎日口にする「食」の裏側には、こんな危険が潜んでいるのかもしれない。そう思わせる圧倒的なリアリティとスリリングな展開が魅力です。 組織の論理と個人の正義がぶつかり合う、緊迫感あふれる物語が繰り広げられます。



食の安全について本気で考えさせられたよ。スーパーで買い物するのがちょっと怖くなっちゃうかも…。
14位『スワン』呉勝浩


もしも、巨大なショッピングモールの中で原因不明の感染症が発生したら?本作は、パンデミックという極限状況を舞台に、そこに閉じ込められた人々の混乱や恐怖、そして人間の本性を描いたパニックミステリーです。
デマや疑心暗鬼が広がる中で、人々はどのように行動するのか。情報社会の危うさや、集団心理の恐ろしさが巧みに描かれています。極限状態に置かれた人間のエゴや善意がぶつかり合う、息をのむような展開から目が離せません。



パニック映画みたいでハラハラしたよ!自分がこの状況にいたらどうするかなって考えちゃった。
15位『コンビニ人間』村田沙耶香
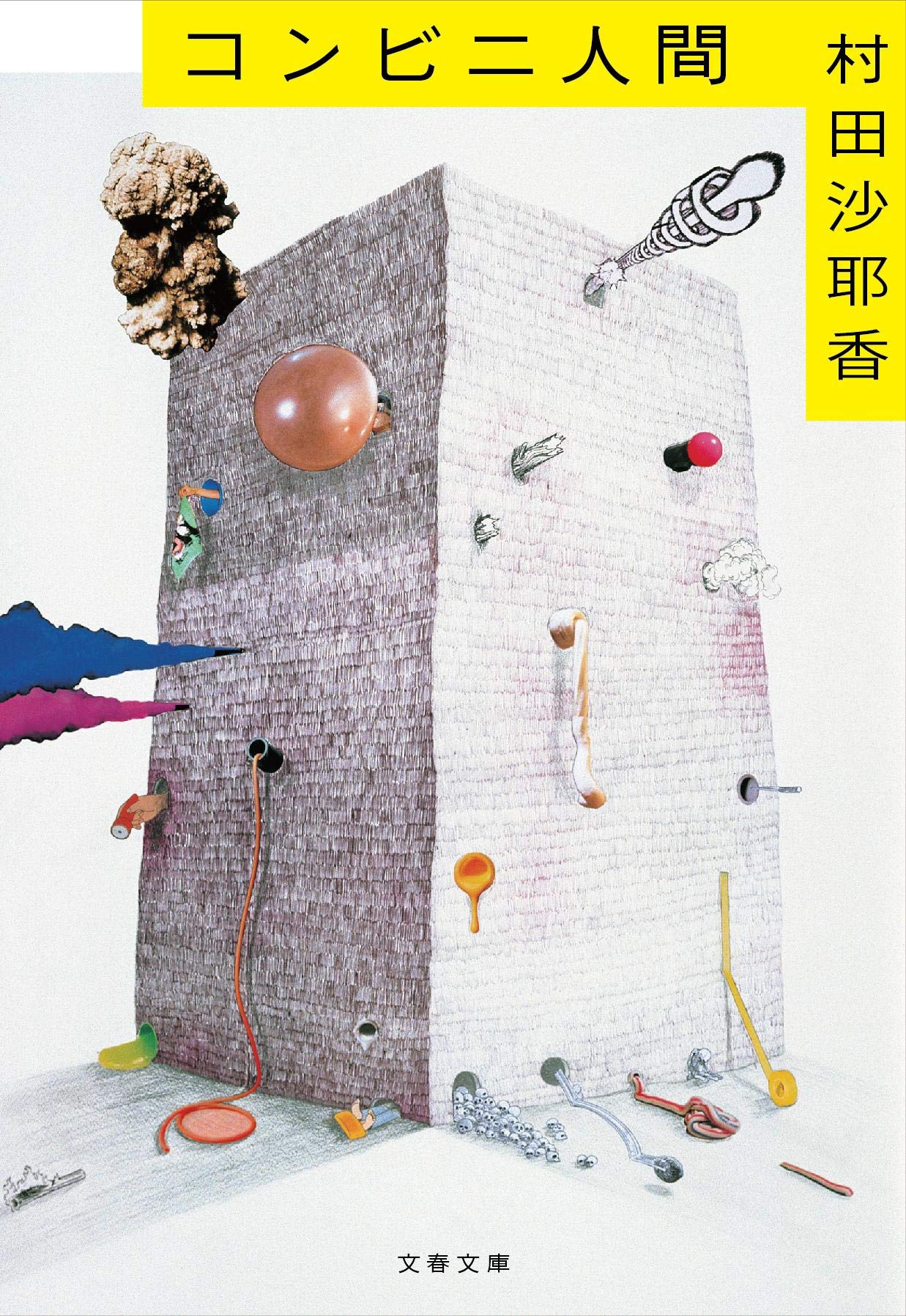
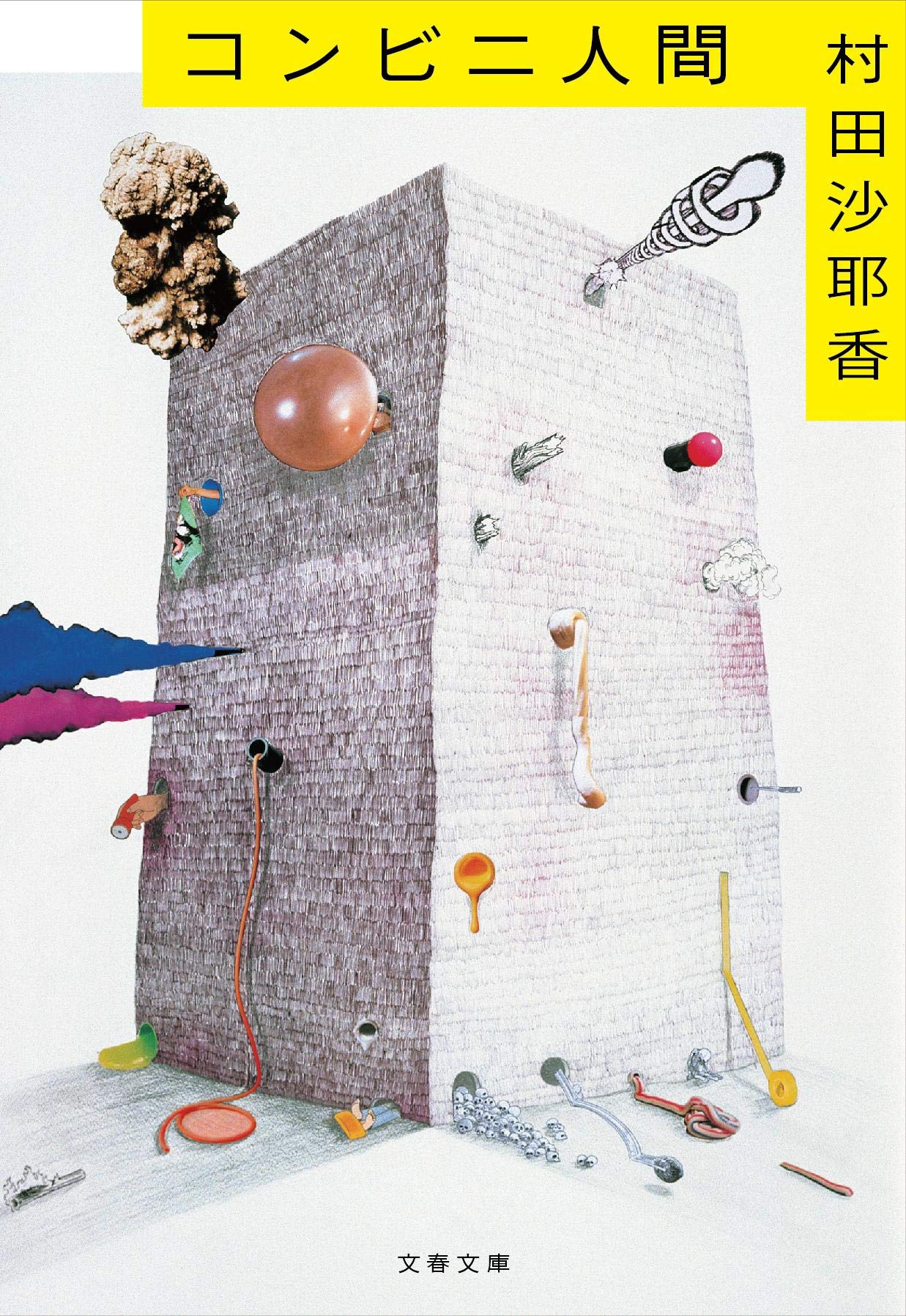
第155回芥川賞を受賞した話題作。36歳未婚、コンビニバイト歴18年の主人公を通して、現代社会における「普通」とは何かを問いかけます。
「普通」の生き方ができない主人公は、マニュアル通りに動くコンビニ店員でいる時だけ、世界の歯車になれると感じています。 彼女の独特な価値観や視点から描かれる世界は、私たちが無意識に囚われている社会の常識や同調圧力に、静かな衝撃を与えます。軽やかな筆致ながらも、現代社会の本質を鋭く突いた一冊です。



「普通」ってなんだろうって、すごく考えさせられたな。主人公の生き方が、ちょっと羨ましくもなったよ。
16位『手紙』東野圭吾
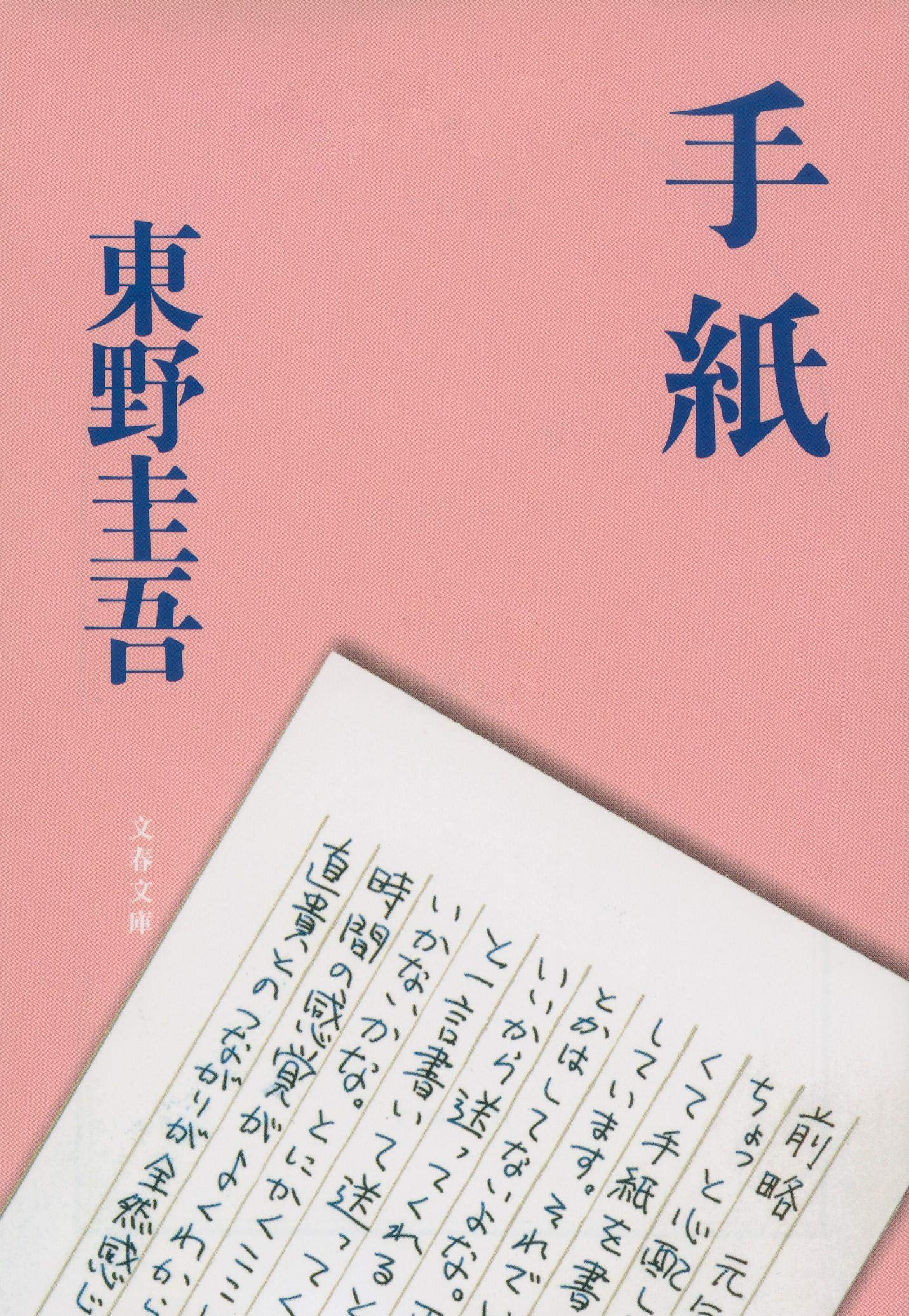
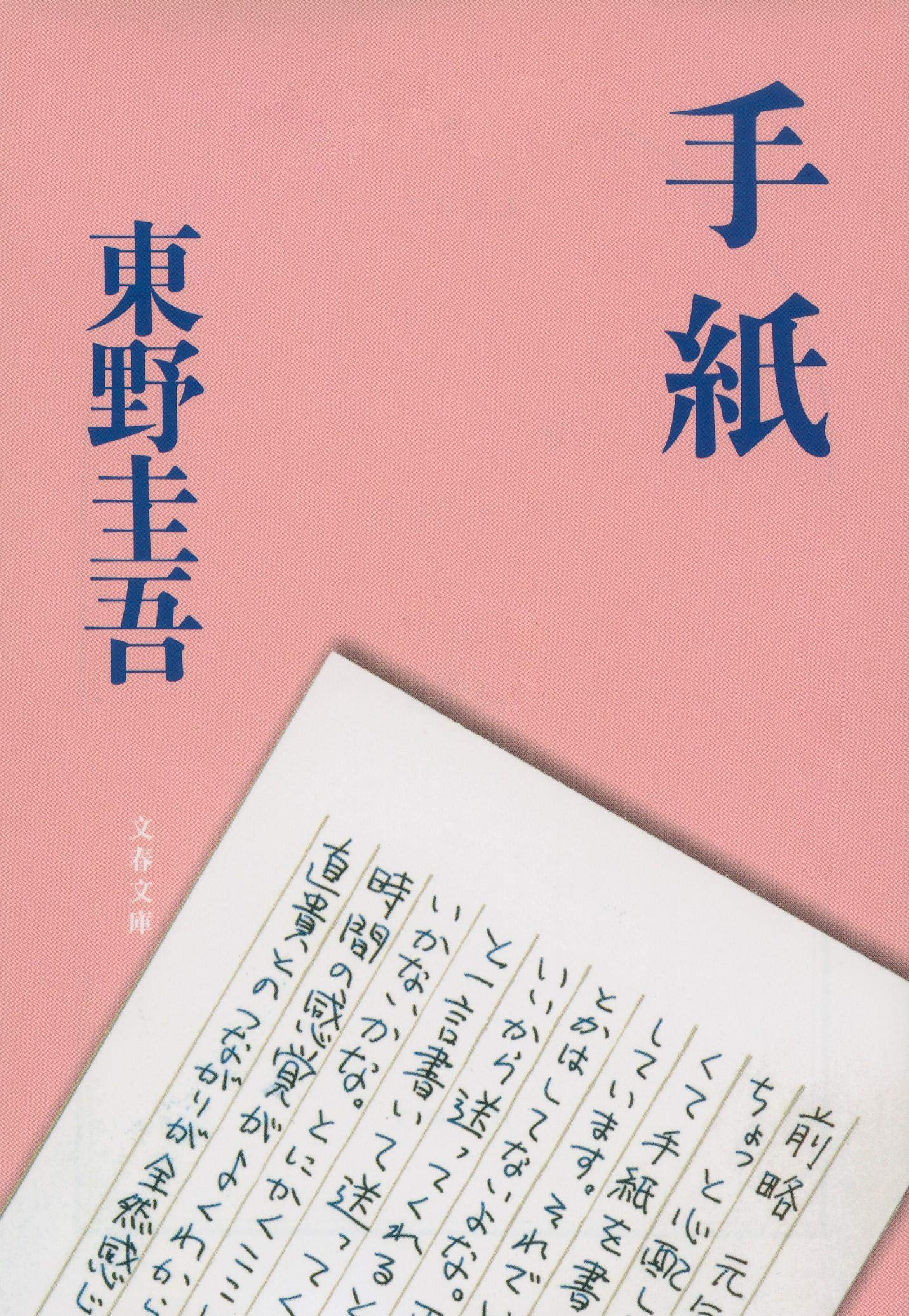
犯罪加害者の家族が、社会からどのような差別や偏見にさらされるのか。その過酷な現実を真正面から描いた、東野圭吾の代表作の一つです。
兄が強盗殺人の罪で服役している弟。彼は進学、恋愛、就職と、人生のあらゆる場面で「殺人犯の弟」というレッテルに苦しめられます。月に一度、刑務所の兄から届く手紙を軸に、兄弟の絆と断絶、そして償いとは何かという重いテーマが描かれます。涙なくしては読めない、感動的な物語です。



加害者家族の苦しみが痛いほど伝わってきて、本当に泣けたよ。兄弟の絆にも感動したな。
17位『八日目の蟬』角田光代
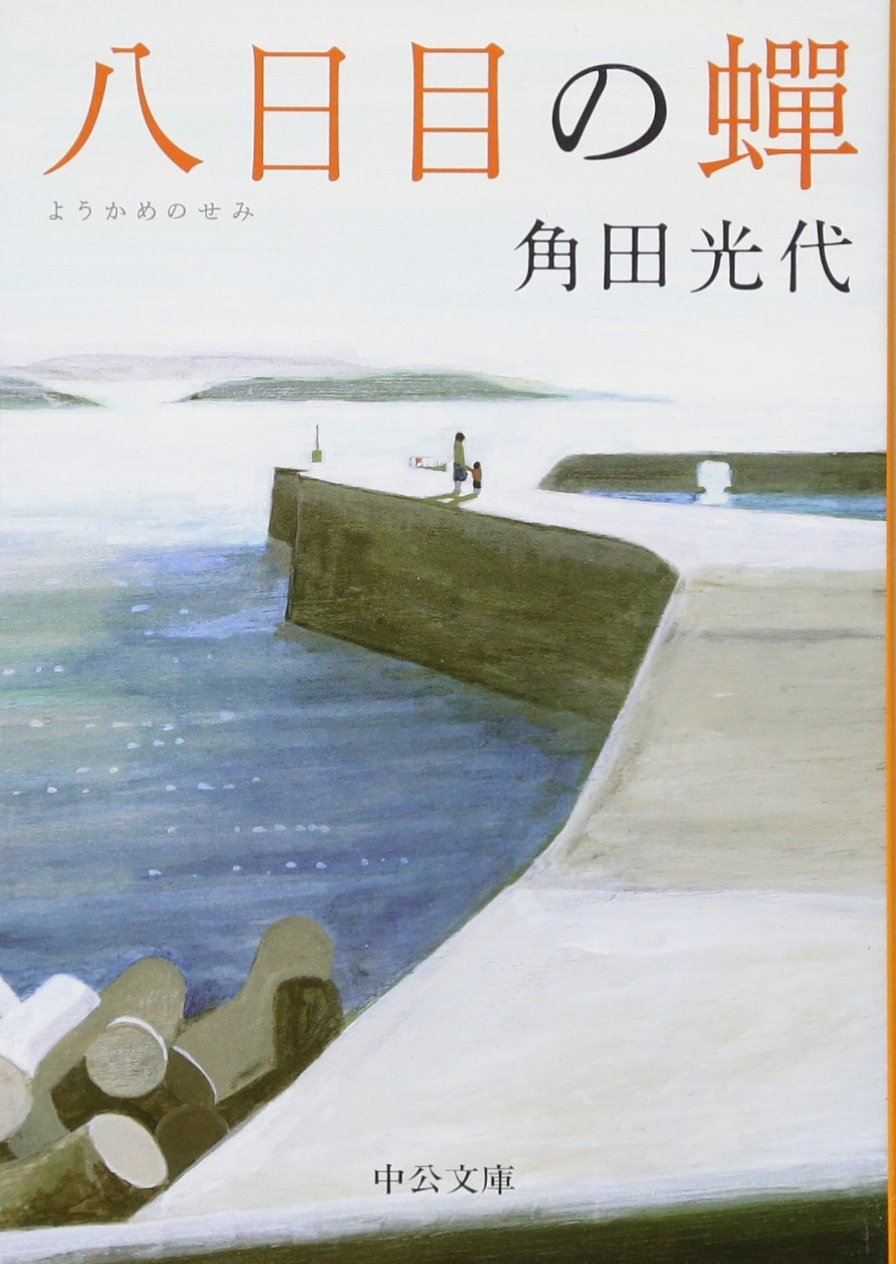
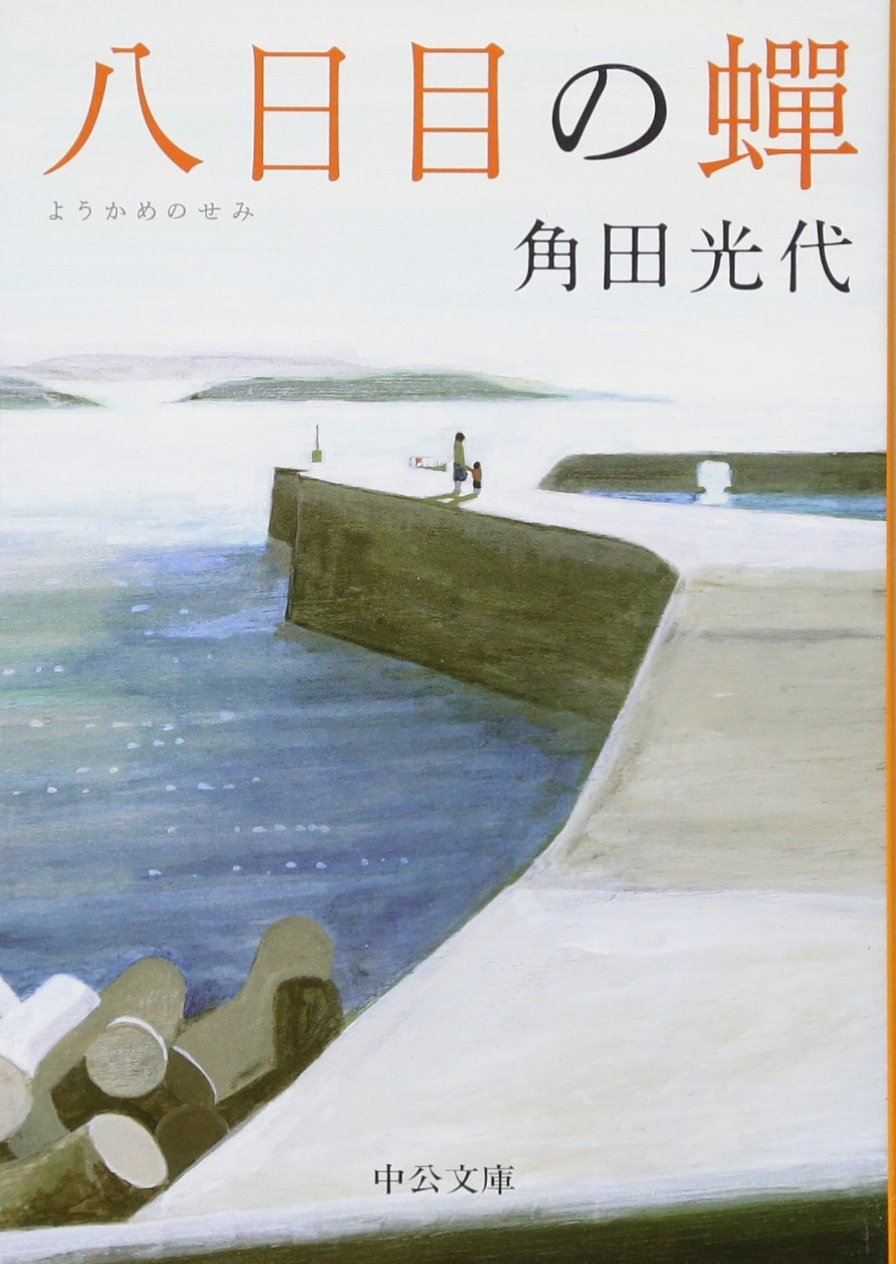
「母性」をテーマに、不倫相手の赤ん坊を誘拐した女性の逃亡劇と、誘拐された少女のその後の葛藤を描いた作品です。 物語は、誘拐犯として4年間娘を育てた女の視点と、事件後に本当の両親の元へ戻り、心を閉ざして生きる娘の視点の二部構成で描かれます。
血のつながりか、共に過ごした時間か。本当の親子とは何か、愛情とは何かを深く問いかけます。 誘拐という犯罪を犯しながらも、娘へ注がれる愛情の深さに、読者は複雑な感情を抱くことになるでしょう。



切なくて、苦しくて、でも美しい物語だったな…。本当の親子ってなんだろうって考えさせられたよ。
18位『神さまを待っている』畑野智美
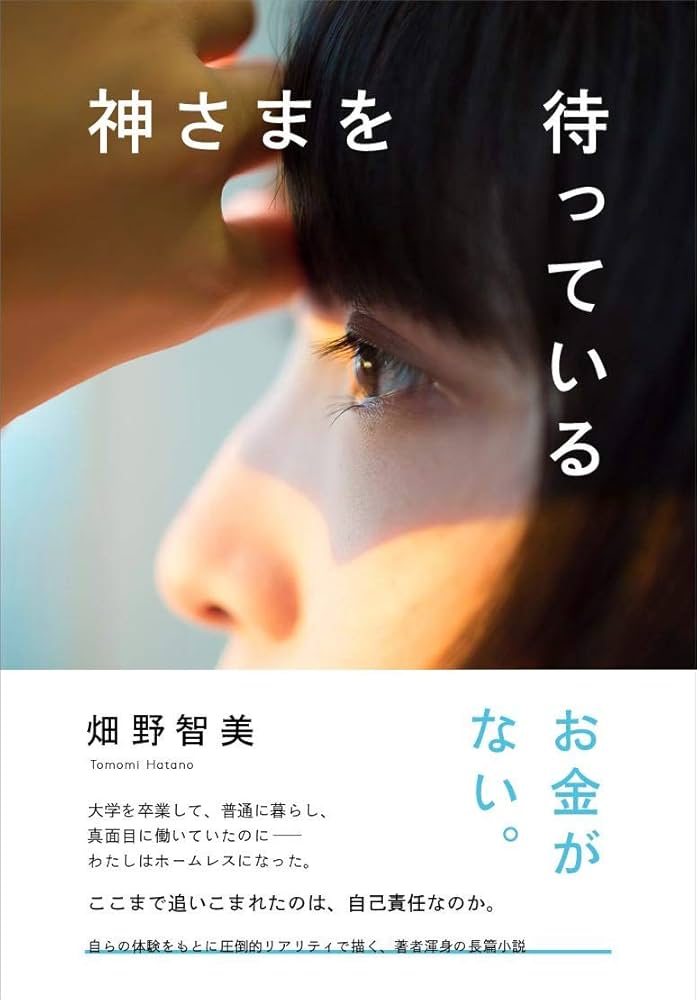
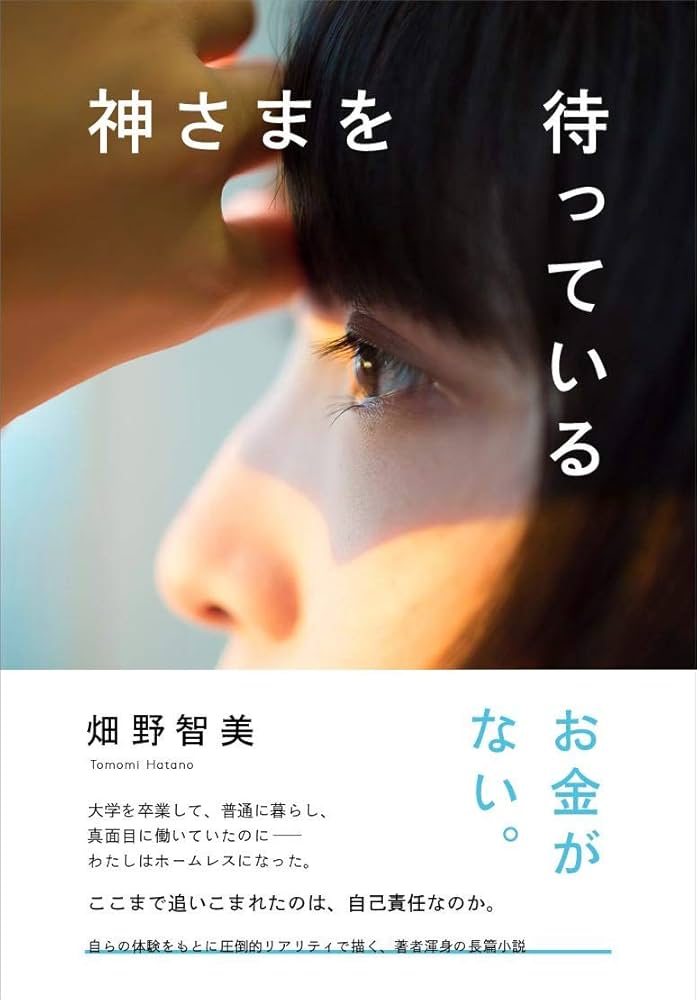
派遣切りに遭い、ホームレスへと転落していく女性の姿を通して、女性の貧困問題をリアルに描いた社会派小説です。 真面目に生きてきたはずの主人公が、なぜ社会のセーフティネットからこぼれ落ちてしまったのか。
現代社会の非情さや、一度つまずくと這い上がることが難しい現実が、痛々しいほどに伝わってきます。決して他人事ではない、現代日本の厳しい一面を浮き彫りにした作品です。



すぐそこにありそうな話で、読んでいてすごく怖くなったよ。社会の仕組みを考えさせられるね。
19位『白い巨塔』山崎豊子
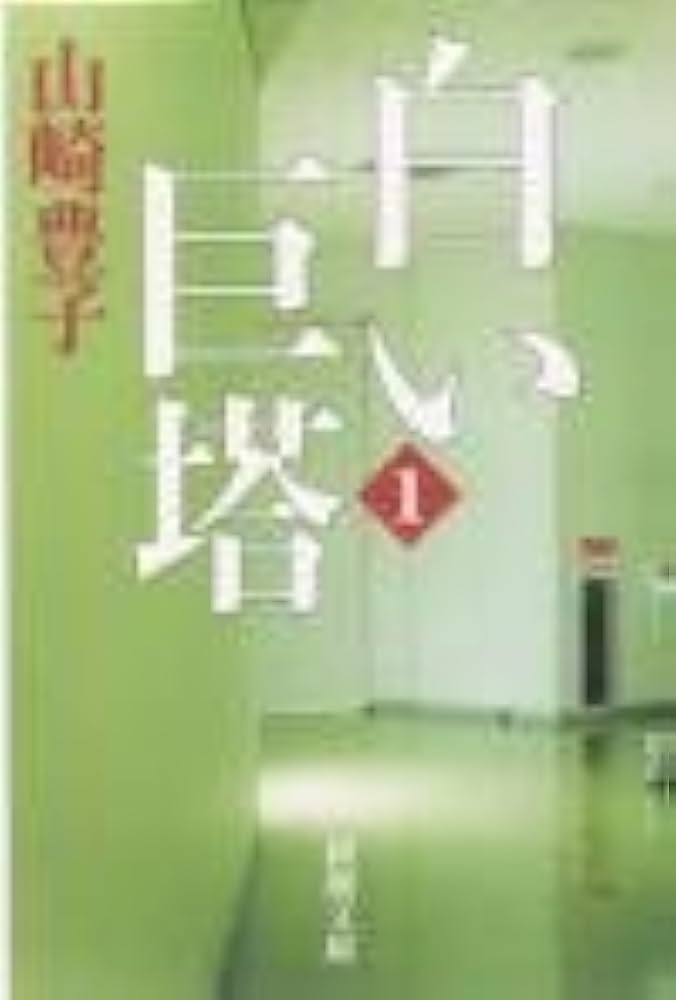
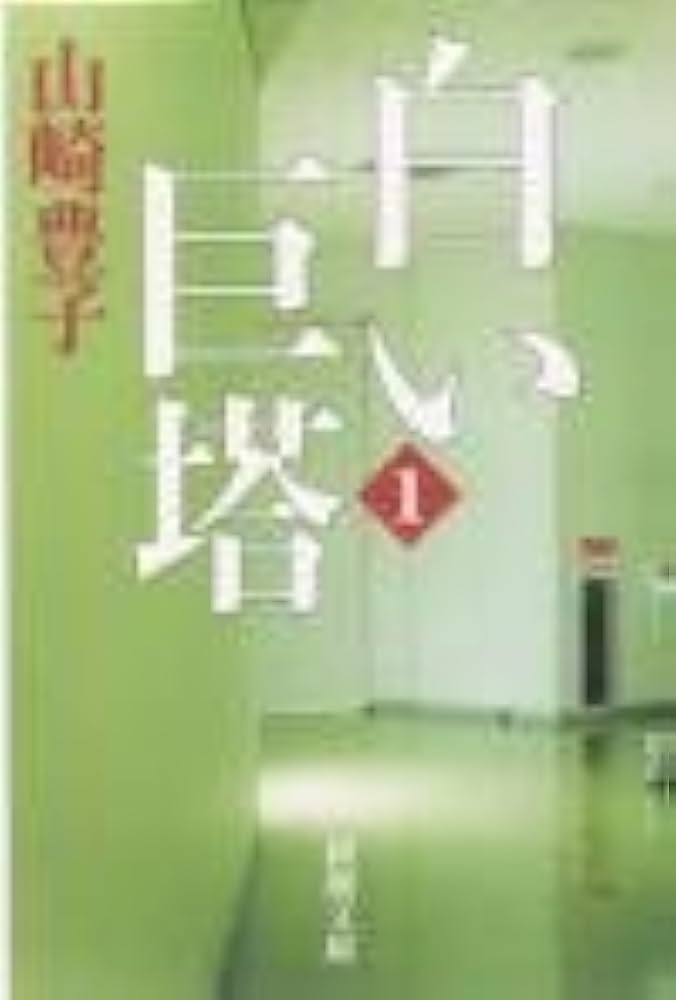
大学病院を舞台に、医療過誤や医局内の熾烈な権力闘争を描いた、社会派小説の不朽の名作です。 主人公は、食道外科の権威でありながら、野心家で傲慢な財前五郎。教授の座を巡る争いや、医療裁判を通して、大学病院という組織の腐敗と、医師の倫理が鋭く問われます。
何度も映像化されているため、ご存知の方も多いかもしれません。しかし、原作小説の圧倒的な取材力に基づいた重厚な物語は、今なお色褪せることのない輝きを放っています。人間の欲望や嫉妬が渦巻く、濃密なドラマに引き込まれます。



これぞ社会派小説の原点って感じだね!財前五郎のキャラクターが強烈で忘れられないよ。
20位『チーム・バチスタの栄光』海堂尊
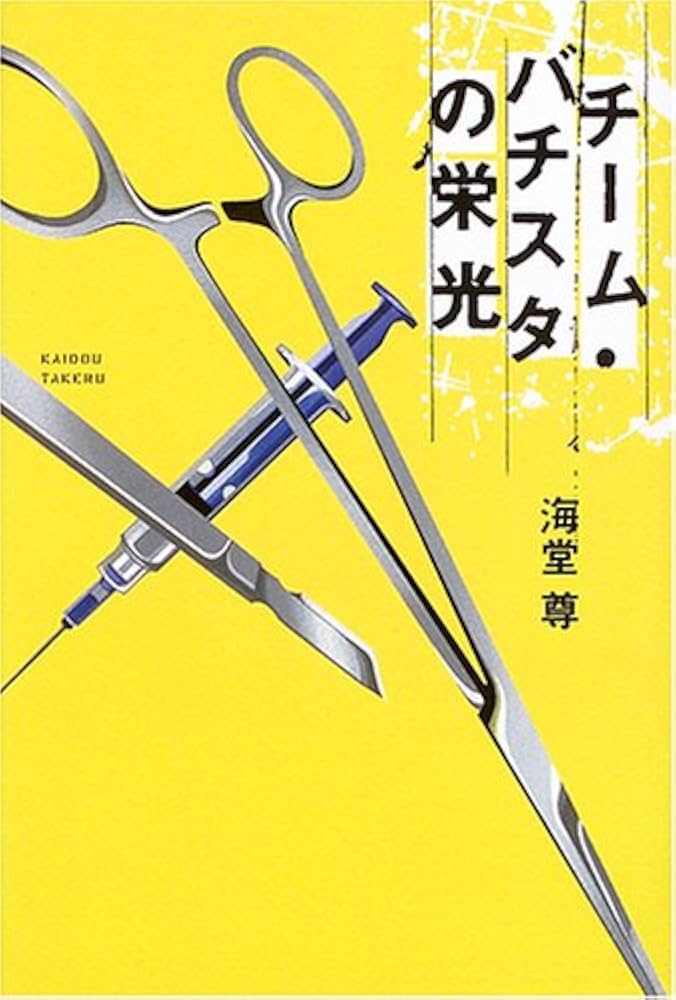
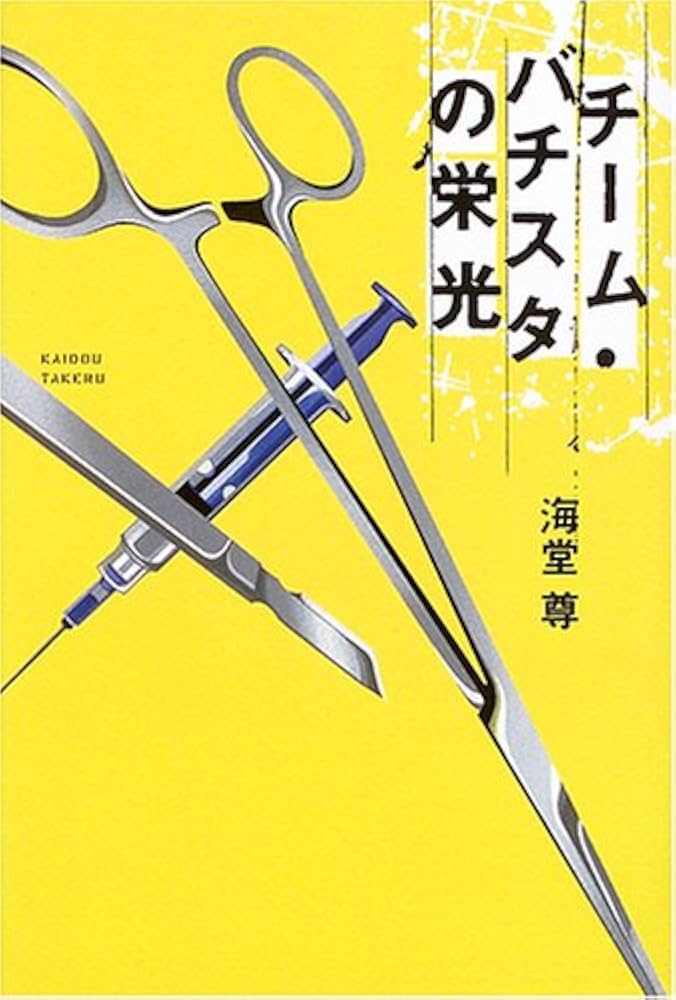
成功率100%を誇っていた心臓手術の専門チーム「チーム・バチスタ」で、立て続けに術中死が発生。その原因を探るため、万年講師の医師と厚生労働省の役人が内部調査に乗り出す医療ミステリーです。
本作のテーマは、現代医療が抱える問題点。医療ミスの真相を追う謎解きの面白さはもちろん、個性豊かなキャラクターたちの掛け合いも魅力です。エンターテイメント性の高い作品でありながら、チーム医療の難しさや、医師たちの葛藤を巧みに描き出しています。



ミステリーとして純粋に面白い!キャラクターも魅力的で、シリーズで追いかけたくなっちゃうね。
21位『13階段』高野和明
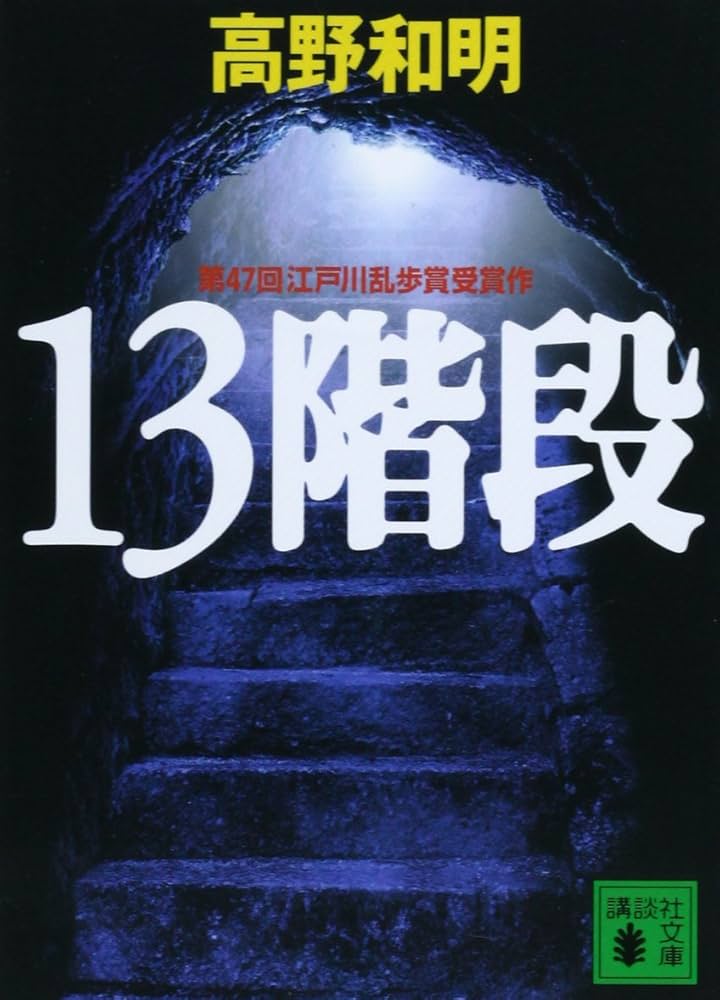
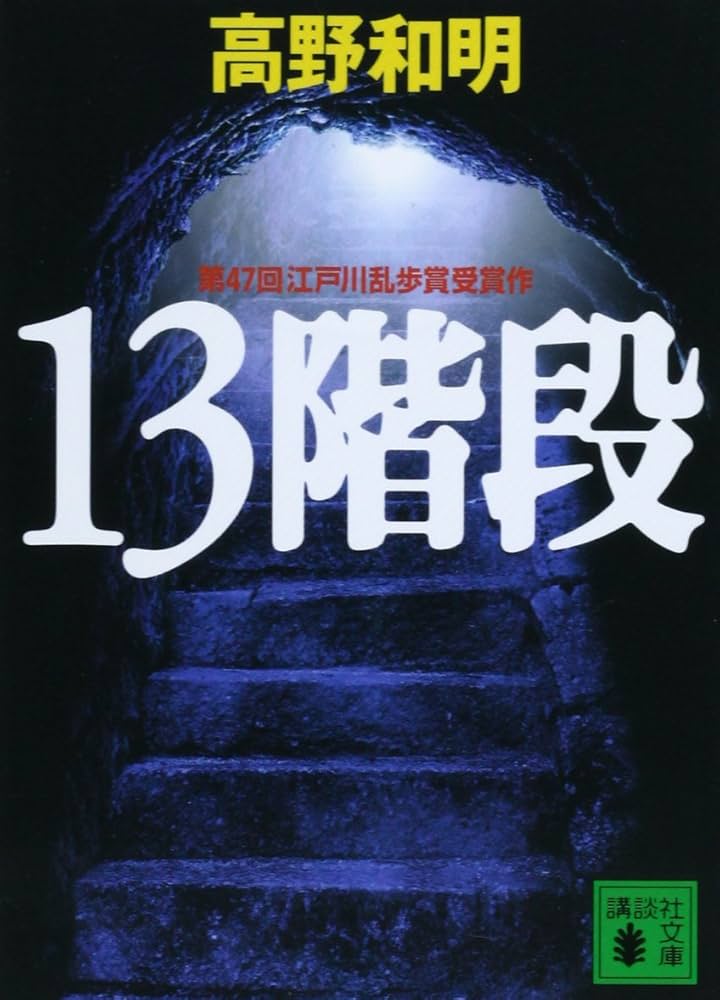
死刑制度や冤罪といった、司法の根幹を問うテーマを扱った社会派ミステリーです。 仮釈放中の青年とベテラン刑務官が、記憶を失った死刑囚の冤罪を晴らすため、事件の真相を追います。 残された時間はわずか。唯一の手がかりは、死刑囚がおぼろげに記憶している「階段」のイメージだけです。
タイトルの「13階段」とは、絞首台を意味します。 人の命を奪う「死刑」という制度の重みと、冤罪の可能性が、緊迫感あふれるストーリーの中で描かれます。 第47回江戸川乱歩賞を受賞した、著者のデビュー作にして傑作です。



本作における死刑制度というテーマの扱い方は極めて冷静であり、読者に一方的な見解を押し付けることはない。
22位『告白』湊かなえ
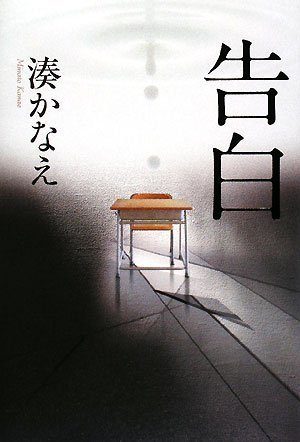
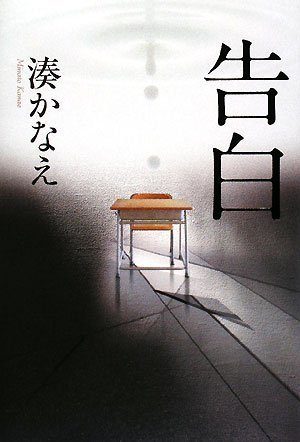
中学校を舞台に、娘を殺された女性教師の復讐劇を描いた衝撃的なミステリー。事件に関わった人物たちが、それぞれの視点から事件を「告白」していく形式で物語が進行します。
少年犯罪やいじめ、学級崩壊といった教育現場が抱える闇が、冷徹な筆致でえぐり出されていきます。人間の悪意や身勝手さが次々と暴かれていく展開に、ページをめくる手が止まらなくなるでしょう。「イヤミス(読んだ後に嫌な気分になるミステリー)」の女王、湊かなえの代表作です。



この作品が内包する人間の悪意の描写は、他の追随を許さないレベルにあると言えるだろう。
23位『何者』朝井リョウ
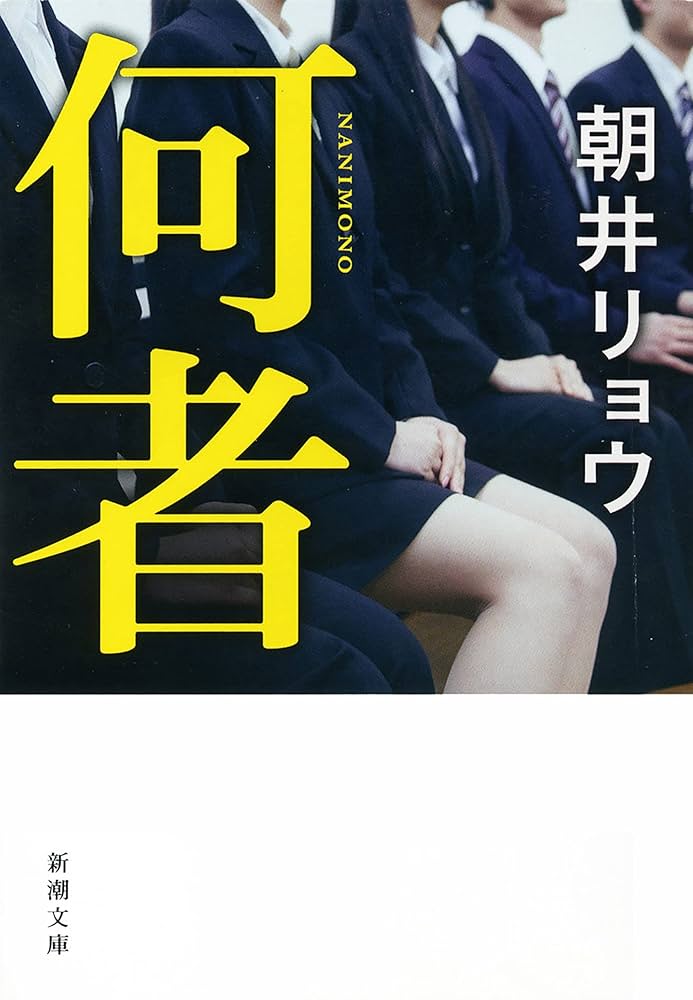
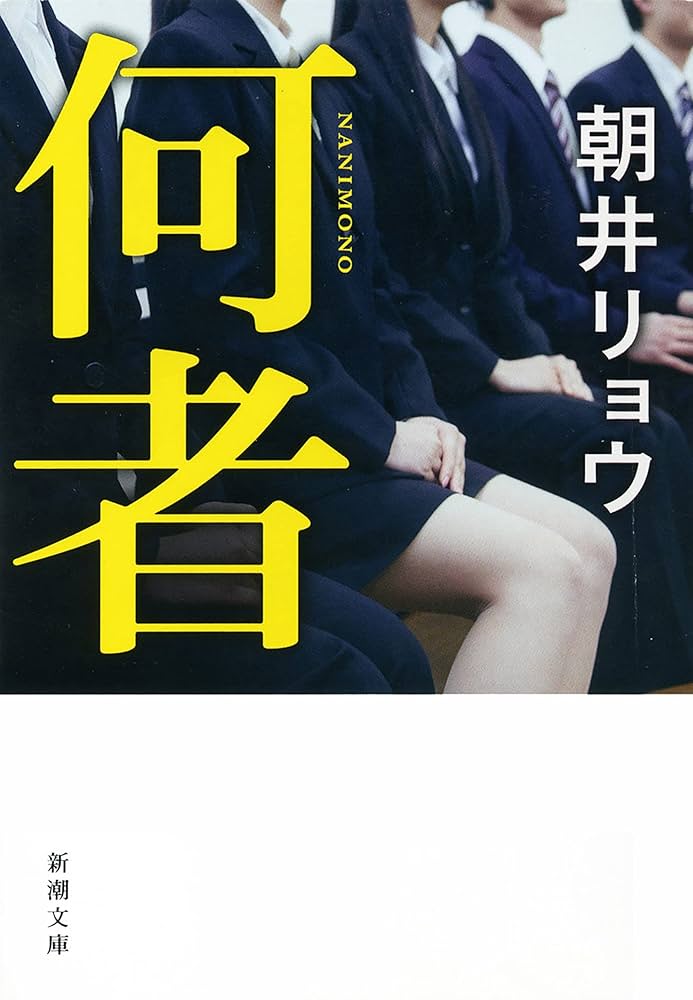
就職活動を通して、現代の若者たちのリアルな心情や人間関係を描き、第148回直木賞を受賞した作品です。 就活対策のために集まった5人の大学生。彼らはSNSで互いの動向を探り合い、内定を目指して様々な戦略を駆使します。
SNS上での自己アピールと、その裏に隠された本音や自意識。 SNS社会におけるコミュニケーションのあり方や、自分が「何者」であるかを模索する若者たちの焦燥感が、痛々しいほどリアルに描かれています。



就活を思い出して胸がズキズキしたよ…。SNSの裏側とか、リアルすぎて怖い!
24位『テミスの剣』中山七里
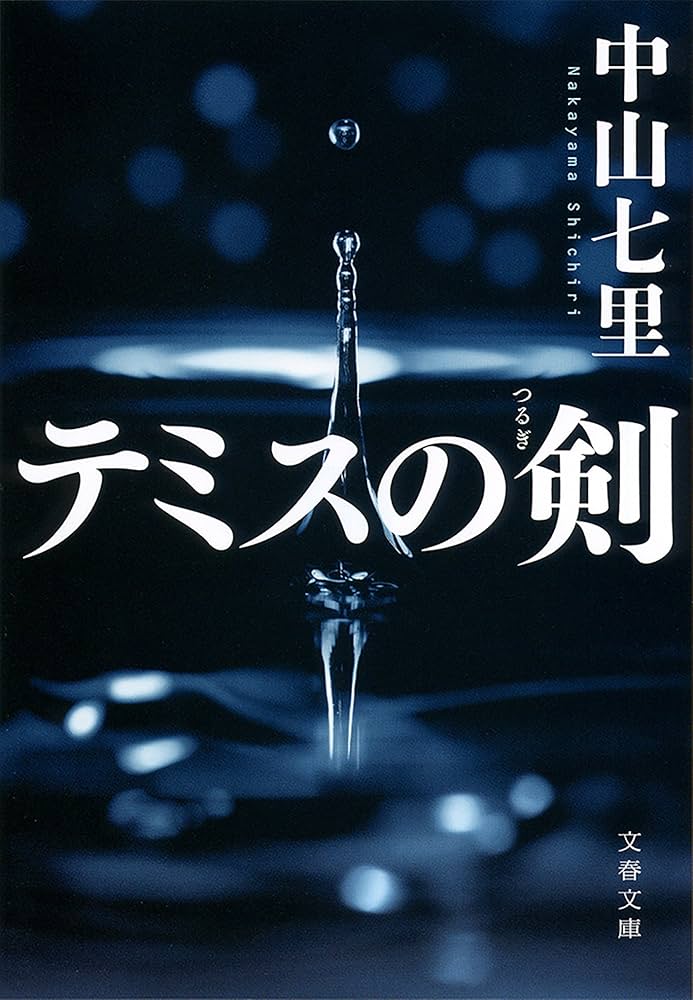
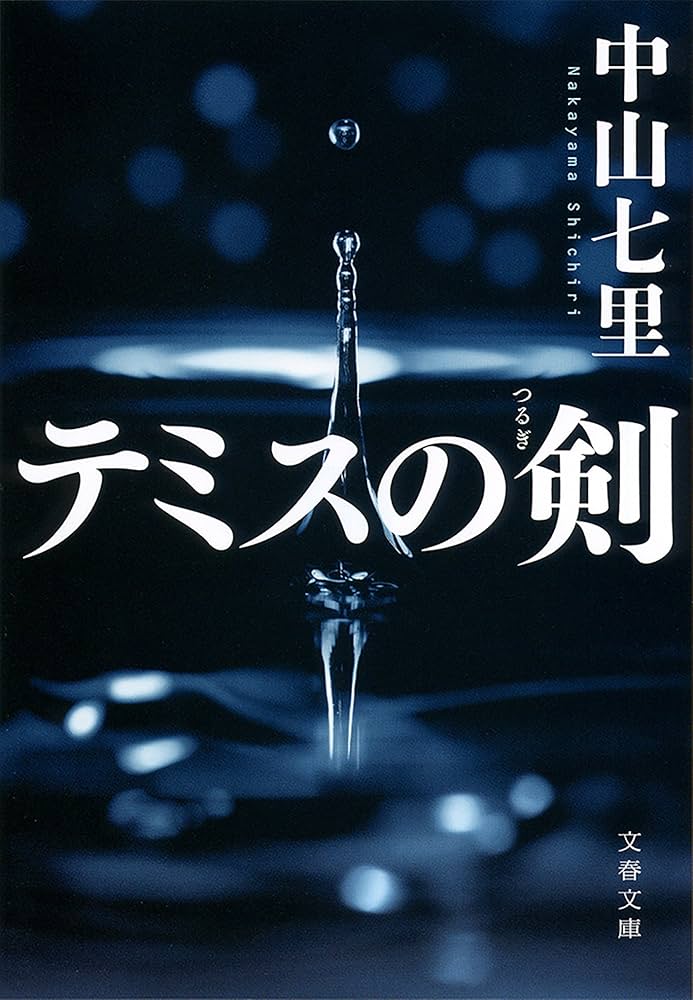
冤罪事件をテーマに、日本の司法制度や警察組織の闇に鋭く切り込んだ社会派ミステリーです。主人公は、かつて担当した事件で犯人を自白に追い込み、死刑判決を確定させた刑事。しかし数年後、真犯人を名乗る人物が現れたことで、彼の信じてきた正義が根底から覆されます。
一度下された判決は本当に正しかったのか。取り返しのつかない過ちを前に、刑事、検察、裁判官、そしてメディアがどのように機能し、あるいは機能不全に陥るのかが描かれます。正義とは何か、真実とは何かを問う、重厚な物語です。



どんでん返しの連続で、最後まで目が離せなかったよ。司法のあり方を深く考えさせられたな。
25位『スクラップ・アンド・ビルド』羽田圭介
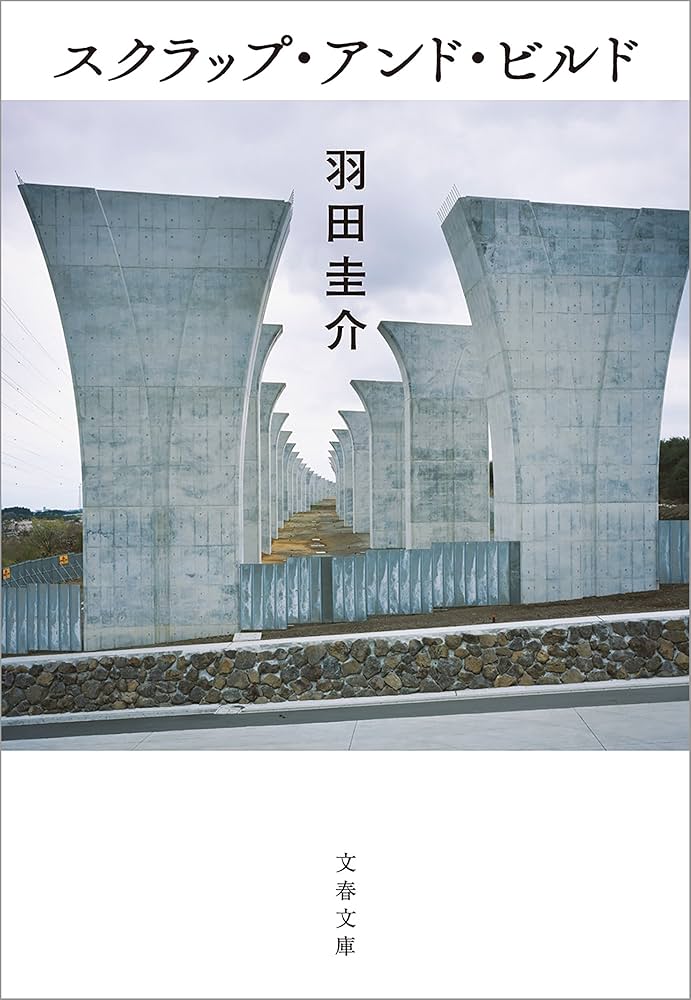
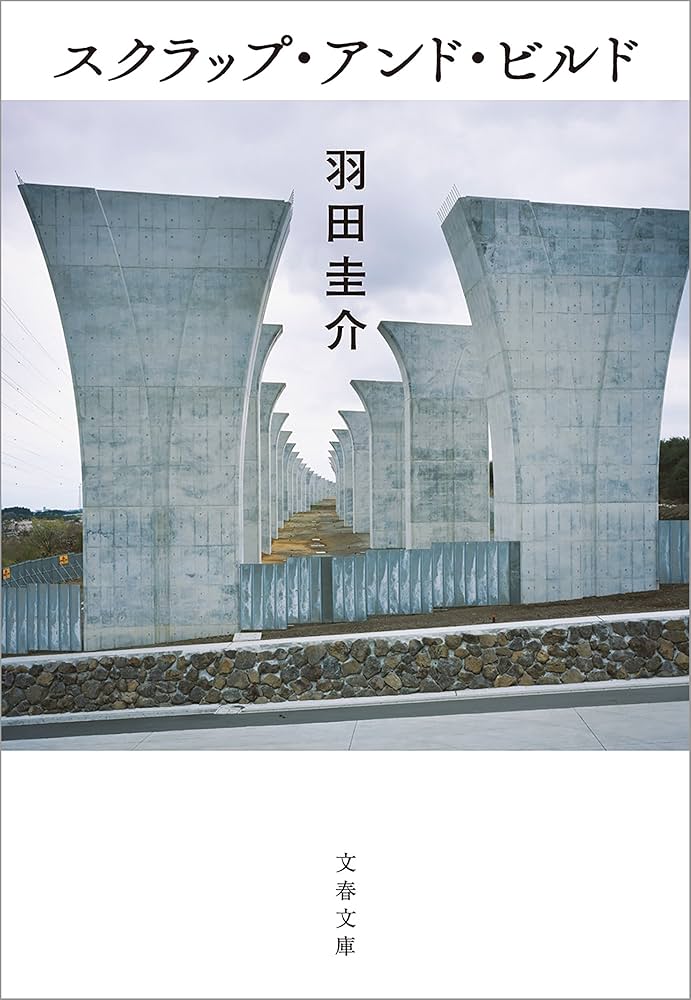
第153回芥川賞を受賞した本作は、「介護」と「老い」をテーマに、現代の家族が抱える問題をシニカルな視点で描いています。主人公は、就職もせず、要介護の祖父の面倒を見ている青年。
彼は祖父の「もう死にたい」という口癖を聞き、どうすれば祖父を安らかに死なせてあげられるかを考え始めます。高齢化社会における尊厳死や、若者の閉塞感といった重いテーマを扱いながらも、ユーモアを交えた軽快な文体で読みやすいのが特徴です。新しい形の家族小説として、多くの議論を呼びました。



テーマは重いけど、主人公の考え方がユニークで面白いな。介護について違う角度から考えられたよ。
26位『流浪の月』凪良ゆう
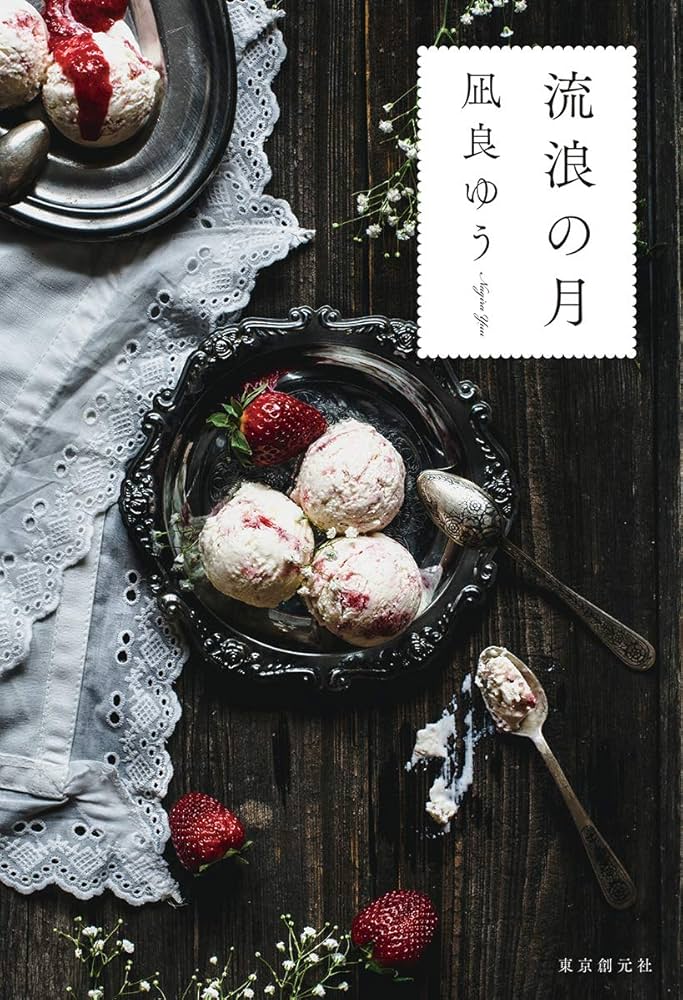
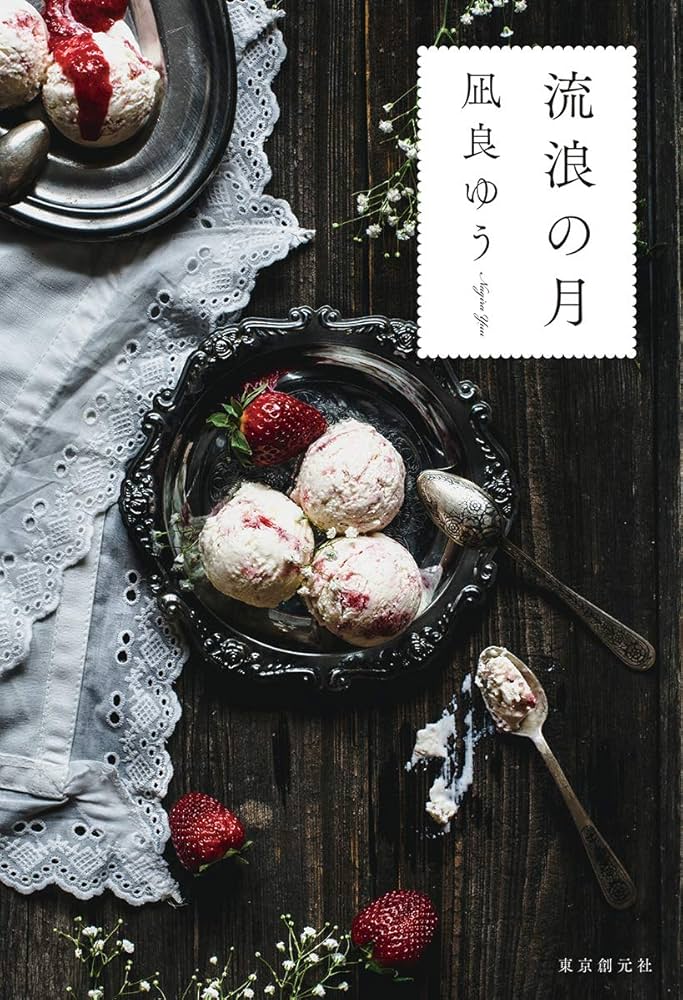
ある雨の日に、少女は大学生の男の部屋へ行くことを決意します。二人は穏やかな時間を過ごしますが、その関係は「誘拐」として世間に知られ、二人は「被害女児」と「誘拐犯」というレッテルを貼られてしまいます。
本作は、世間の常識や偏見によって歪められてしまう、二人の特別な関係性を繊細に描いています。普通とは何か、正しさとは何か。当事者にしかわからない真実と、世間が作り上げる物語とのギャップに、深く考えさせられるでしょう。2020年本屋大賞を受賞した感動的な一冊です。



二人の関係が切なくて美しくて、涙が止まらなかった…。真実を見ることの大切さを教えられたよ。
27位『正欲』朝井リョウ
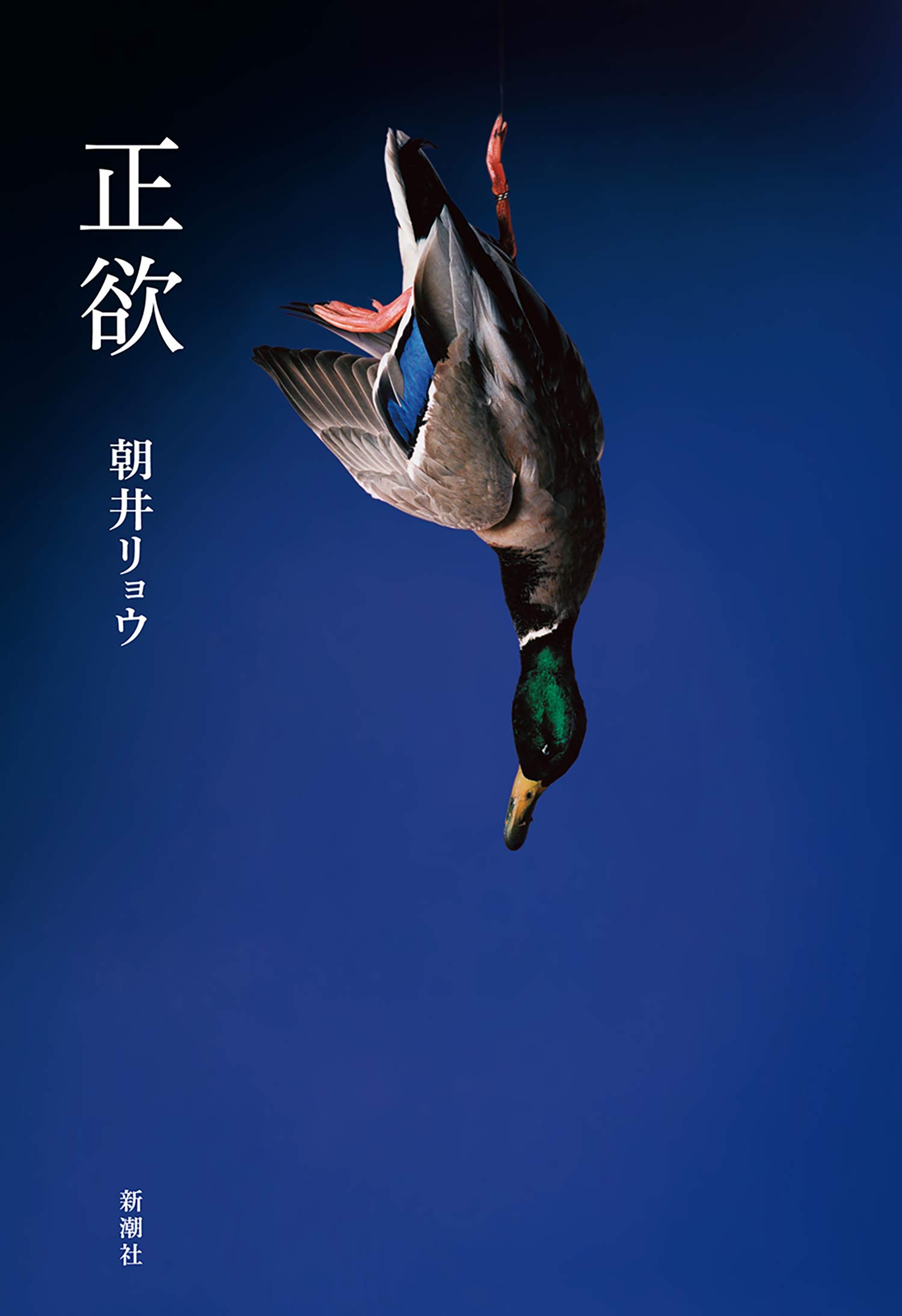
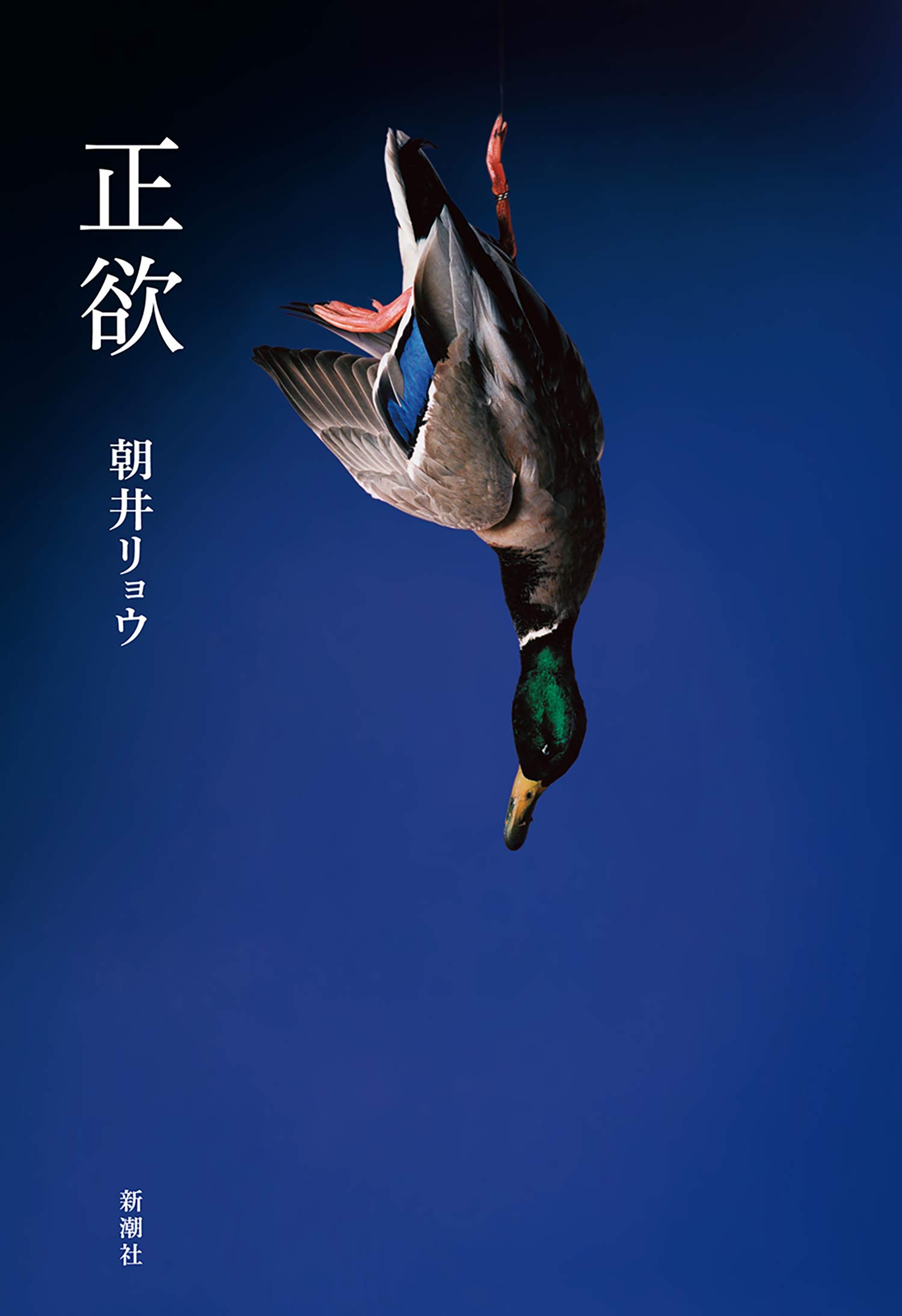
検事、大学生、販売員など、異なる背景を持つ登場人物たちの視点を通して、現代社会における「多様性」の本質に迫る意欲作です。彼らが抱える、世間からは理解されがたい「欲望」とは何なのか。
物語が進むにつれて、一見無関係に見えた彼らの人生が交錯し、驚くべき真実が明らかになります。「多様性」という言葉が広まる一方で、社会から切り捨てられてしまうマイノリティの存在を浮き彫りにします。読者の価値観を根底から揺さぶる、衝撃的な一冊です。



多様性って言葉を、わたしはちゃんと理解できてたかなって考えさせられたよ。衝撃的だけど読んでよかったな。
28位『沈まぬ太陽』山崎豊子
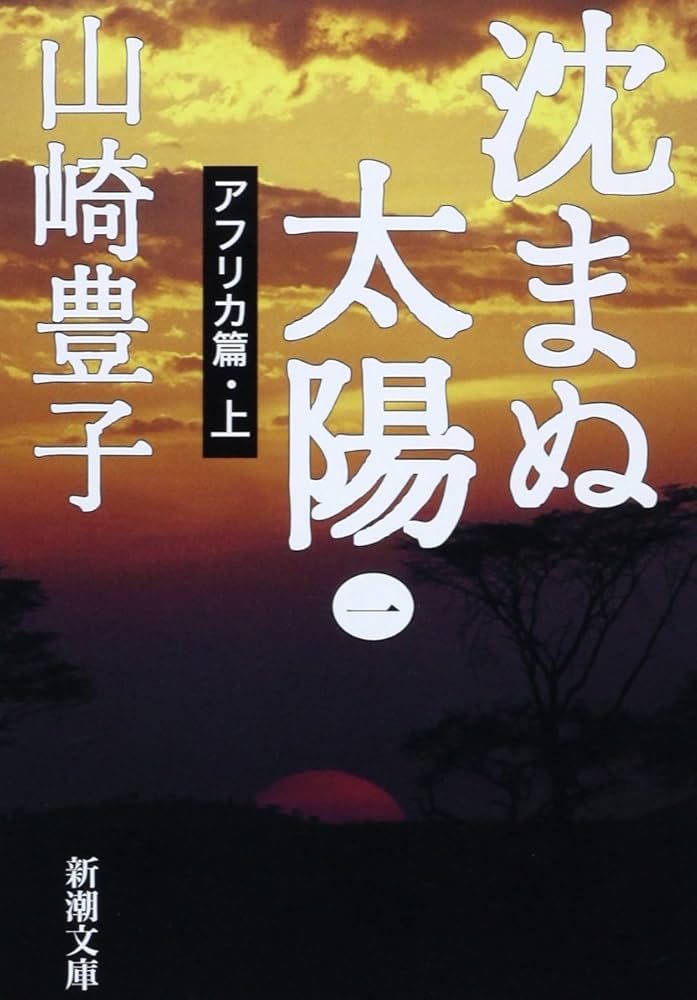
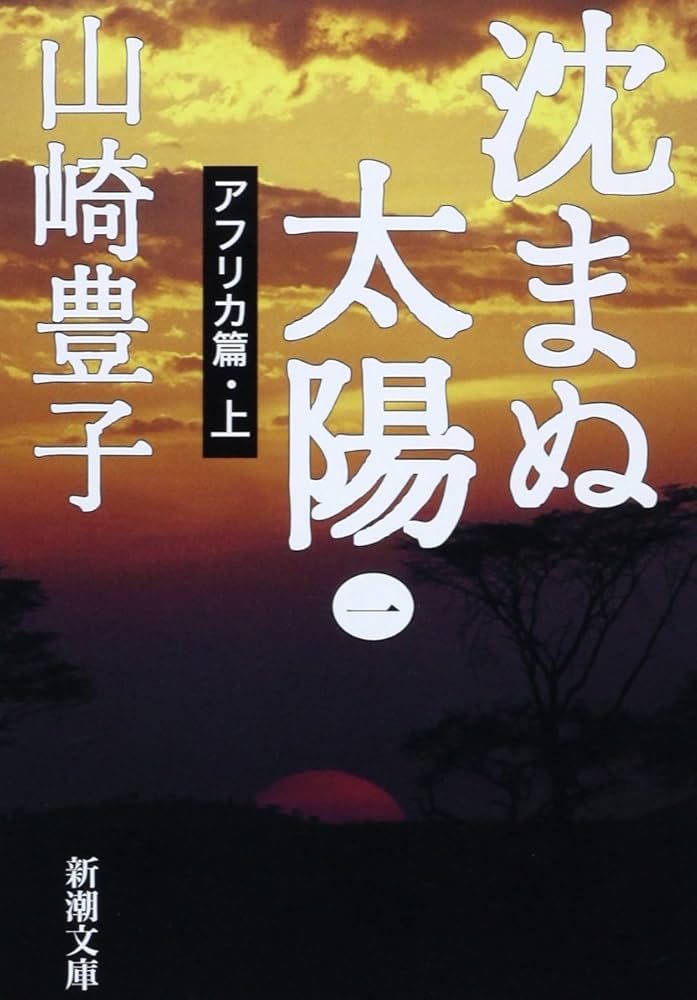
日本の大手航空会社を舞台に、労働組合の委員長を務めたことで海外の僻地へ左遷された主人公の不屈の人生と、御巣鷹山で起きたジャンボ機墜落事故を描いた社会派大作です。 日本航空とその元社員、そして日本航空123便墜落事故をモデルにしています。
巨大組織の不正や腐敗に立ち向かい、自らの信念を貫き通す主人公の生き様は、多くの読者に感動と勇気を与えました。 企業の社会的責任とは何か、そして人の命の尊さを問いかける、山崎豊子の代表作です。



組織の圧力に屈しない主人公の姿に感動したよ。人間の尊厳を考えさせられる不朽の名作だね。
29位『ある男』平野啓一郎


弁護士の主人公が、亡くなった依頼者の夫の身元調査を行ううちに、彼の驚くべき過去にたどり着くミステリー。死んだ男は、全くの別人として生きていたのです。
なぜ彼は名前を変え、別人として生きなければならなかったのか。その謎を追う過程で、戸籍や国籍、そして過去によって規定される「アイデンティティ」とは何かという哲学的な問いが浮かび上がります。在日韓国人三世という出自を持つ登場人物を通して、日本社会に根強く残る差別や偏見の問題にも光を当てています。



ミステリーとしても面白いし、アイデンティティについて深く考えさせられたな。自分とは何者か、見つめ直すきっかけになったよ。
30位『恍惚の人』有吉佐和子
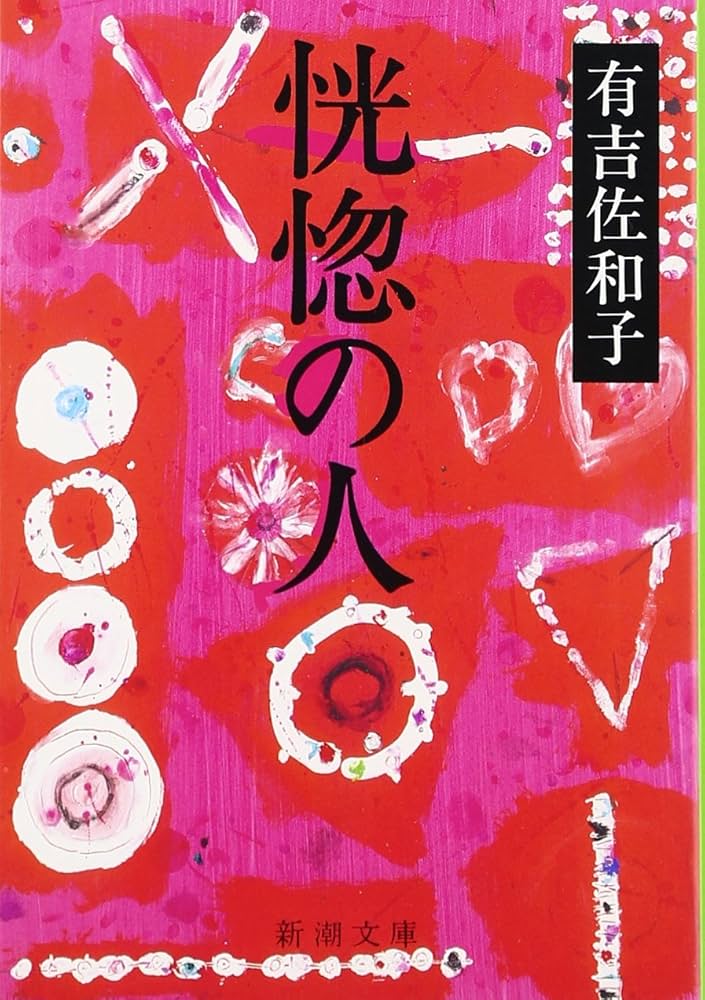
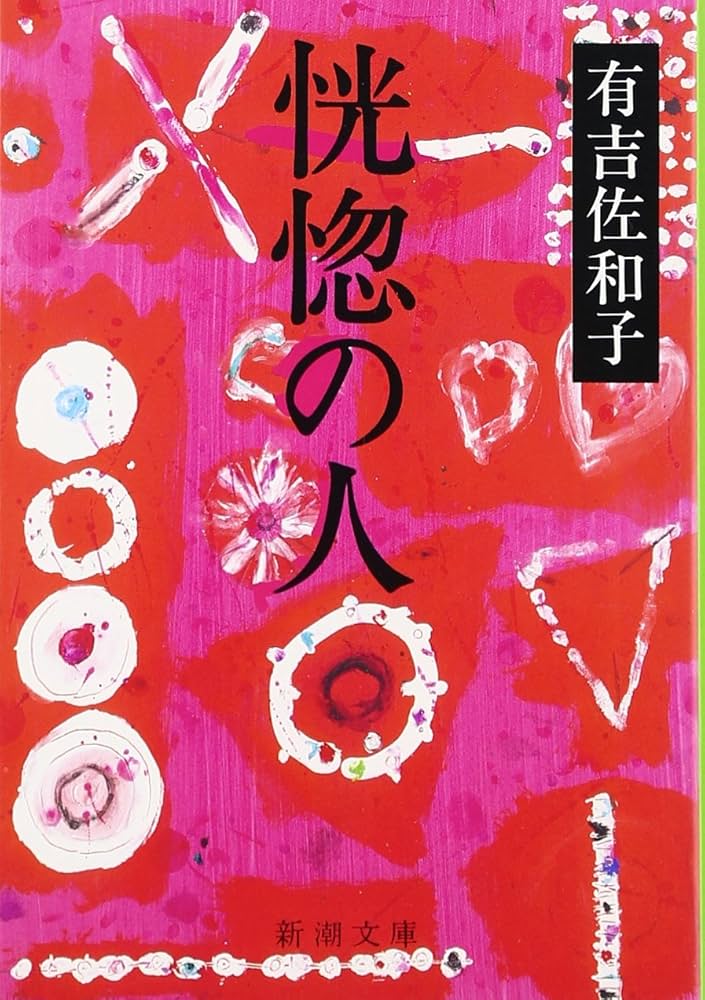
1972年に発表され、「恍惚」という言葉を流行語にした、認知症介護小説の草分け的存在です。義父が認知症になり、その介護に追われる嫁の姿を通して、高齢化社会が抱える問題をいち早く描き出しました。
今でこそ広く知られるようになった認知症ですが、当時はまだ理解が進んでいませんでした。そんな時代に、介護の過酷な現実と、家族の葛藤をリアルに描いた本作は、社会に大きな衝撃を与えました。時代を超えて読み継がれるべき、日本の高齢化社会を予見した名作です。



これが50年以上も前に書かれたなんて信じられないよ。介護の問題は今も昔も変わらないんだね。
まとめ:おすすめの社会問題小説を読んで、私たちの社会について考えてみませんか
ここまで、社会問題をテーマにしたおすすめの小説を30作品ご紹介してきました。気になる一冊は見つかりましたか?
小説を通して社会問題に触れることは、ニュースを見るだけでは得られない、深い理解と共感をもたらしてくれます。登場人物たちの人生を追体験することで、これまで他人事だと思っていた問題が、自分自身の問題として心に響くはずです。
今回ご紹介した作品が、あなたが社会について考え、新たな視点を得るきっかけになれば幸いです。ぜひ、気になった小説を手に取って、物語の世界に飛び込んでみてください。