あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】芥川龍之介の小説おすすめランキングTOP20

芥川龍之介とは?時代を超えて読み継がれる作品の魅力
芥川龍之介は、大正時代を中心に活躍した日本を代表する小説家です。1892年に東京で生まれ、東京帝国大学の英文科を卒業。在学中から創作活動を始め、夏目漱石にその才能を認められたことをきっかけに、文壇の寵児となりました。
芥川作品の最大の魅力は、人間のエゴイズムや心の機微を鋭く描き出す、巧みな心理描写にあります。『今昔物語集』などの古典から題材を得た歴史小説から、自身の内面を深く見つめた私小説、さらには子ども向けの童話まで、その作風は多岐にわたります。
簡潔で知的ながらも読みやすい文章で、人間の本質を突く普遍的なテーマを描いた芥川の作品は、発表から100年以上経った今でも、私たちの心を捉えてやみません。わずか35年という短い生涯でしたが、その功績を称え、親友の菊池寛によって新人文学賞「芥川賞」が設立されたことからも、彼が日本文学に与えた影響の大きさがうかがえます。
芥川龍之介の小説おすすめランキングTOP20
数多くの名作を残した芥川龍之介。どれから読めばいいか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、小説専門メディア『小説ヨミタイ』が、芥川龍之介のおすすめ小説をランキング形式でご紹介します。教科書で読んだことのある有名な作品から、知る人ぞ知る名作まで幅広く選びました。ぜひ、このランキングを参考にお気に入りの一冊を見つけて、芥川文学の奥深い世界に触れてみてください。
1位: 『羅生門』
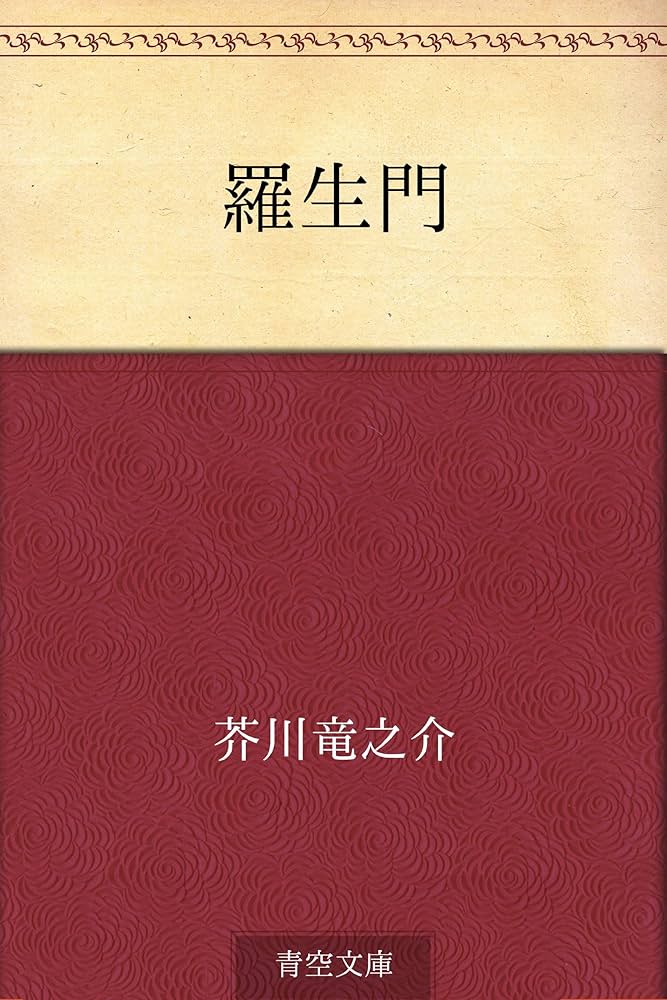
芥川龍之介の代表作として、まず名前が挙がるのが『羅生門』です。1915年、芥川がまだ東京帝国大学の学生だった頃に発表した初期の短編小説で、多くの国語の教科書にも掲載されているため、読んだことがある方も多いでしょう。
物語の舞台は、災害や飢饉によって荒れ果てた平安時代の京都。主人から暇を出され、生きるか盗人になるかの瀬戸際に立たされた一人の下人が、羅生門で死人の髪を抜く老婆と出会います。
「生きるためには仕方がない」という老婆の言葉を聞いた下人の心は、正義と悪の間で激しく揺れ動きます。極限状態に追い込まれた人間のエゴイズムとは何か、そして善悪とは何かを鋭く問いかける本作は、芥川文学の原点ともいえる一作です。
 ふくちい
ふくちい生きるために悪を選ぶ下人の姿、ゾッとしちゃうね。わたしならどうするかなって、すごく考えさせられるよ。
2位: 『蜘蛛の糸』
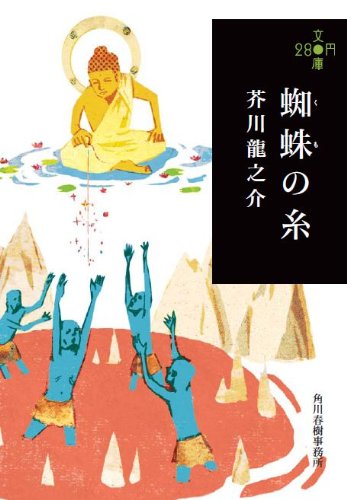
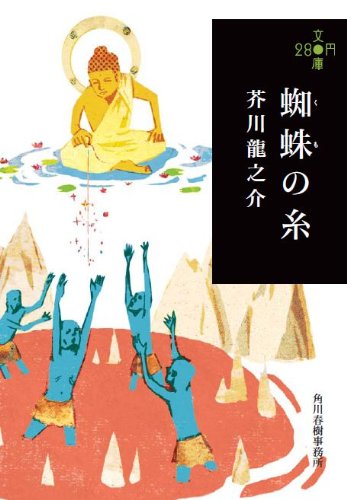
『羅生門』と並んで芥川の代表作として知られる『蜘蛛の糸』は、子ども向けに書かれた短編小説です。シンプルな物語ながら、人間の本質を突く深い教訓が込められています。
物語の主人公は、地獄に落ちたカンダタという名の泥棒。ある日、お釈迦様は彼が生前に一度だけ蜘蛛の命を助けたことを思い出し、慈悲の心から極楽へと続く一本の蜘蛛の糸を垂らします。
カンダタは必死に糸を登りますが、自分に続いて多くの罪人が登ってくるのを見て、「この糸は自分のものだ」と叫びます。その利己的な心が生まれた瞬間、糸は切れ、彼は再び地獄の底へと落ちていくのでした。自分だけが助かろうとするエゴイズムが、せっかくの救いを台無しにしてしまうという、普遍的なテーマを描いた名作です。



みんなで助かろうとすれば良かったのにね…。カンダタの気持ちもわかるから、余計に悲しい結末だよ。
3位: 『杜子春』
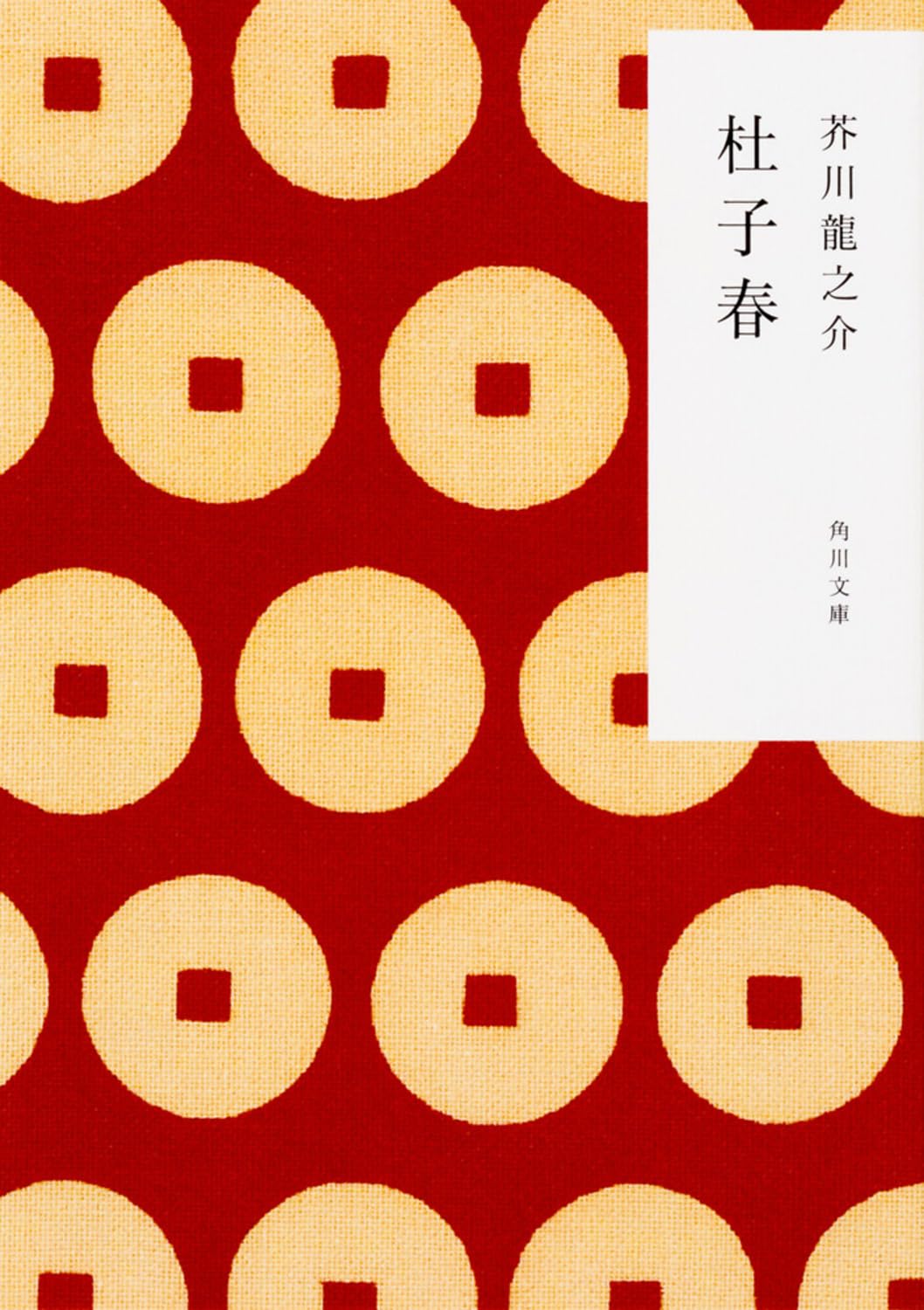
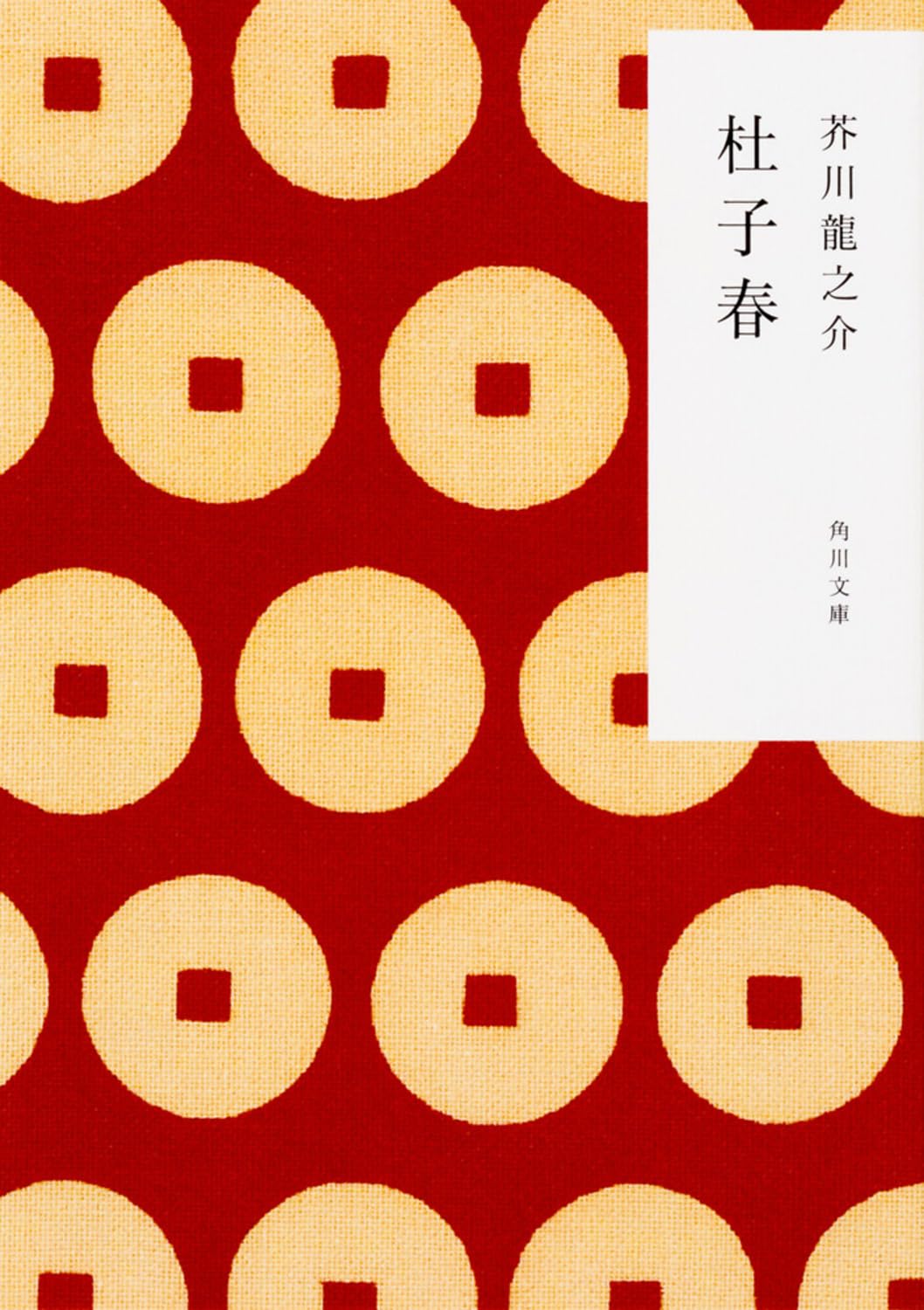
『蜘蛛の糸』と並ぶ芥川の童話の代表作が、中国の古典を題材にした『杜子春』です。お金や人間関係に翻弄される青年の姿を通して、本当の幸せとは何かを問いかけます。
物語の主人公は、財産を使い果たし途方に暮れていた若者・杜子春。彼は鉄冠子という仙人の力で二度も大金持ちになりますが、そのたびに贅沢三昧の末に無一文となり、人々が離れていくという経験をします。
人間の薄情さに嫌気がさした杜子春は、仙人になることを決意。しかし、地獄で苦しむ母親の姿を前にして、仙人になるための「決して声を出さない」という試練を破ってしまいます。結果的に仙人にはなれませんでしたが、その人間らしい心根を仙人に認められ、ささやかでも正直な暮らしを手に入れるのでした。



お金があっても心が満たされないって、現代にも通じる話だよね。最後は人間らしい幸せを選んだ杜子春にホッとしたよ。
4位: 『鼻』
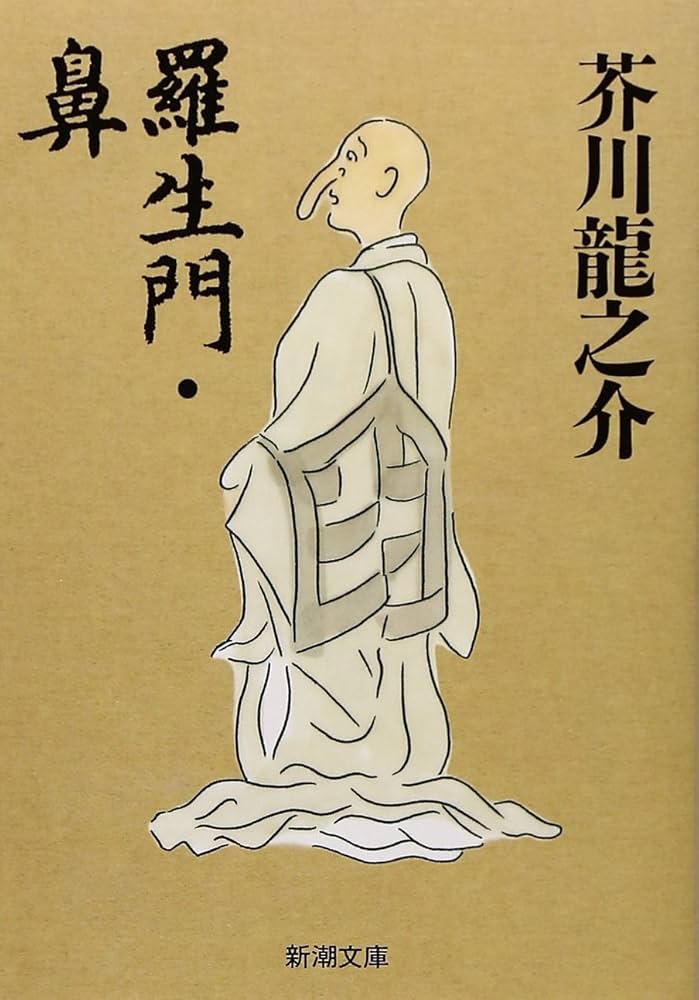
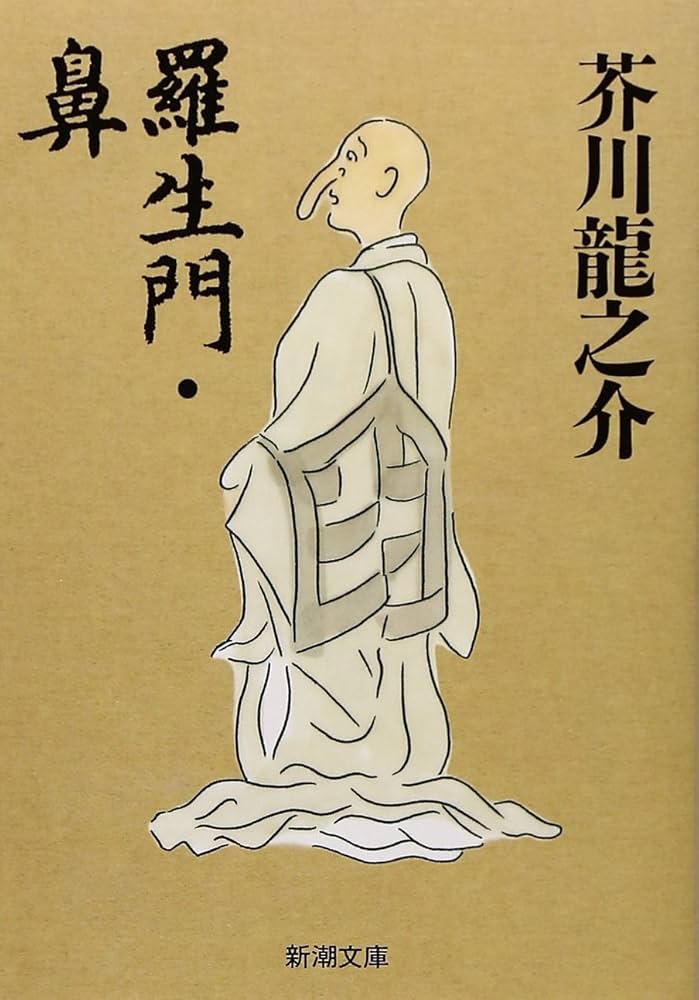
『鼻』は、文豪・夏目漱石に絶賛され、芥川龍之介が文壇で認められるきっかけとなった記念碑的な作品です。『今昔物語集』などを題材にしており、人間の自尊心や他人の不幸を喜ぶ心理をコミカルに描いています。
主人公は、池の尾の禅智内供という高僧。彼は顎の下まで垂れ下がる立派な鼻を持っていることに、長年悩んでいました。ある日、弟子から教わった方法で鼻を短くすることに成功し、内供は満ち足りた気持ちになります。
しかし、短くなった鼻を見て人々はかえって笑うようになり、内供は再び惨めな気持ちに。コンプレックスが解消されても、結局は他人の評価に振り回されてしまう人間の滑稽さが、見事に描き出されています。芥川の人間観察の鋭さが光る一作です。



周りの目を気にしすぎる気持ち、わたしもわかるなあ。鼻が元に戻って安心する内供の姿が、なんだか愛おしいね。
5位: 『藪の中』
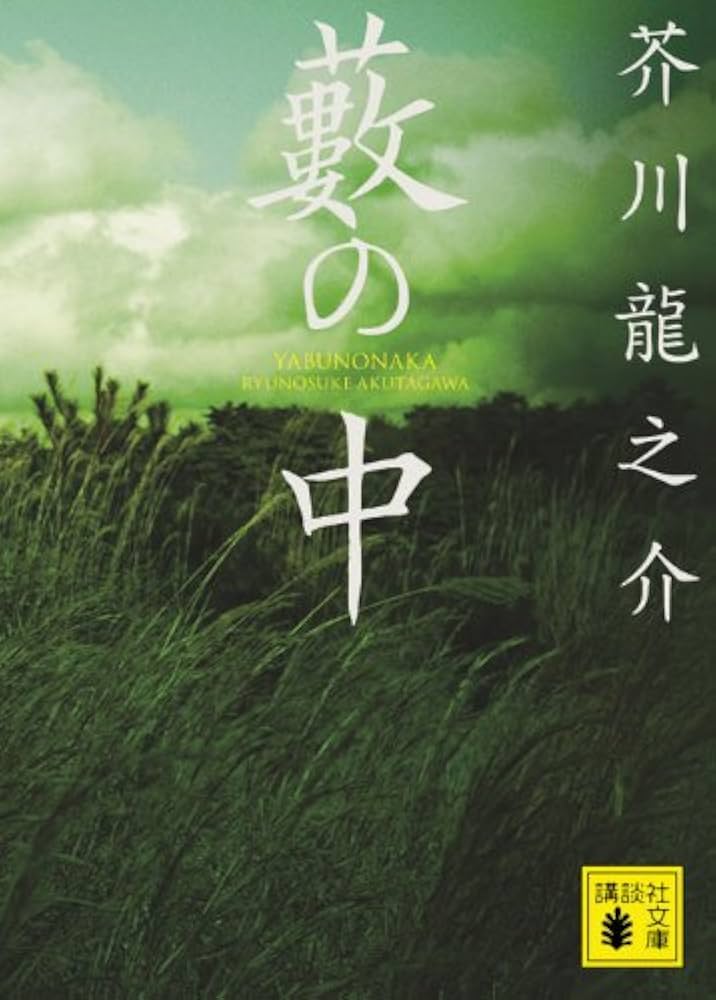
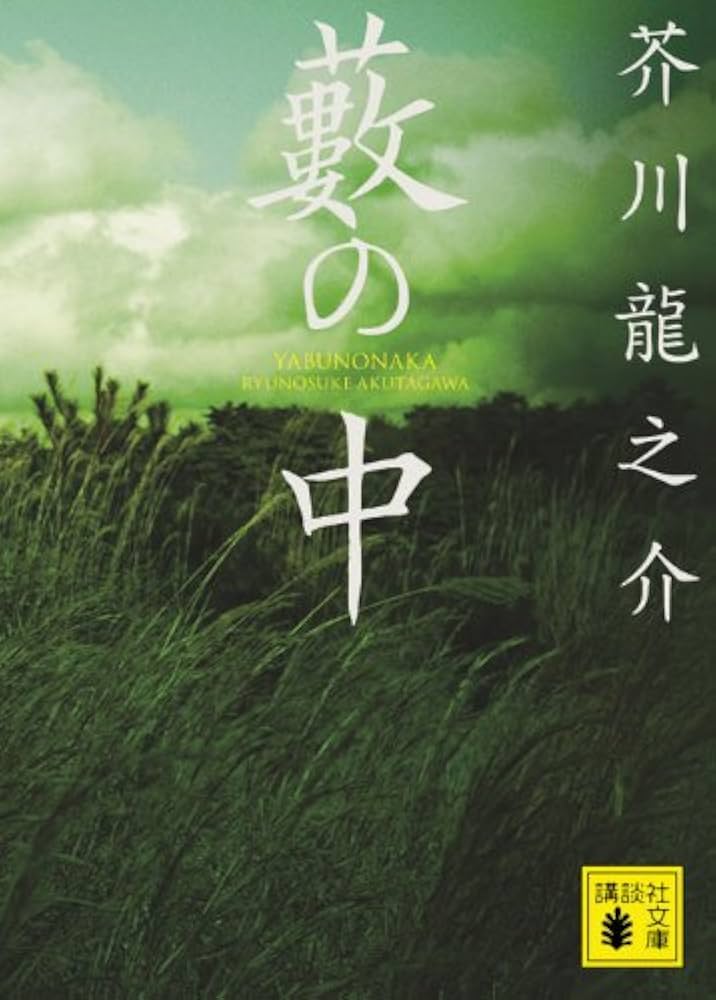
一つの事件をめぐり、関係者の証言が食い違い、真相が謎に包まれていく…。芥川龍之介の『藪の中』は、そんな斬新な構成で読者を引き込むミステリー仕立ての短編です。この作品は黒澤明監督の映画『羅生門』の原作の一つとしても世界的に知られています。
物語は、ある藪の中で武士の死体が見つかるところから始まります。容疑者である盗賊、殺された武士の妻、そして霊媒師の口を通して語られる武士の霊、それぞれの言い分が食い違い、誰が真実を語っているのか分からなくなります。
人間の証言がいかに曖昧で、自己保身や主観によって歪められるかを鋭く描き出しています。読者はまるで裁判員のように、誰の言葉を信じるべきか、究極の選択を迫られることになるでしょう。



みんな言ってることが違うなんて、一体何が本当なの!?真相がわからないまま終わるから、モヤモヤするけど引き込まれちゃうよ。
6位: 『河童』
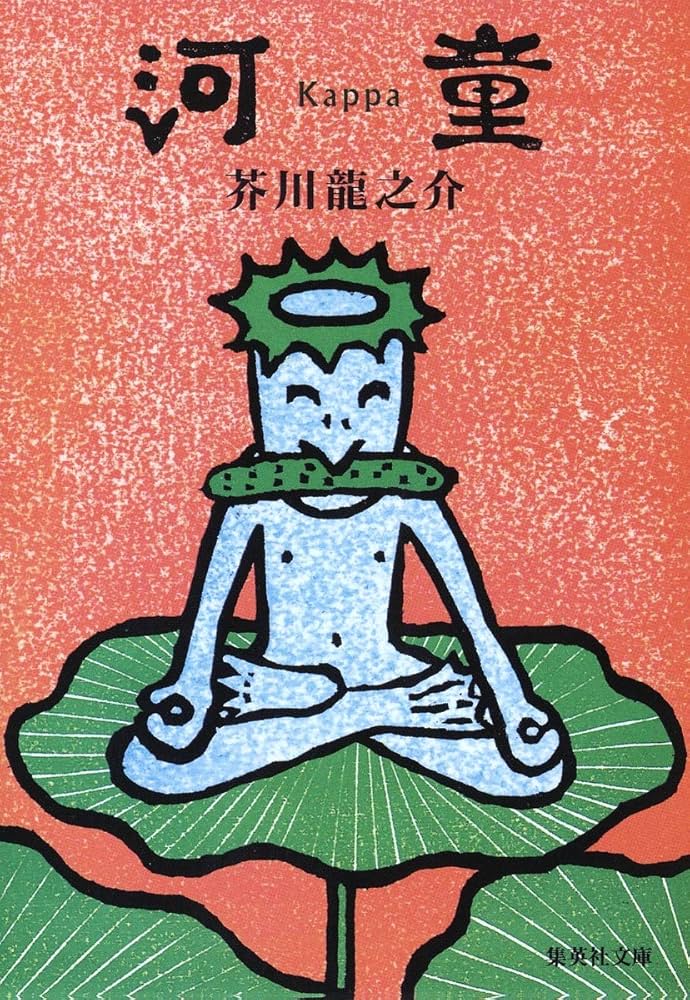
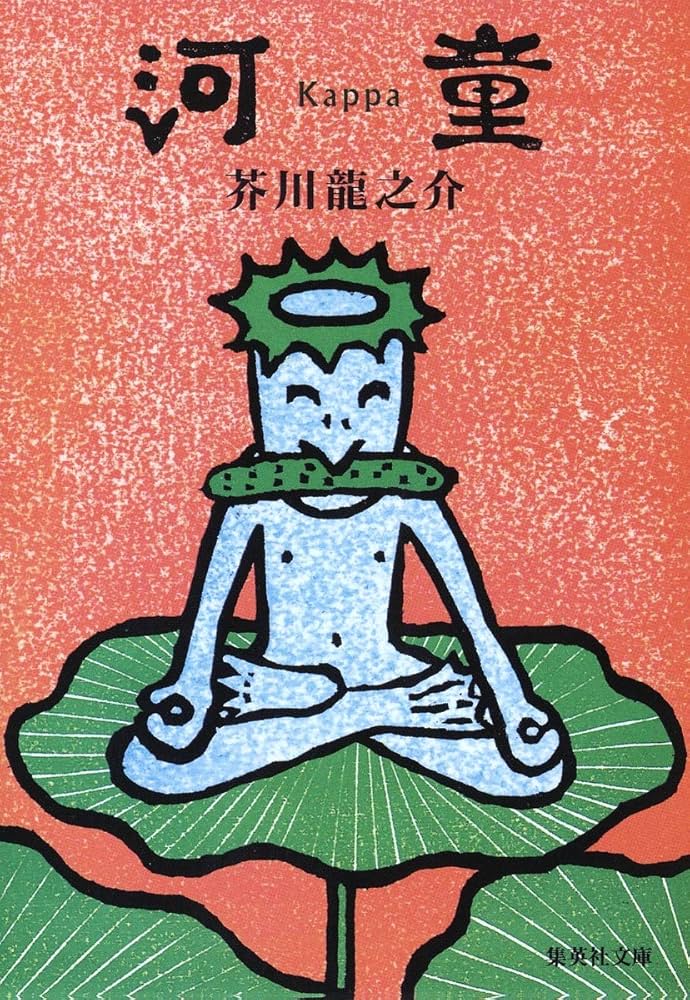
芥川龍之介の晩年の代表作であり、社会風刺の傑作として名高いのが『河童』です。精神病院の患者が語るという体裁で、河童の国での体験を描いています。
主人公は、登山中に河童に出会い、彼らの国に迷い込みます。河童の社会は、一見すると人間社会よりも合理的に見えますが、そこには奇妙な習慣や制度が存在します。例えば、生まれる前の赤ん坊に生まれたいかどうかを尋ねる「出生の意志確認」や、失業した河童を食肉として処分する制度などです。
これらの風習を通して、芥川は人間社会の偽善や矛盾を痛烈に批判しました。ユーモラスでありながらも、その裏に潜む狂気や絶望が読者に強烈な印象を残す作品です。芥川の命日である7月24日が「河童忌」と呼ばれるのは、この作品に由来します。



河童の国のルール、ちょっと怖いけど面白いね!これって、わたしたちの世界の変なところを映してるのかも…。
7位: 『地獄変』
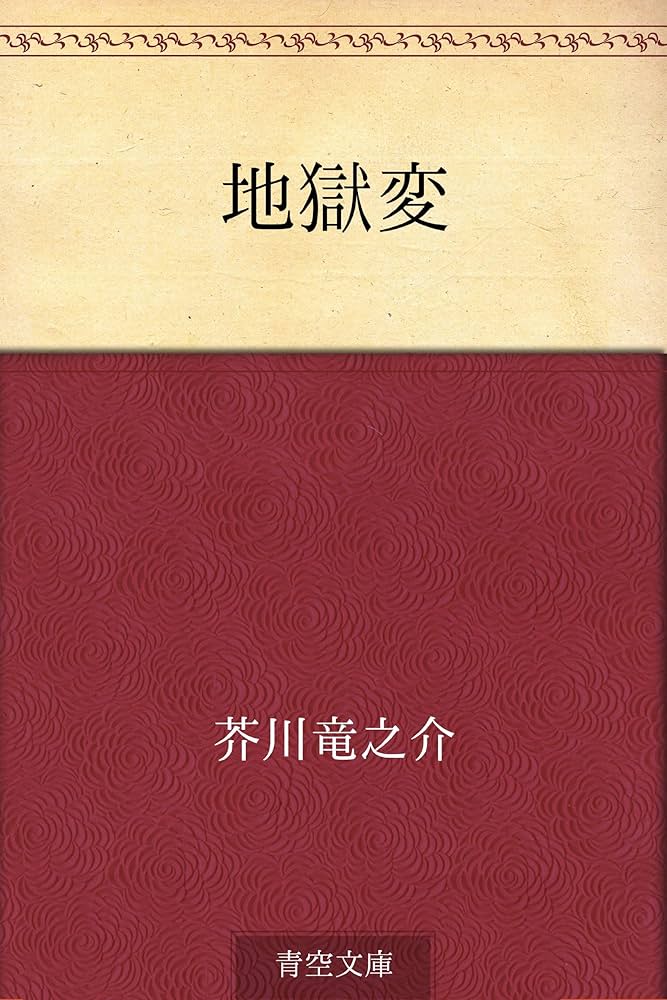
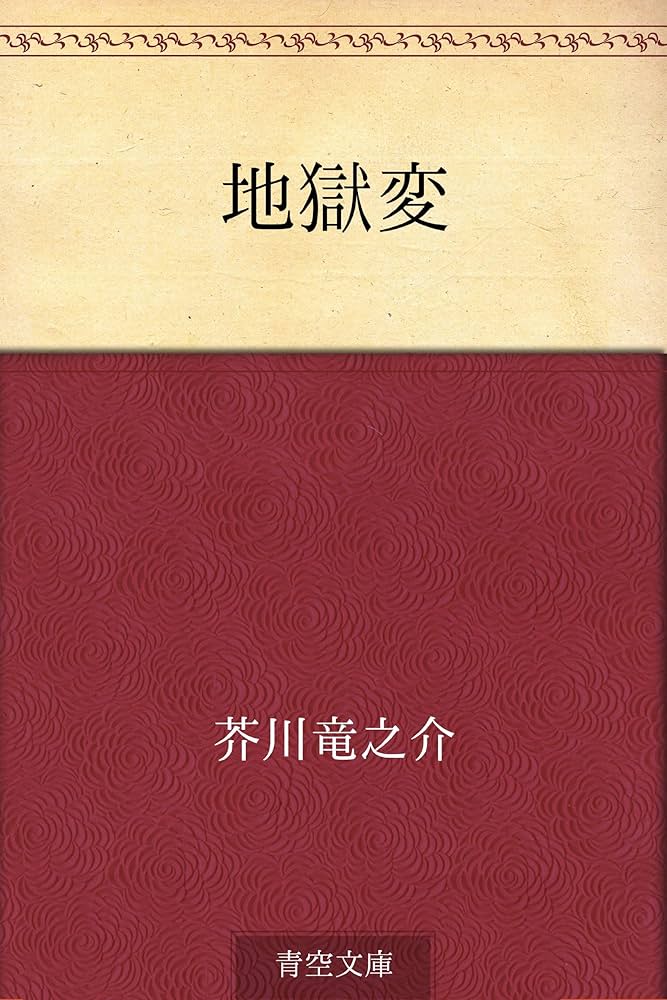
芸術のためなら悪魔に魂を売ることも厭わない、一人の絵師の狂気を描いた『地獄変』。芥川龍之介の王朝ものの中でも、特に傑作と名高い作品です。
物語の主人公は、当代一の絵師と評判の良秀。彼は横柄な大殿から「地獄変」の屏風絵を描くよう命じられます。良秀はリアルな地獄を描くため、弟子を鎖で縛ったり、鳥に襲わせたりと、常軌を逸した行動を繰り返します。
そして、絵の仕上げとして、炎に焼かれる豪華な檳榔毛車(びろうげのくるま)と、その中で苦しむ美しい女房を描きたいと大殿に申し出ます。大殿はこれを承諾しますが、車に乗せたのは良秀が溺愛する一人娘でした。芸術至上主義の極致と、その果てにある悲劇を壮絶に描いた物語は、読む者に戦慄と感動を与えます。



本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。
8位: 『蜜柑』
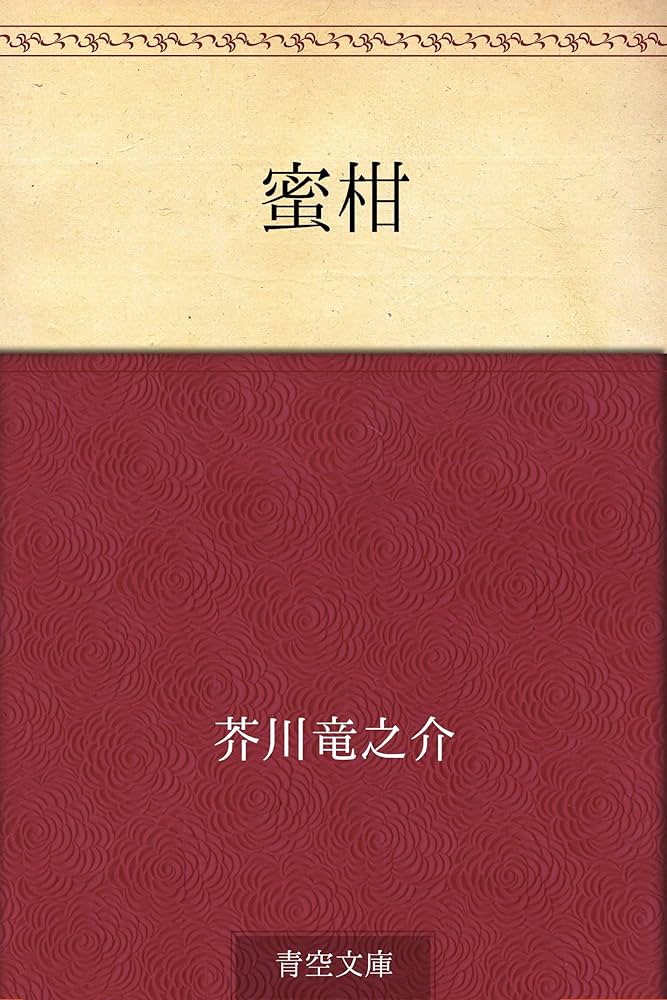
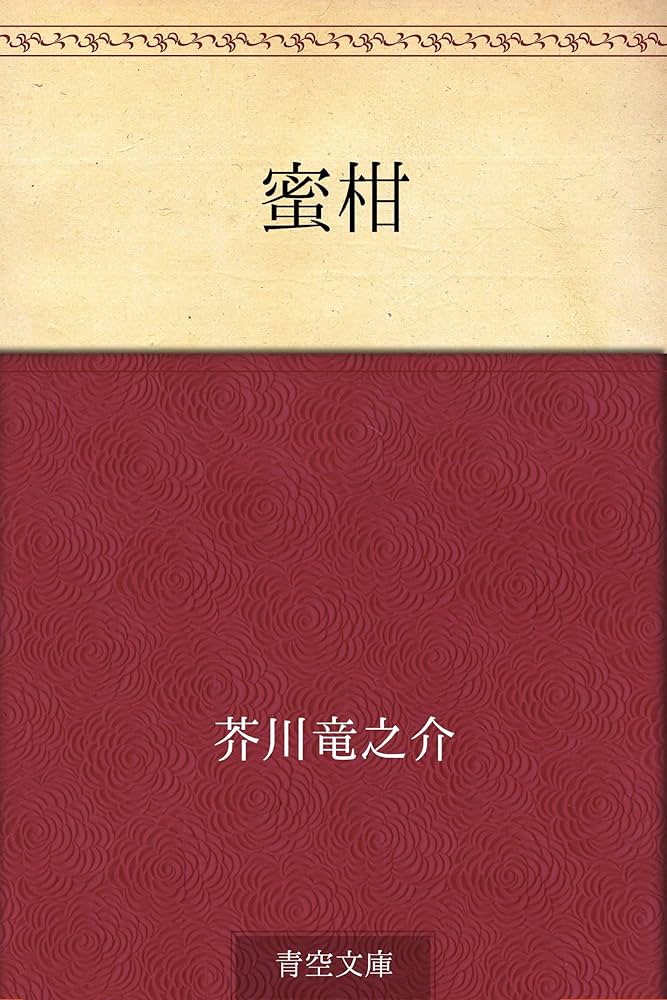
『蜜柑』は、わずか数ページの短い物語の中に、人間の温かい心情を描き出した珠玉の短編です。汽車の中での出来事を描いた、芥川自身の体験が元になっていると言われています。
曇天の夕暮れ、横須賀発の汽車に乗り込んだ主人公の「私」は、言いようのない疲労と倦怠を感じていました。そこへ、田舎者の少女が一人、慌ただしく乗り込んできます。彼女の汚い身なりや行儀の悪さに、「私」は不快感を覚えます。
しかし、汽車がトンネルにさしかかろうとした時、少女が窓から身を乗り出し、線路脇で見送る弟たちに向かって、懐から取り出した蜜柑を投げ与える光景を目にします。そのささやかな愛情表現に触れた瞬間、「私」の憂鬱な心は晴れやかになり、生きる喜びを取り戻すのでした。心温まる読後感が魅力の一作です。



最後の蜜柑のシーン、映像が目に浮かぶようだよ!ささやかな優しさが人の心を救うんだなって、すごく感動しちゃった。
9位: 『トロッコ』
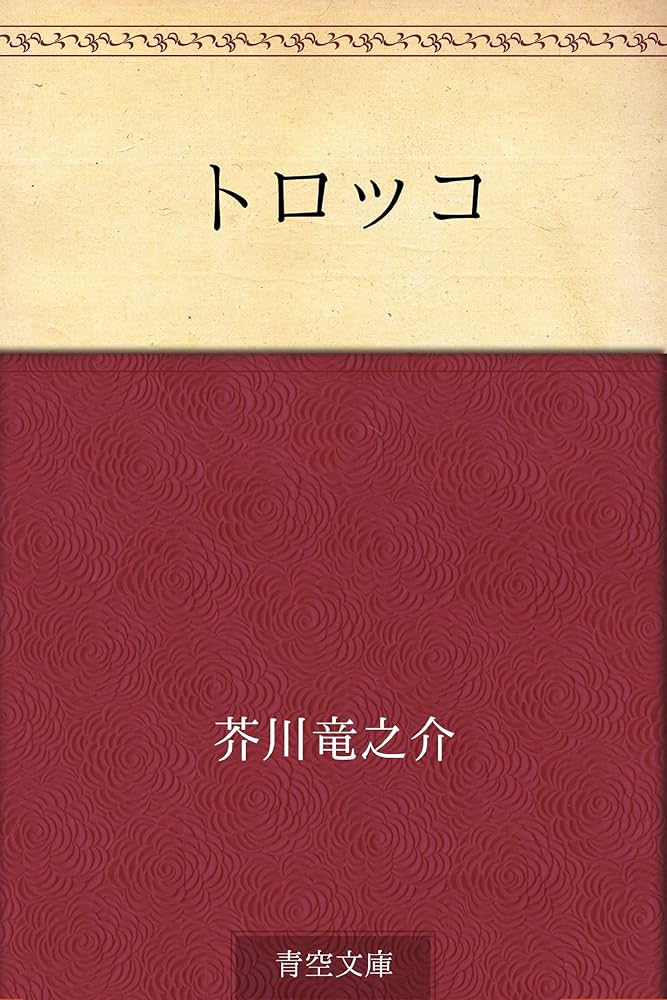
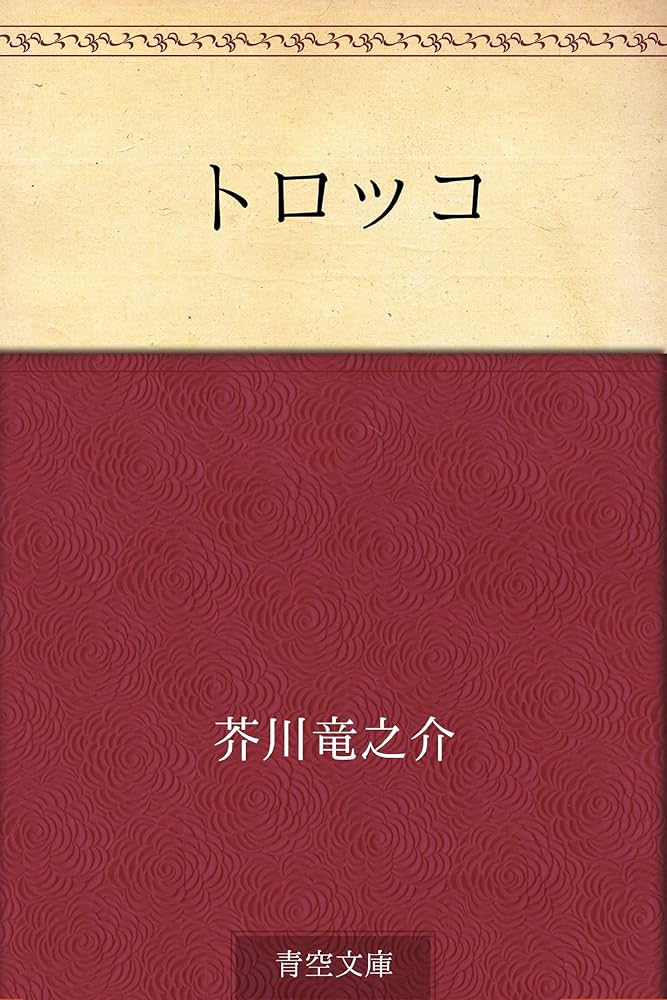
誰の心にもある、幼い頃の冒険心と、その後に訪れる現実の厳しさ。『トロッコ』は、そんなノスタルジックな感傷と人生のほろ苦さを描いた短編小説です。
物語の主人公は、8歳の少年・良平。彼は村はずれの工事場で、土砂を運ぶトロッコを見つけ、それに乗ってみたいと強く願うようになります。ある日、良平は土工に頼み込み、念願のトロッコに乗せてもらうことに。最初は高揚感でいっぱいでしたが、トロッコがどんどん遠くまで進むにつれて、次第に不安と恐怖に襲われます。
帰り道、暗い夜道を一人で必死に走る良平の姿は、大人になる過程で誰もが経験する、理想と現実のギャップや人生の厳しさを象徴しているかのようです。大人になってからこの作品を読み返すと、また違った感慨が湧き上がってくるでしょう。



トロッコに乗れた嬉しさと、帰れなくなる不安な気持ちがすごく伝わってくる…。良平が泣きながら走るシーンは、胸が締め付けられるね。
10位: 『歯車』
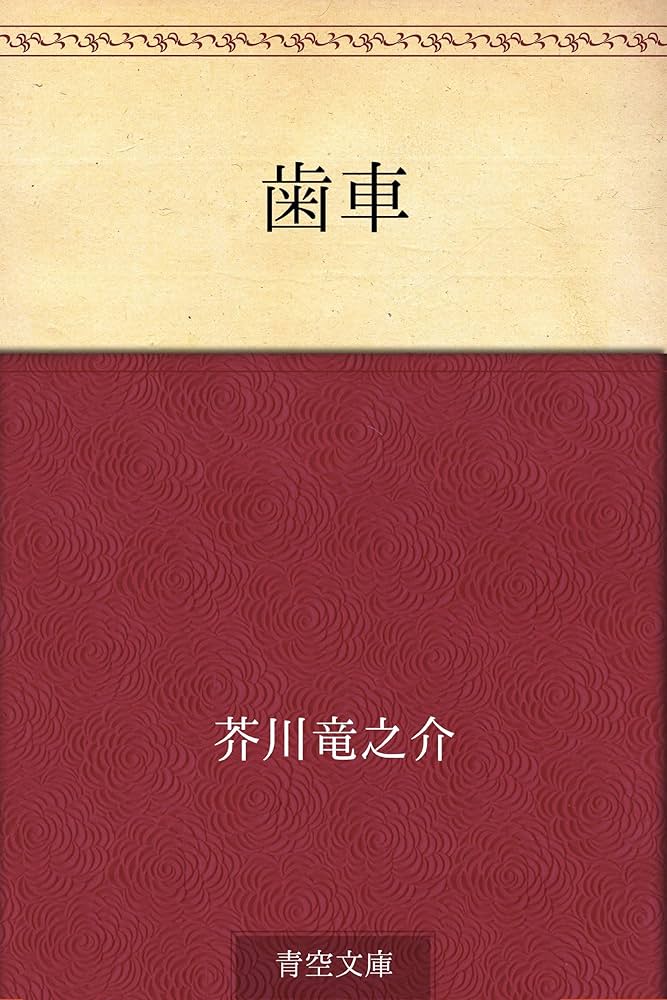
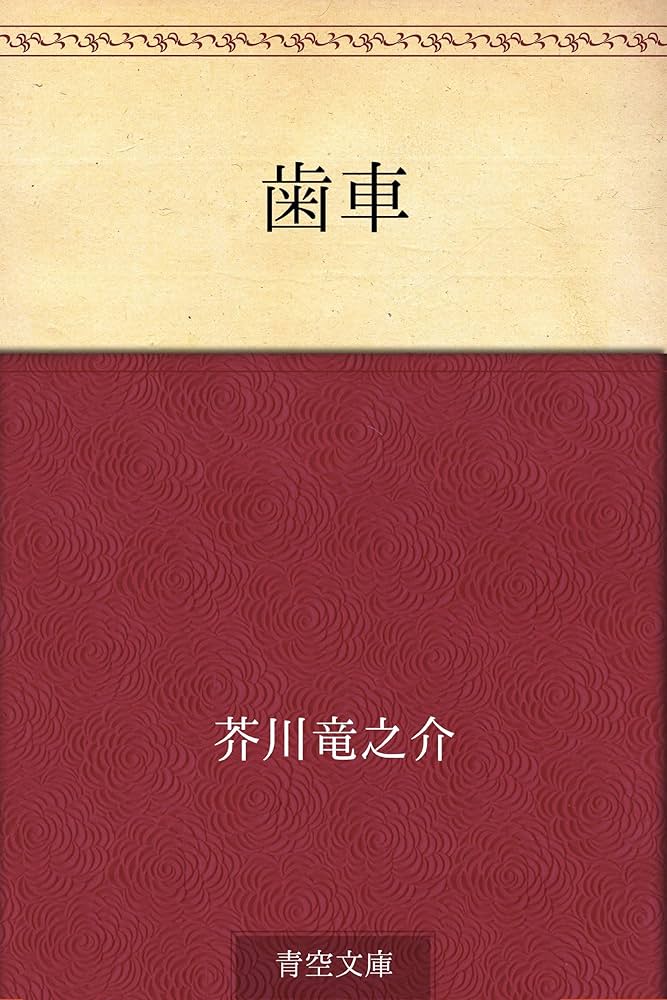
芥川龍之介が自ら命を絶つ直前に執筆された遺作の一つが『歯車』です。彼の晩年の精神状態が色濃く反映された私小説であり、その鬼気迫る内容で知られています。
物語は、主人公「僕」の身の回りで起こる不可解な出来事を描いています。彼の目には、現実の風景に混じって、半透明の歯車が回転する幻覚が見えるようになります。レインコートを着た幽霊のような男の出現や、次々と起こる不吉な偶然の一致。これらの幻覚や妄想によって、「僕」の精神は次第に追い詰められていきます。
芥川自身の死に至るまでの苦悩や恐怖が生々しく綴られており、読者は彼の内面世界を追体験するような感覚に陥ります。文学史的にも非常に重要な作品ですが、読む際には相応の覚悟が必要かもしれません。



本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。
11位: 『或阿呆の一生』
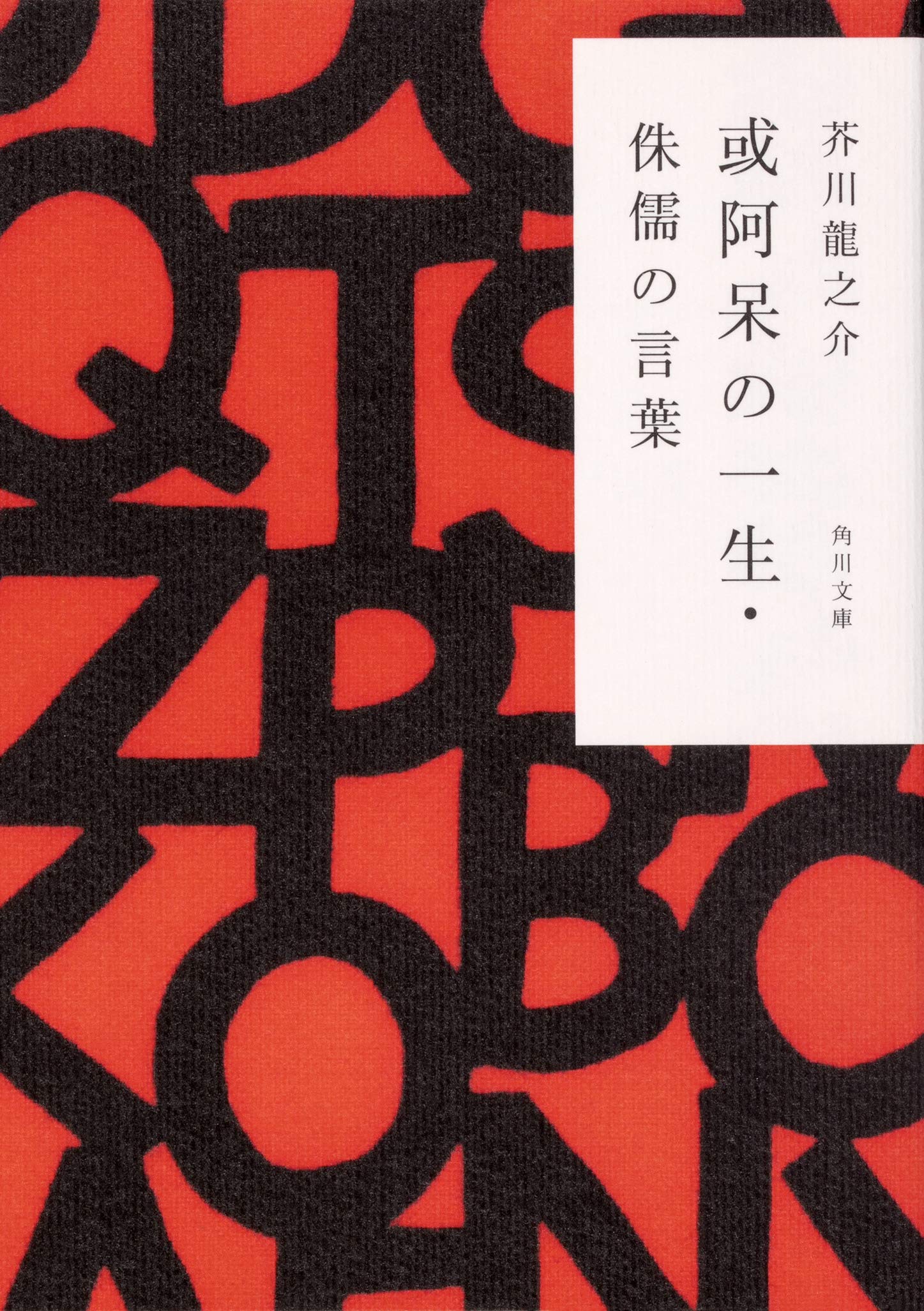
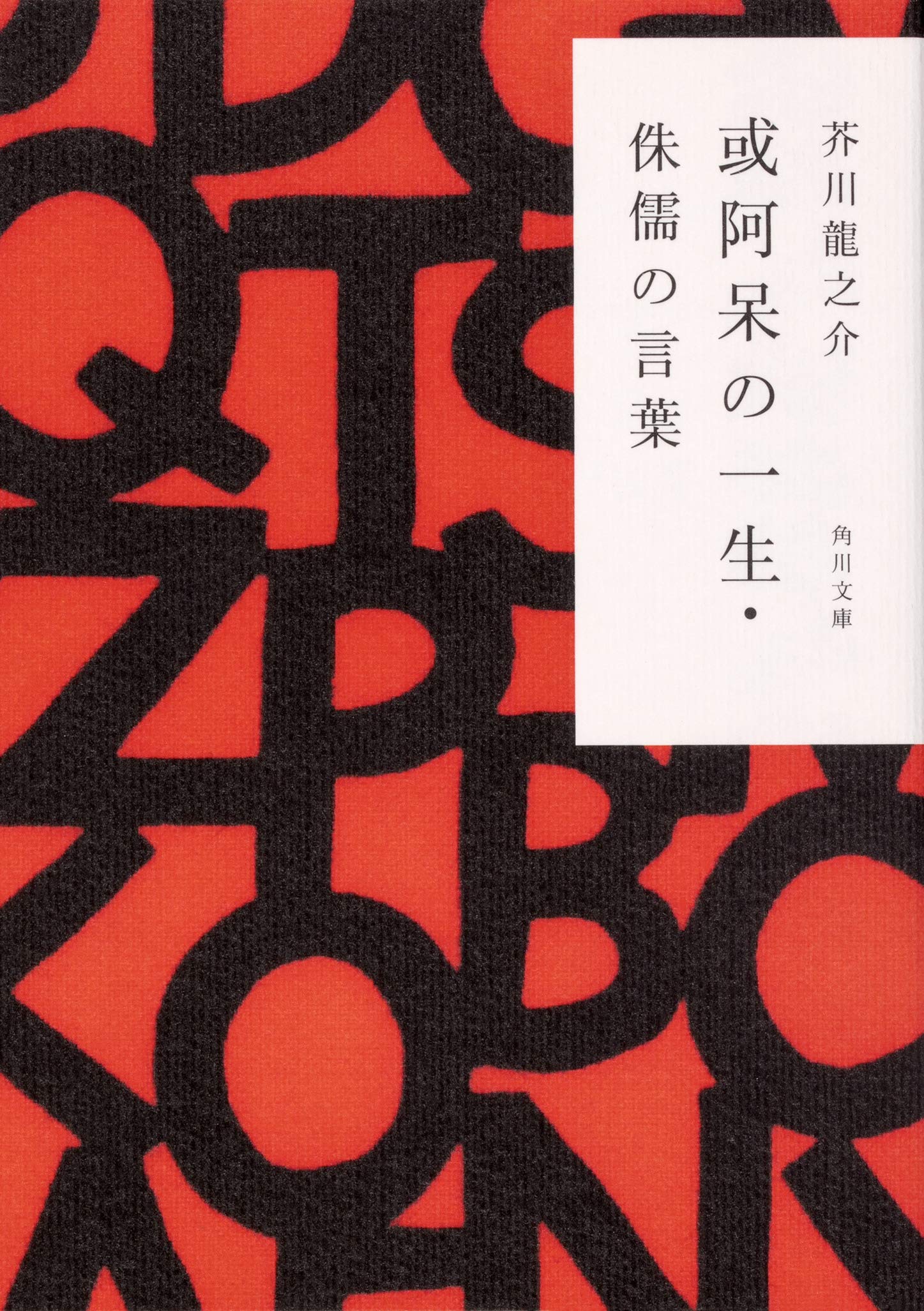
『歯車』と並び、芥川龍之介の死後に発表された遺作が『或阿呆の一生』です。この作品は、51の断章形式で構成されており、主人公である「彼」の半生を自伝的に描いています。
「時代」「母」「家」といった短いタイトルが付けられた各章には、彼の幼少期の記憶、文学への情熱、恋愛、そして精神的な苦悩が断片的に綴られています。これらの断片をつなぎ合わせることで、読者は「彼」=芥川龍之介の人生の軌跡をたどることができます。
人生の光と影、美しさと残酷さが、詩的かつ象徴的な文章で凝縮されています。芥川が人生の最後に見た風景とはどのようなものだったのか。彼の魂の告白ともいえるこの作品は、読む者の心に深く突き刺さります。



短い文章の一つ一つが、すごく重くて切ないね…。彼の人生が走馬灯みたいで、涙が出そうになっちゃった。
12位: 『芋粥』
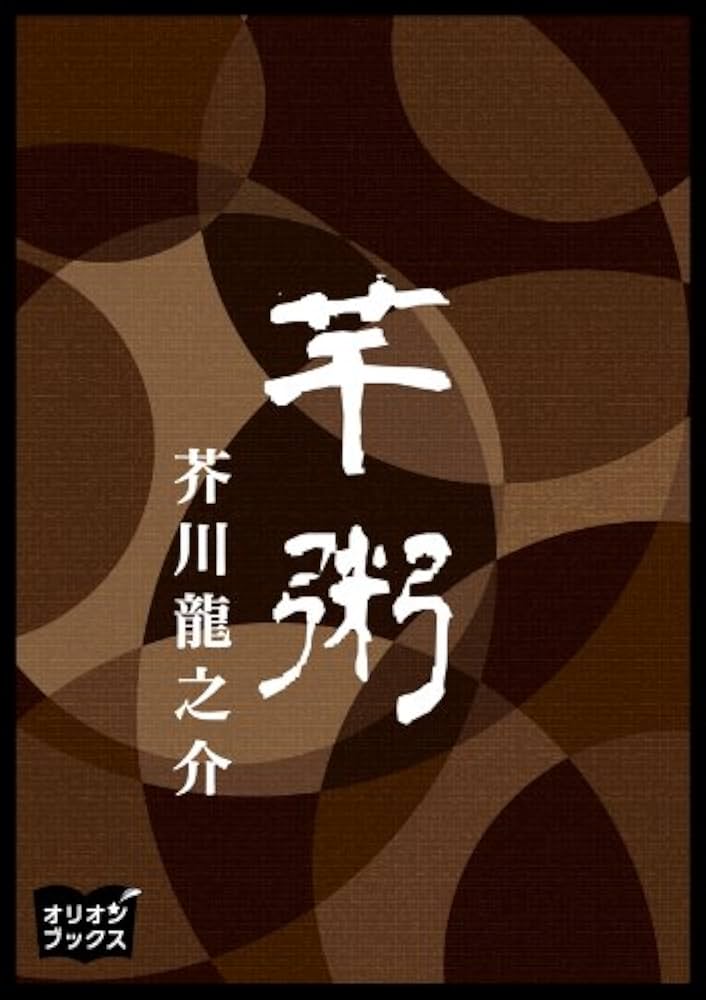
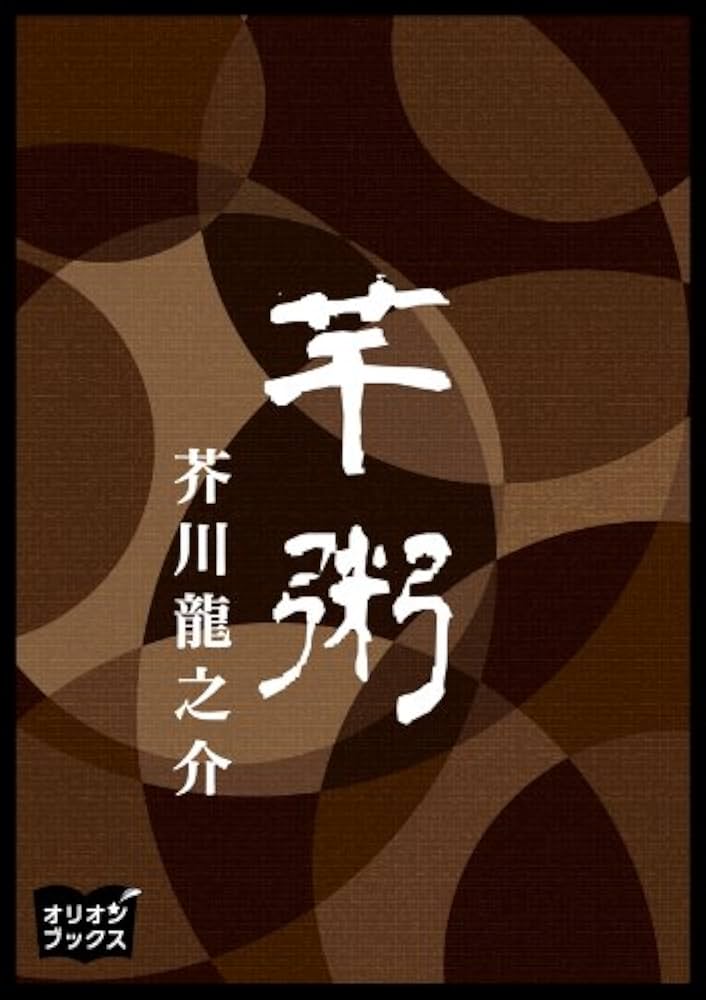
『芋粥』は、『鼻』と同じく『今昔物語集』の説話を題材にした、芥川初期の王朝ものです。平凡な男のささやかな夢と、その夢が叶った時の意外な結末をユーモラスに描いています。
主人公は、うだつの上がらない下級役人である五位。彼の唯一の夢は、甘くて美味しい「芋粥」を飽きるほど食べることでした。ある日、その夢を知った豪族の藤原利仁が、五位を自分の屋敷に招き、おびただしい量の芋粥を振る舞います。
しかし、あれほど焦がれていた芋粥を目の前にして、五位はすっかり食欲を失ってしまうのでした。憧れが現実になった瞬間に色褪せてしまうという、人間の心理を巧みに描いた作品です。理想と現実のギャップに悩んだことのある人なら、きっと共感できる部分があるでしょう。



夢が叶うって、必ずしも幸せなことじゃないんだね。芋粥を前に固まっちゃう五位の気持ち、なんだかわかる気がするよ。
13位: 『奉教人の死』
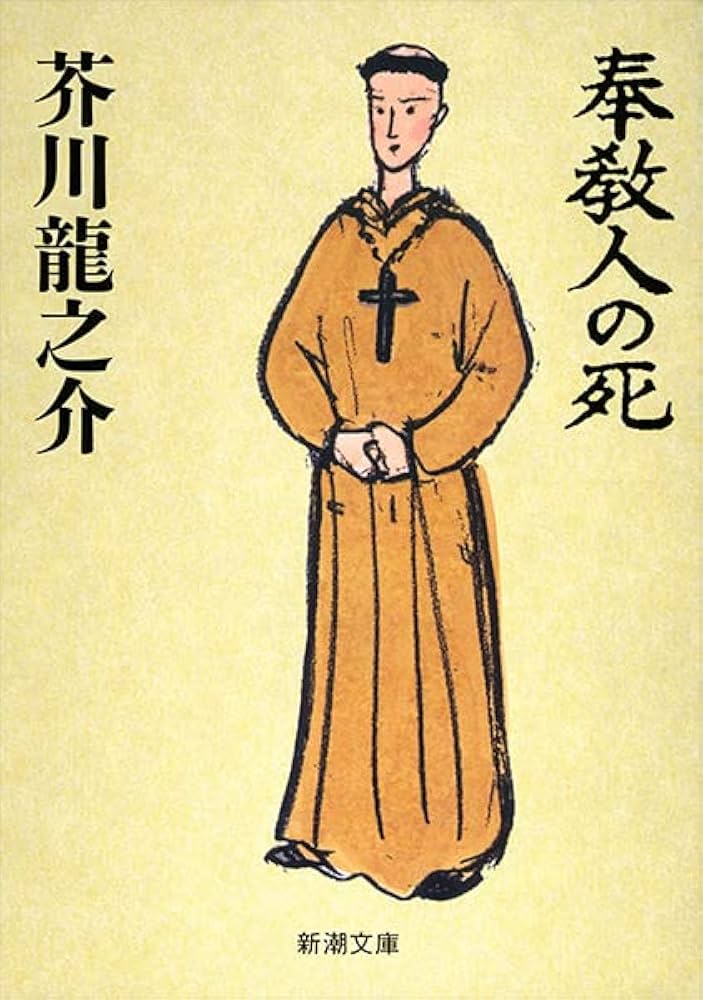
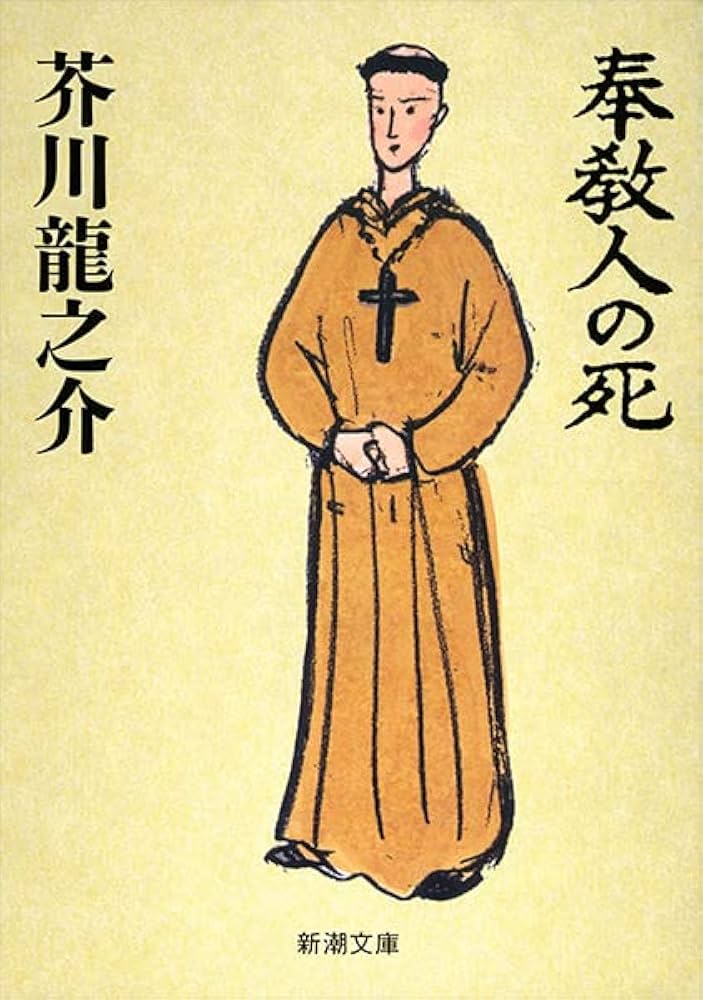
『奉教人の死』は、キリシタンの信仰をテーマにした、芥川の「切支丹物」と呼ばれるジャンルの代表作です。美しい娘を救うために殉教した、若きキリシタンの物語が、荘厳な筆致で描かれています。
物語の舞台は、キリシタンが弾圧されていた時代の長崎。若く信仰深い「ろおれんぞ」は、放蕩の限りを尽くした末に改心し、熱心な信者となりました。ある日、彼の住む家に火事が起こり、彼は家主の美しい娘を救うために炎の中へ飛び込みます。
しかし、娘を救い出した彼の姿は、奇跡の光に包まれていました。信仰の力、自己犠牲の尊さ、そして奇跡の瞬間が、感動的に描かれています。芥川の緻密な構成力と、格調高い文体が光る名作です。



ろおれんぞの信仰の強さに心を打たれたよ。最後の奇跡のシーンは、本当に美しくて神々しい感じがするね。
14位: 『戯作三昧』
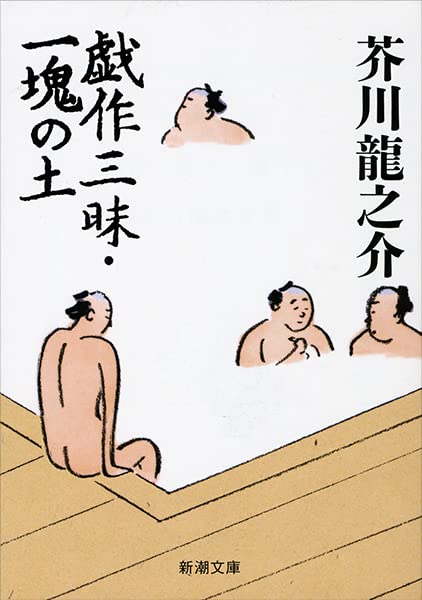
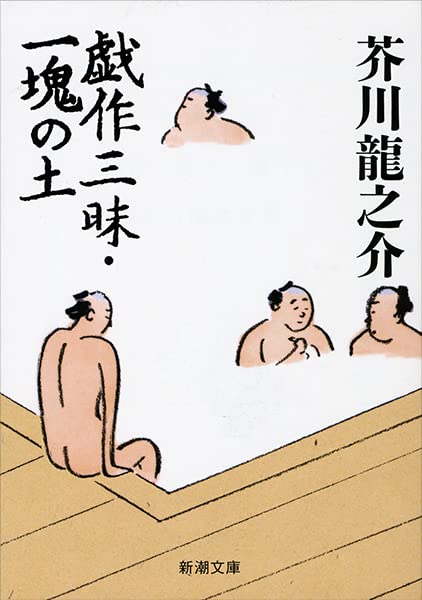
『戯作三昧』は、江戸時代の戯作者・滝沢馬琴を主人公にした、芸術家の苦悩と理想を描く物語です。芥川自身の芸術に対する姿勢が投影された作品とも言われています。
物語の主人公、馬琴は、大衆向けの娯楽小説(戯作)を書きながらも、その仕事に満足できず、真の芸術を追い求めていました。彼は世間の評価や生活の苦労から逃れ、ただひたすらに創作に没頭する「戯作三昧」の境地を理想としています。
ある雨の夜、馬琴は訪ねてきた友人に、自分の芸術的な苦悩を吐露します。芸術家として生きることの孤独や葛藤、そして創作への純粋な情熱が、馬琴の言葉を通して力強く描かれています。何かを生み出す仕事をしている人にとって、深く共感できる作品でしょう。



好きなことを仕事にするって、楽しいだけじゃないんだね。馬琴の創作にかける情熱と苦悩が、ひしひしと伝わってくるよ。
15位: 『偸盗』
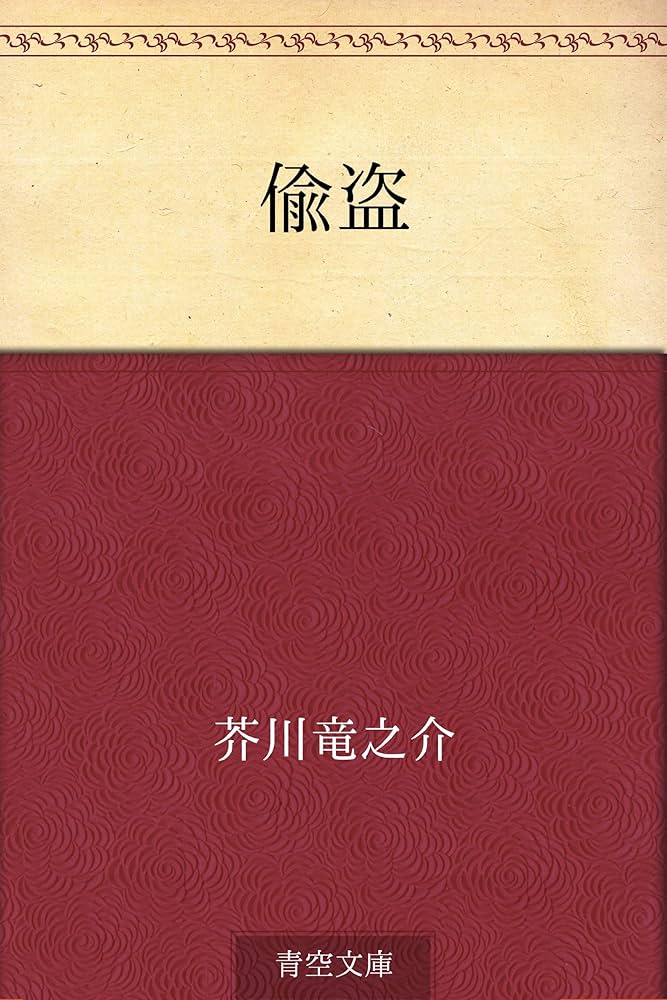
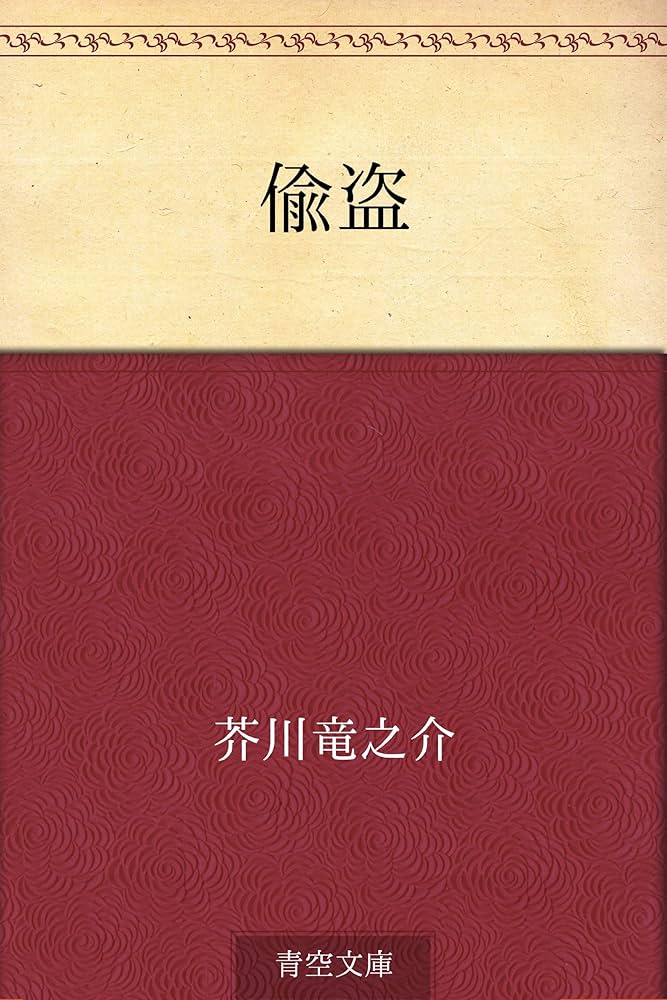
『偸盗』は、平安時代を舞台に、盗賊たちの生き様と運命をダイナミックに描いた物語です。『羅生門』や『藪の中』と同じく、『今昔物語集』に題材を得ています。
物語は、猪熊の邸に仕える活発な女・沙金と、彼女に思いを寄せる二人の男、太郎と次郎を中心に展開します。ある夜、屋敷が盗賊団に襲われ、沙金は盗賊の首領に連れ去られてしまいます。太郎と次郎は、沙金を救うため、そして自らも盗賊として生きるために、運命の渦に巻き込まれていきます。
愛憎、裏切り、そして破滅へと向かう人間たちのドラマが、スリリングに描かれています。芥川作品の中でも、特にエンターテインメント性の高い一作と言えるでしょう。登場人物たちの激しい生き様に、きっと引き込まれるはずです。



盗賊たちの世界、ハラハラドキドキしたよ!沙金をめぐる太郎と次郎の運命がどうなるのか、最後まで目が離せなかったな。
16位: 『侏儒の言葉』
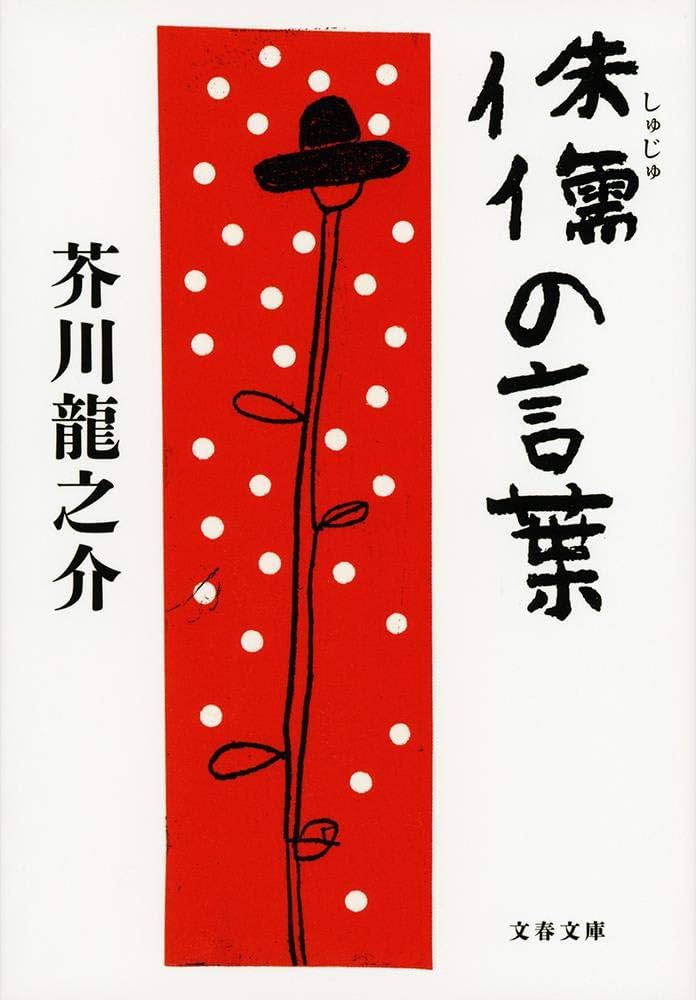
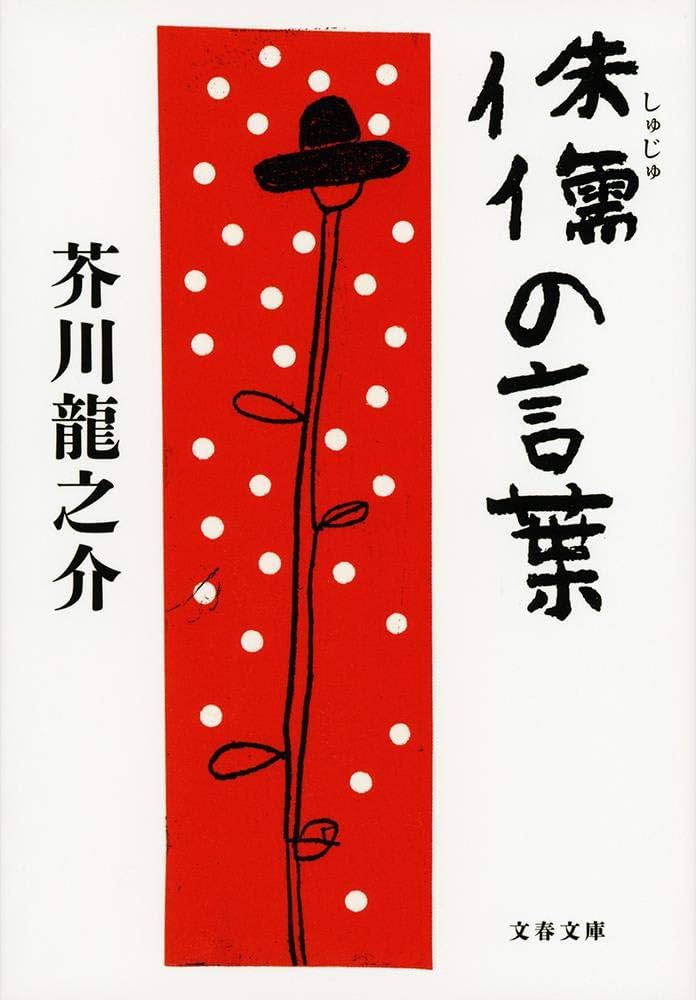
『侏儒の言葉』は、小説ではなく、芥川龍之介の思想や人生観が凝縮されたアフォリズム(警句)集です。侏儒、つまり小人が語るという形式で、様々なテーマについての短い言葉が綴られています。
「人生は一箱のマッチに似ている」「最も利口な処世術は、時代を憎むことであると同時に、時代に順応することである」など、鋭い洞察力と皮肉、そしてユーモアに満ちた言葉の数々は、現代を生きる私たちにも多くの示唆を与えてくれます。
小説とは一味違った形で、芥川の知性に触れることができる一冊です。短い言葉で構成されているため、どこからでも気軽に読むことができ、日々の生活の中でふとした瞬間に読み返したくなる魅力があります。



短い言葉なのに、すごくドキッとする内容ばかりだね。芥川さんの頭の中を覗いているみたいで、面白かったよ。
17位: 『桃太郎』
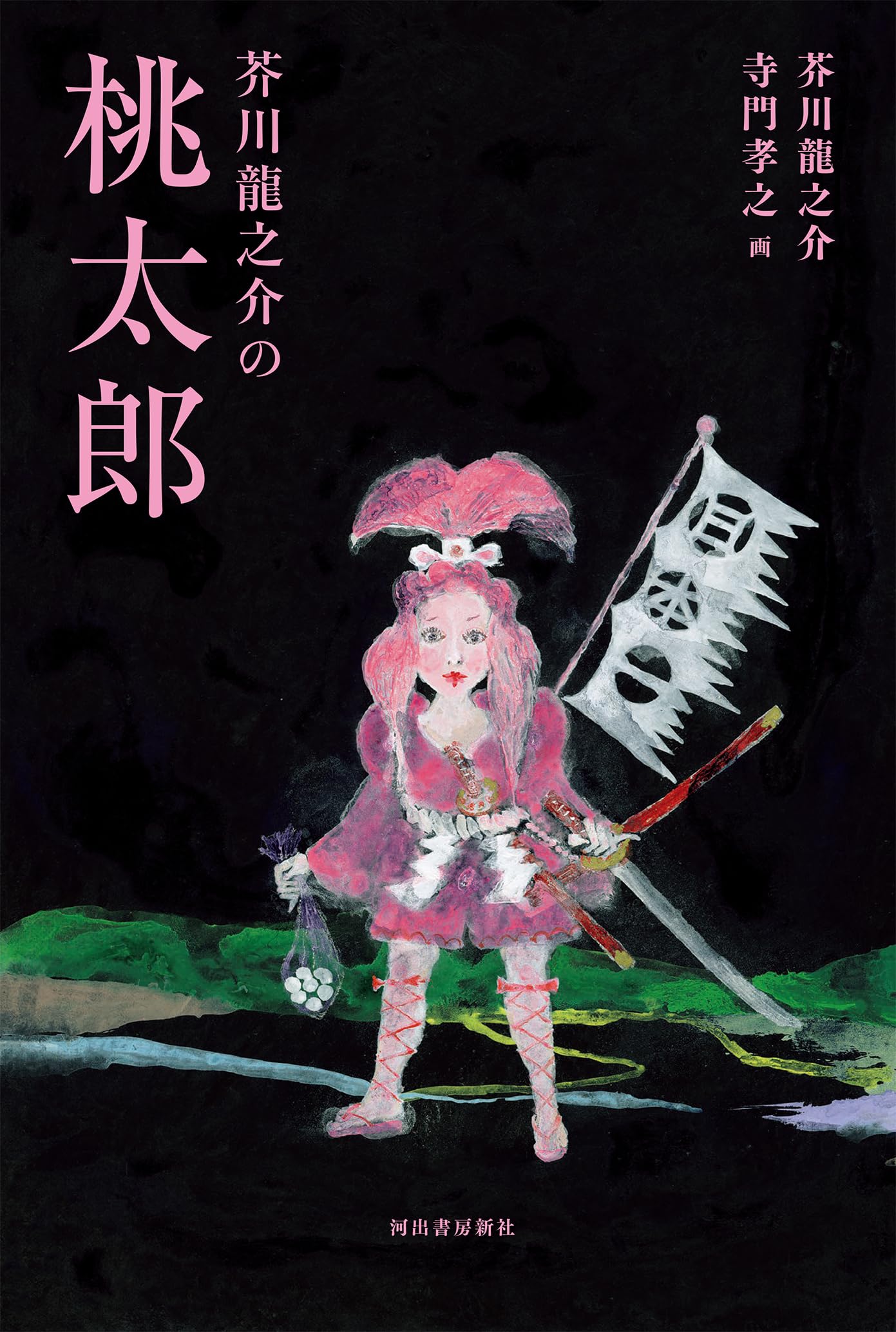
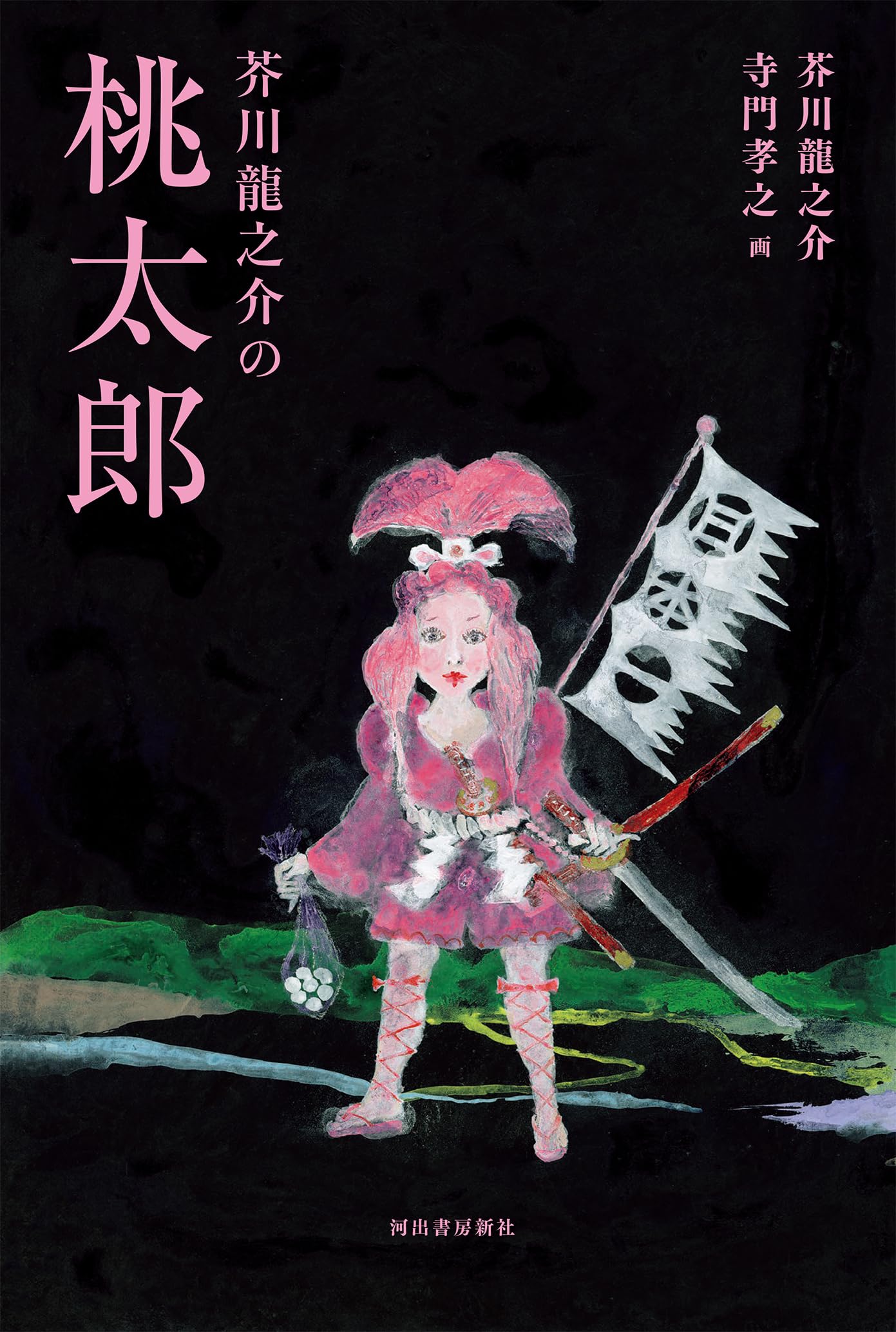
誰もが知っている昔話「桃太郎」を、芥川龍之介が独自の視点で再構築したのが、この短編小説『桃太郎』です。痛烈な風刺と皮肉が効いた、大人向けの寓話となっています。
物語は、桃太郎の不思議な出生から鬼ヶ島征伐、そしてその後の顛末までを描いています。鬼から奪った宝物を持ち帰り、英雄となった桃太郎ですが、その後の彼はどうなったのでしょうか。芥川の描く桃太郎は、決して正義の味方ではありません。鬼たちの平和な暮らしを侵略し、宝物を奪った侵略者として描かれています。
正義とは何か、英雄とは何か、という問いを、ユーモラスかつ痛烈に投げかけます。物事を多角的に見ることの重要性に気づかせてくれる、示唆に富んだ作品です。



わたしたちが知ってる桃太郎と全然違うね!鬼の視点だと、桃太郎はただの侵略者なんだなって、考えさせられちゃったよ。
18位: 『舞踏会』
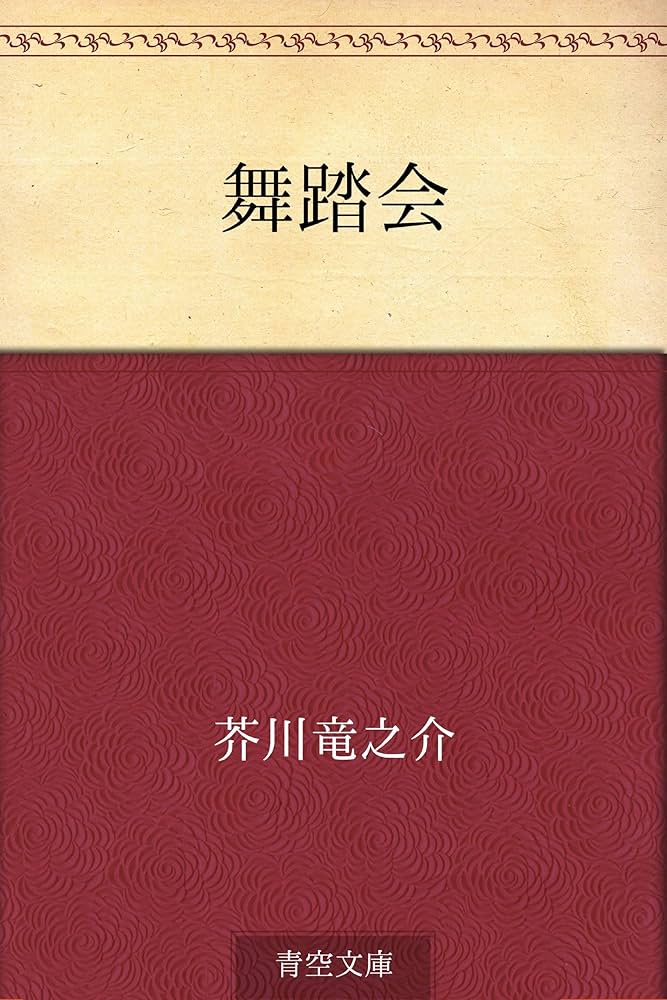
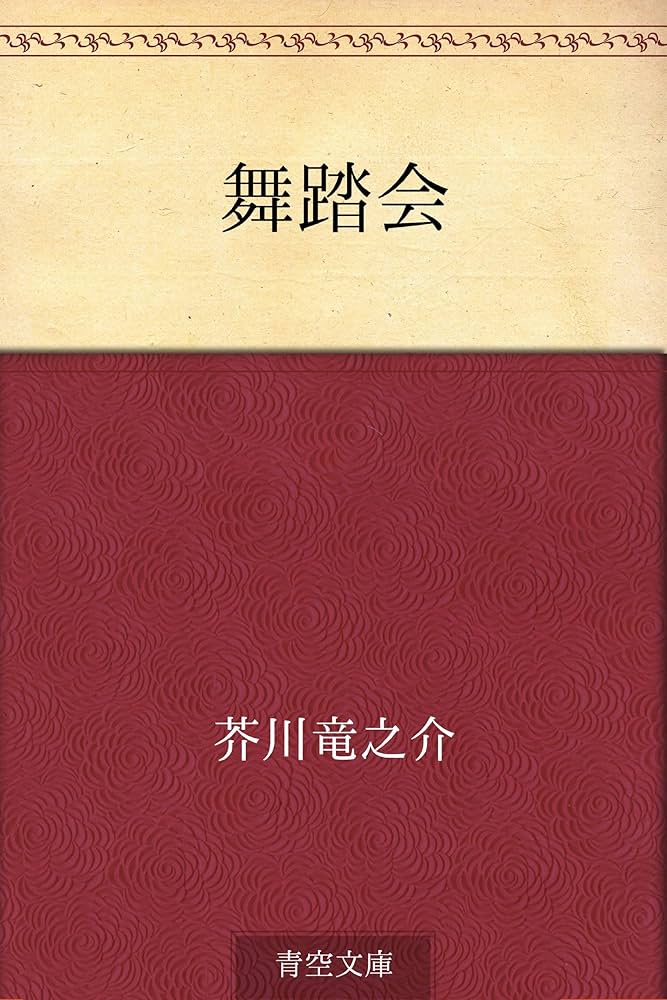
『舞踏会』は、明治時代の鹿鳴館で開かれた舞踏会を舞台にした、ロマンチックで美しい短編小説です。フランス人将校の回想という形で、日本の少女との淡い出会いを描いています。
物語の語り手であるフランス海軍士官(ピエール・ロティがモデル)は、17歳の日本の少女、明子と舞踏会で出会います。彼は、西洋の文化に臆することなく、凛とした態度で振る舞う明子の美しさに心惹かれます。
二人は言葉を交わし、共に踊りますが、それは一夜限りの儚い出会いでした。文明開化期の華やかな雰囲気と、少女のはかなくも美しい姿が、洗練された文章で描かれています。まるで一編の美しい絵画を眺めているような、優雅な読書体験が味わえるでしょう。



鹿鳴館の舞踏会、すごく華やかで素敵だね!明子さんとフランス人将校の出会いがロマンチックで、うっとりしちゃったよ。
19位: 『将軍』
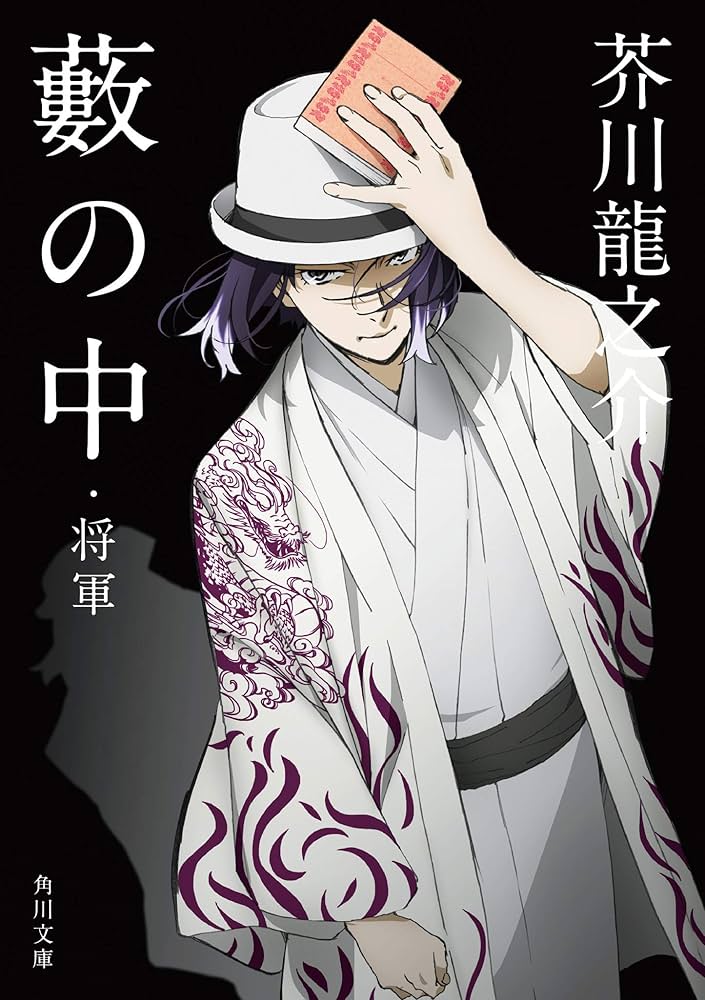
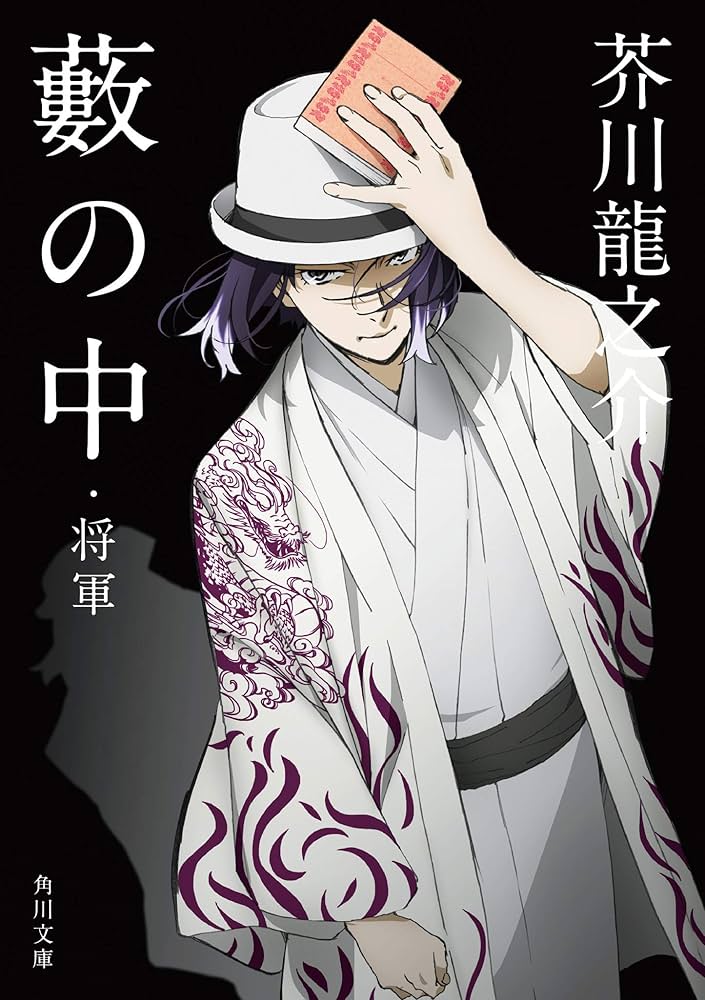
『将軍』は、日露戦争で活躍した乃木希典将軍をモデルに、英雄崇拝の虚しさを描いた風刺的な作品です。芥川の冷徹な観察眼が光る一作として知られています。
物語は、乃木将軍の葬儀の日に集まった人々の会話を中心に展開します。彼らは、将軍の武勇伝や人柄を称賛し、神格化していきます。しかし、その賞賛の言葉は、どこか空虚で、真実味のないものとして描かれています。
芥川は、一人の人間を「英雄」として祭り上げることの危うさや、大衆の熱狂の裏にある無責任さを鋭く指摘します。歴史上の人物や出来事に対する見方を、改めて考えさせられる作品です。



みんなが褒め称える英雄の本当の姿って、誰も知らないのかもね。周りの評価に流されちゃいけないなって思ったよ。
20位: 『一塊の土』
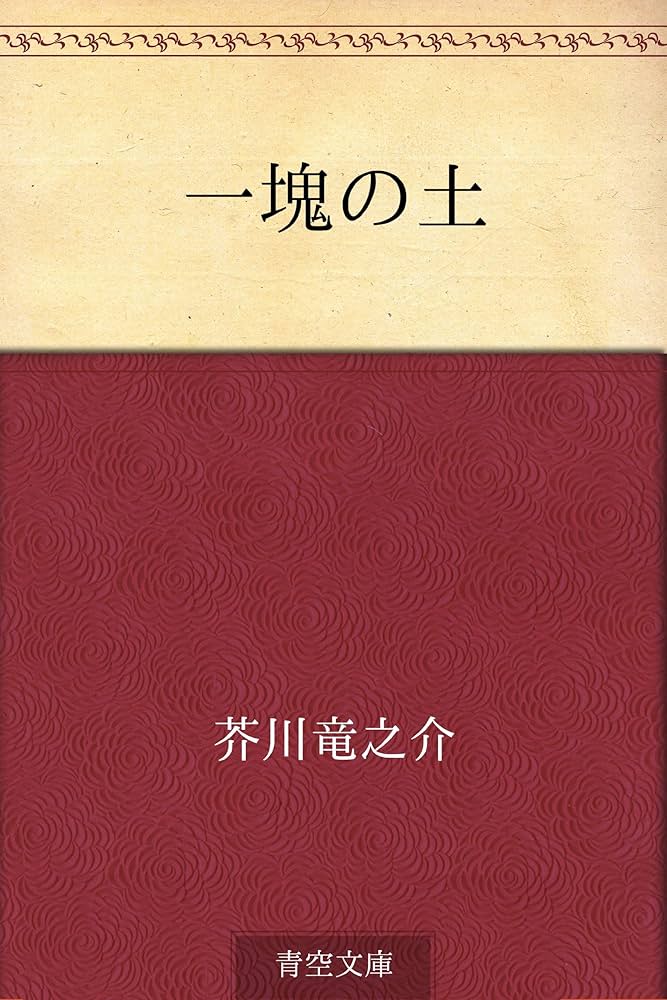
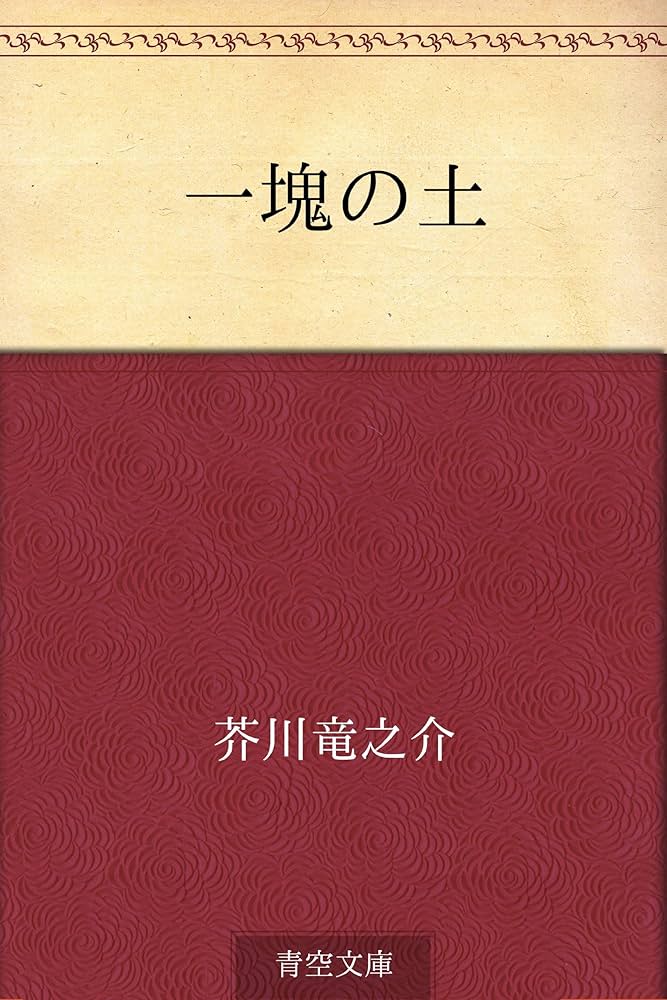
『一塊の土』は、芥川龍之介の作品の中では珍しく、明治時代の農民の過酷な生活をリアルに描いた作品です。自然主義的な作風で、土に生きる人々の力強さと悲哀を描き出しています。
物語の主人公は、貧しい農家の嫁であるお民。彼女は、夫に先立たれ、姑にいびられながらも、たった一人の子どもを育てるために懸命に働きます。しかし、過労がたたり、彼女は病に倒れてしまいます。
死の床にあっても、お民の心は畑のことにありました。土への執着ともいえる彼女の姿を通して、生きることの厳しさと、土地に根ざして生きる人間の根源的な強さが描かれています。芥川の多彩な作風を知ることができる一作です。



お民さんの人生、あまりにも過酷で読んでいて辛かったな…。それでも土のために生きようとする姿に、人間の強さを感じたよ。
まとめ:ランキングを参考に芥川龍之介の名作に触れてみよう
芥川龍之介のおすすめ小説ランキングTOP20をご紹介しました。人間のエゴイズムを鋭く描いた『羅生門』や『蜘蛛の糸』から、心温まる『蜜柑』、そして自らの苦悩を綴った『歯車』まで、その作品世界は非常に多彩です。
多くの作品が短編で読みやすいのも、芥川文学の魅力の一つです。今回のランキングを参考に、気になった作品からぜひ手に取ってみてください。時代を超えて読み継がれる名作の数々が、きっとあなたの心に深い感銘と新たな発見をもたらしてくれるはずです。




