あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】吉村昭のおすすめ小説ランキングTOP20

史実を克明に描く記録文学の巨匠・吉村昭の魅力
記録文学の第一人者として知られる文豪、吉村昭。彼の作品が時代を超えて読者を惹きつけてやまない理由は、徹底した取材に基づいた圧倒的なリアリティにあります。執筆前には膨大な資料を読み解き、現地へ足を運び、関係者の声に耳を傾けることで、歴史の断片を丹念に拾い集めました。
戦争や自然災害、歴史上の事件など、多岐にわたるテーマを扱いながらも、その視点は常に客観的で冷静です。自身の主観を排し、淡々とした筆致で事実を積み重ねていく作風は、読者にまるでその場にいるかのような臨場感を与え、「生と死」や「人間の本質」といった普遍的なテーマを浮かび上がらせます。このように、史実の重みを信じ、人間のドラマをえぐり出す姿勢こそが、吉村文学の最大の魅力と言えるでしょう。
吉村昭のおすすめ小説ランキングTOP20
ここからは、記録文学の巨匠・吉村昭の数ある名作の中から、特におすすめの小説をランキング形式で20作品ご紹介します。
史実を基にした重厚なノンフィクションから、人間の業を描く歴史小説、手に汗握るパニック小説まで、多彩なラインナップとなりました。まだ吉村作品に触れたことのない方も、次の一冊を探しているファンの方も、ぜひこのランキングを参考に、気になる作品を見つけてみてください。
1位: 『羆嵐』
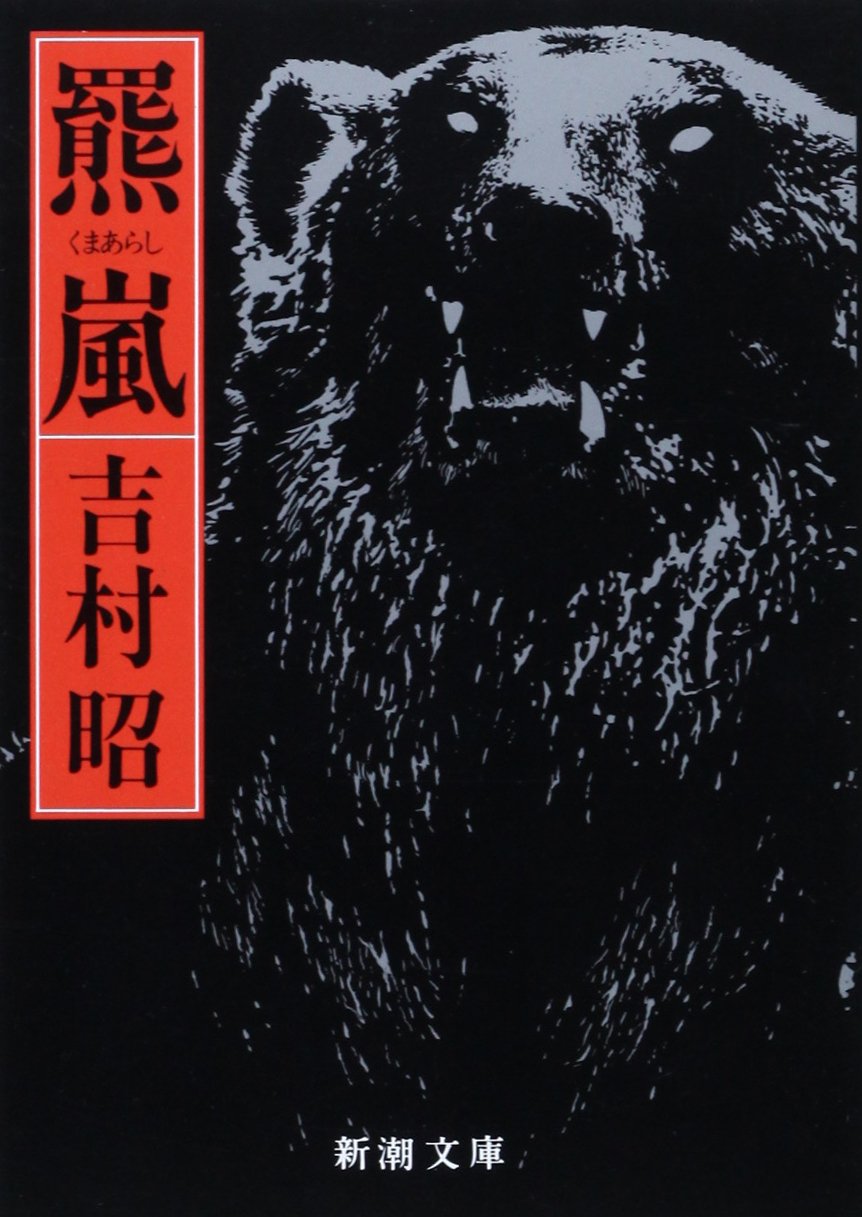
ランキングの1位に輝いたのは、日本獣害史上最悪とされる「三毛別羆事件」を題材にした『羆嵐』です。史実を基に、巨大なヒグマの恐怖と、それに立ち向かう人々の壮絶な戦いを描いた記録小説の金字塔です。
吉村昭の徹底した取材によって、当時の状況や人々の心理が克明に再現されており、その圧倒的なリアリティが読者を恐怖の渦に引き込みます。自然の脅威と、極限状態に置かれた人間の本性が容赦なく描かれ、単なるパニック小説にとどまらない、深い人間ドラマとしても読み応えのある一冊です。
 ふくちい
ふくちい本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。
2位: 『漂流』
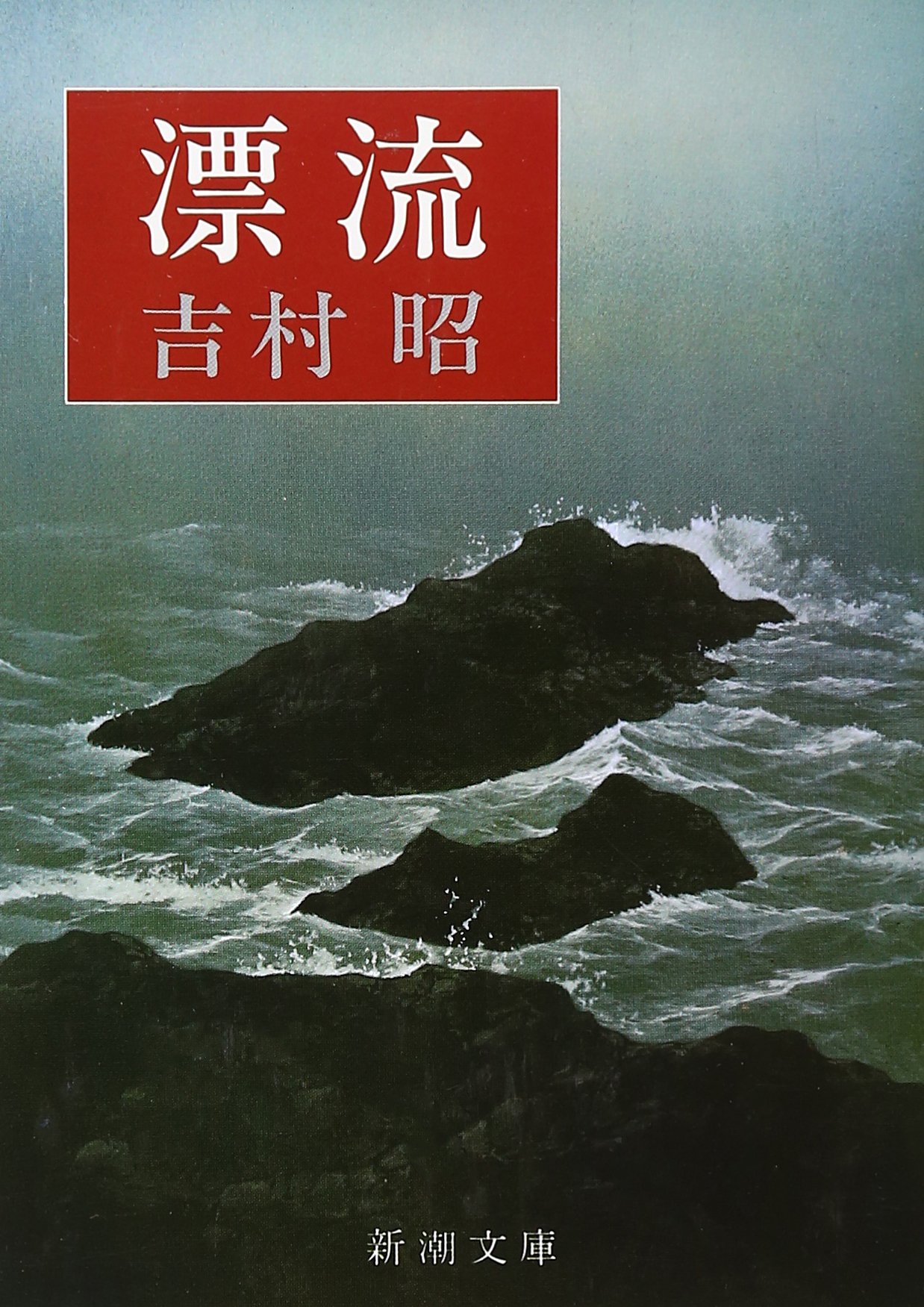
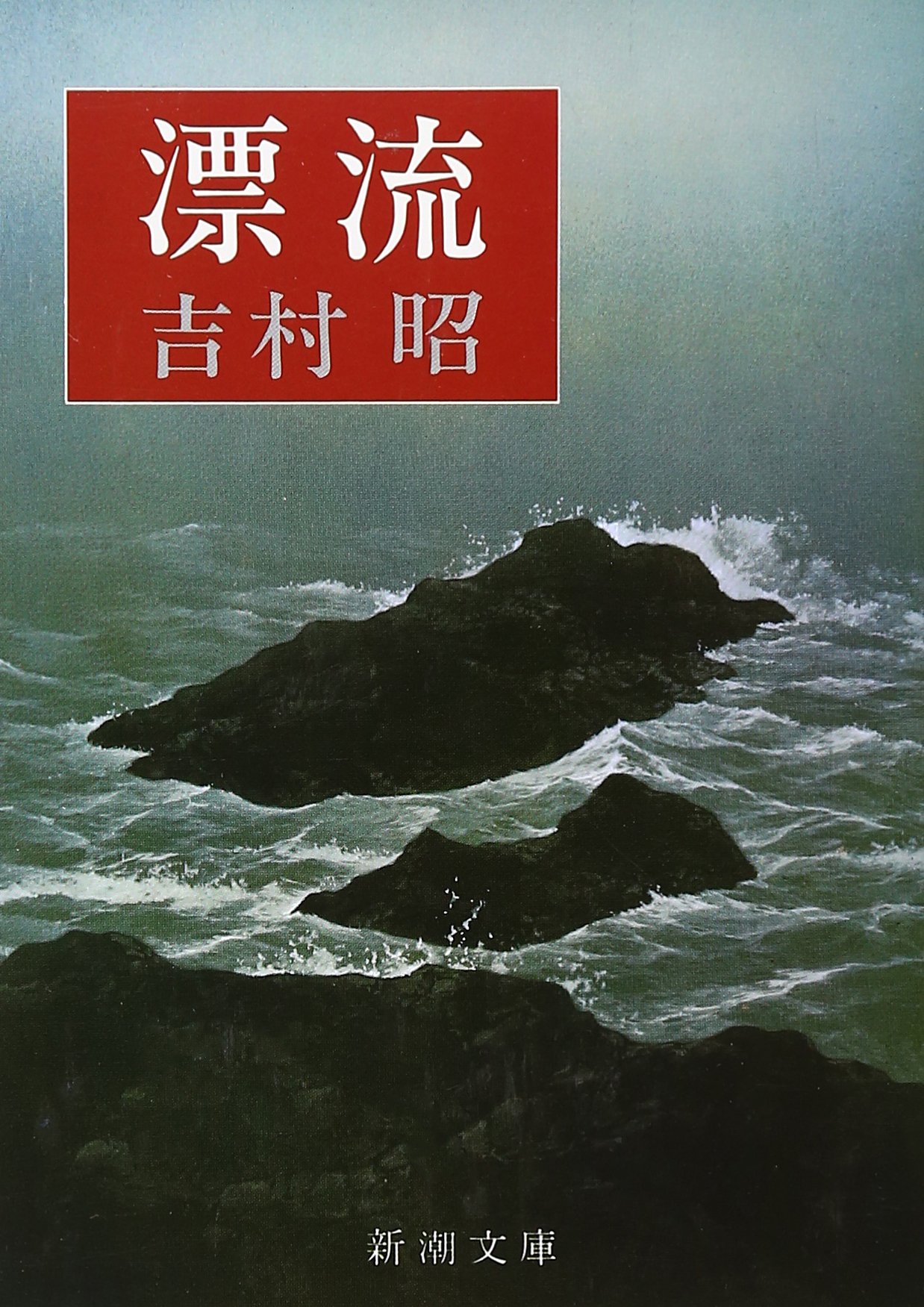
第2位は、江戸時代の実話を基にした『漂流』。嵐で遭難し、無人島に漂着した4人の男たちの壮絶なサバイバル生活を描いた物語です。
水も食料も限られた極限状況の中で、仲間割れや絶望を乗り越え、生き抜こうとする人間の生命力の強さが描かれています。吉村昭の筆致は、ここでも冷静かつ客観的でありながら、人間の内面に深く迫ります。生きることの意味を問いかける、感動的な傑作です。



わたし、こういう極限状態でのサバイバル生活を描いた話、大好きなんだ。ハラハラドキドキが止まらないよ!
3位: 『破獄』
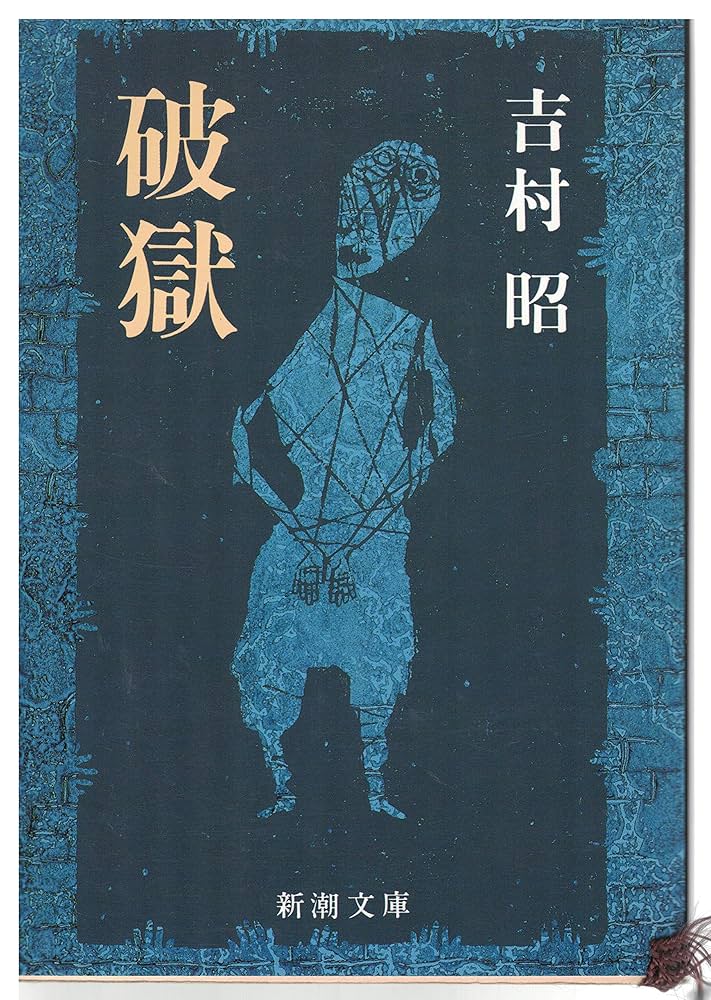
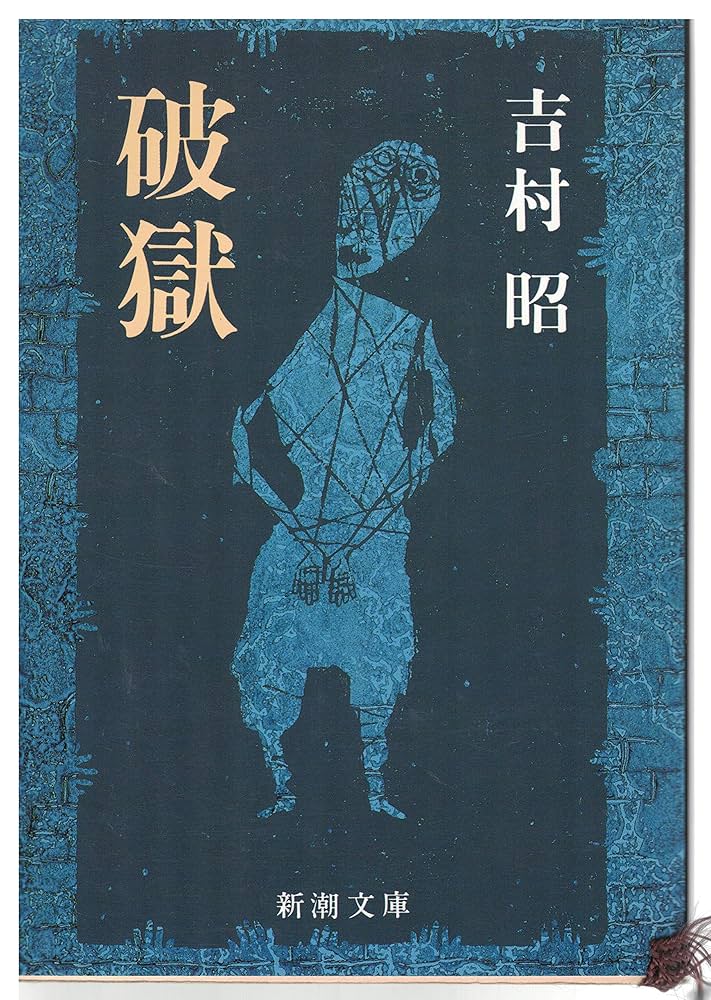
3位にランクインしたのは、”昭和の脱獄王”と呼ばれた実在の人物をモデルにした『破獄』です。誰にも破れないと言われた監獄から、何度も脱獄を繰り返した男の執念と、それを追い続ける看守の攻防を描いています。
緻密な取材に基づき、当時の監獄の様子や脱獄の手口がリアルに描写されています。人間の持つ驚異的な執念と生命力、そして組織と個人の対立というテーマが、読者に強烈な印象を残す作品です。



脱獄にかける情熱がすごすぎて、もはや芸術の域だよね。でも、その力を別のことに使えなかったのかなって思っちゃう。
4位: 『高熱隧道』
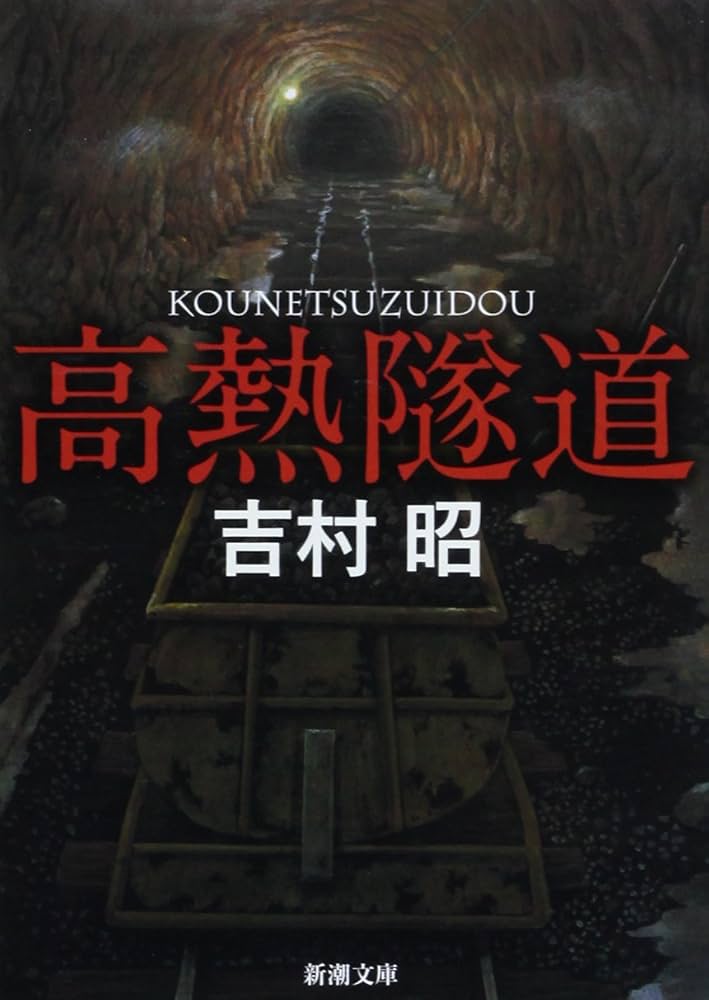
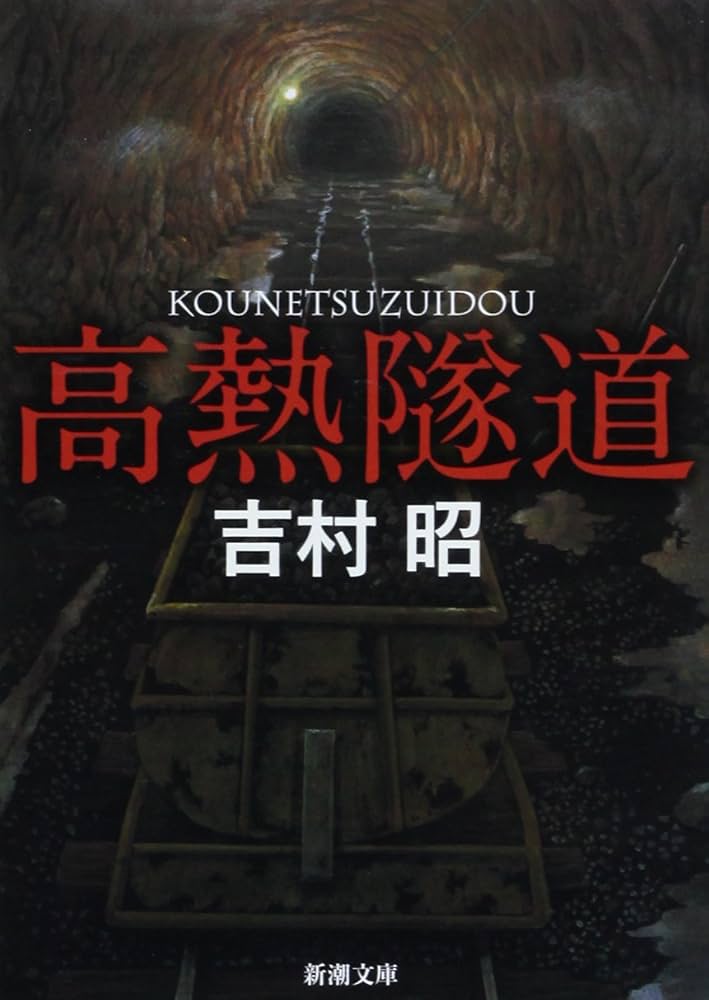
第4位は、黒部ダム建設の中でも最も過酷を極めたと言われる、関電トンネル工事を描いた『高熱隧道』。摂氏160度を超える高熱地帯でのトンネル掘削という、想像を絶する難工事に挑んだ男たちの姿を描いた記録文学の傑作です。
噴出する高温の湯とガス、いつ崩落するとも知れない岩盤という死と隣り合わせの環境で、使命感に燃える技術者と労働者たちの苦闘が克明に綴られています。人間の力の偉大さと、自然の恐ろしさを同時に体感できる、手に汗握る一作です。



こんな過酷な現場で働いていた人たちがいたなんて信じられないよ…。まさに命がけのプロジェクトだね。
5位: 『戦艦武蔵』
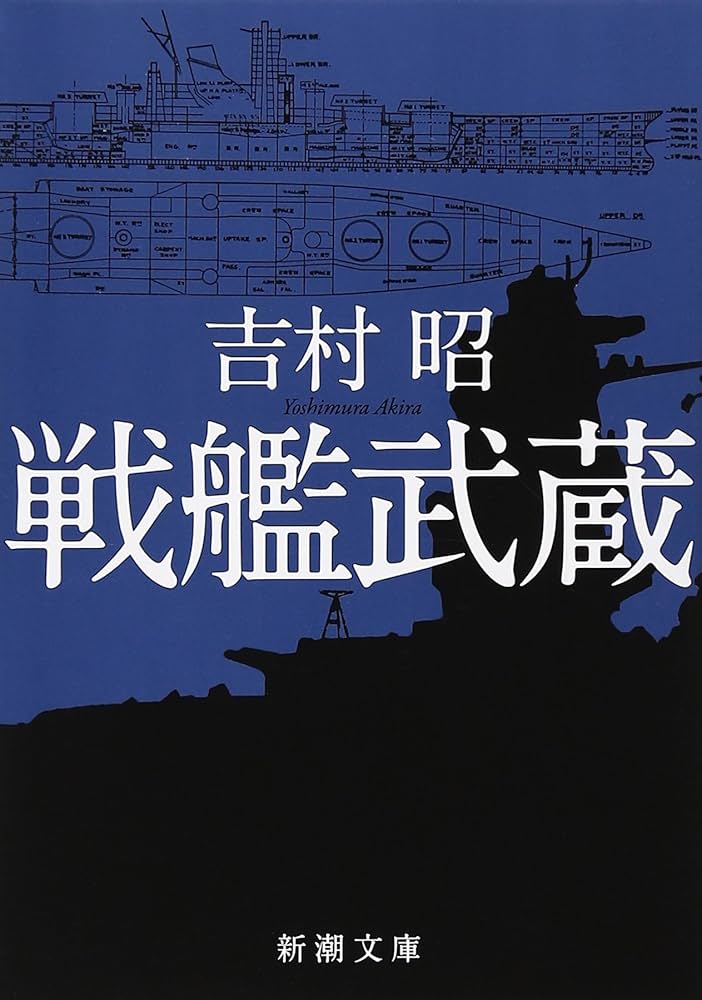
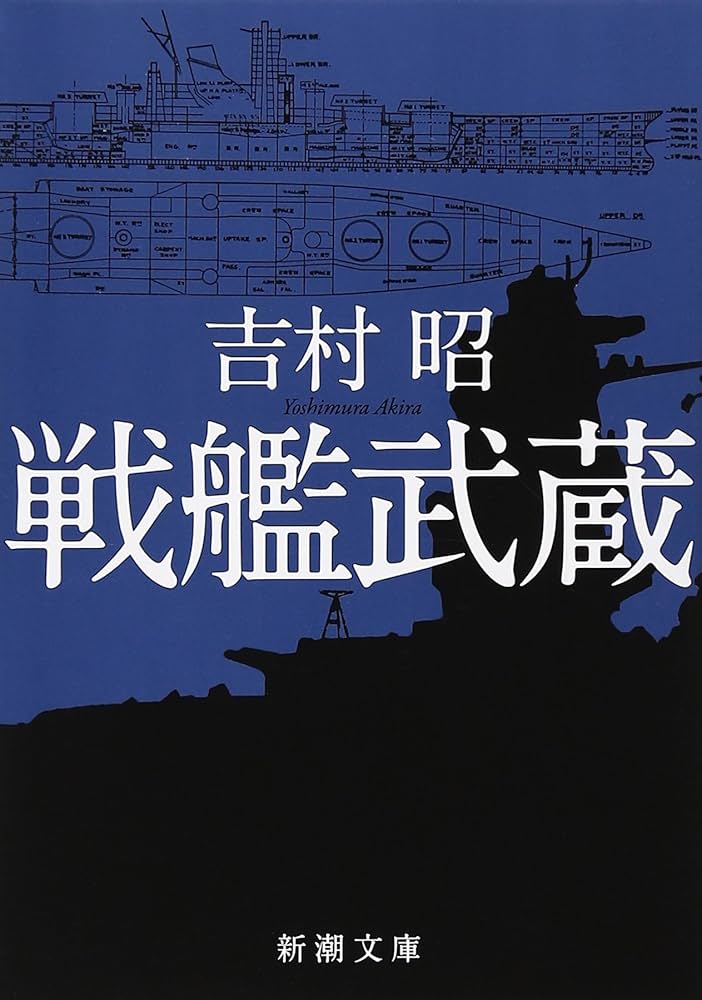
5位は、太平洋戦争中に建造された巨大戦艦「武蔵」の運命を描いた『戦艦武蔵』です。国家の威信をかけて極秘裏に進められた建造計画から、その壮絶な最期までを、多くの関係者への取材を基に描き出しています。
吉村昭は、この作品を含む一連のドキュメント作品で菊池寛賞を受賞しました。戦争という狂気の中で、巨大な科学技術の結晶がいかにして生まれ、そして消えていったのか。その歴史の真実を、冷静かつ重厚な筆致で後世に伝える不朽の名作です。



巨大な戦艦が沈んでいく光景を想像すると、なんだか切なくなるね。戦争の虚しさを感じる一冊だよ。
6位: 『関東大震災』
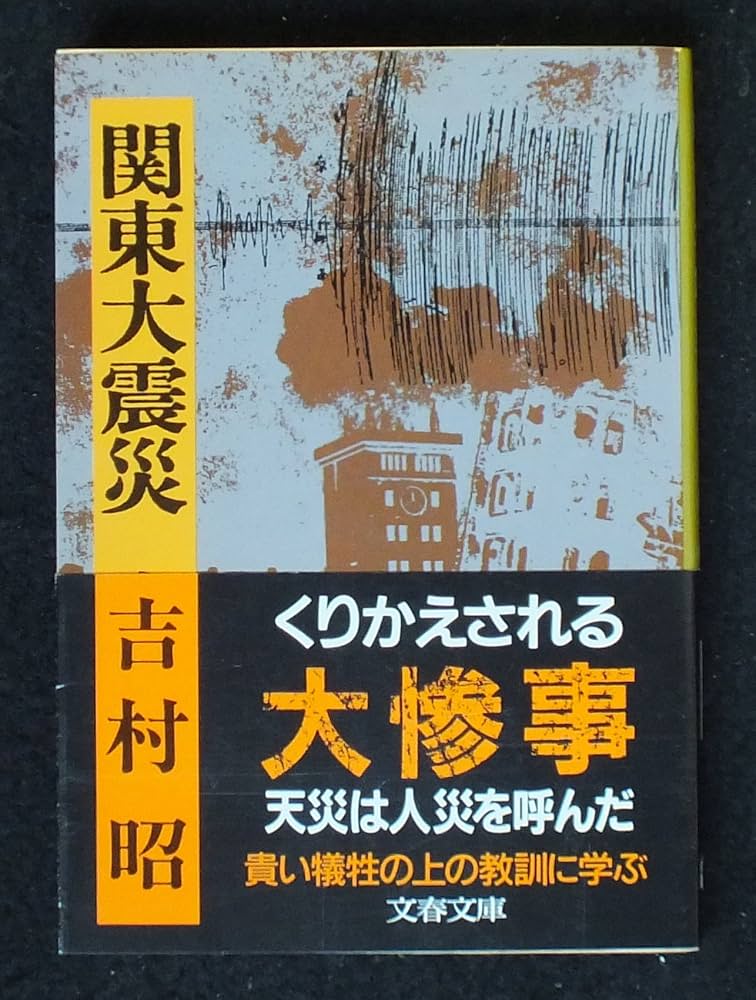
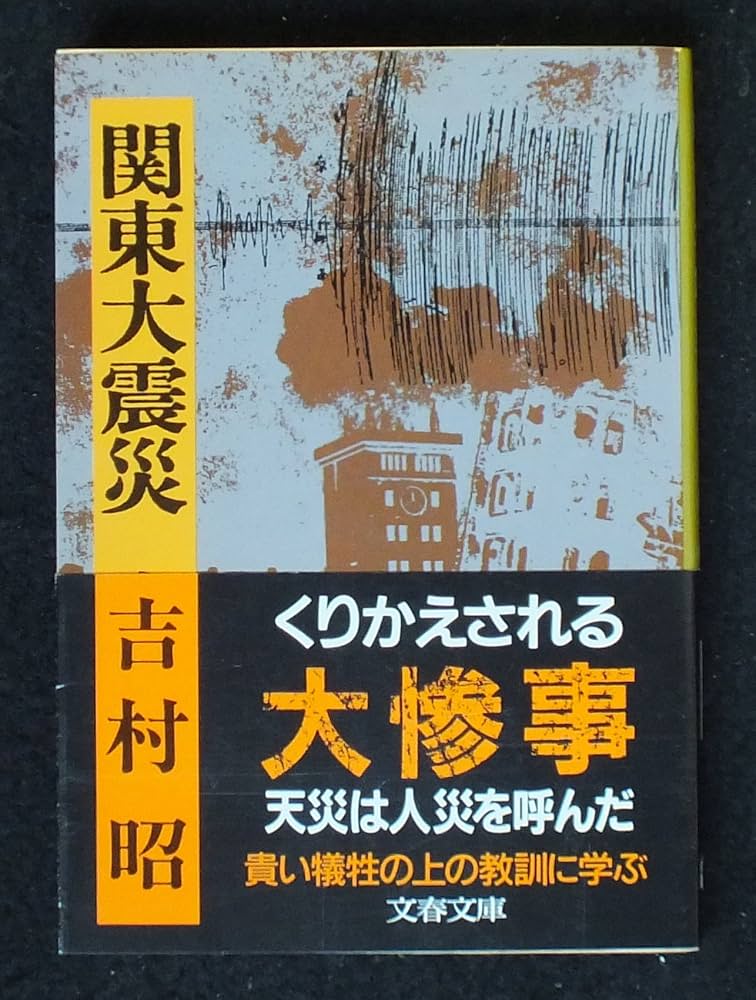
第6位には、1923年に発生した未曾有の大災害を描いた『関東大震災』がランクイン。吉村昭の徹底した調査によって、地震発生の瞬間から火災の延焼、そしてその後の混乱と人々の姿を克明に記録したドキュメンタリーノベルです。
様々な立場の人々の証言や記録を丹念に拾い集め、モザイクのように組み合わせることで、災害の全体像を立体的に浮かび上がらせています。自然災害の恐ろしさと、極限状態における人間の行動様式を浮き彫りにした、今こそ読まれるべき一冊です。



災害の描写がリアルすぎて、読んでいて胸が苦しくなったよ…。いつ自分の身に起こるかわからないから、備えが大事だね。
7位: 『三陸海岸大津波』
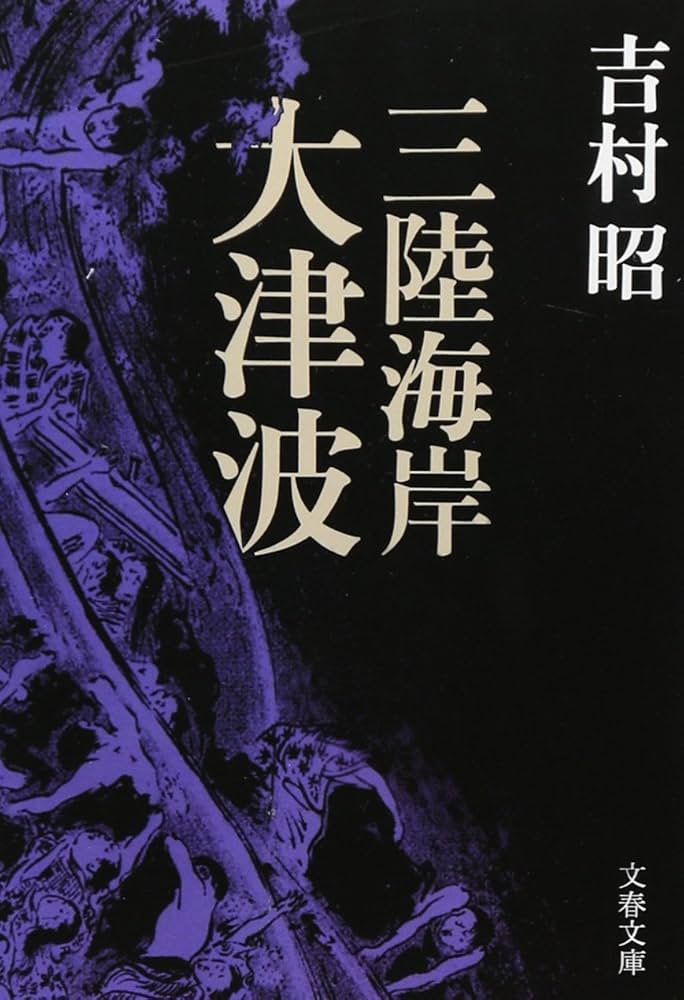
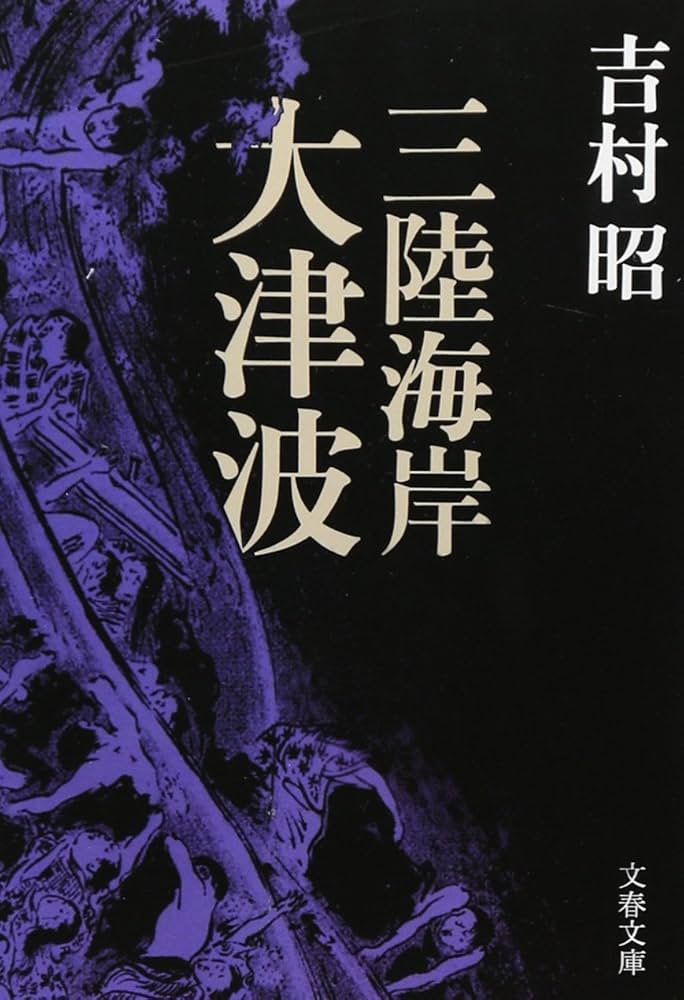
7位は、明治、昭和の二度にわたって三陸海岸を襲った大津波の悲劇を記録した『三陸海岸大津波』です。生存者の貴重な証言を基に、津波がどのように発生し、人々の生活を飲み込んでいったのかを恐ろしいほどリアルに再現しています。
自然の猛威の前では人間がいかに無力であるか、そしてその悲劇が繰り返される歴史の残酷さを突きつけられます。東日本大震災を経験した私たちにとって、過去の災害から学ぶことの重要性を改めて教えてくれる、必読の書と言えるでしょう。



津波の恐ろしさが本当に伝わってくる…。大切な人を一瞬で失う悲しみは、想像するだけで涙が出ちゃうよ。
8位: 『桜田門外ノ変』
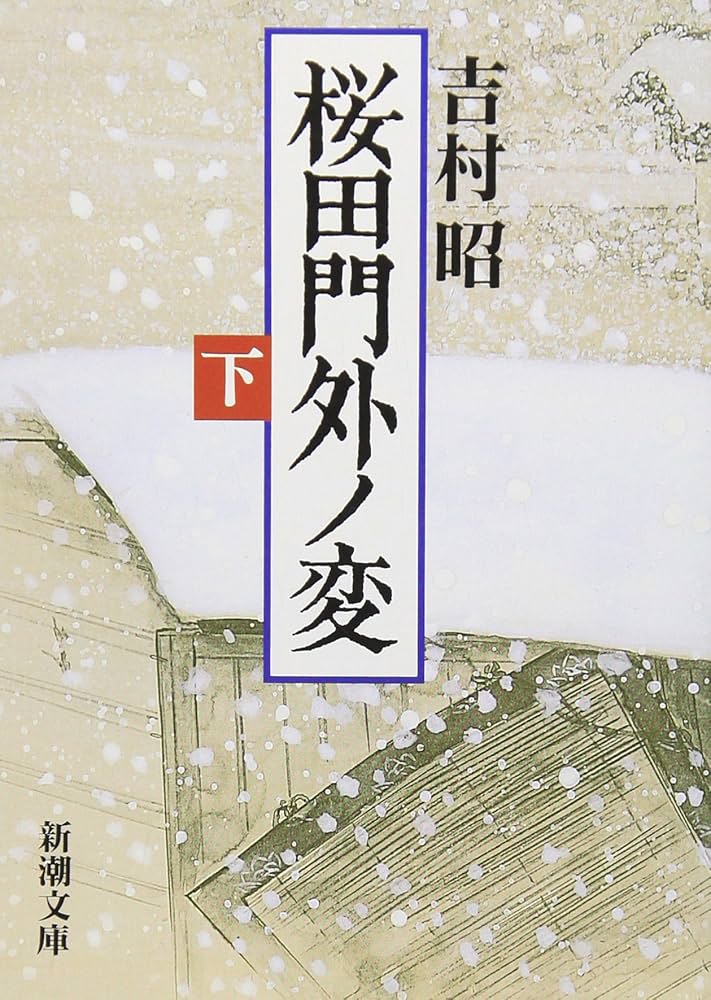
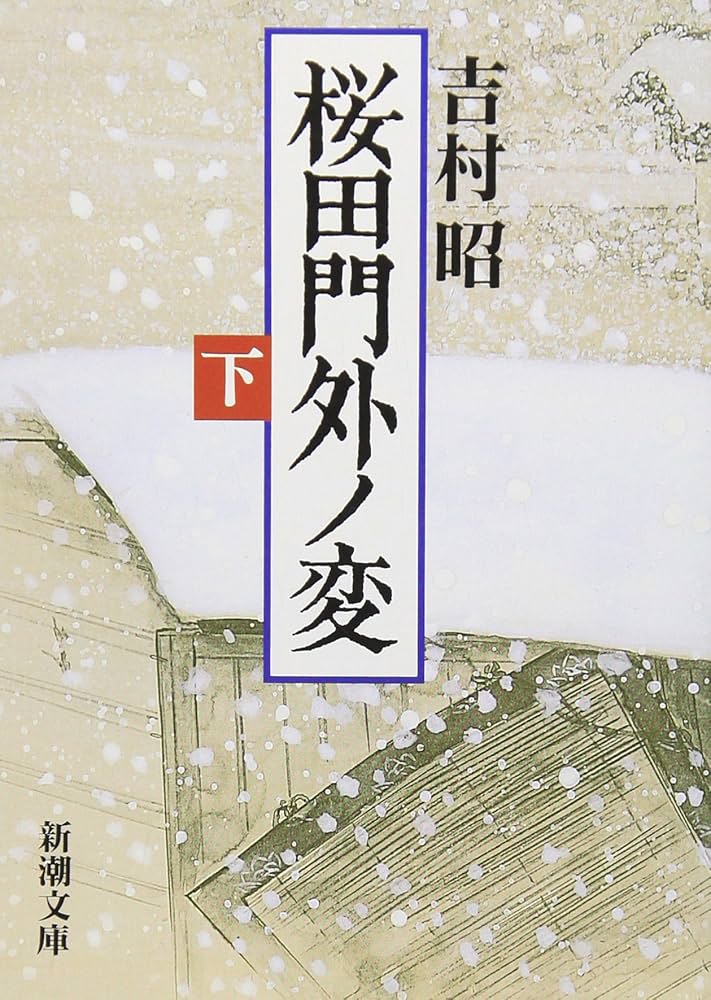
第8位は、幕末の歴史を揺るがした大事件、井伊直弼暗殺を描いた歴史小説『桜田門外ノ変』です。多くの作品が幕府側から描くのに対し、本作は暗殺を実行した水戸浪士たちの視点から事件の真相に迫っていきます。
なぜ彼らは決起に至ったのか。その思想的背景や計画の全貌、そして事件後の浪士たちの過酷な運命を、吉村昭ならではの緻密な構成で描き出します。歴史の裏側に隠された人間ドラマに引き込まれる、重厚な一作です。



歴史の教科書では数行で終わる事件の裏に、こんなに濃い人間ドラマがあったなんて驚きだよ。歴史の見方が変わるかも!
9位: 『ふぉん・しいほるとの娘』
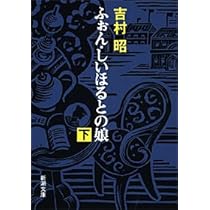
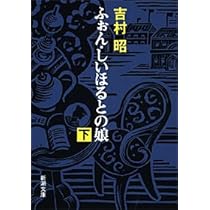
9位にランクインしたのは、シーボルトの娘として生まれ、日本初の女性産科医となった楠本イネの生涯を描いた『ふぉん・しいほるとの娘』。この作品で吉村昭は吉川英治文学賞を受賞しました。
父の追放、母との別れ、そして女性であることへの偏見など、数々の困難に立ち向かいながらも、医学への情熱を胸に力強く生き抜いたイネの姿が感動を呼びます。幕末から明治という激動の時代を背景に、一人の女性の生き様を鮮やかに描き出した傑作です。



逆境にも負けずに夢を追いかけるイネの姿、かっこいい!わたしも頑張ろうって勇気をもらえたよ。
10位: 『ポーツマスの旗』
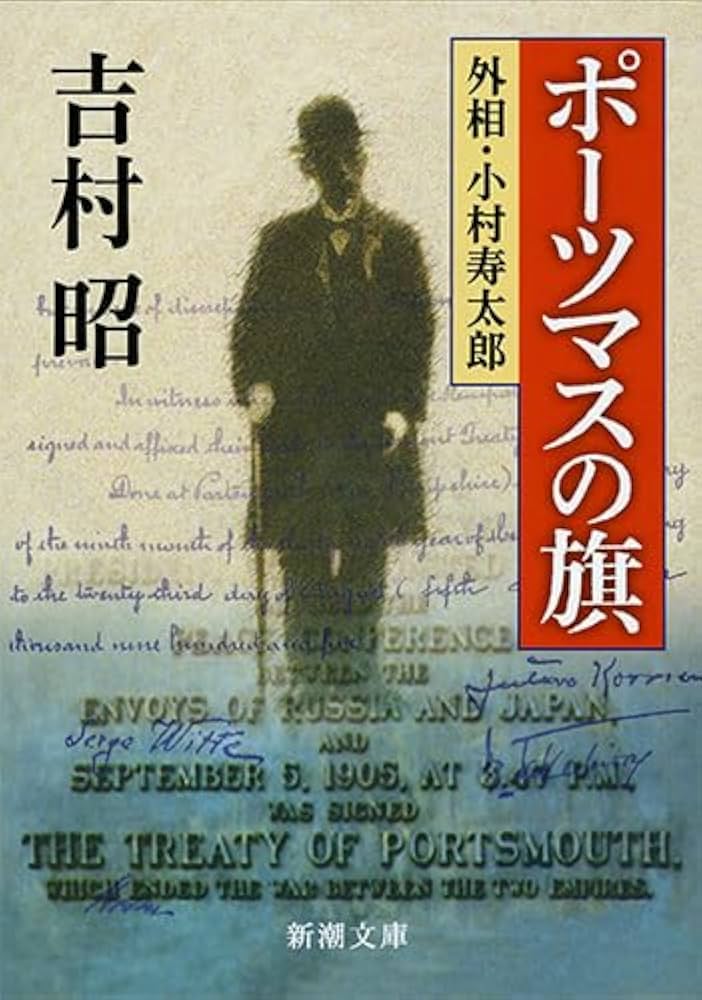
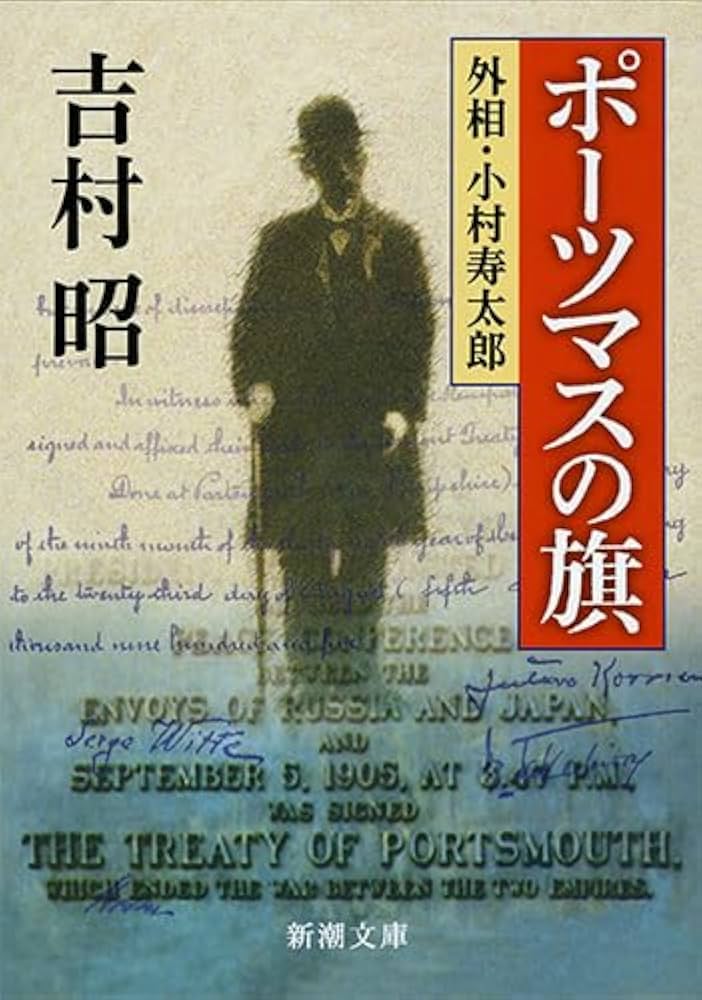
第10位は、日露戦争の講和条約締結のため、アメリカのポーツマスに乗り込んだ全権大使・小村寿太郎の苦闘を描いた『ポーツマスの旗』です。国益を背負い、大国ロシアとの熾烈な交渉に挑む外交官たちの姿を、緊迫感あふれる筆致で描いています。
情報戦、世論操作、そして各国の思惑が複雑に絡み合う外交の舞台裏が、実にリアルに再現されています。不利な状況をいかにして乗り越えようとしたのか、歴史の転換点における男たちの戦いを描いた、社会人にもおすすめの一冊です。



外交って、言葉の戦争なんだね。小村寿太郎のプレッシャーを思うと、胃がキリキリしちゃうよ。
11位: 『赤い人』
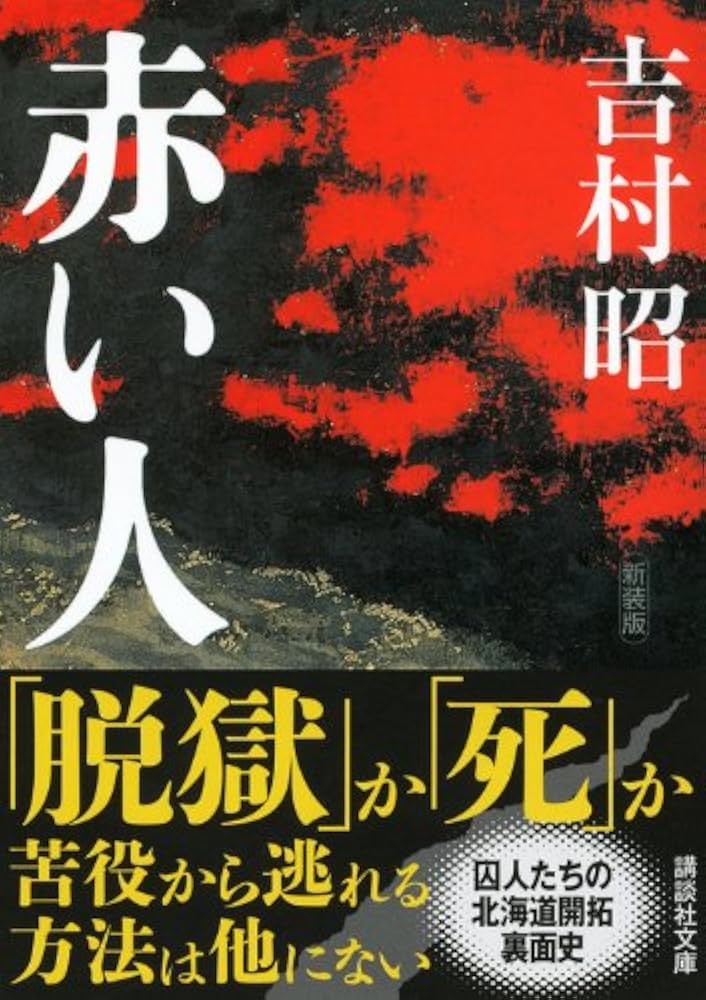
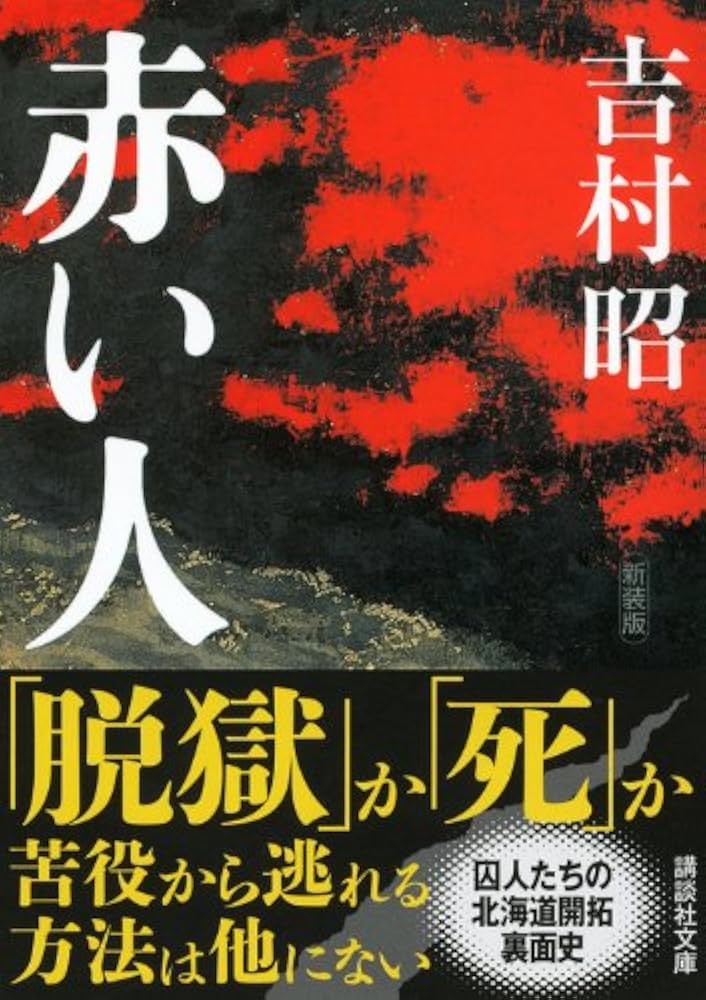
11位は、北海道開拓の暗部を描いた長編歴史小説『赤い人』です。物語の舞台は明治時代、強制労働を科せられる囚人たちが送り込まれた北海道の開拓現場。
極寒の地で、劣悪な環境の中、過酷な労働を強いられる囚人たちと、彼らを管理する看守との間に生まれる敵意と緊張関係を描いています。国家事業の裏側で、人権が軽視されていた時代の闇に光を当てた社会派作品であり、人間の尊厳とは何かを問いかけます。



国の発展の裏で、こんなにひどいことが行われていたなんて…。読んでいてすごく考えさせられたよ。
12位: 『冬の鷹』
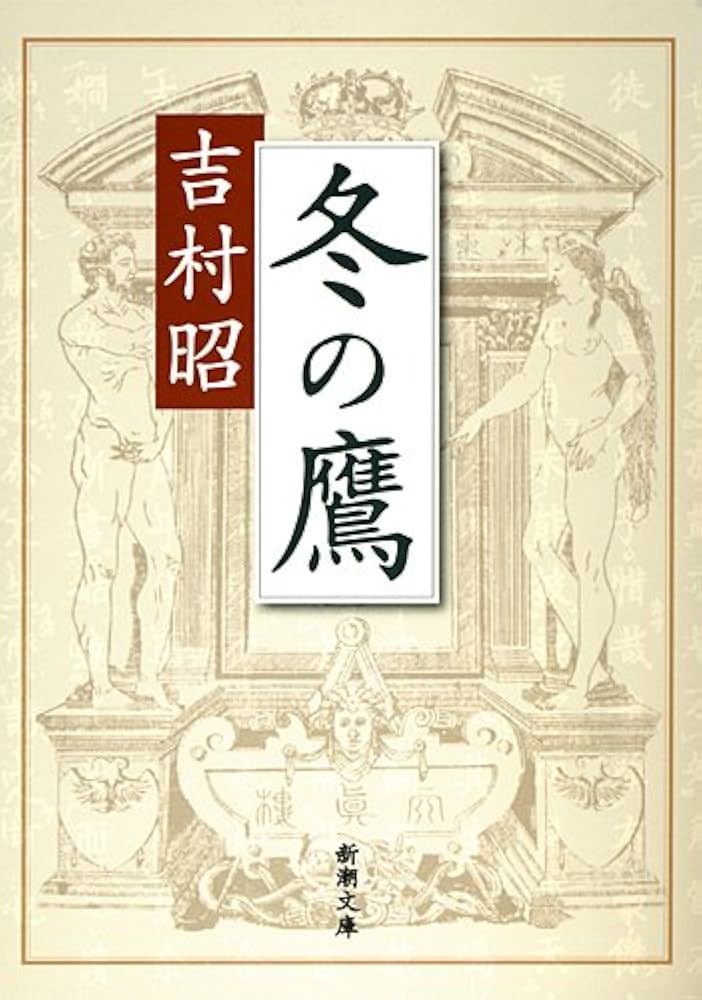
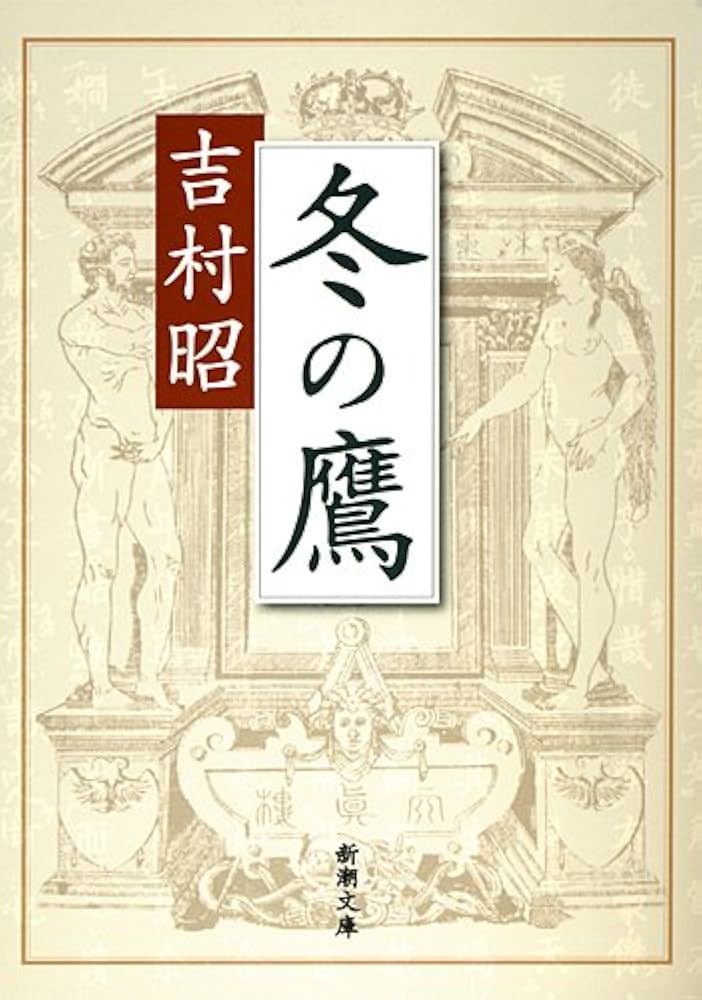
12位は、日本初の西洋医学解剖書『解体新書』の翻訳に挑んだ二人の蘭学者、杉田玄白と前野良沢の対照的な人生を描いた『冬の鷹』です。偉業を成し遂げ、名声を得た玄白と、その陰で正当な評価を得られなかった良沢の姿を対比的に描いています。
真理の探究に生涯を捧げた学者の執念と、名誉や人間関係の複雑さが絡み合う物語は、非常にドラマチックです。歴史に埋もれた知られざる偉人の功績に光を当てた、吉村昭ならではの一作と言えるでしょう。



才能があるのに報われないって、なんだか切ない話だね。でも、自分の信念を貫く良沢の生き方は素敵だと思うな。
13位: 『零式戦闘機』
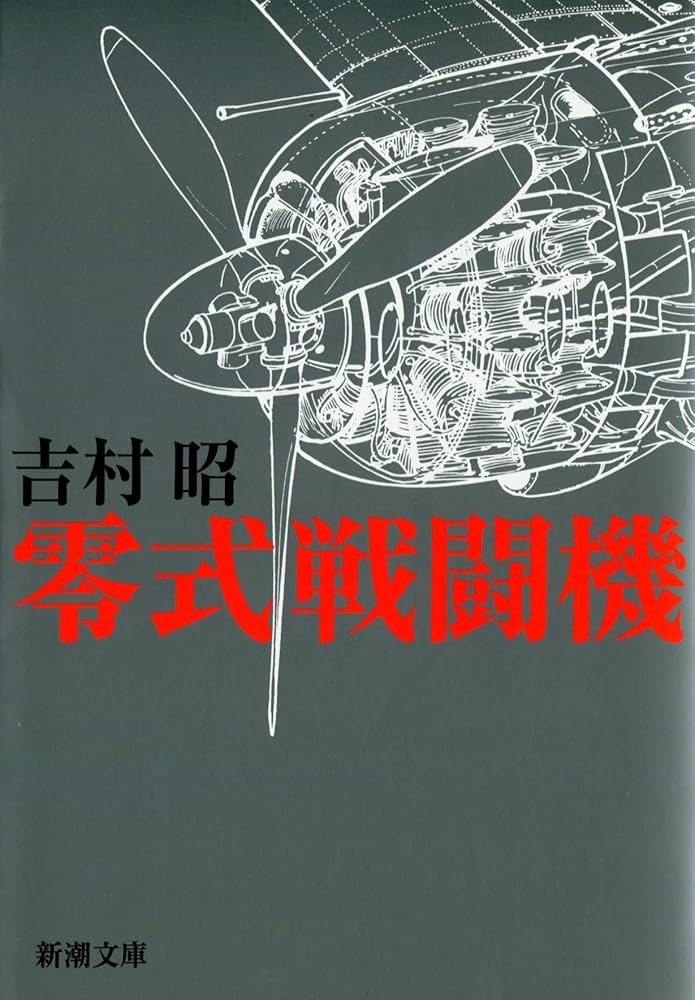
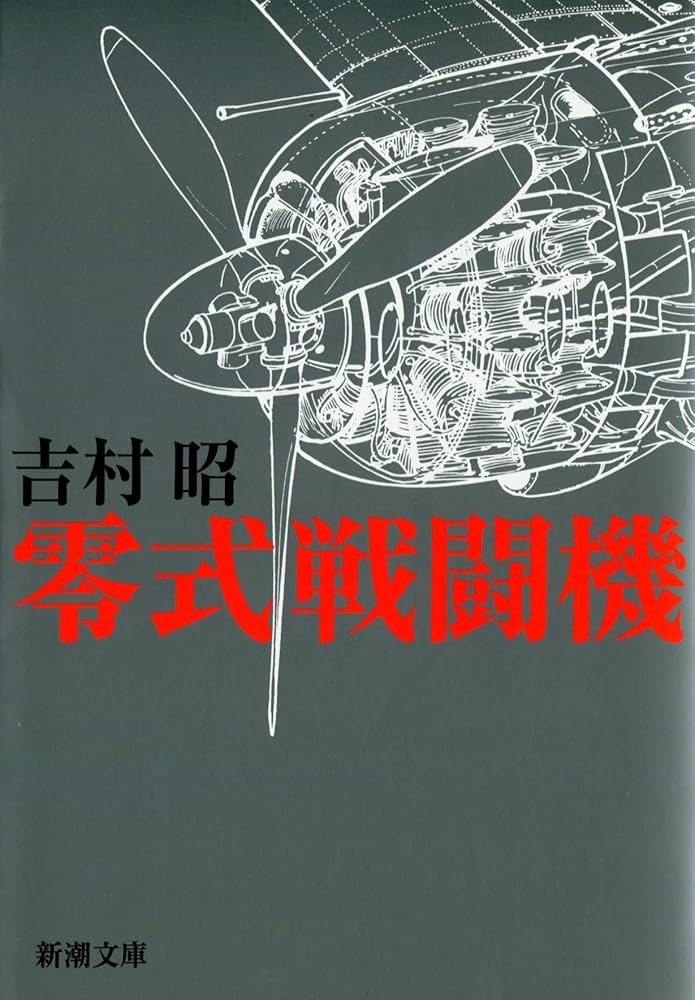
第13位は、太平洋戦争で日本の主力戦闘機として活躍した「零戦」の開発から終焉までを描いた記録小説『零式戦闘機』です。開発者たちの苦悩と情熱、そして戦局の変化とともに悲劇的な運命をたどる戦闘機の姿を克明に追っています。
優れた技術が、戦争という目的のためにいかに利用され、消費されていったのか。技術者たちの視点から戦争の虚しさを描き出した作品です。航空ファンや技術史に興味のある方はもちろん、多くの人に読んでもらいたい一冊です。



最高の技術が戦争の道具になってしまうのは悲しいね。技術は人々の幸せのために使われるべきだよ。
14位: 『海の史劇』
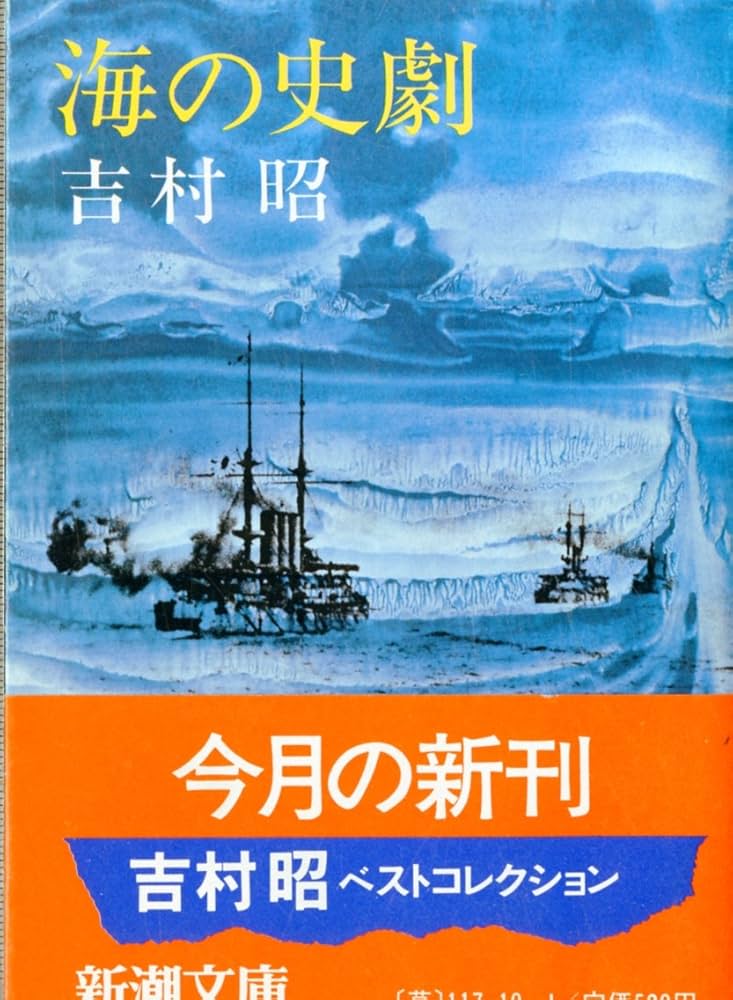
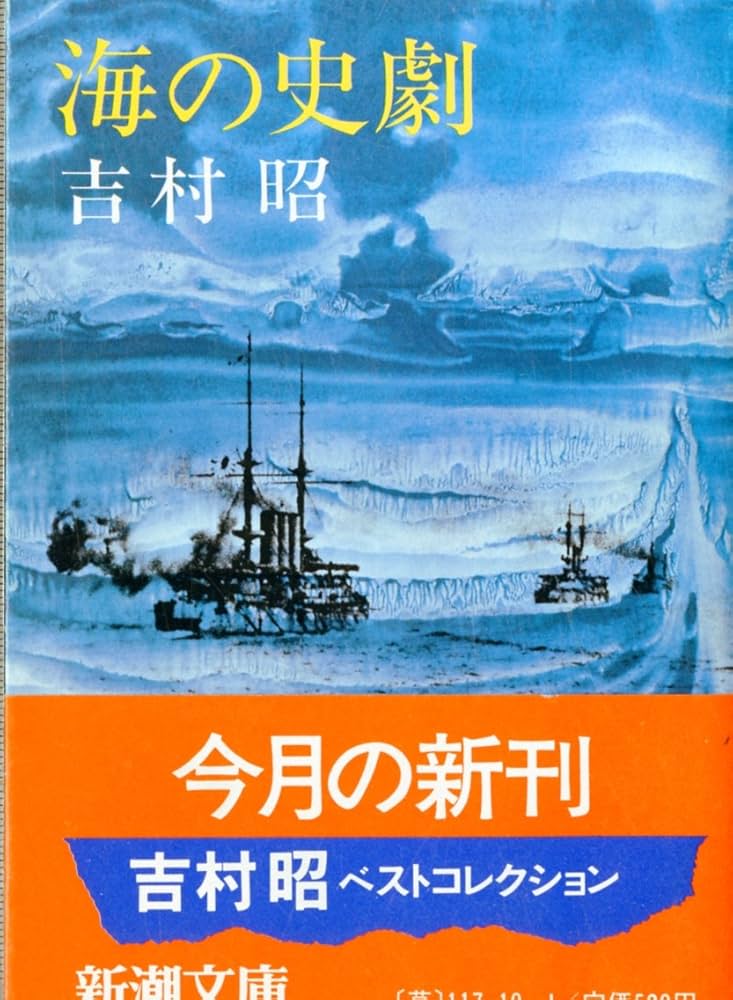
14位には、日本人として初めてアメリカに渡り、日米の架け橋となったジョン万次郎の数奇な運命を描いた『海の史劇』がランクイン。漁の最中に遭難し、アメリカの捕鯨船に救助されたことから始まる、彼の波乱万丈の生涯を描いています。
言葉も文化も違う異国で生き抜き、帰国後は通訳や教師として活躍した万次郎。その冒険心と行動力、そして激動の時代を生き抜いた彼の人生は、私たちに大きな勇気と感動を与えてくれます。



ジョン万次郎の人生、ドラマチックすぎる!こんなすごい人が日本にいたなんて、なんだか誇らしい気持ちになるね。
15位: 『星への旅』
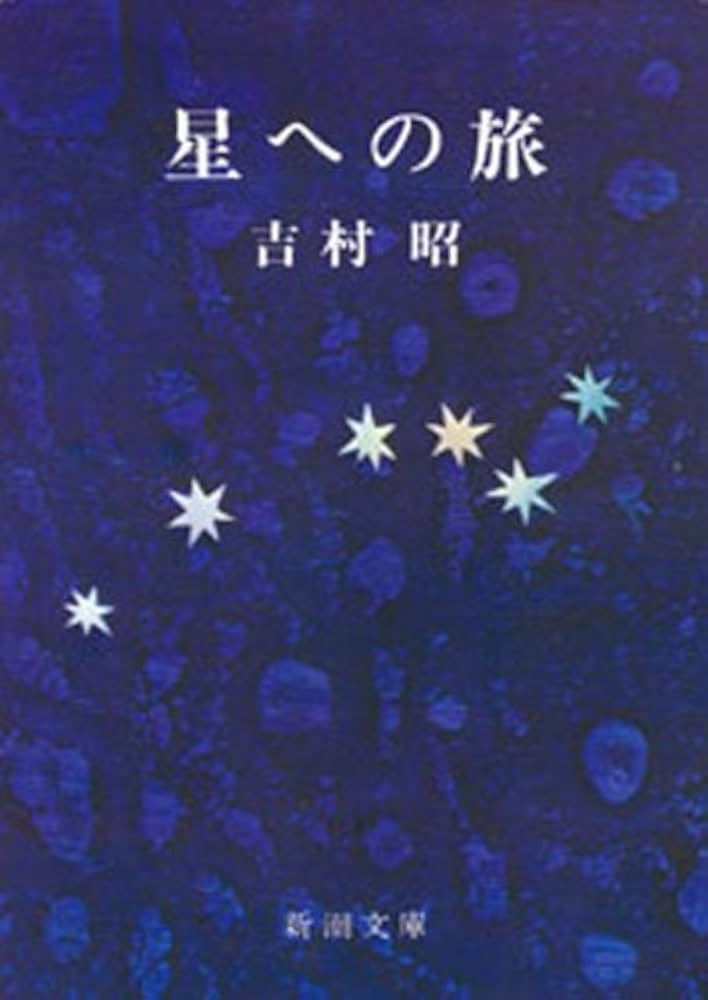
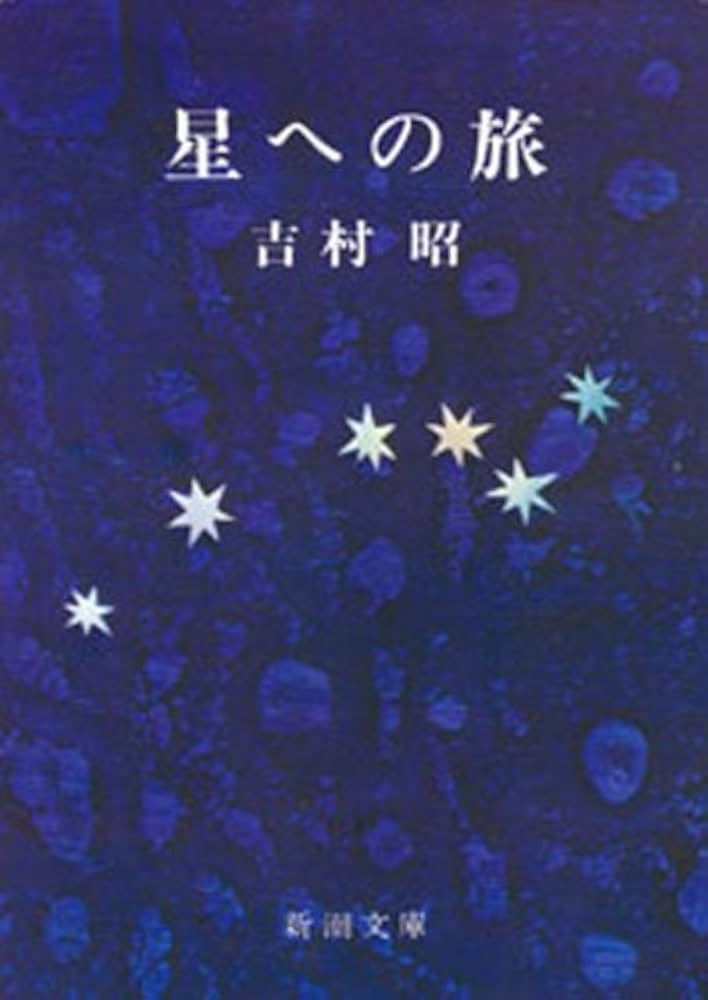
15位は、吉村昭が太宰治賞を受賞した初期の代表作『星への旅』です。実際に起きた若い男女の心中事件を題材に、二人が死に至るまでの心の軌跡を繊細な筆致で描いた純文学作品です。
他の記録文学とは異なり、登場人物の内面描写に深く踏み込んでいるのが特徴です。なぜ二人は死を選ばなければならなかったのか。社会や家族との関係の中で追い詰められていく若者の孤独と絶望が、静かに、しかし鋭く胸に迫ります。



若い二人が追い詰められていく様子が、読んでいてとても苦しかった…。誰か助けてあげられなかったのかなって思っちゃう。
16位: 『魚影の群れ』
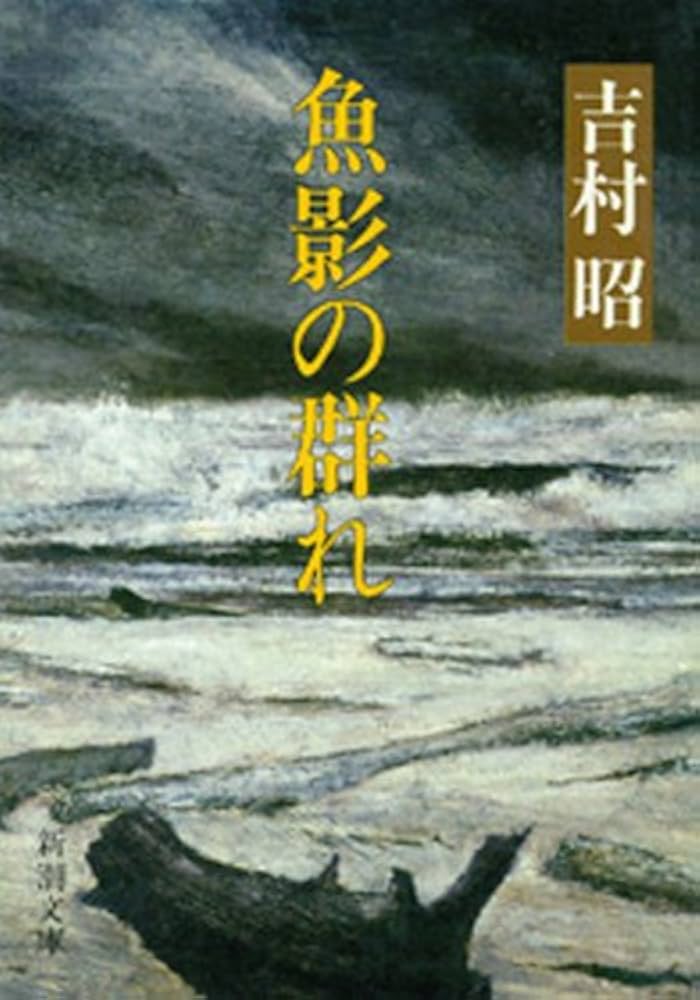
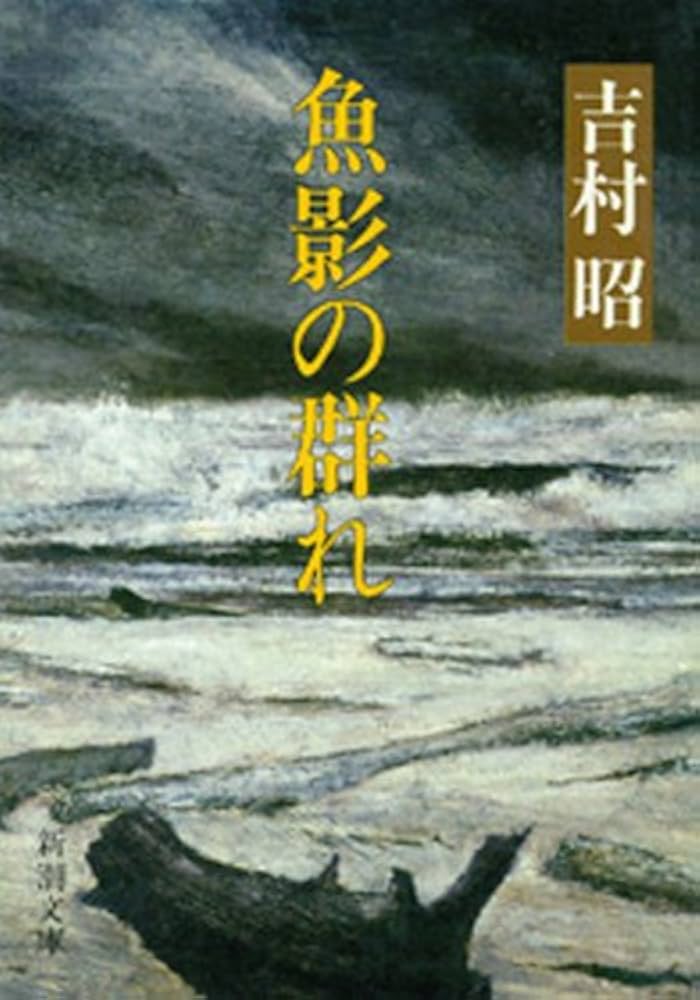
第16位は、表題作を含む4編を収録した短編集『魚影の群れ』です。この作品集では、マグロ漁師をはじめ、海と共に生き、海で死んでいく男たちの姿が力強く描かれています。
厳しい自然と対峙しながら、黙々と己の仕事に向き合う海の男たち。その無骨ながらも純粋な生き様が、吉村昭の簡潔で力強い文章によって鮮やかに描き出されています。短編集なので、吉村作品の入門編としてもおすすめです。



海で生きる男たちの世界、かっこいいね!寡黙だけど、内に秘めた情熱が伝わってくるよ。
17位: 『雪の花』
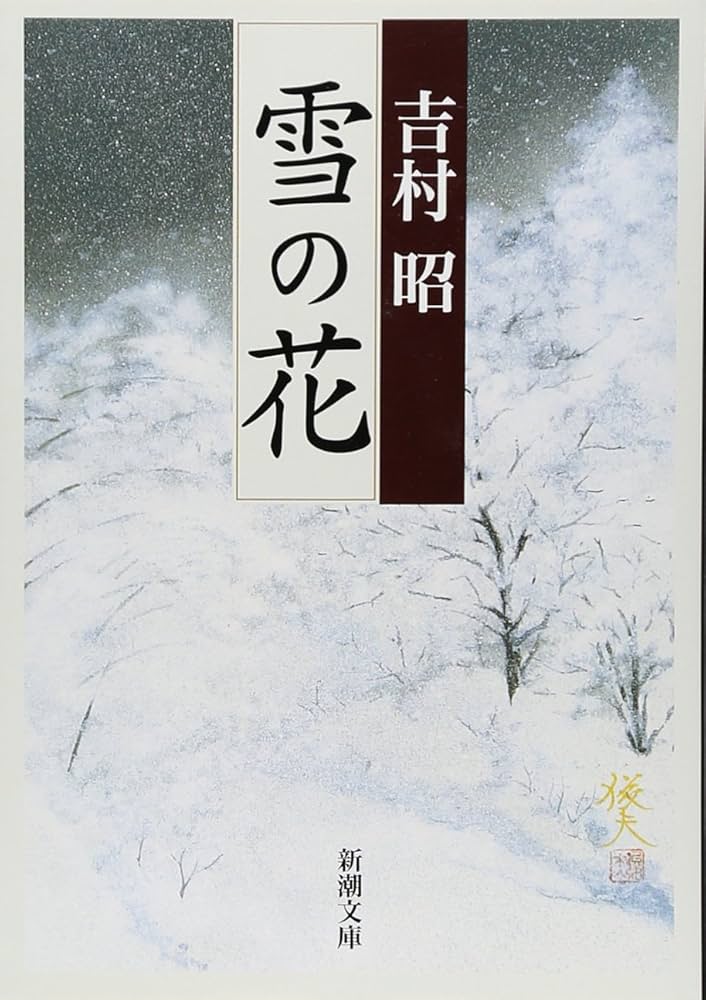
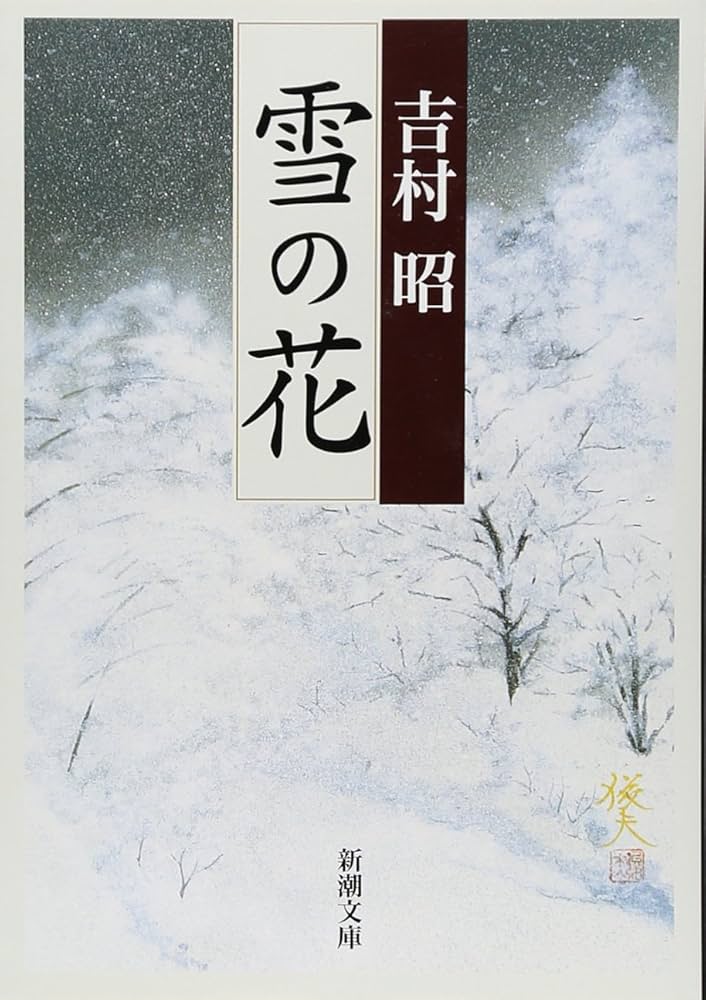
17位は、江戸時代に天然痘の予防接種である「種痘」の普及に尽力した福井藩の町医者・笠原良策の物語『雪の花』です。当時、多くの人々の命を奪っていた天然痘から子供たちを救うため、私財を投じ、周囲の無理解と闘いながら奔走する医師の姿を描いています。
人々の命を救いたいという一心で、困難に立ち向かう主人公の姿には胸を打たれます。医療の歴史に埋もれた先人たちの偉大な功績に光を当てた、感動的なヒューマンドラマです。



自分の利益を考えずに、人のために尽くせるって本当にすごいことだよね。こういうお医者さんがいたから今の私たちがあるんだな。
18位: 『冷い夏、熱い夏』
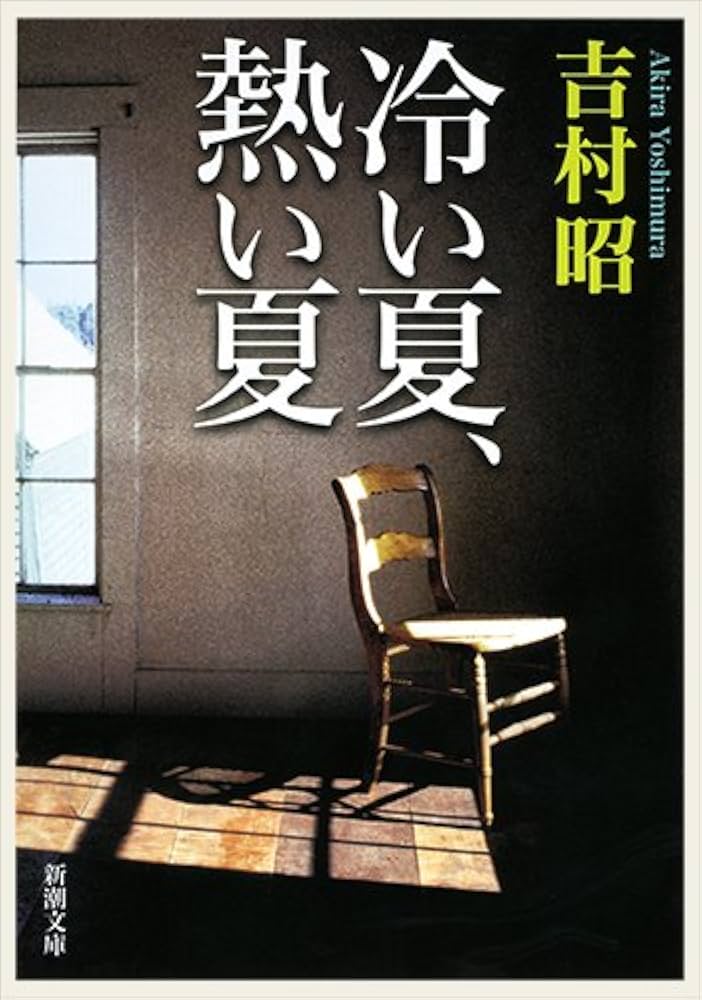
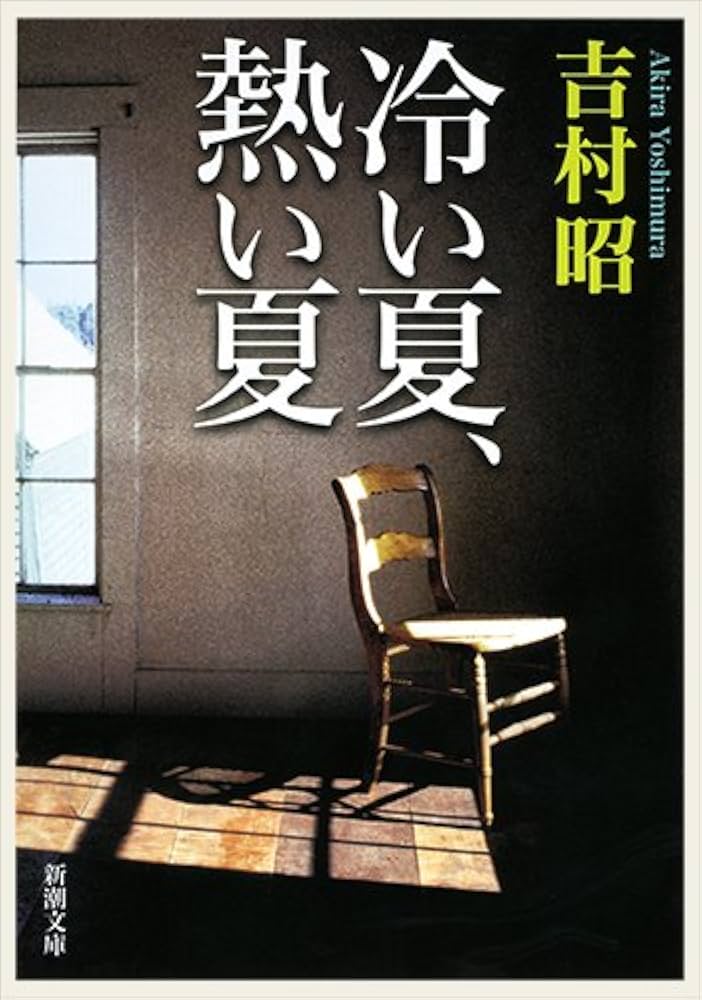
第18位は、実際に起きた冤罪事件「島田事件」を題材にした『冷い夏、熱い夏』です。無実の罪で死刑判決を受けた青年と、その無実を信じ、絶望的な状況の中で再審を求め続ける家族や弁護士たちの長い戦いを描いています。
司法の誤りという重いテーマを扱いながら、最後まで希望を捨てずに戦い抜いた人々の姿を通して、人間の尊厳と正義とは何かを問いかけます。社会の不条理に立ち向かう人々の姿に、心を揺さぶられる作品です。



無実なのに死刑判決なんて、考えただけで恐ろしいよ…。家族の支えがなかったら、心が折れちゃいそうだね。
19位: 『遠い日の戦争』
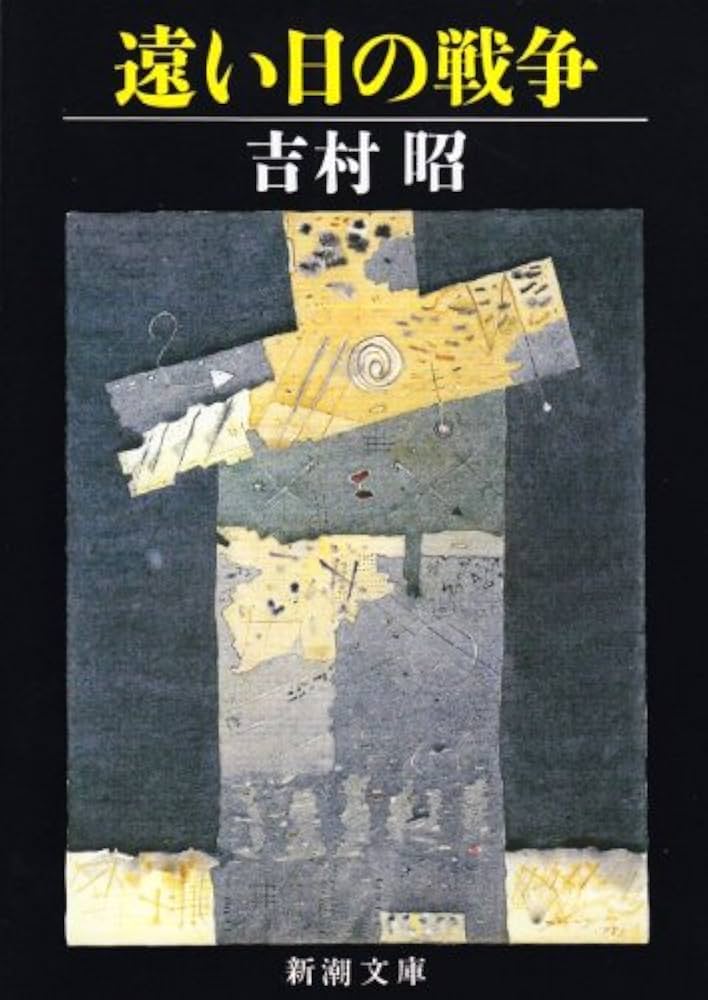
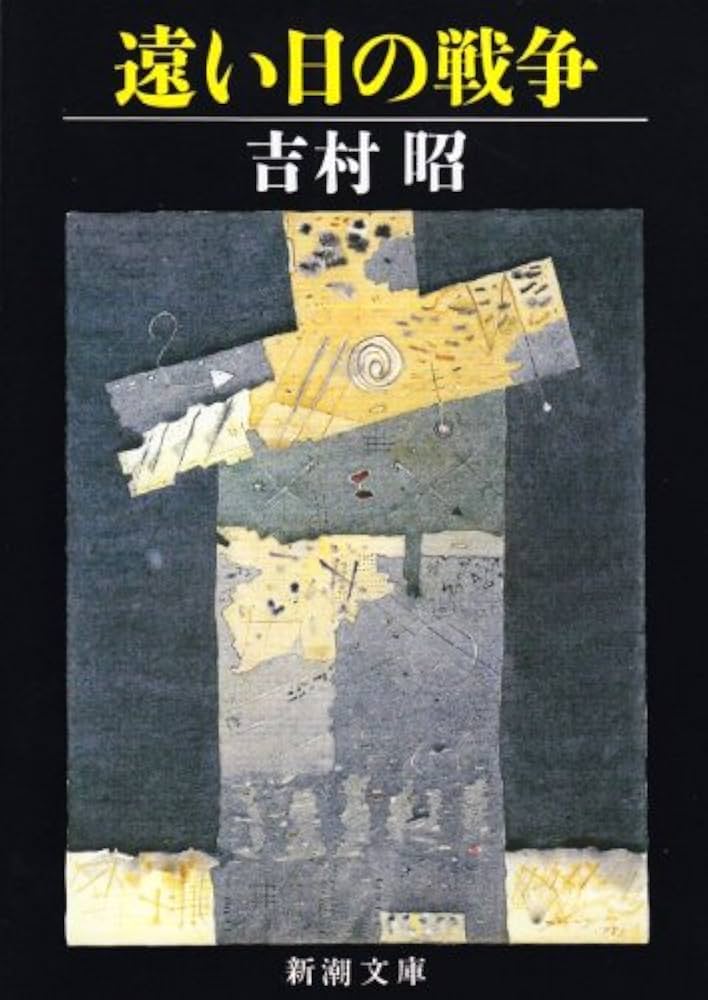
19位には、吉村昭自身の戦争体験を色濃く反映した私小説的な作品『遠い日の戦争』がランクイン。少年期に戦争を経験した主人公の目を通して、戦時下の日常や人々の様子、そして戦争がもたらした心の傷跡を描いています。
他の作品のような徹底した取材に基づく記録文学とは一味違い、作家個人の記憶や感情が静かに織り込まれています。戦争を体験した世代が抱える思いを、後世に伝える貴重な一冊です。



作家自身の体験が元になっているから、言葉の重みが違うね。戦争が遠い昔のことじゃないって、改めて感じたよ。
20位: 『破船』
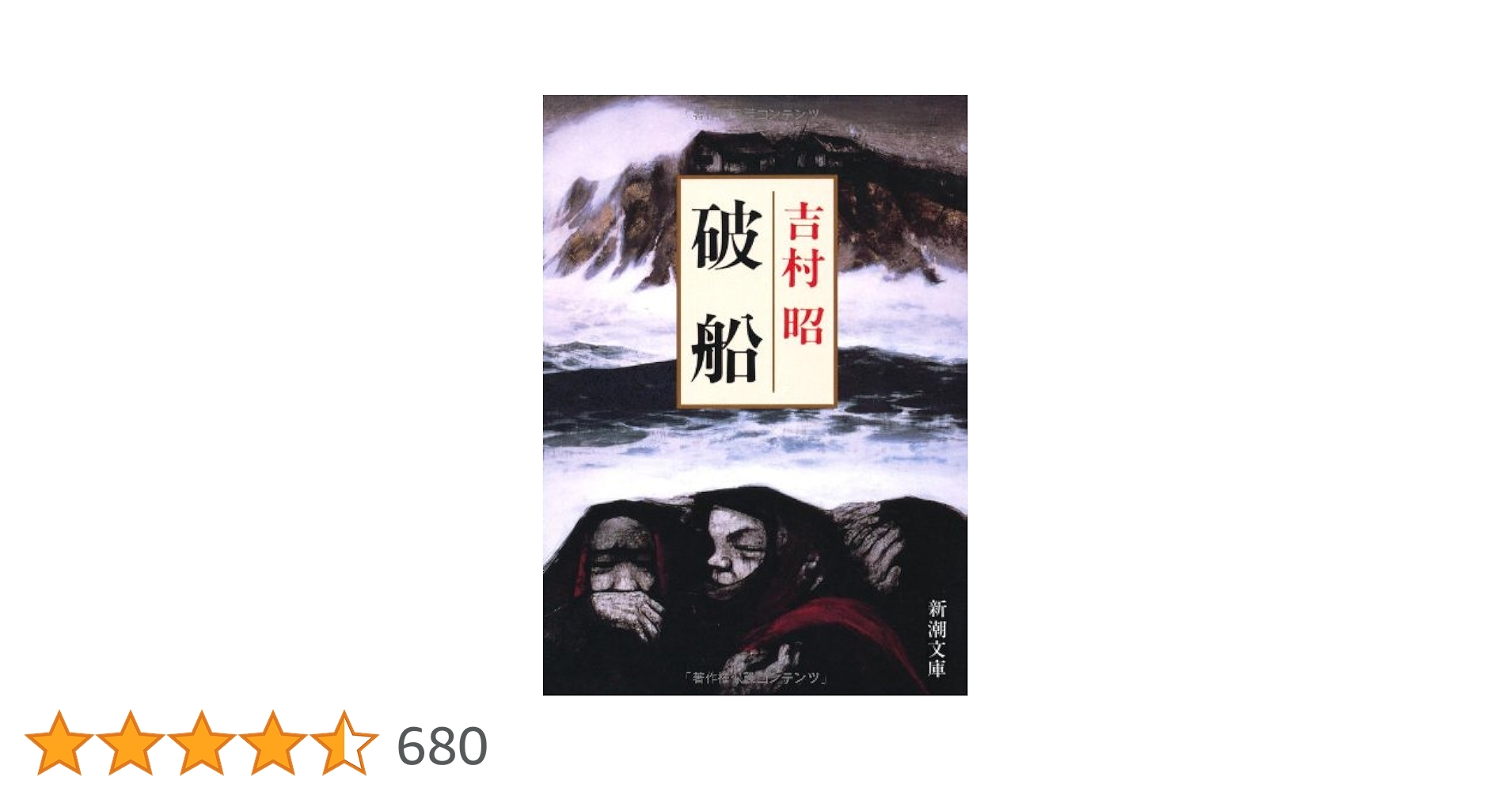
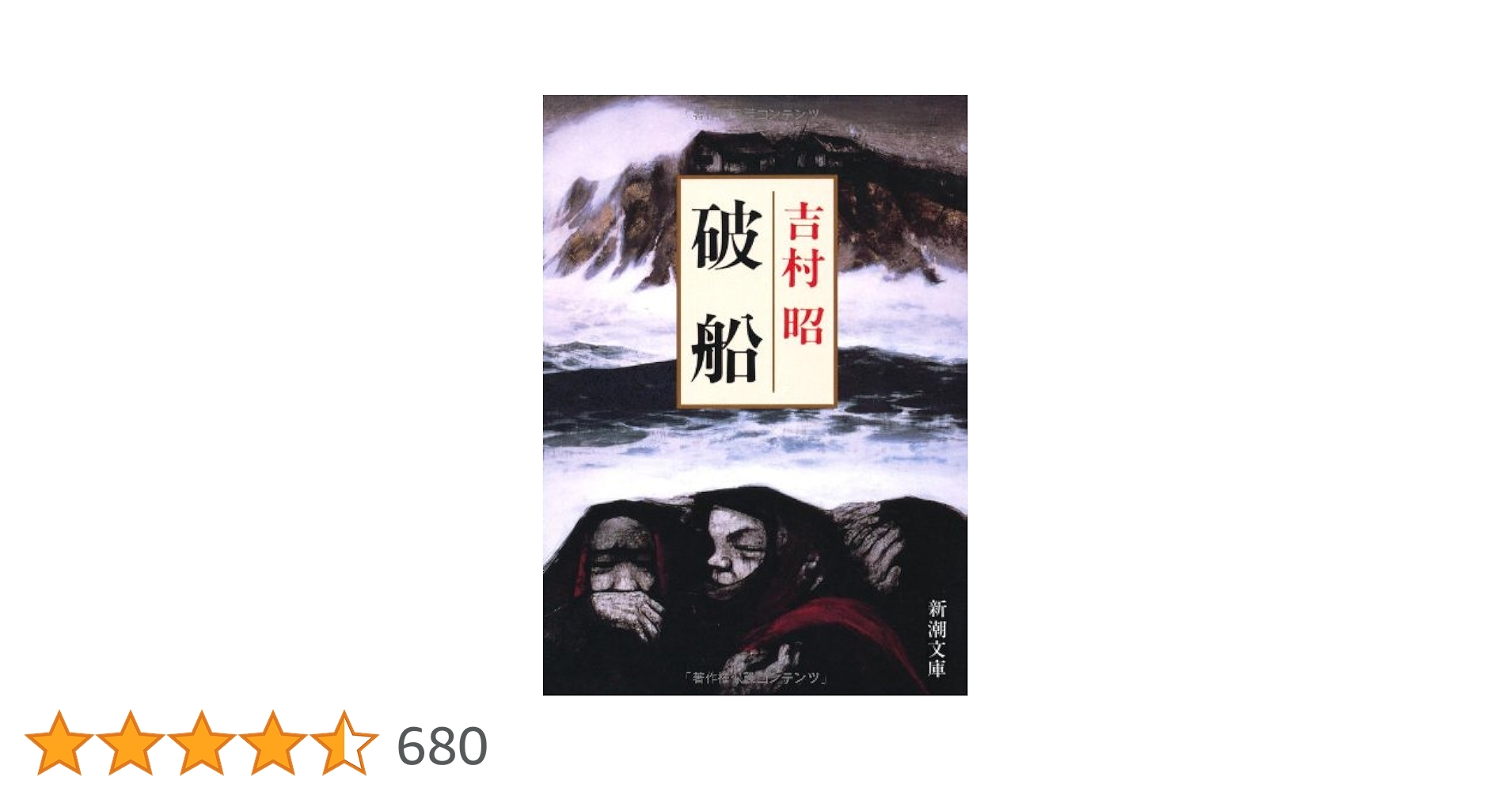
ランキングの最後を飾る20位は、閉鎖的な村の恐ろしい因習を描いた『破船』です。物語の舞台は、嵐で難破した船が積荷と共に浜に打ち上げられる「お船様」を恵みとして生きる村。ある日、村に流れ着いた一隻の船が、村の秩序を静かに狂わせていきます。
極限状況に置かれた人間のエゴや、集団心理の恐ろしさが、静かな筆致で淡々と描かれることで、かえって不気味さが際立ちます。人間の心の闇を覗き込むような、一度読んだら忘れられない強烈なインパクトを残す作品です。



本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。
吉村昭の小説で歴史の真実と人間の生き様を体感しよう
吉村昭の小説は、単なる歴史の解説書ではありません。徹底した取材によって掘り起こされた事実は、私たちに歴史のリアルな姿を突きつけ、その中で生きた人々の喜びや悲しみ、そして力強い生命力を伝えてくれます。
今回ご紹介した20作品は、いずれも吉村文学の魅力を存分に味わえる傑作ばかりです。気になる作品があれば、ぜひ手に取ってみてください。きっと、歴史の真実と人間の奥深さに触れる、忘れられない読書体験が待っているはずです。

