あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】泉鏡花の小説おすすめランキングTOP20

泉鏡花とは?今なお愛される幻想文学の巨匠
泉鏡花(いずみ きょうか)は、明治後期から昭和初期にかけて活躍した日本の小説家です。本名は泉鏡太郎(いずみ きょうたろう)といい、石川県金沢市で生まれました。小説だけでなく、戯曲や俳句も手掛け、その多才ぶりを発揮しました。
鏡花の作品は、幻想的で怪奇的な要素と、美しい日本語が織りなすロマン主義的な作風が特徴です。師である尾崎紅葉の影響を受けつつも、「鏡花調」と呼ばれる独自の流麗な文体を確立しました。彼の物語は、現実と非現実が交錯する幽玄な世界観や、母性への強い憧憬が描かれることが多く、今なお多くの読者を魅了し続けています。
【決定版】泉鏡花の小説おすすめランキングTOP20
ここからは、泉鏡花の数ある名作の中から、特におすすめの作品をランキング形式でご紹介します。
幻想的な戯曲から、切ない悲恋を描いた小説、読みやすい短編まで、さまざまな魅力を持つ作品がランクインしました。ぜひ、あなたのお気に入りの一冊を見つけて、鏡花文学の奥深い世界に触れてみてください。
1位: 『高野聖』
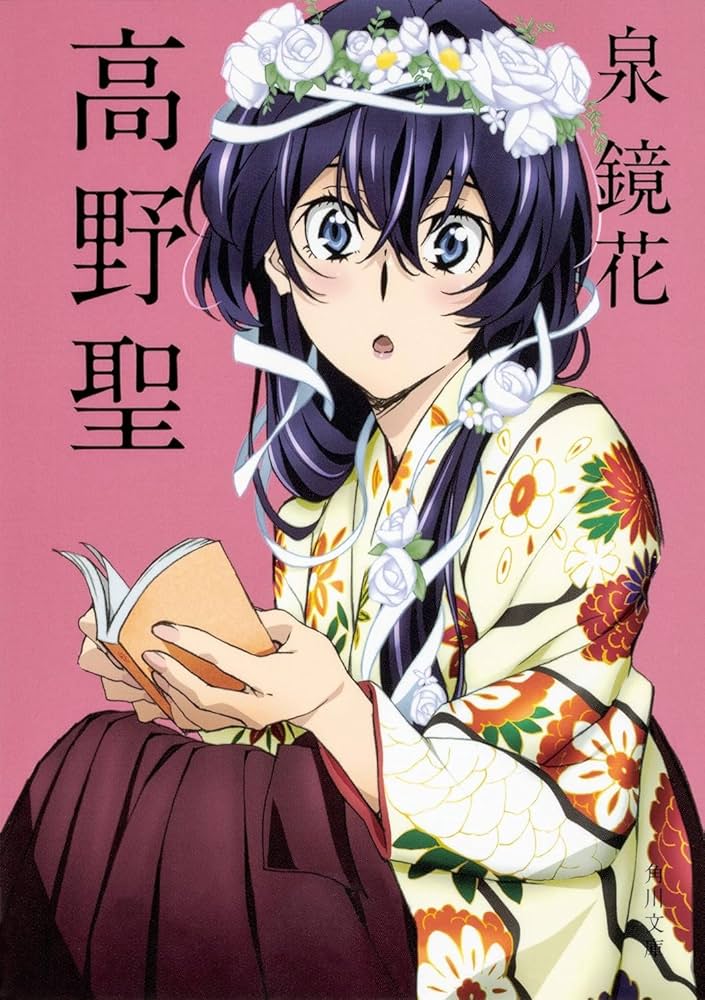
『高野聖』は、1900年に発表された泉鏡花の代表作の一つです。物語は、旅の僧侶が山中で道に迷い、妖艶な美女が一人で暮らす一軒家にたどり着くところから始まります。
この作品の魅力は、エロティシズムと怪奇的な雰囲気が融合した、幻想的な世界観にあります。美女の正体や、彼女が男たちを動物に変えてしまうという魔性の力、そして僧侶がその誘惑に打ち勝とうとする葛藤が、美しい自然描写とともに描かれています。泉鏡花の幻想文学の傑作として、今なお高く評価されています。
 ふくちい
ふくちい美女の正体が気になってドキドキしちゃった!自然の描写が美しくて、物語にぐっと引き込まれるよ。
2位: 『天守物語』
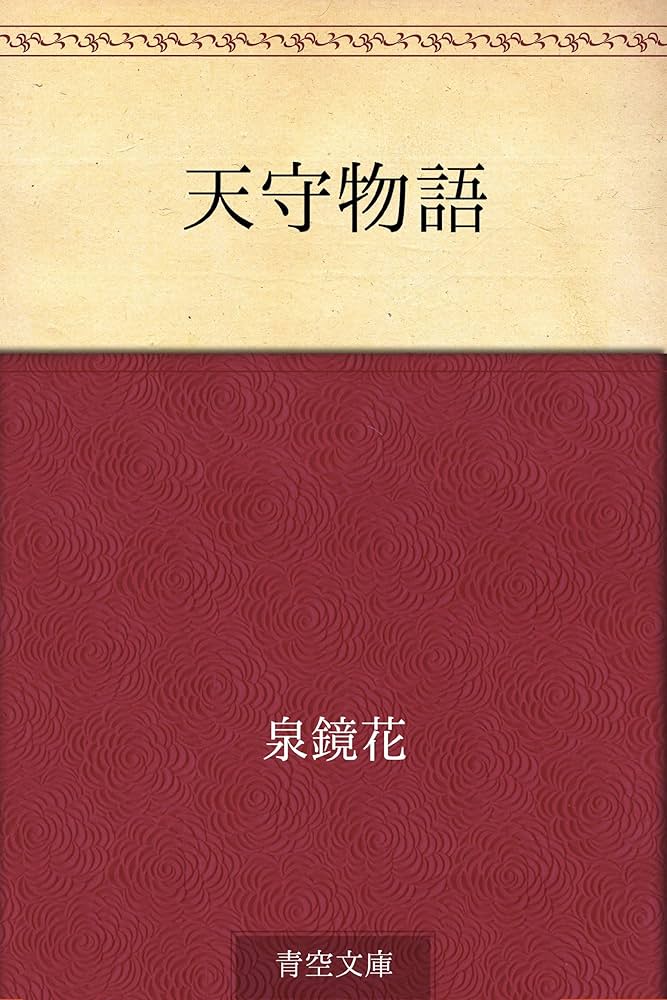
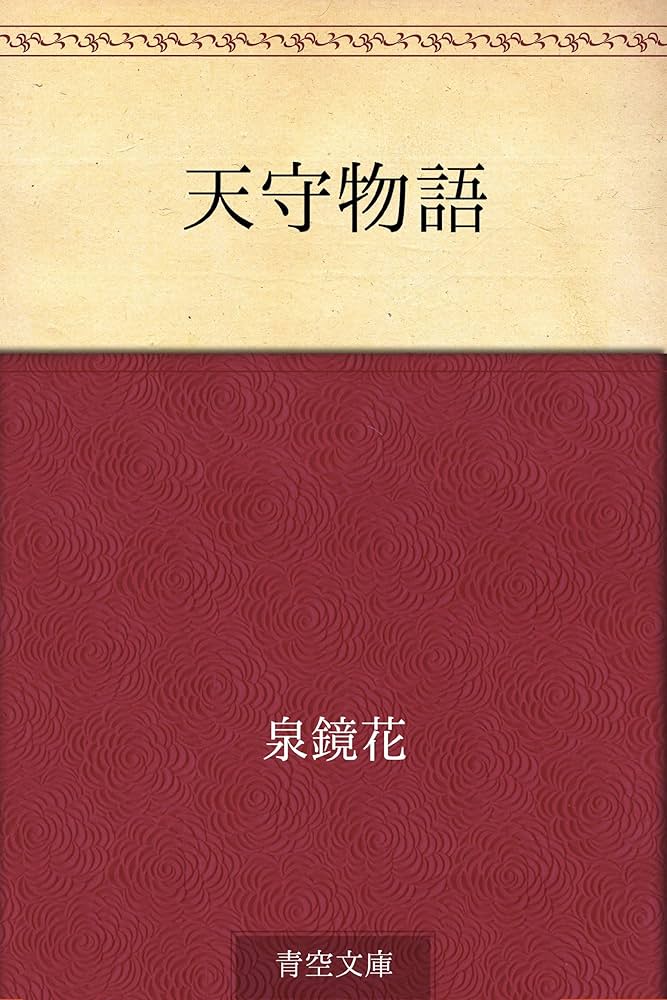
『天守物語』は、1917年に発表された戯曲で、泉鏡花の戯曲作品の中でも最高傑作と名高い作品です。物語の舞台は、姫路城の天守閣。そこに住む美しい異形の者たちの主・富姫と、人間の若き鷹匠・図書之助との許されざる恋を描いています。
人間と異界の住人という、決して結ばれることのない二人の切ない悲恋が、詩的で美しいセリフ回しによって綴られていきます。幻想的な設定の中にも、純粋な愛の姿が描かれており、多くの読者の心を打ちます。坂東玉三郎による舞台化も有名で、鏡花文学の美しい言葉の世界を堪能できる一作です。



人間とあやかしの恋、切なすぎるよ…。富姫の一途な想いに涙が出ちゃった。
3位: 『夜叉ケ池』
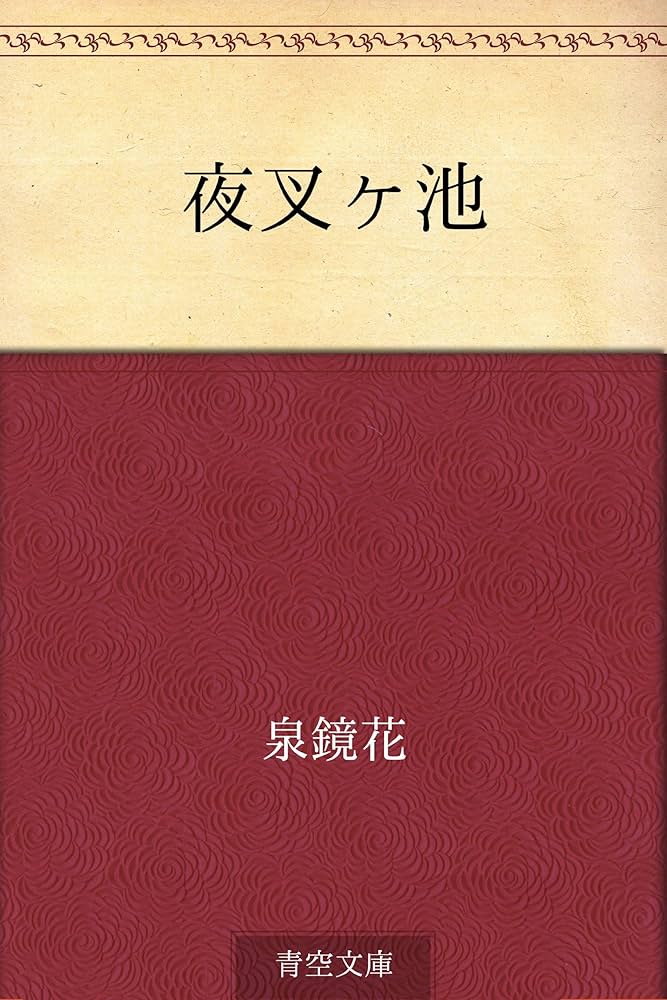
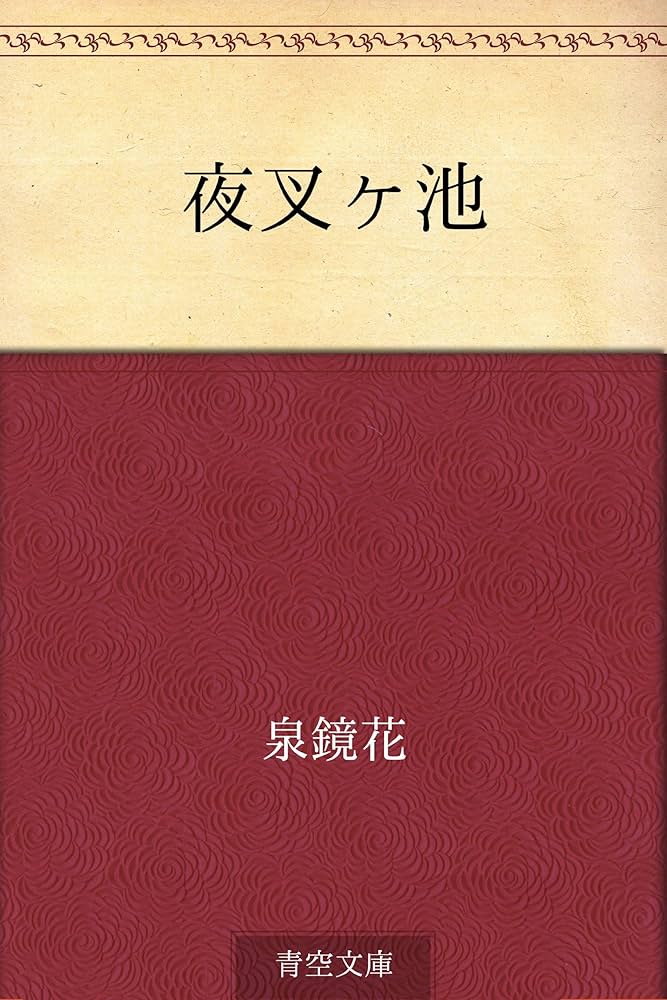
『夜叉ケ池』は、1913年に発表された戯曲で、人間と異界の者との交流を描いた幻想的な物語です。物語の中心となるのは、竜神が封じられていると伝えられる「夜叉ケ池」の伝説。
村の鐘を日に三度撞くことで竜神の怒りを鎮めているという掟があり、もし破られれば村は洪水で沈んでしまうとされています。この伝説を背景に、鐘楼守の男と竜神の化身である姫との悲恋、そして自己犠牲のテーマが壮大に描かれます。幻想的な世界観と、登場人物たちの強い意志が織りなすドラマが魅力の作品です。



竜神の伝説ってワクワクするよね!自己犠牲をテーマにした壮大な愛の物語に感動しちゃった。
4位: 『外科室』
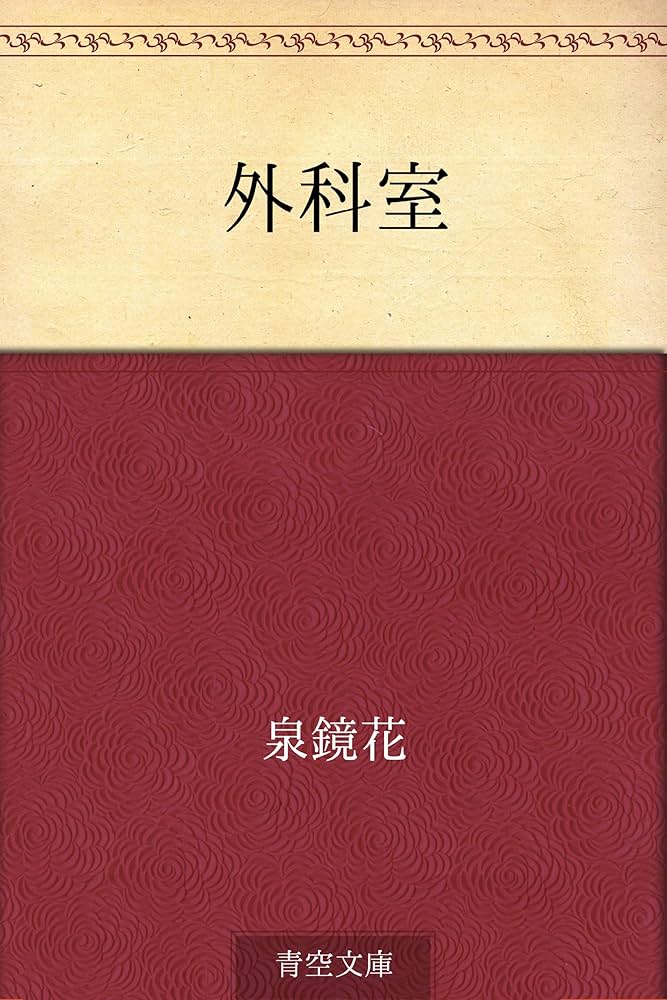
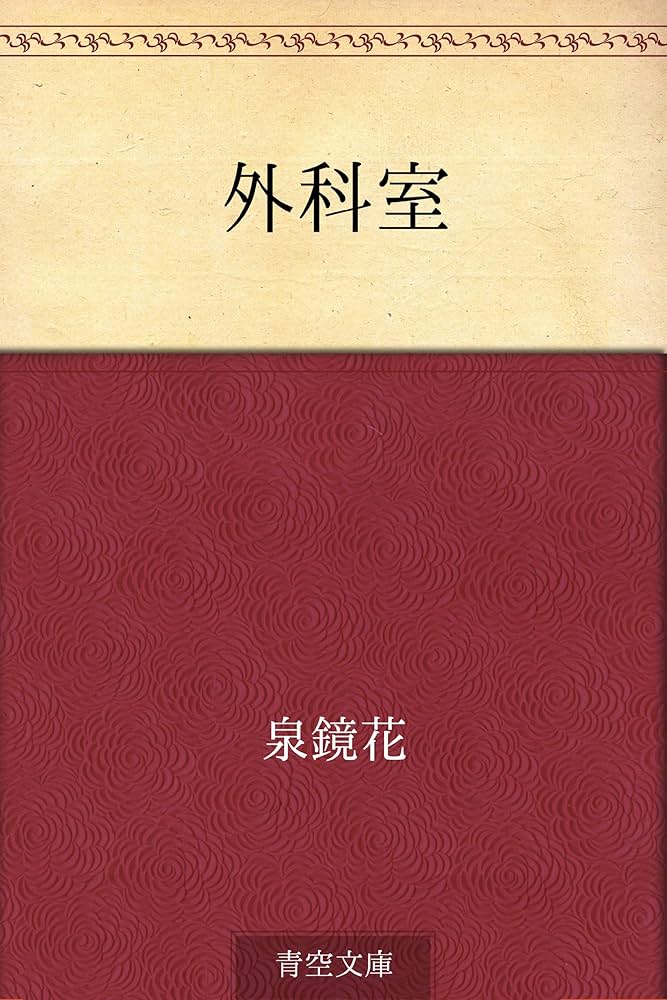
『外科室』は、1895年に発表された泉鏡花の初期の短編小説です。この作品は「観念小説」と呼ばれ、鏡花の出世作の一つとなりました。物語は、伯爵夫人が胸の手術を受ける場面から始まりますが、彼女は「秘密を漏らしてしまうから」と頑なに麻酔を拒否します。
執刀医は、彼女が9年前に一度だけ出会い、一目惚れした相手でした。言葉を交わさずとも通じ合う二人の純粋で一途な愛が、手術室という緊迫した空間で、衝撃的な結末へと向かっていきます。社会的な身分や制度を超えた、愛の至高の形を描いた作品として、強い印象を残します。



言葉を交わさなくても通じ合う愛ってすごい…。でも、結末が衝撃的すぎて胸が苦しいよ。
5位: 『婦系図』
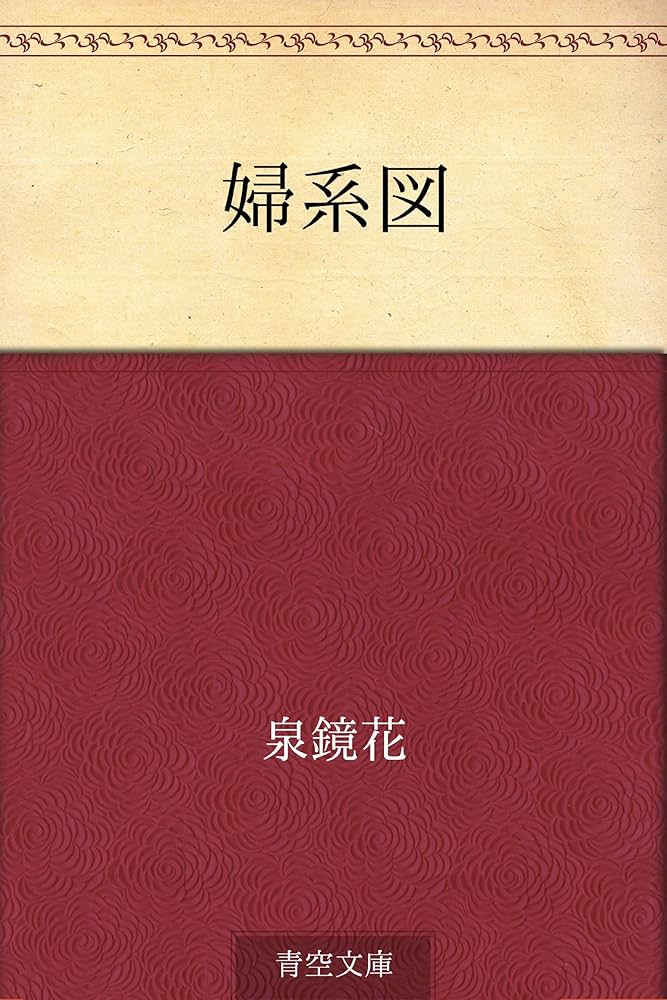
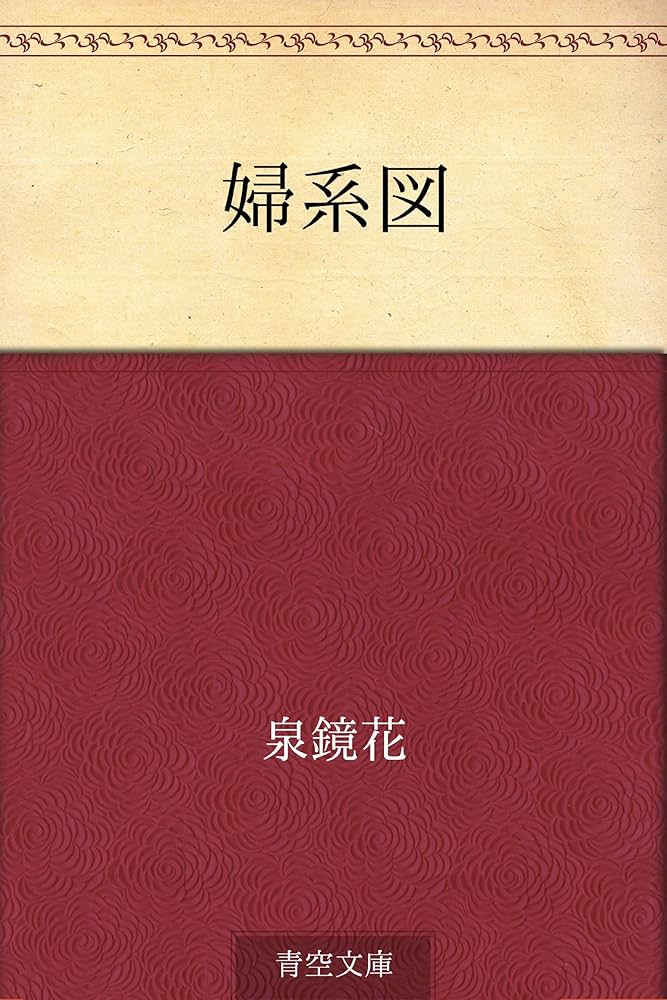
『婦系図』は、1907年に発表された小説で、新派悲劇の代表作として何度も舞台化や映画化がされてきました。物語は、学者である早瀬主税と、彼を支える元芸者のお蔦との悲恋を描いています。
主税は、恩師への義理と、お蔦への愛情との間で深く葛藤します。特に、湯島天神の境内でお蔦が主税に別れを告げる場面は非常に有名で、「別れろ切れろは芸者の時に言う言葉」というセリフは多くの人の涙を誘いました。社会的な制約の中で愛を貫こうとする二人の姿が、美しくも切なく描かれた名作です。



有名な「別れろ切れろは〜」のセリフ、ぐっときちゃう。お蔦の覚悟を思うと涙なしには読めないよ。
6位: 『歌行燈』
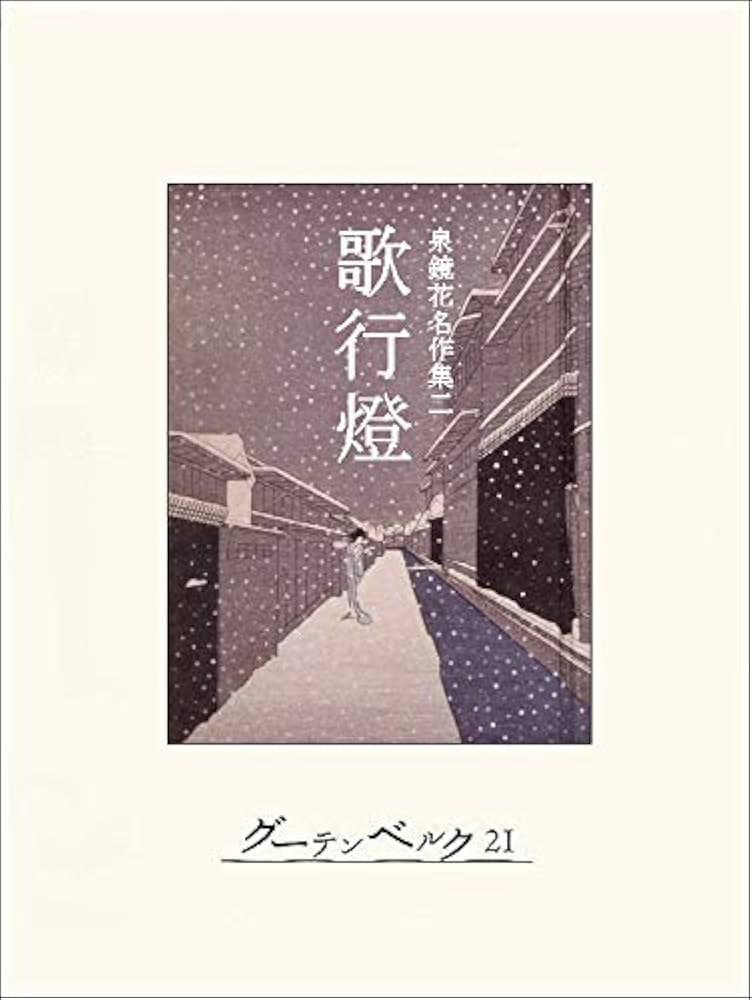
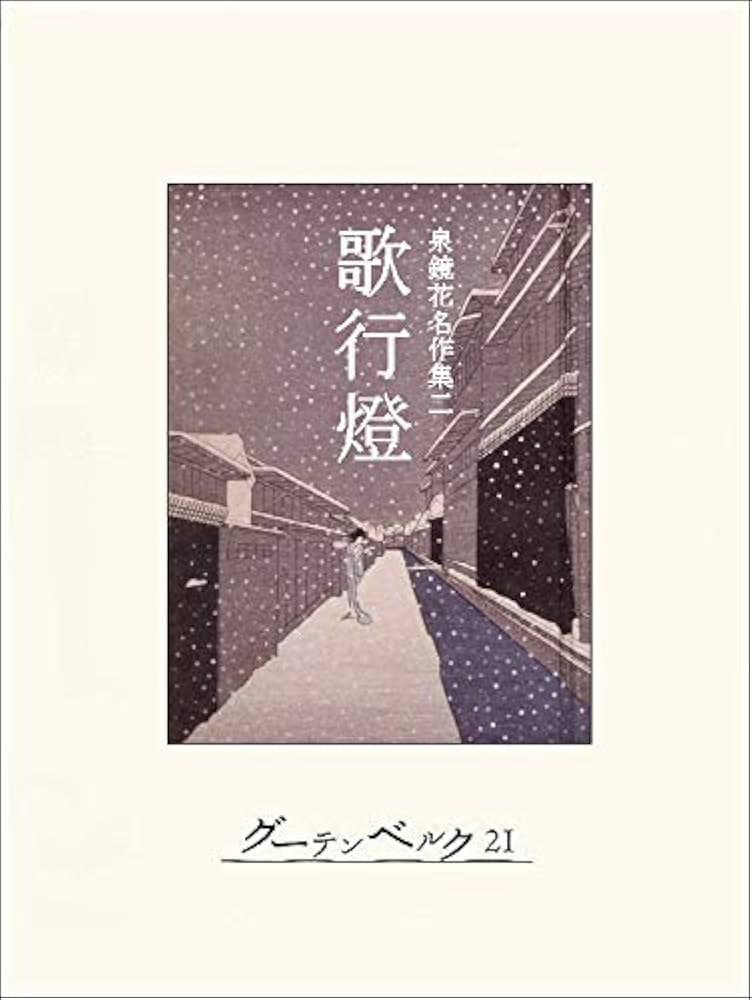
『歌行燈』は1910年に発表された小説で、芸の道に生きる人々の葛藤とプライドを描いた作品です。物語の中心となるのは、かつて能楽界で将来を嘱望されながらも、ある事件がきっかけで破門された能役者・恩地喜多八です。
彼は、過去の因縁によって巡り合った人々と関わる中で、再び芸の道と向き合うことになります。能楽という日本の伝統芸能を背景に、芸の厳しさと、それを通じて魂が救済されていく様が描かれています。泉鏡花の芸術至上主義的な思想が色濃く反映された、格調高い物語です。



芸の道の厳しさと誇りが伝わってくるよ。静かな感動が心にじんわり広がる物語なんだ。
7位: 『草迷宮』
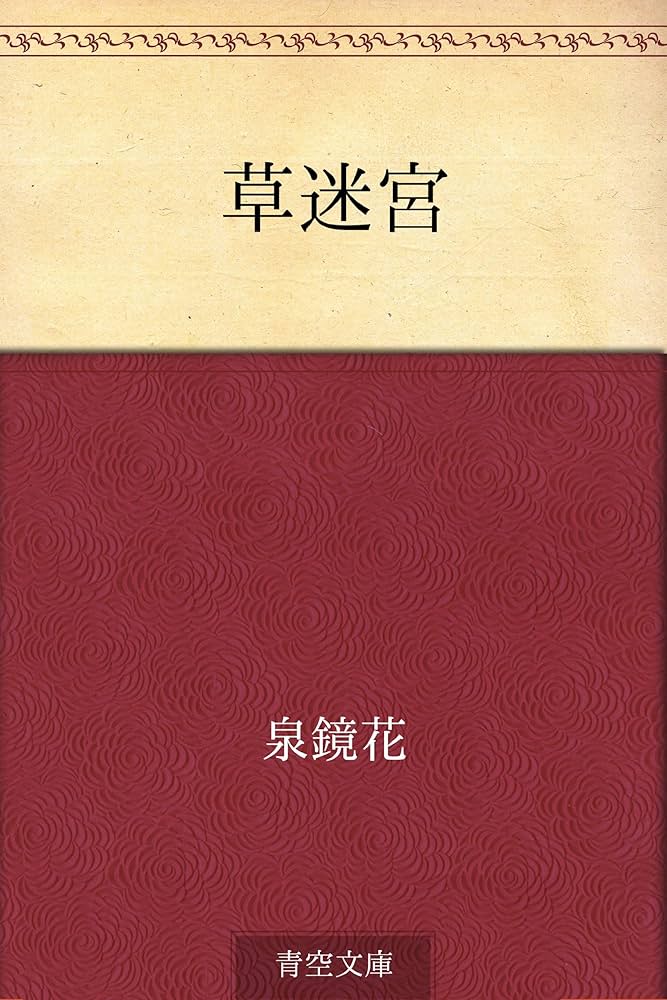
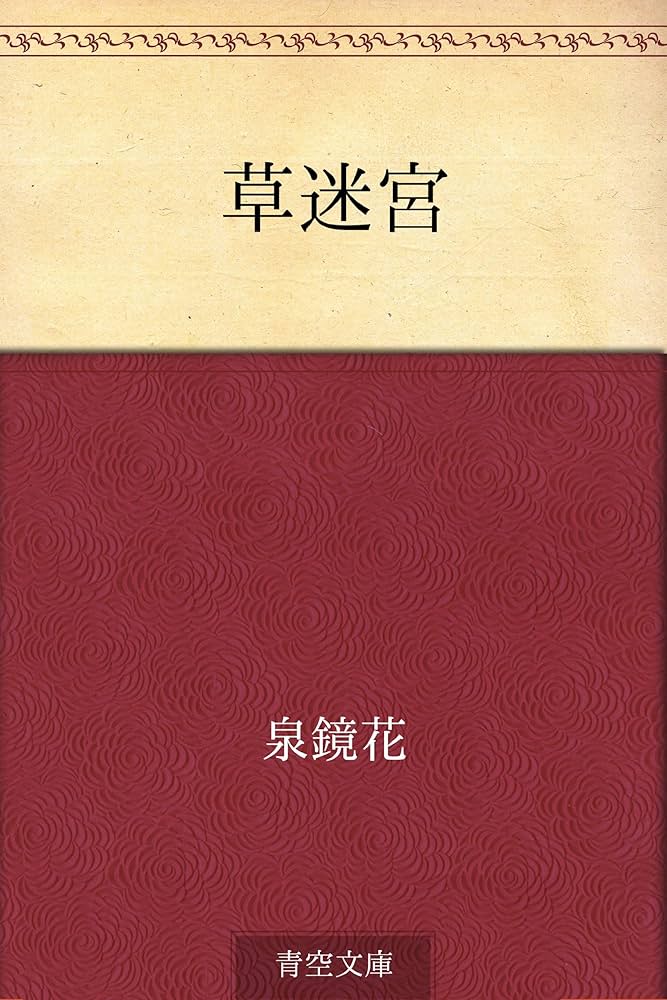
『草迷宮』は1908年に発表された、泉鏡花の幻想小説の代表作の一つです。物語は、旅の青年・葉越明が、幼い頃に亡き母から聞いた手毬唄の謎を追い求めて旅をするというもの。彼は「草迷宮」と呼ばれる怪異が起こる屋敷にたどり着きます。
この作品の魅力は、現実と幻想、過去と現在が入り混じる迷宮のような世界観です。母への思慕の念が、物語全体を幻想的でどこか懐かしい雰囲気に包み込んでいます。読者もまた、明とともに不思議な世界に迷い込んだかのような感覚を味わうことができるでしょう。



本当に迷宮に迷い込んだみたいな不思議な感覚になるんだ。手毬唄の謎が気になって一気に読んじゃったよ。
8位: 『春昼・春昼後刻』
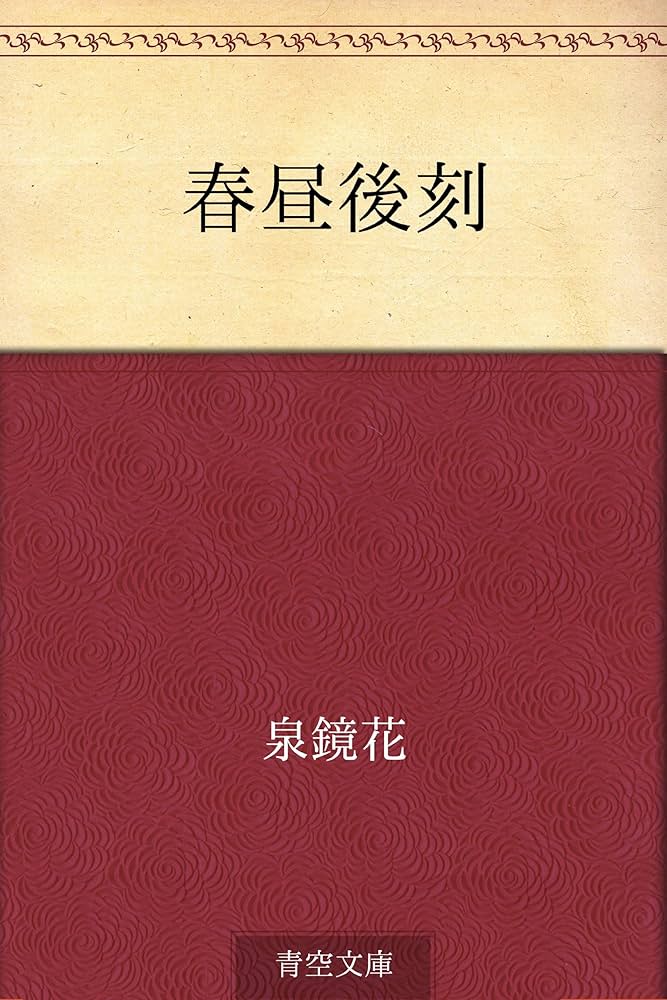
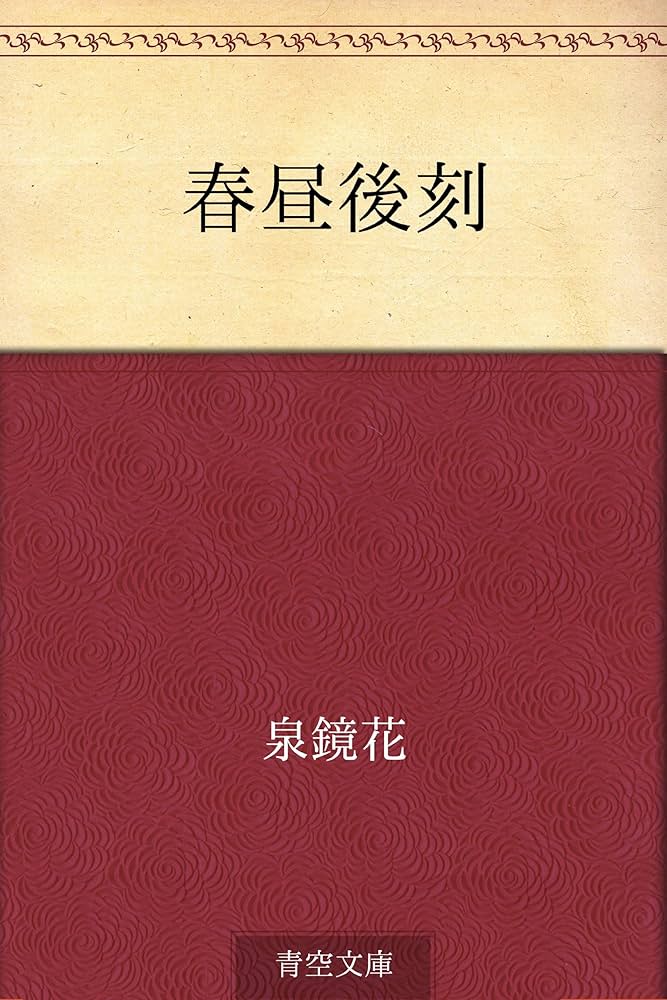
『春昼』とその続編である『春昼後刻』は、1906年に発表された怪談風味の幻想小説です。物語は、主人公が不思議な屋敷に迷い込み、そこで出会う美しい女性たちとの奇妙な体験を描いています。
この作品は、夢と現実の境界が曖昧模糊とした世界観が特徴です。登場する女性たちは、この世の者とは思えないほどの美しさと妖しさをまとっており、読者を不安で幻想的な気分にさせます。泉鏡花ならではの、美しくもどこか恐ろしい物語の世界を堪能できる一作です。



夢か現か判然としない世界観の構築が見事である。読者の不安を煽る語り口は、まさに鏡花文学の真骨頂と言えよう。
9位: 『化鳥』
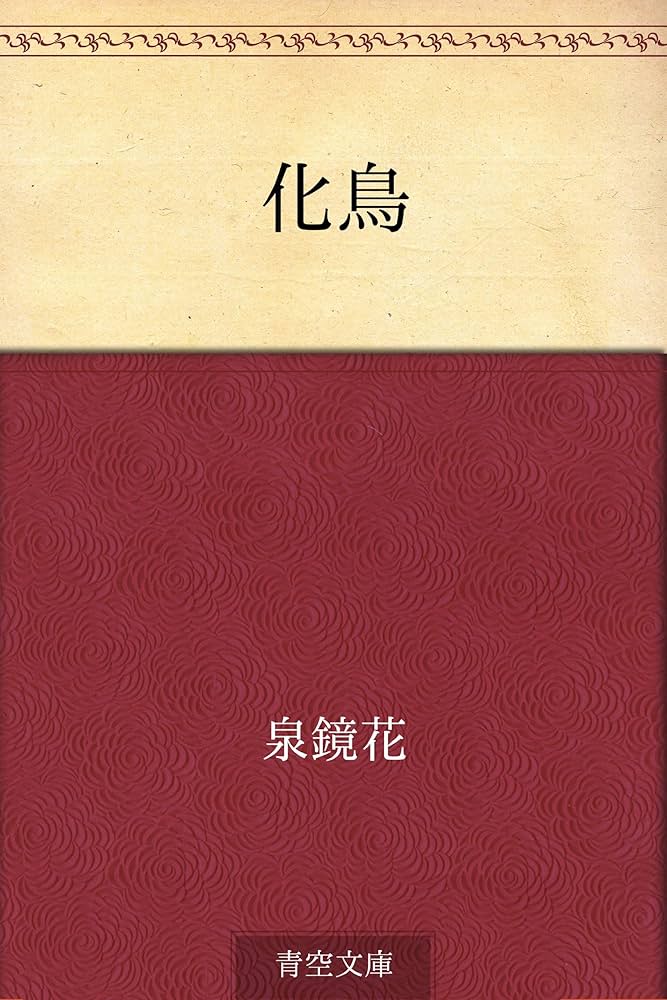
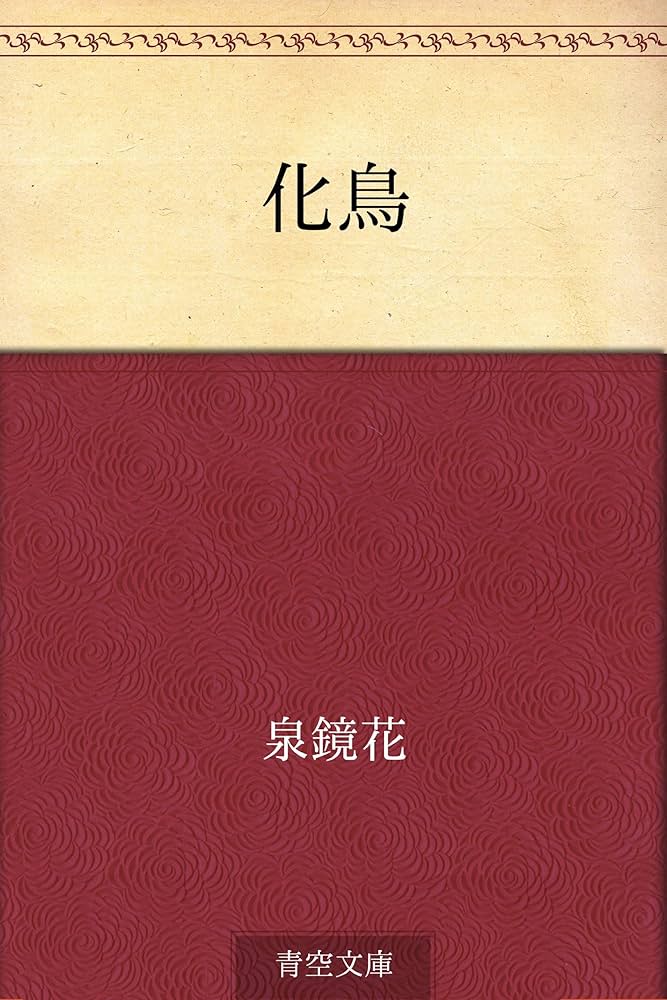
『化鳥』は1897年に発表された短編小説で、泉鏡花が初めて口語体で書いた作品としても知られています。物語は、橋のたもとで暮らす少年・廉と母親の視点から描かれます。彼らは、橋を行き交う人々を鳥や獣に見立てて暮らしていました。
ある日、川に落ちた廉は、羽の生えた美しい「姉さん」に助けられます。この人間と異界の者との交流と、母への強い思慕の念が、美しくもどこか切ない筆致で描かれています。幻想的ながらも、少年の純粋な心が胸を打つ物語です。



異界の者との交流って、どうしてこんなに切ないんだろう…。少年の純粋な心に胸を打たれたよ。
10位: 『日本橋』
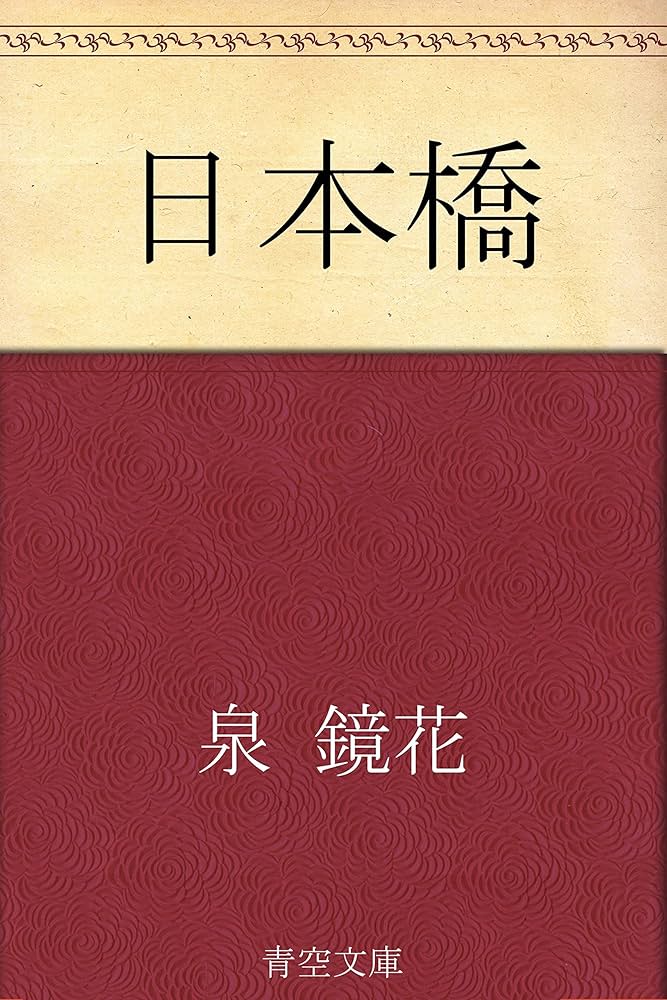
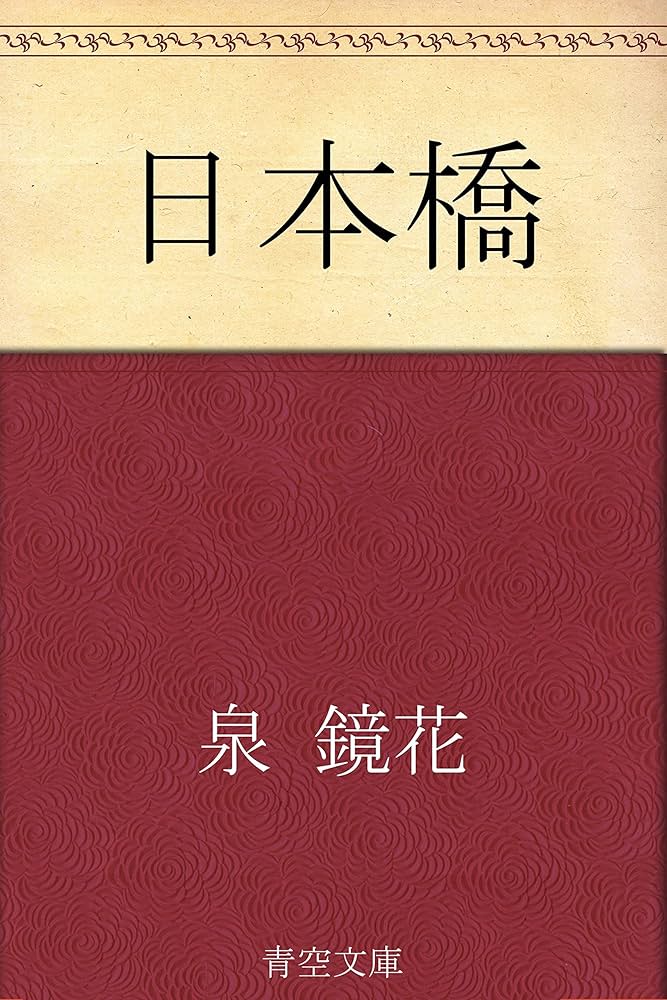
1914年に発表された戯曲『日本橋』は、江戸情緒あふれる日本橋を舞台に、芸者たちの生き様を鮮やかに描いた作品です。物語の中心となるのは、二人の人気芸者、お孝と清葉、そして彼女たちが思いを寄せる医学士・葛木です。
芸者たちの意地やプライド、そして淡い恋心が、華やかな世界の裏側で繰り広げられます。登場人物たちの粋なセリフ回しや、当時の花柳界の雰囲気が巧みに表現されており、読者を江戸の世界へと引き込みます。女性たちの強く美しい生き様が印象的な作品です。



芸者さんたちの意地とプライドがぶつかり合うのがかっこいい!華やかな世界の裏側を覗けるのが面白いよ。
11位: 『海神別荘』
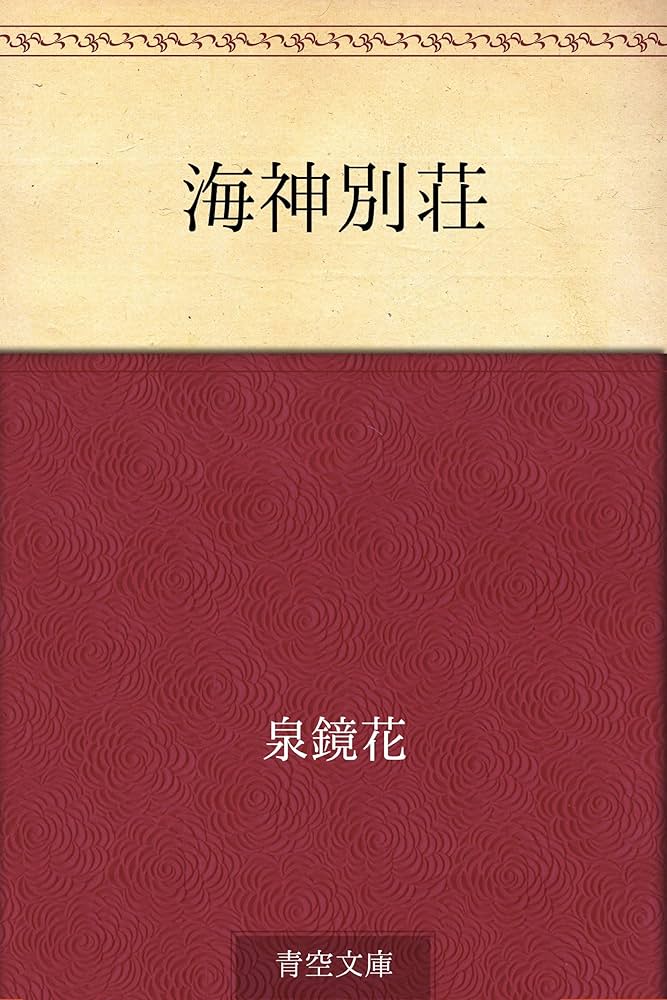
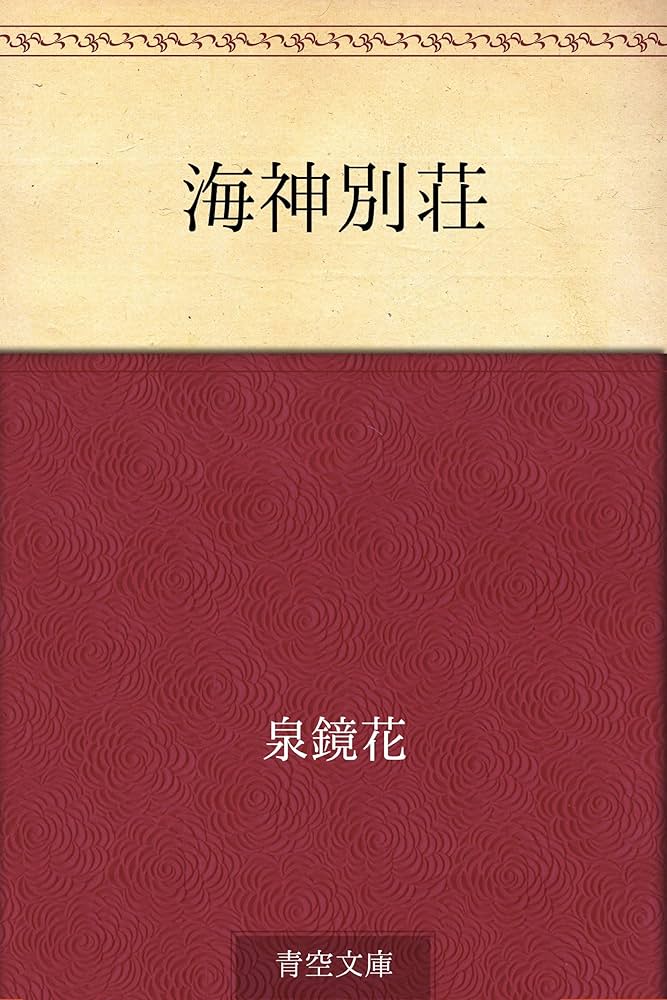
『海神別荘』は1914年に発表された戯曲で、異類婚姻譚の一つです。物語は、人柱として海の神の世継ぎである公子のもとへ嫁ぐことになった美女が主人公。海底の美しい別荘で、彼女は故郷を思い、人間界へ戻ろうとしますが、そこには厳しい現実が待っていました。
陸に戻った彼女の姿は、家族にも分からぬほど変わり果てていたのです。人間界と異界との隔絶と、それを受け入れて愛に生きることを決意する美女の姿が幻想的に描かれます。坂東玉三郎によって『天守物語』『夜叉ヶ池』とともに「泉鏡花三部作」として上演されています。



最初は悲しい運命だと思ったけど、愛を選んだ彼女は強いね。幻想的な世界観がすごく素敵だよ。
12位: 『義血侠血』
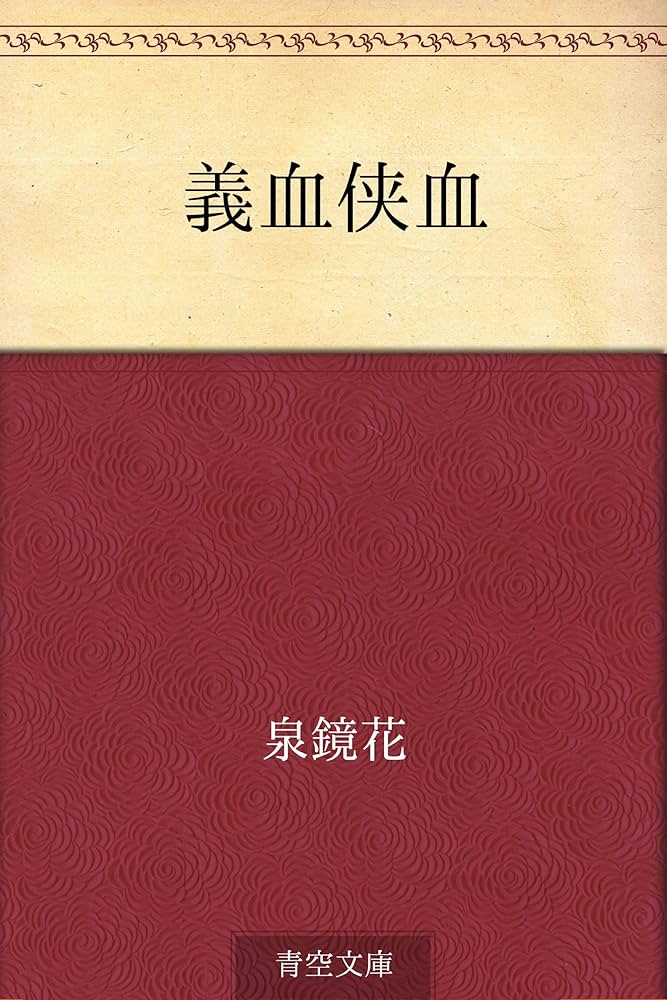
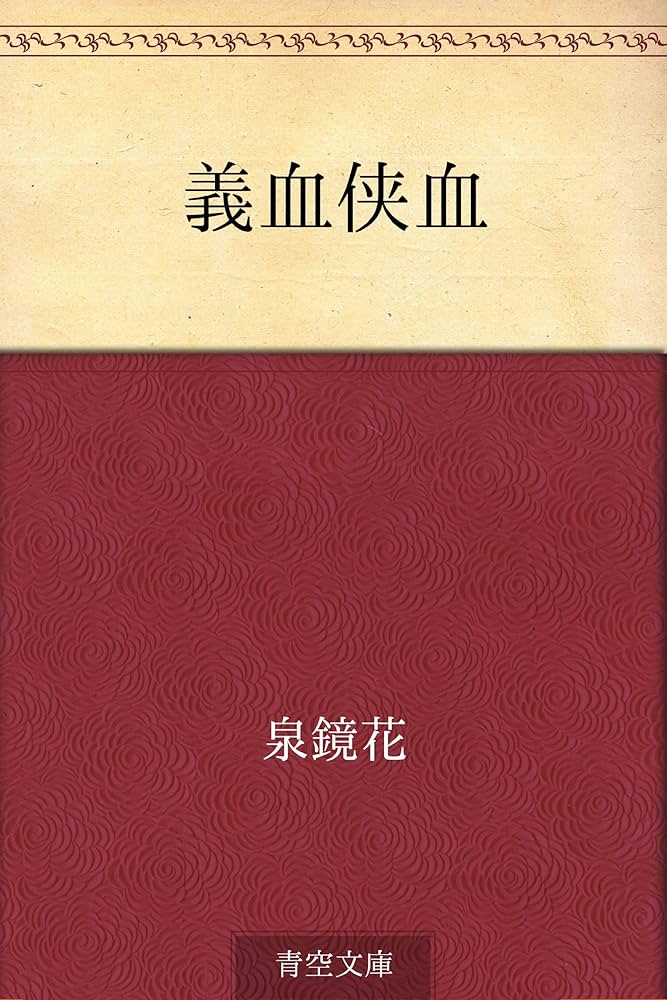
『義血侠血』は1894年に発表された泉鏡花の初期の短編小説です。物語の主人公は、水芸の太夫として人気の滝の白糸。彼女は、法律家を目指す貧しい青年・村越欣弥と出会い、彼の学費を援助することを約束します。
しかし、運命のいたずらにより、白糸は強盗殺人の罪を犯してしまいます。そして、彼女を裁く法廷に現れたのは、立派な検事となった欣弥でした。純粋な愛情と自己犠牲の精神が、皮肉な運命によって悲劇へと転じていく様が描かれた、美しくも切ない物語です。



純粋な気持ちが悲劇につながるなんて、運命が残酷すぎるよ…。あまりにも切なくて涙が止まらないんだ。
13位: 『照葉狂言』
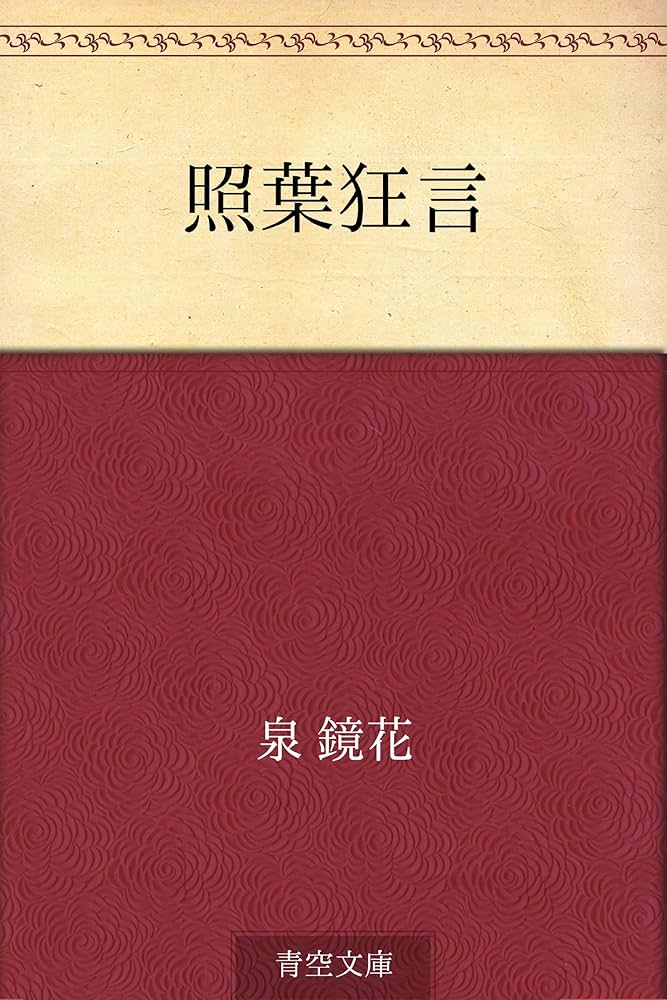
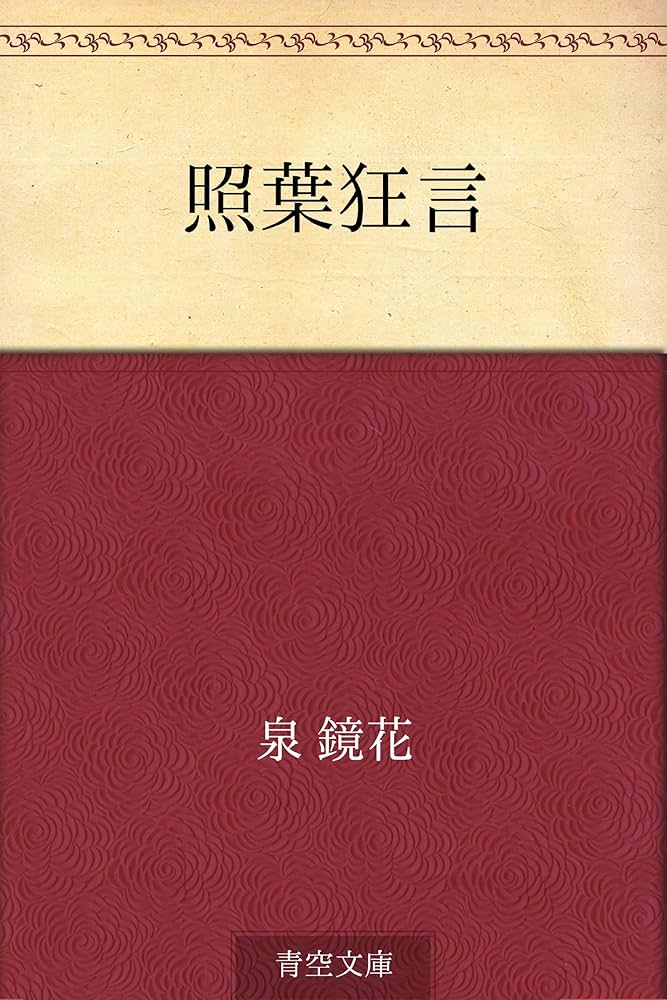
『照葉狂言』は、泉鏡花が1896年に発表した小説です。物語は、孤児の少年・貢と、彼が慕う年上の女性お雪、そして彼を庇護する照葉狂言一座の師匠・小親との関係を描いています。
この作品は、身分違いの恋や、純粋な心が引き起こす悲劇がテーマとなっています。鏡花特有の美しい言葉遣いと、幻想的な雰囲気が物語全体を包み込んでおり、登場人物たちの繊細な心情が巧みに表現されています。美しくも儚い、夢のような世界観が魅力の一作です。



純粋な心が悲劇を招いてしまうのが切ないね。儚くて美しい、夢みたいな物語だよ。
14位: 『竜潭譚』
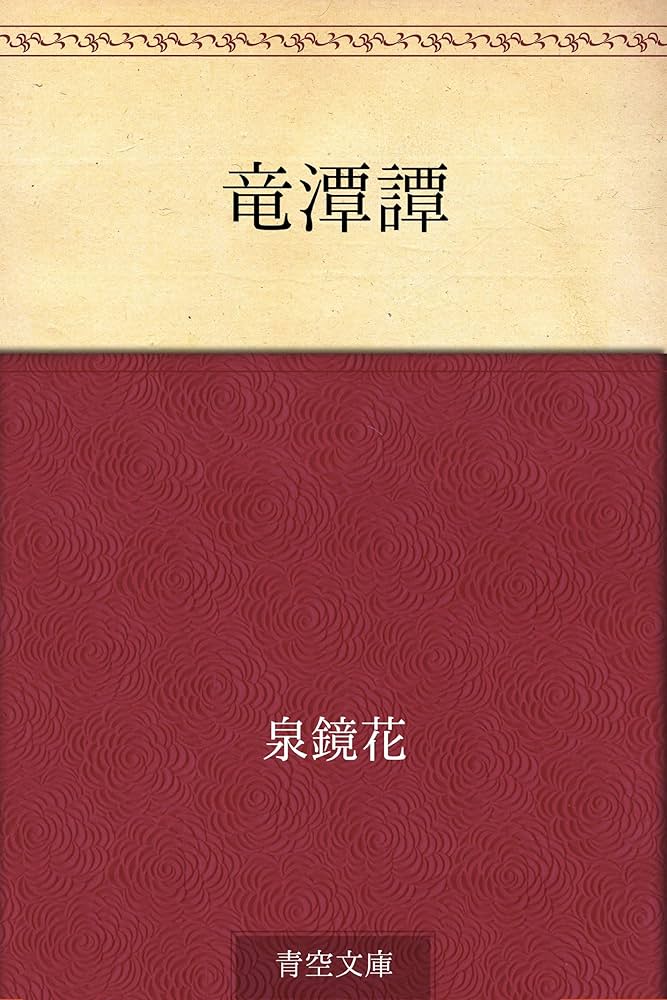
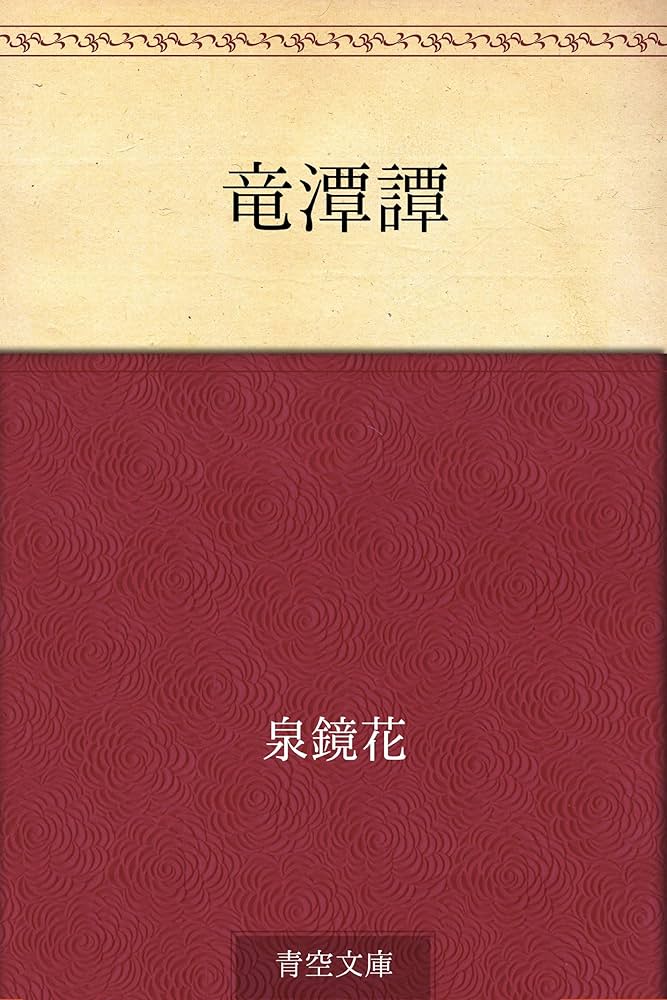
『竜潭譚』は1896年に発表された小説で、母を亡くした幼い少年・千里が体験する不思議な出来事を描いた物語です。美しい毒虫に刺されて顔が醜く変わってしまった千里は、道に迷い、神隠しにあったと噂される山奥の谷で美しい女性に助けられます。
この作品は、亡き母への思慕と、幻想的な異界への憧れが色濃く反映されています。子供の視点から描かれる、現実と幻想が入り混じった世界は、どこか懐かしくも恐ろしい雰囲気を漂わせています。鏡花の描く母性への憧憬が感じられる一作です。



神隠しの話って、ちょっと怖いけどワクワクしちゃう!わたしも不思議な世界に迷い込んでみたいかも。
15位: 『眉かくしの霊』
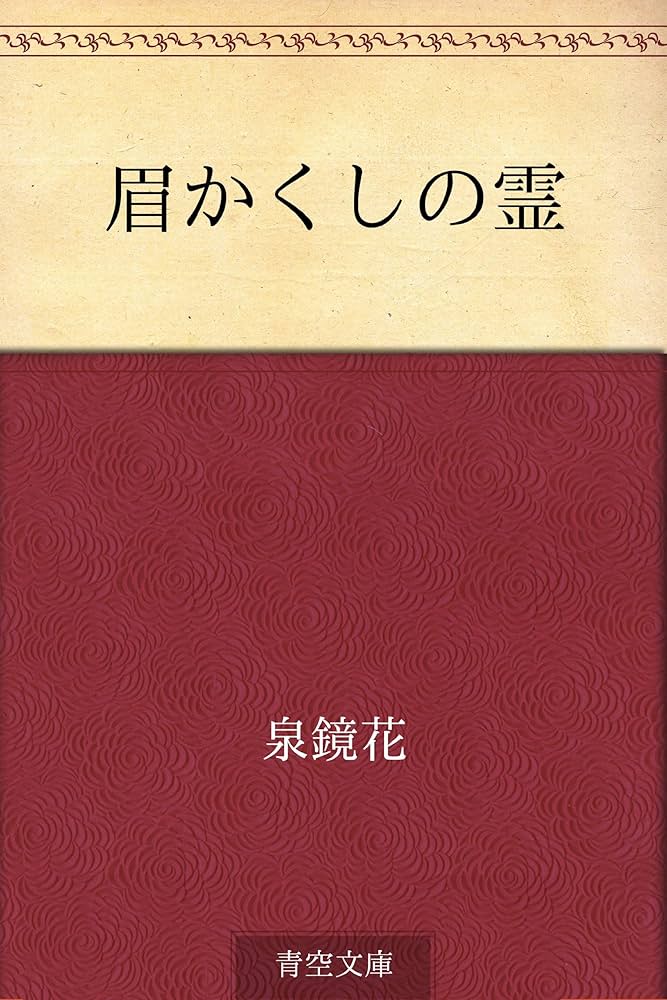
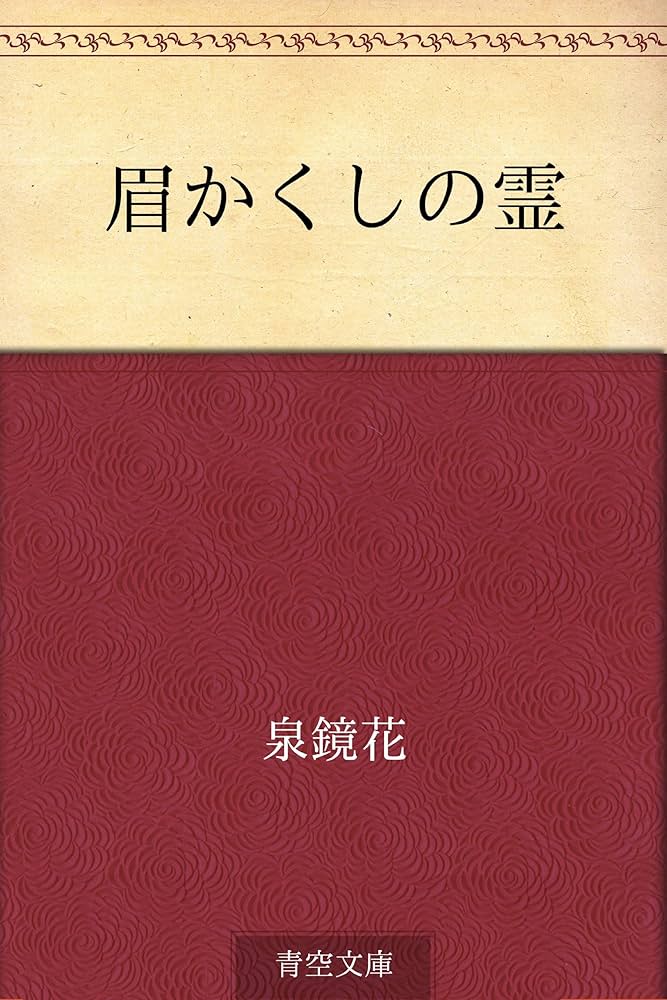
『眉かくしの霊』は、怪談や伝承を題材にした幻想的な物語です。物語は、ある旧家に伝わる「眉をかくした花嫁の幽霊」の伝説を軸に展開します。
この作品の魅力は、日本の伝統的な怪談話のような、じっとりとした恐怖と美しさが融合した独特の雰囲気にあります。泉鏡花らしい流麗な文体で描かれる幽霊の姿は、恐ろしくもどこか妖艶で、読者を物語の世界に深く引き込みます。夏の夜に読むのにぴったりの、涼しくなれる一作です。



本作における幽霊の描写は、単なる恐怖の対象としてではなく、美と哀愁を帯びた存在として描かれている。その造形は、日本古来の美意識と怪奇趣味の融合体として極めて完成度が高い。
16位: 『湯島詣』
『湯島詣』は、明治時代の東京・湯島を舞台にした物語で、芸者・蝶吉の視点から描かれます。この作品は、鏡花の妻となった元神楽坂の芸妓・すずがモデルの一人と言われています。
物語は、蝶吉が湯島天神へ願掛けに訪れる場面を中心に、花柳界に生きる女性の日常や恋愛模様をリアルに描き出しています。当時の風俗や人情が色濃く反映されており、鏡花の作品の中でも比較的写実的な作風が特徴です。江戸情緒の残る東京の街並みと、そこで生きる人々の姿が生き生きと描かれています。



明治時代の東京の雰囲気が伝わってきて面白いよ。蝶吉さんの恋を応援したくなっちゃうんだ。
17位: 『黒百合』
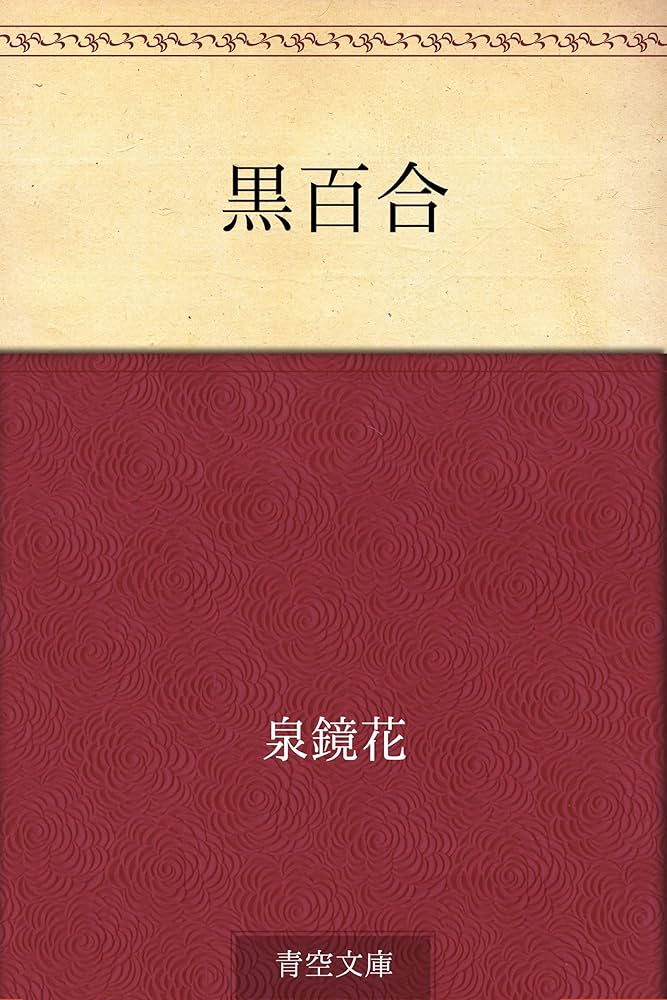
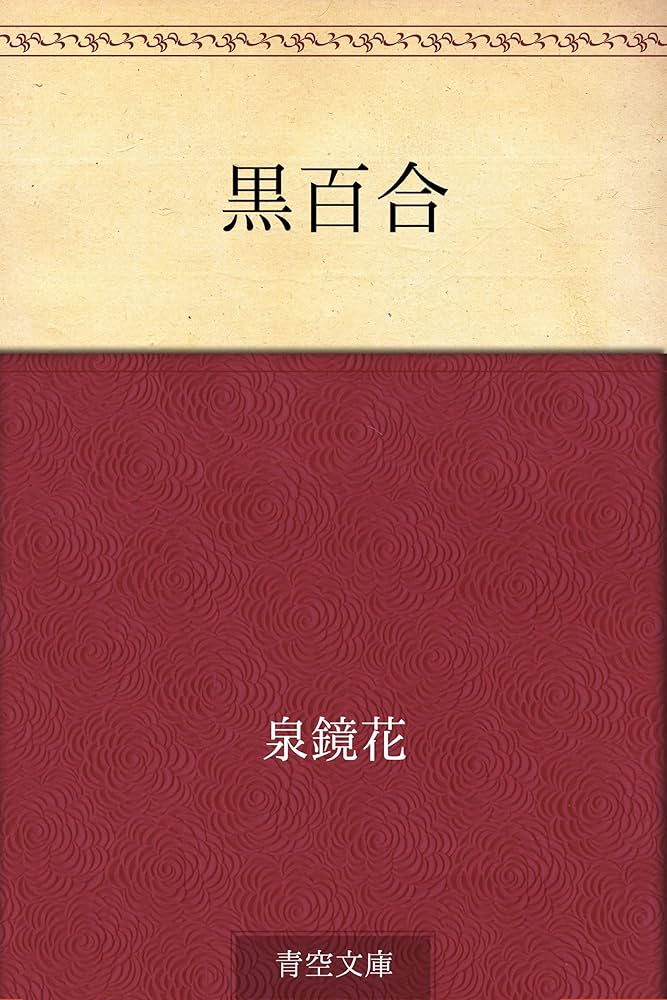
『黒百合』は、人間の心の奥底に潜む情念や狂気を描いた物語です。物語の中心となるのは、ある女性の嫉妬心。その強い思いが、やがて恐ろしい出来事を引き起こしていきます。
この作品は、人間の内面の闇を、幻想的かつ象徴的に描き出している点が特徴です。「黒百合」という花が、物語全体を通して不吉で妖艶なイメージを放ち、読者の不安をかき立てます。愛憎が渦巻く、鏡花の描くダークな世界観に触れることができる一作です。



嫉妬という感情の持つ破壊的なエネルギーが、黒百合というモチーフを通して巧みに表現されている。人間の心理の深淵を覗き見るような作品だ。
18位: 『註文帳』
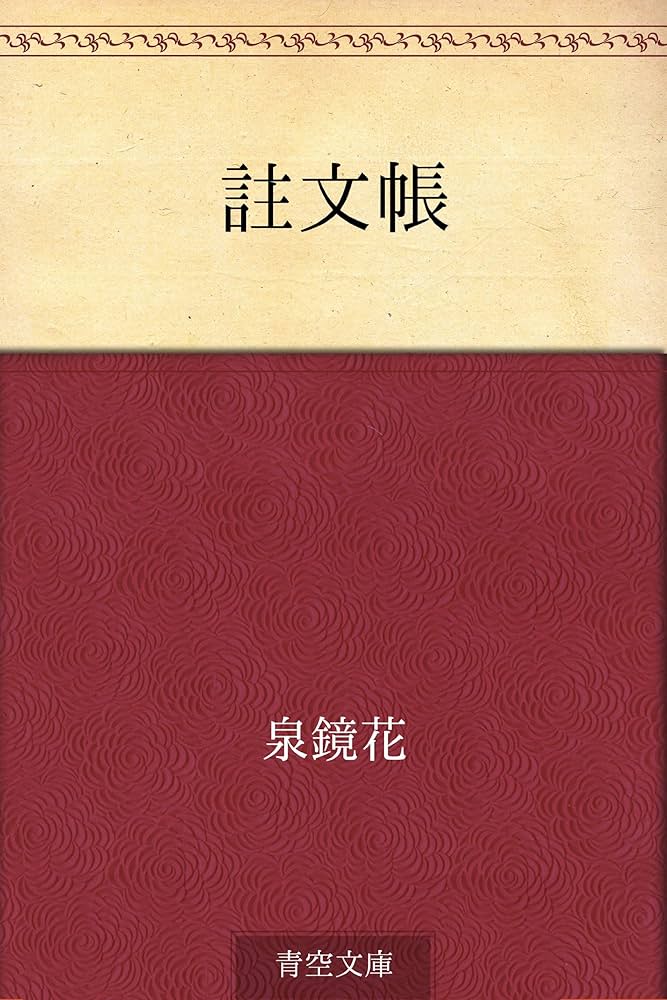
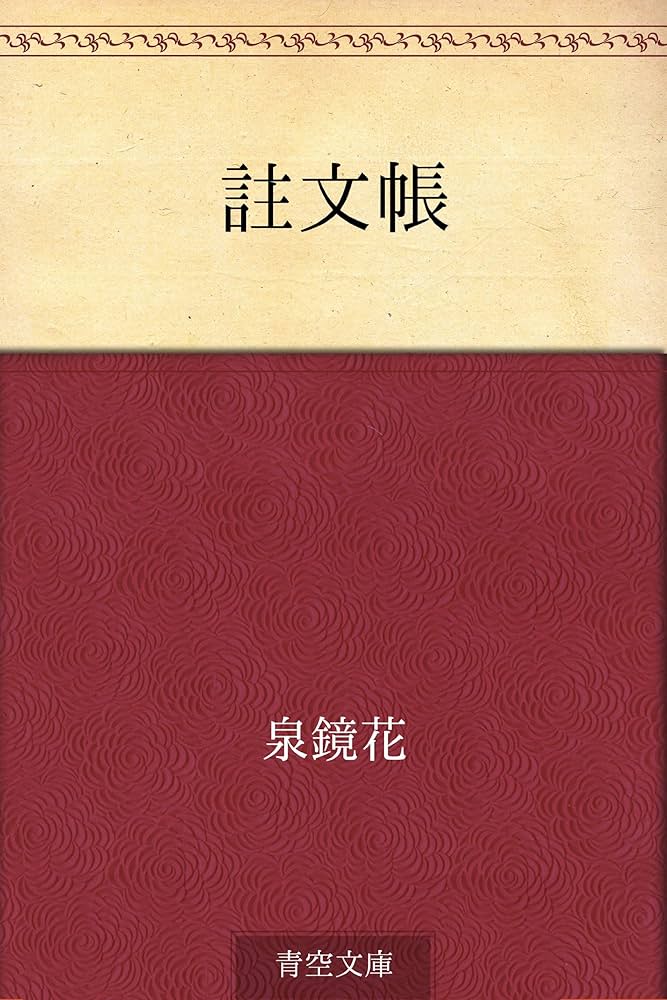
『註文帳』は、吉原遊廓を舞台にした物語です。主人公は、吉原で働く剃刀研ぎ職人の五助。彼は、ある理由から毎月十九日の仕事を固く断っていました。
物語は、五助がなぜその日を特別視するようになったのか、その過去の出来事を解き明かしていく形で進みます。遊郭という華やかな世界の裏にある、人々の悲しみや宿命が、鏡花らしい筆致で描かれています。ミステリアスな展開と、切ない結末が心に残る作品です。



なぜその日だけ仕事をしないのか、謎が気になって一気に読んじゃった。理由がわかると本当に切ないよ。
19位: 『海の使者』
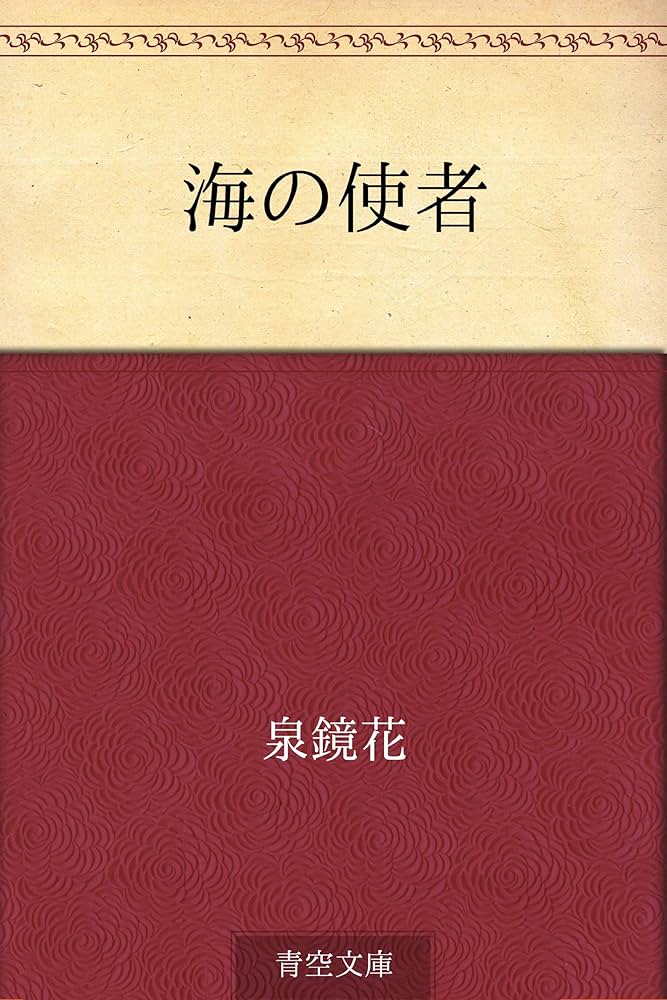
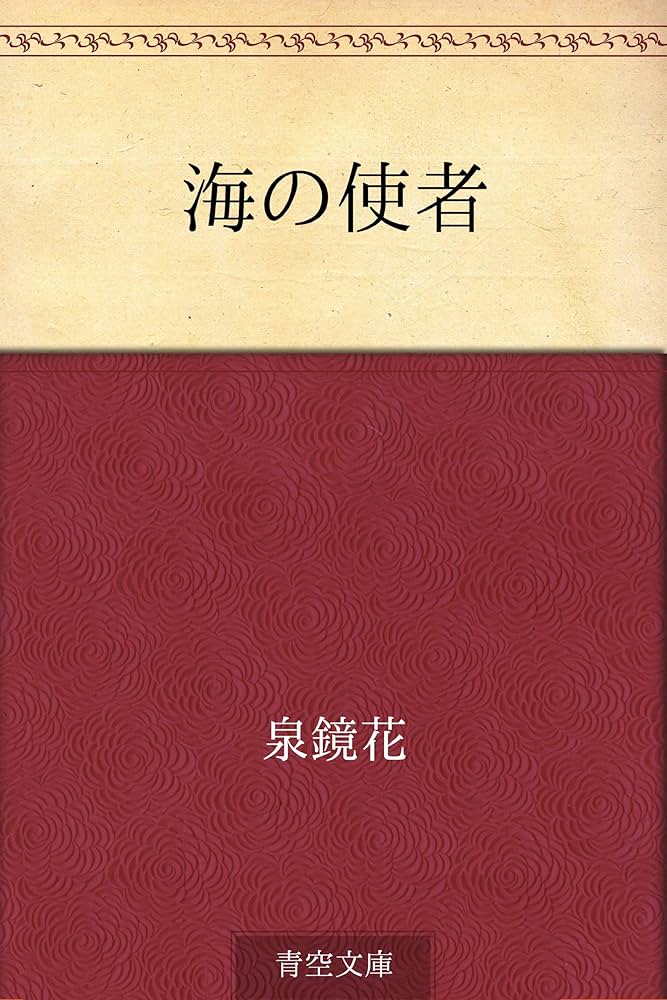
『海の使者』は、海を舞台にした幻想的な物語です。物語は、海からやってきた不思議な存在と、人間の少女との交流を描いています。
この作品は、鏡花が好んで描いた「異界との交流」というテーマが色濃く出ています。美しい海の描写とともに、人間ではない存在への憧れや、決して交わることのできない切なさが描かれています。子供の頃に読んだ童話のような、どこか懐かしくも物悲しい雰囲気が魅力の短編です。



海からの使者ってどんな姿なんだろうって想像が膨らむね。童話みたいで、どこか懐かしい気持ちになるよ。
20位: 『縷紅新草』
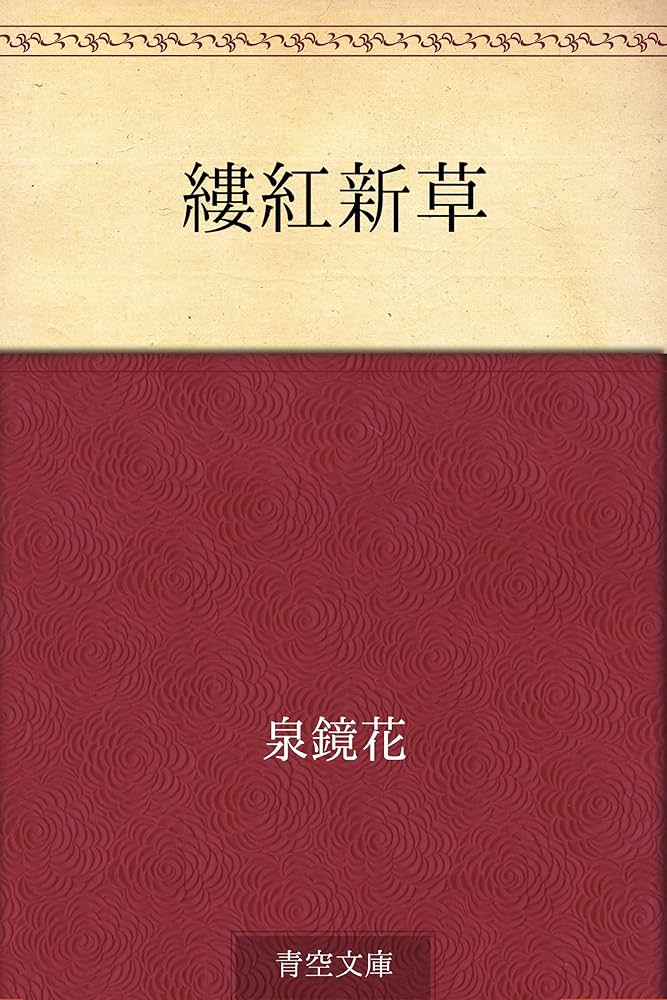
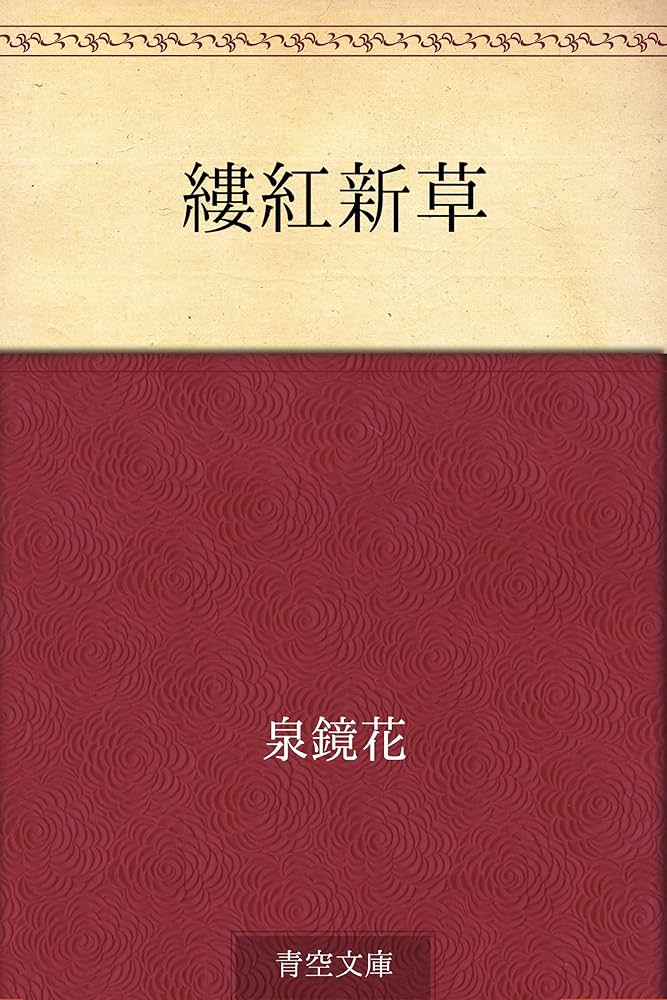
『縷紅新草』は、1939年に発表された泉鏡花の絶筆となった作品です。物語は、古い因習が残る地方の町を舞台に、若い男女の悲恋を描いています。
この作品は、鏡花が晩年に至ってもなお持ち続けていた、純粋な愛への憧れと、それを阻む社会への批判的な視線が感じられます。鏡花文学の集大成ともいえる美しい文体で綴られており、その幽玄な世界観は最後まで健在です。三島由紀夫が絶賛したことでも知られています。



これが最後の作品だと思うと、なんだか感慨深いな。鏡花文学の魅力が詰まった集大成だよ。
初心者必見!泉鏡花作品の選び方と楽しむコツ
泉鏡花の作品は、その独特の文体と幻想的な世界観から、少し敷居が高いと感じる方もいるかもしれません。しかし、選び方次第で誰でもその魅力的な世界に浸ることができます。
ここでは、泉鏡花文学の初心者に向けた作品の選び方と、より深く楽しむためのコツを3つのポイントに分けてご紹介します。ぜひ参考にして、あなたにぴったりの一冊を見つけてください。
まずは代表作で幻想世界に触れる
何から読めばいいか迷ったら、まずは『高野聖』や『天守物語』といった広く知られている代表作から手に取ってみるのがおすすめです。これらの作品には、泉鏡花文学の魅力である幻想的な美しさ、怪奇趣味、そして美しい日本語の響きが凝縮されています。
多くの人に愛されてきた物語は、やはり面白さも格別です。物語の世界に引き込まれるうちに、自然と鏡花独特の世界観に慣れ親しむことができるでしょう。まずは有名な作品で、鏡花文学の真髄に触れてみてください。
読みやすい短編から始める
「鏡花調」と呼ばれる独特の文体に慣れないうちは、長編小説を読み通すのが難しいと感じるかもしれません。そんな方には、『外科室』や『化鳥』のような、比較的短い作品から始めるのがおすすめです。
短編は物語の構成がシンプルで、話の筋を追いやすいため、鏡花の世界観を掴むのに最適です。物語の結末まで一気に読み終えることができるので、達成感も得やすいでしょう。まずはサクッと読める短編で、言葉の美しさや幻想的な雰囲気を味わってみましょう。
戯曲で言葉の美しさを味わう
泉鏡花は小説だけでなく、優れた戯曲も数多く残しています。『天守物語』や『夜叉ケ池』、『海神別荘』などの戯曲作品は、セリフが中心で物語が進むため、小説よりもストーリーを追いやすいと感じる方も多いでしょう。
何よりも、戯曲では鏡花調の流麗で詩的なセリフの美しさをダイレクトに堪能することができます。声に出して読んでみるのもおすすめです。まるで舞台を観ているかのように、物語の世界に没入できるはずです。
まとめ:泉鏡花のおすすめ小説を読んで、幽玄な世界に浸ろう
今回は、幻想文学の巨匠・泉鏡花のおすすめ作品をランキング形式でご紹介しました。怪奇的で美しい物語から、切ない悲恋を描いたもの、そして言葉の響きが魅力的な戯曲まで、その世界は多岐にわたります。
独特の文体は初めは少し難しく感じるかもしれませんが、一度その世界に足を踏み入れれば、きっとあなたもその幽玄な魅力の虜になるはずです。ぜひこの記事を参考に、気になる作品から手に取って、泉鏡花の織りなす唯一無二の文学世界に浸ってみてください。

