あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】開高健のおすすめ小説ランキングTOP15

はじめに:行動派作家・開高健の小説世界へようこそ
『小説ヨミタイ』編集長のふくちいです。今回は、日本の文学界に大きな足跡を残した作家、開高健(かいこう たけし)の魅力に迫ります。彼の作品は、ただの物語にとどまらない、強烈なメッセージと生命力に満ちあふれています。
開高健は、サントリー(旧:壽屋)のコピーライターとして「人間らしくやりたいナ」といった名キャッチコピーを生み出した異色の経歴を持つ作家です。 1958年には『裸の王様』で芥川賞を受賞し、その文才を世に知らしめました。 彼の最大の特徴は、自ら世界中を飛び回り、その体験を作品に昇華させた行動派作家であること。 特に、ベトナム戦争の取材経験は、彼の代表作に大きな影響を与えています。
この記事では、そんな開高健の数ある名作の中から、特におすすめの小説をランキング形式でご紹介します。戦争文学から社会風刺、ユーモアあふれるエッセイまで、彼の多岐にわたる作品世界を旅してみましょう。
開高健のおすすめ小説ランキングTOP15
それでは、いよいよ開高健のおすすめ小説ランキングを発表します。今回は、彼の代表作や、その文学的評価、そして読者からの人気などを総合的に判断してTOP15を選出しました。
戦場のリアルを描いた重厚な作品から、人間の滑稽さやたくましさを浮き彫りにした初期の傑作まで、多彩なラインナップとなっています。どの作品も、一度読んだら忘れられない強烈な印象を残すものばかりです。あなたの心に響く一冊が、きっとこの中に見つかるはずです。
1位『輝ける闇』
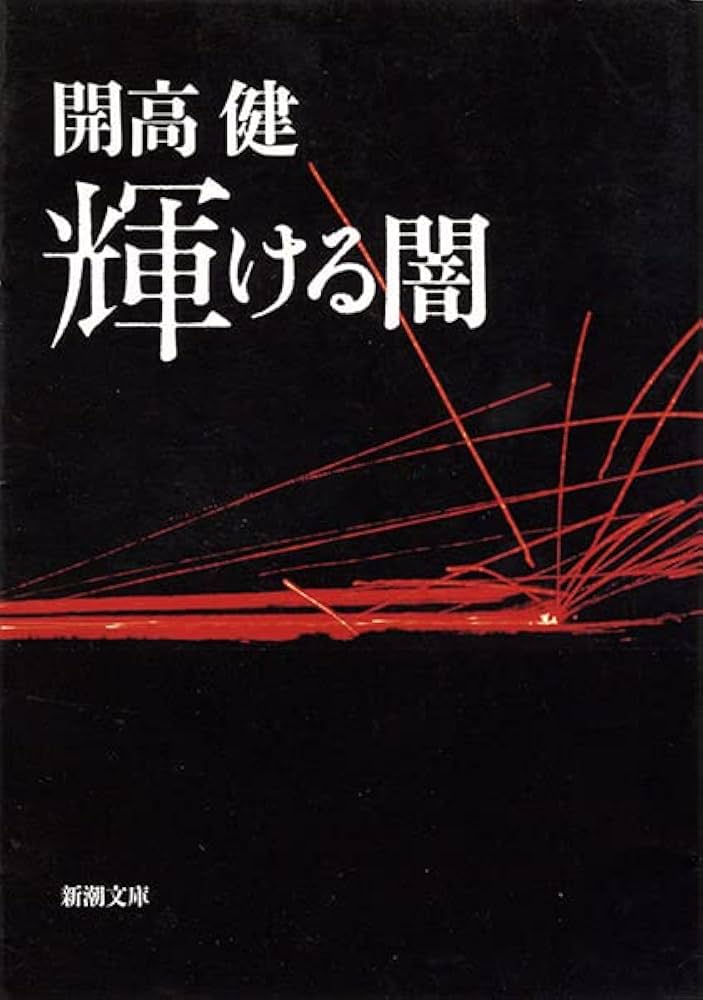
堂々の1位は、開高健の最高傑作との呼び声も高い『輝ける闇』です。この作品は、作家自身が朝日新聞の臨時特派員として体験したベトナム戦争が色濃く反映されています。 物語は、日本人特派員を主人公に、戦争の狂気と日常が混在するサイゴンの様子を圧倒的な筆力で描き出します。
生と死が隣り合わせの極限状況の中で、人間の本質とは何かを問いかける本作は、1968年に毎日出版文化賞を受賞しました。 戦争文学の枠を超え、人間の尊厳を問う普遍的なテーマを持つこの物語は、今なお多くの読者に衝撃を与え続けています。開高文学の神髄に触れたいなら、まず手に取るべき一冊と言えるでしょう。
 ふくちい
ふくちい戦争のリアルな描写がすごすぎて、読んでて息が詰まりそうだったよ。人間の本質がむき出しになる瞬間が描かれていて、色々と考えさせられるんだ。
2位『夏の闇』
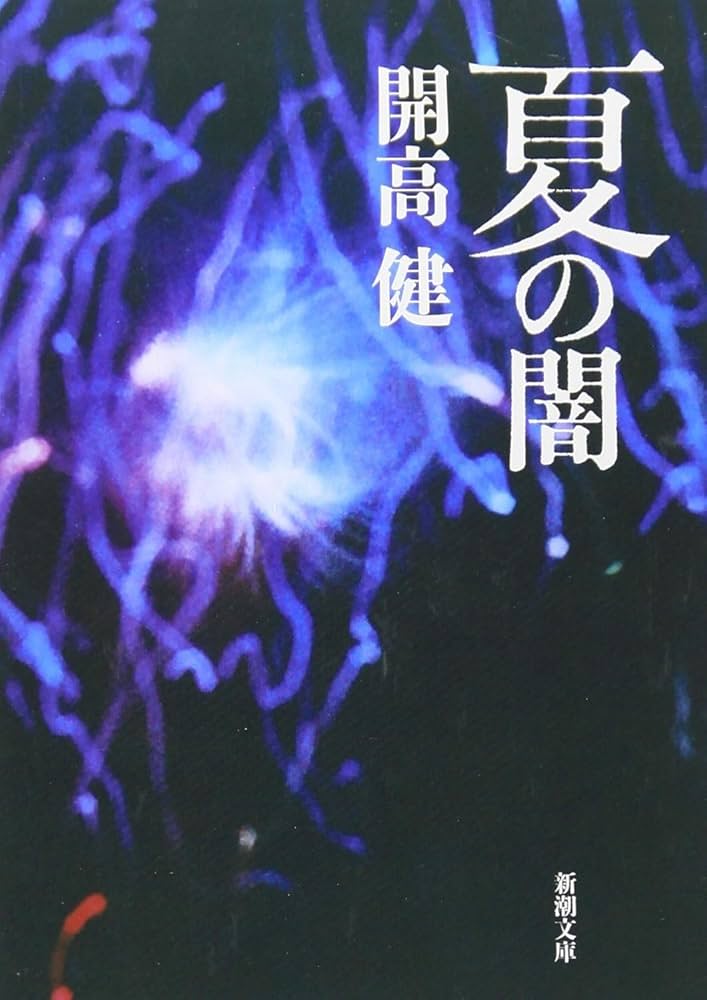
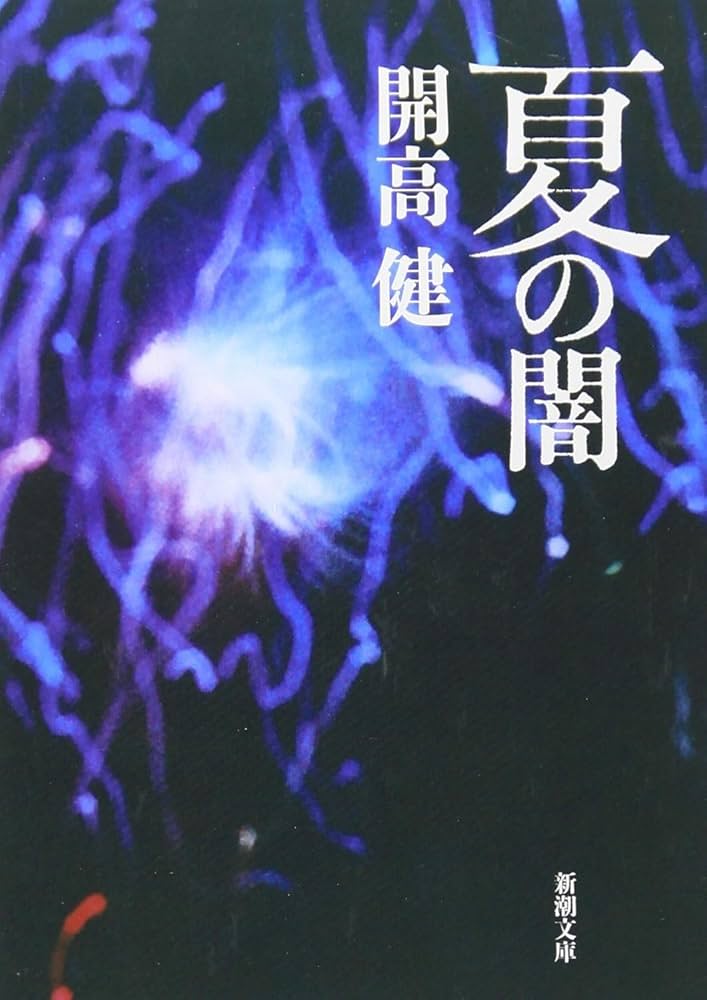
2位にランクインしたのは、『輝ける闇』の続編にあたる『夏の闇』です。前作で描かれた戦争の記憶を背負った主人公が、平和な日常に戻った後の心の虚無や葛藤を描いた物語です。
舞台はヨーロッパに移り、ある女性との愛憎を軸に物語は展開します。戦争という非日常から生還した男が、日常の中でいかにして魂の渇きと向き合っていくのか。その内面的な思索が、開高健ならではの濃密な文章で綴られていきます。戦争の傷跡というテーマを、より深く個人の内面から描いた傑作です。



戦争が終わっても心の中の闇は続くんだね…。主人公の虚しさが伝わってきて、なんだか切なくなっちゃったよ。
3位『パニック・裸の王様』
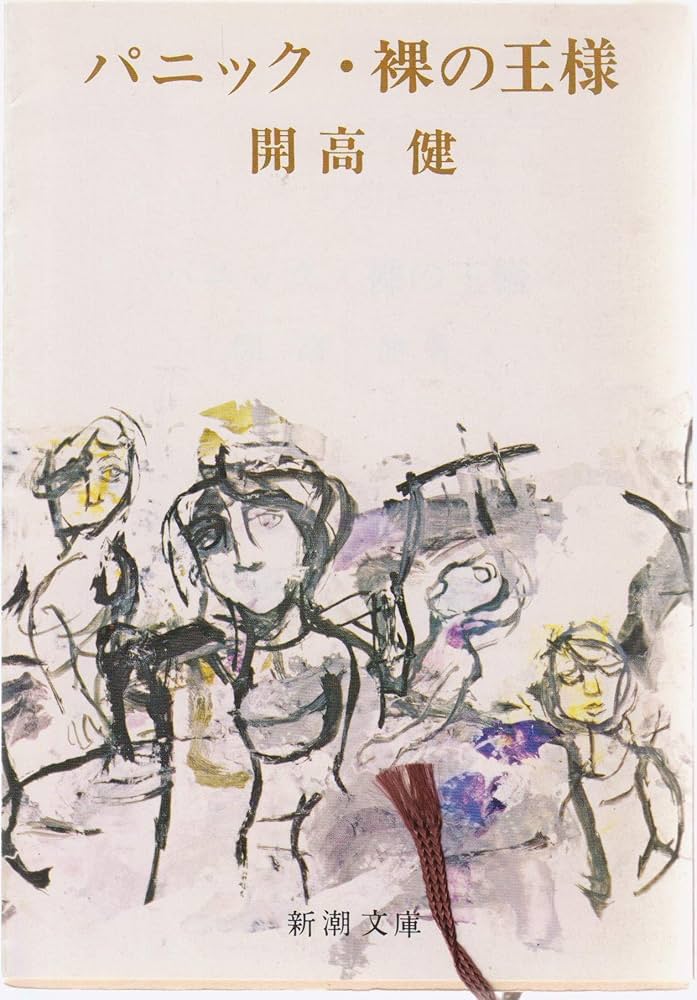
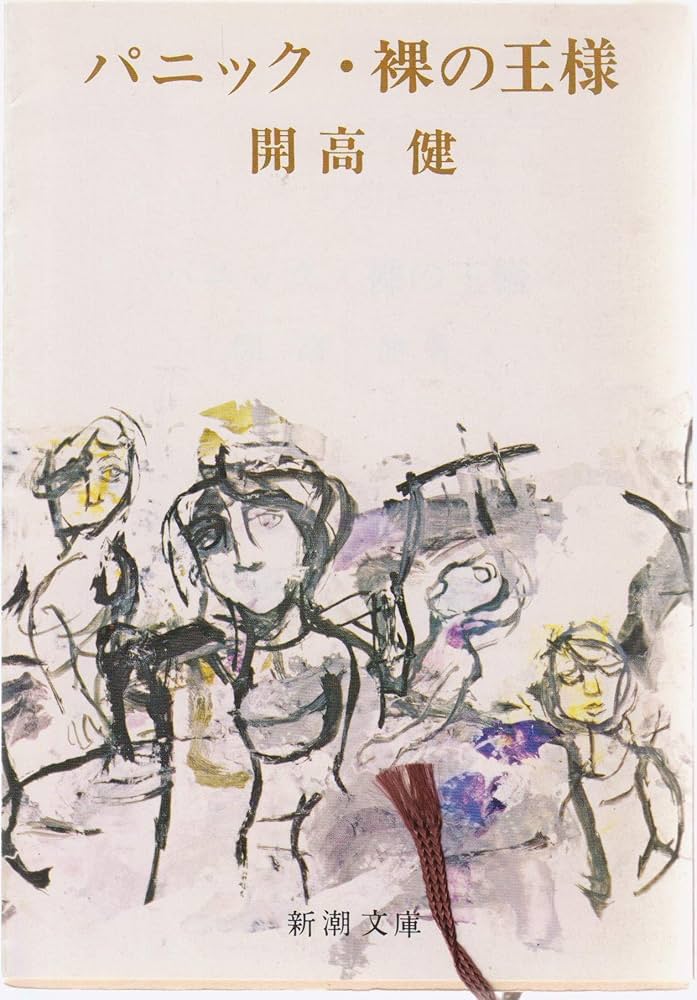
3位は、開高健の初期の代表作2編を収めた『パニック・裸の王様』です。『パニック』は、突如として大量発生したネズミによって引き起こされる社会の混乱を、『裸の王様』は、大企業の偽善を子供の絵を通して暴き出す物語です。
どちらの作品にも共通しているのは、組織や社会のメカニズムに対する鋭い風刺の視点です。 特に『裸の王様』は、1958年に第38回芥川賞を受賞した作品であり、開高健の名を世に知らしめた記念碑的な一作でもあります。 若き日の才気と、社会を見る冷徹な目が光る、痛快でありながらも奥深い作品集です。



組織のタテマエとか偽善をズバッと描いてて爽快だよ!ちょっと皮肉っぽいけど、そこがまた面白いんだよね。
4位『日本三文オペラ』
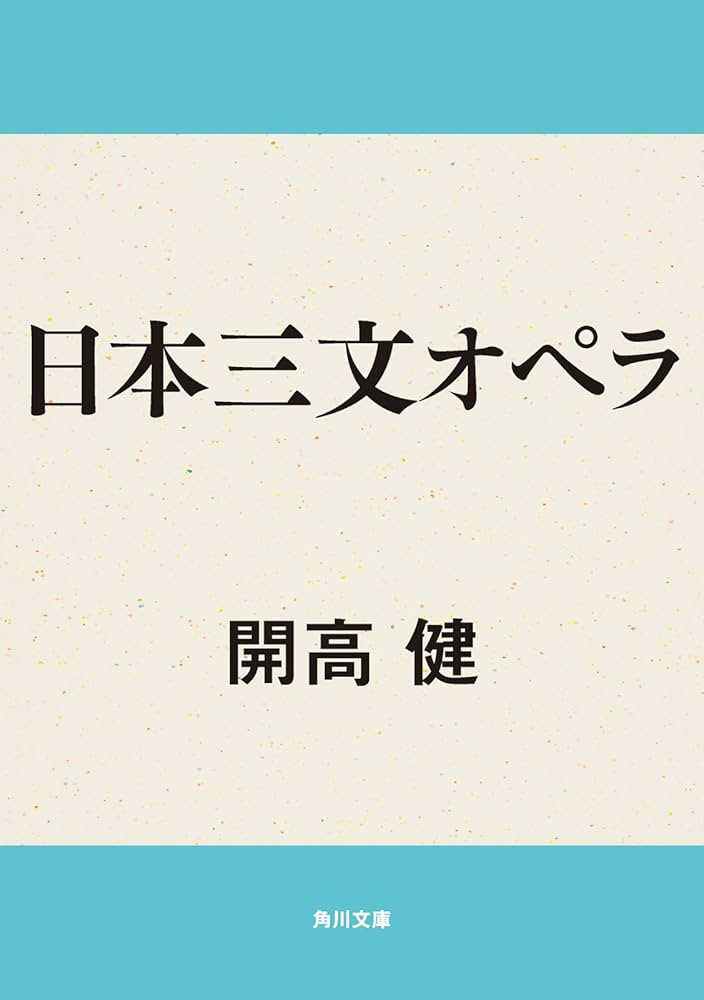
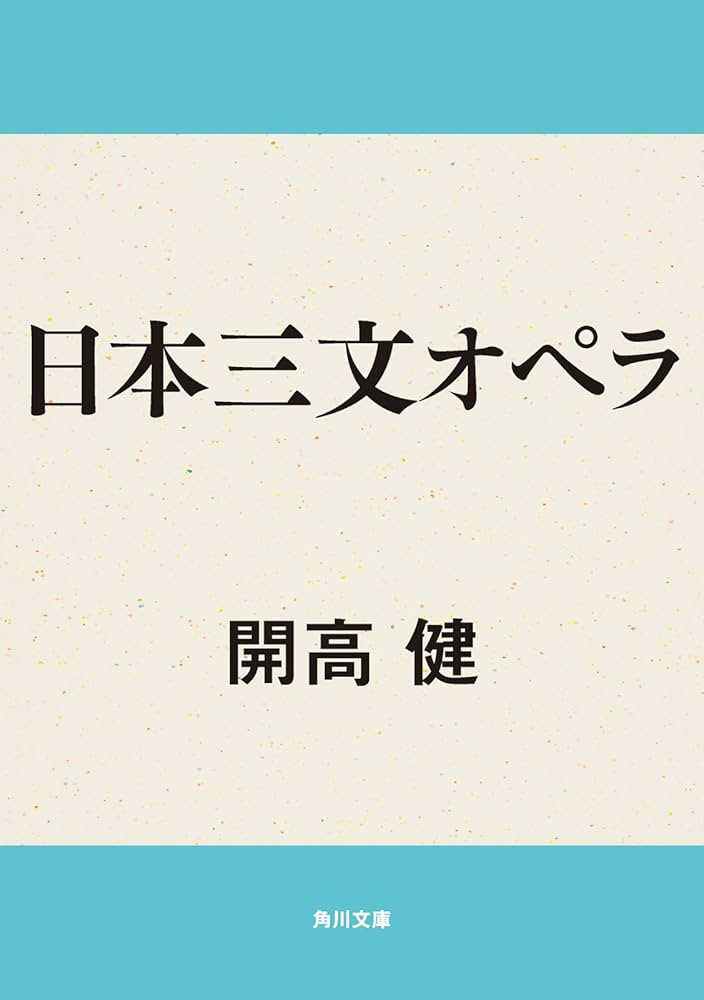
4位は、戦後の大阪を舞台にした『日本三文オペラ』です。この作品は、大阪の軍需工場跡地に住み着き、廃品回収などで生計を立てる人々のたくましい生活を描いています。
開高健自身の初期の代表作であり、ルポルタージュのような手法で、そこに生きる人々のエネルギーを鮮やかに描き出しているのが特徴です。貧しさの中にあっても、したたかに、そして陽気に生き抜こうとする人々の姿は、読む者に強烈な生命力を感じさせます。戦後の日本の原風景ともいえる世界が、ここにはあります。



登場人物がみんなパワフルで、読んでるこっちまで元気が出てくるよ!たくましく生きるって、こういうことなんだなって思うんだ。
5位『珠玉』
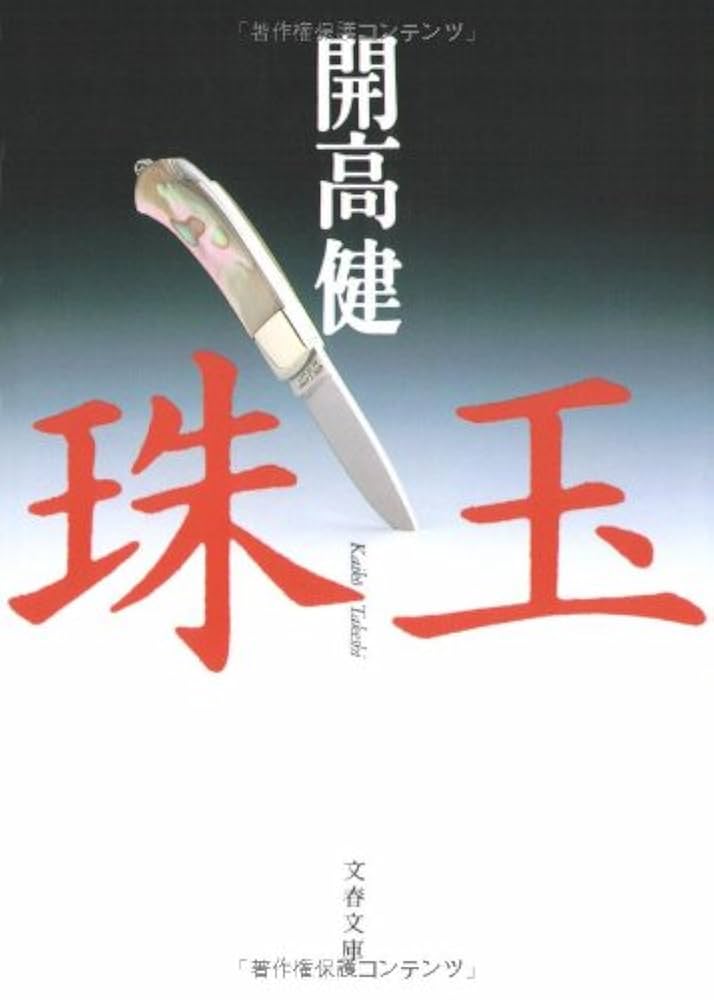
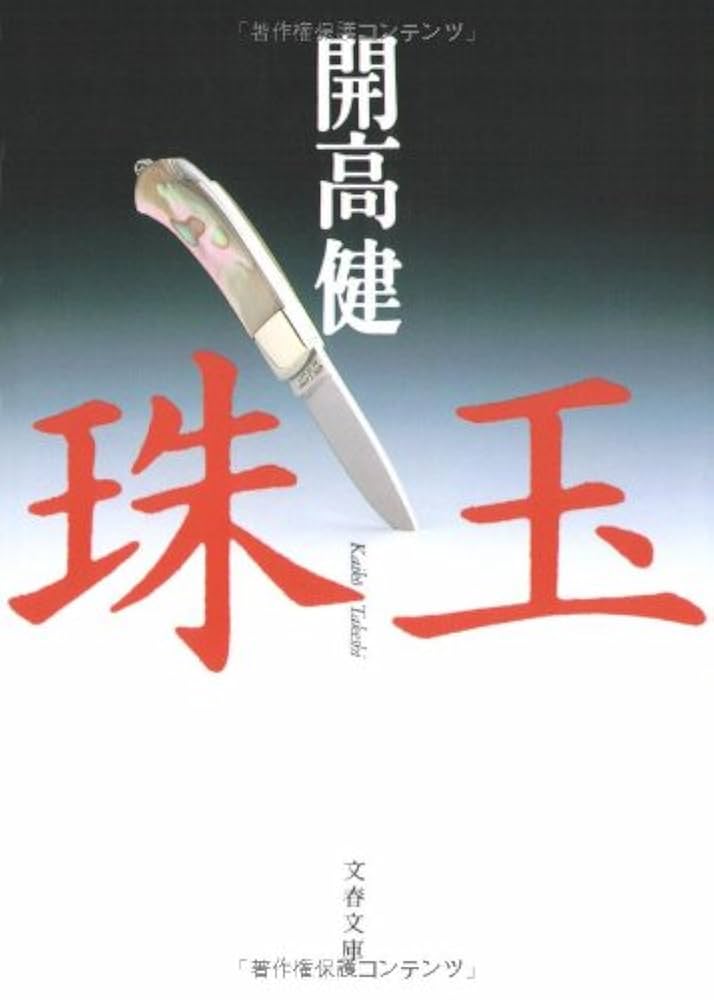
5位には、短編集『珠玉』がランクインしました。この作品集には、表題作の「珠玉」をはじめとする、粒ぞろいの短編が収められています。開高健の文章の切れ味や、物語を構築する巧みさを存分に味わうことができる一冊です。
彼の作品は長編のイメージが強いかもしれませんが、凝縮された世界観の中に人間の業や哀歓を描き出す短編もまた、大きな魅力を持っています。一つ一つの物語が、まるで宝石(珠玉)のように磨き上げられており、読後に深い余韻を残します。開高健入門としても、おすすめできる作品集です。



短いお話の中に、ぎゅっと魅力が詰まってる感じだね。どの話も面白くて、一気に読んじゃったよ。
6位『六つの短篇小説 ロマネ・コンティ・一九三五年』
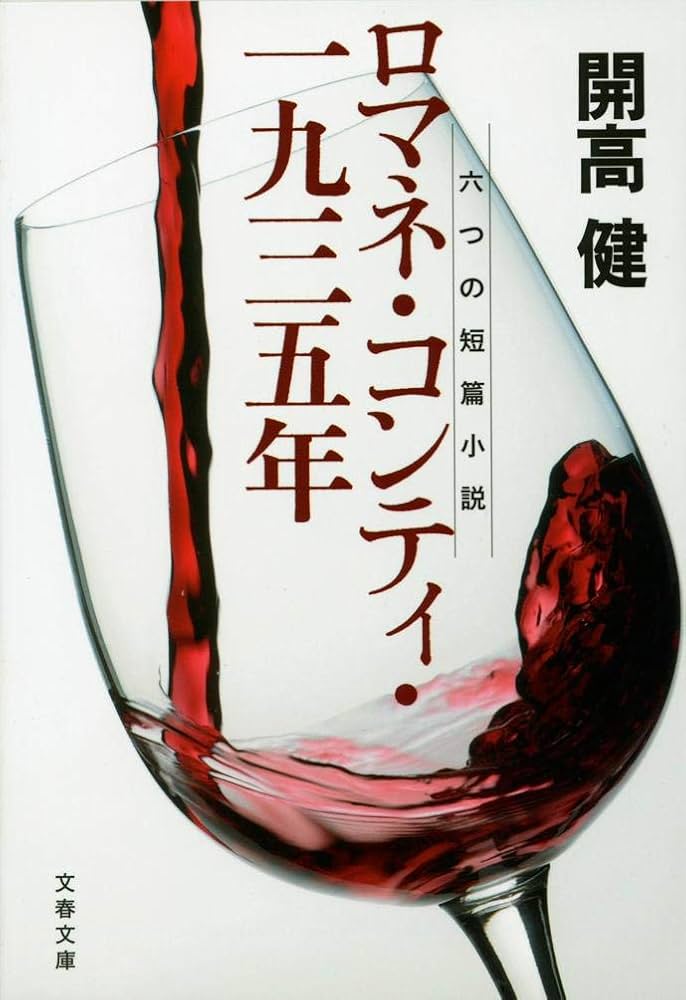
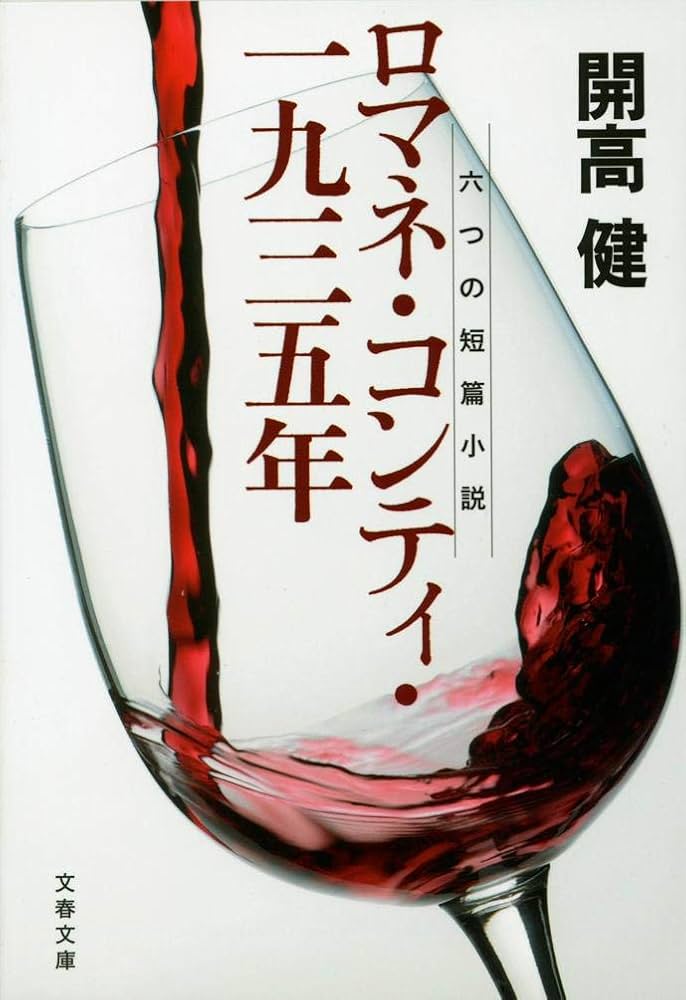
6位は、美食家としても知られた開高健らしい一冊、『六つの短篇小説 ロマネ・コンティ・一九三五年』です。この短編集には、表題作であり、幻のワインをめぐる物語「ロマネ・コンティ・一九三五年」や、川端康成文学賞を受賞した「玉、砕ける」などが収録されています。
食や酒、釣りといった自身の趣味や美学が色濃く反映された作品群は、他の小説とはまた一味違った魅力を放っています。洗練された大人のユーモアと、人生の機微を知り尽くした作家の円熟した筆致が光る、まさに珠玉の短編集と言えるでしょう。



ワインの話とか、すごくおしゃれで大人の世界って感じがするよ。読んでるとお腹が空いてきちゃうかも!
7位『玉、砕ける』
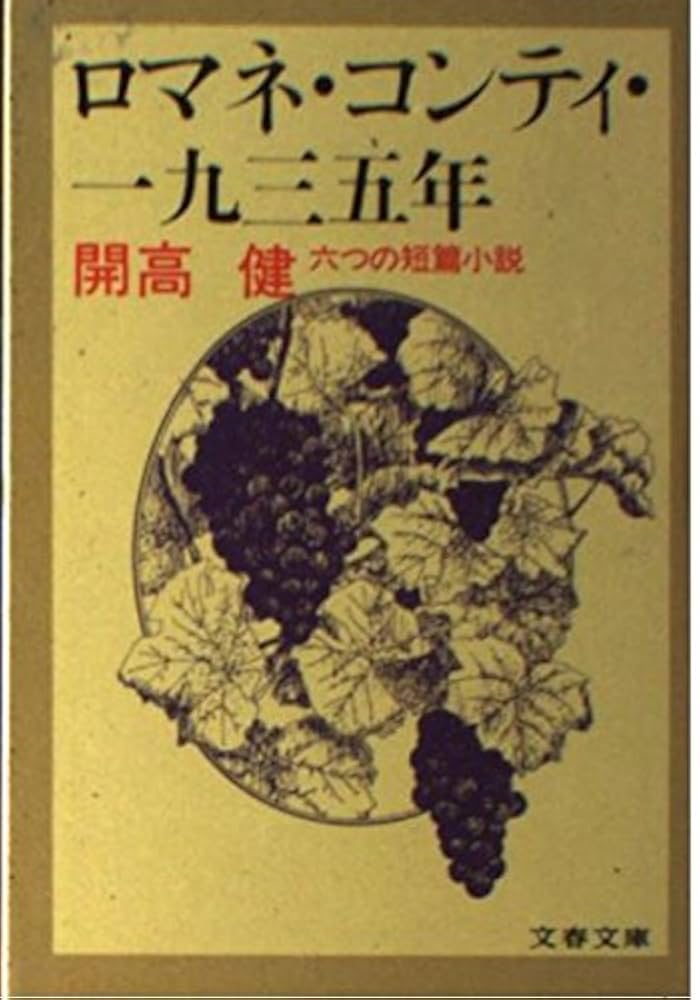
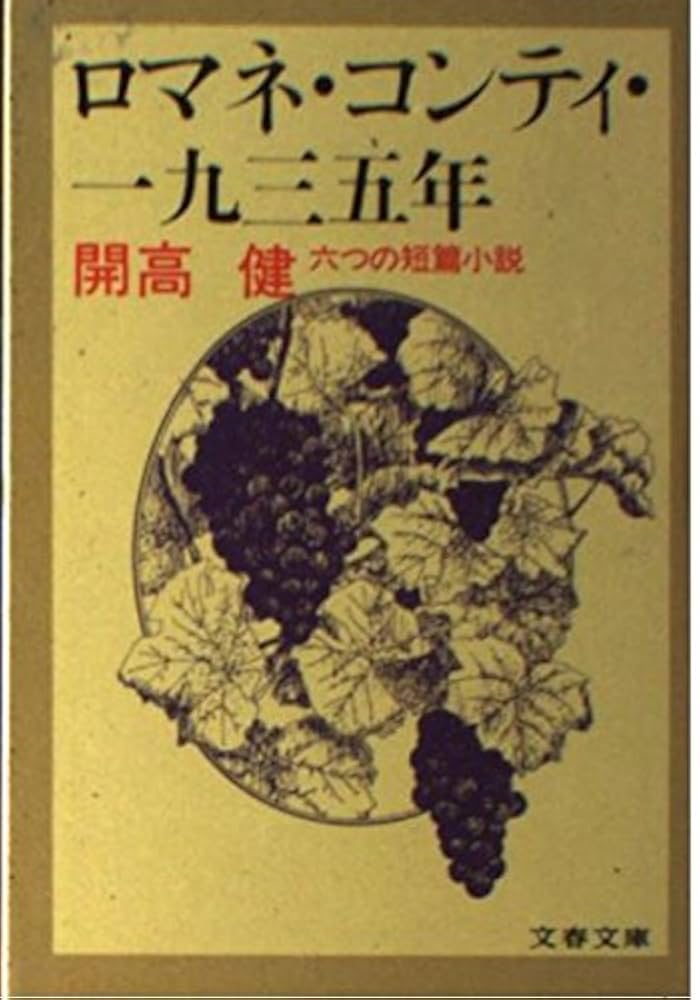
7位にランクインしたのは、短編の名手としての開高健の真骨頂を示す『玉、砕ける』です。この作品は、1979年に第6回川端康成文学賞を受賞しており、文学的に非常に高い評価を受けています。
物語は、中国を舞台に、ある高貴な器の運命をめぐって展開されます。美の儚さと、それに魅せられた人々の情念が、格調高い文章で描かれています。歴史の大きな流れの中で翻弄される個人の姿を、一つの器を通して描き出したこの物語は、短いながらも壮大なスケールを感じさせます。



ひとつの器をめぐるお話なのに、すごく壮大な物語だったな。美しいものが持つ不思議な力について考えさせられたよ。
8位『流亡記』
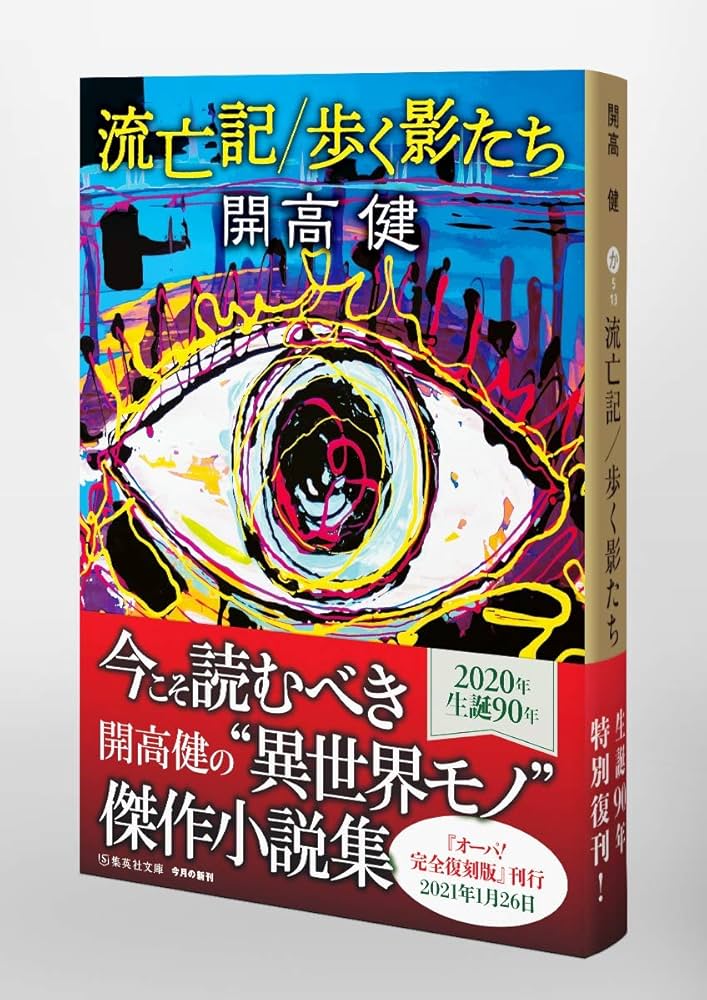
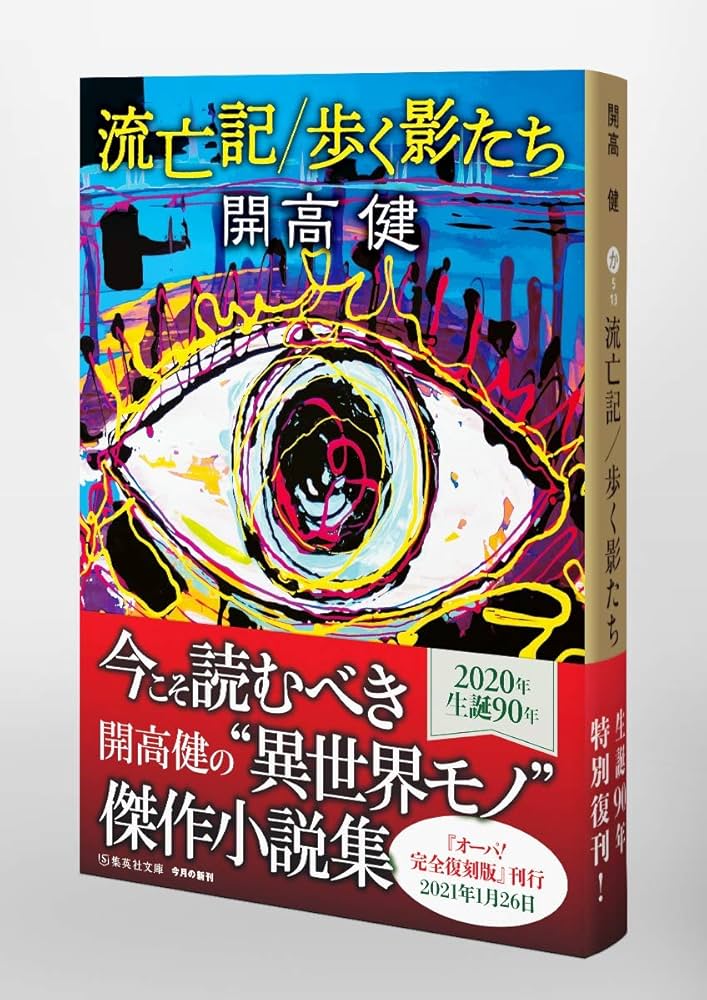
8位は、初期の長編小説『流亡記』です。
巨大なダムの底に沈む運命にある村を救うため、個性豊かなアウトローたちが立ち上がるというストーリーは、反骨精神とユーモアにあふれています。若き日の開高健の、ほとばしるような才能とエネルギーが感じられる一作です。 後のベトナム戦争を題材にした作品群とは異なる、エンターテイメント性の高い物語もまた、彼の大きな魅力の一つです。



なんだか現代版の水滸伝って感じでワクワクするよ!個性的なキャラクターたちが集まって、大きな力に立ち向かうのがカッコいいんだ。
9位『歩く影たち』
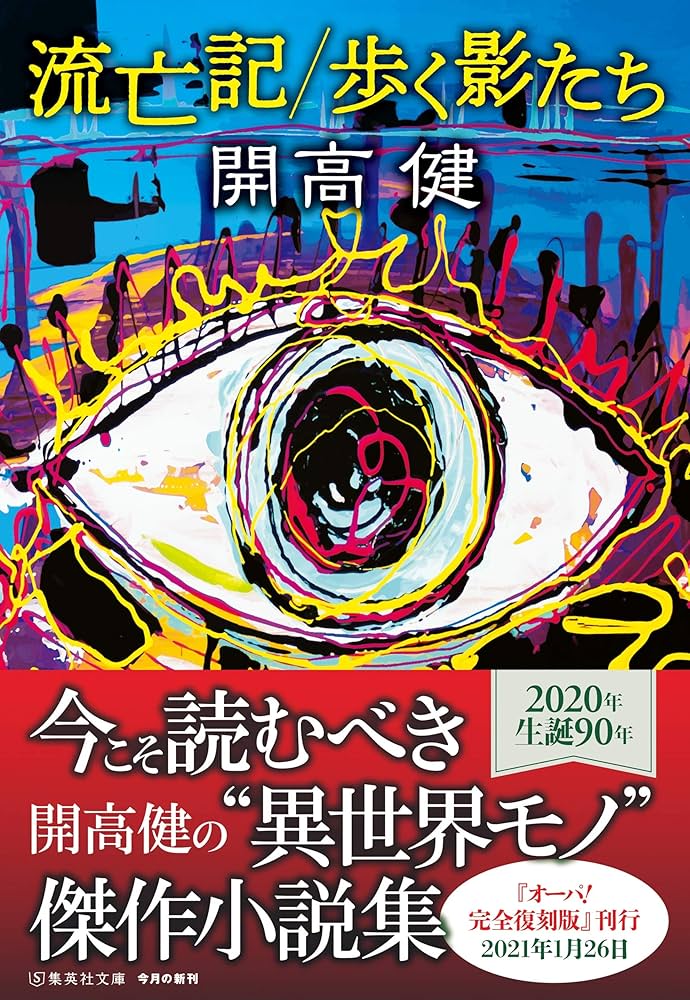
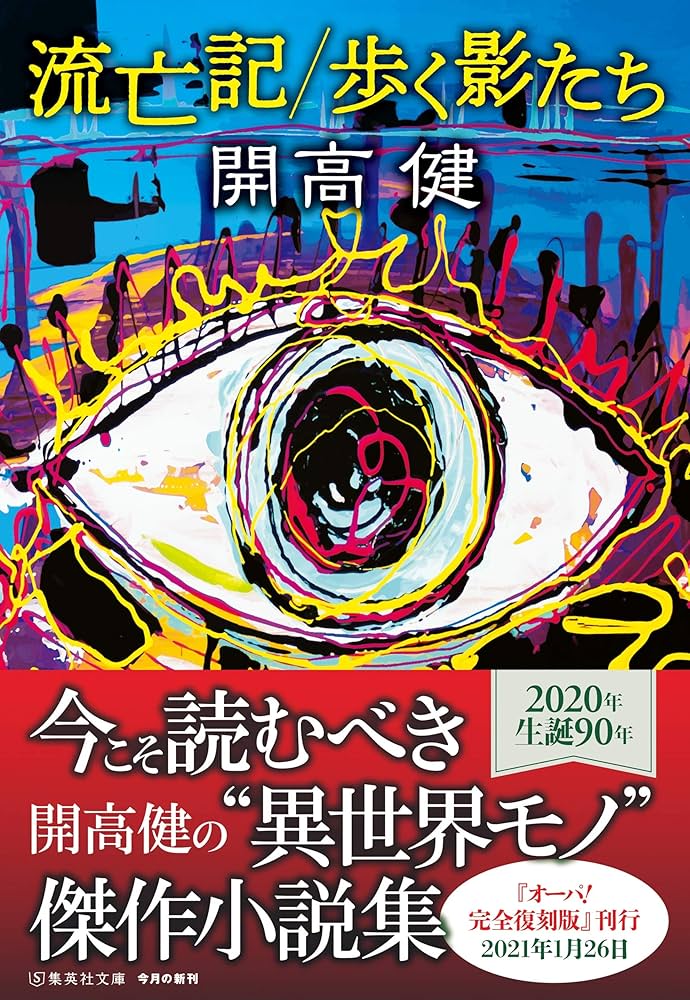
9位は、世界中を旅した開高健ならではの視点が光る短編集『歩く影たち』です。さまざまな国を舞台にした物語が収められており、読者を異国情緒あふれる世界へと誘います。
この作品集の魅力は、旅先で出会う人々の人間模様や、その土地の空気を巧みに切り取っている点にあります。鋭い観察眼と、異文化への深い洞察力を持つ開高健だからこそ描ける、リアルで深みのある物語が詰まっています。ページをめくるたびに、まるで世界を旅しているかのような気分を味わえる一冊です。



いろんな国のお話が読めて、旅行してるみたいで楽しいな。世界には本当に色々な人がいるんだね。
10位『巨人と玩具』
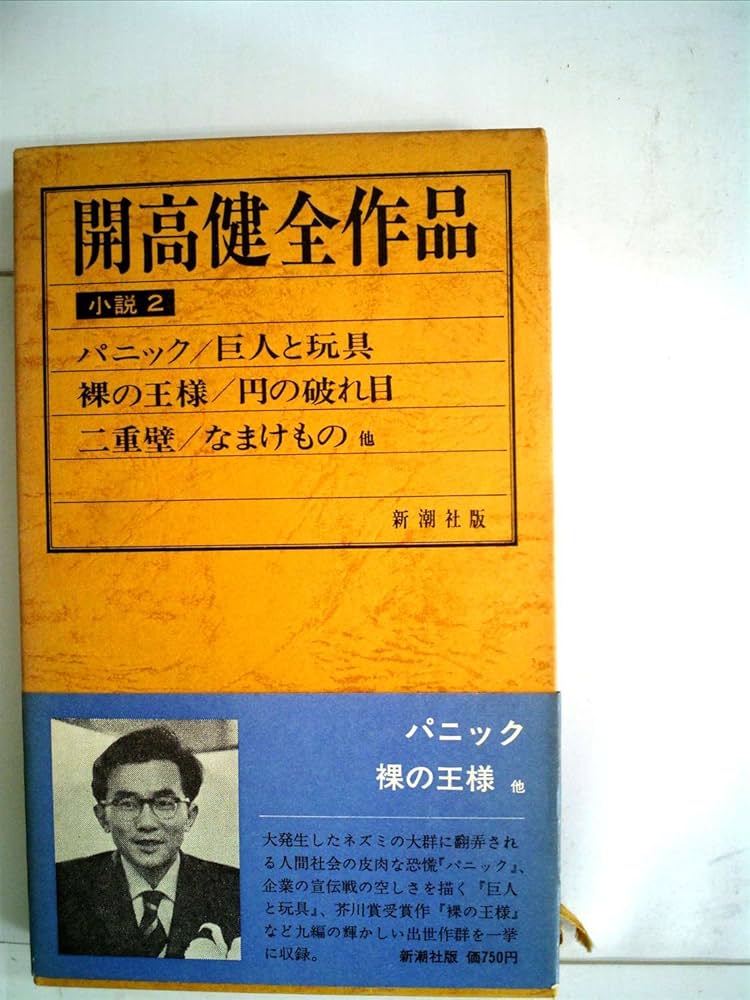
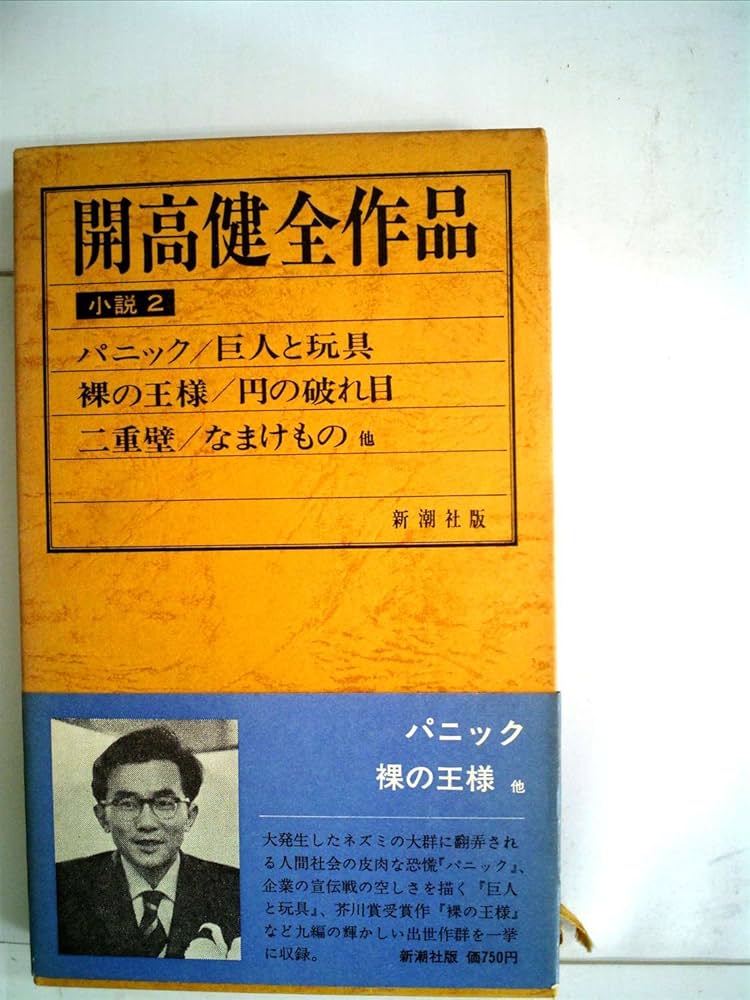
10位には、開高健がコピーライターとして活躍していた経験が生かされた小説『巨人と玩具』がランクインしました。この作品は、製菓会社の熾烈な販売競争を舞台に、広告業界の裏側をコミカルかつ痛烈に描いています。
マス・メディアに翻弄される大衆や、過剰な宣伝合戦の虚しさを描き出した本作は、現代の消費社会にも通じる鋭い批判精神を持っています。企業という組織の中で働く人々の悲喜こもごもを、ユーモアを交えて描く手腕はさすがの一言。社会派エンターテイメントとして、今読んでも色褪せない面白さがあります。



広告業界の裏側って、こんなに大変なんだね…。キラキラして見える世界の裏には、色々なことがあるんだなあって思ったよ。
11位『青い月曜日』
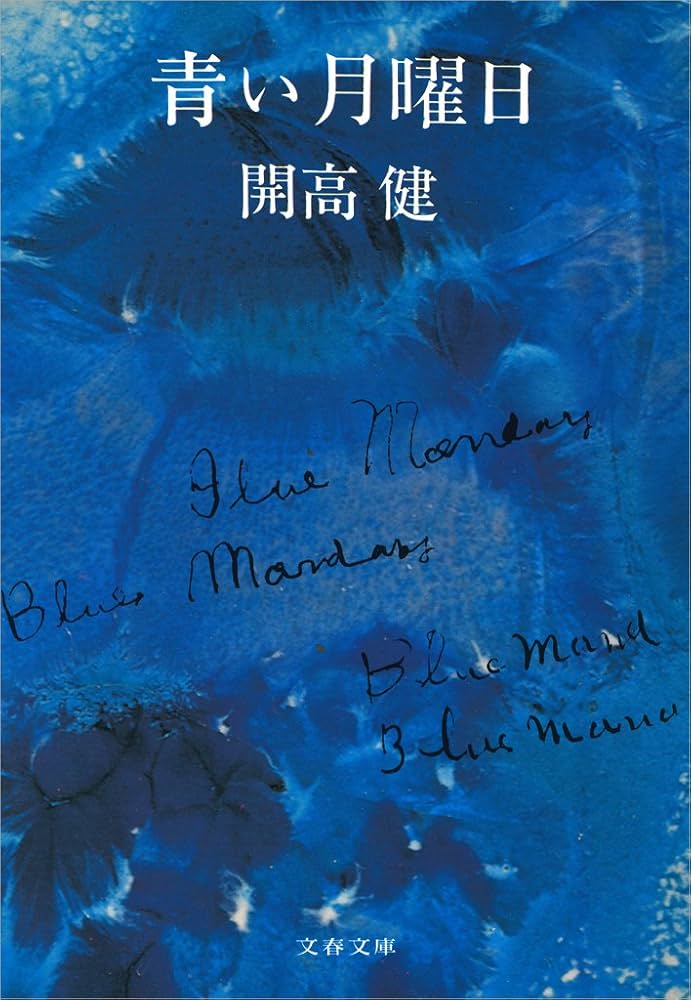
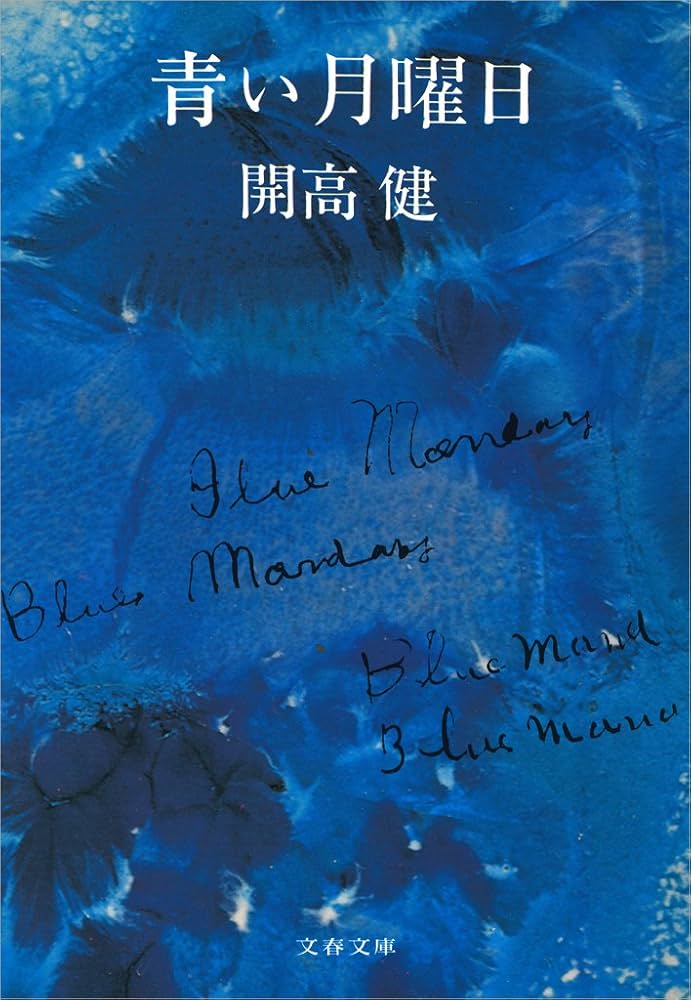
11位は、開高健の自伝的要素が強い小説『青い月曜日』です。 この作品は、終戦直後の混乱した時代を背景に、多感な少年期から青年期へと移りゆく主人公の姿を描いています。
戦争による価値観の崩壊や、将来への漠然とした不安、そして旺盛な知的好奇心。そんな青春時代特有の鬱屈とした感情や焦燥感が、瑞々しい筆致で綴られています。 開高健という作家が、どのような時代を生き、何を感じてきたのか。その原点に触れることができる、ファンにとっては必読の一冊と言えるでしょう。



なんだか主人公の気持ち、少しわかる気がするな。将来のこととか、色々考えちゃう時期ってあるよね。
12位『破れた繭』
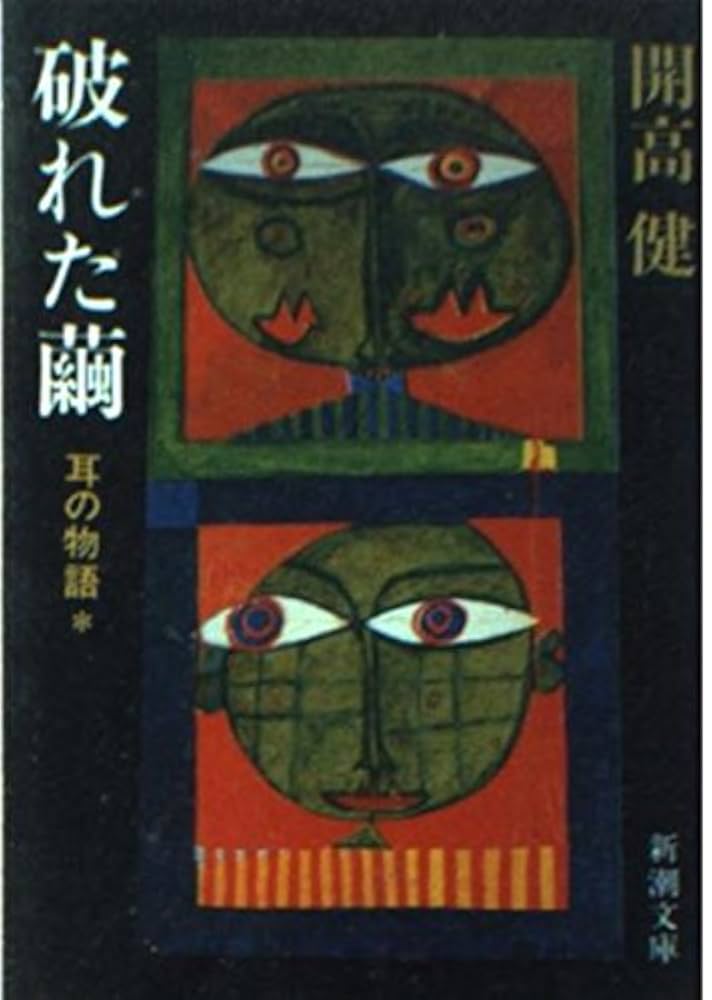
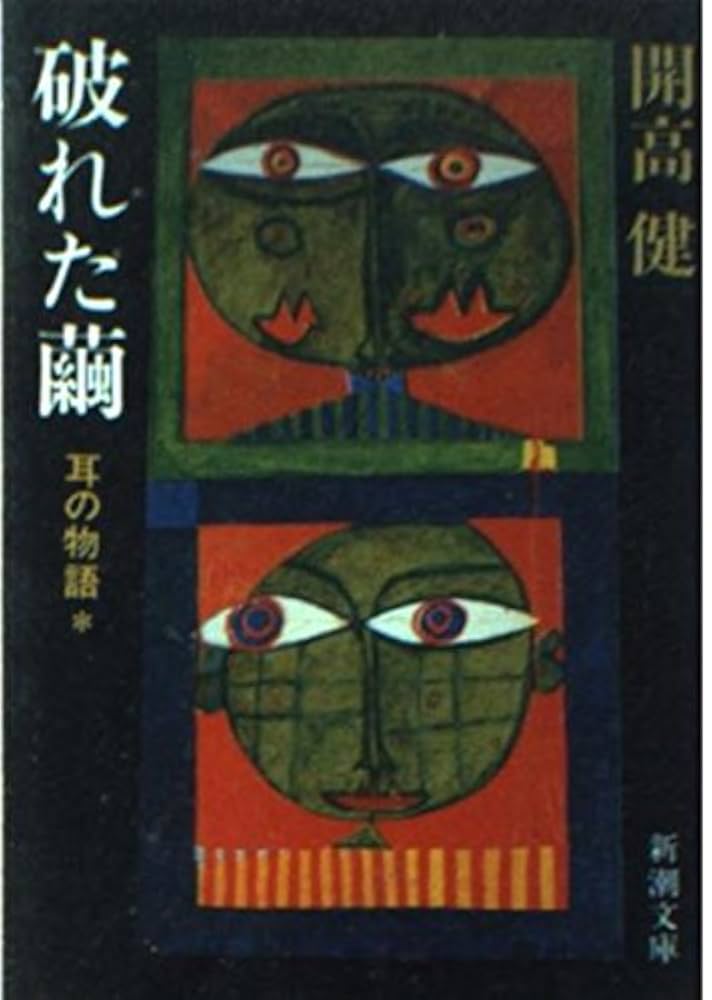
12位は、開高健の後期の代表作の一つである『破れた繭』です。この作品は、中年を迎えた主人公が、自らの過去や人生と向き合う姿を描いた物語です。
人生の折り返し地点に立ち、これまで築き上げてきたものや、失ってきたものに思いを馳せる主人公の姿は、多くの読者の共感を呼ぶでしょう。円熟期に入った作家が描く、人生の哀愁や深みが感じられる一作です。若い頃とは違う視点で人生を見つめ直す、静かな思索の時間が流れる小説です。



大人になるって、色々なことを考えたり、振り返ったりすることなんだね。ちょっとしんみりしちゃうけど、素敵な物語だよ。
13位『片隅の迷路』
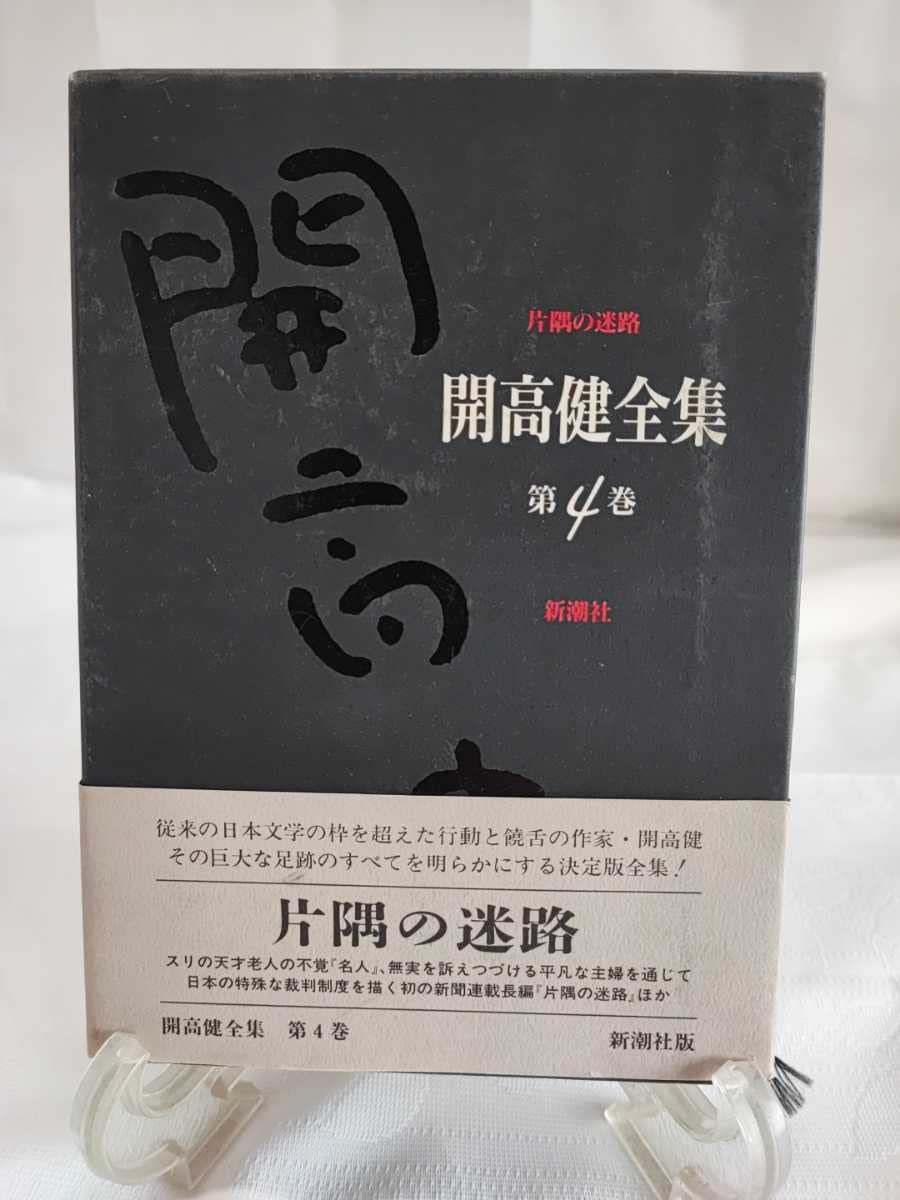
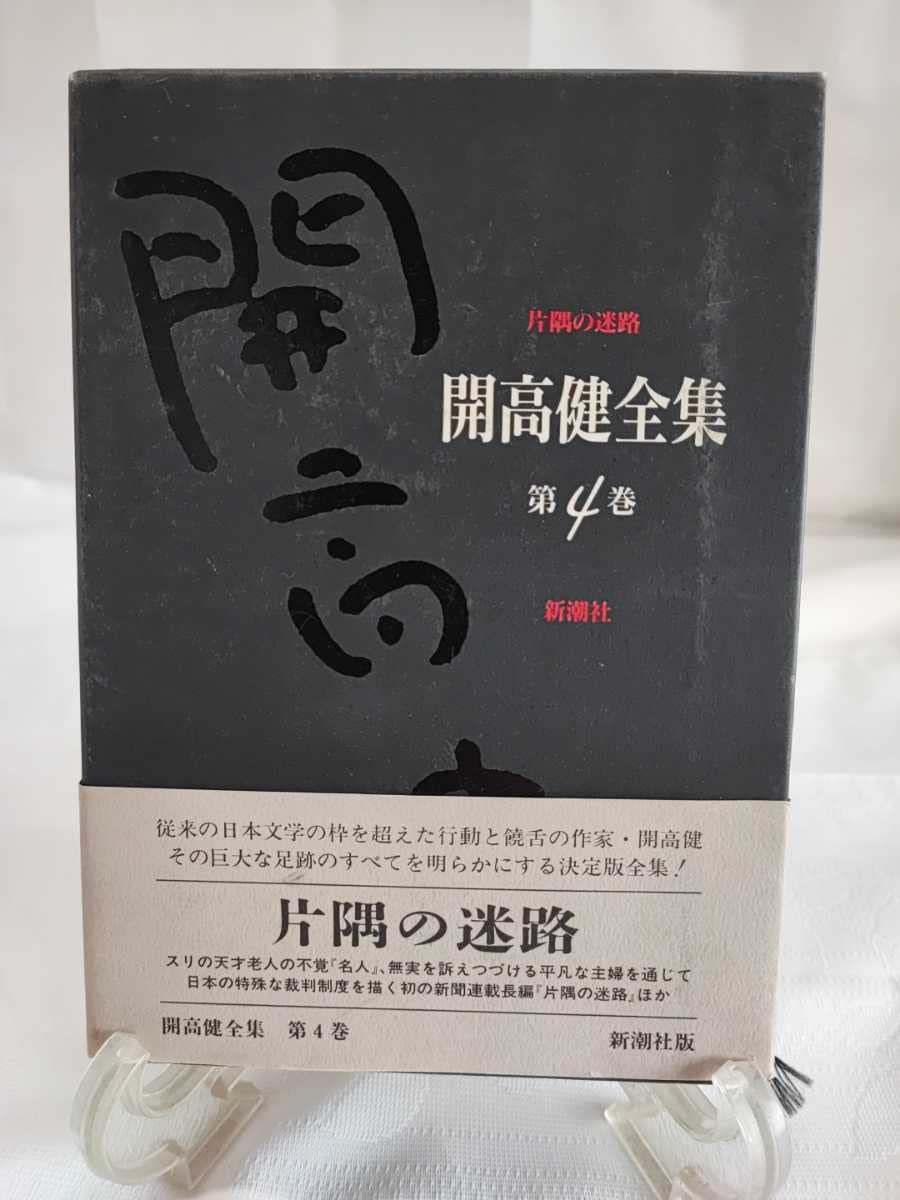
13位は、社会の片隅で生きる人々を描いた『片隅の迷路』です。この作品では、華やかな表舞台ではなく、日陰でひっそりと暮らす人々の人生にスポットライトが当てられています。
開高健の弱者や社会の周縁に追いやられた人々へ向ける温かい眼差しが感じられる作品です。人間の弱さや愚かさを描きながらも、その奥にある愛おしさや尊厳を見つめる視点は、彼の作品に共通する魅力の一つです。派手さはありませんが、読者の心に静かに染み入るような味わい深い一冊です。



みんな一生懸命生きてるんだなって思ったよ。うまくいかないことがあっても、それでも生きていく姿に感動しちゃった。
14位『耳の物語』
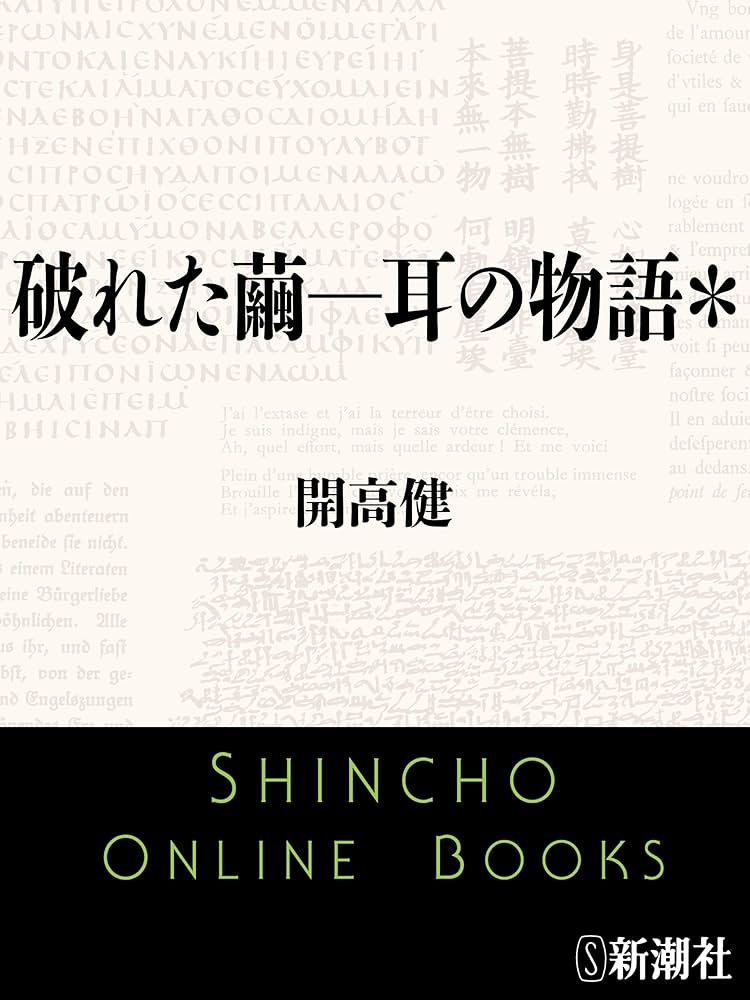
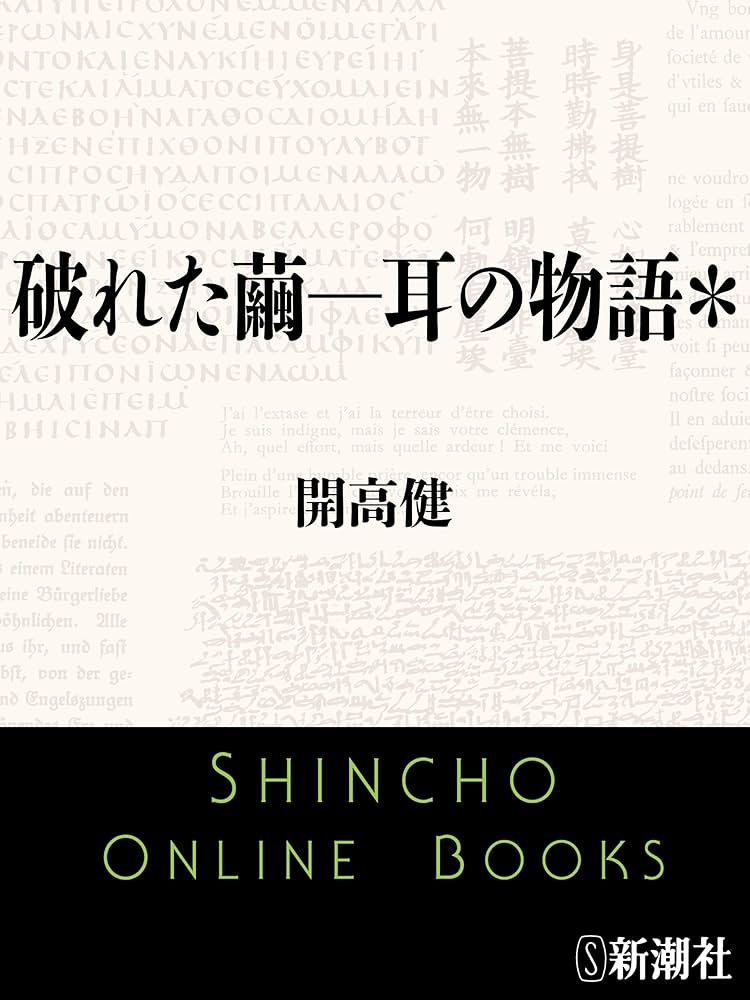
14位は、1987年に日本文学大賞を受賞した自伝的長編『耳の物語』です。 この作品は、作家自身の幼少期から青年期までの体験を基に、一人の人間が「作家・開高健」として形成されていく過程を描いています。
戦争体験や読書遍歴、そして様々な人々との出会い。それらが彼の精神にどのような影響を与えたのかが、克明に綴られています。一人の作家の誕生秘話であると同時に、戦中戦後という激動の時代を生きた若者の肖像でもあります。開高文学のルーツを知る上で欠かせない重要な作品です。



開高健さんがどんな子供だったのか、知ることができて面白かったな。たくさんの本を読んで、色々な経験をして作家になったんだね。
15位『花終る闇』
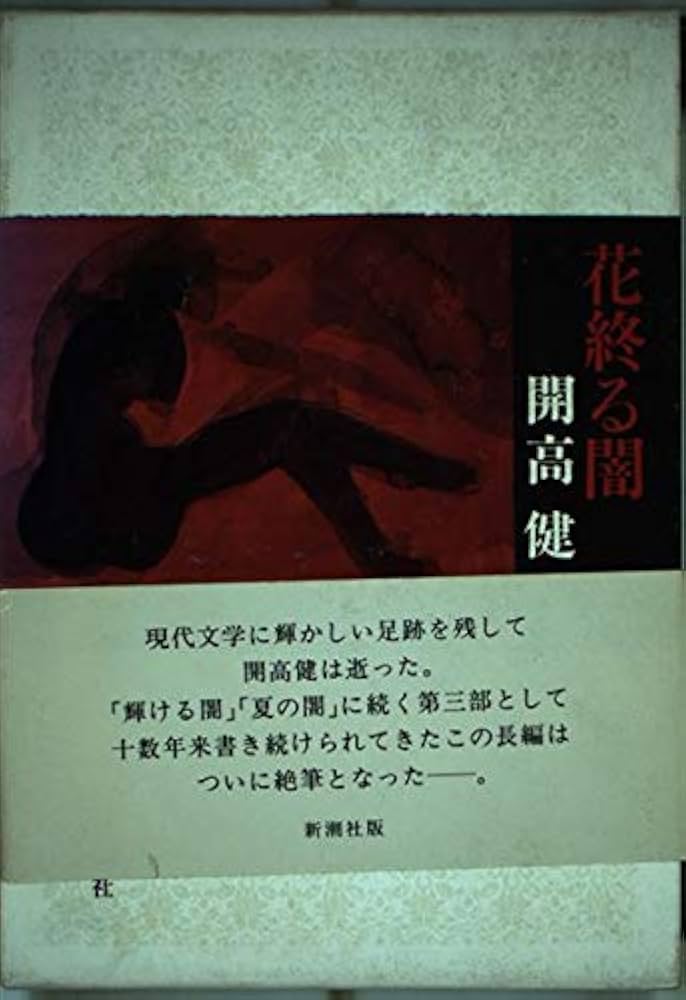
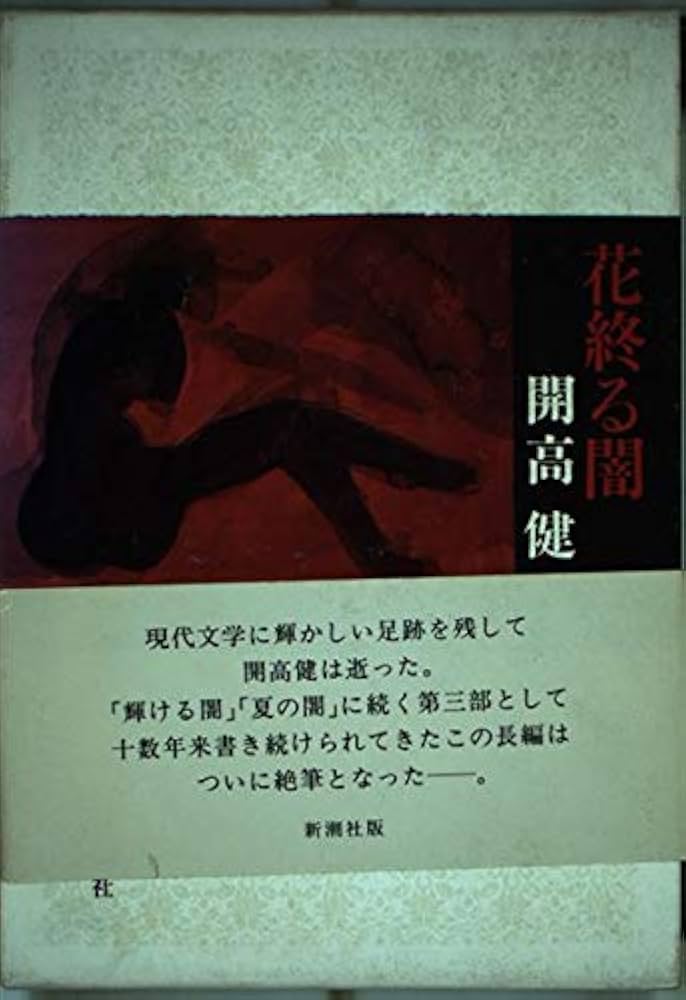
ランキングの最後を飾るのは、開高健の遺作となった未完の長編『花終る闇』です。この作品は、『輝ける闇』『夏の闇』に続く「闇三部作」の完結編として執筆されていましたが、作家の死によって中断されました。
未完でありながらも、この作品からは作家の最後の魂の燃焼が感じられます。再びアジアの地を舞台に、壮大な物語が紡がれるはずでした。完成した物語を読むことは叶いませんが、残された断片から、開高健が最期に描こうとした世界の大きさを想像することができます。ファンであれば、ぜひ手に取ってほしい一冊です。



最後まで読みたかったなあ…。でも、未完だからこそ、この先どんな物語が待っていたんだろうって想像が膨らむね。
まとめ:開高健の小説を手に未知なる文学の旅へ
今回は、行動派作家・開高健のおすすめ小説をランキング形式でご紹介しました。彼の作品は、ベトナム戦争の体験を基にした重厚な物語から、社会を鋭く風刺した初期の傑作、そして世界中を旅する中で生まれた物語まで、非常に多岐にわたります。
どの作品にも共通しているのは、自らの足で歩き、目で見たものだけを信じるという彼の姿勢と、圧倒的な生命力にあふれた文章です。もし、どの作品から読めばいいか迷ったら、芥川賞受賞作である『パニック・裸の王様』や、彼の最高傑作と名高い『輝ける闇』から手に取ってみてはいかがでしょうか。
開高健の小説は、あなたをまだ見ぬ世界へと連れて行ってくれるはずです。ぜひ、その力強い物語の世界に飛び込んでみてください。


