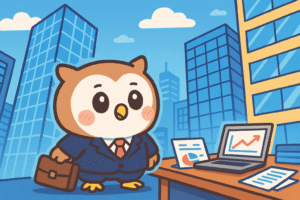あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】津村記久子のおすすめ小説ランキングTOP18

はじめに:津村記久子の小説が愛される理由とは?
『小説ヨミタイ』編集長のふくちいです。今回は、現代日本を代表する作家の一人、津村記久子さんの作品世界にご案内します。津村さんの小説は、なぜこれほどまでに多くの読者の心を掴むのでしょうか。
その魅力の根源は、私たちの日常に寄り添う、温かくも鋭い眼差しにあります。 会社員としての経験を持つ津村さんは、働く人々の喜びや葛藤、理不尽さ、そしてその中にきらめく希望を、ユーモアを交えて描き出します。 決して派手な事件が起こるわけではなくても、登場人物たちが抱える悩みや、ささやかな幸せに、私たちは自分の姿を重ねずにはいられません。 閉塞感のある現代社会を生きる私たちに、津村さんの小説は「それでも大丈夫だ」と、そっと背中を押してくれるような優しさに満ちているのです。
【2025年最新】津村記久子のおすすめ小説ランキングTOP18
それでは、数ある津村記久子さんの名作の中から、特に読んでほしいおすすめ小説をランキング形式でご紹介します。デビュー作から最新の人気作まで、多彩なラインナップを揃えました。
どの作品にも、明日を生きるための小さなヒントが隠されています。あなたにとって、心に残る一冊がきっと見つかるはずです。気になる作品から、ぜひ手に取ってみてください。
1位『水車小屋のネネ』
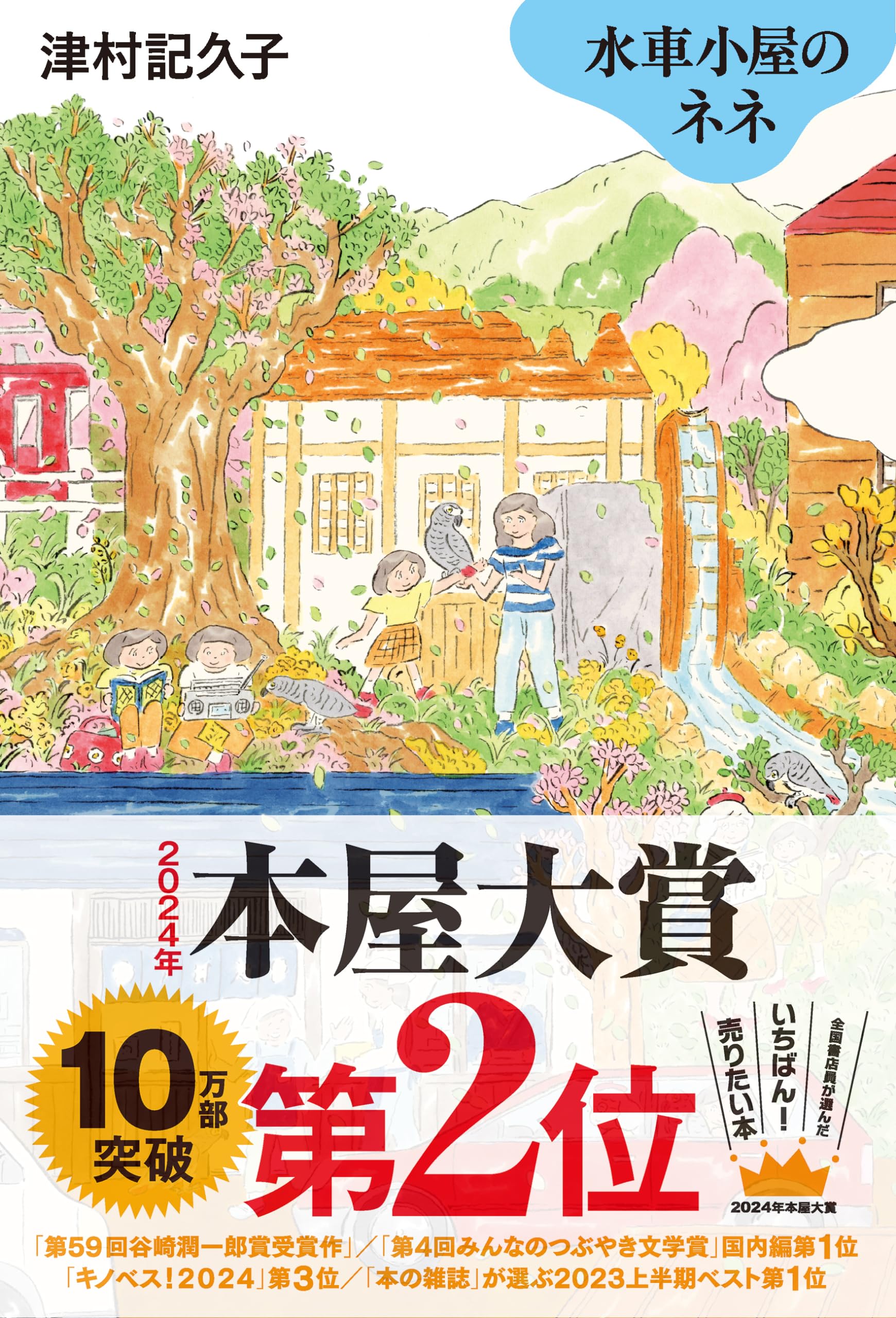
堂々の1位は、2024年の本屋大賞で第2位に輝き、第59回谷崎潤一郎賞も受賞した『水車小屋のネネ』です。 多くの読者の心を打ち、津村さんの新たな代表作となりました。
物語は1981年、身勝手な親から逃れるため、18歳の姉・理佐と8歳の妹・律が二人で生きていくことを決意するところから始まります。 姉妹がたどり着いた町の蕎麦屋には、人の言葉を話す賢いヨウムの「ネネ」がいました。 物語はネネに見守られながら、姉妹とその周りの人々が助け合い、支え合いながら歩む40年間の軌跡を丁寧に描き出します。 誰かに親切にすることの大切さや、平凡な日常にこそある幸せを、静かに、しかし深く伝えてくれる長編小説です。 読後、温かい余韻に包まれること間違いなしの一冊です。
 ふくちい
ふくちい40年という長い歳月を、姉妹とヨウムのネネが紡いでいく物語なんだ。人との繋がりの温かさに、心がじんわりするよ。
2位『この世にたやすい仕事はない』
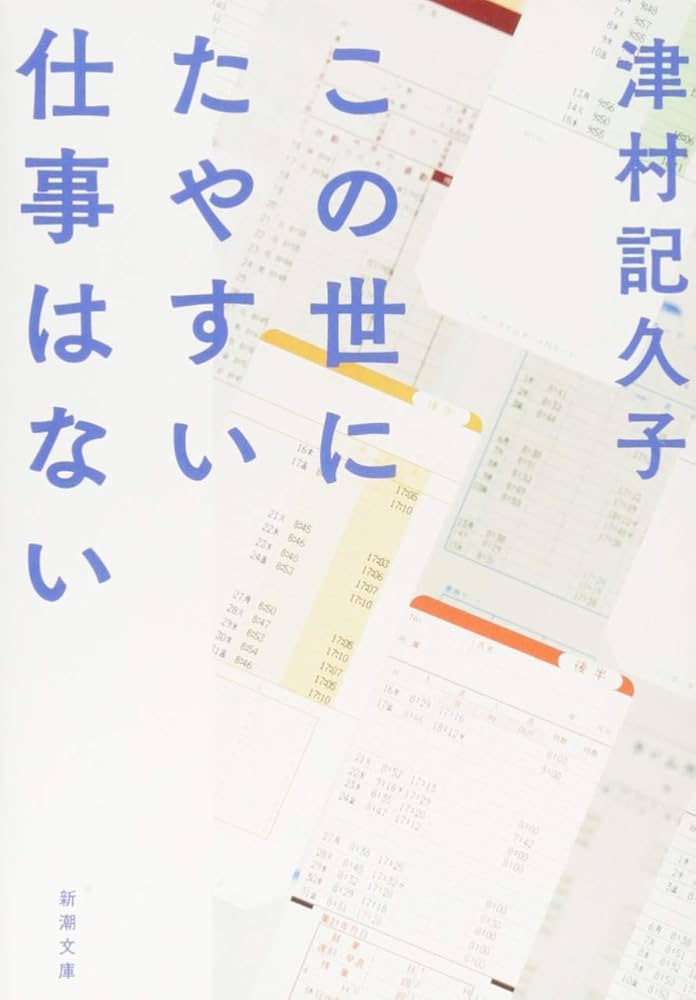
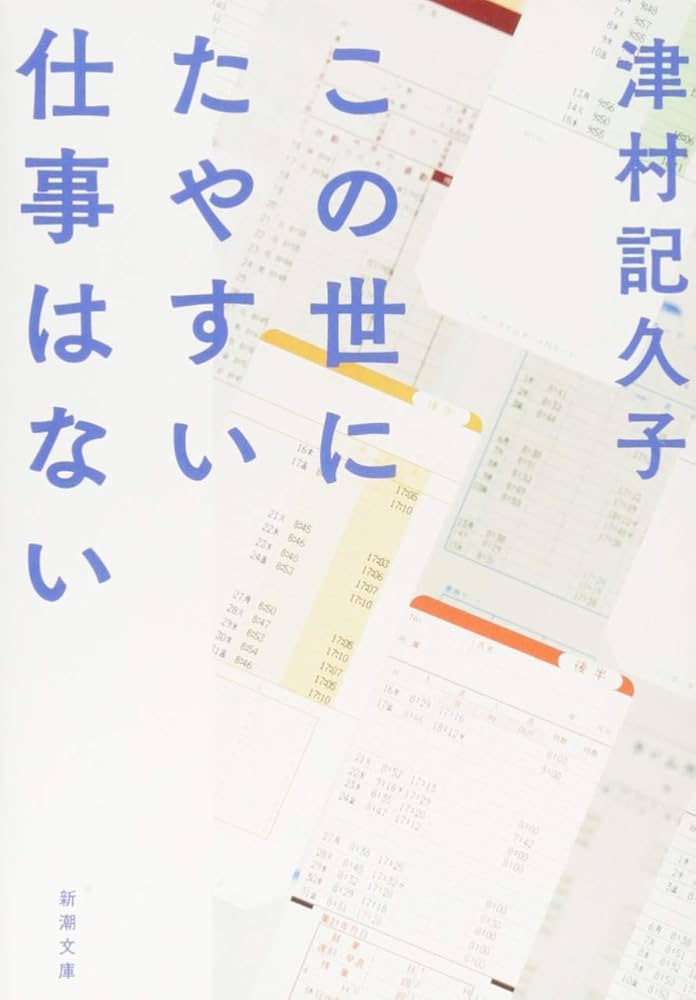
2位は、ユニークな仕事観が光る『この世にたやすい仕事はない』です。2016年に芸術選奨新人賞を受賞した作品で、津村さんの「お仕事小説」の代表格と言えるでしょう。
燃え尽き症候群で前の仕事を辞めた主人公が、ハローワークで見つけた風変わりな仕事に次々と就いていく物語です。バスの乗客数を数える仕事、おかきの袋の裏の文章を考える仕事など、一見「たやすそう」に見える仕事にも、それぞれ奥深さや大変さがあることをユーモラスに描いています。
「働くとは何か?」という普遍的なテーマを、軽やかな筆致で問い直してくれる本作。仕事に悩んでいる人はもちろん、毎日をなんとなく過ごしている人にも、新たな視点を与えてくれるはずです。



いろんなお仕事を追体験できるのが面白いよね。わたしもやってみたい仕事が見つかるかな?
3位『ポトスライムの舟』
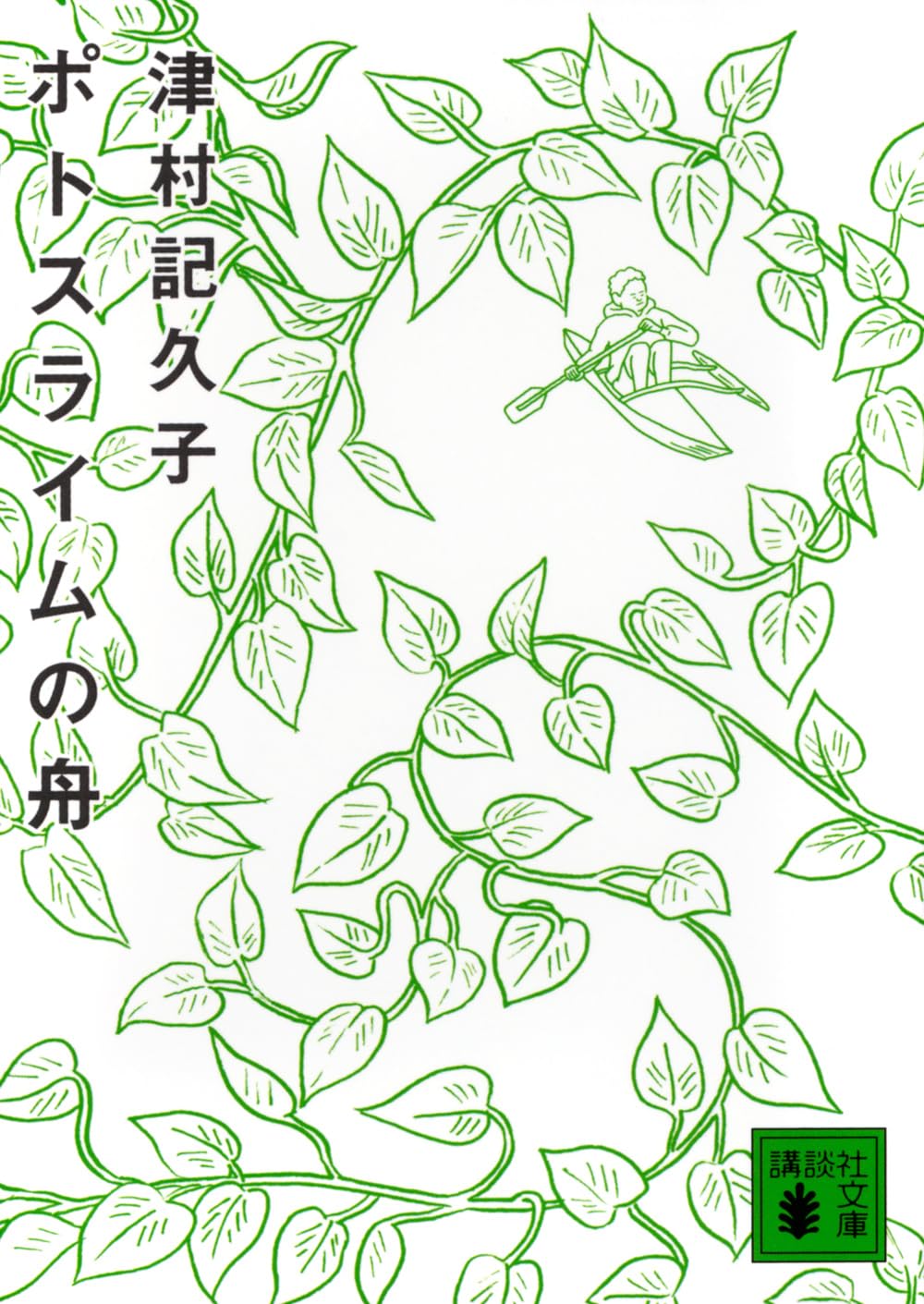
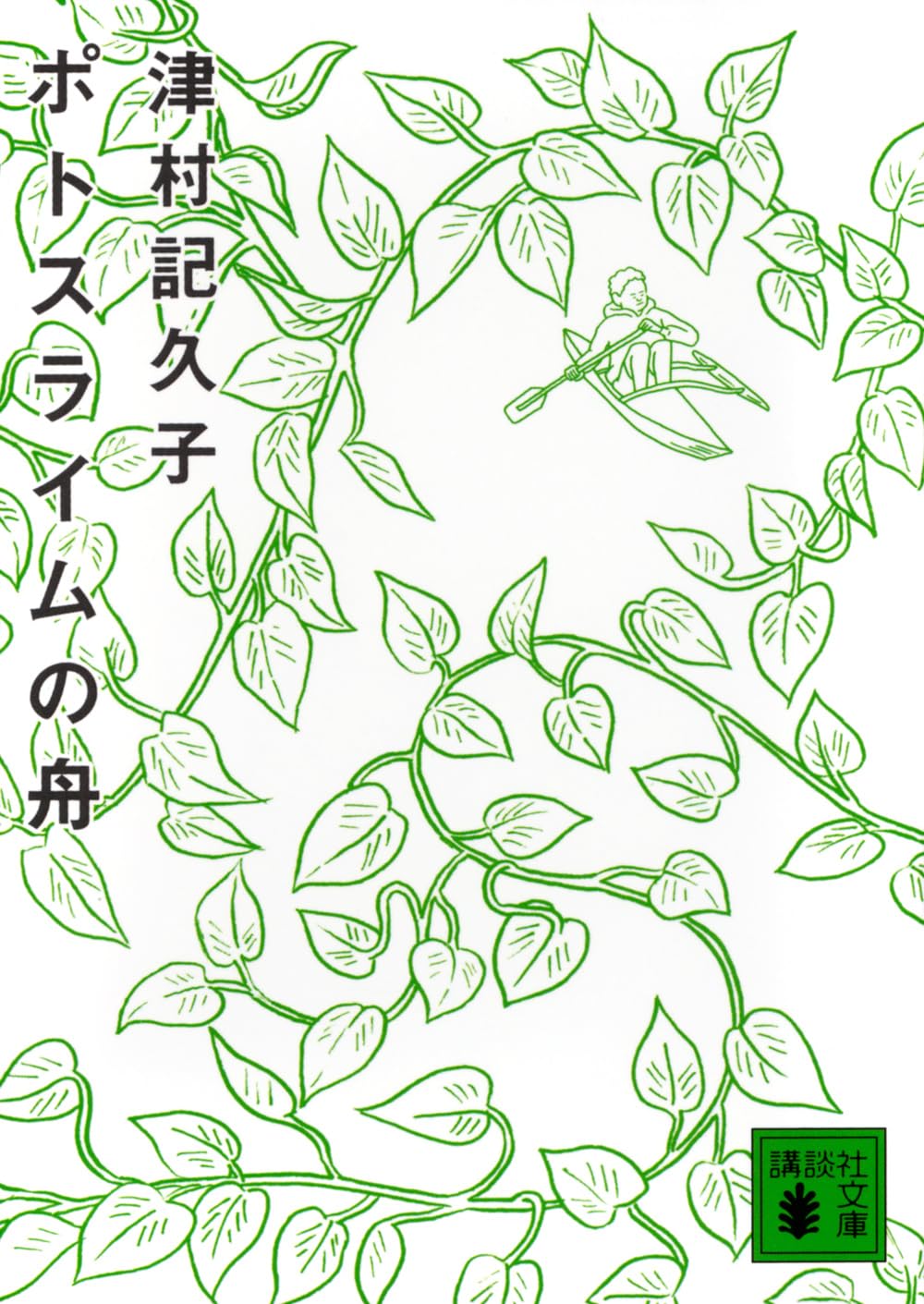
3位にランクインしたのは、2009年に第140回芥川賞を受賞した『ポトスライムの舟』です。 津村さんの名を一躍世に知らしめた、記念碑的な作品です。
主人公は、工場で契約社員として働く29歳の女性ナガセ。 手取り年収163万円という厳しい現実の中、「時間を金で売る」ことの虚しさを感じながら日々を過ごしています。 ある日、世界一周クルーズの費用が自分の年収とほぼ同額だと知った彼女は、その費用を貯めることを目標にしますが、その決意が彼女の日常に少しずつ変化をもたらしていきます。
お金や労働といったシビアな現実を扱いながらも、決して暗くならず、どこか飄々とした主人公の姿が印象的です。 閉塞感を抱えながらも、自分なりの希望を見つけようとする姿に、多くの読者が共感しました。



芥川賞受賞作だよ!働くことの虚しさと、それでも見つけ出す小さな希望の物語なんだ。
4位『君は永遠にそいつらより若い』
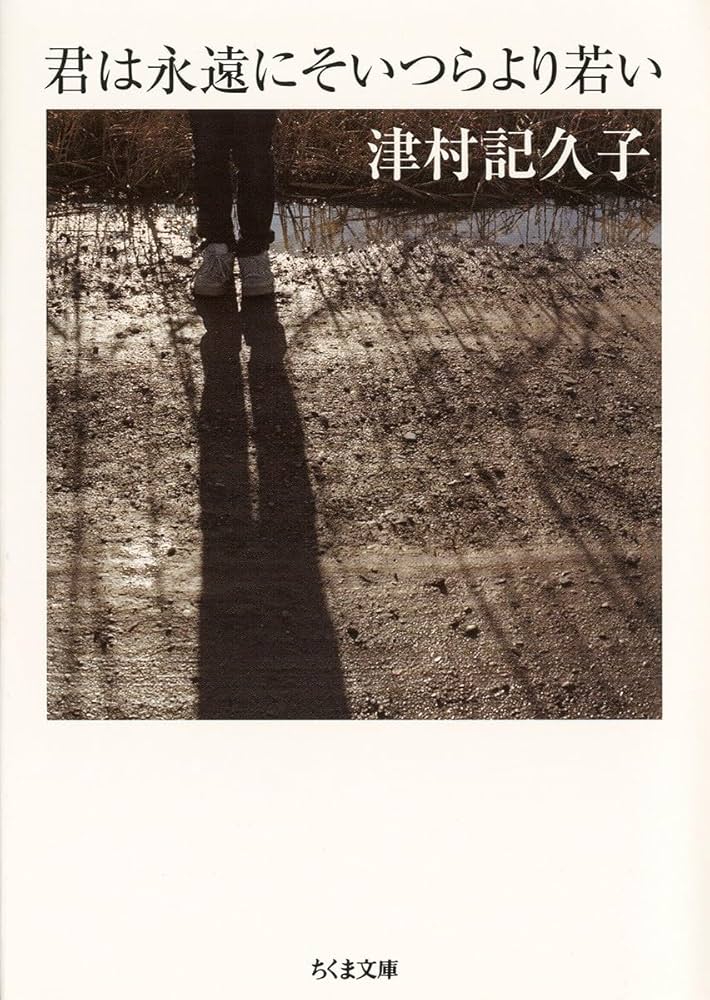
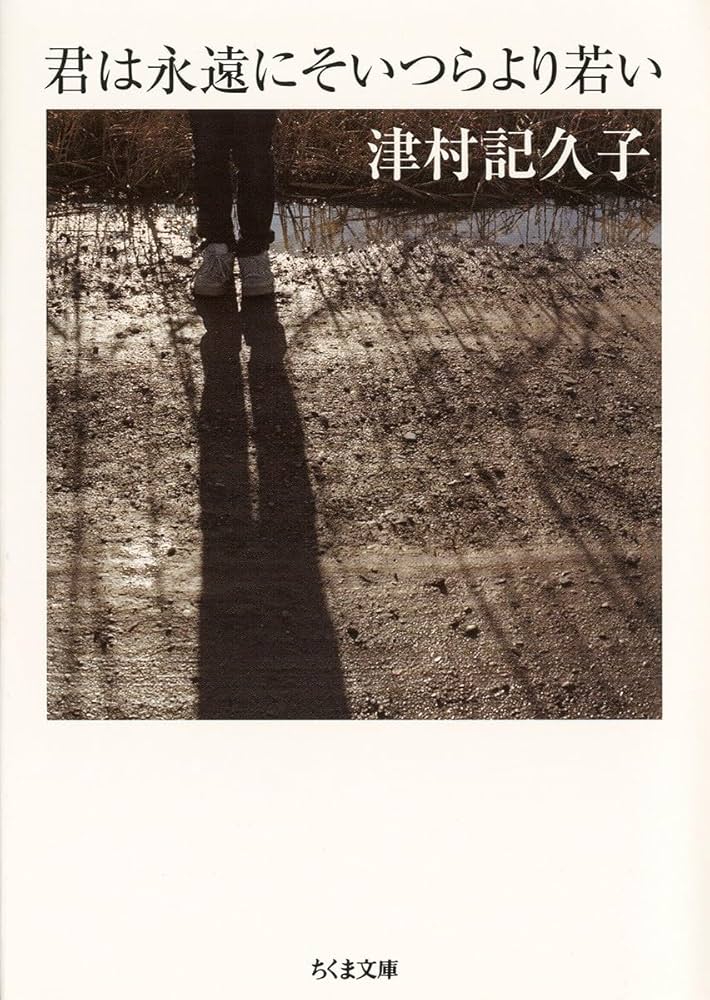
4位は、津村さんの鮮烈なデビュー作『君は永遠にそいつらより若い』です。 2005年に「マンイーター」というタイトルで第21回太宰治賞を受賞し、改題して刊行されました。 2021年には映画化もされ、再び注目を集めました。
大学卒業を間近に控えた主人公ホリガイの、少し手持ち無沙汰な日常が描かれます。 友人との他愛ない会話や、アルバイト先での出来事。そんな平凡な日々の裏に潜む、暴力や哀しみがふとした瞬間に顔をのぞかせます。 社会に出る前の、宙ぶらりんな時期の焦燥感や、漠然とした不安を巧みに描き出しています。
若者特有の万能感と無力感が入り混じった複雑な心情を、リアルな筆致で切り取った本作は、今読んでも色褪せない魅力を放っています。



デビュー作にしてこの切れ味!若さゆえの痛みとか、モラトリアムな感じがすごくリアルなんだよね。
5位『つまらない住宅地のすべての家』
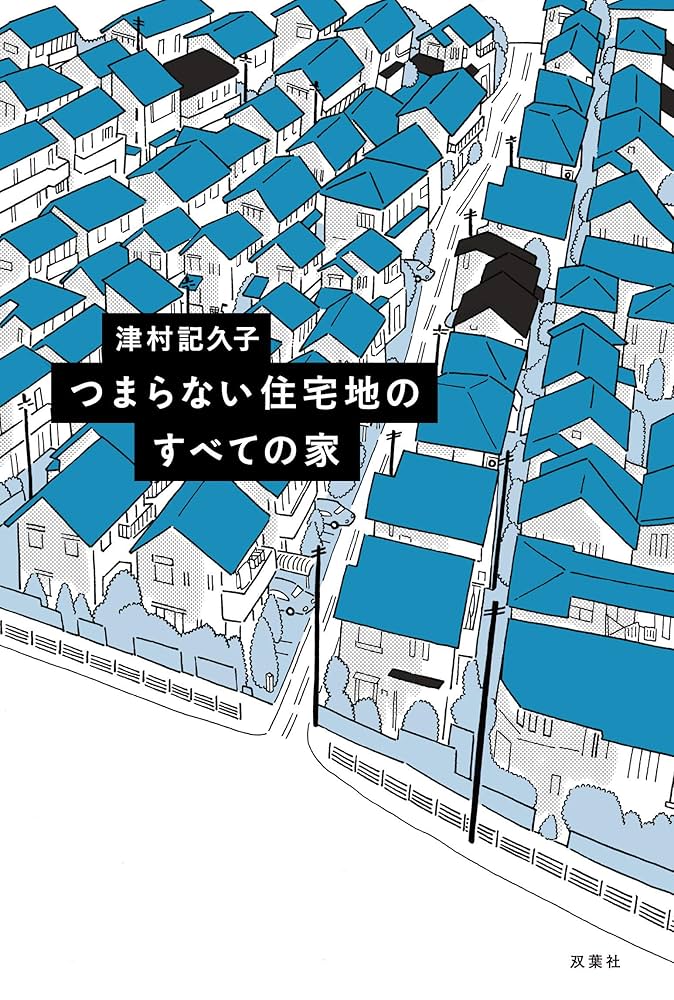
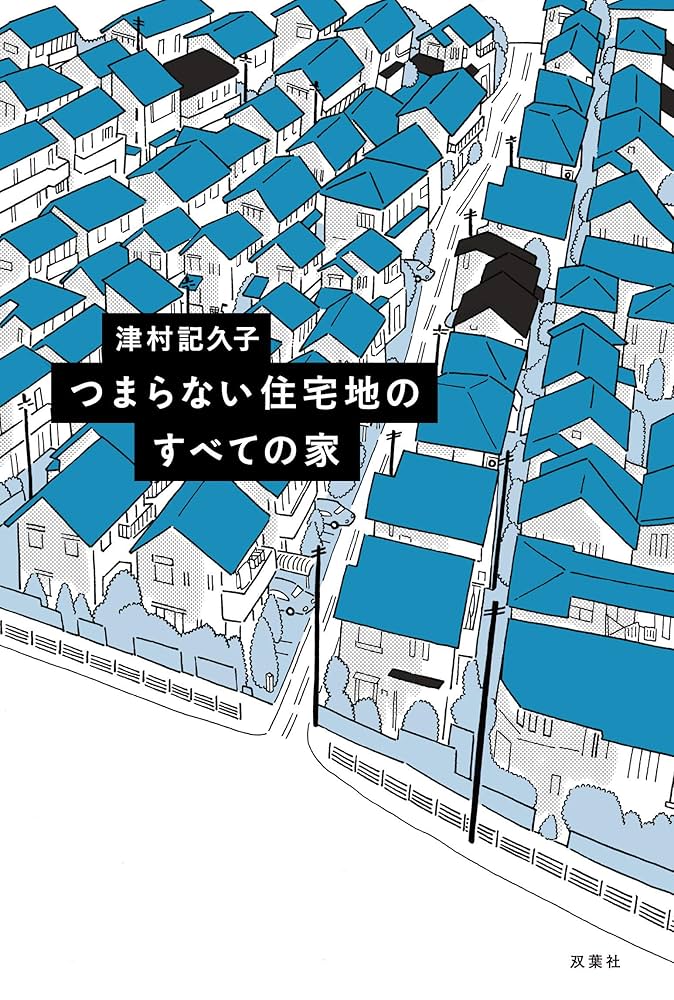
5位は、ありふれた日常に潜むサスペンスが魅力の『つまらない住宅地のすべての家』です。2022年にはテレビドラマ化もされ、話題となりました。
物語の舞台は、その名の通り、どこにでもありそうな平凡な住宅地。 ある日、女性受刑者が刑務所から脱走し、この町に向かっているらしいというニュースが飛び込んできます。 新任の自治会長が住民たちに交代での見張りを提案したことから、それぞれの家庭が抱える事情や秘密が、少しずつ明らかになっていきます。
何気ないご近所付き合いの中に潜む緊張感と、ユーモアあふれる人間模様が巧みに描かれた群像劇です。 平凡な日常が、一つのニュースをきっかけに非日常へと変わっていく様に、ページをめくる手が止まらなくなるでしょう。



ただの住宅地だと思ったら大間違い!脱走犯のニュースで、ご近所さんたちの秘密がどんどん暴かれていくのがハラハラするよ。
6位『ワーカーズ・ダイジェスト』
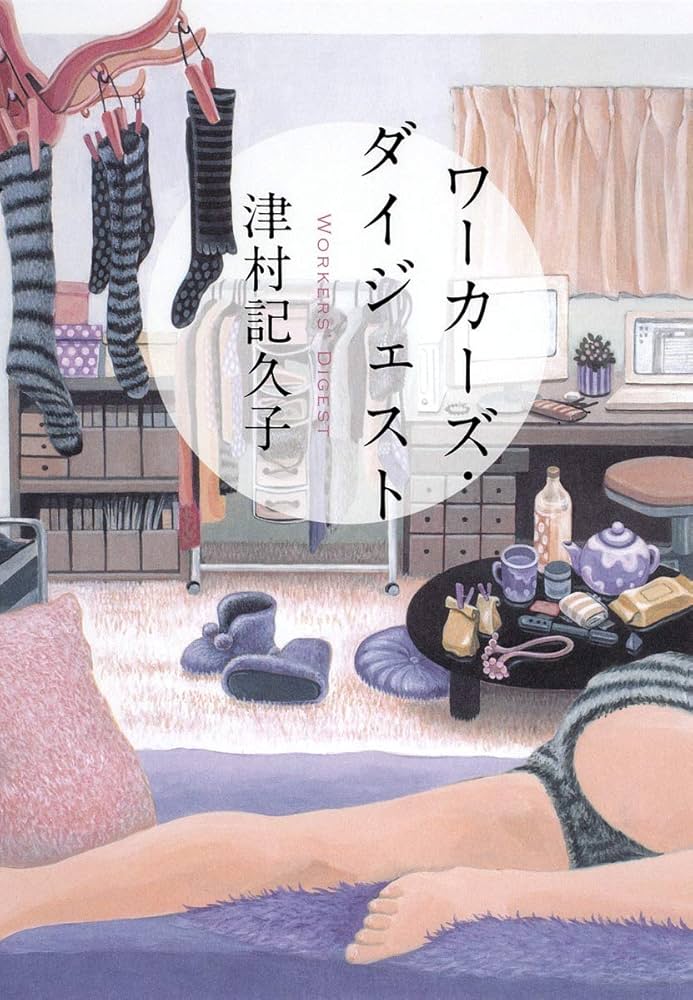
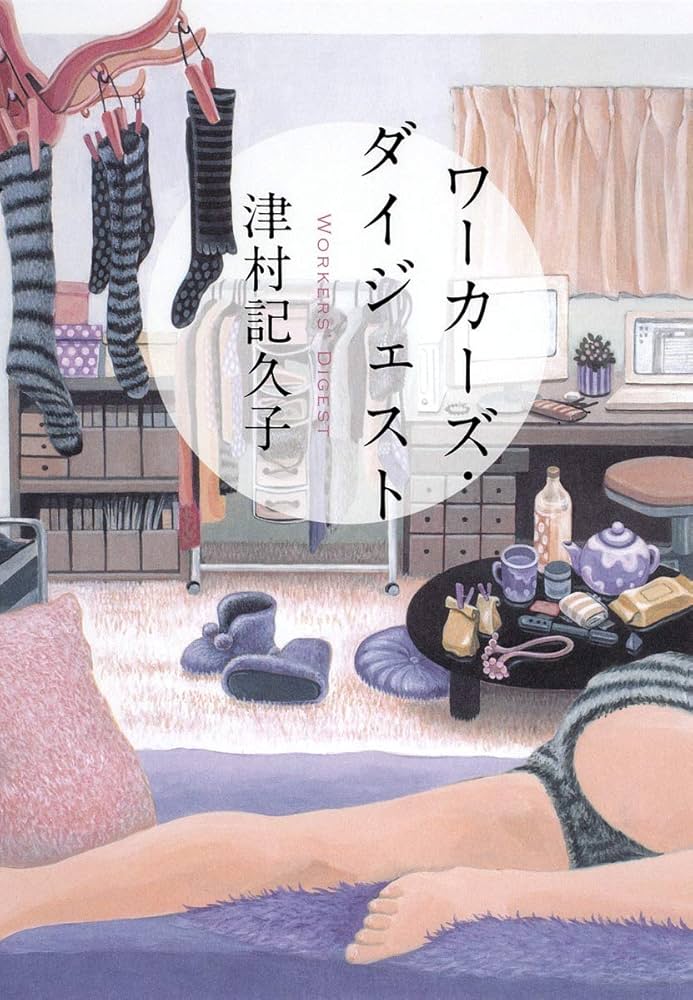
6位には、働く人々の姿を多彩に描いた『ワーカーズ・ダイジェスト』がランクイン。2011年に第28回織田作之助賞を受賞した、津村さんの真骨頂ともいえるお仕事小説集です。
本作は、さまざまな職場で働く人々を主人公にした7つの物語で構成されています。会社の資料室で働く女性、アパレルショップの店長、フリーペーパーの編集者など、登場人物の職業は多岐にわたります。
それぞれの仕事ならではの「あるある」ネタや、人間関係の悩み、仕事への矜持などがリアルに描かれており、読者はまるでその職場で一緒に働いているかのような感覚を味わえます。どんな仕事にも、それぞれのドラマがあることを教えてくれる一冊です。



いろんな職業の裏側が覗けるみたいでワクワクするね。自分の仕事と比べてみるのも面白いかも!
7位『サキの忘れ物』


7位は、一冊の本が人生を動かすきっかけとなる物語『サキの忘れ物』です。表題作を含む、輝きに満ちた9編が収録された短編集です。
表題作の主人公は、高校をやめて病院の喫茶店でアルバイトをしている千春。 特に夢中になれるものもなく日々を過ごしていた彼女ですが、ある日常連客が忘れていった「サキ」という作家の短編集を手に取ったことから、彼女の人生がゆっくりと動き始めます。
本を読むという行為が、いかに人の内面を豊かにし、世界を広げてくれるかを、静かな感動とともに描いています。 物語の力、そして人と人との出会いの温かさを感じさせてくれる、心に染みる一冊です。



一冊の本との出会いが、人生を変えるなんて素敵だよね。わたしも誰かの人生を変える一冊を紹介したいな。
8位『とにかくうちに帰ります』
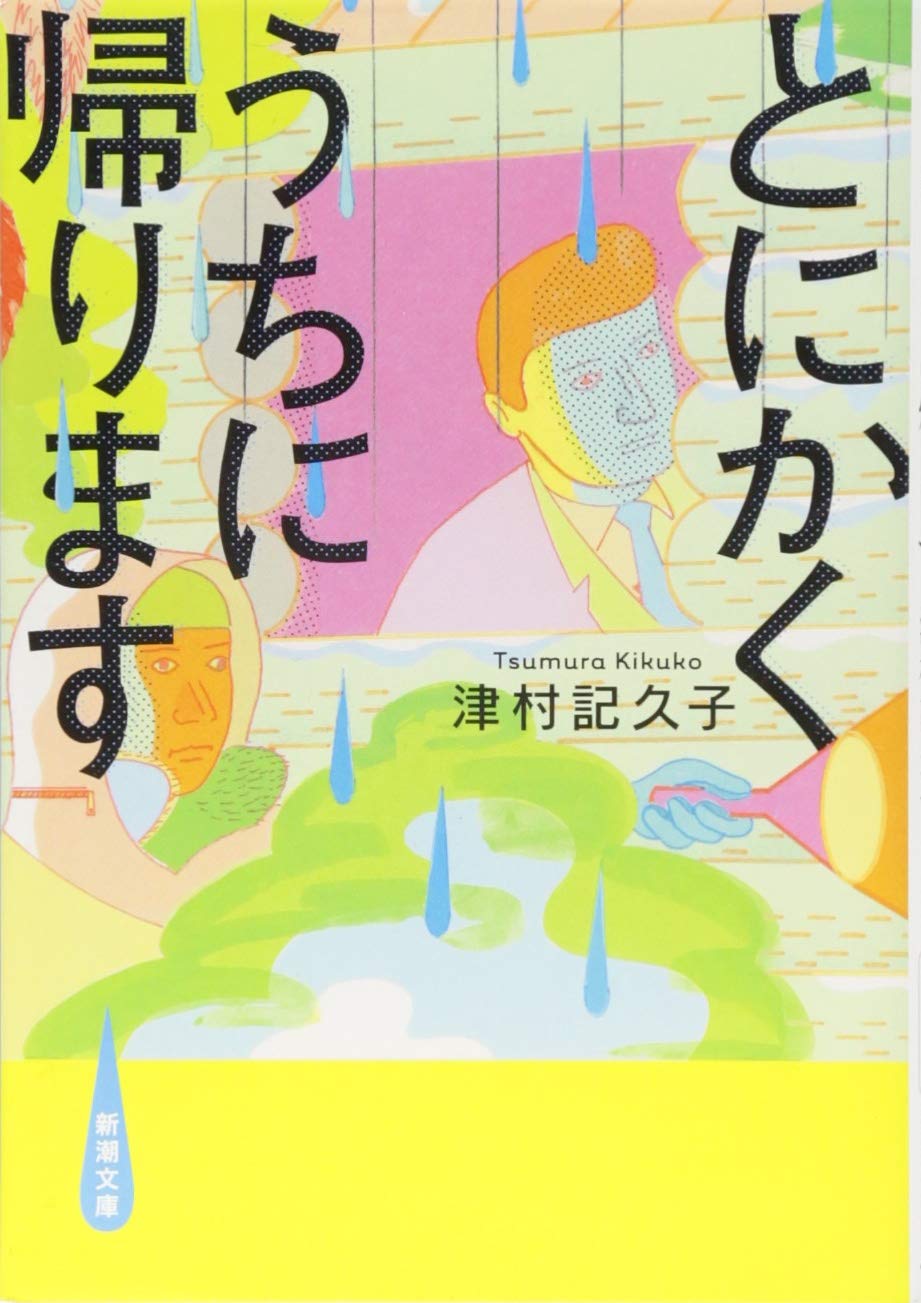
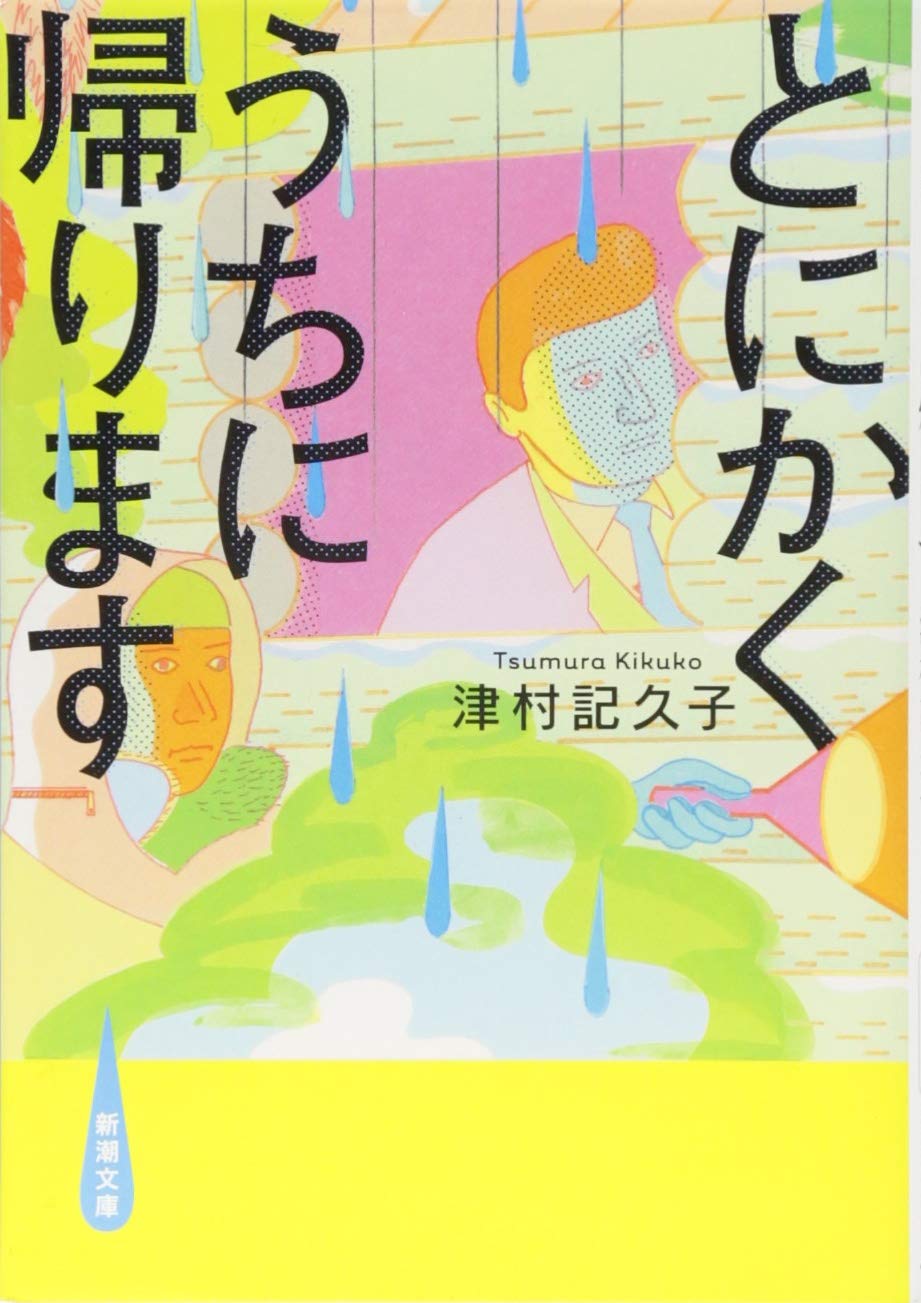
8位は、日々のささやかな出来事に焦点を当てた『とにかくうちに帰ります』です。仕事や学校を終え、「家に帰る」までの道のりを描いた7つの物語が収められています。
登場人物たちは、それぞれ異なる場所から自宅を目指します。その道中で起こる、ちょっとした出来事や、頭に浮かぶ様々な思い。派手な事件は起こりませんが、一日の終わりにある「家に帰る」という行為が、いかに私たちにとって大切で、心を落ち着かせる時間であるかを再認識させてくれます。
疲れた日に読めば、登場人物たちと一緒に家に帰るような、ほっとした気持ちになれるはず。日常を愛おしむ津村さんの優しい視線が感じられる作品集です。



「家に帰る」って当たり前のことだけど、そこには小さなドラマがたくさんあるんだね。なんだか自分の帰り道も楽しくなりそうだよ。
9位『ミュージック・ブレス・ユー!!』
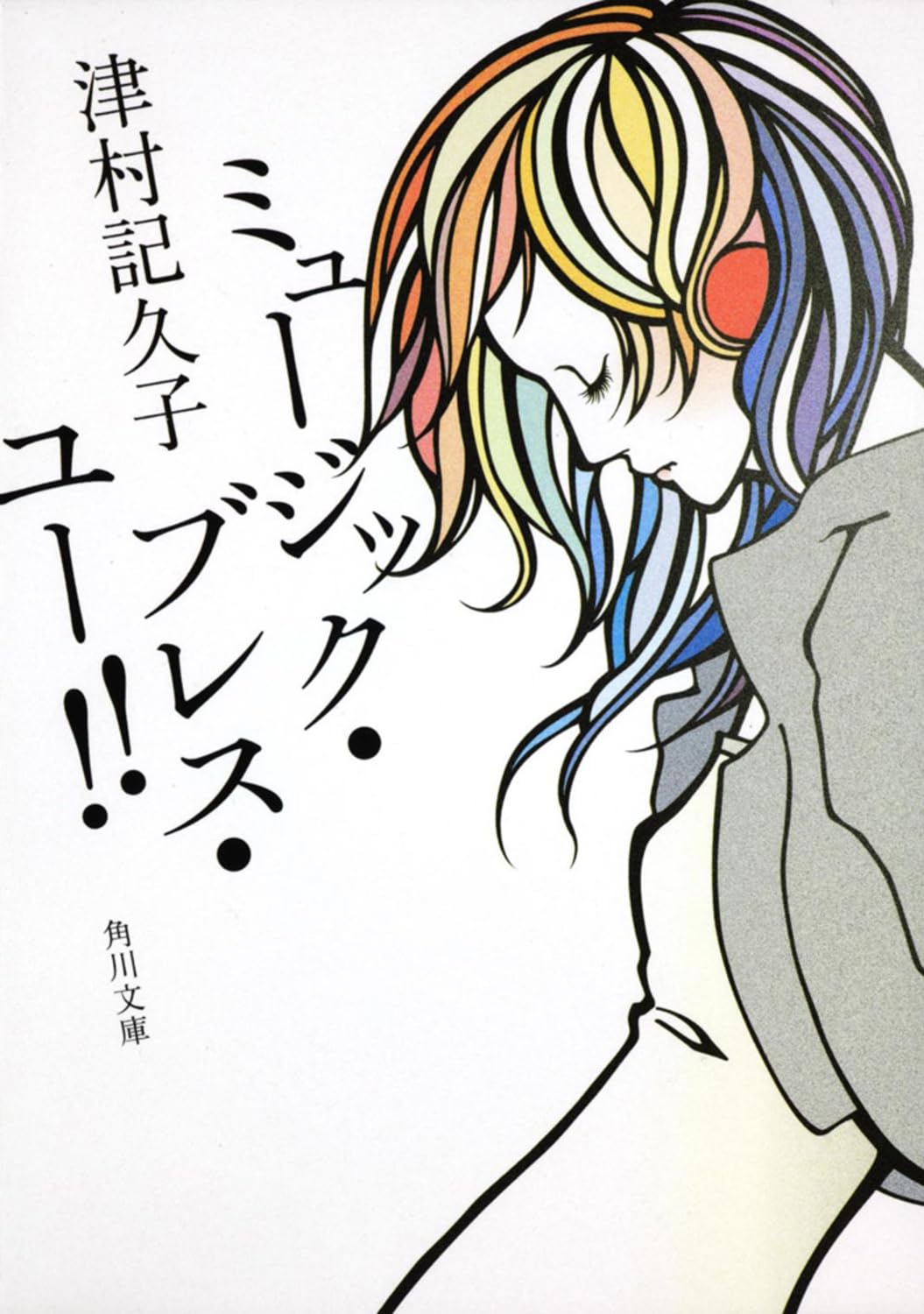
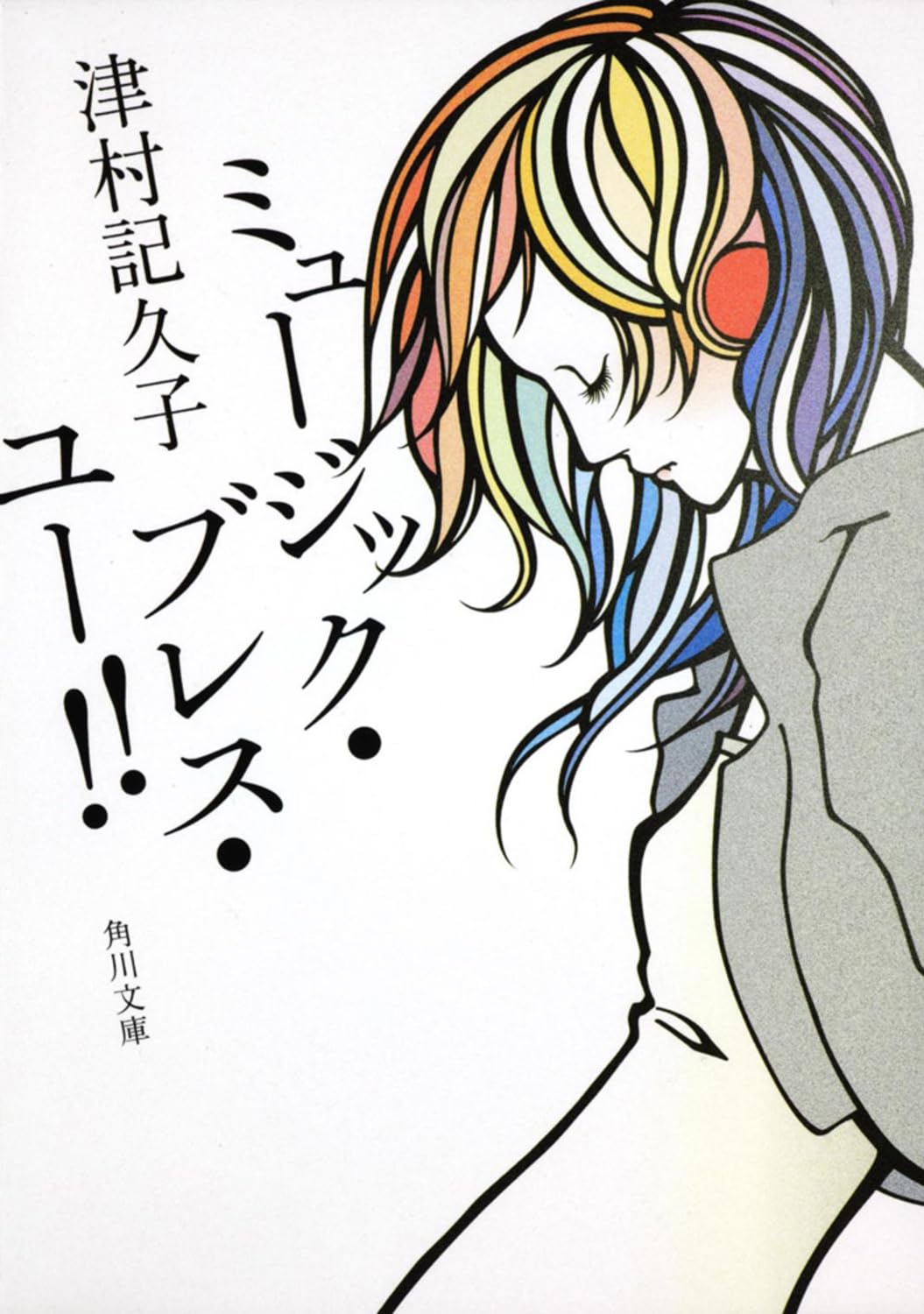
9位にランクインしたのは、音楽の力が人と人とを繋ぐ物語『ミュージック・ブレス・ユー!!』。2008年に第30回野間文芸新人賞を受賞した作品です。
物語の主人公は、ロンドンで暮らすことになった日本の大学生。ひょんなことから、現地のインディーズバンドの追っかけをすることになります。言葉も文化も違う場所で、音楽を通じて人々との交流を深めていく姿が瑞々しく描かれています。
好きなものがあることの強さや、それがもたらしてくれる出会いの素晴らしさを教えてくれる青春小説です。音楽好きはもちろん、何かに夢中になった経験がある人なら、きっと胸が熱くなるはずです。



音楽って国境を越えるんだね!好きなバンドを追いかける主人公の姿に、こっちまでワクワクしちゃうよ。
10位『うそコンシェルジュ』


10位は、思わずクスリと笑ってしまう設定が魅力の短編集『うそコンシェルジュ』です。 日常のちょっとした困りごとを「うそ」で乗り切る物語が11編収められています。
表題作の主人公は、大学のサークルを辞めたい姪のために、もっともらしい「うその理由」を考えてあげたことから、周りの人々から「うそ請負人」として頼られるようになってしまう女性。 誰かを助けるための優しい嘘が、思いがけない展開を巻き起こします。
「うそ」という少しネガティブなテーマを、津村さんらしいユーモアで軽やかに描いた作品です。 人間関係のストレスや日々のモヤモヤを、機転と優しさで乗り越えていく登場人物たちの姿に、心が少し軽くなるような一冊です。



誰かのための優しい嘘って、時には必要だよね。わたしも困っている人がいたら、素敵な嘘を考えてあげたいな。
11位『やりなおし世界文学』
11位は、津村さんの読書愛が詰まったエッセイ集『やりなおし世界文学』です。小説とは一味違う、作家の素顔が垣間見える一冊として人気を集めています。
誰もが一度は名前を聞いたことがあるような世界文学の名作を、津村さんならではのユニークな視点で読み解いていきます。「もしもこの登場人物が現代にいたら?」といった自由な発想で語られる作品解説は、難しそうだと敬遠していた文学作品へのハードルをぐっと下げてくれます。
「文学ってこんなに面白くて自由なんだ!」と再発見させてくれる本書。これから世界文学に挑戦したい人はもちろん、昔読んだけれど内容を忘れてしまったという人にもおすすめです。



世界文学って難しそうだけど、これなら楽しく読めそう!津村さんの解説で、名作の新しい魅力に気づけるかも。
12位『現代生活独習ノート』
12位には、日常の観察眼が光るエッセイ集『現代生活独習ノート』がランクイン。津村さんのユーモアと知性が詰まった、もう一つのおすすめエッセイです。
日々の生活の中で津村さんが感じたこと、考えたことが、軽妙な筆致で綴られています。電車で隣に座った人のこと、街で見かけた不思議な光景、自身の失敗談など、取り上げられるテーマは様々。何気ない日常も、作家の目を通すとこんなにも面白くなるのかと驚かされます。
津村作品の魅力の源泉である、人間や社会に対する温かくも鋭い視点が存分に味わえる一冊。小説のファンはもちろん、エッセイ好きにもぜひ読んでほしい作品です。



作家さんの頭の中をこっそり覗いているみたいで楽しいね。日常の解像度が上がりそうな一冊だよ。
13位『浮遊霊ブラジル』
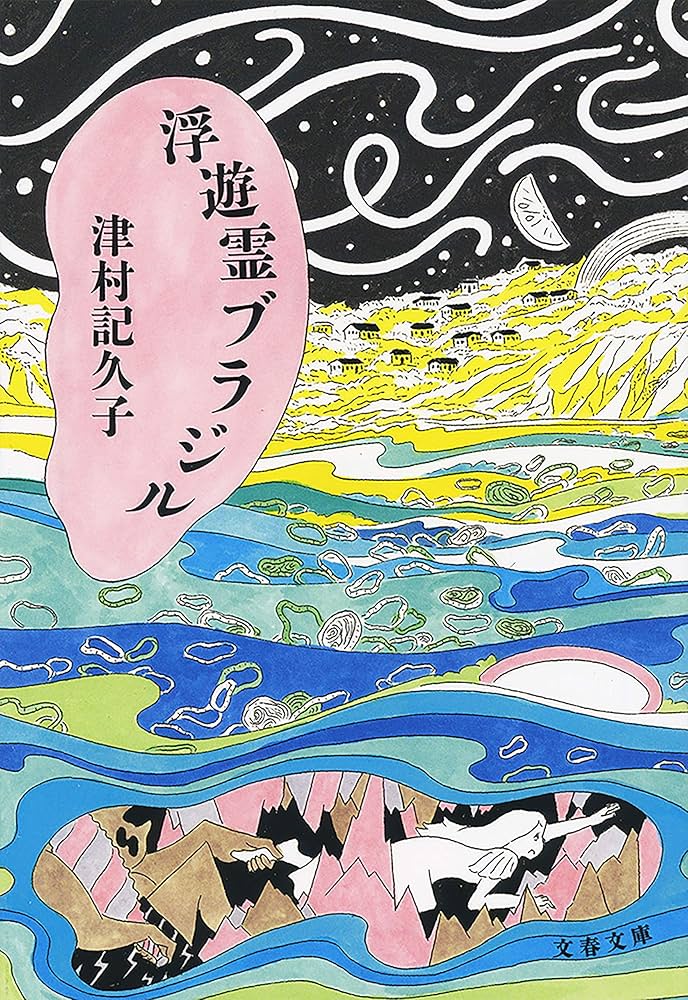
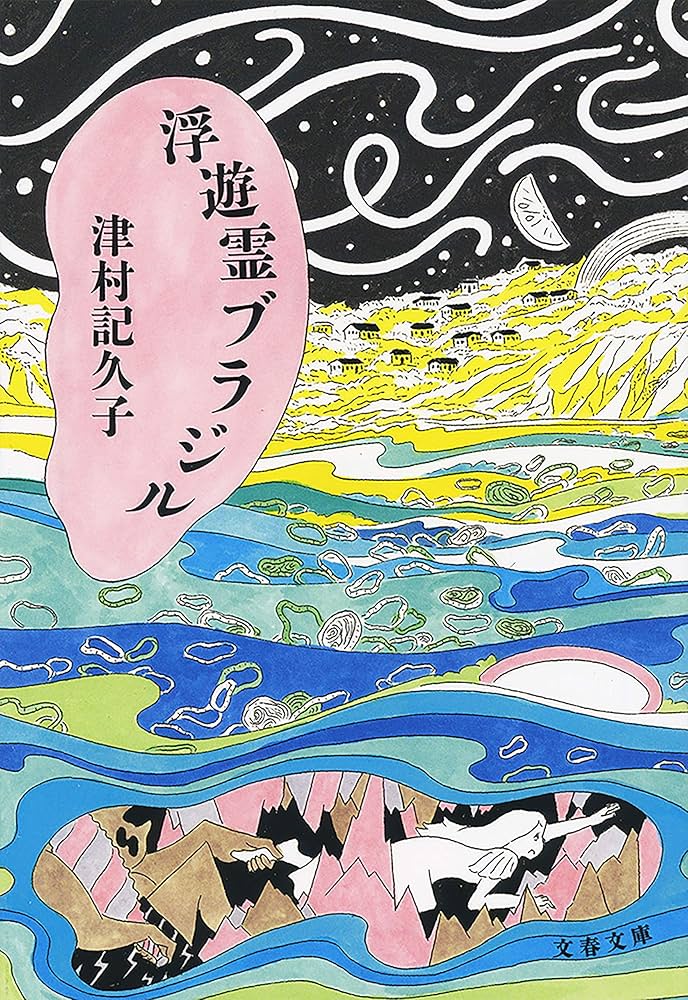
13位は、少し不思議な設定が心に残る『浮遊霊ブラジル』です。2017年に第27回紫式部文学賞を受賞した、幻想的な魅力を持つ作品です。
主人公は、ある日突然、自分にしか見えない「ブラジル」と名乗る浮遊霊につきまとわれるようになります。ブラジルとの奇妙な共同生活を通して、主人公は自身の過去や、抱えている喪失感と向き合っていくことになります。
突飛な設定でありながら、描かれているのは誰もが抱える孤独や悲しみに寄り添う、普遍的な物語です。現実と非現実が入り混じる独特の世界観に引き込まれ、静かな感動が胸に広がります。



浮遊霊との同居生活なんて、一体どうなっちゃうんだろう…。悲しいだけじゃない、不思議な温かさがある物語なんだ。
14位『カソウスキの行方』
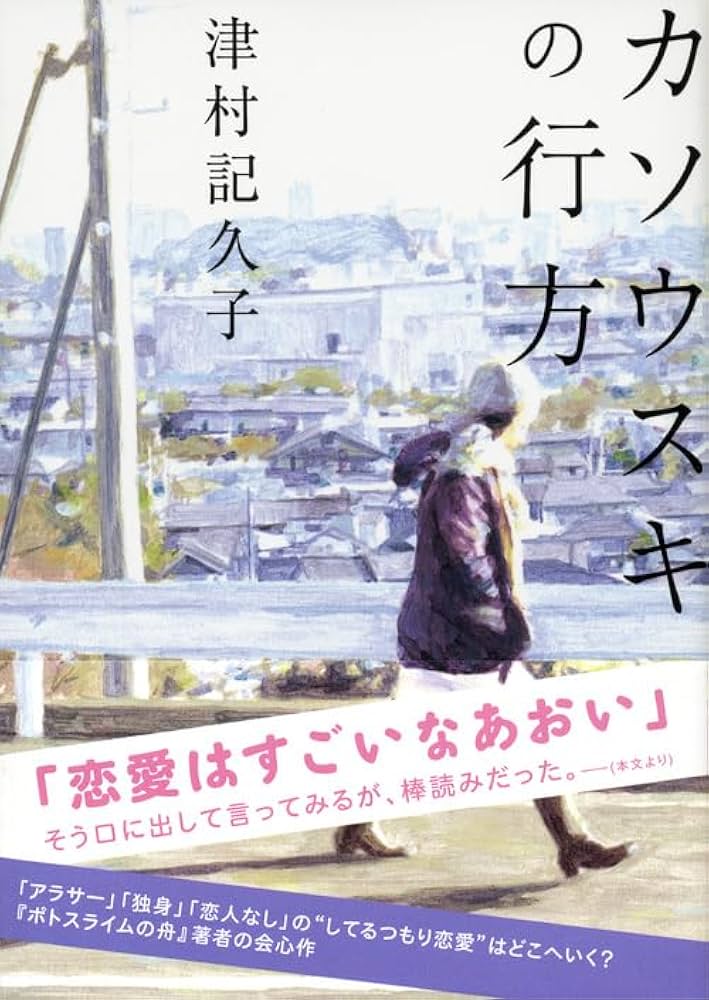
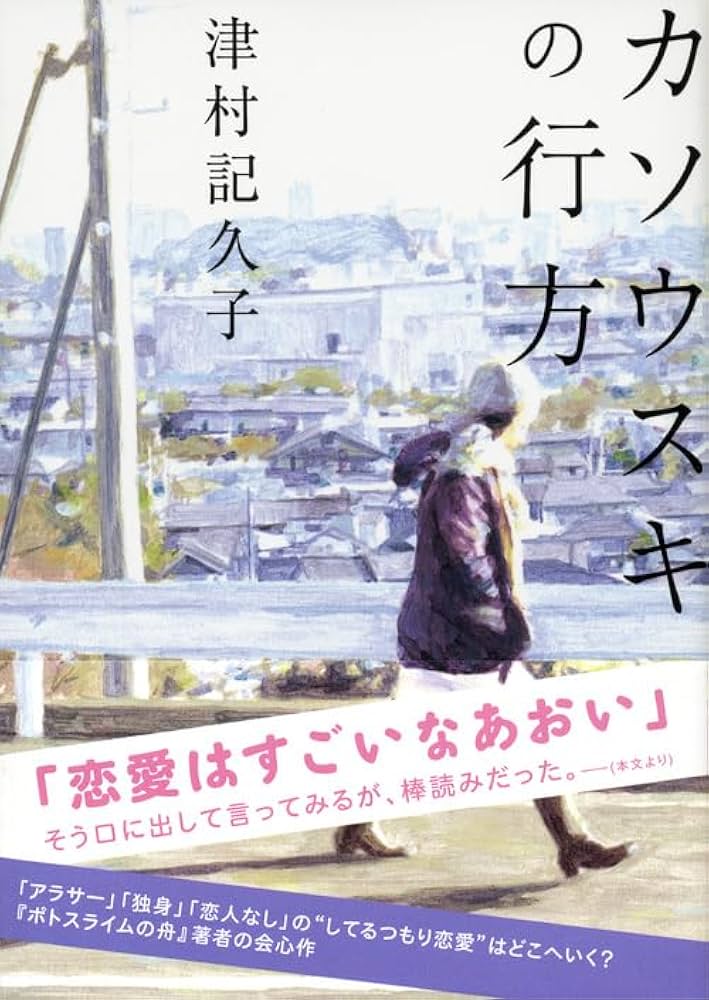
14位は、芥川賞候補にもなった初期の重要作『カソウスキの行方』です。 会社という組織の中で働くことの理不尽さや、そこで生まれる奇妙な連帯感を巧みに描いています。
主人公が勤める会社に、かつて在籍していたという伝説の社員「カソウスキ」。誰もが彼の噂をするけれど、その実態は誰も知らない。主人公は、カソウスキの行方を追ううちに、会社の奇妙な人間関係や、働くことの意味について深く考えるようになります。
津村さんならではのユーモアと皮肉が効いたお仕事小説であり、謎の人物を追うミステリーのような面白さも兼ね備えています。初期作品ながら、その後の作風に繋がる魅力が詰まった一冊です。



伝説の社員「カソウスキ」って一体何者なんだろう?会社の不思議な噂話から始まるミステリー、気になっちゃうね!
15位『アレグリアとは仕事はできない』
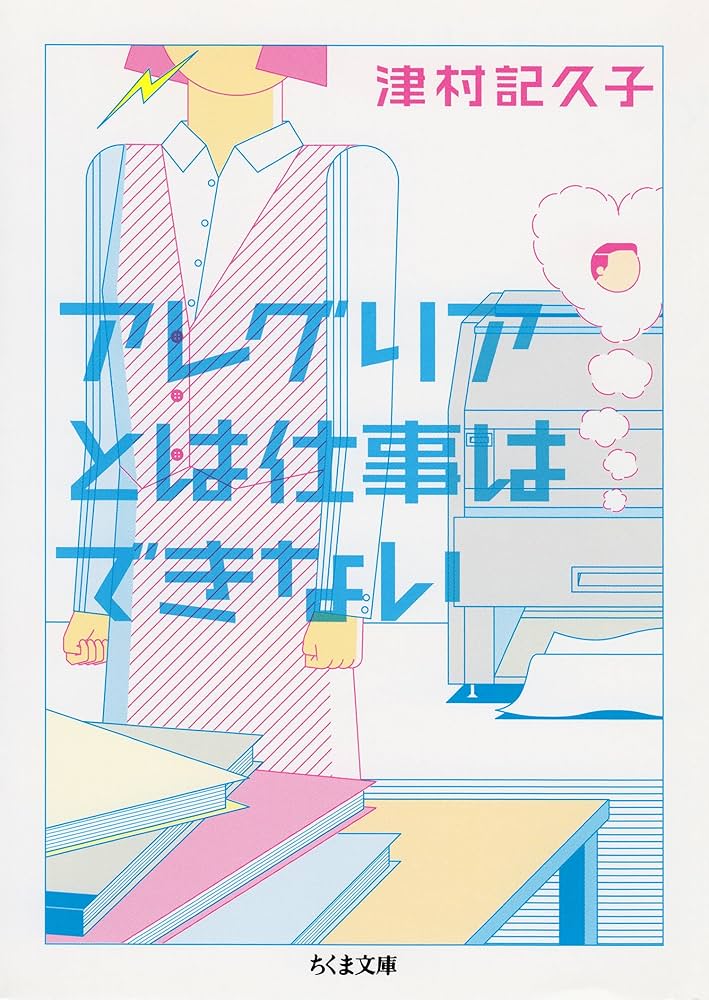
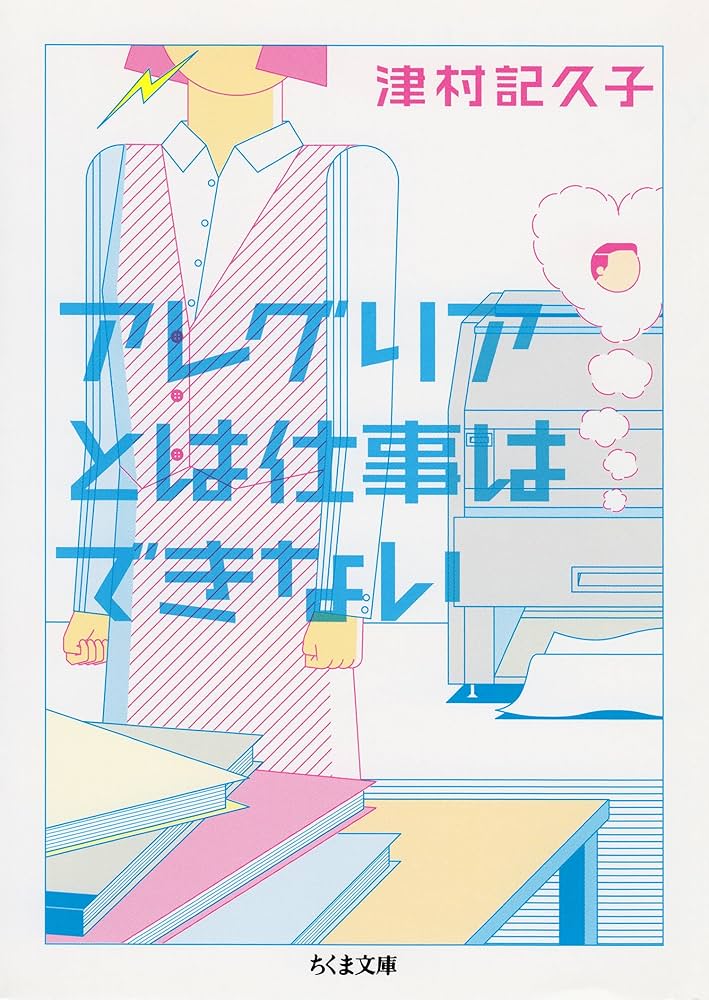
15位は、働く人の怒りと共感を誘う『アレグリアとは仕事はできない』です。 主人公の敵は、人間ではなく、言うことを聞かない会社の大型複合コピー機「アレグリア」。
主人公のミノベは、地質調査会社で報告書を製本する仕事をしています。 しかし、新しく導入されたアレグリアは、すぐに機嫌を損ねて動かなくなり、ミノベの怒りは募るばかり。 コピー機相手に本気で憤慨するミノベの姿が、滑稽でありながらも、理不尽な職場で働く多くの人々の共感を呼びます。
機械を擬人化し、会社組織の矛盾やストレスをユーモラスに描き出した本作は、読めばスカッとすること間違いなし。毎日仕事でストレスを溜めているあなたにこそ、読んでほしい一冊です。



コピー機に本気でキレる主人公、他人事じゃないかも…。職場の「あるある」が詰まってて、笑いながらも共感しちゃうんだ。
16位『ディス・イズ・ザ・デイ』
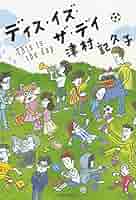
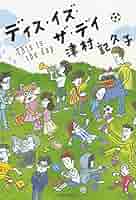
16位は、サッカーファンならずとも胸が熱くなる群像劇『ディス・イズ・ザ・デイ』です。 サッカーJ2リーグの最終節、同じ日、同じ時間にキックオフされる11試合を応援する、22チーム22人のサポーターたちの物語が描かれます。
職場の人間関係に悩む会社員、親離れする息子と母、離婚した両親のせいで久しぶりに再会した祖母と孫など、登場するのはごく普通の人々。 彼らがそれぞれの人生を背負い、愛するチームの勝敗に一喜一憂する姿が、エモーショナルに綴られます。
何かを、誰かを、熱く応援することの素晴らしさを教えてくれる連作小説集です。 サッカーに興味がなくても、登場人物の誰かにきっと自分を重ねてしまうはずです。



サッカーの試合を通して、いろんな人の人生が交差するんだね。応援するって、自分の人生を応援することにも繋がるのかも!
17位『ポースケ』
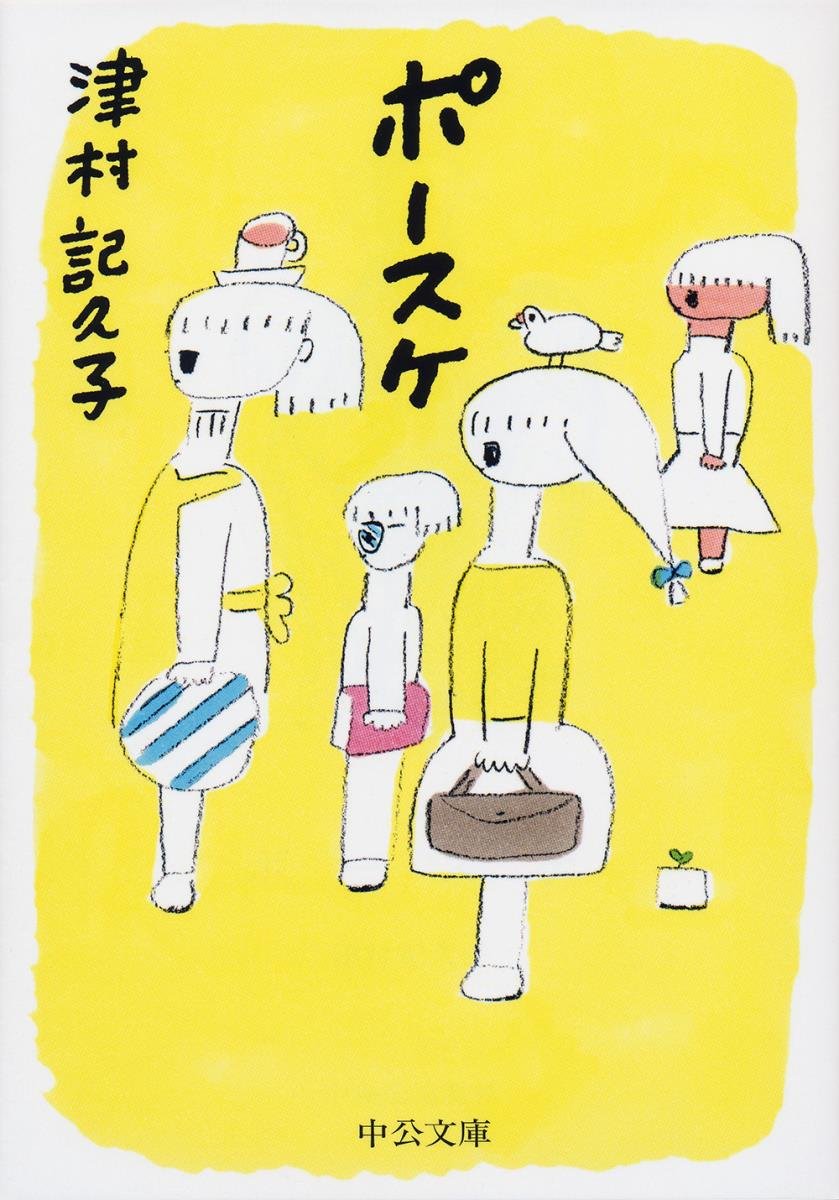
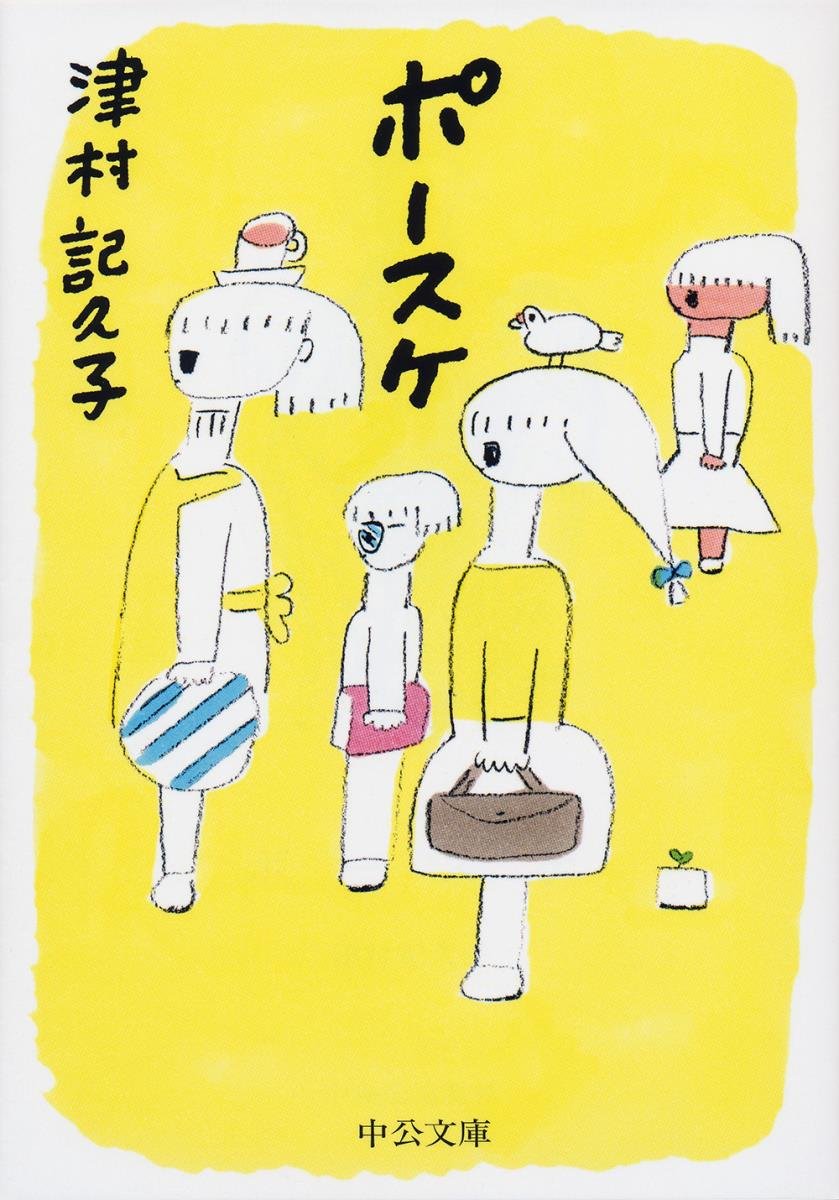
17位には、孤独な主人公と不思議な生き物の交流を描いた、心温まる物語『ポースケ』がランクインします。
主人公の部屋に、ある日突然現れた謎の生き物「ポースケ」。言葉は話さないけれど、どこか人間味のあるポースケとの共同生活が、主人公の孤独な日々に彩りを与えていきます。
大きな事件が起こるわけではありませんが、一人と一匹(?)の間に流れる穏やかで優しい時間に、心が癒やされます。誰かと一緒にいることの温かさや、言葉を超えたコミュニケーションの大切さを感じさせてくれる、絵本のような魅力を持った小説です。



謎の生き物ポースケ、気になる!言葉が通じなくても、一緒にいるだけで心が通じるって素敵だね。
18位『これからお祈りにいきます』
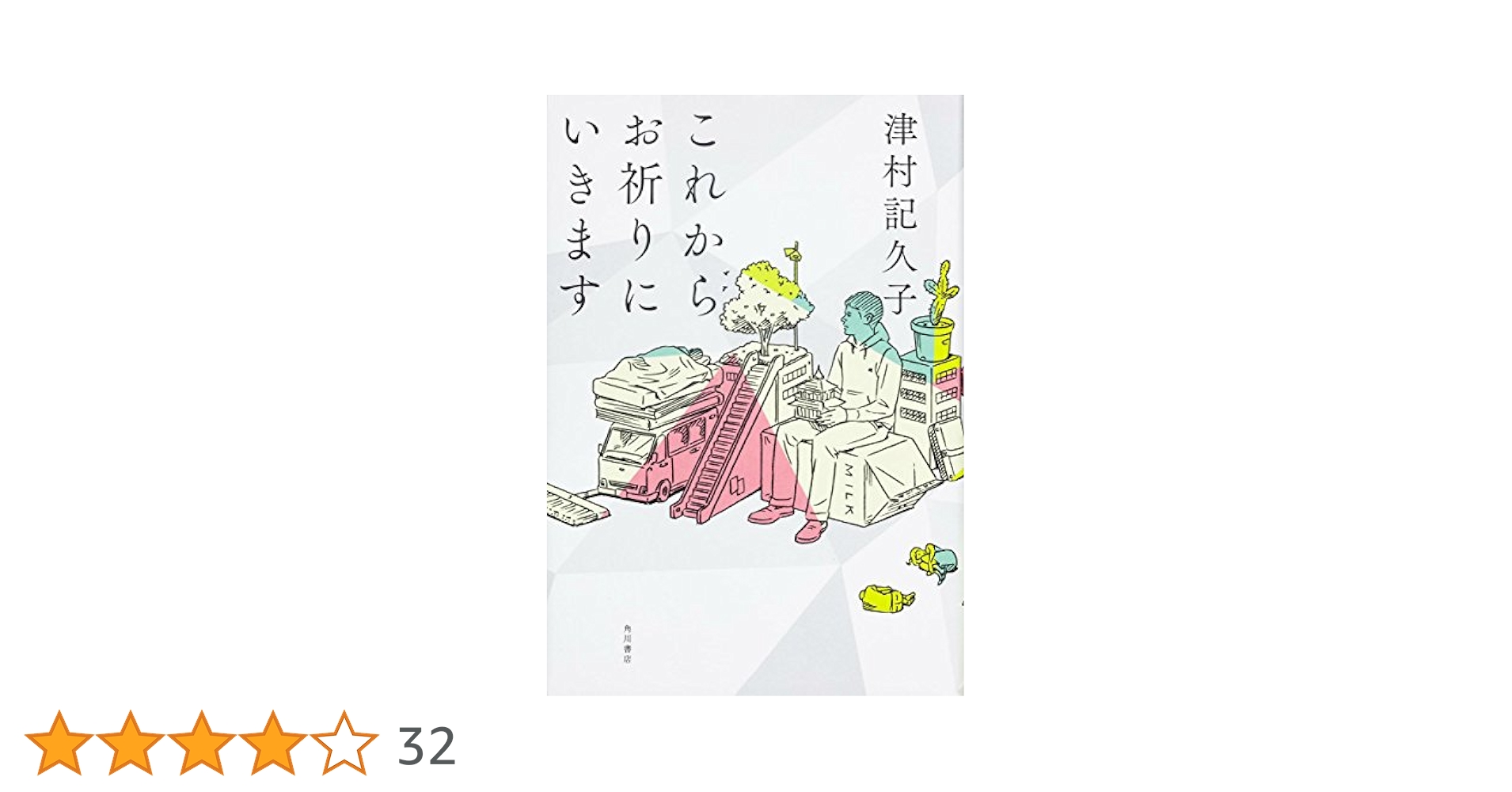
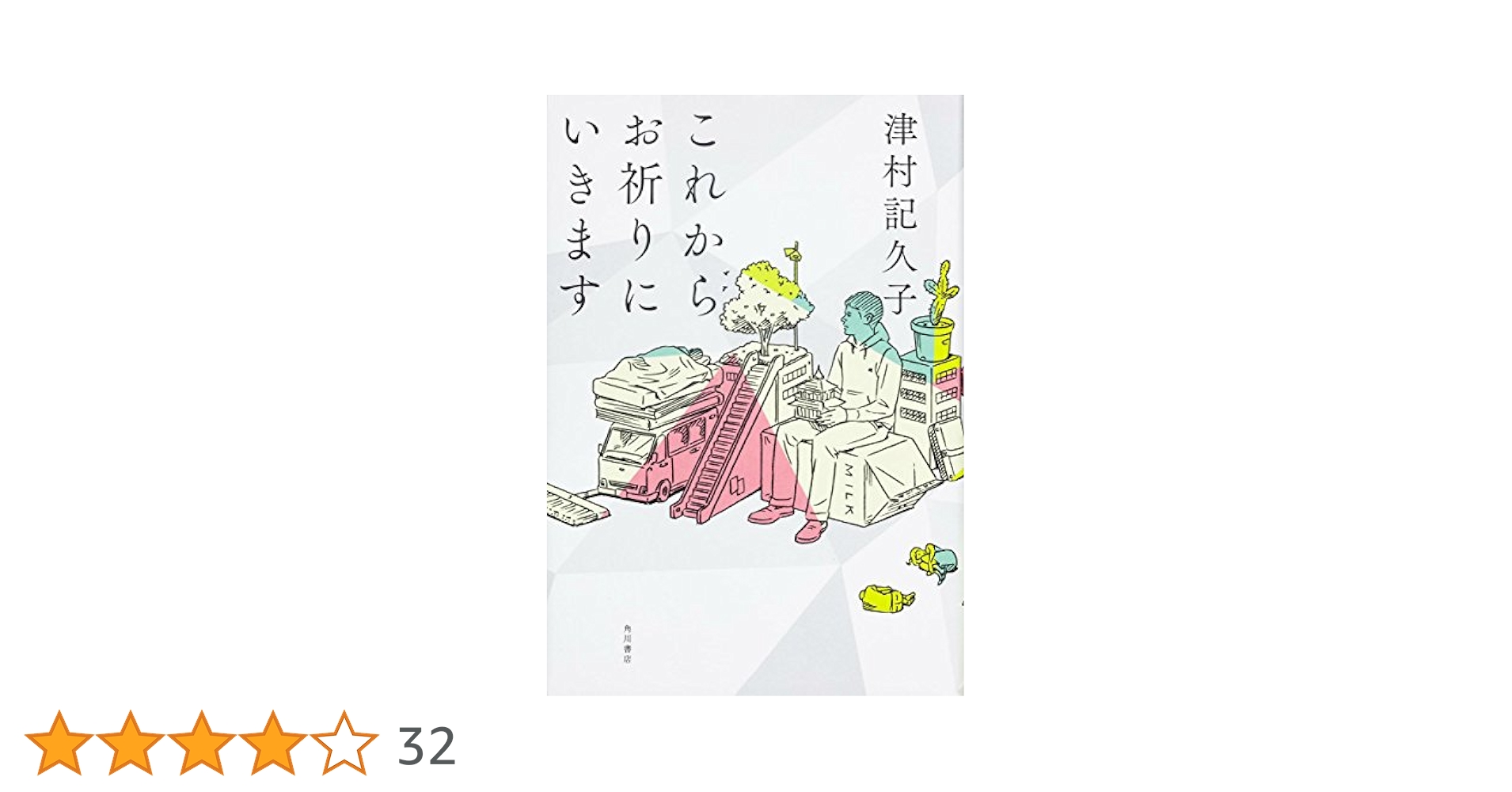
ランキングの最後を飾るのは、人々の様々な「祈り」のかたちを描いた短編集『これからお祈りにいきます』です。
登場するのは、大きな願い事から、日常の些細な願いまで、心に「祈り」を抱える人々。その祈りは、神様に届くものもあれば、誰にも知られず消えていくものもあります。
人が何かを祈るときの、切実で、時に滑稽で、そして愛おしい姿を、津村さんらしい温かい眼差しで切り取っています。読者自身の心の中にある小さな祈りに、そっと光を当ててくれるような作品集です。



みんな、心の中でいろんなことを祈っているんだね。この本を読むと、自分の小さな願いも大切にしようって思えるよ。
まとめ:気になる一冊から津村記久子の世界へ
ここまで、津村記久子さんのおすすめ小説をランキング形式でご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。お仕事小説から、家族の物語、少し不思議な設定の作品まで、その作風は非常に多彩です。
しかし、どの作品にも共通しているのは、現代を生きる私たちの日常に寄り添い、ままならない現実の中に確かな希望を見出そうとする優しい視線です。津村さんの小説は、読後、明日をもう少しだけ頑張ってみようと思わせてくれる、不思議な力を持っています。
今回のランキングを参考に、あなたが今一番惹かれる一冊をぜひ手に取ってみてください。そこから、豊かで奥深い津村記久子の世界が広がっていくはずです。