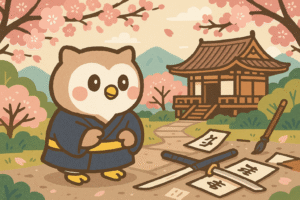あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】井出孫六のおすすめ小説・名著ランキングTOP20

井出孫六とは?歴史の真実を追い求めた作家
井出孫六(いで まごろく)は、1931年生まれの日本の小説家・ルポライターです。2020年に89歳で亡くなるまで、数多くの作品を世に送り出しました。長野県出身で、東京大学文学部を卒業後、教師や出版社勤務を経て著述業に専念するという経歴の持ち主です。
彼の作品は、小説やルポルタージュが中心で、綿密な調査に基づいて歴史の真実を追求するスタイルが特徴です。1975年には『アトラス伝説』で第72回直木賞を、1986年には『終わりなき旅 「中国残留孤児」の歴史と現在』で第13回大佛次郎賞を受賞するなど、高く評価されています。特に、自身のライフワークとして中国残留孤児問題に深く関わり、精力的な取材と執筆活動を続けました。
井出孫六のおすすめ小説・名著ランキングTOP20
ここからは、井出孫六のおすすめ小説や名著をランキング形式でご紹介します。
歴史の波に翻弄された人々の声なき声に耳を傾け続けた井出孫六。その作品群は、私たちに歴史の深淵を覗かせ、現代を生きる意味を問いかけてくれます。重厚なノンフィクションから、人間味あふれる評伝まで、あなたの心に響く一冊がきっと見つかるはずです。
1位『抵抗の新聞人 桐生悠々』

『抵抗の新聞人 桐生悠々』は、戦前の暗い時代に、反戦と不正追及の姿勢を貫いたジャーナリスト・桐生悠々(きりゅう ゆうゆう)の生涯を描いた傑作ノンフィクションです。桐生悠々は、明治から昭和初期にかけて、軍国主義化していく日本社会に警鐘を鳴らし続けた反骨の新聞人として知られています。
信濃毎日新聞の主筆として、乃木大将の殉死を批判した社説や、軍部の防空演習を痛烈に批判した「関東防空大演習を嗤ふ」は特に有名です。軍からの圧力で職を追われてもなお、個人雑誌『他山の石』を発行し、たった一人で軍部批判を続けたその生き様は、現代に生きる私たちにも大きな問いを投げかけます。井出孫六は、時代の流れに屈することなく言論の自由を求め続けた一人の人間の、燃えるような68年の生涯を見事に描き切っています。
 ふくちい
ふくちい権力に屈しない桐生悠々の生き様、かっこいいね!こういう骨のあるジャーナリストがいたって知れてよかったよ。
2位『終わりなき旅 「中国残留孤児」の歴史と現在』
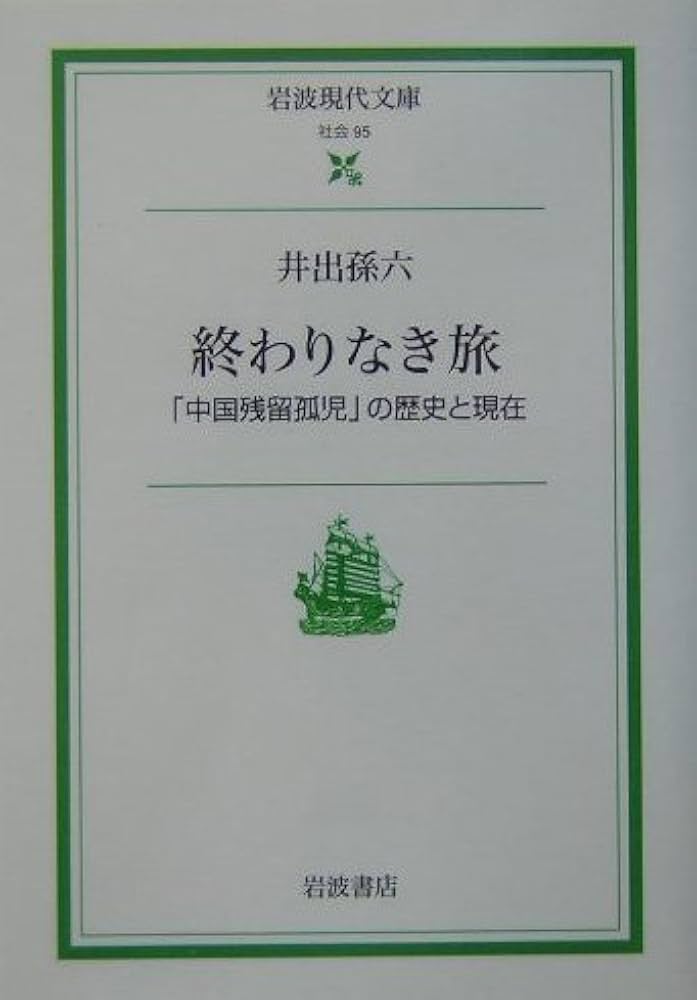
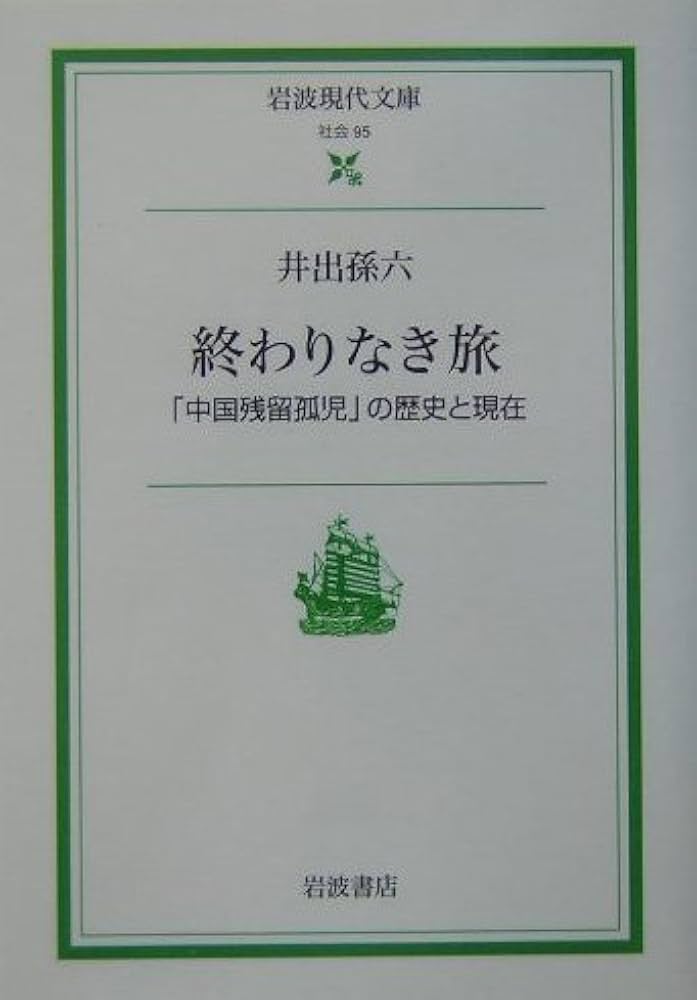
『終わりなき旅』は、井出孫六の代表作の一つであり、1986年に大佛次郎賞を受賞した長編ルポルタージュです。本書が光を当てるのは、国策によって満州に渡り、敗戦によって置き去りにされた「中国残留孤児」たちの悲劇。著者は、特に多くの開拓団を送り出した自身の故郷・長野県に焦点を当て、その歴史と現在を丹念に取材しています。
貧困からの脱出と国防を掲げた国策が、いかにして多くの人々を過酷な運命に導いたのか。そして、戦後も長く続いた彼らの苦難とは何だったのか。本書は、一人ひとりの証言を通して、庶民にとって国家とは、戦争とは何かという根源的な問いを私たちに突きつけます。井出孫六自身もこの問題に深く関わり、訴訟の証人として法廷に立つなど、その活動は執筆だけにとどまりませんでした。



国策に翻弄された人々の人生が重すぎる…。戦争が終わっても苦しみは終わらないなんて、悲しいよ。
3位『アトラス伝説』
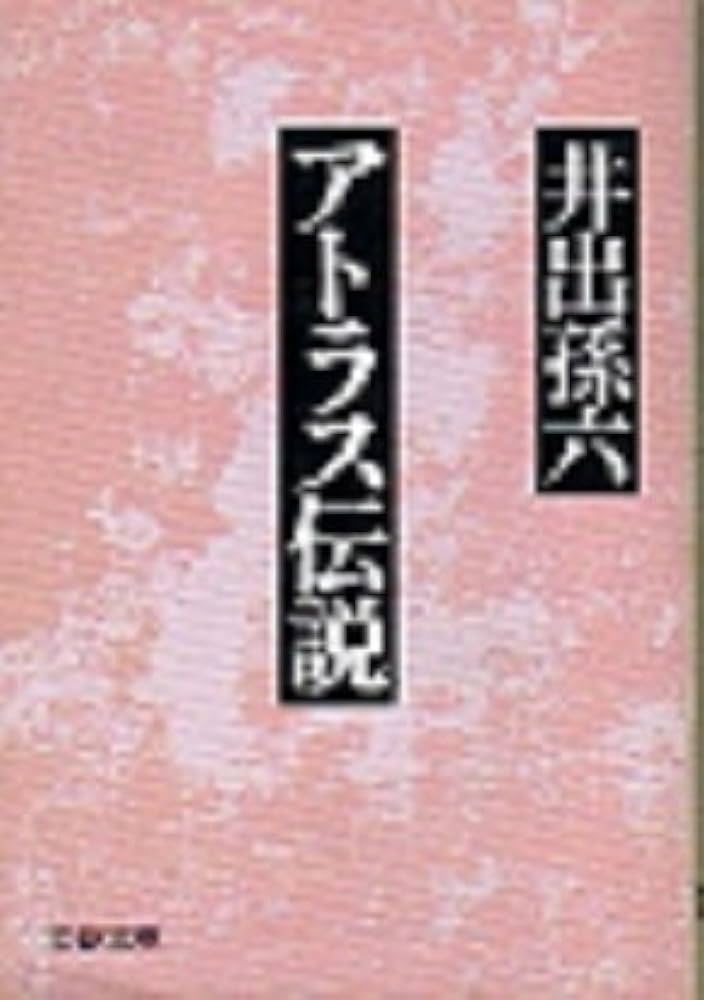
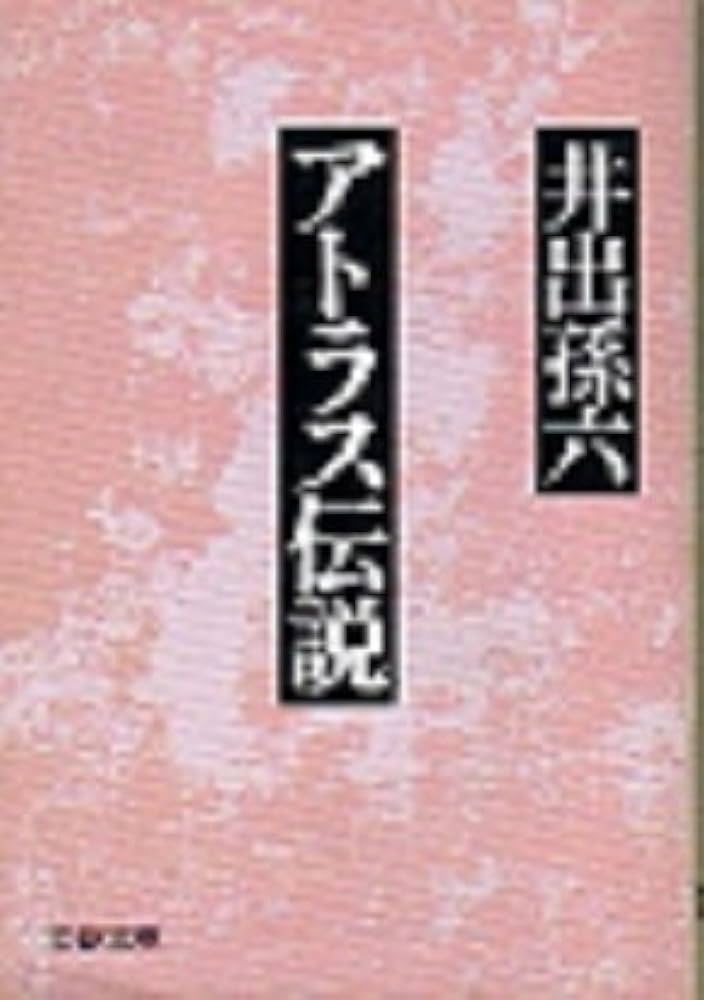
1974年に第72回直木賞を受賞した『アトラス伝説』は、井出孫六の名を世に知らしめた作品です。本書は、明治初期に実際に起きた地図の密売事件と、その渦中で謎の死を遂げた洋画家・川上冬崖(かわかみ とうがい)の生涯に迫る歴史ノンフィクション。
川上冬崖は、高橋由一らを育てた近代洋画の先駆者でありながら、陸軍で地図製作にも携わっていた人物です。彼がなぜ地図密売の嫌疑をかけられ、自ら命を絶たねばならなかったのか。その背景には、陸軍内部の権力争いがあったとも言われています。井出孫六は、史実を丹念に追いながら、歴史の闇に葬られた一人の画家の悲劇を鮮やかに描き出しています。同じく直木賞候補となった、野口英世の虚像に迫る「非英雄伝」も収録された短編集です。



歴史のミステリーみたいだね!才能ある画家がなぜ…って、すごく引き込まれちゃうよ。
4位『中国残留邦人 置き去られた六十余年』
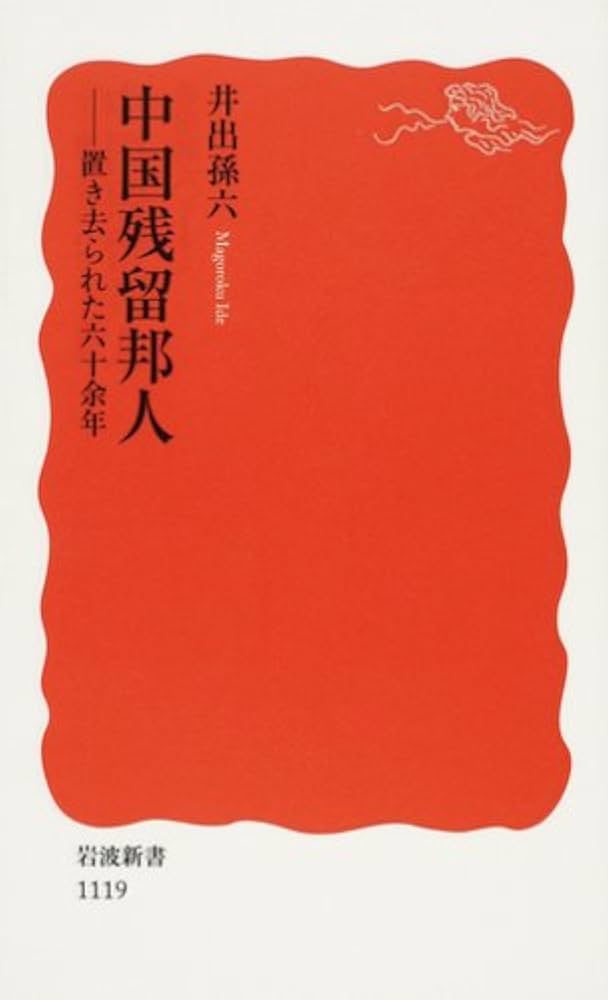
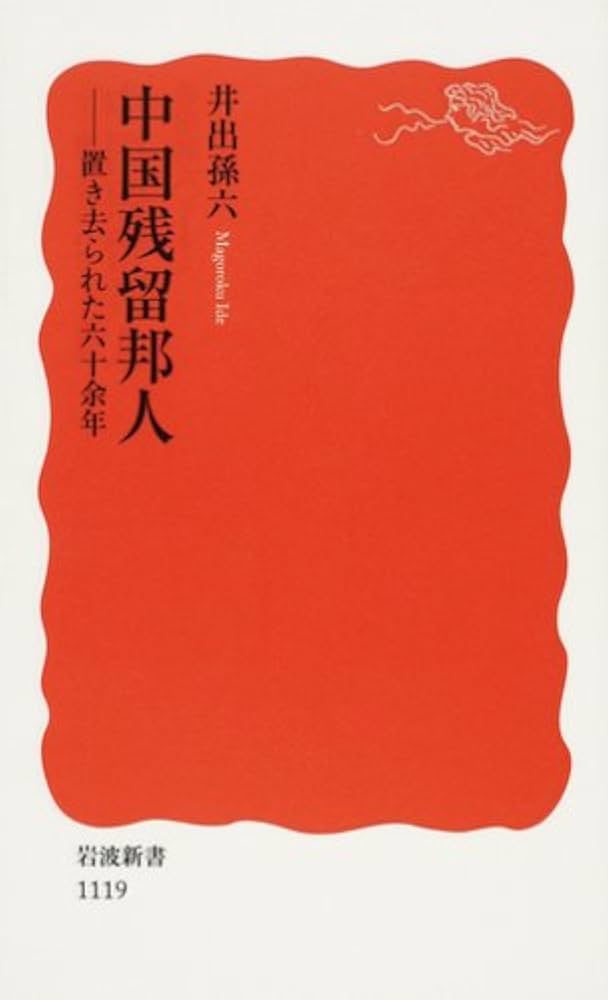
『終わりなき旅』から二十数年の時を経て、井出孫六が再び中国残留邦人問題と向き合ったのが本書です。国策によって満州へ送られ、敗戦で置き去りにされた人々の苦難は、日本への帰国が実現した後も続いていました。
念願の祖国へ戻った彼らを待ち受けていたのは、言葉の壁や文化の違い、そして生活の困窮という厳しい現実でした。なぜ彼らは、ようやく帰ってきた日本を相手に、裁判という手段で訴えなければならなかったのでしょうか。本書は、帰国後の残留邦人たちが直面した課題に焦点を当て、「国家の怠慢」によって翻弄され続ける人々の姿を浮き彫りにします。個人にとって国家とは何か、その責任とは何かを、改めて鋭く問いかける一冊です。



やっと帰ってこれたのに、また苦労が続くなんてひどいよ。国はちゃんと責任を取るべきだよね。
5位『秩父困民党群像』
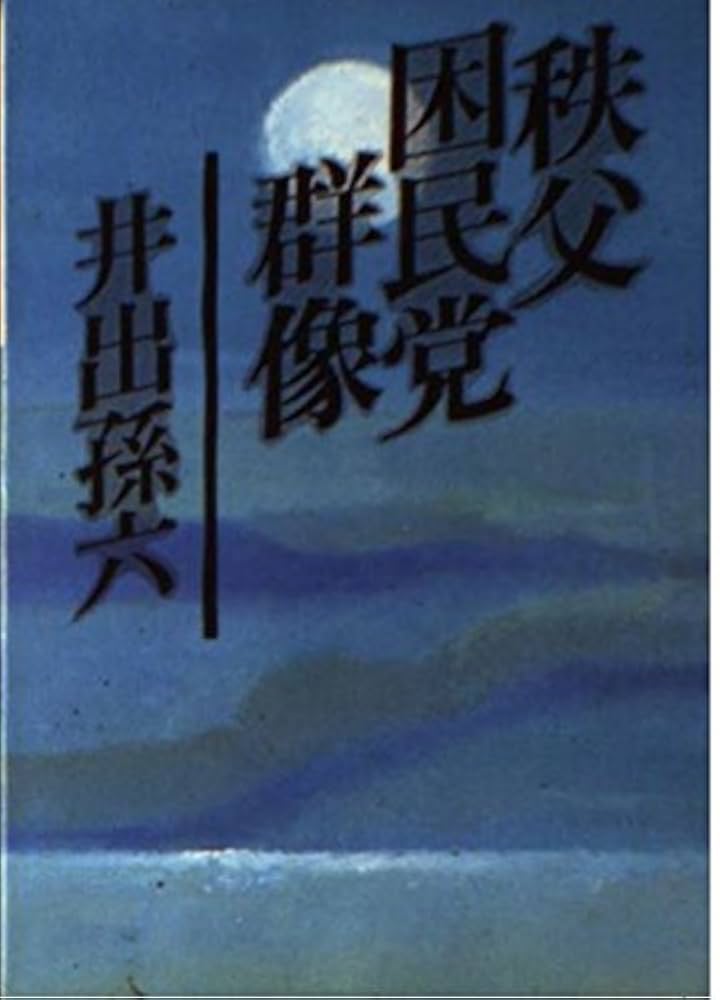
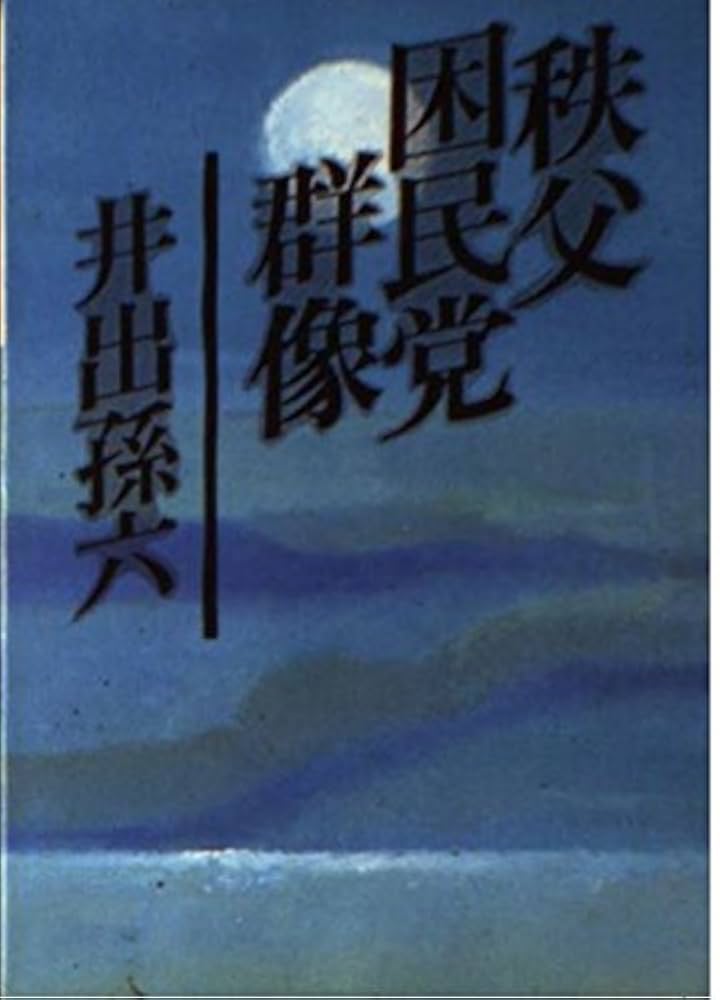
『秩父困民党群像』は、井出孫六の作家としてのデビュー作であり、その後の作風を決定づけた重要な作品です。本書が描くのは、明治17年(1884年)に起きた「秩父事件」。当時の深刻な不況の中、重税や借金に苦しむ農民たちが「困民党」を名乗り、武装蜂起した日本近代史上最大規模の民衆運動です。
井出孫六は、膨大な史料を基に、この事件を率いたリーダーたちの人間像に迫ります。総理・田代栄助や会計長・井上伝蔵といった中心人物から、名もなき参加者まで、一人ひとりの思いや行動を生き生きと描き出すことで、単なる歴史事件ではない、血の通った人間のドラマとして秩父事件を現代に蘇らせました。歴史の大きなうねりの中で、必死に生きようとした人々の姿が胸を打つノンフィクションです。



民衆のパワーってすごいんだね!歴史の教科書だけじゃわからない、人々の熱い思いが伝わってくるよ。
6位『峠の廃道 秩父困民党紀行』
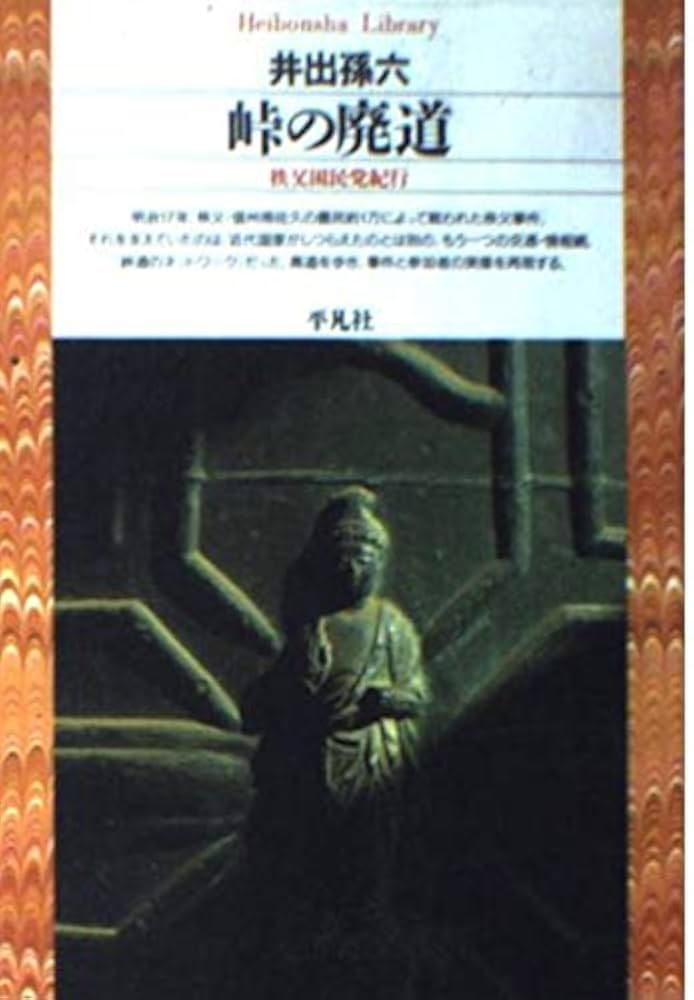
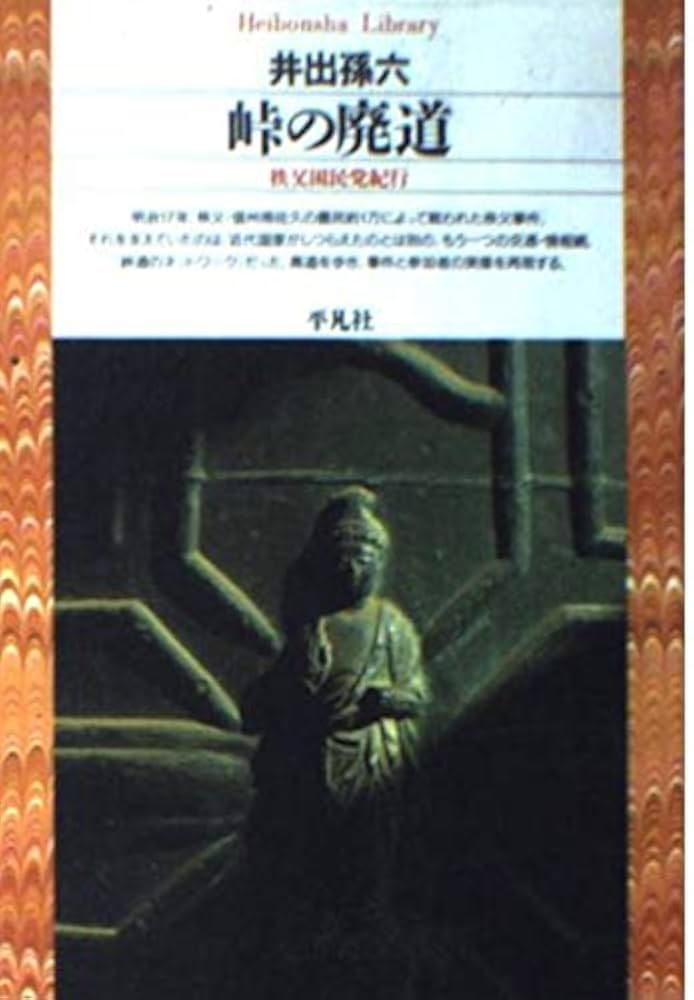
『秩父困民党群像』で事件そのものを描いた井出孫六が、今度は自らの足で事件の舞台を歩き、その軌跡を辿ったのがこの『峠の廃道 秩父困民党紀行』です。秩父事件で蜂起した困民党は、山深い秩父の峠道を巧みに利用して行動しました。そして鎮圧された後も、一部は十石峠を越えて信州へと落ち延びていったのです。
著者は、近代化の波の中で忘れ去られ、今では廃道となってしまった峠道を実際に歩きます。その道を辿ることで、困民党の人々が見たであろう風景や、彼らの心情に思いを馳せるのです。秩父の風土や人々の暮らし、信仰といった背景を描きながら、事件の深層に迫るユニークな紀行文であり、優れた歴史ノンフィクションでもあります。



昔の人が歩いた道を自分も歩いてみるってロマンがあるなあ。歴史を肌で感じるって、こういうことなのかもね。
7位『石橋湛山と小国主義』
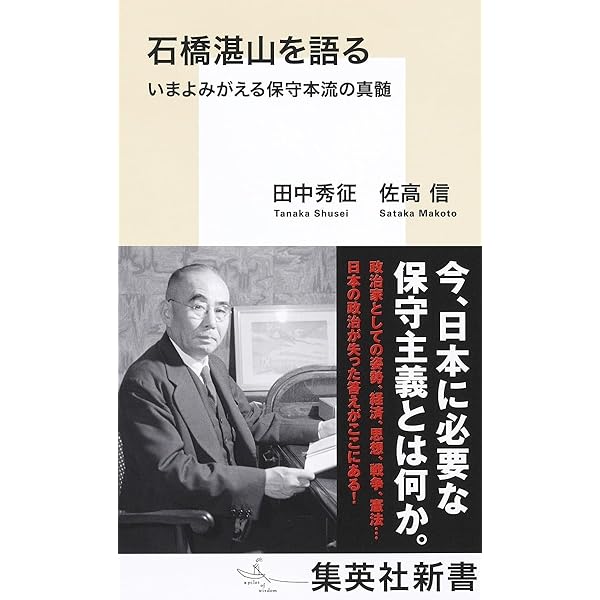
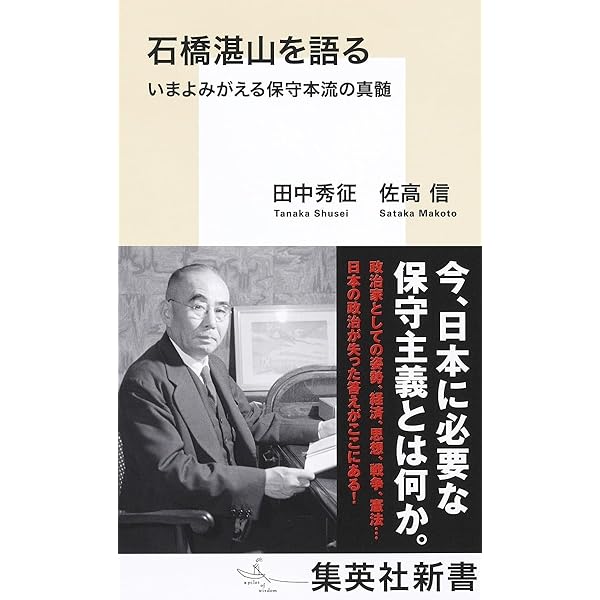
本書は、戦前から戦後にかけて活躍したジャーナリストであり、後に総理大臣も務めた石橋湛山(いしばし たんざん)の思想に迫った一冊です。井出孫六は、軍国主義へと突き進む時代の中で、湛山がいかにしてリベラルな言論を貫いたかを描き出します。
湛山の思想の核となったのが「小国主義(小日本主義)」です。これは、軍備拡張や植民地支配による「大日本主義」を批判し、軍縮と自由貿易によって平和な通商国家を目指すべきだという考え方でした。井出孫六は、大正デモクラシーという時代の空気の中で育まれた湛山の思想が、戦後日本にどのような影響を与えたのかを考察します。時代の潮流に流されることなく、自らの信念を貫いた稀有なジャーナリストの精神に触れることができるでしょう。



戦争に向かう時代に「軍縮しよう」って言えるの、すごい勇気だよね。こういう人がいたこと、もっと知られるべきだよ。
8位『ねじ釘の如く 画家・柳瀬正夢の軌跡』
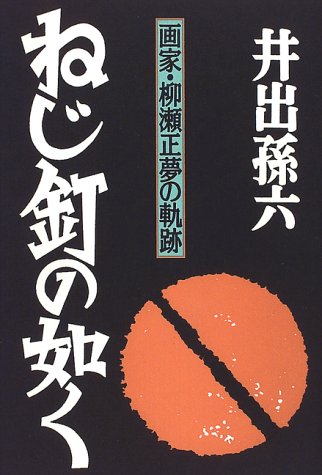
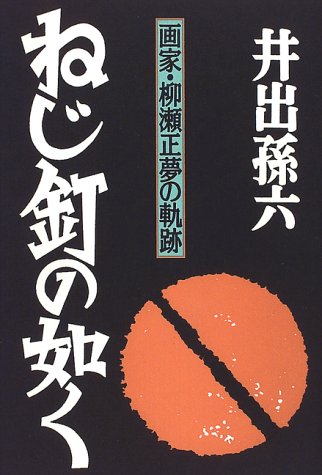
『ねじ釘の如く』は、大正から昭和にかけて、激動の時代を駆け抜けた画家・柳瀬正夢(やなせ まさむ)の評伝です。15歳で天才画家としてデビューした正夢は、やがて前衛芸術運動に身を投じ、その後プロレタリア美術運動の中心的な担い手となります。
絵画だけでなく、風刺漫画やポスター、舞台美術など、多彩な才能を発揮した正夢。彼は自らのサインに、社会を支える「ねじ釘」でありたいという思いを込めて、ねじ釘のマークを用いていました。治安維持法による弾圧を受けながらも創作への情熱を失わず、最後は終戦間近の東京大空襲で命を落とすという壮絶な生涯。井出孫六は、時代と真摯に向き合い続けた一人の芸術家の軌跡を丹念に描き出しています。



「ねじ釘」のサイン、素敵だなあ。自分の仕事に誇りを持ってたんだろうね。空襲で亡くなったなんて悲しすぎるよ。
9位『いばら路を知りてささげし――石井筆子の二つの人生』
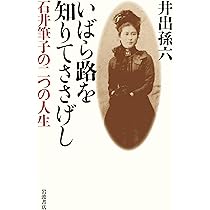
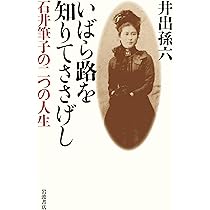
本書は、明治から昭和にかけて、二つの全く異なる人生を歩んだ女性、石井筆子(いしい ふでこ)の感動的な生涯を描いた物語です。彼女の前半生は、まさに華やかそのもの。ヨーロッパ留学を経験し、帰国後は華族女学校の教師として活躍、「鹿鳴館の華」とまで呼ばれました。
しかし、娘の障害や夫との死別といった度重なる不幸が彼女を襲います。この苦難が、筆子の人生を大きく変えました。彼女は知的障害を持つ長女を、日本初の知的障害児施設「滝乃川学園」に預けます。そして、創設者である石井亮一と出会い、その志に深く共感。周囲の反対を押し切って彼と再婚し、後半生をすべて知的障害児の教育と福祉に捧げたのです。女子教育の先駆者から福祉の母へ。その壮絶な「二つの人生」は、私たちに深い感動を与えてくれます。



すごい人生だね…。自分のつらい経験を、他の人を助ける力に変えたなんて、本当に尊敬するよ。
10位『野口英世』
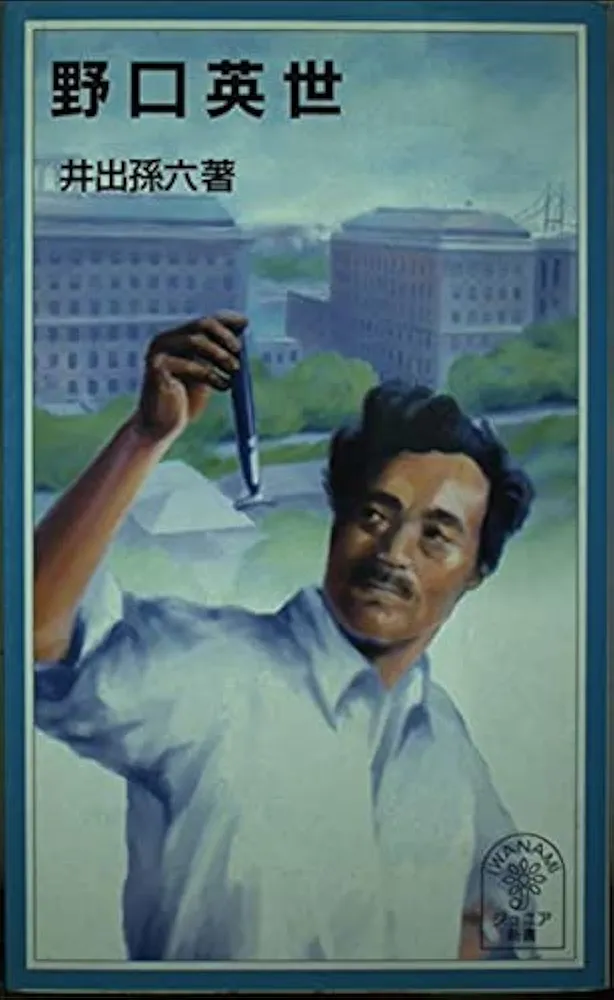
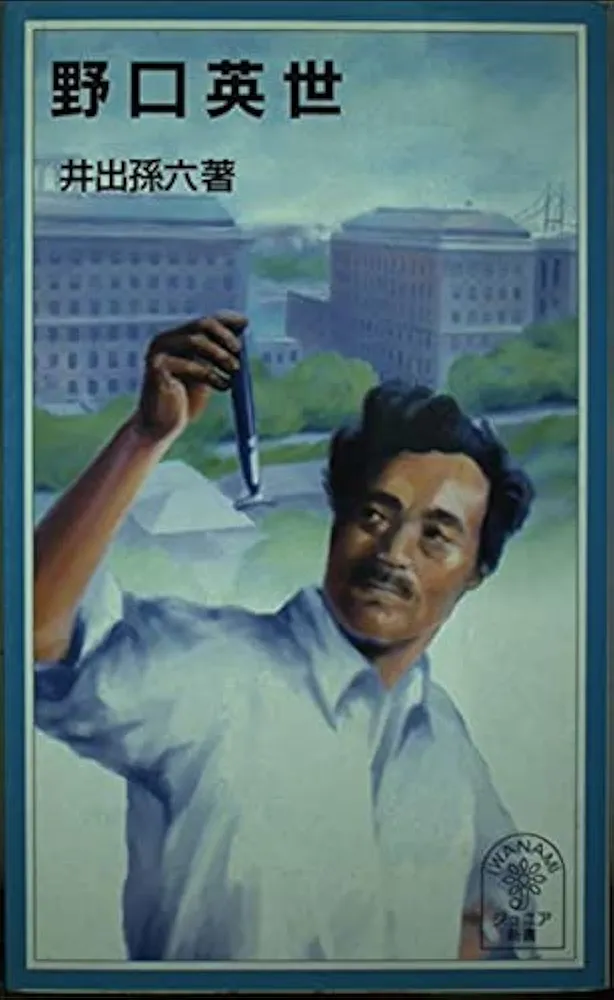
誰もが知る偉人、野口英世。しかし、私たちは本当に彼のことを知っているでしょうか。本書は、「貧しさと障害を乗り越えた偉大な細菌学者」という一般的なイメージの裏に隠された、人間・野口英世の実像に迫る伝記です。
井出孫六は、野口英世の栄光と挫折の生涯を、彼を支え続けた母親や恩師、友人たちとの人間ドラマを軸に描き出します。幼い頃の火傷による左手の障害、貧しい家庭環境といった逆境を乗り越え、世界的な研究者へと駆け上がっていく一方で、金遣いの荒さなどの人間的な弱さも隠さずに描かれています。偉人伝だけではわからない、野口英世という人物の強烈な個性と魅力に触れることができる一冊です。井出孫六は、直木賞候補作となった「非英雄伝」でも野口英世を取り上げており、その人物像に長年惹きつけられていたことがうかがえます。



偉人にも意外な一面があるんだね。完璧じゃないからこそ、なんだか親しみが湧いてくるなあ。
11位『満蒙の権益と開拓団の悲劇』


本書は、国策として推進された「満蒙開拓」が、いかにして多くの人々を悲劇に導いたかを克明に記録したノンフィクションです。昭和恐慌下の農村救済と、満州国の支配強化という目的のもと、日本全国から約27万もの人々が「満蒙開拓団」として満州へ送られました。
しかし、彼らを待ち受けていたのは過酷な現実でした。与えられた土地は現地農民から強制的に買い上げたものであり、常に緊張関係にありました。そして1945年8月、ソ連軍が侵攻すると、関東軍は開拓団を置き去りにして撤退。残された老人や女性、子どもたちは、略奪や暴行、飢えや病によって約8万人が命を落とすという未曾有の悲劇に見舞われたのです。この悲劇が、後に「中国残留孤児」という新たな問題を生み出しました。なぜこのような悲劇が起きたのか、その歴史的背景に鋭く迫ります。



本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。
12位『小説 佐久間象山』
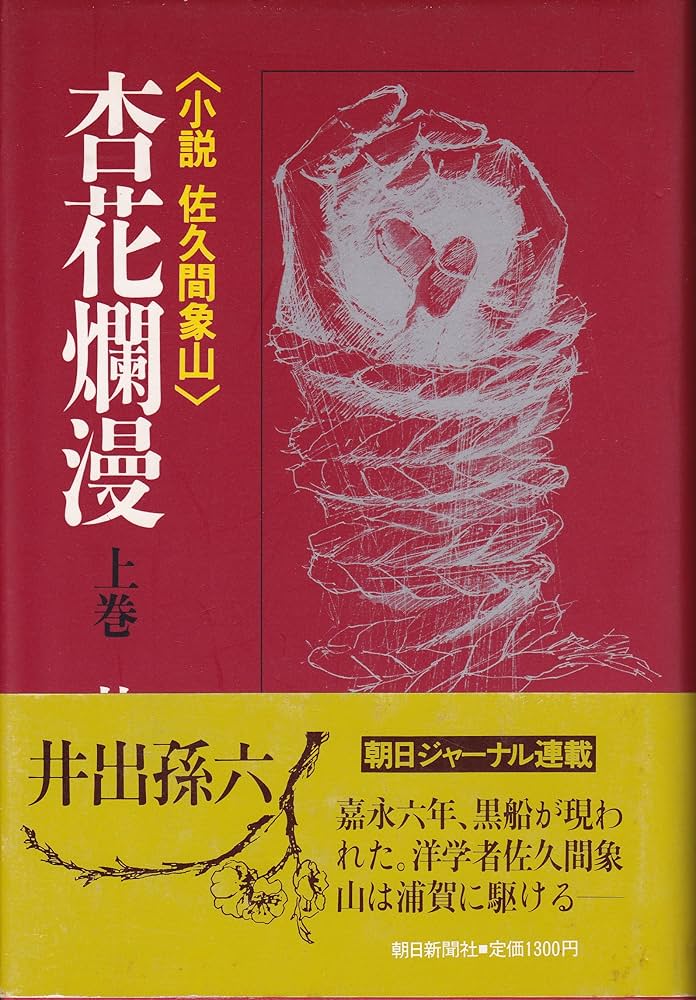
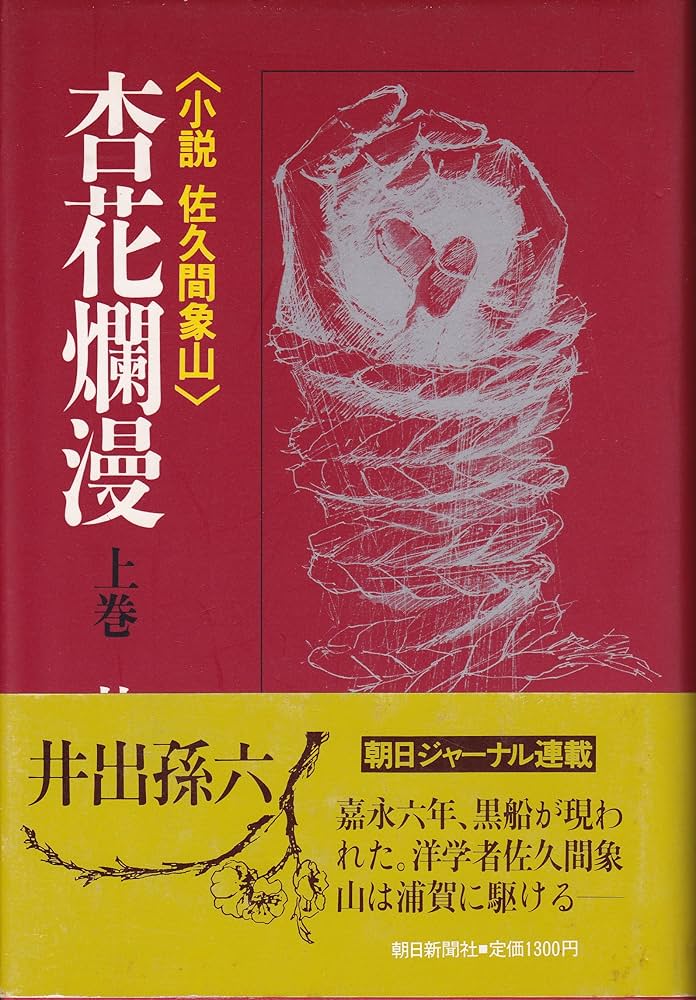
『小説 佐久間象山』は、幕末の日本に大きな影響を与えた思想家・佐久間象山(さくま しょうざん)の生涯を描いた歴史小説です。信州松代藩に生まれた象山は、儒学や兵学、科学など幅広い分野で才能を発揮した、まさに「幕末の巨人」でした。
江戸に開いた私塾には、勝海舟、吉田松陰、坂本龍馬といった、後の時代を動かす若者たちが集いました。彼はペリー来航を機に、いち早く開国の必要性を説きましたが、その先進的な思想と自信過剰ともいえる性格は多くの敵も作りました。門人・吉田松陰の密航事件に連座しての蟄居生活、そして志半ばで攘夷派の凶刃に倒れるまで、その波乱に満ちた生涯がドラマチックに描かれています。



幕末のヒーローたちのお師匠さんなんだね!この人がいなかったら、日本の歴史は変わっていたかもって思うとワクワクするよ。
13位『日本百名峠』
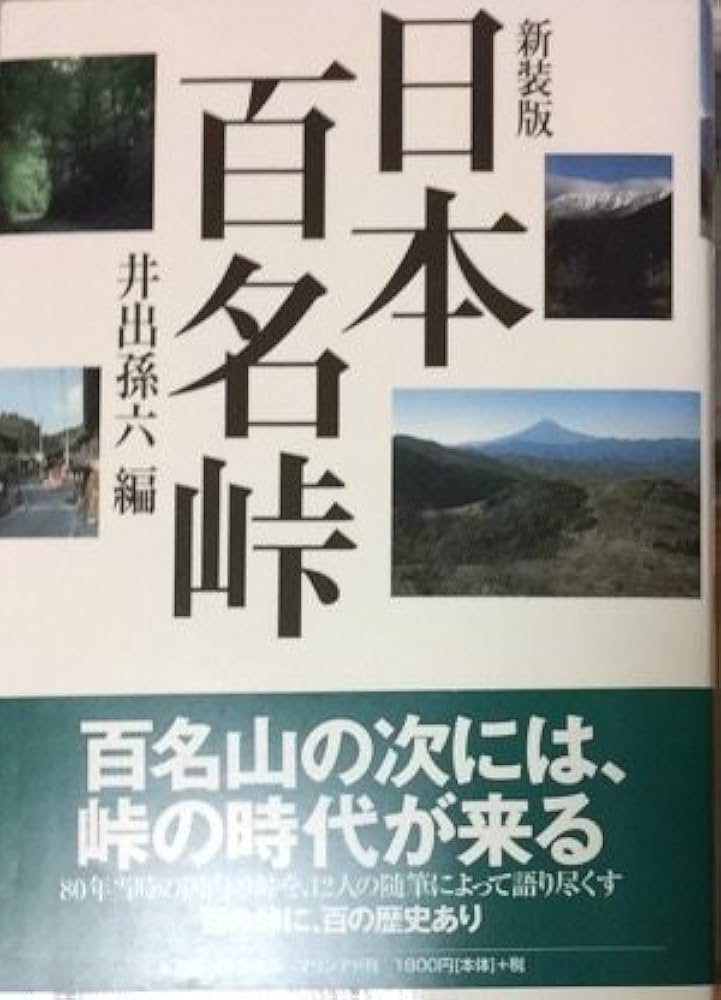
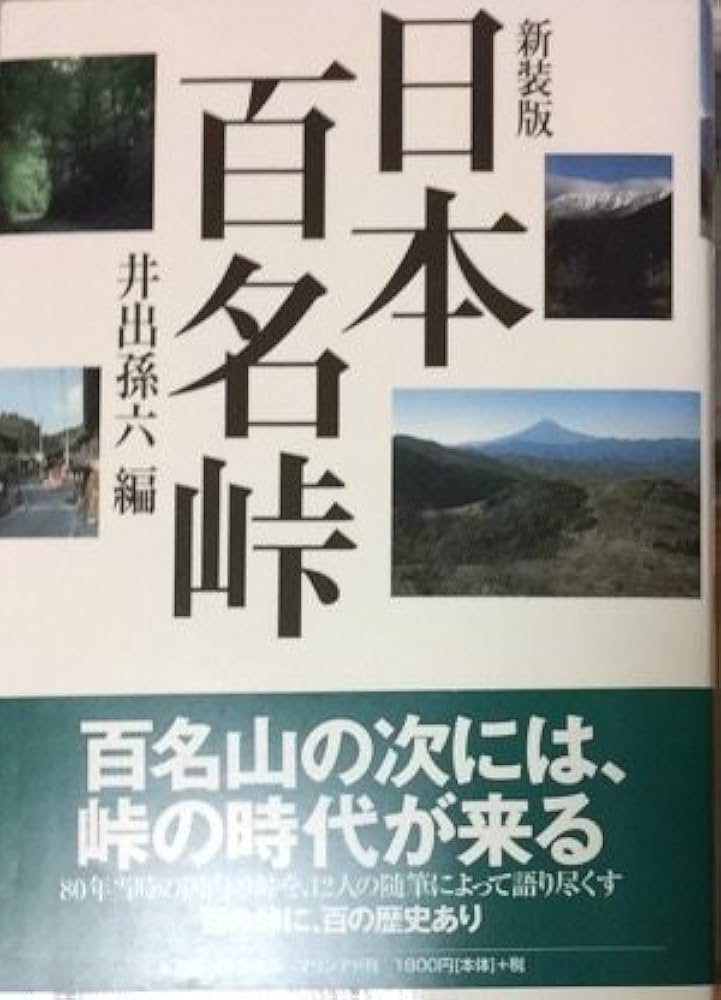
『日本百名峠』は、井出孫六が編者を務め、12人の書き手と共に日本全国の峠を選び、その魅力を綴った随筆集です。深田久弥の『日本百名山』が登山ブームの火付け役となったように、本書は「峠」という存在に新たな光を当てました。
選ばれた100の峠は、単に景色が良い、道が有名といった基準ではありません。その峠が刻んできた歴史、そこにまつわる人々の物語や伝説、知られざるエピソードといった点に重きが置かれています。交通の要所として、また文化の境界として、峠は常に人々の暮らしと深く関わってきました。井出孫六をはじめとする執筆陣が、自らの足で峠を歩き、その歴史と風土を肌で感じながら綴った文章は、私たちを奥深い峠の世界へと誘ってくれます。



峠ってただの通り道だと思ってたけど、いろんな歴史や物語があるんだね。今度ドライブする時、ちょっと意識してみようかな。
14位『山里の四季をうたう 信州・1937年の子どもたち』
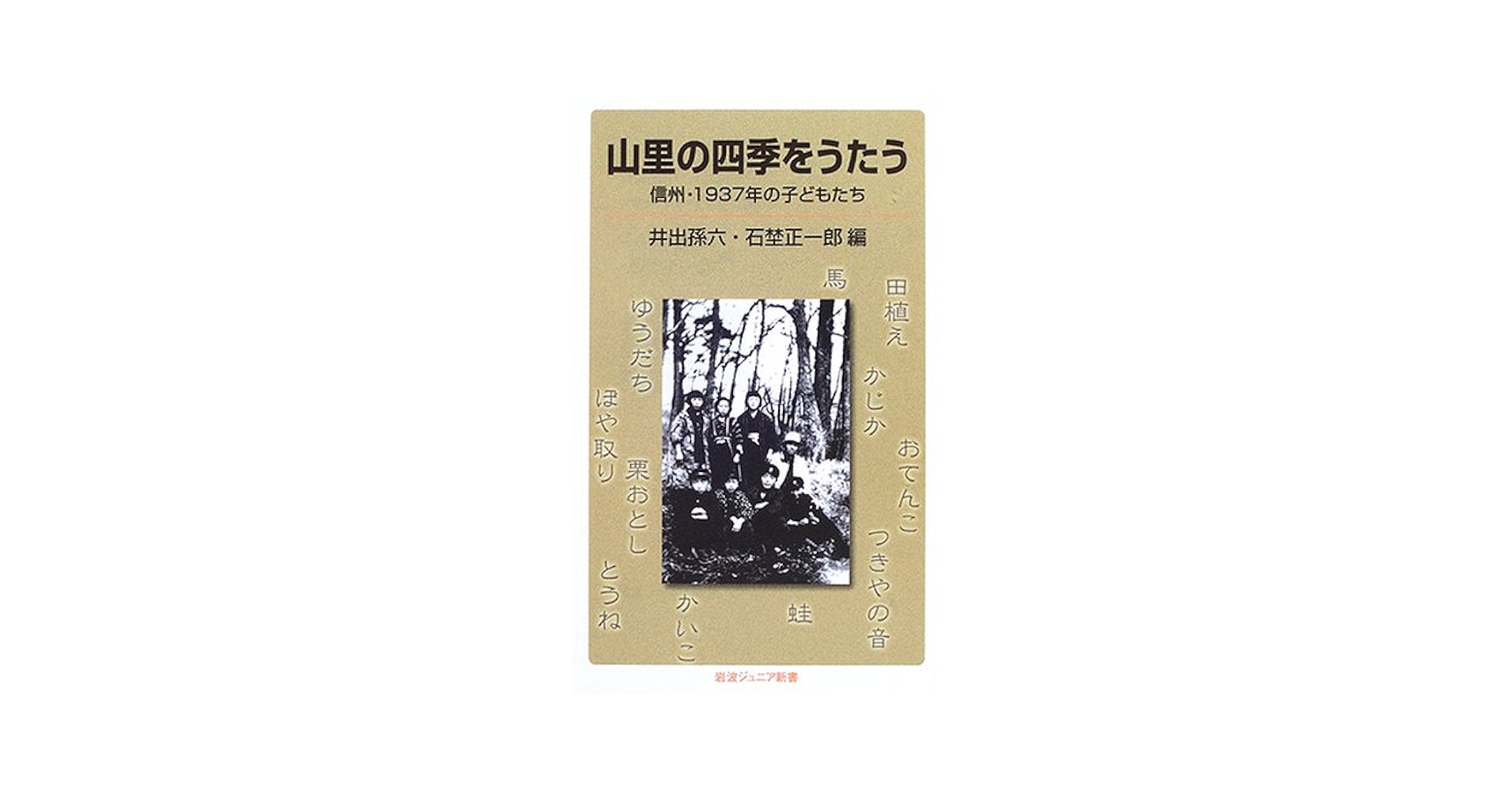
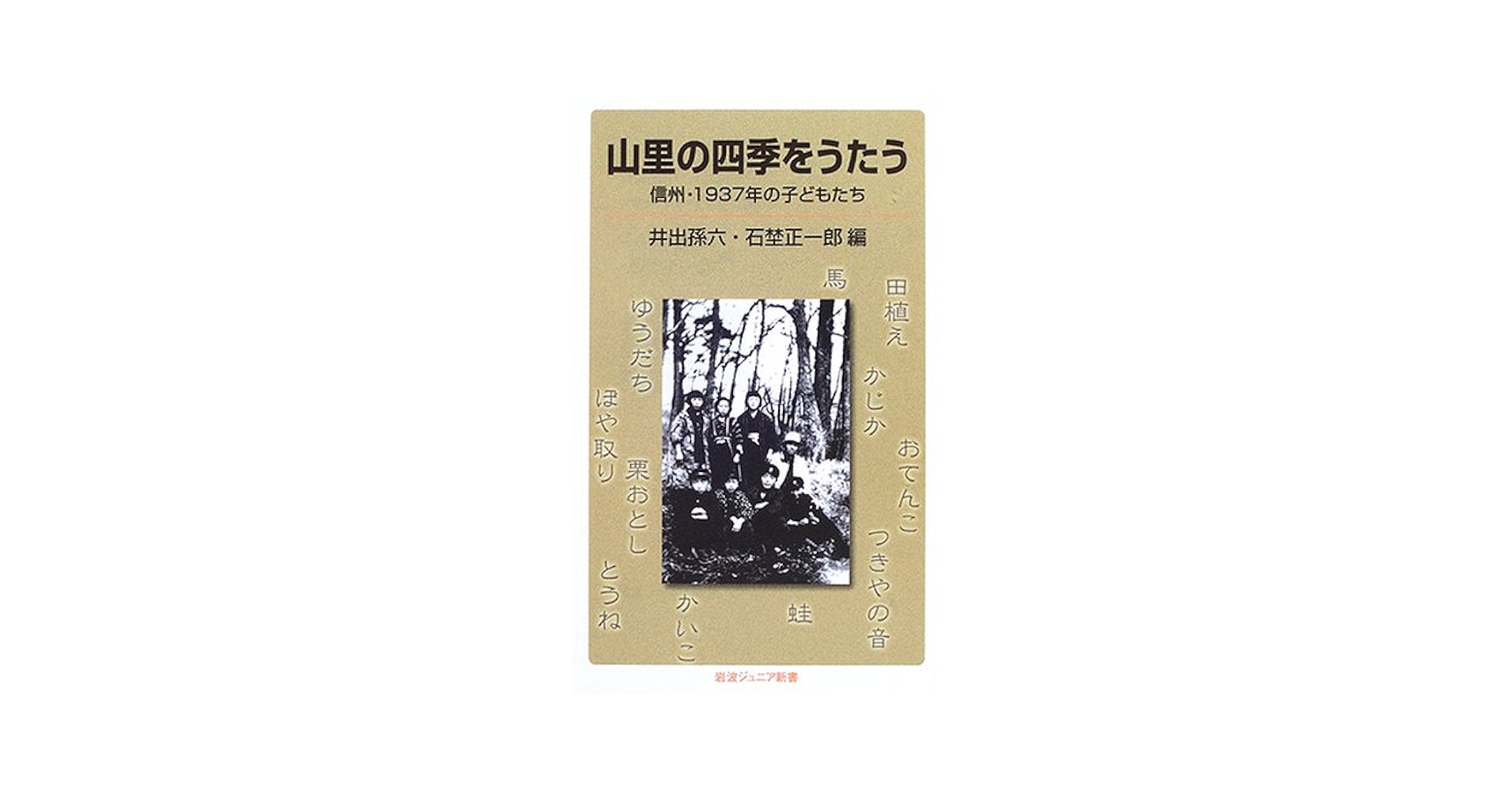
本書は、井出孫六が編纂した、心温まる子どもたちの詩集です。舞台は、今から70年以上前の1937年(昭和12年)、信州の山里にある小さな小学校。そこに赴任してきた若い代用教員の指導のもと、子どもたちが日々の暮らしの中で感じたことを素直な言葉で綴った250編あまりの詩が収められています。
田植えの喜び、朝露に光る草の美しさ、家族と囲む食卓の温かさ。子どもたちの目線で切り取られた日常は、どれも生き生きとした輝きに満ちています。方言がそのまま使われた素朴な詩からは、当時の山里の四季の移ろいや人々の暮らしぶりが伝わってきます。日中戦争が始まろうとするきな臭い時代背景の中、子どもたちの純粋な言葉が、忘れかけていた大切なものを思い出させてくれる一冊です。



子どもたちの詩、すごくピュアでかわいいね!昔の暮らしって大変だったろうけど、素敵なこともたくさんあったんだな。
15位『その時この人がいた 昭和史を彩る異色の肖像37』
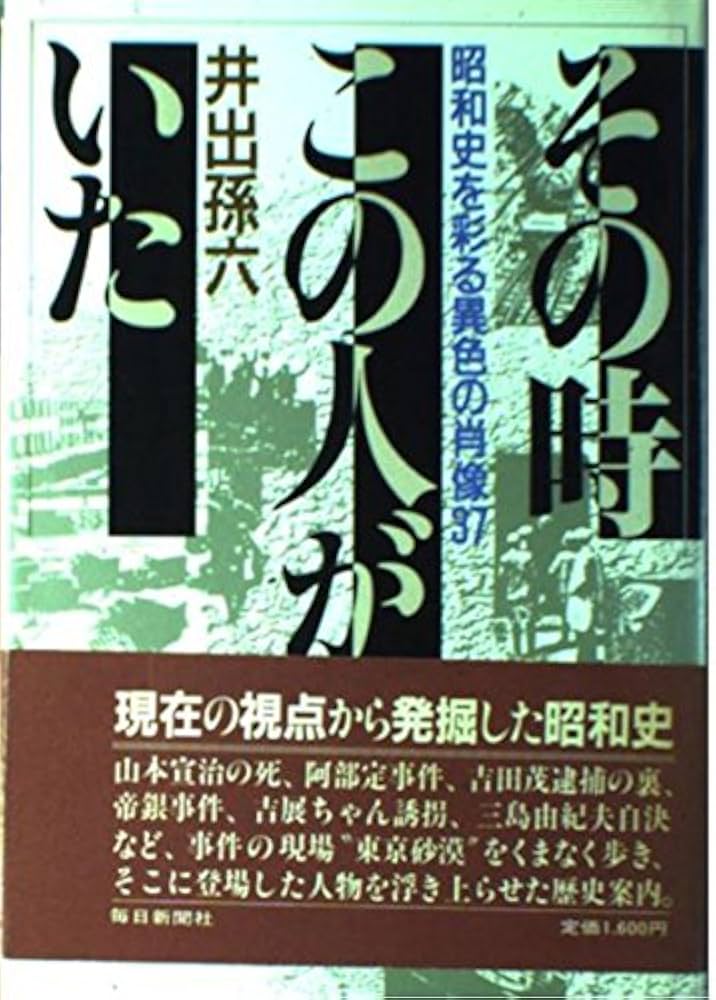
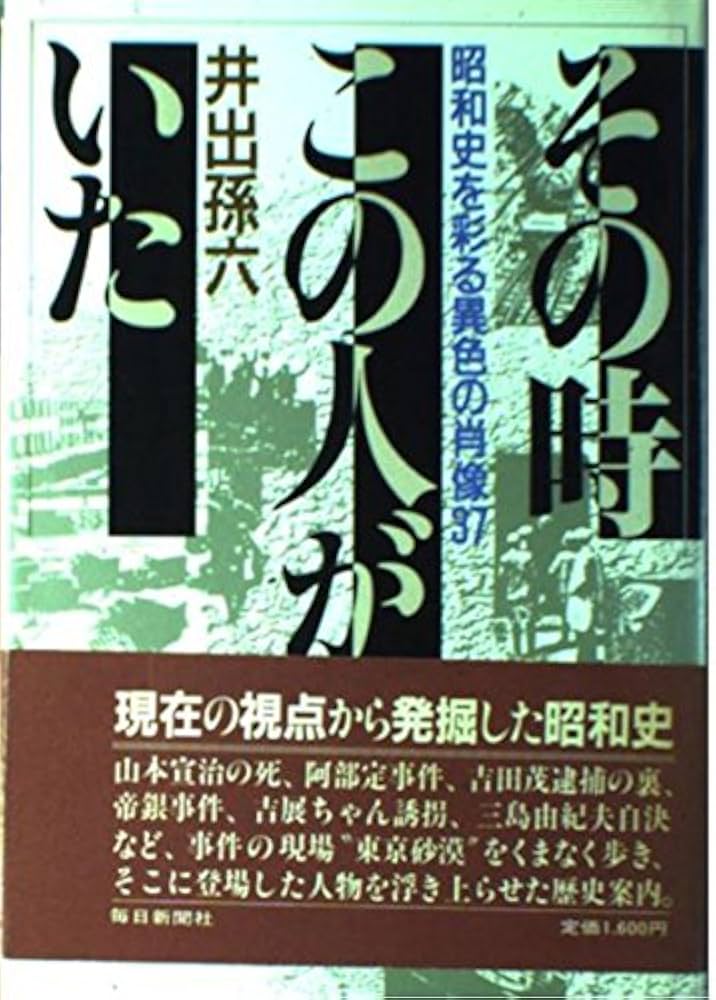
『その時この人がいた』は、激動の昭和史を彩った37人の「異色の人物」にスポットを当てたノンフィクション作品です。井出孫六は、歴史の教科書には載らないような、しかし時代を象徴する事件や出来事の中心にいた人々の肖像を鮮やかに描き出します。
取り上げられるのは、昭和金融恐慌の引き金となった銀行頭取、反戦を訴え暗殺された政治家、世間を震撼させた阿部定事件の阿部定、未解決の帝銀事件の容疑者、そして三島由紀夫まで、実に多彩な顔ぶれです。著者は事件の現場を歩き、残された資料を丹念に読み解くことで、彼らが「その時」何を考え、どう生きたのかを浮き彫りにしていきます。昭和という時代の光と影を、人物を通して体感できる興味深い一冊です。



昭和って、本当にいろんな事件があったんだなあ。ニュースで知ってる事件の裏に、こんな人たちがいたなんて驚きだよ。
16位『柳田国男を歩く 遠野物語にいたる道』
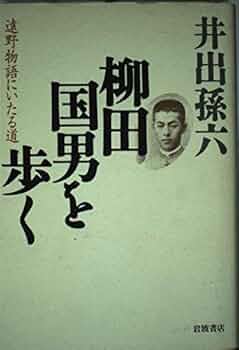
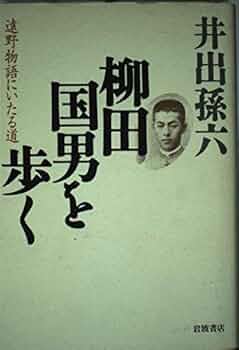
本書は、日本民俗学の父・柳田国男が、不朽の名著『遠野物語』を生み出すまでの足跡を、井出孫六が自らの足で辿った紀行文です。『遠野物語』は、岩手県遠ono地方に伝わる河童や座敷童子などの不思議な話を収めた説話集として知られていますが、柳田はなぜこの地に関心を持ったのでしょうか。
井出孫六は、柳田が「日本一小さな家」と語った故郷から、若き日に文学者たちと交流した日々、そして民俗学へと向かう転機となった旅路を追体験します。柳田国男という巨人が、何を考え、何を見つめていたのか。その思想の源流を探る旅は、私たちを日本の原風景へと誘ってくれます。『遠野物語』を片手に、柳田が歩いた道を追体験したくなる一冊です。



『遠野物語』って、ただの昔話じゃなかったんだね。柳田国男の人生と深く繋がってるんだ。わたしも旅に出てみたくなったよ。
17位『八月十五日ぼくはナイフをすてた』
本書は、井出孫六自身の戦争体験を基にした自伝的な作品です。太平洋戦争末期の1944年から、敗戦を迎える1945年8月15日まで。著者が故郷・信州佐久で過ごした旧制中学校時代が、みずみずしい筆致で描かれています。
軍事教練、勤労奉仕、そして日に日に厳しくなる食糧事情。戦争という非日常が日常であった時代を、多感な少年はどのように生きたのでしょうか。本書は、若い世代に向けて、戦争が人々の暮らしや心をどう変えてしまうのかを静かに、しかし力強く語りかけます。「戦争の記憶を消してはいけない」という著者の強い思いが込められた、今こそ読まれるべき一冊です。



戦争中の学生生活って、想像もつかないよ…。当たり前の日常がどれだけ大切か、考えさせられるなあ。
18位『信州奇人考』
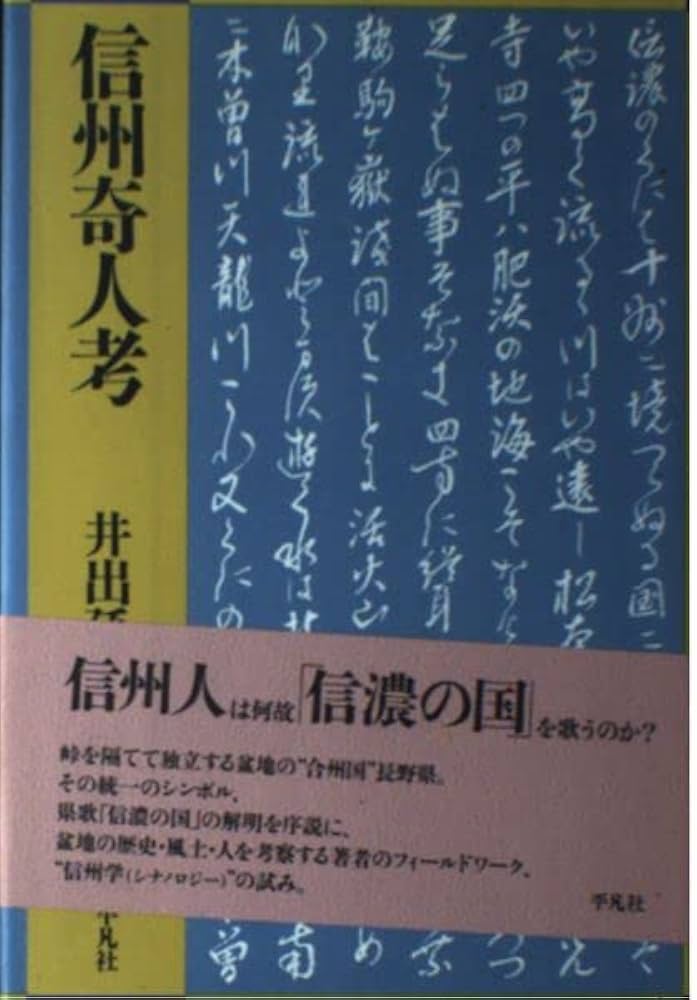
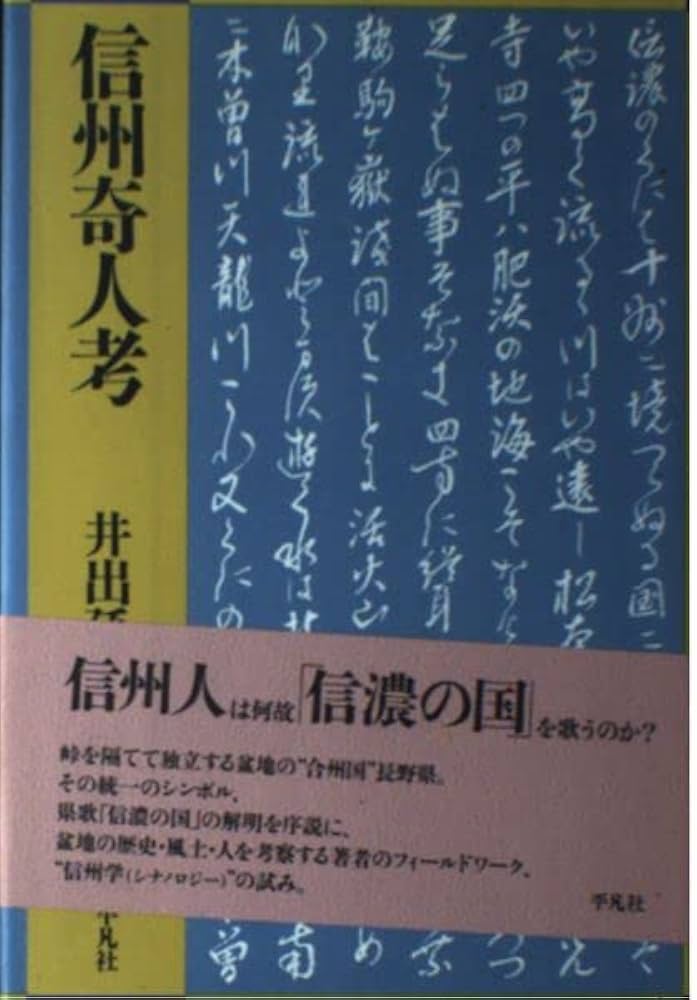
『信州奇人考』は、著者の故郷である信州(長野県)にゆかりのある、一風変わった人々の生涯を綴ったユニークな人物評伝集です。井出孫六は、信州の風土が生み出した「奇人」たちの生き様に、深い愛情と共感の眼差しを向けています。
本書に登場するのは、歴史上の有名人から、地元で語り継がれる名もなき人々まで様々。彼らは、世間の常識や権威に縛られることなく、自らの信じる道を突き進んだ人々です。その生き方は、時に滑稽で、時に哀しく、そしてどこか人間味にあふれています。信州という土地の懐の深さと、そこに生きた人々の多様な価値観に触れることができる、味わい深い一冊です。



「奇人」って言われる人、わたしは好きだなあ。自分らしく生きてるってことだもんね!
19位『ルポルタージュ 戦後史』
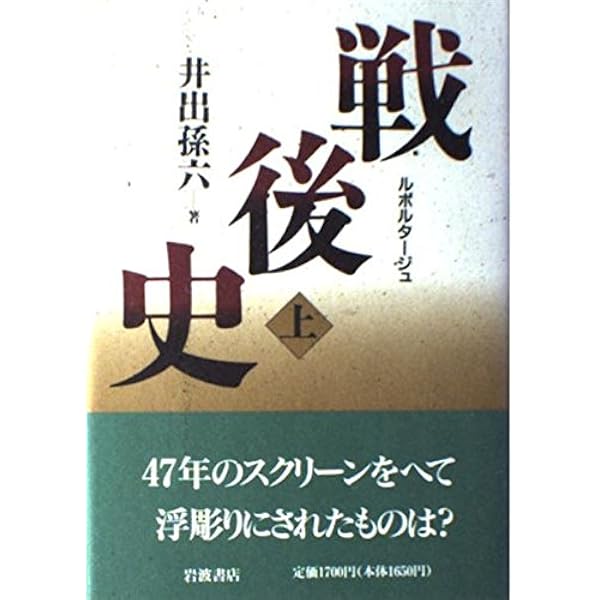
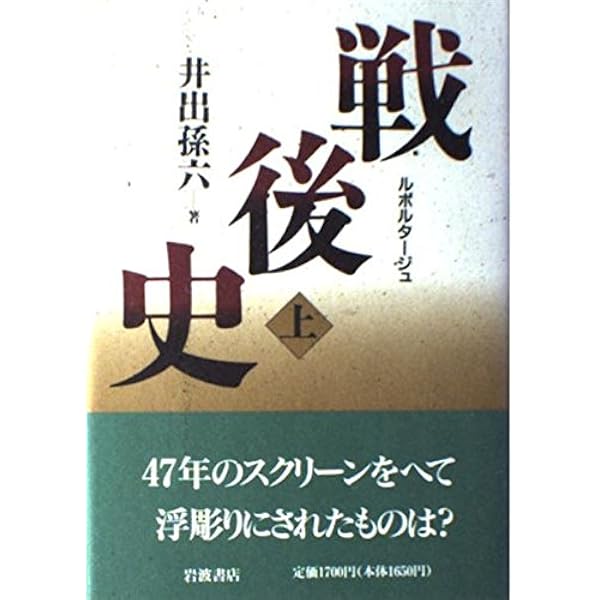
『ルポルタージュ 戦後史』は、井出孫六のジャーナリストとしての側面が存分に発揮された大作です。本書は、敗戦から始まる日本の戦後史を、様々な事件や事象を通して編年体で描き出したノンフィクション。
著者は、目まぐるしく移り変わる戦後の社会を、独自の視点と丹念な取材で切り取っていきます。歴史の大きな流れだけでなく、その時代に生きた人々の息づかいや社会の空気を伝えることに重きを置いているのが特徴です。忘れ去られがちな戦後の出来事を、もう一度その時点に立って見つめ直すことで、現代日本が抱える問題の根源が見えてくるかもしれません。歴史の証言としても非常に価値の高い一冊です。



戦後の日本って、本当にいろんなことがあったんだね。今の時代の当たり前は、こうやって作られてきたんだなあって実感するよ。
20位『日本名城紀行』
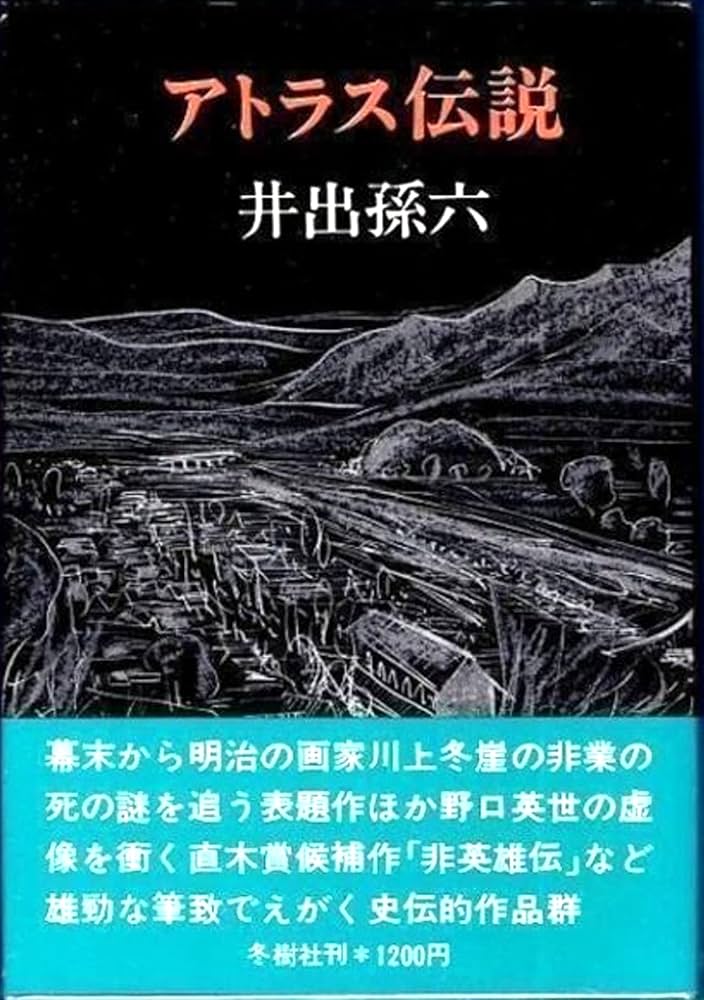
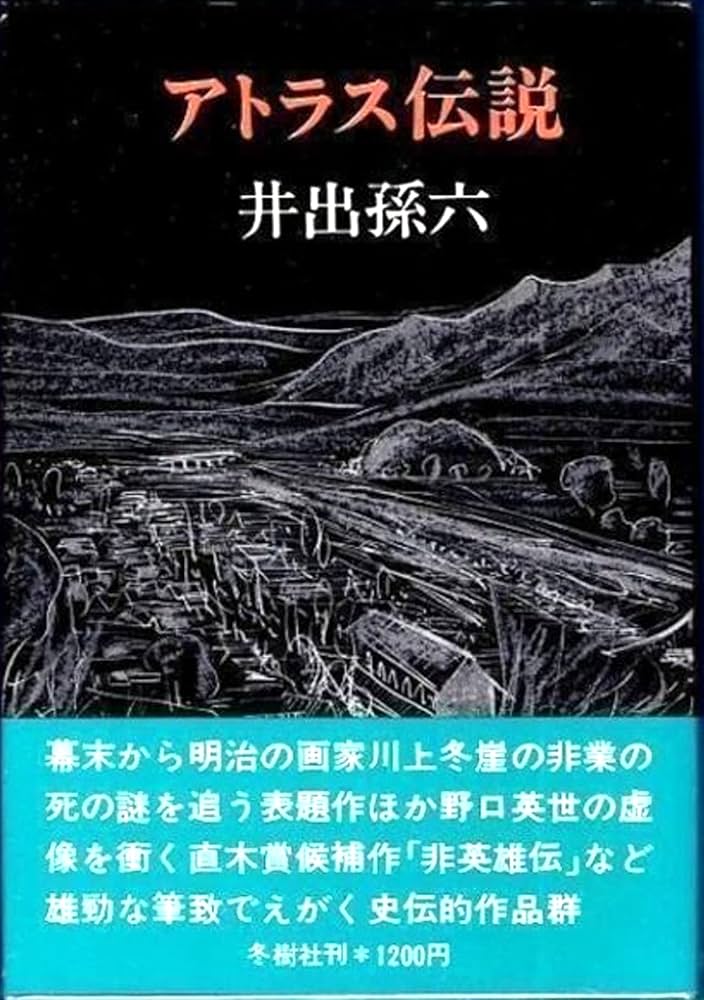
『日本名城紀行』は、井出孫六をはじめとする複数の文豪たちが、日本各地の城を訪ね、その歴史や魅力について綴ったエッセイ・紀行文シリーズの一冊です。井出孫六は、このシリーズの第5巻に参加しています。
城は、単なる建造物ではありません。そこには、築城した武将の思い、繰り広げられた戦いの記憶、そして城下町の人々の暮らしの歴史が刻まれています。作家たちは、それぞれの個性的な視点で城と向き合い、その奥深い物語を読み解いていきます。歴史好き、城好きはもちろん、旅好きな人にもおすすめしたい、知的好奇心を刺激されるシリーズです。



お城って、見る角度によって全然違う顔を見せるんだね。作家さんの目を通すと、ただの観光地じゃない特別な場所に思えてくるよ。
まとめ:井出孫六の人気作品を読んで歴史の深淵に触れよう
井出孫六の作品世界はいかがでしたでしょうか。彼のペンは、歴史の教科書が語らない、名もなき人々の声や埋もれた真実を丹念に拾い上げ、私たちの目の前に描き出してくれます。
中国残留孤児問題や秩父事件といった重厚なテーマから、故郷・信州の風土やユニークな人物伝まで、その関心は多岐にわたります。しかし、その根底に流れているのは、常に弱い立場の人々への温かい眼差しと、歴史に対する真摯な姿勢です。井出孫六の作品を読むことは、過去を知り、今を考えるための、深く、そして豊かな旅となるでしょう。ぜひ、この機会に一冊手に取ってみてください。