あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】尾崎一雄のおすすめ小説ランキングTOP8
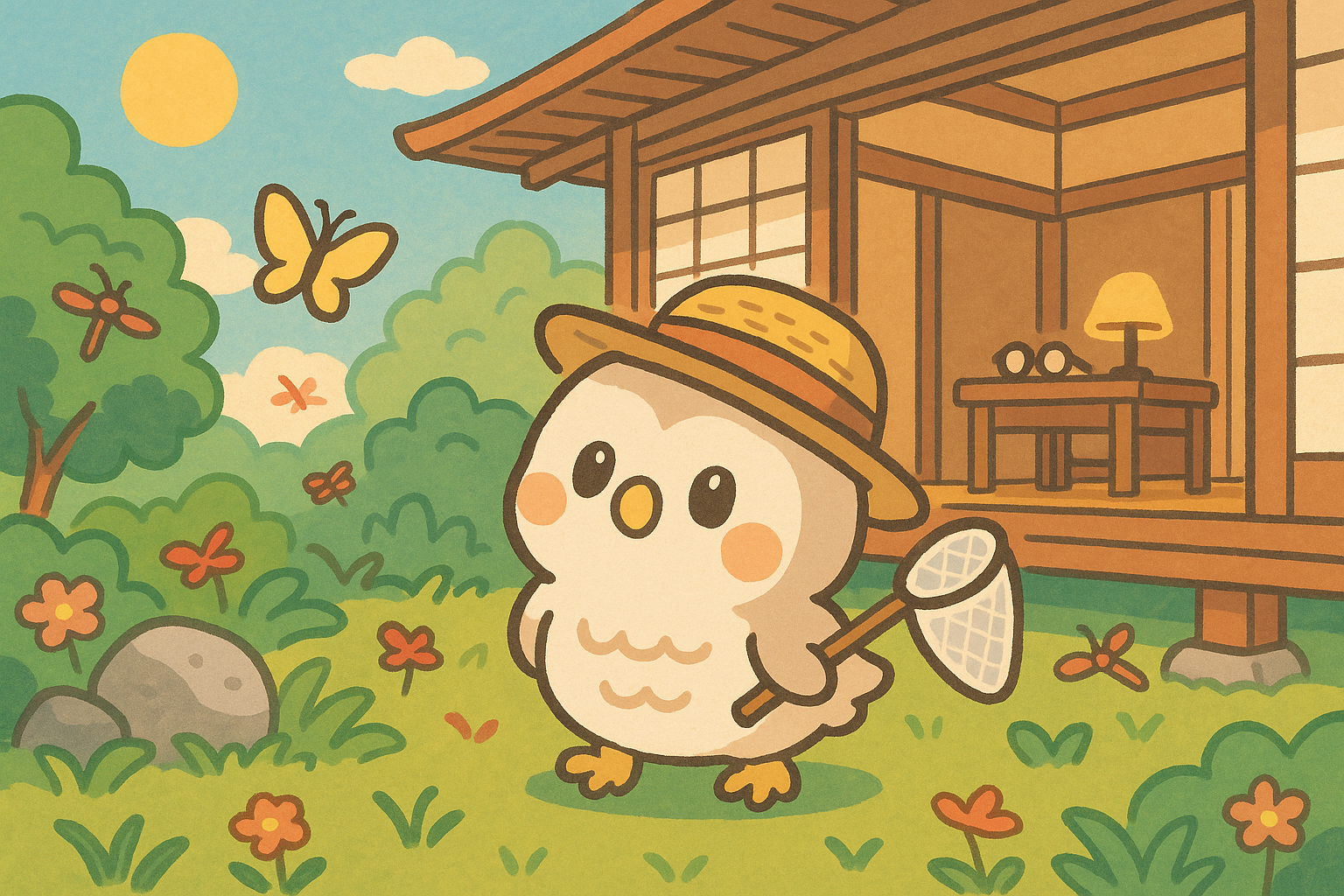
はじめに:私小説の名手・尾崎一雄の魅力とは
「私小説」と聞くと、少し暗くて重たいイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、そのイメージを軽やかに塗り替えてくれるのが、今回ご紹介する作家・尾崎一雄です。彼は、自身の体験や身の回りの出来事を赤裸々に描きながらも、どこか飄々としたユーモアを忘れない作風で知られています。
貧しい生活や病気といった苦境さえも「暢気な眼鏡」を通して見つめ、人間味あふれる物語へと昇華させてしまうのが尾崎文学の真骨頂。日常のありふれた風景に潜む、ささやかな喜びや哀しみ、そしておかしみ。そんな彼の作品に触れれば、きっと心がふっと軽くなるような、温かい気持ちになれるはずです。
尾崎一雄とはどんな作家?その生涯と作風を解説
尾崎一雄は、1899年に三重県で生まれ、昭和を代表する私小説家として活躍しました。中学生の時に読んだ志賀直哉の『大津順吉』に衝撃を受け、作家を志すようになったと言われています。早稲田大学に進学後、その志賀直哉に師事し、本格的に文学の道を歩み始めました。
作家としての道のりは決して平坦ではありませんでした。当初は師である志賀直哉の影響と、当時流行していたプロレタリア文学との間で自身の作風を見出せず、苦しんだ時期もありました。しかし、1931年に山原松枝と結婚してからは、自由闊達な作風を確立し、貧しいながらもユーモアに満ちた日常を描く独自のスタイルを築き上げます。1937年には、その集大成ともいえる短編集『暢気眼鏡』で第5回芥川賞を受賞し、作家としての地位を不動のものとしました。
彼の作品は、自らの体験をありのままに描く「誠実さ」が特徴で、読者に深い共感を呼び起こします。苦しいことや恥ずかしいことでさえも、彼の手に掛かればどこかユーモラスで愛すべき物語に変わってしまうのです。その温かい眼差しは、晩年の作品に至るまで一貫しており、多くの読者を魅了し続けています。
| 生年月日 | 1899年12月25日 |
|---|---|
| 出身地 | 三重県宇治山田町(現・伊勢市) |
| 出身大学 | 早稲田大学文学部国文科 |
| 師事した作家 | 志賀直哉 |
| 主な受賞歴 | 第5回芥川賞、第15回・第28回野間文芸賞、文化勲章 |
尾崎一雄のおすすめ小説ランキングTOP8
ここからは、いよいよ尾崎一雄のおすすめ小説をランキング形式でご紹介します。「私小説の名手」が紡ぎ出す、ユーモアとペーソスにあふれた作品の数々をぜひお楽しみください。
どの作品も、私たちの日常にそっと寄り添ってくれるような温かさを持っています。気になった一冊から、尾崎一雄の世界に足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。
1位『暢気眼鏡 虫のいろいろ 他十三篇』
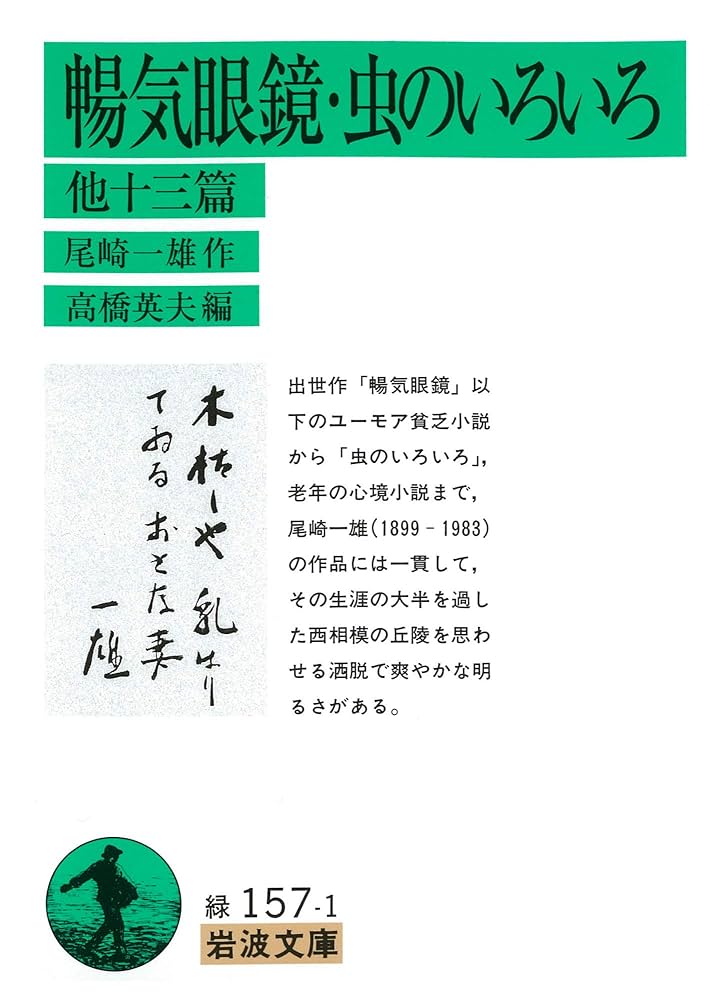
尾崎一雄の代表作であり、第5回芥川賞を受賞した短編集『暢気眼鏡』を含む珠玉の作品集です。表題作の「暢気眼鏡」は、作者自身をモデルにした貧乏な作家と、その妻とのユーモラスな日常を描いた物語。貧しさの中にあっても決して暗くならず、むしろそれを楽しむかのような夫婦の姿が、温かい笑いを誘います。
この作品集には、ほかにも尾崎文学の魅力が詰まった短編が多数収録されています。彼の作品に初めて触れる方は、まずこの一冊から読んでみるのがおすすめです。日常の何気ない風景が、いかに豊かで面白いものであるかを教えてくれるでしょう。
 ふくちい
ふくちい貧乏なのに、なぜか読んでいて心が和むんだ。夫婦のやり取りが最高に面白いよ。
2位『まぼろしの記・虫も樹も』
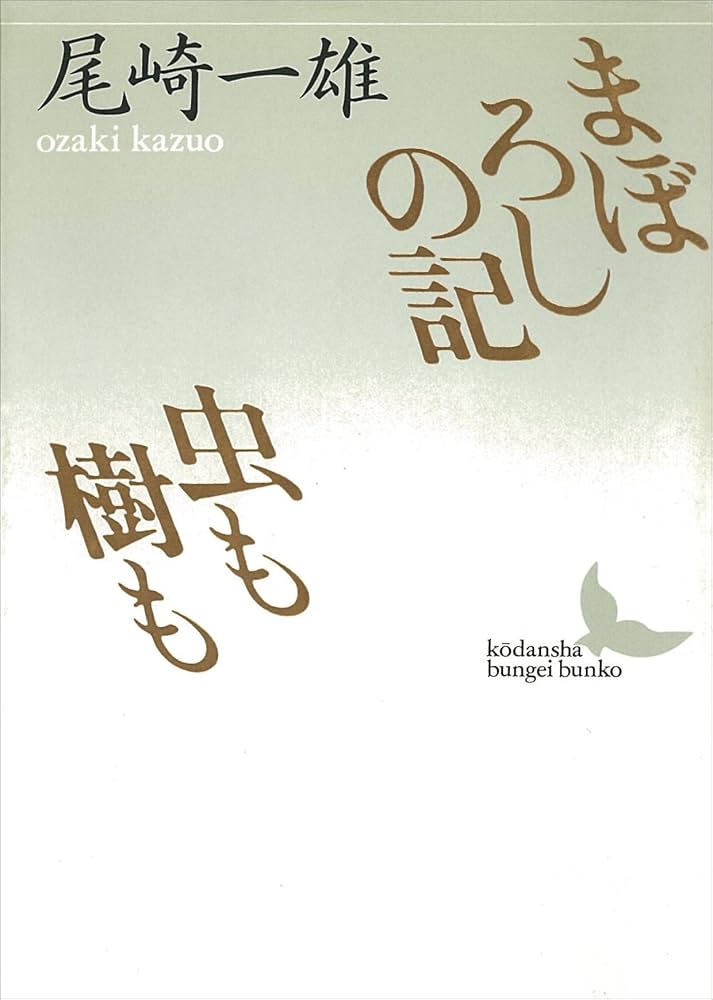
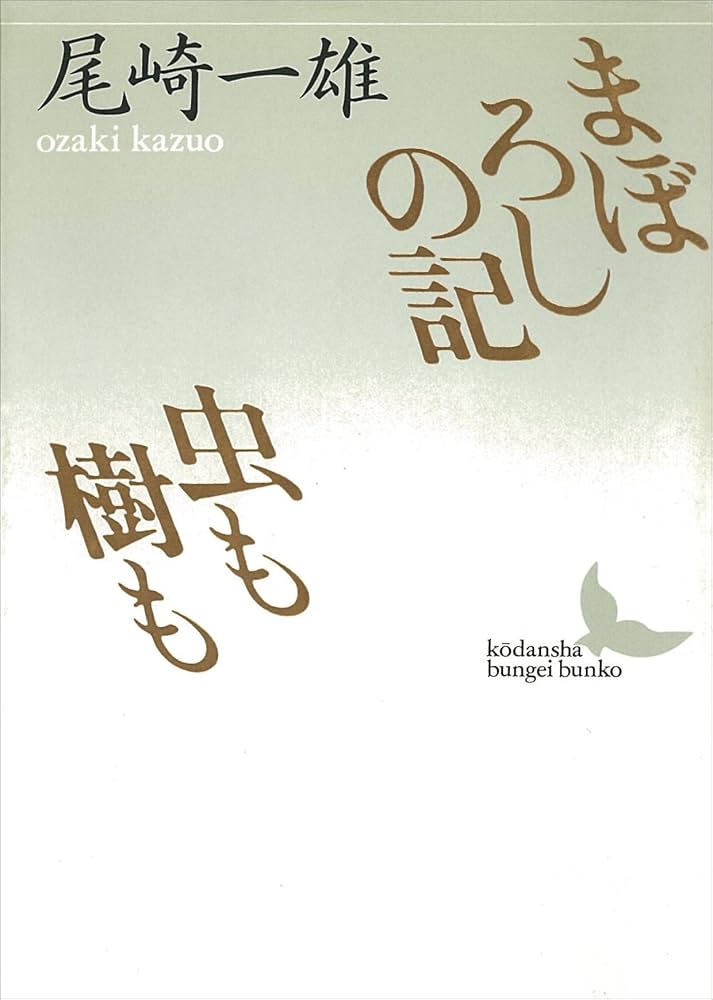
晩年の尾崎一雄の心境小説の代表作であり、『まぼろしの記』は第15回野間文芸賞を受賞しました。老境に達した作家が、自らの半生や死生観、そして身の回りの自然について、静かで澄み切った筆致で綴っています。
若い頃のユーモアあふれる作風とはまた違った、円熟した作家の深い思索に触れることができる一冊です。人生の機微や、生きとし生けるものへの慈しみに満ちた眼差しは、読む者の心に静かな感動をもたらします。



人生の深みを感じさせる作品だね。自然の描写がすごく綺麗で、心が洗われるみたいだよ。
3位『美しい墓地からの眺め』
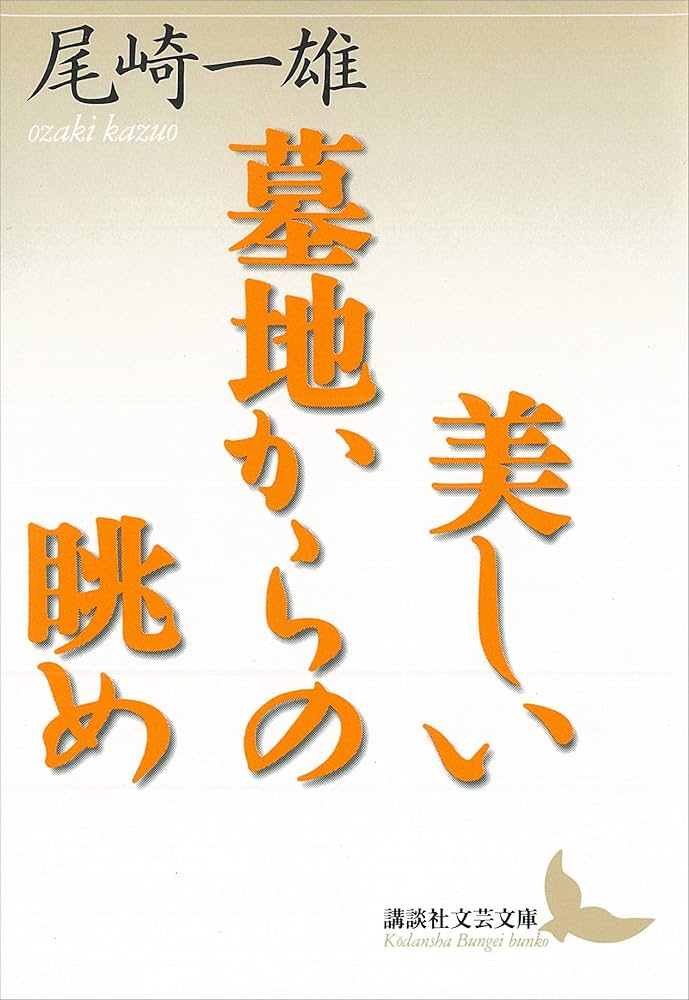
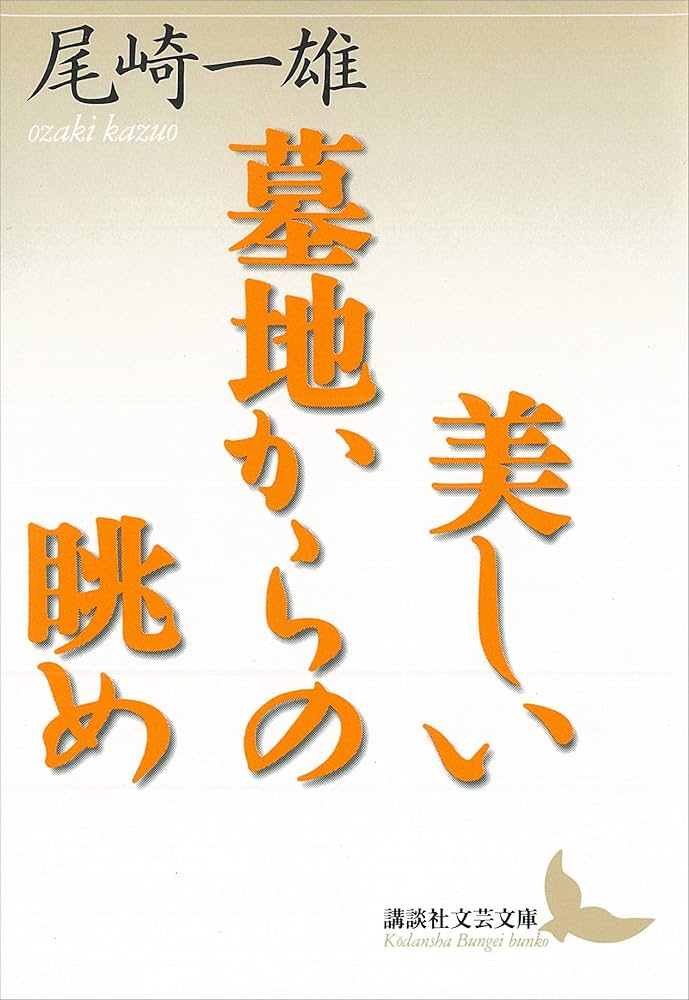
尾崎一雄が晩年を過ごした神奈川県小田原市下曽我にある、自身の家の墓地からの眺めを題材にした作品です。蜜柑畑に囲まれた墓地から見える風景を通して、自身の人生や家族、そして先祖への思いが静かに語られます。
死という重いテーマを扱いながらも、作品全体を包むのは温かく穏やかな雰囲気です。尾崎一雄の死生観や、故郷への深い愛情が感じられる一冊で、人生の終盤をどのように見つめるかについて、深く考えさせられるでしょう。



お墓の話なのに、全然暗くないのが不思議。むしろ、すごく穏やかで優しい気持ちになれるんだ。
4位『新編 閑な老人』
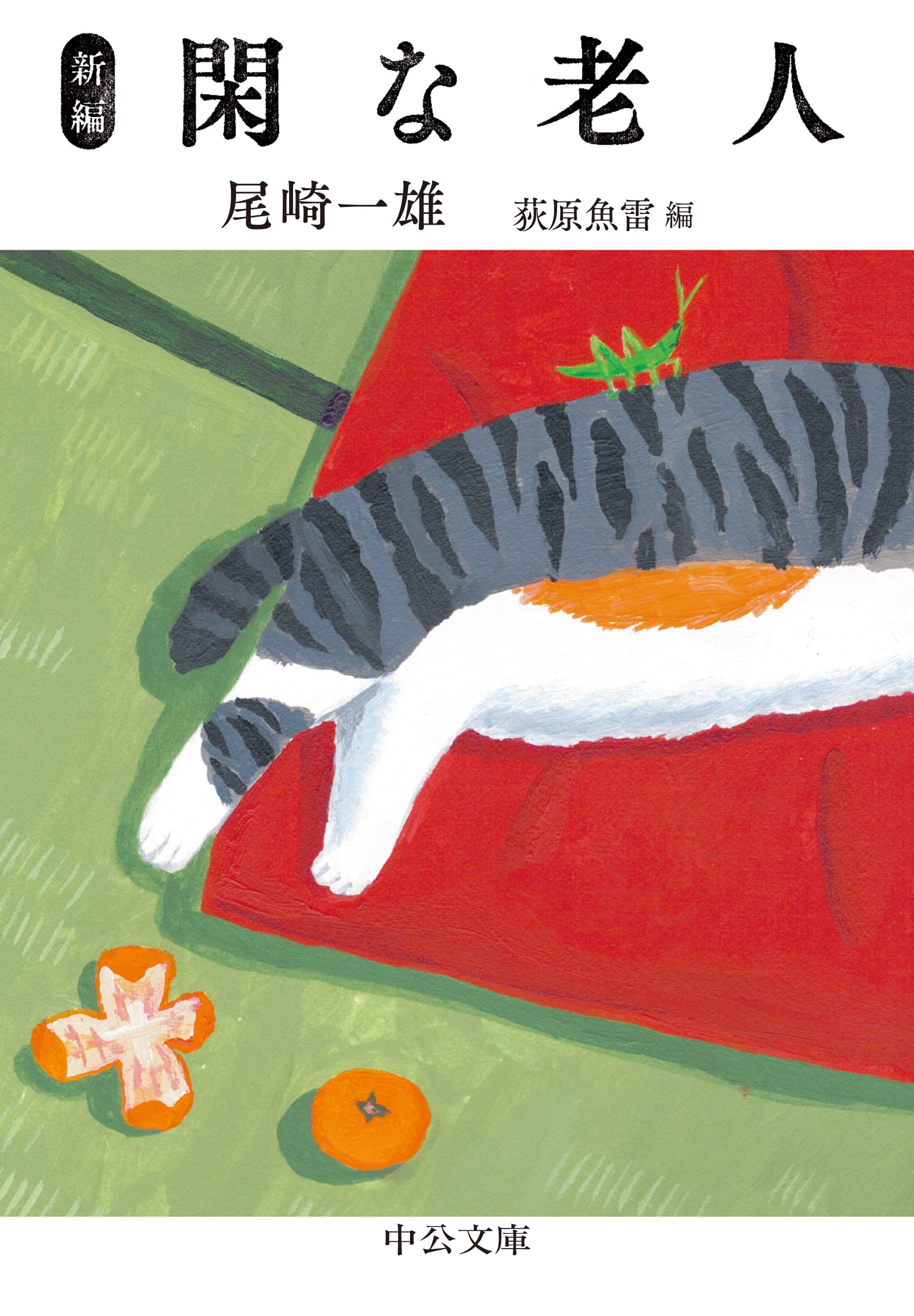
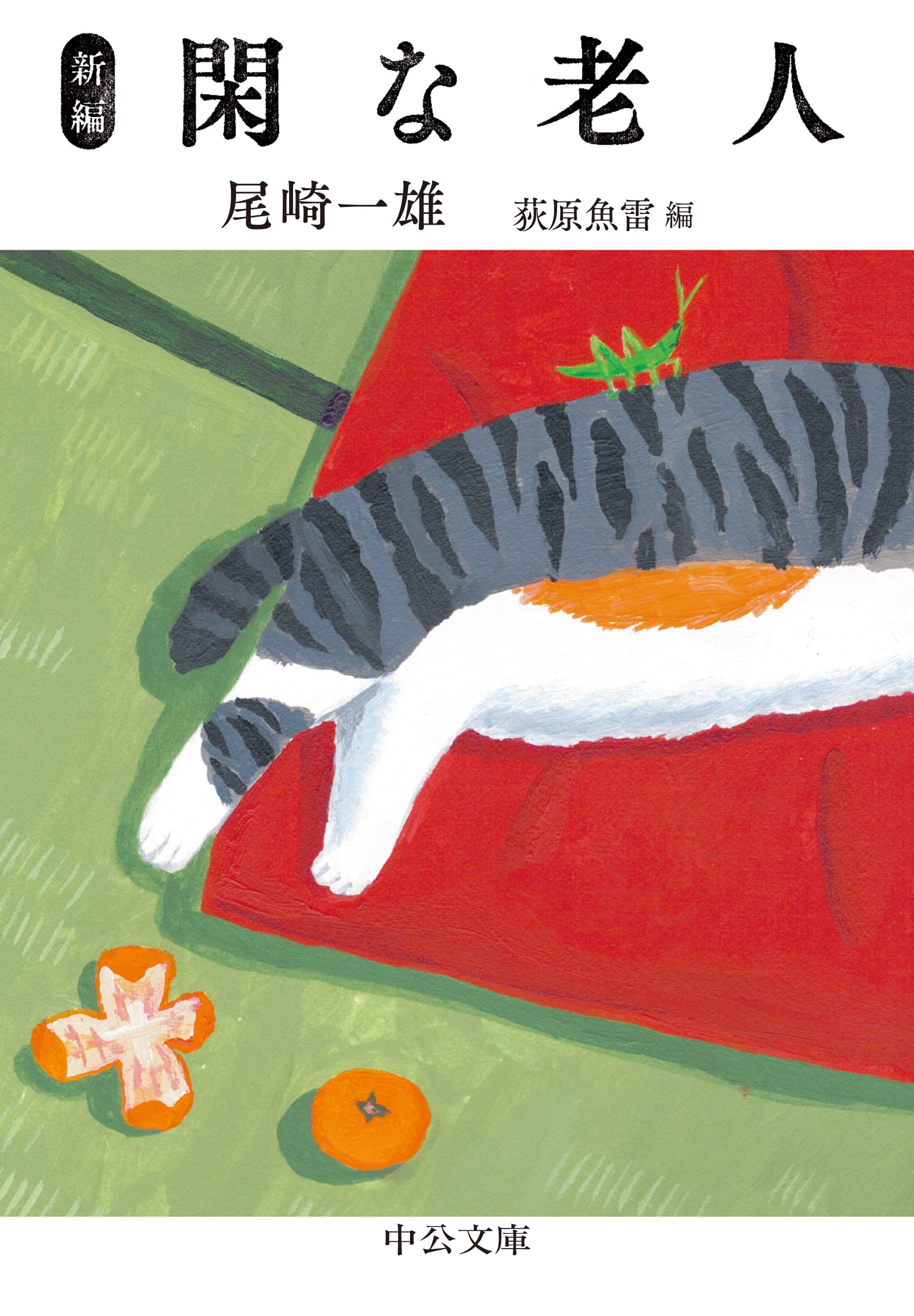
老境に入った作家の日常を、ユーモアを交えて描いた随筆や短編を集めた一冊です。タイトル通り、のんびりとした老人の日々が綴られていますが、その観察眼は鋭く、何気ない日常の中に潜む人間の面白さや哀しさを見事に捉えています。
肩の力を抜いて楽しめる作品が多く、尾崎一雄の飄々とした人柄がよく表れています。日々の暮らしにちょっとした笑いや発見を見つけたい時にぴったりの一冊と言えるでしょう。



おじいちゃんの日常って、こんなに面白いんだ!って思わせてくれるよ。くすっと笑える話がたくさんあるんだ。
5位『単線の駅』
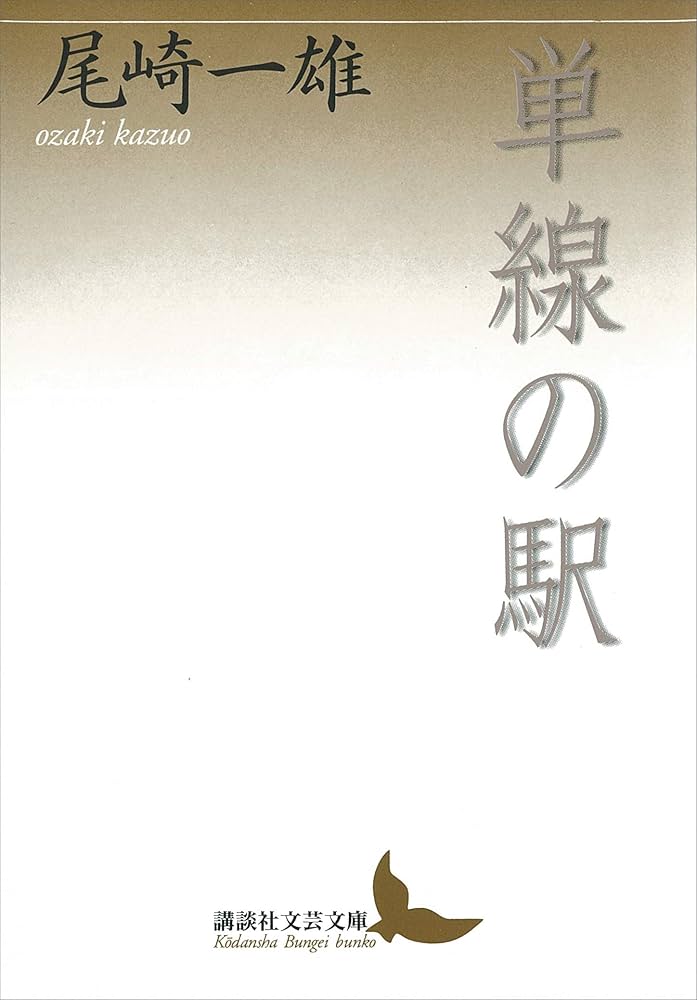
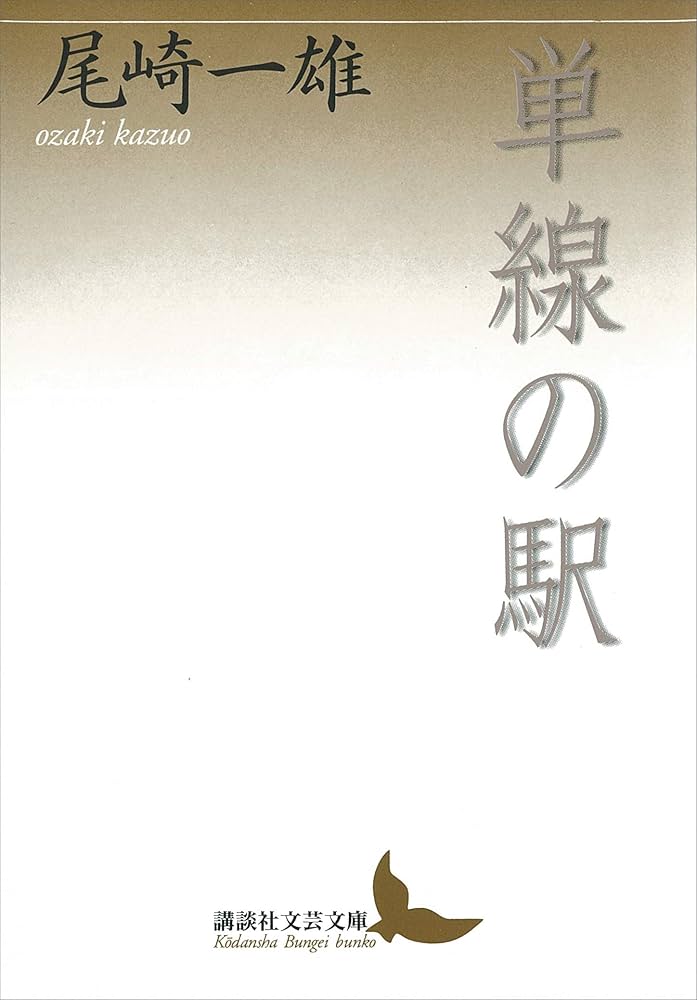
ある地方の単線の駅を舞台に、そこに集う人々の人間模様を描いた作品です。
駅という小さな空間で交差する人々の人生が、淡々とした筆致の中にも情感豊かに描かれています。派手な事件が起こるわけではありませんが、読後には心にじんわりと温かいものが残る、そんな味わい深い一冊です。



駅にいる人たちを、そっと観察している気分になるね。それぞれの人生が垣間見えて、なんだか切ないよ。
6位『暢気眼鏡』(新潮文庫)
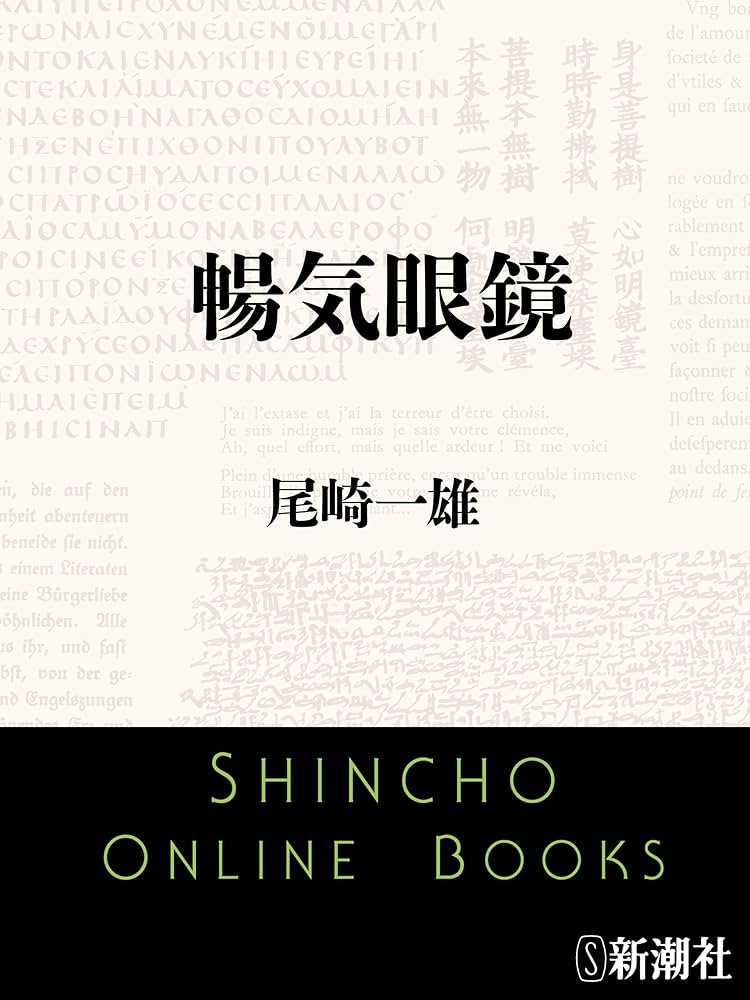
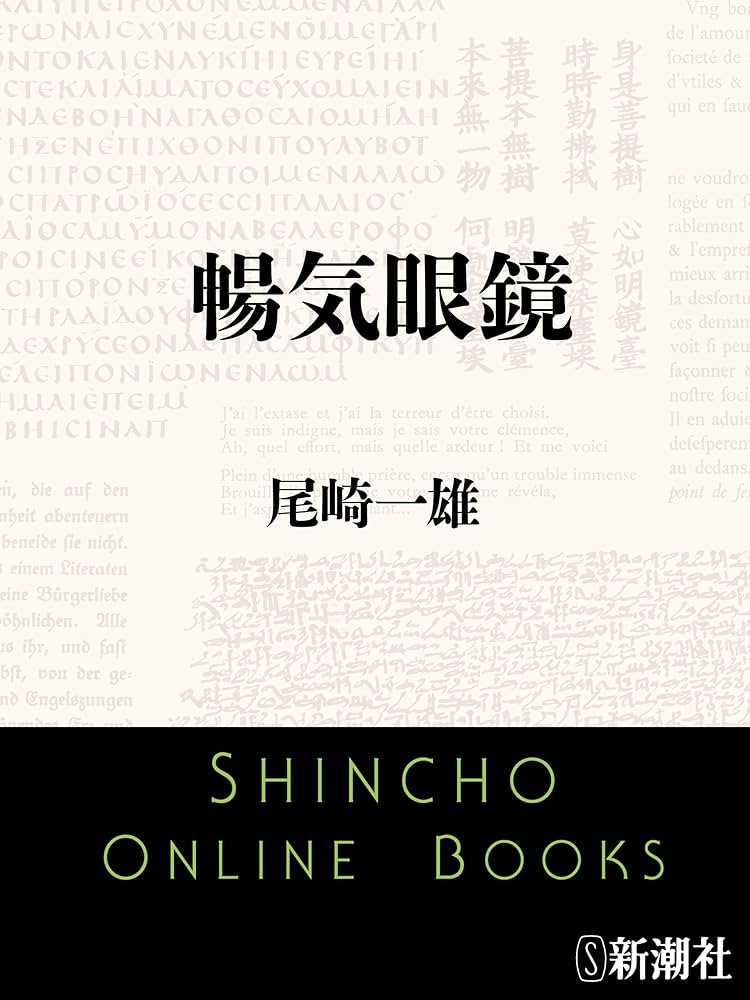
尾崎一雄の代名詞ともいえる『暢気眼鏡』を手軽に読める新潮文庫版です。芥川賞受賞の表題作をはじめ、妻・松枝をモデルにした「芳兵衛もの」と呼ばれる一連の作品が収録されており、尾崎文学の入門編として最適です。
貧乏暮らしを明るくユーモラスに描いた作品群は、時代を超えて多くの読者に愛されています。何度読んでも新しい発見があり、その度に心が温かくなるような、まさに名作と呼ぶにふさわしい一冊です。



やっぱりこの作品は外せないよね!わたし、芳兵衛さんが大好きなんだ。こんな奥さんがいたら毎日楽しそうだなあ。
7位『あの日この日』
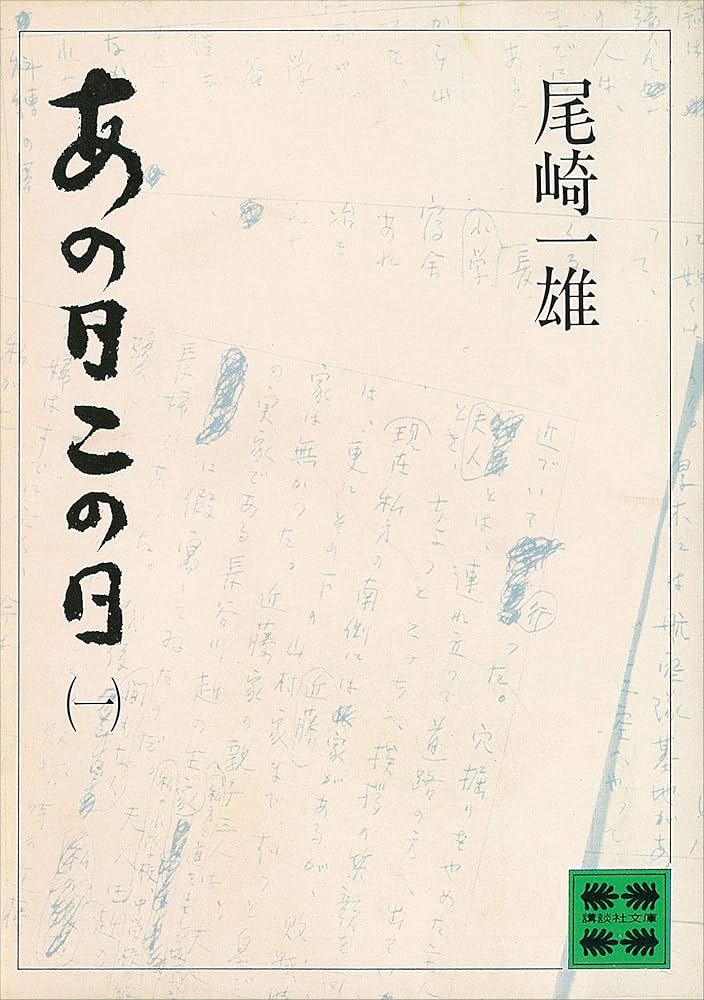
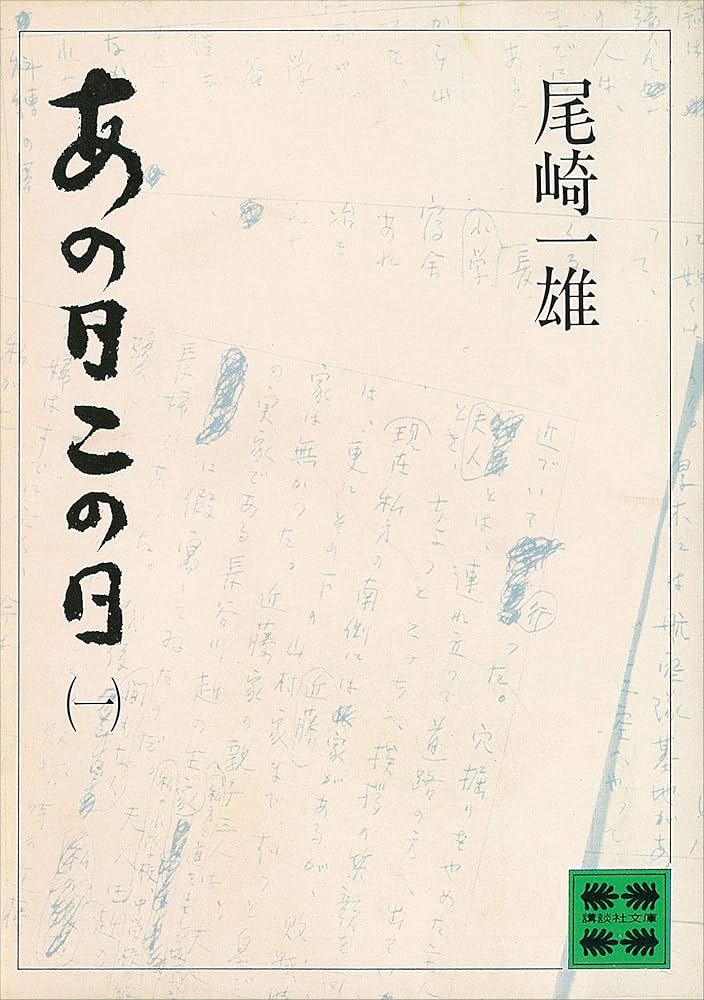
作家自身の半生を振り返った自伝的な長編小説で、1975年に第28回野間文芸賞を受賞しています。作家としてデビューするまでの道のりや、妻との出会い、そして文壇の友人たちとの交流などが、飾らない言葉で綴られています。
一人の作家がどのようにして生まれ、その作風を確立していったのかを知ることができる貴重な作品です。尾崎一雄という作家の人間的な魅力に、より深く触れたい方におすすめします。



作家さんの人生って、やっぱり波瀾万丈なんだね。これを読むと、他の作品ももっと深く味わえる気がするよ。
8位『懶い春』
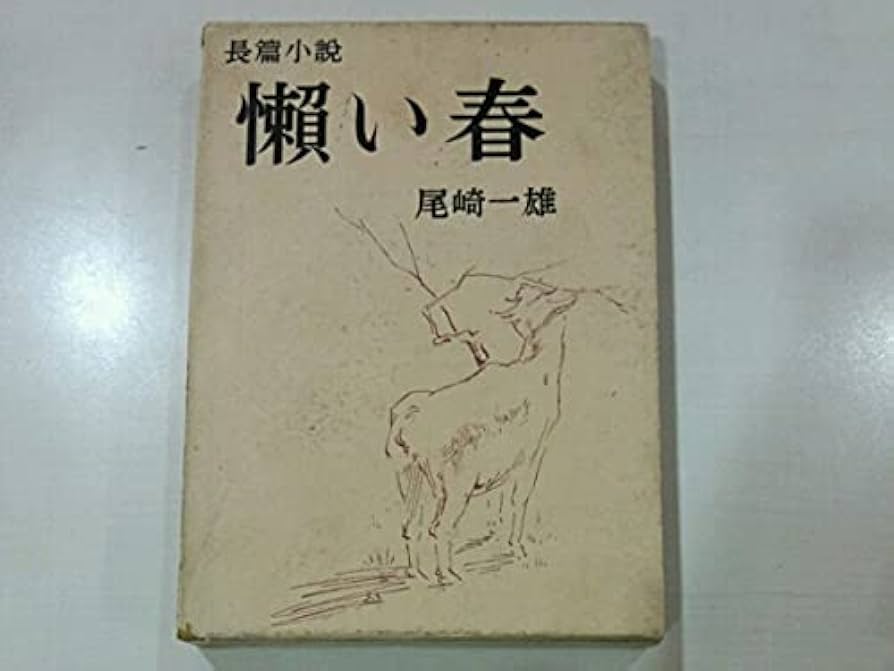
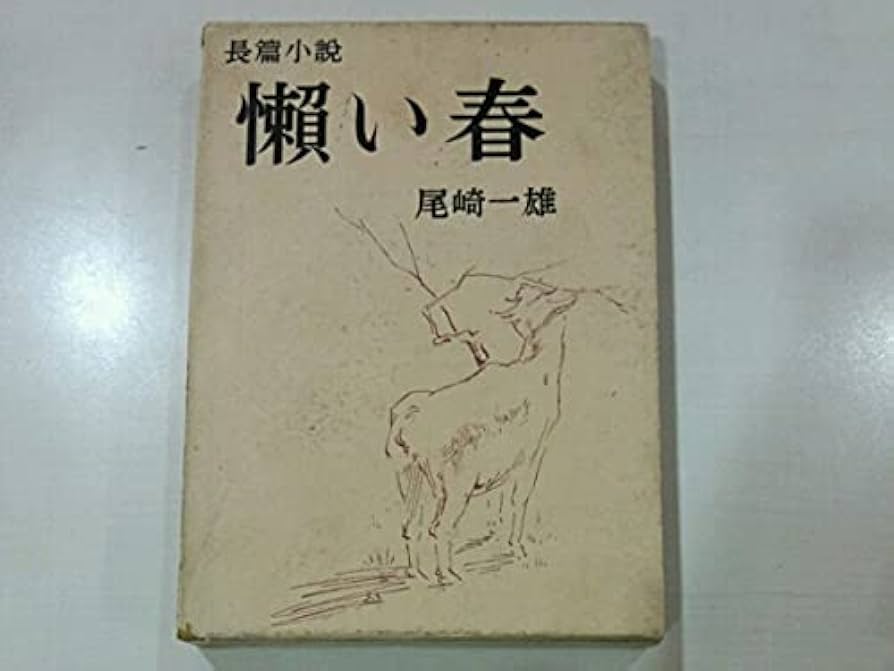
ある夫婦の倦怠期のような、気だるい日常を描いた短編です。大きな事件が起こるわけではなく、夫婦の間の微妙な空気感や心理描写が巧みに描かれています。
派手さはありませんが、誰しもが経験するかもしれない夫婦関係の機微をリアルに捉えており、読者は思わず自らの経験と重ね合わせてしまうかもしれません。人間の心の奥深くを静かに見つめる、尾崎一雄の観察眼が光る一作です。



なんだかドキッとする話だなあ。夫婦って、こういう時期もあるのかなって考えさせられちゃった。
まとめ:尾崎一雄のおすすめ人気小説を読んでみよう
今回は、私小説の名手・尾崎一雄のおすすめ小説をランキング形式でご紹介しました。彼の作品は、自らの人生を題材にしながらも、決して独りよがりにならず、普遍的な人間の喜びや悲しみをユーモアを交えて描いています。
貧しい生活や老い、死といったテーマでさえも、彼の「暢気な眼鏡」を通すことで、どこか温かく、愛おしいものとして私たちの目に映るでしょう。日々の生活に少し疲れた時、心がささくれている時に、ぜひ尾崎一雄の小説を手に取ってみてください。きっと、凝り固まった心を優しくほぐしてくれるはずです。


