あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】五味康祐のおすすめ小説ランキングTOP17

五味康祐とは? 昭和の剣豪小説ブームを牽引した作家
五味康祐(ごみ やすすけ)は、1921年生まれの日本の小説家です。 1952年に発表した『喪神』で芥川賞を受賞し、文壇にデビューしました。 その後、時代小説、特に剣豪を扱った作品で高い評価を受け、昭和の剣豪小説ブームを牽引した存在として知られています。
代表作である『柳生武芸帳』は、1956年の『週刊新潮』創刊から連載され、絶大な人気を博しました。 この作品は、それまでの剣豪小説とは一線を画し、柳生一族を単なる剣術指南役ではなく、政治的な隠密集団として描くという新しい視点で注目を集めました。 この成功をきっかけに、「五味の柳生か、柳生の五味か」と評されるほど、柳生一族をテーマにした作品で知られるようになります。
また、五味康祐は小説家としてだけでなく、多彩な趣味人としても有名でした。 特にクラシック音楽とオーディオには深い造詣があり、「オーディオの神様」とも呼ばれるほどで、音楽に関する評論も数多く残しています。 麻雀や観相学にも精通しており、その多才ぶりは多くの文化人に影響を与えました。 1980年に58歳でその生涯を閉じましたが、彼の作品は今なお多くの読者を魅了し続けています。
【2025年最新】五味康祐のおすすめ小説ランキングTOP17
五味康祐の作品は、手に汗握る剣戟シーンだけでなく、緻密な人間描写や、武士の生き様を描いた深い物語性が魅力です。彼の作品は数多くありますが、今回はその中でも特に読んでおくべき名作をランキング形式でご紹介します。
剣豪小説の金字塔から、少し意外な作品まで、五味康祐の多彩な世界に触れることができるラインナップとなっています。どの作品から読めばいいか迷っている方は、ぜひこのランキングを参考に、お気に入りの一冊を見つけてみてください。
1位『柳生武芸帳』
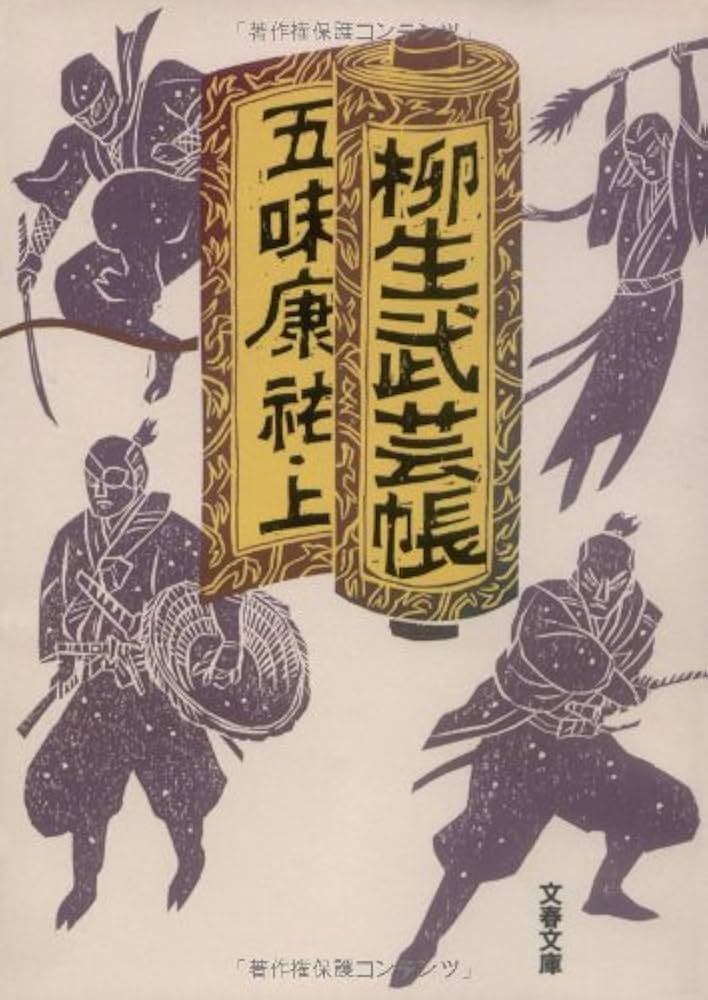
五味康祐の代表作であり、剣豪小説の歴史にその名を刻んだ不朽の名作が『柳生武芸帳』です。1956年から『週刊新潮』で連載が開始され、柴田錬三郎の『眠狂四郎無頼控』と並んで爆発的な人気を博し、一大剣豪小説ブームを巻き起こしました。
物語は、柳生家に伝わる三冊の武芸帳を巡る争奪戦を軸に展開されます。この武芸帳には、柳生新陰流の奥義だけでなく、幕府転覆を企む者たちの名が記されているとされ、柳生宗矩と十兵衛親子をはじめ、多くの剣士たちが入り乱れて死闘を繰り広げます。単なる剣術の物語にとどまらず、政治的な陰謀や人間ドラマが複雑に絡み合う壮大なスケールが、多くの読者を惹きつけました。
残念ながら物語は未完に終わっていますが、それを補って余りあるほどの魅力と熱量がこの作品には込められています。 五味康祐を知る上で、そして剣豪小説の真髄に触れる上で、絶対に外すことのできない一冊と言えるでしょう。
 ふくちい
ふくちい壮大な物語の幕開けにワクワクが止まらないよ!未完だからこそ、物語の続きを想像する楽しみもあるんだよね。
2位『薄桜記』
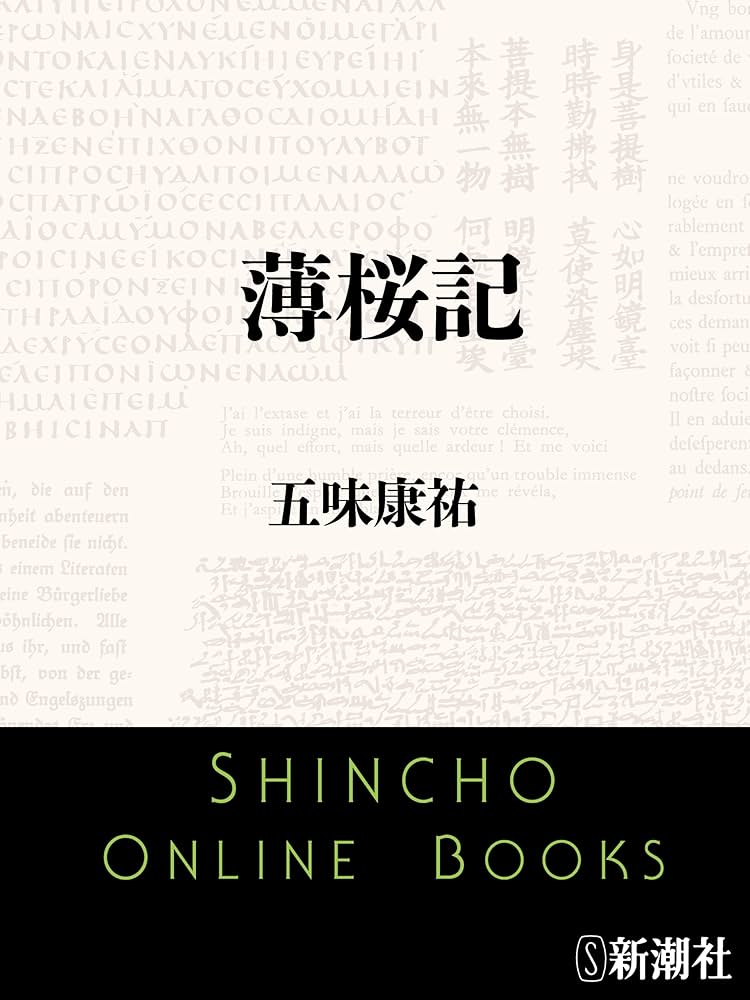
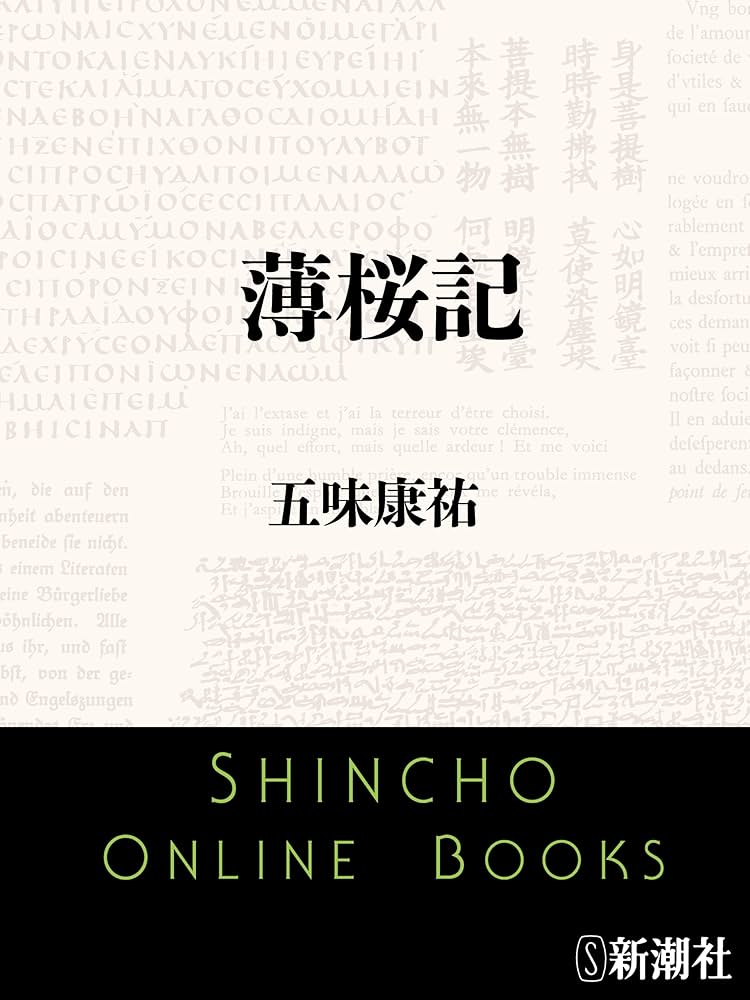
『薄桜記』は、忠義と愛憎が渦巻く人間ドラマを描いた五味康祐の傑作時代小説です。赤穂浪士の吉良邸討ち入り事件を背景にしながらも、その中心にいるのは無名の武士たち。彼らの生き様を通して、武士道とは何か、そして愛とは何かを問いかけます。
主人公は、片腕を失った剣の達人・丹下典膳と、その妻を奪った同門の堀部安兵衛。典膳の安兵衛に対する復讐心と、妻への断ち切れぬ想いが、物語に深い陰影を与えています。極限状況に置かれた人間の心理描写が巧みで、読者は登場人物たちの葛藤に心を揺さぶられることでしょう。
派手な剣戟シーンだけでなく、登場人物たちの心の機微を丁寧に描いた本作は、五味康祐のもう一つの魅力を教えてくれます。武士の矜持と悲哀が胸を打つ、感動的な物語です。



武士の生き様が切なくて…。わたし、こういうのに弱くて涙が出ちゃうんだ。
3位『秘剣・柳生連也斎』
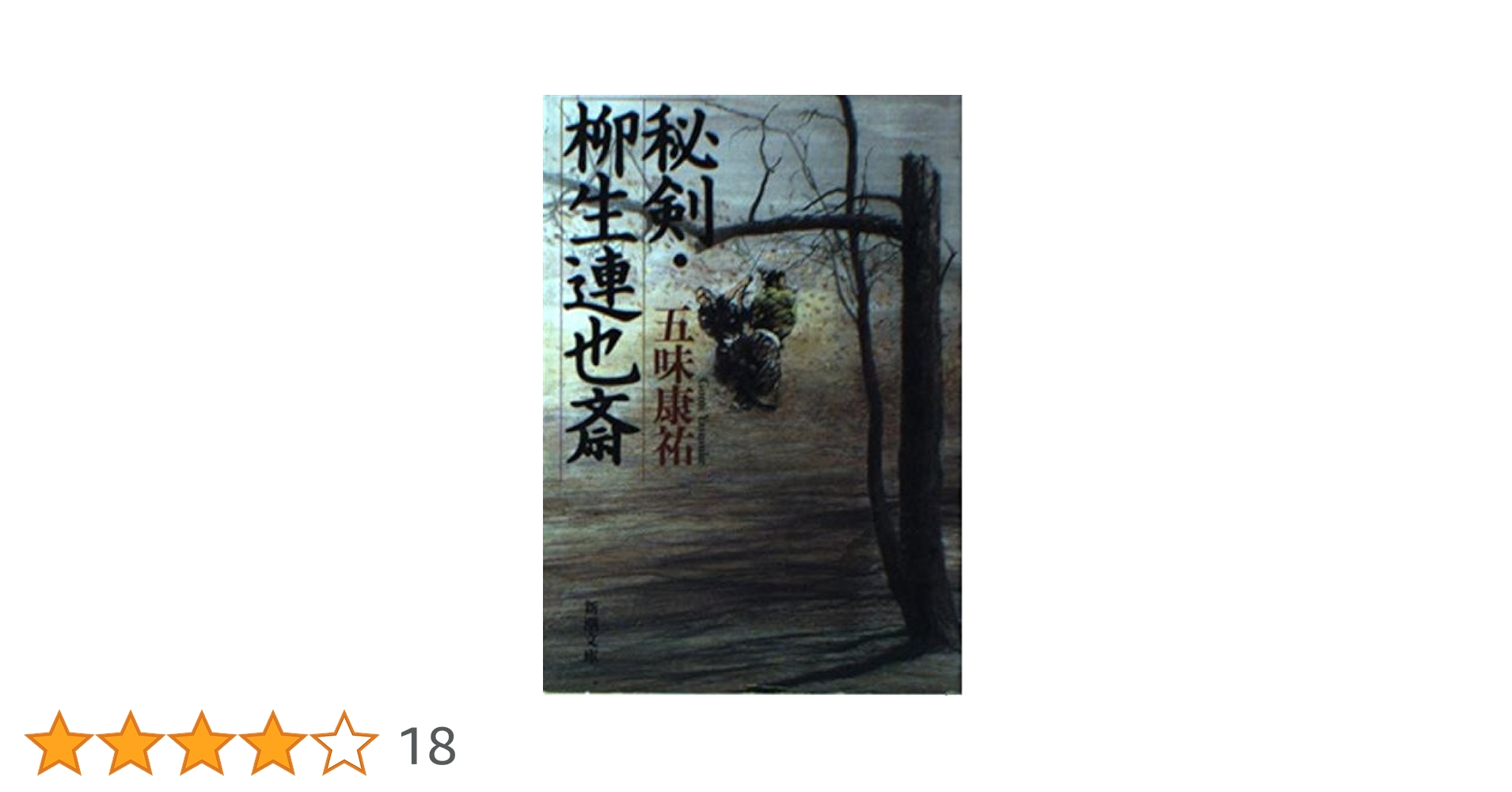
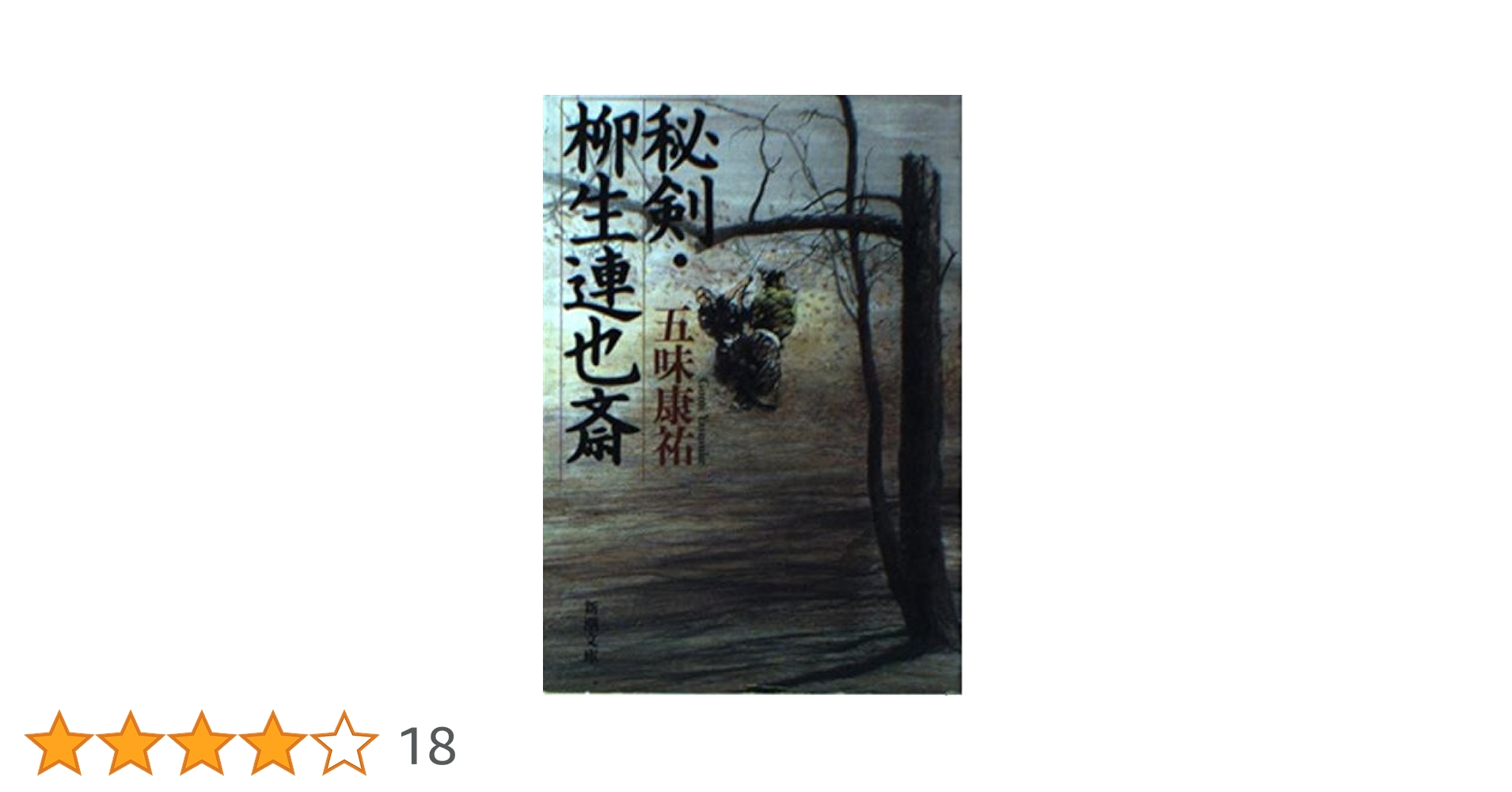
『秘剣・柳生連也斎』は、実在した謎多き剣豪、柳生連也斎(本名:柳生厳包)を主人公にした物語です。連也斎は、将軍家指南役である江戸柳生とは一線を画し、尾張の地で独自の剣を追求した孤高の剣士として描かれています。
本作の魅力は、なんといっても連也斎の圧倒的な強さと、そのストイックな生き様です。彼は、剣の道を極めることのみに生涯を捧げ、権力や名声には一切興味を示しません。その姿は、まさに求道者そのもの。五味康祐の筆致は、連也斎の放つ気迫や、一瞬の勝負にかける剣士の緊張感を見事に描き出しています。
柳生一族の中でも異彩を放つ連也斎の生き様を通して、真の強さとは何かを問いかける作品です。剣の道に生きる男の純粋な姿に、きっと心を打たれるはずです。



ひたすら剣の道を追い求める姿、かっこいいなあ。こういう職人気質なキャラクター、わたしは好きだよ。
4位『二人の武蔵』
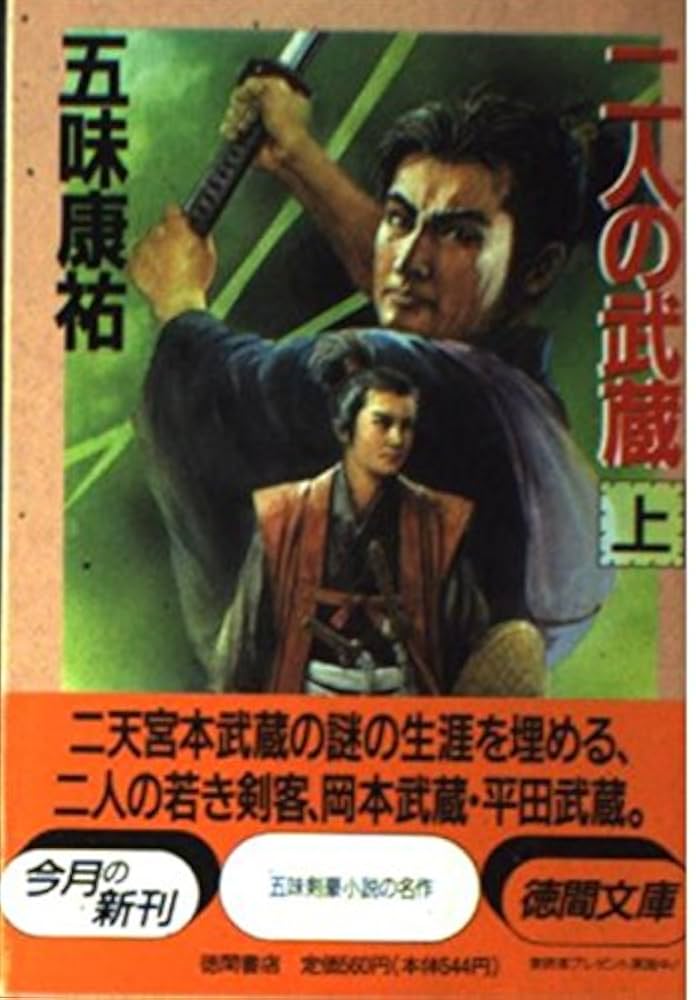
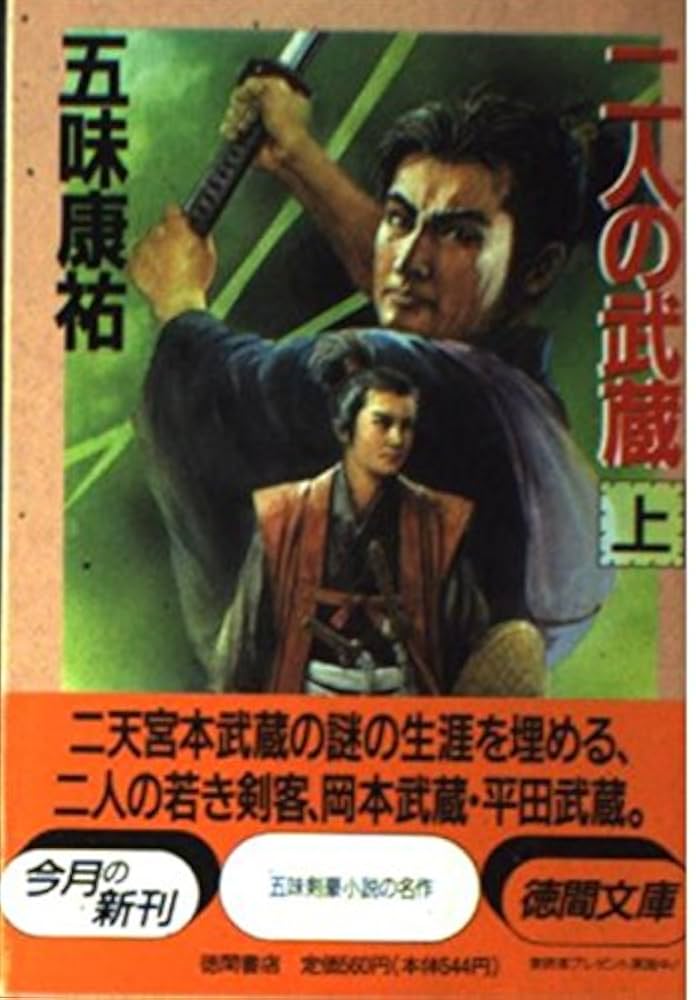
宮本武蔵といえば、吉川英治の小説が有名ですが、五味康祐は全く新しい武蔵像を『二人の武蔵』で描き出しました。本作は、その名の通り、二人の「武蔵」が登場するという意欲的な作品です。
一人は、私たちがよく知る剣豪・宮本武蔵。そしてもう一人は、武蔵の名を騙る偽物です。物語は、この二人の武蔵の人生が交錯しながら進んでいきます。本物と偽物、英雄と凡人という対比を通して、人間の真実とは何かを鋭く問いかけます。
偽物の武蔵が抱く、本物への憧れや嫉妬、そして苦悩。その人間臭い姿に、読者はかえって感情移入してしまうかもしれません。従来の英雄譚とは一味違った、五味康祐ならではの宮本武蔵の物語を楽しめる一冊です。



本物と偽物、どっちが本当の自分なんだろうって考えさせられるね。ちょっと哲学的なテーマで面白いかも。
5位『柳生宗矩と十兵衛』
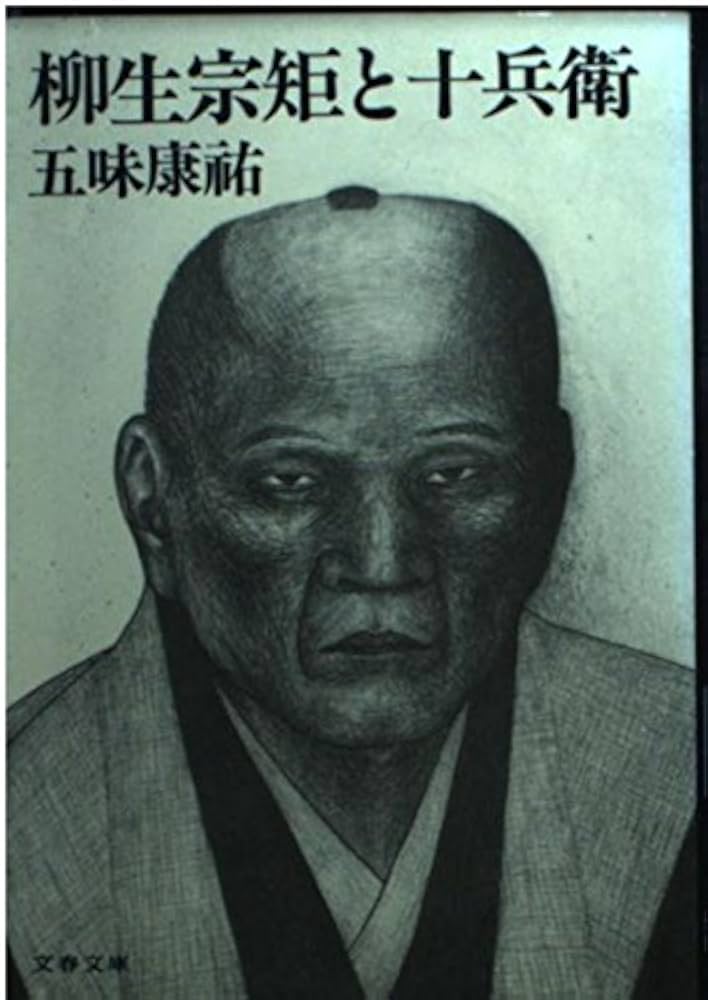
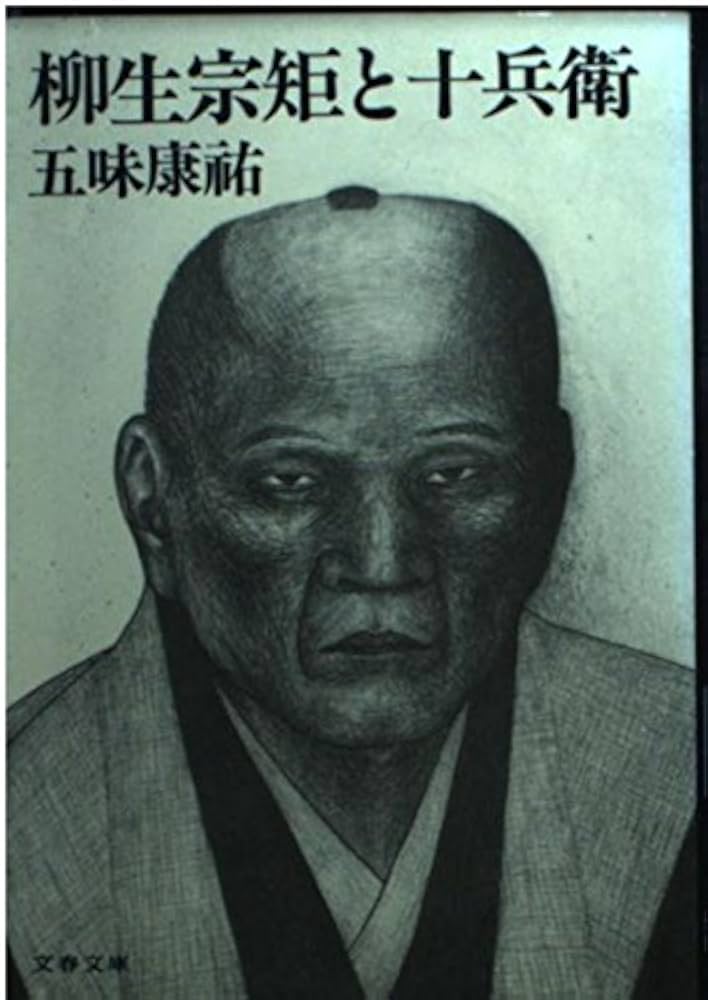
『柳生武芸帳』でも重要な役割を担った柳生宗矩と十兵衛。本作は、この偉大な父と天才的な息子の確執と宿命に焦点を当てた物語です。親子でありながら、剣の道、そして生きる道において全く異なる価値観を持つ二人の対立が、物語の主軸となっています。
徳川幕府の安泰のために非情な策謀を巡らす父・宗矩と、自由奔放に剣の道を生きる息子・十兵衛。二人の関係は、単なる親子の対立を超え、組織に生きる者と個として生きる者の哲学的な対立としても描かれています。五味康祐は、二人の内面を深く掘り下げ、その葛藤を鮮やかに描き出しました。
『柳生武芸帳』と合わせて読むことで、柳生一族の物語をより深く理解することができるでしょう。父と子の宿命的な物語は、読む者の胸に強く迫ります。



お父さんと息子の考え方が違うって、なんだかハラハラする展開だね。どっちの気持ちもわかるから複雑だよ。
6位『剣法秘伝』
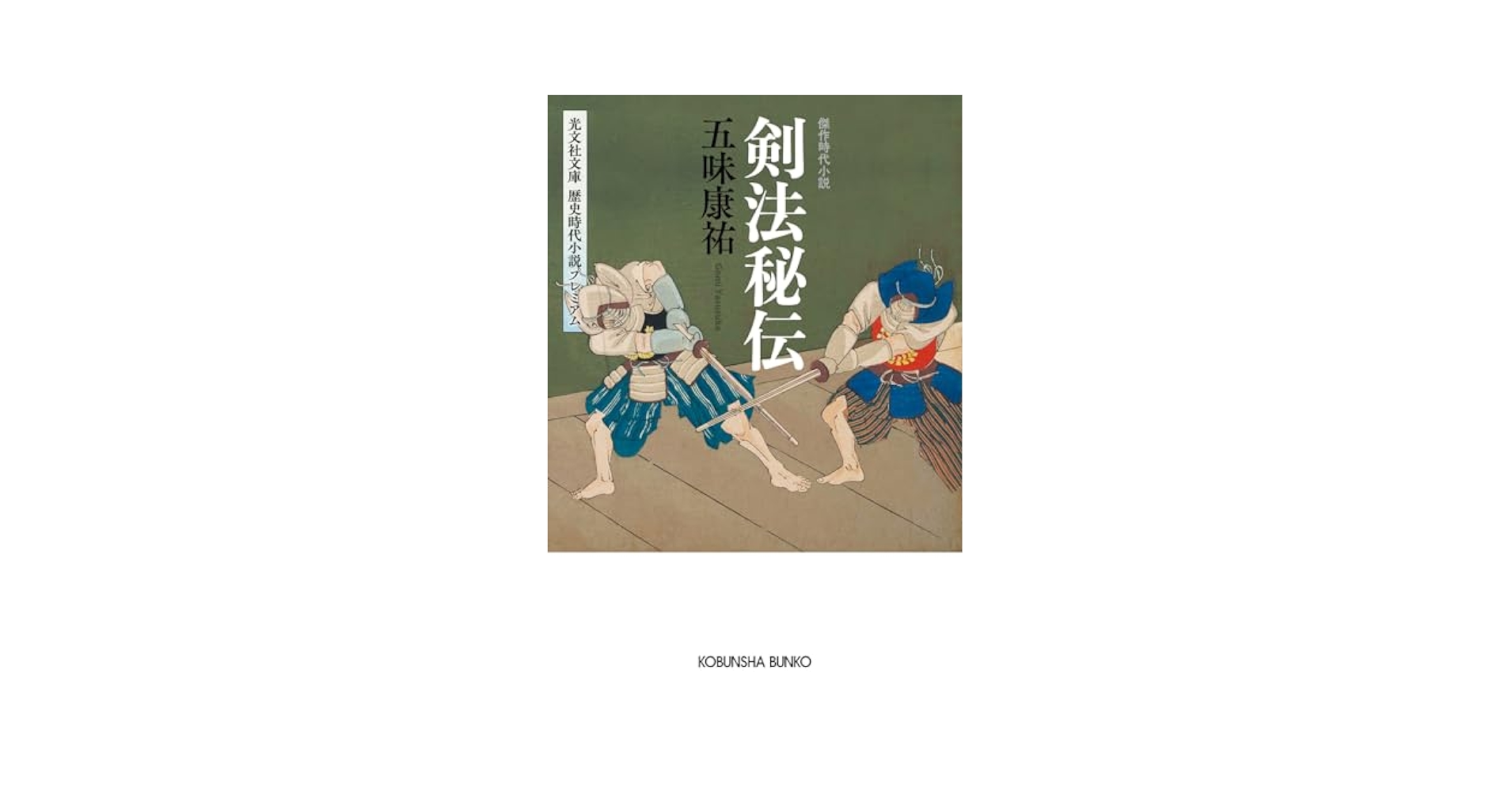
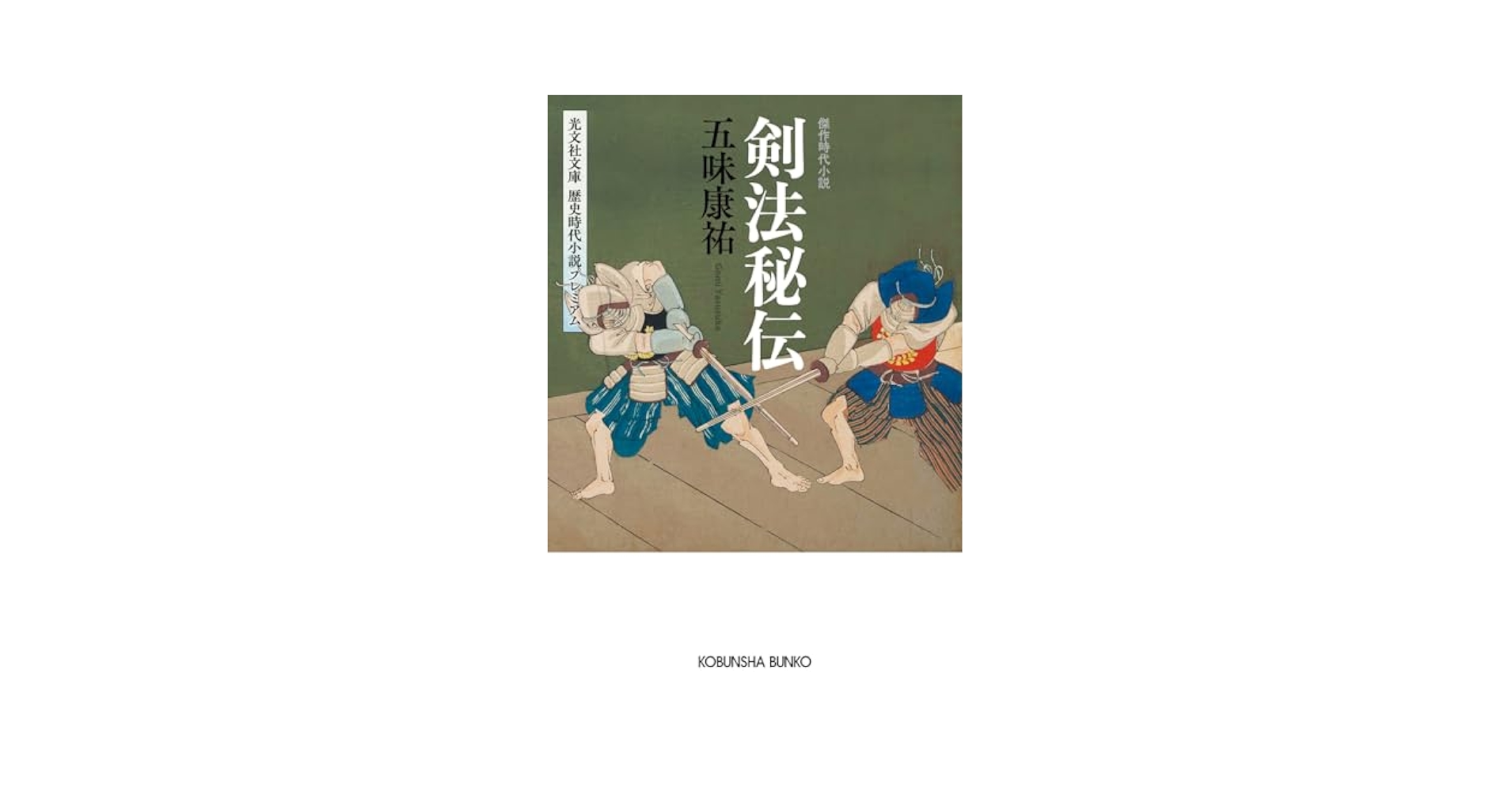
『剣法秘伝』は、様々な剣豪たちの知られざるエピソードを描いた短編集です。柳生石舟斎や宮本武蔵といった有名な剣豪から、歴史の影に埋もれた無名の達人まで、多彩な人物が登場します。
短編集ならではの魅力は、一話完結で読みやすく、それでいて各話が非常に濃密であることです。五味康祐は、短い物語の中に、剣士たちの生き様や哲学、そして人間的な魅力を凝縮させています。剣の勝負の緊張感はもちろん、そこに至るまでの剣士の苦悩や覚悟が丁寧に描かれており、読後には深い余韻が残ります。
どの話から読んでも楽しめるので、五味康祐の剣豪小説に初めて触れる方にもおすすめです。一編読むごとに、剣の道の奥深さに引き込まれていくことでしょう。



短いお話がたくさん詰まってるんだね。ちょっとした時間にサクッと読めるのは嬉しいな。
7位『兵法柳生新陰流』
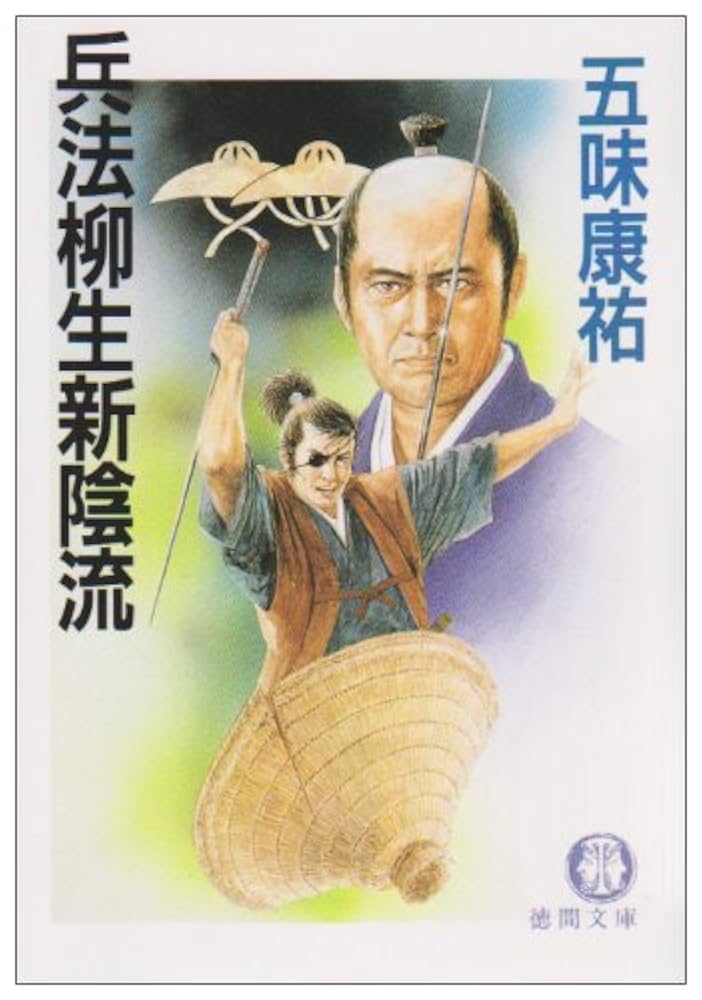
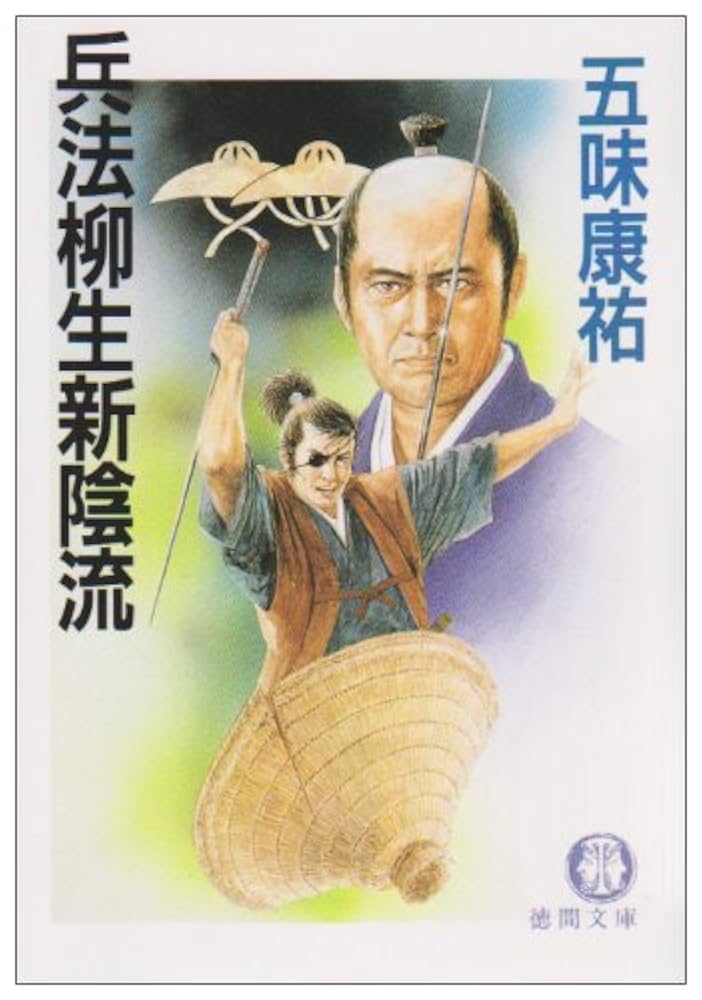
『兵法柳生新陰流』は、柳生新陰流の神髄に迫る、非常に読み応えのある一冊です。単なる剣術の解説書ではなく、柳生石舟斎から宗矩、そして十兵衛へと受け継がれていく兵法の思想と哲学を、物語を通して深く掘り下げています。
本作で描かれる柳生新陰流は、ただ敵を斬り倒すための技術ではありません。それは、「活人剣」という思想に代表されるように、いかにして戦わずして勝つか、いかにして人を活かすかという、深い哲学に基づいています。五味康祐は、難解になりがちな兵法の思想を、具体的なエピソードを交えながら分かりやすく解説しています。
剣豪小説ファンはもちろん、武道や日本の思想に興味がある方にとっても、多くの発見がある作品です。柳生一族の強さの根源にある、その深い精神性に触れてみてください。



剣の強さだけじゃなくて、その裏にある考え方まで描かれているんだね。なんだかすごく奥が深そうだよ。
8位『人斬り彦斎』
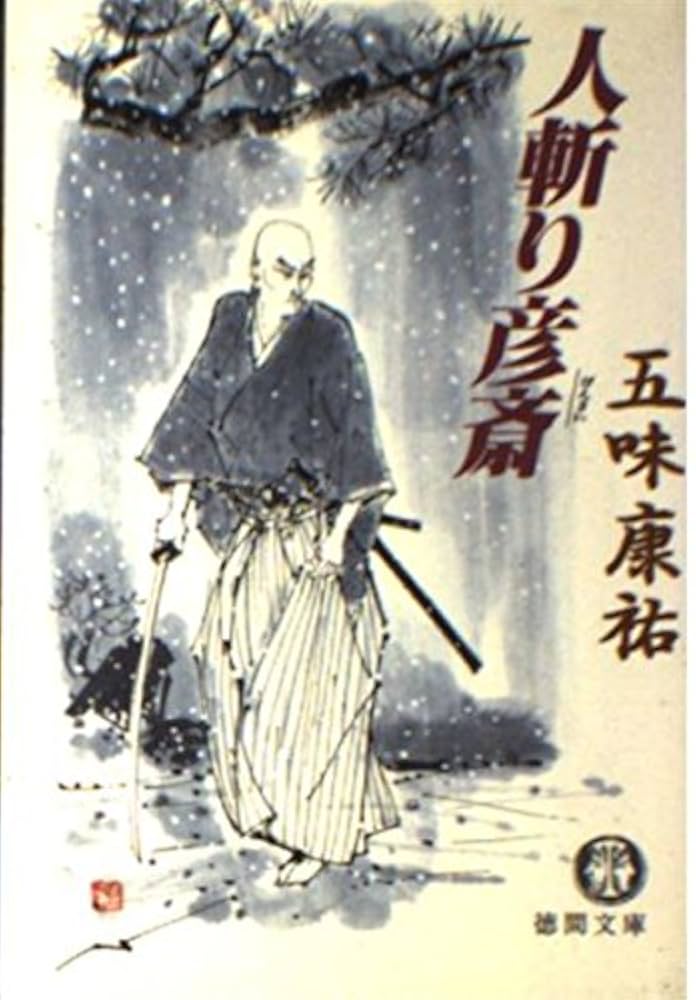
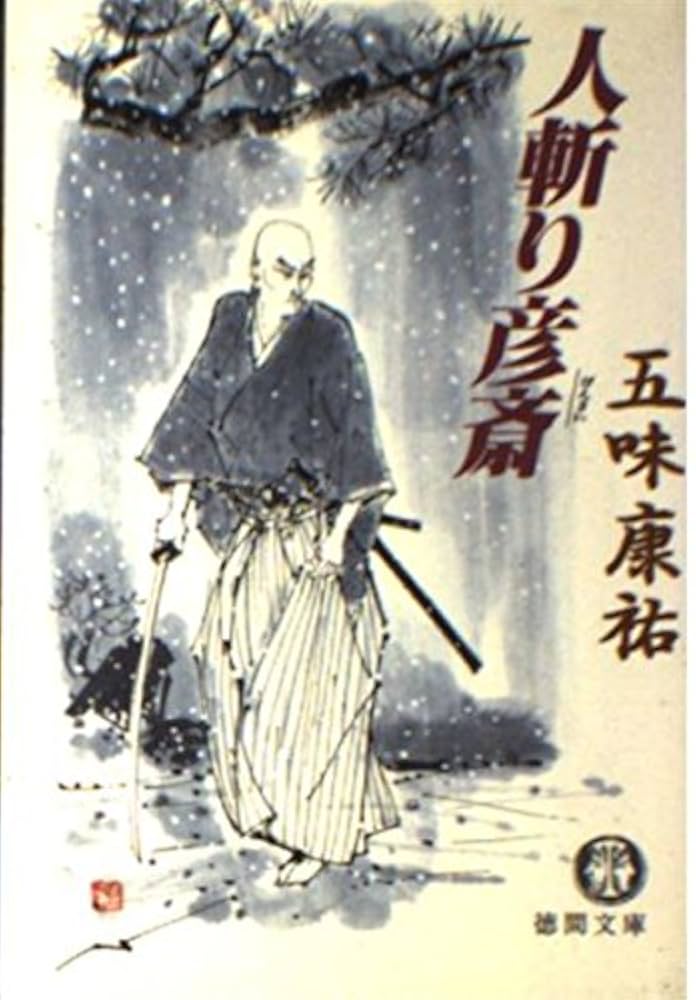
幕末の動乱期に「人斬り彦斎」として恐れられた実在の人物、河上彦斎の生涯を描いた作品です。彦斎は、幕末四大人斬りの一人に数えられながらも、その生涯には謎が多い人物として知られています。
五味康祐は、このミステリ-アスな剣客の姿を、独自の解釈で鮮やかに描き出しました。本作の彦斎は、純粋な理想のために剣を振るう一方で、人斬りとしての宿命に苦悩する人間的な姿が印象的です。彼の振るう剣は恐ろしくもどこか美しく、その生き様は儚く、読む者の胸を打ちます。
激動の時代に翻弄されながらも、自らの信念を貫こうとした一人の男の物語。歴史の裏側で生きた剣客の孤独と悲哀に満ちた生涯に、深く引き込まれる作品です。



本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。
9位『スポーツマン一刀斎』
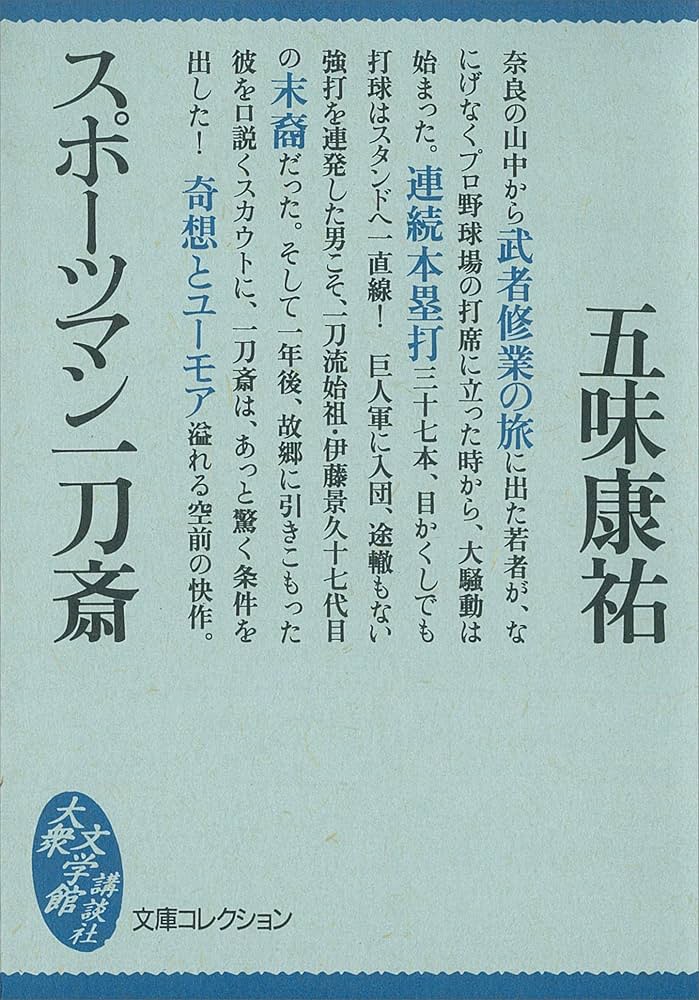
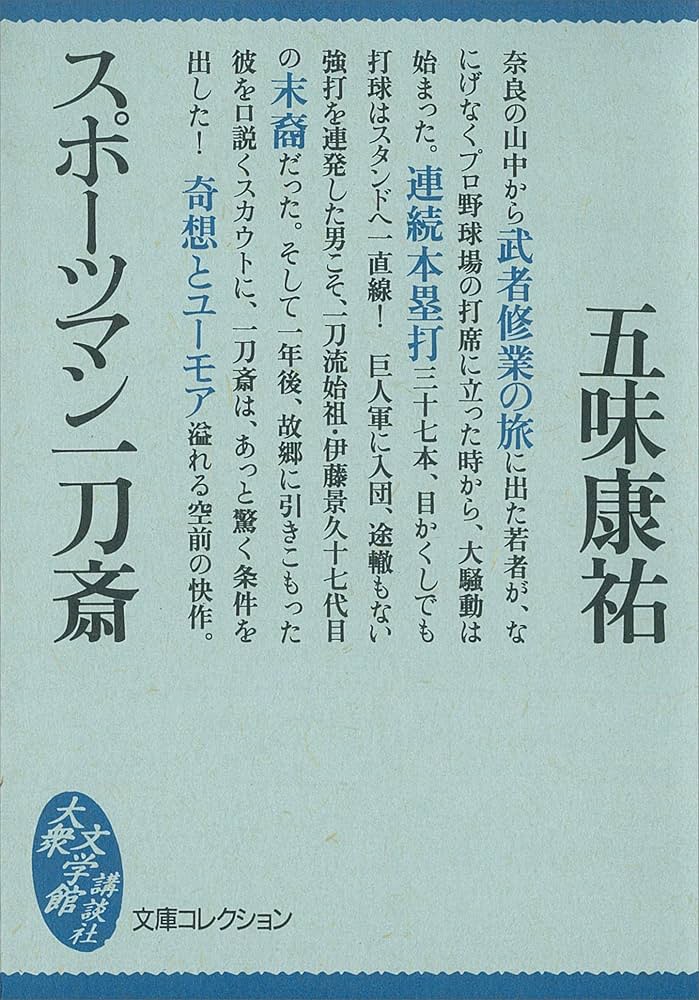
五味康祐の作品の中でも、ひときわ異彩を放つユニークな一冊が『スポーツマン一刀斎』です。本作は、戦国時代の剣豪・伊藤一刀斎を、なんと現代的なスポーツマンシップを持った人物として描くという奇抜なアイデアに基づいています。
作中の一刀斎は、正々堂々とした勝負を好み、卑怯な手を嫌う、まさにスポーツマン。彼の剣の修行や他流試合は、さながらスポーツの試合のように爽やかに描かれます。この斬新な設定により、従来の剣豪小説の重厚なイメージが覆され、全く新しいエンターテインメントが生まれています。
時代小説の枠にとらわれない五味康祐の自由な発想力が光る快作です。シリアスな剣豪小説とは一味違った、明るく痛快な物語を読みたい方におすすめです。



剣豪がスポーツマンだなんて、すごく面白い発想だね!どんなお話なのか、すごく気になるよ!
10位『一刀斎忠臣蔵異聞』
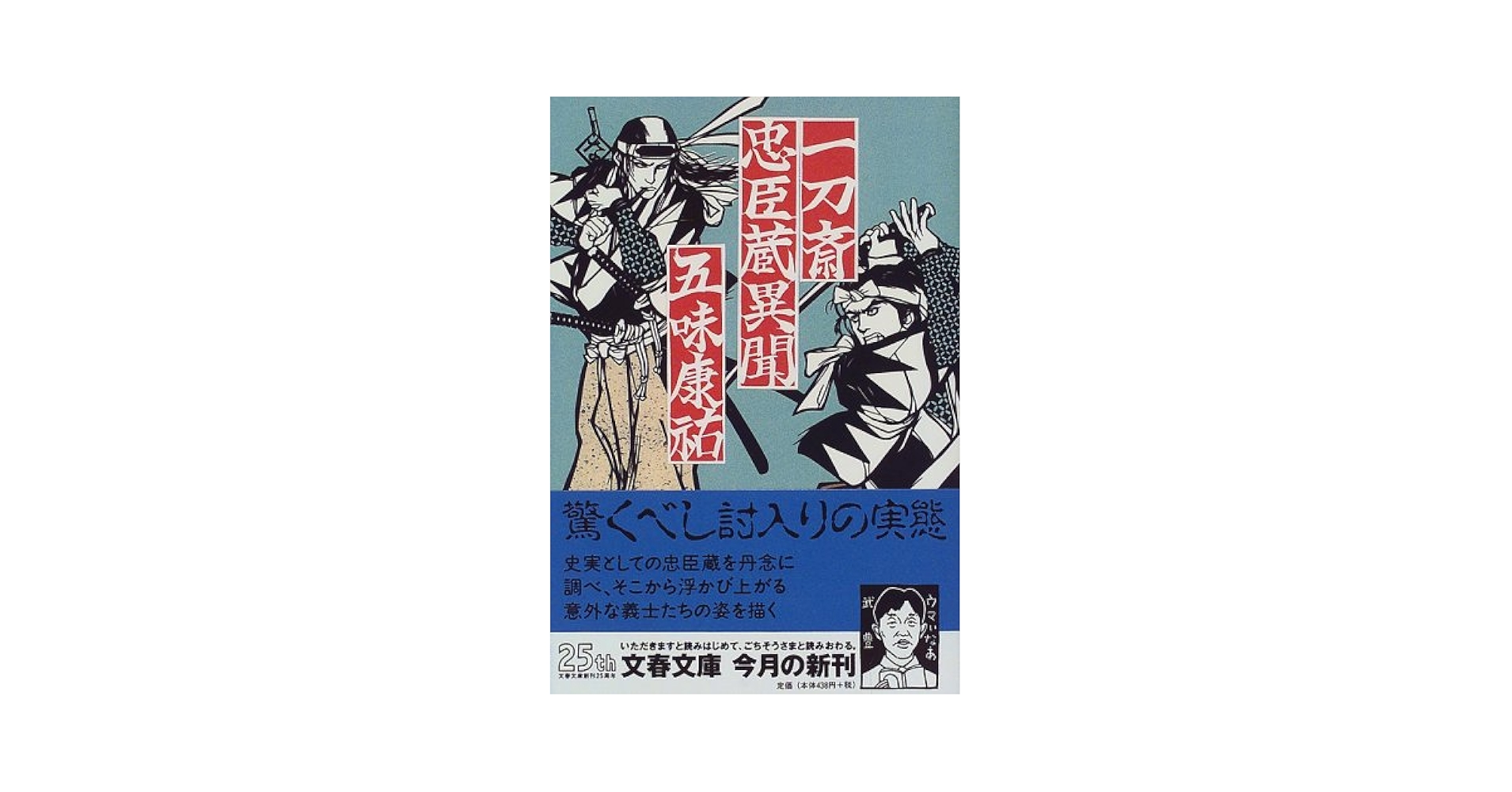
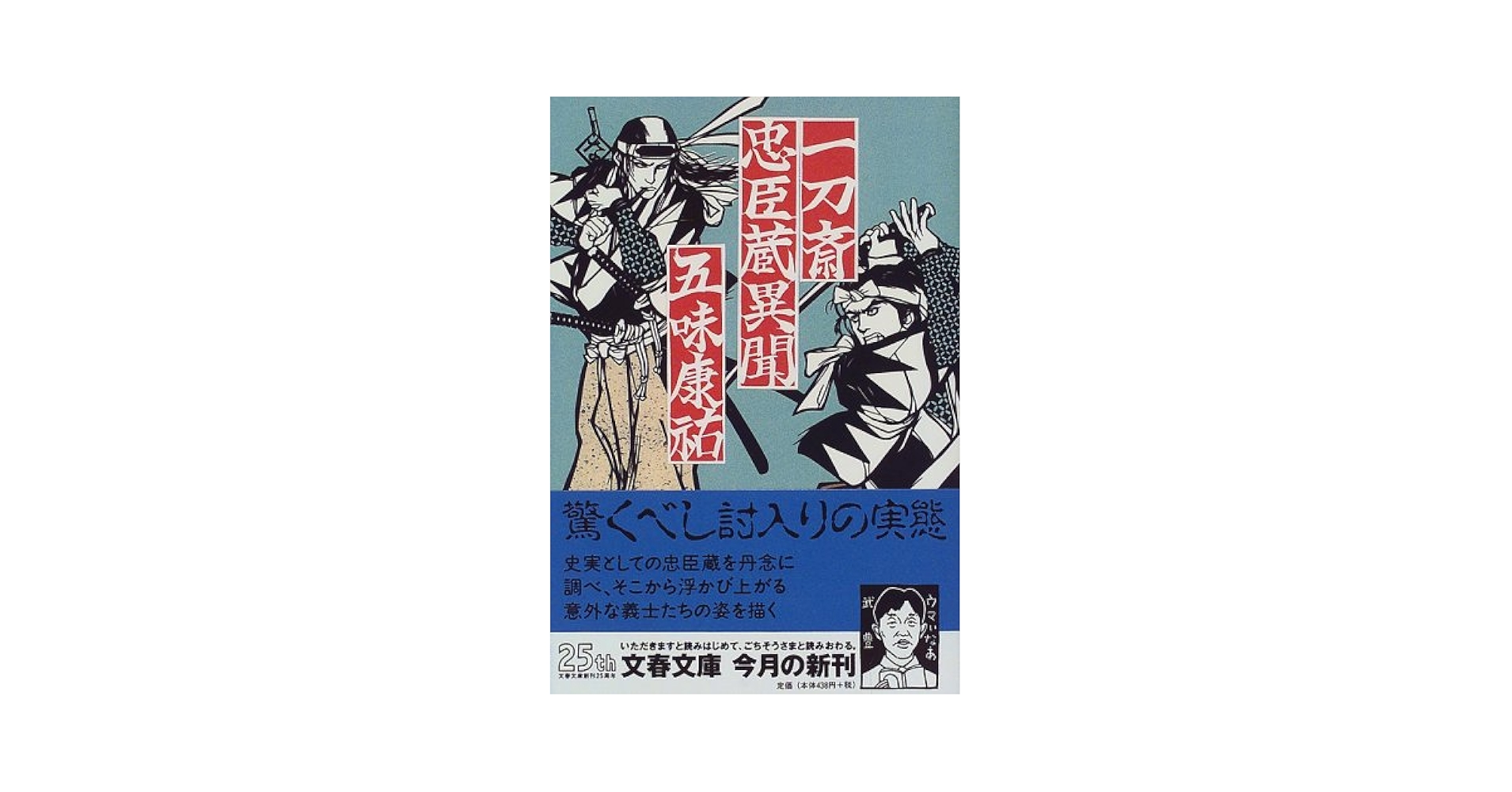
日本人なら誰もが知る「忠臣蔵」の物語を、剣豪・伊藤一刀斎の視点から描くという大胆な構想の作品です。史実や講談で語られる忠臣蔵の物語に、もしも一刀斎が関わっていたら…というIFの世界が繰り広げられます。
本作では、赤穂浪士の討ち入り事件の裏で、一刀斎がどのように動いていたのかが、五味康祐ならではの想像力で描かれています。お馴染みの登場人物たちが、一刀斎という異分子と絡むことで、新たな魅力を放ち始めます。歴史の「もしも」を楽しむ、伝奇小説の醍醐味が詰まった一冊です。
誰もが知る物語に新たな光を当てることで、全く違う面白さを引き出すことに成功しています。忠臣蔵ファンも、そうでない方も、新鮮な驚きを持って楽しめる作品です。



あの有名な忠臣蔵に一刀斎が出てくるなんて!歴史のifを考えるのって、すごくワクワクするよね。
11位『柳生天狗党』
『柳生天狗党』は、柳生一族の物語に、天狗や忍術といった伝奇的な要素をふんだんに盛り込んだエンターテインメント性の高い作品です。史実とフィクションが巧みに融合し、読者を奇想天外な世界へと誘います。
物語は、柳生十兵衛が謎の天狗集団と対決するところから始まります。次々と現れる強敵、繰り広げられる奇想天外な術の応酬など、ページをめくる手が止まらなくなるような冒険活劇の面白さに満ちています。シリアスな剣豪小説とはまた違った、五味康祐のサービス精神旺盛な一面が垣間見える作品です。
難しいことを考えずに、純粋に物語の世界に没頭したいときにおすすめの一冊。柳生十兵衛が繰り広げる、荒唐無稽で痛快な大冒険をお楽しみください。



柳生と天狗が戦うなんて、少年マンガみたいで楽しそう!こういう派手なアクション、大好きだよ。
12位『柳生石舟齋』
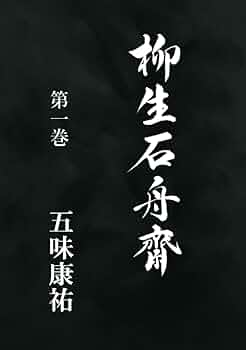
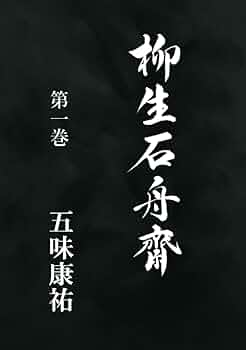
柳生新陰流の創始者であり、柳生一族の礎を築いた偉大な剣豪、柳生石舟斎宗厳(むねよし)。本作は、その石舟斎の生涯を描いた、重厚な歴史小説です。
若き日の武者修行から、上泉信綱との出会いを経て新陰流を継承し、やがて「無刀取り」の極意を掴むに至るまで。一人の剣士が、いかにして伝説的な存在へと至ったのかが、丹念に描かれています。剣の道をひたすらに歩み続けた男の、求道的な生き様が胸を打ちます。
宗矩や十兵衛といった華やかな子孫たちの物語とは対照的に、静かで深い感動が味わえる作品です。柳生一族の物語の原点を知る上で、欠かすことのできない一冊と言えるでしょう。



すべての始まりの人のお話なんだね。伝説が生まれる瞬間をのぞき見してるみたいで、ドキドキするよ。
13位『陽気な殿様』
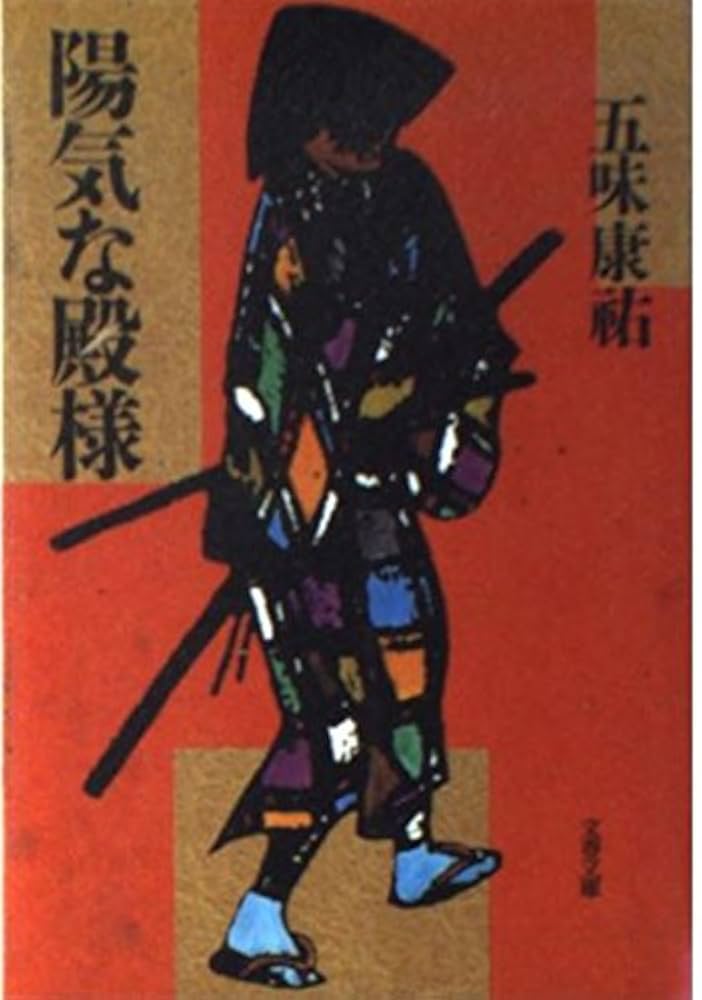
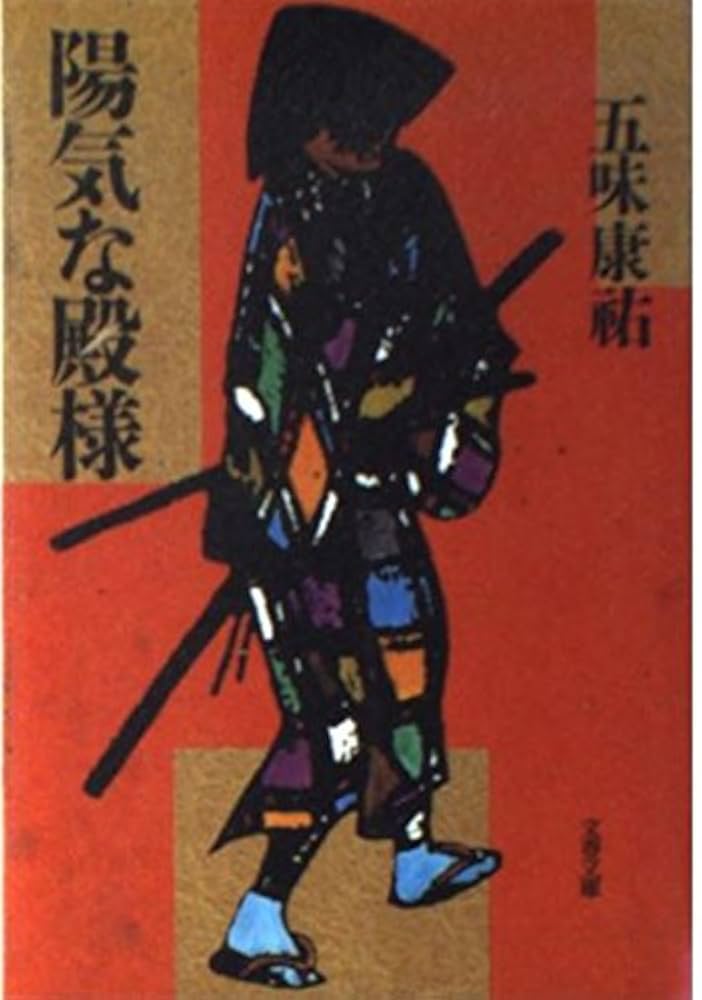
五味康祐の作品は剣豪小説だけではありません。『陽気な殿様』は、そのタイトル通り、明るくユーモラスな作風が魅力の時代小説です。剣豪たちのシリアスな世界とは打って変わって、江戸の町を舞台にした人情味あふれる物語が楽しめます。
主人公は、お人好しでどこか憎めない殿様。彼が巻き起こす騒動の数々が、軽快なテンポで描かれます。五味康祐の持つ、人間に対する温かい眼差しが感じられる作品で、読後にはほっこりとした気持ちになることでしょう。
剣豪小説のイメージが強い五味康祐ですが、こうした肩の力を抜いて楽しめる作品も執筆しています。彼の新たな一面を発見できる、隠れた名作です。



剣豪小説だけじゃなくて、こんなに楽しそうな話も書くんだね!読んでて笑顔になれそうだよ。
14位『いろ暦四十八手』
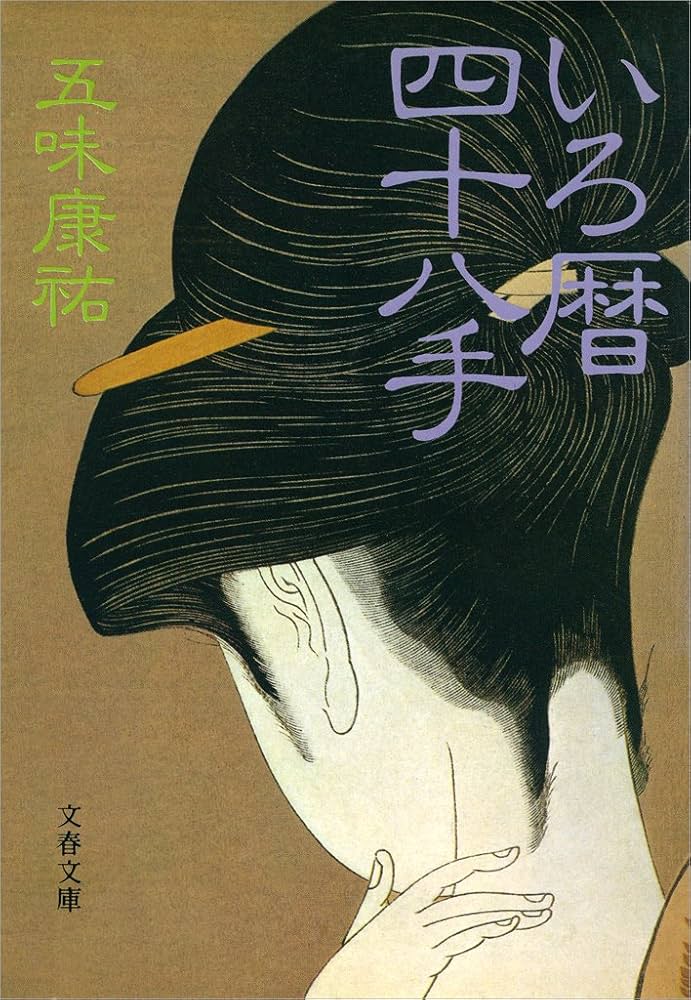
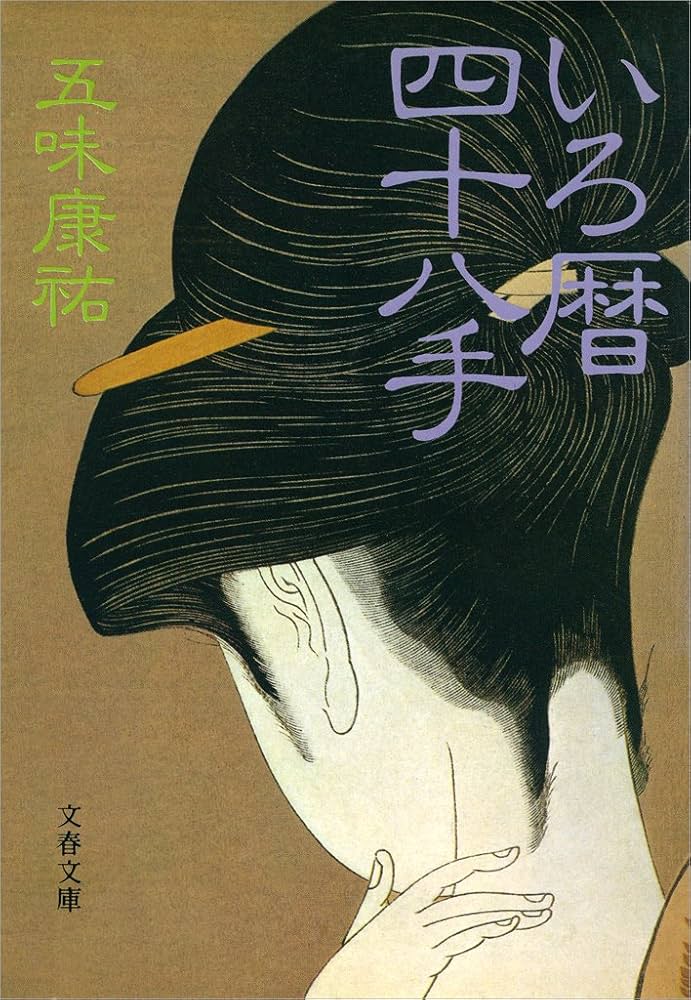
『いろ暦四十八手』は、男女の恋愛模様や色恋沙汰をテーマにした、少し大人向けの作品です。剣豪小説で知られる五味康祐ですが、人間の業や性を描くことにも長けていました。
本作では、様々な男女が登場し、それぞれの愛の形が描かれます。そこには、美しい恋愛だけでなく、嫉妬や裏切り、欲望といった人間の生々しい感情も渦巻いています。人間の持つ多面性や複雑さを、巧みな筆致で描き出しているのが特徴です。
剣豪小説とはまた違った、人間の深淵を覗き込むような面白さがある一冊。五味康祐の作家としての幅広さを感じさせてくれる作品です。



恋愛の話も書くんだね。人間のドロドロした部分も描いているみたいで、ちょっと興味深いかも。
15位『無明斬り』
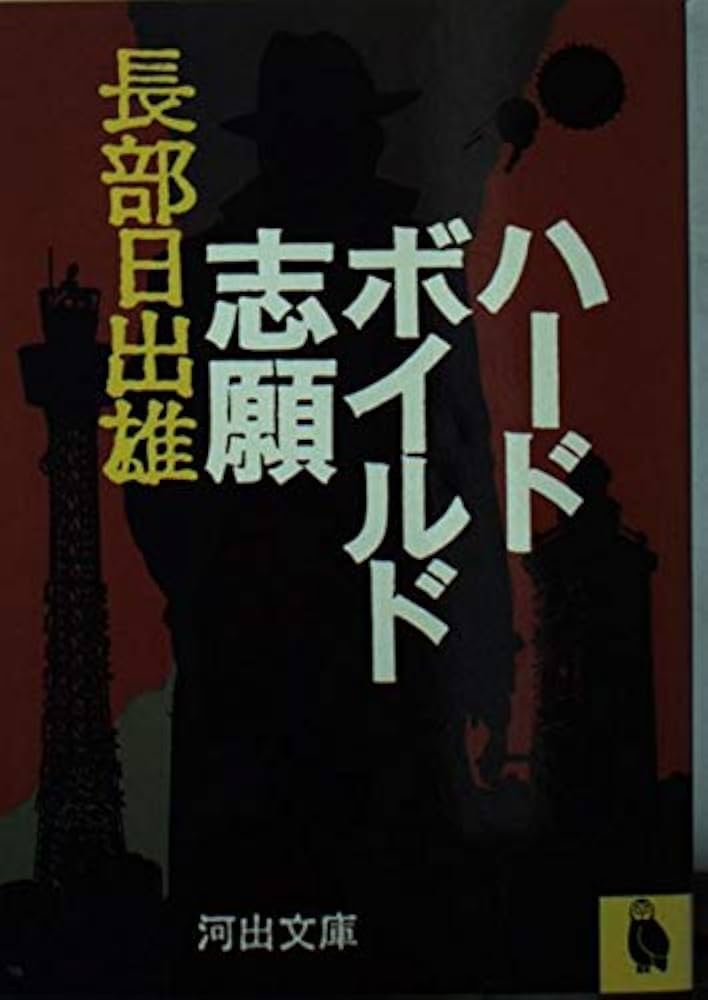
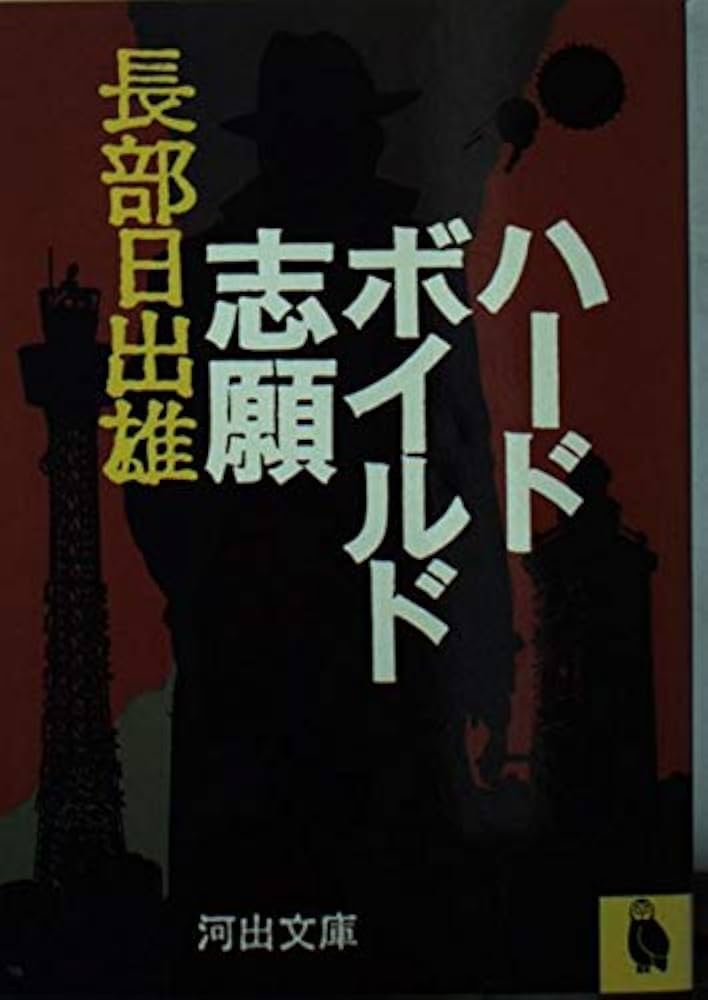
『無明斬り』は、虚無感を抱えた剣士を主人公にした、ダークで哲学的な雰囲気が漂う作品です。強さを求め、敵を斬り続ける中で、主人公は次第に生きる意味を見失っていきます。
本作の魅力は、剣の強さの先にある虚しさを描いている点にあります。華々しい活躍を見せるヒーローではなく、苦悩し、彷徨う剣士の姿は、読者に深い問いを投げかけます。五味康祐の描く剣豪が、単なる強いだけの存在ではないことがよくわかる一冊です。
明るい活劇とは対極にある、人間の内面に深く切り込んだ物語。読後、ずっしりとした余韻が残る、通好みの名作と言えるでしょう。



本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。
16位『刺客』
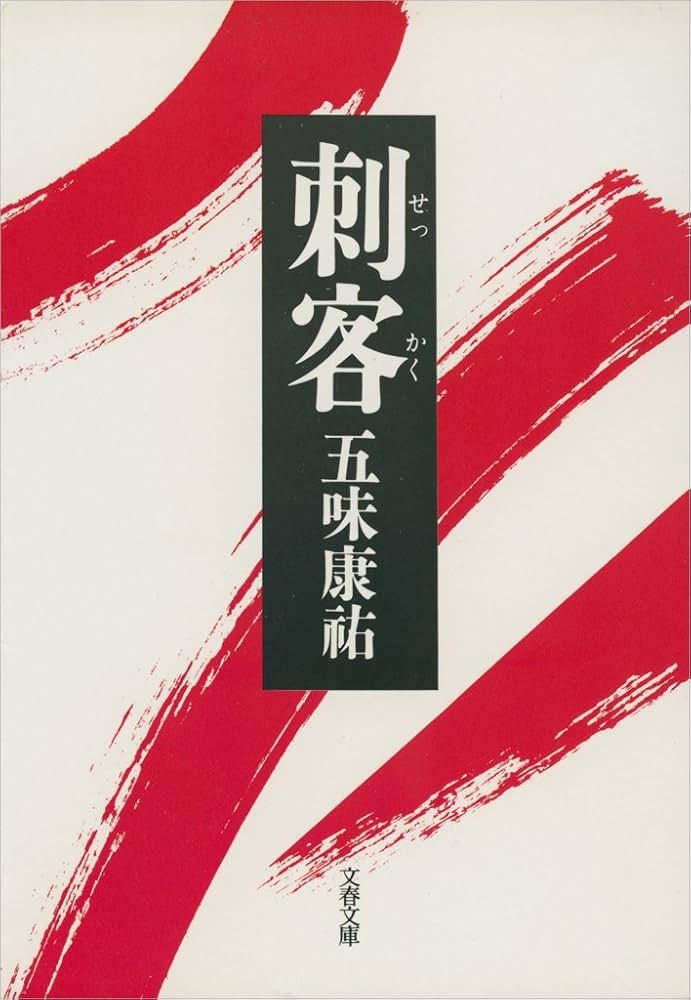
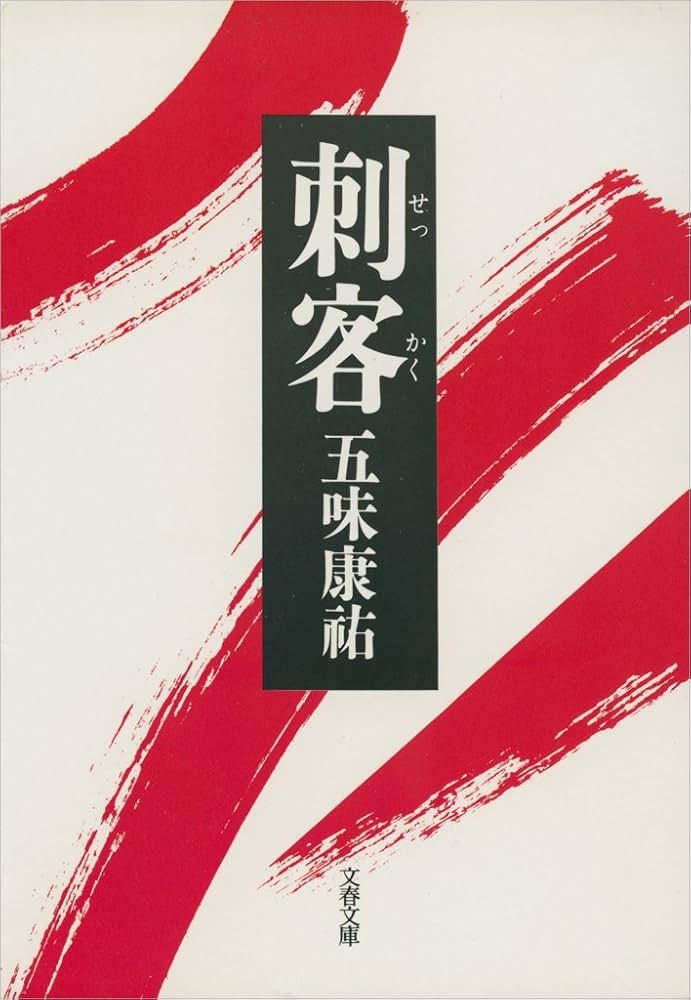
『刺客』は、暗殺を請け負うプロフェッショナル、すなわち刺客の非情な世界を描いた作品です。主人公は、ただ命令のままに人を斬ることを宿命づけられた男。彼の目を通して、裏社会の掟や、命のやり取りの緊張感がリアルに描かれます。
本作は、華やかな剣豪の世界とは異なる、暗く、乾いた世界観が特徴です。主人公に感情移入することは難しいかもしれませんが、その徹底したプロフェッショナリズムや、時折見せる人間的な葛藤には、不思議な魅力を感じさせられます。
五味康祐の作品の中でも、特にハードボイルドな雰囲気が強い一冊。甘さのない、厳しい男の世界を描いた物語が好きな方におすすめです。



本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。
17位『剣には花を』
剣の道に生きる男たちの、不器用ながらも純粋な恋愛模様を描いた作品です。タイトルが示す通り、殺伐とした剣の世界に、恋愛という「花」を添えることで、物語に彩りと深みを与えています。
登場する剣士たちは、普段は強さを追い求める厳しい表情を見せていますが、愛する女性の前では、また違った一面を覗かせます。そのギャップが、キャラクターの人間的な魅力を引き立てています。剣の勝負と恋の行方が絡み合い、読者を最後まで飽きさせません。
手に汗握る剣戟だけでなく、ロマンチックな展開も楽しみたいという方におすすめの一冊。剣豪たちの意外な一面に、きっと心をときめかせることでしょう。



剣豪の恋物語なんて、なんだか切なくてキュンとしちゃうね。わたし、こういうのに弱くて…。
まとめ
ここまで、五味康祐のおすすめ小説をランキング形式でご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。剣豪小説の第一人者として知られる五味康祐ですが、その作品世界は非常に多彩です。
王道の剣豪小説である『柳生武芸帳』から、ユニークな設定が光る『スポーツマン一刀斎』、そして人間ドラマが胸を打つ『薄桜記』まで、様々な魅力を持った作品があります。どの作品にも共通しているのは、人間の本質を鋭く見つめる作者の眼差しです。
このランキングを参考に、ぜひ気になった一冊を手に取ってみてください。きっとあなたを夢中にさせる、五味康祐の世界が待っています。



