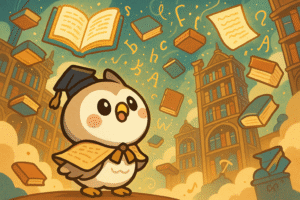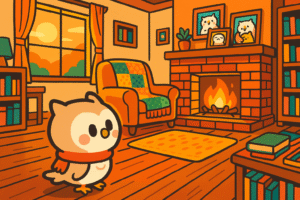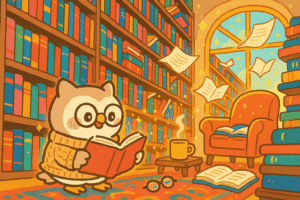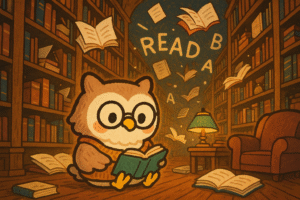あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】重松清のおすすめ小説人気ランキングTOP40

はじめに:心に寄り添う物語を求めるあなたへ、重松清の小説案内
「なんだか心が疲れてしまった」「誰かの優しい物語に触れたい」そんな風に感じたとき、多くの人が手に取るのが重松清さんの小説です。彼の作品は、私たちの日常に潜む喜びや悲しみ、そして家族の絆や友情といった普遍的なテーマを、温かくも鋭い視点で描き出しています。
重松さんの魅力は、なんといっても登場人物の細やかな心理描写にあります。 小学生から定年を迎えた大人まで、様々な年代の主人公たちが抱える葛藤や悩みがリアルに描かれているため、読者はまるで自分のことのように物語に没入し、共感の涙を流すことも少なくありません。 生きていく中で誰もが直面するような辛い現実から、登場人物たちがどうやって希望を見出していくのか、その姿に私たちは勇気づけられます。
この記事では、そんな重松清さんの数ある名作の中から、特におすすめの作品をランキング形式でご紹介します。どの作品も、あなたの心にそっと寄り添い、明日への一歩を踏み出す力をくれるはずです。ぜひ、気になる一冊を見つけてみてください。
【2025年最新】重松清のおすすめ小説人気ランキングTOP40
ここからは、いよいよ重松清さんのおすすめ小説をランキング形式で発表します。このランキングは、インターネット上のレビューデータや各種メディアでの紹介などを基に、特に人気と評価の高い作品を選出しました。
ドラマ化や映画化された有名な作品から、知る人ぞ知る隠れた名作まで幅広くランクインしています。 家族の愛に泣ける物語、思春期のヒリヒリとした感情を描いた青春小説、そしていじめや社会問題に鋭く切り込んだ作品など、多彩なラインナップとなりました。 あなたの心に響く一冊が、きっとこの中に見つかるはずです。
1位『流星ワゴン』
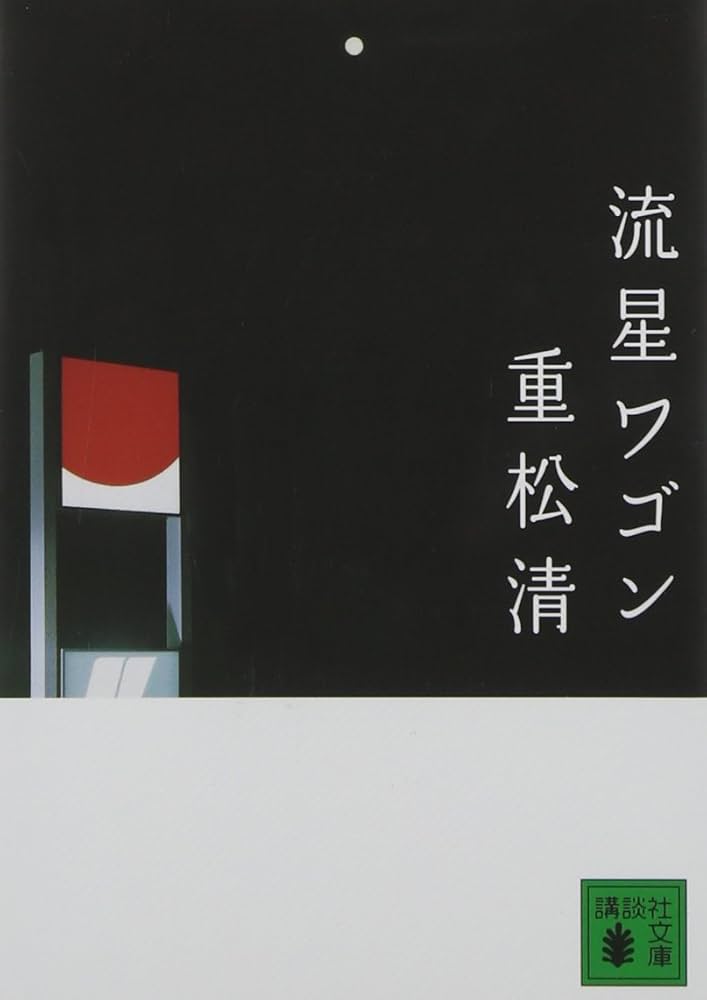
堂々の1位に輝いたのは、多くの読者の涙を誘った不朽の名作『流星ワゴン』です。人生に絶望した38歳の主人公・永田一雄が、突然現れた不思議なワゴンに乗り込み、過去の自分や家族に出会う旅をする物語です。
この作品の魅力は、ファンタジックな設定の中に、「家族の再生」や「後悔との向き合い方」という普遍的なテーマが描かれている点にあります。 破綻してしまった父との関係や、うまくいかない夫婦仲、そして息子の家庭内暴力。過去を旅する中で、一雄はこれまで知らなかった家族の想いに触れ、少しずつ現実と向き合う力を取り戻していきます。
ドラマ化もされ、大きな話題を呼びました。 生きているうちにやり直したいことがある、すべての人に読んでほしい感動の物語です。
 ふくちい
ふくちい家族っていいなって素直に思える話だよ。わたしも過去に戻ってやり直したいことがあるかも…。
2位『とんび』
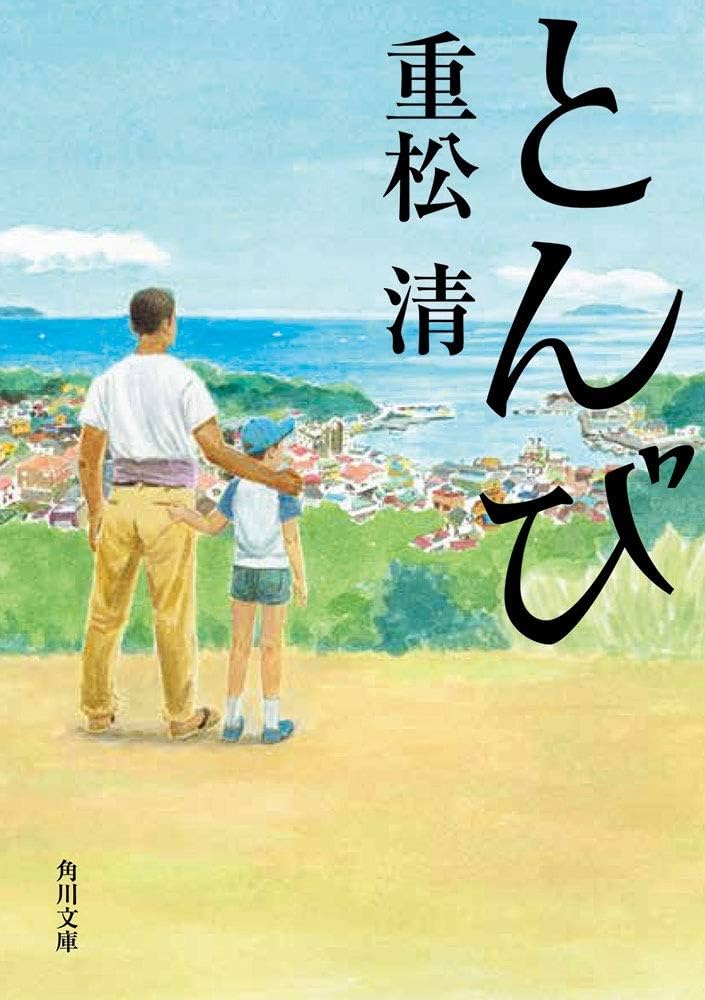
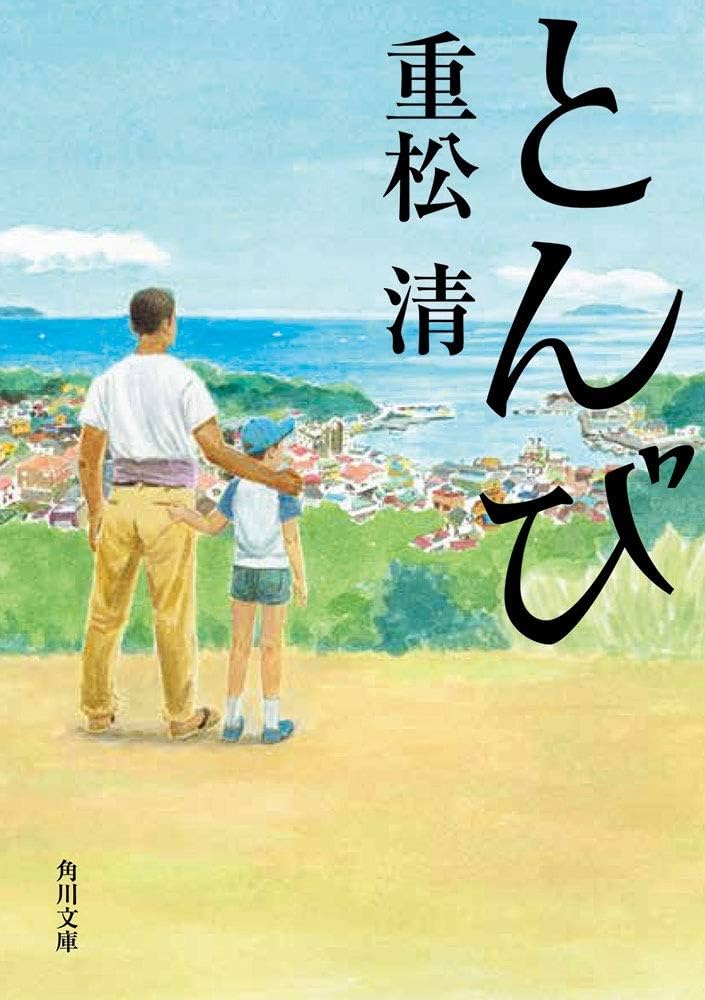
2位は、不器用な父親の愛情を描き、何度も映像化された名作『とんび』です。 物語の舞台は、瀬戸内海に面した小さな町。妻を事故で亡くしたヤスさんが、町の人々の助けを借りながら、一人息子の旭(アキラ)を無骨ながらも深い愛情で育てていく姿を描いています。
学歴もなければ、気の利いたことも言えないヤスさん。しかし、息子の幸せを願う気持ちは誰にも負けません。そんな父と子の絆、そして彼らを取り巻く町の人々の温かさが、涙と笑いと共に描かれています。
時代は昭和。どこか懐かしい風景の中で繰り広げられる物語は、親子の愛とは何か、そして「家族」とは何かを私たちに問いかけます。読み終えた後、自分の親や大切な人に会いたくなる、そんな心温まる一冊です。



不器用な愛情表現にグッときちゃう!ヤスさんみたいな父親、とっても素敵だよね。
3位『きみの友だち』


3位にランクインしたのは、友情の本質を問いかける感動作『きみの友だち』です。足が不自由なことから、クラスでどこか壁を作っていた恵美と、病気がちで休みがちな転校生の由香。二人の少女の出会いと友情を軸に、様々な子どもたちの「友だち」との関係性を描いた連作短編集です。
「みんなと仲良く」という言葉の裏で、知らず知らずのうちに誰かを傷つけたり、孤独を感じたりした経験はありませんか。この物語は、「本当の友だちって、たった一人いればいいのかもしれない」という、優しくも力強いメッセージを伝えてくれます。
映画化もされ、多くの若者の共感を呼びました。 友だち関係に悩んだことのあるすべての人に、そっと寄り添ってくれるような物語です。



本当の友だちってなんだろうって考えさせられるよ。心にじんわりと温かいものが広がる物語なんだ。
4位『ビタミンF』
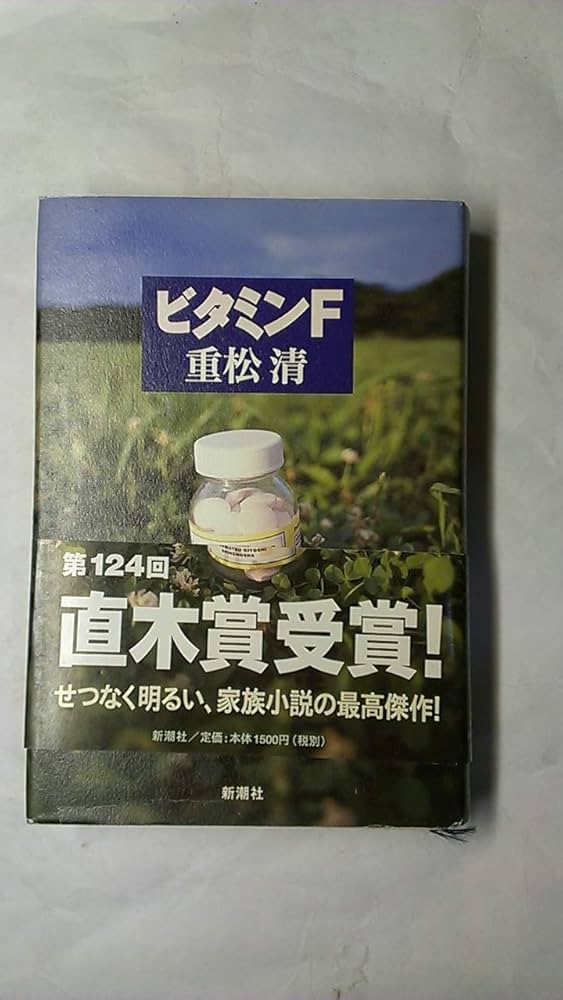
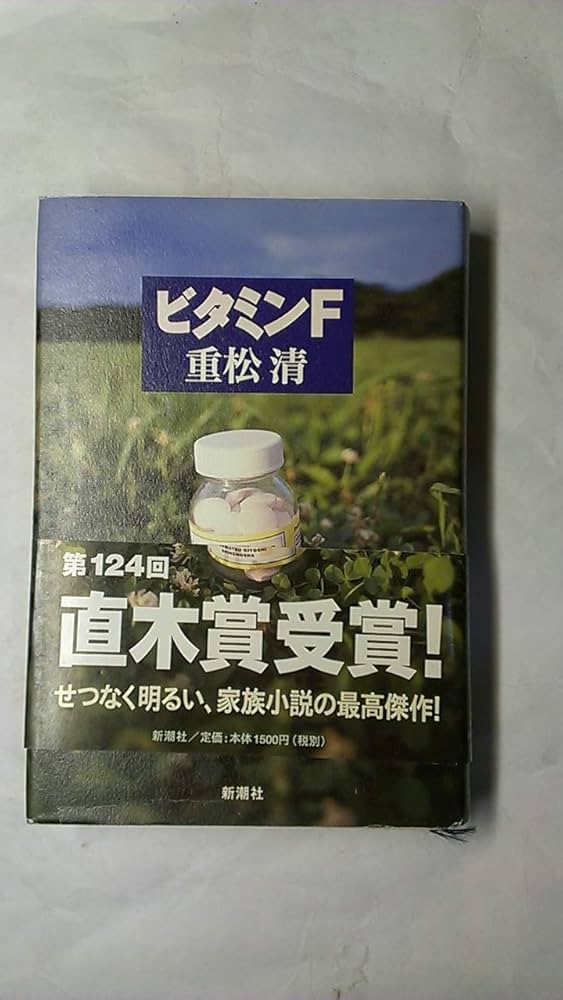
4位は、重松清さんの名を世に知らしめた第124回直木賞受賞作『ビタミンF』です。 家族(Family)や父親(Father)などをテーマにした7つの短編が収録されており、それぞれ異なる立場の「お父さん」たちが主人公です。
リストラ、妻とのすれ違い、反抗期の娘との関係など、中年男性が抱えるリアルな悩みが描かれています。うまくいかないことばかりの毎日の中で、それでも家族のために奮闘する父親たちの姿は、どこか切なく、そして愛おしく感じられます。
「ビタミンF」というタイトルは、作中に出てくる「家族を元気にするビタミン」のこと。この本は、読む人にとって心のサプリメントのような役割を果たしてくれるでしょう。全国のお父さん、そしてその家族に読んでほしい一冊です。



お父さんたちも色々大変なんだなって思ったよ。家族を元気にするビタミン、わたしも欲しいな!
5位『その日のまえに』
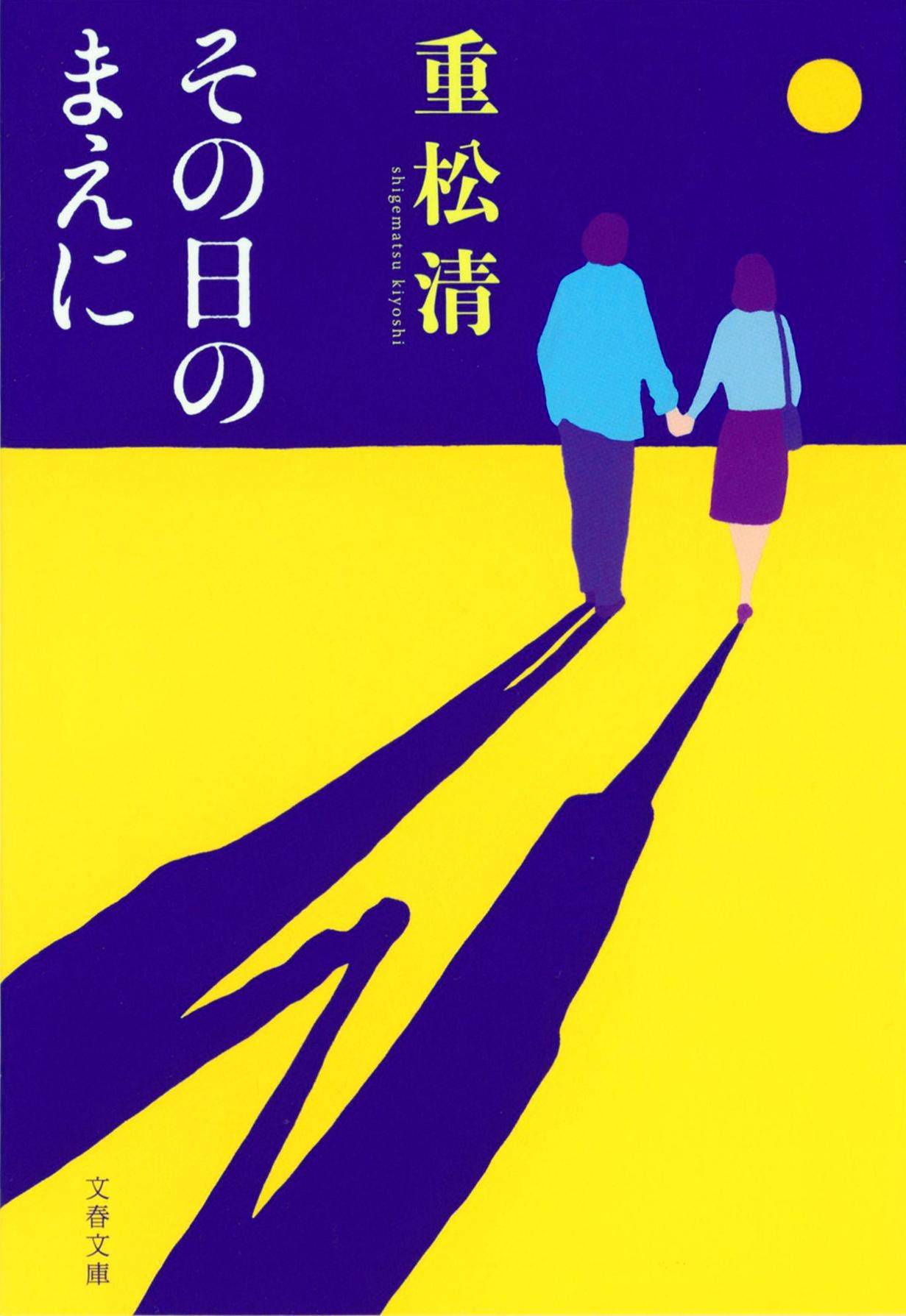
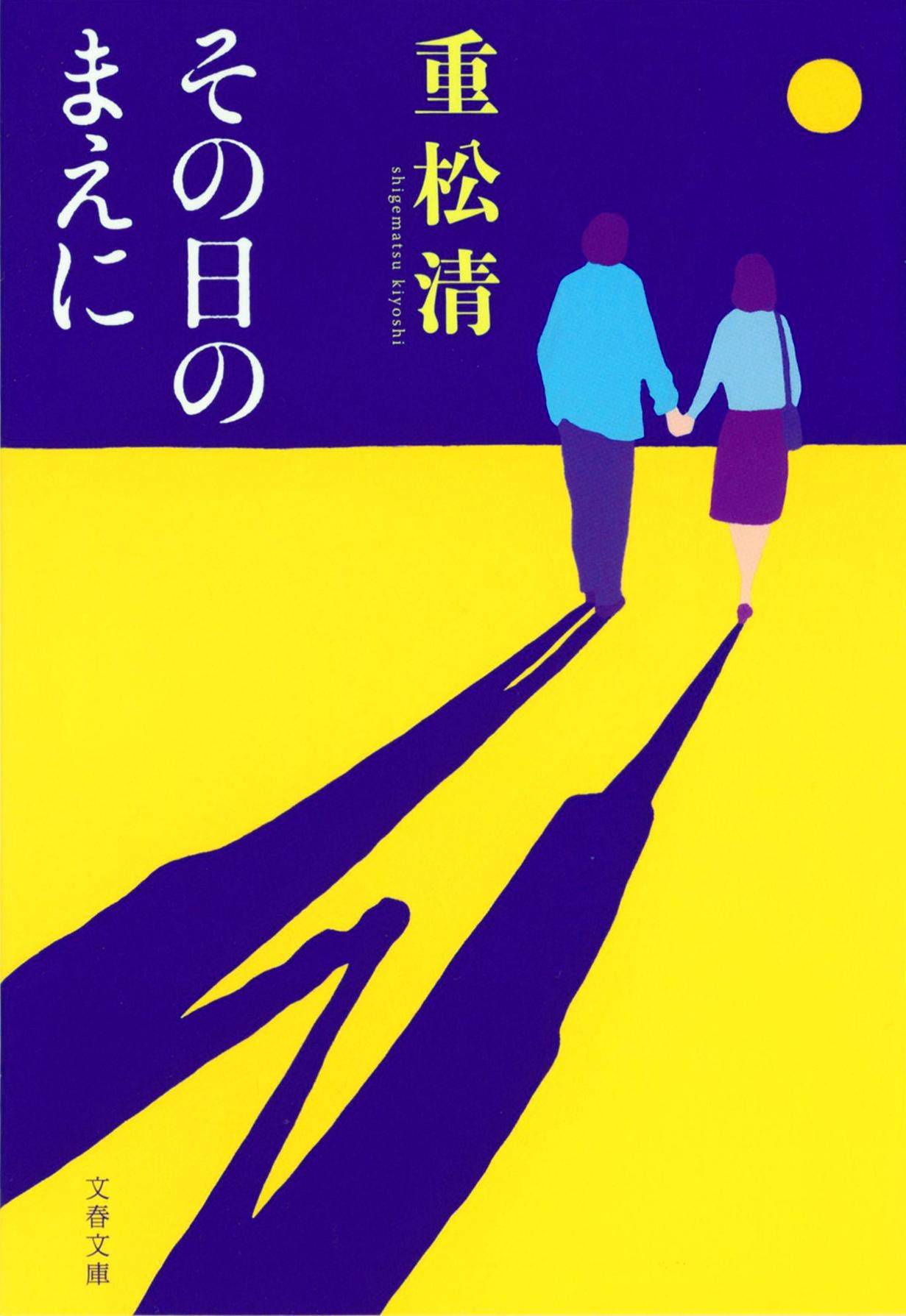
5位は、「死」という重いテーマを扱いながらも、温かい感動を呼ぶ『その日のまえに』です。余命宣告を受けた妻・とし子と、夫・健大、そして二人の息子たちが過ごす最後の日々を、様々な視点から描いた連作短編集です。
この物語は、ただ悲しいだけではありません。残される家族のために、そして自分自身のために、「その日」が来るまでに何をすべきかを考え、懸命に生きる人々の姿が描かれています。愛する人の死とどう向き合い、その後の人生をどう生きていくのか。その問いに対する、優しく切ない答えがここにあります。
映画化もされたこの作品は、命の尊さや家族の絆を改めて感じさせてくれます。 当たり前の日常が、いかにかけがえのないものであるかを教えてくれる、涙なしには読めない一冊です。



大切な人との時間を、もっと大事にしなきゃって思ったよ。涙が止まらなかったんだ…。
6位『きよしこ』
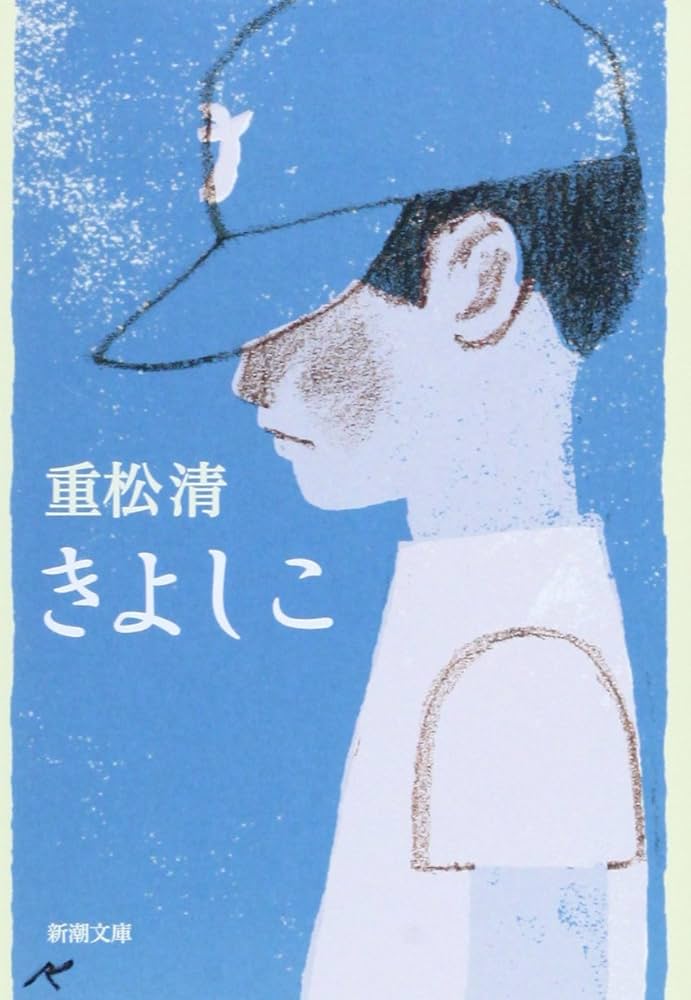
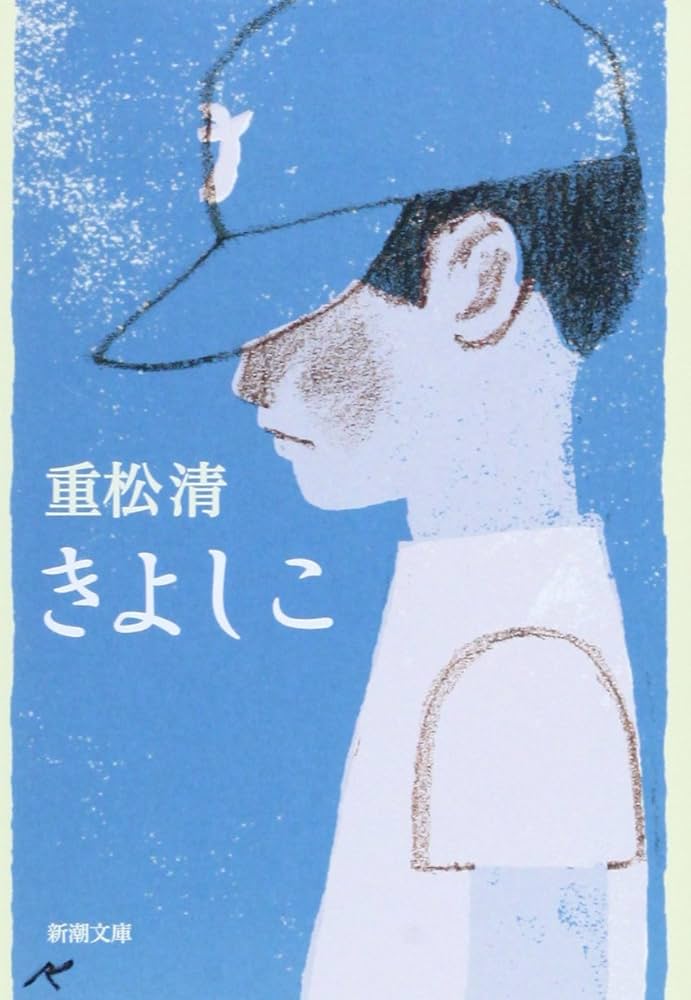
6位には、作者自身の体験が色濃く反映された自伝的小説『きよしこ』がランクインしました。 主人公は、吃音(きつおん)に悩む少年「きよし」。うまく言葉を発することができず、転校を繰り返す中で、孤独やもどかしさを感じながら成長していく姿を描いています。
この作品の魅力は、きよしが心の中に生み出した空想の友だち「きよしこ」の存在です。 うまく話せないきよしの代わりに、きよしこが想いを伝えてくれる。そんな少年時代の繊細な心象風景が、切なくも美しく描かれています。
言いたいことが伝わらない苦しみや、友だち作りの難しさを乗り越え、少しずつ世界と繋がっていくきよしの姿に、胸が熱くなることでしょう。 誰もが経験する成長の痛みに寄り添ってくれる、優しい物語です。



自分だけの友だちがいるって素敵だよね。きよし君の成長に感動しちゃったよ。
7位『ナイフ』
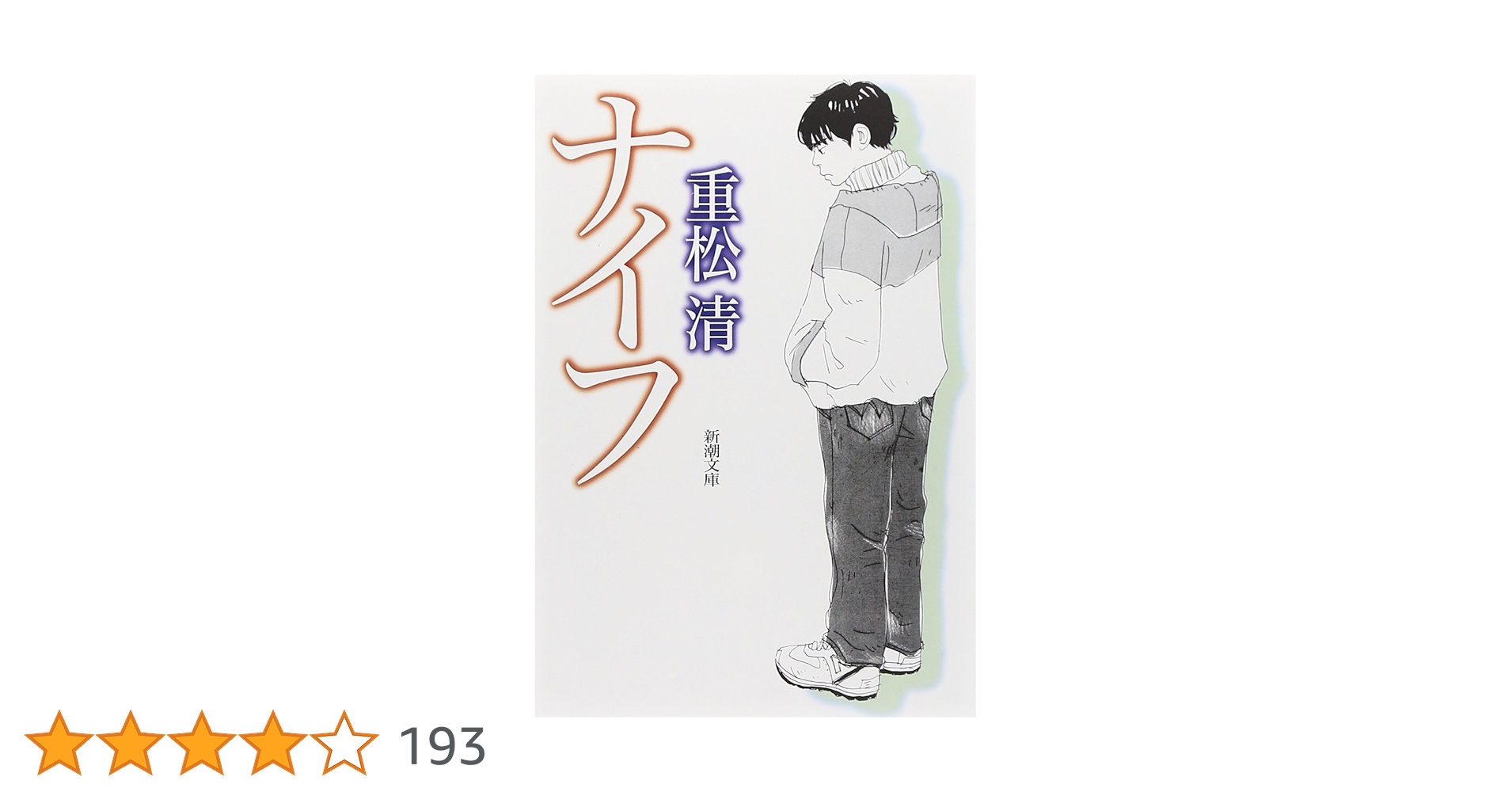
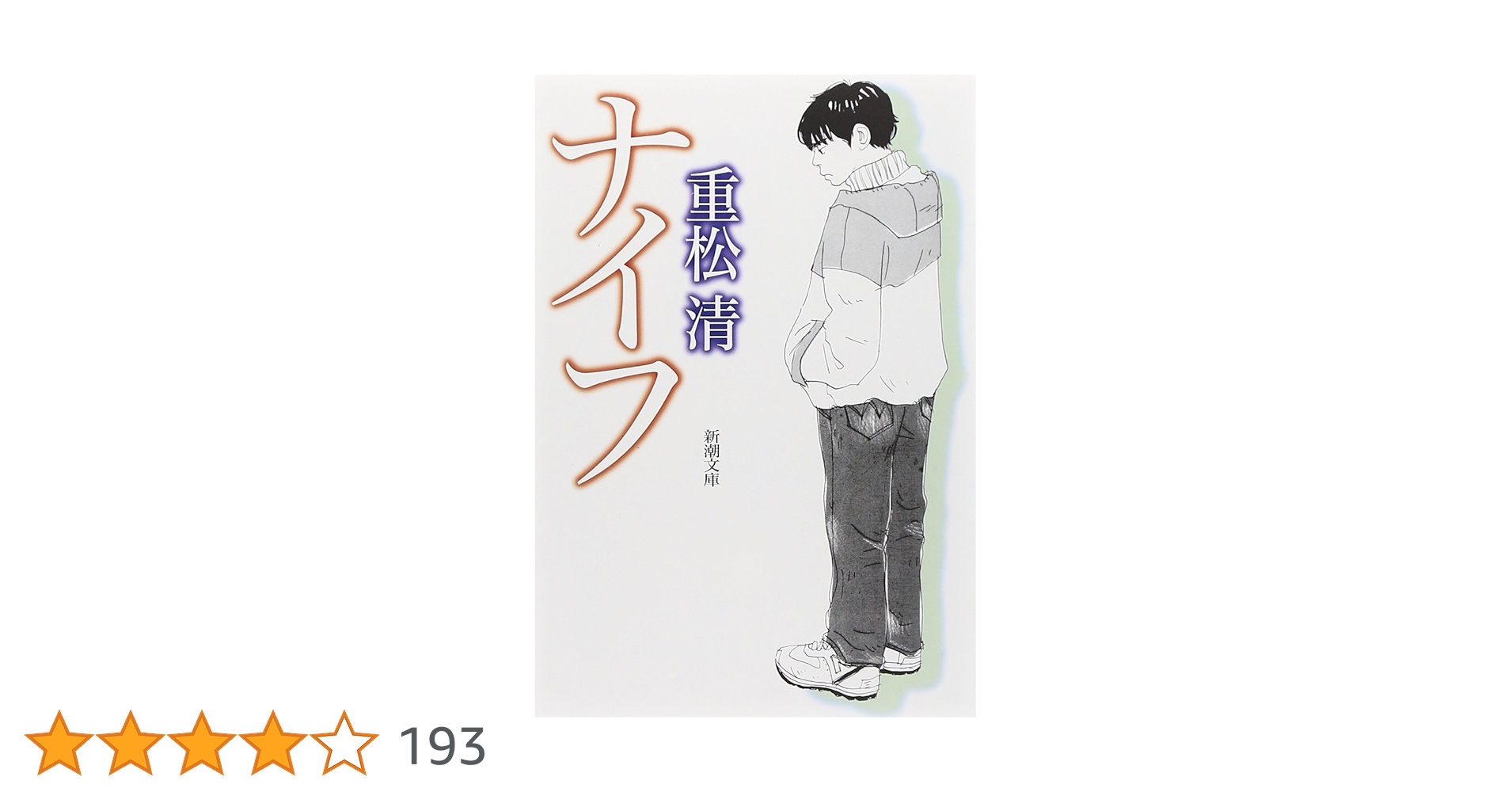
7位は、いじめという深刻なテーマに正面から向き合った短編集『ナイフ』です。この作品で重松さんは坪田譲治文学賞を受賞し、作家としての評価を確固たるものにしました。
収録されている5つの物語は、いじめの被害者だけでなく、加害者や傍観者、そして教師や親といった様々な立場の人々の視点から描かれています。それぞれの葛藤や苦しみがリアルに描写されており、問題の根深さや複雑さを読者に突きつけます。
単に問題を提起するだけでなく、その中で登場人物たちが悩み、傷つきながらも、かすかな光を見出そうとする姿が描かれているのが重松作品ならでは。 教育関係者をはじめ、子どもに関わるすべての人に読んでほしい、社会派な一面も持つ重要な一冊です。



本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。
8位『青い鳥』
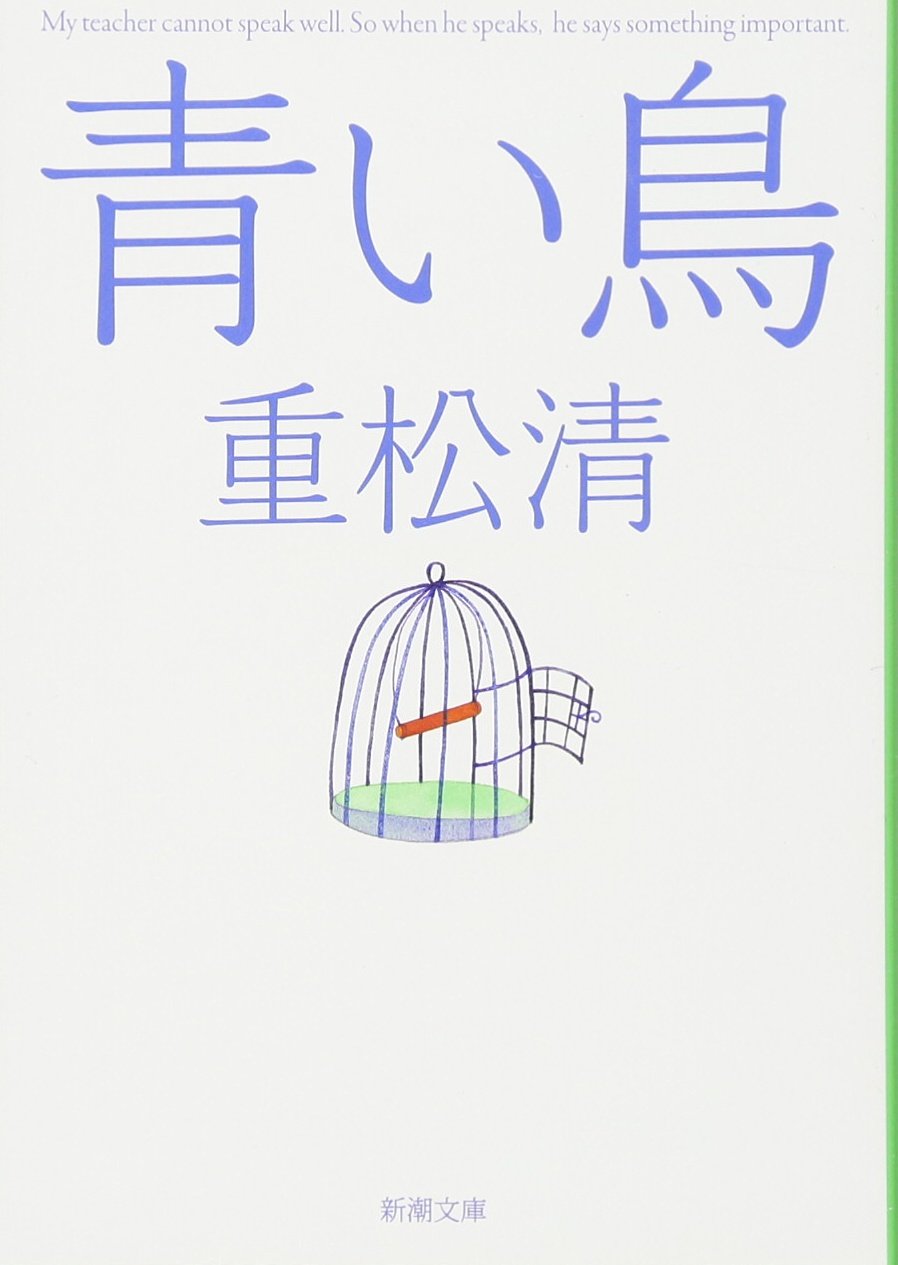
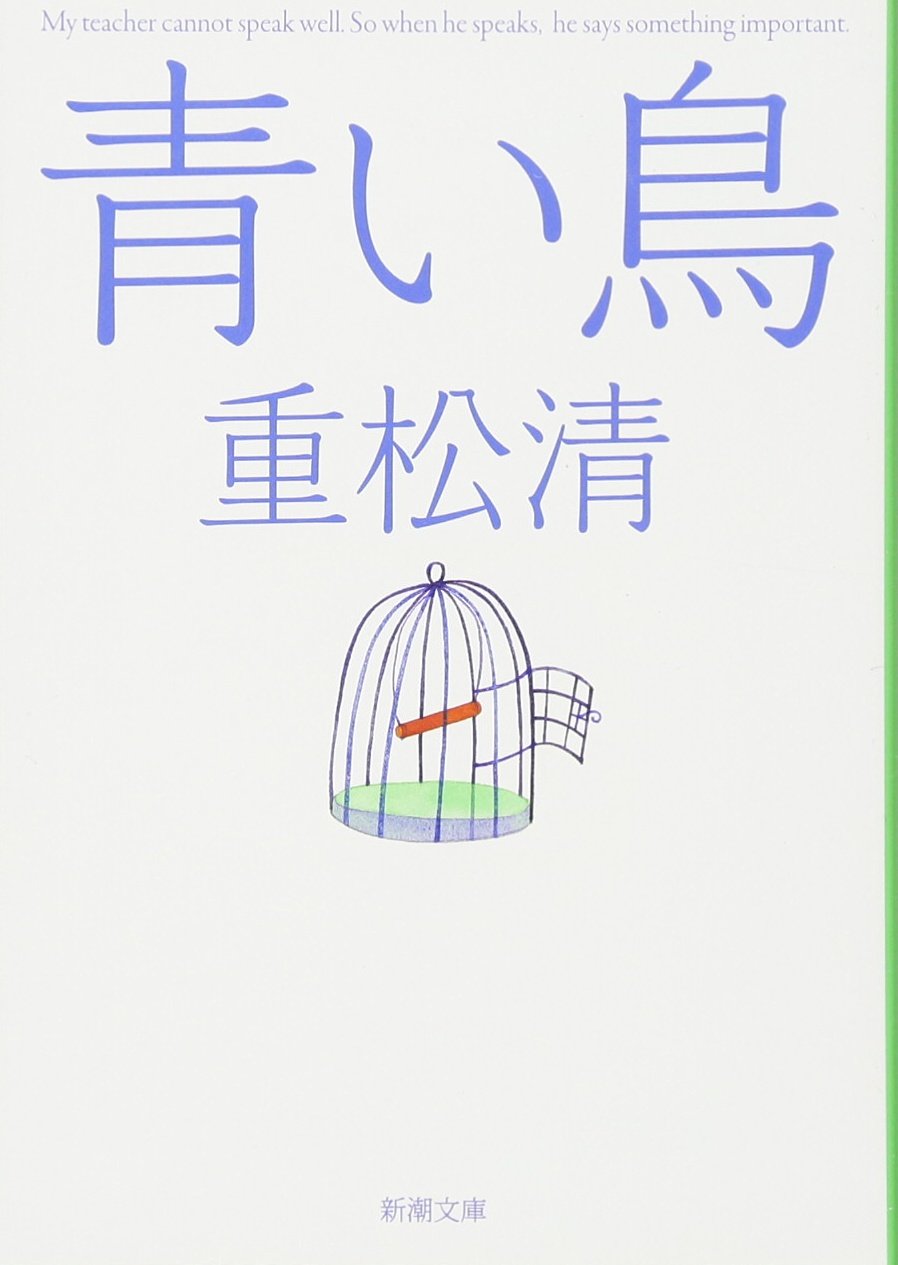
8位にランクインしたのは、心に傷を負った子どもたちと、一人の教師の交流を描いた感動作『青い鳥』です。阿部寛さん主演で映画化もされ、大きな話題となりました。
主人公は、中学校の非常勤講師である村内先生。彼は吃音のため言葉がスムーズに出てきませんが、その分、一つひとつの言葉を大切に、生徒たちの心に届けようとします。 いじめ、親の自殺、虐待など、重い悩みを抱える生徒たちが、村内先生との対話を通じて、少しずつ自分の殻を破っていく姿が描かれています。
うまく話せないからこそ伝わる、真摯な想い。村内先生の言葉は、生徒たちだけでなく、私たちの心にも深く響きます。孤独を感じている人、誰かに寄り添ってほしいと願う人に、希望の光を灯してくれる物語です。



村内先生の言葉がひとつひとつ心に染みるんだ。こんな先生に出会いたかったな。
9位『十字架』
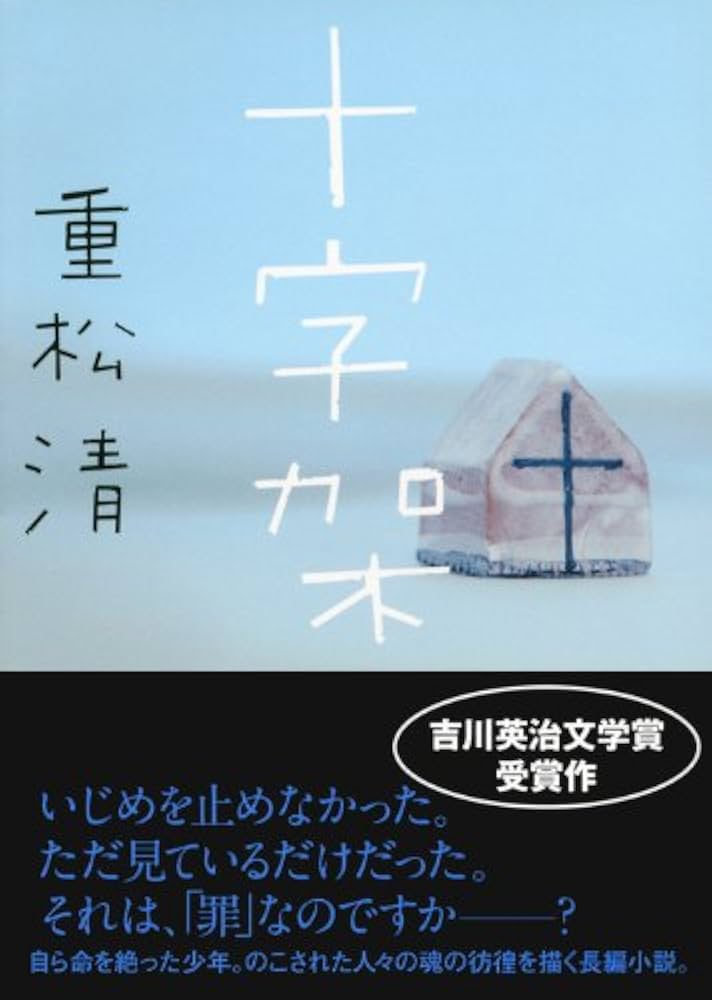
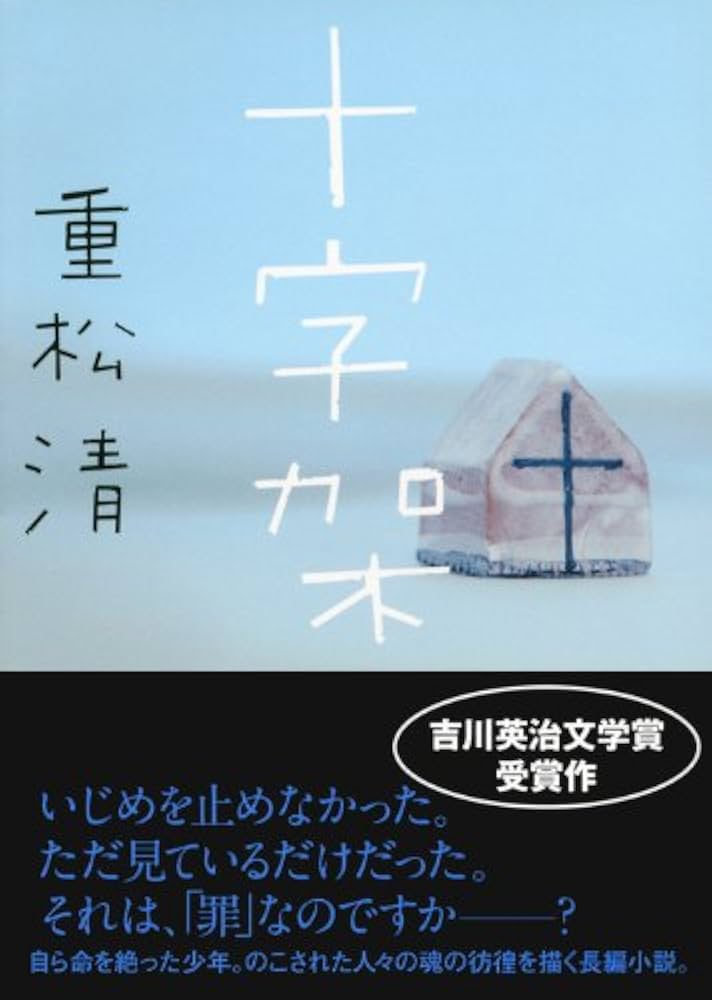
9位は、いじめによる自殺という、さらに重いテーマに踏み込んだ長編小説『十字架』です。この作品で、重松さんは吉川英治文学賞を受賞しました。
「親友になってくれてありがとう」という遺書に名前を書かれた主人公。しかし、彼はいじめていたグループの一員であり、亡くなった同級生を親友だと思ったことは一度もありませんでした。 残された者は、死んだ同級生の「十字架」を背負って生きていくことになります。
罪悪感、後悔、そして世間からの目。いじめがもたらす悲劇は、被害者の死で終わるのではなく、関わった人々の人生を長く深く蝕んでいく。その現実が、痛々しいほどに描かれています。命の重さ、そして「赦し」とは何かを、読者に問いかける衝撃作です。



本作が突きつける「責任」と「赦し」という問いの重さは、読者の心に深く刻印されるだろう。極めて重要な作品である。
10位『エイジ』
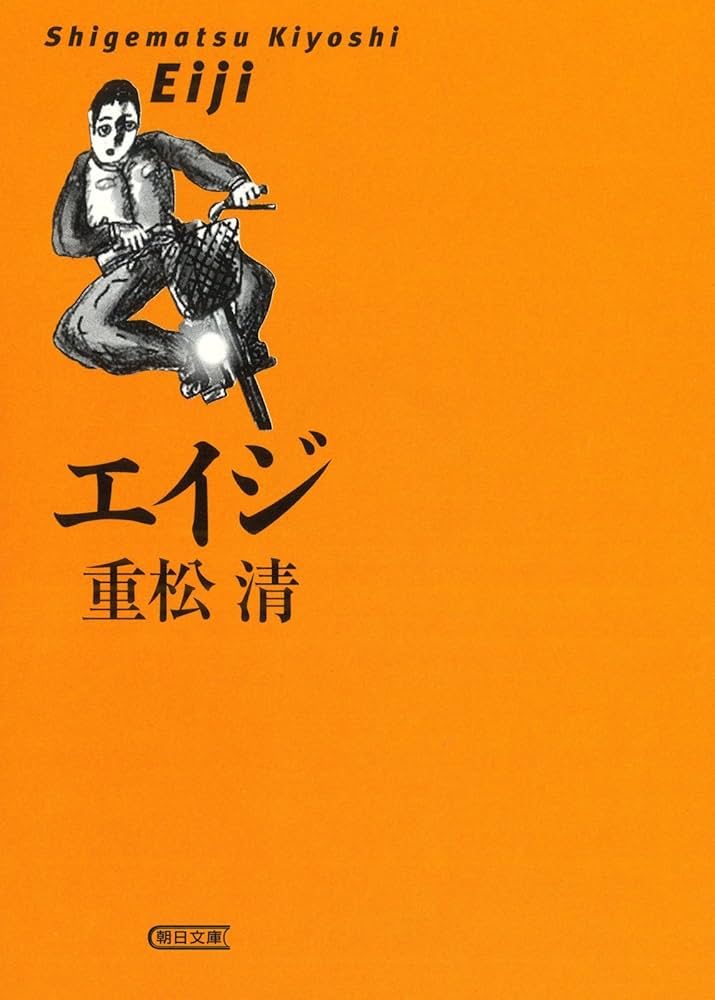
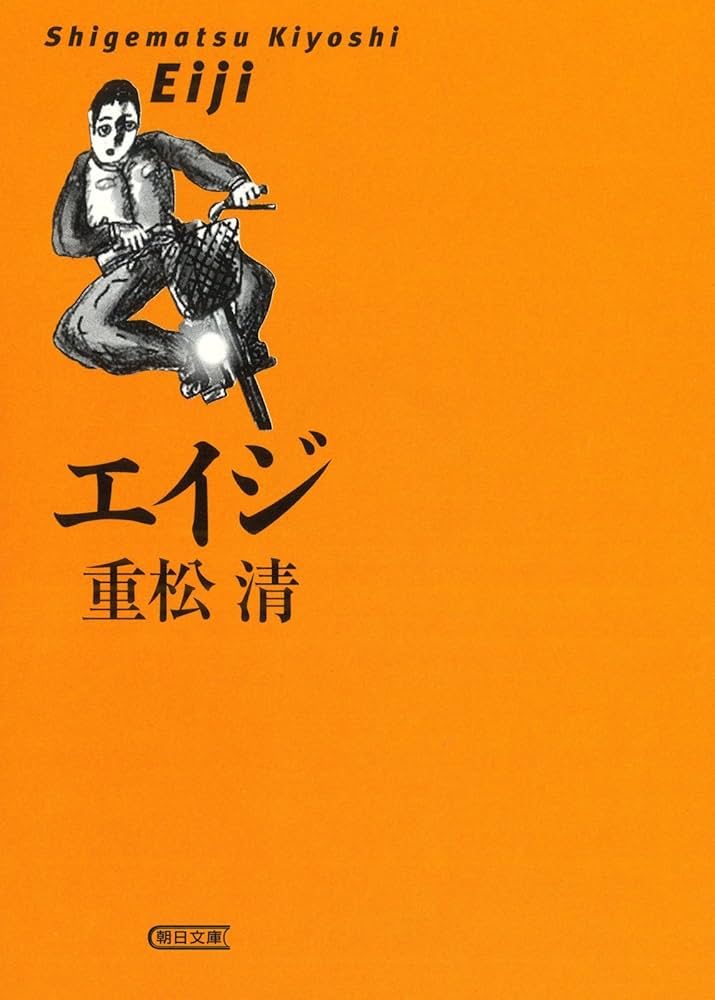
10位は、思春期の少年少女の揺れ動く心をリアルに描いた青春小説の金字塔『エイジ』です。この作品は山本周五郎賞を受賞し、ドラマ化もされました。
物語の主人公は、中学2年生のエイジ。彼が住むニュータウンで連続通り魔事件が発生し、犯人として逮捕されたのは、なんとクラスメイトでした。 この事件をきっかけに、エイジは友人関係や家族、そして自分の中に潜む得体の知れない衝動と向き合うことになります。
大人でもなく、子どもでもない。14歳という危うい年齢の少年少女が抱える焦燥感や孤独、そして性の問題などが、生々しく描かれています。90年代の空気が色濃く反映された本作は、かつて中学生だったすべての大人たちの胸にも突き刺さるでしょう。



思春期特有の無敵な感じと不安が混ざってるよね。なんだかザワザワしちゃうな。
11位『疾走』
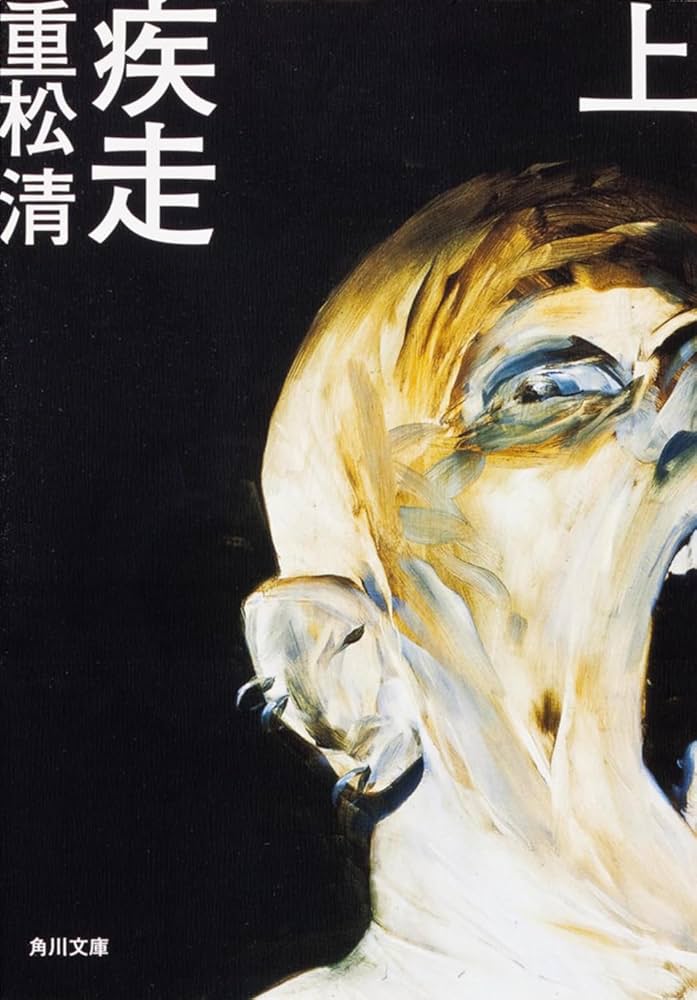
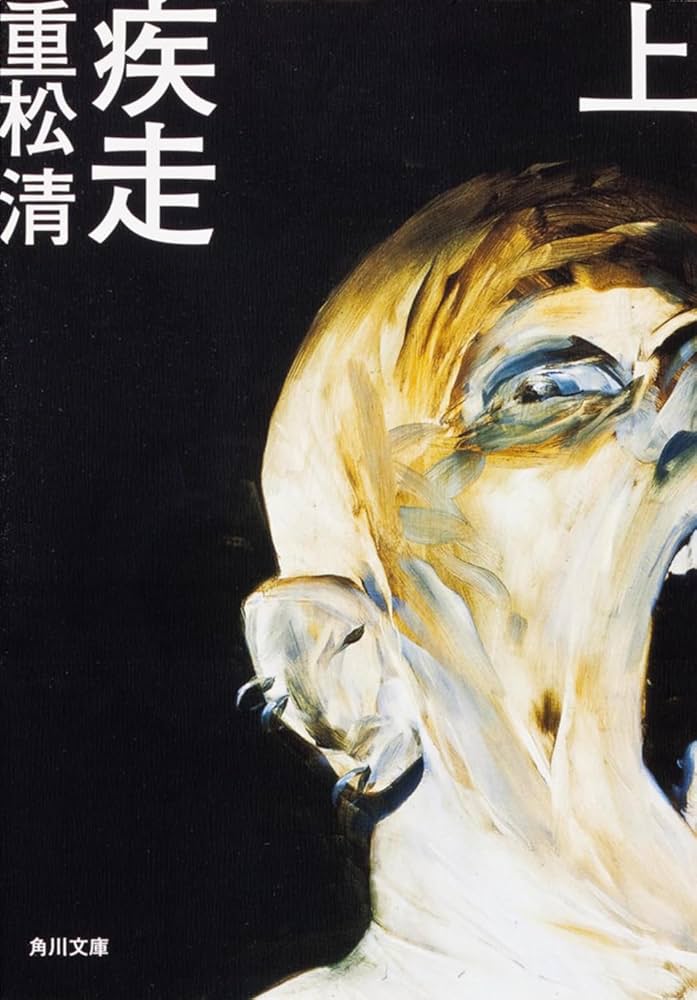
11位は、重松清作品の中でも特に異彩を放つ、重くダークな物語『疾走』です。映画化もされましたが、その救いのない展開から賛否両論を巻き起こしました。
主人公は、海辺の町に生まれた少年シュウジ。次々と不幸に見舞われ、過酷な運命に翻弄されながら、彼は犯罪へとひた走っていきます。 これまで紹介してきたような心温まる物語とは一線を画し、人間の心の闇や社会の不条理を容赦なく描き出しています。
なぜ少年は追い詰められなければならなかったのか。絶望的な状況の中でも、彼が求め続けたものは何だったのか。読後、ずっしりと重い問いが心に残ります。明るい話やハッピーエンドを求める方にはおすすめできませんが、人間の魂の極限状態を描いた作品として、強烈な印象を残す一冊です。



救いのない物語構造の中にこそ、作者の描きたかった本質が潜んでいる。この絶望の描写は他の追随を許さない。
12位『小学五年生』
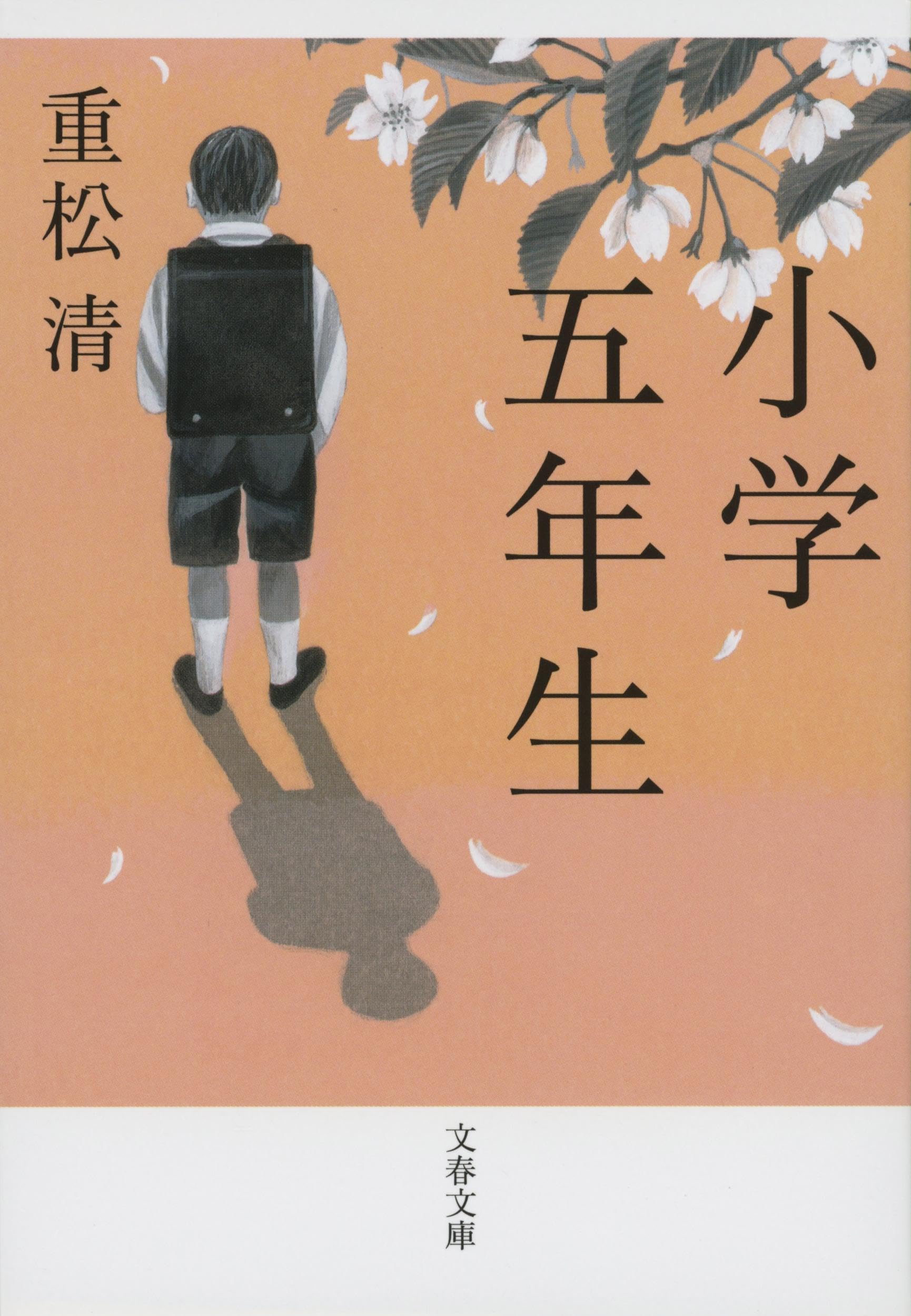
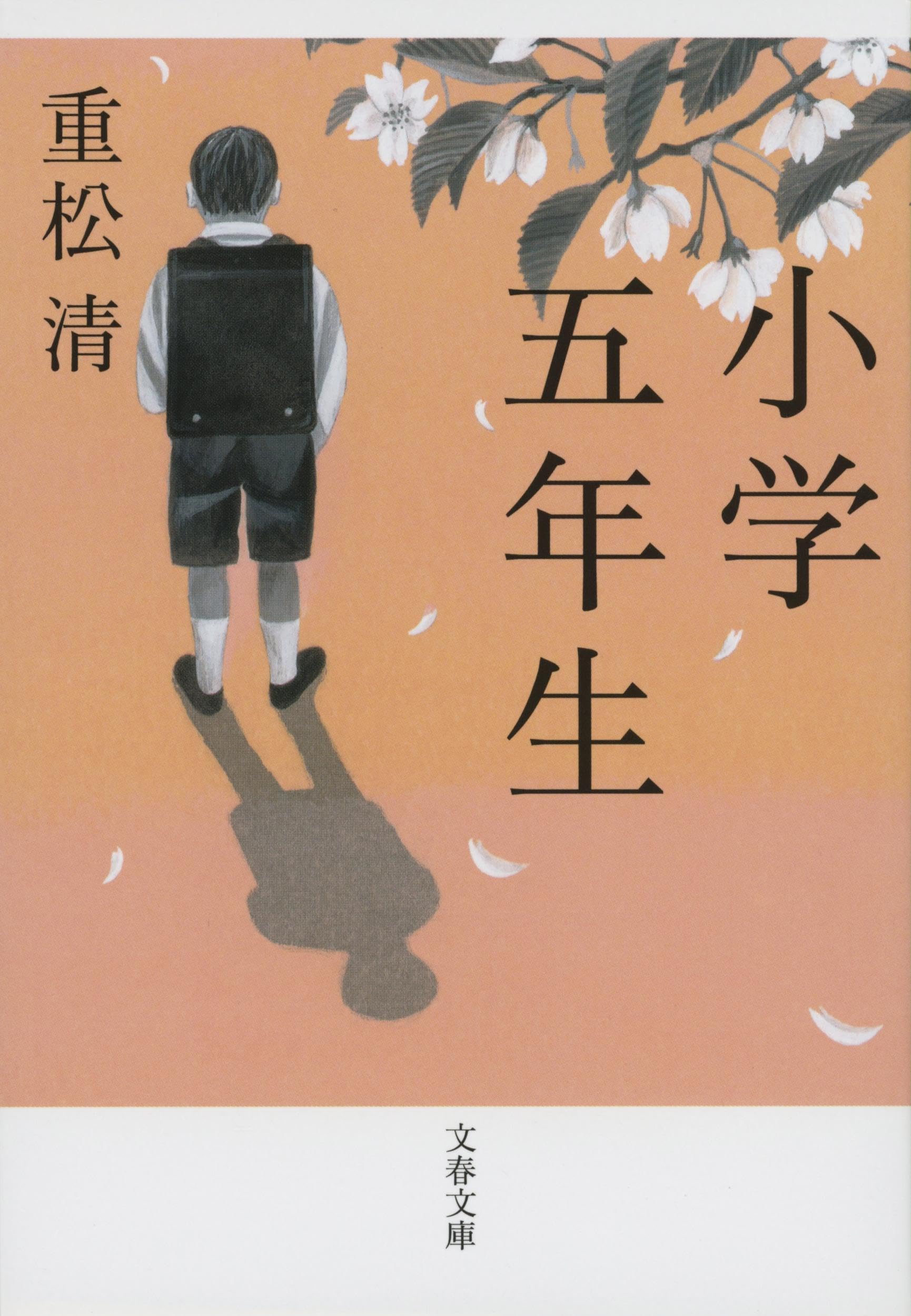
12位には、誰もが通り過ぎてきた「あの頃」の記憶を鮮やかに蘇らせる『小学五年生』がランクイン。大人と子どもの狭間で揺れ動く、小学5年生の少年少女たちの日常を切り取った連作短編集です。
友だちとの関係、家族への想い、そして淡い恋心。子どもならではの純粋さと、少しずつ芽生え始める大人の世界への戸惑いが、瑞々しい筆致で描かれています。子ども時代に感じた、あのキラキラした時間と、チクッとした痛みが詰まった一冊です。
重松さんの作品は、子どもを主人公にした物語が多いのが特徴ですが、本作はその中でも特に傑作と名高い作品です。 かつて小学5年生だったすべての人へ。忘れていた大切な何かを思い出させてくれる、ノスタルジックな物語です。



小学5年生の頃って、急に世界が広がった気がするよね。甘酸っぱい気持ちになれる本だよ。
13位『ステップ』


13位は、若くして妻を亡くした主人公が、男手ひとつで娘を育てる10年間を描いた物語『ステップ』です。映画化もされ、その温かいストーリーが多くの感動を呼びました。
主人公の健一は、妻・朋子の死から一年、30歳でシングルファーザーとなります。仕事と育児の両立に悩み、周囲の人々に助けられながら、娘・美紀と共に一歩一歩、ゆっくりと成長していきます。残された家族が、悲しみを乗り越えて新しい一歩を踏み出していく姿が、丁寧に描かれています。
血の繋がらない家族の形や、新しいパートナーとの関係など、現代的なテーマも盛り込まれています。大切な人を失った悲しみと、それでも続いていく日常の愛おしさを教えてくれる、優しさに満ちた物語です。



健一さんと美紀ちゃんの親子愛に心がぽかぽかするんだ。一歩ずつ進んでいく二人が素敵だね!
14位『くちぶえ番長』
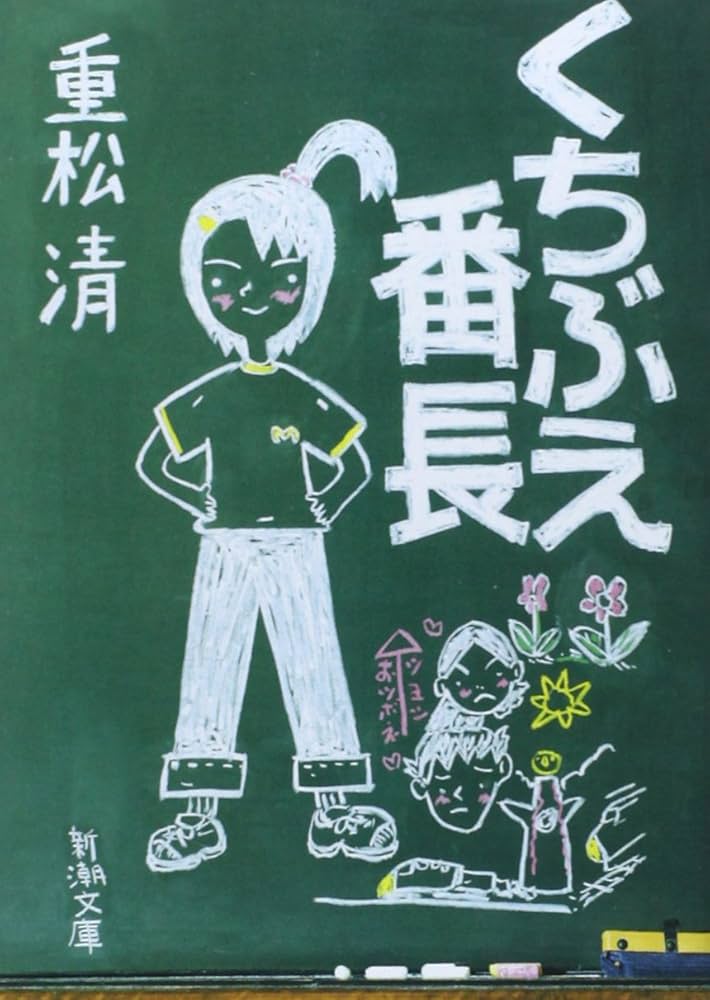
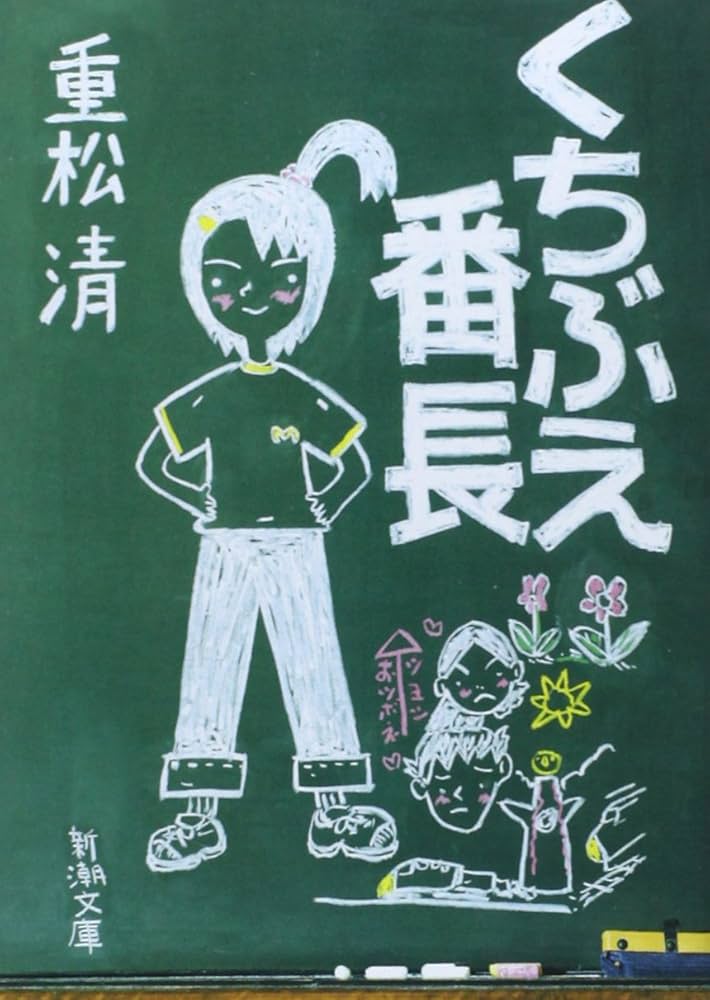
14位は、読書感想文の定番としても知られる、子どもたちに大人気の名作『くちぶえ番長』です。小学4年生のツヨシのクラスに転校してきた、男の子みたいに強くてかっこいい女の子、マコトが主人公の物語です。
いじめっ子にも敢然と立ち向かい、いつも堂々としているマコト。彼女の周りには、自然と友だちの輪ができていきます。ツヨシはそんなマコトに、憧れと淡い恋心を抱くようになります。友情、勇気、そしてちょっぴり切ない初恋が、爽やかに描かれています。
子どもだけでなく、大人が読んでも胸が熱くなる、王道の児童文学です。忘れかけていた真っ直ぐな気持ちを思い出させてくれる、キラキラとした魅力に満ちた一冊です。



マコトみたいに強い女の子、かっこいい!こんな友だちがいたら毎日が冒険みたいで楽しそうだな。
15位『せんせい。』
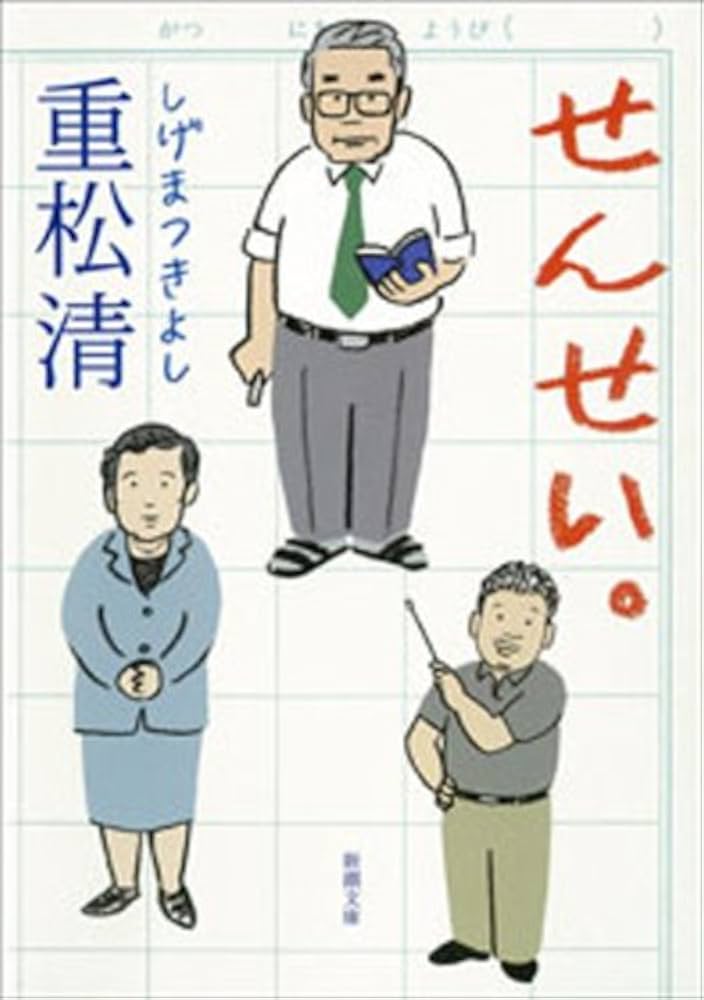
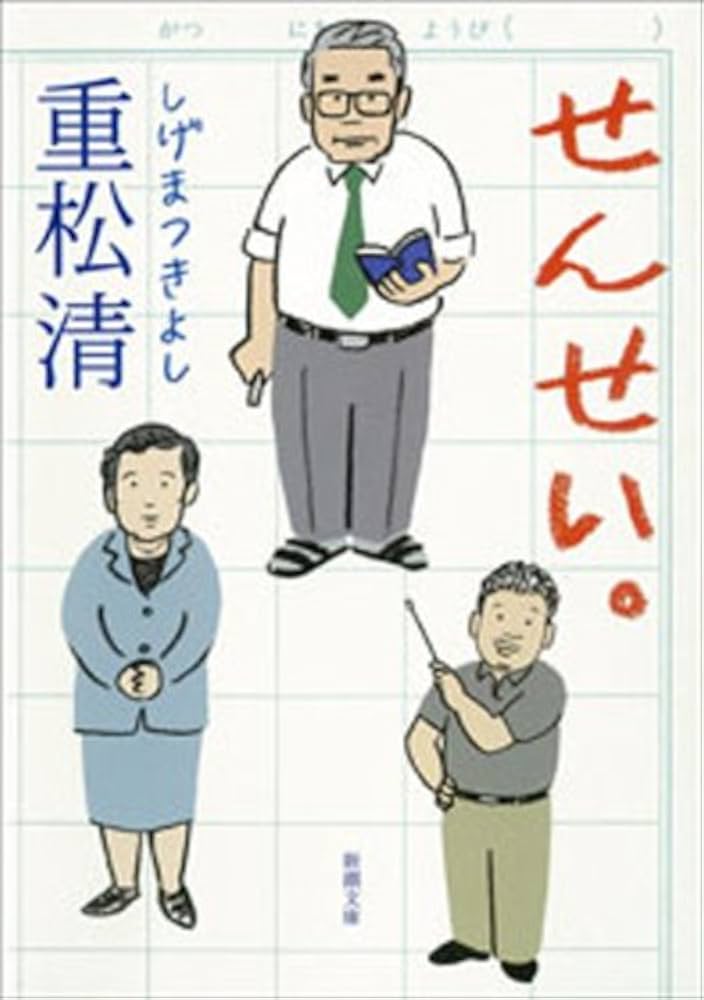
15位には、学校の先生と生徒たちの交流を描いた珠玉の短編集『せんせい。』がランクイン。教育学部出身である重松さんならではの、温かくも鋭い視点が光る作品です。
収録されているのは、小学校から高校まで、様々な学校を舞台にした物語。熱血先生、頼りない先生、ちょっと変わった先生など、個性豊かな「せんせい」たちが登場します。そして、彼らと関わることで、生徒たちが少しだけ成長していく瞬間が鮮やかに切り取られています。
この本を読むと、誰もがお世話になった「先生」のことを思い出すのではないでしょうか。卒業してから気づく、先生たちの不器用な優しさや愛情が、胸にじんわりと広がります。教育の現場にある喜びと難しさを描き出した、感動的な一冊です。



お世話になった先生の顔が浮かんできたよ。先生たちも同じように悩んだりするんだね。
16位『卒業』
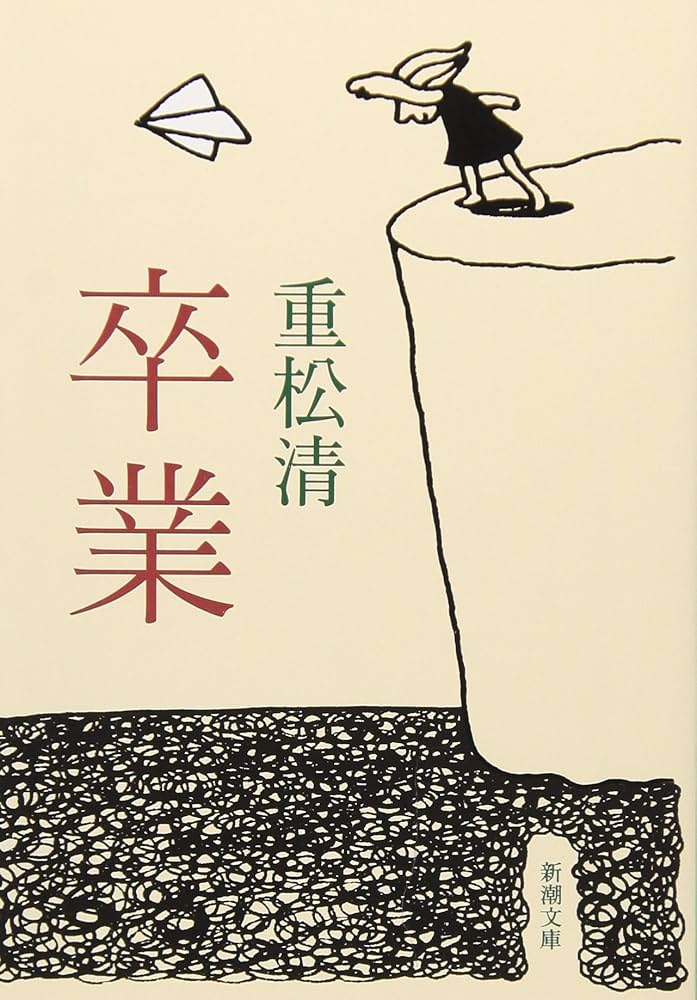
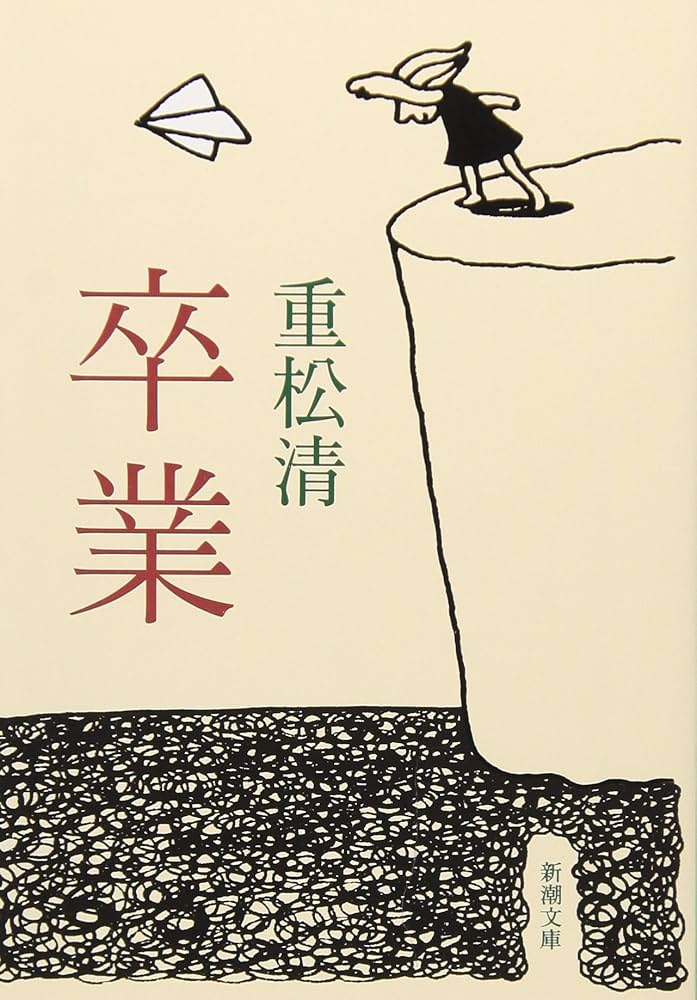
16位は、人生の様々な「卒業」の瞬間を切り取った短編集『卒業』です。学校からの卒業だけでなく、子どもからの卒業、過去の自分からの卒業など、多様な別れと旅立ちが描かれています。
中でも表題作の「卒業」は、中学校の卒業式を目前に控えた生徒と、彼らを見送る教師の視点で語られます。大人になることへの期待と不安、友だちとの別れの寂しさなど、卒業式特有の甘酸っぱく切ない感情が、見事に表現されています。
人生は出会いと別れの繰り返し。一つの季節が終わり、また新しい季節が始まる。そんな当たり前の真理を、重松さんらしい温かい眼差しで描いた作品集です。これから卒業を迎える人にも、遠い昔に卒業を経験した人にも、深く心に響く物語です。



卒業式ってどうしてあんなに泣けるんだろう。この本を読んだら卒業アルバムを開きたくなっちゃったよ。
17位『カシオペアの丘で』
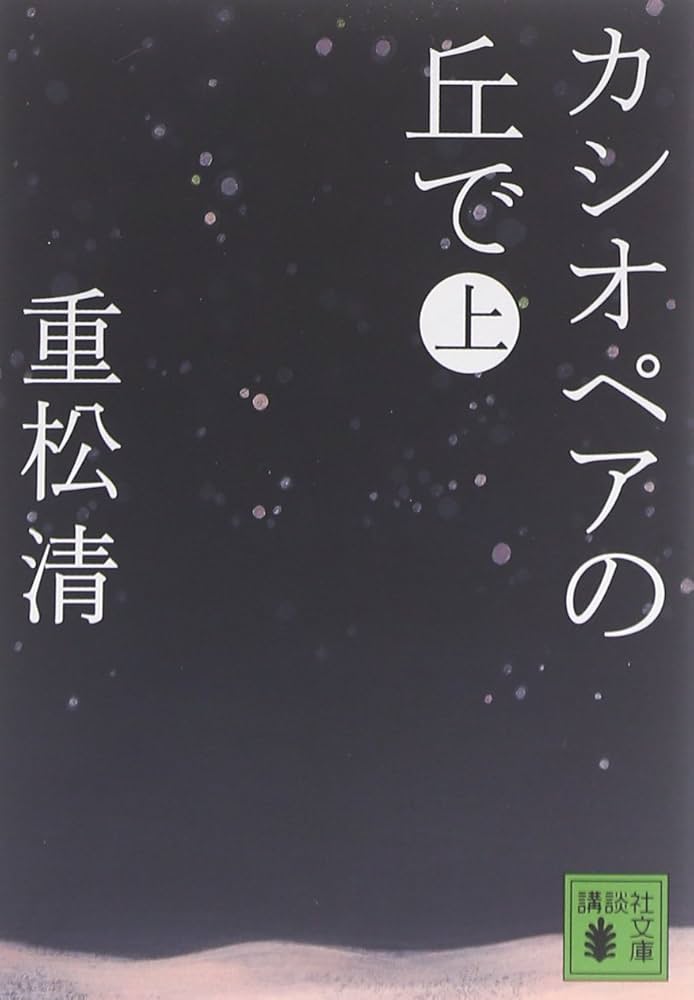
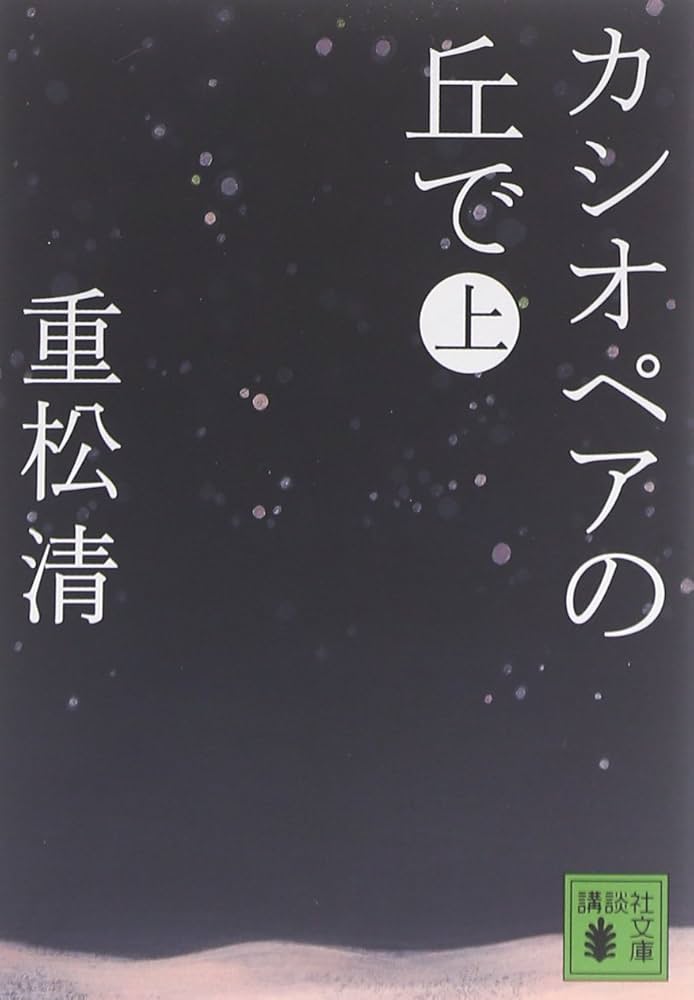
17位は、離婚した夫婦とその子どもたちが、それぞれの形で家族の絆を取り戻そうとする姿を描いた長編小説『カシオペアの丘で』です。一度壊れてしまった家族は、もう元には戻れないのでしょうか。
物語は、別々に暮らす父と息子、母と娘、それぞれの視点から語られます。すれ違い、傷つけ合いながらも、心のどこかでは繋がりを求め続ける4人。そんな彼らが、北海道への旅を通じて、少しずつお互いの想いを理解していく過程が丁寧に描かれています。
家族の形は一つではない。たとえ一緒に暮らしていなくても、絆を結び直すことはできる。そんな希望を感じさせてくれる物語です。現代的な家族のあり方を問いかける、深く、そして優しい一冊です。



家族の形って色々あるんだなって思ったよ。離れていても想い合う気持ちがあれば大丈夫なんだね。
18位『小さき者へ』
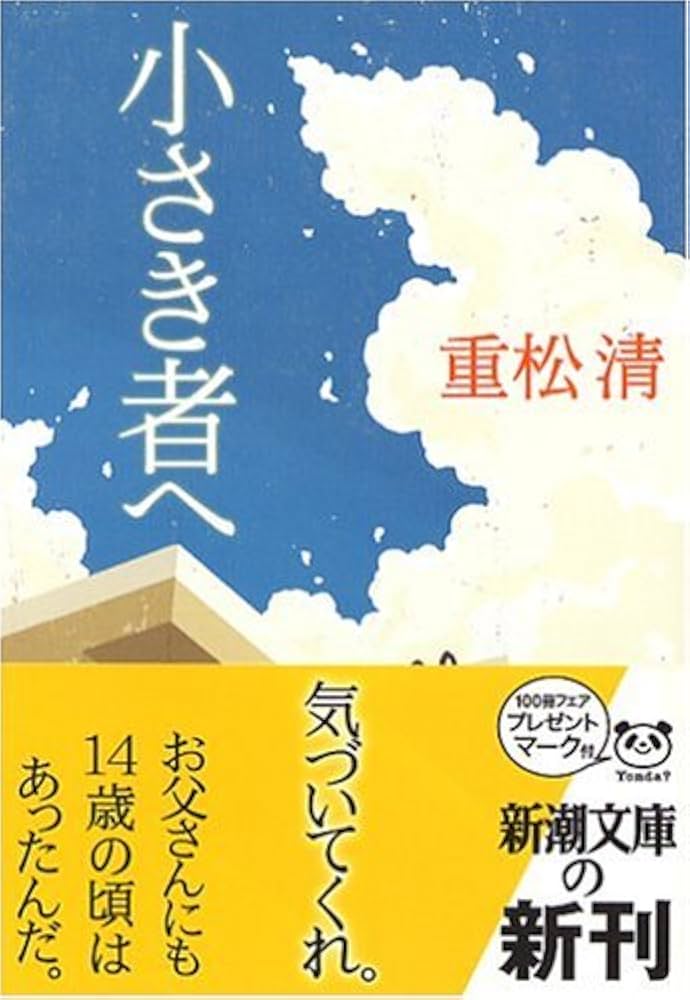
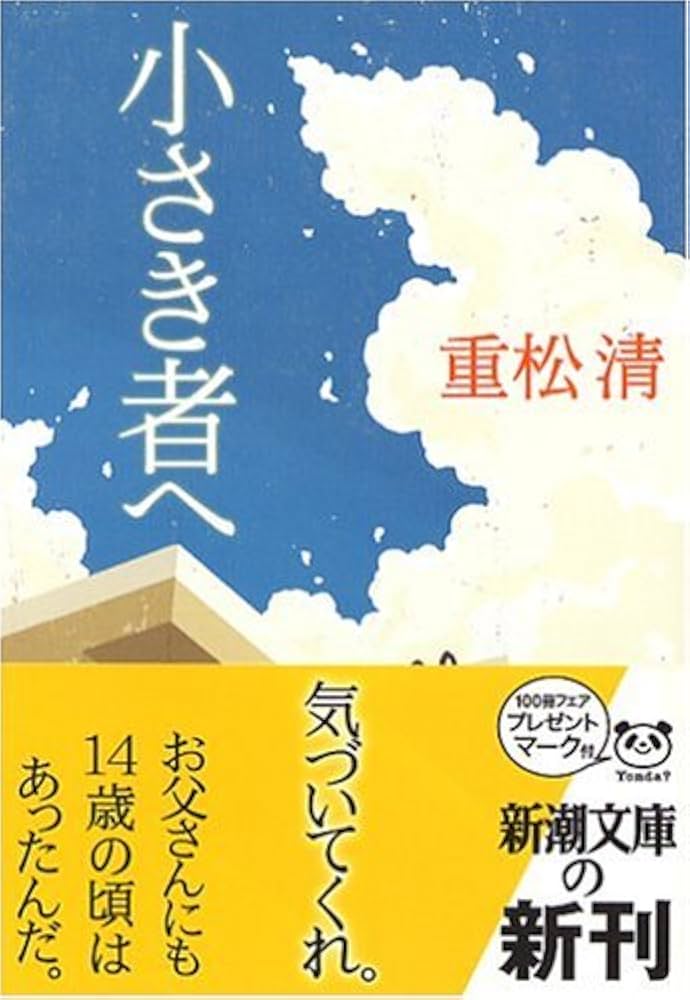
18位にランクインしたのは、重松さんが自身の娘さんたちに向けて書いたとされる、愛情あふれるエッセイ風小説『小さき者へ』です。父親としての、飾らない素直な気持ちが綴られています。
娘の成長を見守る喜び、いつか巣立っていくことへの寂しさ、そして「父親」として何を伝えられるのかという戸惑い。そんな普遍的な親心が、ユーモアを交えながら温かく描かれています。
これから親になる人、子育て真っ最中の人、そしてかつて子どもだったすべての人へ。この本には、家族の愛の原点ともいえるような、かけがえのない想いが詰まっています。読めばきっと、自分の親に感謝したくなる、そんな心温まる一冊です。



お父さんの愛情がたっぷりで幸せな気持ちになるよ。わたしのパパもこんな風に思ってくれてるかな?
19位『定年ゴジラ』
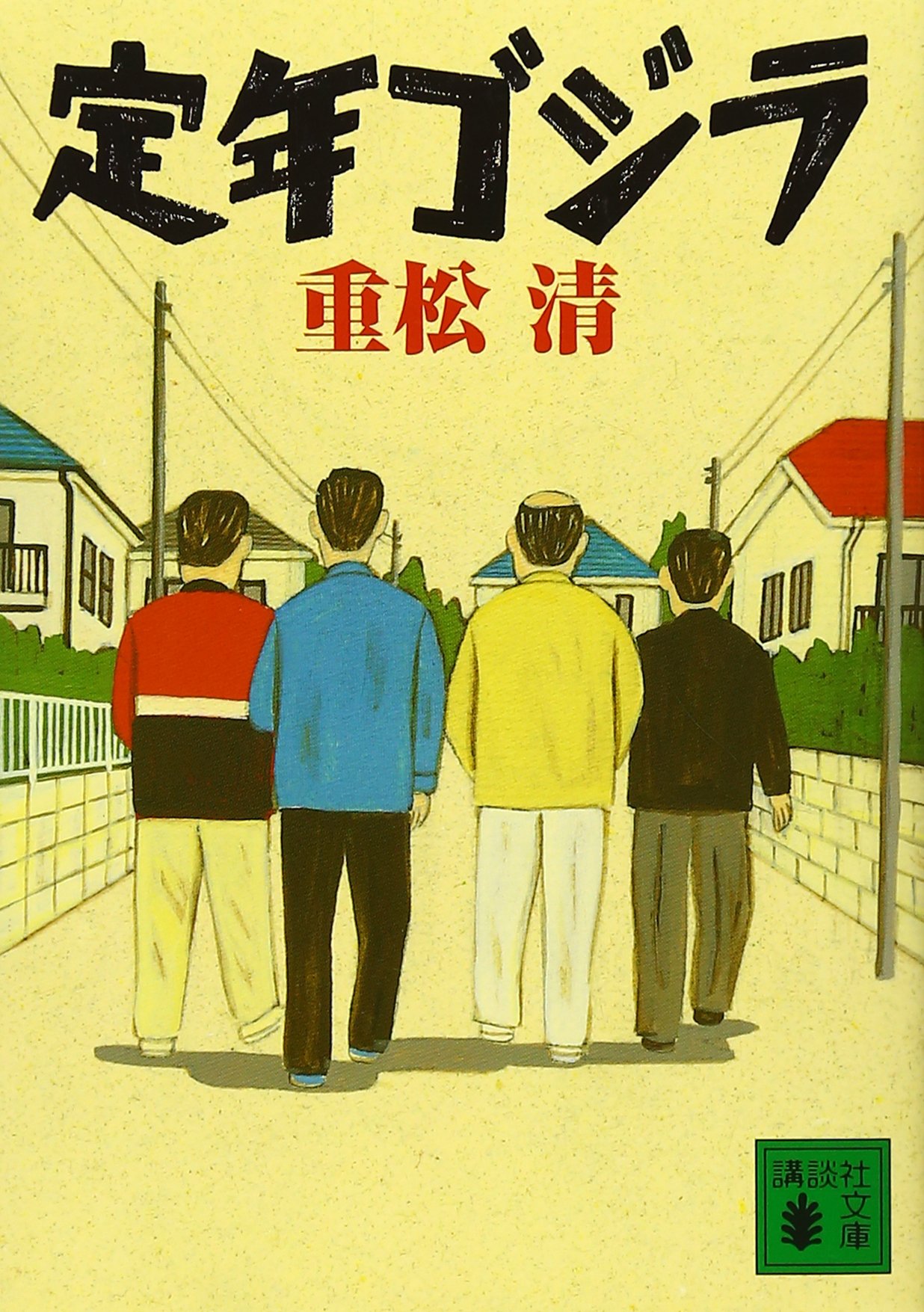
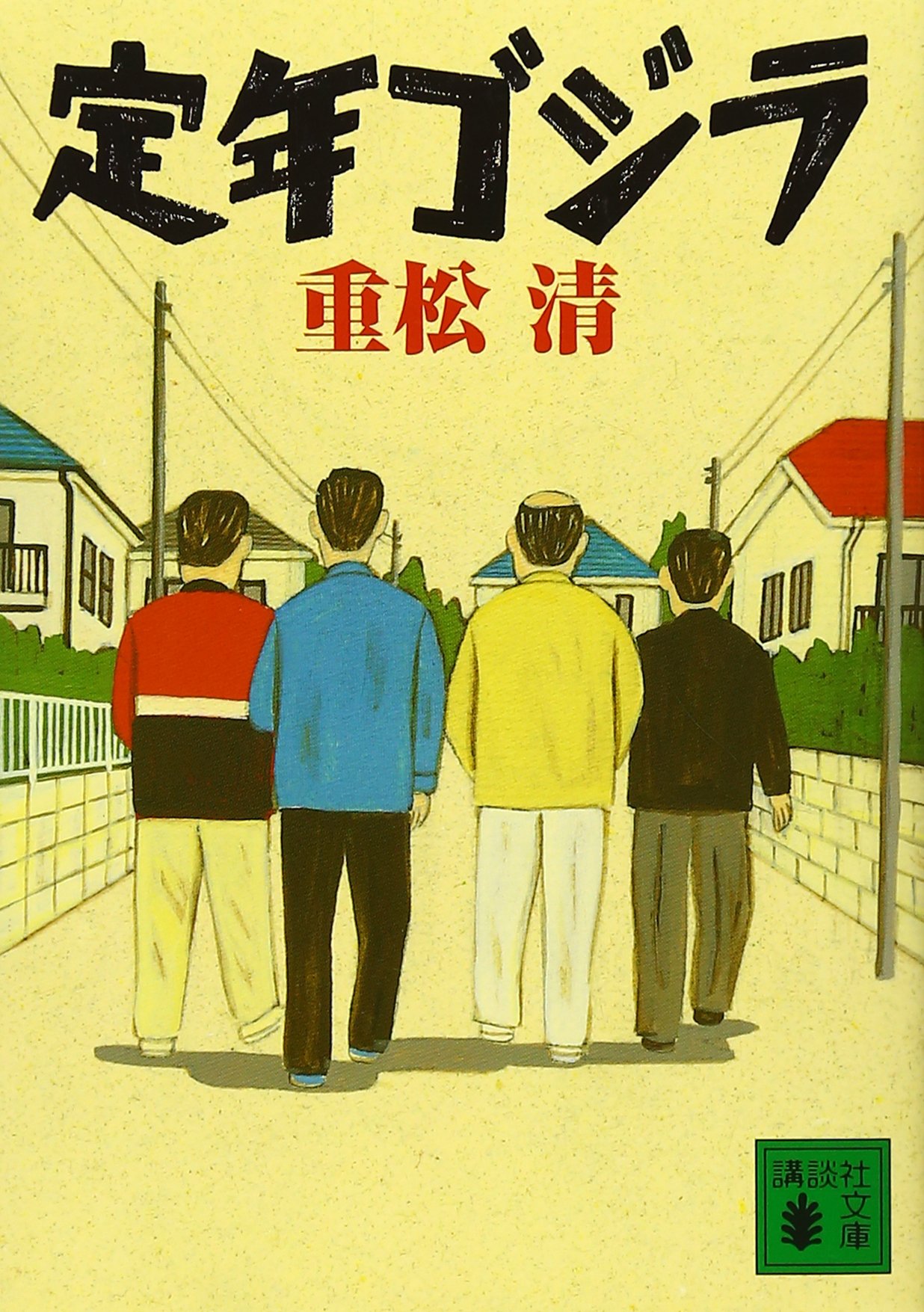
19位は、定年退職した男たちの悲哀と友情を、ユーモラスに描いた『定年ゴジラ』です。仕事一筋だった主人公が、定年を迎え、家庭や地域社会で「濡れ落ち葉」と疎まれる存在になってしまうところから物語は始まります。
居場所をなくした主人公が出会ったのは、同じ境遇の老人たちが集う「ゴジラの会」。彼らは、怪獣ゴジラのように、社会や家庭から厄介者扱いされる自分たちを自嘲的に語り合います。高齢化社会の現実をコミカルに描きつつも、その裏にある切実な問題を浮き彫りにしています。
笑いの中にも、定年後の人生をどう生きるかという、深いテーマが横たわっています。これから定年を迎える世代はもちろん、その家族にもぜひ読んでほしい、現代社会を映し出す物語です。



定年後のお父さんたち、ちょっと可愛いかも。笑えるけどなんだか切ないお話なんだよね。
20位『かあちゃん』
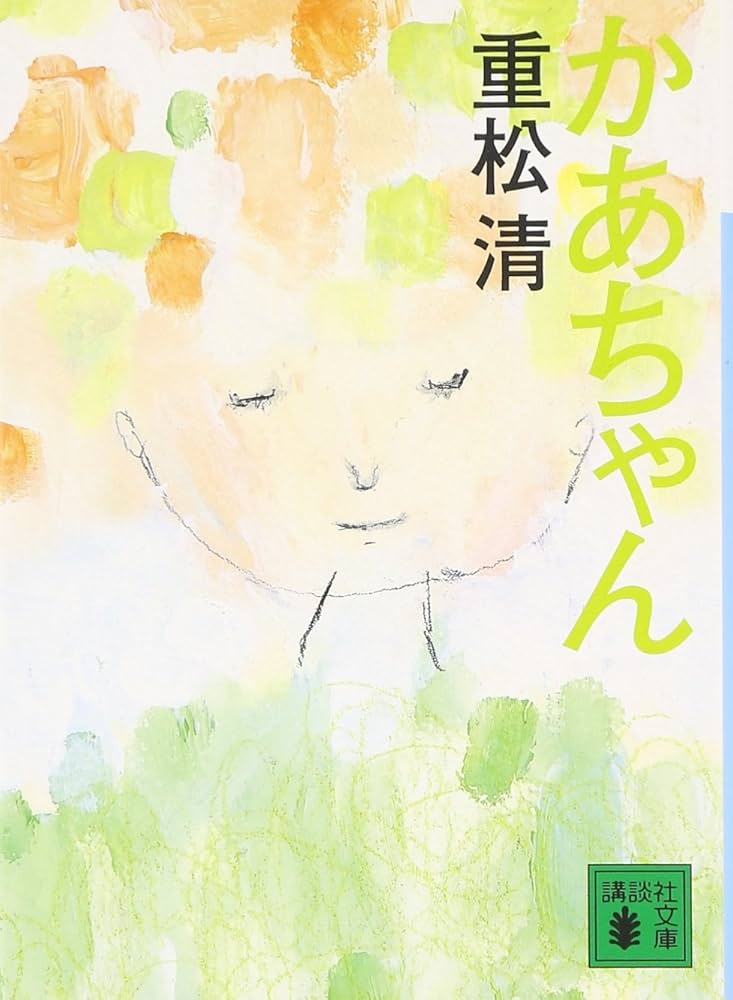
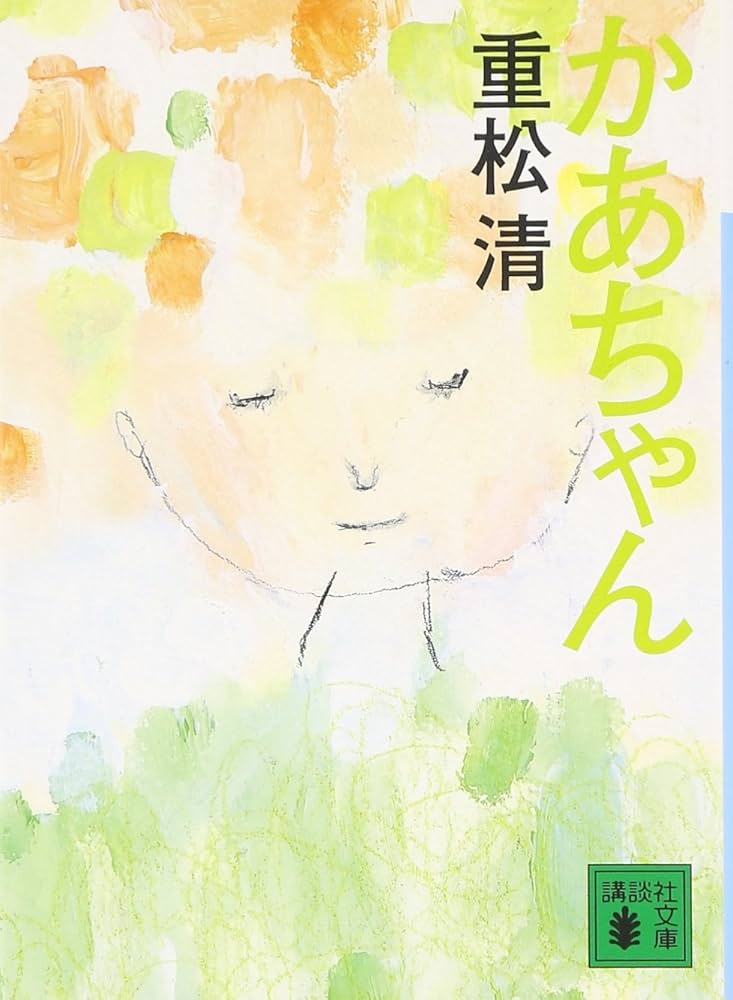
20位は、その名の通り、世の中のすべての「かあちゃん」に捧げられたような物語『かあちゃん』です。様々な境遇にある母親たちの姿を描いた、感動の連作短編集です。
子どもの反抗期に悩む母親、シングルマザーとして奮闘する母親、我が子を亡くした母親。それぞれの物語で描かれるのは、強く、優しく、そして時にもろい、母親たちの等身大の姿です。
どんな状況でも、子を想う母の愛情の深さには変わりありません。当たり前のようにそばにいる「かあちゃん」の存在が、いかに偉大でかけがえのないものかを、改めて気づかせてくれます。母の日や誕生日に、感謝の気持ちを込めてプレゼントするのも素敵な一冊です。



どのお母さんの話も愛情がいっぱいで泣けちゃう。いつもありがとうってちゃんと言わなきゃだね。
21位『ビフォア・ラン』
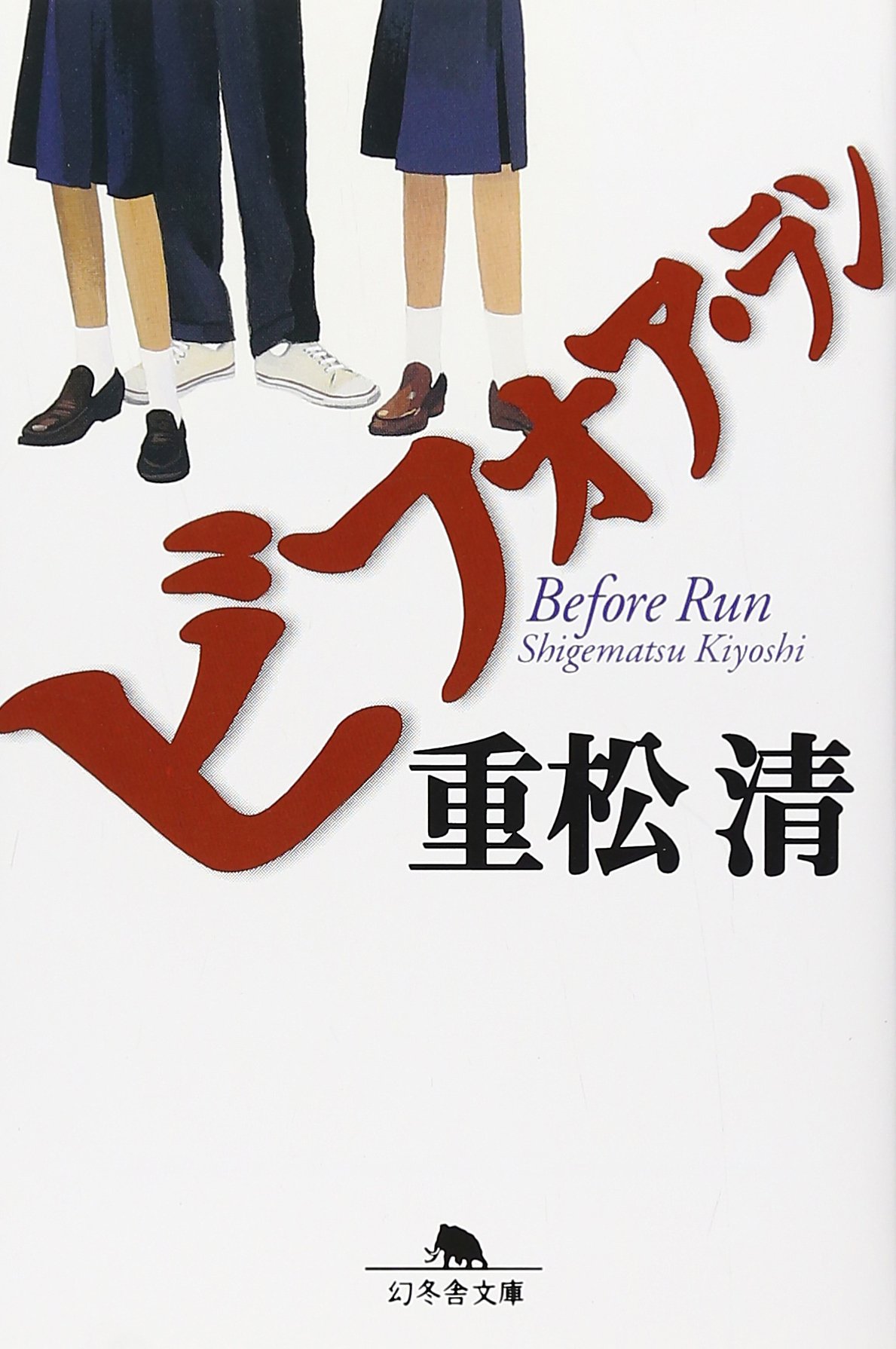
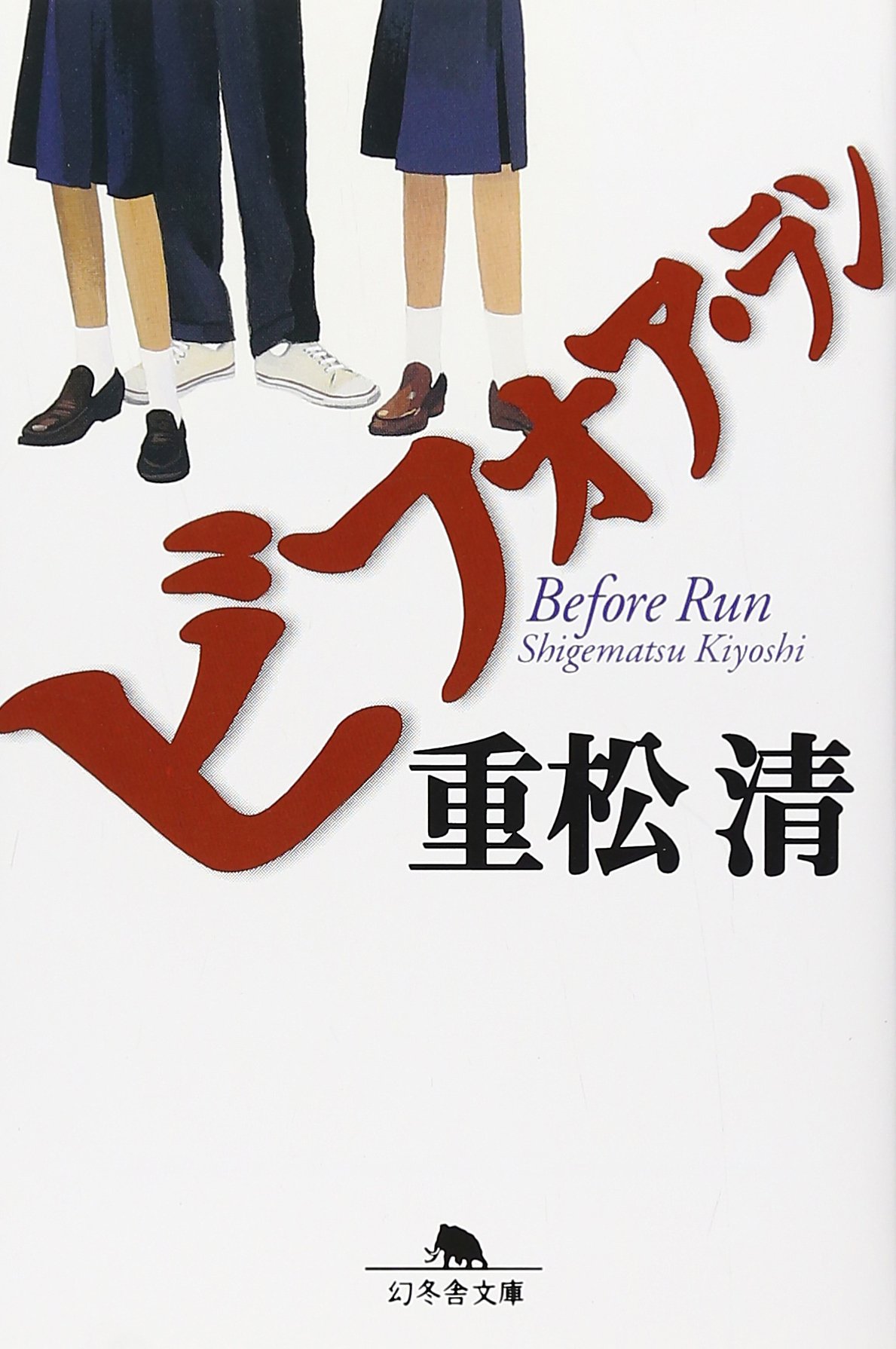
21位にランクインしたのは、1991年に発表された重松清さんの記念すべきデビュー作『ビフォア・ラン』です。 若き日の重松さんの才能のきらめきを感じることができる一冊です。
物語の主人公は、高校の陸上部で長距離ランナーだった青年。かつての夢や情熱を失い、平凡な日常を送る彼が、ふとしたきっかけで再び走り始めます。過去の自分と向き合い、未来へと走り出すまでの心の軌跡が、瑞々しい感性で描かれています。
何かを始める前の、あの独特の高揚感や不安。このタイトルは、そんな「走る前」の瞬間を象徴しています。初期作品ならではの、少し尖った文体も魅力の一つ。重松清ファンならぜひ押さえておきたい、原点ともいえる作品です。



デビュー作って作家さんの原石みたいでワクワクするよね。走り出す前のドキドキ感が伝わってくるよ。
22位『幼な子われらに生まれ』
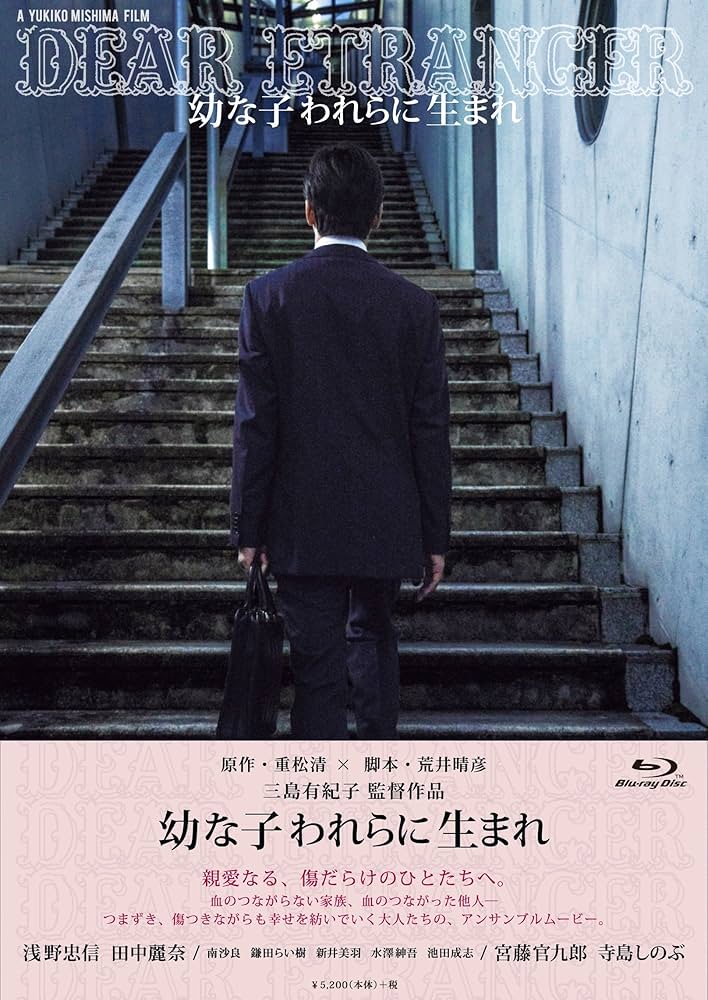
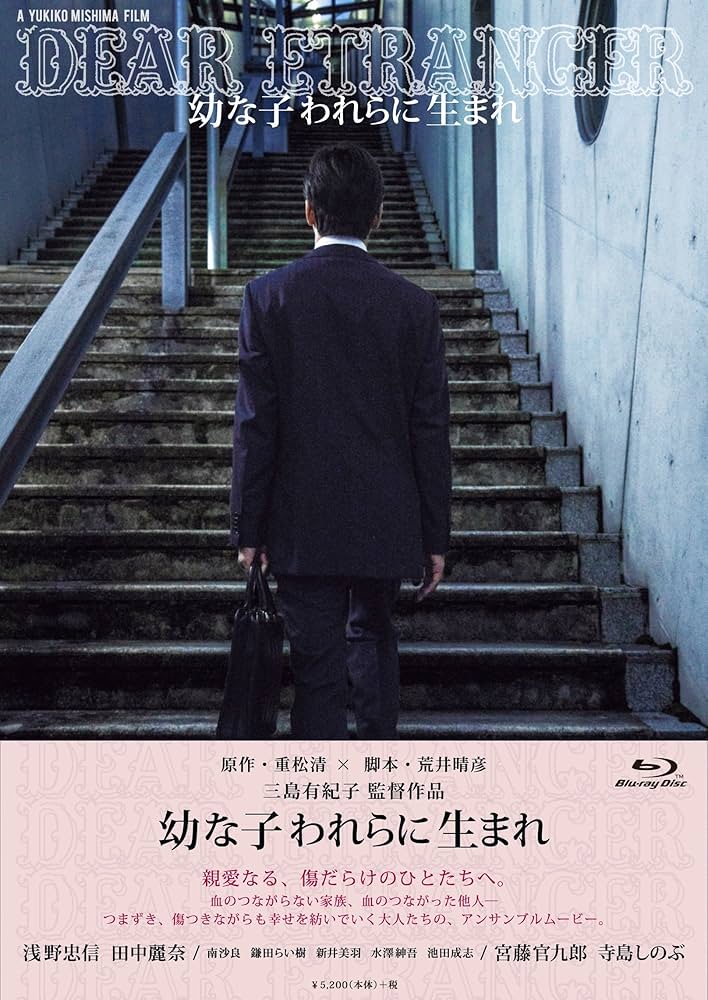
22位は、複雑な家族関係の中で「本当の親子」になろうと葛藤する人々を描いた『幼な子われらに生まれ』です。浅野忠信さん主演で映画化され、その衝撃的な内容が話題を呼びました。
主人公は、バツイチで子連れの女性と再婚したサラリーマン。新しい妻の連れ子である長女は、どうしても彼に懐こうとしません。そんな中、元妻との間に生まれた実の娘との再会が、彼の心を揺さぶります。血の繋がりとは何か、家族とは何かを、痛々しいほどリアルに問いかける物語です。
いわゆる「ステップファミリー」が抱える問題を、綺麗事なしで描き切った意欲作。簡単に答えの出ない問いだからこそ、読者の心に深く突き刺さります。家族の形が多様化する現代において、多くの人が考えるべきテーマを含んだ一冊です。



家族になるって簡単なことじゃないんだね…。すごくリアルで胸が苦しくなっちゃった。
23位『ポニーテール』
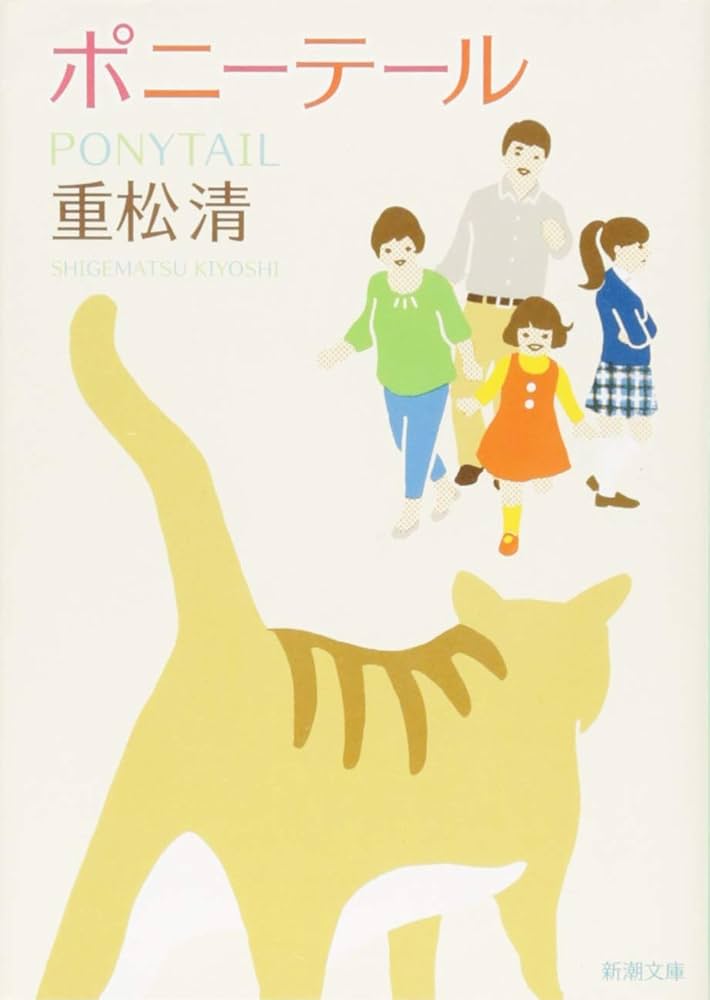
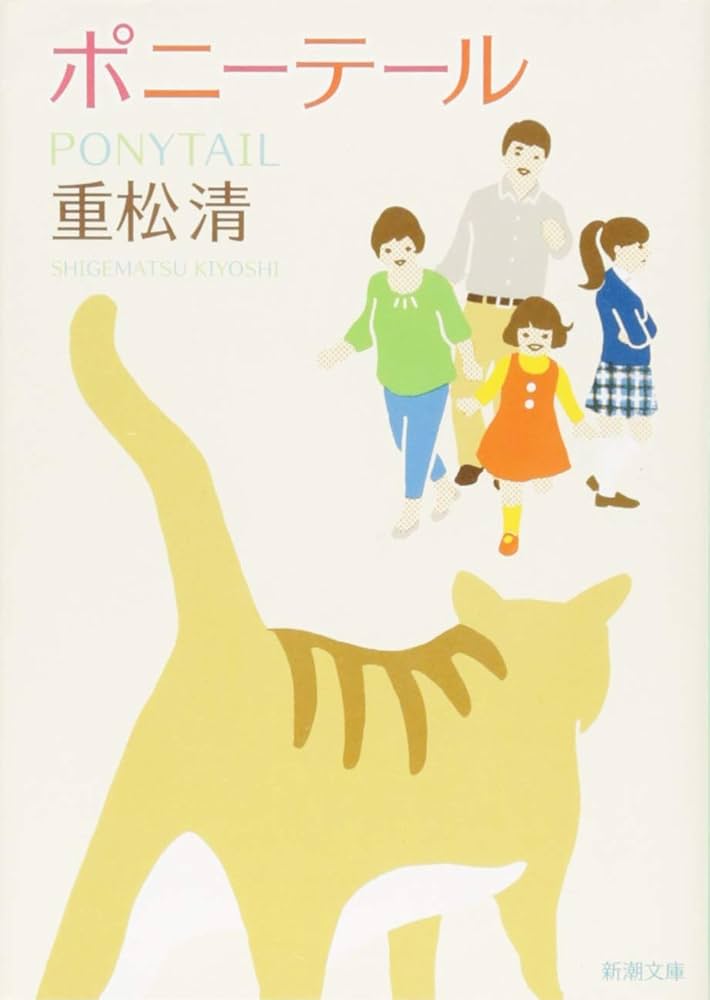
23位には、こちらもステップファミリーをテーマにした物語『ポニーテール』がランクイン。 『幼な子われらに生まれ』が大人たちの葛藤を中心に描いていたのに対し、本作は子どもの視点から、新しい家族の形を見つめています。
主人公は、母親の再婚相手である「シュウちゃん」と暮らすことになった小学生の女の子。最初は戸惑いながらも、不器用だけど優しいシュウちゃんとの間に、少しずつ本当の親子のような絆が芽生えていきます。
子どもならではの素直な視点で描かれることで、家族になっていく過程の温かさや、ささやかな喜びがストレートに伝わってきます。血の繋がりを超えた愛情の形を、優しく描き出した心温まる物語です。



シュウちゃんと女の子の関係が可愛くてほっこりするよ。ゆっくり家族になっていくって素敵だね。
24位『ゼツメツ少年』


24位は、現代社会の歪みの中で生きる少年たちの姿を、少し不思議な設定で描いた『ゼツメツ少年』です。重松作品の中でも、ファンタジー要素が色濃い一作と言えるでしょう。
主人公の少年が出会ったのは、「ゼツメツ」してしまったはずのニホンオオカミの血を引くという転校生。彼は、現代社会で「ゼツメツ」の危機に瀕している様々なものを憂いています。物語は、失われつつある大切なものへの警鐘を鳴らしているかのようです。
いじめ、不登校、そして無関心。生きづらさを抱える少年たちの孤独な魂が、幻想的な世界観の中で描かれています。私たちが当たり前だと思っている日常の裏側にある、危うさや脆さに気づかせてくれる、示唆に富んだ物語です。



「ゼツメツ」って言葉がなんだか寂しい響きだね。失くしちゃいけないものってたくさんあるのかも。
25位『カレーライス』
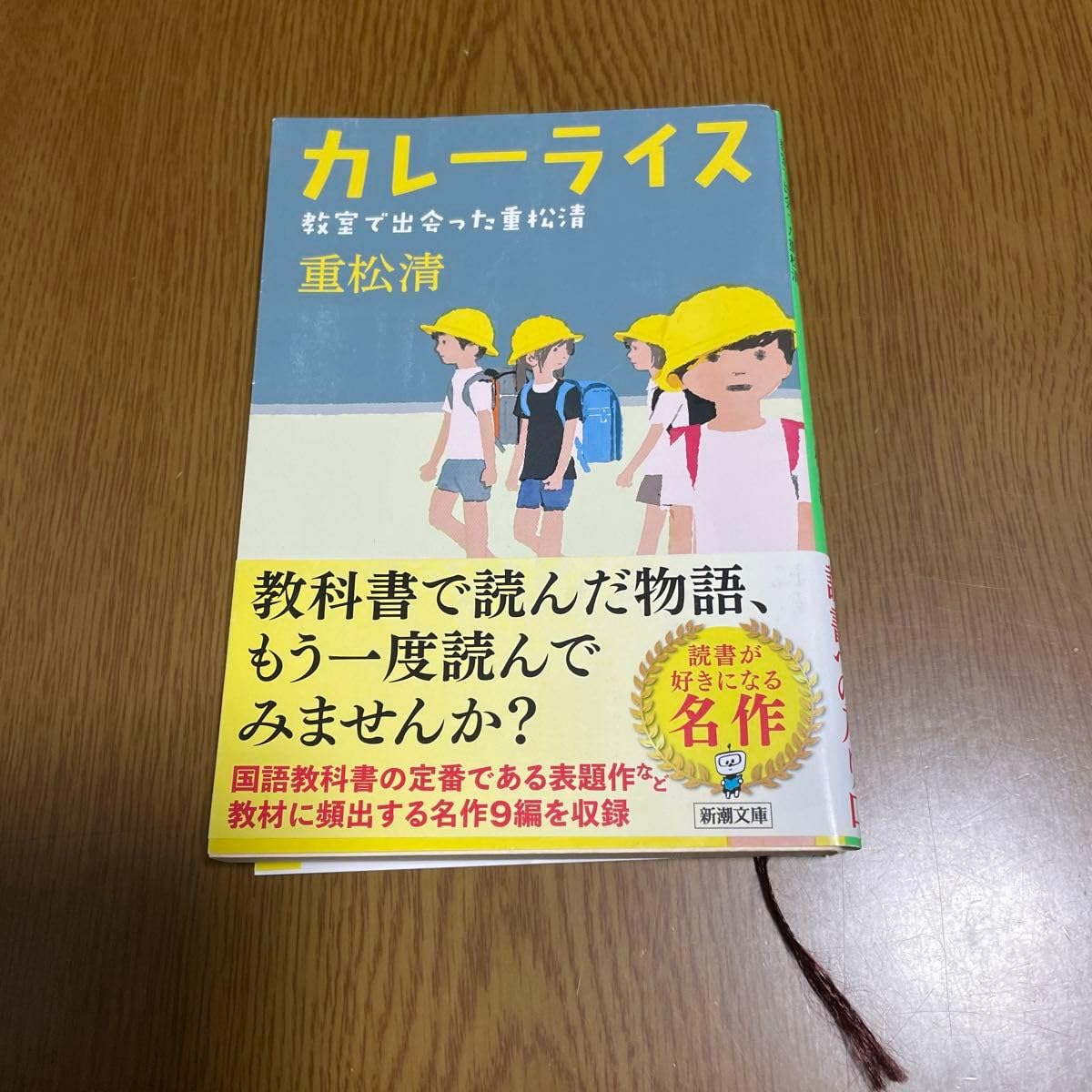
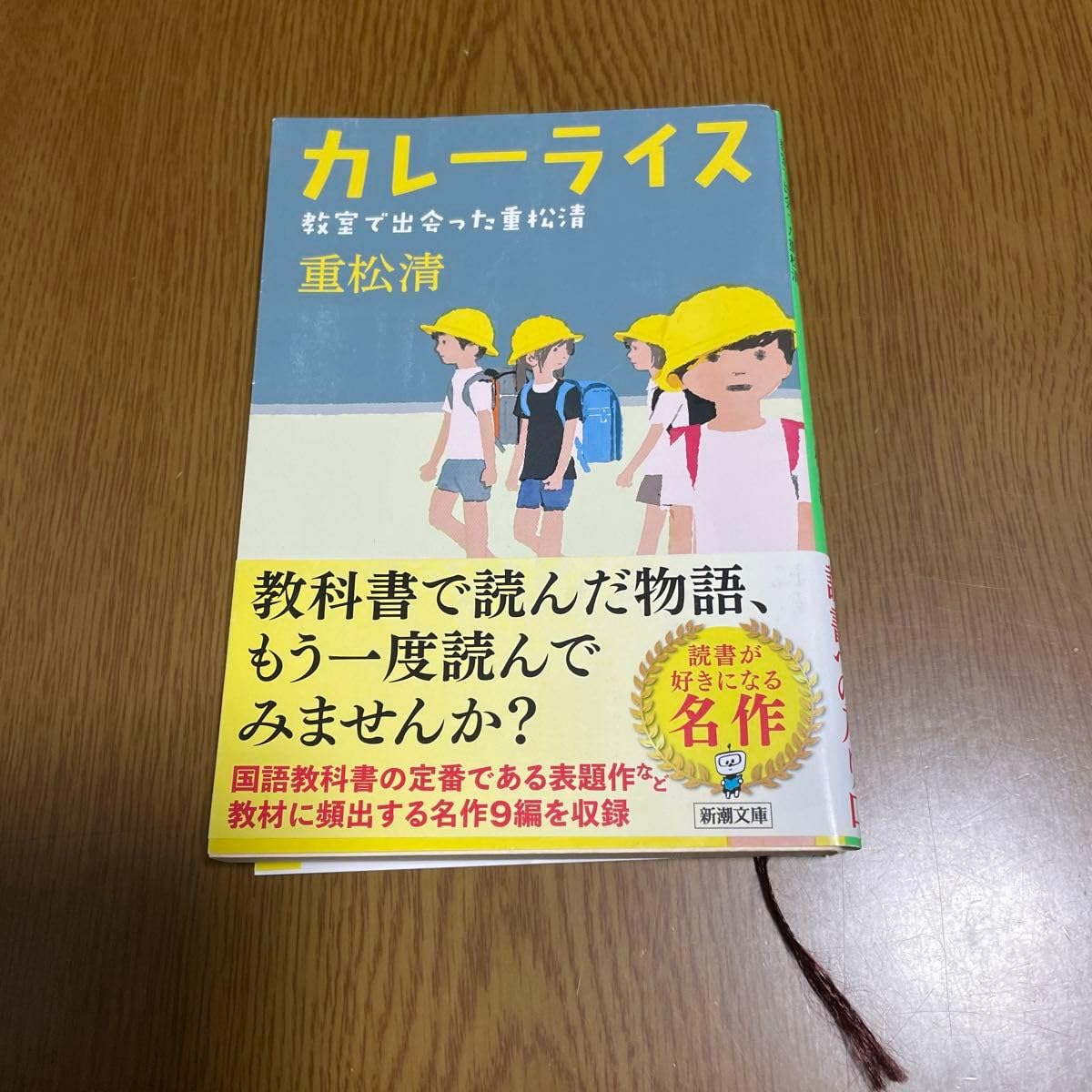
25位は、一皿のカレーライスをめぐる、父と息子の心温まる物語『カレーライス』です。絵本にもなっており、子どもから大人まで楽しめる作品として人気を集めています。
お父さんと二人暮らしのヒロシくん。ある日、お母さんが家を出て行ってしまいます。寂しさをこらえ、気丈に振る舞うヒロシくんですが、お父さんが作るカレーライスを食べるうちに、こらえていた涙が溢れ出してしまいます。食べ物と家族の記憶が結びついた、温かくも切ない物語です。
誰にでも、思い出の味や家族との食卓の記憶があるはず。そんなノスタルジックな感情を呼び覚ましてくれる一冊です。短い物語ながら、親子の深い愛情が凝縮されており、読後には心がじんわりと温かくなります。



カレーの匂いで家族を思い出すってわかるな。わたしも今夜はカレーが食べたくなっちゃったよ。
26位『木曜日の子ども』
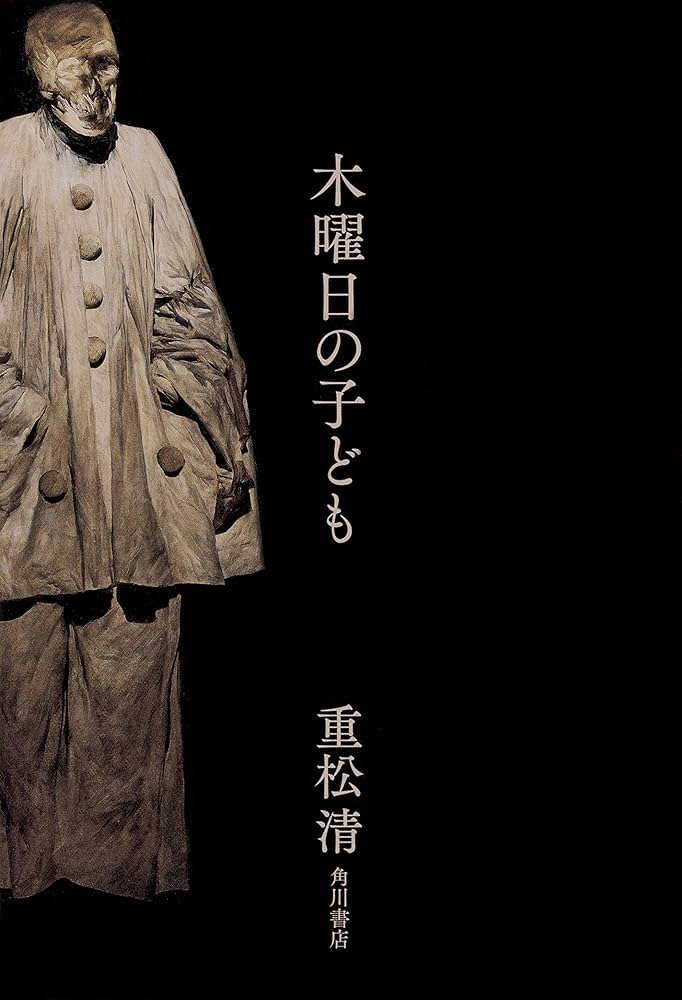
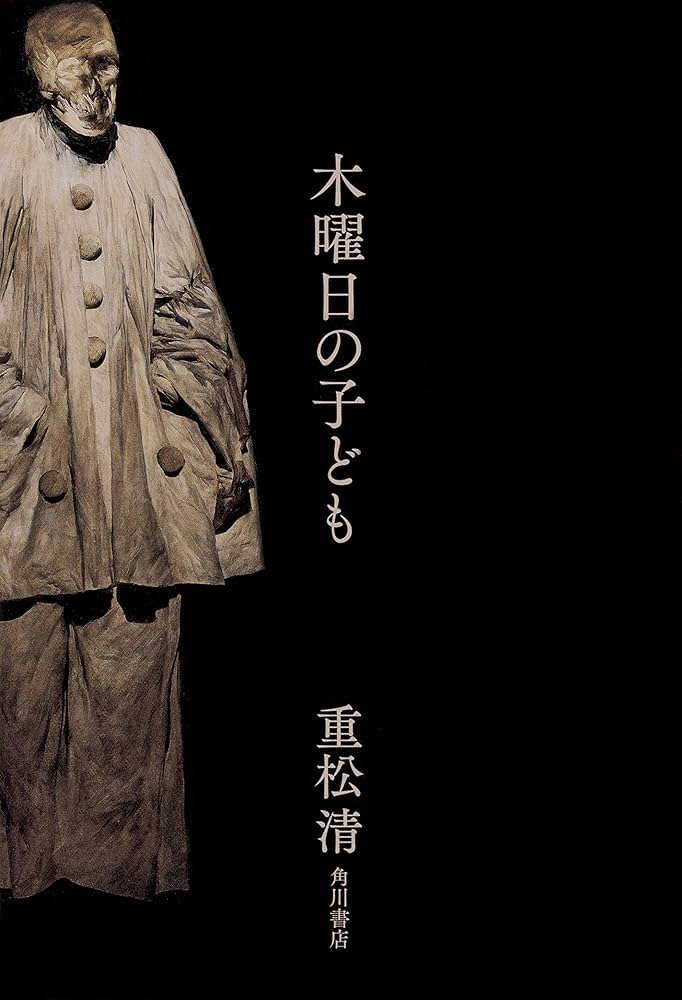
26位は、重松作品の中でも特にサスペンス色の強い異色作『木曜日の子ども』です。ある日突然、8年前に起きた小学生殺害事件の犯人だと名乗る手紙が、新聞社に届くところから物語は始まります。
手紙の送り主は、本当に犯人なのか。事件を追う記者、被害者の父親、そして容疑者とされた男。様々な人々の視点が交錯し、事件の真相が少しずつ明らかになっていきます。人間の心の奥底に潜む悪意や、メディア報道のあり方にまで鋭く切り込んだ、社会派ミステリーです。
いつもの温かい作風とは一味違う、ヒリヒリとした緊張感が全編を貫いています。重松清さんの新たな一面を発見できる、読み応え抜群の一冊です。



人間の心理に潜む闇をここまで克明に描き出すとは。物語の構成力と筆致の鋭さに戦慄を禁じ得ない。
27位『星のかけら』
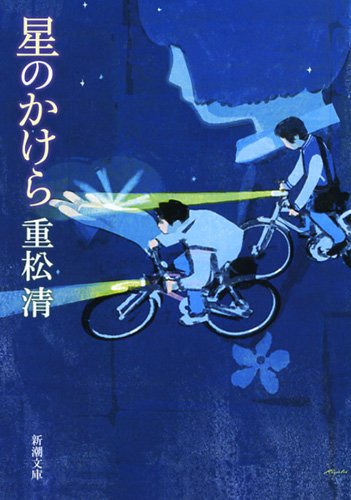
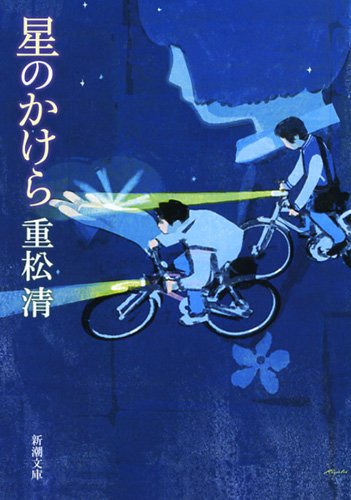
27位には、いじめられっ子の少年が、不思議な少女との出会いを通じて成長していく姿を描いた『星のかけら』がランクインしました。 こちらも児童書として、多くの子どもたちに読まれている作品です。
主人公のユウキは、体が小さく気弱な性格のため、クラスでいじめられています。そんな彼の唯一の心の支えは、星空を眺めること。ある夜、彼は「宇宙人」を自称する不思議な少女、ハルカと出会います。ハルカとの交流を通して、ユウキが少しずつ勇気を見つけていく過程が、優しく描かれています。
ファンタジックな要素を織り交ぜながら、いじめという現実的な問題に立ち向かう少年の姿を描いた物語。今、辛い思いをしている子どもたちに、きっと希望を与えてくれる一冊です。



宇宙人の友だちって考えただけでワクワクするね!ユウキくんが勇気を出すところ、応援したくなっちゃうよ。
28位『ファミレス』
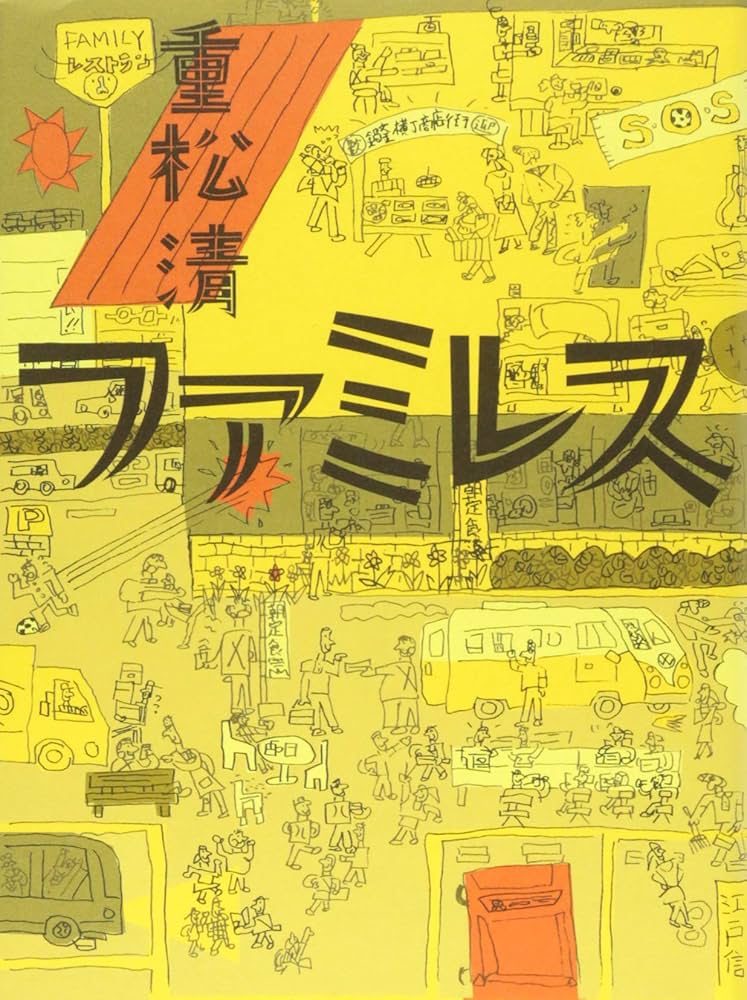
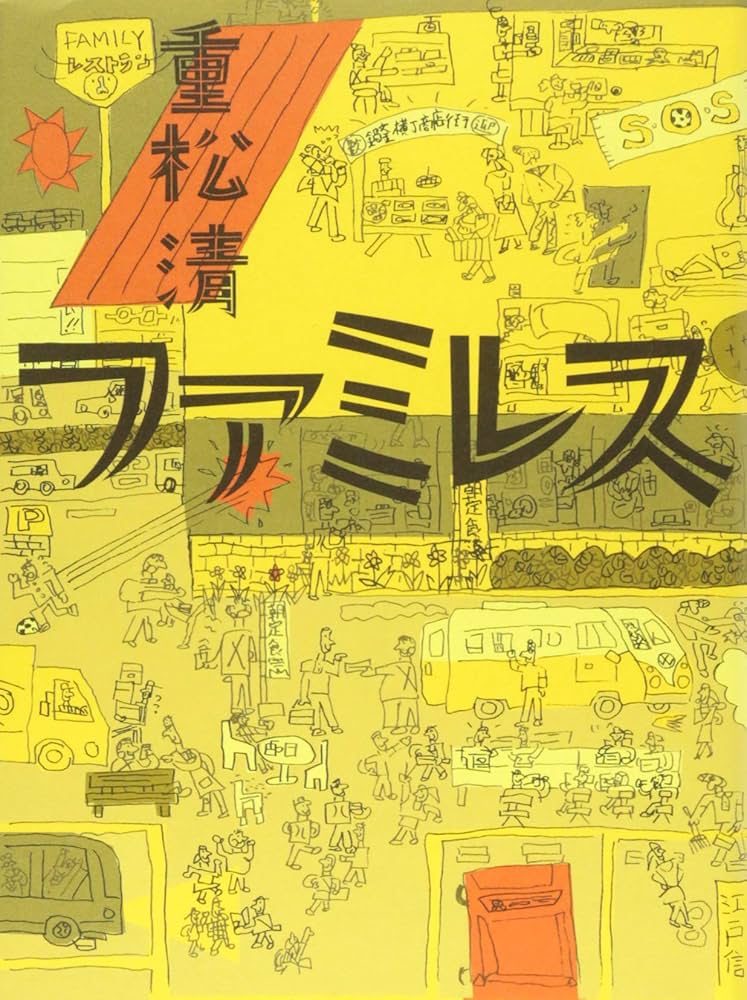
28位は、深夜のファミリーレストランを舞台に、そこに集う人々の人間模様を描いた連作短編集『ファミレス』です。様々な事情を抱えた人々が、夜のファミレスで交差し、またそれぞれの日常へと帰っていきます。
家出してきた高校生、夜勤明けのトラック運転手、別れ話をするカップル。彼らの会話や独白から、それぞれの人生が垣間見えます。何気ない日常の一コマを切り取りながら、現代社会が抱える孤独や不安を巧みに描き出しています。
派手な事件が起こるわけではありませんが、登場人物たちのリアルな息づかいが感じられる作品です。まるで深夜のファミレスの片隅で、人間観察をしているような気分になれる、味わい深い一冊です。



ファミレスって色々な人がいて面白いよね。みんなそれぞれの物語を持ってるんだなって思ったよ。
29位『希望ヶ丘の人びと』
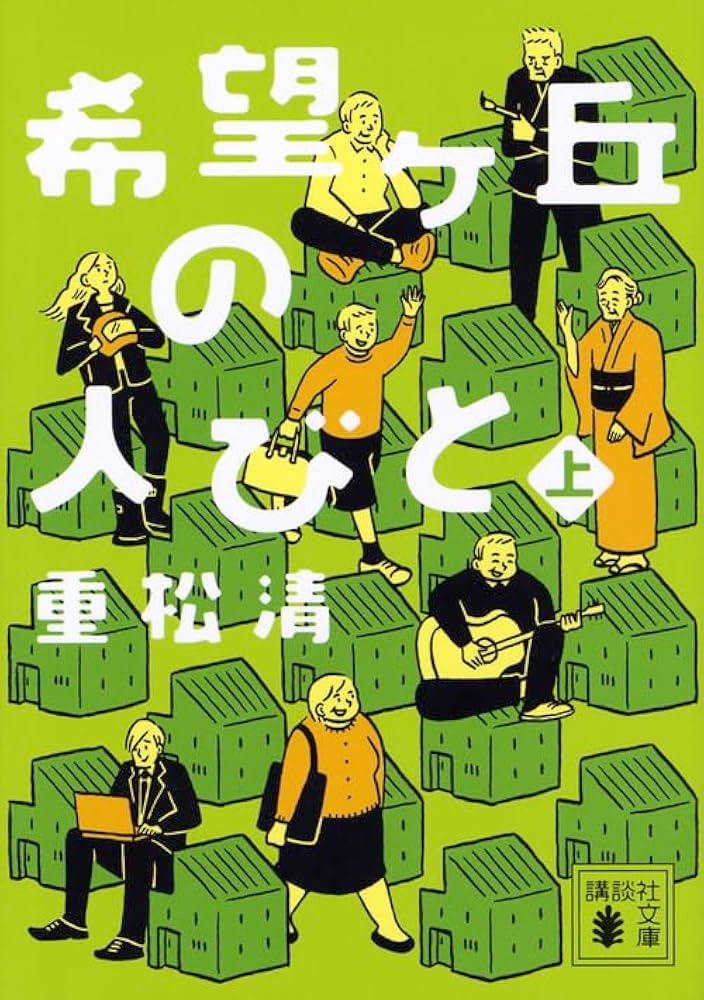
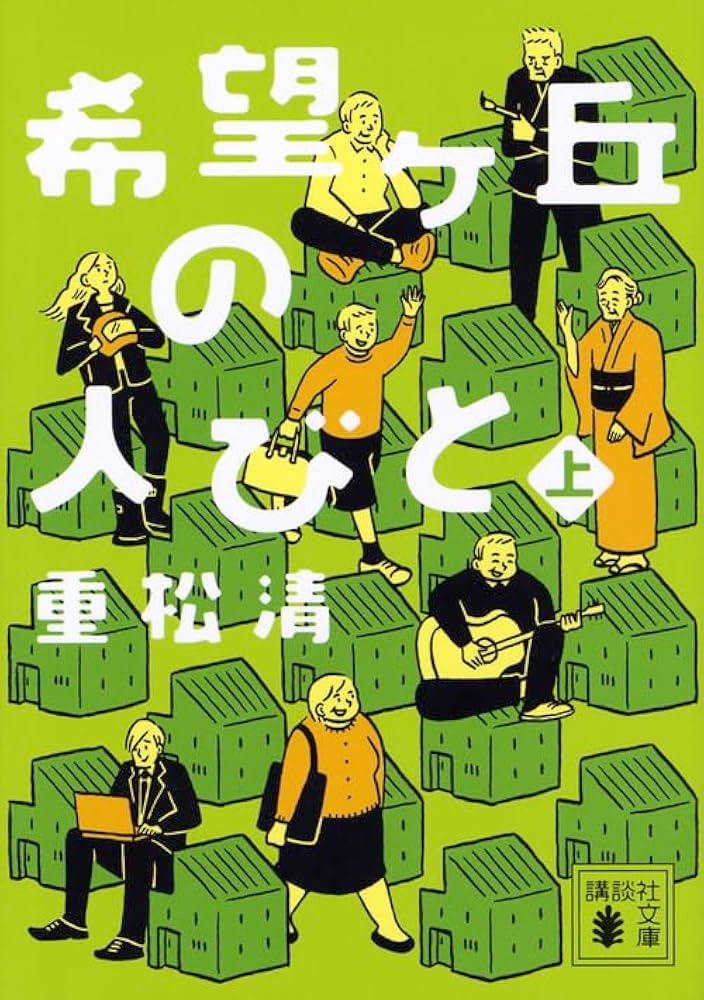
29位は、妻を亡くした主人公が、妻の故郷である「希望ヶ丘」に移り住み、子どもたちと新たな生活を始める物語『希望ヶ丘の人びと』です。ドラマ化もされ、その心温まるストーリーが人気を博しました。
主人公の田島は、亡き妻・圭子の面影を追い求め、彼女が育った町で暮らすことを決意します。そこで出会うのは、圭子のことを知る、個性豊かで温かい町の人々。彼らとの交流を通じて、田島と子どもたちは少しずつ悲しみを乗り越え、前を向いて歩き始めます。
大切な人を失った喪失感と、それでも続いていく日常。その中で見つける小さな希望の光が、優しく描かれています。再生と希望をテーマにした、重松作品の王道ともいえる感動の物語です。



希望ヶ丘って名前がいいよね。温かい人たちに囲まれてたら、また頑張れる気がするな。
30位『一人っ子同盟』
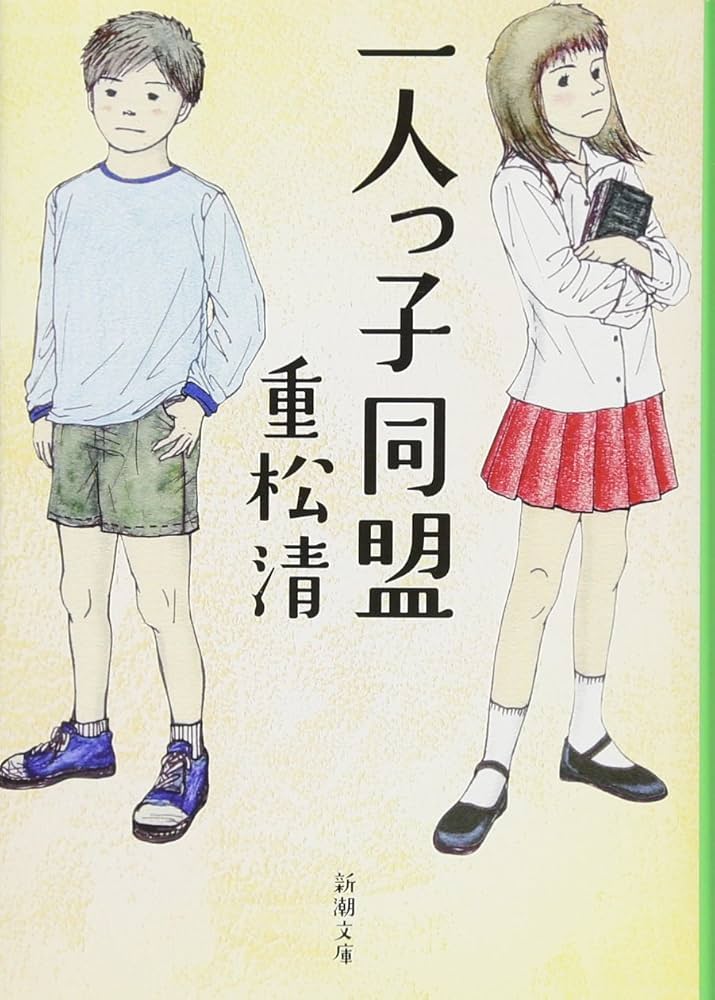
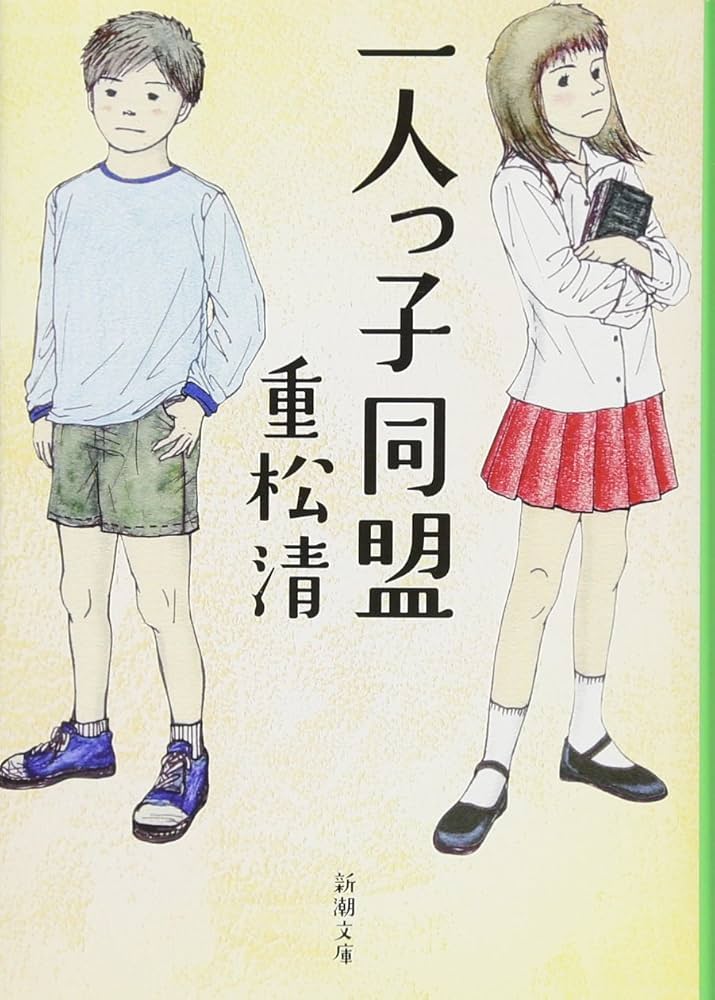
30位には、兄を亡くして「一人っ子」になってしまった少年が主人公の物語『一人っ子同盟』がランクイン。 突然の喪失と、それに伴う家族の変化を、子どもの視点から繊細に描いています。
大好きだったお兄ちゃんがいなくなり、悲しみに沈む両親。主人公の信也は、家の中に自分の居場所がないように感じてしまいます。そんな時、彼は同じようにきょうだいを亡くした経験を持つ仲間たちと「一人っ子同盟」を結成します。
子どもだからこそ感じる、言葉にできない寂しさや疎外感。そして、同じ痛みを分かち合う仲間との絆が、胸に迫ります。家族の死という重いテーマを扱いながらも、子どもたちの健気な姿に希望が感じられる作品です。



お兄ちゃんがいなくなるなんて考えただけで悲しいよ…。でも同じ気持ちの仲間がいたら強くなれるかもね。
31位『半パン・デイズ』
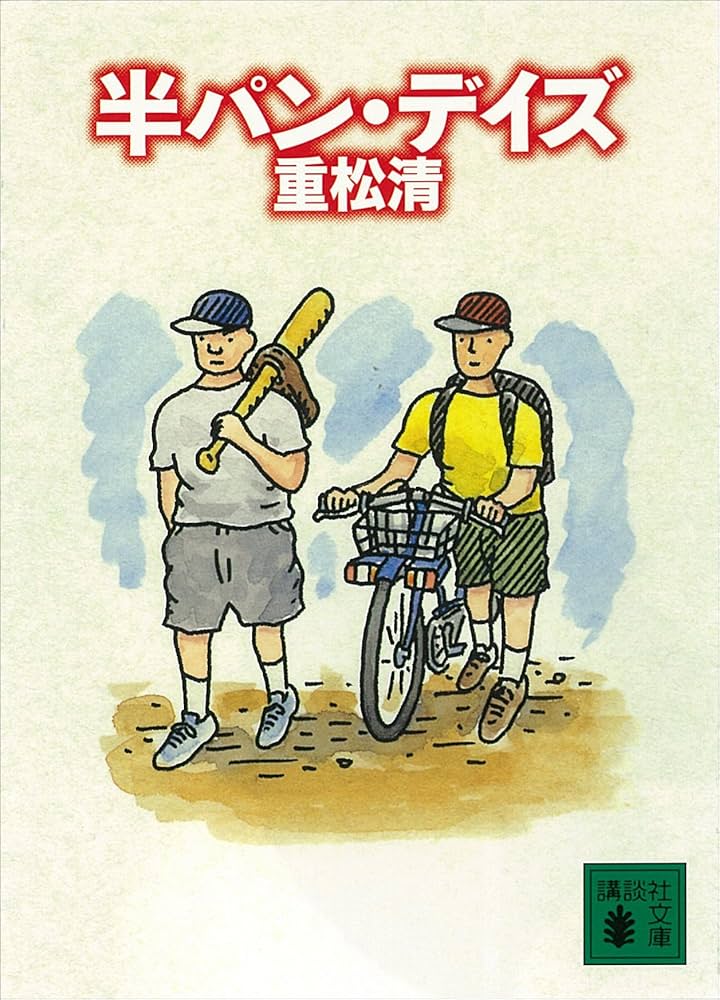
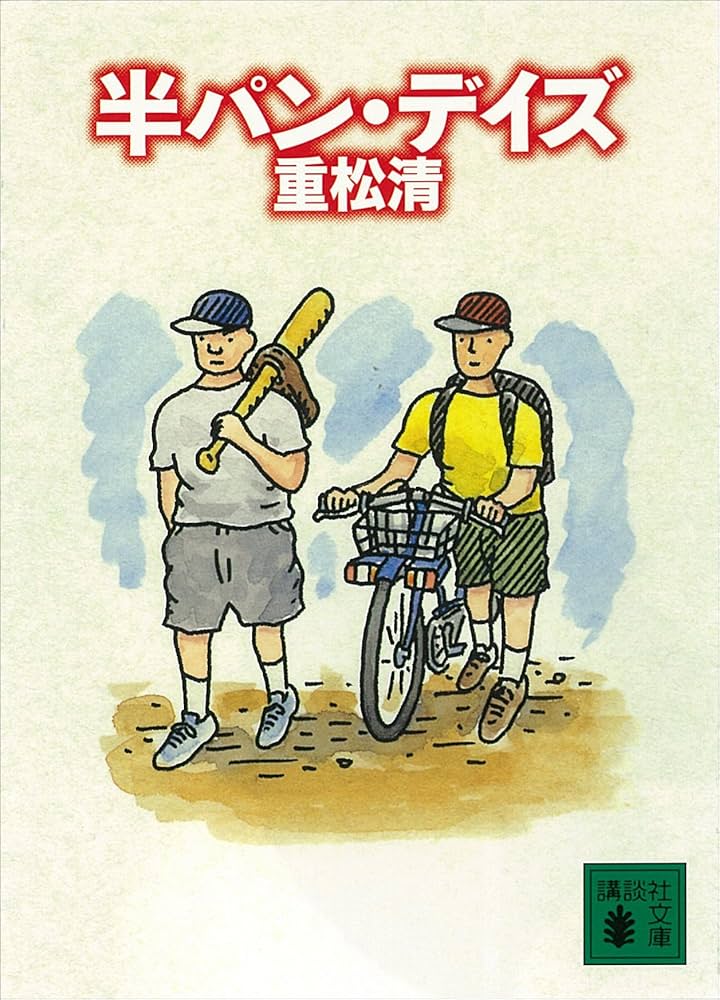
31位は、大人になりきれない大人たちの、ちょっぴり情けなくて愛おしい日常を描いた『半パン・デイズ』です。タイトルの「半パン」は、少年時代の象徴。いつまでも少年の心を忘れない(忘れられない)男たちが主人公です。
昔の仲間と集まっては、くだらない話で盛り上がる。そんな、どこにでもいるような中年男性たちの姿が、ユーモアたっぷりに描かれています。現実の厳しさに直面しながらも、古き良き時代を懐かしみ、友情を確かめ合う彼らの姿に、どこか共感してしまう人も多いのではないでしょうか。
重松作品の中では、比較的軽やかに読める一冊。クスッと笑えて、読後には少しだけ元気になれる、大人のための青春小説です。



大人になっても心は半パンをはいた少年のままなのかも。男の人たちの友情ってなんだか楽しそう!
32位『熱球』
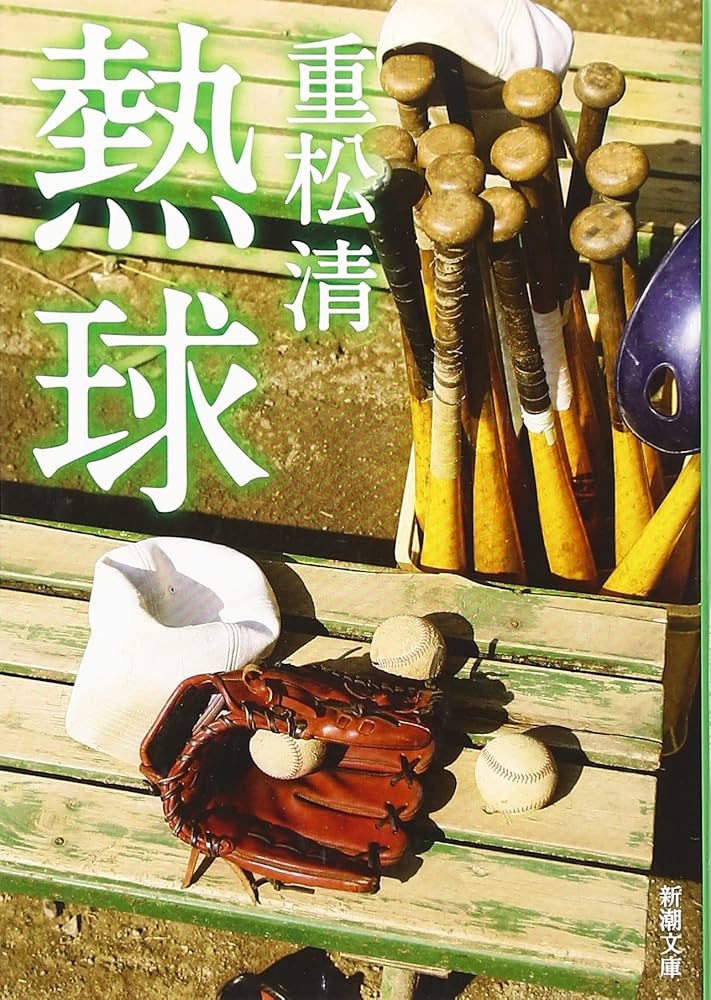
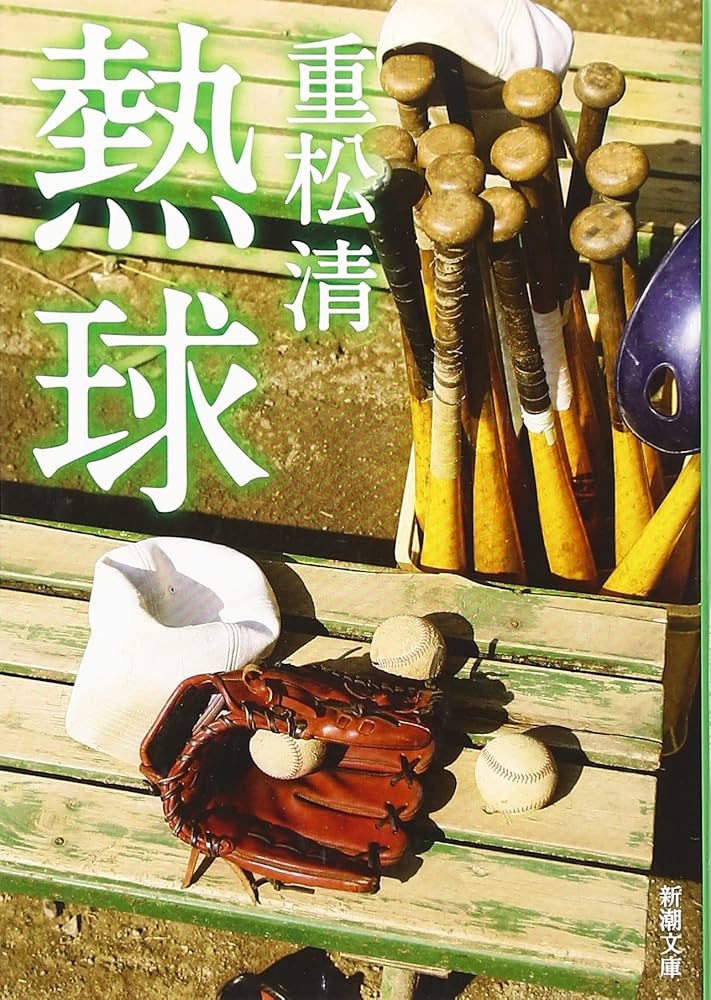
32位は、高校野球をテーマに、夢破れた者たちのその後の人生を描いた物語『熱球』です。重松作品には珍しい、スポーツ小説のジャンルに入ります。
かつて甲子園を目指したものの、地方大会で敗退した元高校球児たち。彼らが20年後、それぞれの人生を背負って再び集まり、マスターズ甲子園を目指します。過去の栄光と挫折、そして現在の自分自身と向き合う男たちの熱いドラマが繰り広げられます。
野球好きはもちろん、何かに夢中になった経験がある人なら、きっと胸が熱くなるはず。人生は勝ち負けだけではない。負けたからこそ見える景色があることを、この物語は教えてくれます。



もう一度夢を追いかけるって素敵だね!わたしも何か熱くなれることを見つけたいな。
33位『みぞれ』
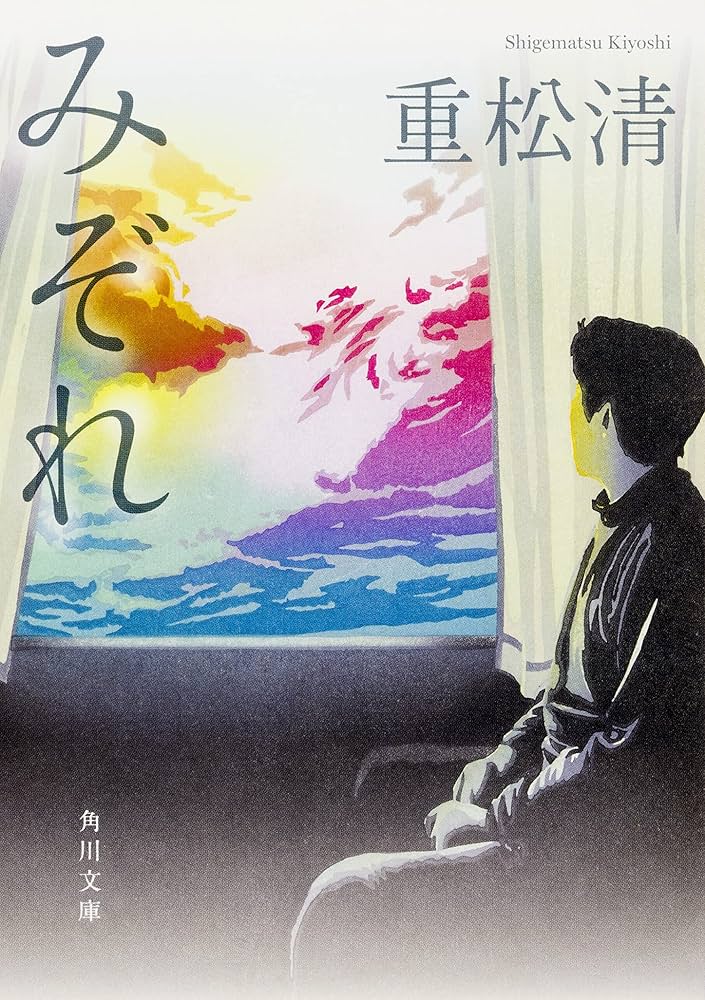
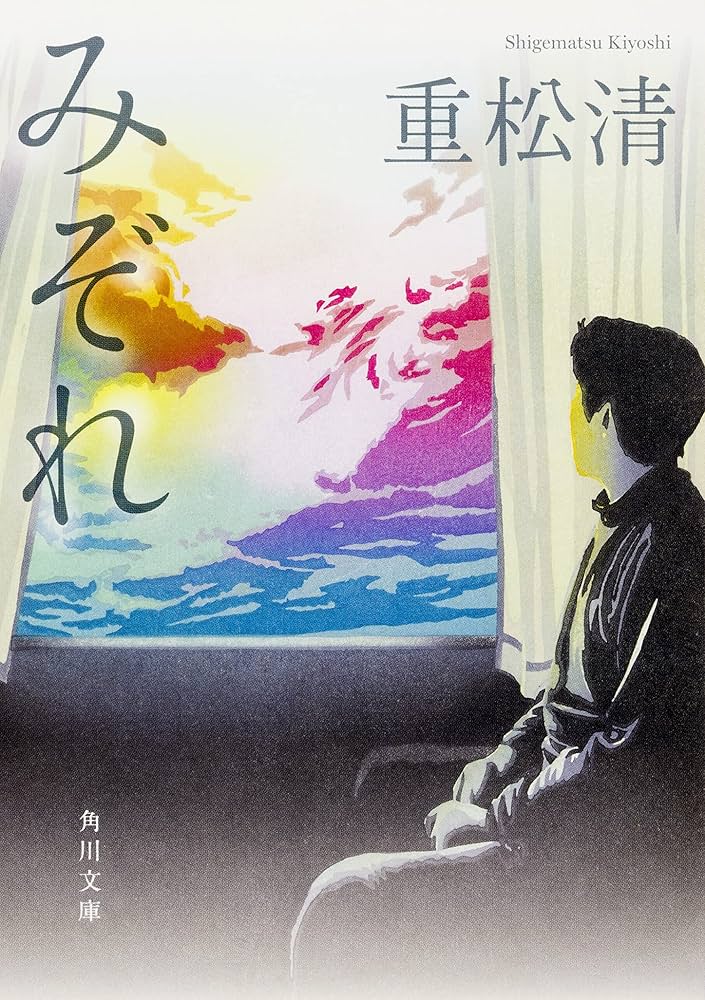
33位にランクインしたのは、冬の季節を背景に、人々の心の機微を描いた短編集『みぞれ』です。雪ではなく、雨でもない「みぞれ」のように、はっきりとしない、曖昧な感情がテーマになっています。
収録されているのは、人生の岐路に立ち、心に迷いを抱えた人々が登場する物語。彼らの心象風景が、冷たいみぞれの降る情景と重なり合います。切なく、ほろ苦い物語が多く、大人の読者の心に深く染み入る作品集です。
派手さはありませんが、日本語の繊細な美しさと、人間の感情の奥深さをじっくりと味わうことができます。寒い冬の夜に、温かい飲み物と共に読みたくなるような、静かな余韻を残す一冊です。



はっきりしない気持ちって誰にでもあるよね。そんな心にそっと寄り添ってくれる静かで綺麗な物語だよ。
34位『おくることば』
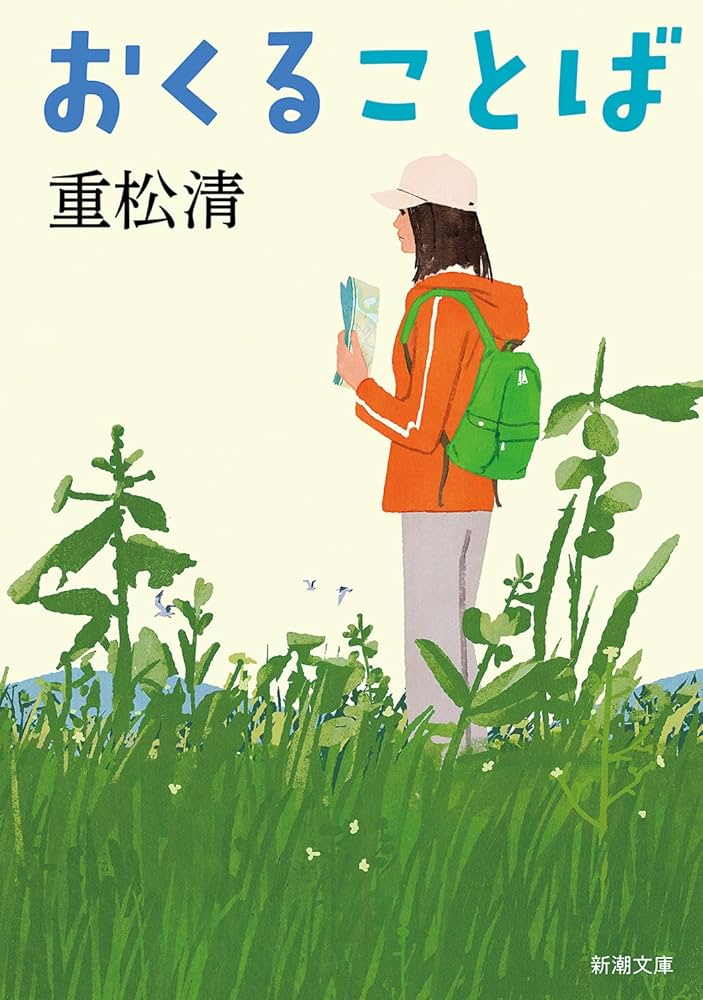
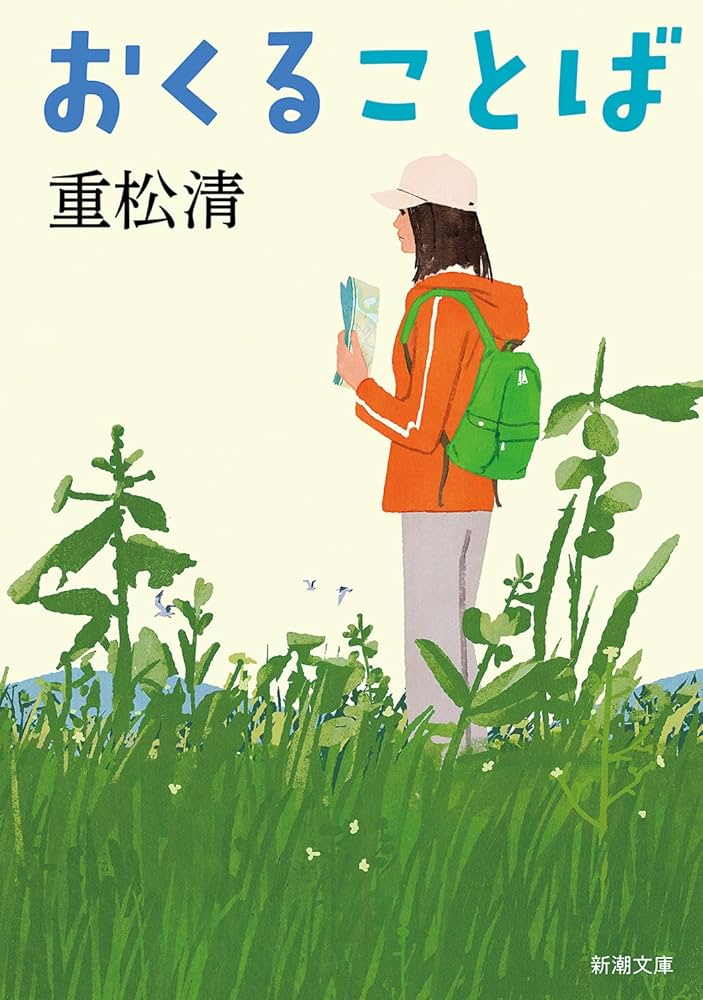
34位は、卒業や別れのシーズンに贈りたい、メッセージ性の強い短編集『おくることば』です。様々なシチュエーションでの「贈る言葉」が、物語の形で紡がれています。
卒業していく生徒へ、結婚する友人へ、そして亡くなった大切な人へ。それぞれの「おくることば」には、相手を想う温かい気持ちと、未来へのエールが込められています。重松さん自身が、読者一人ひとりに語りかけてくれているような、優しい気持ちになれる作品です。
人生の節目を迎える人へのプレゼントにも最適。言葉の持つ力を改めて感じさせてくれる、希望に満ちた一冊です。



誰かのために言葉を贈るって素敵なことだね。わたしも大切な人に心を込めた言葉を伝えたくなったよ。
35位『はるか、ブレーメン』


35位は、認知症になった祖父と、孫娘の心の交流を描いた物語『はるか、ブレーメン』です。高齢化社会という現代的なテーマを、重松さんらしい温かい視点で描いています。
少しずつ記憶を失っていくおじいちゃん。そんなおじいちゃんが、昔飼っていた動物たちの名前を呼びながら、まるで「ブレーメンの音楽隊」のように、どこかへ旅立とうとします。孫娘のはるかは、おじいちゃんの心の世界に寄り添い、その最後の旅を見守ろうとします。
認知症という切ない現実を、ファンタジックな要素を交えて優しく包み込んだ物語。老いていくこと、そして家族の絆について、深く考えさせられる一冊です。



おじいちゃんの心には素敵な音楽隊がいるんだね。切ないけどすごく優しい気持ちになれるお話だよ。
36位『きみの町で』
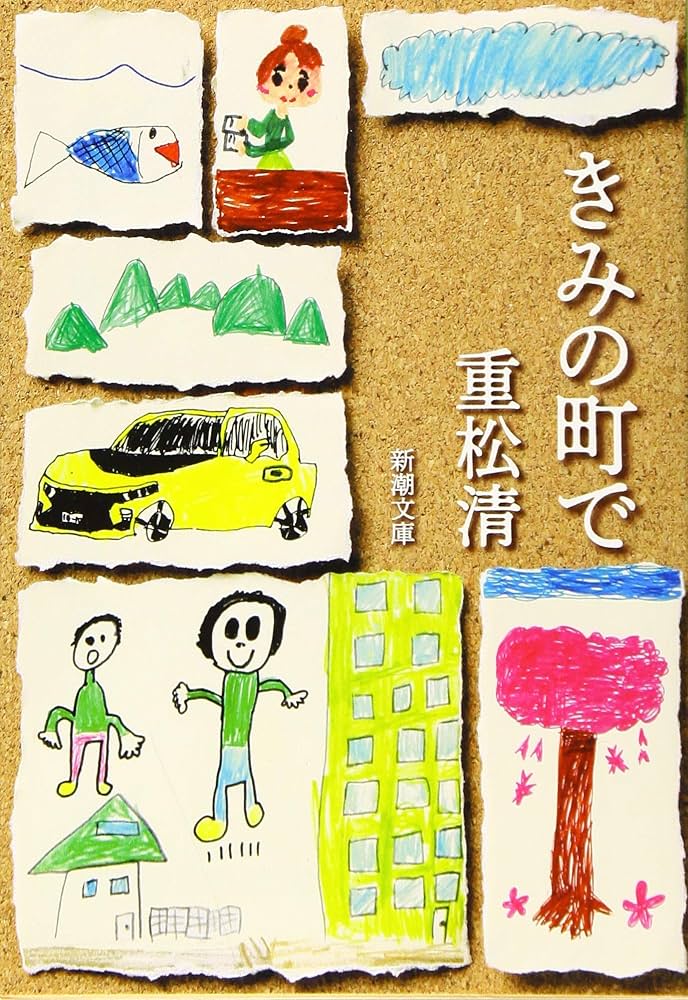
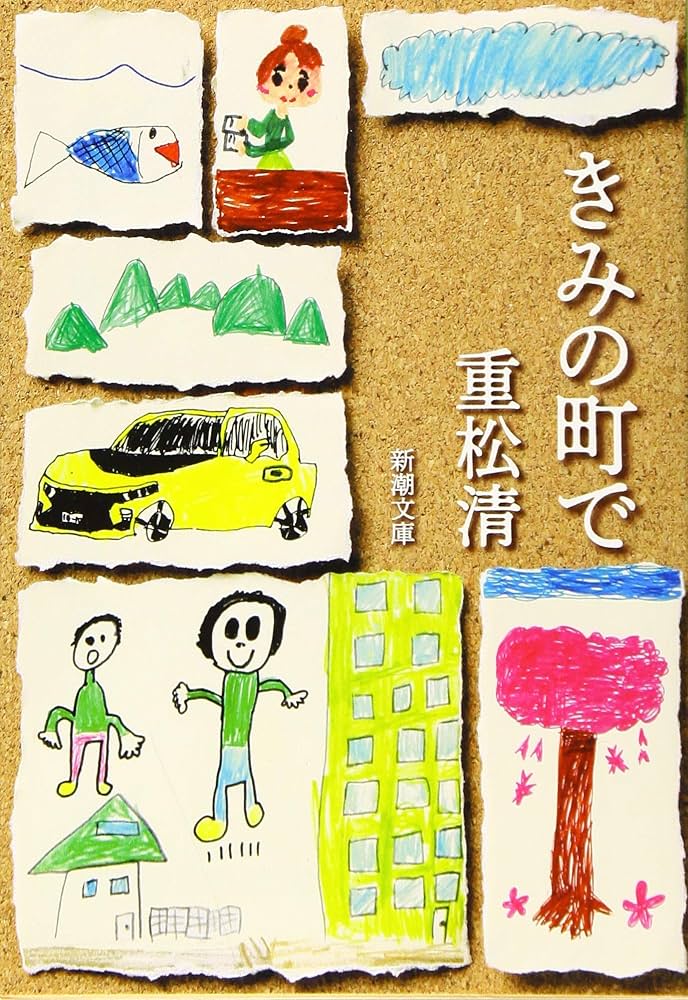
36位には、地方の町を舞台に、そこに生きる人々の日常を丁寧に描いた連作短編集『きみの町で』がランクインしました。 私たちが暮らす、何気ない「町」が物語の主役です。
それぞれの短編は、同じ町に住む、異なる世代の人々を主人公にしています。彼らの人生が、町の風景の中で静かに交錯していきます。どこにでもあるような地方都市の日常が、かけがえのない物語の舞台であることを教えてくれます。
自分の故郷や、今住んでいる町に思いを馳せながら読みたくなる作品です。足元にある日々の暮らしの愛おしさに、改めて気づかせてくれるでしょう。



わたしの住んでる町にも色々な物語があるんだろうな。普段の景色がちょっと違って見えてくるよ。
37位『めだか、太平洋を往け』
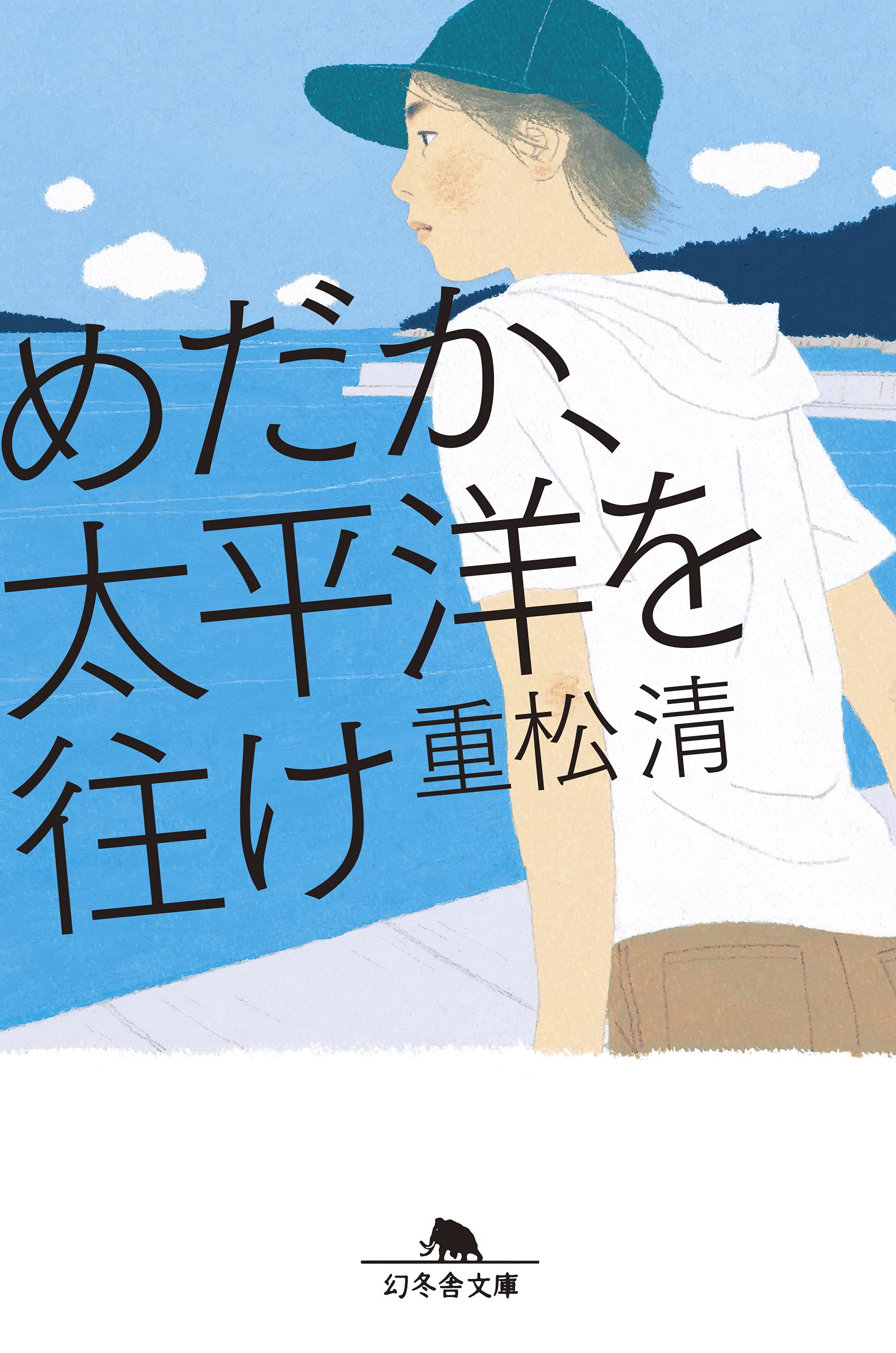
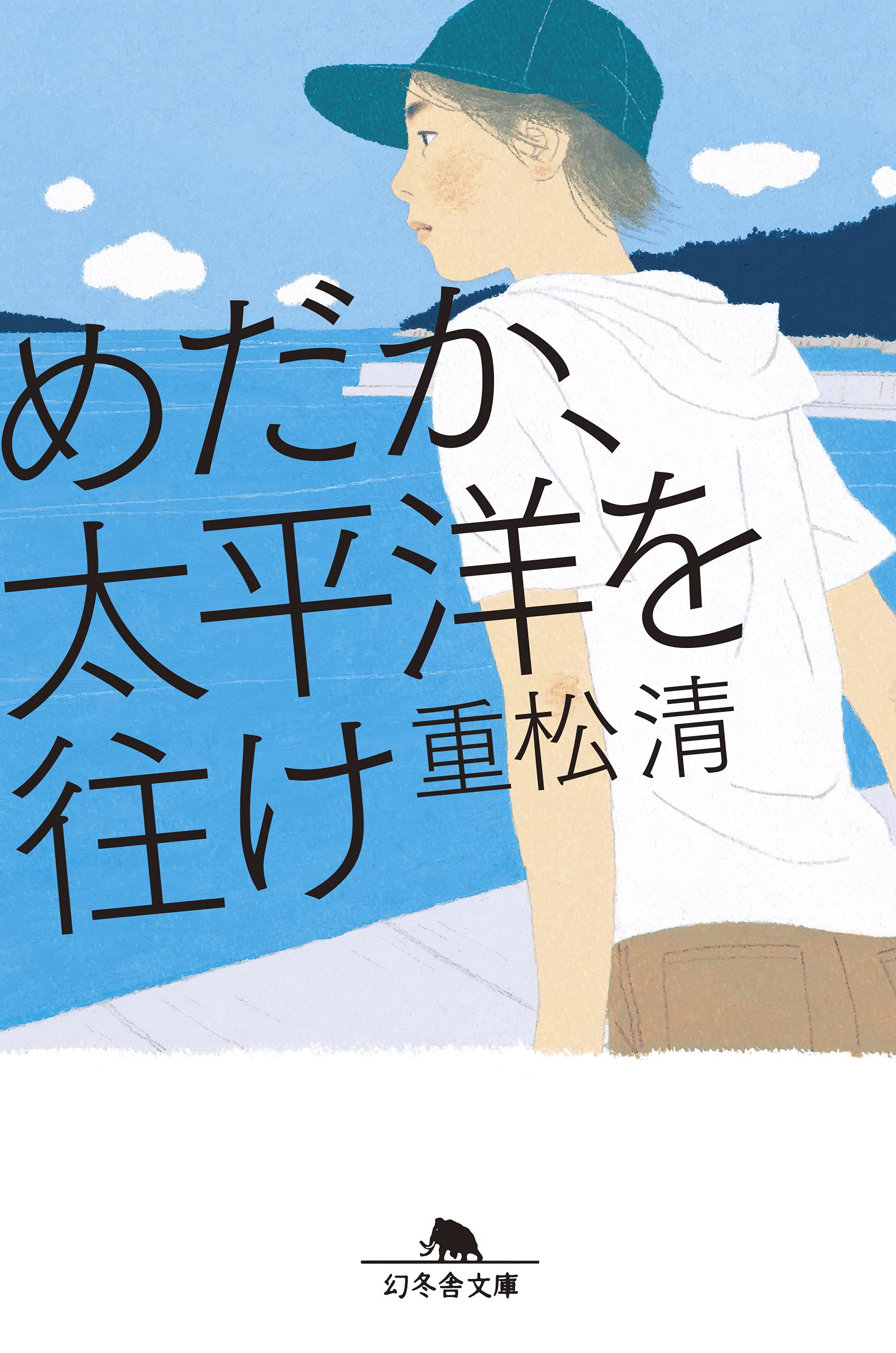
37位は、東日本大震災をテーマにした作品『めだか、太平洋を往け』です。 震災で心に傷を負った人々が、再生へと向かう姿を描いています。
主人公は、被災地にボランティアとして訪れた中学生。そこで彼は、津波で流された「めだか」を探す少女と出会います。小さな命を探すことを通じて、少年少女たちが震災という大きな現実と向き合い、未来への希望を見出していく姿が描かれています。
重松さんが、この大きな悲劇とどう向き合い、物語として紡いだのか。作家としての真摯な姿勢が感じられる、重要な一冊です。



大きな悲しみから小さな希望を見つけるって勇気がいるよね。めだか、見つかるといいな。
38位『答えは風のなか』
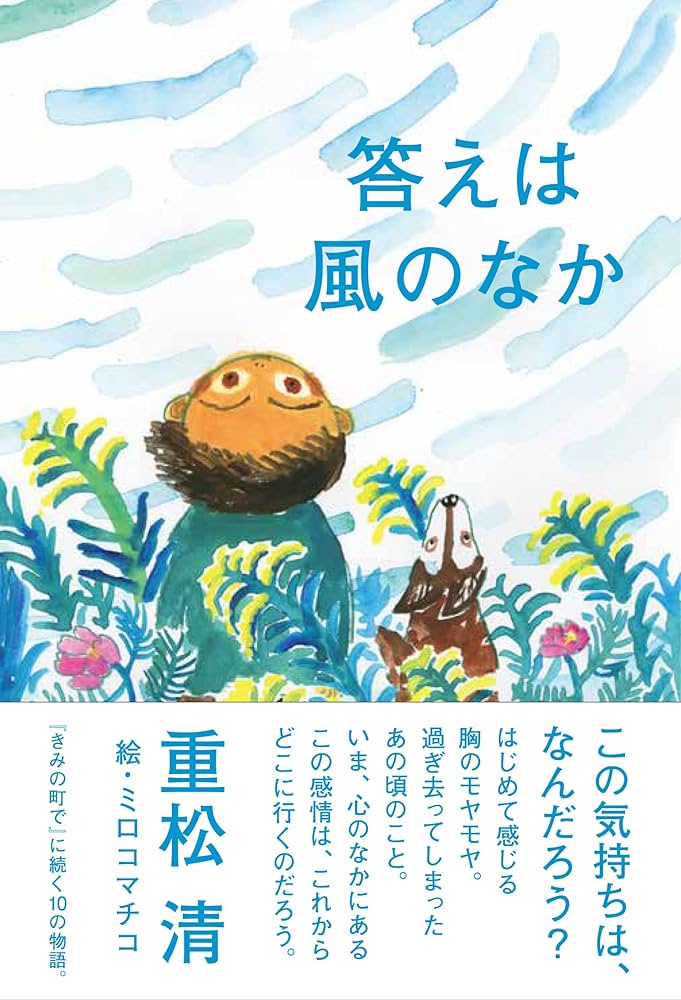
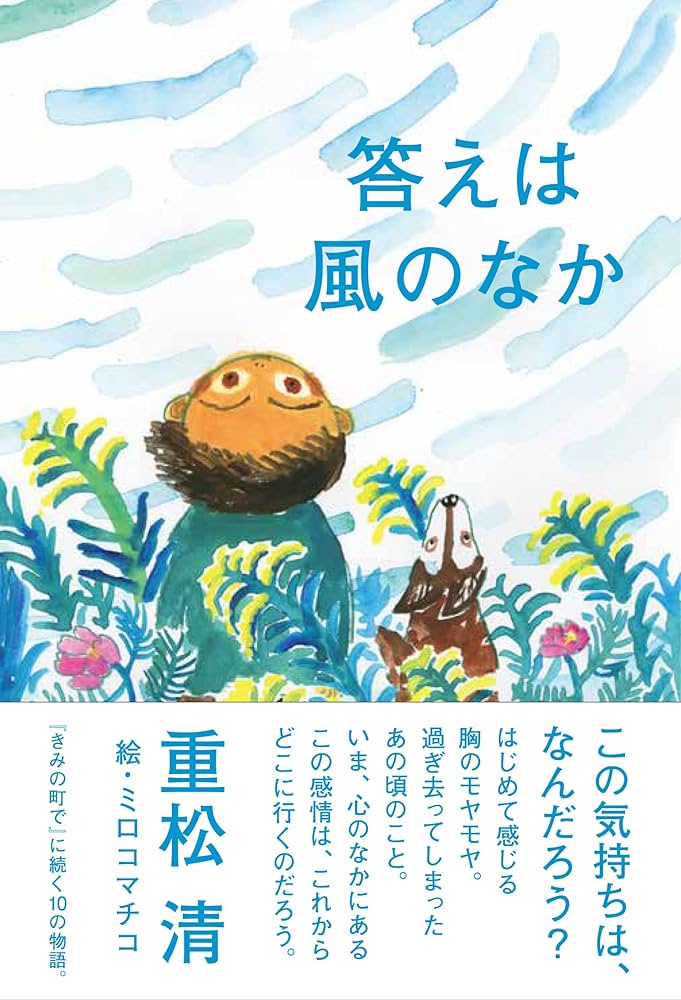
38位は、悩める若者たちに向けて、重松さんが人生相談に答える形式で書かれたエッセイ集『答えは風のなか』です。小説ではありませんが、その温かいメッセージは多くの読者の心を打ちました。
友人関係、恋愛、将来の夢。10代が抱える様々な悩みに、重松さんは真正面から向き合い、自身の経験も交えながら、誠実な言葉で答えていきます。「すぐに答えは見つからなくてもいいんだよ」という、優しいメッセージが心に響きます。
まるで頼れる先輩や先生に相談しているような、温かい気持ちになれる一冊。悩みを抱える若い世代はもちろん、かつて若者だった大人たちにも、多くの気づきを与えてくれるでしょう。



悩んでる時にこうやって話を聞いてもらえたら心強いだろうな。答えは急いで見つけなくてもいいんだね。
39位『かぞえきれない星の、その次の星』
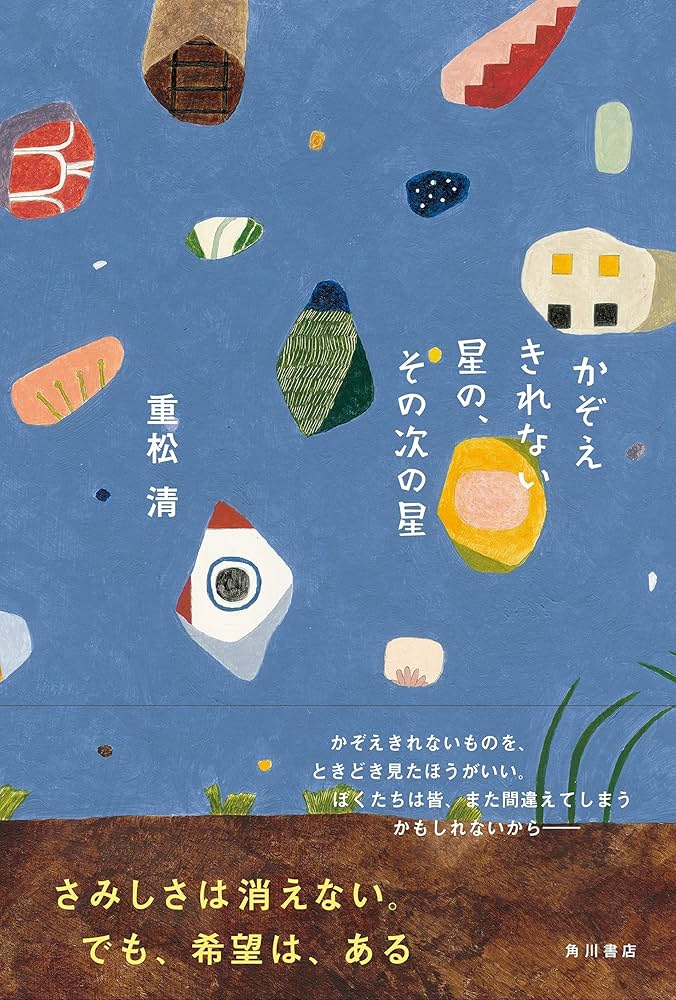
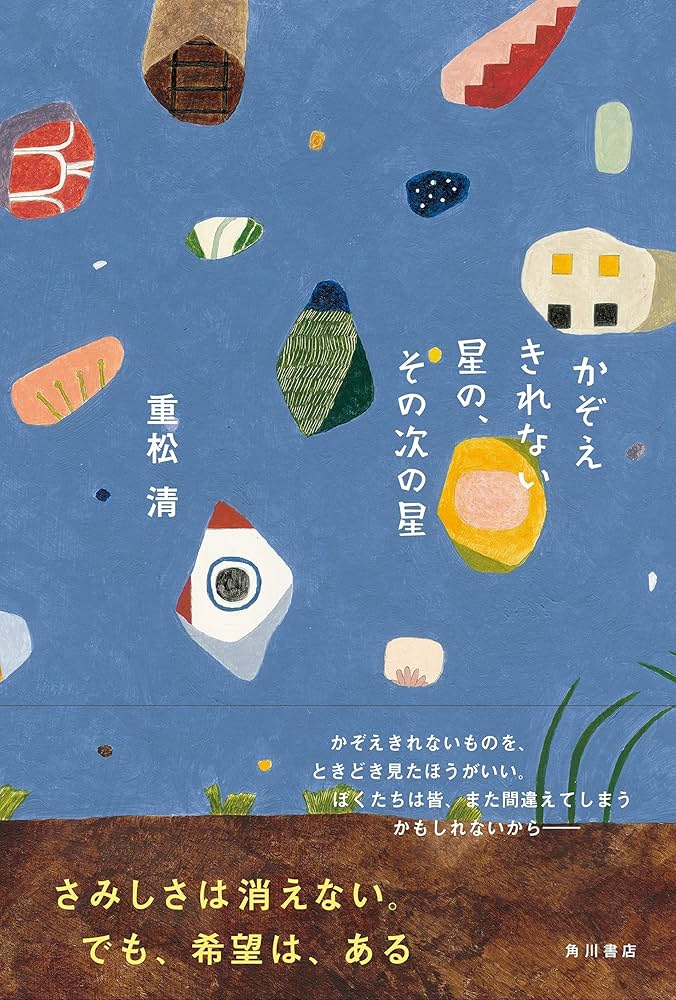
39位にランクインしたのは、2021年に刊行された比較的新しい作品『かぞえきれない星の、その次の星』です。 コロナ禍という、私たちが今まさに直面している現実を背景に物語が描かれています。
会いたい人に会えない、当たり前だった日常が失われてしまった世界。そんな中で、人々がどう繋がり、希望を見出していくのか。現代社会の閉塞感と、それでも失われない人間の温かさを描いた、タイムリーな作品集です。
困難な時代を生きる私たちに、そっと寄り添い、明日への光を示してくれるような物語。今だからこそ読むべき、重松清さんの新たな代表作の一つと言えるでしょう。



大変な時代だけど物語を読むと心が軽くなる気がするよ。悲しみの次には希望があるんだね。
40位『赤ヘル1975』
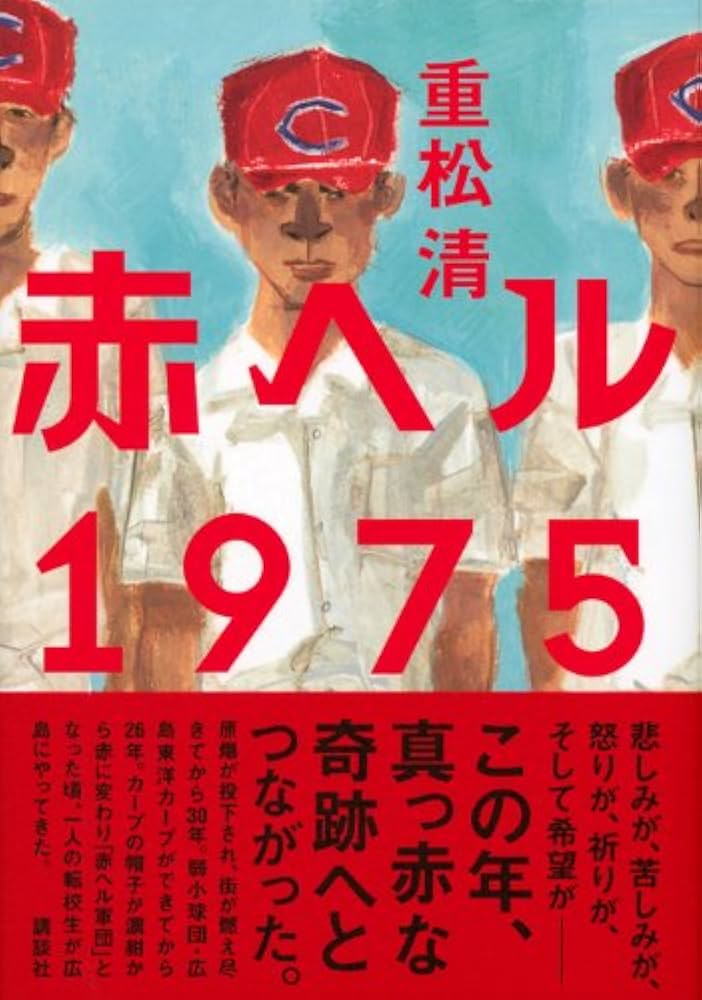
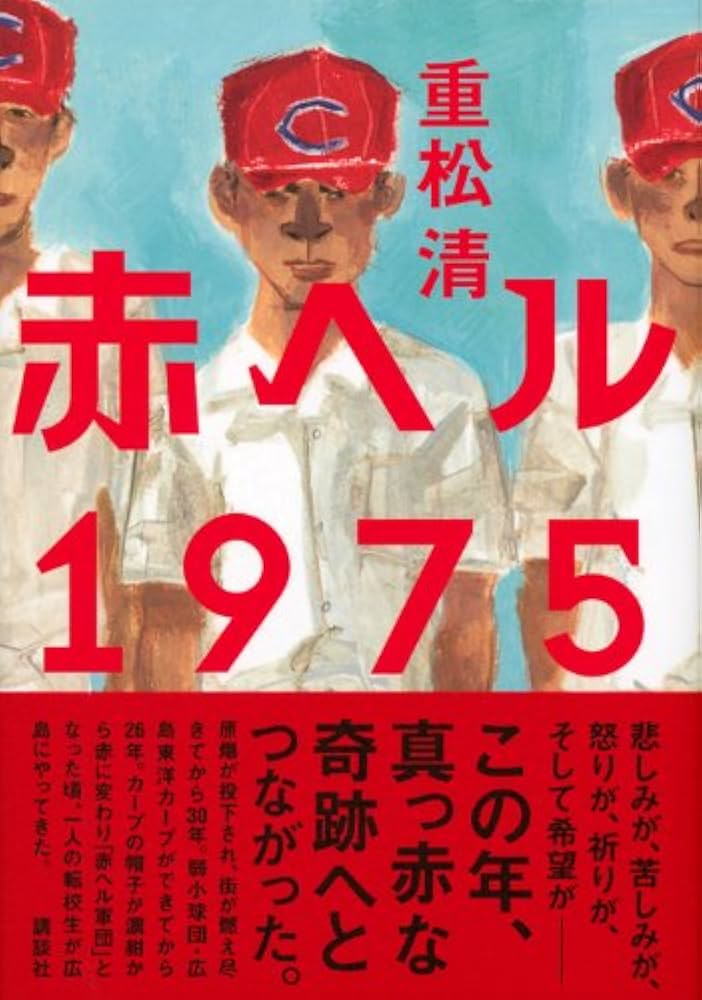
ランキングの最後を飾る40位は、広島東洋カープが初優勝を遂げた1975年を舞台にした、熱い野球小説『赤ヘル1975』です。岡山県出身で、熱心なカープファンとしても知られる重松さんならではの一冊です。
物語は、カープの初優勝に熱狂する少年たちの視点で描かれます。「赤ヘル軍団」の快進撃に、自分の夢や希望を重ね合わせる少年たち。当時の広島の熱気が、生き生きと伝わってきます。
単なる野球小説にとどまらず、少年時代の熱い思いや、故郷への愛情が詰まった青春グラフィティとなっています。カープファンはもちろん、野球を知らない人でも、あの頃の少年たちの興奮と感動を共有できるはずです。



好きなチームが優勝するって最高の瞬間だよね!少年たちの熱い気持ちが伝わってきてワクワクしちゃった!
おわりに:重松清の物語と共に、明日への一歩を
重松清さんのおすすめ小説ランキングTOP40、いかがでしたでしょうか。家族の愛、友情、人生の再生、そして社会が抱える問題まで、その多彩なテーマに改めて驚かされた方も多いかもしれません。
どの作品にも共通しているのは、困難な状況の中でも懸命に生きる人々への、温かく優しい眼差しです。 彼の物語は、私たちの心の柔らかい部分に触れ、忘れていた大切な感情を思い出させてくれます。そして、読み終えた後には、不思議と「明日も頑張ろう」という静かな勇気が湧いてくるのです。
もしあなたが今、何かに悩み、立ち止まりそうになっているのなら、ぜひこの中から一冊手に取ってみてください。重松さんの物語が、あなたの心にそっと寄り添い、次の一歩を踏み出すための道しるべとなってくれるはずです。