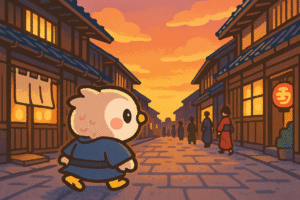あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】中村彰彦のおすすめ小説ランキングTOP12

中村彰彦とは?作品の魅力と選び方のポイント
中村彰彦(なかむら あきひこ)は、1949年栃木県生まれの小説家です。東北大学文学部を卒業後、文藝春秋で編集者として勤務したのち、1991年から執筆活動に専念。1994年には『二つの山河』で第111回直木賞を受賞するなど、数々の文学賞に輝いています。
中村彰彦作品の大きな魅力は、歴史の敗者や、これまで光が当たらなかった人物に焦点を当てている点です。特にライフワークといえるのが会津藩に関する著作で、幕末維新という激動の時代を生きた人々の姿を、史実に基づいて丹念に描き出しています。そのため、歴史の教科書には載らない、人間味あふれる登場人物たちの生き様に触れられます。
中村彰彦の小説を選ぶ際は、まず自分の好きな時代や歴史上の人物が登場する作品から手に取ってみるのがおすすめです。特に幕末や新選組、会津藩に興味がある方なら、どの作品も夢中になって読み進められるでしょう。また、直木賞受賞作の『二つの山河』や、他の受賞作から読み始めるのも、氏の作風を知る良いきっかけになります。
中村彰彦のおすすめ小説ランキングTOP12
ここからは、歴史小説ファンを魅了し続ける中村彰彦のおすすめ小説を、ランキング形式でご紹介します。
数々の名作の中から、特に評価の高い12作品を厳選しました。幕末の動乱を描いた作品から、知られざる武将の生涯に光を当てたものまで、多彩なラインナップとなっています。あなたの心に響く一冊が、きっと見つかるはずです。
1位『二つの山河』
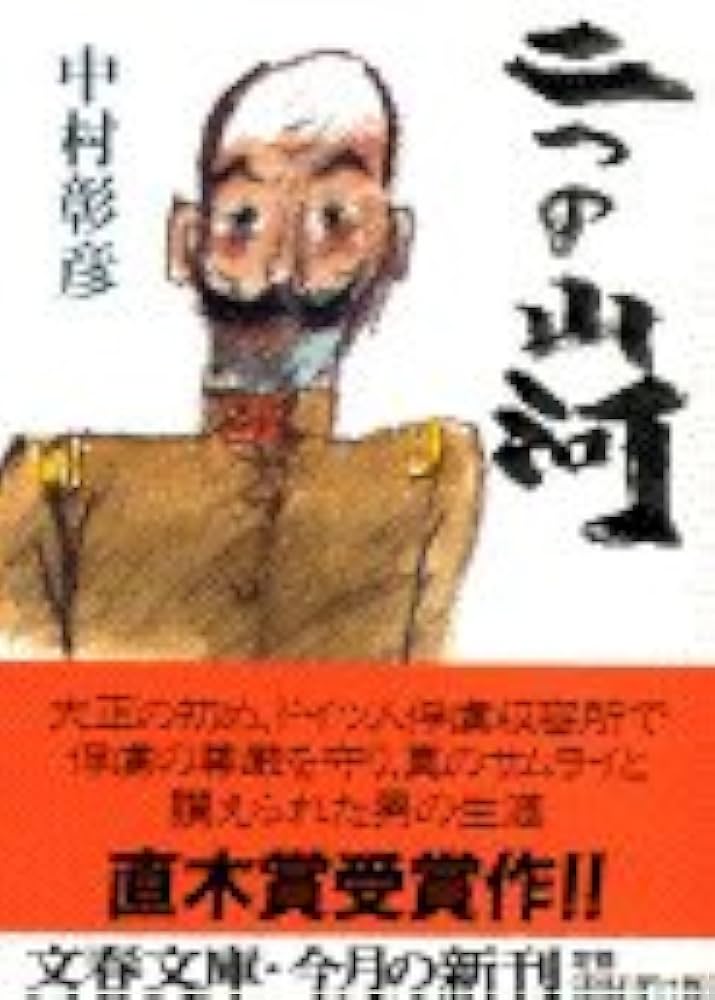
中村彰彦の代表作であり、1994年に第111回直木賞を受賞した不朽の名作です。
敗者となってしまった彼らが、それぞれの信念を胸に激動の時代をどう生き抜いたのかが、重厚な筆致で描かれています。歴史の大きな流れの中で翻弄されながらも、自らの志を貫こうとする主人公たちの姿に、胸が熱くなること間違いありません。歴史小説の醍醐味が詰まった一冊として、多くの読者から支持されています。
 ふくちい
ふくちい信念を貫くって難しいけど、だからこそ彼らの生き様が心に響くんだよね…。わたしも物語の番人として頑張らなくちゃ!
2位『名君の碑 保科正之の生涯』
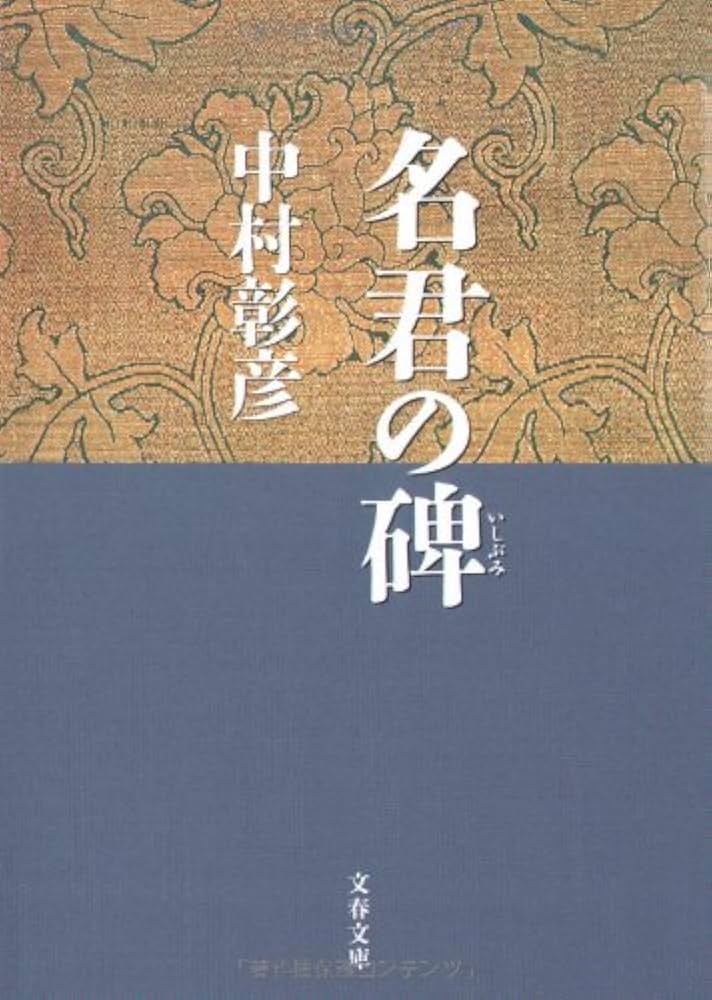
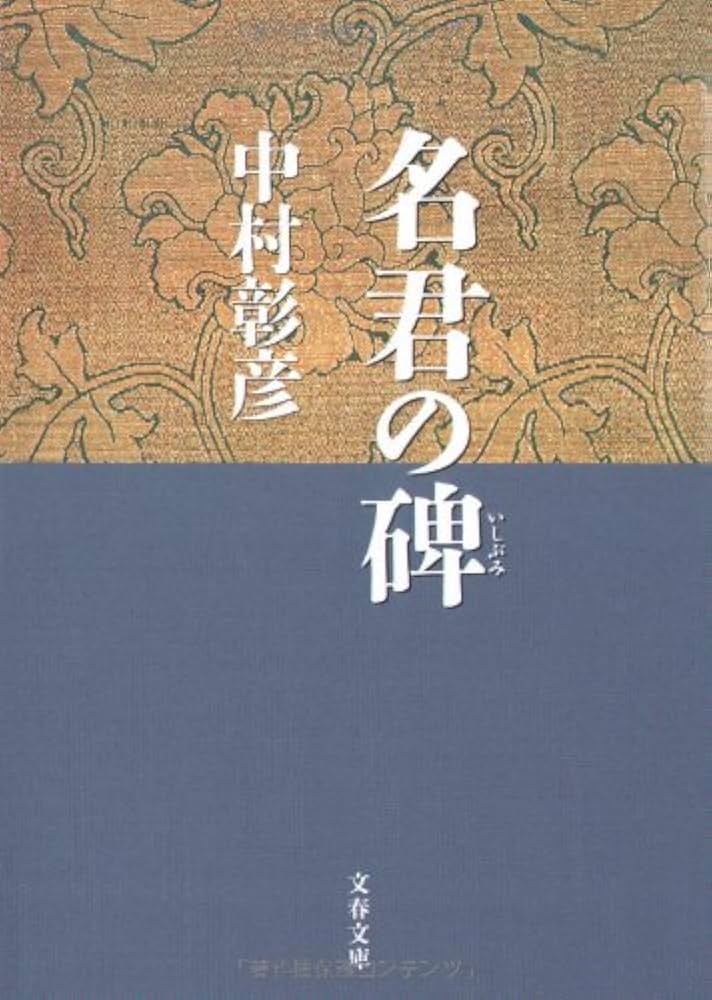
『名君の碑 保科正之の生涯』は、江戸時代初期の会津藩主、保科正之の生涯を描いた歴史小説です。徳川家光の異母弟という立場でありながら、生涯をかけて徳川将軍家を支え続けた名君の姿が描かれています。
武断政治から文治政治へと移行する時代の転換期に、彼がどのようにして善政を敷き、領民から慕われる存在となったのか。その誠実で私利私欲のない生き方は、現代を生きる私たちにも多くの学びを与えてくれます。組織のリーダーや、人の上に立つ立場の人にこそ読んでほしい一冊です。



保科正之みたいな上司がいたら、仕事も楽しくなりそうだなあ。民のために尽くすって、まさに理想のリーダーだよね。
3位『落花は枝に還らずとも』
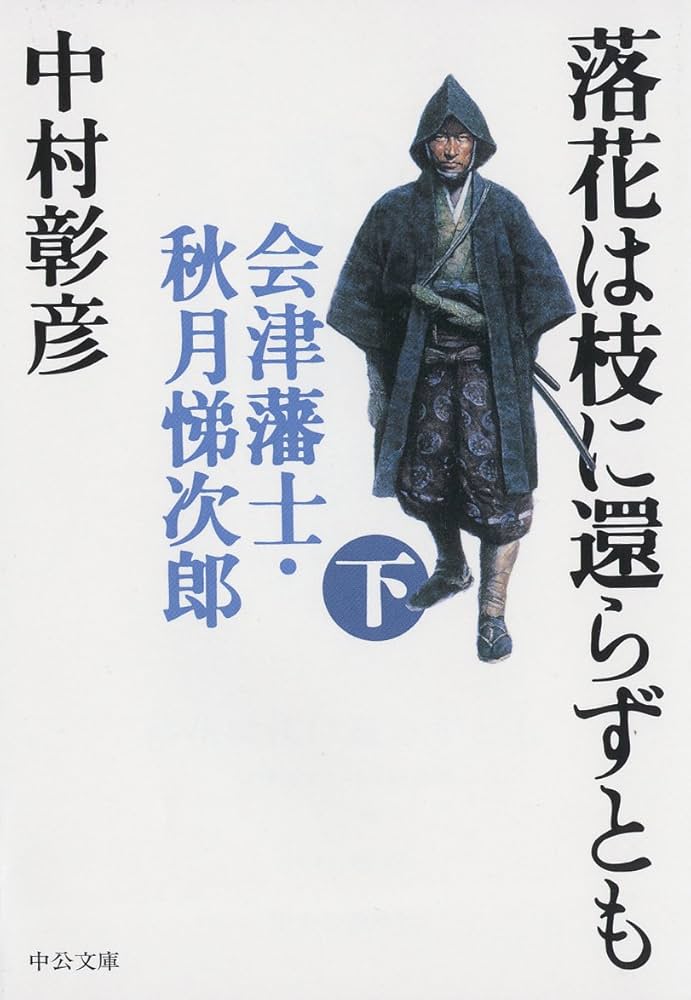
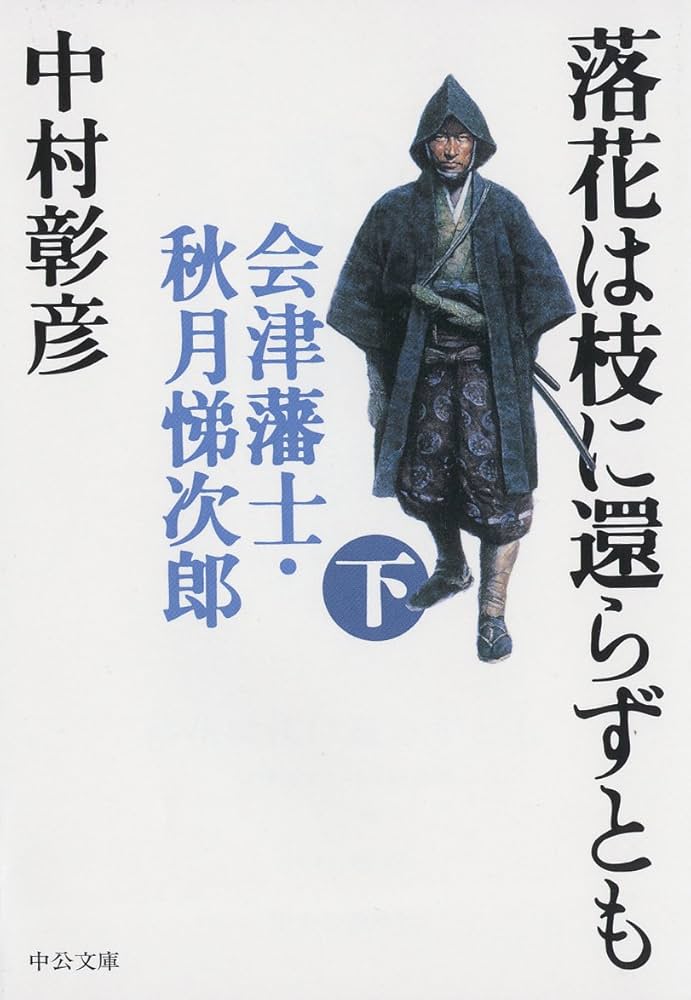
2005年に第24回新田次郎文学賞を受賞した『落花は枝に還らずとも』は、幕末の剣士・伊庭八郎の壮絶な生涯を描いた作品です。彼は、隻腕となりながらも最後まで幕府への忠義を貫き、戊辰戦争を戦い抜きました。
この小説では、伊庭八郎という一人の武士の生き様を通して、時代の大きなうねりと、その中で失われていったものの悲しみが鮮やかに描き出されています。彼の潔い生き方と、最後まで武士としての誇りを失わなかった姿は、多くの読者の心を打ちました。幕末の志士たちの熱い魂に触れたい方におすすめです。



片腕になっても戦い続けるなんて、すごい精神力だよね!伊庭八郎の生き様、かっこよすぎて痺れる!
4位『五左衛門坂の敵討』
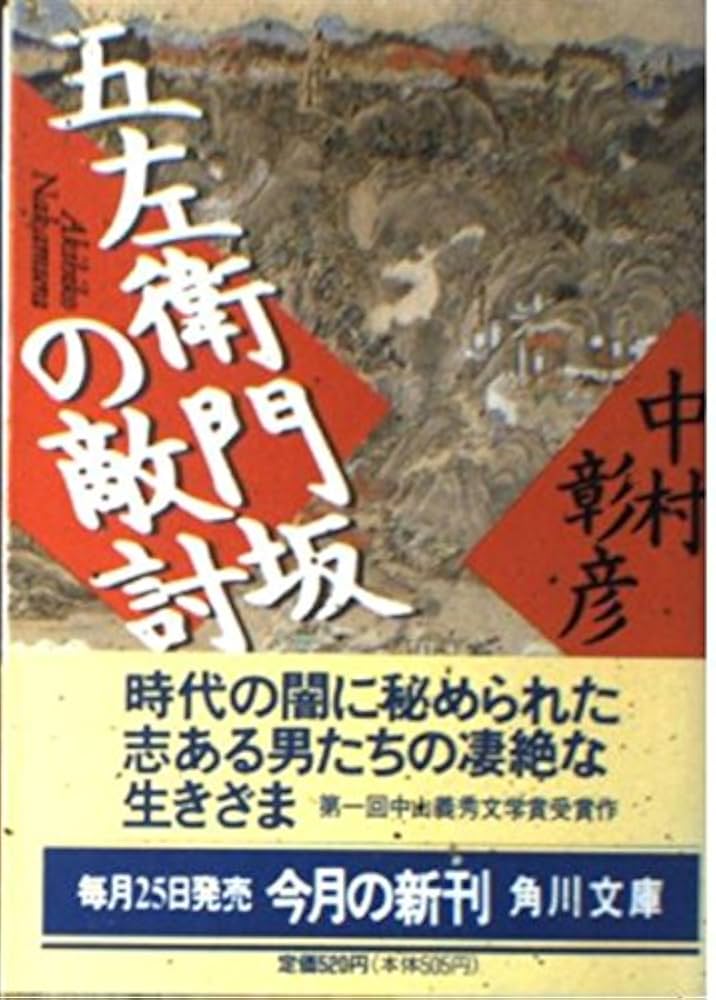
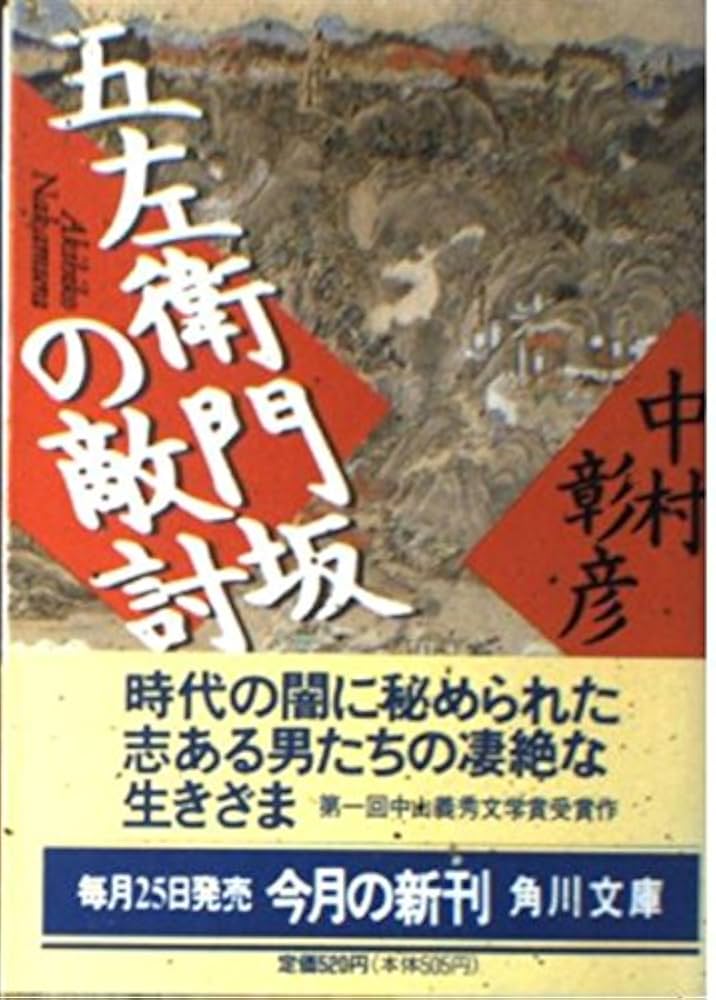
『五左衛門坂の敵討』は、1993年に第1回中山義秀文学賞を受賞した作品です。この小説は、赤穂浪士の討ち入りとはまた違う、ある無名の会津藩士による敵討ちの史実を発掘し、物語として描き出したものです。
武士の意地と執念がぶつかり合う、手に汗握る展開が魅力です。中村彰彦は、歴史の中に埋もれた名もなき人々のドラマを描き出すことを得意としており、本作はその真骨頂ともいえる一冊。忠義や名誉といった武士の価値観を深く理解することができるでしょう。



有名な話だけが歴史じゃないんだって、改めて気づかされるなあ。こういう知られざる物語を見つけ出すのが、わたしの使命でもあるんだ。
5位『明治新選組』
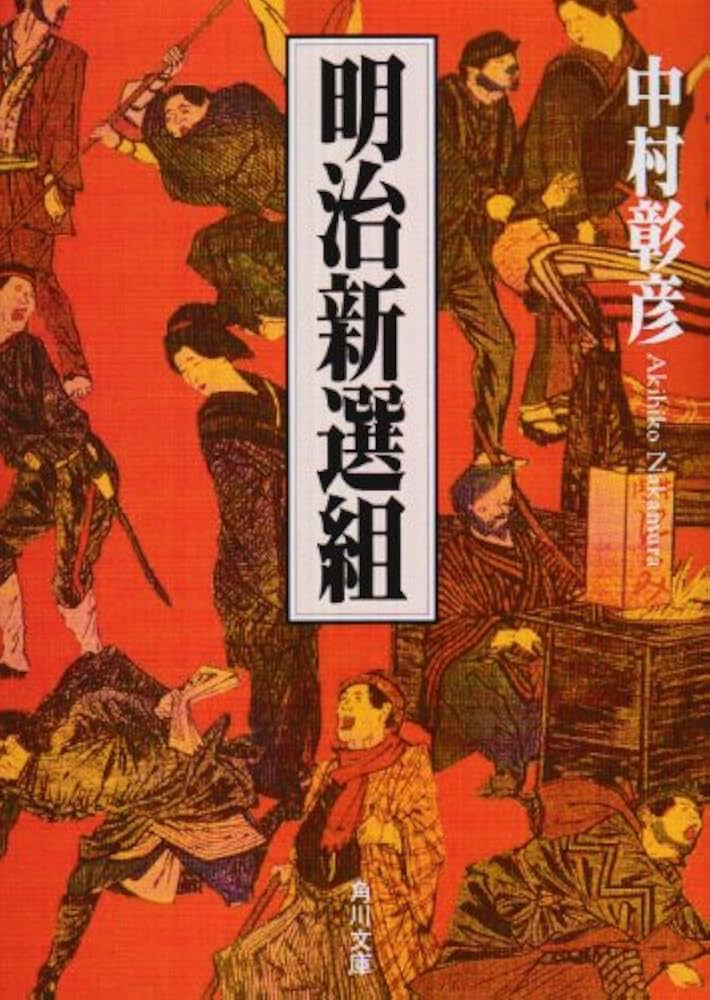
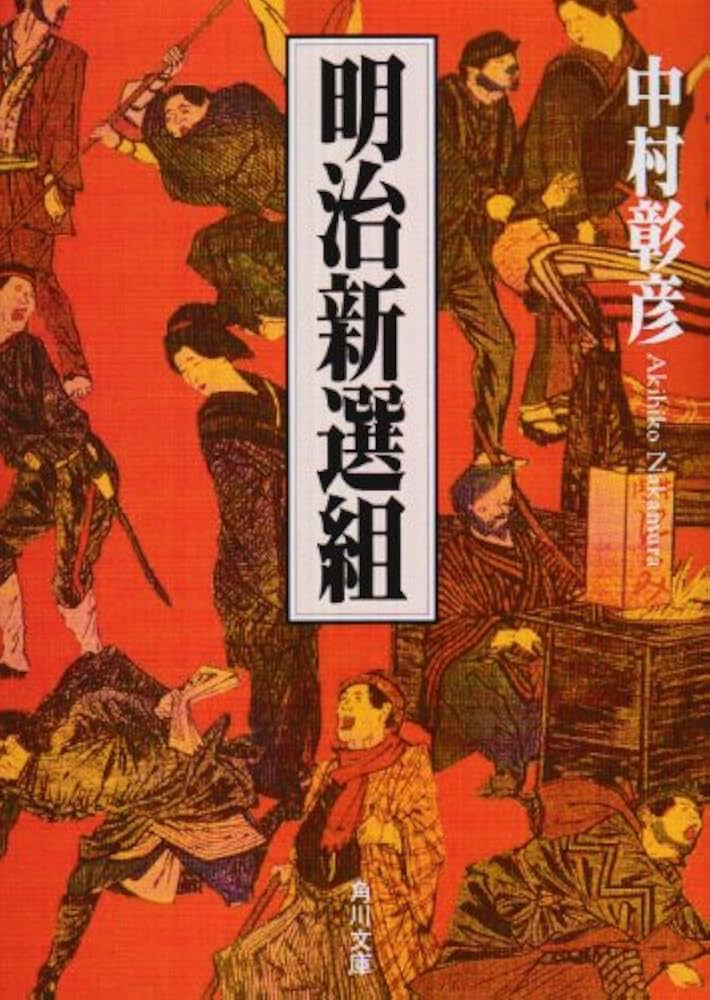
1987年に第10回エンタテインメント小説大賞を受賞した、中村彰彦の初期の代表作です。新選組といえば幕末の動乱期に活躍したイメージが強いですが、この小説では戊辰戦争後、明治の世を生き抜いた元隊士たちに焦点が当てられています。
永倉新八や斎藤一といった有名な隊士たちが、新しい時代とどう向き合い、生きていったのか。かつての仲間との絆や、武士としての誇りを胸に秘めながら、激動の時代を生きる彼らの姿は、新選組ファンならずとも胸を打たれるものがあります。新選組の「その後」を描いた、貴重な一作です。



時代が変わっても生き抜くって大変だよね。元新選組っていうだけで、色々な苦労があったんだろうなあ。
6位『山川家の兄弟 浩と健次郎』
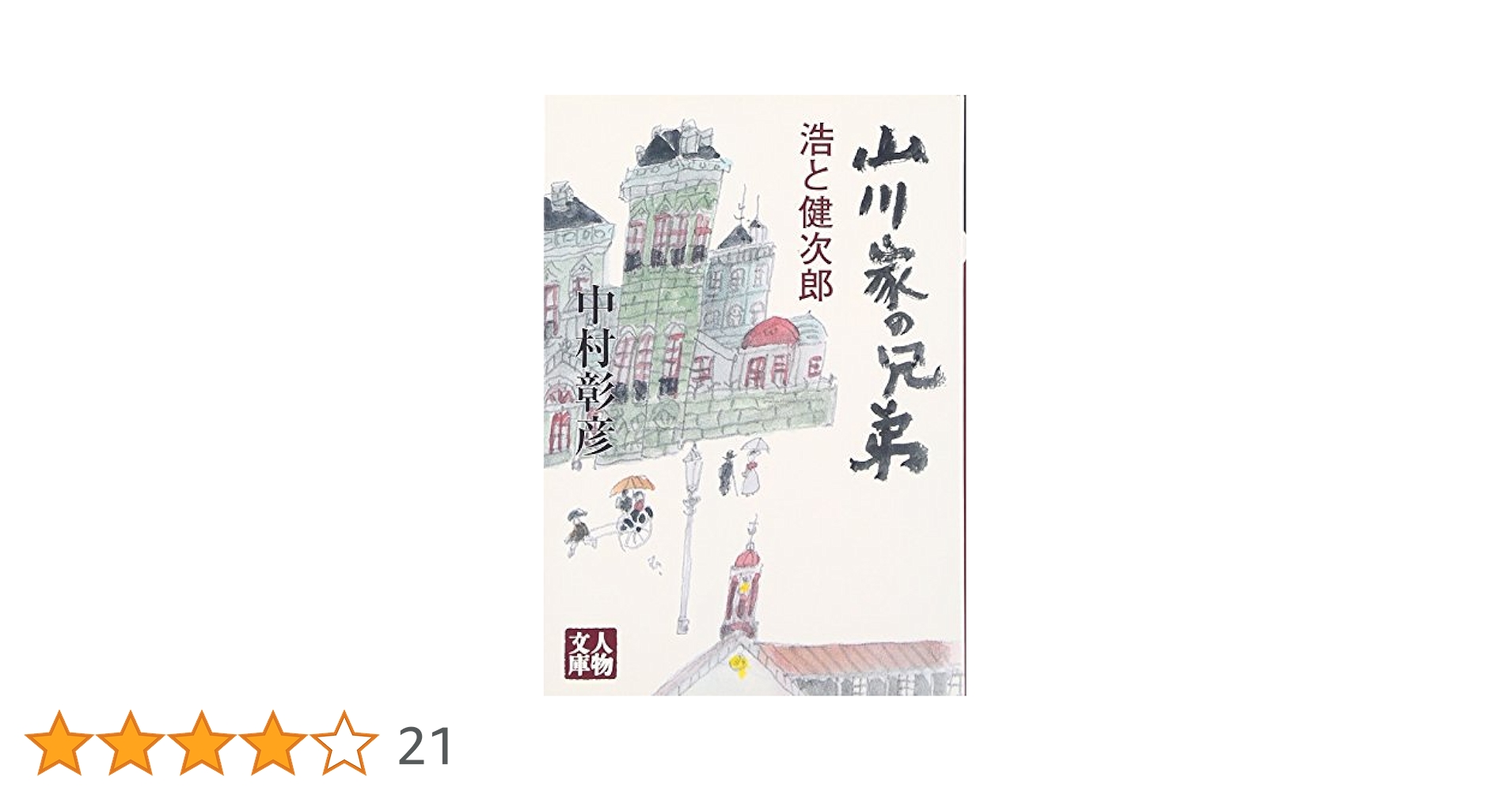
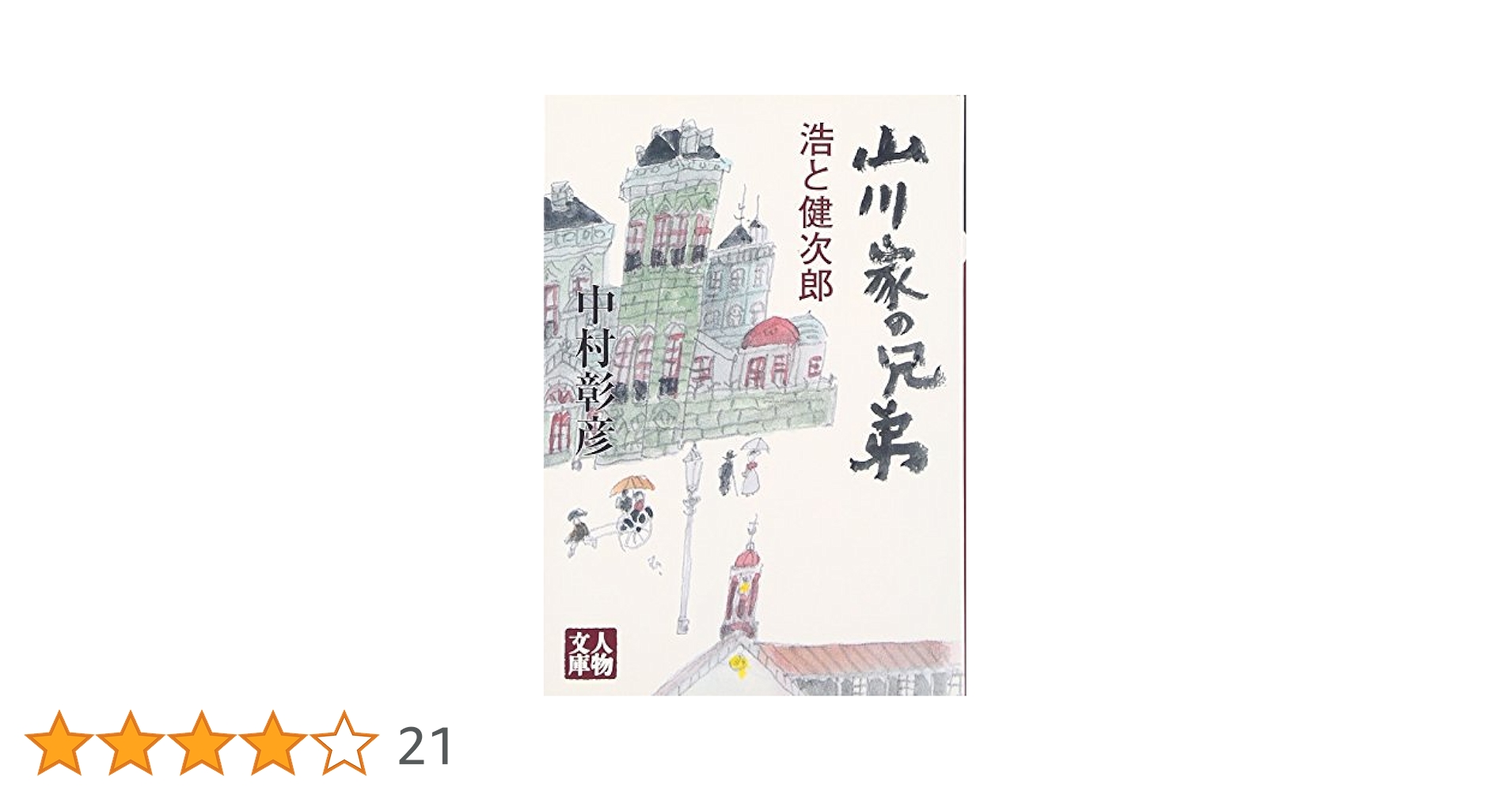
『山川家の兄弟 浩と健次郎』は、戊辰戦争を戦った会津藩の山川兄弟の生涯を描いた物語です。兄の浩は軍人として、弟の健次郎は教育者として、それぞれ異なる道を進みながらも、明治という新しい日本のために尽力しました。
会津藩が「賊軍」とされた後、彼らがいかにして逆境を乗り越え、日本の近代化に貢献していったのかが丁寧に描かれています。兄弟の絆、そして故郷・会津への想いを胸に、それぞれの分野で道を切り拓いていく姿は、私たちに勇気を与えてくれます。会津武士の精神性の高さを感じられる作品です。



兄弟で違う道に進んでも、お互いを支え合って新しい時代を築いていくなんて、感動的だよ…。わたしも兄弟が欲しかったな。
7位『鬼官兵衛烈風録』
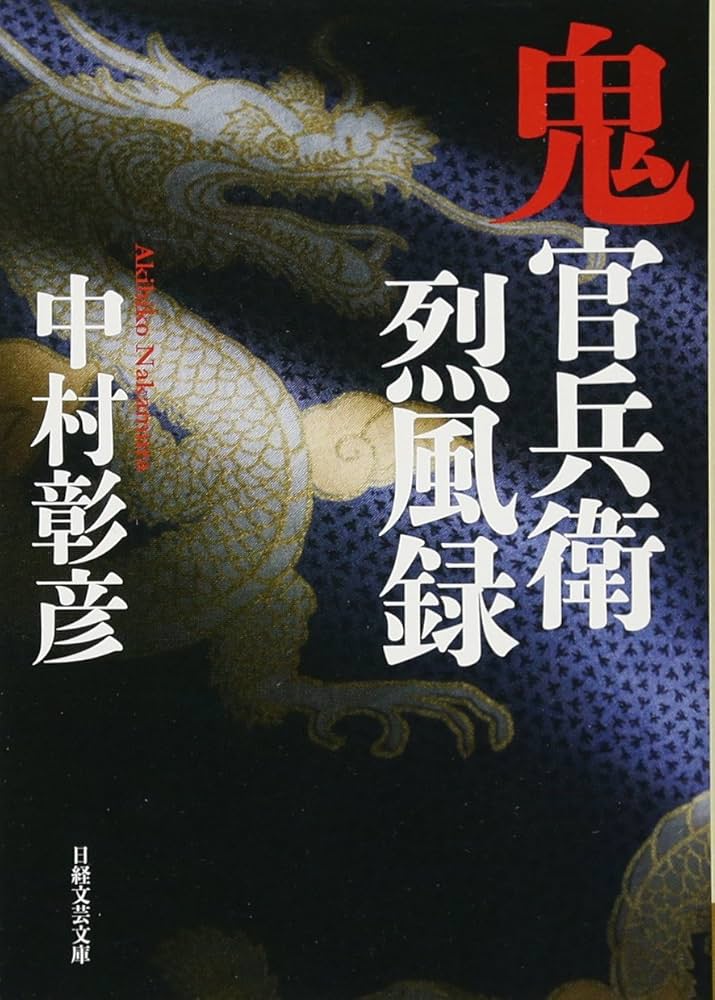
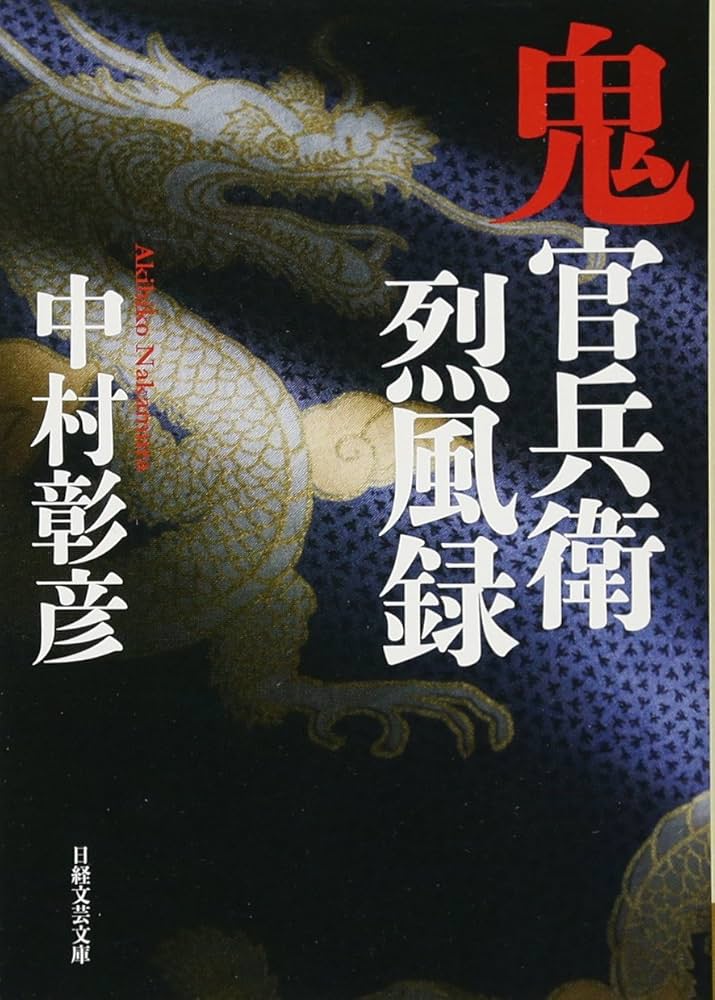
『鬼官兵衛烈風録』は、戦国時代の武将であり、豊臣秀吉の天才軍師として知られる黒田官兵衛(如水)の生涯を描いた長編小説です。その卓越した知略と、時に冷徹とも思えるほどの合理的な判断力で、数々の戦を勝利に導いた官兵衛の姿が生き生きと描かれています。
しかし、その才能ゆえに主君である秀吉から警戒され、不遇な扱いを受けることも少なくありませんでした。組織の中でいかにして自分の能力を発揮し、生き抜いていくか。戦国時代を舞台にしながらも、現代のビジネスパーソンにも通じる教訓が詰まった一冊です。



頭が良すぎるのも考えものなのかな?でも、官兵衛の先を読む力は本当にすごいよね。わたしもそれくらい先が読めたらなあ。
8位『新選組秘帖』
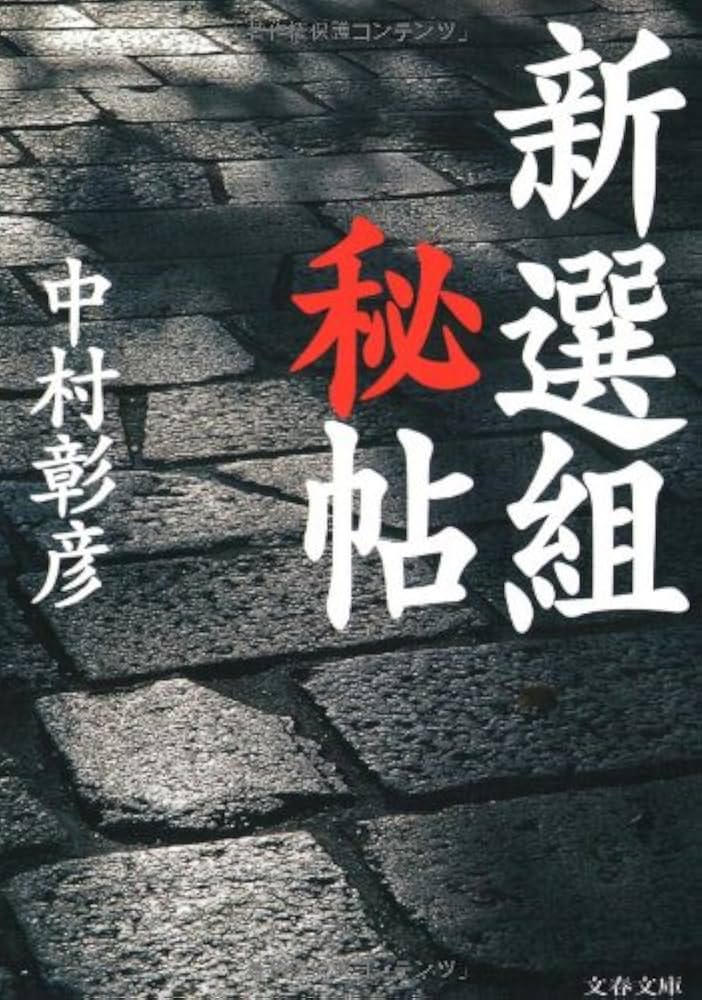
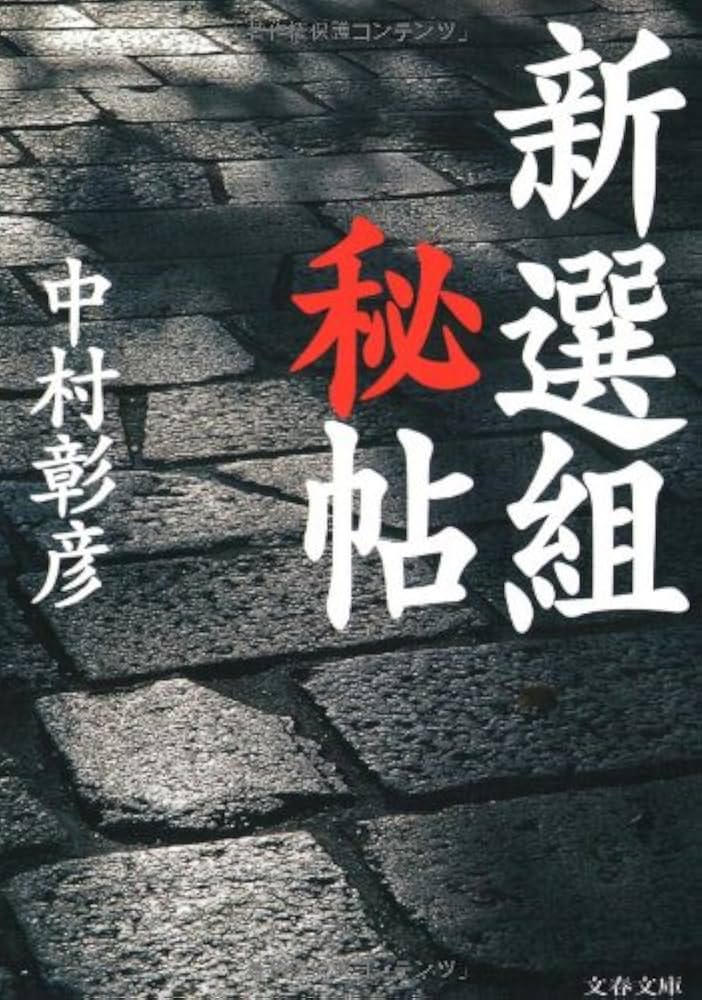
『新選組秘帖』は、新選組の様々な隊士たちにスポットを当てた短編集です。近藤勇や土方歳三といった幹部だけでなく、これまであまり語られることのなかった平隊士たちの知られざるエピソードが収められています。
それぞれの隊士がどのような想いを抱えて新選組に参加し、京の町で何を思い、戦っていたのか。一人ひとりの人間ドラマが丁寧に描かれており、新選組という組織をより多角的に理解することができます。各章で主人公が変わるため、テンポよく読み進められるのも魅力の一つです。



有名な人だけじゃなくて、色々な隊士の話が読めるのが楽しい!一人ひとりに物語があるんだって思うと、歴史がもっと面白くなるよね!
9位『明治無頼伝』
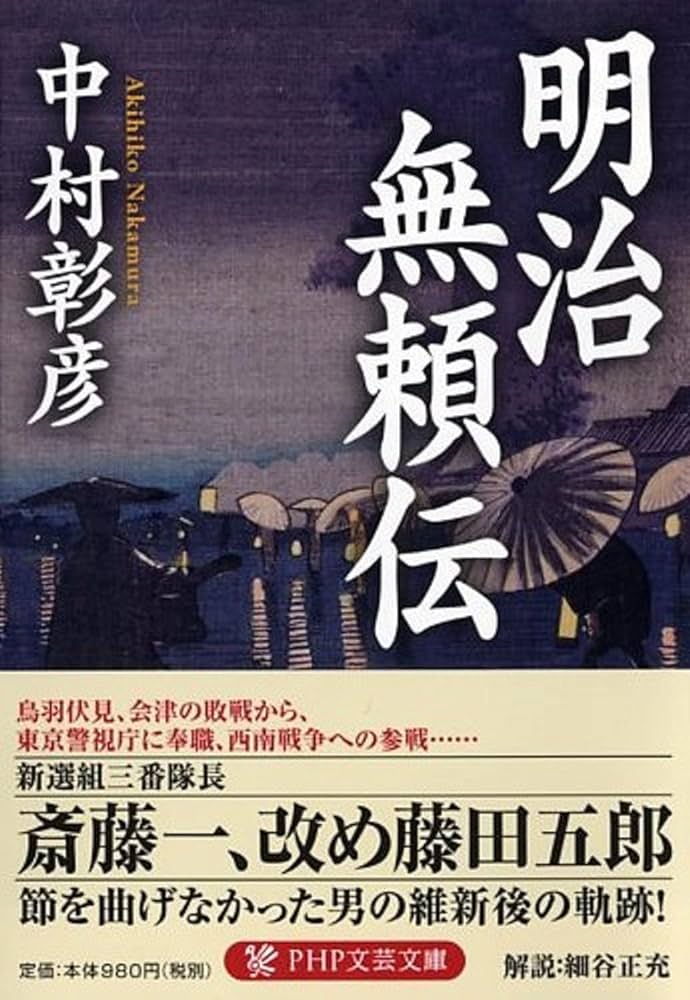
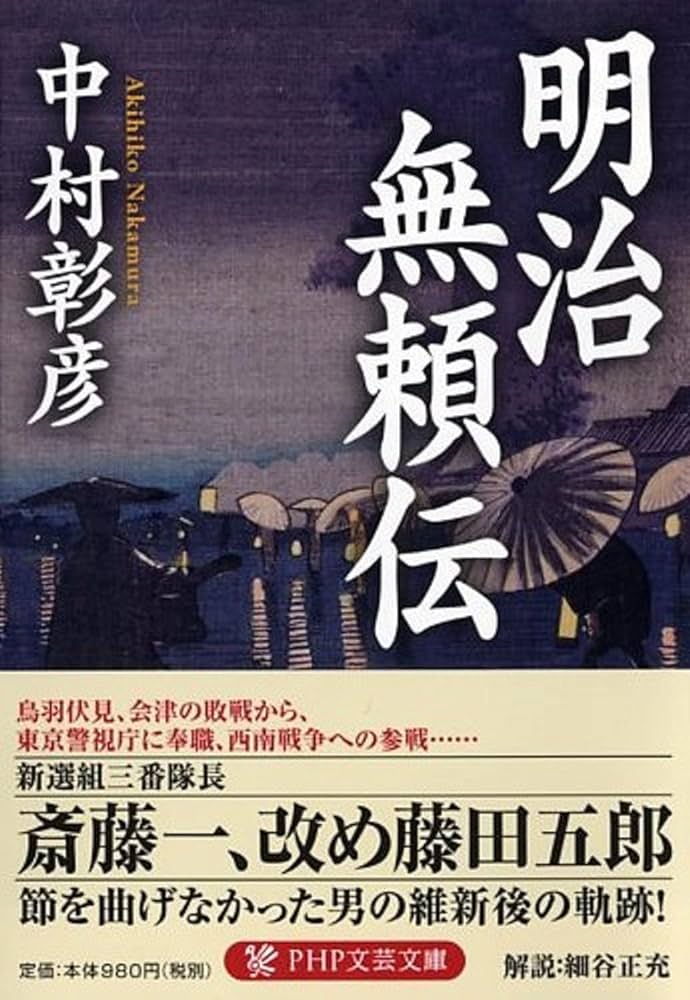
『明治無頼伝』は、明治という新しい時代の光と影を描き出した作品です。文明開化の華やかなイメージの裏で起こっていた、数々の事件や暗闘に焦点を当てています。
この時代、かつての武士たちは刀を捨て、新しい価値観の中で生きることを余儀なくされました。しかし、中にはその流れに抗い、自らの信じる道を突き進んだ者たちもいました。本作では、そうした時代の変わり目に生きた「無頼」な男たちの生き様が、鮮烈に描かれています。明治維新のもう一つの側面を知ることができる、骨太な一冊です。



新しい時代についていけない人たちの気持ち、なんだか分かる気がする…。変化って、時々すごく怖いものだよね。
10位『ある幕臣の戊辰戦争』
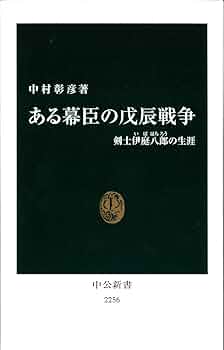
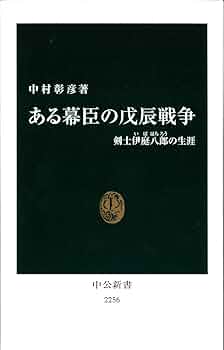
『ある幕臣の戊辰戦争』は、剣士・伊庭八郎の生涯を追ったノンフィクション・ノベルです。この作品は、歴史の表舞台に立つことのなかった一人の幕臣の視点から、戊辰戦争という内乱を見つめています。
有名な将軍や大名ではなく、名もなき一人の武士が、時代の大きな変化をどのように受け止め、戦い抜いたのか。彼の目を通して語られる戦争の現実は、非常に生々しく、読者に強い印象を残します。歴史とは、決して英雄たちだけで作られるものではないということを、改めて教えてくれる作品です。



歴史って、こういう普通の人たちの視点から見ると、また全然違って見えるんだよね。教科書には載らないけど、大切な物語だと思うな。
11位『その名は町野主水』
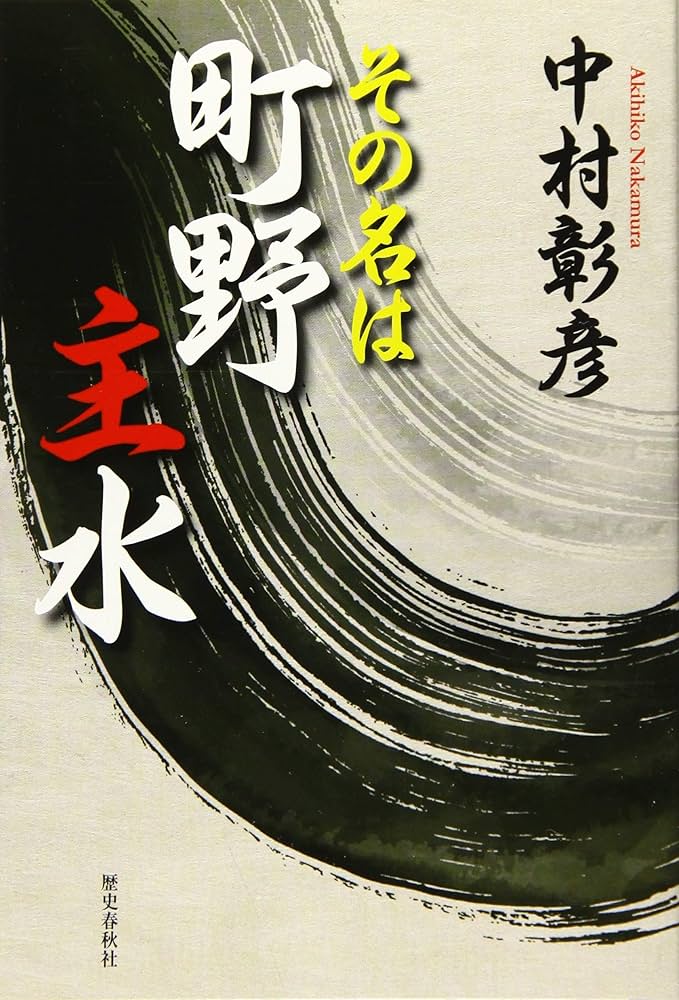
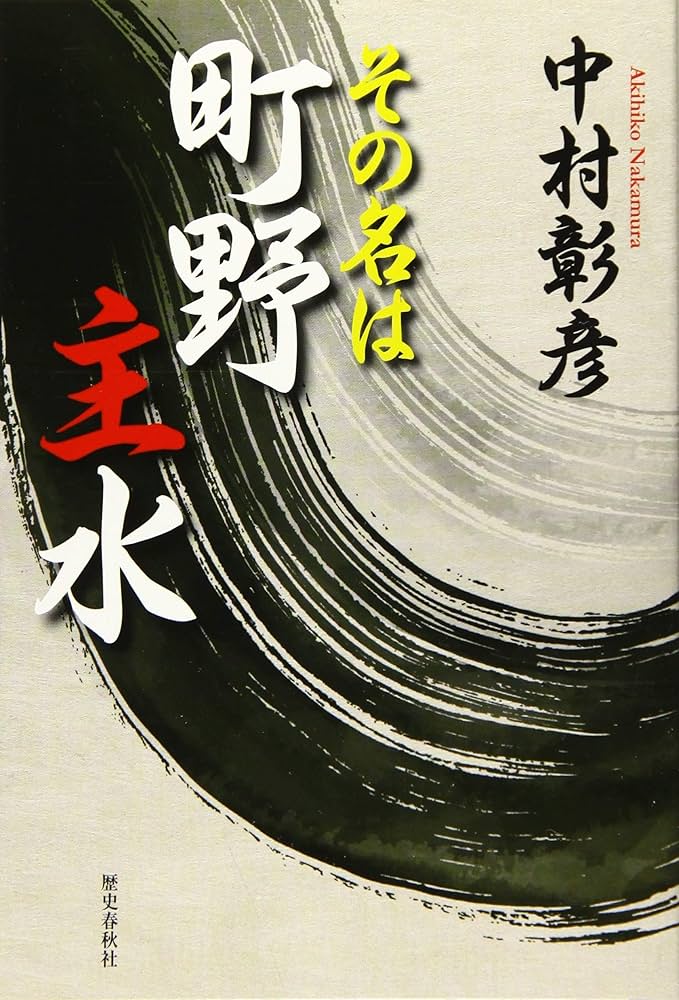
『その名は町野主水』は、会津藩の重臣であった町野主水の数奇な運命を描いた物語です。彼は、藩主・松平容保の京都守護職就任から戊辰戦争、そして明治時代に至るまで、常に会津藩の中枢で激動の時代を生き抜きました。
藩への忠義と、時代の流れとの間で葛藤する彼の姿は、中間管理職のような苦悩を彷彿とさせます。会津藩の義と苦難を一身に背負ったかのような彼の生涯を通して、武士として生きることの意味を問いかける作品です。会津藩の歴史をより深く知りたい方には必読の一冊と言えるでしょう。



忠義を尽くしたいけど、藩の未来も考えなきゃいけないって、すごく大変な立場だったんだろうな…。わたしだったらどうするかなあ。
12位『天保暴れ奉行』
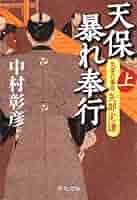
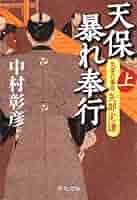
これまで紹介してきた重厚な作品とは少し趣が異なり、『天保暴れ奉行』は痛快な展開が魅力のエンターテインメント時代小説です。天保の改革が行われていた時代の江戸を舞台に、型破りな奉行が巨悪に立ち向かいます。
次々と起こる難事件を、豪快かつ機転を利かせて解決していく主人公の姿は、読んでいて非常に小気味が良く、爽快な気分にさせてくれます。中村彰彦のシリアスな歴史小説とはまた違った魅力を発見できる一冊。時代小説は初めてという方や、気軽に楽しめる作品を読みたい方におすすめです。



悪いやつらをバッサバッサとやっつけるのって、やっぱり見てて気持ちがいいよね!こういう勧善懲悪の物語も大好きなんだ!
まとめ:中村彰彦の人気小説を読んで歴史の深淵に触れよう
ここまで、中村彰彦のおすすめ小説をランキング形式でご紹介してきました。彼の作品は、ただ歴史上の出来事をなぞるだけでなく、その時代を生きた人々の息づかいや葛藤を、私たちに生々しく伝えてくれます。
特に、会津藩や新選組といった、いわゆる「敗者」の側から歴史を描くことで、これまで見過ごされてきた多くの真実や人間のドラマを浮かび上がらせています。一冊手に取れば、きっとあなたも歴史の奥深さと、そこに生きた人々の魅力に引き込まれるはずです。ぜひ、この機会に中村彰彦の世界に触れてみてください。