あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
日野啓三のおすすめ小説案内:人気ランキングで知る孤高の世界

日野啓三のおすすめ小説案内:人気ランキングで知る孤高の世界
日野啓三(ひの けいぞう)は、1929年東京生まれの小説家・文芸評論家です。東京大学卒業後、読売新聞社に入社し、ソウルやサイゴン(現ホーチミン市)に特派員として駐在した経験を持ちます。その経験は彼の創作活動の基盤となり、特にベトナム戦争を題材にした作品で知られています。
彼の作品は、現代都市に潜む幻想を描き出す「都市小説」というジャンルでも高く評価されています。日常と非日常が交錯する独特の世界観は、多くの読者を魅了し続けてきました。1975年に『あの夕陽』で芥川賞を受賞したのをはじめ、『砂丘が動くように』で谷崎潤一郎賞、『台風の眼』で野間文芸賞など、数々の著名な文学賞に輝いています。この記事では、そんな日野啓三の孤高で深遠な文学世界へとあなたをご案内します。
【2025年最新】日野啓三の人気おすすめ小説ランキングTOP16
ここからは、いよいよ日野啓三のおすすめ小説をランキング形式でご紹介します。新聞記者としての鋭い視点と、幻想的な世界観を織りなす小説家としての才能が融合した作品群は、今なお多くの読者を惹きつけてやみません。
ベトナムでの経験を色濃く反映した初期の作品から、現代社会の歪みと人間の孤独を浮き彫りにする都市小説、そして生と死を見つめた晩年の傑作まで、幅広くランクインしています。このランキングを参考に、あなたにとって特別な一冊を見つけてみてください。
1位『夢の島』
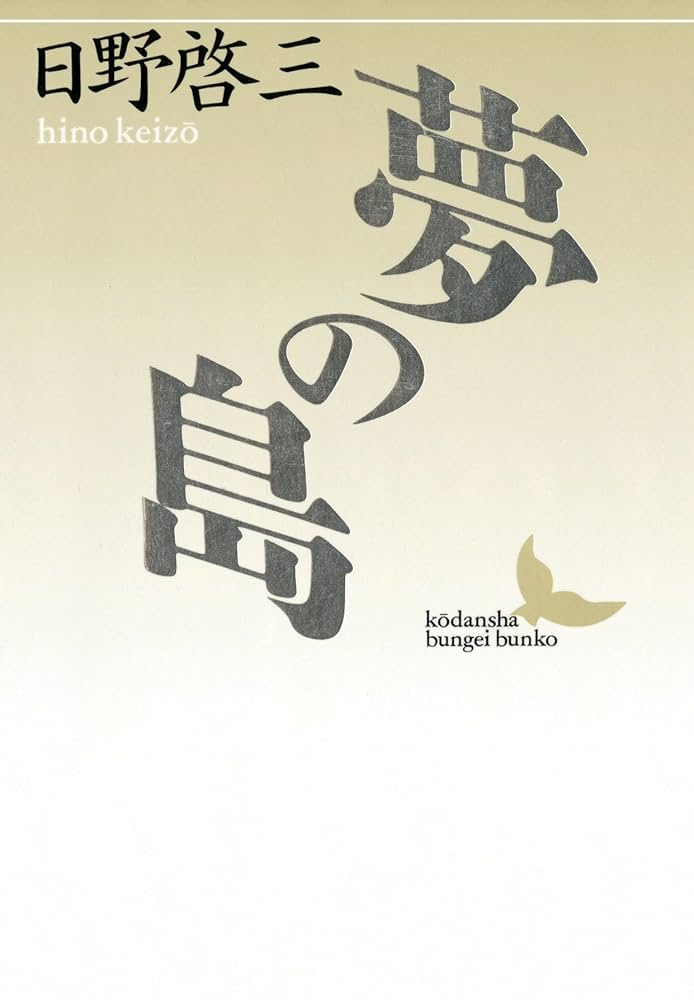
日野啓三文学の最高傑作との呼び声も高い『夢の島』が堂々の1位に輝きました。1985年に発表され、芸術選奨を受賞した長編小説です。妻を亡くした中年男性の建築技師・境昭三が、日常の中で見かける謎めいた二人の女性に惹かれていく物語です。
物語の舞台は、巨大都市のゴミが集まる場所、その名も「夢の島」。主人公はバイクを乗りこなす若い女性・林陽子と出会い、彼女に導かれるようにして非日常の世界へと足を踏み入れていきます。ゴミの集積地という無機質な場所が、やがて主人公にとって特別な意味を持つ”魅惑の場所”へと変わっていく様子が鮮やかに描かれています。
 ふくちい
ふくちいゴミの島が魅惑の場所に変わるなんて、すごい発想力だよね。わたしもその島に行ってみたいな!
2位『あの夕陽』
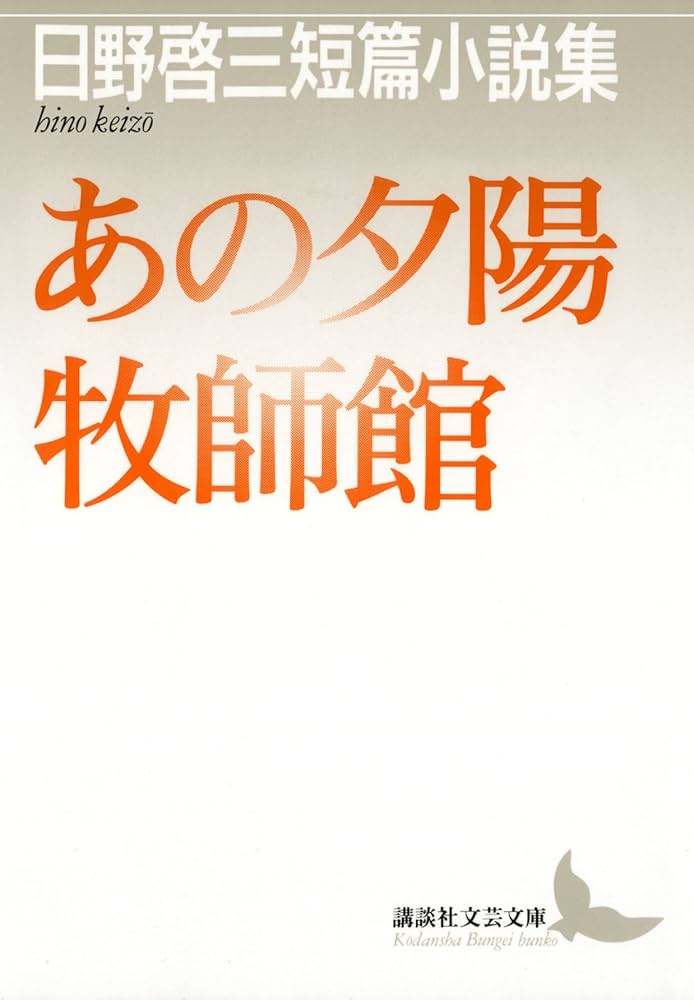
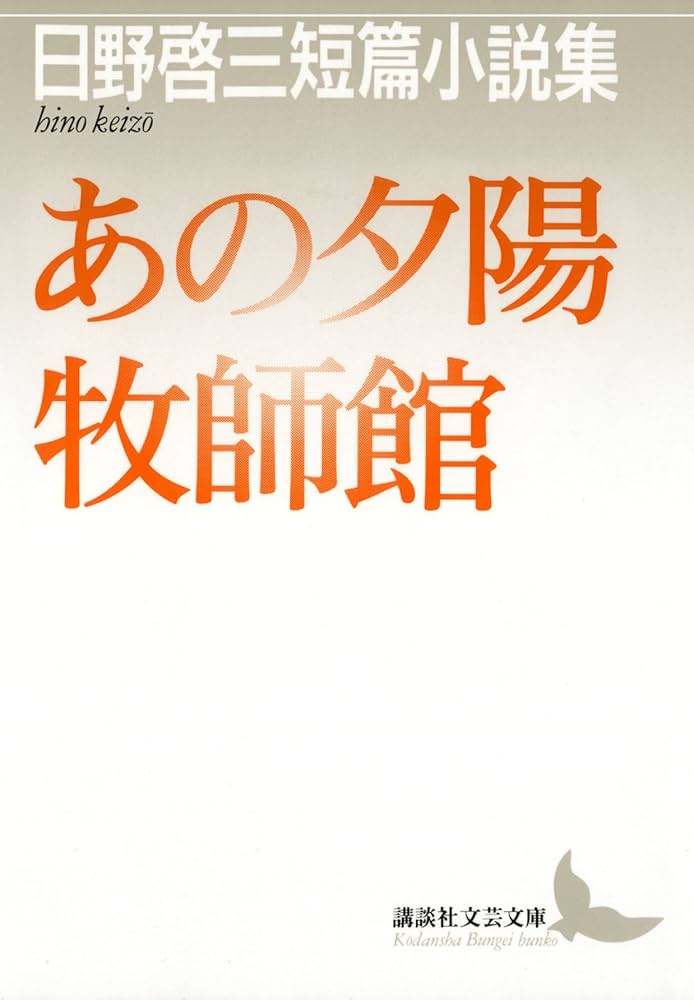
第2位は、1975年に第72回芥川賞を受賞した『あの夕陽』です。この作品は日野啓三自身の離婚体験が基になっており、私小説的な側面を持つ短編小説として知られています。物語は、新聞記者の「私」と妻との淡々とした日常が、かつてソウル特派員時代に出会った韓国人女性・李の存在によって静かに侵食されていく様子を描いています。
少年時代に敗戦を経験し、どこか人生に投げやりになってしまった主人公の虚無感を、タイトルにもなっている「夕陽」が鮮烈に照らし出します。男女間に横たわる深い溝と、関係性が静かに崩れていく様を、日野啓三ならではの筆致で描き出した傑作です。人間関係の複雑さや、心の奥底に潜む暗い感情に触れたい読者におすすめの一冊と言えるでしょう。



自分の体験を小説にするって、どんな気持ちなんだろう。ちょっと複雑な気持ちになりそうだね。
3位『砂丘が動くように』
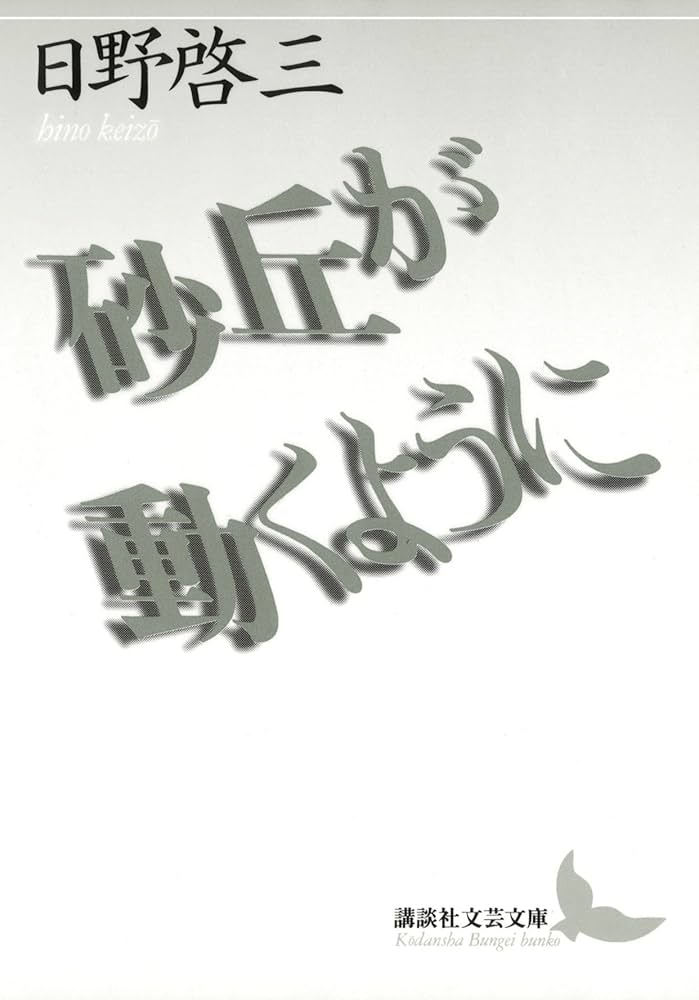
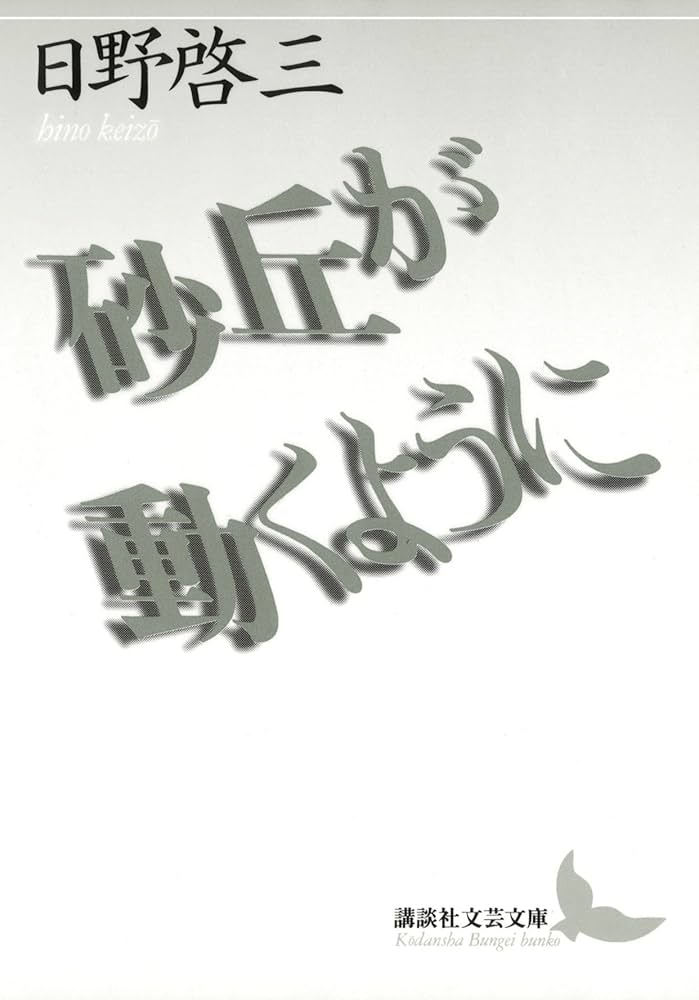
第3位には、1986年に谷崎潤一郎賞を受賞した長編小説『砂丘が動くように』がランクインしました。物語の舞台は、日本海に面した小さな町の外れにある砂丘。防砂林によって動きを止められ、少しずつ活力を失いつつある砂丘が、まるで生き物のように独自の意識を持ち始めるという幻想的な物語です。
この砂丘が発する不思議な何かを、盆栽作りに没頭する少年やその盲目の姉、美しい女装の青年といった、社会の周縁で生きる人々が敏感に感じ取ります。自然と人間の意識が交感する様を、スリリングかつ詩的に描き出した本作は、日野啓三の真骨頂とも言える作品です。宇宙的なスケールで描かれる新しい意識の目覚めは、読者に強烈な印象を残すでしょう。



砂が意識を持つなんて、なんだかロマンチックだね。自然と人間が繋がる話、わたしは好きだな。
4位『台風の眼』
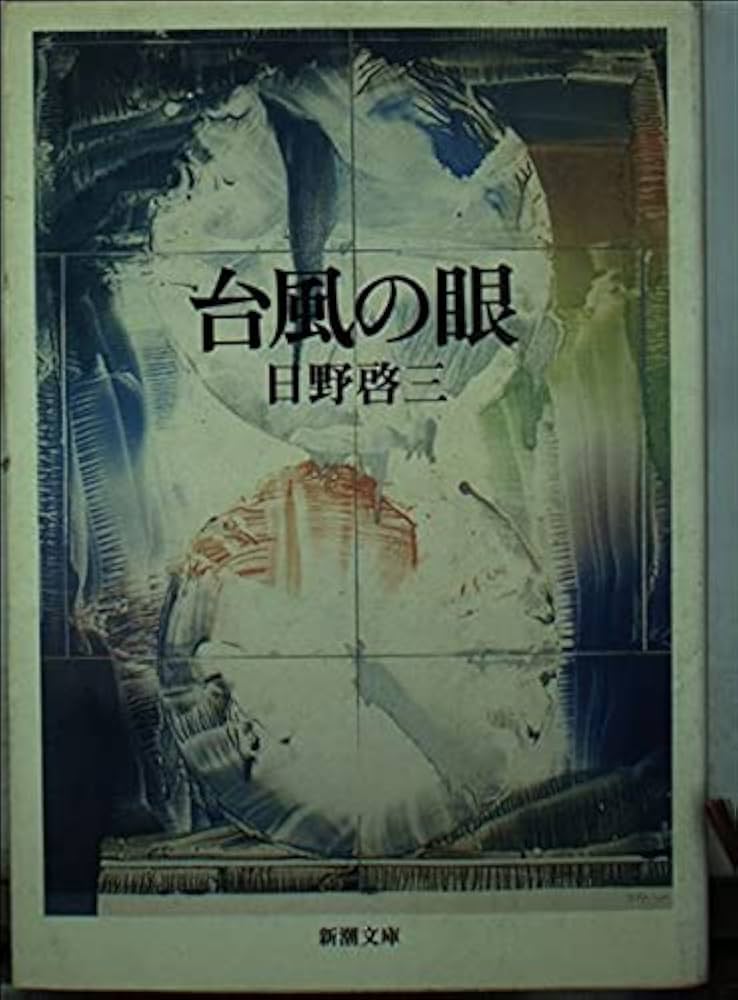
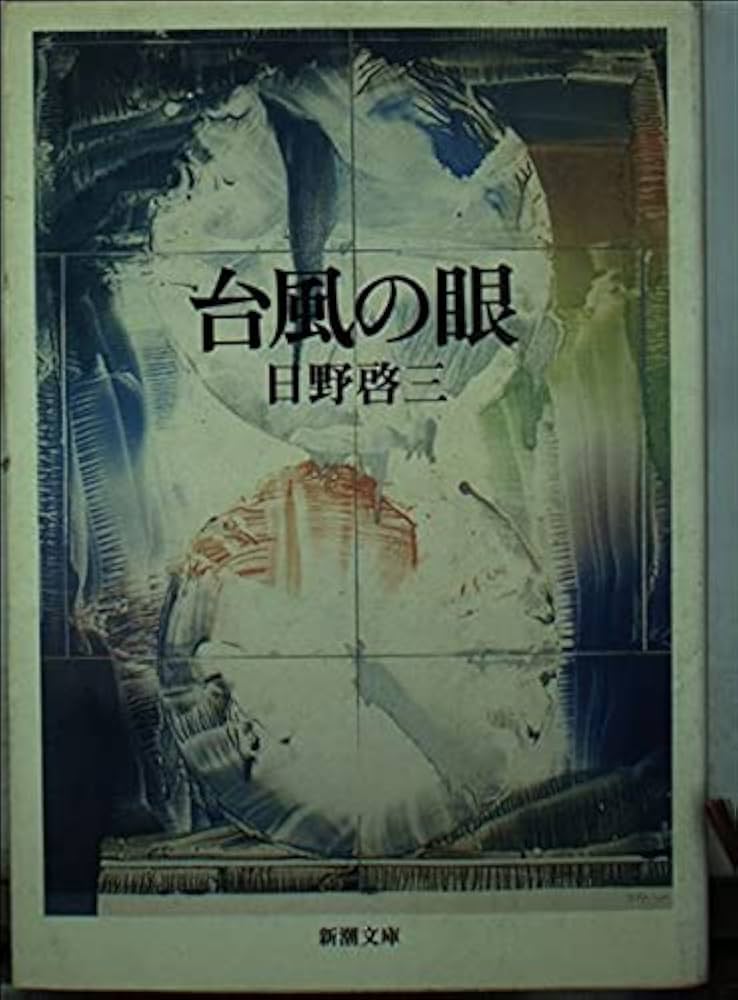
第4位は、1993年に野間文芸賞を受賞した『台風の眼』です。本作は、作者自身が悪性腫瘍の手術を受けた経験を基に執筆されました。「最後になるかもしれない」という覚悟で書き始められたこの小説は、自伝的要素と小説的創造が交錯する、日野文学の新たな試みと言える作品です。
物語は、作家である主人公が、自らの記憶に深く刻まれた情景を辿る形で進行します。4歳の頃に初めて「世界」を感じた東京・赤坂での記憶、植民地時代の朝鮮で過ごした少年期、そして新聞記者として赴任したソウルやサイゴンでの体験。これらの鮮烈な記憶の断片を繋ぎ合わせることで、「自分が確かに生きていた」という実感を取り戻そうと試みます。生と死の狭間で紡がれる、切実で美しい物語です。



自分の人生を振り返るって、すごく勇気がいることだよね。わたしも、いつかそんな風に自分の人生を物語にしてみたいな。
5位『抱擁』
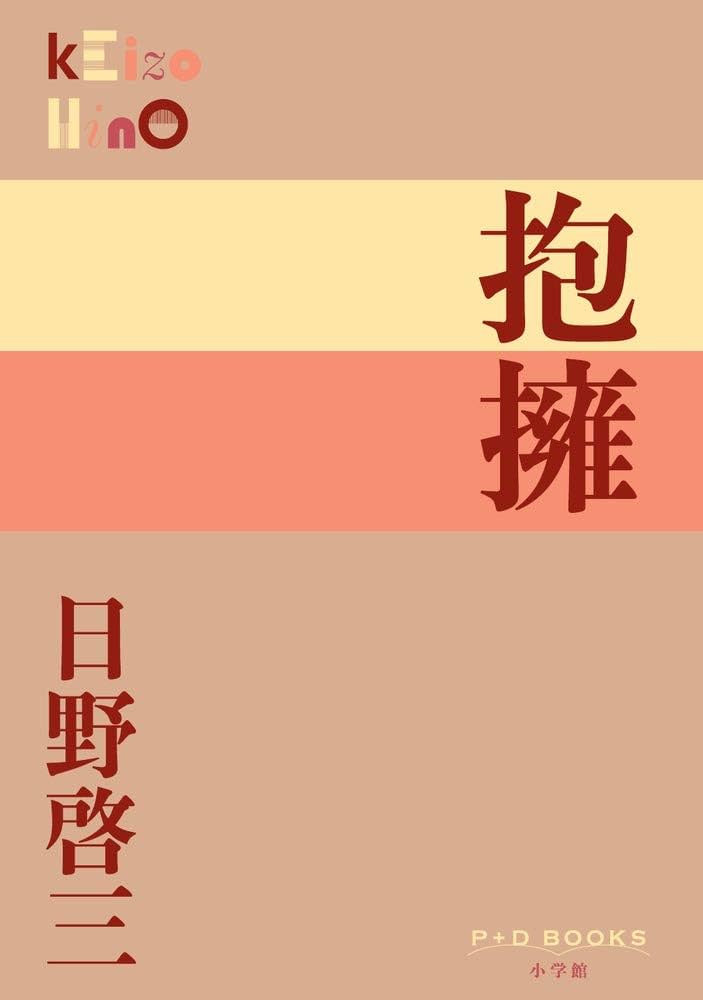
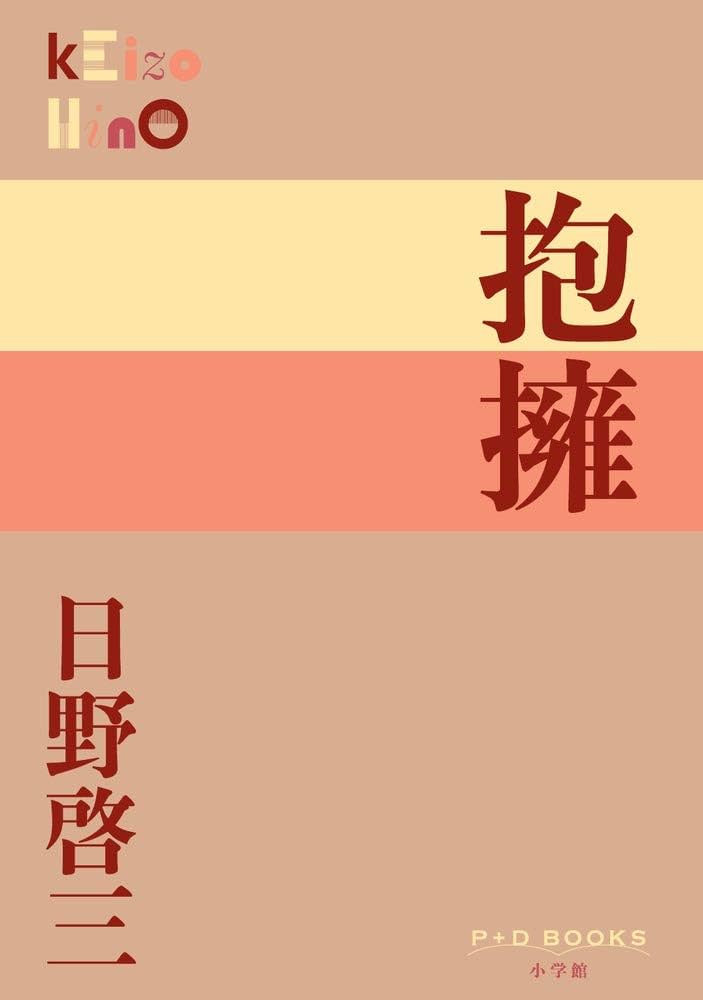
5位にランクインしたのは、1982年に泉鏡花文学賞を受賞した『抱擁』です。これまでの私小説的な作風から一転し、幻想的な世界観を前面に押し出した本作は、日野啓三の新たな境地を切り開いた記念碑的な作品とされています。
物語は、大都会の真ん中に静かにたたずむ古い洋館に、「私」が足を踏み入れるところから始まります。そこで出会ったのは、心を閉ざした幻想的な少女・霧子。彼女の家庭教師として洋館で暮らすことになった「私」は、この館に住む一家の数奇な運命に巻き込まれていきます。妖しい魅力に満ちた洋館を舞台に繰り広げられる、ロマネスクな人間模様が読者を惹きつけます。



古い洋館ってだけでワクワクするよね。ミステリアスな少女との出会い、物語の始まりって感じがするなあ。
6位『光』
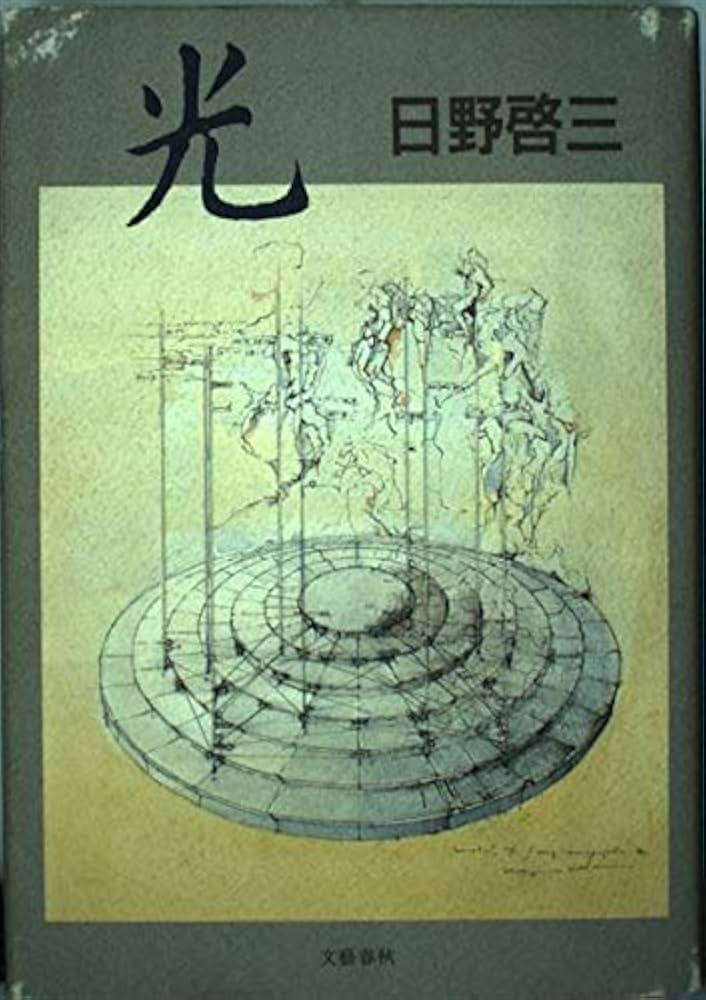
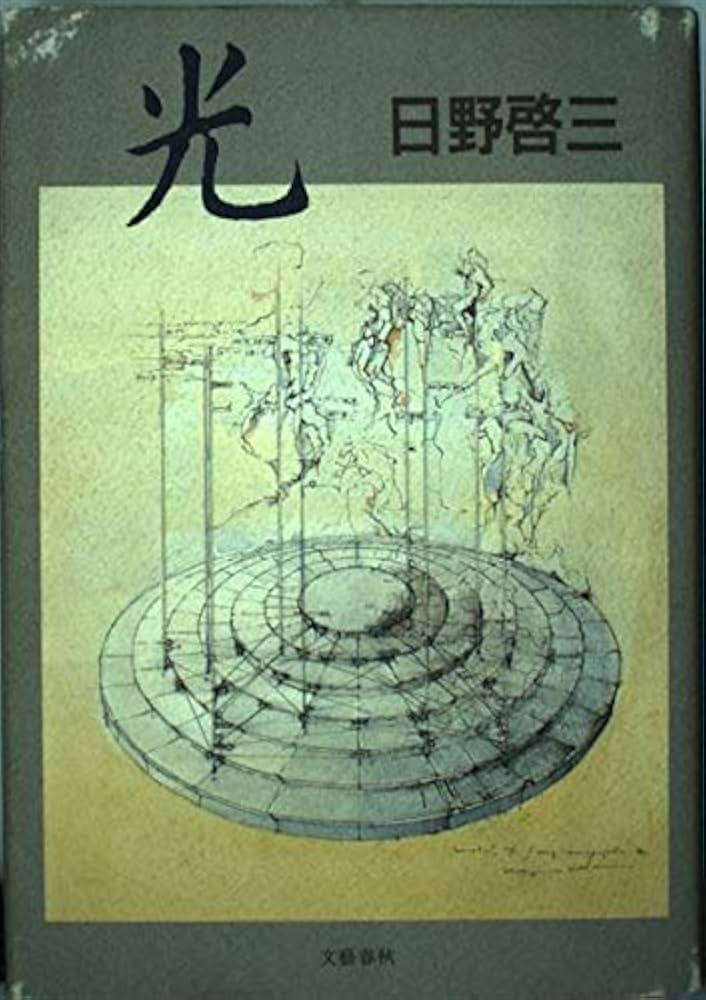
6位には、1996年に読売文学賞を受賞した近未来小説『光』が選ばれました。がんとの闘病生活を経て、生と死の問題に深く向き合った日野啓三が描く「喪失と新生」の物語です。
舞台は近未来の東京。月面での事故によって記憶を失った元宇宙飛行士が、自らの過去を取り戻すために、かつての繁栄を失った東京の街をさまよいます。中国人看護婦やホームレスの老人との出会いを通じて、彼は失われた記憶の断片を拾い集めていきます。記憶の喪失という極限状況の中で、人間がどのようにして再生していくのかを力強く描いた傑作長編です。



記憶をなくすって、自分が自分でなくなるみたいで怖いな…。でも、そこから新しい自分を見つける物語なのかもしれないね。
7位『天窓のあるガレージ』
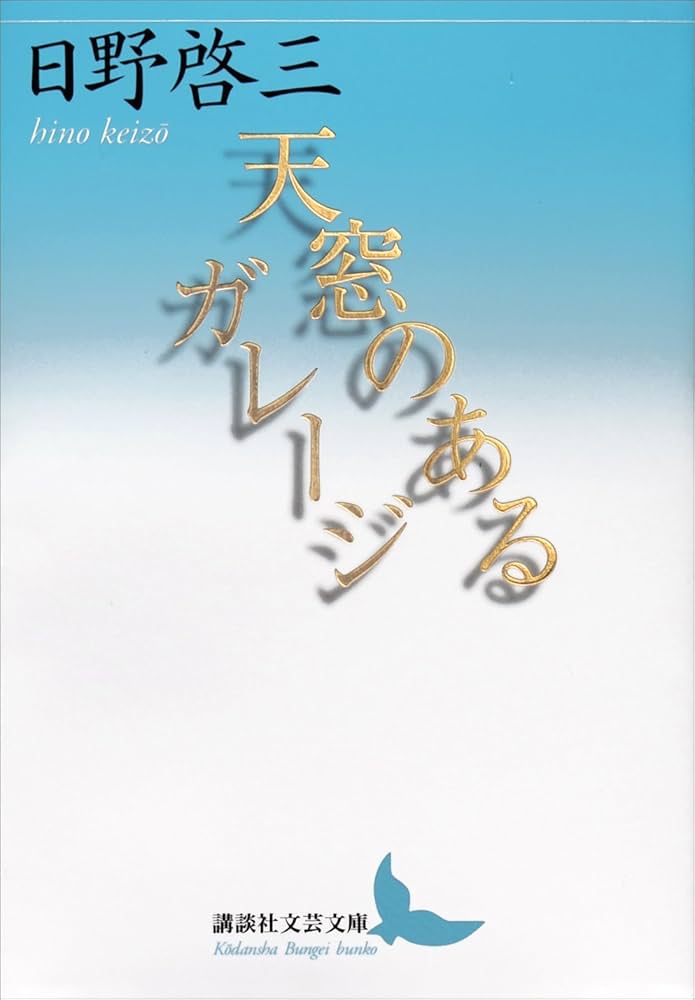
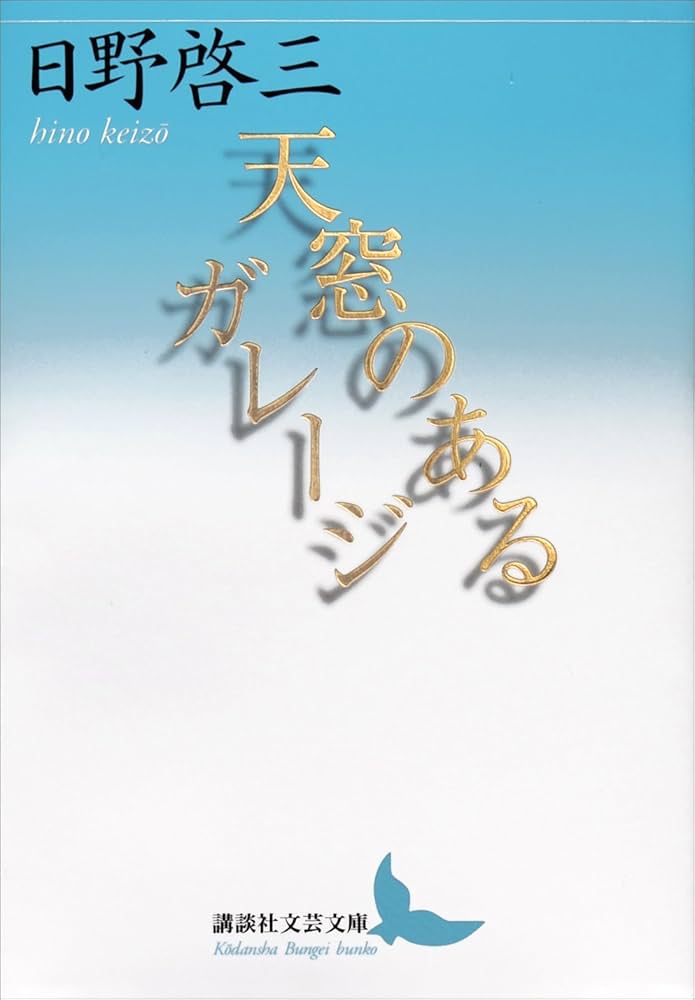
7位には、のちに高く評価される「都市小説」シリーズの先駆けとなった傑作短編集『天窓のあるガレージ』がランクインしました。日常から遠く離れた異国の地や、人を寄せ付けない大自然に身を置くことで、主人公が「私」という枠組みを超えようと試みる物語が収められています。
歴史の遺構が残る土地や手つかずの自然の中で、主人公は自己を超越する体験をします。さらに、若者や女性といった他者との出会いを通じて、その感覚はより深く、新しい世界観へと変貌を遂げていきます。表題作「天窓のあるガレージ」をはじめ、日野文学の転換点ともいえるスリリングな作品群が魅力の一冊です。



日常を飛び出して、自分を超える体験かあ。なんだか冒険みたいでドキドキするね!
8位『夢を走る』
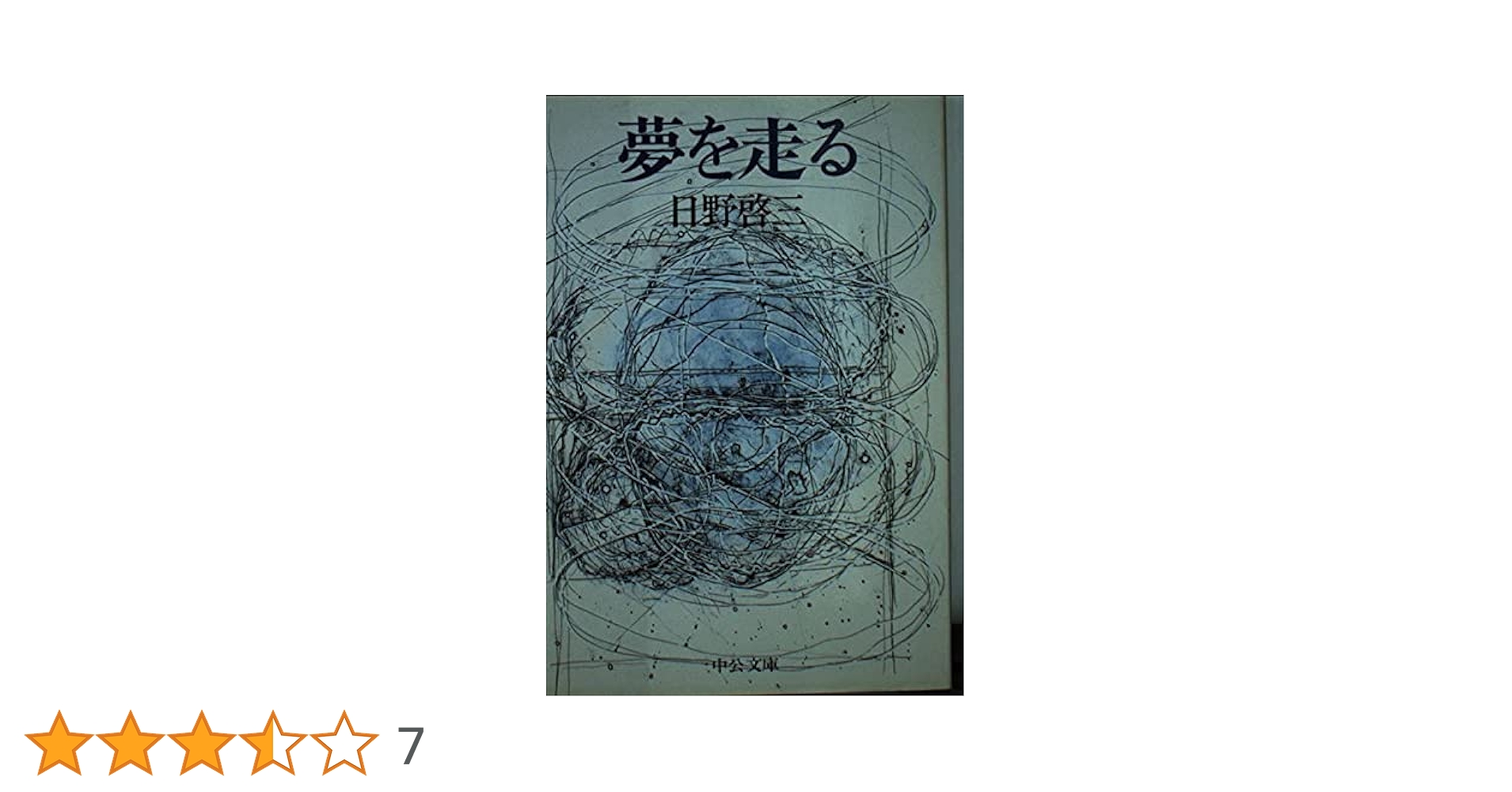
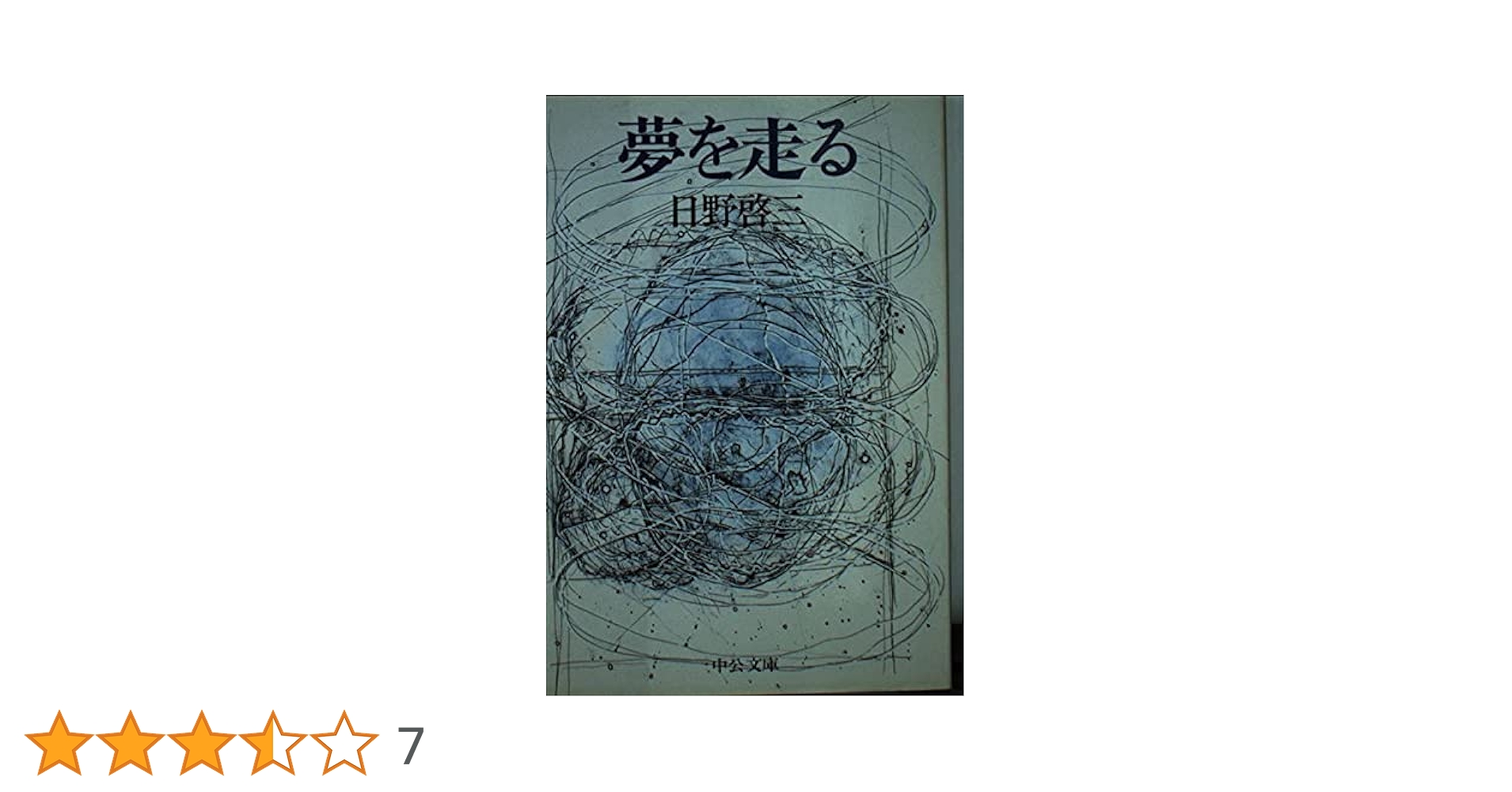
8位は、都市に潜む幻想を鮮やかに描き出した名作短編集『夢を走る』です。目に見える現実世界の裏側にある、もう一つの世界。本作に登場する人物たちは、そんな異次元からの気配を敏感に感じ取る能力を持っています。
異次元と交信する息子と、その様子を静かに見守る父親。古い屋敷に棲む猫の孤独と、崩壊しゆく世界への恐怖を共有する男。彼らは、私たちが普段意識することのない、世界の重層的な姿を垣間見ます。



目に見えない世界を感じるって、どんな感じなんだろう。ちょっと怖いけど、新しい世界が広がりそうだね。
9位『断崖の年』
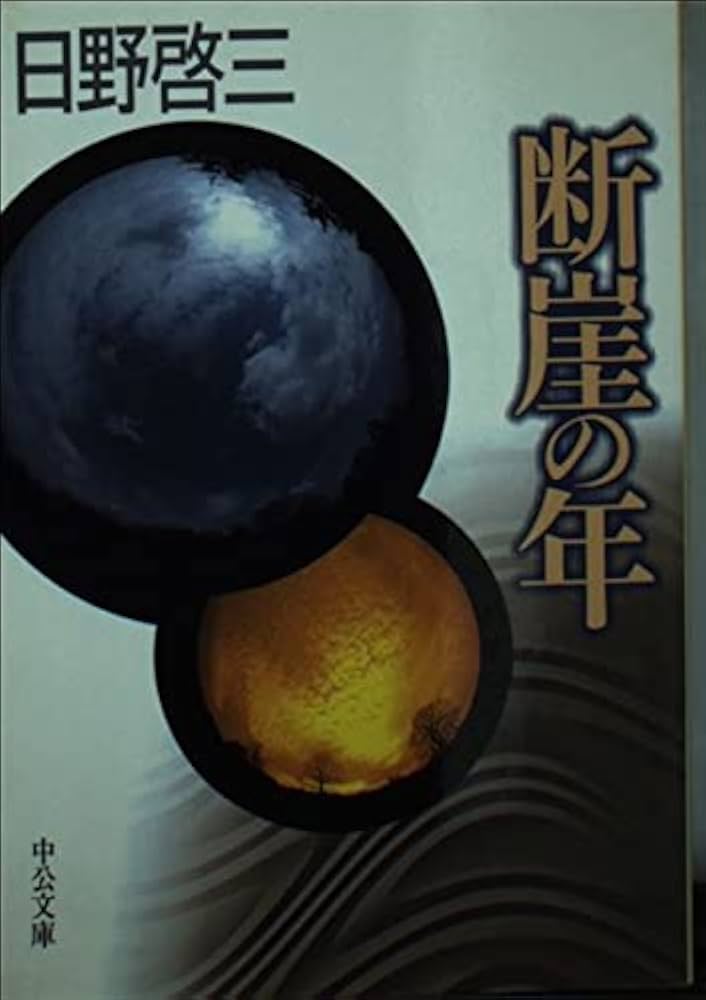
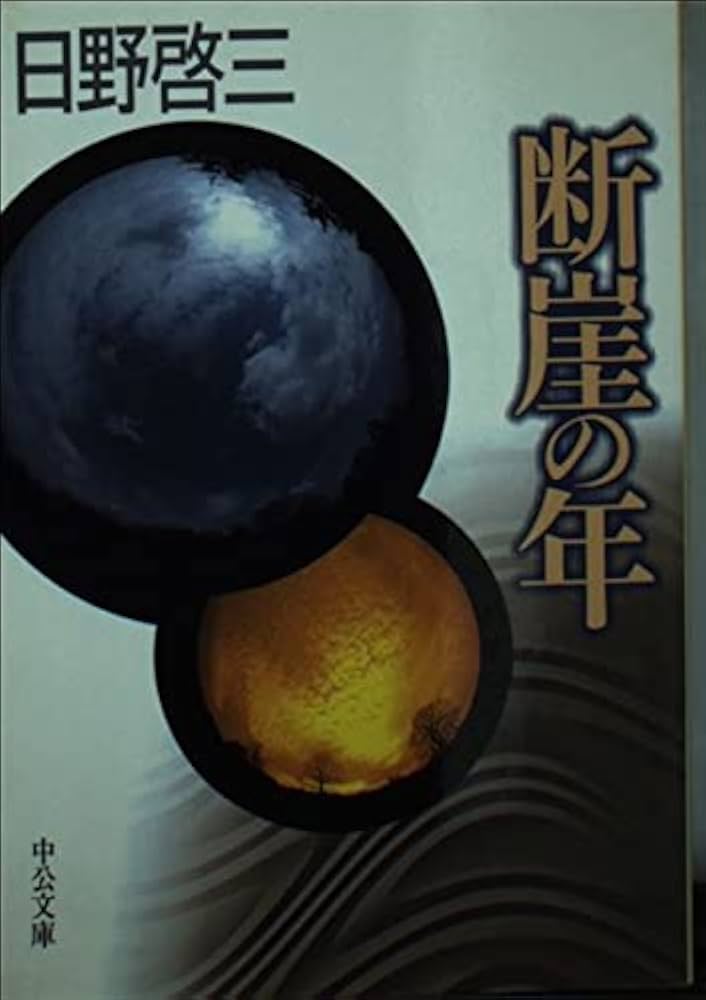
9位は、1992年に伊藤整文学賞を受賞した『断崖の年』です。本作は、著者自身のがん発病から回復までの壮絶な体験を、体験記、小説、エッセイといったジャンルの垣根を越えた自由な文体で綴った連作短編集です。
全身麻酔や手術の痛みによって、主人公は現実と幻覚の狭間をさまよいます。その中で彼は、「これまで現実だと思っていた世界の裏側から、本当の現実が滲み出してき始めた」と感じ、恐怖と同時に官能的な快感を覚えるのです。生と死の境界線上で見えてくる世界の新たな姿を、強烈なイメージと共に描き出した、日野文学の中でも特にパワフルな一冊です。



現実と幻覚の境目がなくなるなんて…。すごく怖いけど、ちょっとだけ見てみたい気もするな。
10位『リビング・ゼロ』
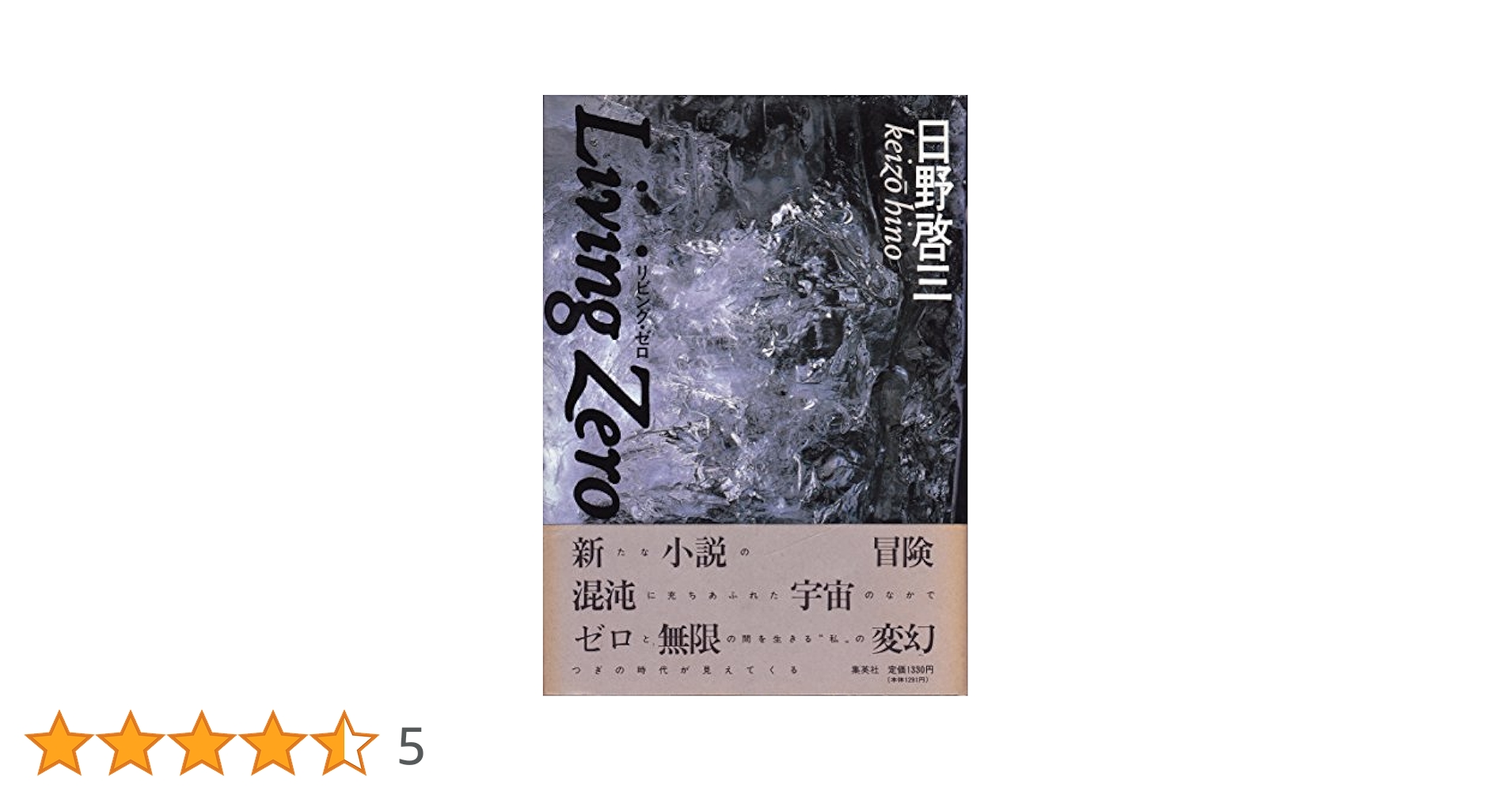
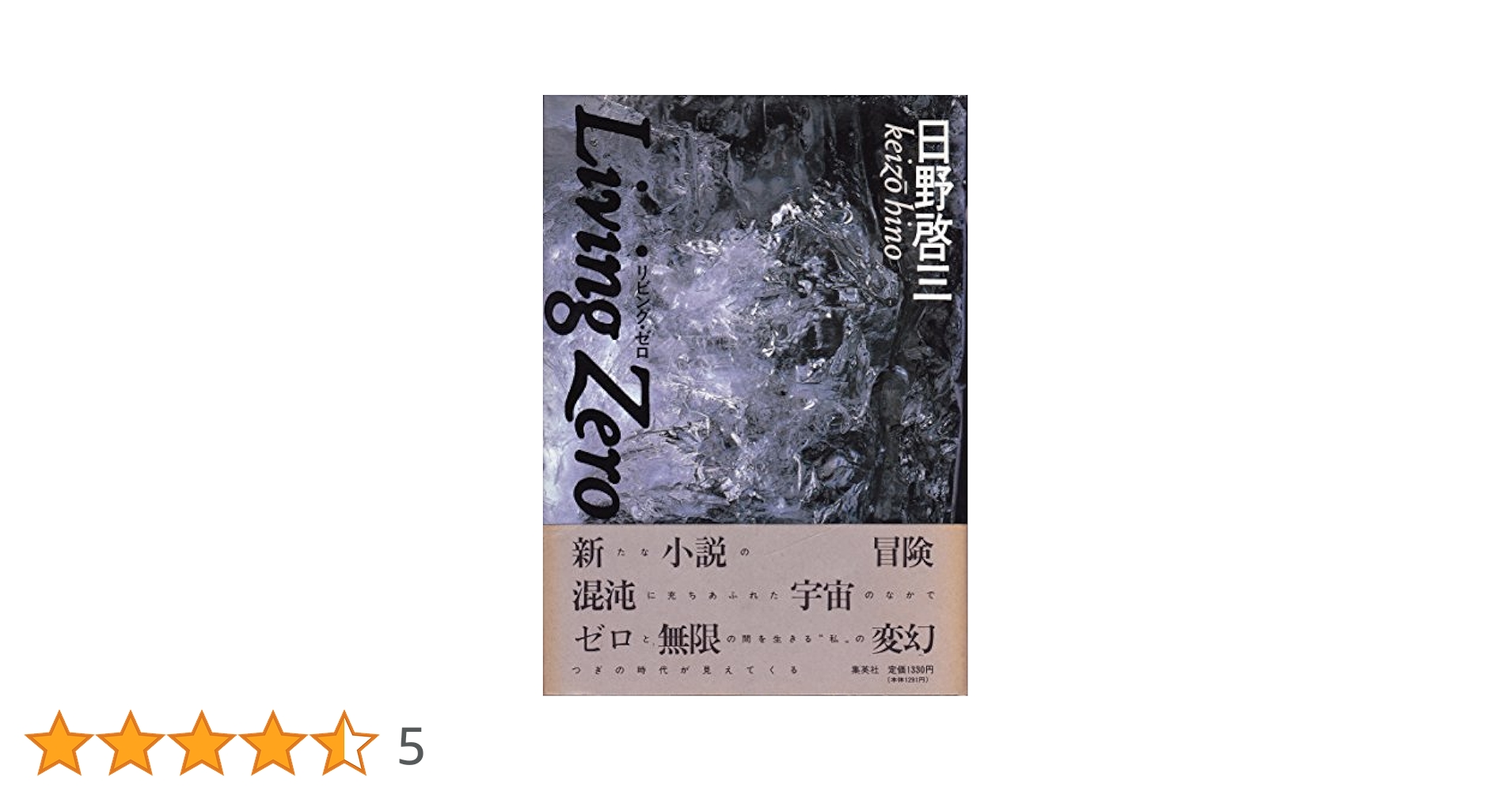
自然科学の知見、SF的な想像力、そして作者自身の経験や記憶が、断片的に、しかし巧みに織り合わされています。
本書では、日常に潜む非日常や、世界の成り立ちそのものに対する深い思索が展開されます。読者は、まるで万華鏡を覗き込むように、次々と現れるイメージの断片を追いながら、日野啓三の広大な思索の世界を旅することになります。知的興奮と詩的な感動が同時に味わえる、唯一無二の作品です。



科学と小説が混ざり合ってるなんて、面白そう!どんな世界が広がっているのか、読んでみたくなったよ。
11位『此岸の家』
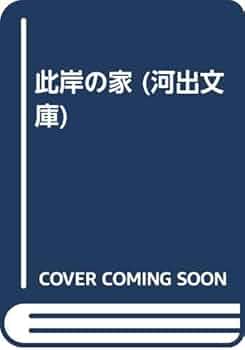
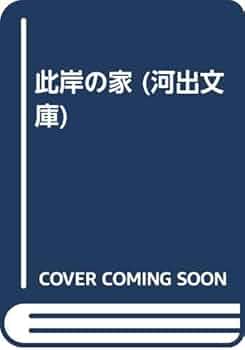
11位は、平林たい子文学賞を受賞した私小説の名編『此岸の家』です。新聞社の韓国特派員である「私」と、朝鮮戦争によって過酷な運命をたどった韓国人女性との国際結婚をテーマに描かれています。
国や文化、育った環境の違いからくるすれ違いや、激しい気性を持つ妻との大波にもまれるような結婚生活が赤裸々に綴られます。周囲の反対を押し切って結ばれた二人の生活は、決して平穏なものではありません。それでもなお、共に生きようとする男女の姿を通して、人間関係の複雑さと、その中に存在する確かな絆を描き出した作品です。



国際結婚って、言葉や文化の壁があって大変そうだよね。でも、それを乗り越えたら、もっと強い絆で結ばれるのかもしれないな。
12位『還れぬ旅』
12位は、日野啓三の初期の作品を収めた短編集『還れぬ旅』です。なお、小説家としてのデビュー作は1966年の「向う側」です。自身の引揚げ体験を色濃く反映した作品群が収録されており、彼の作家としての原点を知る上で欠かせない一冊と言えるでしょう。
どの作品にも共通しているのは、自らの居場所に対する深い問いかけであり、その後の日野文学を貫く重要なテーマとなっています。



自分の帰る場所がないって、すごく寂しいことだよね…。物語を通して、その気持ちが少しだけ分かった気がするよ。
13位『どこでもないどこか』
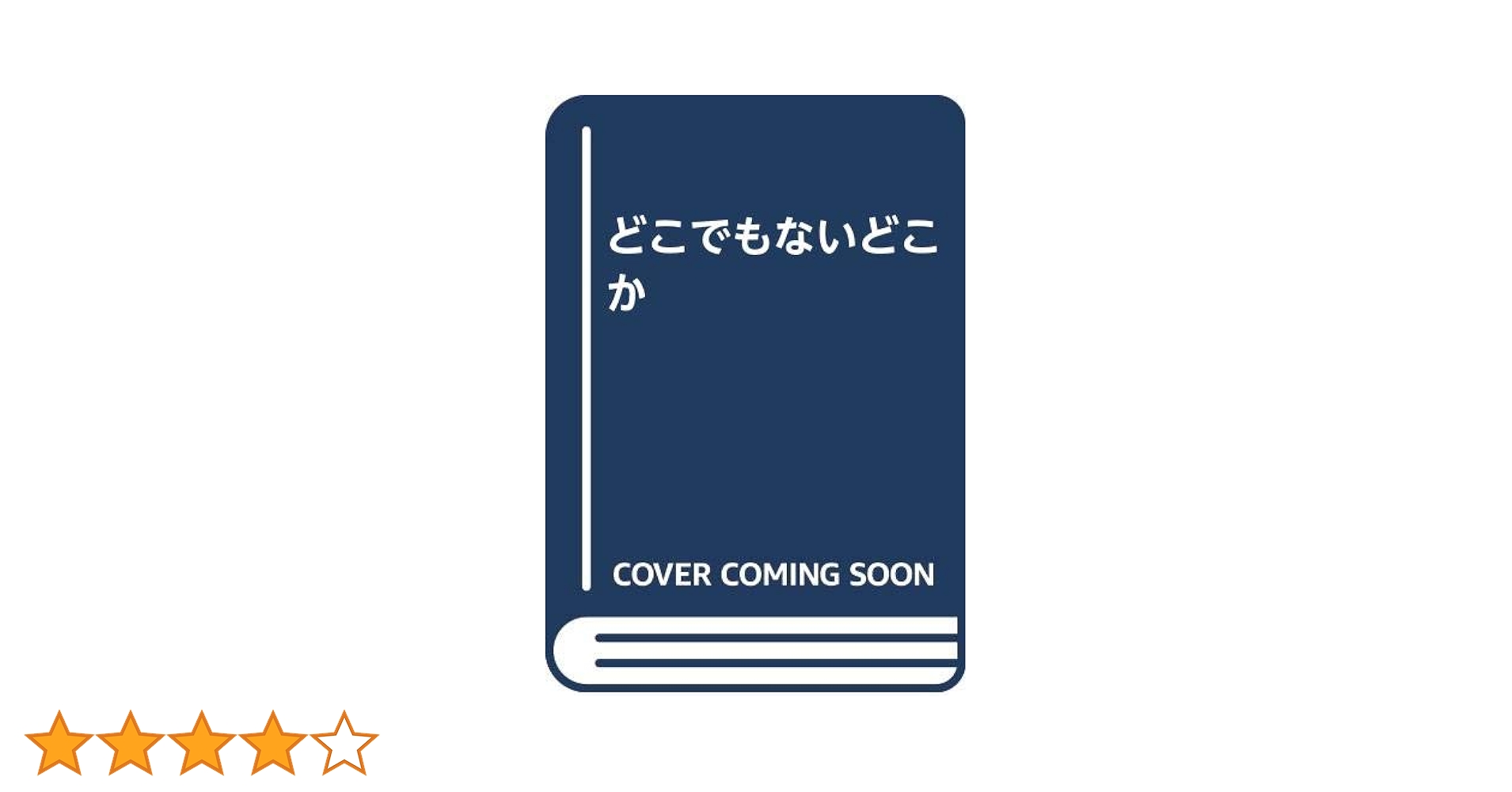
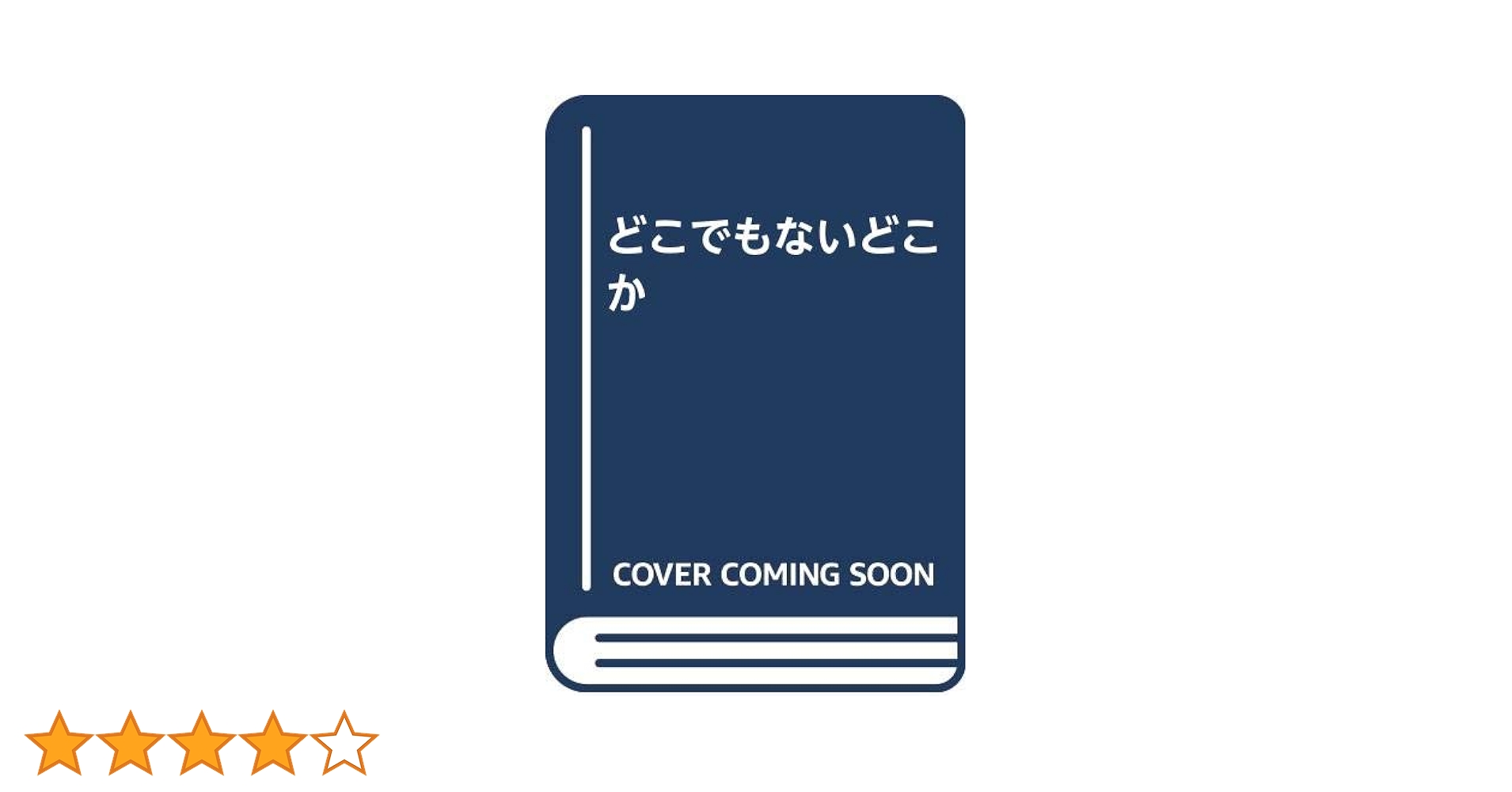
13位は、日野啓三のエッセイ集『どこでもないどこか』です。小説作品とは一味違った、彼の思索の軌跡をたどることができる一冊です。
本書では、都市、自然、宇宙、そして生と死といった、日野文学を特徴づけるテーマについて、より直接的な言葉で語られています。新聞記者として世界各地を取材した経験や、自身の闘病体験などを通して深められた、独自の死生観や世界観に触れることができます。小説家・日野啓三の思考の源泉を知りたい読者にとって、必読の書と言えるでしょう。



エッセイを読むと、その作家さんの考えていることがダイレクトに伝わってくるから面白いよね。小説と一緒に読むと、もっと深く楽しめるかも!
14位『向う側』
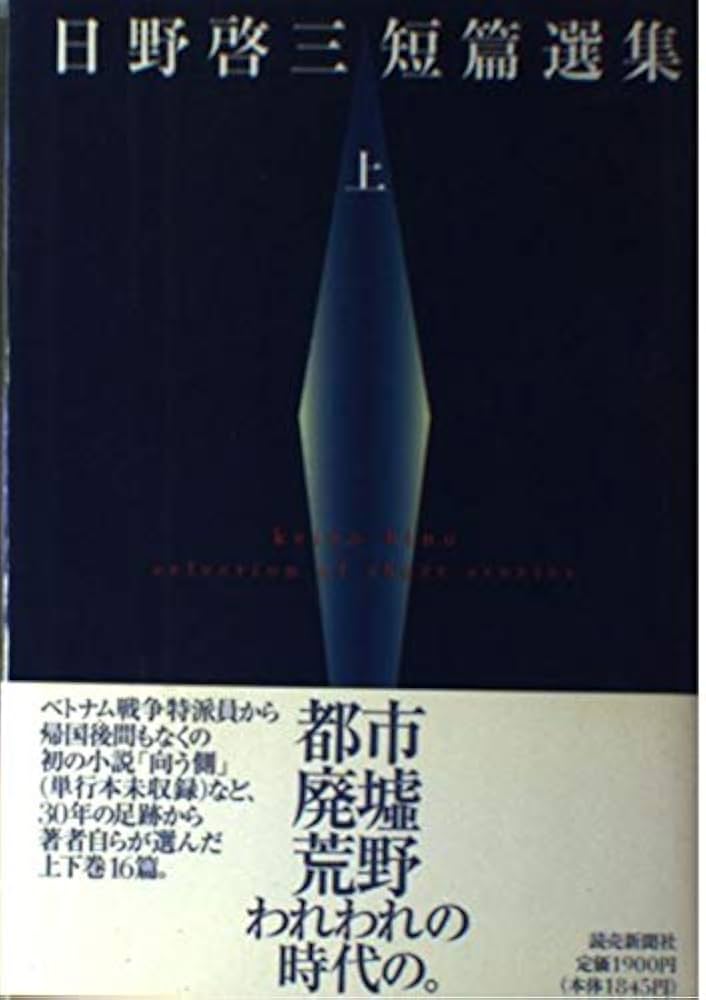
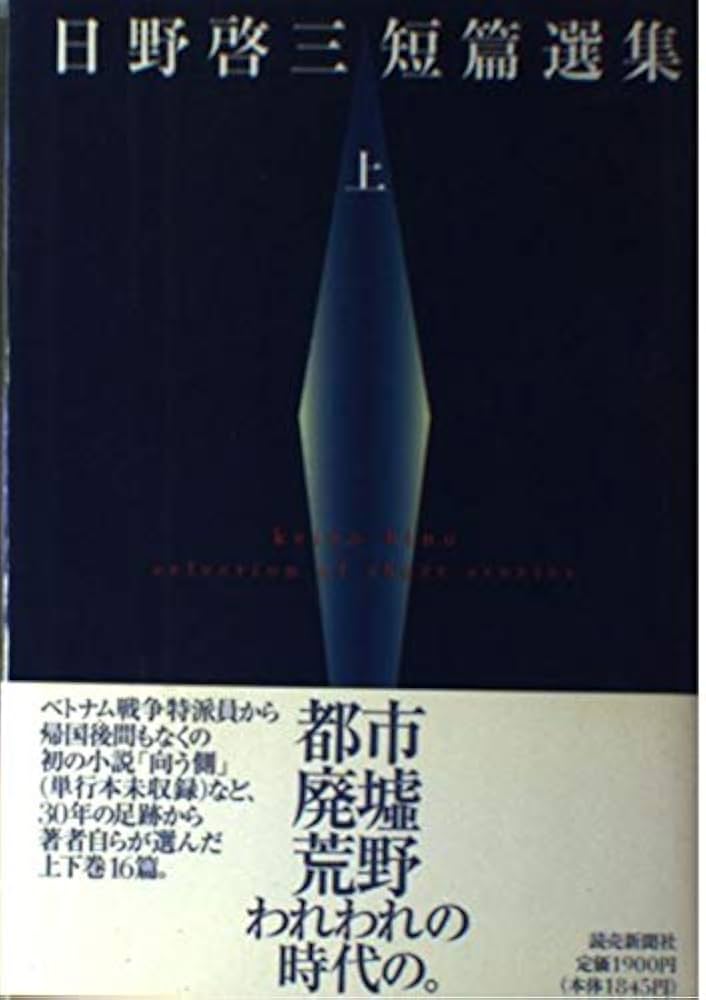
14位には、日野啓三の小説家デビュー作である「向う側」がランクインしました。1966年に発表されたこの短編は、ベトナム戦争下のサイゴンを舞台に、特派員として赴任した主人公が、行方不明になった前任者の足取りを追う物語です。
前任者は「向う側」へ行くと言い残して姿を消したとされています。この「向う側」が意味するのは、解放戦線の支配地域なのか、それとももっと形而上学的な場所なのか、あるいは死や精神の崩壊を指すのか。物語は、戦争という極限状況を背景にしながらも、単なる戦場ルポルタージュに留まらず、人間の存在そのものを問うような深遠なテーマを扱っています。



デビュー作って、その作家さんの全てが詰まっている感じがするよね。「向う側」って言葉、すごく意味深で気になるな。
15位『梯の立つ都市』
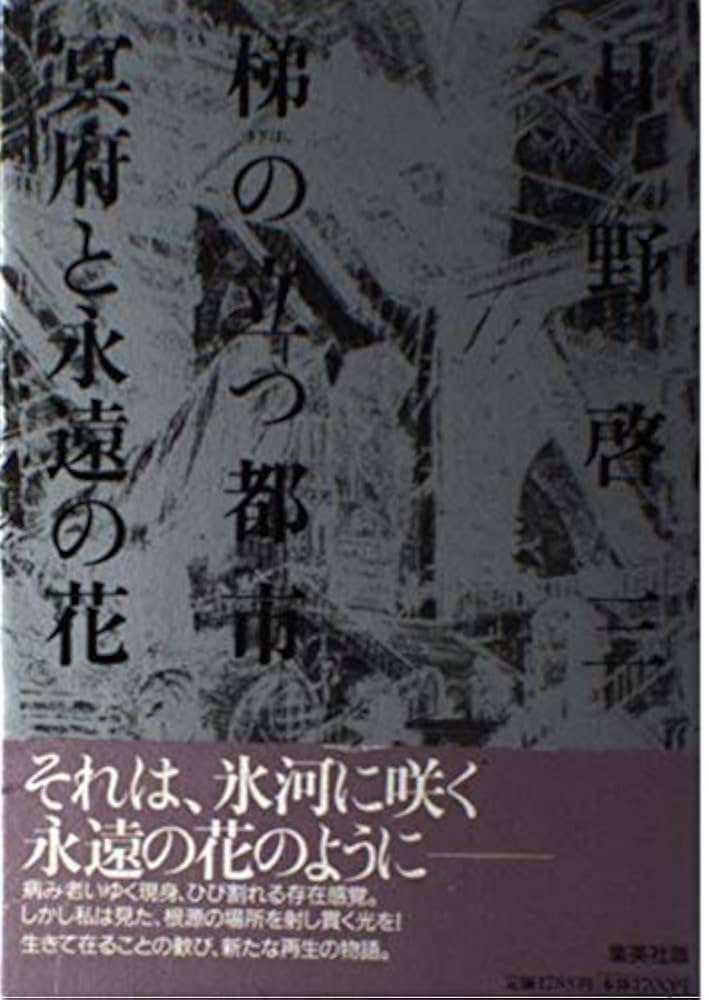
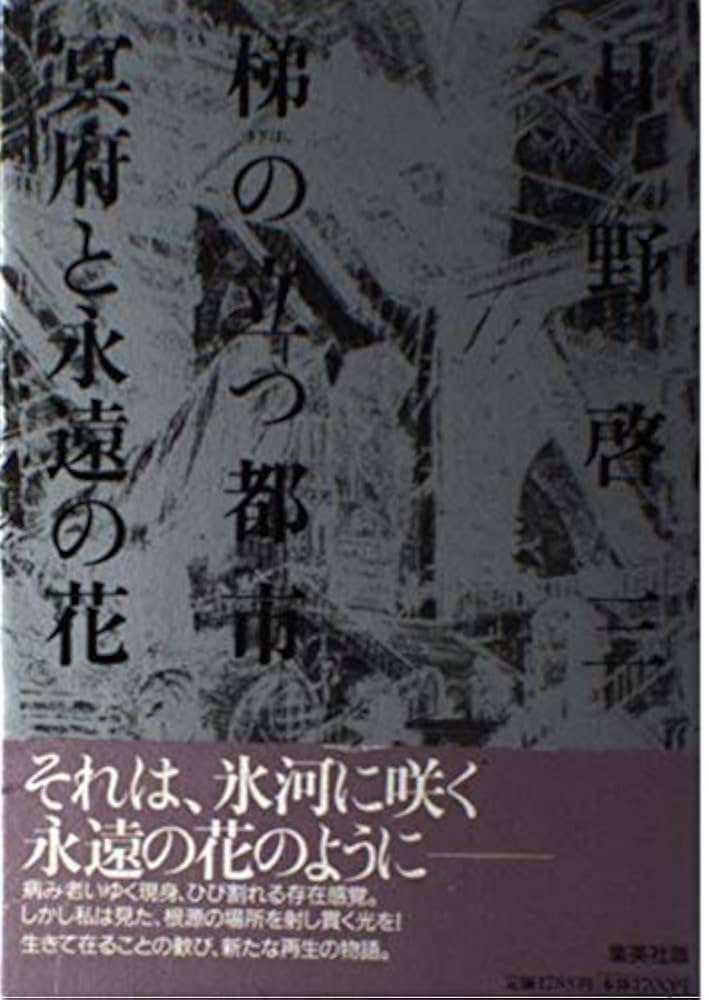
15位は、日野啓三の「都市小説」の魅力を凝縮した短編集『梯の立つ都市』です。物語の舞台は、私たちが日常を過ごすありふれた都会。しかし、主人公たちはふとした瞬間に、現実世界にぽっかりと空いた異次元への入り口を発見してしまいます。高層ビルの屋上に現れる謎の梯子、地下鉄のホームから続く奇妙な通路。日常と非日常が溶け合う独特の世界観は、読者を不思議な感覚へと誘います。



いつもの街に異世界への入り口があるなんて、ワクワクする設定だね!帰り道が冒険に変わっちゃうかも。
16位『単独行者(ソリスト)』
ランキングの最後を飾るのは、ベトナム戦争の体験を色濃く反映した初期の代表作『単独行者(ソリスト)』です。特派員としてサイゴンに滞在する主人公が、戦争の狂気と日常が隣り合わせになった街で、人間の孤独や存在の不確かさと向き合います。戦場の生々しい現実と、個人の内面に広がる幻想的な世界が交錯する本作は、日野文学の原点ともいえる重要な一冊です。ジャーナリストとしての鋭い視点と、小説家としての深い洞察力が見事に融合しています。



戦争の真ん中で孤独を感じるって、想像もつかないな。現実と幻想が混ざり合う感覚、読んで確かめてみたいよ。

