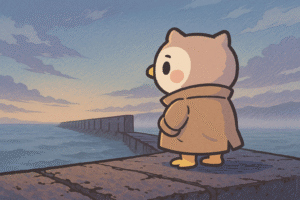あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】森内俊雄のおすすめ小説ランキングTOP20

森内俊雄の小説の魅力とは?静謐な文章で描かれる人気作品をランキングで紹介
森内俊雄(もりうち としお)は、1936年大阪府生まれの小説家・詩人です。早稲田大学文学部露文科を卒業後、編集者として働きながら創作活動を開始しました。1969年に『幼き者は驢馬に乗って』で文學界新人賞を受賞し、その後も5回にわたり芥川賞候補となるなど、早くからその才能を注目されていました。
森内作品の大きな魅力は、詩的で静謐と評される美しい文章です。日常に潜む不条理や不安、人間や人生への深い洞察を、鋭く繊細な感覚で描き出しています。精神を病んだ自らの経験を基にした『氷河が来るまでに』や、故郷や家族への思慕を描いた作品など、そのテーマは多岐にわたります。本記事では、そんな森内俊雄の数ある名作の中から、特におすすめの作品をランキング形式でご紹介します。
森内俊雄のおすすめ人気小説ランキングTOP20
ここからは、森内俊雄のおすすめ人気小説をランキング形式で一挙にご紹介します。読書メーターのランキングやブクログのユーザー評価などを参考に、特に人気の高い作品を選出しました。静かで深い余韻を残す森内文学の世界を、ぜひこのランキングから旅してみてください。
1位『梨の花咲く町で』
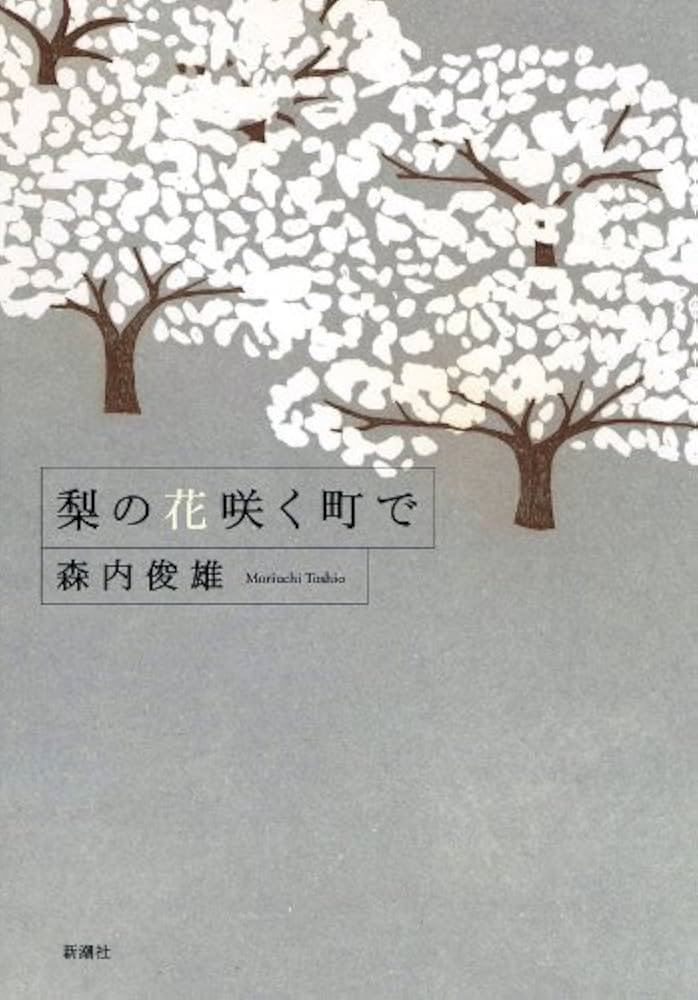
読書メーターのランキングで特に人気が高いのが、2011年に刊行された『梨の花咲く町で』です。物語は静かに進行し、読んでいるとまるで水の中に沈んでいるかのような、音のない世界に引き込まれる感覚を覚える読者もいるようです。
穏やかながらも、生と死や記憶といった普遍的なテーマを扱い、深い余韻を残す一冊。森内文学の真骨頂ともいえる静謐な世界観が凝縮されており、初めて森内作品に触れる方にもおすすめです。
 ふくちい
ふくちい静かな文章が心に染み渡るみたいだね。穏やかな気持ちで読みたいときにぴったりだよ。
2位『道の向こうの道』


2017年に発表された自伝的な連作集『道の向こうの道』は、森内俊雄の読書遍歴と青春時代が色濃く反映された作品です。物語は、1956年に大阪から上京し、早稲田大学の露文科で過ごした学生時代を中心に描かれています。戦争の影が残る時代を背景に、李恢成や宮原昭夫といった個性豊かな同級生たちとの交流や、読書に没頭する日々が生き生きと綴られています。
作中にはドストエフスキーから日本の古典まで、多種多様な書籍が登場し、当時の学生たちの文学への情熱が伝わってきます。目立った起伏はなく、落ち着いた筆致で語られる回想は、読者に心地よい読書体験をもたらしてくれるでしょう。



昔の学生さんの読書熱ってすごいんだね!わたしもいろんな本を読んでみたくなったよ。
3位『氷河が来るまでに』
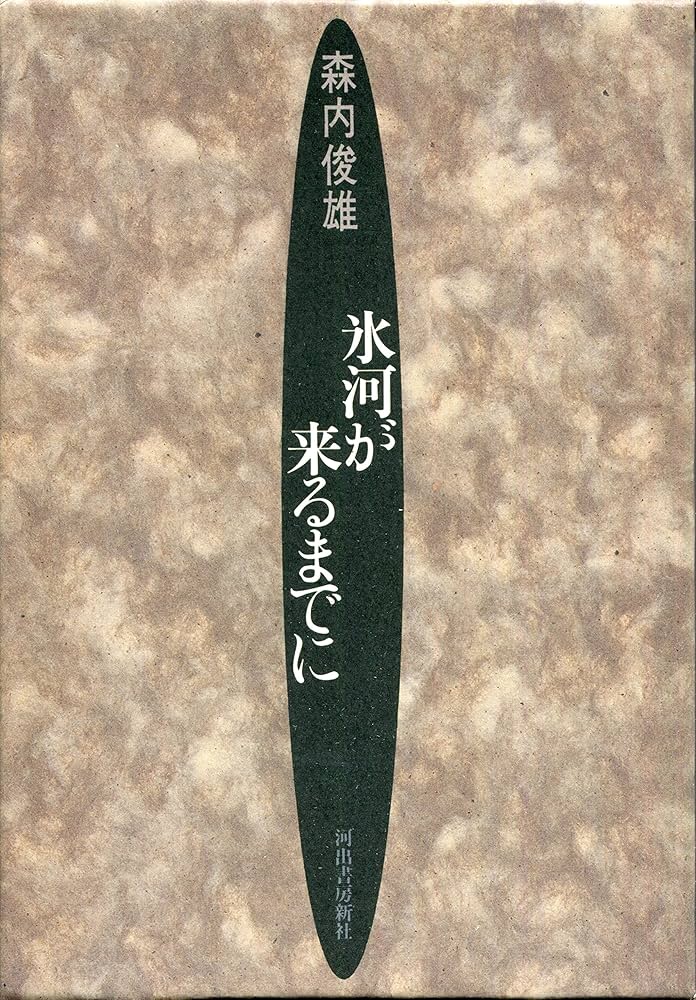
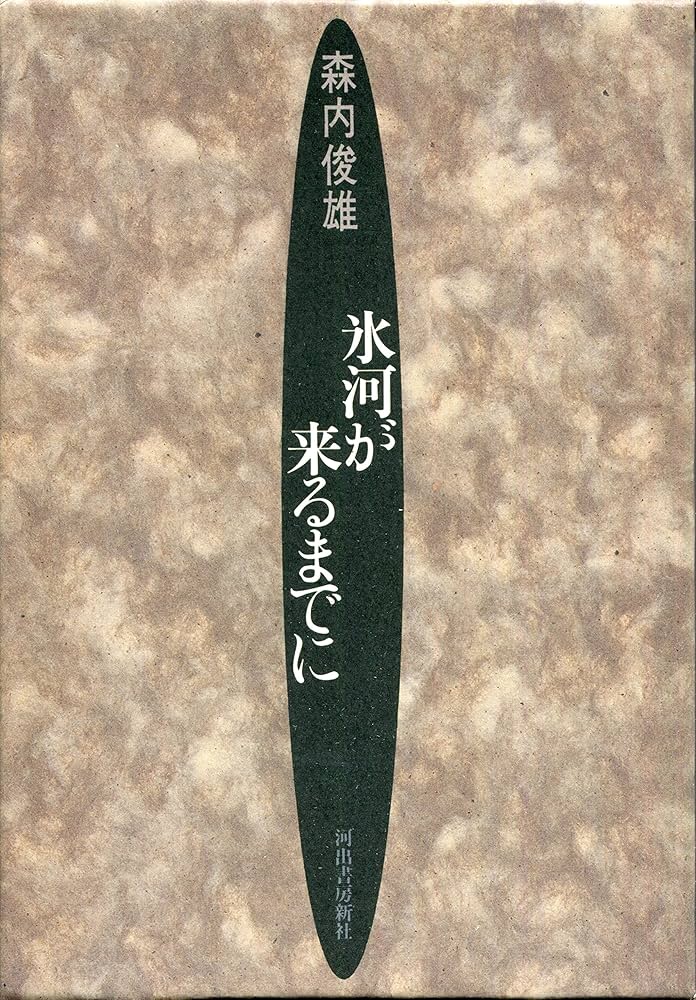
1990年に刊行され、第42回読売文学賞と芸術選奨文部科学大臣賞を受賞した『氷河が来るまでに』は、森内俊雄の代表作の一つです。この作品は、作者自身が精神を病んだ経験を基にしており、その内面が赤裸々に描かれています。高い評価を受ける一方で、そのテーマ性からか、読者にとっては非常に重く、読むのに覚悟がいる作品ともいえるでしょう。
しかし、その静謐な文体で描かれる苦悩と再生の物語は、多くの読者の心を打ち、森内文学の奥深さを感じさせます。現代社会に生きる私たちが抱える不安や孤独と共鳴する部分も多く、時代を超えて読み継がれるべき傑作です。



作者自身の経験が元になってるんだ…。読むのに少し勇気がいるけど、すごく大切なことが書かれていそうだよ。
4位『骨の火』
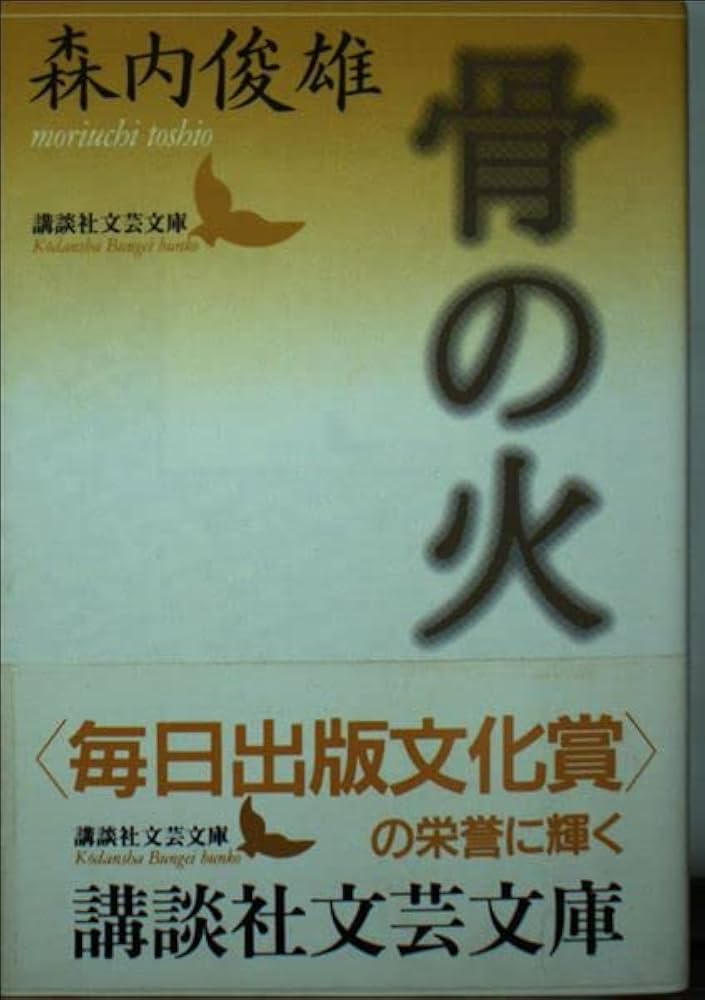
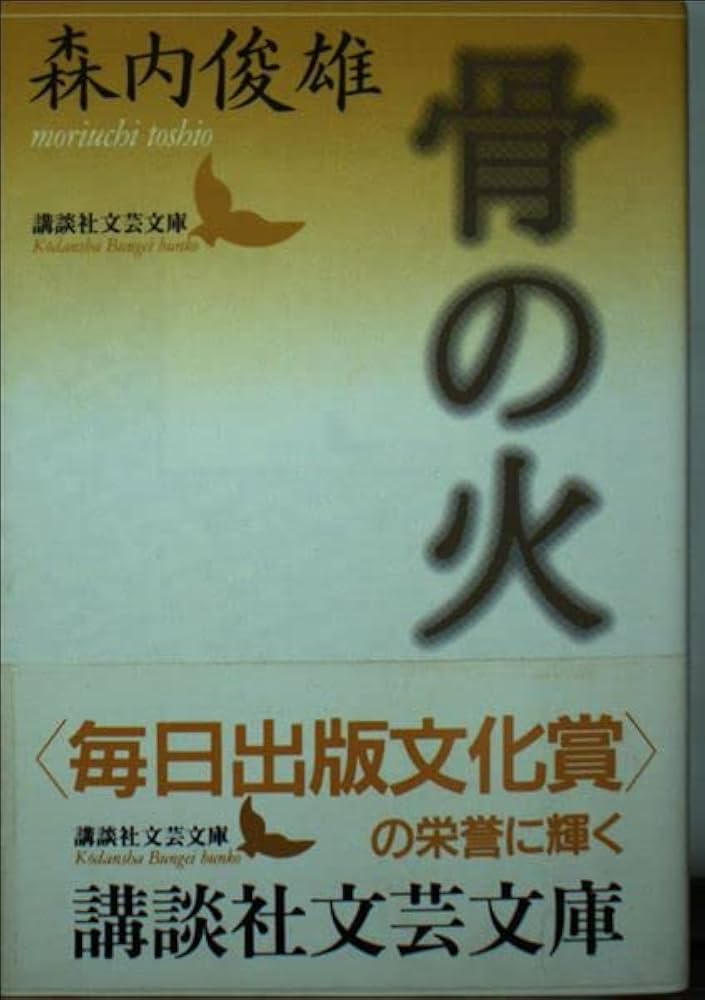
1986年に文藝春秋から刊行された『骨の火』は、森内文学の中でも特に幻想的で、死の匂いが色濃く漂う作品として知られています。物語は、日常の中にふと現れる不条理や、生と死の境界が曖昧になる瞬間を捉え、読者を不思議な世界へと誘います。
静かな筆致で淡々と語られる物語の中には、どこか恐ろしさや不気味さが潜んでおり、その独特の雰囲気が魅力です。派手な展開はありませんが、じわじわと心に染み入るような恐怖と美しさが同居した、忘れがたい読書体験をもたらしてくれます。



本作における静謐な語り口は、死というテーマに対する作者の深い洞察を感じさせる。その筆致からは、恐怖を超えたある種の覚悟すら読み取れる。
5位『十一月の少女』
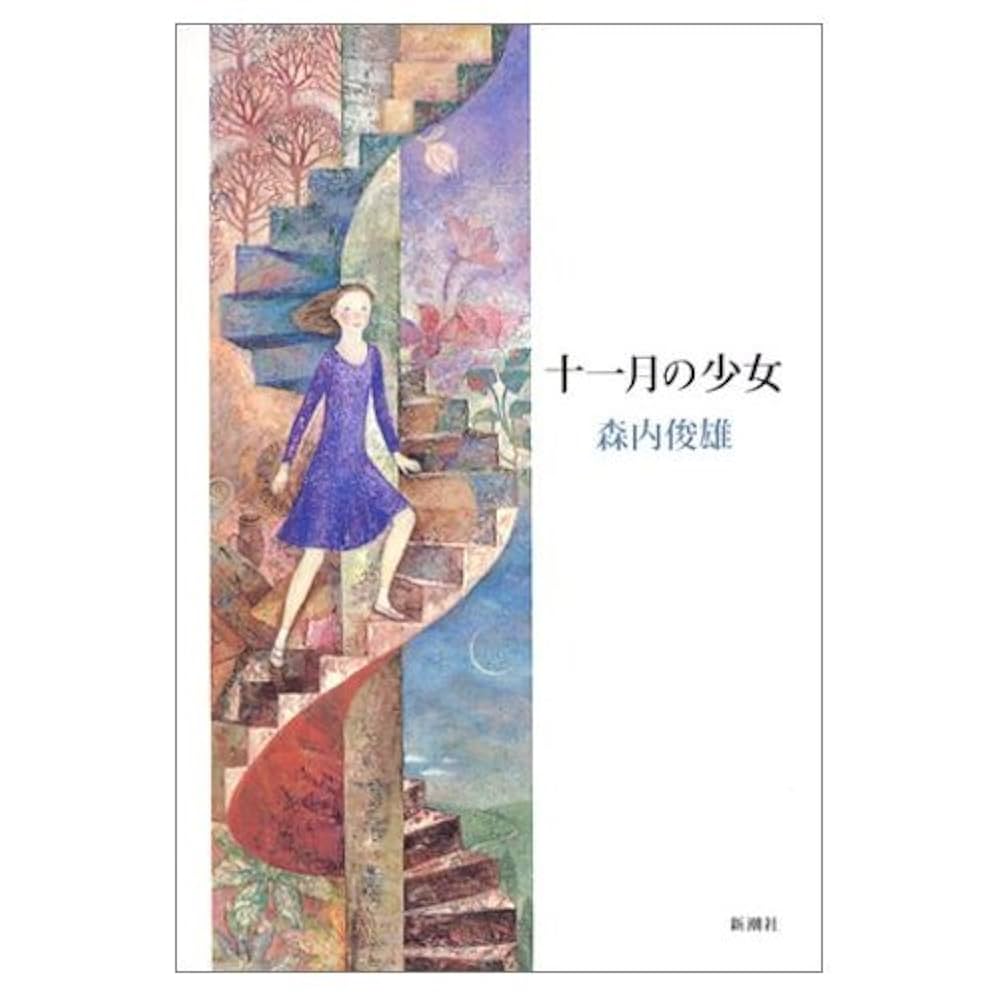
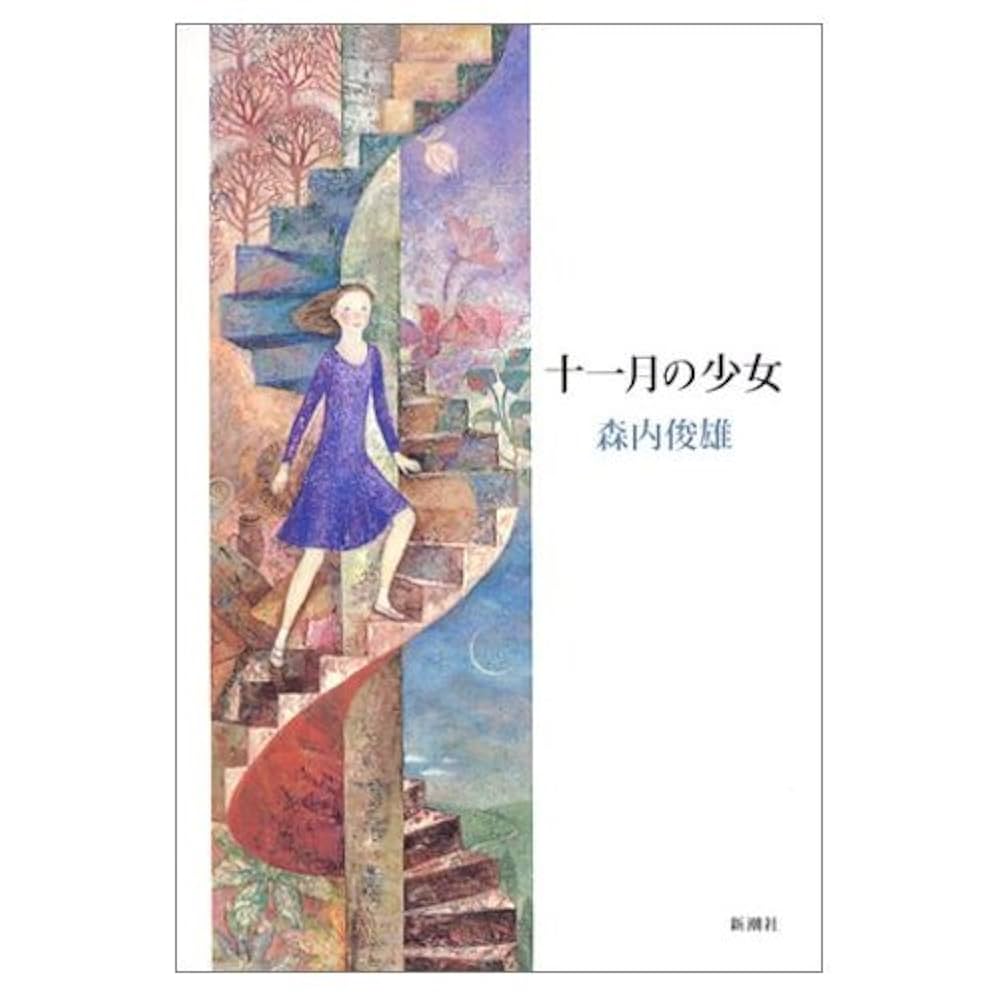
2003年に新潮社から出版された『十一月の少女』は、ある少女との出会いと別れを描いた、切なくも美しい物語です。森内俊雄特有の静かで透明感のある文章が、物語全体を優しく包み込んでいます。読者からは、その独特の文体や世界観に「クセが強い」と感じる声もありますが、それこそが森内文学の魅力ともいえるでしょう。
物語の具体的な筋書きよりも、作中に流れる空気感や情景、登場人物たちの繊細な心の動きを味わう作品です。秋の終わりのような、少し寂しくも澄んだ気持ちに浸りたいときに手に取りたい一冊。読後には、静かな感動が心に残ります。



ちょっとクセがあるみたいだけど、そこがまた魅力的なんだろうね。どんな少女の物語なのか気になるよ。
6位『幼き者は驢馬に乗って』
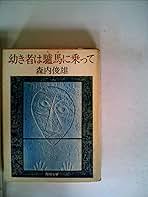
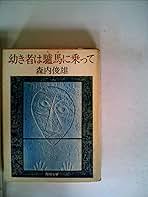
1969年に発表された『幼き者は驢馬に乗って』は、森内俊雄のデビュー作であり、第29回文學界新人賞を受賞した記念碑的な作品です。この作品で文壇に登場した森内は、同作で芥川賞候補にもなり、一躍注目を集めました。
若き日の作者の瑞々しい感性と、後の作品にも通じる静謐な文体の萌芽が見られる一冊です。デビュー作ながら、すでに森内文学の世界観が確立されており、その才能のきらめきを感じることができます。作家・森内俊雄の原点を知る上で、欠かすことのできない重要な短編です。



デビュー作って作家さんの原石みたいでわくわくするよね。ここからあの世界が始まったんだ。
7位『翔ぶ影』
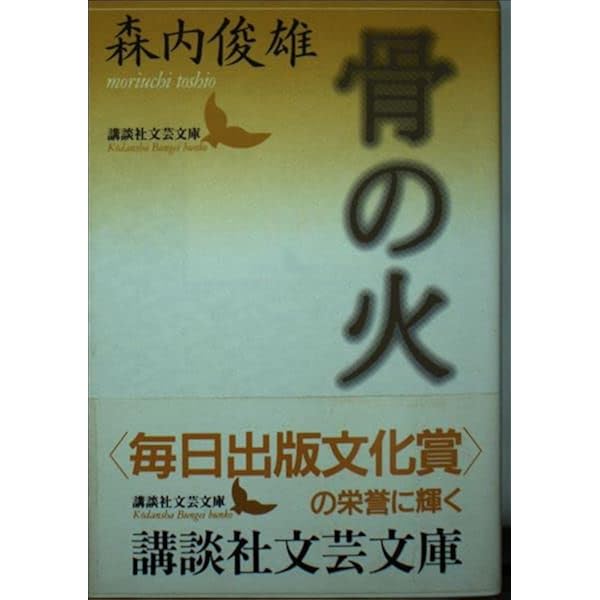
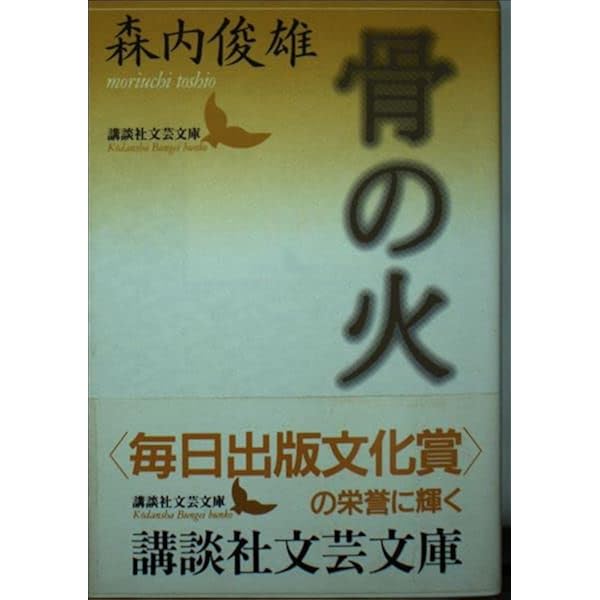
1973年に発表され、第1回泉鏡花文学賞を受賞した『翔ぶ影』は、森内俊雄の初期の代表作の一つです。この作品は、幻想的で詩的な世界観が特徴であり、泉鏡花の文学世界とも通じるものがあります。日常の中に潜む神秘や、人間の心の奥深くにある不可思議な領域を描き出しています。
現実と幻想が交錯するような独特の物語は、読者を現実から少しだけ離れた場所へと連れて行ってくれます。論理では説明できない世界の美しさや妖しさを、静かな筆致で描ききった名作です。森内文学の持つ幻想的な側面に触れたい方におすすめの一冊です。



泉鏡花文学賞を受賞した作品なんだね!幻想的なお話、大好きだからすごく読んでみたいな。
8位『真名仮名の記』
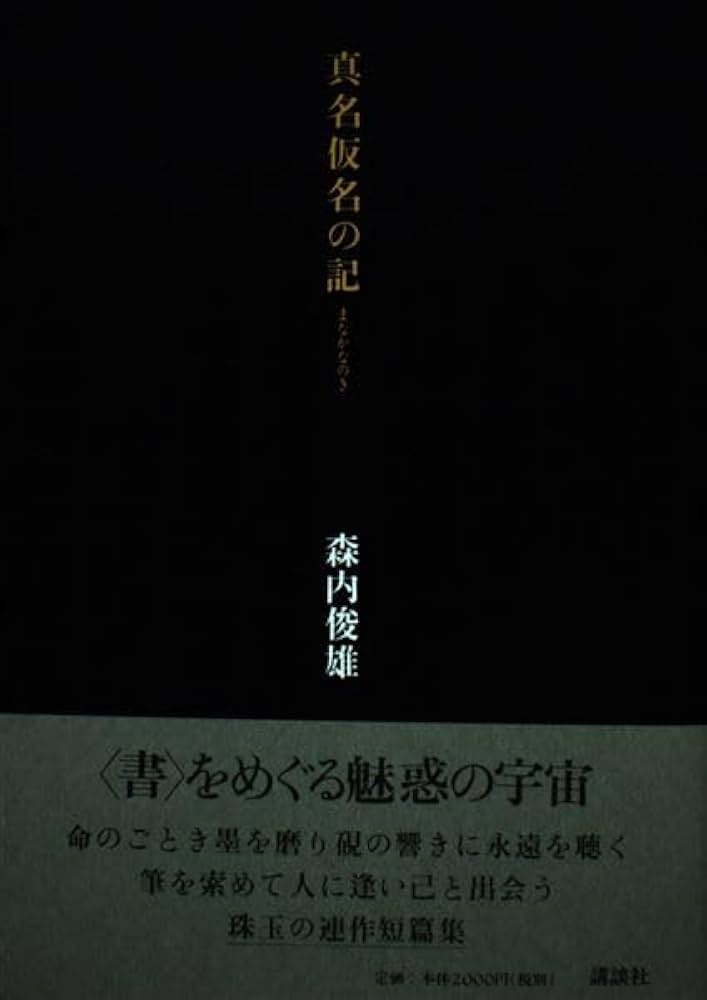
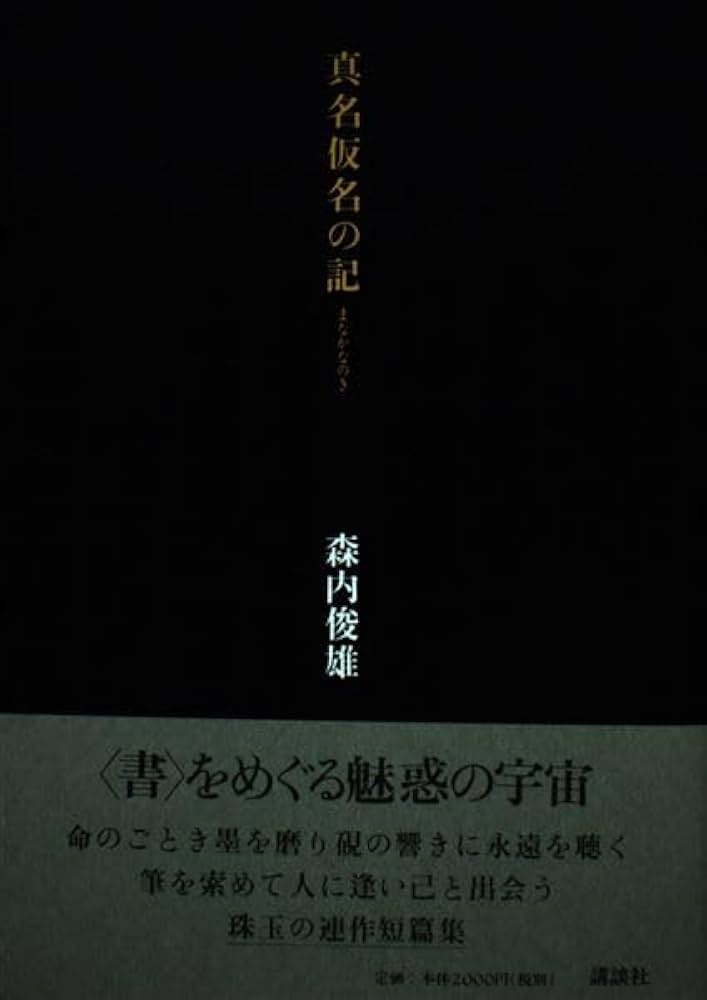
2001年に講談社から刊行された『真名仮名の記』は、エッセイのようでもあり、私小説のようでもある、独特の味わいを持つ作品です。日常の出来事や思索が、森内俊雄ならではの美しい文章で綴られており、その深い思索に触れることができます。
言葉一つ一つを大切に紡いでいくような丁寧な筆致は、読者の心を穏やかにしてくれます。作家の日常や内面を垣間見ることで、他の小説作品をより深く理解する手助けにもなるでしょう。静かな時間に、ゆっくりとページをめくりたい一冊です。



エッセイみたいな小説って作家さんの素顔が少し見える気がして好きだな。どんなことが書かれているんだろう。
9位『夢のはじまり』
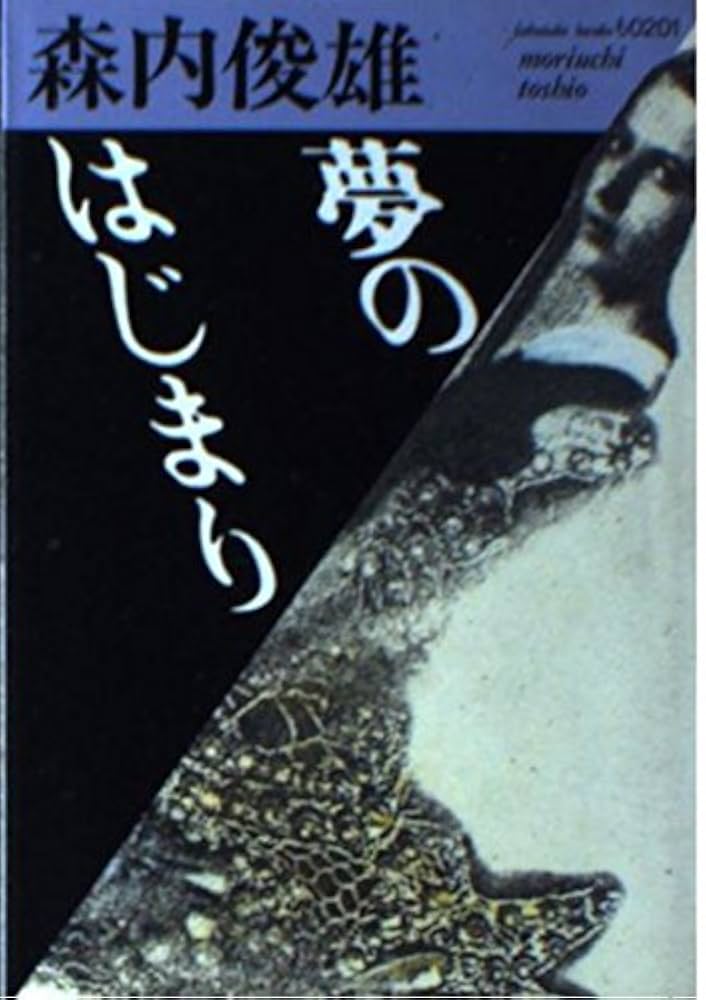
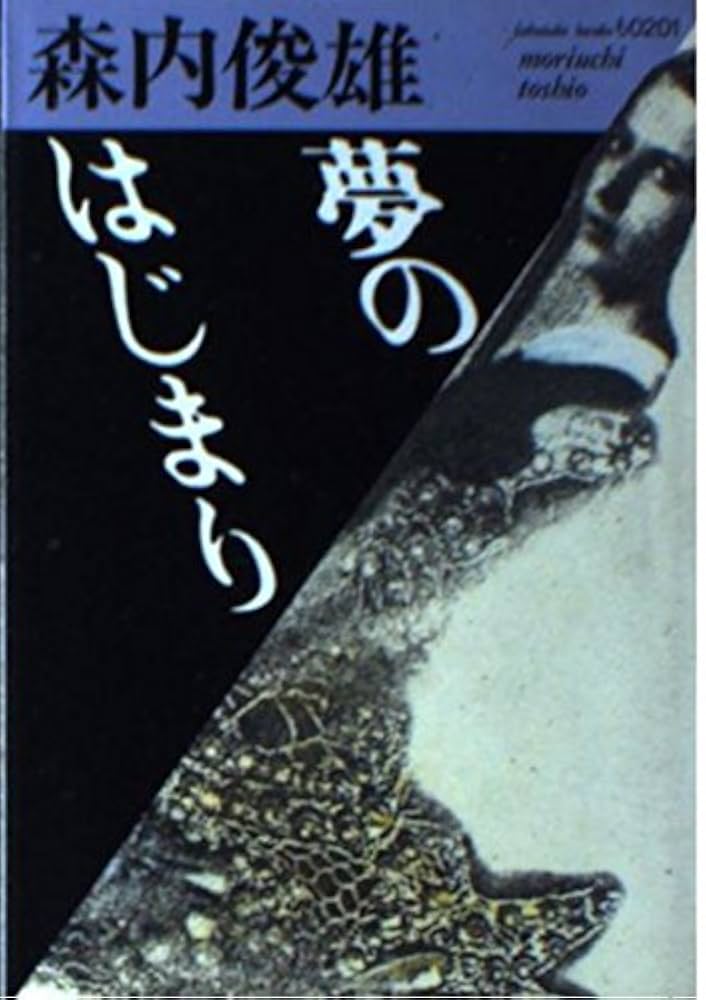
1987年に福武文庫から刊行された『夢のはじまり』は、作者自身が選んだ短編集です。この一冊で、森内俊雄の多様な短編世界の魅力を味わうことができます。初期の作品からこの時期までの代表的な短編が収められており、森内文学への入門書としても最適です。
それぞれの短編は独立した物語でありながら、どこか通底する静謐な空気感や、生と死を見つめる眼差しを感じることができます。どの話から読んでも、その独特の世界に引き込まれることでしょう。森内俊雄の作品を初めて読む方や、どの作品から読めばいいか迷っている方におすすめです。



作者さんが自分で選んだ短編集ってすごく贅沢だよね。まさにベスト盤って感じ!
10位『空にはメトロノーム』
『空にはメトロノーム』は2003年に書肆山田から刊行された詩集で、この作品で森内俊雄は第4回山本健吉文学賞(詩部門)を受賞しました。小説家として知られる森内ですが、詩人としても高い評価を受けていることがわかります。彼の小説の魅力である詩的で美しい文章の源流が、ここにあると言えるでしょう。
言葉を削ぎ落とし、その響きやリズムを大切にした詩の世界は、小説とはまた違った形で心に直接響いてきます。森内文学の静謐さや透明感を、より純粋な形で感じたい方におすすめです。小説と合わせて読むことで、その世界観をさらに深く味わうことができます。



小説だけじゃなくて詩集も出してるんだね!言葉がすごく綺麗だから、詩もきっと素敵なはずだよ。
11位『谷川の水を求めて』
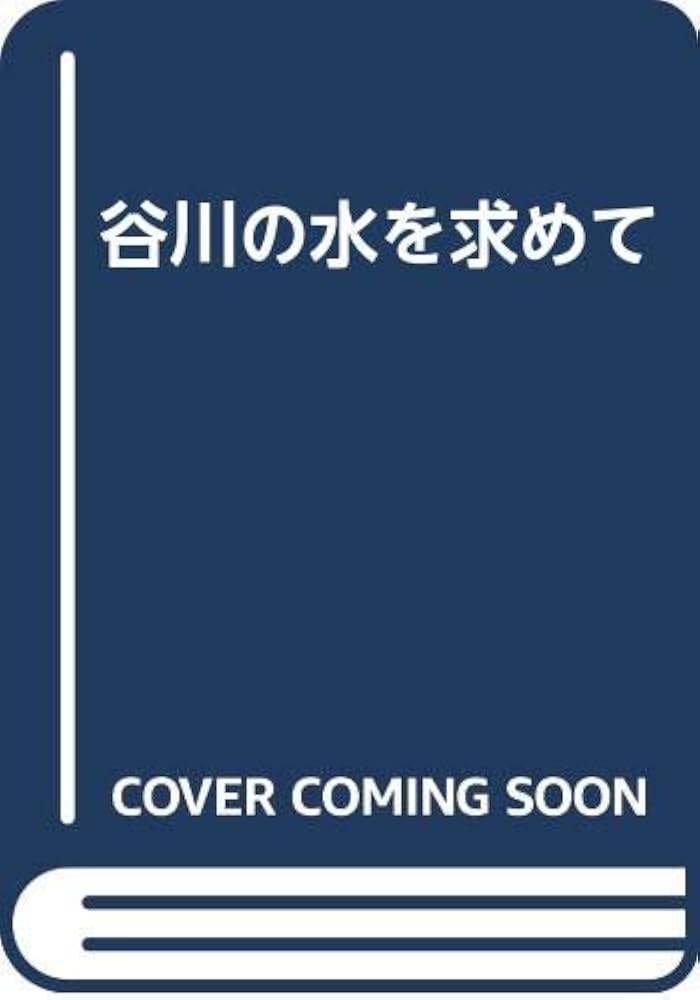
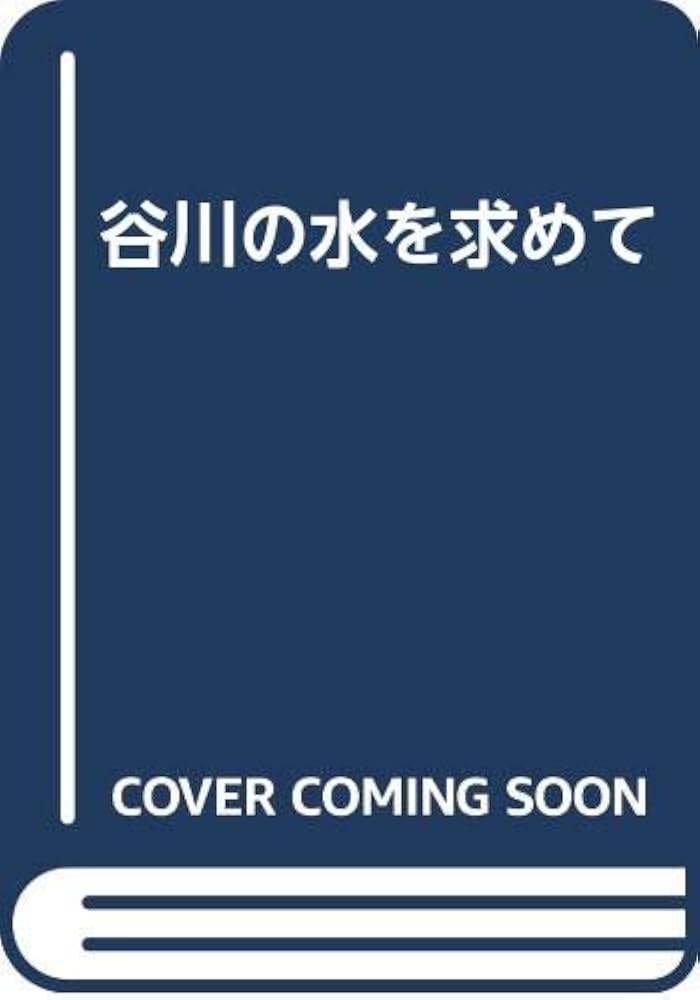
1994年に河出書房新社から刊行された『谷川の水を求めて』は、森内俊雄の精神世界や宗教観が色濃く反映された作品です。高校在学中にカトリックの洗礼を受けたという作者のバックグラウンドが、物語の根底に流れています。しかし、それは決して難解な宗教小説ではなく、普遍的な人間の魂の渇きや救いをテーマにしています。
静かな筆致で描かれる求道の物語は、読者の心に深く染み渡り、生きることの意味を問いかけます。日々の喧騒から離れ、自分の内面と静かに向き合いたいときに手に取りたい一冊です。森内文学の持つ精神性の高さに触れることができます。



なんだか心が洗われるようなお話みたい。静かに自分と向き合いたい時に読んでみたいな。
12位『短篇歳時記』
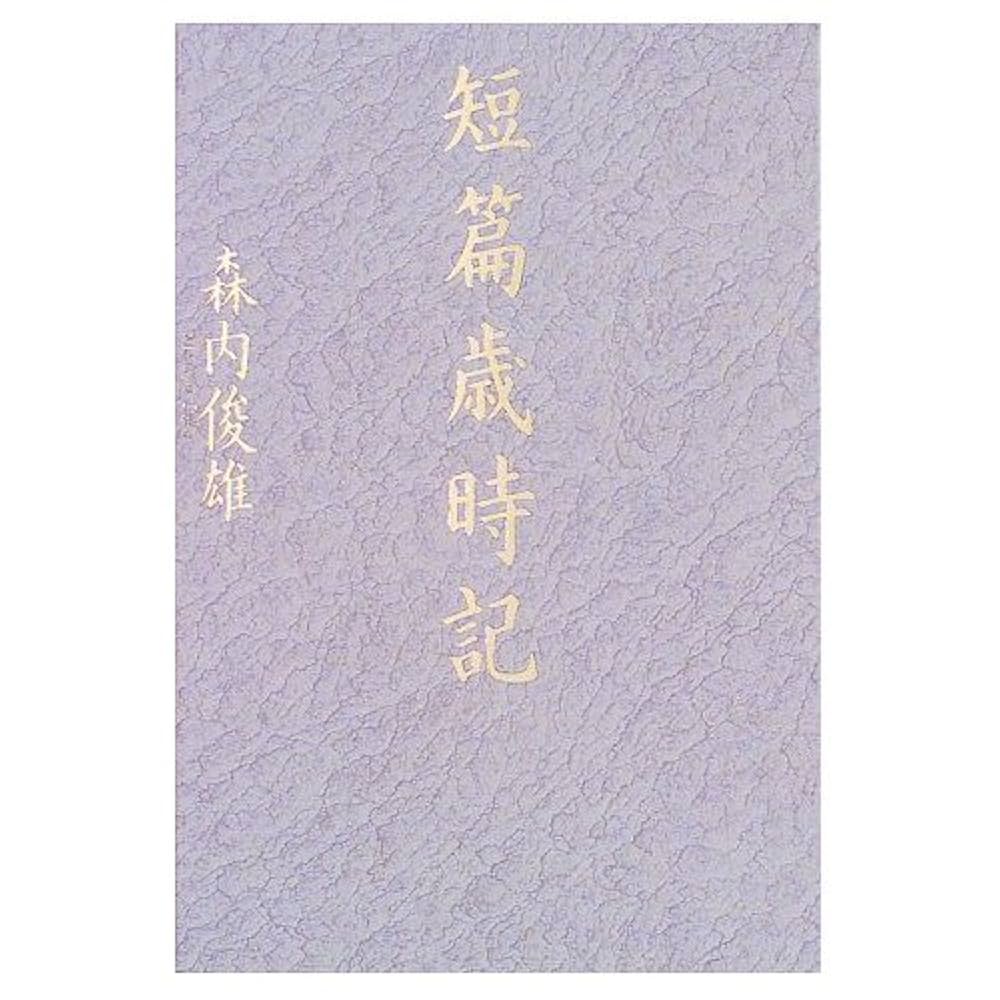
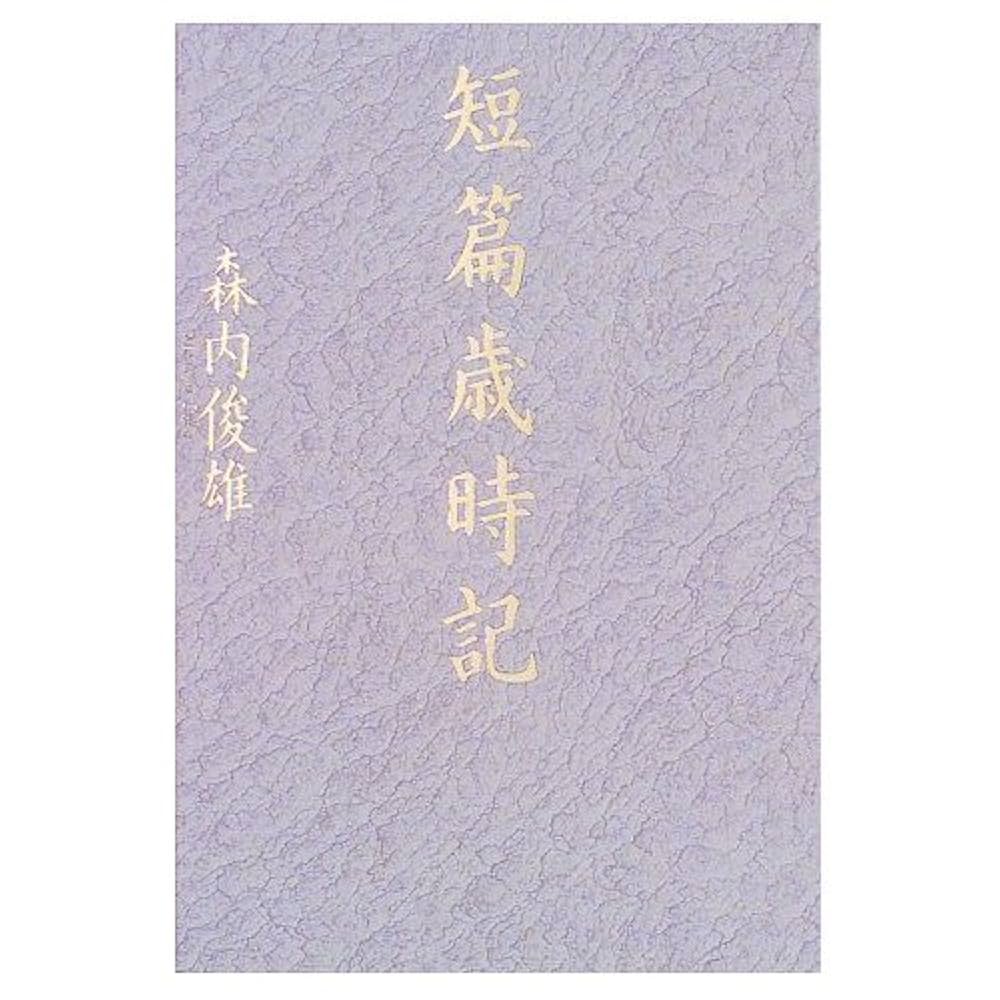
1999年に講談社から刊行された『短篇歳時記』は、百句の俳句を題材にして書かれた百篇の短編小説が収められているユニークな作品集です。季語や俳句の世界観からインスピレーションを得て紡がれた物語は、それぞれが短くも豊かな情景と情感に満ちています。
日本の四季の移ろいや、そこに生きる人々の機微が、森内俊雄ならではの繊細な筆致で描かれています。俳句と小説という二つの文学形式が美しく融合した、他に類を見ない一冊です。どこから読んでも楽しめ、日本語の美しさを再発見させてくれます。



俳句から作った百個の短編だなんて、すごくおしゃれだね!日本の四季を感じられそうで素敵だよ。
13位『一日の光あるいは小石の影』
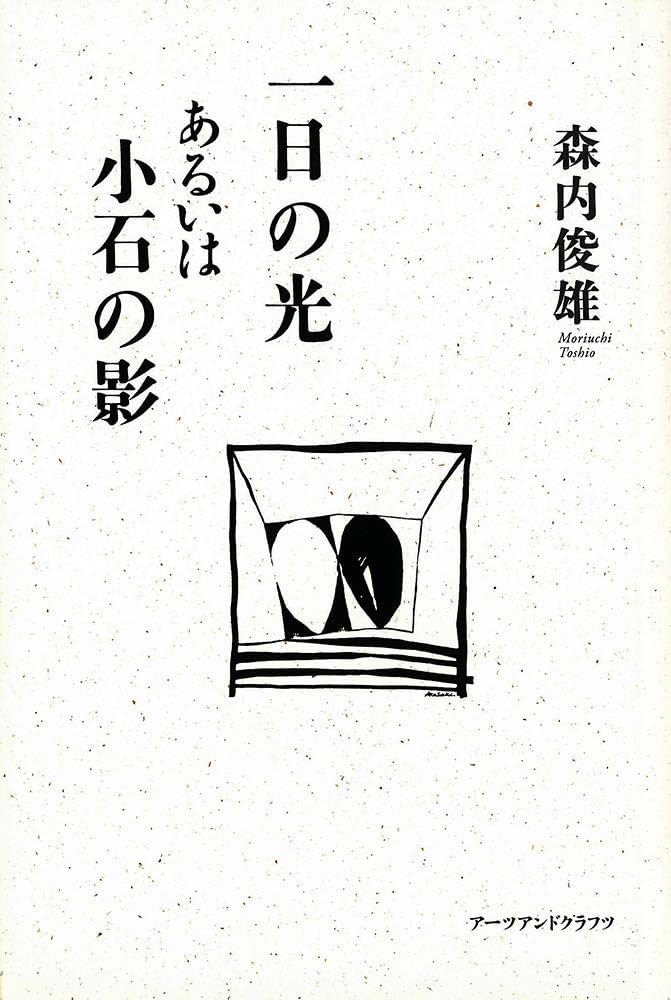
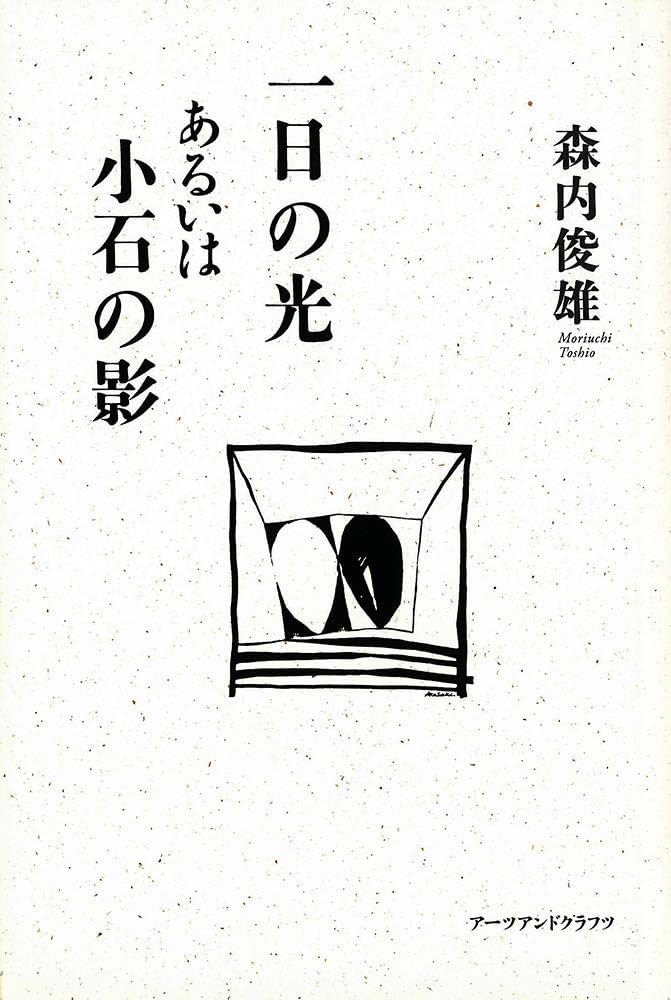
『一日の光あるいは小石の影』は、森内俊雄の晩年の作品の一つです。この作品集では、日常の何気ない風景や出来事の中に潜む、きらめきや影を丁寧にすくい上げています。老境に至った作家の円熟した眼差しが、世界をより深く、そして優しく見つめているのが感じられます。
派手な事件が起こるわけではありませんが、一篇一篇の物語が静かな感動を呼び起こします。小石の影に宇宙を見るような、その繊細な感性は健在です。人生の機微を味わい深く描いた短編の数々は、忙しい日々の中で見失いがちな大切なものに気づかせてくれるでしょう。



日常の小さな光を見つけるようなお話なのかな。なんだか心が温かくなりそうだね。
14位『骨川に行く』
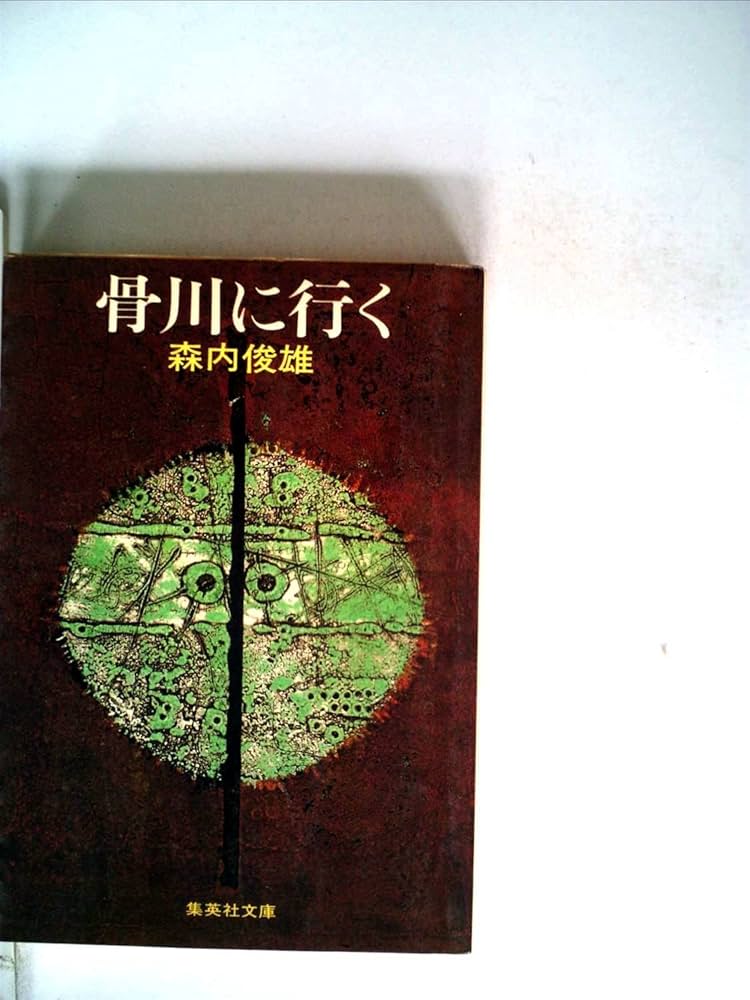
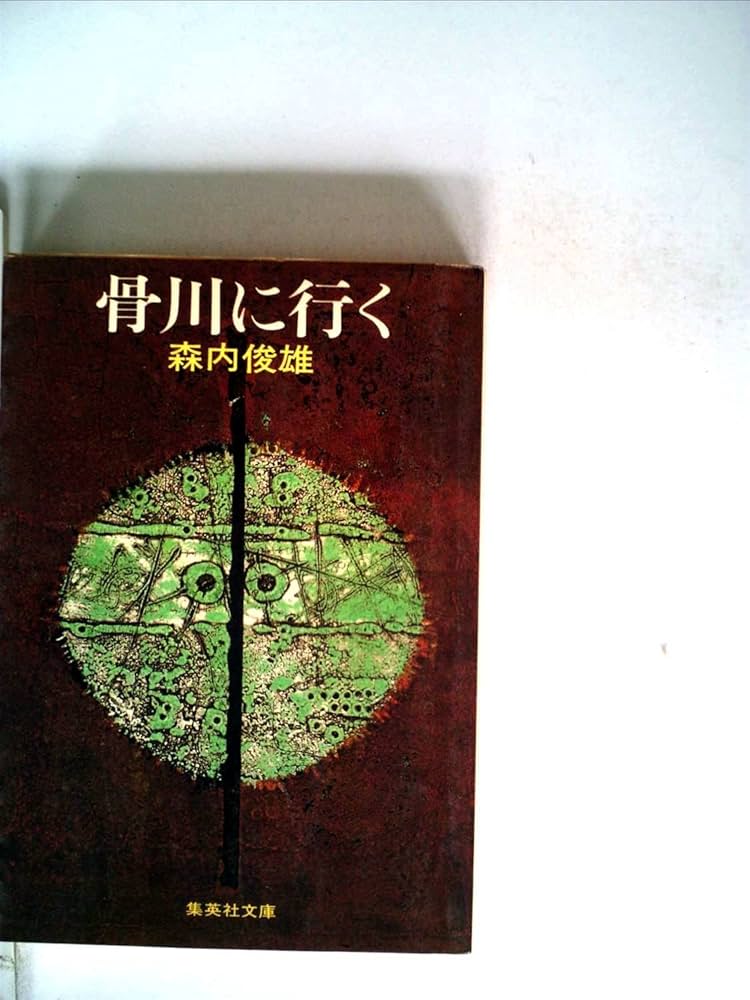
1971年に新潮社から刊行された『骨川に行く』は、森内俊雄の初期の作品で、芥川賞の候補にもなりました。この作品は、死や喪失といったテーマを扱いながらも、どこか幻想的で不思議な雰囲気をまとっています。初期作品ならではの鋭さと、後の作品にも通じる静謐さが同居しています。
「骨川」という象徴的な地名が示すように、物語は生と死の境界線を彷徨うような感覚を読者にもたらします。若き日の森内俊雄が描く、不条理で美しい世界に触れることができる一冊です。その後の作家の歩みを知る上でも重要な作品と言えるでしょう。



「骨川」という地名からして、本作が死の領域に深く踏み込んでいることが窺える。初期作品の持つ荒削りなエネルギーと、研ぎ澄まされた感性の融合は注目に値する。
15位『風船ガムの少女』
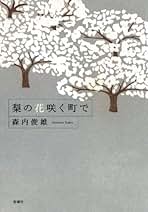
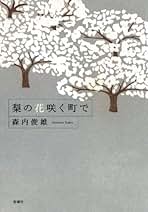
1988年に福武書店から刊行された『風船ガムの少女』は、タイトルからも伺えるように、ある少女をめぐる物語です。森内作品にしばしば登場する、儚げで印象的な少女像がこの作品でも描かれています。日常の中にふと現れた非日常的な存在としての少女が、物語に不思議な彩りを添えています。
現実と幻想の狭間を揺れ動くような、独特の浮遊感が魅力の作品です。読者は少女の謎めいた存在に引き込まれ、物語の世界を彷徨うことになるでしょう。切なくも美しい読後感を味わえる、森内俊雄ならではの一冊です。



風船ガムの少女ってどんな子なんだろう。儚くて、すぐどこかへ消えてしまいそうなイメージだね。
16位『使者』
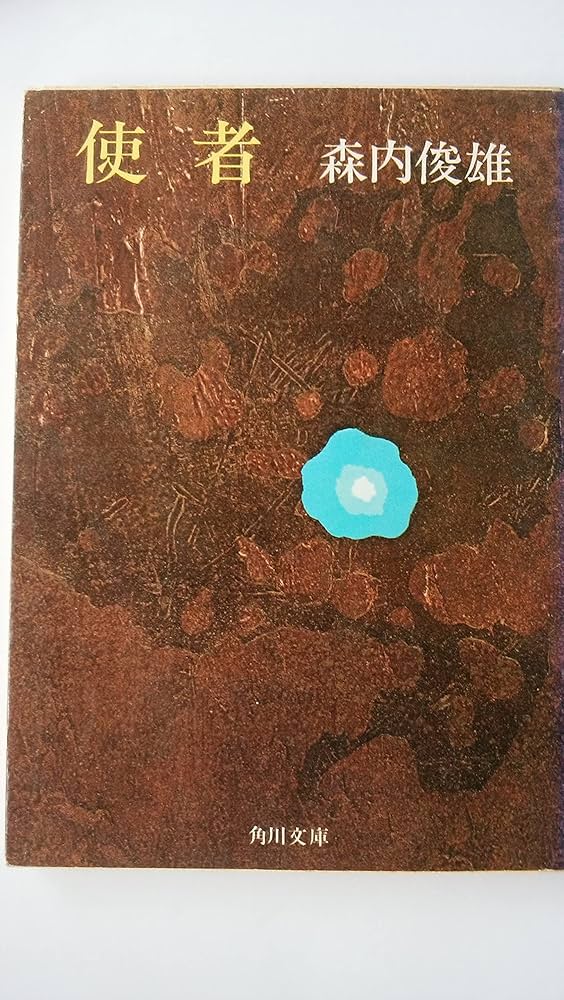
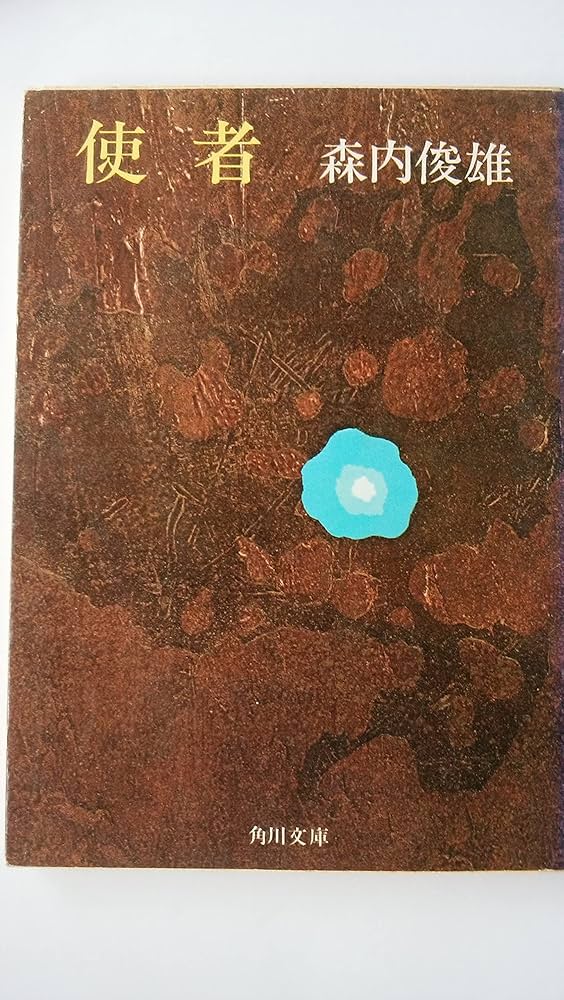
1978年に角川文庫から刊行された『使者』は、森内俊雄の初期の短編集の一つです。この時期の作品には、日常に潜む不条理や、目に見えない世界の存在を鋭く描き出すものが多く見られます。「使者」というタイトルが暗示するように、この世ならざるものからのメッセージや、運命の訪れをテーマにした物語が収められているのかもしれません。
後の作品の円熟した静謐さとは一味違う、若々しい感性が光る作品群です。人間の内面に潜む不安や孤独を、幻想的な筆致で描き出しています。森内文学の初期の魅力を知る上で、手に取ってみたい一冊です。



「使者」ってなんだかミステリアスな響きだね。一体誰が、何を使わしに来るんだろう…。
17位『黄経八十度』
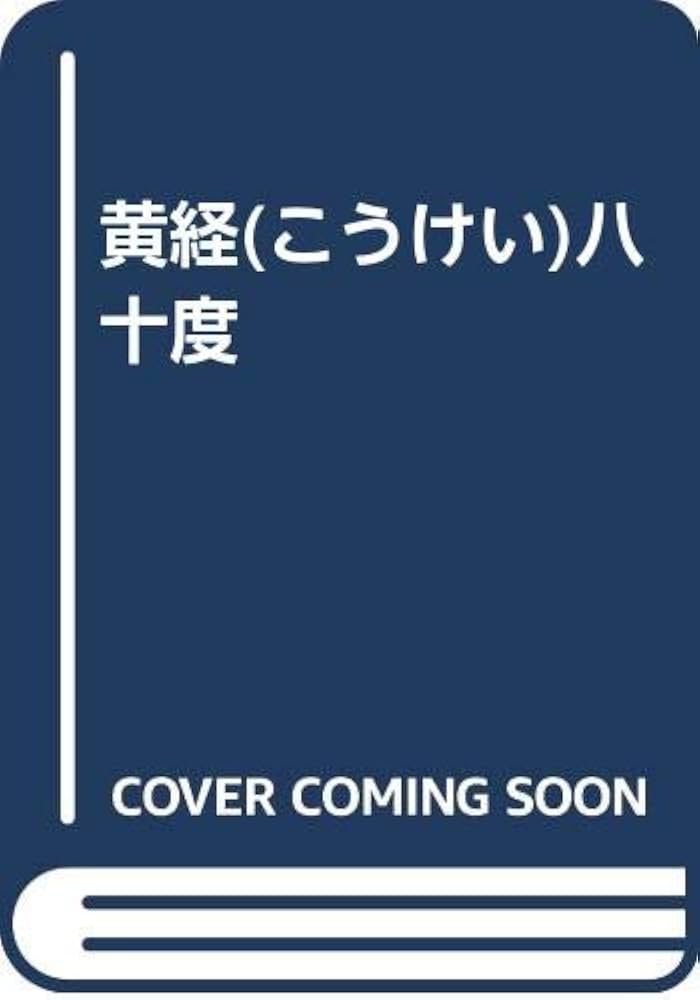
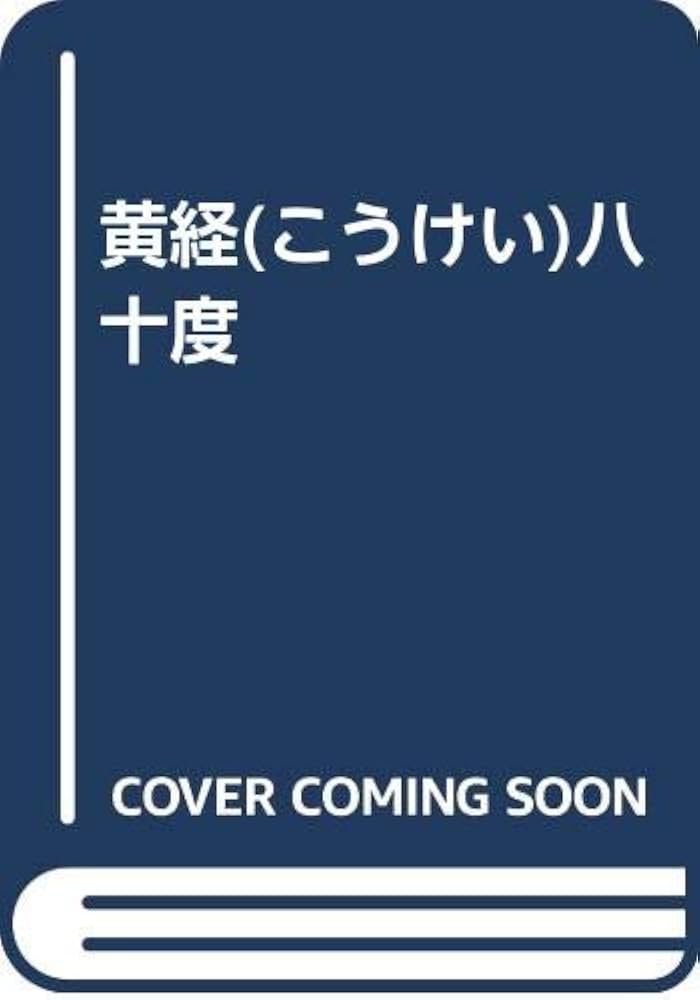
1986年に福武書店から刊行された『黄経八十度』は、異国情緒あふれる設定や、スケールの大きなテーマを扱った作品である可能性がうかがえます。「黄経八十度」という具体的な座標がタイトルになっていることから、ある特定の場所を舞台にした、あるいはそこを目指す旅の物語かもしれません。
森内俊雄の作品は、日本の静かな日常を描いたものが多い印象ですが、この作品ではまた異なる一面を見せてくれることが期待されます。地理的な広がりと、内面的な世界の深化がどのように結びついているのか、興味をそそられる一冊です。



黄経八十度ってどこなんだろう?地図で探してみたくなっちゃうね。冒険の物語なのかな。
18位『晒し井』
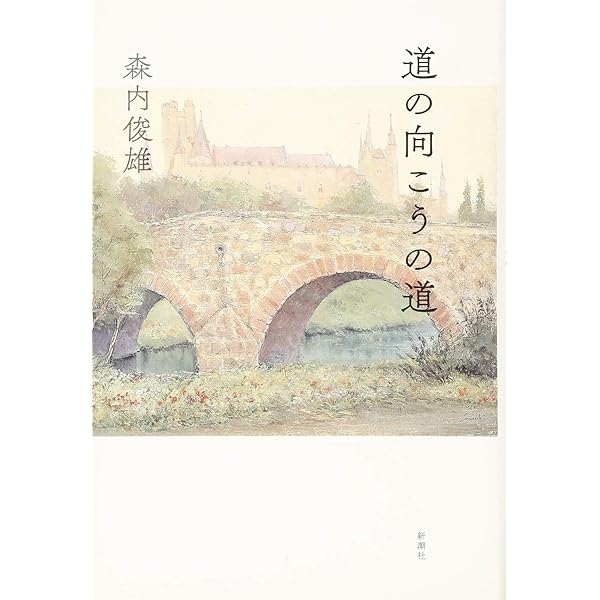
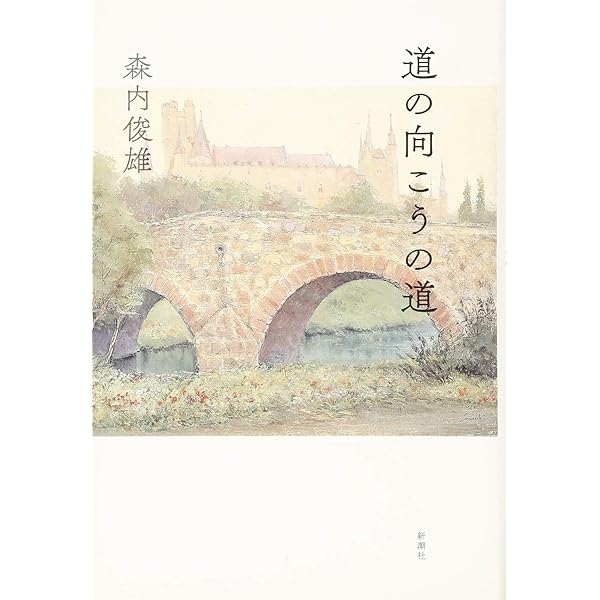
1997年に講談社から刊行された『晒し井』は、日本の古い伝承や風習を思わせるタイトルが印象的な作品です。「晒し井」という言葉には、何かを清める、あるいは白日の下に晒すといったイメージがあり、物語の核心に触れる重要なモチーフとなっていることが推測されます。
森内文学の静謐な文体で、日本の土着的な風土や、そこに根付く人々の営み、あるいは隠された過去が描かれているのかもしれません。民話的な要素や、少しミステリアスな雰囲気を好む読者におすすめできる一冊です。



「晒し井」という言葉の持つ意味合いは深い。浄化と暴露、その二律背反する概念が、物語の中でどのように機能するのか、極めて興味深い考察対象である。
19位『福音書を読む イエスの生涯』
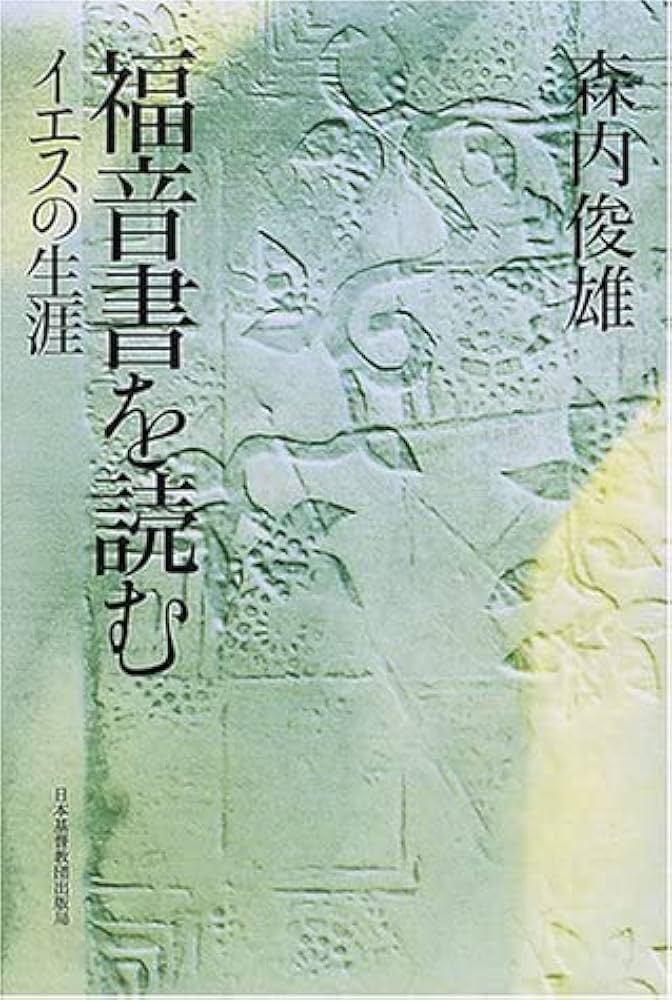
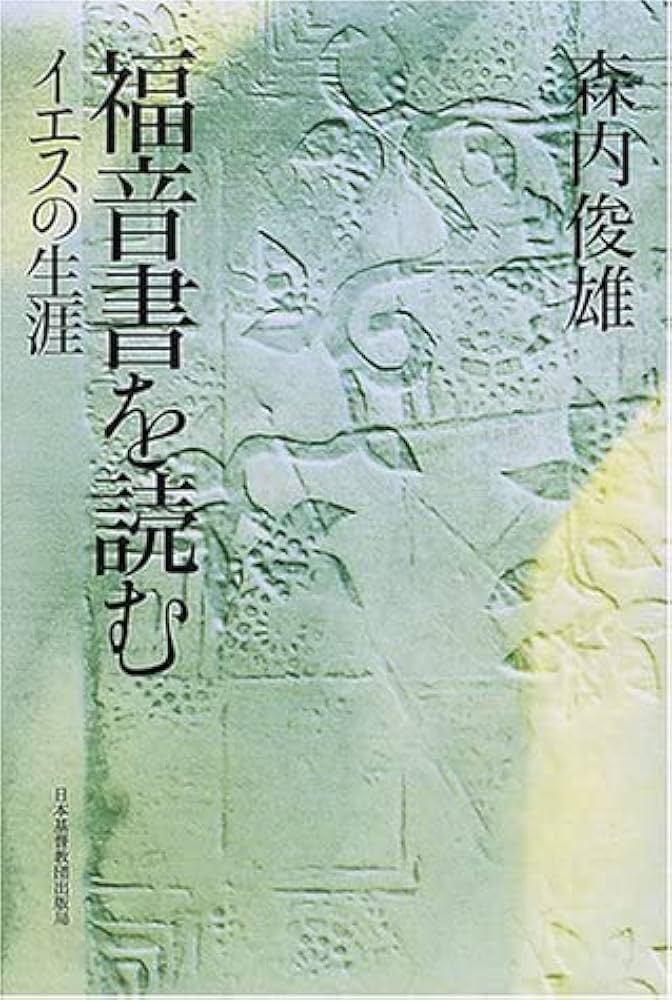
2001年に日本基督教団出版局から刊行された『福音書を読む イエスの生涯』は、小説ではなく、エッセイあるいは解説書に近い作品です。カトリックの洗礼を受けている森内俊雄が、自身の信仰の対象であるイエス・キリストの生涯について、福音書を読み解きながら思索を深めていきます。
作家ならではの深い洞察力と美しい文章で、イエスの言葉や行動が現代に生きる私たちに何を問いかけているのかを解き明かしていきます。信仰の有無にかかわらず、一人の人間としてのイエスの魅力や、聖書の物語が持つ普遍的な力に触れることができるでしょう。



作家さんが聖書を読むとどんな風に見えるんだろう。物語として読んでもすごく深そうだね。
20位『桜桃』
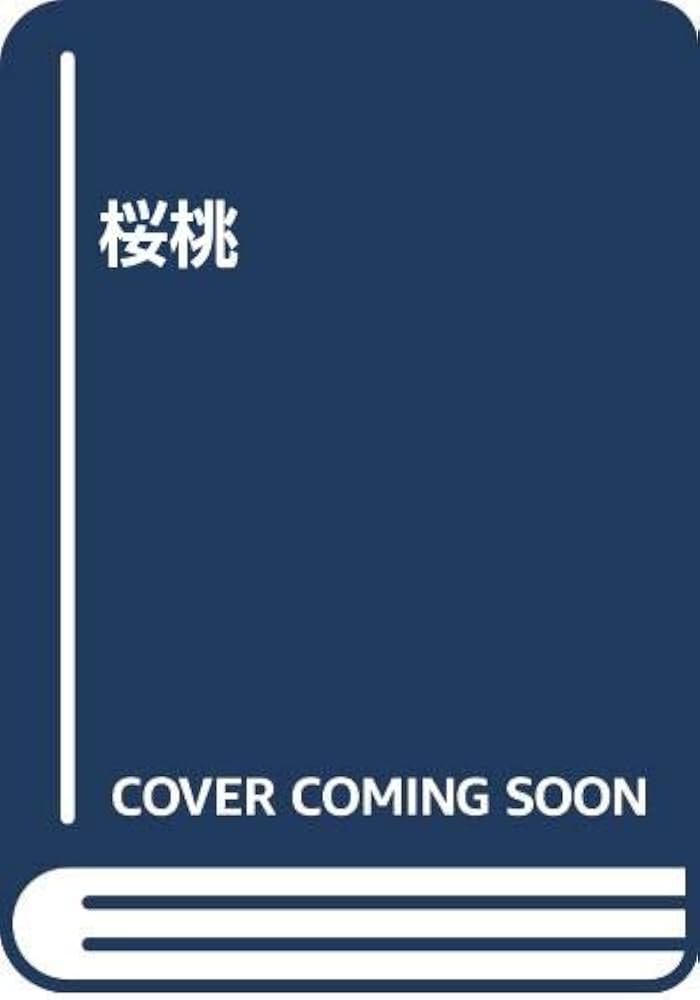
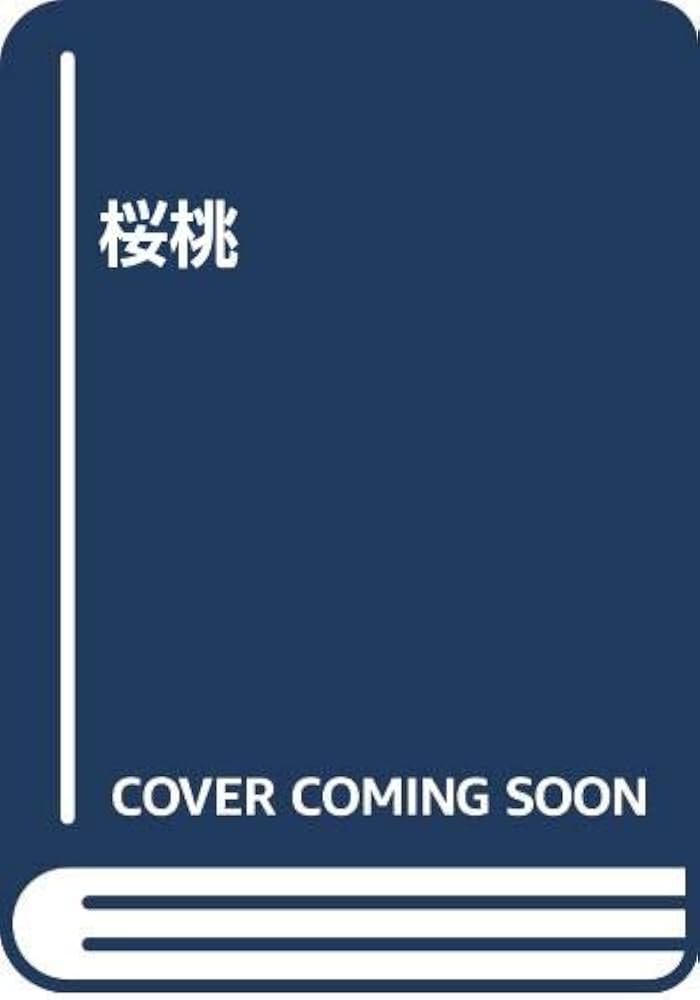
1994年に新潮社から刊行された『桜桃』は、太宰治の同名作品を想起させますが、森内俊雄独自の世界観で描かれた物語です。「桜桃」という果実が持つ、甘酸っぱさや儚さ、そしてどこか退廃的なイメージが、作品のテーマと深く関わっていることが考えられます。
家族や人間関係の中に潜む、微妙な心の揺れ動きや、ままならない現実を、森内俊雄らしい繊細な筆致で描き出しているのかもしれません。静かながらも、人間の業や哀しさを深く見つめた、味わい深い一冊であることが期待されます。



「桜桃」って聞くと、なんだか切ない気持ちになるな…。きっと儚くて美しい物語なんだろうね。
ランキングを参考に森内俊雄の小説を深く味わい、お気に入りを見つけよう
ここまで、森内俊雄のおすすめ小説をランキング形式で20作品ご紹介しました。静謐で詩的な文章で、人間の内面や生と死といった普遍的なテーマを描き続ける森内文学の世界は、一度触れると忘れがたい深い余韻を残します。
自らの体験を基にした重厚な作品から、幻想的な物語、そして日常の機微をすくい取った短編まで、その作風は多岐にわたります。このランキングを参考に、ぜひあなたの心に響く一冊を見つけて、その静かで美しい世界にじっくりと浸ってみてください。