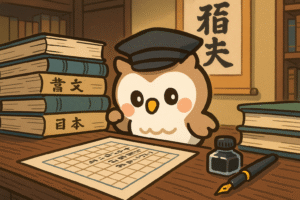あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】怪談小説のおすすめランキングTOP30

本当に怖い、珠玉の怪談小説をご紹介します
夏の夜、背筋が凍るような体験を求めて、あるいは日常に潜む非日常のスリルを味わいたくて、私たちは怪談小説を手に取ります。このジャンルは、単なるお化け屋敷のようなエンターテイメントには留まりません。
人間の心の奥底に潜む闇や、当たり前だと思っていた日常が崩れ去る瞬間の恐怖を描き出し、私たちに強烈な印象を残します。この記事では、古今東西の傑作から最新の話題作まで、あなたを恐怖の世界へ誘う珠玉の怪談小説を厳選してご紹介します。
【2025年最新】怪談小説のおすすめランキングTOP30
誰もが知る不朽の名作から、SNSで話題沸騰中の新感覚ホラーまで、多彩なラインナップでお届けします。あなたの心を鷲掴みにする、運命の一冊がきっと見つかるはずです。
1位: 『残穢』 小野不由美
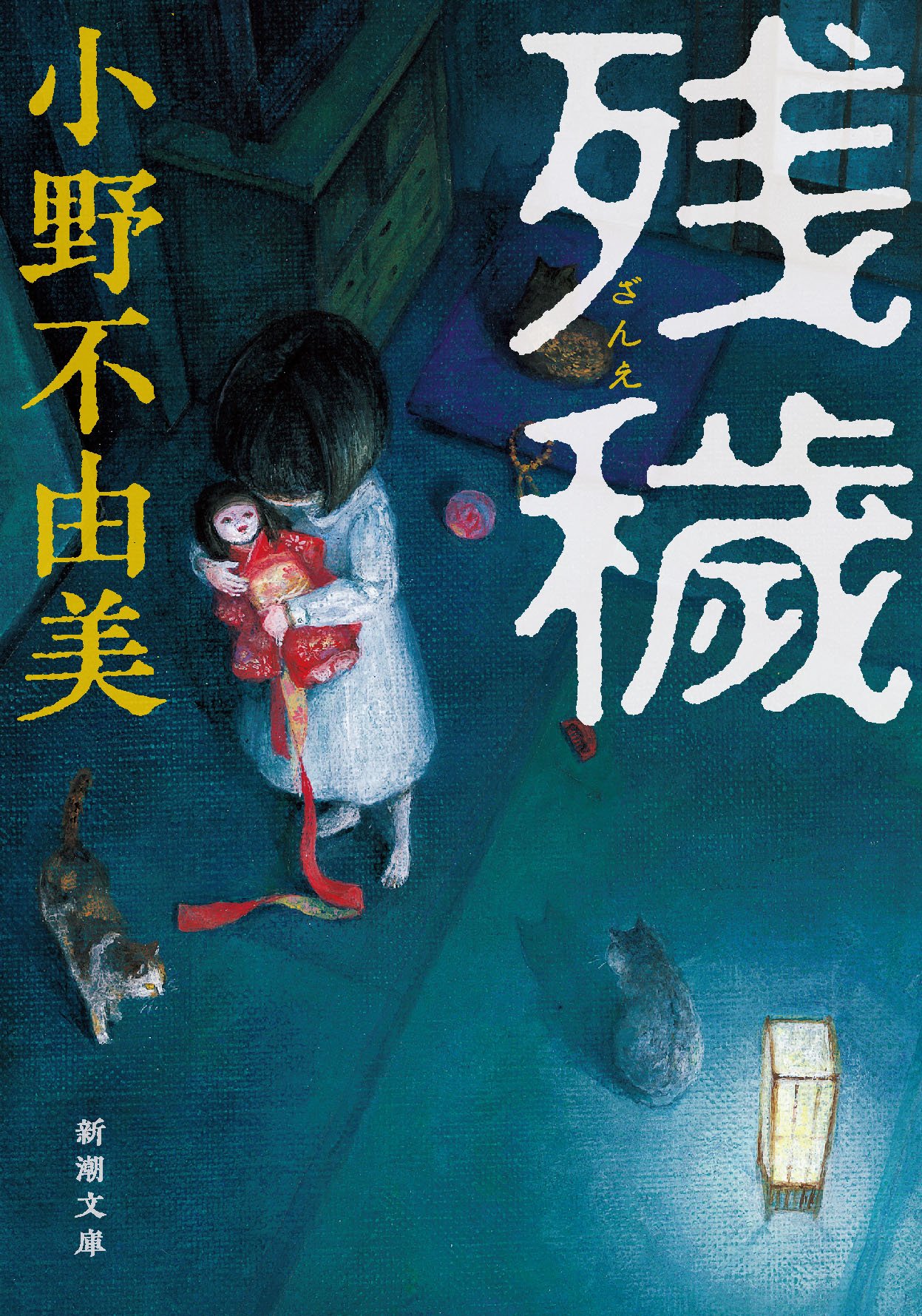
栄えある第1位は、小野不由美による『残穢』です。第26回山本周五郎賞を受賞した本作は、怪談小説の新たな地平を切り開いた傑作として知られています。
物語は、小説家である「私」のもとに、ある読者から届いた一通の手紙から始まります。「今住んでいる部屋で、奇妙な音がするんです」。何気ない相談をきっかけに調査を進めると、その土地に染み付いた恐ろしい「穢れ」の連鎖が明らかになっていきます。ドキュメンタリーのような淡々とした筆致が、かえって現実と虚構の境界を曖昧にし、読者の日常を静かに侵食するような恐怖を生み出します。
 ふくちい
ふくちい怪異の正体を過去へ遡って追跡する構成は、ミステリとしても秀逸だ。穢れが伝染するという設定が、読書体験そのものを恐怖に変える。
2位: 『近畿地方のある場所について』 背筋
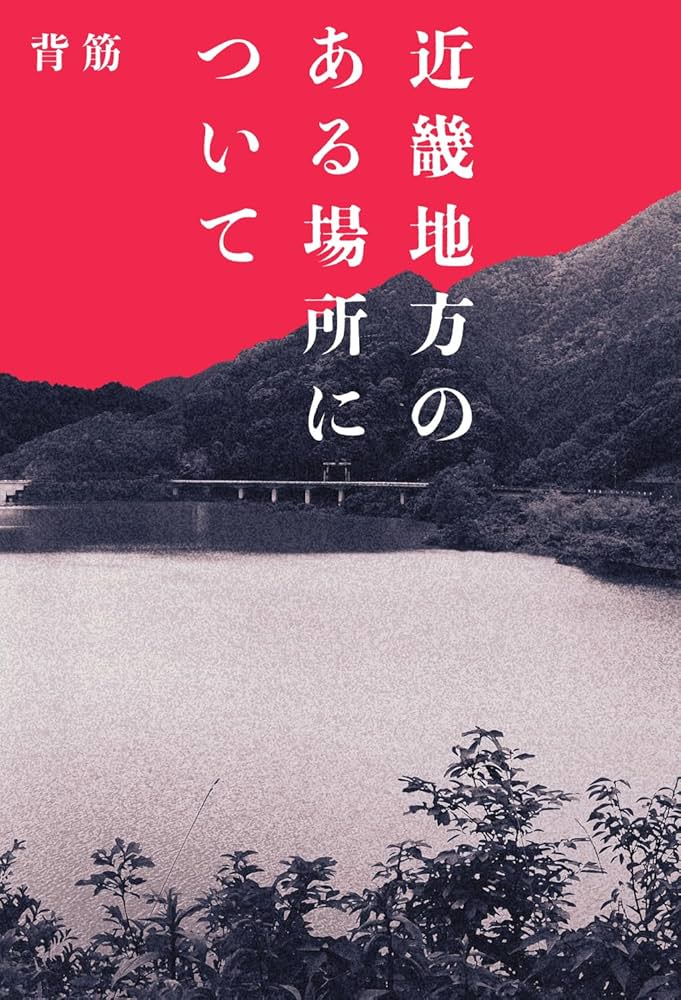
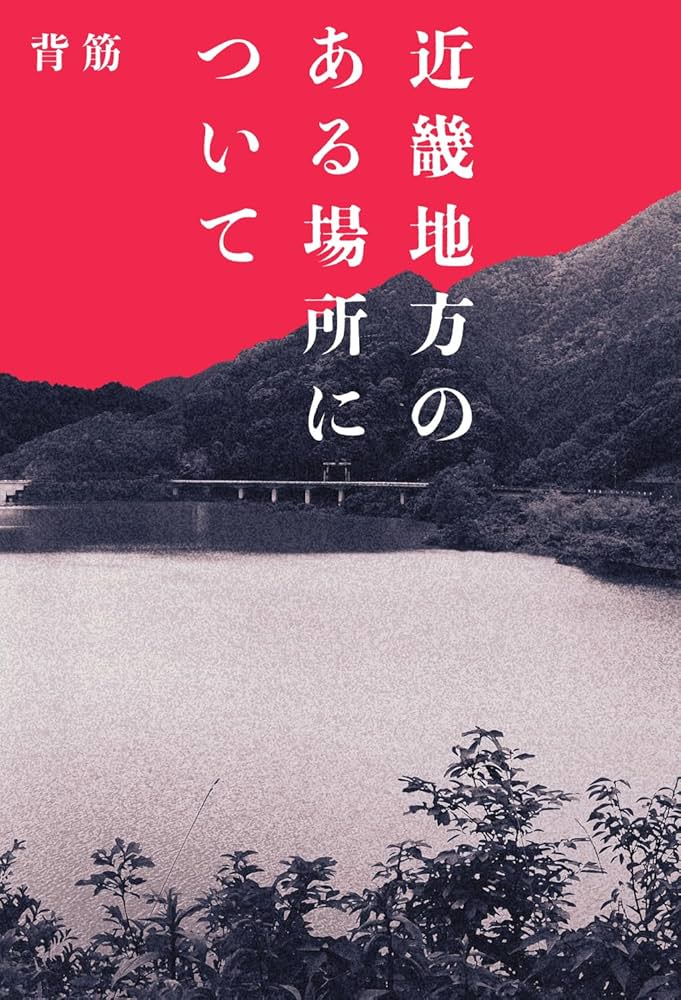
第2位は、ネット発のモキュメンタリーホラーとして絶大な人気を誇る『近畿地方のある場所について』です。ウェブ小説サイト「カクヨム」での連載時から話題を呼び、2023年に待望の書籍化を果たしました。
オカルト雑誌の記者が、ある特定の地域にまつわる奇妙な体験談を調査していく過程が、雑誌記事、インタビュー記録、SNSの投稿といった様々な形式の断片的な資料を通して描かれます。読者はまるで調査員の一員になったかのように、散りばめられた情報を繋ぎ合わせ、恐ろしい真相へと迫っていくことになります。ネット時代の恐怖を巧みに表現した、新感覚のホラー作品です。



複数のメディアから提示される断片的な情報が、読者の能動的な解釈を促す。この参加型の構造こそが、本作の恐怖を増幅させる核心的な装置と言える。
3位: 『黒い家』 貴志祐介
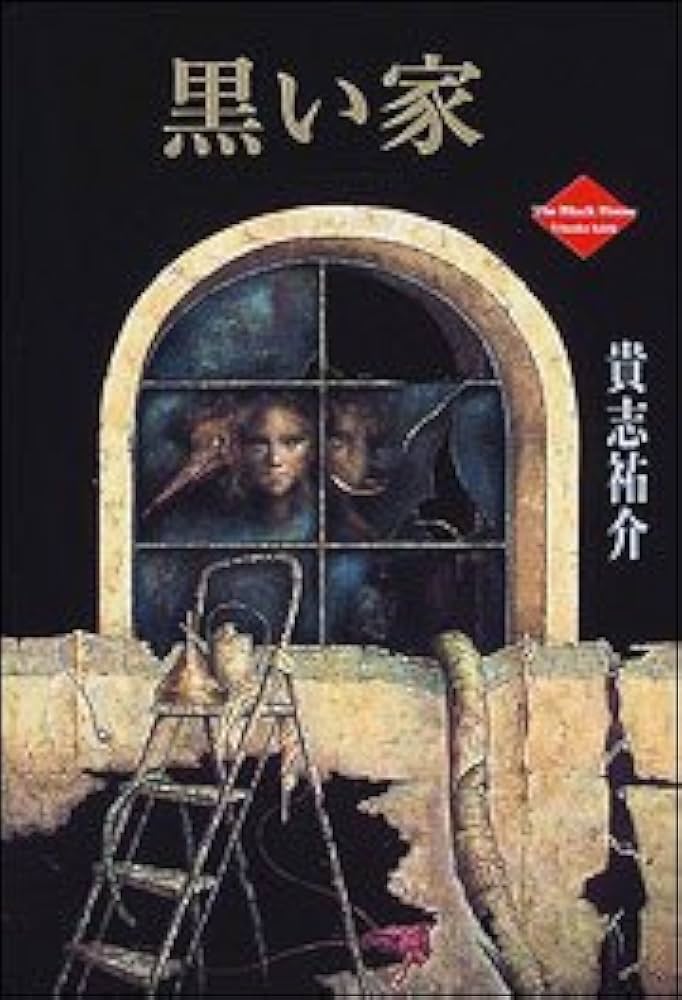
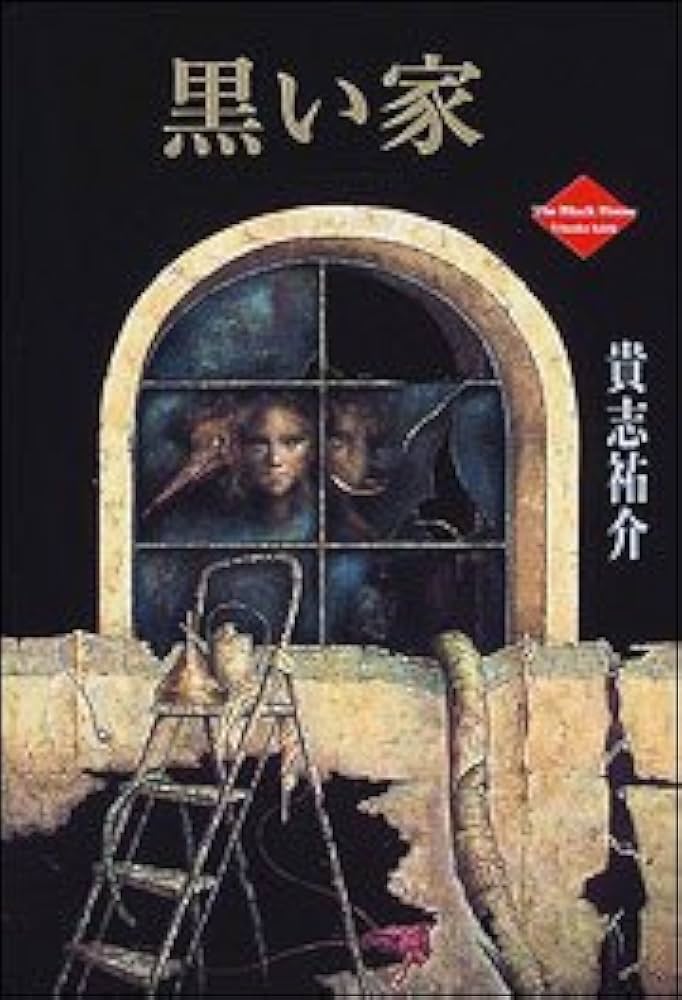
第3位には、第4回日本ホラー小説大賞を受賞した貴志祐介の『黒い家』がランクイン。幽霊や超常現象よりも「生きている人間」こそが最も恐ろしいということを読者に叩きつけたサイコホラーの傑作です。
生命保険会社の社員・若槻が、顧客からの呼び出しで訪れた家で子供の首吊り死体を発見したことから物語は始まります。当初は自殺と思われた事件の裏に、保険金殺人の疑いが浮上。若槻は、人間の理解を超えた純粋な悪意の塊と対峙することになり、自らの命までもが脅かされていきます。その圧倒的な恐怖描写は、多くの読者にトラウマを植え付けました。



本作が提示するのは、共感や理解を一切拒絶する「純粋悪」の存在だ。この絶対的な他者との遭遇が、読者に根源的な恐怖を喚起させる。
4位: 『ぼぎわんが、来る』 澤村伊智
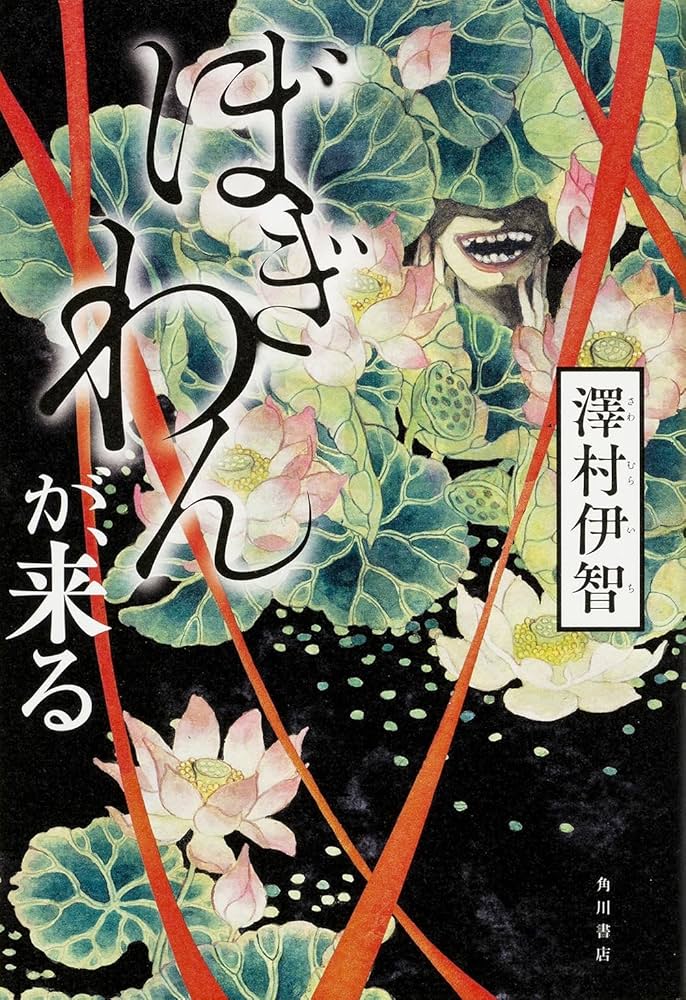
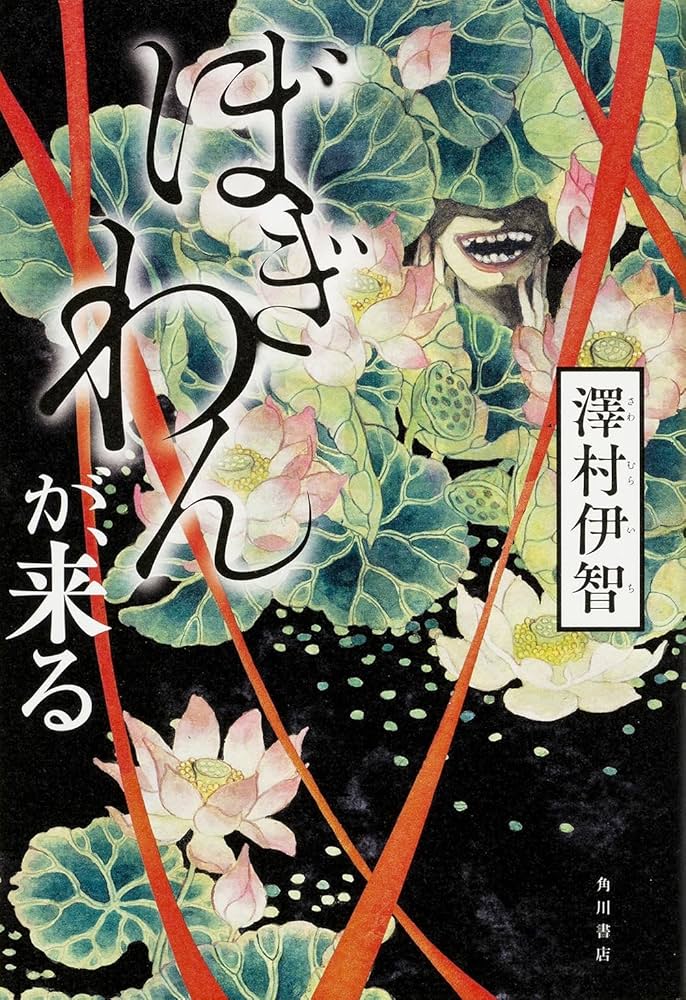
第22回日本ホラー小説大賞〈大賞〉受賞作である『ぼぎわんが、来る』が4位にランクイン。本作は2018年に『来る』というタイトルで映画化もされ、大きな話題を呼びました。
主人公・田原の周辺に現れる謎の訪問者。その正体不明の存在「ぼぎわん」は、人の名前を呼び、姿を真似て、少しずつ日常を蝕んでいきます。古くから伝わる怪異が現代の都市を舞台に蘇るという設定が斬新で、民俗学的な要素と現代的な恐怖が見事に融合しています。



本作における恐怖の根源は、対象の正体が不明であるという点に尽きる。未知の存在が日常の隙間から侵入してくる感覚は、原始的な恐怖を呼び覚ます。
5位: 『変な家』 雨穴
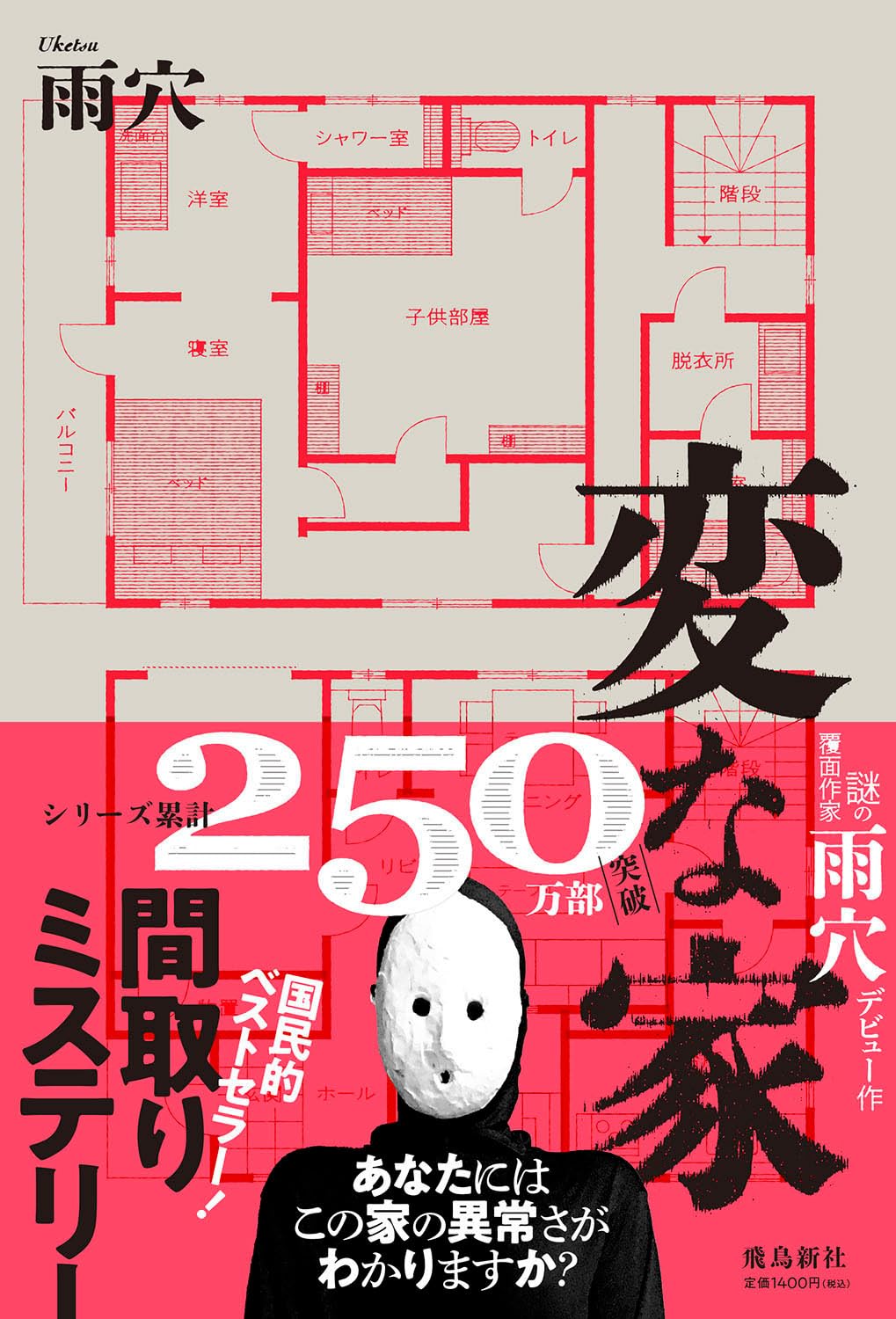
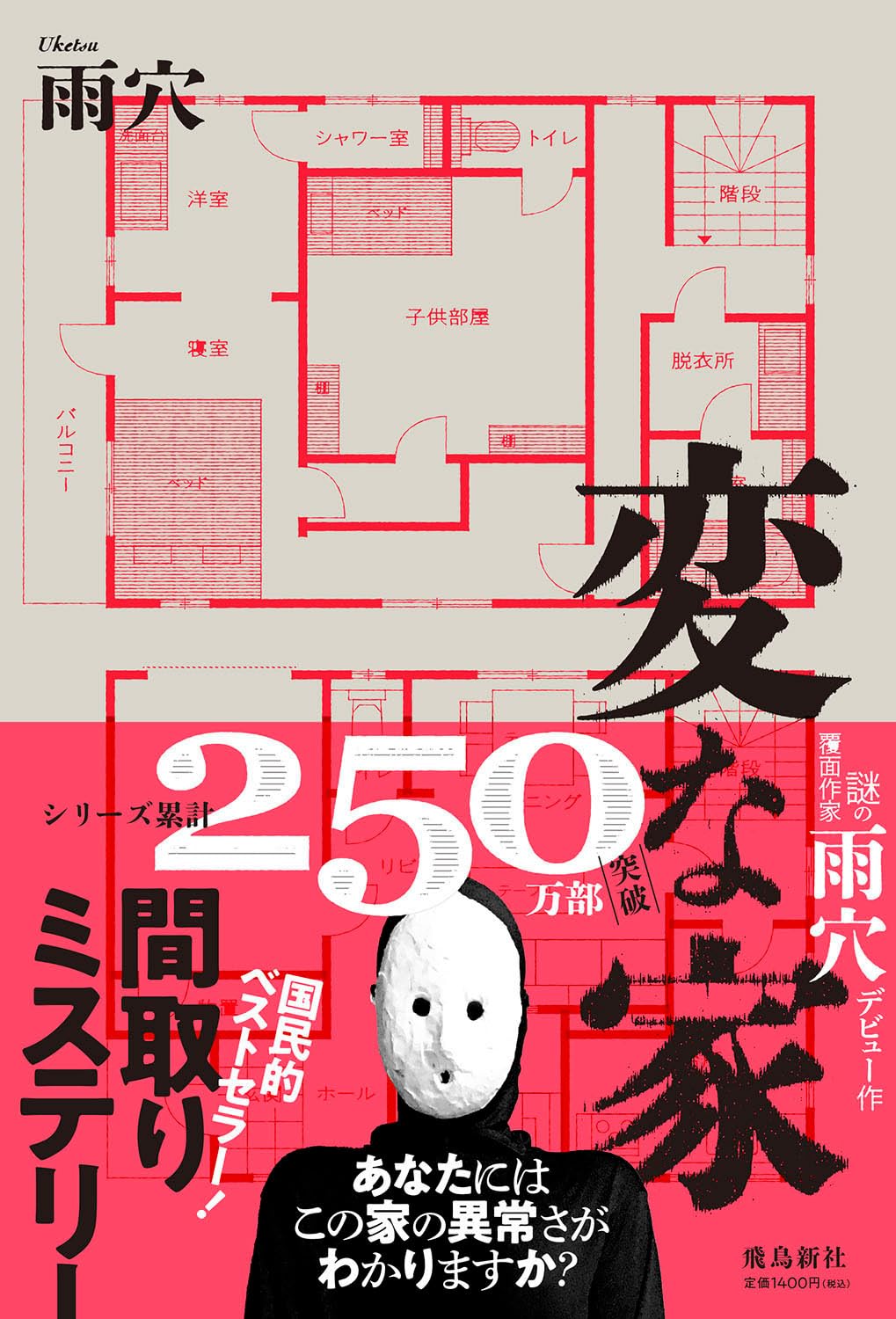
ウェブメディアの記事から人気に火がつき、書籍化、そして映画化もされた異色のホラーミステリー『変な家』が5位です。覆面の人気作家・雨穴による本作は、YouTube動画から生まれた新しい形の小説として注目を集めました。
物語は、ある家の「間取り図」から始まります。一見ごく普通に見えるその間取りには、よく見ると不可解な点がいくつも存在しました。知人の設計士に相談したことから、その家に隠された恐ろしい秘密が次々と明らかになっていきます。間取り図という視覚情報から恐怖を煽る手法が秀逸で、読者はページをめくる手が止まらなくなるでしょう。



間取り図という客観的な情報から異常性を読み解いていく過程が面白いよね。日常に潜む違和感に気づいてしまった時のゾクッと感がたまらないんだよ。
6位: 『おそろし 三島屋変調百物語事始』 宮部みゆき
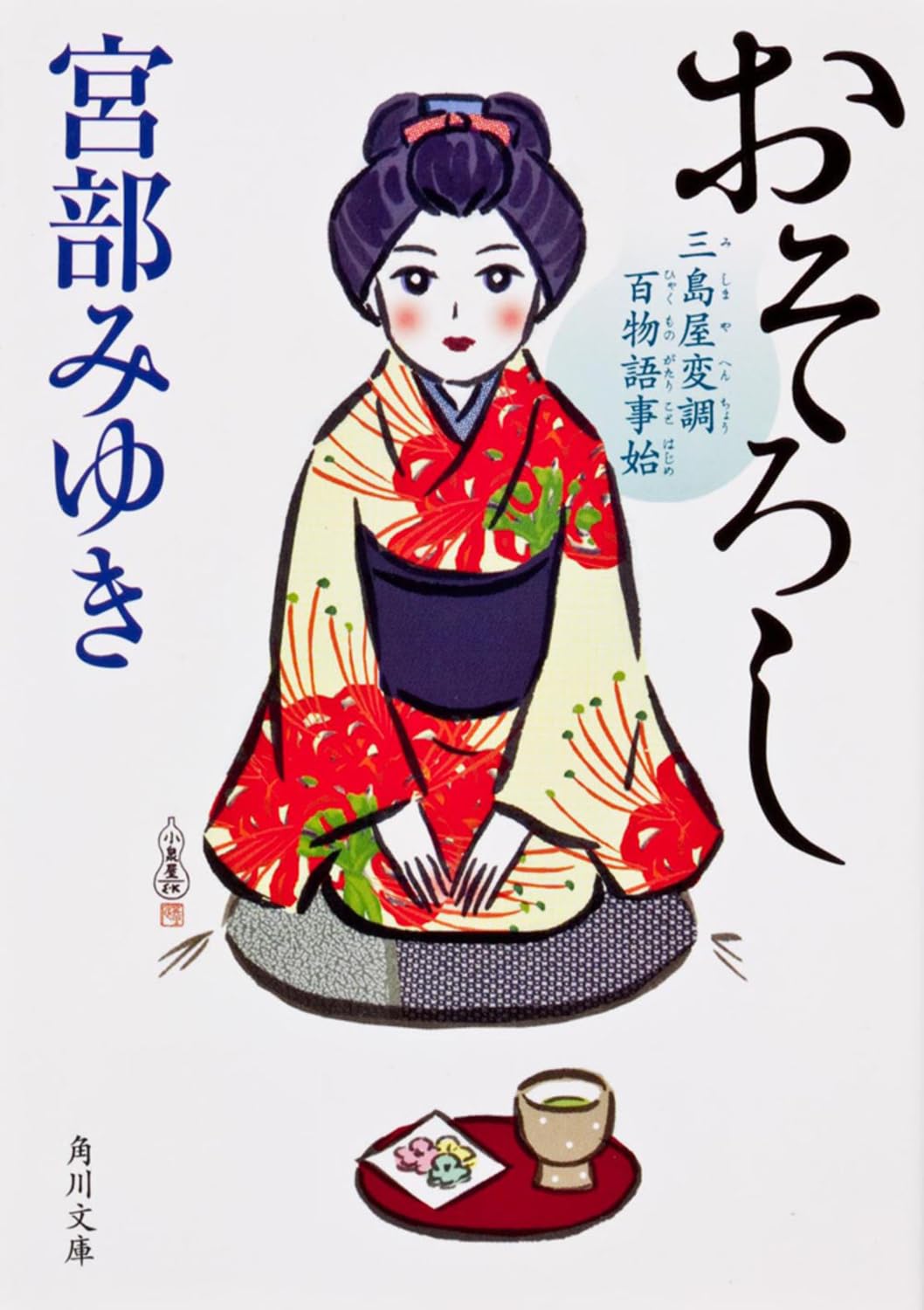
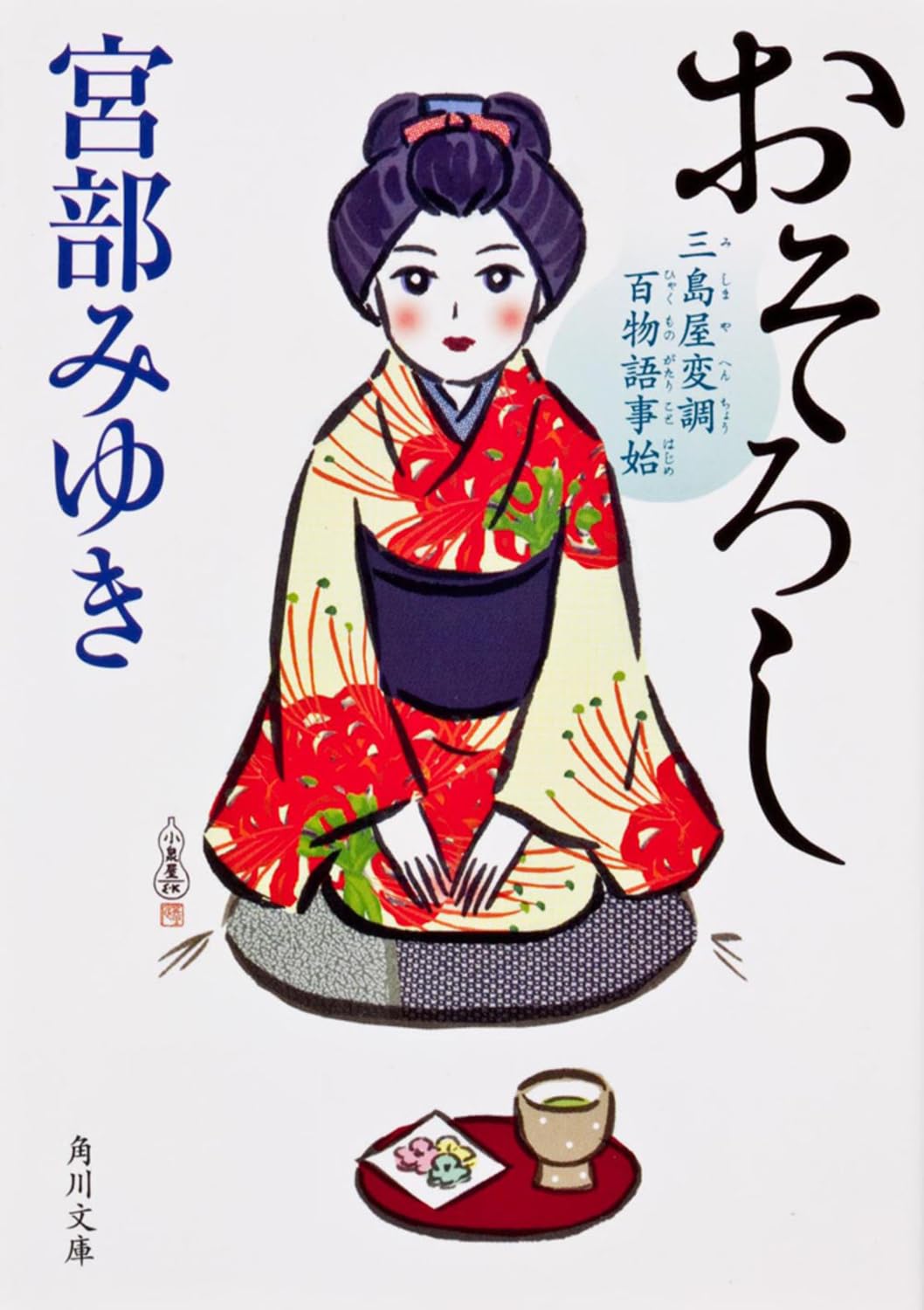
時代小説の名手・宮部みゆきが描く、江戸怪談シリーズの第一作『おそろし』が6位にランクイン。百物語形式で語られる怪談の数々は、恐ろしくもどこか切ない味わいを残します。
江戸で人気の袋物屋「三島屋」を舞台に、主人の姪であるおちかが、訪れる人々から不思議な話を聞き集めていきます。語られるのは、人の情念や業が生み出す怪異譚。宮部みゆきならではの巧みな語り口と、登場人物たちの深い心理描写によって、読者は江戸の闇へと引き込まれていきます。



怖いだけじゃなくて、人の悲しみや優しさが描かれているのがいいんだよね。読んだ後に、じんわりと考えさせられる物語だよ。
7位: 『リング』 鈴木光司
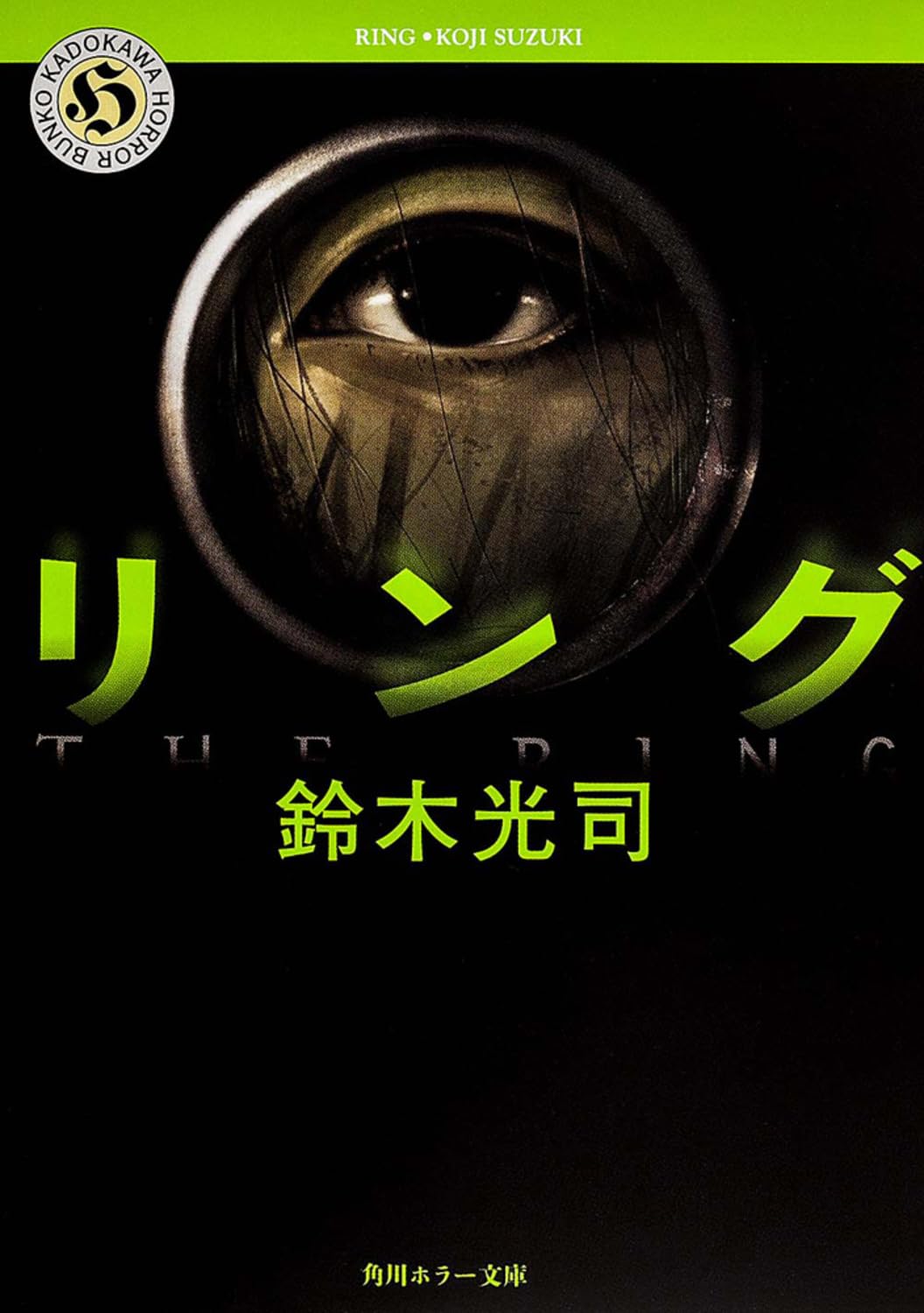
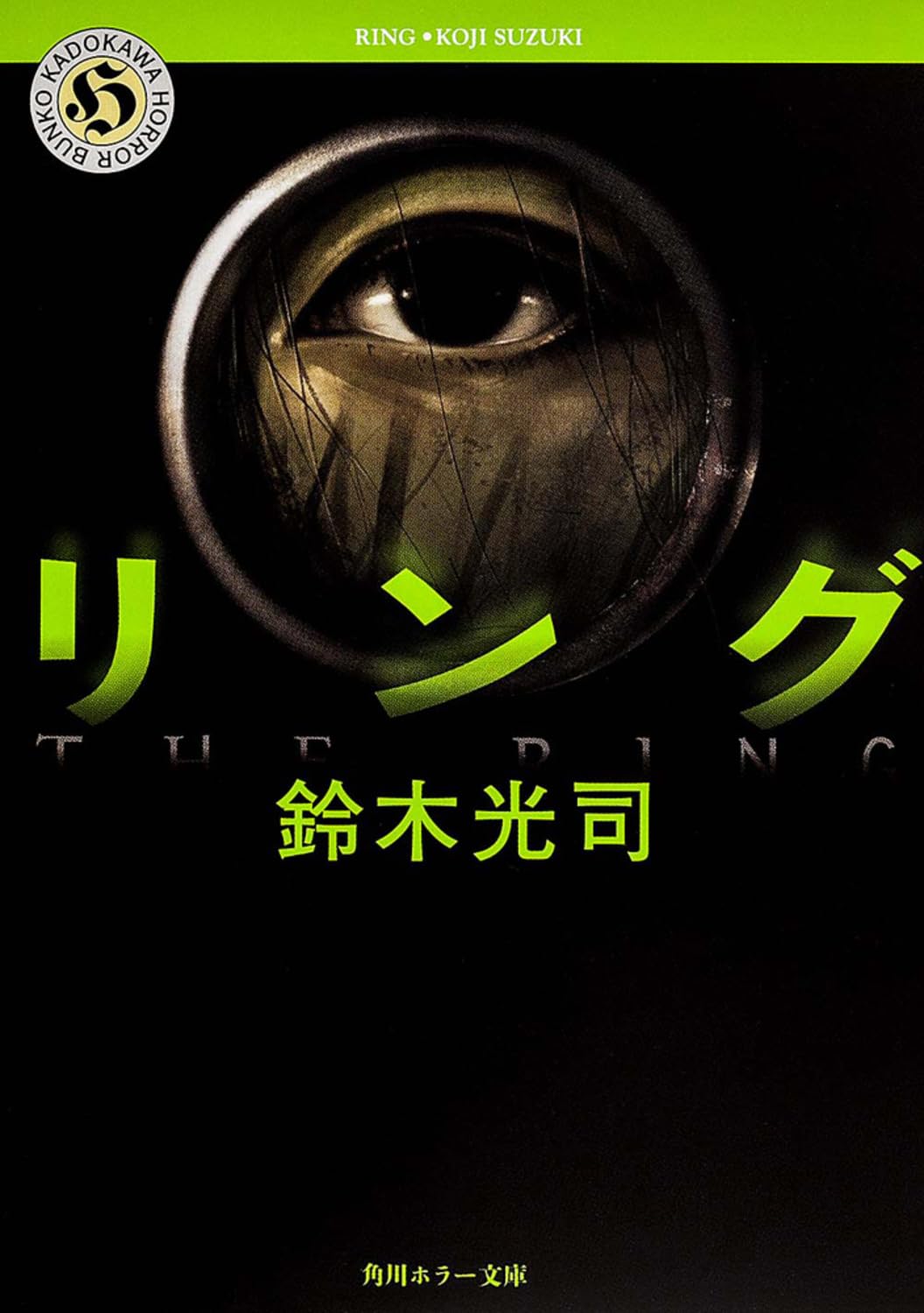
7位は、Jホラーブームの火付け役となった不朽の名作、鈴木光司の『リング』です。「見ると一週間後に死ぬ」という呪いのビデオの恐怖は、日本中を震撼させました。
都市伝説の取材をしていた新聞記者の浅川は、姪の死をきっかけに呪いのビデオの存在を知ります。自らもビデオを見てしまった浅川は、超能力を持つ元妻の協力を得て、呪いを解くために奔走します。科学とオカルトが交錯するスリリングな展開と、ビデオから這い出てくる貞子の衝撃的なイメージは、今なお色褪せることがありません。



ビデオテープを介して呪いが拡散する設定は、当時の情報化社会への批評とも読める。恐怖の増殖プロセスが、極めて現代的だ。
8位: 『鬼談百景』 小野不由美
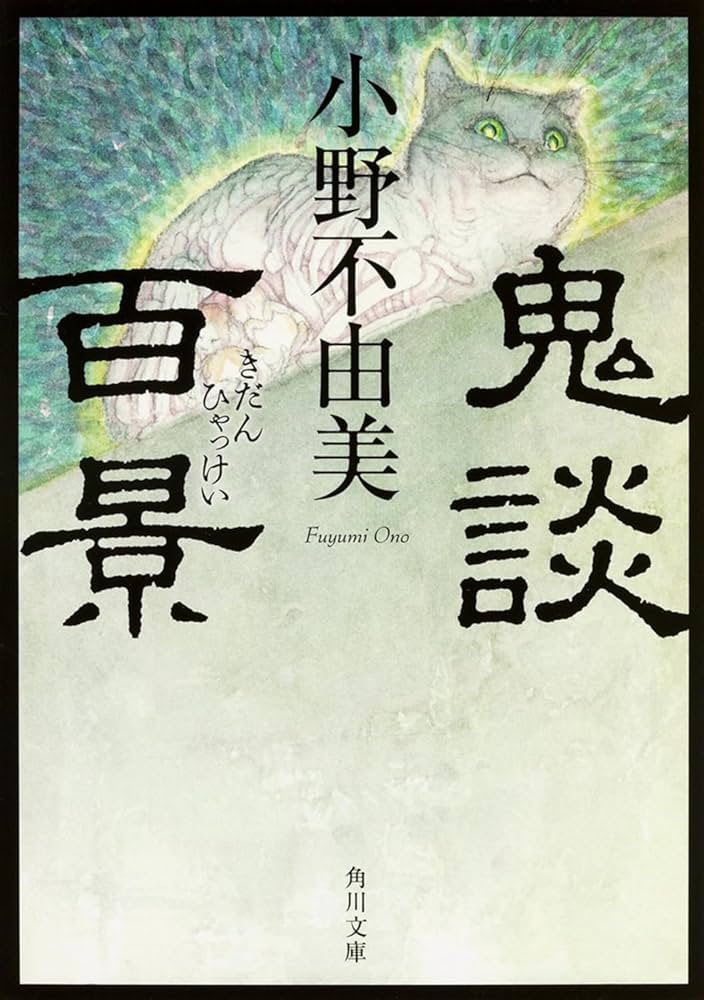
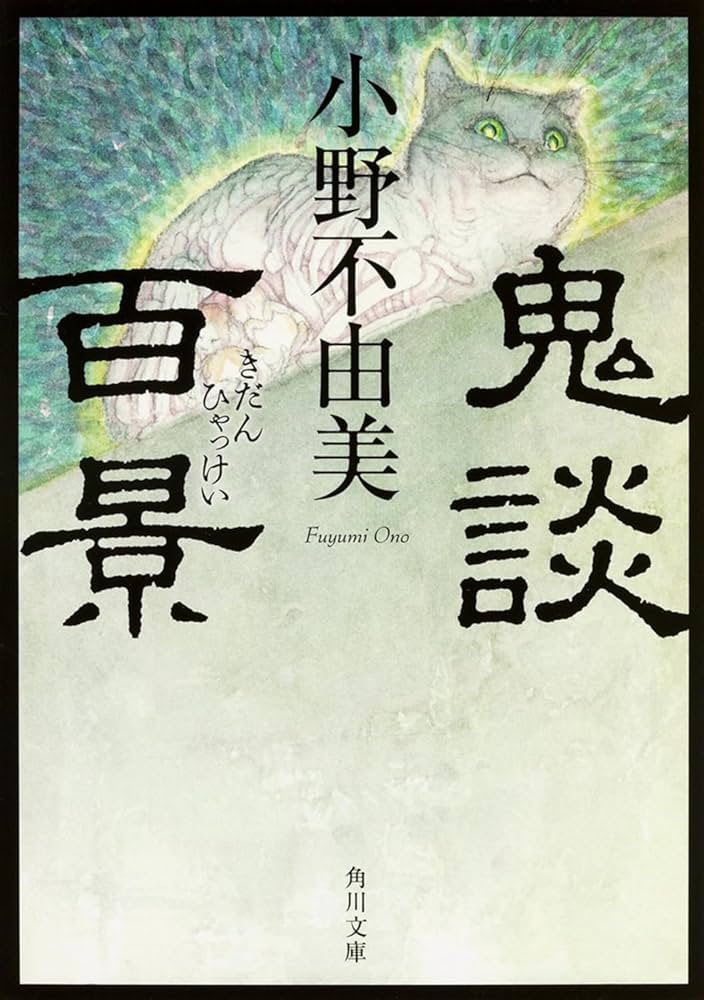
1位の『残穢』と同じく小野不由美による本作は、99の怪談を集めた短編集です。『残穢』の作中で触れられる怪談も収録されており、2作合わせて読むことでより深く恐怖の世界に浸ることができます。
学校、家、病院、道端など、日常のあらゆる場面に潜む怪異が、淡々とした筆致で描かれます。一つ一つの話は短いながらも、読者の想像力を掻き立て、じわりと広がる恐怖を残します。派手な恐怖演出ではなく、静かに忍び寄る「気配」の恐ろしさを堪能できる一冊です。



断片的な怪異譚の集積は、体系化されない恐怖の総体を形成する。個々の物語は、より大きな「穢れ」の一部を示唆しているに過ぎない。
9位: 『火のないところに煙は』 芦沢央
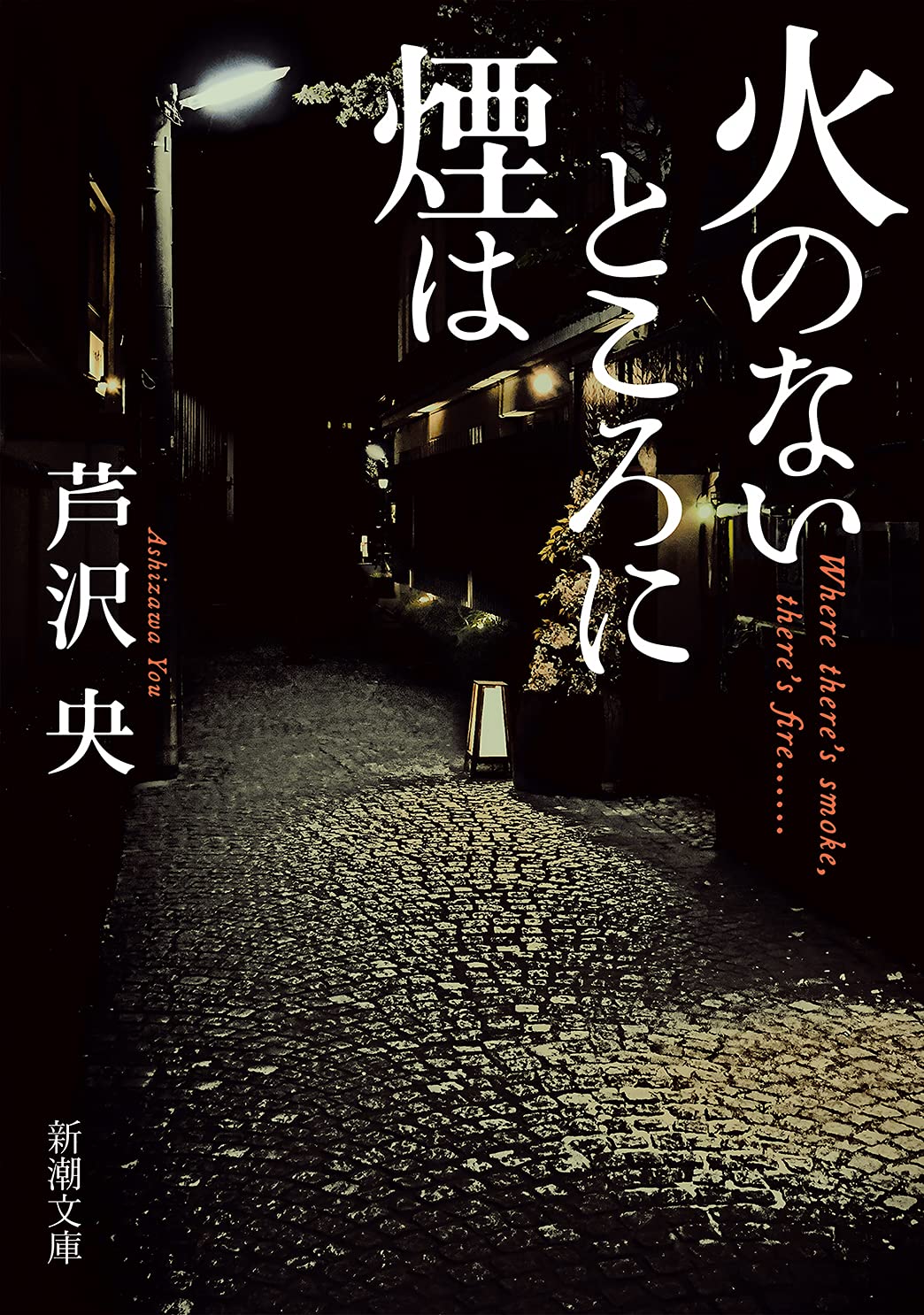
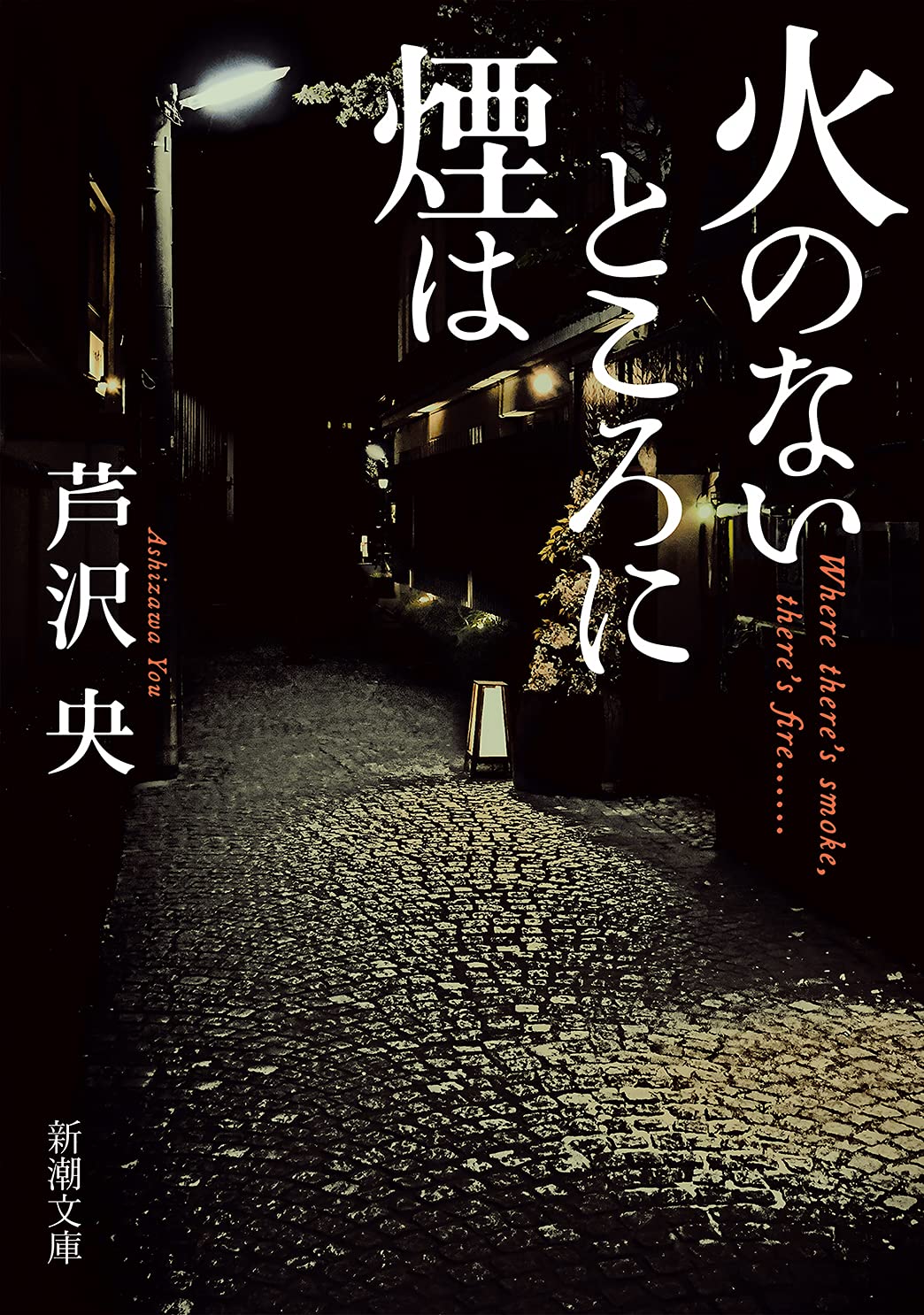
第7回山田風太郎賞の候補作にもなった、芦沢央による連作短編集『火のないところに煙は』。怪談とミステリーが巧みに融合した本作は、読めば読むほど物語の深みにハマっていきます。
作家である主人公が、様々な人々から怪談を取材する中で、それぞれの話が奇妙に繋がり、やがて一つの大きな事件の真相へと収束していきます。「神楽坂を舞台にした怪談」という依頼から始まる物語は、読者を巧みに騙し、最後の最後に驚愕の事実を突きつけます。全ての謎が解けた時、あなたはもう一度最初から読み返したくなるはずです。



怪談だと思って読んでたら、全部繋がっててミステリーになるのがすごい!伏線回収が見事で、最後は「うわー!」って声が出ちゃったよ。
10位: 『新耳袋 現代百物語』 木原浩勝、中山市朗
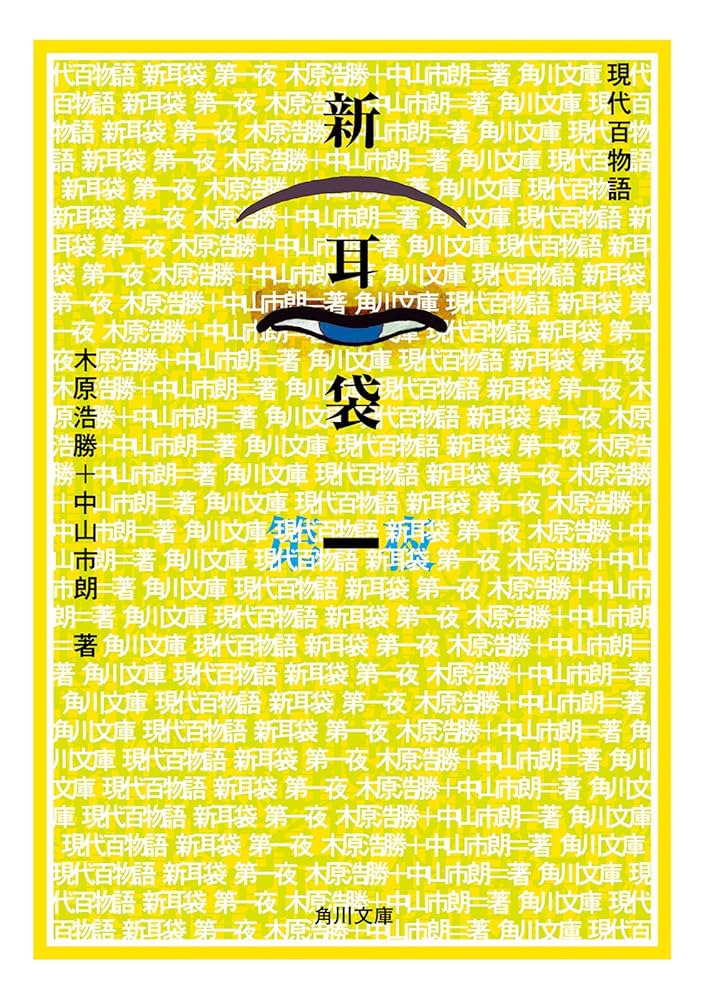
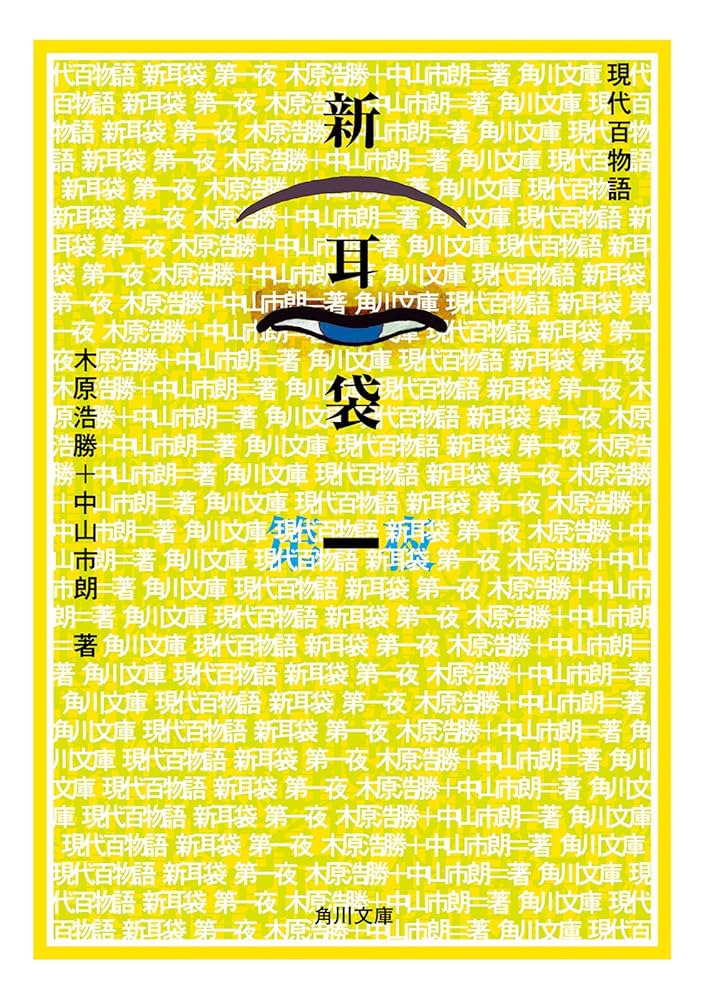
実話怪談の金字塔として、長年にわたり多くのファンを持つ『新耳袋』シリーズが10位にランクイン。実際に収集された膨大な数の怪異譚から厳選された話が、百物語形式で収録されています。
本作の特徴は、徹底した実話主義です。派手な脚色はなく、体験者が語ったままの形で淡々と記述されているため、かえって生々しいリアリティがあります。「誰かの身に本当に起こった話」であるという事実が、読者のすぐそばに潜む恐怖を感じさせます。



本作の価値は、民俗学的な資料としての側面にも見出せる。現代における怪異の発生と伝播の様式を記録した、貴重な一次資料だ。
11位: 『嗤う伊右衛門』 京極夏彦
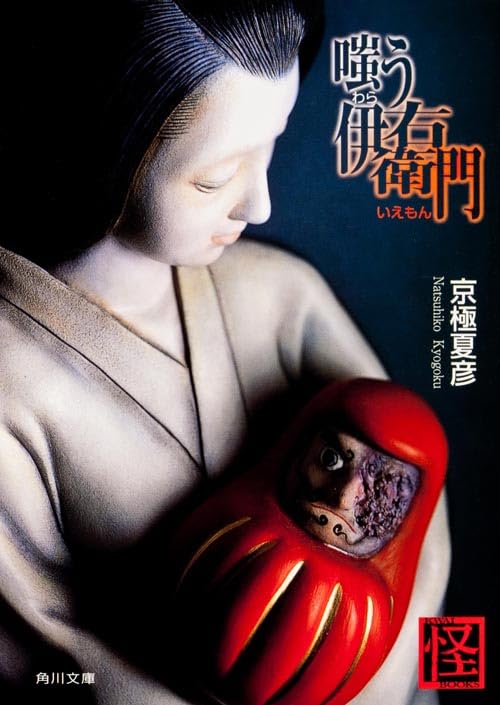
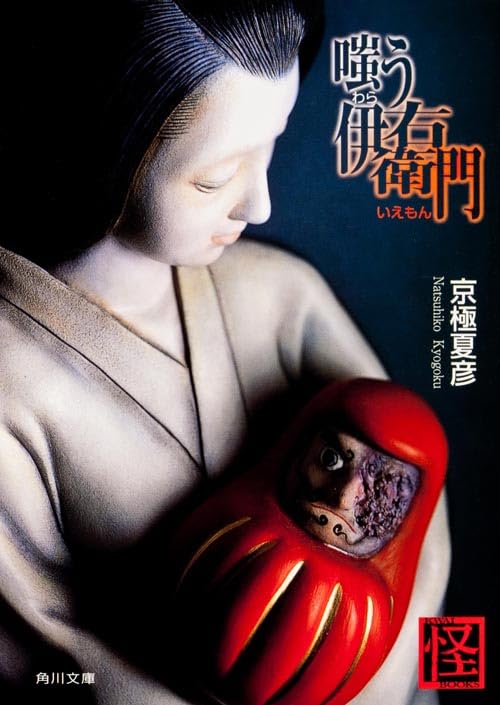
第25回泉鏡花文学賞を受賞した京極夏彦の『嗤う伊右衛門』は、有名な「四谷怪談」を全く新しい視点から描き直した傑作です。
主人公は、妻・お岩を惨殺した冷酷な悪人として知られる民谷伊右衛門。しかし本作では、彼は妻を深く愛し、その愛ゆえに狂気の世界へと足を踏み入れていく男として描かれます。お岩の視点も交えながら、二人の悲しくも美しい愛の物語が、京極夏彦ならではの濃密で妖艶な筆致で紡がれます。これは怪談でありながら、究極の恋愛小説でもあります。



伊右衛門とお岩の純粋な愛が悲劇を生むなんて…。怖いはずなのに、二人の一途な想いに胸が締め付けられて涙が出ちゃったよ。
12位: 『屍鬼』 小野不由美
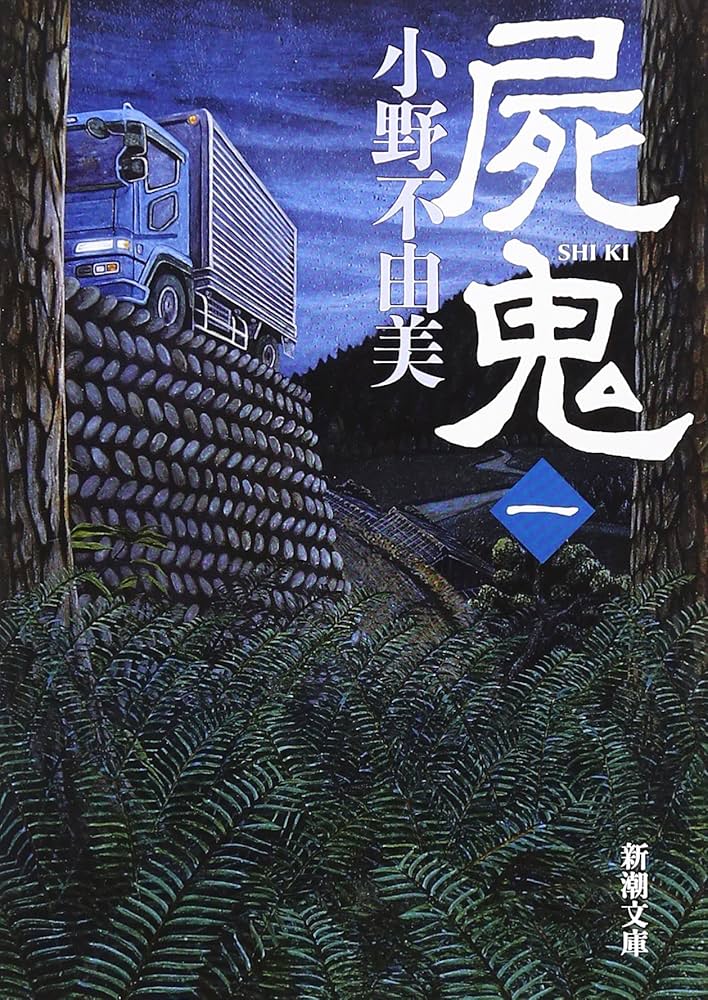
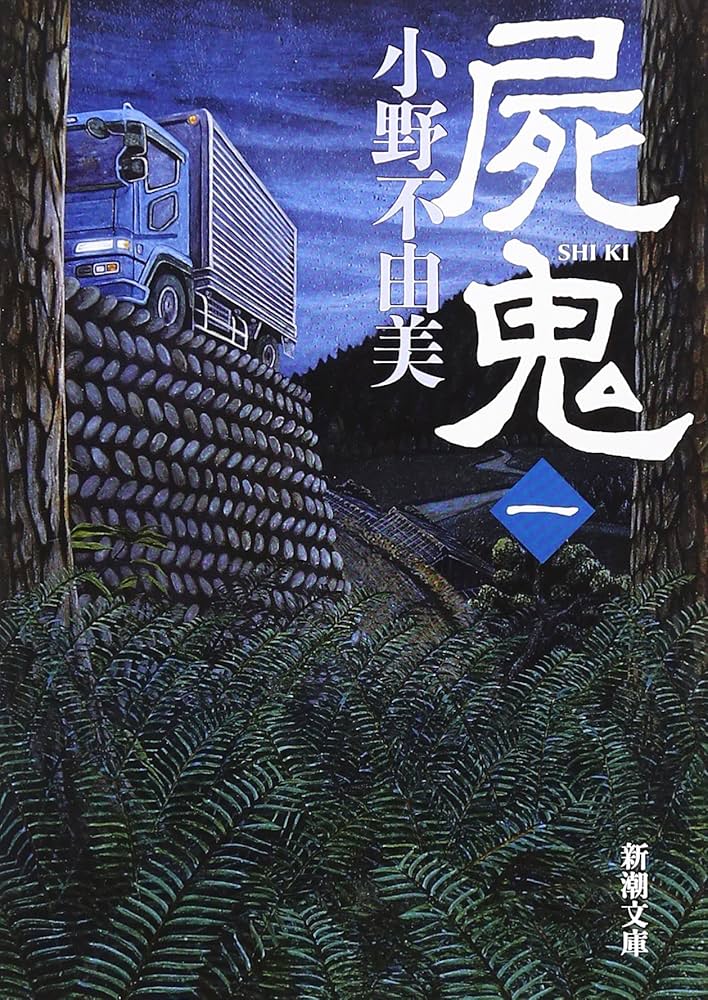
小野不由美による長編ホラー小説『屍鬼』が12位にランクイン。人口わずか1300人の小さな村を舞台に、吸血鬼(屍鬼)と人間の壮絶な生存競争を描いた大作です。アニメ化もされ、その衝撃的な展開で多くの視聴者にトラウマを与えました。
外部から隔絶された外場村で、村人が次々と不審な死を遂げていきます。それは、村に越してきた謎の家族がもたらした「死」の連鎖でした。追い詰められた人間たちは、やがて狂気に駆られ、屍鬼を狩り始めます。どちらが悪でどちらが正義なのか、その境界が揺らぐ中で、物語は凄惨な結末へと突き進んでいきます。



生存を賭けた異種族間の闘争を通じて、人間性の本質と共同体の狂気を鋭く問うている。どちらに正当性があるのかという問いは重い。
13位: 『拝み屋怪談』 郷内心瞳
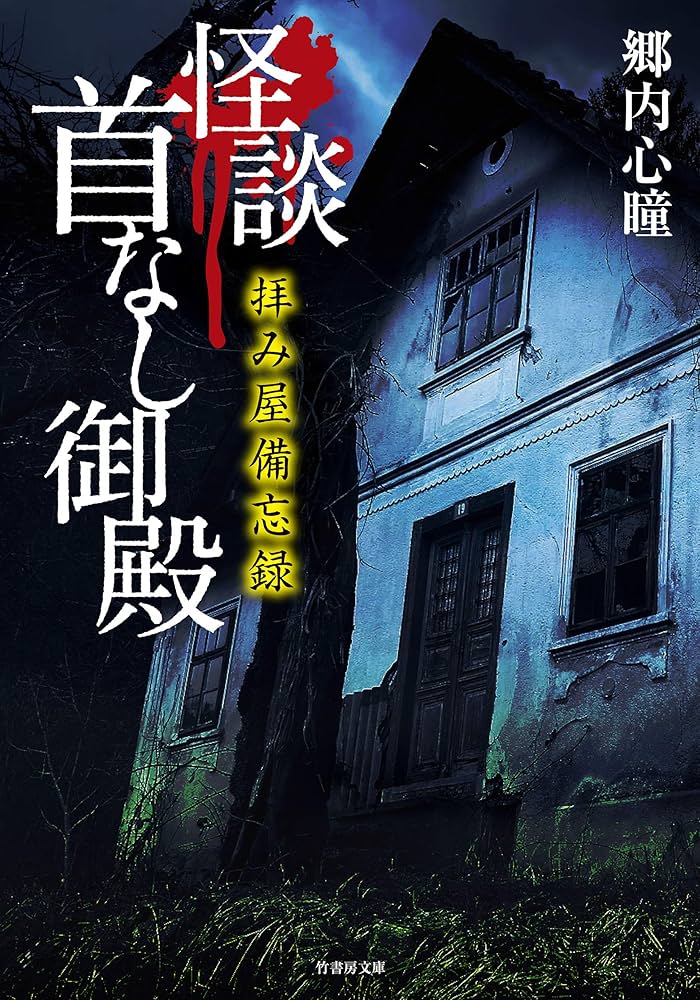
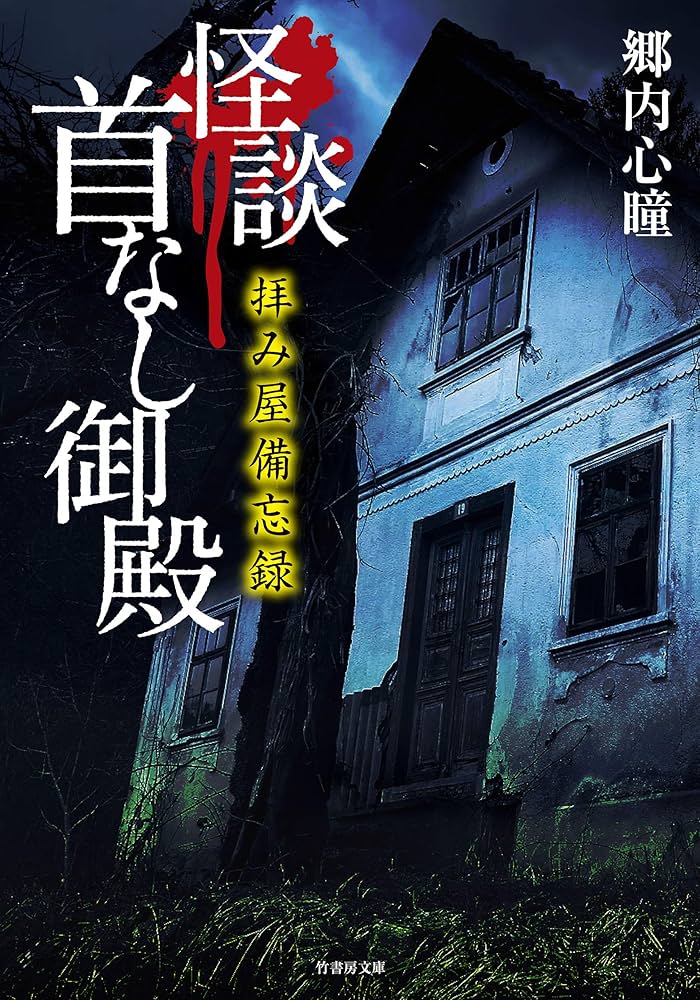
現役の拝み屋(祈祷師)である著者・郷内心瞳が、自らの体験をもとに綴る実話怪談シリーズの第一作。そのリアリティと生々しさは、他の怪談とは一線を画します。
東北の片田舎を舞台に、著者が実際に見聞きし、対処してきた数々の怪異が語られます。依頼者の家に巣食う霊、呪われた土地、危険な憑き物など、プロの目から見た「本物」の怪異は、フィクションとは異なる種類の、底知れない恐怖を感じさせます。拝み屋という仕事の過酷さも伝わってくる、貴重なドキュメンタリーでもあります。



職業的実践者の視点から語られる怪異は、極めて具体的かつ実務的だ。超自然現象を「処理すべき事案」として扱う筆致が、特異なリアリティを生む。
14位: 『のぞきめ』 三津田信三
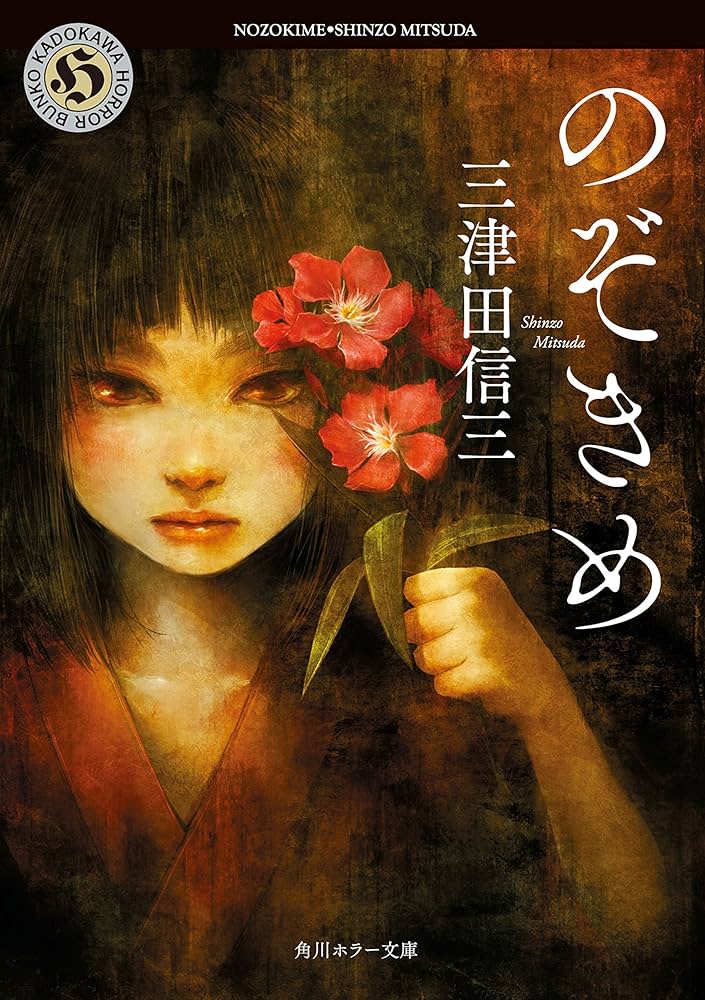
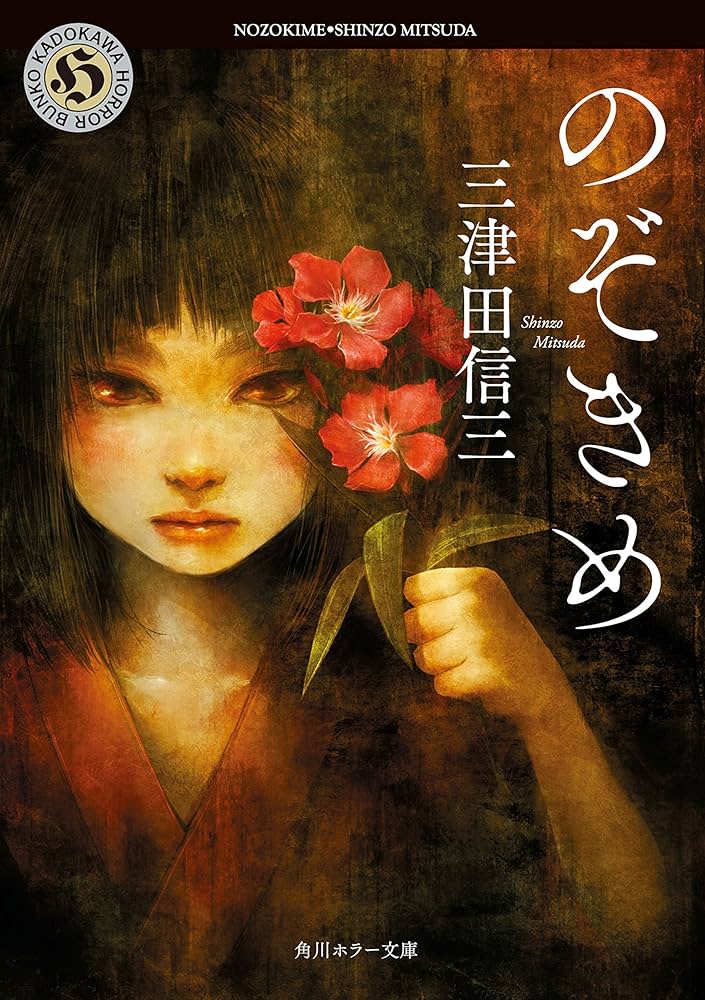
ホラーとミステリーの融合を得意とする三津田信三の『のぞきめ』が14位です。2016年には映画化もされました。物語は、二つの異なる時代の怪異譚が、やがて一つの恐怖へと繋がっていく構成になっています。
辺鄙な山村に伝わる「のぞきめ」という怪物の伝承。その禁忌を破った者たちに、日常のあらゆる隙間から視線を投げかける存在が襲いかかります。過去と現在、二つの物語が交錯し、読者は虚実の入り混じった迷宮へと誘われます。どこからどこまでが創作で、どこからが現実なのか。その境界が揺らぐ恐怖が、本作の醍醐味です。



虚実の境界を曖昧にするメタフィクション構造が、読者を物語の当事者として引きずり込む。計算された恐怖演出だ。
15位: 『かわいそ笑』 梨
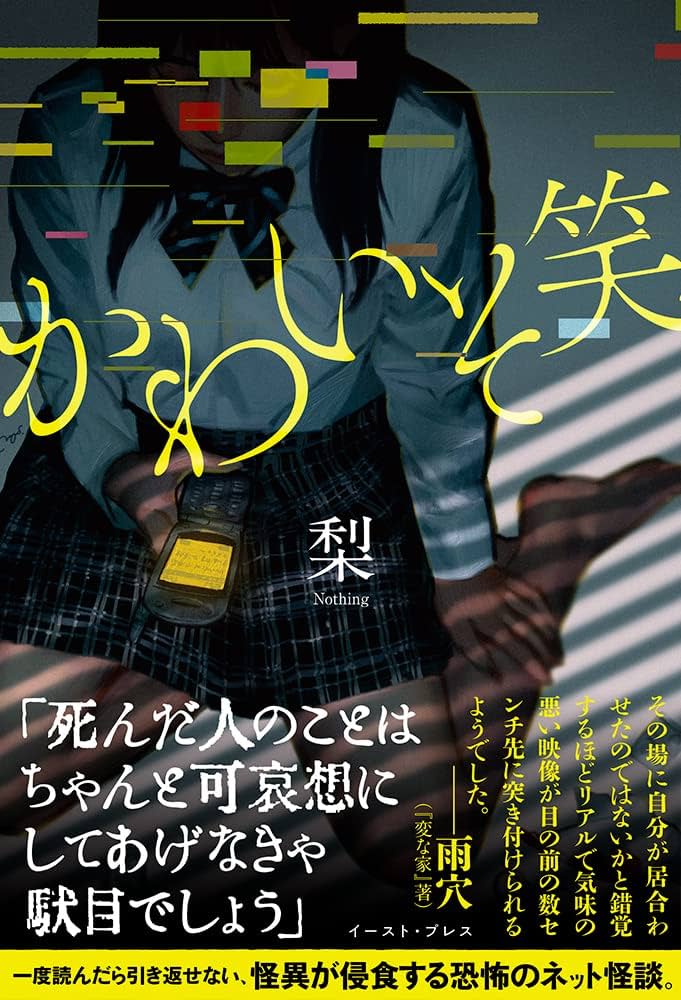
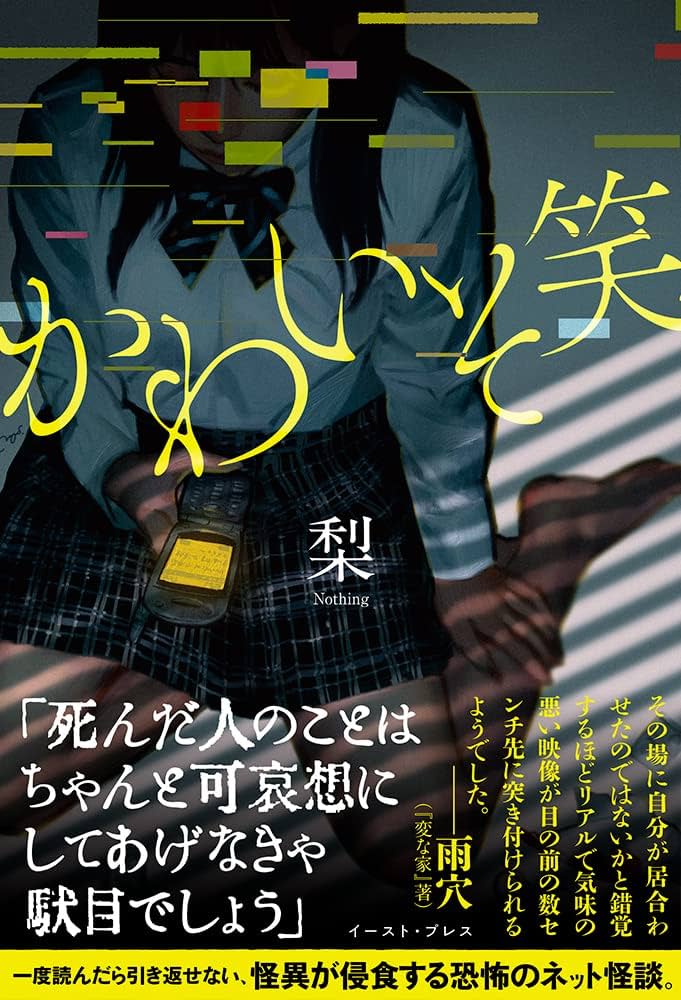
ネット怪談の新たな旗手として注目される作家・梨のデビュー単行本。ウェブサイトやSNSで断片的に語られてきた怪異が、一冊の本としてまとめられています。
本作は、ある女性ライターが友人の失踪の謎を追う中で、様々な怪談に遭遇していくという構成になっています。それぞれの話は独立しているように見えながら、読み進めるうちに奇妙な繋がりが見えてきます。ネットロア特有の、じわじわと不安を煽るような不気味さと、散りばめられた謎解きの要素が魅力の一冊です。



ネットで読んでた話が繋がっていくのが面白い!バラバラだったピースがはまっていく感じが、怖さと同時に快感でもあるんだよね。
16位: 『営繕かるかや怪異譚』 小野不由美
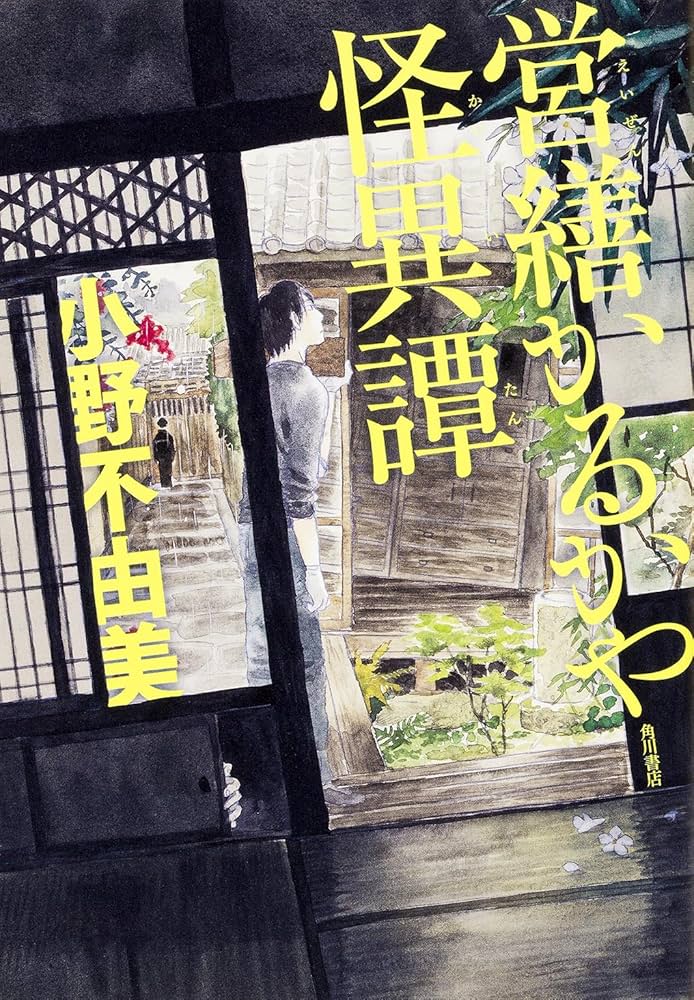
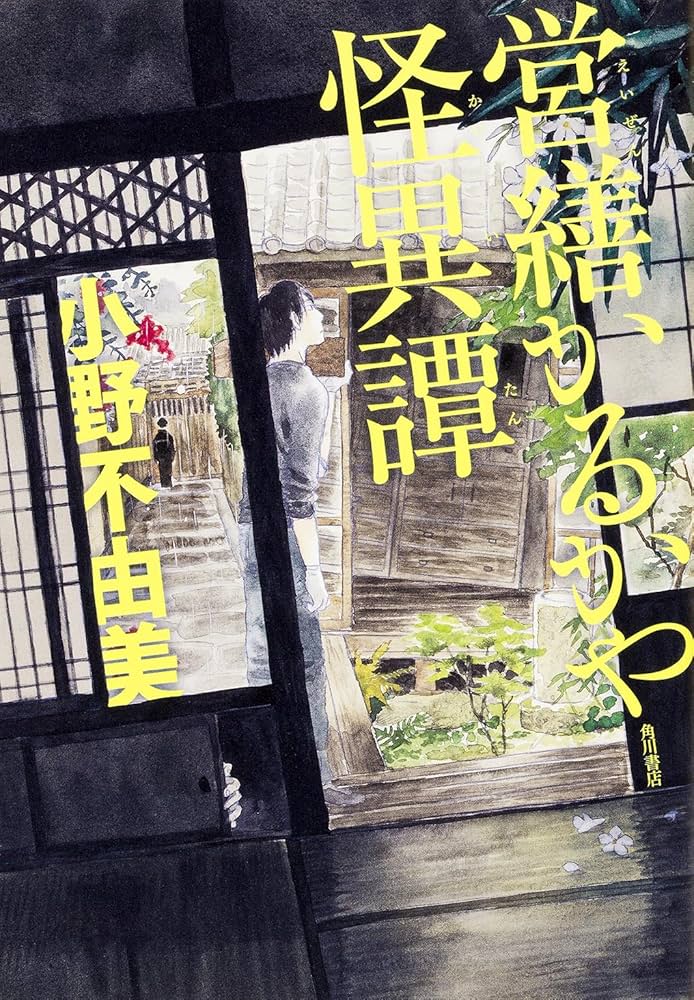
再び小野不由美作品がランクイン。『営繕かるかや怪異譚』は、家にまつわる怪異を「営繕屋」が解決していく、少し不思議で心温まる連作短編集です。
営繕屋の尾端は、建物の不具合だけでなく、そこに住む人々が抱える怪異の相談も請け負います。彼は、家に残された人々の想いや記憶を丁寧に紐解き、怪異の根本にある「疵(きず)」を修繕していきます。怖いだけでなく、読後にはどこか救われたような気持ちになる、優しい怪談です。



怪異をただ怖がるんじゃなくて、その原因を優しく解きほぐしていくのが素敵だよね。わたしもこんな営繕屋さんにお願いしたいな。
17位: 『山の霊異記』 安曇潤平
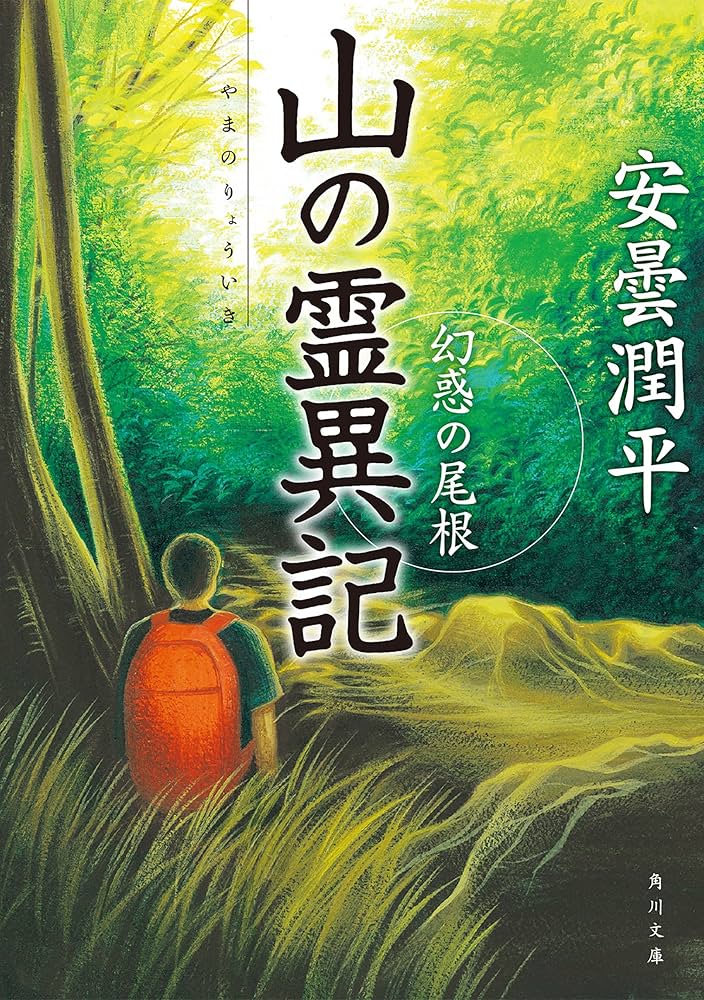
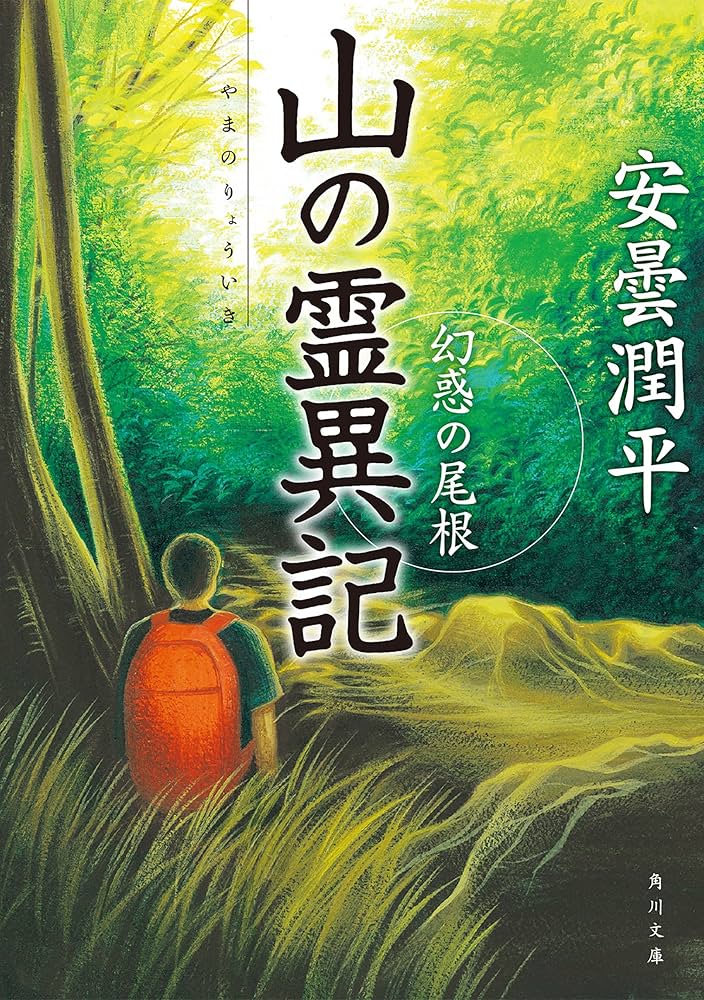
山で起こる不思議な出来事、いわゆる「山怪」をテーマにした実話怪談シリーズの代表作。山岳雑誌の編集者でもある著者が、自らの体験や登山者からの取材をもとに、山にまつわる怪異譚を綴ります。
山小屋で聞こえる謎の足音、道に迷わせる不思議な光、山に棲むとされる未知の存在。大自然への畏敬の念とともに語られる話の数々は、都市の怪談とは異なる、荘厳で根源的な恐怖を感じさせます。登山が趣味の人はもちろん、そうでない人も、山の持つもう一つの顔に引き込まれることでしょう。



山という異界における超常現象の記録は、近代化で失われつつある自然への畏怖を喚起させる。現代のアニミズムの表出とも解釈できる。
18位: 『Another』 綾辻行人
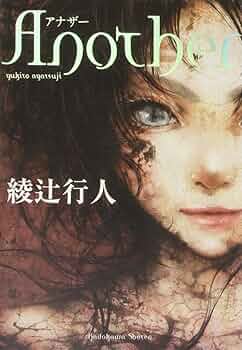
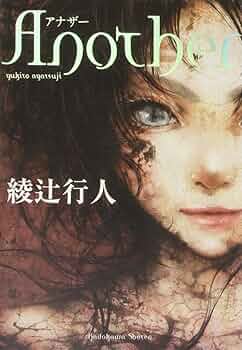
新本格ミステリーの旗手・綾辻行人による学園ホラーミステリーの傑作『Another』。謎が謎を呼ぶ展開と、クラスメイトが次々と凄惨な死を遂げていくスリルで、多くの読者を虜にしました。
主人公の榊原恒一が転校してきた夜見山北中学3年3組には、恐ろしい秘密がありました。それは、クラスに紛れ込んだ「死者」のせいで、毎年クラスの関係者が死んでいくという呪い。恒一は、クラスで「いない者」として扱われる謎の美少女・見崎鳴と共に、呪いを止めるために真相を探ります。ホラーとしての恐怖と、ミステリーとしての緻密な謎解きが見事に融合した作品です。



誰が「死者」なのか、最後まで分からなくてドキドキしたよ!ミステリーとしてもホラーとしても一級品で、一気に読んじゃった。
19位: 『仄暗い水の底から』 鈴木光司
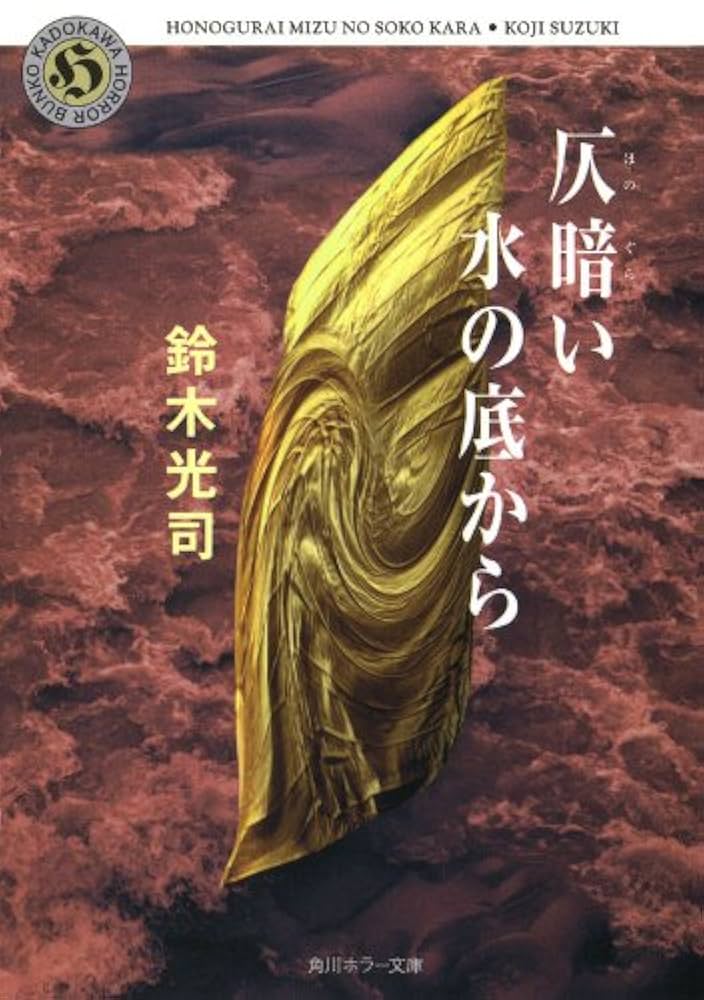
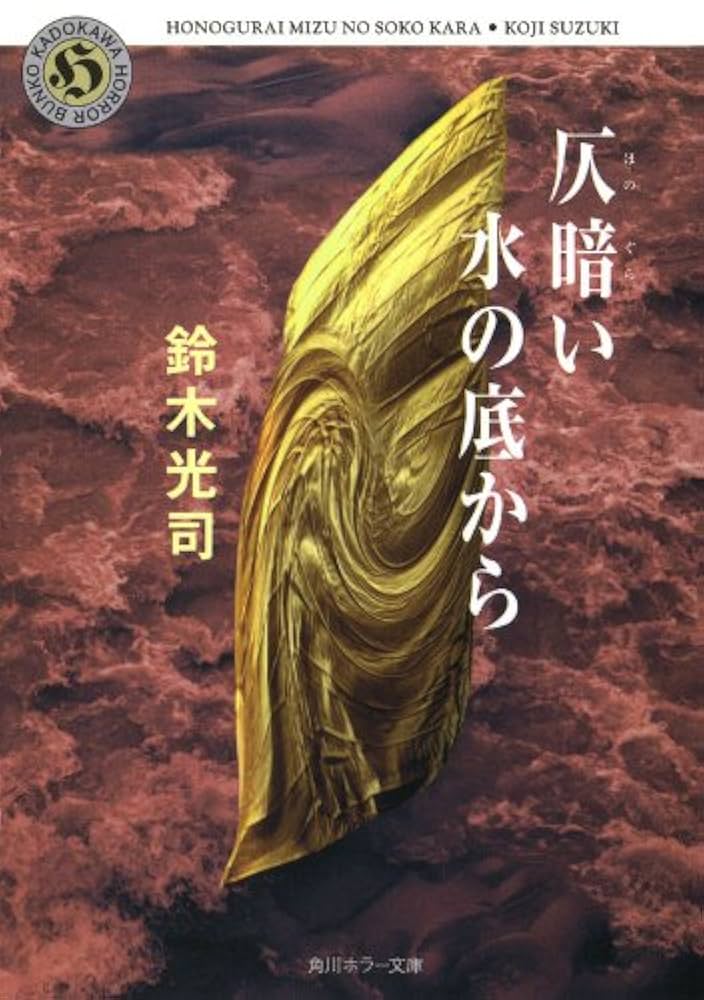
『リング』の鈴木光司が描く、水にまつわる恐怖を集めた短編集。表題作は映画化もされ、そのじっとりとした恐怖描写で高い評価を得ました。
本作に収められているのは、水という日常的な存在に潜む怪異を描いた物語です。古びたマンションの貯水槽、ヨットハーバーに浮かぶ廃船、地下水が湧き出る洞窟など、様々な「水辺」を舞台に、静かで不気味な恐怖が展開されます。派手なショックシーンに頼らず、湿度のある文章で読者の不安を掻き立てる、ジャパニーズホラーの真髄がここにあります。



生命の根源と死の象徴、両義的な水というモチーフが根源的な恐怖を喚起する。湿潤な描写は生理的な嫌悪感と不安を効果的に誘発する。
20位: 『虚魚』 新名智


第10回ハヤカワSFコンテスト〈大賞〉受賞作である『虚魚』は、SFとホラーが融合した異色の作品です。怪談の「解釈」をテーマにした、知的好奇心を刺激する一冊です。
主人公は、怪談を収集し、その発生原因を科学的に(あるいは疑似科学的に)分析する「怪異考現学」の研究者。彼は、ある漁村に伝わる「虚魚」という怪魚の伝説と、それにまつわる怪談の調査に乗り出します。怪談という非合理的な現象を、あくまで合理的に解き明かそうとする試みが、これまでにない新しい恐怖と面白さを生み出しています。



怪談を科学で分析するっていう発想がすごく面白い!怖いんだけど、知的な興奮もあって、新しい読書体験だったよ。
21位: 『厭な小説』 京極夏彦
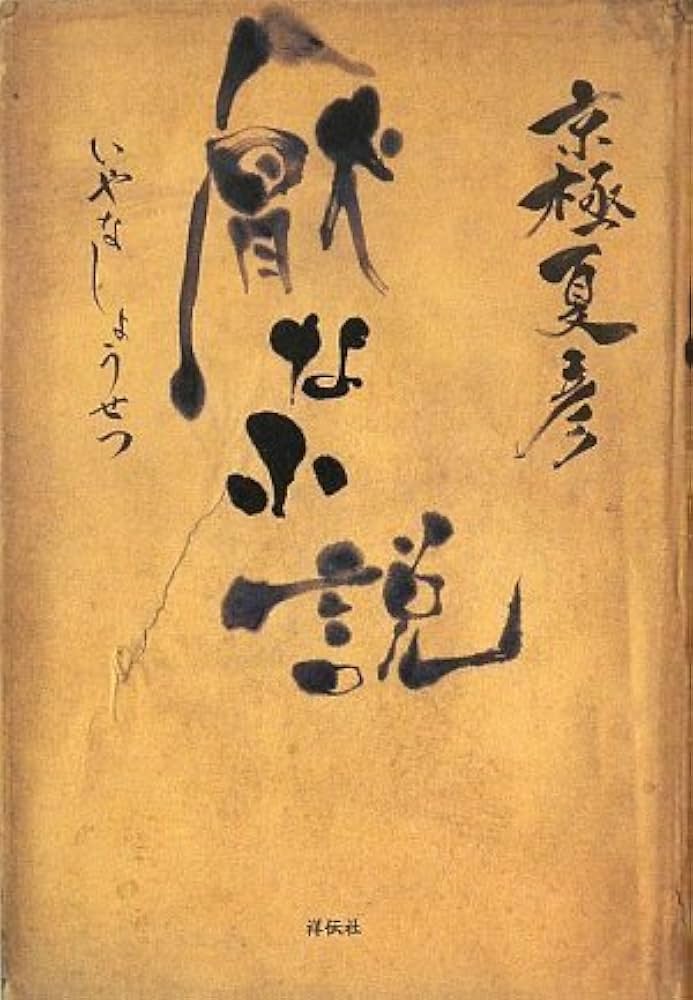
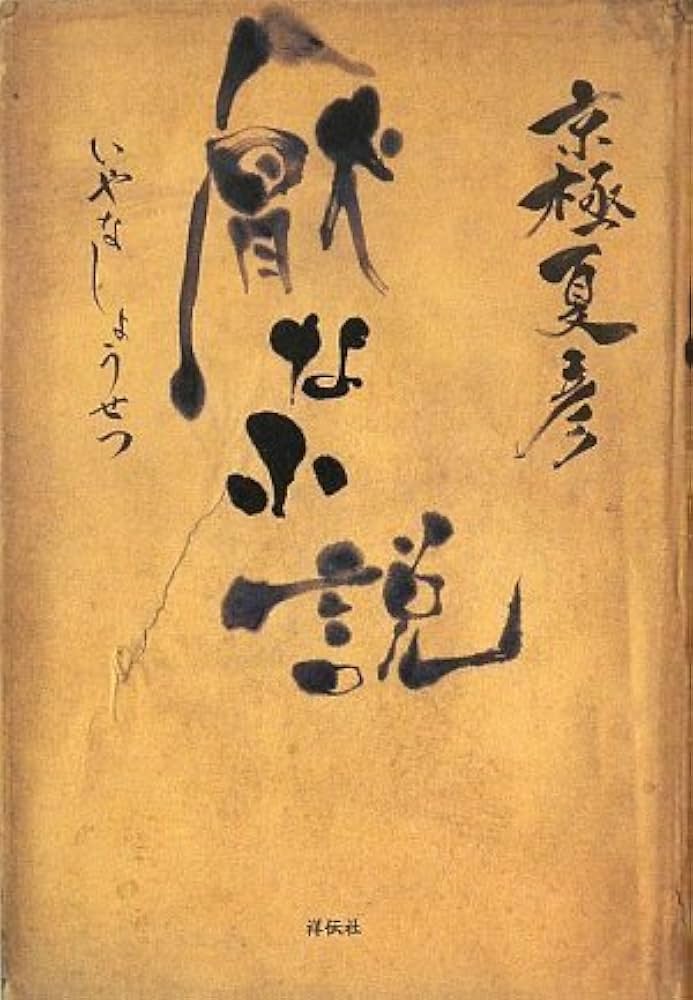
タイトル通り、読後にひたすら「厭な」気分になること間違いなしの短編集。京極夏彦が描く、日常に潜む不条理と狂気が詰まっています。
本作に収録されているのは、明確な怪異が登場するわけではないのに、なぜか不気味で後味の悪い物語ばかりです。「厭な子供」「厭な老人」「厭な家」など、生理的な嫌悪感を呼び起こすテーマが、執拗なまでに描かれます。理解不能な出来事や、登場人物たちの不可解な行動が、読者の心をじわじわと蝕んでいきます。



カタルシスを意図的に排除し、読者に純粋な不快感を与えることを目的としている。この徹底した非エンターテインメント性は、実験的文学の域だ。
22位: 『怪談和尚の京都怪奇譚』 三木大雲
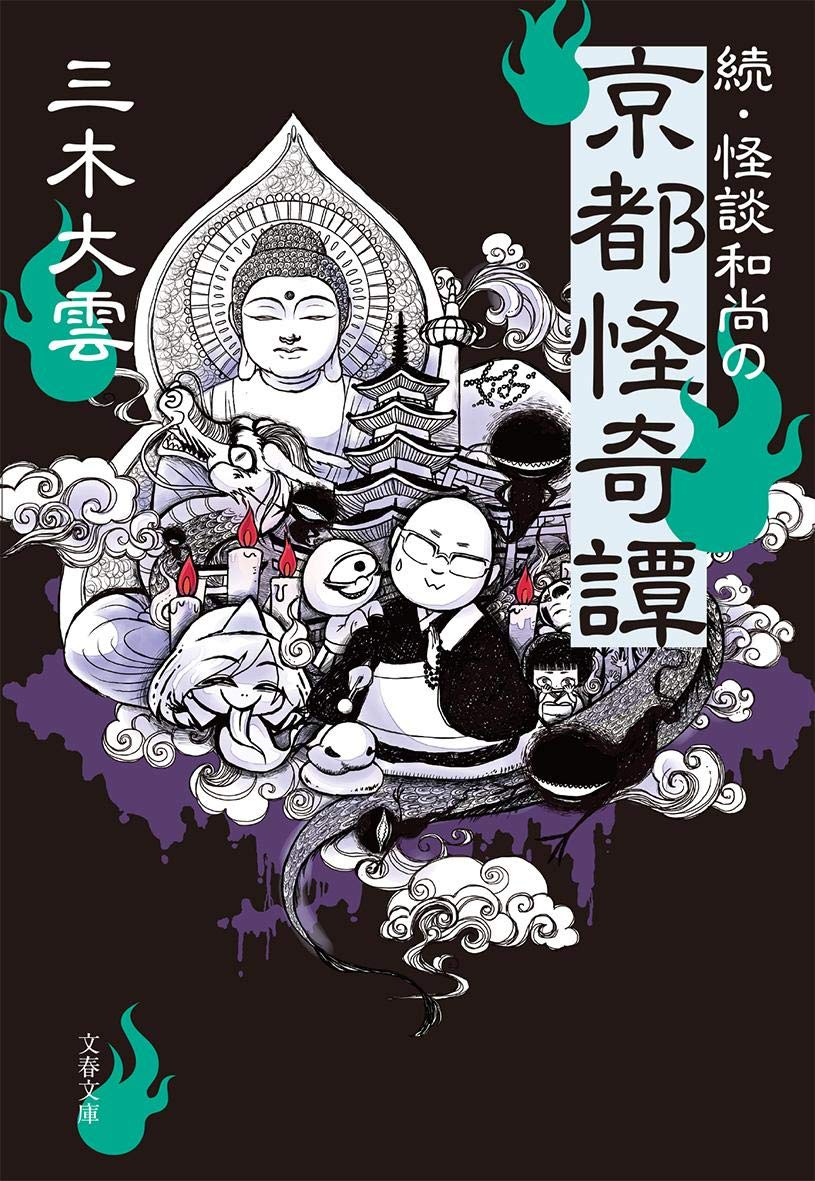
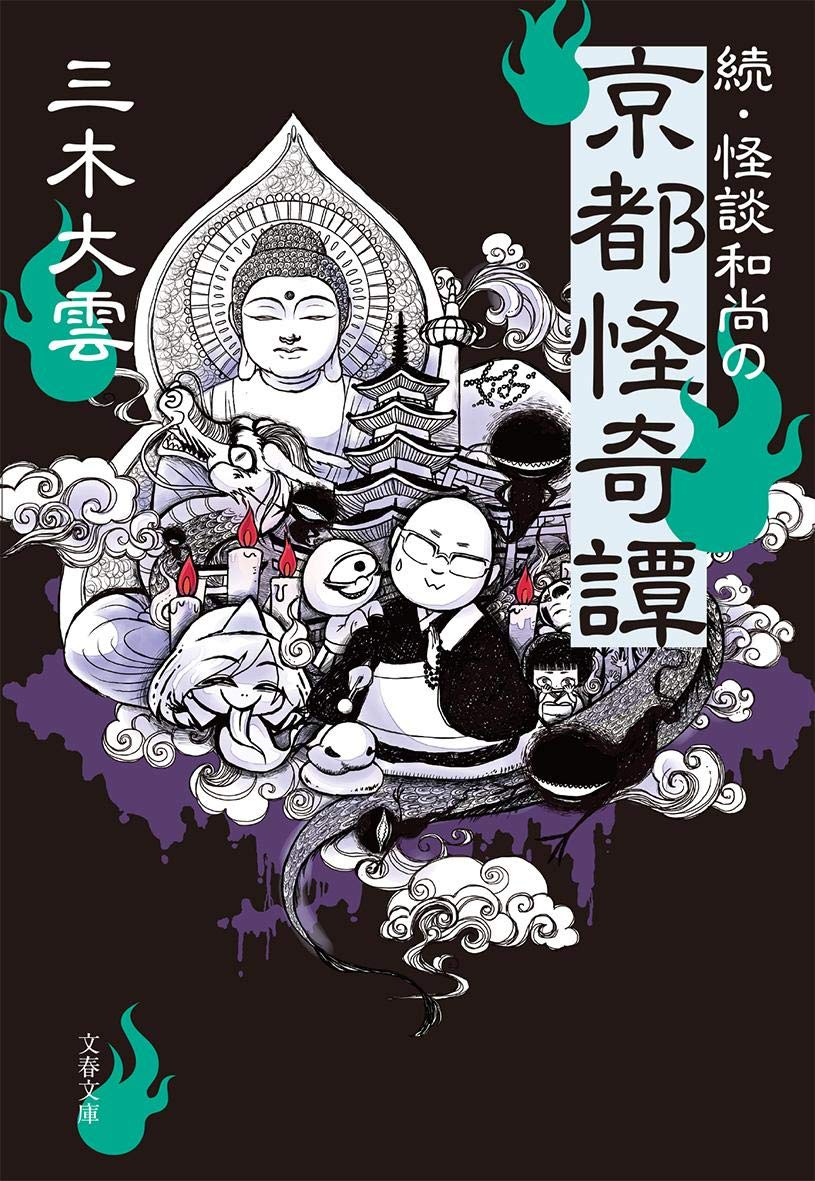
「怪談和尚」として知られる三木大雲住職による実話怪談集。僧侶という立場だからこそ見聞きした、因縁や業にまつわる恐ろしくも有り難い話が満載です。
京都の寺を舞台に、住職のもとに持ち込まれる様々な相談事や、自身が体験した不思議な出来事が語られます。単なる怖い話に終わらず、仏教的な教えや因果応報の理りが説かれているのが特徴です。読後には、恐怖とともに、何か大切な教えを得たような不思議な感覚が残ります。



怖いんだけど、仏様の教えが根底にあるからか、読んだ後に心が少し軽くなる気がするんだ。不思議な魅力のある怪談だね。
23位: 『夜市』 恒川光太郎
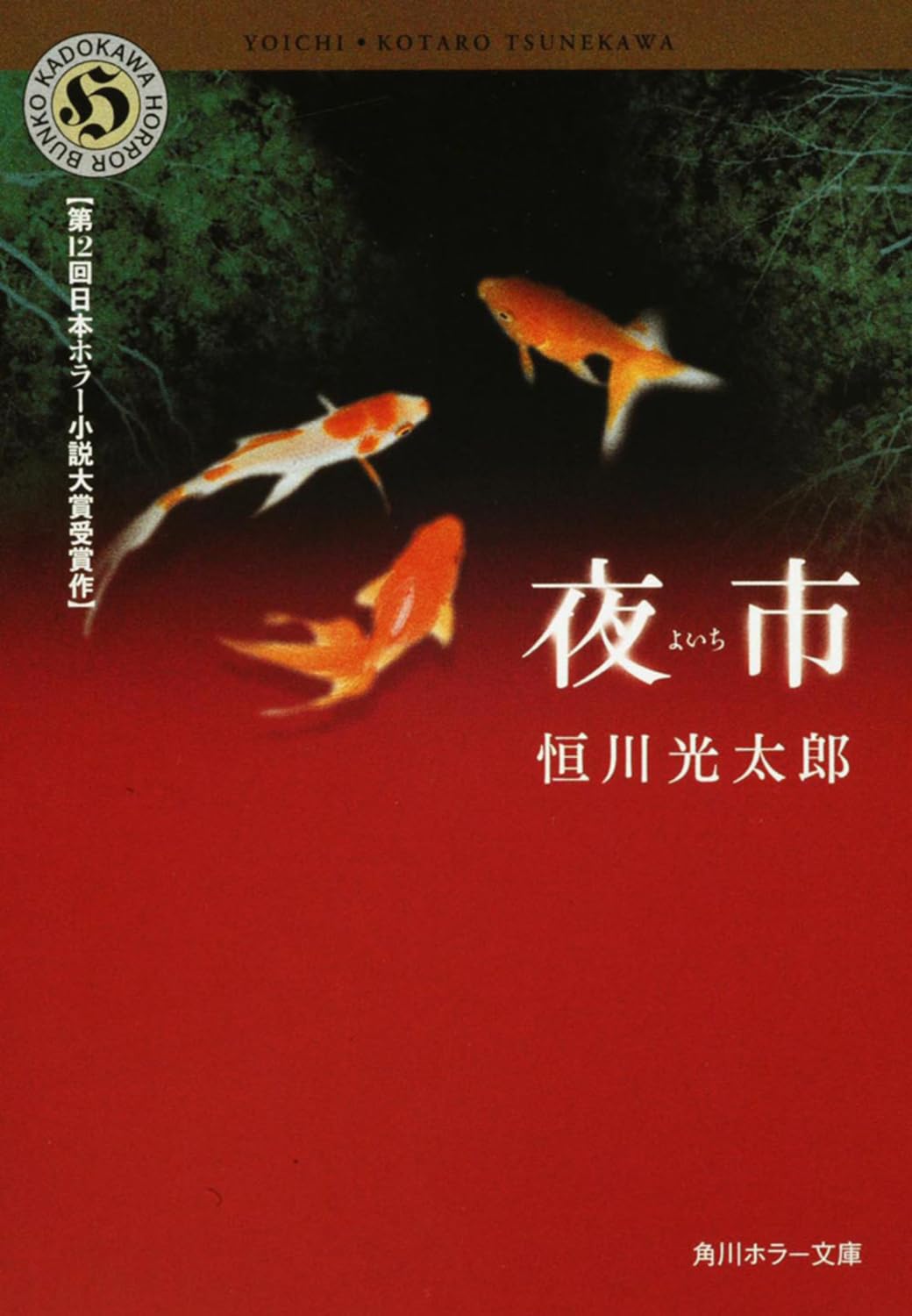
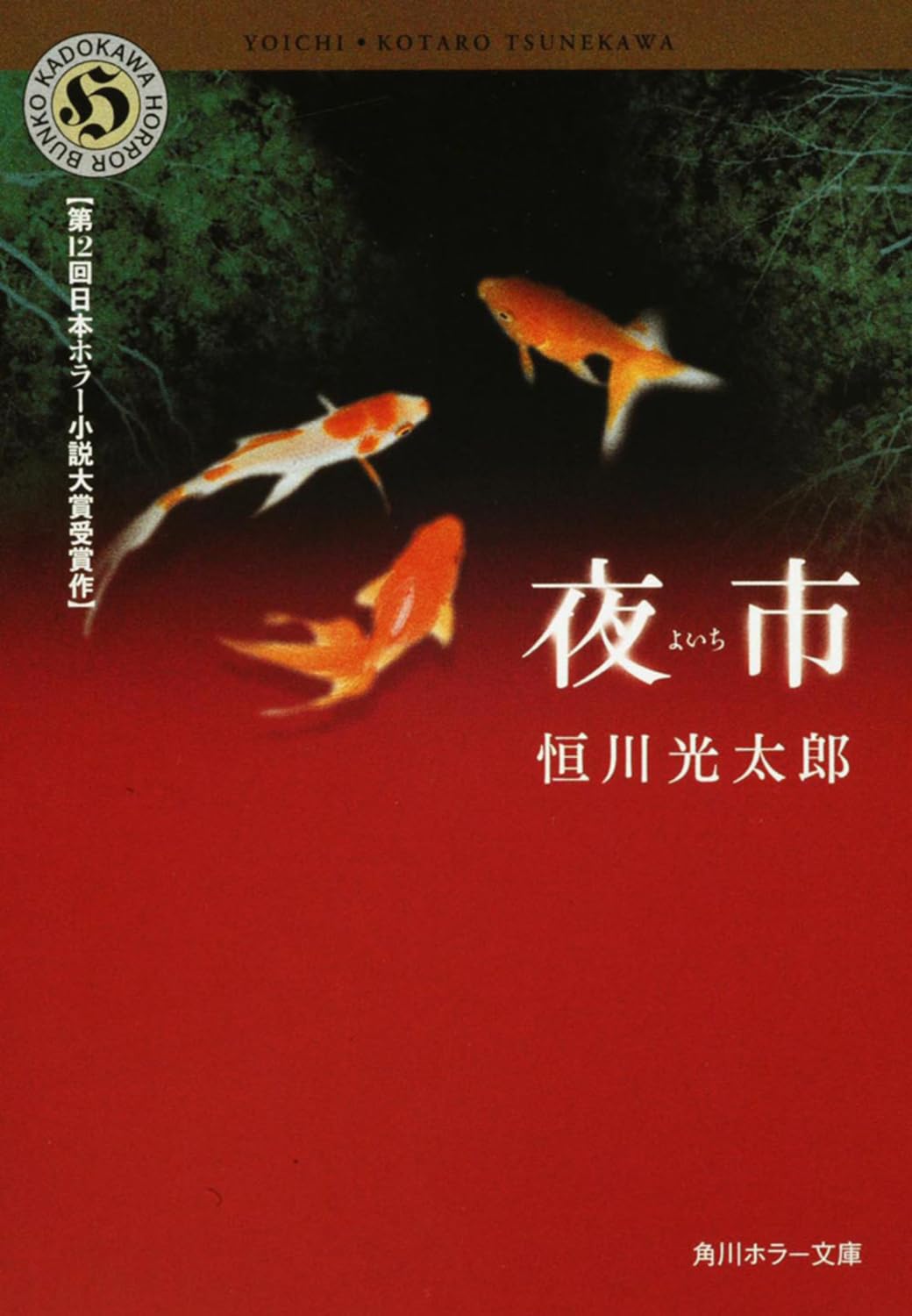
第12回日本ホラー小説大賞を受賞した恒川光太郎のデビュー作。ホラーでありながら、どこか懐かしく幻想的な世界観が魅力の作品です。
表題作「夜市」は、妖怪たちが開く不思議な市場に迷い込んだ兄妹の物語。ここではどんなものでも手に入りますが、そのためには何かを「売らなければ」なりません。もう一編の「風の古道」とともに、異世界に足を踏み入れた人間の運命を、美しくも残酷に描きます。恐怖と郷愁が入り混じった、唯一無二の読書体験ができます。



切なくて、美しい物語だったな…。怖いというより、もう二度と戻れない子供時代を思い出すような、胸が締め付けられる感じがしたよ。
24位: 『るんびにの子供』 宇佐美まこと


第1回幽ブックスホラー小説大賞〈大賞〉受賞作。ある宗教施設で育った子供たちの視点から、信仰の狂気と無垢な魂の悲劇を描いた衝撃作です。
外界から隔絶された施設「るんびに」で暮らす子供たち。彼らは、そこで行われる奇妙な儀式や教えを純粋に信じていました。しかし、ある事件をきっかけに、施設の恐ろしい実態が明らかになっていきます。子供たちの無垢な視点で語られるからこそ、その異常性と残酷さが際立ち、読者に強烈な印象を残します。



閉鎖的コミュニティにおける信仰の暴走というテーマが、社会病理を鋭く抉り出す。無垢な子供の視点により、読者は狂気の内部を追体験させられる。
25位: 『ZOO』 乙一
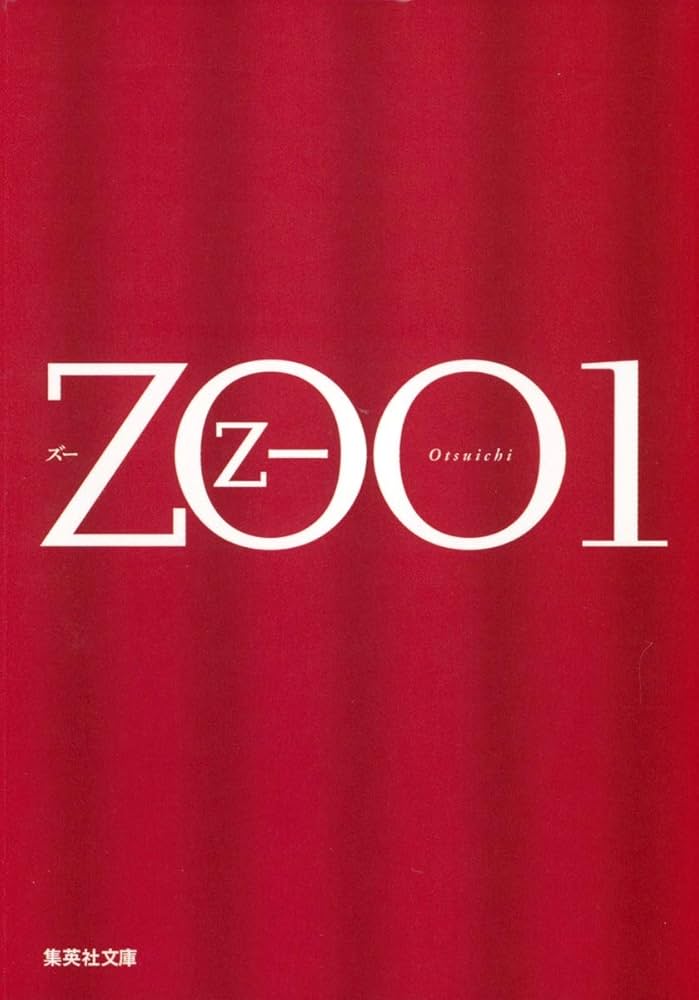
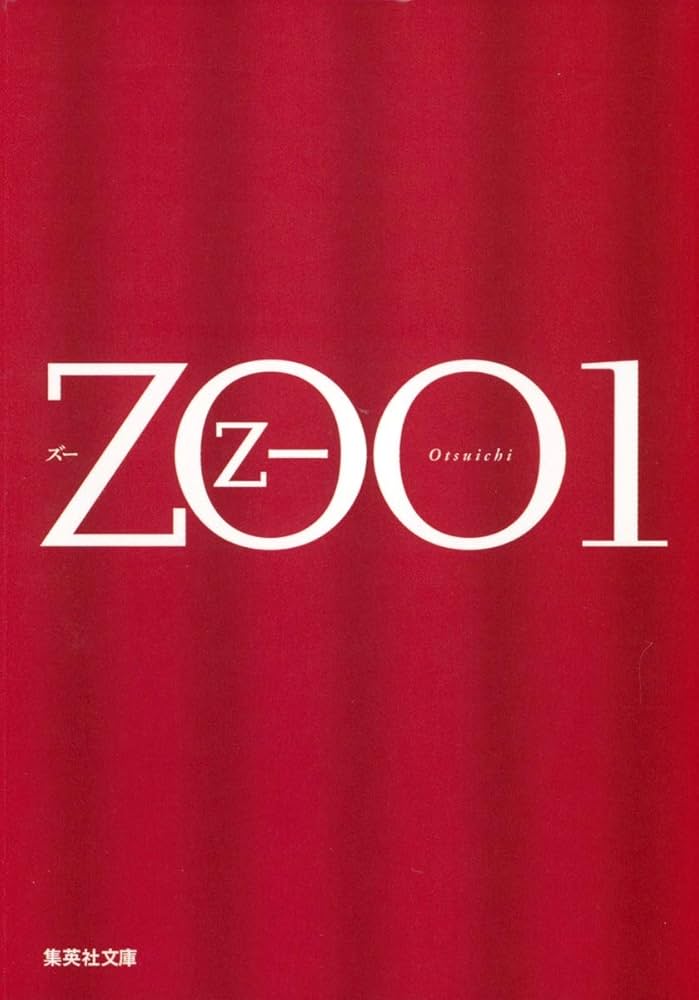
「黒乙一」と「白乙一」の二つの顔を持つ作家・乙一の、「黒」の側面が存分に発揮された短編集。残酷で、グロテスクで、しかしどこか切ない物語が詰まっています。
本作には、ホラー、サスペンス、ダークファンタジーなど、多彩なジャンルの物語が収録されています。姉妹の歪んだ愛情を描く話、毎日バラバラ死体が送られてくる男の話など、どの作品も奇抜なアイデアと巧みなストーリーテリングで読者を引き込みます。人間の持つ狂気や孤独を鋭く描き出した、乙一ワールドの入門編としても最適な一冊です。



怖いしグロいんだけど、なぜか物語の美しさに惹きつけられちゃうんだよね。乙一さんの才能には本当に驚かされるよ。
26位: 『おはしさま 連鎖する怪談』 三津田信三ほか


三津田信三をはじめとする、現代ホラーを代表する作家たちが集結したアンソロジー。一つの怪談が、作家から作家へとリレー形式で語り継がれていくという実験的な一冊です。
最初の作家が提示した「おはしさま」という怪談を、次の作家が自分なりの解釈や展開を加えて語り継いでいきます。同じテーマでありながら、作家ごとに全く異なる恐怖が生み出されていく過程は圧巻です。怪談がどのように生まれ、変化し、伝播していくのかを体感できる、ホラーファン必読の企画本です。



いろんな作家さんの怪談が一度に読めるなんて贅沢!同じお題なのに、こんなに違う話になるんだって感動しちゃった。
27位: 『冥途』 内田百閒
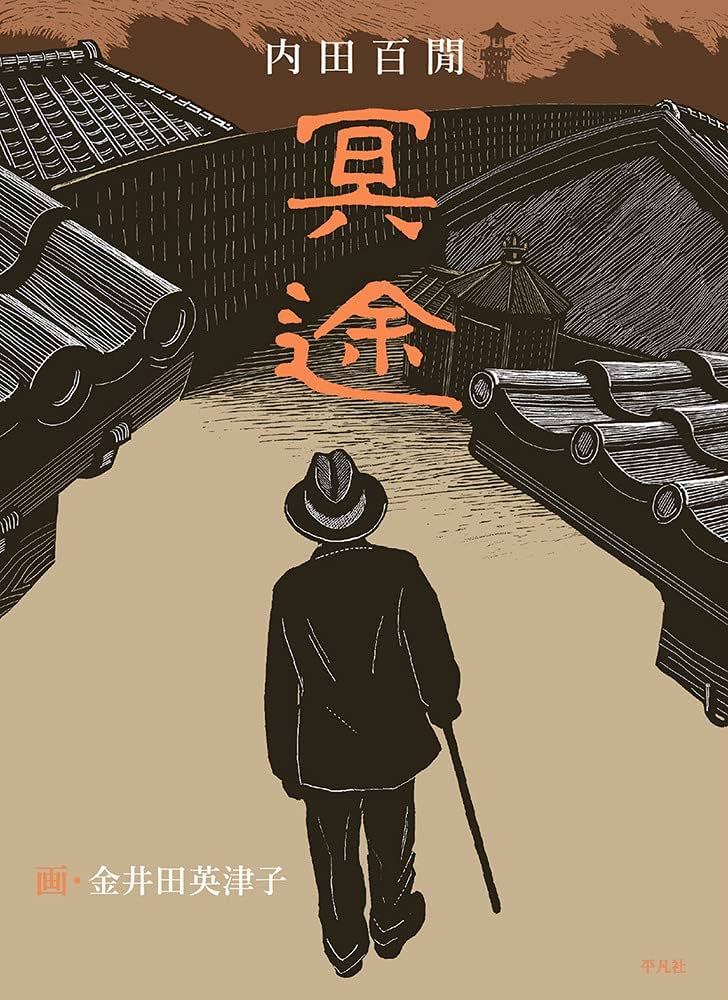
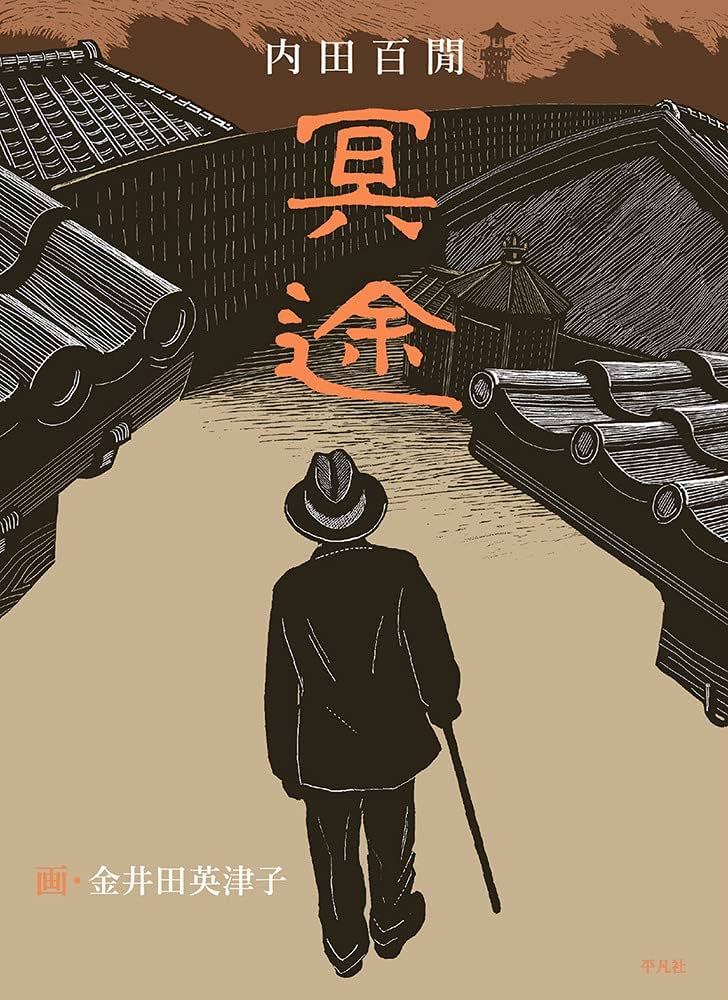
夏目漱石門下の作家としても知られる内田百閒による、幻想的で不条理な短編集。現実と夢の境界が曖昧な世界を描いた、近代日本文学における怪談の古典です。
本作に収められた物語には、明確な筋書きや結末がないものも多く、読者はまるで悪夢の中に迷い込んだかのような感覚に陥ります。論理では説明できない不可解な出来事が、淡々とした美しい文章で綴られており、じわじわと不安を掻き立てられます。近代文学ならではの、知的でシュールな恐怖を味わえる一冊です。



本作の恐怖は、物語の非論理性に由来する。因果律の崩壊した世界が、読者の現実認識を揺るがし形而上学的な不安をもたらす。
28位: 『高野聖』 泉鏡花
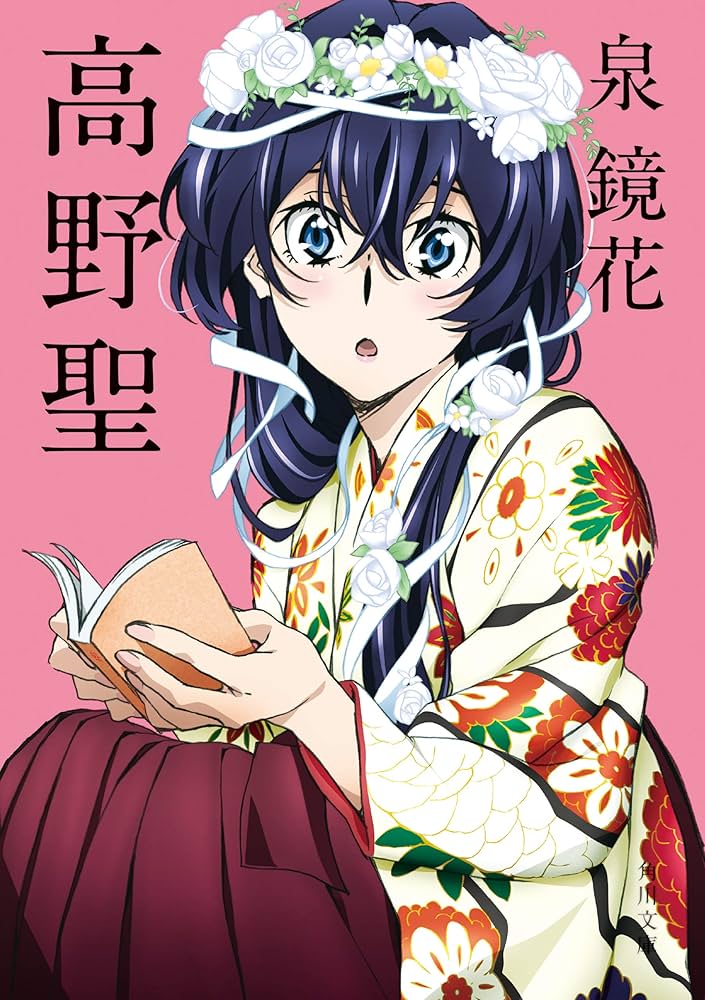
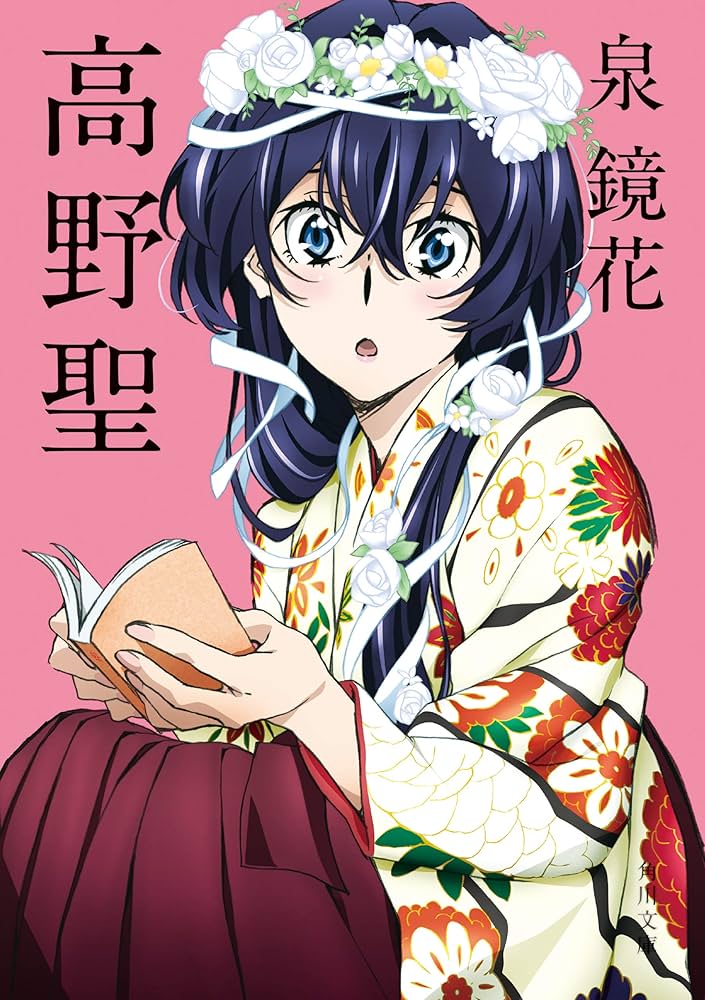
明治の文豪・泉鏡花による幻想文学の傑作『高野聖』。妖艶で神秘的な世界観と、詩的で美しい文体が魅力の作品です。
若い僧侶が、旅の途中で道に迷い、山奥の一軒家にたどり着きます。そこに住んでいたのは、この世のものとは思えぬほど美しい女性でした。しかし、彼女には男を獣に変えてしまう恐ろしい力があったのです。聖なるものと魔なるものが交錯する、幻想的でエロティックな物語は、読者を明治の怪奇ロマンへと誘います。



文章が本当に美しいんだよね…。怖いんだけど、その妖しい美しさにうっとりしちゃう。これぞ文学って感じ!
29位: 『雨月物語』 上田秋成
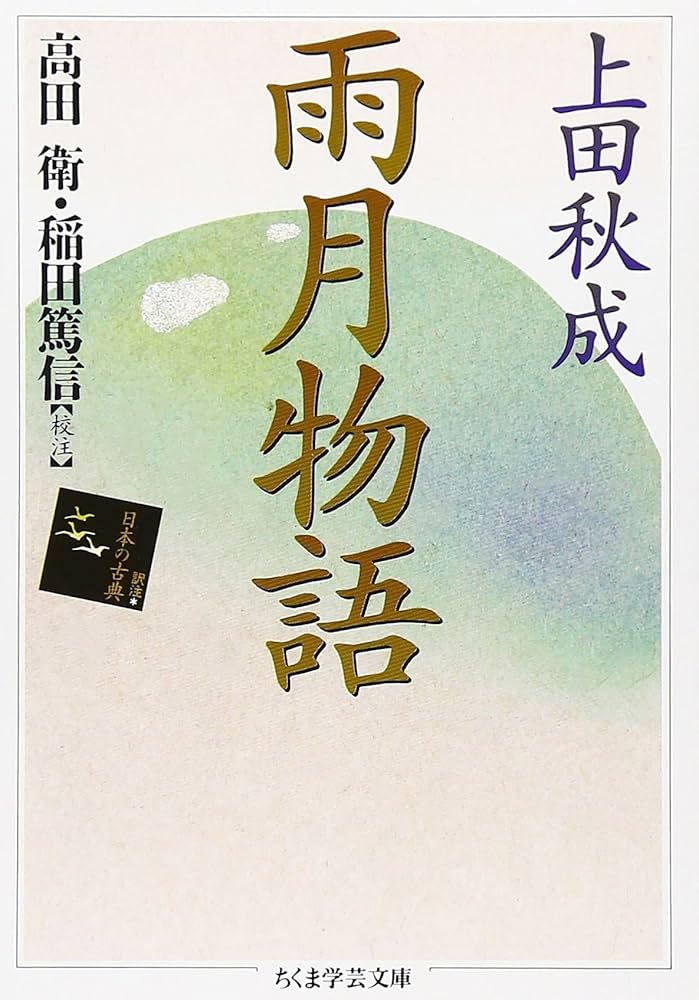
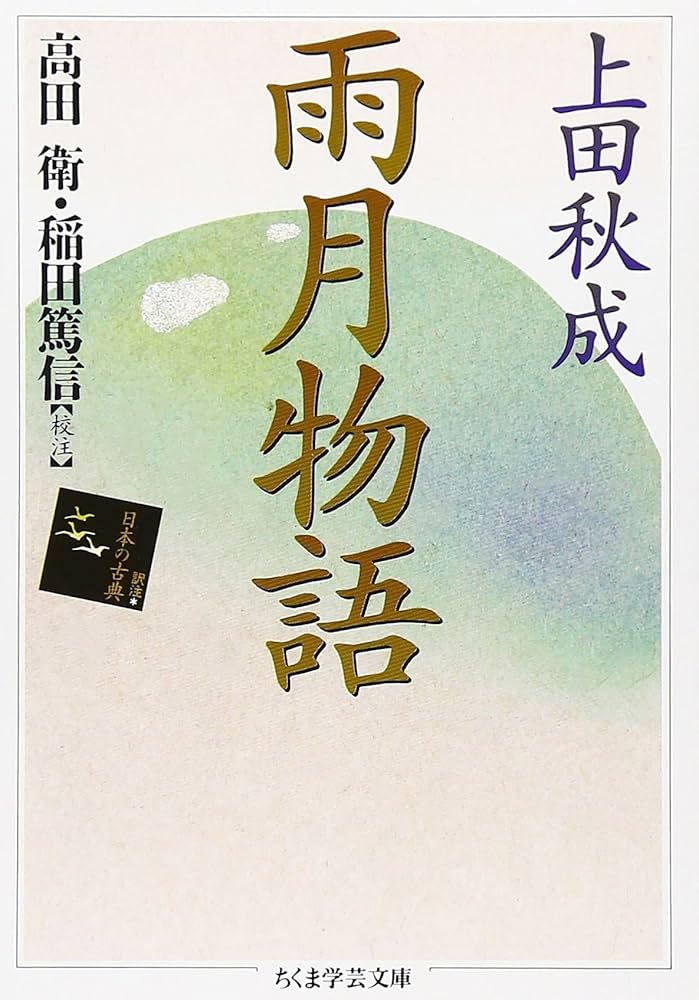
江戸時代後期に成立した、日本の怪談文学における最高傑作の一つ。中国の怪奇小説に影響を受けつつ、日本の歴史や風土に根差した物語が九編収められています。
死んだはずの妻が帰ってくる「浅茅が宿」、人食い鬼と化した元天皇を描く「白峯」など、収録されている物語はどれも有名です。人間の欲望や業、そして無常観といったテーマが、格調高い文章で描かれています。日本の怪談の原点を知る上で、欠かすことのできない古典的名著です。



単なる怪異譚に留まらず、仏教的・儒教的な思想を背景に持つ教訓譚としての側面も強い。人間の普遍的な業を描くからこそ、時代を超えて読み継がれる。
30位: 『四谷怪談』 鶴屋南北
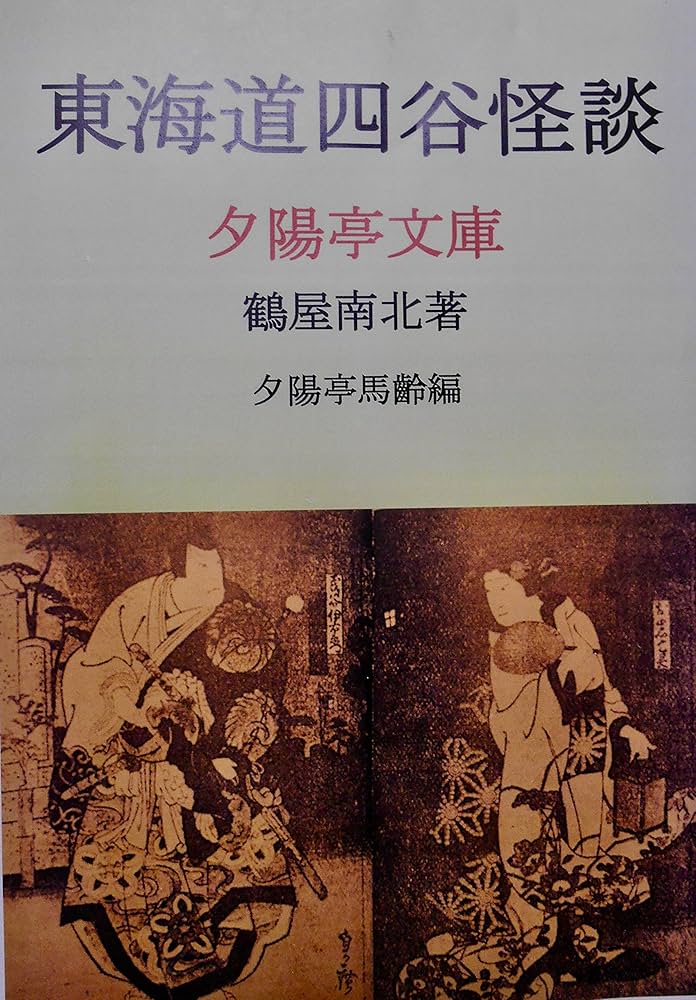
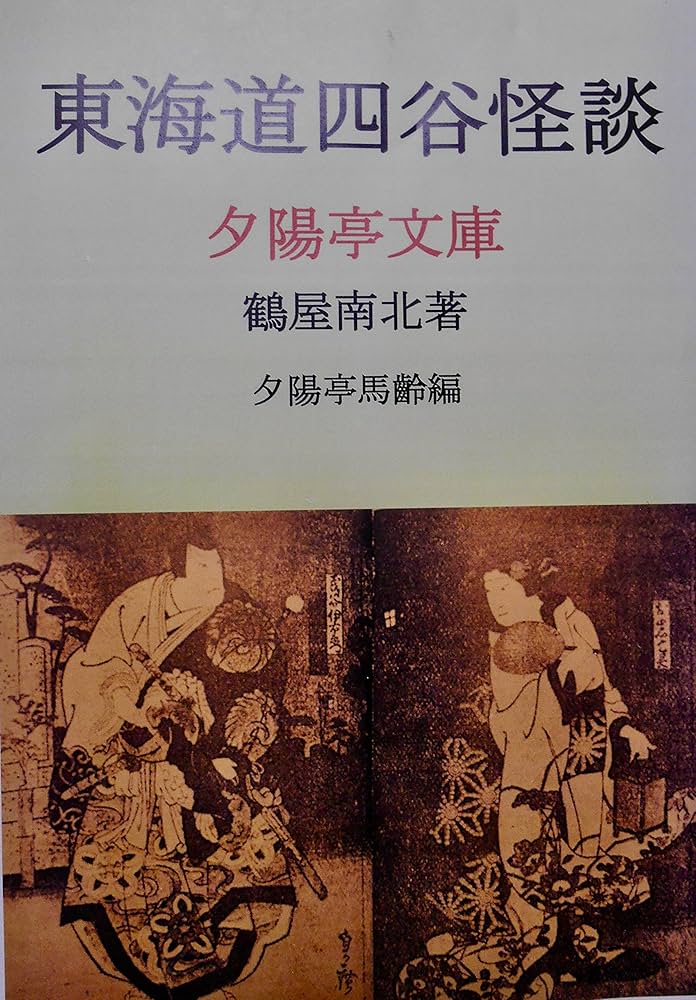
ランキングの最後を飾るのは、日本の怪談の代名詞ともいえる『四谷怪談』です。もとは鶴屋南北によって書かれた歌舞伎の演目『東海道四谷怪談』ですが、その物語は小説としても広く親しまれています。
夫・伊右衛門の裏切りによって惨殺された妻・お岩が、怨霊となって復讐を遂げるという物語は、あまりにも有名です。人間の欲望や裏切りが引き起こす悲劇と、因果応報の恐ろしさを描き、後世の多くのホラー作品に影響を与えました。日本の恐怖の原点に触れたいなら、避けては通れない一作です。



個人の情念が社会秩序を揺るがすという、怪談の基本形式を確立した作品だ。お岩の怨念は、私怨を超えた普遍的な力として描かれている。
あなたを恐怖の世界へ誘う一冊を見つけよう
ここまで、珠玉の怪談小説30作品をランキング形式でご紹介してきました。気になる一冊は見つかりましたでしょうか。
人間の悪意を描くサイコホラーから、じわじわと日常を侵食する静かな恐怖、ネット時代ならではの新感覚ホラー、そして時代を超えて語り継がれる古典まで、怪談小説の世界は実に多彩です。ぜひこのランキングを参考に、あなたの心に深く突き刺さる、最高の恐怖体験を探してみてください。