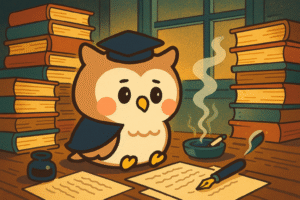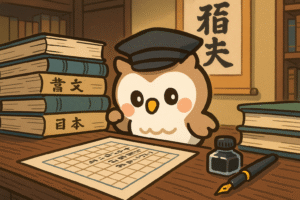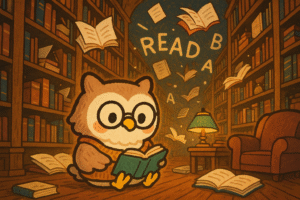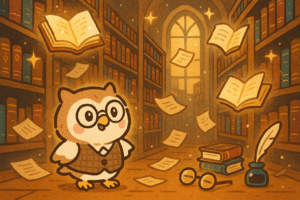あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。
【2025年最新】純文学小説のおすすめランキングTOP30
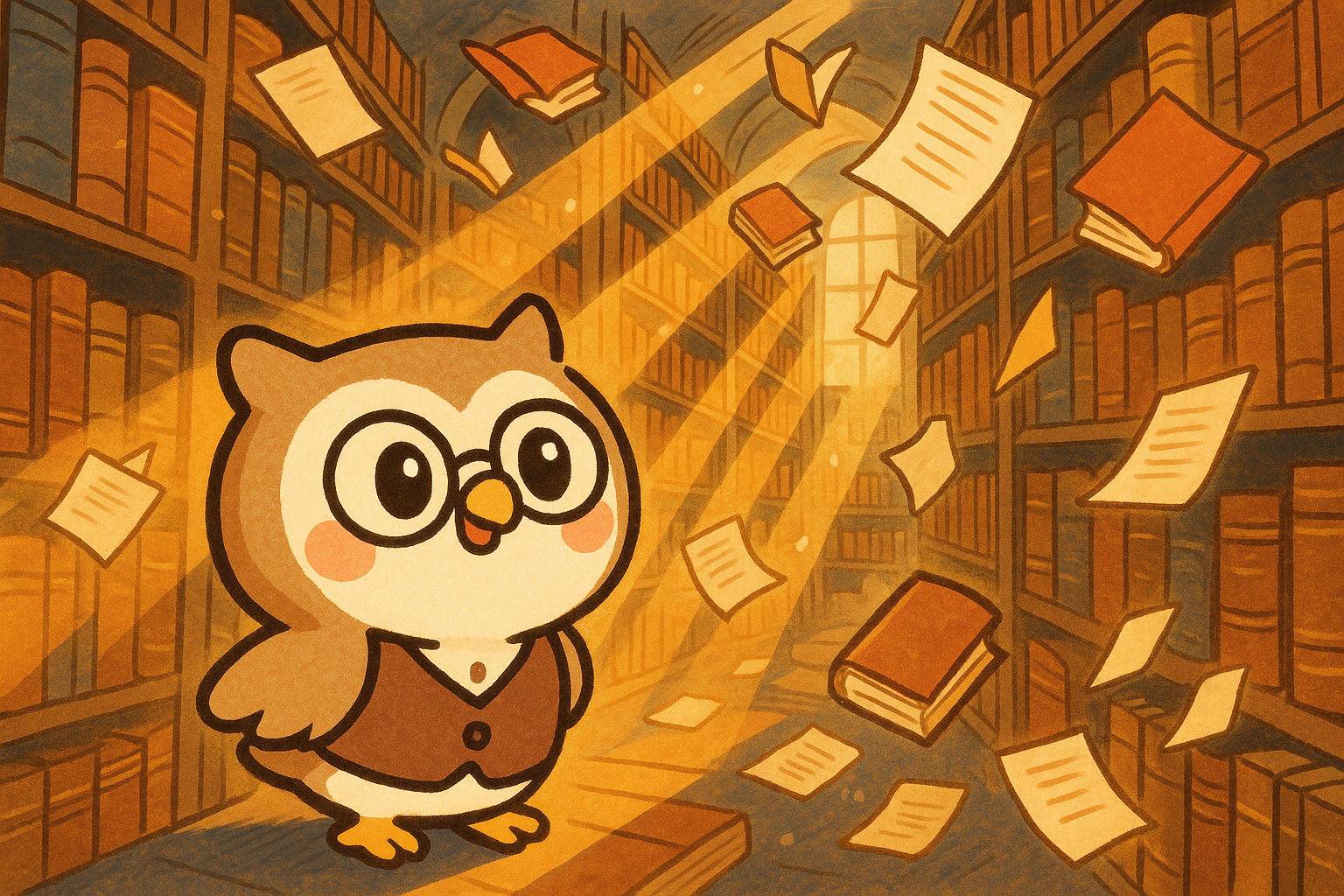
はじめに:純文学の奥深い世界へ
「純文学」と聞くと、少し難しそうなイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、純文学は人間の心の奥深くや、社会の複雑さを鋭く描き出す、非常に魅力的な文学ジャンルです。
エンターテイメント性を重視した大衆小説とは異なり、純文学は芸術性を追求し、読者に深い思索を促します。この記事では、時代を超えて読み継がれる不朽の名作から、現代を生きる私たちの心に響く最新の話題作まで、おすすめの純文学をランキング形式でご紹介します。あなたの心に残る一冊が、きっと見つかるはずです。
純文学小説のおすすめランキングTOP30
ここからは、いよいよ純文学小説のおすすめランキングTOP30を発表します。文豪たちの手による古典的名作から、現代作家が描く新しい純文学まで、幅広く選びました。あらすじや作品のポイントも解説しますので、気になる作品を見つける参考にしてください。
1位: 『人間失格』 太宰治
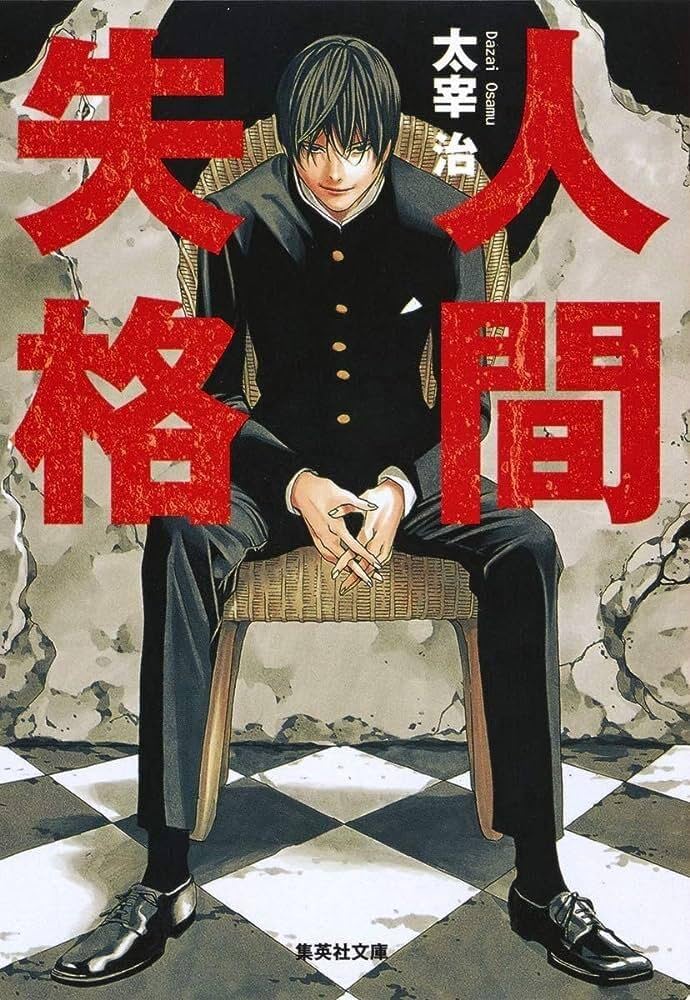
太宰治の代表作であり、日本近代文学の金字塔ともいえる作品です。主人公・大庭葉蔵が、幼少期から青年期にかけて体験する壮絶な人生と、その内面に渦巻く苦悩や疎外感を赤裸々に描いています。
「恥の多い生涯を送って来ました」という有名な一文から始まるこの物語は、人間の弱さや脆さ、そして社会との断絶をテーマにしています。時代を超えて多くの読者の心を捉え、自分とは何か、生きるとは何かを問いかけ続ける不朽の名作です。
 ふくちい
ふくちい主人公の葉蔵に自分を重ねてしまう人は多いんじゃないかな。人間の根源的な孤独が描かれていて、読むたびに胸が締め付けられるよ。
2位: 『こころ』 夏目漱石
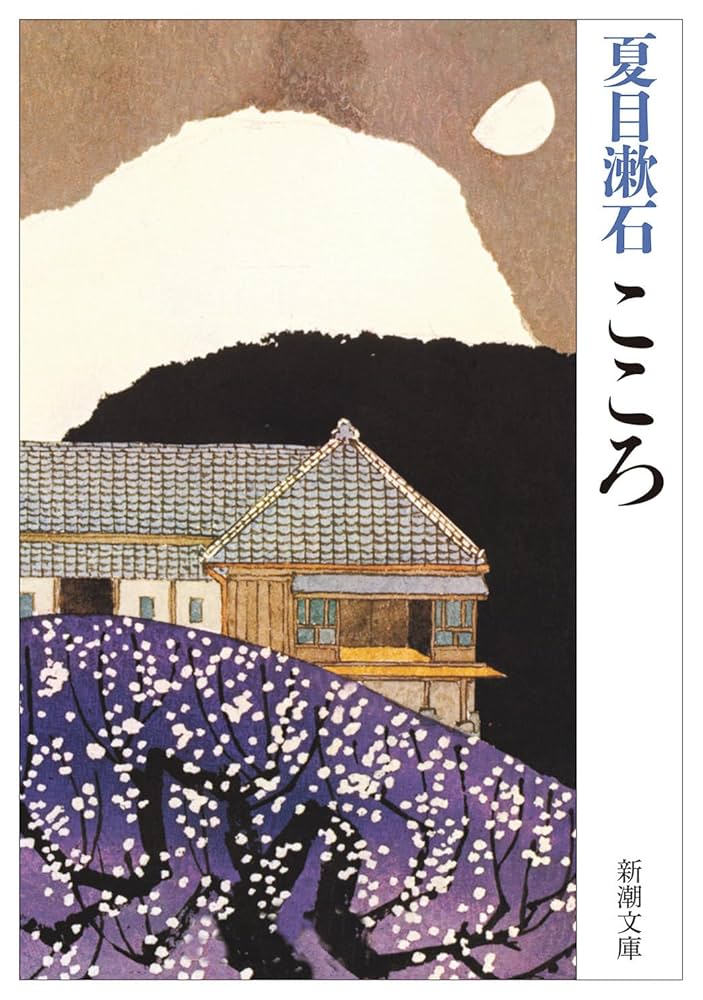
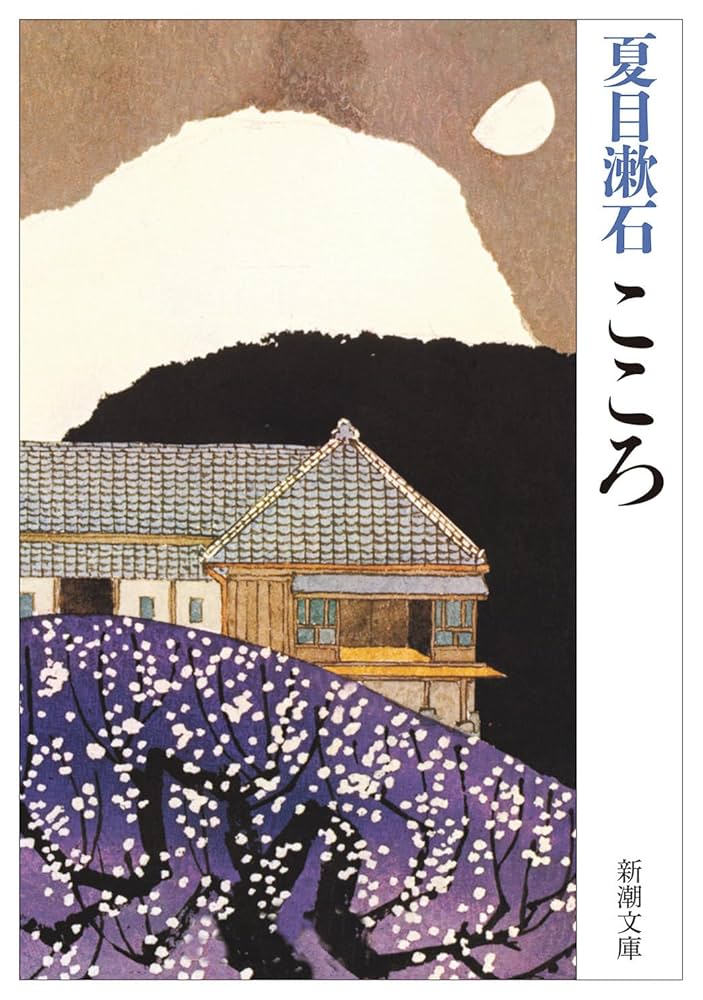
夏目漱石の後期三部作の一つで、多くの教科書にも掲載されている日本近代文学の代表作です。物語は「先生と私」「両親と私」「先生と遺書」の三部構成で、若い学生である「私」と、謎めいた過去を持つ「先生」との交流を描いています。
先生が抱える孤独や罪の意識、そして親友であった「K」をめぐる悲劇が、先生自身の遺書によって明らかにされていきます。人間のエゴイズムや孤独、そして近代化の中で揺れ動く知識人の苦悩を深く描いた作品です。



先生とK、そして奥さんの関係がもどかしいよね。読み返すたびに新しい発見がある、本当に奥深い物語だと思うな。
3位: 『ノルウェイの森』 村上春樹
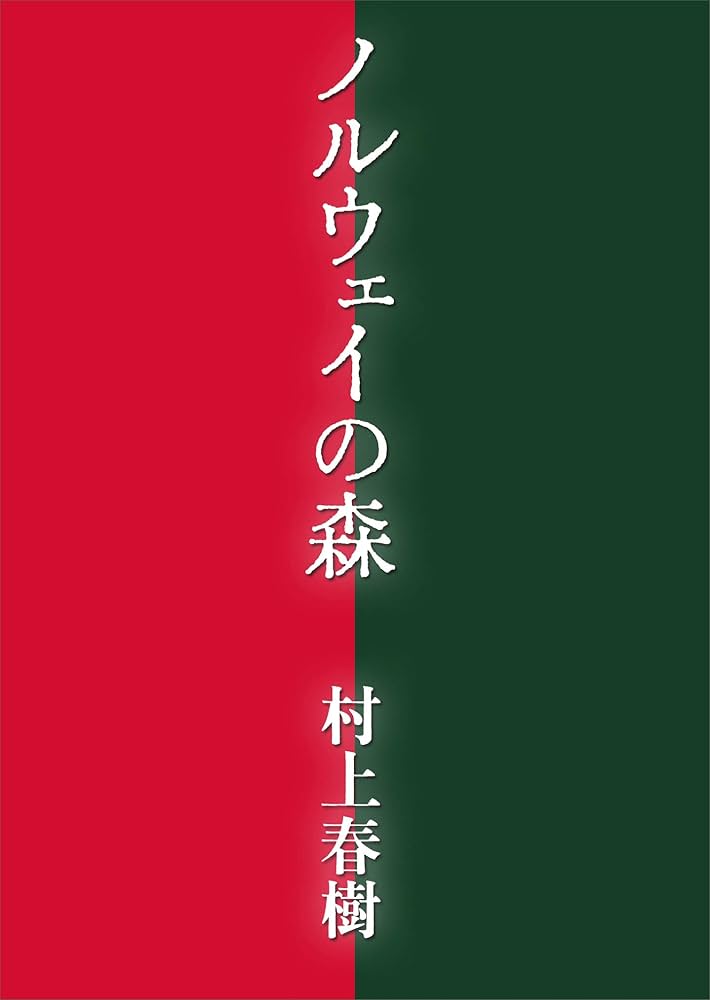
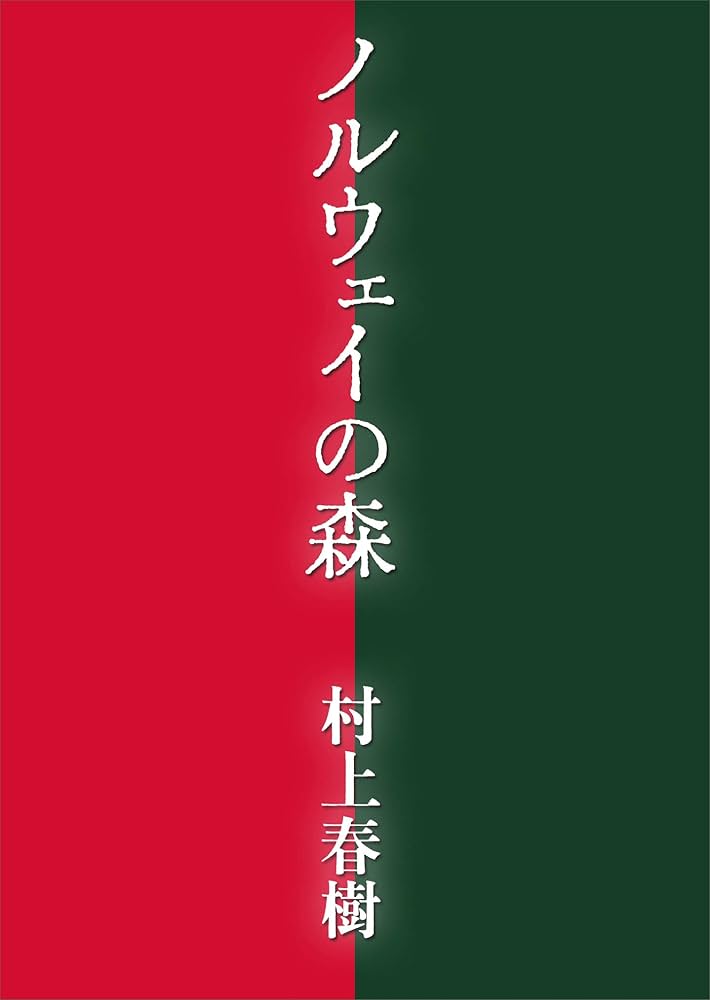
1987年に発表され、社会現象ともいえる大ベストセラーとなった村上春樹の代表作です。1960年代の東京を舞台に、主人公「僕」(ワタナベ)と、親友の元恋人である直子、そして大学で出会った緑との間で揺れ動く恋愛模様を描いています。
物語は、喪失と再生をテーマにしており、登場人物たちが抱える心の痛みや孤独、そしてそれを乗り越えようとする姿が繊細に描かれています。 ビートルズの同名の楽曲がモチーフとなっており、その切ないメロディが物語全体を包み込んでいます。



登場人物たちの会話がすごく魅力的だよね。独特の空気感があって、物語の世界にどっぷり浸れるんだ。
4位: 『コンビニ人間』 村田沙耶香
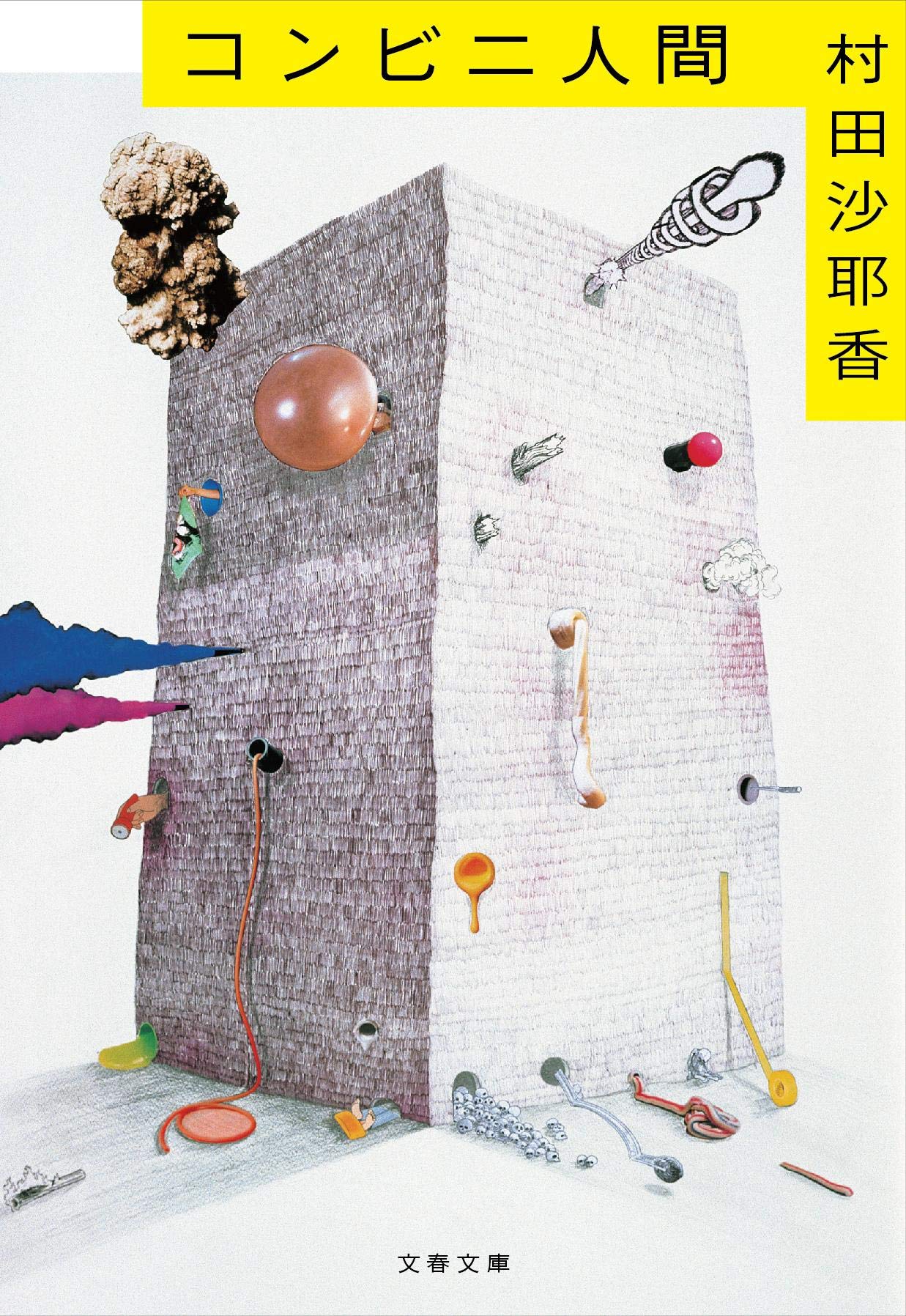
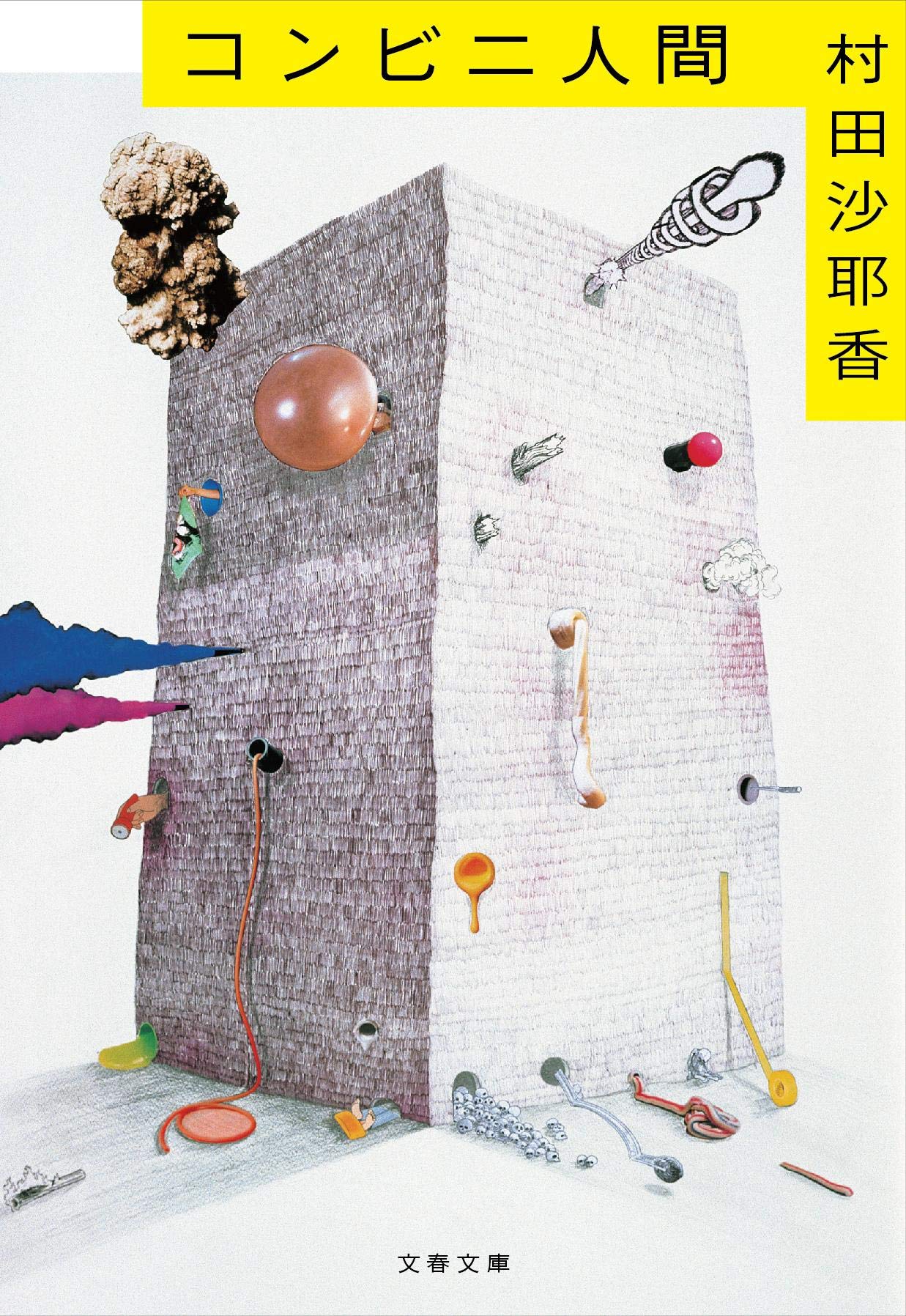
2016年に第155回芥川賞を受賞した、村田沙耶香の代表作です。36歳未婚、コンビニのアルバイト歴18年の主人公・古倉恵子を通じて、「普通」とは何か、「正常」とは何かを問いかけます。
マニュアル通りに動くことでしか社会と関われない恵子の姿は、現代社会の同調圧力や生きづらさを浮き彫りにします。ユーモラスでありながらも、読者の価値観を鋭く揺さぶる衝撃的な作品です。



「普通」ってなんだろうって、すごく考えさせられる一冊だよ。恵子の生き方が、なんだか清々しくも感じられるんだよね。
5位: 『羅生門・鼻』 芥川龍之介
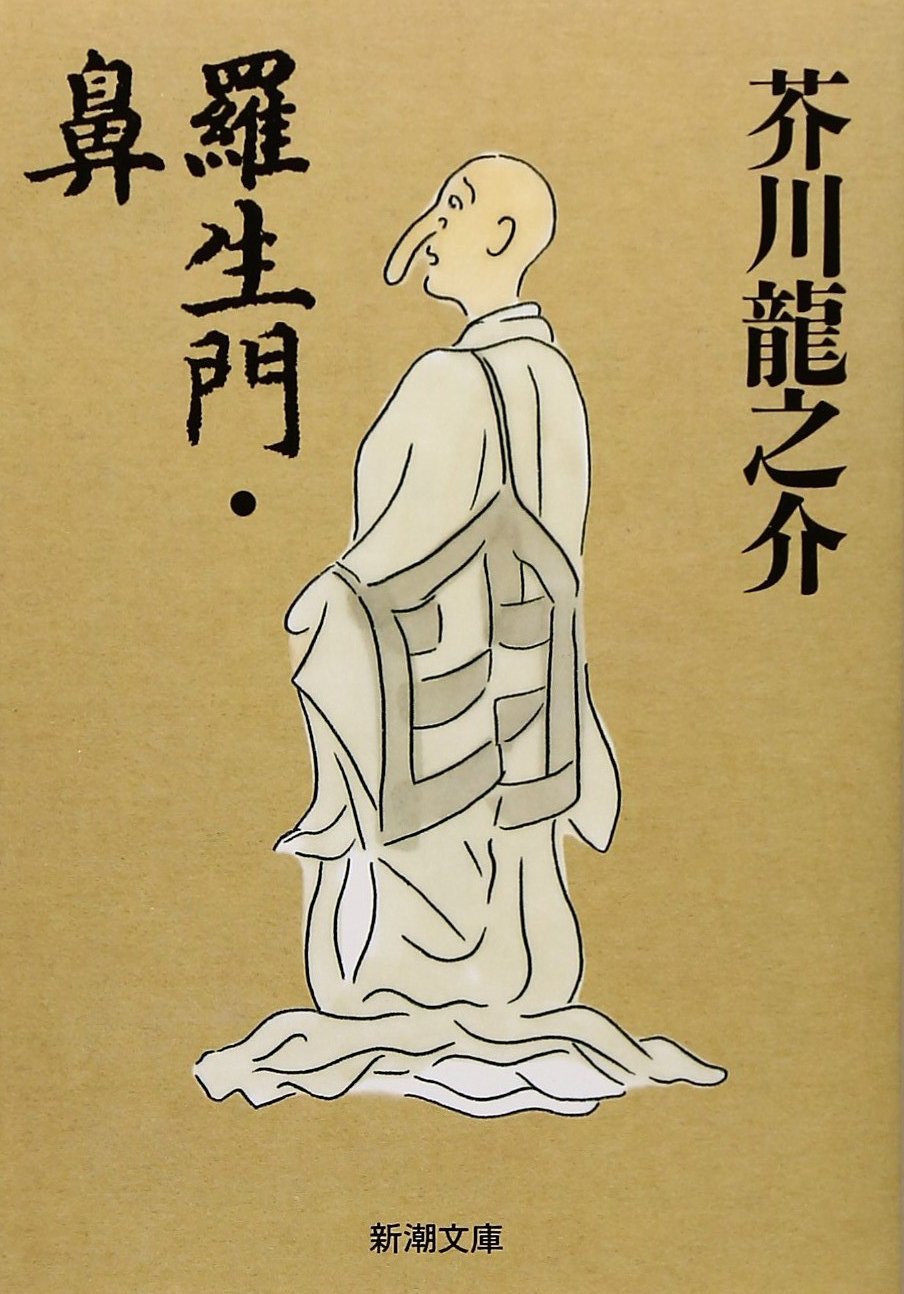
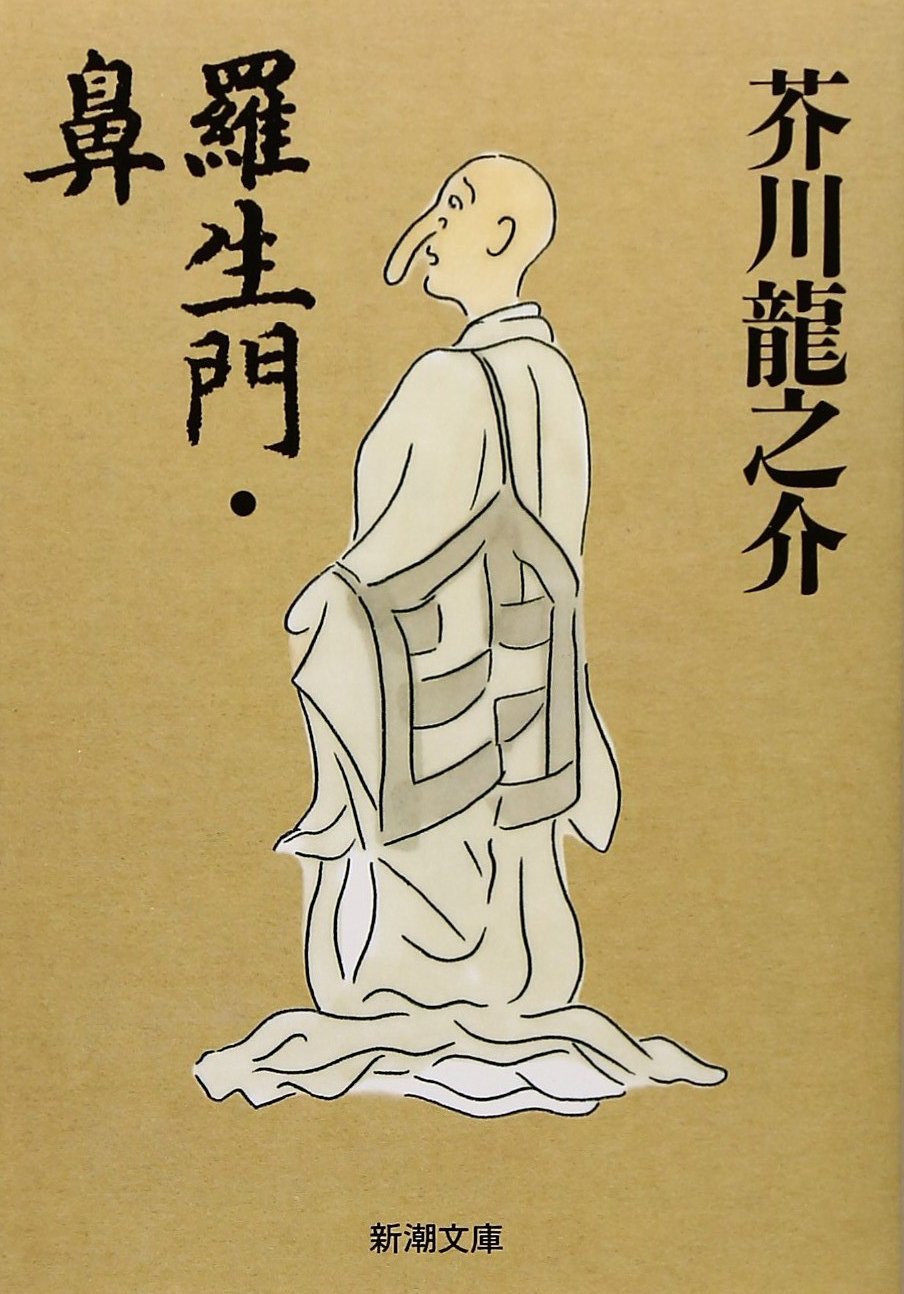
芥川龍之介の初期の短編小説で、彼の名を世に知らしめた作品です。『羅生門』は、荒廃した都で生きるために盗人になるしかない下人の姿を通して、人間のエゴイズムを冷徹な筆致で描いています。
一方、『鼻』は、長い鼻を持つ僧侶の自意識過剰な悩みをユーモラスに描いた作品です。どちらの作品も、人間の心理を深く洞察し、普遍的なテーマを簡潔かつ巧みに表現した、芥川文学の真骨頂といえるでしょう。



短い話なのに、人間の本質がギュッと詰まっている感じがするよ。特に『羅生門』のラストは、何度読んでもゾクゾクするな。
6位: 『火花』 又吉直樹
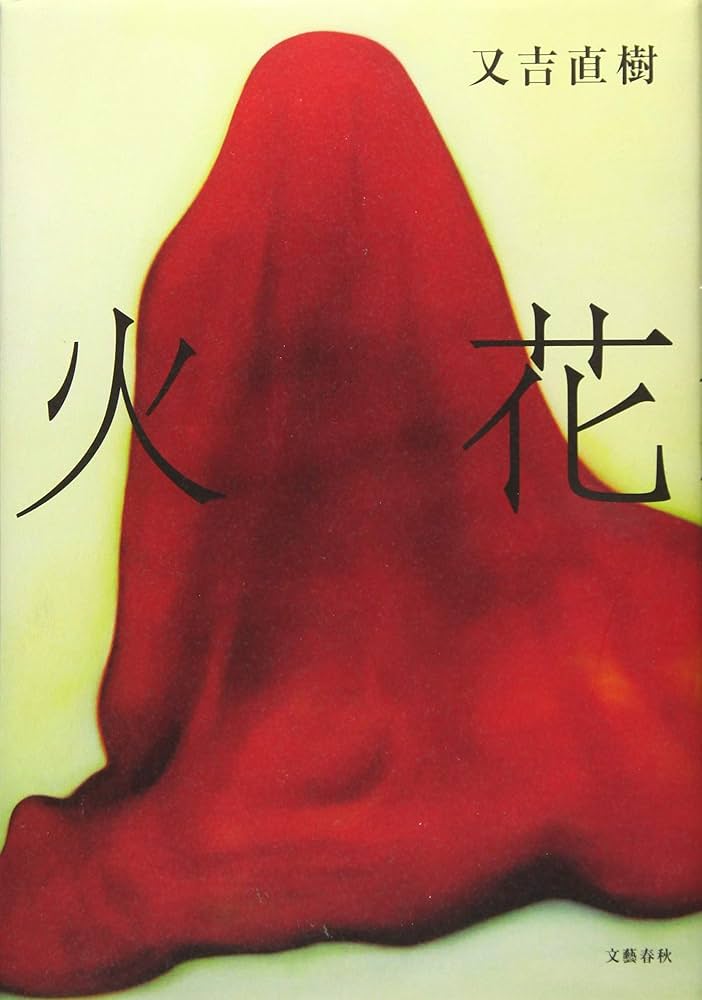
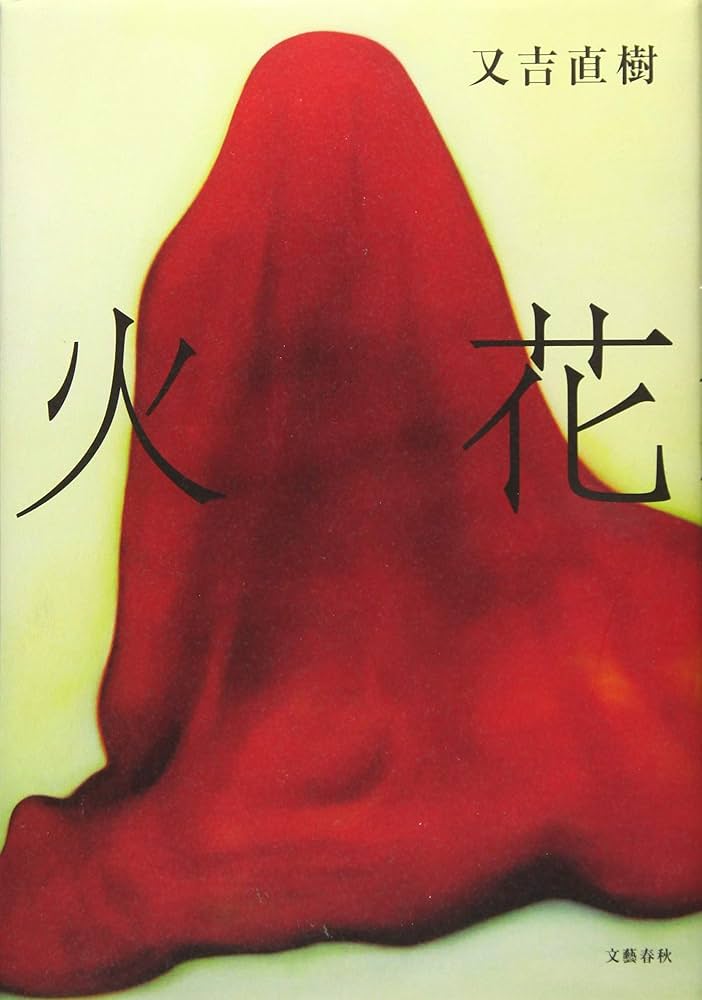
お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹が執筆し、2015年に第153回芥川賞を受賞して大きな話題となった作品です。売れない芸人・徳永が、天才肌の先輩芸人・神谷と出会い、彼の才能に惹かれながらも、お笑いの世界で生きることの厳しさや葛藤を経験する姿を描いています。
夢を追いかける若者の青春物語でありながら、才能とは何か、人間とは何かという普遍的な問いを投げかけます。芸人である作者ならではのリアルな描写と、文学的な表現力が融合した一冊です。



夢を追いかけることのキラキラした部分だけじゃなくて、厳しさや切なさも描かれていて胸が熱くなるよ。ラストシーンは本当に泣ける…。
7位: 『雪国』 川端康成
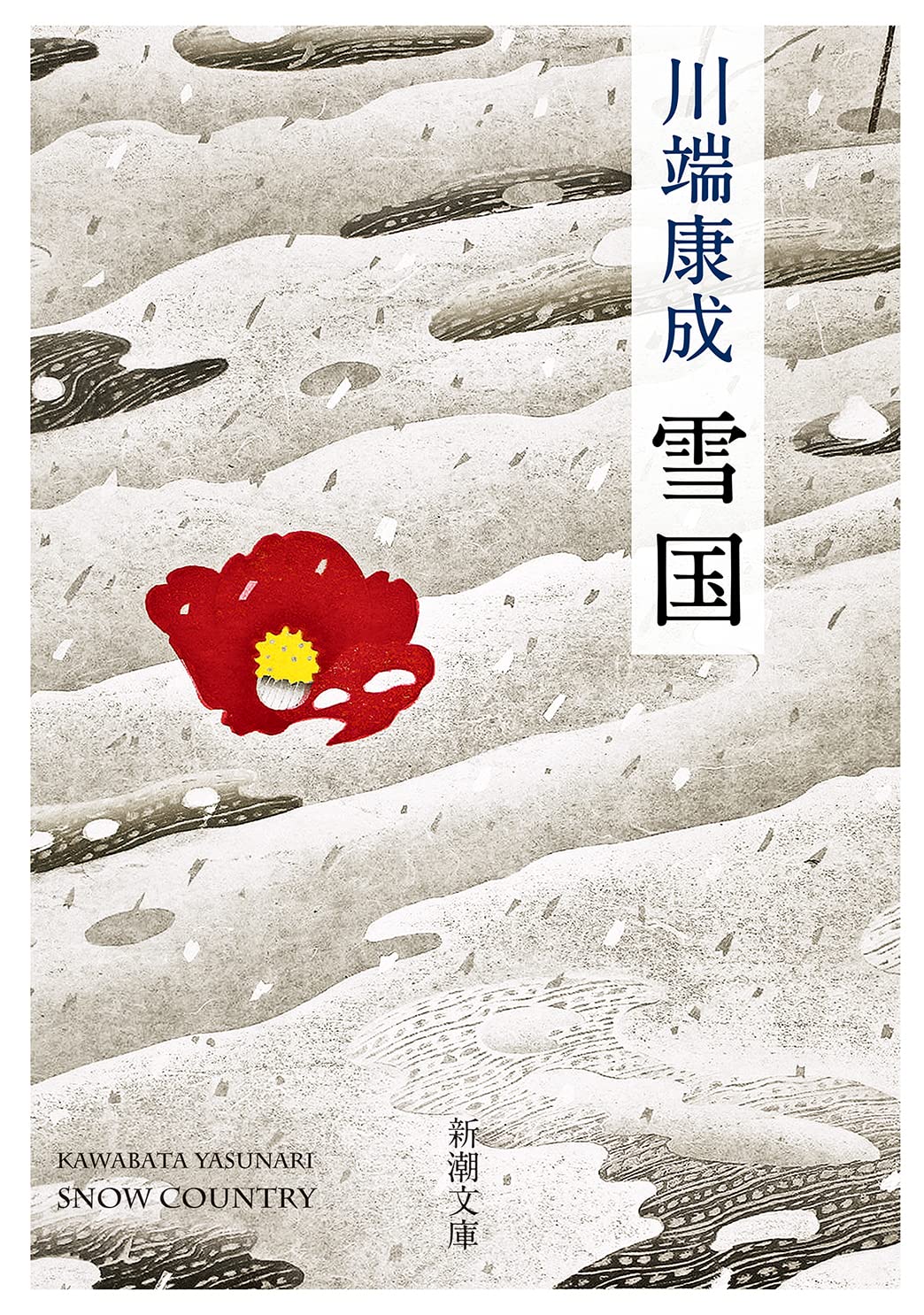
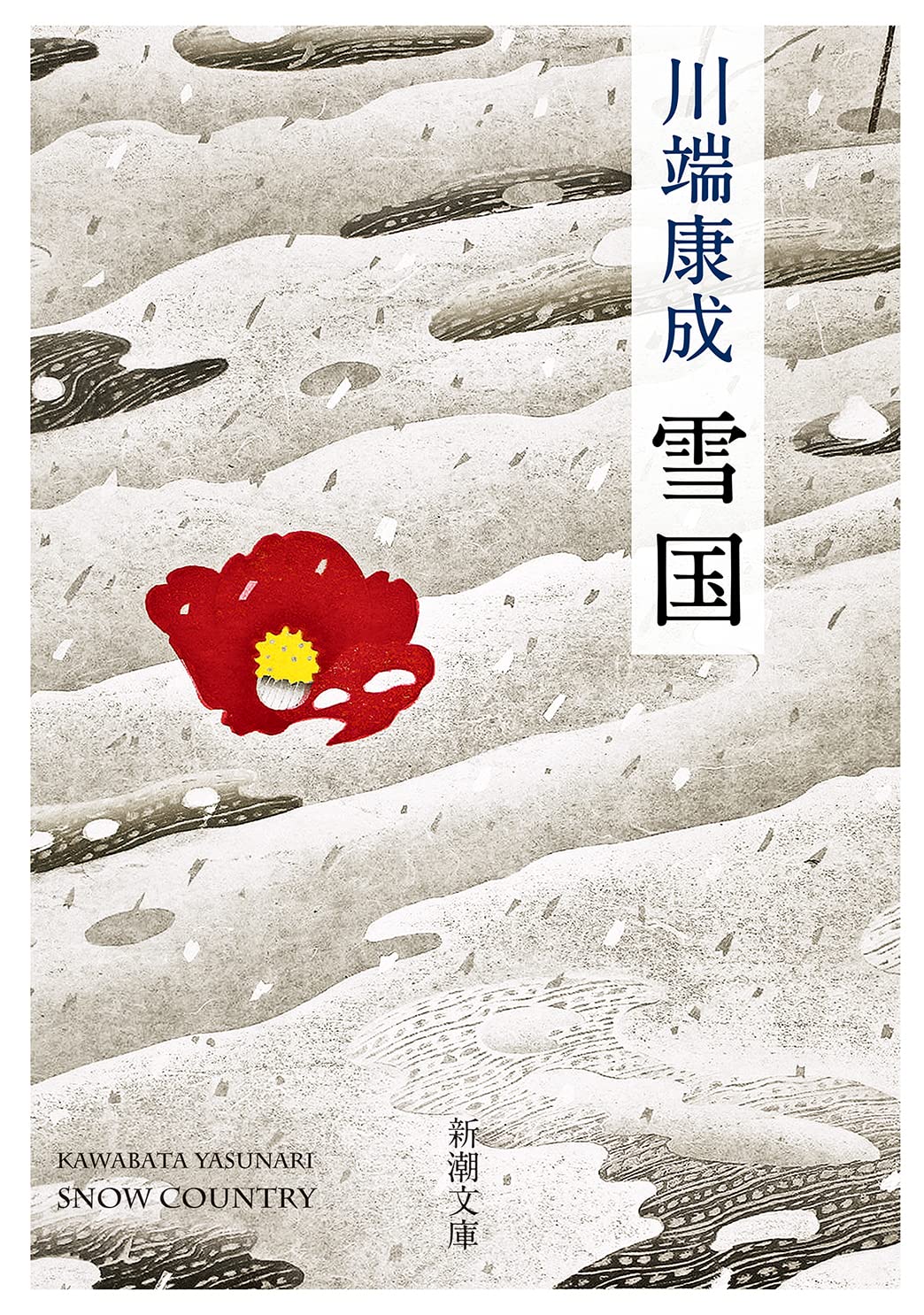
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」というあまりにも有名な一文で始まる、川端康成の代表作です。日本人初のノーベル文学賞受賞のきっかけとなった作品の一つでもあります。
雪深い温泉町を舞台に、妻子ある男・島村と、芸者・駒子、そして美しい少女・葉子の儚くも美しい人間模様が描かれています。日本の伝統的な美意識や、登場人物たちの繊細な心の機微を、簡潔で詩的な文章で表現した日本文学の傑作です。



文章が本当に美しいんだ。情景が目に浮かぶようで、まるで一本の映画を観ているような気分になるよ。
8位: 『推し、燃ゆ』 宇佐見りん
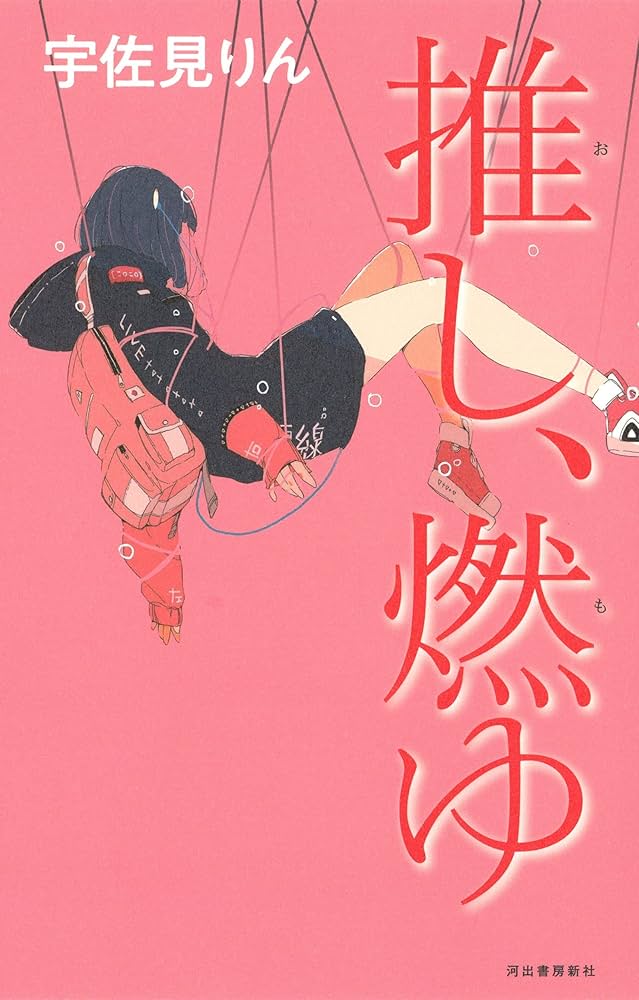
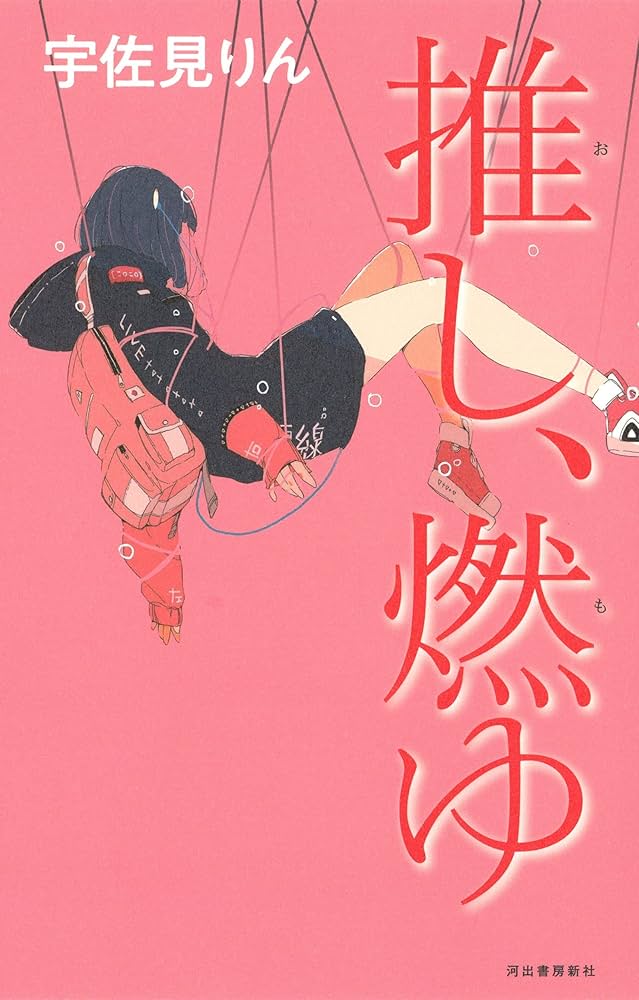
2020年下半期の第164回芥川賞を受賞し、2021年に発表された、宇佐見りんの衝撃作です。 主人公は、男性アイドルグループのメンバーである「推し」を応援することに全てを捧げる女子高生・あかり。 ある日、その推しがファンを殴って炎上したことから、彼女の日常は崩壊していきます。
推しを「解釈」することに心血を注ぎ、それが自分の「背骨」になっているあかりの姿を通して、現代の若者が抱える生きづらさや、SNS社会の危うさを鋭く描き出しています。 まさに現代を象徴する一冊といえるでしょう。



これはもう、他人事じゃないって感じる人が多いんじゃないかな。「推し」がいる人には特に刺さると思う。心がえぐられるような感覚だよ。
9位: 『金閣寺』 三島由紀夫
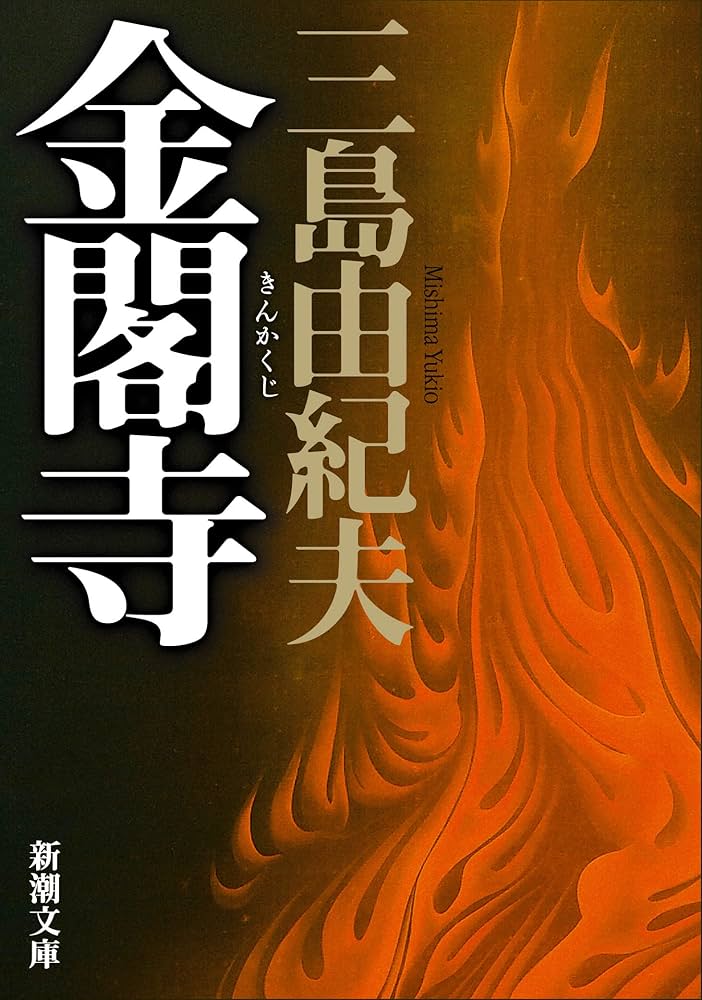
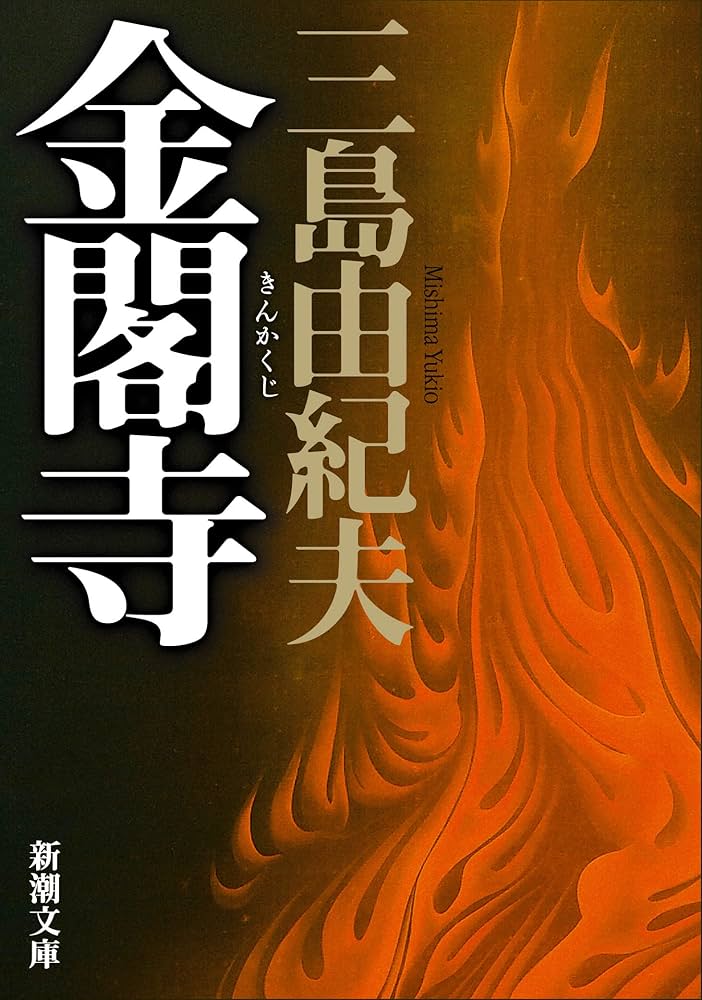
1950年に実際に起きた金閣寺放火事件を題材にした、三島由紀夫の代表作です。 主人公は、吃音と劣等感に悩む若い学僧・溝口。 彼は、父から聞かされた金閣の美しさに魅了され、その美の観念に支配されていきます。
現実の金閣と、自らの内なる金閣のイメージとの乖離に苦しむ溝口は、やがてその美を独占するために放火という狂気的な行動に至ります。 美とは何か、そして美が人間に与える影響とは何かを問いかける、重厚な物語です。



美しすぎるものって、時として人を狂わせるのかもしれないね。溝口の屈折した感情が、読んでいて苦しくなるほど伝わってくるよ。
10位: 『乳と卵』 川上未映子
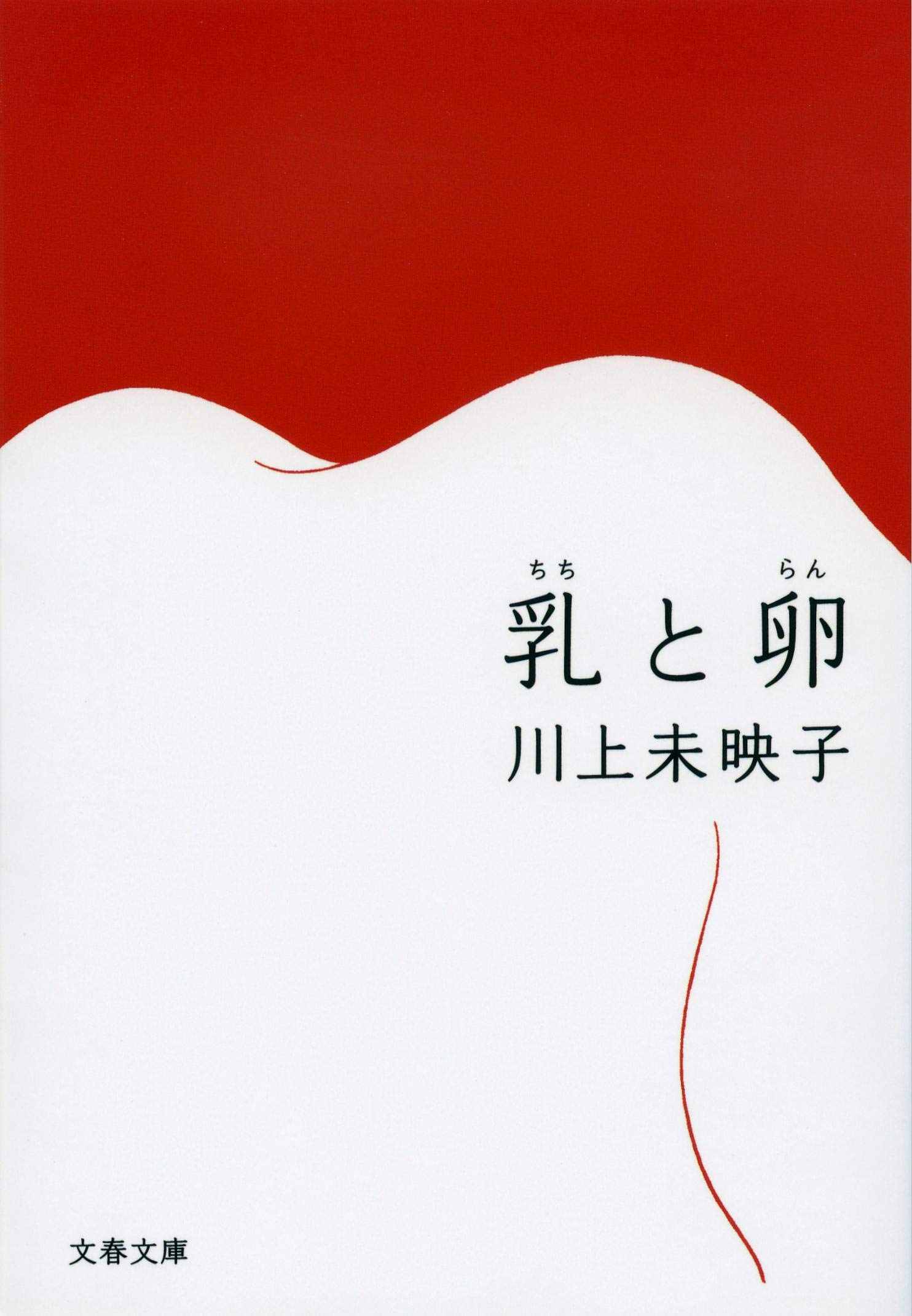
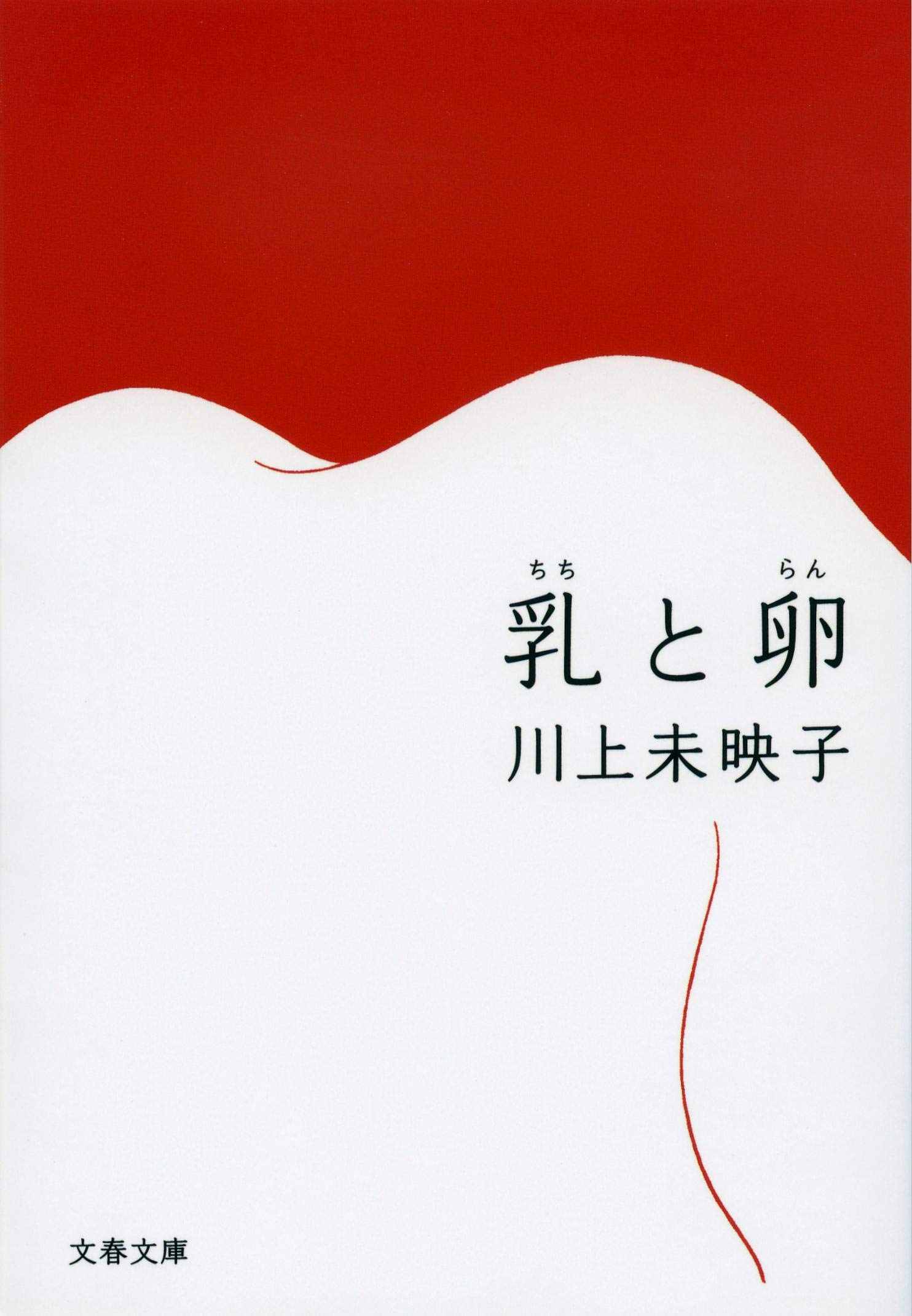
2008年に第138回芥川賞を受賞した作品で、川上未映子の作家としての地位を確立した一冊です。大阪弁の軽快な語り口で、女性の身体や性、そして生命をめぐるテーマを赤裸々に描いています。
物語は、豊胸手術を望む姉・巻子と、思春期で口をきかなくなったその娘・緑子、そして主人公である「私」の三人の女性を中心に展開します。女性が抱える身体的な悩みや、母と娘の関係性をリアルに描き出し、多くの女性から共感を得ました。



女性なら誰でも共感できる部分があるんじゃないかな。シリアスなテーマだけど、大阪弁の語り口で不思議と読みやすいんだ。
11位: 『李陵・山月記』 中島敦
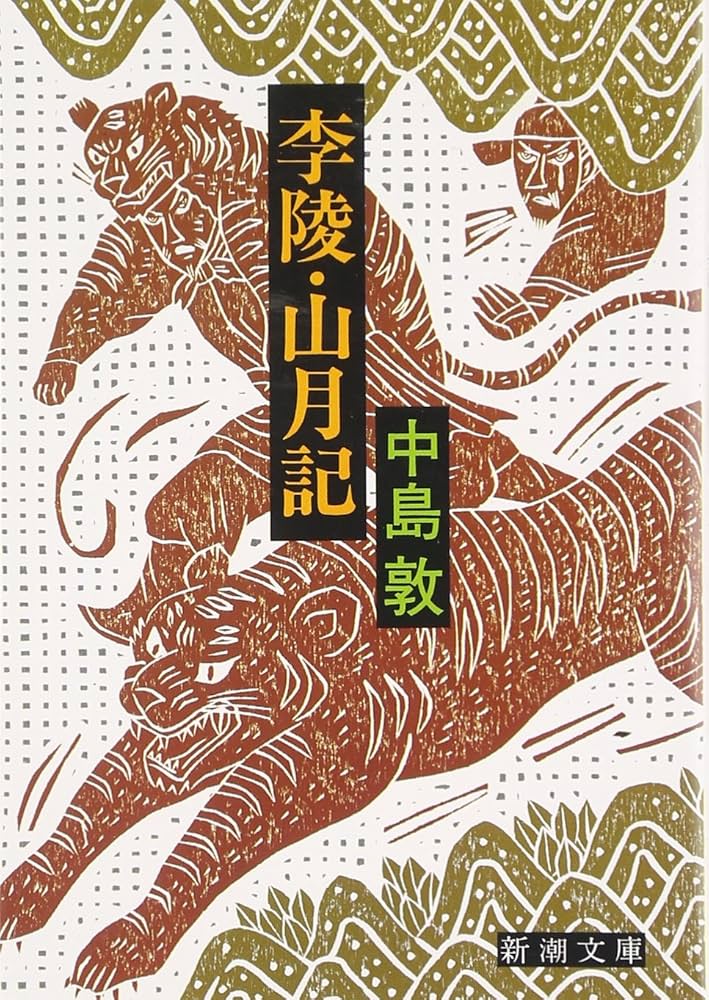
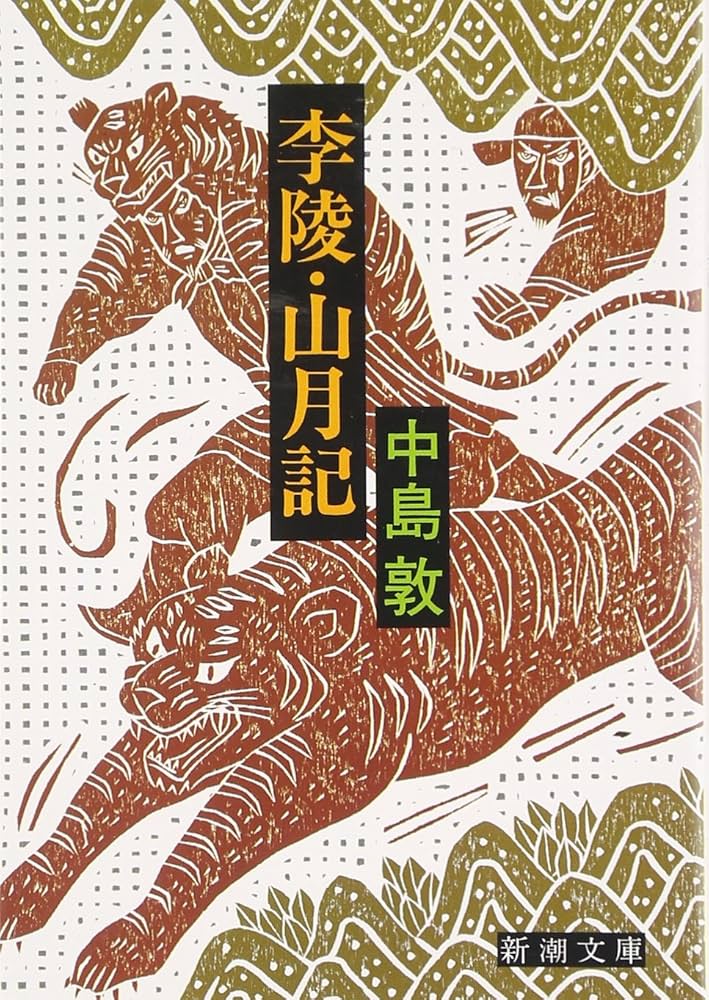
中国の古典を題材にした、中島敦の代表的な短編集です。『山月記』は、自尊心の高さゆえに虎になってしまった男・李徴の悲哀を描き、『李陵』では、漢の将軍・李陵と、彼の友である司馬遷の数奇な運命を描いています。
格調高い文章で、人間の尊厳や才能、そして運命の残酷さといった普遍的なテーマを問いかけます。特に『山月記』の「臆病な自尊心と、尊大な羞恥心」という一節は、多くの人の心に突き刺さる名言として知られています。



虎になってしまった李徴の叫びが、自分のことのように感じられて切なくなるよ。才能とプライドについて深く考えさせられる作品だね。
12位: 『銀河鉄道の夜』 宮沢賢治
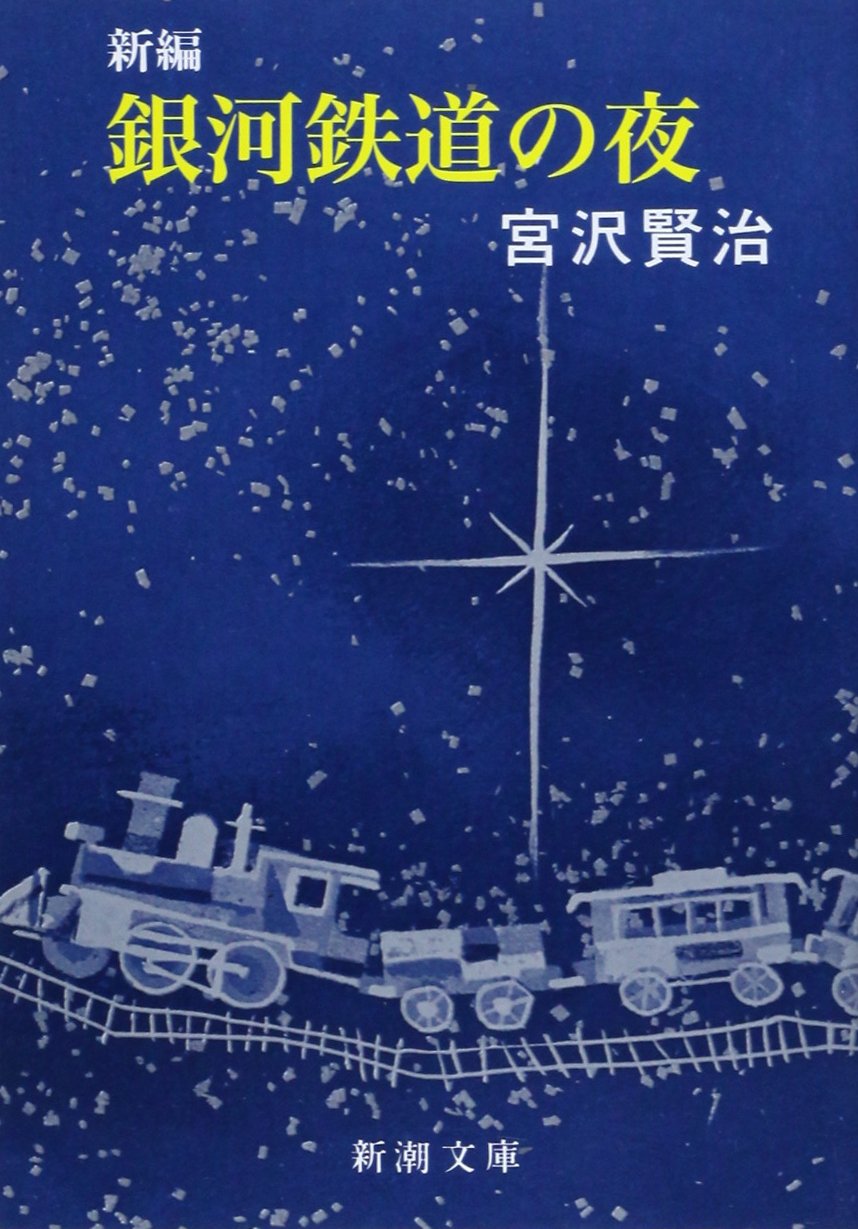
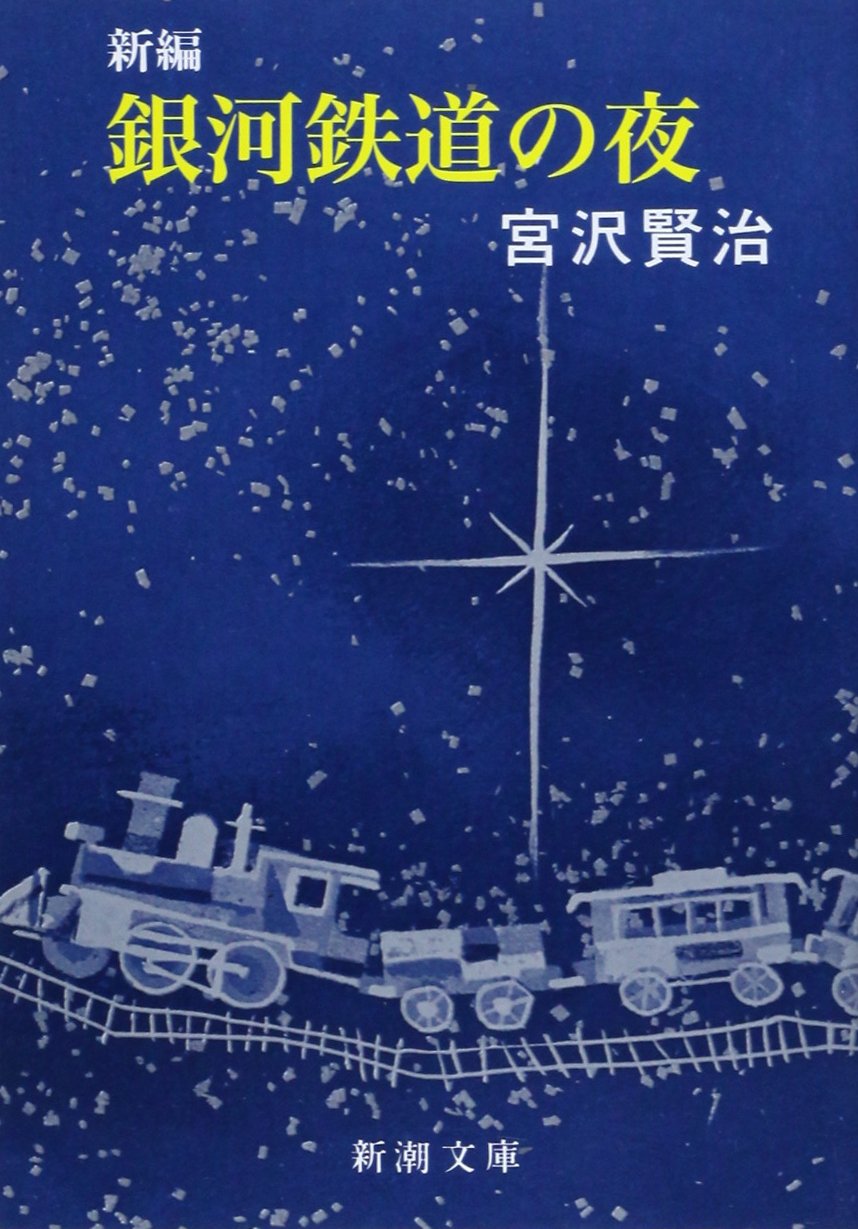
宮沢賢治の代表的な童話であり、幻想的な世界観と深いテーマ性から、大人向けの純文学としても高く評価されています。孤独な少年ジョバンニが、親友カムパネルラと共に銀河鉄道に乗り、宇宙を旅する物語です。
美しい星々の世界を旅する中で、二人は様々な人々と出会い、本当の幸せとは何かを学んでいきます。生と死、自己犠牲、そして他者への愛といったテーマが、美しい情景描写と共に描かれた、感動的な作品です。



読むたびに新しい発見がある、不思議な物語だよ。キラキラした美しい世界観の中に、少し切ない真実が隠されているんだ。
13位: 『博士の愛した数式』 小川洋子
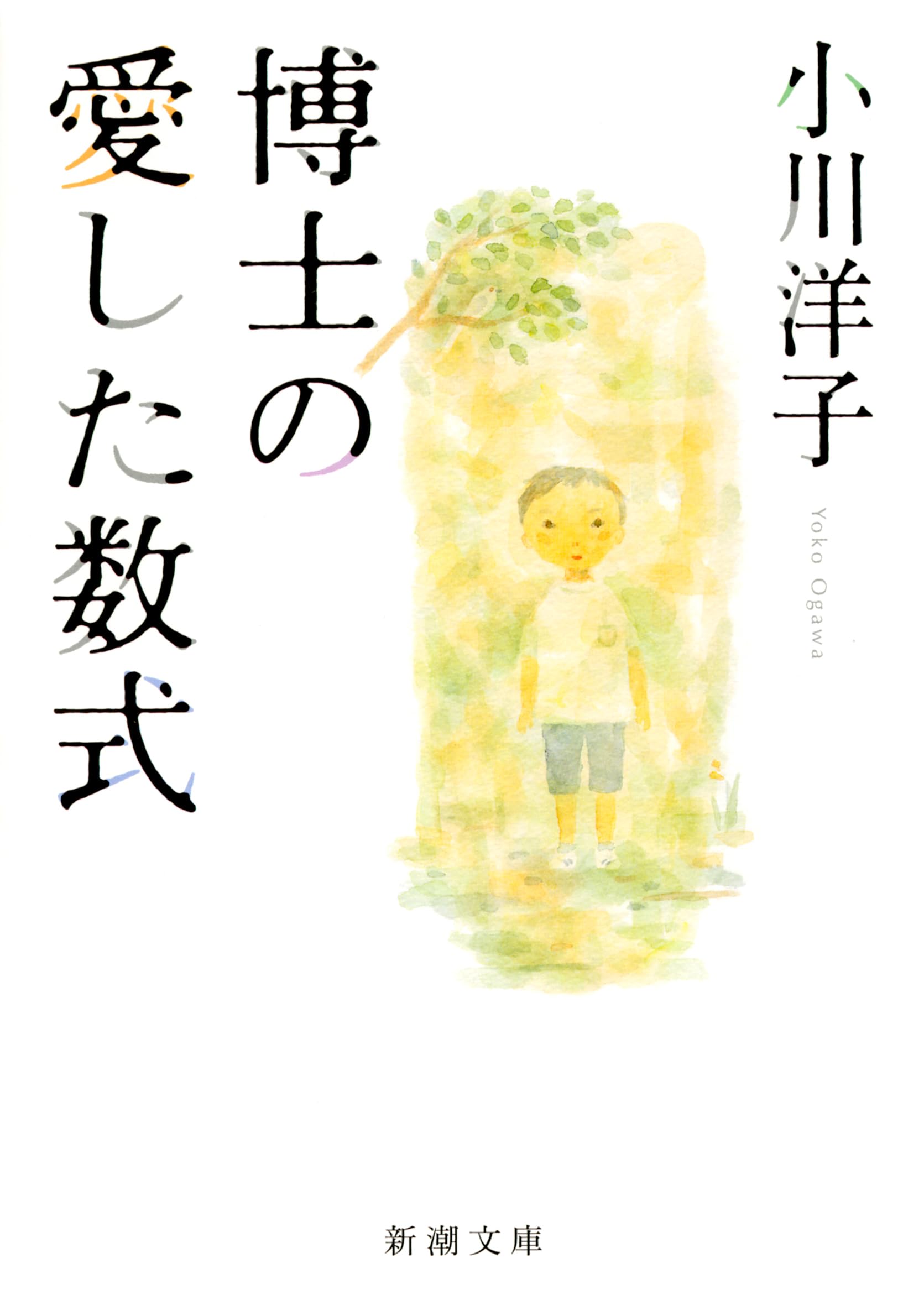
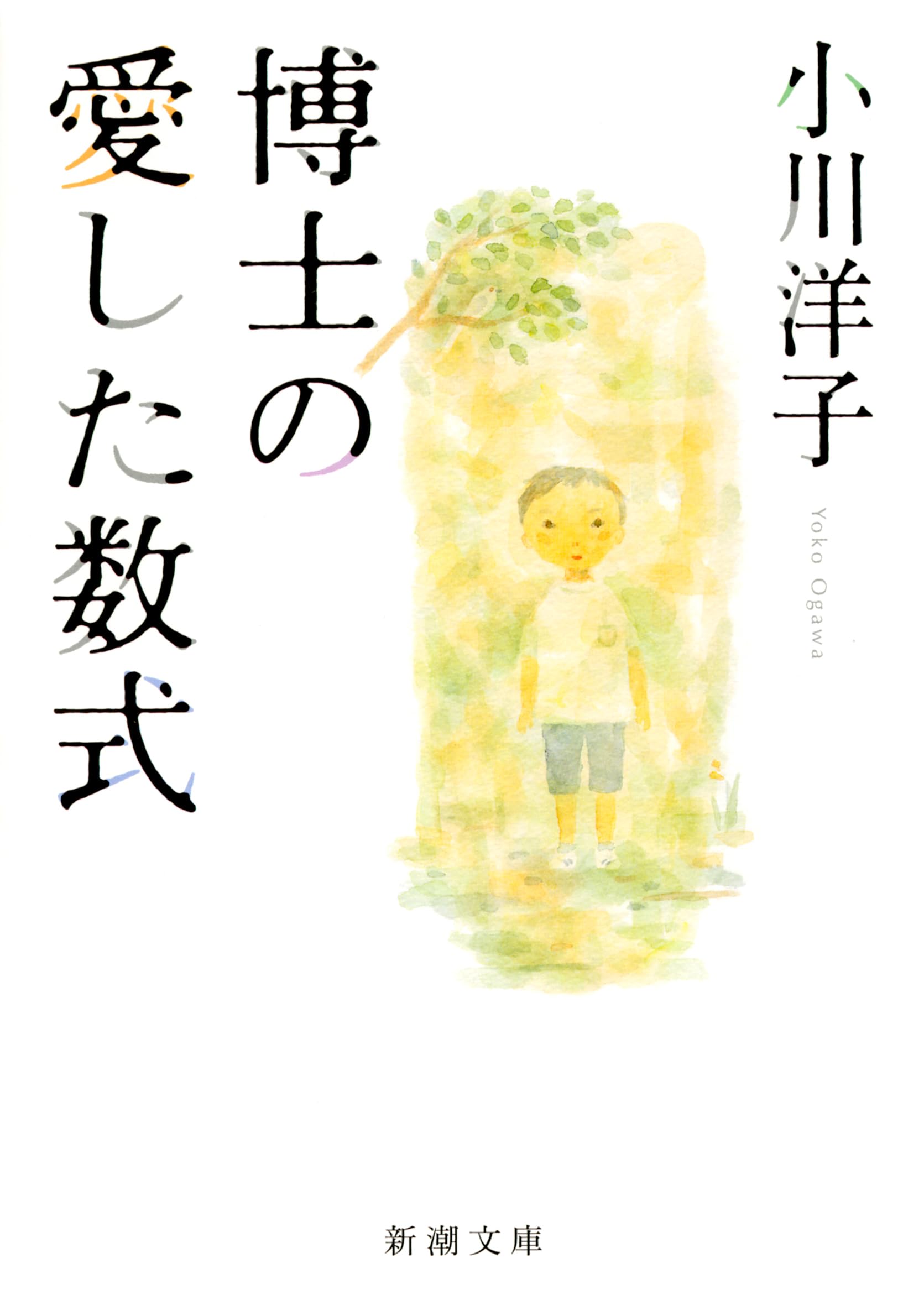
2004年に第1回本屋大賞を受賞した、小川洋子のベストセラー小説です。記憶が80分しか持たない天才数学者「博士」と、彼の世話をすることになった家政婦「私」、そしてその息子「ルート」の心温まる交流を描いています。
数字の美しさや、記憶を失っても変わらない人間の愛情をテーマにした物語です。博士が語る数式の世界は、数学が苦手な人でも楽しめるほど魅力的で、読後は温かい気持ちに包まれるでしょう。



すごく優しくて温かい物語だよ。数字ってこんなに美しいんだって、新しい世界を教えてもらった気分になるな。
14位: 『堕落論』 坂口安吾
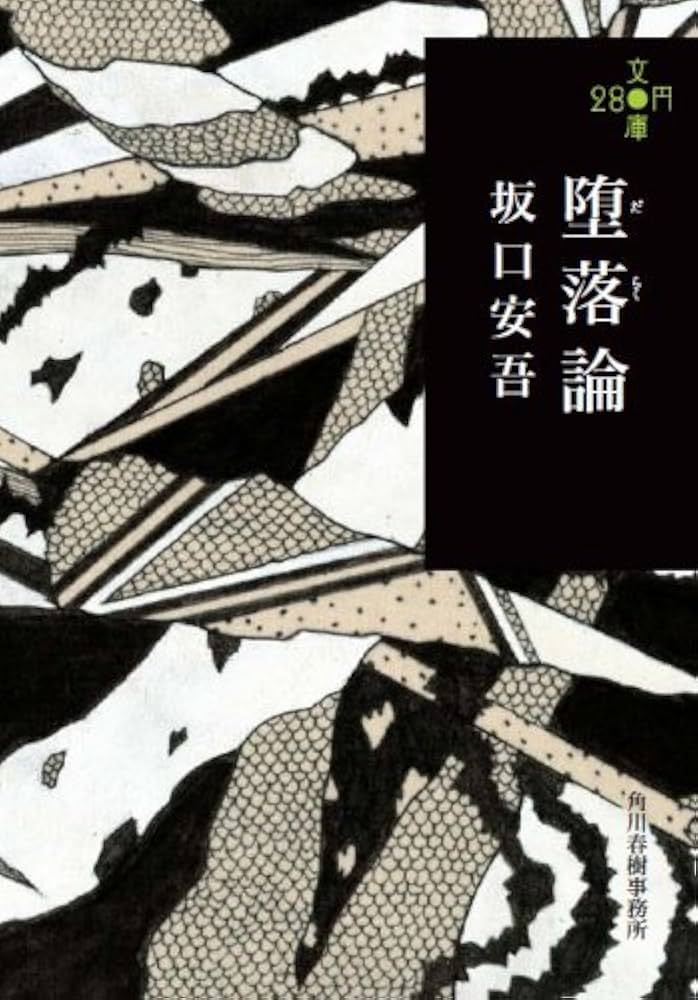
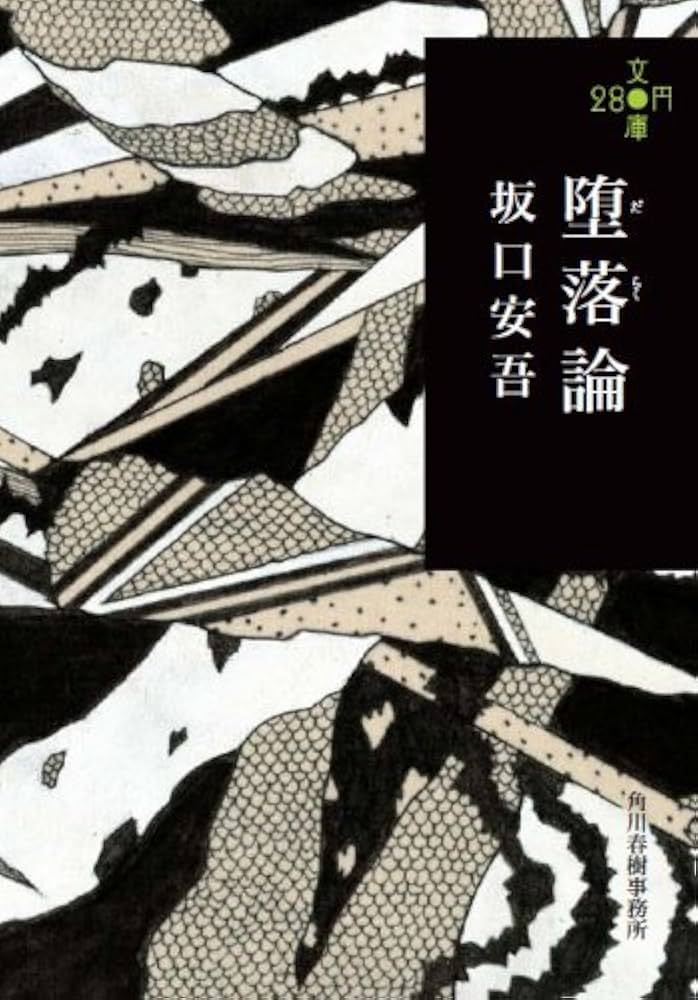
第二次世界大戦直後の1946年に発表された、坂口安吾の代表的な評論・随筆です。 敗戦によって価値観が大きく揺らいだ日本社会において、「生きよ、堕ちよ」と説き、人々に衝撃を与えました。
坂口は、戦争中の美しい道徳や倫理観は虚像であり、人間は本来堕落する存在だと主張します。 そして、その堕落の中から自分自身の真実を見つけ出すことこそが、本当の救いであると説きました。 既存の価値観を打ち破り、人間の本質を鋭く見つめた力強い言葉は、現代を生きる私たちにも多くの示唆を与えてくれます。



常識や綺麗事を全部ひっくり返されるような衝撃があるよ。でも、だからこそ、すごく力をもらえる言葉なんだ。
15位: 『沈黙』 遠藤周作
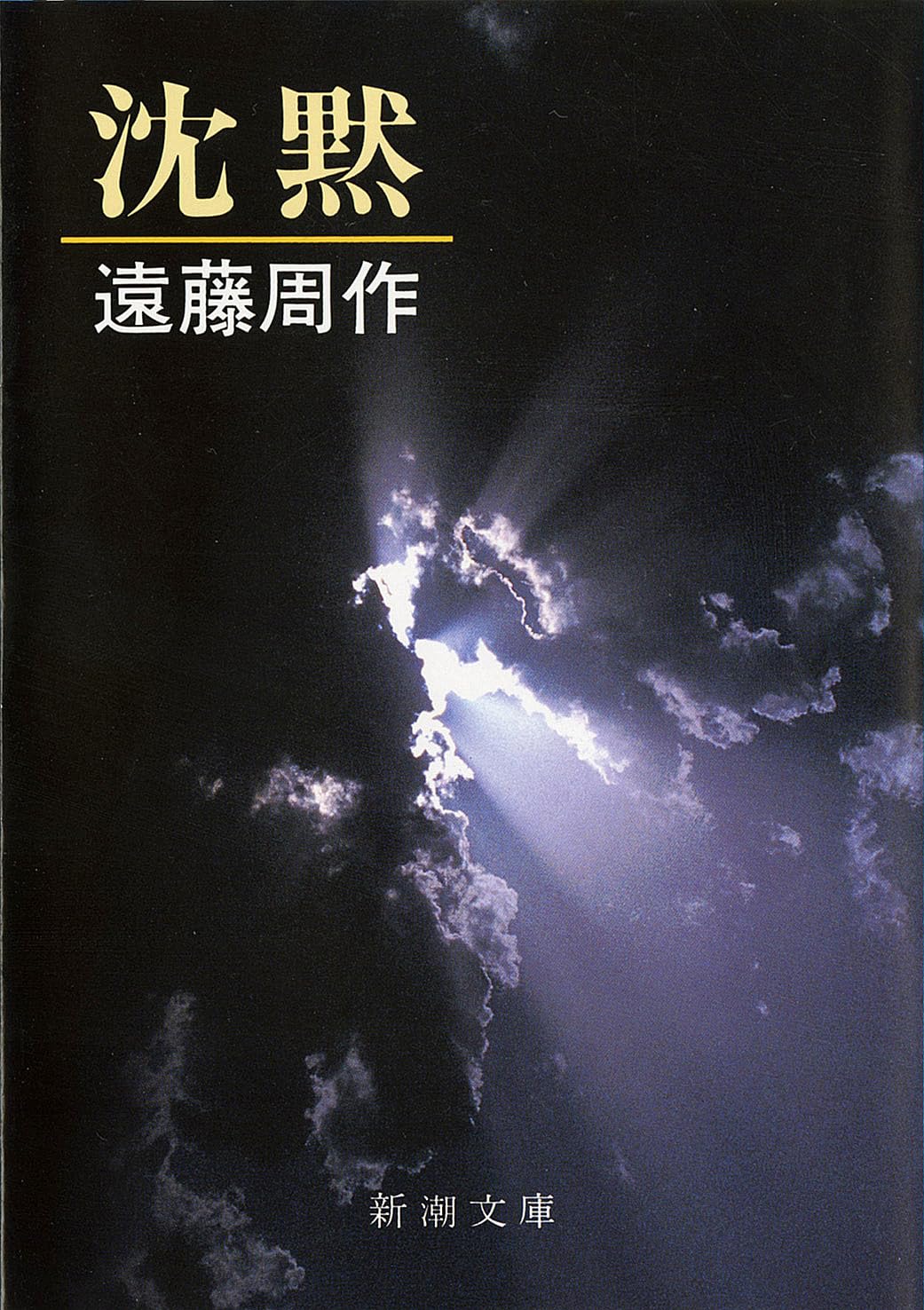
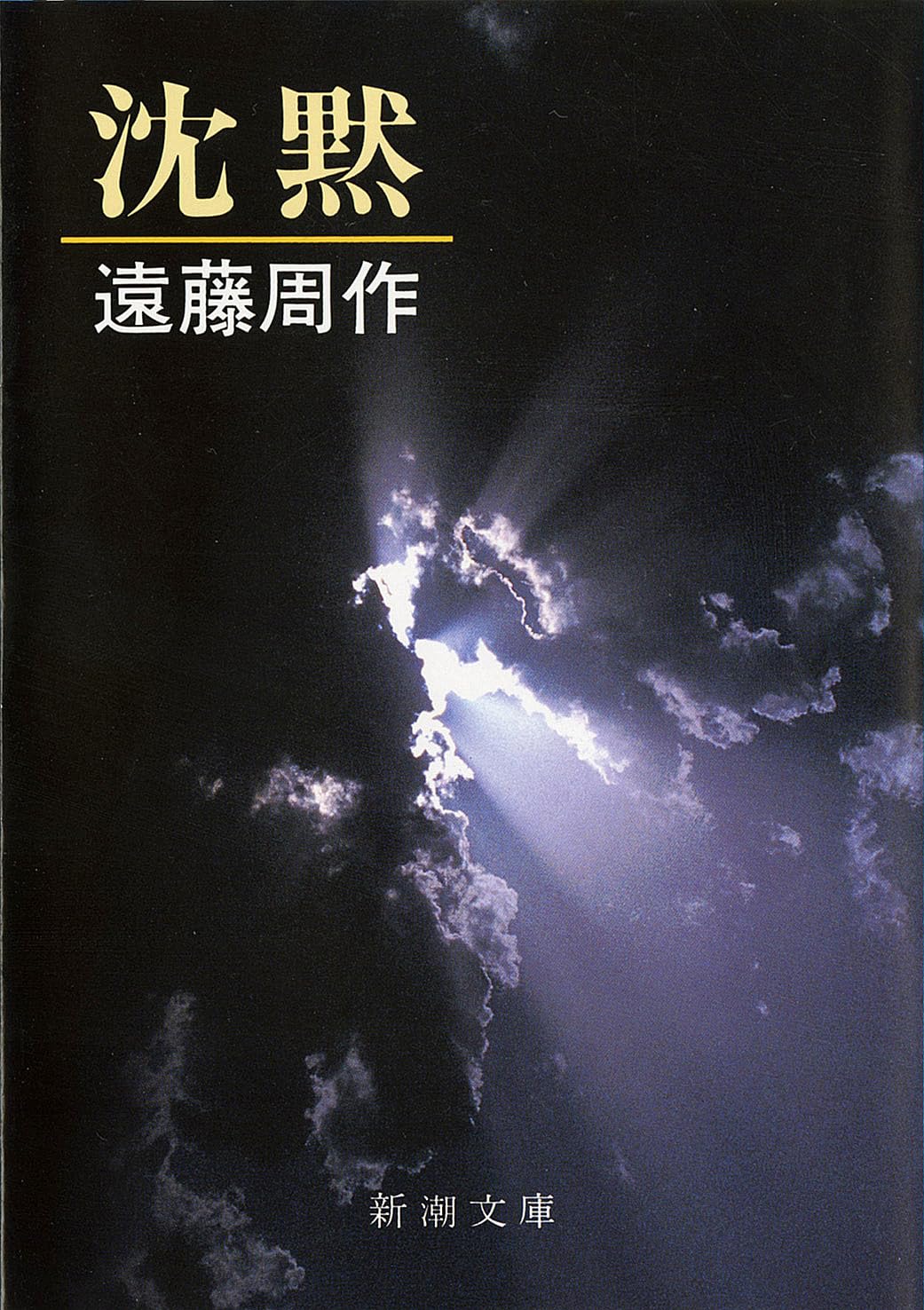
江戸時代初期のキリシタン弾圧を背景に、神と信仰の本質を問うた遠藤周作の代表作です。 日本に潜入したポルトガル人司祭ロドリゴが、信者たちが受ける残忍な拷問を目の当たりにし、神が「沈黙」し続けることに苦悩する姿を描いています。
信者を救うために棄教を迫られるロドリゴの葛藤を通して、西洋的なキリスト教と日本の精神風土との違いや、弱者に寄り添う神のあり方を問いかけます。 重厚なテーマでありながら、物語としての吸引力が非常に高く、世界中で翻訳されている名作です。



神様はなぜ助けてくれないのか、という問いが胸に突き刺さるよ。信仰について、そして人間の弱さについて、深く考えさせられる物語だね。
16位: 『キッチン』 吉本ばなな
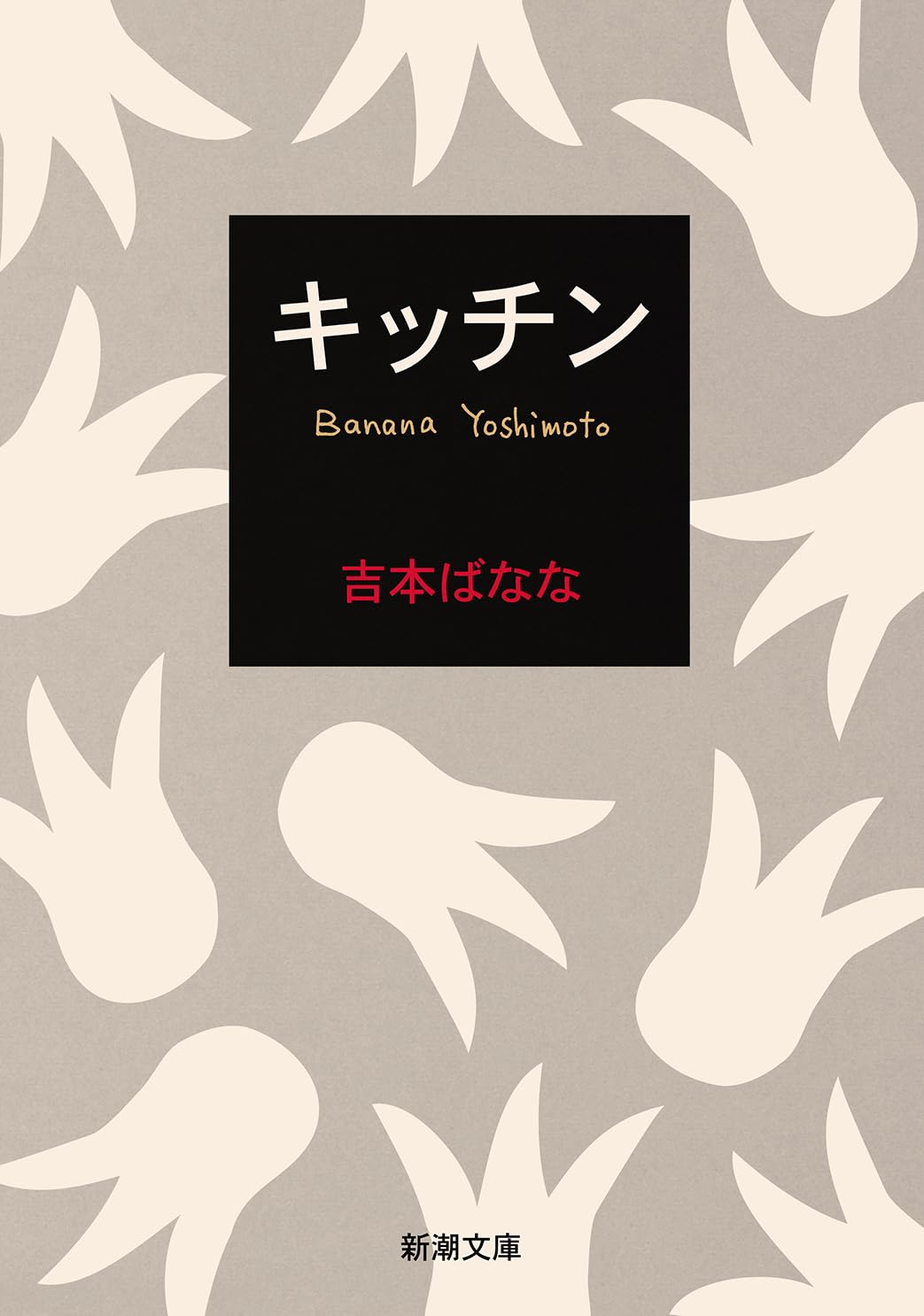
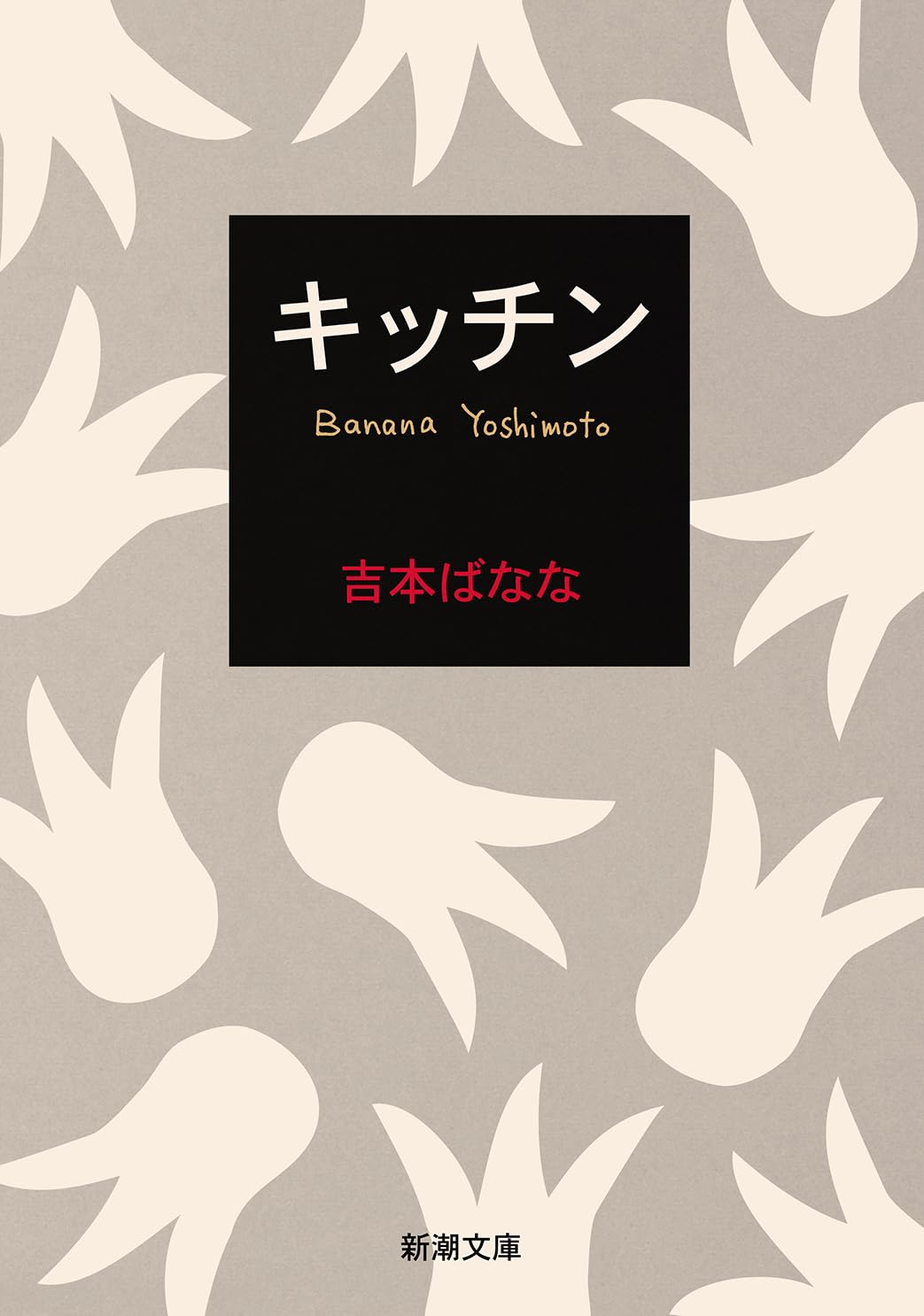
1988年に発表され、社会現象を巻き起こした吉本ばななのデビュー作です。 唯一の肉親であった祖母を亡くし、天涯孤独になった主人公・みかげが、友人である雄一とその母親(実は父親)えり子の家に居候することから物語は始まります。
みかげが心の拠り所とする「台所」を舞台に、喪失と再生、そして家族のかたちを優しく描いています。 軽やかでリズミカルな文体と、どこか切なく温かい世界観が多くの読者の心を掴みました。



辛いことがあっても、美味しいものを食べると元気が出るよね。この小説を読むと、そんな当たり前の日常がすごく愛おしく感じられるんだ。
17位: 『檸檬』 梶井基次郎
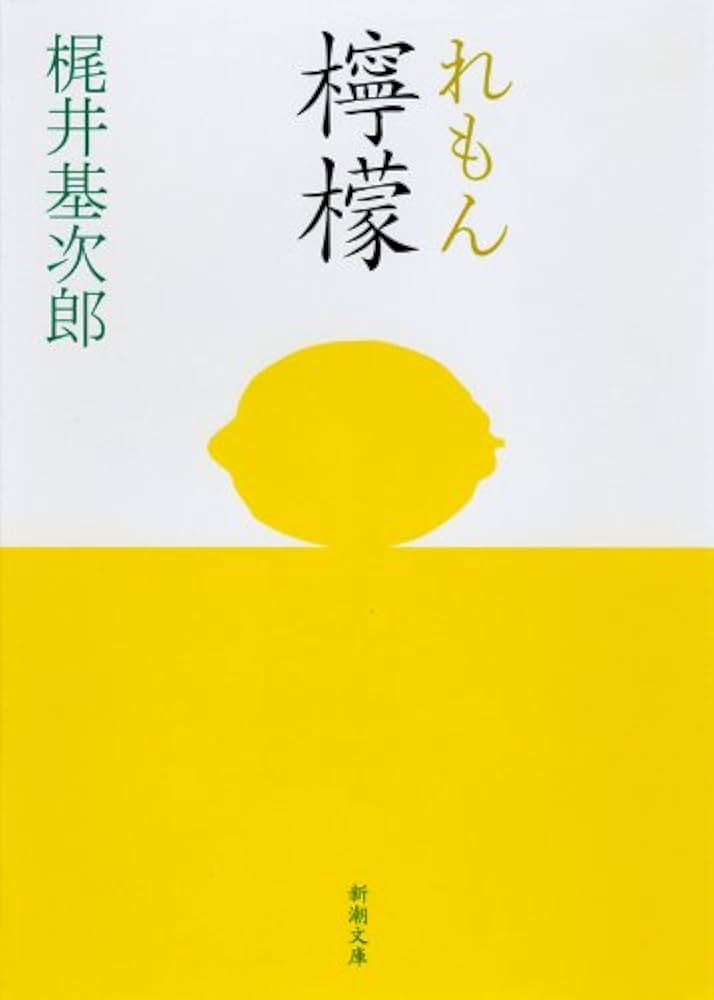
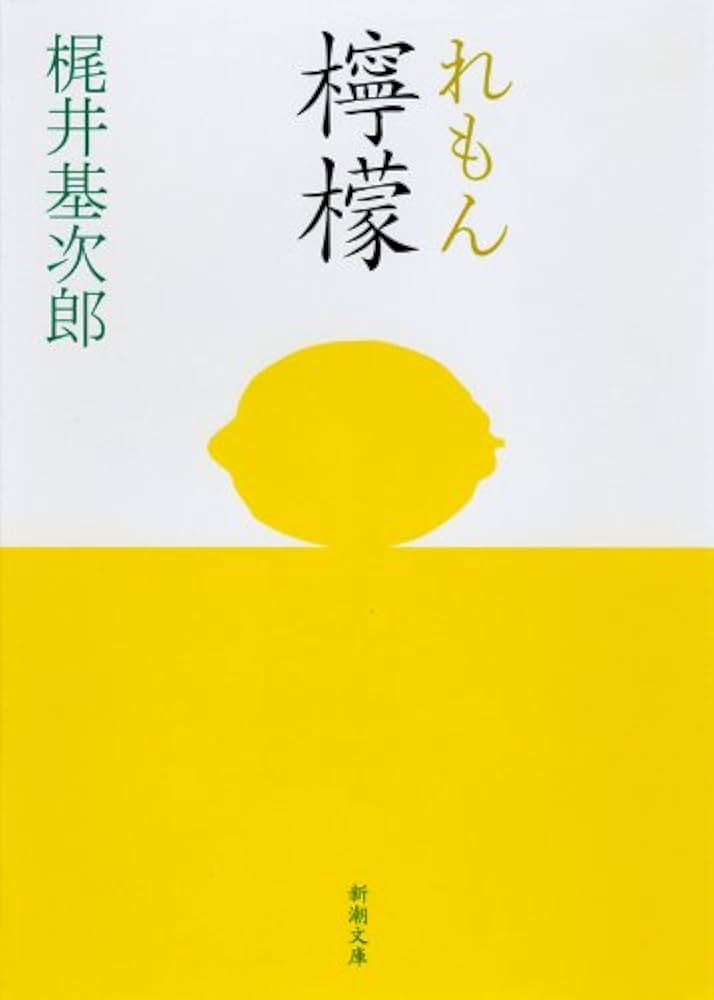
「えたいの知れない不吉な塊」に心を蝕まれた主人公「私」が、一個の檸檬(レモン)に心を救われる物語です。 肺の病や借金に悩み、憂鬱な日々を送っていた彼は、果物屋で手に入れた檸檬の鮮やかな色彩と冷たさに、束の間の幸福感を見出します。
そして、普段は重苦しく感じる書店「丸善」で、画集を積み上げた上に檸檬を置き、それを黄金の爆弾に見立てて店を出るという空想にふけります。 研ぎ澄まされた感覚と詩的な文章で、鬱屈した感情が解放される瞬間を鮮やかに描いた短編の名作です。



憂鬱な気分が、たった一個のレモンで晴れていく感覚がすごくよくわかるな。日常の中の小さな発見が、世界を違って見せてくれることってあるよね。
18位: 『蹴りたい背中』 綿矢りさ
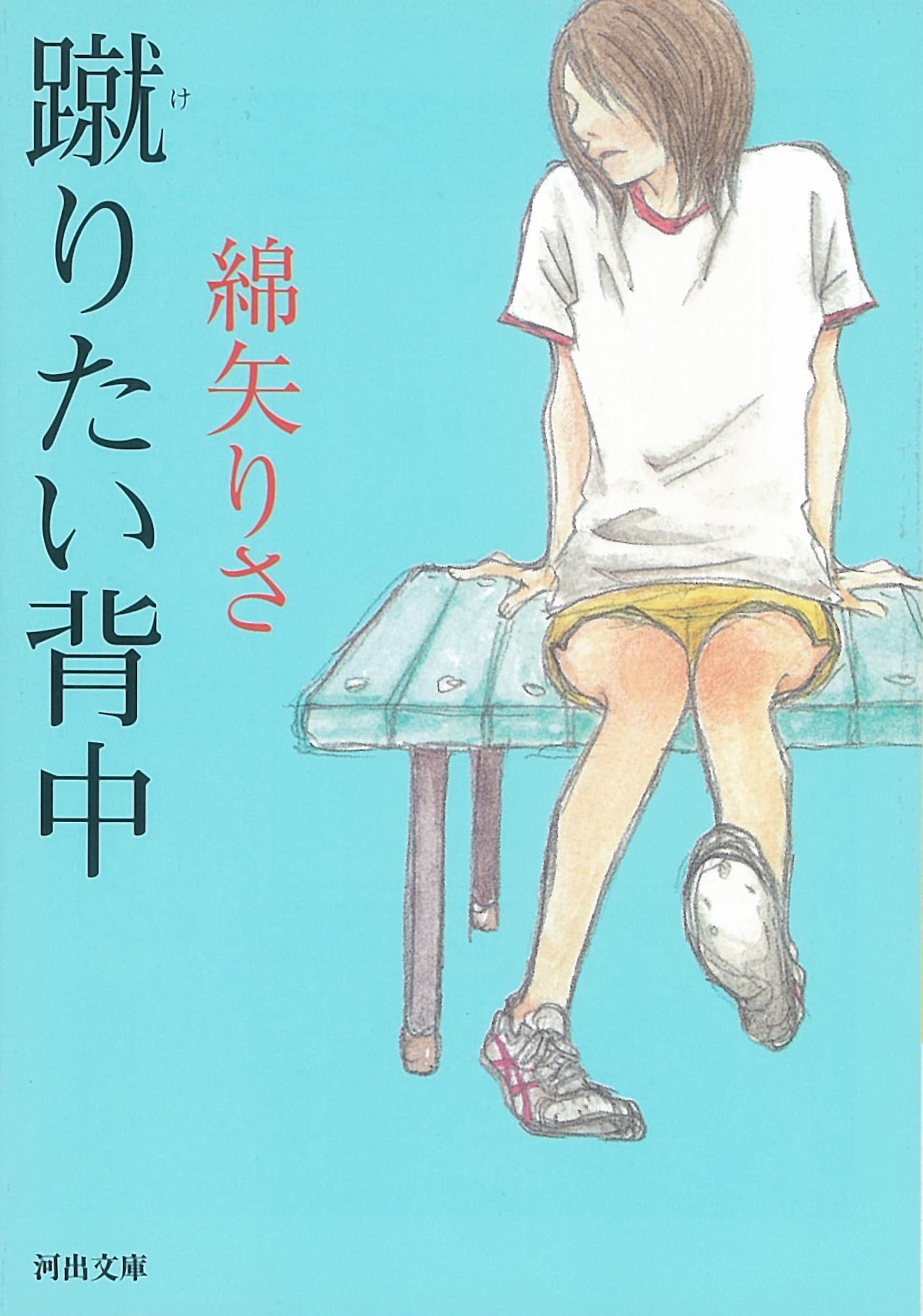
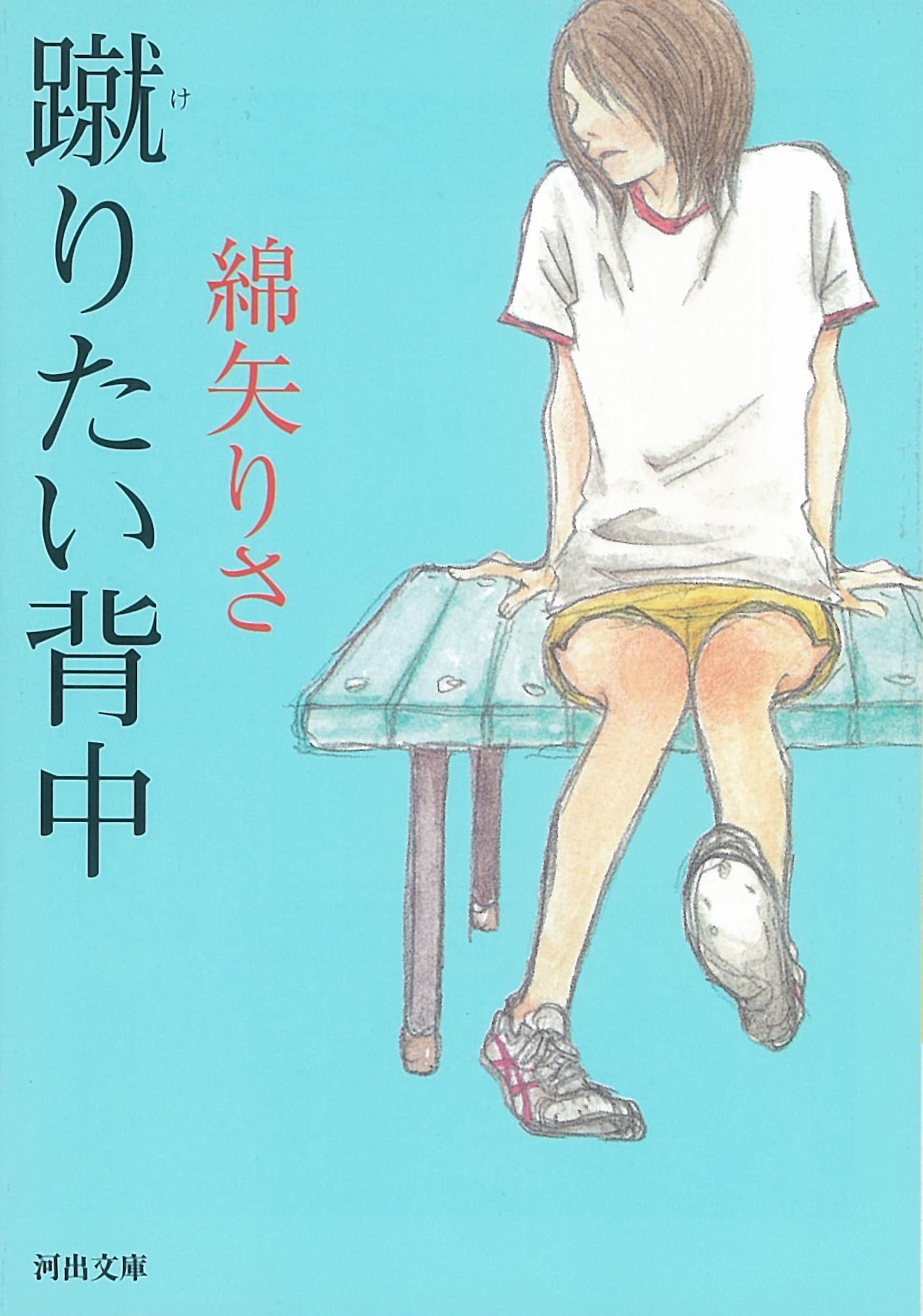
2003年に当時19歳の綿矢りさが執筆し、第130回芥川賞を最年少で受賞した作品です。高校生の主人公・ハツと、クラスで孤立している少年・にな川との奇妙な関係を描いています。
ハツは、モデルの熱狂的なファンであるにな川に興味を持ち、彼の孤独な世界に触れていきます。思春期特有の屈折した感情や、他者との距離感を繊細な感性で描き出し、大きな共感を呼びました。



高校生の頃の、あの独特の空気感を思い出すよ。誰かと繋がりたいけど、素直になれない感じがすごくリアルだよね。
19位: 『ハンチバック』 市川沙央
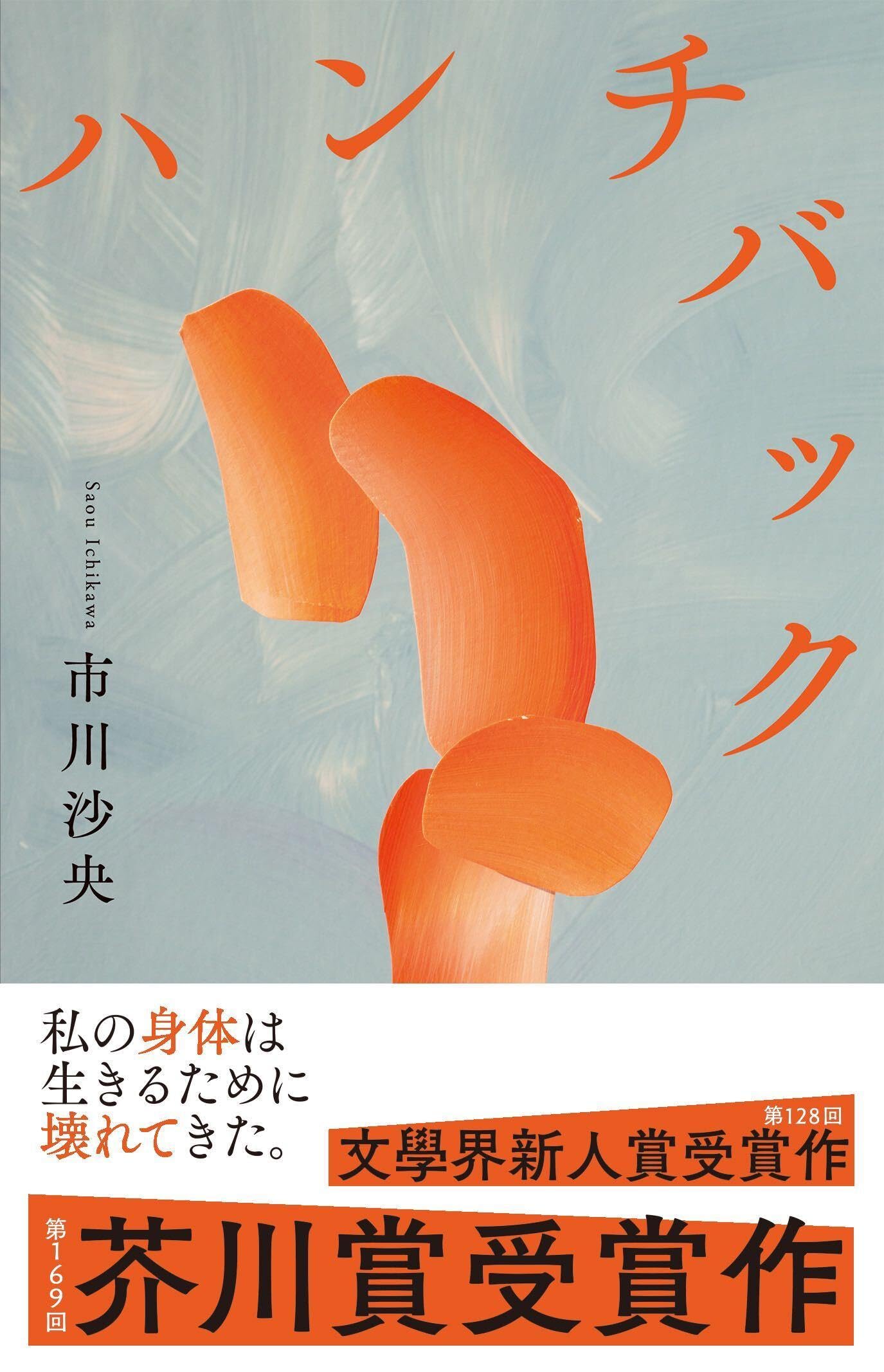
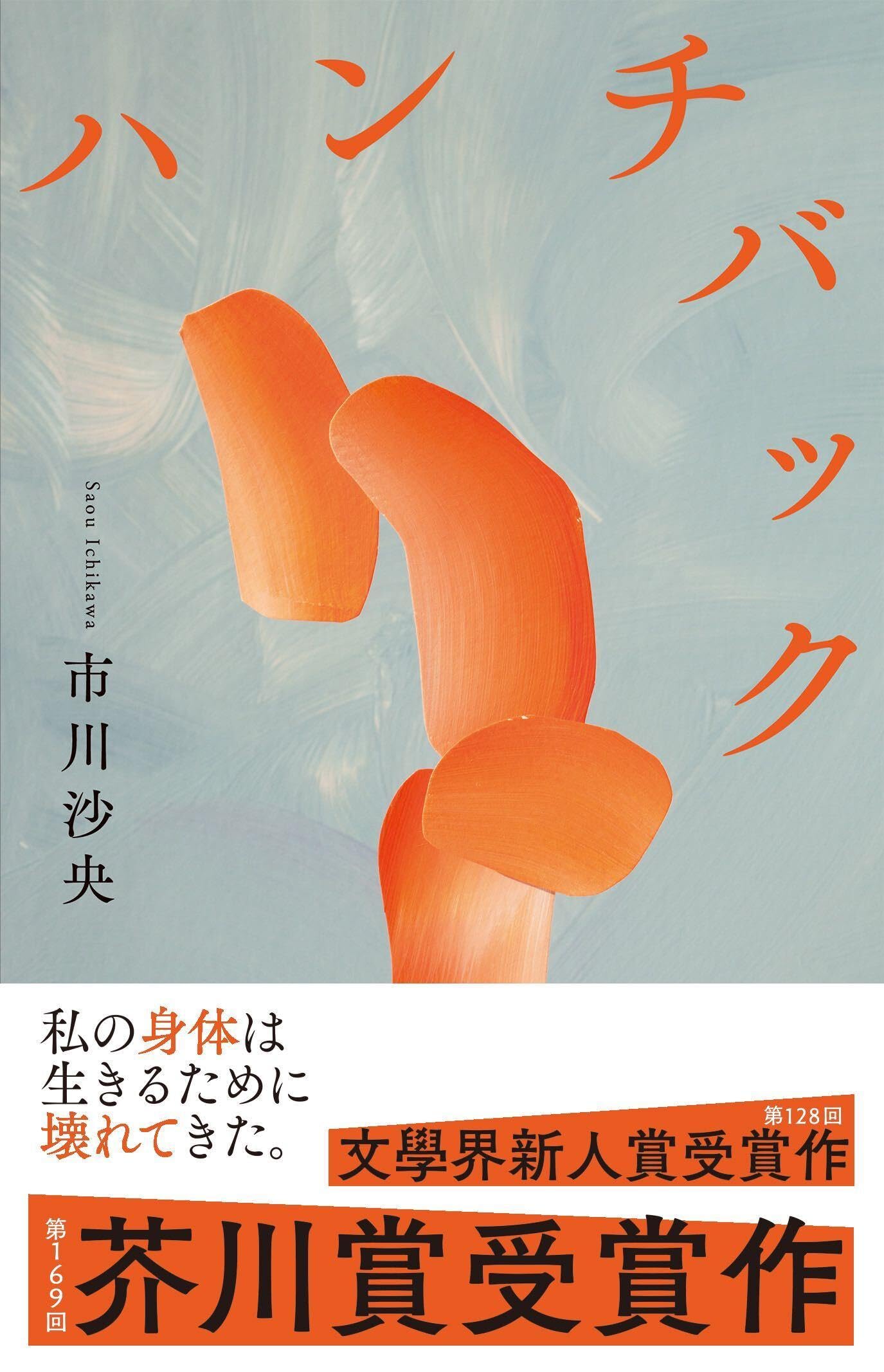
2023年に第169回芥川賞を受賞した、市川沙央のデビュー作です。重度の障害を持つ主人公・井沢釈迦が、グループホームでの生活や、SNSでの活動を通して、社会の欺瞞や健常者中心の価値観を鋭く告発します。
障害者の性や、読書文化における健常者の特権性など、これまであまり語られてこなかったテーマに正面から切り込んだ意欲作です。その衝撃的な内容と、力強い筆致が大きな話題を呼びました。



本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。
20位: 『むらさきのスカートの女』 今村夏子
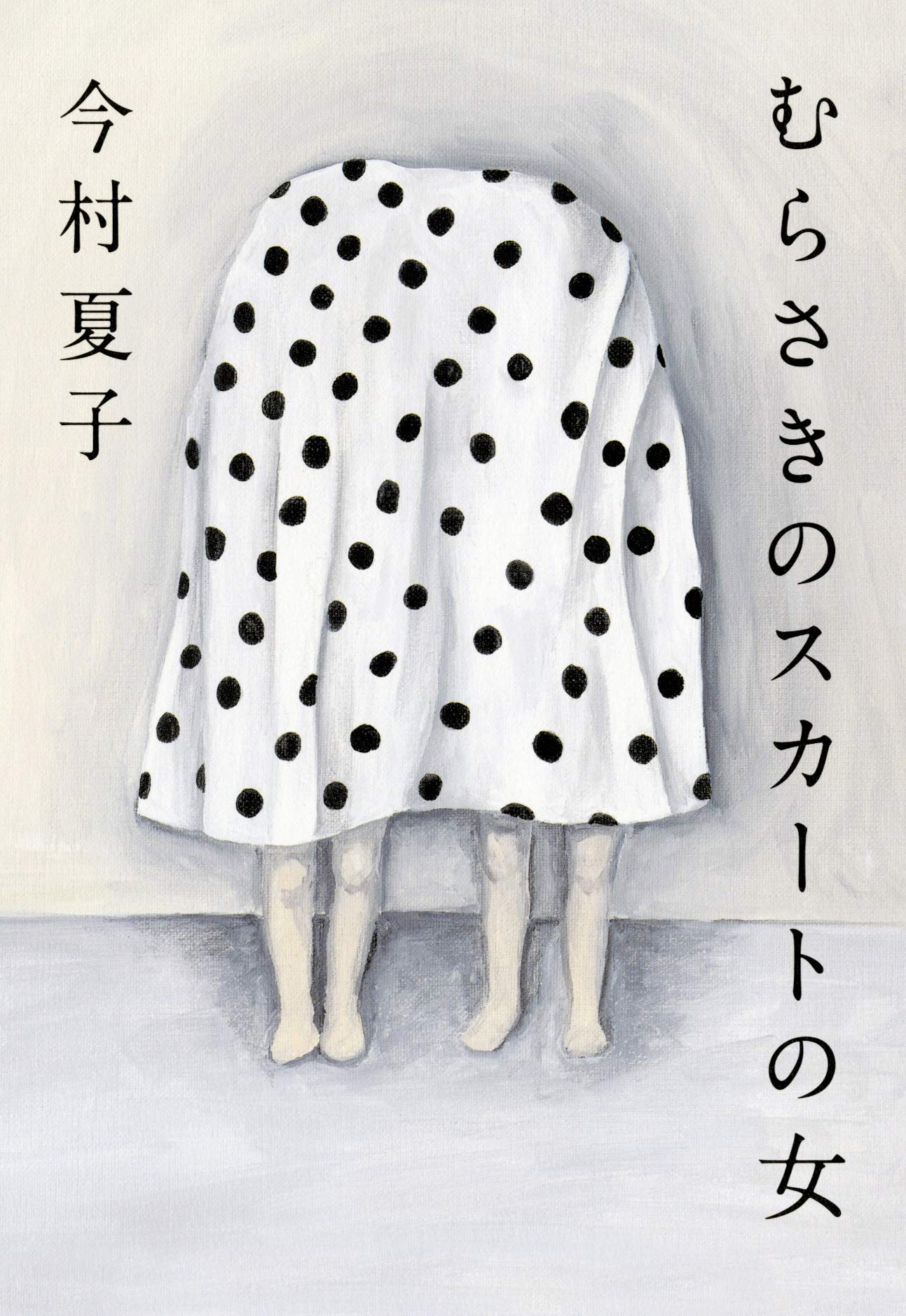
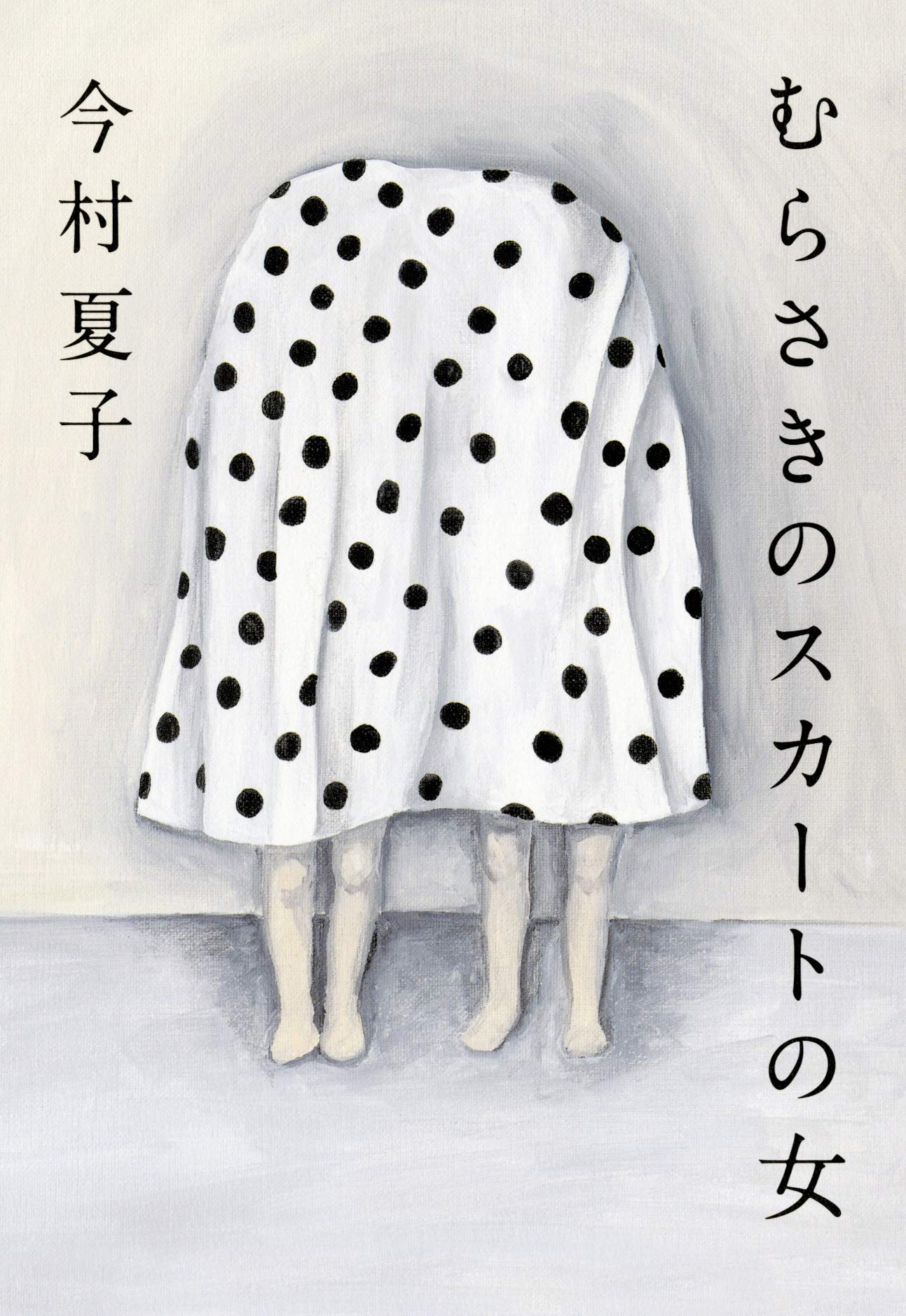
2019年に第161回芥川賞を受賞した、今村夏子の作品です。主人公の「わたし」が、近所に住む「むらさきのスカートの女」に異常な関心を寄せ、彼女のストーカーまがいの観察を続けるという、少し不気味な物語です。
「わたし」は、彼女と友達になりたい一心で、彼女を自分の職場に就職させようと画策します。淡々とした語り口の中に潜む狂気と、予測不能なストーリー展開が読者を引き込みます。人間の孤独や承認欲求を独特の視点から描いた一冊です。



なんだかジワジワと怖さがこみ上げてくる話だよ。でも、誰かを羨んだり、友達になりたいって思う気持ちは、誰にでもあるかもしれないね。
21位: 『砂の女』 安部公房
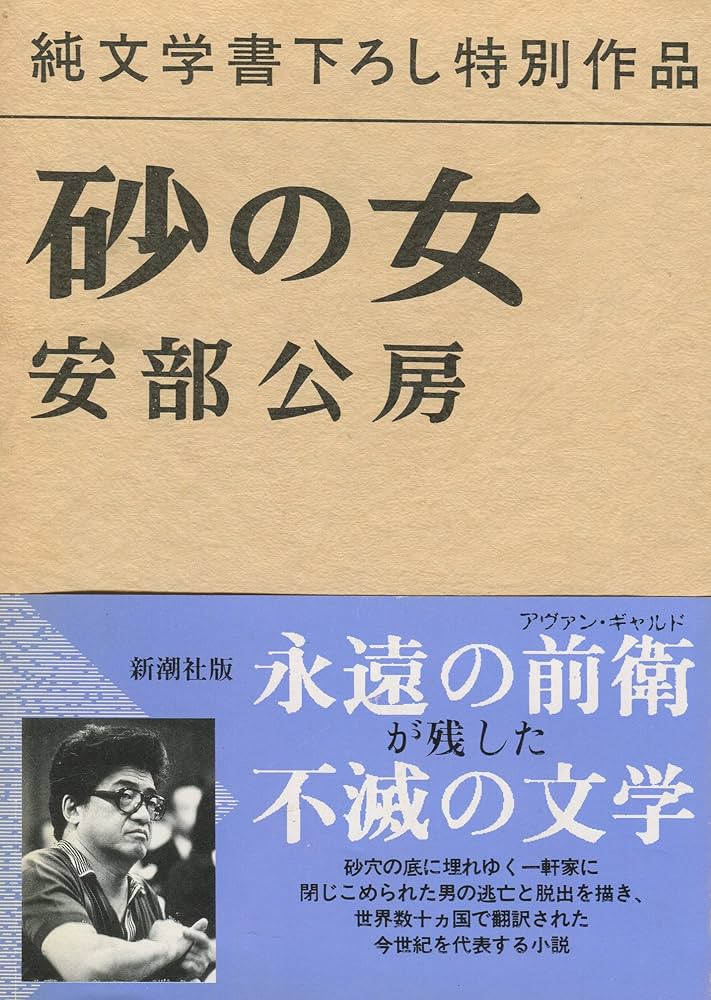
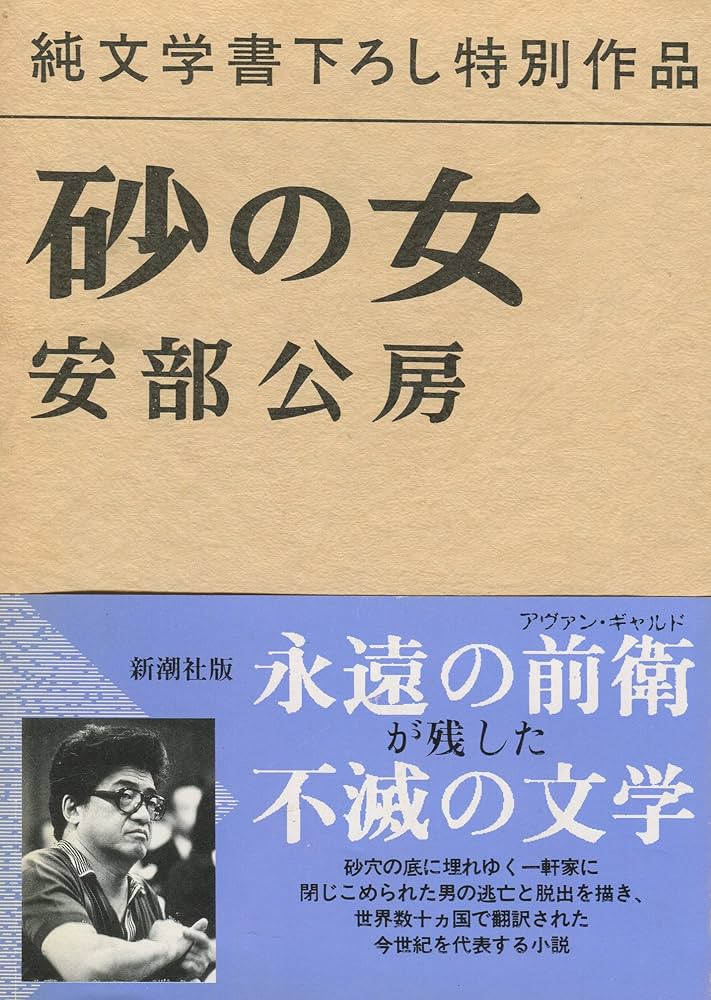
昆虫採集のために砂丘を訪れた男が、砂穴の底にある一軒家に閉じ込められてしまうという、シュールで不条理な物語です。女と共に、絶えず流れ落ちてくる砂を掻き出すという終わりのない労働を強いられる中で、男の日常は次第に崩壊していきます。
安部公房の代表作であり、世界中で高く評価されている作品です。砂の持つ圧倒的な存在感と、極限状況に置かれた人間の心理描写が圧巻です。自由とは何か、生きるとは何かという根源的な問いを投げかけます。



本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。
22位: 『舞姫』 森鴎外
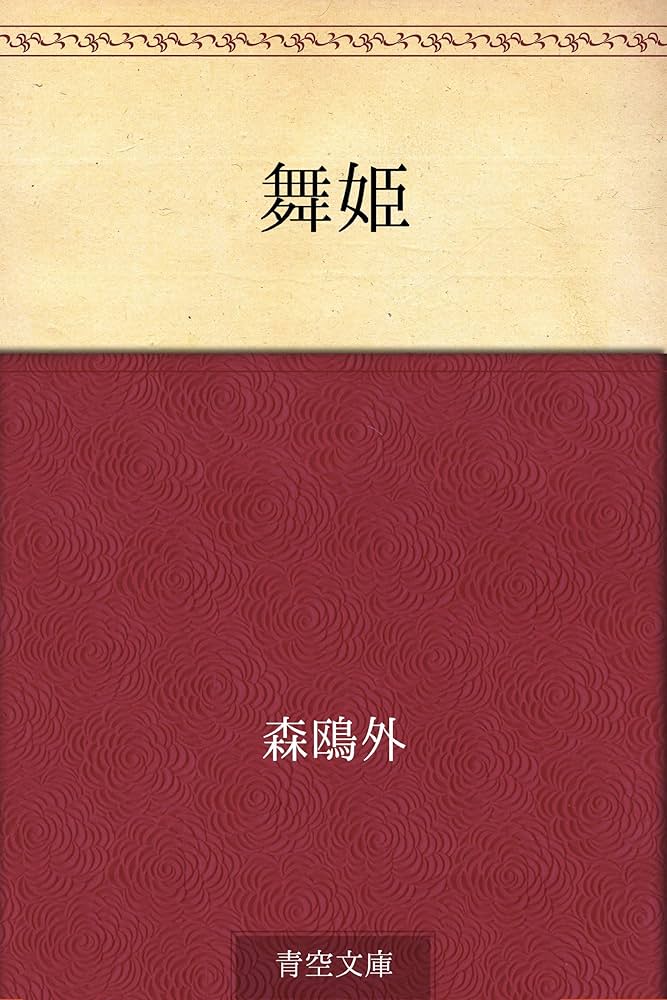
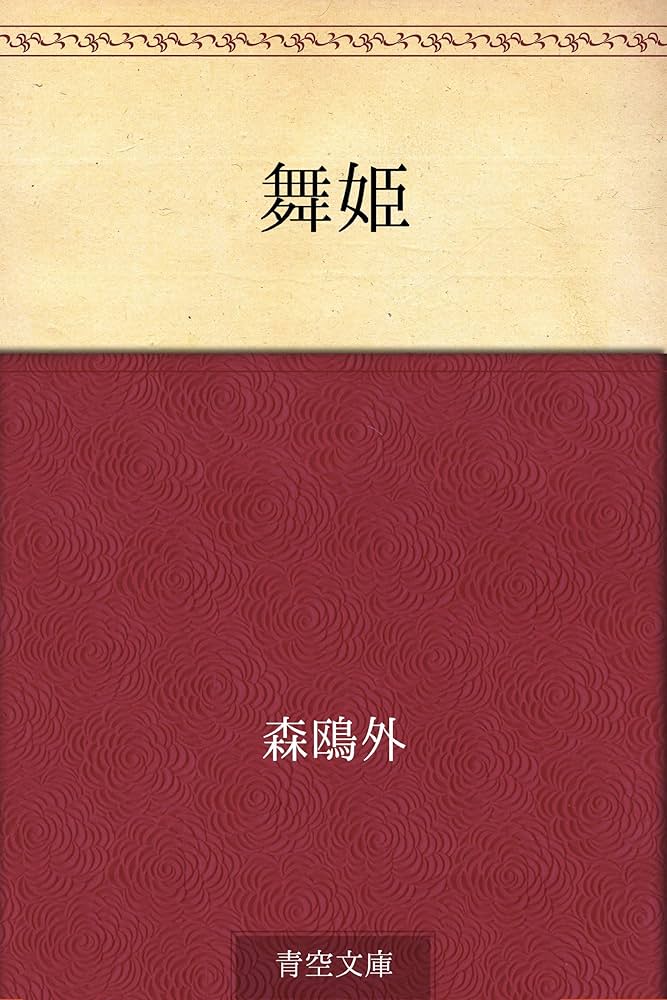
1890年に発表された森鴎外の初期の代表作で、彼自身のドイツ留学経験が基になっていると言われています。 主人公は、エリート官僚としてベルリンに留学した太田豊太郎。 彼は、貧しい踊り子の少女エリスと恋に落ち、彼女との愛に生きることを決意しますが、やがて立身出世の道との間で葛藤します。
近代的な自我に目覚めながらも、社会的な名誉や国家への義務といった古い価値観に縛られる主人公の苦悩を描いています。 日本の近代文学におけるロマン主義の先駆けとされ、その格調高い文体も魅力の一つです。



エリスのことを思うと、豊太郎の決断はあまりにも切ないよね。愛と仕事、どっちを選ぶかなんて、簡単に決められない問題だよなあ。
23位: 『春琴抄』 谷崎潤一郎
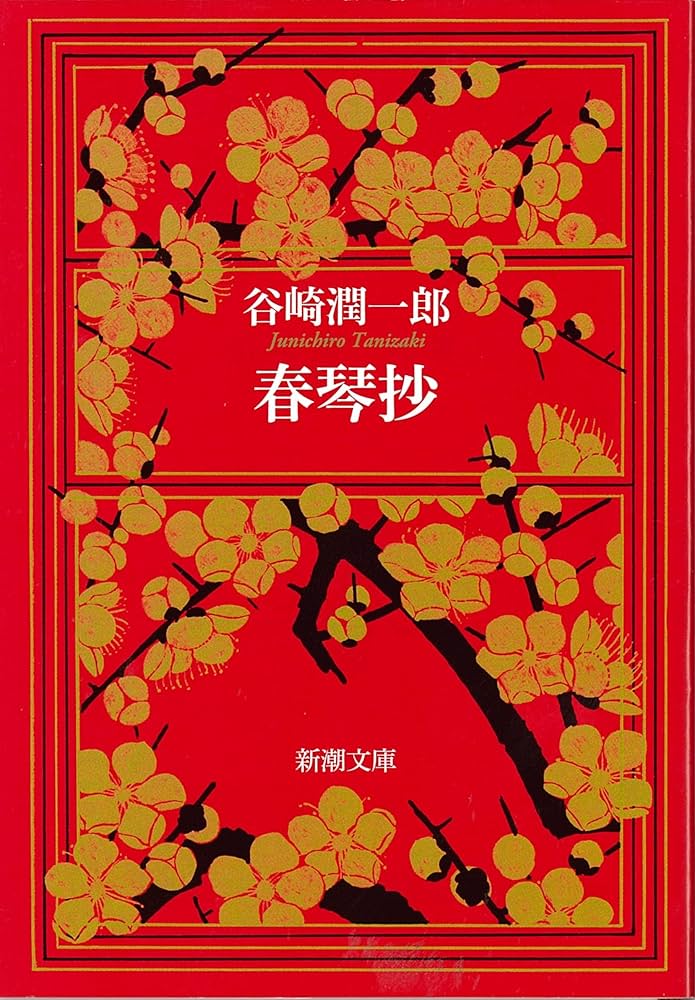
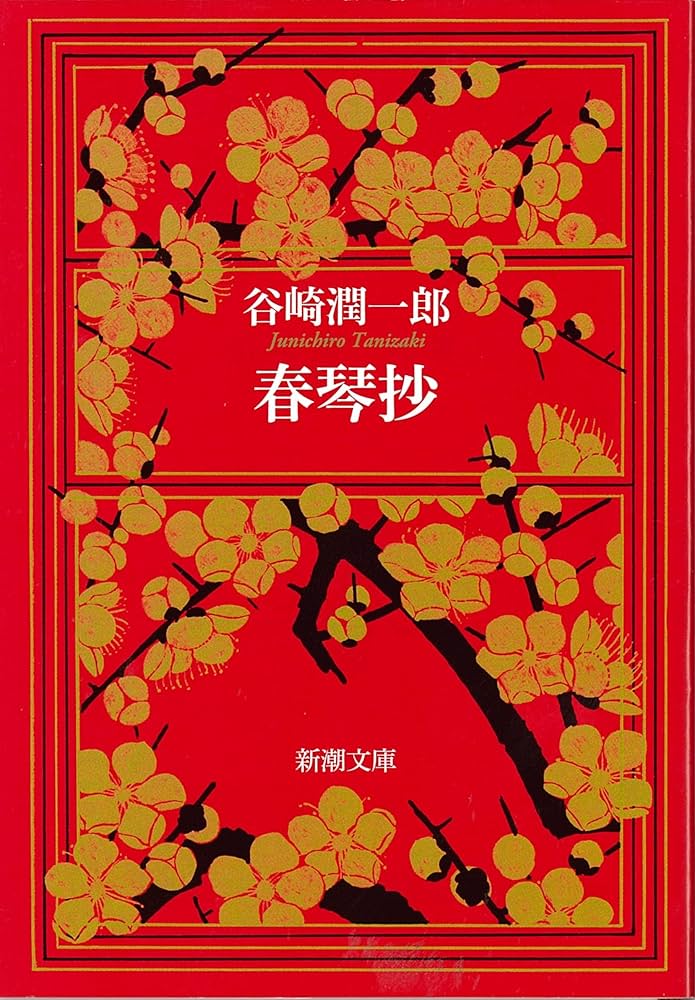
盲目の三味線奏者である春琴と、彼女に献身的に仕える丁稚の佐助との、異様ともいえる師弟関係と愛情を描いた谷崎潤一郎の代表作です。 美貌と才能に恵まれながらも、気性が激しくわがままな春琴に、佐助は絶対的な服従と愛情を捧げ続けます。
ある事件で春琴が顔に大怪我を負うと、佐助は彼女の美しい面影を永遠に心に留めるため、自らの両目を針で突き、失明します。 マゾヒズム的な愛の極致を描きながら、芸術と官能の世界を耽美的に表現した、谷崎文学の傑作です。



佐助の愛は、もはや狂気的とも言えるよね。でも、それほどまでに誰かを愛せるって、ある意味すごいことなのかもしれない。
24位: 『蛇にピアス』 金原ひとみ
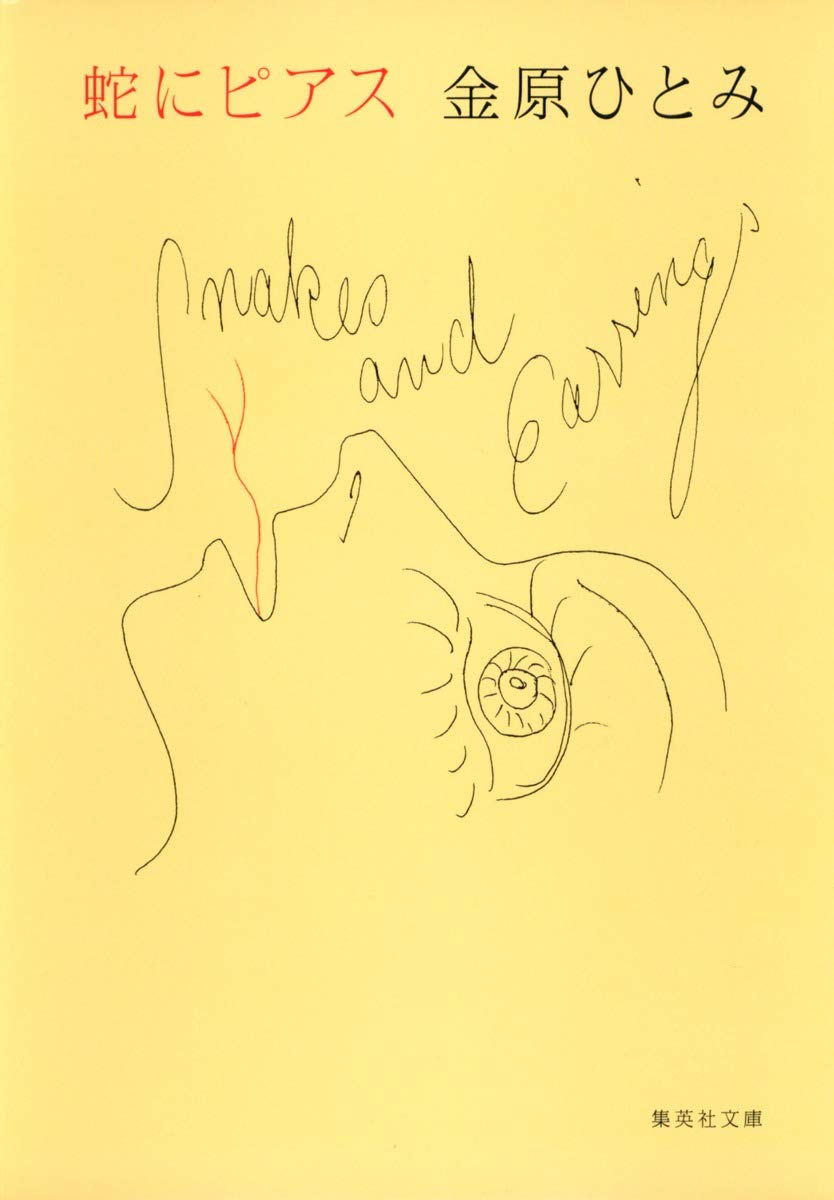
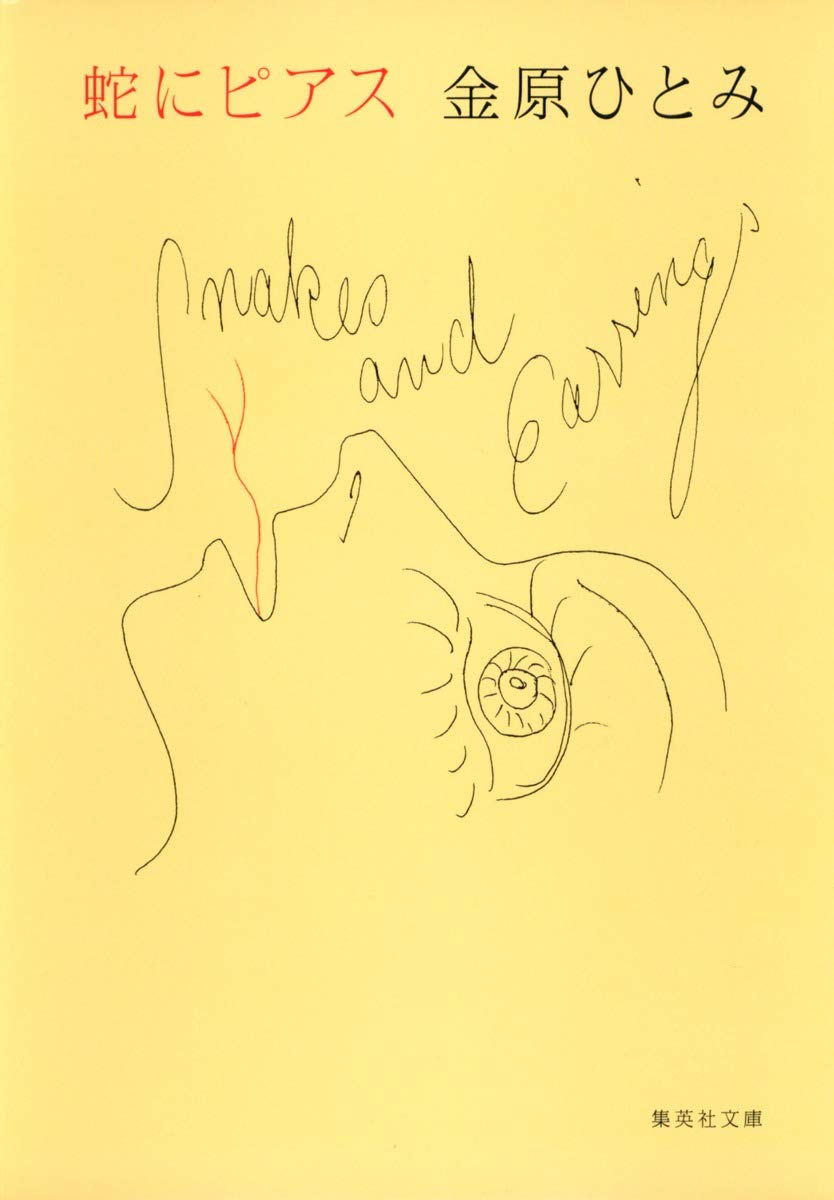
2003年に当時20歳の金原ひとみが執筆し、第130回芥川賞を受賞した衝撃的なデビュー作です。主人公のルイが、スプリットタン(蛇のように舌先を二つに分けること)を持つ男・アマと出会い、身体改造の世界に足を踏み入れていく物語です。
痛みや快感を通してしか生きている実感を得られない若者たちの姿を、クールな文体で描いています。現代社会の虚無感や、希薄な人間関係を象徴する作品として、大きな反響を呼びました。



身体を傷つけることでしか、自分の存在を確かめられない。その感覚が、読んでいてヒリヒリと伝わってくるよ。
25位: 『破戒』 島崎藤村
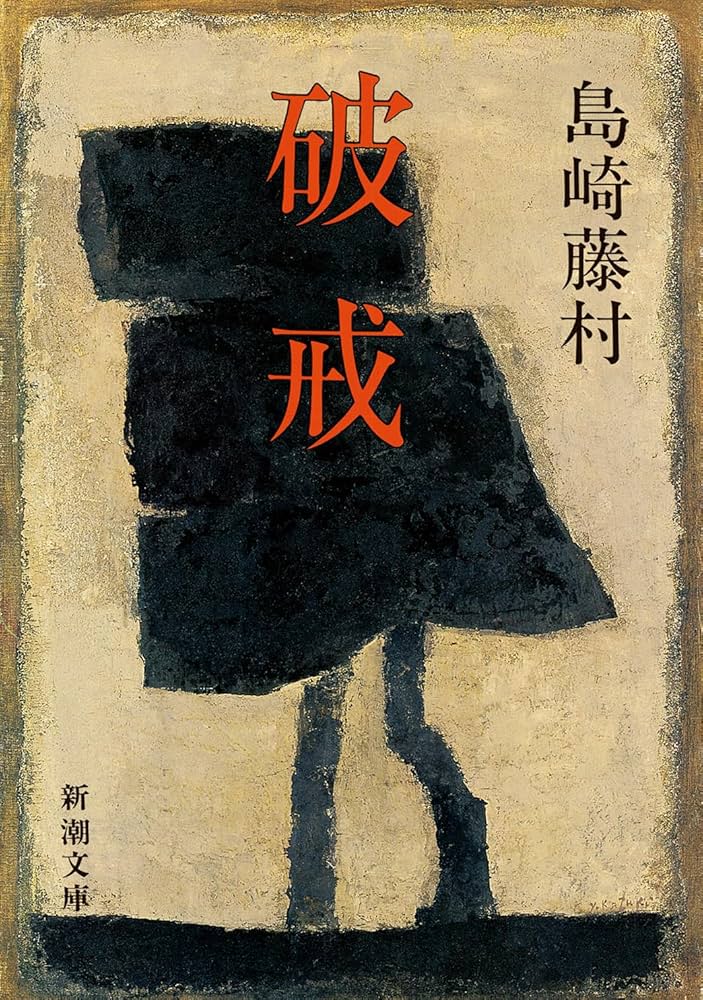
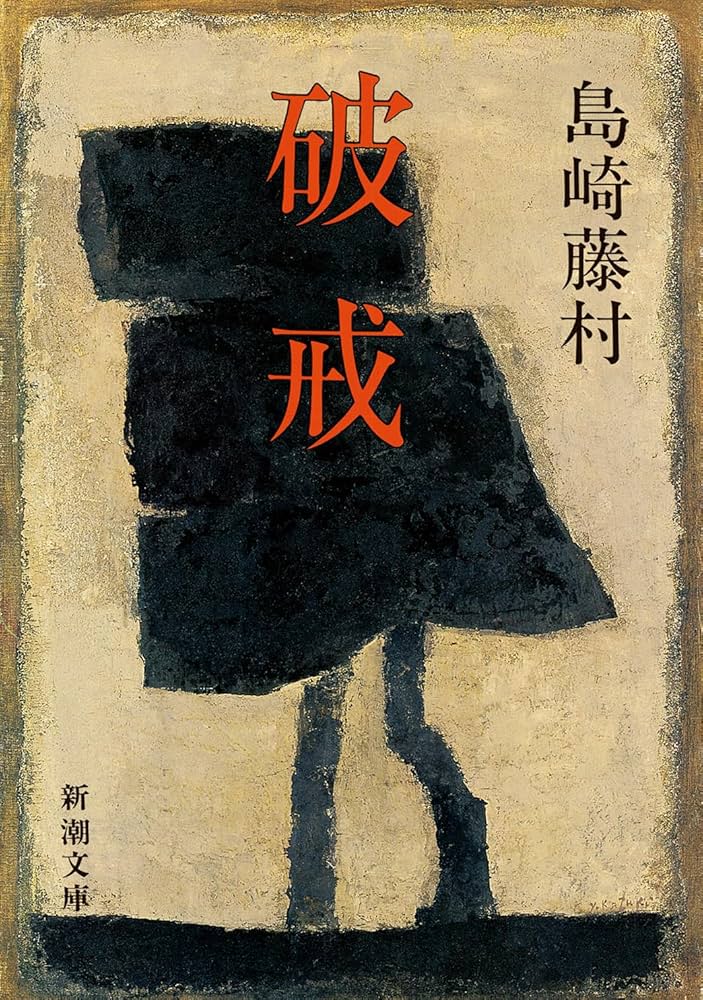
1906年に発表された、島崎藤村の代表作であり、日本自然主義文学の先駆けとされる作品です。 主人公は、被差別部落出身であることを隠して生きる小学校教師・瀬川丑松。 彼は、父から受けた「出自を隠せ」という戒めと、自身の良心との間で激しく葛藤します。
同じく被差別部落出身の思想家・猪子蓮太郎への敬愛を深める中で、丑松は自らのアイデンティティに目覚めていきます。 明治時代の深刻な社会問題であった部落差別を正面から描き、人間の尊厳とは何かを問いかけた社会派小説の傑作です。



自分の出自を隠して生きる丑松の苦しみが、痛いほど伝わってくるよ。戒めを破って告白するシーンは、本当に感動的だね。
26位: 『城の崎にて』 志賀直哉
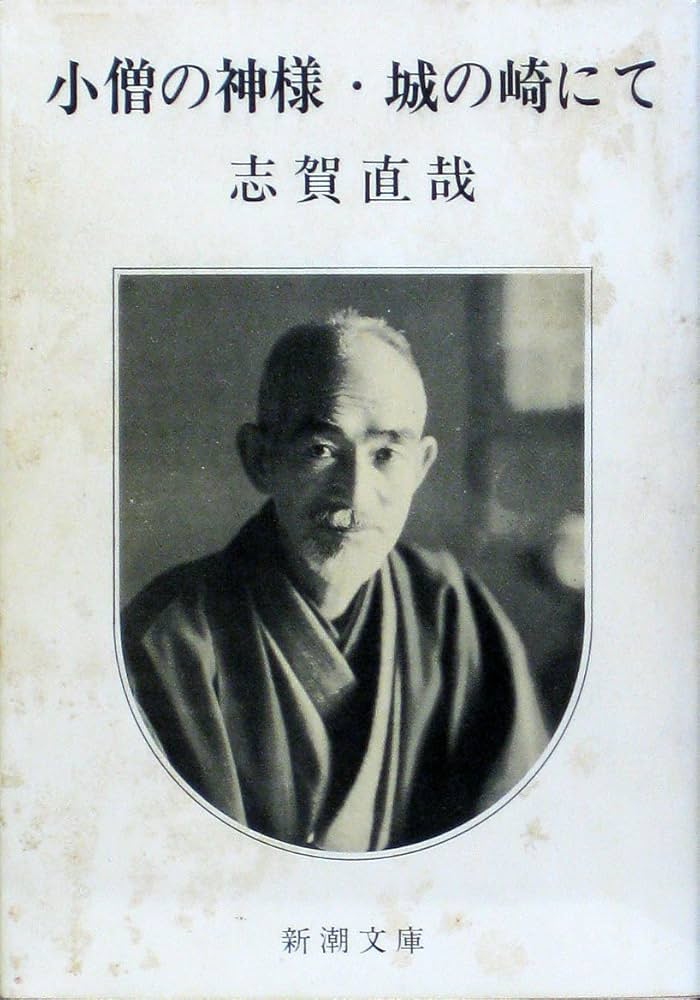
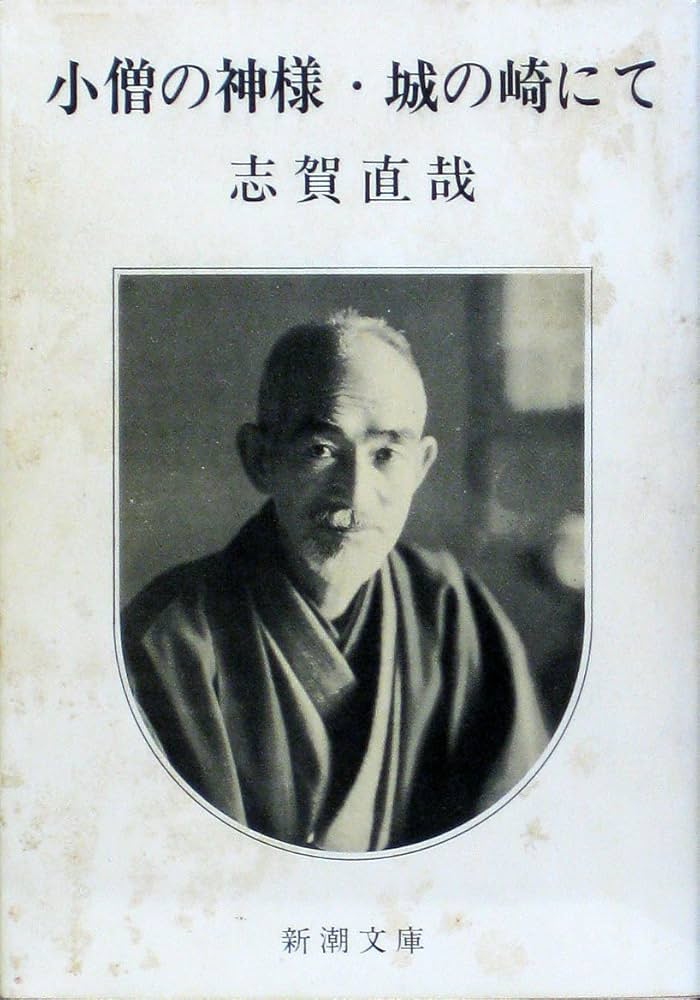
「小説の神様」と称された志賀直哉の代表的な短編であり、心境小説の極致とされる作品です。山手線の事故で重傷を負った主人公「自分」が、兵庫県の城崎温泉で療養する中で、生と死について思索を巡らせる物語です。
蜂や鼠、いもりといった小さな生き物たちの死を目の当たりにすることで、彼は自身の生と死を静かに見つめ直します。無駄のない簡潔な文章で、死生観という普遍的なテーマを深く描いた、日本文学の宝ともいえる一編です。



静かな物語だけど、生きることと死ぬことについて、すごく深く考えさせられるよ。読んだ後、心が洗われるような気持ちになるんだ。
27位: 『限りなく透明に近いブルー』 村上龍
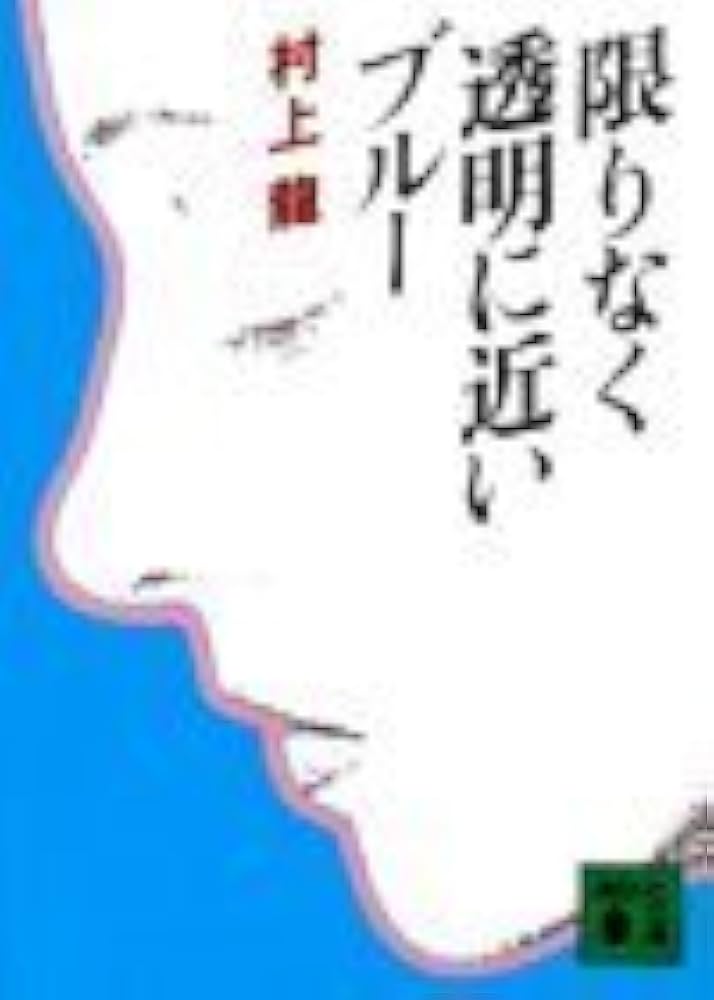
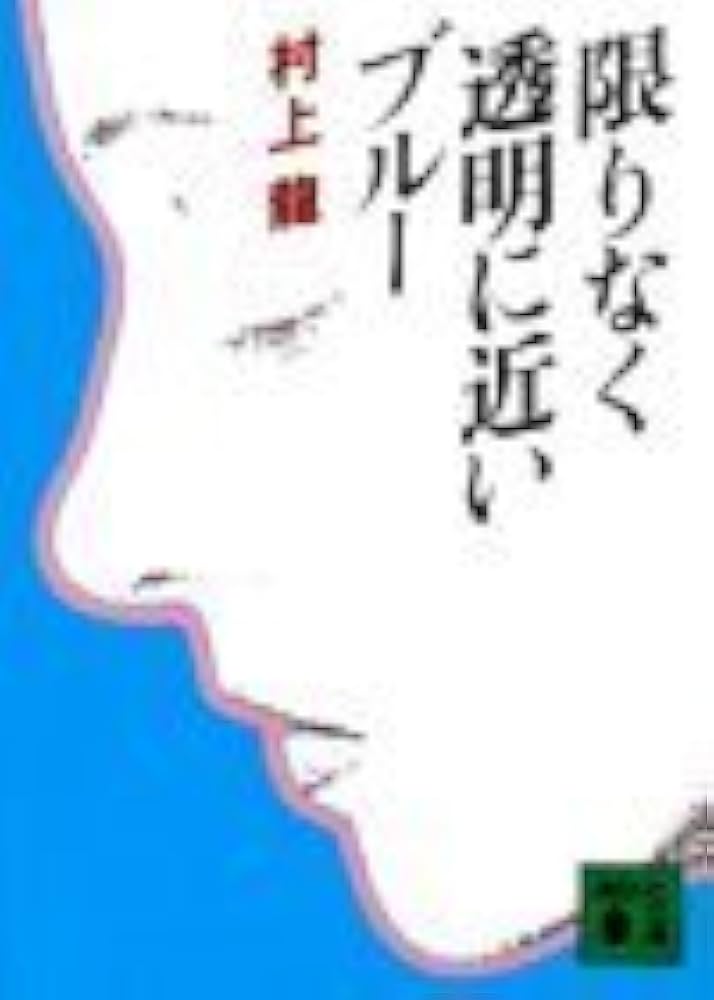
1976年に発表され、第75回芥川賞を受賞した村上龍の鮮烈なデビュー作です。米軍基地のある街・福生を舞台に、ドラッグとセックス、暴力に明け暮れる若者たちの退廃的な日常を描いています。
主人公リュウたちの行動には目的も未来もなく、ただ刹那的な快楽を追い求める姿が、乾いた文体で淡々と描写されます。発表当時はその過激な内容から賛否両論を巻き起こしましたが、ベトナム戦争後の日本の若者が抱える虚無感や閉塞感を鋭く捉えた作品として、今なお多くの読者に衝撃を与え続けています。



本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。
28位: 『旅する練習』 乗代雄介
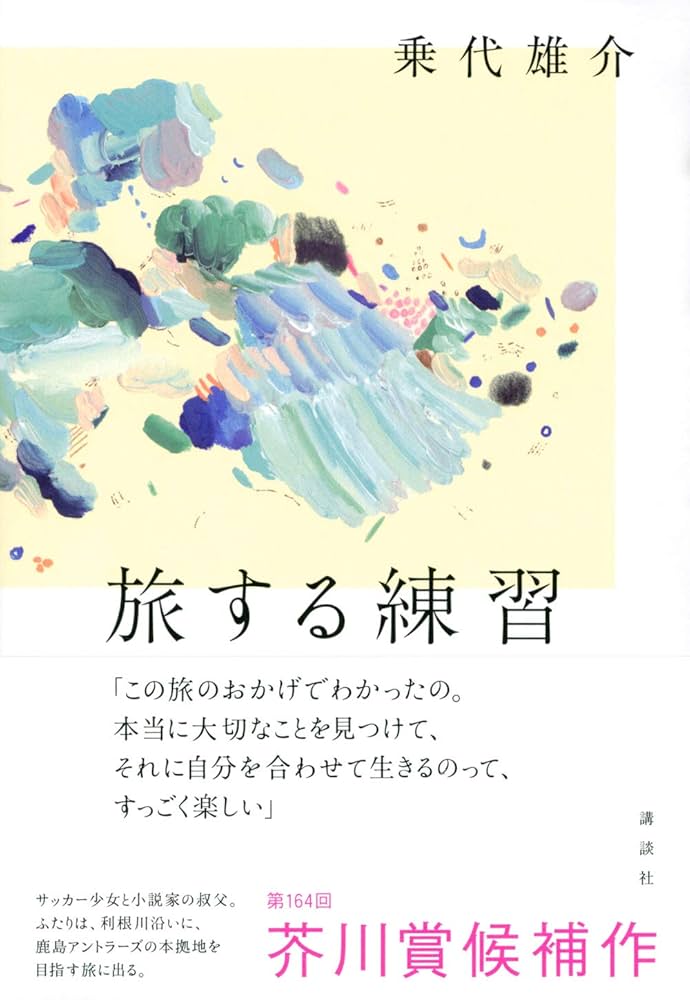
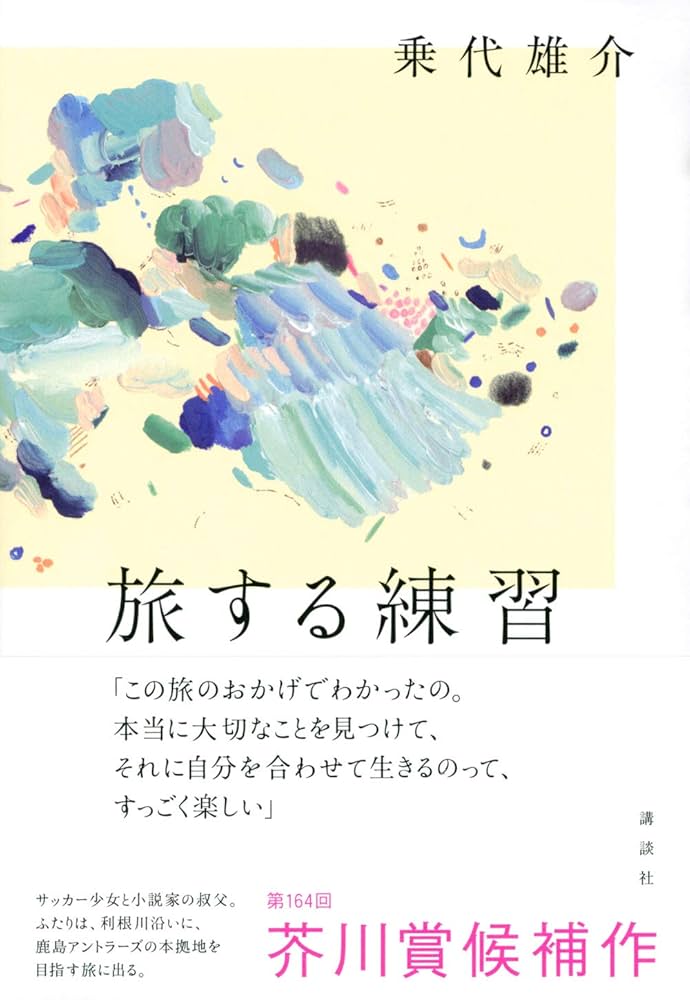
2021年に第34回三島由紀夫賞を受賞した作品です。サッカー選手になる夢を諦めた語り手が、小学生の姪・亜美と共に、彼女が住む茨城から、かつて自分が所属していたサッカーチームのある鹿島までを徒歩で旅する物語です。
特別な事件が起こるわけではない、淡々とした旅の道のりが描かれますが、その中で語り手と亜美の会話や、道中の風景描写を通して、過去の記憶や未来への思いが繊細に紡がれていきます。静かな感動を呼ぶ、新しい時代のロードノベルです。



ただ歩くだけなのに、すごく豊かな時間が流れている感じがするよ。読んだ後、どこかへふらっと旅に出たくなるような一冊だね。
29位: 『影裏』 沼田真佑
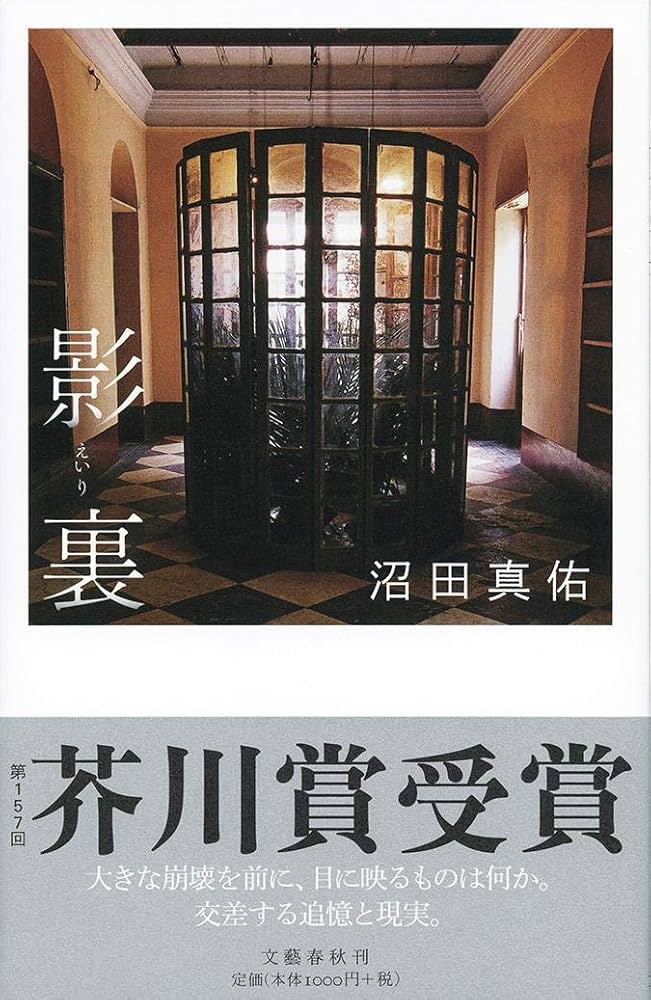
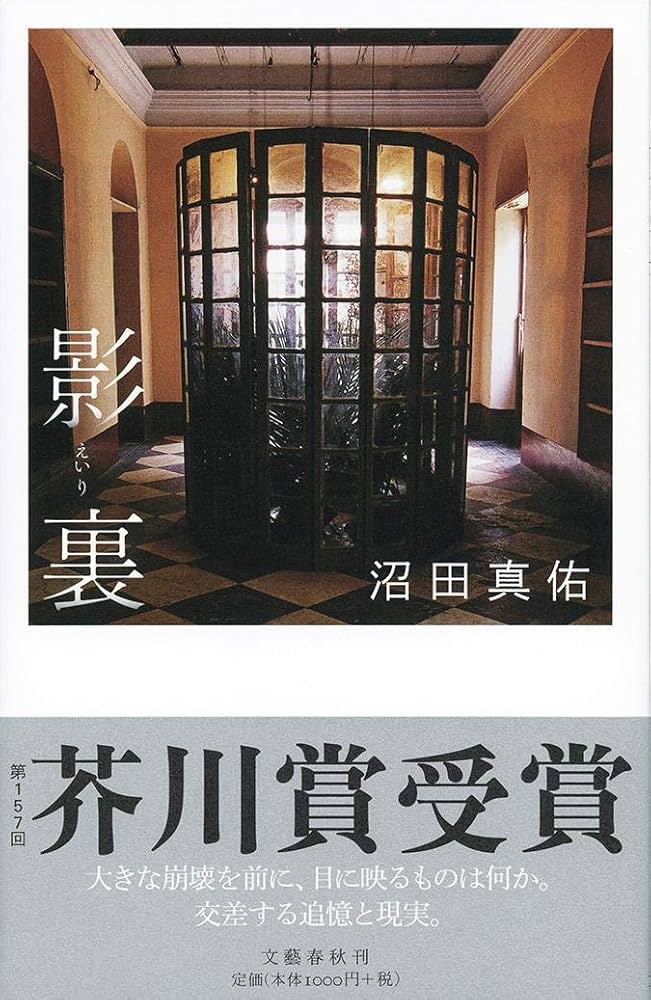
2017年に第157回芥川賞を受賞した、沼田真佑のデビュー作です。主人公・今野が、突然姿を消した同僚・日浅の足跡を追う中で、彼の知られざる素顔に触れていく物語です。
東日本大震災を背景に、親しいと思っていた人間の裏の顔や、人間関係の不確かさがミステリアスに描かれています。美しい自然描写と、人間の内面に潜む影とのコントラストが印象的な作品です。



親しい人のことでも、実は何も知らなかったりするのかもしれない。そんなことを考えさせられて、少し怖くなるような話だよ。
30位: 『季節の記憶』 保坂和志


1995年に発表された保坂和志の代表作です。なお、同年に保坂は『この人の閾』で第113回芥川賞を受賞しています。明確なストーリーはなく、主人公の「僕」と妻、そして彼らの飼い猫との何気ない日常が、断片的なエピソードの連なりとして描かれています。
従来の小説の形式から逸脱し、ただそこにある日常の断片を丁寧にすくい上げることで、生きていることそのものの豊かさや不思議さを描き出そうとしています。読者に新しい読書体験をもたらしてくれる、実験的な一冊です。



大きな事件は起きないんだけど、日常のささいな出来事がすごく愛おしく感じられるんだ。猫の描写がすごくリアルで可愛いよ。
まとめ:ランキングからお気に入りの純文学を見つけよう
純文学のおすすめランキングTOP30、いかがでしたでしょうか。時代を超えて愛される文豪の名作から、現代社会を鋭く切り取る話題作まで、様々な作品をご紹介しました。
純文学は、私たちに普段は意識しないような深い問いを投げかけ、心を豊かにしてくれます。難しそうだと敬遠せずに、まずはこのランキングの中から気になった一冊を手に取ってみてください。きっと、あなたの価値観を揺さぶるような、忘れられない読書体験が待っているはずです。